| ◆ |
10月1日(金) Anjaana Anjaani |
◆ |
「Dabangg」以来、久々にまともなヒンディー語映画が公開された。元々9月24日公開予定だったヒンディー語新作映画「Anjaana Anjaani」だが、アヨーディヤーのバーブリー・マスジド跡地・ラーム生誕地寺院建設予定の所有権を巡る裁判の判決日が重なったため、この映画の公開は1週間延期された。
監督は「Salaam Namaste」(2005年)などのスィッダールト・アーナンド。現代的なラブコメを得意とする若手監督である。主演はランビール・カプールとプリヤンカー・チョープラー。初共演となる。
題名:Anjaana Anjaani
読み:アンジャーナー・アンジャーニー
意味:見知らぬ男、見知らぬ女
邦題:ストレンジャーズ
監督:スィッダールト・アーナンド
制作:サージド・ナーディヤードワーラー
音楽:ヴィシャール・シェーカル
歌詞:ニーリーシュ・ミシュラー、ヴィシャール・ダードラーニー、シェーカル・ラーヴジヤーニー、キャラリサ・モンテイロ、アミターブ・バッターチャーリヤ、アンヴィター・ダット、クマール、カウサル・ムニール
振付:アハマド・カーン
出演:ランビール・カプール、プリヤンカー・チョープラー、ザイド・カーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

プリヤンカー・チョープラー(左)とランビール・カプール(右)
| あらすじ |
ニューヨークで友人たちと証券会社を立ち上げ、成功の道を歩んでいたアーカーシュ(ランビール・カプール)は、リーマン・ショックにより一瞬で全てを失う。会社は倒産し、友人たちとは仲違いし、家は差し押さえられた。人生に絶望したアーカーシュは、橋から河に飛び降りて自殺しようとした。そこで出会ったのがキヤーラー(プリヤンカー・チョープラー)であった。彼女も自殺をしにそこへ来ていた。しかし沿岸警備隊に見つかり飛び降り自殺に失敗する。そこでアーカーシュは走行中の自動車に身を投げ、キヤーラーはもう一度飛び降り自殺しようとして足を滑らせ、頭を打つ。
アーカーシュが目を覚ますと病院にいた。頭を打っただけで命に別状はなかった。見舞いに来た同僚から、会社の買い手が見つかったこと、12月30日に会社譲渡のサインを行うことなどを告げられる。だが、アーカーシュはまだ死ぬ気で、こっそり病院から抜け出そうとする。ところが同じ病院にキヤーラーも入院しており、同様にもう一度自殺しようとして脱走中であった。2人は協力して自殺することにし、とりあえずキヤーラーの家へ行く。
そこで2人はいくつか自殺に挑戦するが、どれも失敗してしまう。キヤーラーは、これは何かのサインではないか、まだ人生でやり残したことがあるから自殺に失敗するのではないか、と言うが、アーカーシュはそんなことは信じない。だが、死ぬ前に思いっきり人生を楽しむという提案には乗り、12月31日にあの橋から飛び降りて自殺すること、その前にお互いがやり残したことを一緒に遂行することを決める。このとき、12月31日まであと20日だった。
実はアーカーシュは童貞であった。ずっと仕事で忙しく、彼女を作る暇もなかった。また、恋愛を信じており、心から愛した人に童貞を捧げようとしていた。アーカーシュはその最期の望みをキヤーラーに打ち明ける。キヤーラーは彼を、ナンパのメッカに連れて行くが、アーカーシュの真の望みは恋愛という困難な望みであったため、行きずりの人と寝ることは出来ず、とりあえずこの願いは保留となる。一方、キヤーラーは大西洋の真ん中で泳ぎたいと言い出す。そこでボートで大西洋に繰り出す。大西洋上でアーカーシュは、「毎日、その日が人生最期の日だと思って生きよう」と書いたメッセージをボトルに入れて海に投げ入れる。ところが、2人は海中に飛び込んだままボートを見失ってしまい、遭難してしまう。だが、幸運にも沿岸警備隊がやって来たため、一命を取り留めることが出来た。
ところで、キヤーラーが自殺しようとした理由は、許嫁の裏切りであった。サンフランシスコで育ったキヤーラーは、幼馴染みのクナール(ザイド・カーン)と結婚を控えていたが、ある日偶然クナールの浮気を知ってしまう。キヤーラーはクナールと別れ、単身ニューヨークに来ていた。だが、クナールの裏切りが忘れられず、自殺をしようとしたのだった。
ふとアーカーシュが目を覚ますと、キヤーラーがいなかった。不安に感じたアーカーシュが彼女を探すと、バスルームで毒を飲んで倒れていた。アーカーシュは急いで彼女を病院に運ぶ。キヤーラーは助かったが、医者から「何度も命を助けても自殺しようとする。もっと命を大切にするように」とたしなめられ、なるべくキヤーラーを喜ばせようと考え出す。
次に2人はキヤーラーのオンボロ車「ブラッシュ」に乗って、ラスベガスへ向かった。2人はカジノで大いにエンジョイする。ラスベガスでアーカーシュははっきりと、キヤーラーを愛していることに気付くと同時に、キヤーラーはまだクナールを忘れ切れていないことも痛感する。そこでアーカーシュは黙って彼女をサンフランシスコへ連れて行く。そして、「僕たちは死に何度もチャンスを与えたけど、死はそれを活かせなかった。ならばなぜ人生にもう一度チャンスを与えないか?」と説き、もう一度クナールとやり直すように促す。キヤーラーはそれを受け容れ、サンフランシスコの自宅に戻り、クナールとも再会する。
一方、アーカーシュは譲り受けた「ブラッシュ」に乗ってニューヨークに戻る。同僚の家に居候し、会社の精算に向けて作業を始める。12月30日に会社の譲渡契約も済ませた。アーカーシュは唯一親身になってくれた同僚と共にインドへ戻ってもう一旗揚げることを決める。
ところで、キヤーラーはクナールと話し合うが、やはり以前のような関係に戻ることは無理だった。2人は友人としてとりあえず関係修復をする。また、クナールは何となくキヤーラーの変化に気付いていた。12月31日、友人の結婚式において、クナールはキヤーラーからアーカーシュのことを聞き出し、ニューヨークへ向かうべきだと勧める。迷いを捨てたキヤーラーは、急いでニューヨークへ向かい、あの橋へ走った。そこには、空港へ向かう途中のアーカーシュが念のために待っていた。2人は再会を喜ぶが、自殺する約束は曲げず、飛び降りる代わりに岸から河の中に入って行く。そこでアーカーシュはあらかじめ用意しておいたメッセージ入りボトルを浮かべる。それを発見したキヤーラーが開けると、中にはプロポーズのメッセージが入っていた。既に深いところに入り込んでおり、溺れかけていた2人だったが、またも沿岸警備隊に助けられた。隊長は、今し方結婚を決めた2人に、「結婚は自殺よりも酷いぞ」と激励(?)の言葉をかける。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ニューヨークを主舞台としながら、出会う人はなぜかほとんどヒンディー語の話せるインド人ばかり、そのくせ変な役回り(例えばクナールの浮気相手や、キヤーラーの愛車「ブラッシュ」を盗んだ同性愛者デブなど)は白人という、インド映画によくありがちなご都合主義な映画であった。前半のテンポはかなりスローで、しかも正常な知能を持っている人なら前半を見ただけで結末が大体予想出来てしまうものであった。ほとんどアーカーシュとキヤーラーしか登場しないにも関わらず、そのアーカーシュとキヤーラーの人物描写が不十分で、感情移入の障害となった。多少下ネタに属するような笑いもあり、家族が安心して見られる作品でもなかった。このような欠点はあったものの、後半ラスベガスに旅に出てからは急にロードムービー的な展開となって閉塞感が取り払われ、面白くなった。全体的にコメディーシーンも外れがなかった。よって、若者向けラブコメ映画として十分楽しい作品だと感じた。ただでさえ若者の間で人気沸騰中のランビール・カプールが主演であるので、都市部を中心にそこそこの興行収入を上げるのではないかと予想される。
この映画で面白かったのは、ヴァージニティーの扱いとインド回帰である。インドでは、都市部の若者を中心に価値観の革命的変化が起きつつあるものの、建前上は、結婚まで処女・童貞を守るのが美徳となっている。アーカーシュも童貞であり、死ぬ前に童貞脱却をしたいと願っていた。ただ、ニューヨークに住み、バリバリの証券マンという設定のアーカーシュが超奥手だという設定にはもう少し説明が必要だったと思う。ランビール・カプールの外見からはあまりそういう匂いがしない。かつて「Mumbai
Matinee」(2003年)でラーフル・ボースが32歳童貞を演じたことがあったが、ラーフル・ボースからは、演技力なのか地なのか、そういう雰囲気が感じられ、自然に納得できた。だが、ランビール・カプールからはあまり感じない。また、アーカーシュの性格についても描写不足であった。「誰とも友達になれない」と言われるまでに独善的な性格らしいのだが、映画中からそういう印象は受けなかった。しかし、アーカーシュの童貞性よりもキヤーラーの処女性の方が面白かった。映画中ではキヤーラーの処女性については全く言及がないのだが、彼女が自殺するきっかけとなった事件のひとつに、許嫁クナールの浮気が発覚した後にバーで飲んでいてナンパされた白人と「寝た」ことであった。キヤーラーは、翌日クナールに浮気を問い詰めると同時に、自分も行きずりの人と「寝てしまった」と打ち明ける。多くは語られなかったが、それが婚約破棄の大きな原因となったことは暗示されていた。つまり、クナールはキヤーラーに自分の浮気を許すように懇願するが、キヤーラーの浮気は許せなかったのである。ただし、キヤーラーが白人と「寝た」シーンはない。それでも観客はそういうことになったのだろうと考える。ところが、後になってキヤーラーは、「実はあの夜、白人との間には何もなかった」と語り出す。そしてどうもそれは真実であった。しかしそれが打ち明けられるのは、酔ったキヤーラーがラスベガスにてアーカーシュと「寝た」後の朝であった。ここでもアーカーシュとキヤーラーが性的関係を持ったことを示す直接的なシーンはないのだが、キスまではあるため、観客もそういうことになったのかと考える。だがその直後にアーカーシュが、「昨晩は何もしなかった」と言い出すのである。つまり単に一緒に寝ただけであった。こうして二度に渡ってキヤーラーの処女性がフェイントを入れながらも守られた訳である。しかし、キヤーラーのキャラクターが曖昧でよく分からないので、観客の方もよく分からなくなって来る。登場シーンの彼女は完全に飲んだくれであり、その後も「遊び方」を知っている派手な女性であると同時に、料理や掃除が出来ない駄目な女性であることも描かれるため、そういう女性かと思ってしまうが、サンフランシスコ時代の彼女の描写は全く正反対の「深窓の令嬢」タイプであり、幼馴染みとの結婚を夢見てきた「白馬の王子様」タイプでもあり、混乱してしまう。しかし、頑なにヒロインの処女性が映画の終わりまで守られていることだけは言える。そういう意味では非常に保守的な価値観の映画だったと言えるだろう。この保守性はしばしば外国人インド映画鑑賞者に大きな混乱を与えがちなのではないかと感じる。いかにも阿婆擦れなヒロインでも、性に関する部分では当然の如く奥手というのがインド映画界の暗黙の了解となっている。ちなみに、アーカーシュが白人同性愛者に「ヴァージン」を奪われそうになるお笑いシーンもあり、とことんヴァージニティーにこだわった映画という印象を受けた。
以上は冗談みたいな批評であるが、インドへの回帰についてはさらに真面目に受け止める必要があるだろう。NRI(在外インド人)のインド回帰を訴える映画は過去にいくつか作られて来た。それはインド本国への帰国であったり、インド文化やインド人アイデンティティーの受容だったり、様々な形で表れて来たが、インドにルーツを持つ人々のインドへの回帰であることには変わりない。古くは「Dilwale
Dulhania Le Jayenge」(1995年)にもその傾向が見られるが、21世紀に入ってからは「American Desi」(2001年)や「Swades」(2004年)などが代表作と言える。「Anjaana
Anjaani」では、リーマン・ショックにより会社を倒産させ、失業したインド人証券マンがインドへ帰ってビジネスチャンスを模索する様子が描かれていた。インドへの憧憬が彼らをインドに呼び寄せたのではなく、もっと現実的な、ビジネス上のやむを得ない事情から導き出されたインド回帰である。このインド回帰はストーリーの本筋とはほとんど関係ない部分であったが、とても斬新に思えた。インド映画には、インド人をやたら海外へ送り出そうとするものと、海外に出たインド人をインドへ呼び戻そうとするものの2つが見受けられるが、「Anjaana
Anjaani」は後者のニュータイプだと言える。
ランビール・カプールとプリヤンカー・チョープラーの演技はとても良かった。2人のスクリーン上のケミストリーも抜群。特に印象に残ったのは、サンフランシスコで2人が別れるシーンだ。2人とも涙を流すが、2人ともお互いの涙を見せない。自殺をしようとした2人が主人公なので、やたらと泣くシーンが多かったのだが、前半の一部を除き、そこまで重たい映画になっていなかったのは、この2人が持って生まれた明るさのおかげだと思った。特別出演のザイド・カーンについてはちょっと場違いな雰囲気かつ場違いな演技をしていたように感じた。
音楽はヴィシャール・シェーカル。ご機嫌なラブソングが多く、サントラCDはヒットしている。タイトルソング「Anjaana Anjaani」は多少スローテンポの曲だが、「Anjaana
Anjaani Ki Kahani」はより明るく、映画の雰囲気を決定している。「I Feel Good」や「Tumse Hi Tumse」も心地よいラブバラードで悪くない。だが、名曲と言えるのはラーハト・ファテ・アリー・ハーンの歌う「Aas
Paas Khuda」だ。自殺を多少茶化した内容になっているこの映画に、「神の意志」を感じさせ、高尚なイメージを多少なりとも付加することに貢献している。また、アーカーシュがゲイバーで踊るダンスは、ミトゥン・チャクラボルティーの出世作「Disco
Dancer」(1982年)のヒット曲「I Am A Disco Dancer」である。
「Anjaana Anjaani」は、プロモや音楽の明るいイメージからすると多少前半スローかつ重たく感じるがが、後半からグッとまとまっており、面白くなる。ロマンスの部分も結末予想可ではあるが納得できるものであるし、コメディー部分は全体的に秀逸である。多少下ネタが多めではあるが、娯楽映画ファンにはオススメできる作品である。
インド初のSF映画は、一般にはリティク・ローシャンの人気を不動のものとした「Koi... Mil Gaya」(2003年)とされている。インド映画がハリウッドばりのSF映画を作ったと聞いて、とんでもないゲテモノ映画になっているに違いないと怖い物見たさで見に行った記憶があるが、意外にインド映画のフォーマットにうまく消化されており、驚いたものだ。もちろん、「未知との遭遇」(1977年)や「E.T.」((1982年)からの影響があまりに大きく、「パクリ」のレッテルを貼られてしまうこともあるのだが、インド映画がハリウッドの得意とするジャンルに果敢に挑戦し始めたことを記念する記念碑的作品だったことには変わりがない。「Koi...
Mil Gaya」の他には、アニル・カプール主演の「Mr. India」(1987年)もSF映画の範疇に入れられることがある。だが、さらに遡って行くと、「Kaadu」(1952年)という映画があるようだ。これは印米合作のSF映画で、英語とタミル語で作られたと言う。英語版の題名は「The
Jungle」である。主演は白人だが、インド人女優スローチャナーがカメオ出演し、音楽、編集などの裏方でインド人スタッフが参加している。
それでも、近年のインド映画におけるSF映画の流行は「Koi... Mil Gaya」の成功の結果だと考えざるをえないだろう。その後、「Rudraksh」(2004年)、「Krrish」(2006年)、「Alag」(2006年)、「Love
Story 2050」(2008年)、「Drona」(2008年)、「Jaane Kahan Se Aayi Hai」(2010年)など、ヒンディー語映画だけでも様々なインド製SF映画が作られて来た。その全てがヒットした訳ではなく、大失敗に終わったものも少なくないのだが、ヒンディー語映画界においてSF映画がひとつのジャンルとして着実に定着しつつあることは確かである。
さて、「Koi... Mil Gaya」が登場したときはかなりの衝撃だったのだが、それを越える衝撃的なSF映画がインド映画界に出現した。しかも南のタミル語映画界から。ロボットをテーマとした「Enthiran/Robot/Robo」が本日全国一斉公開となったのである。
オリジナルのタミル語版タイトルは「Enthiran」。「Endhiran」と綴られることもあり、ブレがあるが、これはタミル文字に有声音と無声音の区別がないためで、タミル文字通りに綴れば「Enthiran」、発音に従えば「Endhiran」となる。タミル語には疎いのだが、おそらくこの単語は、サンスクリット語で「機械」を意味する「yantra」がタミル語的に訛った形であろう。ちなみにジャイプルの世界遺産ジャンタル・マンタルの「ジャンタル」もこのサンスクリット語から来ている。一方、ヒンディー語吹替版の題名は「Robot」、テルグ語吹替版の題名は「Robo」になっている。
「Enthiran/Robot/Robo」の主演はタミル語映画界のスーパースター、ラジニカーント。「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)のおかげで日本でも知名度の高い俳優である。ただ、この映画は最初からラジニカーントのために企画されたものではないようで、元々カマル・ハーサンやシャールク・カーンなどに主役がオファーされていたと言う。また、ラジニカーント映画にはありがちなのだが、今回も彼は一人二役を演じている。ヒロインはインド美人の代名詞アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン。ラジニカーントとアイシュワリヤーの共演は初である。アイシュワリヤーは基本的にヒンディー語映画界で活躍しているが、南インド生まれであり、南インドの言語をいくつか話すため、南インド映画にも時々出演している。つい最近は、ヒンディー語版とタミル語版が同時制作された「Raavan/Raavanan」(2010年)にて、ヒンディー語版とタミル語版のヒロインを務めた。
実は僕も「ムトゥ 踊るマハラジャ」からインド映画の世界に入った1人であり、ラジニカーントには特別な思い入れがある。本当はラジニカーント映画を楽しむためにタミル語を勉強したかったのだが、タミル語留学の情報がなかったのでヒンディー語留学をした経緯がある。結局長いことインドに住みながらタミル語をマスターすることは出来なかったが、ラジニカーント映画をヒンディー語で見ることが出来るのはとても嬉しい。デリーではヒンディー語版とタミル語版が公開となった。コアなラジニ・ファンからは邪道扱いされるかもしれないが、遠慮無くヒンディー語版「Robot」を選んだ。
ちなみに、かつてラジニカーント主演の「Chandramukhi」(2005年)がデリーで公開されたときには、タミル語音声のみであったものの、英語字幕が付いた。同じくラジニカーント主演「Sivaji
- The Boss」(2007年)がデリーで公開されたときにはタミル語音声のみ字幕無しであった。南インド映画のヒンディー語吹替版がデリーで公開されたことは過去にもあり、例えばカマル・ハーサン主演タミル語映画「Dasavathaaram」(2008年)のヒンディー語吹替版「Dasavatar」が公開されたが、タミル語版公開からしばらく経った後の翌年公開であった。また、同じ映画のタミル語版とヒンディー語版を同時制作・同時公開する作戦はマニ・ラトナム監督がよく採っており、「Guru」(2007年)や「Raavan/Raavanan」がその代表例である。
また、特筆すべきは、「Enthiran/Robot/Robo」がインド映画史上最高額の予算である15億ルピーを費やして作られたことである。映画の予算は公表されないことが多く、そういう場合は推定額になってしまうのだが、今までインドの全映画界において、物価の上昇を無視し、額面のみで判断して、もっとも大予算を費やして制作されたのは、ヒンディー語映画「Blue」(2009年)だとされていた。その「Blue」でさえ、7億5千万ルピーほどと推定されている。映画は予算が全てではないが、いかに「Enthiran/Robot/Robo」が巨額の資金を投入して作られた映画か、一応の目安になるだろう。さらに誇張されて、アジア映画最大予算の映画とされることもあるが、少なくとも日本映画の最大予算映画とされる「天と地と」(1990年)の50億円は越えていないと考えられる。また、この巨額の予算の内、40%は特殊効果に費やされたと言う。
監督はシャンカル。タミル語映画「Boys」(2003年)や「Sivaji - The Boss」のヒット作で知られた売れっ子監督である。アイシュワリヤーとも過去に「Jeans」(1998年)で仕事をしている。プロデューサーはカラーニディ・マーラン。タミル・ナードゥ州を中心に展開するテレビ局サン・ネットワークの会長で、同時に新聞社やラジオ局も経営するインドのメディア王である。民間航空会社スパイスジェットも傘下にある。また、彼はタミル・ナードゥ州の現州首相カルナニディの血縁に当たる政治家家系生まれであることにも注目。タミル映画界でインド映画史上最大予算の映画制作が可能だったのは、プロデューサーが握るこの絶大な権力と財力のおかげだと考えても間違いではないだろう。
音楽はグラミー賞・アカデミー賞受賞の音楽家ARレヘマーン。作詞は、ヒンディー語版はスワーナンド・キルキレーになっているが、タミル語版やテルグ語版では異なっている。ヒンディー語版の台詞もスワーナンド・キルキレーが担当した。サウンドデザインは「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)でARレヘマーンと共にアカデミー賞を受賞したラスール・プークッティー。他に、裏方でハリウッドの人材が活用されている。スタント・アクションは「マトリックス」シリーズや「キル・ビル」シリーズで知られる袁和平(ユエン・ウーピン)、コスチュームデザインは「メン・イン・ブラック」(1997年)のメアリーEヴォクト、アニメーションと特殊メイクは、「アバター」(2009年)のスタンウィンストン・スタジオが担当している。
本当はタミル・ナードゥ州の映画館でタミル語オリジナル「Enthiran」を見るのが最大限にこの映画を楽しむ正しい方法であり、この映画の公正な評価もその方法を採った上で初めて可能となるであろうが、一応参考までにヒンディー語吹替版「Robot」を見た感想を、いつもの映画評の形式で記しておく。
題名:Robot
読み:ロボット
意味:ロボット
邦題:ロボット
監督:シャンカル
制作:カラーニディ・マーラン
音楽:ARレヘマーン
歌詞:スワーナンド・キルキレー
アクション:袁和平
衣装:マニーシュ・マロートラー、メアリーEヴォクト
出演:ラジニカーント、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン、ダニー・デンゾンパ、カルナス、シャーンタラーム、デーヴァダルシニー、カラーバヴァン・マニ、コーチン・ハニーファー、サブ・キリルなど
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。
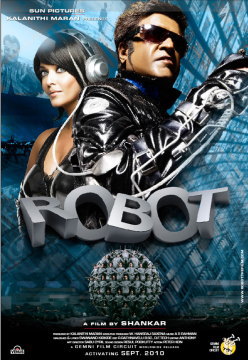
アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン(左)とラジニカーント(右)
| あらすじ |
ロボット工学の科学者ワシーカラン(ラジニカーント)は10年の歳月を費やし、人間と同様の動きをし、かつ人間以上の能力を秘めたロボットの開発に成功する。そのロボットはワシーカランに瓜二つであり、彼の母親にチッティー(ラジニカーント)と名付けられた。ワシーカランはチッティーを軍に配備し、戦争や紛争で死人が出ないようにすることが夢であった。その前にまずは人工知能研究機関であるAIRDから認可を受けなければならなかった。AIRDのトップは、かつてワシーカランにロボット工学を教えたボーラー教授(ダニー・デンゾンパ)であった。
ところでワシーカランにはサナー(アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン)という恋人がいた。サナーは大学で医学を学んでいたが、最近ワシーカランがロボットの開発に没頭して全く相手をしてくれなかったので怒っていた。しかし、サナーはチッティーを見てすっかり気に入ってしまう。チッティーはサナーの勉強を手助けしたり、暴漢から守ったり、大活躍であった。
ワシーカランは学会でチッティーを発表する。学者たちからは絶賛を受けるが、面白く思っていない人物が1人いた。それはボーラー教授であった。ボーラー教授もロボットの研究に昼夜没頭していたが、なかなか成功しなかった。ロボットの開発に重要なのはニューラル・スキーマであった。ボーラー教授はニューラル・スキーマの情報を引き出そうとするが、やはりワシーカランも最重要機密情報としており、ボーラー教授にも明かそうとしなかった。ボーラー教授がロボットの開発を急いでいたのは、影でテロリストに戦闘用ロボットの売却を約束していたからであった。失敗を繰り返したボーラー教授は、やがてテロリストから脅されるようになる。
ワシーカランはまず、AIRDから認可を得ようと、チッティーの能力を披露する。だが、審査委員会の長を務めるボーラー教授は、チッティーの戦闘力が味方にとっても脅威となり得る弱点を巧みに引き出し、認可を却下する。その帰り、ワシーカランは火事の現場に出くわし、チッティーに人々の救出を命令する。チッティーは次々に囚われた人々を救い出す。その様子はテレビで報道され、チッティーの救命能力の格好のアピールとなった。ところが、人間の尊厳などを理解しないチッティーは、裸の女性までもそのままの姿で助け出してしまい、彼女を公衆の面前にさらしてしまう。命を救われた女性もその恥には耐えきれずに自暴自棄になってしまい、その結果自動車に轢かれて死んでしまう。
ボーラー教授はワシーカランに、チッティーに人間の感情を理解し、人を思いやる感情が備わらない限り、AIRDの認可は与えられないと困難な課題を課す。ワシーカランはチッティーに人間の感情を理解するプログラムをセットしようとするがうまく行かない。だが、ある日落雷を受けたチッティーは、そのショックで人間と同様の感情を宿すことになる。チッティーは、熟練の産婦人科医が匙を投げるような難産を、ハイテクを駆使しつつ妊婦の感情を配慮しながらやり遂げ、その新能力をアピールする。おかげでボーラー教授もAIRDの認可を与えざるをえなかった。だが、そのときボーラー教授は新たな勝算を直感していた。
感情を持ったチッティーは、やがてサナーに恋するようになってしまう。次第にワシーカランの命令にも従わなくなる。ワシーカランはサナーの誕生日パーティーに彼女との結婚を公表するが、チッティーはサナーと結婚するのは自分だと主張し出す。ワシーカランは軍の幹部の前でチッティーの能力を証明し、夢を実現しようとするが、チッティーはそれに背き、戦闘能力を披露する代わりに詩を朗読し始める。軍の幹部からは失笑を買い、ワシーカランは大恥をかく。怒ったワシーカランはチッティーをバラバラにし、捨ててしまう。
ボーラー教授はバラバラになったチッティーをゴミ捨て場から見つけ出し、ニューラル・スキーマを入手して修理した後、大量殺戮プログラム「レッドチップ」をセットする。チッティーは完全なるターミネーターとして生まれ変わった。新生「チッティー・バージョン2.0」はワシーカランとサナーの結婚式に乗り込み、サナーを連れ去ってしまう。
それ以降、街中に複数のチッティーが出没し、日用品から石油まで、あらゆるものを強奪し始める。チッティーはボーラー教授を殺害し、自らを増産し始めたのだった。そしてAIRDのオフィスを占拠し、そこにロボット王国を打ち立てた。しかもチッティーは、サナーの子宮にロボット受精卵を移植し、世界初の「ロボ・サピエンス」を誕生させようと画策していた。
一方、ワシーカランは軍隊と協力し、チッティー破壊を計画する。まずワシーカランはチッティーそっくりの容貌となり、破壊したチッティー・コピーのIDを装着して、チッティーの城に乗り込む。そして囚われの身のサナーと会い、チッティー破壊作戦の手順を説明する。それは街中の電力を落とし、チッティーとその無数のコピーたちをバッテリー切れにする作戦であった。サナーはチッティーを誘惑して気を引き、その間に軍は街中を停電にして様子を見た。だが、チッティーとコピーたちは自動車のバッテリーから電源を供給し始めた。この作戦が失敗したことで後は強行突破しかなくなり、コマンドー部隊がチッティーの城に突入する。その隙を突いてワシーカランはサナーを連れて逃げ出す。
チッティーとコピーたちはマグネットパワーを利用して合体し、様々なフォーメーションを組んでコマンドー部隊を翻弄した。ワシーカランはコンピューターウイルスを送り込んだり、マグネットパワーを無効化したりして、チッティーとコピーたちを無力化しようとするが、チッティーたちの圧倒的パワーの前にはほとんど効果がなかった。だが、最終的にはチッティーのボディーから元凶のレッドチップを引き抜くことに成功する。
開発したロボットが街に多大な損害をもたらしたことでワシーカランは罪に問われ、裁判にかけられる。一旦は死刑が宣告されそうになるが、正常に戻ったチッティーが異議を申し立て、ロボット=道具による傷害や破壊は殺人などではなく、事故であると主張する。また、チッティーにレッドチップを埋め込んだのは死んだボーラー教授であることも証明する。それによりワシーカランは無罪放免となる。だが、裁判官は代わりにチッティーの解体を命令する。ワシーカランは涙ながらにチッティーに自己解体を命じ、チッティーは皆に別れと感謝の言葉を告げながら自らをバラバラにする。「私はロボットで良かった。レッドチップを抜き取ることが出来るのだから。だが、人間に埋め込まれたレッドチップは抜き取ることが難しい」というメッセージを残しながら・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ハリウッドにはロボット映画の長い伝統があり、ひとつのジャンルとして確立している。「2001年宇宙の旅」(1968年)、「ブレードランナー」(1982年)、「ターミネーター」(1984年)、「ロボコップ」(1987年)、「アンドリューNDR114」(1999年)、「A.I.」(2001年)、「アイ,
ロボット」(2004年)、「トランスフォーマー」(2007年)、「Wall・E/ウォーリー」(2008年)などがその代表作として挙げられるだろう。さらに、我らが日本では、アニメにおいてロボットが人気のテーマとして根付いており、ロボット(またはそれに似たもの)が登場するアニメには、「鉄腕アトム」、「ドラえもん」、「キテレツ大百科」、「Dr.スランプ アラレちゃん」、「機動戦士ガンダム」、「超時空要塞マクロス」、「鉄人28号」、「マジンガーZ」、「ヤッターマン」、「トランスフォーマー」、「機動警察パトレイバー」、「攻殻機動隊」、「新世紀エヴァンゲリオン」など枚挙に暇がない。まだドラえもんのようなロボットは開発されていないが、少なくとも日本人の多くはそれらの作品を通してロボットに慣れ親しんでいると言えるだろう。しかし、インド映画では、ロボットはまだそれほど開拓されていない分野であった。「Love
Story 2050」で少し出て来たのが記憶にあるぐらいだ。だから、ロボットをテーマにしたインド映画「Robot」が一体どんな感じの映画になるか興味があった。結論から先に言えば、見終わった後に「やはりロボット映画をもインド映画的にうまく料理してしまったか」という強力な脱帽感を感じた。「Koi...
Mil Gaya」を見終わった後の感覚に近い。いや、それ以上か。「Robot」は、タミル語映画の中でも特に独特の特徴を持ち、1ジャンルとして成立しているラジニカーント映画ということもあったが、それ以上にインド映画の王道をひたすら突っ走る潔さが心地よかった。ヒンディー語映画界からは「Dabangg」が生まれたが、タミル語映画界からも強力なレスポンスが返って来た。逆に言えば、「Dabangg」のクッションがなかったら、「Robot」からはさらに大きな衝撃を受けていたに違いない。

「Robot」は、言わば今までハリウッドなどで作られて来たロボット映画のおいしいところを全部まとめてひとつの映画に詰め込んでしまったような作品である。インド映画の感想でよくこういう言い方を見るが、一言で言ったらそう評価するしかない。前半では、圧倒的な計算力、暗記力、戦闘力を持ち、人間を献身的にサポートするロボット像が描かれる。ヒロインのサナーは、恋人ワシーカランの開発したチッティーの能力を使って試験を切り抜けようとするが、この辺りは「ドラえもん」にも似ている。だが、チッティーには人に言われたことを真に受ける弱点もあり、それでいくつものお約束的な笑いを取っていた。中盤では、ロボットが感情を持ったらどうなるか、という、これまたロボット映画によくありがちな問いが映像化される。「Robot」では特にロボットに恋愛感情が生まれるという点が強調され、チッティーがサナーとの結婚を熱望するという面白い展開になる。だが、その熱望は、ロマンス映画の方向ではなく、アクション映画の方向へとストーリーを押しやる。ワシーカランに破壊され、破棄されたチッティーは、テロリストと密通したボーラー教授によって修復され、しかも大量殺戮プログラムを組み込まれる。こうしてチッティーはインド史上最凶最悪の悪役として生まれ変わる。ロボットが人間に反抗するストーリーもロボット映画の定番である。チッティーはサナーを誘拐し、ボーラー教授を殺害しただけでなく、サナーの子宮を使って「ロボ・サピエンス」を生み出そうとする。これは、チッティーが人間と比べて引け目に感じていた「生殖」というコンプレックスを克服するための手段でもあった。このロボットの生殖、もっと言えばロボットの性欲をストーリーに組み込んだのは新しい点かもしれない。そしてコマンドー部隊の突入を受けたチッティーは、自ら複製したコピーたちと合体し、巨大ロボに変身する。ここに至って映画は巨大ロボ物の要素まで持つことになる。チッティーの最期はまた寂しいものだ。「現代の人類にはまだチッティーのようなロボットを使いこなす能力がない」と判断した裁判官は、チッティーの解体を命じる。そしてチッティーは粛々とそれを受け容れ、自己解体する。この終わり方は「ターミネーター2」(1991年)のエンディングを思わすものであった。

馬鹿馬鹿しいまでに娯楽に徹した映画であったが、一応メッセージも込められていた。それは人間の悪意への警鐘である。チッティーは「レッドチップ」という悪意を埋め込まれたせいで殺人マシーンと化してしまったが、そのチップを取り外したことで正常に戻った。だが、一旦人間の脳裏に悪意が埋め込まれてしまうと、そう簡単にそれを取り出すことは出来ない。ロボットも所詮道具であり、それは使う者の善意と悪意によってプラスにもマイナスにも結果をもたらすことになる。そして道具の力が強ければ強いほど、使う者の善意は試されることになる。映画の中で一貫して主張されていたメッセージはこれであり、最後にチッティーの口からそれが明確に語られることになる。もっとも、SF映画というのは基本的に文明批判である訳だが。

チッティー・バージョン2.0
あと、チッティーの弱点は、頻繁にバッテリーを充電しなければならない点である。おかげでチッティー(バージョン2.0を含む)は何度かピンチに陥る。この比較的アナログな問題は、現代人が直面する携帯電話のバッテリーチャージ問題を連想させた。しかし、ここまで超絶パワーを持ったロボットに、太陽光発電とか、自律的な発電機能を付けなかったのは一応突っ込み所になり得る。軍用にするにしても、この電源問題はかなり大きな問題になり得るだろう。

マチュピチュでのダンスシーン
ラジニカーントは今回、科学者ワシーカランとロボットのチッティーという一人二役だが、チッティーは一旦破壊され、殺人マシーンとして生まれ変わるため、事実上一人三役だと言える。ワシーカランを演じたラジニカーントは抑え気味の演技であったが、チッティーではかなり彼の味が出ており、特に殺人マシーンと化した「チッティー・バージョン2.0」では水を得た魚のように自由奔放な演技をしていた。それぞれ良かったのだが、やはり「チッティー・バージョン2.0」が一番好きだ。ヒンディー語の台詞をラジニカーント自身がしゃべっていたかどうかについては不明である。ちなみにこの俳優の名前はデーヴナーグリー文字では「ラジニーカーント」となっている。だが、タミル文字では「ラジニカーント」であり、もっと正確に書けば「ラジニガーント」になる。ここでは「ラジニカーント」を採用している。

アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンはいつになく活き活きとした演技をしていた。ヒンディー語映画界ではあまりコテコテの娯楽映画に出演しなくなってしまったのだが、「Robot」の彼女からはなぜか、デビュー直後のような初々しさや思いっきりの良さが感じられた。ロボットというテーマに合わせてヘンテコなコスチュームに身を包んで踊っているシーンもある。また、「3
Idiots」(2009年)で45歳ながら大学生役を演じたアーミル・カーンのように、今回アイシュワリヤーは既に37歳ながら博士課程の女学生役を演じている。つまり20代後半ぐらいの女性と考えていいだろう。30代後半になって20代女性の役は多少無理があるかと思ったが、「Robot」の彼女はどこか若返っているような気さえした。そういえば「Robot」の撮影は2008年から2010年の2年に渡って行われたため、シーンによっては2年前の彼女を見ていることになる。しかし、それが理由でアイシュワリヤーからそういうピチピチしたオーラが出ている訳ではないと思われる。やはりラジニカーントとの共演や、ラジニカーント映画の独特の雰囲気が彼女をそう見せているのだと思う。ちなみに、ヒンディー語吹替版における彼女のヒンディー語の台詞は彼女自身が吹き込んでいたと思われる。

意外な配役はダニー・デンゾンパである。ヒンディー語映画界で悪役や脇役で登場することの多いスィッキム系の俳優であり、東洋顔をしているので東洋人の役を演じたりもできるのだが、おそらくタミル語は出来ないはずで、タミル語映画出演はかなり思い切った配役だと感じた。演技力はある俳優なので、演技自体は悪くなかった。
音楽はARレヘマーン。「Robot」の音楽には少し詳しく触れたい。まず、やはりARレヘマーンの作曲能力が光る。最近、彼が作曲した英連邦スポーツ大会(CWG)テーマソングが不人気で、才能の枯渇を問われたり、高額な報酬に疑問の声が上がったりしているが、「Robot」の音楽を聴く限り、彼がインドにおいて依然として最先端を行くトップクラスの作曲家であることは否定のしようがない。元々メカっぽい音作りが得意だったので、ロボットをテーマとしたこの映画の曲にこれ以上適任な人物はいない。
どれも一癖も二癖もある曲ばかりなのだが、まず一番印象的なのは「Boom Boom Robo Da」であろう。重低音が心地よく、いかにもARレヘマーンと言った感じのノリノリの曲だ。歌詞の中にニュートンやアインシュタインと共にホンダのアシモの名が入っているような気がする。また、「おお、新人類よ」という意味の「O
Naye Insaan」は、いかにもSF映画といったミステリアスな雰囲気の曲だ。ダンスナンバー「Kilimanjaro」は、ペルーのマチュピチュで撮影されているにも関わらず、「キリマンジャロ」と「モヘンジョダロ」で押韻するという荒技が使われており、面白い。また、南米っぽいバックダンサーが多数登場してアイシュワリヤーと踊る。変な動物もわざとらしく背景で佇んでいたが、アルパカであろうか。「Naina
Miley」はハイテンポのダンスナンバーだが、冒頭19秒辺りで「アリガトウゴザイマス」という日本語が入っていきなり驚かされる。しかしこの「アリガトウゴザイマス」は、ストーリー、ダンス、映像などとは何の脈絡もない。ARレヘマーンはかつて「One
2 Ka 4」(2001年)という映画で「Osaka Muraiyua」という曲を作っている。これは「大阪村井屋」とされているが、全くナンセンスなフレーズとして使われている。それを思わせる日本語の使い方だ。日本にもファンが多いラジニカーントの映画であるため、やはり日本市場を念頭に置いたサービスだろうか?ちなみに映画中にはもうひとつ日本向けサービスがある。チッティーのモーターは、架空日本企業「ハヤタ」製という設定であり、映画中の台詞の中でもそれがはっきりと出て来る。
予算の40%を費やしたとされる特殊効果(CG、特殊メイクなど)は、まだハリウッド映画と比べて稚拙さが残るものの、インド映画最高レベルと評価していいだろう。そして何と言ってもその使い方に、ハリウッド映画にはあまりない粋さがあり、大いに楽しめる。特にクライマックスのチッティー合体はいろいろな意味で圧巻である。また、ラジニカーントのメイクだけでも3千万ルピーが費やされたと言う。
映画はチェンナイを主な舞台としているが、いくつか特徴的なロケ地の風景が使われている。筆頭はペルーの世界遺産マチュピチュ。マチュピチュでインド映画のロケが行われたのは初のことだと言う。ただ、マチュピチュが使われるダンスシーンの曲名は「Kilimanjaro」である。他に序盤のダンスシーン「Pagal
Anukan」で使われた風景も印象的であった。砂漠に真っ青な湖や河があるのだ。これはブラジルのどこからしい。後はヒマーチャル・プラデーシュ州やゴア州でも撮影が行われたようだ。
「Robot」は元々タミル語映画だが、今回はヒンディー語吹替版を見たため、隅々までかなり理解することが出来た。ヒンディー語版とオリジナルのタミル語版の間で大きな違いはないはずである。ただ、画面にヒンディー語(デーヴナーグリー文字)が使われるシーンがいくつかあった。そのシーンはおそらく言語ごとに違う文字が使われているのではないかと予想される。
「Robot」は、日本でも知名度の高いラジニカーントの最新作。インド映画史上最大の予算をかけ、ハリウッドの技術陣をも動員して作られたインド製ロボット映画であり、一瞬たりとも観客を飽きさせない、娯楽のマシンガンのような作品である。ヒロインのアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンもいつになくハッスルしている。音楽、ダンス、ダンスシーンのロケ地も申し分ない。これは本気でインド娯楽映画の最高傑作、今年必見の一本。ヒンディー語が分かる人にはやはりヒンディー語吹替版「Robot」を勧めるが、タミル語が分かる人を含めてそれ以外の人はオリジナルの「Enthiran」を見るべきであろう。
最近の日記で何度も言及して来たが、デリーは第19回英連邦競技大会(CWG)のホスト国となっていた。2010年10月3日~14日の開催に合わせ、かなりスロースタートだったものの、特に今年に入って急ピッチで準備が進められて来た。最優先なのはスポーツ競技が行われる各種競技場、開会式・閉会式が行われるジャワーハルラール・ネルー・スタジアム(JLNスタジアム)、選手や関係者が宿泊する選手村の建築と整備であったが、その他にも各種インフラの整備が進められており、フライオーバーの建設、インディラー・ガーンディー国際空港第3ターミナルの開港、デリー・メトロの路線拡大、ローフロア・バスの導入などが行われて来た。開催期間中にデリーを訪れる内外の観光客にアピールするため、文化コンテンツの充実も勧められた。例えばデリー中の主要な遺跡がリノベーションされている。
ちなみに、日本は英連邦の加盟国ではないのでCWGとも関係がなく、日本ではCWGの知名度はかなり低い。だが、参加国・地域の数はアジア競技大会よりも多く、総合競技大会としてはオリンピックに次ぐ規模のスポーツ祭典となっている。デリーは1951年と1982年にアジア競技大会のホスト国となっており、特に1982年のアジア競技大会はデリーの発展にとって大きな分岐点となった。しかし、その後総合競技大会とはしばらく縁のない時期が続いた。21世紀に入り、アジアの大国として双璧を成す中国が北京五輪のホスト国となったことで、中国の発展を追うインドもオリンピック開催を狙うようになり、五輪へのステップとして、デリーがCWGのホスト国に名乗りを上げることになった。CWG開催実績は、デリー五輪実現のために有利な判断材料となることは必至で、その成功は不可欠であった。
しかし、CWGデリー大会は負の面でニュースになることが多かった。工事の遅れ、設備の低品質さ、運営委員会(OC)の汚職、巨額の無駄遣いなどが次々に明るみに出て、連日CWGの責任者たち――OC会長スレーシュ・カルマーディー、デリー州首相シーラー・ディークシト、スポーツ大臣MSギル、都市開発大臣ジャイパール・レッディーなど――は矢面に立たされて来た。おまけに天候までCWG運営者に味方しなかった。北インドは大体6月~9月が雨季になっている。北インドではここのところずっと雨季の雨が不安定で旱魃に近い状態が続いて来たのだが、今年は例年に比べて雨量が多く、モンスーンの後退も遅かった。8月~9月にかけてデリーに降った大雨は、ただでさえ遅れ気味だった工事をさらに遅れさせた。デリーがCWGホスト国に決定したのはインド人民党(BJP)率いる国民民主連合(NDA)政権時であったが、具体的な準備を進めて来たのは国民会議派率いるUPA(統一進歩連合)政権に入ってからで、CWGの不手際はそのまま国民会議派にとっての失点となった。最近行われたデリー大学学生自治会選挙では国民会議派下部組織学生団体NSUIが惨敗し、CWG効果と噂された。ここのところデリー州政府は3期連続で国民会議派が勝っているが、次期選挙では苦しい戦いを強いられるのではないかとの予想もある。CWGテーマソングを担当したARレヘマーンもCWGの負のオーラを覆すことが出来なかったばかりか、アカデミー賞やオスカー賞と言った国際的な賞を受賞し、インド人の間で絶大な尊敬を集める彼にとっておそらく初めて、創造性に関する部分で国民の批判を浴びることになった。彼の作曲したテーマソングは大部分のインド人に好まれず、彼が受け取ったとされる5,500万ルピーの報酬も「高額すぎる」「国のためにただで引き受けるべきだった」と非難材料となった(参照)。CWGに関わる人々の運気は軒並みダウンとなり、CWG期間中デリー脱出を宣言する人々も続出した。国民会議派のベテラン政治家マニシャンカル・アイヤルはCWG批判の急先鋒で、CWG期間中にデリーを脱出することを宣言したばかりでなく、「CWGが成功したら私は嬉しくない」という主旨の発言までした。
それでも、CWGを開催するにあたり最低限必要な施設の工事は、日が近付くにつれて徐々に何とか完成と言えるだけのものとなって行った。しかし、CWG直前に、参加者・関係者はもとより、全インド人が不安のどん底に突き落とされるような3つの事件が起こった。ひとつは選手村の常軌を逸した不衛生さである。ヤムナー河河畔に建造された選手村は9月23日にオープンしたのだが、到着した外国人選手たちが「とてもじゃないが住めない」と苦情を出し、入村を拒否したのである。その後、選手村の住居の写真がすっぱ抜かれたが、そこに映し出されていたものは、インド人であっても住みたくないような地獄絵図であった。また、折からの雨のせいで住居の地下部分は湖になっており、デング熱などの伝染病発生も心配された。

CWG選手村住居の写真
もうひとつは、開会式と閉会式の会場となっているJLNスタジアムの近くで建設中だった歩道橋の崩落である。これは6万人収容のこのスタジアムへ観客を誘導するために重要な吊り橋で、10月3日の開会式に合わせて最後の仕上げが行われていたのだが、9月21日に突然崩落してしまい、作業中だった労働者たちが多数負傷した。

崩落した歩道橋
後ろに見えるのがJLNスタジアム
みっつめは、9月19日にオールドデリーのジャーマー・マスジドで起こった銃撃事件である。バイクに乗った2人組の男による銃撃により、台湾人取材クルー2人が負傷し、病院に搬送された。その後、今までデリー、ジャイプル、アハマダーバード、プネー、バンガロールなどのテロ事件に関与して来たとされるテロ組織インディアン・ムジャーヒディーンが犯行声明を出し、CWG中にテロを行うことを宣言した。
これら3つの事件は、前々から根強かったCWGの成功への疑念をさらに強めることになった。一応選手村は民間会社の力を借りて集中的に清掃が行われ、歩道橋も軍隊の力を借りて6日間で仮設の橋が建造された。しかし、ジャーマー・マスジド銃撃事件の犯人はまだ捕まっていない。それに加えて、60年以上係争中の、ウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーのバーブリー・マスジド跡地・ラーム生誕地寺院建設予定の所有権に関する裁判の判決が9月30日に出された。この問題は1992~93年にかけてインド全国でヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間でコミュナル暴動を引き起こした経緯があり、細心の注意を払わなければならない。よりによってその重要な判決がCWG直前に出されることになっただけでも不安要素だったが、判決は多くの識者の予想を超えるほどにヒンドゥー教徒側に圧倒的に有利なものとなり、コミュニティー間で緊張が走った。
これら様々な不安要素のせいで、健康面や安全面などを懸念してCWG参加を個人的に取り止めるスポーツ選手も出て来たのだが、参加予定とされていた71ヶ国・地域の中に国・地域として参加をキャンセルするところは幸いひとつもなく、開催日前までに全ての国・地域の代表団がデリーに到着した。ひとまず参加予定国の全参加が成功の試金石とされていただけに、運営側はホッと胸をなで下ろしたに違いない。
さて、このCWGであるが、デリー市民の一人としてかなり前からとても楽しみにしていた。ここ数年間、デリーがこのイベントを目標にして発展して行っているのが目に見えて分かったため、少なくともCWGまではデリーに滞在したいと考えていた。愛するデリーの晴れ舞台をこの目で目撃したいと心から願っていた。CWGが近付くにつれてネガティブな情報も随分出て来て、長年の熱情にも幾分冷や水を浴びせられることになったのだが、それでもCWGを目撃するという意志に変わりはなかった。
CWGを目撃するにあたって、やはり何より重要となるのは開会式である。10月3日午後7時~9時まで、JLNスタジアムで行われる開会式は、CWGが成功か失敗かを予想し、判断する大きな材料となる。この開会式に行くことがとりあえずの目標であった。チケットは高価で、4つのカテゴリーがあり、一番高いAが50.000ルピー、Bが25,000ルピー、Cが5,000ルピー、Dが1,000ルピーとなっている。さすがに5万ルピーや2万5千ルピーを払う気にはなれないので、僕はチケット現物が発売された9月初めにCを購入した(オンライン予約は6月に始まっていた)。ちなみに、通常競技のチケットは100~1,000ルピーの、より手頃な値段設定となっている。
開会式を鑑賞するにあたって、ネットを駆使してかなり情報収集をした。主に懸念だったのは、どうやってJLNスタジアムまで行くか、という点と、カメラを持って行くか否か、という点である。
JLNスタジアムまで行く方法については、開会式前日や当日の新聞にかなり詳細にスタジアム周辺の道路規制について情報が掲載されていたため、そんなに迷うことはなかった。開会式当日にはスタジアム周辺の広範なエリアは道路封鎖され、自家用車などでスタジアムへ行く人は、かなり遠くに用意された駐車場に駐車して、そこからバスでスタジアム近くまで搬送され、そこからさらに数km歩かなければならなかった。それを考えると、バイクで会場へ行く手段は賢明ではなかった。もっとも簡単にスタジアムにアクセスする方法はデリー・メトロであった。JLNスタジアム最寄り駅はJLNスタジアム駅またはジャングプラー駅で、そこからならかなり短い距離を歩くだけでスタジアムに辿り着くことができる様子であった。入場ゲートはいくつかあったが、チケットにはゲートの指定もあり、そのゲートによってJLNスタジアム駅で下りた方がいい場合と、ジャングプラー駅で下りた方がいい場合があった。僕の購入したチケットは第14番ゲートとなっていたので、そのゲートにもっとも近いJLNスタジアム駅を利用することにした。
ところで、このJLNスタジアム駅やジャングプラー駅は、デリー・メトロの最新路線であるバイオレット・ライン上に位置している。このバイオレット・ラインはなんと開会式当日の午前8時に開通という、とんでもないギリギリズムであった。この路線が開通しないことには、デリー・メトロでJLNスタジアムへ向かうことがかなり困難になってしまう。一応、既に開通済みのイエロー・ライン上ジョールバーグ駅から、バスと徒歩でスタジアムへ向かうという代替手段はあり得たが、6万人の観衆の大半がメトロでスタジアムに来ることを考えると、全くもって現実的なオプションではなかった。よってバイオレット・ラインの開通は必須であった。
実は僕の住むカールカージーもバイオレット・ライン沿線に位置しており、このラインが開通すれば、ネルー・プレイス駅、カールカージー駅、ゴーヴィンドプリー駅などからJLNスタジアム駅まで一本で行くことが可能であった。午後2時からスタジアムのゲートが開き、入場が可能となると聞いていたので、午後2時少し前にネルー・プレイス駅まで行って様子を見てみた。するとメトロは無事運行しているようだったので、メトロでスタジアムまで向かうことにしたのだった。ちなみに、CWGチケットにはメトロ乗車無料券が付いていおり、メトロでの移動が促進されている。
しかしネルー・プレイス駅はまだ未完成のまま操業していた。まるで戦争で破壊されたかのような状況である。しかしネルー・プレイス駅からはロータス・テンプルやISKON寺院などがよく見渡せ、すばらしい景色であった。開通したばかりのこのラインはまだ不安定な運行で、途中で電車が止まったりしたが、大きな問題なくJLNスタジアム駅まで行くことが出来た。後日の新聞によれば、このラインはずっと安定しなかったようで、1時間ほど運行が停止したりして、開始時間の直前にメトロで会場へ向かった人の中には、開会式の開始に間に合わなかった人もいたようだ。それを考えると早めにスタジアムへ向かったのは正解だった。
もうひとつの懸念は、カメラの持ち込みは可能かという点であった。入場に5,000ルピーも払ったので、記念のために写真撮影ぐらいはしておきたいという当然の感情があった。CWGのパンフレットに記載された持ち込み禁止アイテムリストには、ハンディカムは含まれていたもののスティルカメラは含まれておらず、持って入れるだろうという楽観的な予想をしていた。だが、ちゃんとそこには、「状況に応じて持ち込み禁止アイテムを追加することもある」との注意書きもあった。また、前述の通り、CWG直前にテロと見られる事件が起きたり、CWG妨害を目的としたテロの予告があったりして、警戒態勢はより引き締められた。CWG公式ウェブサイトをチェックしてみたら、2つの異なる情報を掲載していた。あるページでは持ち込み禁止アイテムリストの中にカメラが含まれておらず、FAQでもスティルカメラの持ち込みは許可すると明記されていた。だが、別のあるページでは持ち込み禁止アイテムリストの中にちゃんとカメラが含まれていた。直前にCWGの公式FacebookやTwitterでカメラの持ち込みについて情報収集したところ、カメラ付き携帯電話の持ち込みは可能だが、カメラは持ち込み禁止となったとの情報が得られた。情報源はCWGボランティアを自称する人物だったので、かなり正確な最新情報だと判断できた。よって、カメラを持って行くことは諦めたのだった。ついでに携帯電話も財布も何も持って行かなかった。持って行った物は、お金とIDカードのみであった。それでも入場時には服をまくられたり紙幣を1枚1枚見せさせられたりしてかなり厳重にチェックされ、装着していた腕時計(カシオのプロトレック)まで念入りに検査された。
セキュリティーチェックでカメラを没収されたりしたら嫌だったのでここまで神経を使ったのだが、会場に入ってみたら、案外カメラを持ち込んでいる人が多くてガッカリした。会場にいたボランティアに聞いてみたら、やはりカメラ持ち込み禁止のお触れが出ていたようなのだが、どこかの時点でなし崩し的に許可されてしまったようである。しかしスタジアムでのショーを、コンパクトデジカメで綺麗に撮影するのは困難であるし、今更悔いても仕方ないので、ショーをしっかり目に焼き付けることにした。そういえば2004年にコールカーターで行われたFIFAワールドカップ予選インド対日本戦を観戦しに行ったときも(参照)、カメラを会場に持って行くかどうかで悩んだ。チケットにははっきりと「カメラ持ち込み禁止」と明記されていた。だが、悩んだ末に持って行った。そうしたら結局ノーチェックで会場に入れた上に、日本人だったらチケットがなくても入れたのではないかというほどザルのセキュリティーで驚いた。さすがに今回はかなりしっかりとしたセキュリティーが敷かれていたが、ちゃんと下調べして来た人にアンフェアになるような状況は出来れば避けてもらいたいものである。
しかしながら、後日新聞でCWG開会式関連の記事を読んでいたら、禁止アイテムのことを知らずにビデオカメラを持ち込もうとして入場を拒否され、高価なチケットを買い、はるばるスタジアムまで来たのに、何も見ずに引き返さざるをえなくなった不幸な外国人などの話が載っており、やはり事前に情報収集しておくことは重要だと感じた。カメラを持参した場合、この人と同じ目に遭った可能性もあった訳で、それが避けられたでも良かったと言えるだろう。
CWG開会式と閉会式は全席指定席となっている。厳重なセキュリティーをくぐり抜け、自分の席を見つけて座ったときにはまだ午後3時になっておらず、会場ではまだ最後の準備が行われていた。グランドの中央部には、開会式の目玉であるエアロスタット(巨大風船)が横たわっていた。このエアロスタットは40mx80mx12mの、世界最大のもので、価格は7億ルピーとのこと。ヘリウムガスで宙に浮かんでいるが、今のところは低く抑えられていた。ところで、僕に宛がわれたのは、VIP席から見て左翼にあたる結構いい席で、VIP席も見渡せたし、グランドも斜め上から見下ろすことが出来た。もっとも不幸な席はVIP席の反対側にあたる席であろう。一応メインのショーはどこからでも楽しめるようになっていたが、基本的にパフォーマーはVIP席を向いてパフォーマンスを行うので、反対側にいた人々は損な気分になったに違いない。

世界最大のエアロスタット
(以下、写真はCWG公式サイトなどから転載)
午後7時から開始とのことだったが、午後5時過ぎからちょっとした前座が始まった。シヴァーニー・カシヤプ、アーナンド・ラージ・アーナンド、ヴィクラムジート・サーニーなどのミュージシャンたちが歌を披露し、CWGマスコットのシェーラーも登場して会場を沸かせた。この前座は1時間ほど続いた。開始時刻の午後7時になる頃にはほぼ会場は観客で埋め尽くされた。まとまった空席も見られたが、視界が悪いために敢えて空席にしている席もあったようで、ほぼ満席と言っていい状態であろう。会場には、チャールズ英皇太子夫妻、プラティバー・パーティール印大統領夫妻、マンモーハン・スィン印首相夫妻、CWG連盟(CGF)のマイク・フェネル会長、シーラー・ディークシト・デリー州首相、スレーシュ・カルマーディーOC会長、MSギル・スポーツ大臣、ジャイパール・レッディー都市開発大臣、ソニア・ガーンディー国民会議派党首、ラーフル・ガーンディー、APJアブドゥル・カラーム前印大統領などが出席していた。

CWGマスコット、シェーラー
前座では特にアーナンド・ラージ・アーナンドによるCWG非公式テーマソングが盛り上がっていたのだが、やはり前座は前座、本番に比べたら何でもなかった。さすがに「インド時間」はここでは適用されず、ショーは午後7時ジャストから始まった。秒読みを経て開始時刻を迎えると、まずは国歌斉唱があり、全員起立して「Jana
Gana Mana」を聴いた。それが終わると、シャンク(法螺貝)やシェヘナーイー(縦笛)やチベットのラグドゥン(大笛)などの音が響き渡り、世界中にCWG開会式の開始が告げられた。すると、中央部にあったエアロスタットが徐々に宙に浮かび上がり、吊り下げられた巨大な操り人形が踊りを踊り始めた。第一の演目「Puppets
from Rajasthan」である。同時に、インド各地の太鼓が勢揃いし、第二の演目「Rhythm of India」も始まった。ラダック、パンジャーブ、ケーララ、マニプル、メーガーラヤ、アーンドラ・プラデーシュ、カルナータカなどの伝統的な太鼓の奏者およそ1000人がグランドで太鼓を打ち鳴らし、さらにステージ上ではプドゥッチェリー(ポンディシェリー)準州出身7歳のタブラー奏者ケーシャヴ君が陽気にタブラーを打ち鳴らした。また、エアロスタット側面には太鼓奏者の映像が映し出されていた。

「Puppets from Rajasthan」と「Rhythm of India」
通常、操り人形は上から操るものだが、エアロスタットに吊り下げられた人形たちは下から操られていた。会場の中央にある祭壇上のステージではダンサーたちが踊りを繰り広げていた。だが、やはり操り人形の方に目が行ってしまう。動きはそんな複雑なものではなく、複数の人形同士で整合性のある動きをしていた訳でもなかったが、やはりその巨大さには目を奪われた。まだこのときまでは開会式の成功に幾ばくかの疑問を感じていたため、その内人形のどれかが落っこちたりするのではないかと内心ビクビクしていたが、そんなことはなかった。宙に浮かぶ世界最大のエアロスタットとインドの伝統芸能をうまく組み合わせたスケールの大きな演目で、とりあえず掴みはばっちりだった。この最初の演目が終わる頃には既に開会式の成功を疑う気持ちは微塵も残っていなかった。
次に歌手ハリハランが登場し、第三の演目「Swagatam」が始まった。「Swagatam」とは「ようこそ」という意味で、デリーにやって来た人々を歓迎する内容の歌をハリハランが歌った。歌も良かったが、視覚的にとても面白い効果を出していたのが、同時に行われた児童たちによるパフォーマンスであった。白い衣装に身を纏った無数の児童たちがステージの一角に集まって形を作るのだが、それだけだといまいち何のことだか分からない。だが、会場に設置された大型ディスプレイに映し出された、上空のカメラからそれを捉えた映像を見ると、女性が手を合わせた「ナマステー」の形になっているのである。赤い半円状のゲートみたいなものがあったが、それは上から見るとバングルになっていた。また、途中で児童たちの上に白い布がかぶせられるのだが、児童たちは下から赤い染料でその布を塗り出す。すると、上から見るとメヘンディーの模様になって行くのである。「ナマステー」と「メヘンディー」。またもインドを代表するモチーフが上手にパフォーマンスの中に組み込まれていた。さらに、エアロスタットには世界各国の言語と文字で「ようこそ」というメッセージが映し出されていた。

「Swagatam」
赤い物体が上から見るとバングルに見える
この後、スポーツ選手入場があった。前回CWG開催国オーストラリアから、ABC順に、国・地域ごとにスポーツ選手が入場し、グランドを1周して、グランド上にある特等席に着席した。最後はホスト国のインド入場となった。やはりインド入場のときに場内は大歓声となり、皆立ち上がって歓声を送った。だが、とても感動的だったのは、パーキスターン入場のときに同じくらい熱狂的に歓声が送られたことである。バングラデシュ、スリランカなど、他の南アジア諸国へも温かい声援が送られた。しかし一方で、聞いたことのないようなかなりマイナーな国や地域も参加しており、世界の広さを思い知った。これはオリンピックの開会式でも感じることだが。

選手入場
旗手は北京五輪金メダリスト、アビナヴ・ビンドラー
選手が全員着席したところで、マイク・フェネルOGF会長、スレーシュ・カルマーディーOC会長、マンモーハン・スィン首相などのスピーチがあった。スレーシュ・カルマーディーのスピーチのときは、観客からブーイングが出ていた。CWGを巡る混乱の最大の責任者は彼だからだ。一方、会場に来ていたアブドゥル・カラーム元大統領は依然としてインド人の間で人気で、彼の名前が呼ばれる度に、また彼の姿がディスプレイに映し出される度に、観客から歓声と拍手が上がっていた。
次にエリザベス英女王のメッセージが入ったクィーンズバトンの入場になった。クィーンズバトンは、2009年10月29日にバッキンガム宮殿を出発し、CWG加盟71ヶ国・地域を巡り、インド中を駆け巡って、先日デリーに到着した。ヴィジェーンドラ・スィン、メリー・コム、スシール・クマールなど、最近実績を挙げたインド人スポーツ選手が最後のリレーランナーを務め、スシール・クマールがチャールズ皇太子にバトンを渡した。チャールズ皇太子は女王のメッセージを読み上げ、CWGの開始を告げ、プラティバー・パーティール大統領がそれを引き継ぐ形で改めてCWG開始を宣言した。通常、CWG開始はエリザベス女王が行うことになっているのだが、今回エリザベス女王が訪印を見送ったため、チャールズ皇太子とパーティール大統領のどちらが開会宣言を行うか、ちょっとした議論になっていた。だが、結局はチャールズ皇太子がその役割を担うことになったようだ。

チャールズ皇太子とクィーンズバトン
アビナヴ・ビンドラーによる選手宣誓が行われた後、ショーが再開された。第四の演目は「The Knowledge Tree」。エアロスタット下の空洞部から木の幹に見立てた柱がニョキニョキ出て来て、エアロスタット側面に葉の模様が映し出された。グランドとステージでは、インド各地の6つの古典舞踊の群舞が同時に展開された。各舞踊はインドの6つの季節を表していると言う。オリッスィーは春、バラタナーティヤムは夏、カッタクは雨季、マニプリーは秋前半、モーヒニアッタムは秋後半、クチプリーは冬である。この演目はカッタクの巨匠パンディト・ビルジュー・マハーラージによって振り付けが行われた。

「The Knowledge Tree」
第五の演目は「Yoga」。ひとまず「知識の樹」の幹となっていた部分は引っ込み、グランド上では2000人の児童生徒たちが、スーリヤナマスカールなど、ヨーガのアーサナを組織的に披露した。そのパフォーマンスが佳境に入ると、エアロスタット下の空洞部から巨大な人型の電光模型が浮かび上がった。座禅したその人型模型の中には、6つのクンダリニー・チャクラが光り輝いていた。クンダリニー・ヨーガでは、力を下のチャクラから順に上に昇華させて行くことが実践され、一番上のチャクラを開花させることで解脱が得られると考えられている。それを示すように、下から順にチャクラが灯されて行った。

「Yoga」
第六の演目はインド鉄道プロデュースの「Great Indian Journey」。全ての演目の中でもっともカラフル、エネルギッシュ、カオティックで楽しかった。ゴージャスに飾り立てた列車を中心としたパレードで、それがグランドを一周するのだが、それとは関係なくグランド上を、インドの町や村の風景を象徴した様々なキャラクター――チャーイ屋、パーパル屋、風船屋、バングル屋、鍜治屋、牛乳屋、綿菓子屋、ダッバーワーラー、大道芸人などなど――が縦横無尽に駆け巡る。列車自体も単なる列車ではなく、様々なインドらしい部品の集合体となっていた。共和国記念日パレードとは比較にならないほど楽しいパレードであった。音楽はヒンディー語映画「Dil
Se」(1998年)のヒット曲「Chaiyya Chaiyya」。機関車の上ではTV俳優フサイン・クワージェールワーラーが踊っていた。フサインは、現在グルガーオンのキングダム・オブ・ドリームスで上演されているインド初のミュージカル「Zangoora
- The Gypsy Prince」の主演を務めている。またエアロスタット側面にはインド各地の観光地が映し出されていた。

「Great Indian Journey」
第七の演目は「Celebration」。前日の10月2日に141回目の誕生日を迎えたマハートマー・ガーンディーをテーマにしたパフォーマンスで、まずはエアロスタットの下に巨大なガーンディーのデフォルメ肖像が浮かび上がり、ステージやグランドではインド各地の様々な舞踊――古典舞踊から民俗舞踊まで――が群舞を繰り広げる。エアロスタットの側面には、「塩の行進」のイラストが子供たちの手によって徐々に描き出されて行った。また、BGMとしてガーンディーのお気に入り曲のひとつ「Vaishnav
Jan To」が流れた。

「Celebration」
最後にARレヘマーンが登場し、CWGテーマソングと、国際的な知名度を誇る「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)の曲「Jai Ho」を歌った。CWGテーマソングはずっと批判にさらされて来たのだが、最終的にはかなり多くの人に受け容れられていた感じである。しかし「Jai
Ho」の方が圧倒的な人気を誇っており、観客は一体となって「Jai Ho!」と熱唱した。

ARレヘマーン
誰もが一時はどうなることかと思ったCWGだが、この開会式は全ての不安を吹き飛ばし、全ての批判を黙らせるだけのパワーを持った、脅威のショーだった。正直言って、インドに、巨大スタジアムを舞台にしたここまで大規模のショーをオーガナイズする力があるとは思っていなかった。インドの説話の常套句を借りて言えば、まるで「ジンが一夜で作り上げた」幻のショーのようにも感じるが、そんなはずはなく、しっかりと準備を進めて来た結果のものなのだろう。しかしここまで圧倒的なショーが出来るとは!確かにボリウッド・スターのショーは世界各国で行われており、そのおかげでノウハウが蓄積されたかもしれない。最近グルガオーンにキングダム・オブ・ドリームスというアミューズメントパークがオープンし、舞台ミュージカルが上演されるようになったことも、このようなショーの下積みになったかもしれない。クリケット・リーグIPLも開会式や閉会式でかなりゴージャスなショーを行っている。だが、それらの経験をもってしても、やはりこれだけ大規模な人数と設備を駆使したショーをオーガナイズするには強力なリーダーシップと確かな技術力と強固な組織力が必要だったはずであり、1回のみ与えられたチャンスの中でここまで素晴らしいショーを世界に誇示することが出来たのは、相当な自信になったはずである。意外にもボリウッド・パワーに依存していなかったことにも好意が持てたし、何よりインドが外国に対してアピールできるものをうまく組み合わせてショーにしており、インド人にとっては誇り高く、外国人にとっては楽しい開会式になっていた。この一連のショーがオリンピックの開会式であっても全く問題なかっただろう。ずっとこの日を待ちわびていただけに、上から目線になるが、「ラルカー・バラー・ホー・ガヤー(息子が大人になった)」という喜びを感じた。1982年にデリーで開催されたアジア競技大会開会式がどんな感じだったのかは分からないが、2010年のCWG開会式は、今後確実にインドの歴史に燦然と輝くことになるだろう。その生の目撃者となれたことはとても幸運だったし、一生の想い出になるに違いない。帰る途中、群衆の誰かがこう言っていた。「20年後に『オレはCWGオープニングを見た』って自慢できるな!」まさにインド人観客の全てがその感動と誇りを噛みしめていただろう。CWG開会式はインドの現代史のひとつの転換点になるだけの潜在性を秘めており、今日JLNスタジアムでそれを目撃した観客は正に歴史の生き証人なのである。しかし20年後・・・おそらくその頃までにはデリー五輪が行われているはずである!僕は多分その目撃者にはなれないだろうが、デリー五輪開会式はさらに素晴らしいものになることを願って止まない。インドよ、君なら出来る!
本当に風向きが変わってしまった。CWG開会式を生で見た人々の感動は筆舌に尽くしがたいものがあるが、テレビで鑑賞した人々も同様に感動を受けたようで、CWGに対する評価はガラリと変化した。今までCWG運営委員会は批判の的となって来たが、CWG開会式が予想を遙かに上回る成功だったため、今度はCWGに対してネガティブ・キャンペーンをしていたメディアが人々の批判にさらされることになった。当のメディアも途端に鞍替えし、全力でCWG開会式を絶賛し出した。
ところで、開会式の翌日、チャーンドニー・チャウクのタウンホールで開催されたムシャーイラー(詩会)へ行った。これはCWG関連の文化行事、「ディッリー・セレブレイツ」の中の「ジャシュネ・ディッリー」というイベントのひとつで、最近インド最高の文学賞ギャーンピート賞受賞が決まったシェヘリヤールを筆頭に、ワスィーム・バレールヴィー、ムナッワル・ラーナー、ミラージ・ファイザーバーディー、マンザル・ボーパーリーなど、多数のウルドゥー語詩人が集って詩を披露した。午後7時から開始されたこのムシャーイラーは深夜12時まで続く熱狂振りで、大いに詩の力に酔った。ムシャーイラーには本当はヒンディー語映画界で活躍中の脚本家・作詞家・詩人ジャーヴェード・アクタルも来ることになっていたのだが、病気のため欠席だった。だが、ジャーヴェード・アクタルの不在が問題にならないほどの盛り上りを見せていた。中でも司会を務めたアンワル・ジャラールプリーという人物の詩才は飛び抜けており、彼の当意即妙なしゃべりは観客を大いに沸かせていた。ムシャーイラーでは「ジャシュネ・ディッリー(デリー祭)」ということでデリーをテーマにした詩が多く読まれたのだが、面白かったのは参加した詩人の多くがCWG開会式について言及していたことである。やはり皆その素晴らしさをただただ絶賛しており、「世界にインドの底力を見せ付けた」と愛国心を高揚させていた。他にはアヨーディヤー問題もホットなトピックであった。こういう時事ネタの詩がポンポン出て来るところは、ムシャーイラーが今でも生きている何よりの証拠であろう。そして詩人たちの詩の中でCWG開会式が絶賛されたことで、さらにその成功は歴史の1ページにおいて力強く輝くことになるだろう。
ちなみに、CWG開会式のクリエイティブ・ディレクターはバラトバーラーのようである。
2009年にオーストラリアで「カレー・バッシング」と呼ばれるインド人排斥運動が起こり、在豪インド人が次々と襲われたことは記憶に新しい。最近は時事ネタを即座に映画に採り入れる風潮が加速しており、本日より公開の新作ヒンディー語映画「Crook」はそのカレー・バッシングをテーマとしている。監督は「Woh
Lamhe」(2006年)や「Raaz - The Mystery Continues」(2009年)などのモーヒト・スーリー。先日公開された「We
Are Family」(2010年)も実は元々カレー・バッシングに関するシーンがあったようだが、最終段階でカットされたと聞く。インド人側からカレー・バッシングを映画化するとどうなるのか、興味津々で映画館に出掛けた。
題名:Crook
読み:クルーク
意味:詐欺師
邦題:クルーク
監督:モーヒト・スーリー
制作:ムケーシュ・バット
音楽:プリータム
歌詞:クマール
出演:イムラーン・ハーシュミー、ネーハー・シャルマー(新人)、アルジャン・バージワー、カヴィーン・デーヴ、グルシャン・グローヴァー、スマイル・スーリー、シェーラ・アレン、フランシス・マイケル・コーラーなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ネーハー・シャルマー(左)とイムラーン・ハーシュミー(右)
| あらすじ |
ムンバイーで生まれ育ったジャイ(イムラーン・ハーシュミー)の父親は密輸ギャングだったが、自分が密輸した爆弾がテロに使われたことを知り、警察に自首する。とある良心的な警官(グルシャン・グローヴァー)が彼を警視総監に引き合わせるが、手っ取り早い功績を求めた警視総監は彼をその場で射殺し、テロリストに仕立て上げる。ジャイはその良心的警官によって育てられたが、「テロリストの息子」のレッテルを貼られ、ぐれていった。仕方なく警官は彼に偽のアイデンティティーを与え、オーストラリアに送る。
スーラジを名乗ったジャイはメルボルンに降り立つ。空港で、奨学金を得て留学しに来たロミー(カヴィーン・デーヴ)や、オーストラリア在住インド人の相談を聞くラジオ番組のジョッキーを務めるスハーニー(ネーハー・シャルマー)と出会う。スハーニーは、兄のサマルト(アルジャン・バージワー)から、ロミーと結婚するように強要されていた。
ジャイはゴールディーというパンジャーブ人の経営するタクシー会社で働き出す。だが、折しもオーストラリアでは印パ人を狙った人種差別的暴行事件が頻発していた。ジャイ自身もその様子を目の当たりにする。だが、その過程でニコル(シェーラ・アレン)という白人女性とも出会う。ニコルはストリップバーのダンサーで、彼女の兄のラッセル(フランシス・マイケル・コーラー)はカレー・バッシングの扇動者の一人であった。
ジャイとスハーニーは次第に惹かれ合うようになって行くが、サマルトはジャイを認めていなかった。ある夜、ジャイとスハーニーがデートをしている間、ロミーが白人の暴徒に襲撃されてしまう。サマルトはジャイを殴って「二度とスハーニーに近付くな」と警告すると同時に、インド人留学生を率いて抗議運動を行う。だが、サマルトは暴力を振るったことで逮捕されてしまう。
実はサマルトとスハーニーの間には、シーナー(スマイル・スーリー)という姉妹もいた。しかしシーナーは白人との恋愛の末に妊娠し、白人を憎むサマルトによって無理矢理中絶させられた。だが、そのときシーナーは絶命してしまったのだった。
サマルトが逮捕されたことでスハーニーはジャイに助けを求めるが、ジャイは無用の争いに巻き込まれるのを嫌い、それを断る。これをきっかけにジャイとスハーニーの仲は疎遠となる。ジャイはそのままニコルと接近するが、ニコルは兄からの情報でジャイの行動を全て把握しており、サマルトの命が危ないことを教える。そのとき、留置所から釈放されたサマルトを狙い、ラッセルらが襲いかかっていた。ジャイはその場へ急いで駆けつけ、サマルトを救う。ジャイはサマルトを病院に運ぶが、昏睡状態となっていた。駆けつけたスハーニーは、ジャイに感謝する。
事件の目撃者となったジャイは、スハーニーと共に警察署を訪れる。だが、警察内部にラッセルとの密通者がいた。しかもジャイが偽のアイデンティティーでオーストラリアに来ていることがばれてしまった。ジャイとスハーニーは急いで逃げ出す。一方、昏睡状態のサマルトにもラッセルが襲撃を掛けていた。異変に気付いたロミーはサマルトを病院から運び出し、姿をくらます。
メルボルンから遠く離れた場所に身を隠したジャイとスハーニーであったが、メルボルンでは白人襲撃事件が頻発しており、その容疑者としてジャイが指名手配されていた。ニコルの働くストリップバーも焼き討ちされた。だが、それを実行していたのは意識を取り戻したサマルトとロミーであった。しかしそんなことを知らないジャイは単身メルボルンに戻り、ニコルの家に押し入る。だが、ちょうどそのときそこにはサマルトとロミーがいた。サマルトはジャイを拘束し、ニコルを誘拐する。一方、スハーニーのところにはラッセルら白人暴徒が押しかけていた。ジャイはスハーニーとニコルのどちらを助けるか迷うが、スハーニーに言われてニコルを助けることにする。
サマルトは、シーナーが死んだ場所にニコルを連れて来ており、そこで公開処刑を行おうとしていた。そこへジャイが突入し、ニコルを救出する。ジャイはサマルトの反撃を受けてピンチに陥るが、洗脳の解けたロミーがサマルトを惨殺し、ジャイは救われる。一方、ラッセルはスハーニーを襲っていなかった。ラッセルとスハーニーはその場へ駆けつける。
白人女性を救ったジャイの行動は、オーストラリアの白人とインド人の結束を強めることとなり、ジャイは一躍ヒーローとなった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
この映画は、全く異なる2つのストーリーが組み合わされてひとつの映画になっていたと言える。ひとつめはカレー・バッシングの要素、もうひとつはイムラーン・ハーシュミーに典型的な狂おし系のロマンスである。
映画中にはインド人に対する人種差別的暴行を行う白人グループが登場し、様々な事件を起こすが、意外にも映画の最終的な「悪」はインド人キャラクターのサマルトになっていた。元々の人種差別主義者はサマルトであり、彼は妹シーナーが白人との子供を身ごもったことを許さずに堕胎させ死なせてしまう。そのシーナーの恋人だったのがラッセルで、これが原因でラッセルは仲間たちと共にインド人に対し襲撃事件を起こすようになる。それに対しサマルトはインド人留学生を動員して抗議運動を起こす。ラッセルらに瀕死の重傷を負わされながらも一命を取り留めたサマルトは、白人を惨殺してさらに両コミュニティー間の亀裂を広げる。最後にサマルトはラッセルの妹ニコルを誘拐して殺害しようとする。時を同じくしてラッセルはサマルトの妹スハーニーを襲撃するが、結局は彼女に何もしなかった。サマルトはインド文化を守ることを大義名分にしてこれらの行動を起こす。サマルトはオーストラリア人に対して、「結婚前に子供を産み、誰とでも寝る」「犯罪者の子孫」などと言った偏見を持つ一方で、、インドを「数千年の歴史を持つ国」と盲目的に誇っていた。
一方、サマルトの妹スハーニーは、インド人とオーストラリア人がお互いの文化を理解し合うことが重要だと考えており、新しくオーストラリアにやって来たインド人にオーストラリア文化を紹介する活動や、オーストラリア在住のインド人の相談窓口となるラジオ番組を持っていた。
これに加え、イムラーン・ハーシュミーが得意とする、ちょっと悪だが男気があり頭の回転が速い主人公が、狂おしいほど熱いロマンスを繰り広げるストーリーが織り交ぜられる。彼の演じるジャイは、基本的にスハーニーと恋愛をするが、白人女性ニコルともホットなシーンがある。
しかし、どちらも中途半端になってしまっていたのが残念だった。まず、カレー・バッシングをテーマとしながら、その責任を全て白人側の人種差別に帰因せず、発端をインド人側にしたことは、意表を突いた脚本であった。それはそれでアイデアとして面白いのだが、元凶であるサマルトのキャラクターが非現実的で、結局現実世界で今でも起こっているインド人移民に対する暴行事件の真相に迫る努力が払われていなかったし、まとめ方も楽観的過ぎた。クライマックスでのロミーの行動(突然サマルトをスコップで殴り出す)も突発的すぎてギャグにしか思えなかった。それに、インド人観客に対してこの問題に関してインド人を悪とする脚本はインド人には受けないだろう。殊に人種差別に関わる問題にはインド人は敏感なので、普通にインド人受けするストーリーとは思えない。また、イムラーン・ハーシュミーが主導するロマンス部分も、スハーニーとの恋愛などは序盤かなり良かったのだが、最終的にはカレー・バッシングのプロットに埋もれてしまい、うやむやになってしまっていた。ニコルとの関係については全くジャイの真意が分からず、蛇足的であった。また、ニコルの際どい背面トップレスシーンやセミストリップシーンなどもあり、必要以上にヴィジュアル的色気に頼っていたこともマイナス評価となる。そもそもジャイがカレー・バッシングを解決するヒーローとなるのに、映画中で前面に押し出されていたようなずる賢いキャラである必要はなかった。
イムラーン・ハーシュミーは独特の不思議な魅力を持った男優で、最初は生理的に受け付けなくても、我慢して見ていると次第に引き込まれていくものがある。ちょっとした仕草や表情に男臭さや脆い危なさがあり、それが狂おしいロマンスにとても似合っている。「Crook」の特に序盤ではイムラーン節が堪能できるいくつかのシーンがあった。例えばスハーニーと初デートの後のシーン。ジャイはスハーニーの手を握り、「手を握っていい?」と聞く。スハーニーが「それで?」と聞くと、ジャイは「君がして欲しいと思うものをしていい?」と聞く。スハーニーが「私がして欲しいものって?」と聞くと、ジャイは「僕が口に出せないもの」と答える。この辺のやり取りはとても良かった。だが、イムラーンを主演に据えたが故にか、映画の本題からずれたシーンが多くなってしまい、結果的にはキャスティングミスと言える映画になってしまっていた。そういえば、映画のとあるシーンでイムラーンが吸血鬼っぽい格好をするのだが(下の写真)、それを見て、日本のとあるお笑い芸人にそっくりであることに気が付いた。現在休養中らしいので、イムラーンを代わりに呼んだらどうだろうか?

偶然だろうが、「Crook」では、北インド出身ながらテルグ語映画で地盤を固めた俳優が2人出演している。1人はヒロインのスハーニーを演じたネーハー・シャルマーである。ビハール州出身ながら、「Chirutha」(2007年)や「Kurradu」(2009年)などのテルグ語映画に出演し、本作がヒンディー語映画デビュー作となる。目が印象的な女優である。もう1人は最終的な悪役サマルトを演じたアルジャン・バージワーだ。2001年から「Arundhati」(2008年)など何本ものテルグ語映画に出演しており、ヒンディー語映画でも「Guru」(2007年)や「Fashion」(2007年)などに脇役で出演して来た。今回は悪役ながら物語の中心的人物であり、かなりインパクトが強かった。
音楽はプリータム。イムラーン・ハーシュミー映画にありがちな狂おしい音楽が多く、特に「Tujhko Jo Paaya」はとても心に響く歌だが、全体的に見たらパワー不足である。ちなみに映画中では「De
Dana Dan」(2009年)の「Paisa Paisa」や「Murder」(2004年)の「Bheege Hont Tere」などが使われていた。
「Crook」は、オーストラリアで問題となったカレー・バッシングをテーマにしたインド映画である。それだけ聞くと興味をそそられるかもしれないが、特に主題を真剣に扱おうとする気概は感じられず、主演のイムラーン・ハーシュミーをフルに活かしたロマンス映画にもなっていなかった。最近「Dabangg」や「Robot」など、王道娯楽映画の傑作が続いたため、それらの後に見るとさらにしょぼく映る。無理して見なくてもいいだろう。
現代インド史において、「アヨーディヤー」は決して無視することの出来ない重要なキーワードである。アヨーディヤーはインド二大叙事詩のひとつ「ラーマーヤナ」において、主人公ラーム王子の支配する街の名前とされており、神話や文学の分野でも一定の重要度を持ってはいる。だが、その重要度は現代インドの政治史、社会史、宗教史におけるものと比べたら、本末転倒だが、二次的だと言わざるを得ない。
神話に登場するアヨーディヤーと同名の町がウッタル・プラデーシュ州に存在し、一般にはそこが「ラーマーヤナ」中のアヨーディヤーと同一だとされている。アヨーディヤーにはかつて、16世紀に建造されたモスクが建っていた。ムガル朝初代皇帝バーバルの治世に建築されたとされるため、バーブリー・マスジドと呼ばれていた。平行に3つのドームを抱く、ローディー朝からムガル朝初期にかけての時期に典型的な様式の建築物だった。だが、ヒンドゥー教徒の間では、アヨーディヤーの中でもバーブリー・マスジドが建つ場所こそがラーム王子の生誕地だと長らく信じられており、19世紀頃からヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で、バーブリー・マスジドの建つ土地の所有権を巡って何度か争いがあった。それでも英領時代、モスクの建物部分はイスラーム教徒の礼拝の場、境内部分はヒンドゥー教徒の信仰の場として分割され、均衡が保たれていた。ヒンドゥー教徒は、境内に建てられたラーム・チャブータラーという祭壇にてプージャー(祭礼)をしていたようである。
両教徒の間で土地の所有権を巡る争いがヒートアップしたのは、印パ分離独立から間もなくの1949年であった。同年12月22日から23日にかけての深夜、モスク中央ドーム下にラームとその妻スィーターの像が「出現」したことをきっかけに、ヒンドゥー教徒がモスクに押し寄せるようになった。この混乱の結果、裁判所の介入によりモスク建物はロックされ、立入禁止となった。以後、モスクの土地所有権、モスクに置かれた神像の扱い、礼拝の可否などを巡ってヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で長く裁判が行われることになった。以後40年以上に渡って様々な団体や個人がこの問題に関する訴訟を行って来た。
それでもアヨーディヤーがインド全土に決定的な影響力を及ぼすことになったのは1992年になってからである。1992年12月6日、ヒンドゥー教主義を掲げる団体、政党、政治家に扇動された群衆がアヨーディヤーに押し寄せ、バーブリー・マスジドを破壊してしまったのである。この事件をきっかけにヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で一気に緊張が高まり、インド各地でコミュナル暴動が散発した。1993年3月のムンバイー連続爆破テロの遠因もこのバーブリー・マスジド破壊事件だとされている。
そのバーブリー・マスジド破壊事件とは関係なく、ラーム生誕地とされる土地の所有権を巡っては延々と裁判が続いており、今年9月30日にようやく高等裁判所の判決が出た。神像出現後の初訴訟が行われた1949年から数えておよそ60年越しの判決となる。まだ最高裁判所への上告が残っているため、確定とは言えないのだが、高裁判決は予想以上にヒンドゥー教徒側に有利なもので、イスラーム教徒コミュニティーでは衝撃が走った。簡単に言えば、係争地の3分の2をヒンドゥー教徒関連団体に、3分の1をイスラーム教徒関連団体に分割するというもので、しかも、かつてモスクの中央ドームがあった場所はヒンドゥー教徒側に宛がわれるとされた。
この裁判でまず面白いのは、人間が裁判によって神様の生誕地を認めるという、普通に考えると馬鹿馬鹿しい行為が大真面目に行われていることである。もちろん、無神論的に神様は人間が作り出した想像の産物とするならばそれは一応受け容れられるものとなるが、インドではそういう考えは稀である。まず神様は万物の創造主として認めつつ、その神様の生誕地を裁判で認定するという行為が行われていると捉えた方がより正確である。アヨーディヤー裁判におけるひとつの大きな争点だったのは、バーブリー・マスジドが建っていた場所が本当にラーム生誕地なのか、という点だった。もしラームがその土地で生まれていなかったら、その土地はヒンドゥー教徒にとって全く重要なものではなくなる。だが、本当に生まれていたのなら、宗教的に重要な場所として認定され得る。しかしそもそもラームは神話伝承上の登場人物、兼、神様が人間を救うために人間の姿で地上に降り立った化身、兼、神様自身であり、たとえ歴史のどこかで実在した人物がモデルになっていたとしても、その神話的存在がどこで生まれたのかを特定するのは不可能に近いし、それは裁判所の本来の仕事でもない。それでも高等裁判所は3人の裁判官の判決を総合し、物的証拠よりも伝承に従って、係争地はラームの生誕地だと認めてしまった。これがヒンドゥー教徒にとって有利な判決になった大きな要因のひとつである。
ところで、アヨーディヤー裁判に関して多くの人物が申し立てを行って来たのだが、訴訟の性格が同一であるため、申立人は主に3者にまとめられている。ひとつはアヨーディヤーの地元ヒンドゥー教団体ニルモーヒー・アカーラー、ひとつはイスラーム教関連公共財産管理組織スンニ・ワクフ・ボード、もうひとつは「ラーム・ララー」である。この最後の申立人は、言わばラーム王子本人となっている。これがアヨーディヤー裁判とインドの司法のもっとも面白い部分である。
インドの司法では、神様が人間と同じように裁判を争えることになっている。寺院などの土地の所有者の名前は、昔から寺院を管理する僧侶などではなく、そこで祀られている神様の名前で登録されていることが多く、神様が法人格として認められていることになる。よって、もし寺院の土地や財産などに関して争議が起こった場合、神様が裁判の当事者として扱われることとなる。神様の定義はかなり柔軟で、一定の人格を持った神様だけでなく、火や風のようなアニミズム的神様まで認められるようである。
アヨーディヤー裁判の場合、ラーム本人と言うよりも、もっと正確に言えば、「ラーム生誕地」が信仰対象として認められ、法人格として申立人扱いを受けている。そして「ラーム生誕地」という言葉のイメージから、その法人格は未成年だと認められている。アヨーディヤー裁判中によく出て来る「ラーム・ララー」という用語は「ラーム坊ちゃん」みたいな意味で、ラームが未成年であることを強調している。そして申立人が未成年であるが故に、「保護者」が代理人に立つことがちゃんと法律で許されている。アヨーディヤー裁判において、この代理人となる保護者はヒンディー語では「ラーム・サカー」、英語では「Ram's
next friend」と呼ばれており、つまりは「ラームの親友」を名乗っている。アヨーディヤー裁判が始まって以来、3人がラーム・サカーを襲名し、裁判を争い続けて来ている。初代がデーオキーナンダン・アガルワールで、1989年~2002年まで、二代目がTPヴァルマーで2002年~20010年まで、現在のラーム・サカー、トリローキーナート・パーンデー氏は3人目のラーム・サカーとなっている。ちなみに、ラームを信奉するヒンドゥー教徒なら誰でもラーム・サカーに立候補できるようだ。
このような神様を法人格として認める司法制度は、よく考えてみるとヒンドゥー教のような多神教に有利である。ヒンドゥー教では有象無象何でもかんでも、神様として崇め寺院にしてしまう傾向があるため、寺院の数だけ法人格があることになる。しかも「ラーム生誕地」のように、地理的な特徴など他の寺院と差別化が出来れば、そこでしかその祭礼は出来ないことになり、より排他的権利が強まる。一方、イスラーム教のような一神教、かつ、非偶像崇拝宗教の場合、神様を法人格として扱いにくい。イスラーム教の宗教施設と言えば第一にモスクだが、あくまで信者が集団で礼拝を行う場所で、神様の住処ではないため、モスクは神様の所有物とは認められていない。しかも、イスラーム教では礼拝はモスクでなくても出来るし、モスクが必ずその場所にある必要もない。つまり、インドでは法律的にモスクはヒンドゥー教寺院よりも弱い立場にある宗教施設だと言える。だが、イスラーム教ならではの武器もある。それは墓地である。ヒンドゥー教徒は一般に墓を作らず、墓地も持たない(ただしヒンドゥー教徒でも墓を作る一派がいるので注意)。だが、イスラーム教徒は死ぬと墓地において墓に土葬される。どうも墓地は所有者がよりはっきりし、その土地との結び付きも強くなるため、モスクよりも強く所有を主張できる宗教施設のようだ。よってアヨーディヤー裁判においてもイスラーム教徒側はバーブリー・マスジドの土地を「墓地」と主張して所有権を明確にし、乗り切ろうとしていた。だが、破壊されたバーブリー・マスジドの建築物とその土地は、結局モスクとしても墓地としても存在をうまく立証できず、それが今回の不利な判決の遠因になったように思える。
10日3日から12日間に渡ってデリーの「支配者」となって来た英連邦競技大会(CWG)も今日が最終日。マラソン、バドミントン、ホッケーなどいくつか重要な競技の試合が残っていたが、本日のメインイベントは何と言っても閉会式である。元々開会式は見る予定だったのだが、閉会式についてはどうしようか迷っていた。だが、開会式があまりに素晴らしかったため(参照)、閉会式も生で鑑賞したいという気持ちが強くなり、急いでチケットを購入した次第である。やはりチケットは4カテゴリーあり、上からAが50,000ルピー、Bが20,000ルピー、Cが4,000ルピー、Dが750ルピー。Dは売り切れだったため、Cを購入した。
ところで、開会式へ行って見て気付いたのだが、チケットの値段は席の価値に比例している訳ではない。より良好な席はスタジアムの西半分のどれか、つまりVIP席側であり、損な席はその逆の東半分、VIP席に対面する側である。パフォーマンスは基本的にVIP席を向いて行われるため、VIP席と反対側に回ってしまうと、パフォーマーの背中ばかりを見ることになってしまう。また、B以上の席は前方だが低い位置になってしまい、見晴らしはそんなによくないと思われる。開会式のときはCカテゴリーの席ながらVIP席側の非常にいい席に座れたのだが、今回はチケットの購入が遅かったためか、VIP席と正反対の損な席に回されてしまった。閉会式でもショーの多くはVIP席を意識して行われていたため、楽しさ半減であった。
また、開会式のときは14番ゲートからの入場だったが、今回は9番ゲートからの入場となっていた。9番ゲートの最寄り駅はバイオレット・ラインのジャングプラー駅であった。
午後7時から開演だったが、混雑を避け、開場する午後2時頃に会場のジャワーハルラール・ネルー・スタジアム(JLNスタジアム)へ向かった。一応開場は開演5時間前とされていたが、午後2時ピッタリには開かず、多少待たされた。だが、しばらく待っていたらゴーサインが出て、中に入ることが出来た。あとはただひたすらショーが始まるのを待っていた。ただ、今回は開会式のときと違って心の余裕があったので、スタジアム内をブラブラしたりして暇を潰した。警備にあたる軍隊・治安部隊・警察や道案内を務めるボランティアたちにも開会式のときに比べて余裕が見られた。
閉会式の演目などについて漏れて来る情報は錯綜していた。閉会式は開会式と違ってしめやかに行われるものだという話もあったが、開会式を越えるようなゴージャスなショーに土壇場で変更されたという噂もあった。とにかく直前まで変更があったみたいである。どうせなら開会式を越える規模のショーになることを期待していた。

閉会式は国歌にて開始
結論から先に言ってしまえば、閉会式は開会式ほど豪華なショーではなかった。やはり祭りの終わりという雰囲気が強く、特にCWGデリーのマスコットキャラ、シェーラーとのお別れマーチは若干悲しい雰囲気の中で行われた。CWG前には、デリーで本当にCWGのようなイベントが開催できるのか皆が心配し、批判していたが、それに反比例してシェーラーの人気だけはなぜかうなぎ登りとなり、今やデリーの風景に欠かせない存在になってしまった。そのシェーラーともお別れである。1982年にデリーで開催されたアジア競技大会のマスコット、象のアップーにちなんでかつてプラガティ・マイダーンの隣にアップーガルという遊園地があったが、噂ではCWGを記念するためにシェーラーガルの建設が計画されているらしい。

シェーラーとのお別れ
歌手のシャーンがシェーラーの歌を歌った
そのように悲しい雰囲気も入り交じる閉会式だったのだが、冒頭ではインド中のマーシャルアーツを大集合させた勇壮な「Agni」や、児童生徒たちによるインドの三色旗をアレンジした様々な模様を集団でグランドに映し出す「ヴァンデー・マータラム」ど、いくつか派手な見せ物はあった。「Agni」では、カラリパヤット、ナガ武術、タンタ、ガトカ、スィランバン、アカーラー、ダン・パッター、タルワール・ラスなどインド中の様々なマーシャルアーツが一堂に会した。「Vande
Mataram」では、ARレヘマーンの「Vande Mataram」に合わせて児童生徒たちが衣装と色粉をうまく組み合わせて様々な巨大模様をグランド上に出現させていた。中心にはインドの国旗の中心に据えられたアショーカ・チャクラ(法輪)が回転していた。

インドのマーシャルアーツ大集合「Agni」
しかし、エアロスタットを有効活用した開会式ほどのサプライズはなかったことは認めざるをえない。閉会式中最初から最後までエアロスタットはずっと空中に浮いたままで、側面に映像が映し出されてはいたものの、あまり存在感はなかった。開会式ではエアロスタットとその直下のステージを中心にパフォーマンスが行われていたため、パフォーマンスに求心性があった。だが、今回ステージはなく、グランドは単なる平面となっていて、その上で行われるパフォーマンスも中心性を欠いていた。ちなみに現在運営委員会はエアロスタットの買い手を探しているらしい。

「Vande Mataram」
閉会式は、ショーの部分がメインではなく、あくまで本体は儀式の部分という印象を受けた。会場に掲揚されたCWG旗を次回CWG開催都市グラスゴーの運営委員長に渡す儀式や、スレーシュ・カルマーディーCWGデリー運営委員長、CWG連盟(CGF)会長マイク・フェネル、デリー総督テージェーンドラ・カンナー、エドワード王子などの挨拶もあった。選手・スタッフの入場もあったし、2万人のボランティアたちのちょっとしたパフォーマンスもあった。だが、それらの形式的な儀式は中だるみしてしまい、見ていて退屈だった。また、序盤になぜか知らないが三軍の楽隊によるパフォーマンスもあったが、これも退屈だった。一応国民歌の演奏などのときには盛り上がっているインド人もいたが、「早く終われ~」の拍手のようにも感じた。

三軍楽隊の演奏
次回CWGはスコットランドのグラスゴーで開催される。その予告編として、スコットランドのチームのパフォーマンスもあった。スコットランドと言えばスカート状の伝統衣装キルトとバグパイプ。バブパイプ演奏者をフィーチャーしながら、キルトを着用した一団が巨大な半円状の物体を使っていくつかのモチーフを作り出していた。グラスゴーでは「アルマジロ」と呼ばれる特徴的な形状をしたホールがあってランドマークになっているようで、最終的にはそのアルマジロを表現していた。

グラスゴー名物「アルマジロ」
スコットランドのパフォーマンスがあった後、再びショーの主導権はインドに戻り、閉会式の最後、そしてCWGの最後を飾るクライマックスが訪れた。まず観客の度肝を抜いたのが、レーザー光線ショー。スモークが噴出されると同時に、スタジアムの四方八方から様々な色のレーザー光線が照射され、エアロスタットの下にまるで色とりどりの図形が立体的に浮かび上がっているように見えた。

レーザー光線ショー
そしてそのまま最後を締めくくる「ミュージック・オブ・ユニバーサル・ラブ」へ。先程シェーラーと共に登場したシャーンをはじめ、カイラーシュ・ケール、シャンカル・マハーデーヴァン、シュバー・ムドガル、ズィラー・カーン、スクヴィンサル・スィン、シヤーマク・ダーヴァル、スニディ・チャウハーン、シヴァマニなど、ボリウッドで活躍するプレイバックシンガーやミュージシャン、そしてその他人気DJが登場し、ボリウッドのヒット曲をメドレーで歌い出した。「Allah
Ke Bande」、「Desi Girl」、「Ab Ke Saawan」、「Where's Party Tonight」、「Chak De India」、「Koi
Kahe Kehta Rahe」など、ここ10年ぐらいのヒット曲が網羅されており、同じだけデリーに住む僕にとっては感慨深いものがあった。意外だったのはクィーンの「We
Will Rock You」やブルーの「One Love」など、洋楽も入り交じっていたことである。ただ、それらはインド人の若者にも人気の曲であった。総じてその選曲を見ると、インドのディスコや結婚式でよく流れるものばかりで、スタジアムを大ディスコ化して閉会式を終わらせようという魂胆が丸見えであった。しかしインド人をもっともよく知るのは結局インド人、待ってましたとばかりに観客は大いに盛り上がっていた。また、一応グランドではダンサーたちによる群舞も行われていたが、練習不足で大したものではなかった。しかし、ダンサーたちも最後は振り付けとはあまり関係なく自由に踊っていたような感じで、もはや無礼講であった。

「ミュージック・オブ・ユニバーサル・ラブ」
開会式とは違って、閉会式からはあまりまとまりが感じられず、儀式的な部分も冗長過ぎて、ショーとしての完成度は低かった。しかしながら、CWGの無事開催と成功を皆で祝おうという、お祭りムードは十分感じられ、会場を後にするときには、閉会式としてはこういう形でも良かったのではないかと思えるようになった。ちなみに、今回の大会でインドは金メダル38枚、銀メダル27枚、銅メダル36枚、合計101枚を獲得し、国別メダルランキング(金メダル数優先)ではオーストラリアに次いで堂々の2位。インドのスポーツと言うと今までそれほど強いイメージはなかったが、このCWGをきっかけにクリケット以外のスポーツにも俄然注目が集まるようになり、各分野でスター選手も数多く生まれた。インドのスポーツにはまだまだ問題が山積しているが、今回のCWGが大きなターニングポイントとなる可能性は十分ある。また、重要なのはCWGの成功がデリー五輪の夢につながっていることだ。五輪開催という点で、BRICsの中でインドはもっとも遅れを取っている。2008年には北京五輪が行われ、2016年はリオデジャネイロ五輪が開催予定だ。ロシアはまだ五輪を開催していないものの、ソ連時代の1980年にモスクワ五輪が開かれている。だが、今回のCWGの成功によって、デリー五輪の実現はグッと近付いたと言える。CWGでせっかく盛り上がったクリケット以外のスポーツへの関心を維持し、CWG準備中・開催中に直面した様々な問題を繰り返さないように努力すれば、デリー五輪は決して不可能ではないと思う。その日が来るのが待ち遠しい。
インドではここ数年、「名誉殺人」と呼ばれる殺人事件がクローズアップされている。家族やコミュニティーの名誉を守るための殺人で、特に異カースト間や同ゴートラ間で駆け落ち結婚した若いカップルがその被害に遭うことが多い。ただ、名誉殺人が増えたという訳ではないようだ。名誉殺人自体は昔からあり、特に農村部では密かに行われ密かに処理されていた。最近その被害者がデリーのような都会にも現れるようになり、やっと事件として取り上げられるようになったというのが実態のようである。
本日より公開の新作ヒンディー語映画「Aakrosh」は、ビハール州を舞台にし、名誉殺人をテーマにした映画である。実話を基にしたフィクションとのこと。監督は「コメディーの帝王」として知られるプリヤダルシャン。ハチャメチャなコメディー映画を得意とするが、時々シリアスな映画も撮っており、多作かつ多様なフィルモグラフィーを持っている。アジャイ・デーヴガンとアクシャイ・カンナーの共演も見所である。
題名:Aakrosh
読み:アークローシュ
意味:憤怒
邦題:オナー・キリング
監督:プリヤダルシャン
制作:クマール・マンガト・パータク
音楽:プリータム
歌詞:イルシャード・カーミル
出演:アジャイ・デーヴガン、アクシャイ・カンナー、ビパーシャー・バス、アミター・パータク、ウルヴァシー・シャルマー、パレーシュ・ラーワル、サーミラー・レッディー(特別出演)など
備考:PVRアヌパムで鑑賞。
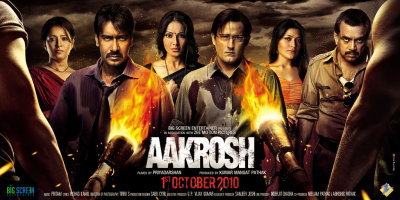
左から、アミター・パータク、アジャイ・デーヴガン、ビパーシャー・バス、
アクシャイ・カンナー、ウルヴァシー・シャルマー、パレーシュ・ラーワル
| あらすじ |
デリーで医学を学ぶ大学生3人が行方不明になるという事件が発生。既に失踪から2ヶ月が経つが何も手掛かりはなく、デリーでは学生たちによるデモ活動が続いていた。捜査は中央情報局(CBI)に委ねられ、CBIに所属するプラタープ・クマール(アジャイ・デーヴガン)とスィッダーント・チャトゥルヴェーディー(アクシャイ・カンナー)が捜査を担当することになった。2人は3人の大学生が最後に目撃されたビハール州ジャーンジャルに降り立つ。
だが、ジャーンジャルの警察は全くCBIに協力的ではなかった。特にアジャトシャトル・スィン(パレーシュ・ラーワル)は何かに付けてプラタープとスィッダーントをからかった。また、村人たちも地元の権力者に怯えており、誰も口を開こうとしなかった。さらに、ジャーンジャルではシュール・セーナーと呼ばれる過激団体が暗躍しており、プラタープとスィッダーントは早速シュール・セーナーの襲撃を受ける。
ところで、プラタープは偶然アジャトシャトルの妻が、かつての恋人ギーター(ビパーシャー・バス)であることを発見する。プラタープはダリト(不可触民)の生まれで、幼少時に両親を亡くし、マスタージー(教師)に育てられていた。ギーターはマスタージーの娘であった。マスタージーはダリトのプラタープを育てたが、ギーターとは結婚させようとしなかった。マスタージーにそれを伝えられたプラタープはギーターを諦めて立ち去った。そんな過去があったのだった。プラタープはギーターに話しかけようとするが、ギーターは彼のことを全く無視していた。
捜査が行き詰まっていた頃、運良く大学生たちが乗っていた自動車が川底から見つかる。だが、どうやら車は落ちたのではなく落とされたようであった。その車を調べてみたところ、地元有力政治家の娘ローシュニー(アミター・パータク)の携帯電話が発見される。プラタープとスィッダーントはローシュニーを連行し、尋問を行う。その結果、ローシュニーは行方不明の大学生の1人ディーヌーと恋仲にあり、友人2人の助けを借りて駆け落ち結婚をしようとしたが、警察に捕まってしまったことが分かる。だが、ローシュニーはどの警察がその場にいたのかを覚えておらず、彼女の証言を元に立証することは出来なかった。プラタープとスィッダーントは上司からも叱られ、調査は終了ということになってしまった。
大学生行方不明事件が一段落付いたところで、CBIに協力した者への反撃が始まった。権力者の圧政に反対の声を上げたジャーンジャルの村は焼き討ちに遭い、ディーヌーと接点のあった女性(ウルヴァシー・シャルマー)の夫と息子が殺されてしまう。ギーターはプラタープが帰るのを知って心を改め、その女性とプラタープを引き合わせようとする。ところがその女性は誘拐されてしまい、舌を切り取られてしまう。そこで今度はギーターがプラタープに直接アジャトシャトルの家で見たことを話す。
やはり行方不明の大学生3人はアジャトシャトルに捕まっていた。地元有力政治家がディーヌーを殺し、他の2人はアジャトシャトルが殺していた。そして遺体を森林の遺跡の中に捨てていた。それを知ったプラタープとスィッダーントはその場を捜査し、3人の遺体を発見する。遺体が発見されたことで事件は急展開を迎え、俄然マスコミの注目を集めることになる。ところが、ギーターがプラタープに情報を漏らしたことを知ったアジャトシャトルはギーターに酷い暴行を加える。
プラタープとスィッダーントはアジャトシャトルら実行犯の中からもっとも弱そうな人物に狙いを定め、彼を証人にならざるをえない状況に陥れる。その結果、アジャトシャトルらの有罪が確定し、懲役刑が言い渡された。だが、すぐに釈放されることは目に見えていた。そこでスィッダーントは密かに、夫と息子を殺され舌を切られた女性に銃を渡しており、彼女に復讐させた。アジャトシャトルらはその場で射殺され、報いを受けた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
円熟期に入ったアジャイ・デーヴガンとアクシャイ・カンナーの見事な共演、それにパレーシュ・ラーワルら脇役陣の好演により、重厚なドラマとなっていた。それに加え、プリヤダルシャン映画が得意とするコメディーとはタッチの異なるシニカルな笑いも盛り込まれていたし、スリリングなアクションシーンも盛りだくさんで息を付かせない展開であった。ただ、残虐な暴力シーンが多く、脚本も細かい部分で詰めの甘さが見られた。
3人の大学生の失踪事件から名誉殺人へと展開して行く映画ではあったが、映画の真のテーマはインドの農村部に根強く残るカースト制度、もっと正確に言うならばカースト意識であった。映画中では、相手の名前を聞いてカーストを判断しようとするシーンがいくつも登場する。インド人の名前の多くはカーストの指標となっており、名前を聞けばその人の大体の出身地やカーストが分かってしまう。それ故に敢えてカーストを隠す名前を名乗っている人もいるが、カースト制度から逃れることは難しい。映画中では主に2つのカースト差別被害者が出て来た。ひとつはメインの事件である大学生失踪事件の関連。地元有力政治家の娘と結婚しようとした大学生はダリト(不可触民)であり、そのために正攻法では結婚が許されず、駆け落ちを実行せざるを得なかった。そしてそれが失敗したことで命を落とすことになる。もうひとつはプラタープの身の上である。プラタープ自身もダリトであり、カースト差別の被害に遭って一家を失った経歴を持っていた。その上、育ての親からも、カーストを理由にその娘ギーターとの結婚を認めてもらえなかった。だからプラタープはカーストによる差別に常に反対していた。農村の人々の意識にどこまでカースト制度から来る恐怖が植え付けられているか、映像化することによく成功していたと言える。
「Love Sex Aur Dhokha」(2010年)でも名誉殺人が部分的に取り上げられていたが、どちらかというと都市型名誉殺人で、駆け落ちしたカップル両方が女性側家族に殺害された。一方、「Aakrosh」では駆け落ちしようとしたカップルの内男性とその友人たちが女性側家族などに殺され、女性は無理矢理結婚させられようとしていた。「Aakrosh」で描かれた名誉殺人はどちらかというと軽い方で、外国人にも理解しやすい。最近ニュースになる名誉殺人は、女性側家族が禁断の恋をした娘を殺害する事件が多い。相手の男性が殺されるかどうかは状況次第である。
近年のヒンディー語映画は海外を舞台にした都市志向の映画が支配的だったのだが、今年のボリウッドは農村または地方都市を舞台にした良作が続いており、揺り戻しの年となっている。「Ishqiyaa」、「Pipli
[Live]」、「Antardwand」、「Dabangg」など、今年話題になった映画のいくつかは非都市映画である。「Aakrosh」がヒットするかどうかはまだ未知数であるが、これもビハール州の架空の町ジャーンジャルを舞台にしている。また、映画中に登場した地元有力政治家は、ビハール州の名物政治家ラールー・プラサードをモデルにしていることは明らかだった。
アジャイ・デーヴガンは最近立て続けにダリト役を演じている。「Raajneeti」(2010年)ではダリト青年政治家スーラジ・クマールを演じ、今回はダリトCBI捜査官プラタープ・クマールを演じた。恐らく肌の色が黒いためにダリト役をオファーされるのだろう(一般に肌の色が白いほどカーストが高い傾向がある)。アジャイは前から渋かったが、特にここ最近はその渋さに磨きがかかったように感じる。対するアクシャイ・カンナーも眉毛を総動員させた表情豊かな演技で、久し振りに存在感を示せていた。プリヤダルシャン監督のお気に入り、パレーシュ・ラーワルは、悪役ながら主役を食う怪演。本当にうまい俳優だ。
映画には3人のヒロインが登場する。その内の第一ヒロインと言えるのがビパーシャー・バス。ゴージャスな役を演じることが多いビパーシャーであるが、今回は家庭内暴力に苛まれる抑圧された女性役で、かなりシリアスな演技力を要する役であった。メイクを最小限に抑え、精一杯セレブオーラを放出しないようにしていたが、やはりどこか煌びやかな印象はぬぐえず、この役にはマッチしてなかった。残りのアミター・パータクとウルヴァシー・シャルマーについてはそれほど見せ場がないのだが、特にウルヴァシー・シャルマーの方はビパーシャー・バスよりもさらに酷い目に遭う女性を演じており、潔さを感じた。もう1人、サミーラー・レッディーがアイテムナンバー「Isak
Se Meetha」でアイテムガール出演していた。
音楽はプリータム。基本的にハードボイルドな映画で、挿入歌・ダンスシーンは控え目だった。アイテムナンバー「Isak Se Meetha」は「Omkara」(2006年)の「Beedi」などを意識した曲だろうが、「Dabangg」のアイテムナンバー「Munni
Badnaam」が目下大ヒット中であるため、インパクトに欠けた。
「Aakrosh」は、名誉殺人というホットな話題をテーマにした、実話に基づいたフィクションドラマである。アジャイ・デーヴガンとアクシャイ・カンナーの渋い共演が最大の見所。次から次へとスリリングなシーンが続くため、アクションスリラーとしても一級品である。ただ、多少暴力シーンが多く、脚本も詰めが甘かったように感じた。それでも見て損はない映画であることには変わりない。
| ◆ |
10月16日(土) Ramayana - The Epic |
◆ |
インドの二大叙事詩のひとつに数えられ、現在でもインド人に絶大な人気を誇る説話「ラーマーヤナ」は、今まで何度かアニメ化されて来た。初のアニメ「ラーマーヤナ」は日本のNHKとの合作で、日本では「ラーマーヤナ:ラーマ王子伝説」という邦題で1998年に公開された。インド国産のアニメとしては、「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーンを主人公にした「Hanuman」(2005年)がある。アニメ大国日本から来た者の視点から見ると稚拙さが目立った映画ではあったが、インド人には大いに受けてスマッシュヒットとなり、続編「Return
of Hanuman」(2007年)も作られた。これらは2Dアニメだったが、3Dアニメも作られるようになり、やはりハヌマーンを主人公に据えた3Dアニメ映画「Bal
Hanuman」(2007年)とその続編「Bal Hanuman 2」(2010年)も作られた。
このように「ラーマーヤナ」はインドのアニメの発展と密接な関係を持ち続けて来ている。既に飽和状態になっているようにも見えるのだが、インド人はよっぽど「ラーマーヤナ」が好きなようで、またひとつ、その叙事詩を題材にした3Dアニメ映画が公開された。今週より公開の「Ramayana
- The Epic」である。今まで公開された3Dアニメ映画の中ではもっとも多額の予算を投じて制作されており(2.0~2.4億ルピーとされる)、予告編で見る限りダントツでクオリティーも高かった。配給は、インド市場を虎視眈々と狙うハリウッドのプロダクション、ワーナー・ブラザースが担当。ちょうどラームリーラーの真っ最中に公開されたこともあり、タイミング的にもバッチリである。今日日本に一時帰国する予定でダシャハラー祭には参加できないため、一足早くこの「Ramayana
- The Epic」を見て、悪に対する善の勝利を祝うことにした。
ちなみに、あらすじは一般的な「ラーマーヤナ」を全く逸脱していなかったため、割愛する。
題名:Ramayana - The Epic
読み:ラーマーヤナ:ジ・エピック
意味:叙事詩ラーマーヤナ
邦題:ラーマーヤナ
監督:チェータン・デーサーイー
制作:ディーパー・サーヒー、ニーラジ・ブーカンワーラー
音楽:シャーラング・デーヴ・パンディト
歌詞:ラーメーンドラ・トリパーティー
声の出演:マノージ・バージペーイー、ジューヒー・チャーウラー、アーシュトーシュ・ラーナー、ムケーシュ・リシ、リシャブ・シュクラ
備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

「ラーマーヤナ」の内容を大まかに映像化した作品だった。フォーカスはラームとハヌマーンが出会って以降になっており、それ以前のストーリーはラクシュマンがハヌマーンに語り聞かせるという形で端折って語られていた。また、救出されたスィーターのアグニパリークシャー(火の中に入って潔白を証明する儀式)や、ラームがアヨーディヤーに戻って以降の話などは省略されていた。非常にコンパクトにまとめられていたが、ラームが14年のワンワース(追放刑)を受けるシーン、スィーターが救出に来たはハヌマーンを帰し、ラーム自身が迎えに来るように命じるシーン、そして1年振りのラームとスィーターの再会などのシーンは、分かっていてもホロリとさせられた。
3Dの映像はかなりのレベルに達している。特に背景やラーヴァンの衣装の描き込みは緻密かつ豪勢で、美しかった。ただ、登場人物の動きや表情にはCG特有の固さが残っており、まだまだ改善の余地があった。
声はボリウッドの俳優が担当している。ラームはマノージ・バージペーイー、スィーターはジューヒー・チャーウラー、ラーヴァンはアーシュトーシュ・ラーナーなどである。特にラーヴァンの人物設定や台詞回しにはかなり気合いが入っており、羅刹王の圧倒的な迫力が十二分に表現されていた。10の頭を持つラーヴァンを、本当に10の頭を持つ姿で描くがどうかは、「ラーマーヤナ」を映像化する作家の悩み所である。どうしても10の頭を持たせると滑稽な姿になってしまうのだ。この「Ramayana
- The Epic」では結局ラーヴァンはひとつの頭しか持っていなかった。だが、多重人格的に描かれており、心の中の葛藤の中で10人のラーヴァンが話し合うシーンがいくつかあった。
ボリウッド映画のお約束にのっとって、ダンスシーンも盛り込まれていた。特に大きな見せ場となっていたのは、猿の王国キシュキンダーの登場シーン。猿の群衆がご機嫌なダンスを繰り広げる。
神話を題材にしたアニメ映画にありがちだが、言語はサンスクリット語をベースとした純ヒンディー語で、ヒンディー語初学者にとっては多少理解が困難になるだろう。だが、発音はクリアなので、美しいヒンディー語を学ぶための教材としてはとてもいい。こういう話し方を実生活でするとからかわれるだけだが、マスターしておくだけでも損はない。
「Ramayana - The Epic」は、インドのアニメ産業の発展の一段階として記録される映画となるだろう。日本のアニメの視点から見ても、ハリウッドのアニメの視点から見ても、それらに匹敵するレベルにはまだ達していないが、「Hanuman」以来数年でインドもかなりのレベルのアニメが作れるようになったことが見て取れるだろう。
ここ最近新作ヒンディー語映画の数が多い。1週間日本に一時帰国していたが、その間にも容赦なく複数のヒンディー語映画が公開された。全て見ている暇はないが、どれもそれぞれ面白そうでどれを見ようか迷ってしまう。今日見た「Jhootha
Hi Sahi」は、「Jaane Tu... Ya Jaane Na」(2008年)で監督デビューして新鮮な旋風を巻き起こしたアッバース・タイヤワーラーの第二作。「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」は、作風や俳優の点でボリウッド映画の世代交代を強烈に印象づけた作品であり、アッバース・タイヤワーラー監督の第二作には自然と期待が高まっていた。音楽も前作同様ARレヘマーンが担当。ただ、アッバース・タイヤワーラー監督の妻パーキーがストーリーライターと主演を務めており、その身内起用がどう作品に影響してくるかは不安要素であった。
題名:Jhootha Hi Sahi
読み:ジューター・ヒ・サヒー
意味:嘘でもいい
邦題:嘘でもいいさ
監督:アッバース・タイヤワーラー
制作:マドゥ・マンテーナー
音楽:ARレヘマーン
歌詞:アッバース・タイヤワーラー
出演:ジョン・アブラハム、パーキー、ラグ・ラーム、マナスィー・スコット、アナイター・ナーイル、オマル・カーン、アリシュカー・ヴァルデー、ジョージ・ヤング、プラシャーント・チャーウラー、マーダヴァン(特別出演)、ナンダナー・セーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
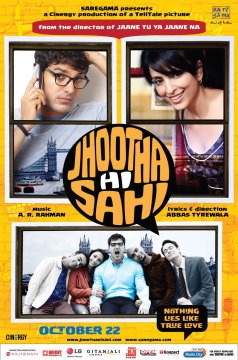
上段左はジョン・アブラハム、右はパーキー
下段は左からオマル・カーン、パーキー、ジョン・アブラハム、
ラグ・ラーム、ジョージ・ヤング
| あらすじ |
ロンドン在住のインド人スィッダールト(ジョン・アブラハム)は、友人たちと本屋を経営する純朴な青年であった。美人の前などで緊張するとどもってしまう癖があり、それを引け目に感じていた。スィッダールトにはクルティカー(マナスィー・スコット)というガールフレンドがいた。スィッダールトと同じアパートには、パーキスターン人のオマル(ラグ・ラーム)とその妹アーリヤー(アリシュカー・ヴァルデー)が住んでおり、親しかった。他に、アーリヤーの恋人ニック(ジョージ・ヤング)、アミト(オマル・カーン)、ウダイ(プラシャーント・チャーウラー)など、仲のいい友人たちがいた。
ある晩、スィッダールトの電話に、これから自殺をしようとする男から電話が掛かって来る。スィッダールトは悪戯だと思いつつも誠意をもって返答する。だが、それが3回も続き、ほとほと困り果てる。翌日、オマルやアミトとそのことについて相談するが、謎は解けない。だが、突然スィッダールトを訪ねて来たバーヴナー(ナンダナー・セーン)が全てを明らかにする。バーヴナーは「ドースト・インディア」というボランティアグループに所属しており、自殺志望者の相談に乗るためのホットラインを運営していた。そのポスターに間違ってスィッダールトの電話番号を載せてしまったため、自殺志望者から何度も電話が掛かって来るようになってしまったのだった。
スィッダールトは、もし今後も自殺志望者から電話が掛かって来たら、自分が相談に乗ると申し出る。だが、デート中にも自殺志望者の話に必死に耳を傾ける様子にクルティカーは愛想を尽かし始める。
あるとき、スィッダールトの電話にミシュカー(パーキー)という女性から電話が掛かって来る。ミシュカーは恋人のカビール(マーダヴァン)に振られ、自殺しようとしていた。電話では彼女はほとんど何も言葉を発しなかったが、スィッダールトは温かく彼女を励まし、黙って電話の向こうの彼女と共に一夜を過ごす。この件をきっかけにスィッダールトのところにはミシュカーから頻繁に電話が掛かって来るようになる。その中でスィッダールトはミシュカーに惹かれ始める。だが、スィッダールトは決して本名など自らの素性を明かさなかったため、ミシュカーは彼のことをフィダートと呼ぶようになる。
ミシュカーの相談に乗る中で、スィッダールトは彼女の個人情報をある程度手に入れていた。ミシュカーは元々画家志望だったが夢破れ、現在はビデオショップの店員をしていた。ある日偶然ミシュカーはスィッダールトが働く本屋を訪れ、その後スィッダールトも彼女が働くビデオショップに立ち寄り、それがきっかけでスィッダールトはミシュカーと会うようになる。そして夜にはフィダートとなってミシュカーから自分についての話を聞き出し、彼女にスィッダールトとの関係を深めるようにアドバイスしていた。ミシュカーもスィッダールトに恋をするようになる。だが、同時にクルティカーとの仲は冷えて行った。スィッダールトは、クルティカーのことを自分の元彼女だとミシュカーに語っていたが、彼女には決して会わせなかった。また、ミシュカーが忘れられなかった元恋人カビールが再び彼女の人生に現れるようになった。カビールは新しい恋人を連れていた。だが、ミシュカーもスィッダールトという新しい心の支えが出来ていたため、何とか精神的に持ちこたえられた。
あるとき、クルティカーを除いてスィッダールトの友人たちがミシュカーを迎えて会食をすることになった。だが運悪くそこへクルティカーが来てしまう。クルティカーにはミシュカーのことがばれ、ミシュカーにはクルティカーのことがばれてしまった。スィッダールトはミシュカーに必死に弁明し、これ以上嘘は言わないという条件付きで何とか許してもらえる。クルティカーとは完全に破局したが、なぜか彼女はオマルと付き合うことになった。
スィッダールトは正式にミシュカーに愛していることを伝える。だが、そのときカビールが事故に遭って入院したことが分かり、彼女はカビールをお見舞いに行く。その場でカビールはミシュカーに関係修復を懇願する。ミシュカーの心も揺れた。
ところで、スィッダールトは引き続きドースト・インディアの代理をしていた。あるとき、ミシュカーの隣に住む少年アンクルからのヘルプコールがあった。アンクルは既に大量の睡眠薬を飲んでしまっていた。ちょうどフィダートとなってミシュカーと話していたスィッダールトは、彼女にアンクルを至急助けるように頼む。その後スィッダールトはアンクルの家に駆けつけるが、そこでミシュカーに目撃されてしまう。ミシュカーはそのとき初めて、フィダート=スィッダールトだと確信する。ミシュカーはスィッダールトに2度も裏切られたことを知り、彼と絶交する。ミシュカーはかねてからの夢だったパリ留学に、スィッダールトと行くことを計画していたが、1人で行くことを決める。
ミシュカーに振られてしまったスィッダールトはすっかり意気消沈していた。だが、ニックとアーリヤーの結婚式には何とか出席していた。ちょうどその頃、ミシュカーはカビールの運転する車で空港へ向かっていた。カビールはミシュカーにもう一度恋人の関係になることを提案するが、ミシュカーは友人のままの関係を希望する。そして自分はスィッダールトに恋していることに気付き、カビールを捨ててスィッダールトに電話をする。ミシュカーはタワーブリッジの向こう側に立ち、10分以内に来るようにスィッダールトに言う。スィッダールトは結婚式を飛び出し、タワーブリッジへ走る。タワーブリッジの橋が上がる時間になるが、スィッダールトはギリギリでそれを飛び越え、ミシュカーと抱き合う。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Jaane Tu... Ya Jaane Na」に引き続き、新感覚のオシャレな都会派ラブストーリー。「Jaane Tu... Ya Jaane
Na」では20代前半くらいの若者たちが主人公で、そのくらいの年齢層かまたは10代後半ぐらいの新世代若者たちをターゲットにした作品だと感じた。自分がもうその世代ではなくなっているため、「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」を見たときはまるで自分が隠居世代に押しやられているかのような衝撃を受けた。ストーリーの新しさというよりも、登場人物たちが代表する文化の新しさに旧世代として危機感を覚えたものであった。だが、「Jhootha
Hi Sahi」は、やはりインド映画離れしたハイセンスなストーリーながら、もう少し高めの年齢層をターゲットにした作品で、比較的安心して見られた。
ストーリーの導入部は、主人公スィッダールトの元に自殺志願者たちから突然電話が掛かって来るようになるというミステリアスなもので、一気に引きつけられるものがある。だが、ロマンス映画の類型の中に当てはめてみれば、インド映画に時々見られる、「恋愛相手の個人情報を一方的に把握して恋愛を有利に進める」というプロットの変形であり、展開自体にそれほど目新しさはない。例えば「Milenge
Milenge」(2010年)は、ヒロインの日記を盗み見て彼女の好みを完全把握した主人公が彼女の理想の男性を演じて近づくというプロットで、「Jhootha
Hi Sahi」のあらすじと遠くはない。このようなプロットでは、必ずと言っていいほどその秘密が相手にばれ、せっかく築かれた信頼関係は崩壊寸前となって映画の盛り上がりとなる。「Jhootha
Hi Sahi」でも、やむを得ない事件を経て、冴えない本屋店員スィッダールトと、自殺志願者ホットラインで相談役を務める自称冒険家フィダートが同一人物であることがヒロインのミシュカーにばれてしまった。
目新しかったのはやはり登場人物の設定や人間関係であった。物語の中心となっていたのはロンドンに住むインド人とパーキスターン人の仲良しサークルで、国境や宗教を越えたリベラルな人間関係を築いている。時々ジョークで国籍ネタや宗教ネタが出てくるが決して本気ではない。また、妊娠してしまったガールフレンドに必死にプロポーズする男(ニックとアーリヤー)や、同性愛者のウダイなど、脇役ではあるが、インド本国のモラルを逸脱した関係もサラリと描かれる。主人公スィッダールトと恋人クルティカーの仲もかなり曖昧だ。伝統的にはインド映画で描かれる恋愛は「生きるか死ぬか」の問題であるが、この2人の恋愛はかなり淡泊で、むしろ欧米の恋愛観に近い。しかもスィッダールトと別れたクルティカーは、その日の晩に彼の親友オマルと関係を持ってしまうし、それもライトタッチでサラリと流されてしまう。こういうライトなノリの恋愛関係が今後インド映画でも主流となって行くのかもしれないが、旧世代の人間としては何か寂しいものも感じる。
それでいてクライマックスは新感覚を求めるあまり思考が一周して戻って来てしまったかのようなコテコテの典型的エンディングであった。開閉することで有名なロンドンのランドマーク、タワーブリッジを効果的に使い、橋が開こうとする中、向こう側にいる恋人を目指して全力疾走するというもので、間一髪の大ジャンプまで披露する。英国人でも小っ恥ずかしくて採用しないようなコテコテのまとめ方だ。だが、敢えてエンディングの展開を王道中の王道の演出にする判断は悪くはない。これは「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」のエンディングでも共通して見られた特徴である。
スィッダールトは緊張するとどもる癖がある設定だったが、この設定は最近のヒンディー語映画の流行だ。「Kaminey」(2009年)や「Ajab
Prem Ki Gazab Kahani」(2009年)でどもり症またはそれに似た言語障害のキャラクターが出て来て、そのしゃべり方がストーリーにも関係して来たりしていた。また、インド人に人気のコメディー映画「Golmaal」シリーズでは唖のキャラクター(トゥシャール・カプールが演じている)が出て来て最大の笑いを取っている。「Jhootha
Hi Sahi」ではスィッダールトの吃音が大きな伏線になっていた訳ではないが、彼は電話ではどもらずに話すことができ、それがスィッダールトとフィダートが同一人物であることにミシュカーが気付かなかった大きな要因のひとつとなっていた。
全体的に洗練された映画だと感じたが、細かい部分で疑問に思ったところもあった。この映画の大きなポイントは「嘘」にある。スィッダールトは自殺志願者ホットラインのボランティアを装って自殺志願者の相談に乗るようになるが、それは映画中でも指摘されていた通り、素人が他人の生死を左右する危険な行為であり、もっと慎重にならなければならないものであった。モラルの点で問題となるのは、最期の望みとして電話を掛けて来た人の信頼に嘘で応える行為だった。それが結局は、自殺志願者として電話を掛けて来たミシュカーとの関係のわだかまりとなってしまう。それだけでなくスィッダールトはクルティカーという恋人がいながら、ミシュカーに恋してしまい、真実を隠して付き合おうとする。最終的に2つの嘘がばれてしまい、2つ目の嘘、つまりスィッダールト=フィダートであることがばれた時点で、ミシュカーはスィッダールトを見捨てる。しかしミシュカーは自分で考え直してスィッダールトに電話をし、彼に最後のチャンスを与える。ミシュカーの心変わりは自発的なもので、スィッダールトの禊などはない。この展開を見ると、嘘を付いたことが許されずにそのまま流されてしまっており、嘘を戒める伝統的なインド映画のモラルから逸脱している。そういえば「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」でも、男らしさという名の暴力が礼賛され、非暴力の伝統の中で発展して来たインド映画のモラルを逸脱していた。アッバース・タイヤワーラー監督はこれらの作品で意図的に暴力と嘘というインド映画のタブーに挑戦したのかもしれない。だが、それがわざとでないとすると、インド映画の文脈からかなり外れた展開の作品だと評せざるを得ない。
ワイルドで大味なイメージのあるジョン・アブラハムは、最近等身大の人間を演じるようになって来ており、繊細な演技力を要する役にも果敢に挑戦している。ジョン・アブラハムにはアクション映画に適した無骨さの反面、人なつっこさもあり、それがうまく活かされるとアクション映画以外でもいい演技をする。「Jhootha
Hi Sahi」ではどもり気味のドジで冴えない青年を演じ、今までの彼のイメージをガラリと変える役柄だったが、かなり成功していたと言える。決して上等の演技派俳優ではないが、映画のイメージに合わせた的確な演技だったと言える。
ヒロインのパーキーは、アッバース・タイヤワーラー監督の妻で、映画のストーリーライターも務めている。過去に出演作があるが、「Jhootha Hi
Sahi」で本格デビューしたと言っていいだろう。実質上この映画は彼女のために作られたものだと言える。彼女が演じたミシュカーは、自殺志願者として登場しながら割と明るくポジティブな面もあり、多少焦点が定まっていなかったが、彼女自身の演技力は合格点だ。ただ、老けて見えるときがあり、女優としては損をしている。セカンドヒロインのクルティカーを演じたマナスィー・スコットはストーリーの進行と共にだんだん存在感がなくなって行く。
脇役陣はほとんど無名の俳優ばかりだがなかなか個性派揃いだった。かろうじて有名作品に出演歴のあるのは数人。アーリヤーを演じたアリシュカー・ヴァルデーは「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」に出演、スシーを演じたアナイター・ナーイルは「Chak De India」(2007年)出演のいわゆるチャク・デー・ガールズの1人。他はおそらく新人である。中でも光っていたのはスィッダールトの親友オマルを演じたラグ・ラーム。ニヒルな演技が笑いを誘った。他にマーダヴァンとナンダナー・セーンが特別出演していたが、特にマーダヴァンの恋敵振りは秀逸であった。他に、アビシェーク・バッチャン、リテーシュ・デーシュムク、イムラーン・カーンが自殺志望者として声のみ出演している。
音楽はARレヘマーン。「Jaane Tu... Ya Jaane Na」に引き続き上品な曲が多い。ジャズ調の「I've Been Waiting」から映画が始まるところも似ている。あまりに「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」と音楽の雰囲気が似ているため、続編のような印象も受ける。いい曲が多いが、中でも「Cry Cry」や「Maiyya
Yashodha」などが秀逸。だが、映画の本筋が洗練され過ぎていて、挿入歌のいくつかは蛇足に思えた。それでも、ヒンディー語映画としての枠組みの中で新しいことに挑戦しようとする意気込みは十分感じられた。ストーリーや音楽に新感覚を求めながら挿入歌の伝統をしっかり守るところは気に入った。
「Jhootha Hi Sahi」は、「Jaane Tu... Ya Jaane Na」の監督が再び送り出した新感覚ボリウッドロマンス。ヒンディー語映画の中でもかなり洗練されたストーリー、演出、音楽で出来ており、多めの挿入歌さえ受け入れられれば、もはやインドやインド人のことをほとんど知らない日本人が見ても普通に楽しめるレベルまで来ている。「Jaane
Tu... Ya Jaane Na」が気に入った人には是非お勧めしたいが、同作よりもターゲットとなる年齢層は高めだ。
ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは非常に多作な映画監督・プロデューサーで、今まで数々の名作を送り出して来たが、特に得意とするのがアンダーワールドを舞台にした暴力映画である。「Satya」(1998年)、「Company」(2002年)、「Sarkar」(2005年)、「Contract」(2008年)などによって、世の中の変化に従って変容して行くアンダーワールドの有様を描き続けて来た。そのラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の最新作が「Rakht
Charitra」である。この映画は実話に基づいて作られた作品で、主人公プラタープのモデルとなっているのは、アーンドラ・プラデーシュ州の政治家パリターラ・ラヴィーンドラである。パリターラ・ラヴィーンドラはナクサライト(極左反政府ゲリラ)出身で後にテルグ国民党(TDP)の政治家となり、2005年に暗殺された人物である。また、この映画は最初から二部作として作られており、「Rakht
Charitra 2」は11月19日公開予定となっている。「Rakht Charitra 2」では、パリターラ・ラヴィーンドラを暗殺したスーリーをモデルにしたスーリヤを主人公にした作品になるようだ。また、「Rakht
Charitra」はヒンディー語版の他、テルグ語版とタミル語版も同時制作されている。
題名:Rakht Charitra
読み:ラクト・チャリトラ
意味:血の伝記
邦題:復讐伝
監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー
制作:マドゥ・マンテーナー、シータル・ヴィノード・タルワール、チンナ・ヴァースデーヴァ・レッディー、ラージクマール
音楽:スクヴィンダル・スィン、イムラーン・ヴィクラム、ダラム・サンディープ、バッピー・トゥトゥル
歌詞:ループ、シャッビール・アハマド、ヴァーユ、アビシェーク・チャタルジー、サリーム・モーミン
出演:ヴィヴェーク・オベロイ、アビマンニュ・スィン、コーター・シュリーニヴァース・ラーオ、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、ラーディカー・アプテー、シャトゥルガン・スィナー、ザリーナー・ワヒーブ、ラージェーンドラ・グプター、スシャーント・スィン、タニケッラ・バラニ、スディープ、ダルシャン・ジャリーワーラー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左はシャトゥルガン・スィナー、右はヴィヴェーク・オベロイ
| あらすじ |
血で血を洗う闘争が日常茶飯事となった町アーナンドプル。この町を支配していたのはナラスィンハデーヴ・レッディー(タニケッラ・バラニ)という政治家であった。そして不可触民出身ながら奉仕と忠誠によりナラスィンハデーヴ・レッディーの信頼を勝ち得ていたのがヴィールバドラ(ラージェーンドラ・グプター)であった。選挙が近づきつつある中、ヴィールバドラは自らの所属するカーストの候補者を全選挙区で擁立し、コミュニティーの地位向上を図っていた。ところがナラスィンハデーヴの兄ナーガマニ・レッディー(コーター・シュリーニヴァース・ラーオ)は、ヴィールバドラのことをよく思っておらず、ナラスィンハデーヴにヴィールバドラの悪口を吹き込む。惑わされたナラスィンハデーヴはヴィールバドラを遠ざけるが、ヴィールバドラはそれで引き下がる男ではなく、同カーストの仲間たちを率いてナラスィンハデーヴに牙をむいた。そこでナラスィンハデーヴとナーガマニは、ヴィールバドラの右腕マンダー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)を誘拐して脅し、彼にヴィールバドラを暗殺させる。
ところでヴィールバドラには2人の息子がいた。兄のシャンカル(スシャーント・スィン)は父のそばに常に付き添っており、父の暗殺後はゲリラとなってナラスィンハデーヴの仲間たちに復讐を開始した。ナーガマニの息子で「羅刹」と恐れられていたブッカー・レッディー(アビマンニュ・スィン)は父以上に残忍な男で、ヴィールバドラの血縁を根絶やしにするために行動を開始する。一方、弟のプラタープ・ラヴィ(ヴィヴェーク・オベロイ)は都市で大学に通っていた。プラタープにはナンディニー(ラーディカー・アプテー)という恋人がおり、結婚を希望していたが、彼女の両親は彼のカーストなどを理由に認めようとしていなかった。プラタープは父が殺されたことを知り、急いでアーナンドプルへ向かう。プラタープはシャンカルと再会するが、その直後にシャンカルはナーガマニの息のかかった警察に捕まってしまい、殺されてしまう。父と兄を失ったプラタープは、ナラスィンハデーヴ、ナーガマニ、ブッカーの3人を1人1人殺すことを誓い、復讐を開始する。まずはナラスィンハデーヴを白昼堂々殺害し、次にナーガマニを殺害した。また、プラタープはナンディニーと結婚し、共にゲリラ生活をし始める。
ナラスィンハデーヴとナーガマニが死んだことで、ブッカーの兄プル・レッディーが後継者となり、選挙に立候補する。同時にブッカーは対立候補者の殺害を部下たちに命じる。折しも、映画スターのシヴァージーラーオ(シャトルガン・スィナー)が新党民国党(PDP)を立ち上げ、キャンペーンを開始していた。シヴァージーラーオはアーナンドプルでも選挙ラリーを行ったが、ブッカーは爆弾テロを行い、シヴァージーラーオに挑戦する。そこでシヴァージーラーオは、ブッカーのライバル、プラタープと密会し、仲間に引き入れる。暗殺だけでは何も変わらないことに気付いていたプラタープは、システムの中からシステムを変えることを決意し、シヴァージーラーオと手を結ぶ。プラタープはシヴァージーラーオの政党の公認候補者としてアーナンドプルの選挙区から立候補し、プルを破って当選した。シヴァージーラーオの政党は州で第一党となり、シヴァージーラーオは州首相に就任した。党内にはプラタープを面白く思わない人物もいたが、シヴァージーラーオは彼を大臣に抜擢する。プラタープはすぐに州内のマフィアを呼び寄せて引き締めを行う。
プルが落選したことで立場を弱くしたブッカーは警察に逮捕されてしまうが、プルがシヴァージーラーオのライバル政党に働きかけを行ったことで、ブッカーはすぐに釈放されてしまう。自由の身となったブッカーは姿をくらまし、プラタープへの復讐を練っていた。それを耳にしたプラタープは、ブッカーの居所を突き止め、先手を打ってブッカーを暗殺する。向かうところ敵なしとなったプラタープであったが、彼の前にひとつの大きな障害が立ちはだかろうとしていた・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
根が映画オタクであるラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の作品は当たり外れが大きく、見る前に慎重にならなければならないのだが、「Rakht Charitra」は暴力が嫌いでなければ当たりに分類される作品だと言えるだろう。復讐が復讐を呼ぶ復讐の負のサイクルを、実話に基づいたストーリーによって淡々と語る映画で、俳優陣の好演や台詞の格好良さもあり、非常に重厚なドラマとなっていた。登場人物に完全なる善人は存在せず、モラルも何もない中、復讐のみが正義として存在し、登場人物たちを突き動かす。よって、映画の真の主人公は復讐と言ってもいいだろう。インド映画では、腐敗したシステムを変えるために、システムの外から変えるべきか、システムの中から変えるべきか、ということが時々語られるが、「Rakht
Charitra」のストーリーは、システムの中からシステムを変える手段を是としていた。主人公プラタープ・ラヴィは最初システムの外からシステムをひっくり返そうとする。ナラスィンハデーヴを殺し、ナーガマニを殺したが、次々と後継者が現れ、大きな変化は生まれなかった。そこでプラタープは、復讐相手を1人1人暗殺するという直接的手段ではなく、政治という巨大なシステムの中に入って、不可触民を弾圧し続けて来たシステムそのものを根本から覆すため、映画スターから政治家に転身したシヴァージーラーオと手を結ぶのであった。
実話に基づいているだけあり、主要登場人物の何人かは実在の人物がモデルとなっている。主人公プラタープ・ラヴィのモデルは前述の通りパリターラ・ラヴィーンドラである。他にモデルとなった著名人は何と言ってもNTラーマラーオ(NTR)だ。NTRはテルグ語映画界の大スターで、テルグ国民党(TDP)の創設者でもあり、アーンドラ・プラデーシュ州の州首相を3期に渡って務めた。劇中ではシヴァージーラーオとなっており、同じく俳優から政治家に転身したシャトルガン・スィナーが演じている。とりあえず「Rakht
Charitra」を見れば、1980年代にアーンドラ・プラデーシュ州の政界で起こった激変のエッセンスを理解できる。また、劇中でシヴァージーラーオのライバル政党として描写されながら具体的な言及がなかった政党(プルがブッカー釈放のために懇願しに行った)はおそらく当時中央で与党となっていた国民会議派であろう。
復讐劇自体は手に汗を握る展開で楽しめたのだが、映画としての完成度は決して高くなかった。もっとも気になったのは、専らナレーションでストーリーを進めていく手法である。全二部作中の第一部作ながら、まだ多くの要素を詰め込み過ぎていた。映画という媒体はまず映像で物を語るべきであり、映像に凝ることで知られるラーム・ゴーパール・ヴァルマーはそのことを重々承知のはずであるが、「Rakht
Charitra」ではストーリー進行上重要な部分はほとんどナレーションで手っ取り早く説明して済まされており、手抜きを感じた。ただ、ナレーションの語り口は独特で面白かった。ナレーションの問題と関連していると思われるが、シーンが中途半端にカットされてしまっている部分がいくつかあった。昔のインド映画によくあった、音楽が途中でぶつ切りされて次のシーンへ以降する現象が「Rakht
Charitra」でも見られた。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー映画の最大の欠点は音楽や音響の大袈裟な使用である。特に彼のホラー映画では、観客を怖がらせるために音響に大きく依存してる。「Rakht
Charitra」でも音楽がうるさすぎて映像の力をそいでいた。
主人公ヴィヴェーク・オベロイの演技は素晴らしかった。元々彼はラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の「Company」でブレイクした男優であるが、徐々に凋落して行った。だが、この「Rakht
Charitra」によって改めて実力を知らしめることに成功した。ヴィヴェークはラーム・ゴーパール・ヴァルマーに頭が上がらないだろう。極悪の悪役ブッカー・レッディーを演じたアビマンニュ・スィンの存在感も際立っていた。最近は「Gulaal」(2009年)で好演していたが、それを越える好演だと言える。名優シャトルガン・スィナーも貫禄の演技であったし、ナーガマニ・レッディーを演じたコーター・シュリーニヴァース・ラーオも良かった。他にもスディープ、スシャーント・スィン、ラージェーンドラ・グプターなども端役ではあったが印象深かった。
インド映画の伝統的フォーマットに従い、挿入歌がいくつか入っていたが、大したものはなかった。音楽や効果音のうるささに加えて音楽の弱さもこの映画の欠点に数えられるだろう。
劇中では舞台となっているアーナンドプルがどの州の町なのか明言がなかったが、看板の文字や自動車のナンバーから、アーンドラ・プラデーシュ州であることが分かった。だが、登場人物のしゃべる言語はビハーリー方言訛りで、多少そのギャップが気になった。ちなみにアーナンドプルのモデルとなっているのは、アーンドラ・プラデーシュ州のアナントプルである。
「Rakht Charitra」はラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督渾身の暴力映画。復讐のみが正義の世界が淡々と描写される。二部作の内の第一部作であるため、最終的な評価は第二部作の方を見てからでないと出来ないが、これだけでも一応完結しており、十分楽しめる。いくつか欠点はあるが、それを補って余りある俳優陣の演技が見所。特にヴィヴェーク・オベロイのファンは見逃せないだろう。
今年6月26日に長男が誕生した。最近はインドで出産する日本人駐在員の奥様も多いのだが、出産後のことなども考え、妻には日本で出産してもらった。名前はペルシア語起源のヒンディー語で「空」を意味する「アースマーン」から明日真(あすま)と名付けた。しばらくは妻の実家ですくすくと育っていたのだが、生後3ヶ月を過ぎた辺りで首も座ったため、デリーに呼び寄せることにした。英連邦競技大会(CWG)閉会式の2日後、ダシャハラー祭の1日前の10月16日に僕が日本まで迎えに行き、10月23日に僕と共に妻と明日真はデリーにやって来たのであった。
10月23日の夕方に空港に到着し、タクシーでカールカージーの自宅へ向かった。その途中、サフダルジャング・エンクレイヴに住むインド人の友人宅にも立ち寄って、明日真を見せた。自宅に到着したのは午後9時頃だったと記憶している。11月以内に引っ越す予定があったため、次の借家人候補に部屋を見せることが出来るようにと、家の鍵は階下に住む大家さんに預けていた。ただ、大家さんは病気で入院しており、大家さんの奥さんから鍵を返してもらった。この日の夜は、飛行機の長旅と突然の環境の変化に驚いてか、明日真は泣きじゃくっていた。
翌日10月24日の朝、とりあえず食料がなかったため、近所を歩き回っている野菜売りの行商から野菜を買った。その際、毎日自宅にゴミ集めに来ているお婆さんがやって来て「帰って来たのかい?」と聞かれたので、「帰って来た。子供も来たよ」と答えた。
同日の昼頃、昼食を食べ終えた頃に、突然ドアベルが鳴った。誰かと思って見てみると、女装してはいるが明らかに男性のインド人、つまりヒジュラーがいた。とりあえず1人しか見えなかったのでドアを開けて中に招き入れたら、後からゾロゾロと仲間たちがやって来た。合計5、6人はいただろうか。
ヒジュラーとは、名目上は両性具有者(半陰陽者、ふたなり)のコミュニティーである。インド各地でいろいろ呼び方はあるようだが、公の場ではキンナルと呼ばれることが多い。両性具有にも様々な状態があるのだが、全てひっくるめて男性とも女性とも言えない性器を持って生まれて来る子供の数は、数千人に1人とされており、それほど低い確率ではない。そんな両性具有者の子供が生まれると、インドではどこからともなくヒジュラーがやって来て、その子供を引き取って行くとされている。男でも女でもない存在のヒジュラーはインドの伝統社会では生殖を司る生き神として畏怖されており、結婚式や出産など、生殖と関わる場に現れて、新郎新婦や新生児に祝福を施すと同時に、バダーイーと呼ばれる祝い金を巻き上げる。特に田舎ではヒジュラーは今でも人々から畏敬を受けている。一応祝い金を巻き上げるだけあってテリトリー内の子供の成長を気に掛けており、育児の良き相談役となっている場合もある。逆に、生殖を司る生き神ヒジュラーの股間を見ると生殖能力を失って不能者になると信じられており、ヒジュラーが怒ると服をまくり上げて股間を見せようとして来る。この生殖に関する事柄がヒジュラーの主な仕事であるのだが、ヒジュラーは地域を統括する暴力団のような存在でもあり、テリトリー内に出店する店や新築の家の主などからバスティーと呼ばれる所場代を巻き上げたりもする。
ただ、実際にはヒジュラーの大部分を占めるのは生来の両性具有者ではなく、性転換者だとされている。しかも男性として生まれながら何らかの理由で男性器を切除した人が大半を占める。普通に考えたら性同一性障害が理由であろうが、性転換してヒジュラーとなった人々の性転換の動機は、そう単純ではないと報告されている。しかし、本来両性具有者コミュニティーとされているヒジュラーにとって、性転換手術の存在は秘密中の秘密であり、外部の人にそのときの状況が漏れることはほとんどないようである。しかしながら、現代の一般のインド人も、両性具有者としてではなく、オカマのような存在としてヒジュラーを見ているところがある。よって、以下「ヒジュラー」という用語は、両性具有者よりも性転換者として考えて使用することにする。
中国の宦官と同様に、王宮に仕えるヒジュラーもいた。インドの歴史上もっとも有名なヒジュラーは、デリー・サルタナト朝の皇帝アラーウッディーン・キルジーに仕えたマリク・カフールであろう。元々ヒンドゥー教の青年だったが、その美貌に一目惚れしたアラーウッディーンは彼をイスラーム教に改宗させただけでなく、去勢して寵愛した。マリク・カフールは後に軍才を発揮して将軍に抜擢され、南インドまで遠征して王朝に巨万の富をもたらした。「Mughal-e-Azam」(1960年)など、中世インドの王宮を舞台にしたヒンディー語映画などでも、当然のようにヒジュラーが登場する。
しかし、都市部を中心にヒジュラーの地位は下がって来ており、生き神としての畏敬はおろか、単なる厄介者扱いされることも多くなってしまった。多くの場合、ヒジュラー自身からも生き神としての威光は感じられず、乞食同然に道端や列車の中で人々から金銭を巻き上げるヒジュラーもいれば、赤線地帯で売春をするヒジュラーもいる。外国人によるインド旅行記を読むと、結構な割合でヒジュラーに遭遇して金を巻き上げられたり巻き上げられそうになったりした旨が記されているし、ムンバイーの赤線地帯カーマティープラーには、売春ヒジュラー専門のデール・ガリーという地域もある。「ヒジュラー」という言葉は、情けない男に対する悪口にもなっている。もはや都市部ではヒジュラーは嘲笑の対象である。
その一方で、最近はヒジュラーが政治的に組織化されても来ている。特にマディヤ・プラデーシュ州でその動きが活発だ。シャブナムというヒジュラーが同州の州議会議員に当選したこともあったし、ヒジュラーの市長も誕生している。ちなみに、シャブナムの半生を元にした伝記映画「Shabnam
Mausi」(2005年)も公開されている。
ところで、インドには主に2ヶ所、ヒジュラーが集まる寺院がある。グジャラート州のバフチャラー寺院とタミル・ナードゥ州クーヴァガム村のアラヴァン寺院である。バフチャラー寺院はアハマダーバードから近くアクセスしやすいし、アラヴァン寺院でのクーヴァガム祭を題材にした「Navarasa」(2005年)という映画も公開されている。また、デリーのメヘラウリーには「ヒジュラーたちのカーンカー」と呼ばれる中世の壁モスク兼墓地があり、かつてデリーに生きたヒジュラーたちが眠っている。
ヒジュラーについては、インドに住み始めた当初から多大な関心を抱いて来た。その直接のきっかけは、「ヒジュラ インド第三の性」(青弓社)の著者、石川武志氏の調査に通訳として同行したことだった。アジメールやデリーのヒジュラーを訪ね回り、ヒジュラーの実態を目の当たりにした。ただ、ヒジュラーの実態と言っても、想像していたような黒魔術師や悪魔崇拝者のようなおどろおどろしいものではなく、他のインド人と同様に、寝っ転がってテレビドラマを見たりしているような、とても親しみの沸くものだった。それでも、アジメールのような比較的田舎町でヒジュラーがいかに地元の人々から尊敬されているかを目にすることが出来、ヒジュラーに対する畏敬の念は僕の心にもしっかりと植え付けられた。もしデリーだけでヒジュラーを見ていたら、やはり単なる厄介者としか見なしていなかったかもしれない。しかし、いかに尊敬されていようとヒジュラーが付き合いにくい存在であることには変わりなく、日常で遭遇することは極力避けたい。インド人のおばさんは時々体格が良すぎて真性の女性なのにヒジュラーに見えたりもして(ヒゲが生えていることもあり)、「あれ、ヒジュラーかな?」と身構えてしまうこともよくある。
しかし、日本帰国の翌日に自宅の前に現れたヒジュラーを見たときは、「あれ、ヒジュラーかな?」と考える間もなくヒジュラーだと分かった。長男が誕生しデリーに連れて来たという心当たりがあったからである。しかしどうやって僕が長男と共に帰って来たことを知ったのか?前日の夜に自宅に到着し、その翌日の昼に訪問である。そちらの方が不思議であった。ただ、ヒジュラーとは言わば腐れ縁であるし、自分もヒジュラー訪問の当事者となったことに少し感動して、とりあえず家の中に招き入れたのであった。
残念ながら、家にやって来たヒジュラーは、儀式よりも金を巻き上げることが第一の、都市的ヒジュラーであった。長男誕生を祝う歌や踊りがあるはずだが、楽器などを持参した様子もなかった。誰から聞いたのか聞いてみたが、答えをはぐらかされた。どこから来たのか、という問いには、ニューデリー駅の近くから来たと答えただけだった。そんな遠くからわざわざ来るものなのか。どうやらカールカージー一帯はこのグループのテリトリーであるようだった。
誰から聞いたのか依然としてはっきりしなかったが、わざわざ来てくれたので、奮発してとりあえずバダーイー(祝い金)として500ルピー(約千円)を渡そうとした。長男誕生のときにヒジュラーにいくら払えばいいのか知らなかったが、かなり奮発したつもりだった。だが、ヒジュラーたちは「そんな少額の金は受け取れない」と言い出した。ではいくらなのか聞いてみたら、破格の11000ルピー(約2万円)を要求された。ヒジュラーたちは、住んでいる家が賃貸物件なのかそれとも購入したマイホームのかを執拗に聞いて来たため、おそらくそれによってバダーイーをどれだけふんだくれるか値踏みしているようであった。当然賃貸なので、それを主張し、しかも自分たちは学生と主婦で大した収入はないことを訴えた。そうすると要求額は一気に5100ルピー(約1万円)まで下がった。それでもまだ高い。ちょうど財布の中には500ルピー札4枚とその他の紙幣数枚しか入っていなかった。財布を開けて見せて、「これしか持っていないから5100ルピーは無理だ」と言って、もう1枚500ルピー札を渡し、合計1000ルピー(約2千円)を提示額として提示した。すると、「とりあえず今はこれだけもらっておいて、明日来るから、そのときに残りを払え」と言い出した。その後押し問答がしばらく続いたが、グループの中の1人が2100ルピー(約4千円)を提示した。他のヒジュラーたちはそれを制止しようとしたが、値段交渉の決まりとして一度提示した最低額または最高額は却下不可能であるためか、「仕方ない、2100ルピーでどうだ」ということになった。財布に入っているお金のほぼ全額だったため、こちらとしても出し尽くした感を出しやすい。それで交渉成立ということで、2100ルピーをバダーイーとして支払った。
ちなみに金額がキリの悪い数字になっているのは、「割り切れない数字は縁起がいい」というインドの習慣に基づくもので、慶事に受け渡しされるお金の額は大体21ルピーとか501ルピーとか半端な数字となっている。11000ルピー、5100ルピー、2100ルピーなどというのは割り切れる数で本当はおかしいのだが、1ルピーを余分にもらうよりも100ルピーをもらった方がいいという、ヒジュラーたちに都合のいい解釈なのであろう。
このときヒジュラーが行ったのは、米粒を部屋の四方にばらまくという簡素な儀式だけだった。その米粒も自宅にあったもので、あらかじめ小皿に盛ってヒジュラーに渡していた。その儀式が終わった後に残った米粒はバルカー(聖なる力)があると言って返してもらったのだが、その後普通に炊飯して食べてしまった。実はその米は日本米だったのだが、ヒジュラーのボスは日本米に興味を持ったようで、儀式用の米とは別に持ち帰り用の米をいくらから袋に入れて持って行った。こうして台風のように襲来したヒジュラーたちのグループは、僕たちから2100ルピーと少量の日本米を巻き上げて帰って行ったのである。
ヒジュラーが去った後、ヒジュラーがどうやって我々の情報を得たのか、ヒジュラーの情報網を調べることにした。我々がデリーの空港に着いてからヒジュラーが自宅にやって来るまでに出会った人は限られており、特定はかなり容易であった。まず翌日、床掃除にやって来た掃除人のおばさんに念のために聞いてみることにした。彼女は毎週月曜日から金曜日まで床掃除をしてもらっている。デリーに帰って来てからこのとき初めて会ったが、彼女には10月23日に息子を連れて帰って来ることをあらかじめ話していたため、彼女が犯人である可能性があった。彼女の返答は、「そういうことはヒジュラーに自然に知れてしまうのよ」という、いかにも迷信深いもので、はっきり判別できなかった。よって保留としておくことにした。ちなみに彼女曰く、ヒジュラーに支払う金額は大体5000ルピーくらいのようだ。我々は値下げ交渉し過ぎたようである。
次に、空港から自宅へ行く途中に立ち寄ったインド人の友人にヒジュラーのことを聞いてみた。そうしたら普通に大笑いしていたので、彼ではないだろうと判断できた。他にはタクシーの運転手や大家さんの奥さんなども可能性がないではなかったが、彼らではないだろうと漠然と感じられた。
もっとも怪しいのは、ゴミ集めのお婆さんである。インドでは毎朝戸口までゴミ集めに来るカチュラーワーラーと呼ばれる人々がいる。昔、ガウタムナガルに住んでいるときは1ヶ月40ルピーを払っていたが、カールカージーでは毎月80ルピー支払っている。地域の各家庭に出入りしているので情報通である。思い出してみると、デリー帰還の翌日朝に野菜売りから野菜を買っていたときに、我々の家に出入りしているゴミ集めのお婆さんが話しかけて来た。そのとき僕は彼女に「息子も来た」と情報を漏らしていた。そしてその直後にヒジュラーがやって来た。犯人は彼女である可能性が高かった。と言うより彼女しか考えられなかった。
ヒジュラー訪問から数日後、ゴミ集めに来たお婆さんと顔を合わせたので、「日曜日にヒジュラーが来たが、あんたが呼んだのかい?」と聞いてみた。そうしたら屈託のない笑顔で「そうよ、私が呼んだよ」と返答した。
一気に謎は解けた・・・。
あまりに邪心のない笑顔だったため、こちらも何か言う気が失せた。2100ルピーを巻き上げられたものの、面白い体験が出来たので、別に責める訳ではなかったのだが、こういうことはひた隠しにするものだと勝手に思っていたため、その正直な返答に拍子抜けしてしまった。しかしよく考えてみたら、携帯電話を持ってなさそうなお婆さんがどうやってヒジュラーに連絡を取ったのか(ヒジュラーは携帯電話を持っていた)、ヒジュラーからコミッションなどは入るのか、など、いくつか新たな疑問点も沸き上がって来た。ヒジュラーの生態だけでなく、ヒジュラーの周辺にいる協力者やその情報網なども掘り下げて調べてみると面白そうだ。インドの社会を下から支配する巨大な組織が浮かび上がって来るはずである。



