| ◆ |
10月1日(土) Saheb Biwi aur Gangster |
◆ |
インドが誇る名監督・俳優グル・ダットの傑作に「Sahib Biwi aur Ghulam」(1962年)があるが、それとよく似た題名の新作ヒンディー語映画が公開された。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の「Saheb
Biwi aur Gangster」である。だが、グル・ダットの上記作品のリメイクではない。主演はジミー・シェールギル、ランディープ・フッダーとマーヒー・ギル。
題名:Saheb Biwi aur Gangster
読み:サーヒブ・ビーヴィー・アォル・ギャングスター
意味:主人と夫人とギャングスター
邦題:ご主人、奥様、ギャングスター
監督:ティグマーンシュ・ドゥーリヤー
制作:ラーフル・ミトラ、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー
音楽:アミト・スィヤール、スニール・バーティヤー、ジャイデーヴ・クマール、アヌージ・ガルグ、アビシェーク・ラーイ、アンキト・ティワーリー、ムクタル・サホーター
出演:ジミー・シェールギル、ランディープ・フッダー、マーヒー・ギル、ヴィピン・シャルマー、ディーパル・シャー、ディープラージ・ラーナー、シュレーヤー・ナーラーヤン
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

左からジミー・シェールギル、マーヒー・ギル、ランディープ・フッダー
| あらすじ |
ウッタル・プラデーシュ州デーヴガルのラージャー・サーヒブ(ジミー・シェールギル)は、過去の栄光や地元における政治力こそ何とか維持していたものの、経済的には困窮していた。サーヒブは亡き父親の妾の子であり、正妻バリー・ラーニーとは不仲であった。しかし全財産はバリー・ラーニーが握っており、サーヒブは事あるごとに彼女から金を無心しなければならなかった。サーヒブは2度結婚していた。最初の妻は自殺し、2番目の妻チョーティー・ラーニー(マーヒー・ギル)は気が触れてしまっていた。その大きな原因は、サーヒブが入れ込んでいる娼婦マフアー(シュレーヤー・ナーラーヤン)の存在であった。サーヒブは週に何度もマフアーの元へ通っていた。
また、サーヒブは地元マフィアのゲーンダー・スィン(ヴィピン・シャルマー)と敵対しており、地元の土木工事の入札で争っていた。サーヒブは州大臣のティワーリーに恩を売っていたが、ティワーリーはゲーンダー・スィンと通じていた。
あるときチョーティー・ラーニーの運転手スンダルが轢き逃げにあって重傷を負う。その代わりにサーヒブの邸宅に運転手としてやって来たのがスンダルの甥のラリト、通称バブルー(ランディープ・フッダー)であった。バブルーは片思いしていた女の子のボーイフレンドに暴行を加えて意識不明の重体としてしまい、容疑を掛けられていた。それから逃れるためにゲーンダー・スィンに相談したのだが、ゲーンダー・スィンは彼を助ける代わりにスパイとしてサーヒブの家に送り込んだのだった。スンダルの轢き逃げもゲーンダー・スィンの手によるものだった。
バブルーは当初、サーヒブの腹心カナイヤー(ディープラージ・ラーナー)の娘ビジュリー(ディーパル・シャー)をはじめ、サーヒブ、チョーティー・ラーニーを含め、サーヒブの家にいる人間はみんな気違いだと考える。だが、孤独を感じていたチョーティー・ラーニーに気に入られることになり、彼女と恋仲になってしまう。徐々にバブルーはチョーティー・ラーニーを手に入れることだけを考えるようになる。
そのためにまずはサーヒブの信頼を勝ち取ろうとする。バブルーはまずサーヒブに、自分がゲーンダー・スィンのスパイとして送り込まれたことを自ら明かす。そして二重スパイになることを申し出る。最初は怒ってバブルーに暴行を加えたサーヒブであったが、バブルーの言った通りにゲーンダー・スィンの手下から襲撃を受けたことで、バブルーを信頼するようになる。バブルーは表向きはサーヒブの腹心として、裏ではチョーティー・ラーニーの愛人として、権力を握り始める。
チョーティー・ラーニーはマフアーを殺そうと画策していた。そのためにバブルーは妙案を考える。バブルーはサーヒブとマフアーが一夜を過ごそうとしていた密会の場にゲーンダー・スィンを招き入れる。それと同時にサーヒブにもゲーンダー・スィンの襲撃を密告する。そのおかげで密会の場を襲撃したゲーンダー・スィンは逆に返り討ちに遭って死んでしまう。また、バブルーは予めマフアーの携帯電話からゲーンダー・スィンに何度も電話を掛けていた。携帯電話の請求書からわざとそれを発覚させ、サーヒブがマフアーを疑うように仕向ける。サーヒブはまんまと計略に乗り、マフアーを殺してしまう。
マフアーが死んだことでチョーティー・ラーニーはサーヒブの愛情を受けるようになる。チョーティー・ラーニーはそれで満足するが、既にチョーティー・ラーニーの虜となっていたバブルーはサーヒブを殺そうと考える。バブルーは次期選挙でサーヒブと戦うことになるティワーリー大臣にも根回しし、サーヒブ暗殺を実行する。しかしサーヒブは瀕死の重傷を負いながらも一命を取り留めた一方、バブルーはチョーティー・ラーニーに殺されてしまう。
選挙が行われ、半身不随となりつつもサーヒブは当選する。表立ってサーヒブを支えていたのはチョーティー・ラーニーであった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
シェークスピア劇や、シェークスピア劇を北インドの田舎に置き換えて作られたヴィシャール・バールドワージ監督の「Maqbool」(2003年)や「Omkara」(2006年)を思わせる、重厚な人間ドラマであった。
この映画の重要なテーマは「裏切り」である。サーヒブの家では、サーヒブとその片腕カナイヤーの信頼関係などいくつかの例外を除き、あらゆる人間関係がうまく行っていない。そして主人公となる3人――サーヒブ、ビーヴィー(チョーティー・ラーニー)、ギャングスター(バブルー)――がそれぞれ裏切りを行う。封建領主の身分を引きずるサーヒブにとっては裏切ることも裏切られることも大した問題ではなく、娼婦に散財するのも支配者の特権であり、敵に命を狙われるのも支配者の運命だと考えている。チョーティー・ラーニーは、夫に冷遇される毎日を過ごす中で精神に異常をきたすが、若い運転手が来たことで彼を性欲のはけ口とし、夫を裏切る。しかし夫への愛情は冷めておらず、サーヒブの愛人を暗殺しようと画策する。バブルーはサーヒブの敵ゲーンダー・スィンによってスパイとしてサーヒブの家に送り込まれたため、最初から裏切りの男である。だが、チョーティー・ラーニーに惚れ込んでしまったことで、まずはゲーンダー・スィンを裏切り、次にサーヒブを殺そうとする。このように裏切りに裏切りを重ねるドラマとなっている。ただし劇中には忠実な人物もおり、例えばサーヒブに絶対的服従をするカナイヤーや、サーヒブに娼婦としての対応以上の愛情を注ぎ込むマフアーにそれが見られた。しかし裏切りの連鎖反応の中では、彼らの忠信も裏切りの引き立て役にしか見えない。これらのドロドロとした人間関係が、薄汚れた邸宅の中で巧みに展開される映画だった。そして主役、脇役に関わらず、俳優たちの演技も素晴らしかった。
旧藩王末裔の衰退しつつある栄光がかなり写実的に描かれていたのも魅力的だった。地元の村人たちからは政府役人よりも信頼されているサーヒブであるが、州政府の政治家やそれに取り入るマフィアたちからは敵視されている。また、サーヒブの人物設定で特徴的だったのは、亡き父親の妾の子であること、父親の正妻つまり継母と不仲であること、そして経済的実権を継母に握られていることである。父親が妾に子供を産ませたように、サーヒブ自身も妻よりも娼婦マフアーに没頭してしまっている。そしてサーヒブがもっとも嫌うのが、他人から懐事情の心配をされることだった。旧王族としてのプライドから彼は財政的に困窮していることを他人から指摘されることを極度に嫌っていた。だが、誰の目にも彼の経済的困窮は明らかで、愛人のマフアーからそういうことを言われたときにも彼は不機嫌になった。そういう退廃的な旧王族の実態がストーリーによく絡められていたし、それを演じたジミー・シェールギルの演技力も賞賛されて然るべきものだった。正当に評価されていない俳優の一人であるが、確かな演技力と存在感を持つ男優に成長した。
チョーティー・ラーニーへの恋慕の情から最終的にサーヒブ暗殺まで計画する「ギャングスター」バブルーを演じたランディープ・フッダーも素晴らしかった。元々渋い演技をする男優であったが、今までそれほど役柄に恵まれて来た訳でもなかった。だが今回彼は映画の出来を左右するほど重要な役に抜擢され、それを難なくこなした。演技でもっと深みを持たせることもできたとは思うが、とりあえず合格点だと言える。今までの彼の出演作の中でベストの演技であろう。
しかし圧巻だったのはチョーティー・ラーニーを演じたマーヒー・ギルである。「Dev. D」(2007年)で既に存在感を示していたが、しばらくは「Dabangg」(2010年)の端役など、不遇の時を過ごして来た。しかし今年に入り、「Not
A Love Story」(2011年)に続いてセンセーショナルかつ演技力のいる役をもらえ、それを存分に活かしていた。濡れ場も何のその。遅咲きの女優であるが、今後ますます活躍しそうだ。
サブ・ヒロインの扱いになるが、娼婦マフアーを演じたシュレーヤー・ナーラーヤンもマーヒーと同じくらい濡れ場に挑戦していたが、かわいらし過ぎてあまり娼婦という感じがしなかった。あまり情報がないが、基本的にはテルグ語映画界の女優のようだ。また、ディーパル・シャーも端役で出演していた。ディーパルは「Kalyug」(2005年)でセクシーな衣装と共にかなり衝撃的なデビューをしたのだが、その後が続かず、いつの間にか目立たない穏やかな端役女優に落ち着いてしまった。「Saheb
Biwi aur Gangster」も彼女のキャリアには大きな影響を及ぼさないだろう。
ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督はシリアスな社会派映画で知られた映画監督であるが、この作品を見て、人と人との複雑な絡み合いもかなり巧みに描写できる監督だと改めて感心した。手前味噌になるが、ティグマーンシュ・ドゥーリヤーは、僕が出演した「Paan
Singh Tomar」の監督である。撮影現場やアフレコの場で観察した彼からは、何だかいい加減かつ優柔不断な感じがして、それほど才能を感じなかったのだが、この作品を見て見直した。ちなみに「Paan
Singh Tomar」は未だに公開されていない。「Saheb Biwi aur Gangster」の方が後から撮られたはずだが、こちらの方が先に公開となってしまった。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督のインタビューによると2012年3月公開予定とのこと。僕がインドにいる間に公開されるだろうか?
音楽は多数の作曲家による合作となっている。重厚なストーリーながら、恋愛のシークエンスなどで効果的に挿入歌が入っており、決して場違いな雰囲気ではなかった。しかしひとつひとつの楽曲の力は弱い。
舞台はウッタル・プラデーシュ州の片田舎にある架空の旧藩王国デーヴガルであったが、ロケはグジャラート州のデーヴガル・バーリヤーで撮影された。サーヒブの邸宅など、とてもいい雰囲気の建築物であった。
「Saheb Biwi aur Gangster」は、ヴィシャール・バールドワージ監督の一連のシェークスピア映画を彷彿とさせる重厚な人間ドラマ。俳優たちの演技も素晴らしい。今週公開された多数の新作映画の中で、もっとも見る価値のある作品であろう。
現在インドは9夜続くナヴラートリ期間に入っており、この後ダシャハラー、ダンテーラス、ディーワーリー、バーイー・ドゥージなど、ヒンドゥー教の大きな祭りが続く。年間を通し、インド人の経済活動がもっとも活発になる時期であり、企業は大々的なセールやキャンペーンをするのが通例である(最近の新聞は広告だらけだ)。また、それに伴って多額の現金や高価な貴重品を持ち歩いたり家に置いたりする機会が増えるため、スリ、空き巣、泥棒の活動が活発になるのもこの時期である。
デリーでは今年も各地でラームリーラーが行われている。ラームリーラーは叙事詩「ラーマーヤナ」を題材にした野外劇で、ナヴラートリの9日間にその翌日のダシャハラーを加えた合計10日間、毎晩上演される。もっとも有名なのはオールド・デリーのラームリーラーで、ラール・キラー前の広場やトゥルクマーン門前のラームリーラー・マイダーンなどでお互い競い合うようにラームリーラーが行われる。また、ラームリーラーが開催される広場では隣接してメーラーと呼ばれる遊園地が設置されることが多く、行ってみると面白い。
ラームリーラーのクライマックスは何と言っても最終日のラーヴァン・ダハンである。「ラーマーヤナ」に登場する羅刹王ラーヴァン(サンスクリット語読みでラーヴァナとも書かれる)と、その兄弟であるクンブカランとメーグナードの像が燃やされる。神話ではこの日にラームがラーヴァンを殺したとされているためだ。ダシャハラーは「悪に対する正義の勝利」を祝う祭りであり、ラームリーラーと同時並行的に祝われているドゥルガー・プージャー(ヴィジャイ・ダシャミー)でも、この日にドゥルガー女神が悪魔マヒシャーを退治した神話上の出来事が祝われる。ダシャハラーはヒンドゥー教の数ある大晦日・新年のひとつであり、特に商人コミュニティーにとって重要な祭日となっている。

ラーヴァンとその兄弟の像
ところが、面白いことにインドでは「ラーマーヤナ」で一般的に敵役とされているラーヴァンを信仰するコミュニティーもある。以前、ウッタル・プラデーシュ州のビスラクという村を訪ねたことがあった(参照)。ノイダとグレーター・ノイダの間に位置するこの村はラーヴァンの生まれ故郷とされており、古いシヴァリンガを祀る寺院が残っている。ラーヴァンはシヴァ神の信奉者だと言われており、村人たちはラーヴァンを信仰している。よってビスラク村ではダシャハラーは祝われず、ラーヴァン・ダハンも行われない。
インド各地にある「ラーヴァン教」の話題はダシャハラー近くなると時々新聞などで取り上げられることがある。10月1日付けのタイムズ・オブ・インディア・クレストにはウッタル・プラデーシュ州ラマーバーイー・ナガル県のプクラーヤン村(Pukhrayan)で毎年開催されるラーヴァン・メーラーの記事が載っていた。
カーンプルの近くに位置するプクラーヤン村のラーヴァン・メーラーは、他所のラーヴァン信仰とは違って、非常に政治色が強い。まずは主催団体がある。バールティーヤ・ダリト・パンサー委員会という団体がこのメーラーを主催している。その名の通り、ダリト(不可触民)の団体である。しかも彼らは、面白いことにラーヴァンの出自を、ウッタル・プラデーシュ州では指定カースト(ST)となっているゴーンド族だとし、仏教徒だと考えている。そして、ダシャハラーの日に近隣から後進部族や後進カーストなどの社会的弱者を集め、ラーヴァンの像を載せた御輿を行進させた後、プクラーヤン村の農商業委員会広場(クリシ・マンディー・サミティ・マイダーン)にて仏僧の導きにより集団で仏教に改宗する「ディークシャー(入信式)」を行っている。深い歴史のある行事ではなく、18年前から始まったものだと言う。
おそらくラーヴァンはインド神話上もっとも複雑なキャラクターであり、様々な解釈をされている。インド神話ではラーヴァンは創造神ブラフマーのひ孫とされ、富の神クベールの異母兄弟でもある。だが、アーリヤ人の侵入以前にインド亜大陸に住んでいたアーディワースィー(先住民)やドラーヴィダ人の王または神だったとされることもある。プクラーヤン村のラーヴァン信仰者たちはどうもダリトのようだが、インド各地に点在するラーヴァン信仰者たちにはブラーフマンも多い。例えばマディヤ・プラデーシュ州ラーヴァングラーム村のラーヴァン信仰者たちはカーンニャクブジャ・ブラーフマンであるらしい。ラーヴァンはしばしば10の頭を持つ恐ろしい(もしくはユーモラスな)姿で描かれるが、それも様々な解釈がされる。有名なのは、10の頭はラーヴァンの全知全能を示すものとする説だ。「10」という数字は北、北東、東、南東、南、南西、西、北西の8方位と上下を合計した数でつまり全方位を指し、彼の知恵と知識が全方位に及ぶことを示しているとされる。
しかしながら、ラーヴァンを仏教徒とする信仰は初耳であった。確かに仏教文献においては、ヒンドゥー教徒が一般に信じる「ラーマーヤナ」と違って、ラーヴァンを善玉とし、ラームを悪玉とするものがあるらしい。また、ラーヴァンが支配するランカー島は、一般に現在のスリランカとされている。スリランカの人口の7割は仏教徒である。しかし、ラーヴァンを仏教徒とする根拠としては、それらはあまり関係なさそうだ。もしラーヴァンが仏教徒ならば、仏教誕生(紀元前5世紀)以降に「ラーマーヤナ」の出来事が起こったことになる。それでいいのだろうか?おそらくラーヴァンを仏教徒とする信仰は、プクラーヤン村の新仏教徒ダリト・コミュニティーが勝手に後付けしたのだろう。一般的にはラーヴァンはシヴァ派のブラーフマンとされるため、アンチ・ブラーフマンの立場に立って政治活動を行うことが多いダリトたちがラーヴァンを信仰するのはおかしな現象のように見えることだろう。ちなみに、プクラーヤン村から近い産業都市カーンプルにはラーヴァン寺院があり、ダシャハラーの午前中にだけご開帳となる。この地域には元々ラーヴァン信仰が根付いていたようで、ダリトのコミュニティーが、毎年燃やされるラーヴァンを被抑圧者の象徴と考え、それに便乗したのではないかと思われる。
それはともかくとして、ラーヴァンの異なったパーソナリティーは、インド神話における、メインストリーム信仰とマイナーかつローカルな民間信仰の間のギャップのひとつの例と言えるだろう。歴史上の人物の中にも、とある国では英雄扱いなのに、別の国では悪鬼羅刹扱いということがある。例えばアレキサンダー大王はヨーロッパでは英雄だが、イランでは悪魔扱いである。インド神話に登場するアスラ(悪魔)が、ゾロアスター教ではアフラ・マズダという神として信仰されているのも有名だ。インド神話にも、インド国内に限っても、そういうことが多々ある。例えば「マハーバーラタ」の登場人物カルナは好例だ。カルナはマハーバーラタ戦争で悪玉とされるカウラヴァ兄弟に味方し、善玉とされるパーンダヴァ兄弟の宿敵となったために、メインストリームのストーリーでは悪役とされるが、南インドの民間伝承ではカルナこそが英雄視されている。
ちなみに、マニ・ラトナム監督の映画「Raavan」(2010年)も、「ラーマーヤナ」神話の矛盾点や民間信仰とのギャップをうまく突いた作品であった。シャールク・カーンの期待の新作「Ra.One」も題名がラーヴァンを意識したものとなっており、アルジュン・ラームパール演じるRa.Oneがどのようなキャラクターとなるか楽しみである。また、2006-2008年にはラーヴァンを主人公にしたテレビドラマも放映された。現代でもラーヴァンは人々の関心を惹き付けている。インド神話でもっとも面白いキャラクターである。
ベテラン俳優が監督業やプロデューサー業に進出するのはヒンディー語映画界でも別段珍しいことではなく、アーミル・カーン、シャールク・カーン、アニル・カプール、アジャイ・デーヴガン、サイフ・アリー・カーン、アクシャイ・クマール、ラーラー・ダッター、アルジュン・ラームパールなど、多くの俳優が映画の監督・制作を手掛けている。30年間俳優として活躍して来たサンジャイ・ダットもそのバンドワゴンに乗り、主演兼プロデュース作品を送り出して来た。本日より公開のコメディー映画「Rascals」である。監督はコメディーの帝王デーヴィッド・ダワン。サンジャイ・ダットとは「Jodi
No.1」(2001年)や「Shaadi No.1」(2005年)などいくつかのヒット・コメディー映画で仕事をして来た。共演はアジャイ・デーヴガン。最近ローヒト・シェッティー監督の「Golmaal」シリーズなどでコメディアンとして開花している。ヒロインはこれまた最近コメディー映画によく出演しているカンガナー・ラーナーウト。
題名:Rascals
読み:ラスカルズ
意味:ごろつきたち
邦題:ラスカルズ
監督:デーヴィッド・ダワン
制作:サンジャイ・ダット、サンジャイ・アフルワーリヤー、ヴィナイ・チョークスィー
音楽:ヴィシャール・シェーカル
歌詞:イルシャード・カーミル、アンヴィター・ダット・グプタン
出演:サンジャイ・ダット、アジャイ・デーヴガン、カンガナー・ラーナーウト、アルジュン・ラームパール、リサ・ヘイドン、チャンキー・パーンデーイ、サティーシュ・カウシク、ヒテーン・パインタール、ムシュターク・カーンなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からリサ・ヘイドン、アジャイ・デーヴガン、
サンジャイ・ダット、カンガナー・ラーナーウト
| あらすじ |
こそ泥のチェータン・チャウハーン、通称チェートゥー(サンジャイ・ダット)とバガト・ボースレー、通称バッグー(アジャイ・デーヴガン)はムンバイーで別々にマフィアのアンソニー・ゴンザルベス(アルジュン・ラームパール)から50万ルピーとベンツを盗み、バンコクへ高飛びする。たまたまバンコク行きの飛行機の中で同席となったチェートゥーとバッグーは知り合いとなる。
バッグーはバンコクの高級ホテルのスイートルームに宿泊し、高級コールガールのドリー(リサ・ヘイドン)と遊びまくる予定だった。バッグーは隙を見てチェートゥーの財布を盗むが、チェートゥーの方が一枚上手で、偽の財布を掴まされ、逆に時計と財布を盗まれてしまった。しかもチェートゥーはバッグーになりすましてホテルに泊まり、ドリーと遊んでいた。バッグーは傷心のままインドに帰ろうとする。
チェートゥーは相棒のナノ(ヒテーン・パインタール)と共にバンコクで「アート・オブ・ギビング」という新興宗教団体を起こし、金持ちから寄付と称して多額の金を巻き上げていた。だが、チェートゥーの真のターゲットはバンコクで豪遊する大金持ちの娘クシー(カンガナー・ラーナーウト)であった。チェートゥーはクシーをパートナーとし、アート・オブ・ギビングの活動を拡大する。
チェートゥーとクシーは盲人のためのマラソンを主催する。そこへ盲人を装って飛び入り参加し、優勝したのがバッグーであった。賞品としてチェートゥーの泊まっているホテルにバッグーも宿泊することになった。バッグーはインドへ帰ろうとしていたのだが、空港でクシーを見掛けて一目惚れし、彼女の後を追い掛けて来たのだった。バッグーは盲人の振りをしてクシーの同情を誘い、彼女を物にしようとする。こうしてクシーを巡ってチェートゥーとバッグーは醜い騙し合いを繰り広げることになる。ホテルの支配人BBC(チャンキー・パーンデーイ)も何かと2人の争いに巻き込まれる。だが、最終的に2人は同時にクシーと結婚しようと寂れた教会を訪れる。神父(サティーシュ・カウシク)は2人をボクシングで対決させ、勝った方がクシーと結婚できると言う。2人はボクシングを始めるが、ボコボコに殴られたのはレフリーとなった神父であった。
ところがアンソニーがバンコクまで追い掛けて来ていた。アンソニーはクシーを誘拐し、身代金を要求する。チェートゥーとバッグーは銀行強盗をしようとするが、その銀行で本物の銀行強盗から銀行を救ってしまう。何とかどこかから金を用意したチェートゥーとバッグーはその金と交換にクシーを助け出そうとする。ところがクシーは実はアンソニーのガールフレンドであり、アンソニーから送り込まれていた。しかも神父もBBCもアンソニーの手下であった。チェートゥーとバッグーは袋詰めにされ放置される。2人の完全敗北だと思われた。
しかし、身代金として用意した金は、実はアンソニーの家から盗んで来たものだった。銀行強盗に失敗した後、2人は急いでムンバイーに戻り、アンソニーの家にサンタクロースの扮装をして入り込み、どさくさに紛れて金庫から金を盗み出したのだった。チェートゥーとバッグーは詐欺師を止めることをお互いに誓って別れる。
数年後・・・。チェートゥーはガウタムという名の半身不随者を演じ、金持ちの集まるパーティーで治療のために寄付金を集めようとしていた。ところがそこに現れたのは医者ガンビールを名乗るバッグーであった。バッグーはチェートゥーに棒で襲い掛かり、荒療治する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
デーヴィッド・ダワン監督のコメディー映画は定評があり、期待するレベルも自ずから高くなる。その期待から言えば「Rascals」は力不足であった。コメディー映画としての出来は平均以上であるが、デーヴィッド・ダワン映画の中では平均以下と言える。しかもタイミングの悪いことに、つい3ヶ月前に公開された「Double
Dhamaal」(2011年)と酷似したプロットで、新鮮さがなかった。「Double Dhamaal」とは、プロットのみならず、サンジャイ・ダットとカンガナー・ラーナーウトというキャストまで共通しており、既視感が否めなかった。
映画の大半はチェートゥーとバッグーの間の、クシーを巡る騙し合いであり、コメディーの中心もここにある。しかし、2人が酔っ払って教会へ行ってクシーと同時に結婚しようとするところなどは、それまでの流れから見て不可思議であった。ラストは多少唐突過ぎる感もあったが、十分意外性のあるもので、エピローグもまあまあ面白かった。全体的にはコメディー映画としての必要最低限の義務は果たしており、ストーリーの大きな破綻もなく、佳作と言える出来ではあるが、やはりデーヴィッド・ダワン監督にはもう少し上のコメディー映画を求めてしまう。もしかしたら時代は「Munnabhai」シリーズなどのラージクマール・ヒーラーニー、「Golmaal」シリーズなどのローヒト・シェッティー、「Singh
is Kinng」(2008年)などのアニース・バーズミーなどに移行しているのかもしれない。
アクション映画で本領を発揮する2人のベテラン筋肉派俳優が主演だったが、2人ともコミックロールにも定評があり、「Rascals」でも大暴れしていた。サンジャイ・ダットとアジャイ・デーヴガンはコメディー映画「All
the Best」(2009年)でも共演しているが、コンビを組んだのは今回が初めてであろう。スクリーン上での相性は悪くなかった。
カンガナー・ラーナーウトはデビュー以降、精神的に破綻をきたすようなシリアスな役柄で名声を獲得して来たのだが、「No Problem」(2010年)や「Tanu
Weds Manu」(2011年)などライトな映画にも積極的に出演するようになり、かなりイメージが変わった。彼女の甘ったるくてハスキーで少し舌足らずの声は、コミックロールを演じると何だか本当の馬鹿女のように聞こえてしまうのが難点ではあるが、コメディー女優としてもかなり地盤を固めて来たように思える。
変わったところではアルジュン・ラームパールが特別出演扱いで出ていたことだ。しかし彼に任された役は決して小さくない。アルジュンがコメディー映画に出演したのはこれが初めてではなく、「Housefull」(2010年)など前例があるが、コミックロールは未だない。「Rascals」でも真面目な悪役であった。また、オーストラリア出身のモデル、リサ・ヘイドンがサブ・ヒロイン扱いで出ていた。しかしながら単なるセクシー・アイテムであった。
音楽はヴィシャール・シェーカル。コメディー映画らしく派手で明るい音楽が多かったが、ヴィシャール・シェーカルとしてはかなり肩の力を抜いて作った曲ばかりだと感じた。それほど印象に残る曲はなかった。
映画中には、過去の映画や実在の人物のパロディーが随所に見られた。例えば主人公2人の名前チェータンとバガトは、売れっ子小説家チェータン・バガトから取られている。エピローグで2人が名乗るガウタムとガンビールも、人気クリケット選手ガウタム・ガンビールがネタ元だ。サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」(2005年)や「Guzaarish」(2010年)なども笑いのネタにされていた。それらひとつひとつを特定するのも楽しい。
映画の大半はバンコクで撮影されていた。それも舞台はほぼパン・パシフィック・ホテルの中のみで、かなり短期間にかなり限られたロケーションで手っ取り早く撮影された映画であろうことが予想された。
「Rascals」はコメディーの帝王デーヴィッド・ダワン監督の最新コメディー映画。サンジャイ・ダットがプロデューサーに挑戦したことも特筆すべき。コメディー映画としては合格だが、デーヴィッド・ダワン監督にはもっと上のレベルを目指して欲しかったと思う。ヒンディー語映画初心者にはあまり勧められない。
ニューデリーのタージマハル・ホテル前、カーン・マーケットの裏にあるクリスチャン・セメタリー(新EICHER「Delhi City Map」P116
G3: York Cemetery)に、デリー近郊に墜落した日本航空471便の犠牲者慰霊碑があると聞いて、訪ねてみた。
僕の生まれる前の出来事で全く知らなかったが、1972年6月14日に日本航空の南回りヨーロッパ線の飛行機がデリー近郊に墜落する事件があった。便名はJL471、機体記号はJA8012、機種はDC-8-53型。日本航空が海外で起こした最初の墜落事故のようである。
クリスチャン・セメタリーは独立前から存在する歴史ある墓地で、凹型の敷地内に多数のキリスト教徒が葬られている。名前を見てみると外国人とインド人の両方の墓があった。おそらく独立前は英国人専用だったのではないかと思われる。大統領官邸の北、グルドワーラー・ラカーブガンジの西にある教会カセドラル・チャーチ・オブ・リデンプション(Cathedral
Church of Redemption)が管理している。

クリスチャン・セメタリー
問題の慰霊碑は、墓地のゲートをくぐって直進するとすぐに見つかる。日本語で大きく「JA8012号機遭難者慰霊碑」と書かれている。英語ではさらに詳しく、「In
memory of those who died in the air disaster at Jaitpura, near Delhi, on
14th June 1972, whose ashes are buried here(1972年6月14日、デリー近郊ジャイトプラーでの墜落事故で亡くなった人々を偲んで。彼らの遺灰はここに眠る)」と書かれている。

JA8012号機遭難者慰霊碑
墜落地として刻まれていた「ジャイトプラー」がどこなのか特定できなかったが、もしジャイトプル(Jaitpur)ならば、グレーター・ノイダにその名の村がある。しかしながら、ウィキペディア情報によれば、墜落場所は「パーラム国際空港(現インディラー・ガーンディー国際空港)より27km手前のヤムナー河畔」とのこと。グレーター・ノイダのジャイトプルは空港よりさらに遠いので、別の村である可能性が高い。
墜落した飛行機には乗客78名、乗員11名が乗っていた。この内生存者が3名おり、86名が死亡。また、運悪く墜落地には工事作業員が工事をしており、その内の4名が亡くなった。
この慰霊碑には米国人3名、オーストラリア人5名、英国人14名、ドイツ人1名、オランダ人1名、日本人1名、ペルー人1名、スウェーデン人2名の名前が刻まれている。記録されている犠牲者数からすると少ない。残りはみんなインド人だったという訳でもなかろう。少なくとも日本人の死者はもっといたはずだが、「Tetsuro
Yamada」という名前のみが刻まれている。他の犠牲者はキリスト教徒ではなかったからここに葬られなかったのであろうか?それとも慰霊碑の建立に出資した遺族の名前のみが刻まれているのだろうか?40年前の事故にしては、慰霊碑が新しいように見えたが、最近建てられたものなのだろうか?墓地の管理人がいなかったためにその辺りのことは聞けなかった。

キリスト教なのにインドらしい墓
ちなみにこの事故で死んだ著名な日本人としては宮崎松記(1900-1972年)がいる。インドのハンセン病根絶のために尽くした医者で、「アジアの救ライの父」や「日本のシュバイツァー」などと呼ばれた。彼は1964年、アーグラーにらいセンターJALMA(Japan
Leprosy Mission for Asia、現在はNational JALMA Institute of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases)を開院した。タージ・マハルの東には彼の名にあやかったドクター宮崎通り(Dr. M. Miyazaki Marg)もある。タクシーなどでタージ・マハルを訪れる観光客のための駐車場(シルプグラーム)からタージ・マハルまでの道が何を隠そうこのドクター宮崎通りであり、宮崎博士が創設したらいセンターはその向かい側にある。

宮崎松記
宮崎博士の母校、熊本県八代市立日奈久小学校には宮崎博士の記念碑があるようだが、デリーのこの墓地には宮崎博士の死を祈念するものはなかった。
最近、1週間に何本もの新作ヒンディー語映画が公開されている。しかもどれも決定的な話題作ではないことが多く、取捨選択が難しい。こういうときに僕が指標としているのは、どの映画がどれだけの上映回数を得ているかである。映画が一般公開される前に新作のことをもっともよく知っているのは映画館の人間であり、当然のビジネス戦略としてヒットの見込める映画ほど上映回数を増やす傾向にある。よって、逆に言えば上映回数の多い映画ほど面白い作品であることが多い。特に近所の映画館PVRプリヤーで何が上映されるかに注目している。この映画館は昔ながらの単館ながら、インド最大のマルチプレックス・チェーンであるPVRグループの発祥の地である。単館であるためにマルチプレックスのように全てを上映することはできず、厳選される。場所柄、上流層から下流層まで老若男女幅広い観客層にアピールする作品を選ぶ傾向にあり、この映画館の上映作品チョイスはかなり信頼が置ける。僕はPVRプリヤーで上映される映画を最優先で見ることにしている。今週はと言うと、ハリウッド映画「The
Three Musketeers」が主な上映作品となっていたが、ヒンディー語映画も2本公開されている。本日は同映画館で1回のみ公開の「My Friend
Pinto」を見に行った。
「My Friend Pinto」の監督はラーガヴ・ダルという新人である。だが、プロデューサーに名を連ねているのが大御所のロニー・スクリューワーラーとサンジャイ・リーラー・バンサーリーであり、期待が持てる。主演は「Dhobi
Ghat」(2010年)などで知られるプラティーク・バッバルや「Dev. D」(2009年)のカールキー・ケクラン。純粋に期待の持てる布陣である。
題名:My Friend Pinto
読み:マイ・フレンド・ピントー
意味:我が友ピントー
邦題:マイ・フレンド・ピントー
監督:ラーガヴ・ダル
制作:ロニー・スクリューワーラー、サンジャイ・リーラー・バンサーリー
音楽:アジャイ・アトゥル
歌詞:アミターブ・バッチャーチャーリヤ、ディーパー・シェーシャードリー
衣装:シャビーナー・カーン、ダルシャン・ジャラン
出演:プラティーク・バッバル、カールキー・ケクラン、アルジュン・マートゥル、シュルティ・セート、マールカンド・デーシュパーンデー、ラージ・ズトシー、ディヴィヤー・ダッターなど
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
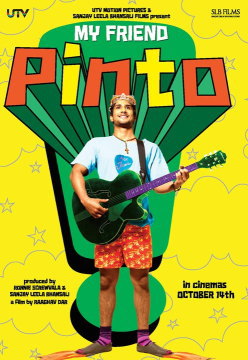
プラティーク・バッバル
| あらすじ |
ムンバイー在住のサミール(アルジュン・マートゥル)はスハーニー(シュルティ・セート)と結婚して2年経っていた。スハーニーとの関係は必ずしもうまく行っていなかった。大晦日の夜、突然故郷ゴアから電話が掛かって来る。電話の主は幼少時代よりお世話になった神父だった。神父はサミールに、ピントーが列車でムンバイーへ向かっていることを伝え、彼の面倒を見るように言いつける。ピントーはサミールの幼馴染みであったが、最近は全く連絡を取っていなかった。ピントーはたくさんの手紙を書いてよこしていたが、ムンバイーの忙しい生活に染まったサミールは封筒を開けもしなかった。また、スハーニーは、天然ボケで何かとトラブルを引き起こすピントーを嫌っていた。ピントーがいきなりムンバイーへ来るということでサミールは慌てるが、駅まで彼を迎えに行く。また、駅でピントーはたまたまマギー(カールキー・ケクラン)という女の子と出会う。
サミールとスハーニーはニューイヤー・パーティーに出席する予定だった。2人はピントーを家に置いて勝手にパーティーへ行ってしまう。1人残されたピントーはベランダに出たところでオートロックの窓に閉め出されてしまう。ピントーは何とか脱出を図るが、失敗して下の階に突っ込んでしまう。そこでは男同士の痴話喧嘩が繰り広げられていた。ピントーは彼らに連れられてムンバイーの街へ繰り出すことになる。
一方、ムンバイーでは誘拐事件が起こっていた。双子のマフィア、アジャイとヴィジャイは、大ボス(マールカンド・デーシュパーンデー)には内緒で、中ボス(ラージ・ズトシー)の命令に従って金持ちの息子を誘拐し、多額の身代金をせしめてようとしていた。ところが身代金を受け取りに行ったマヘーシュが裏切ろうとする。マヘーシュは実はマギーの恋人で、身代金を持ち逃げしてマギーとデリーへ逃げようとしていた。しかしアジャイとヴィジャイに追われ、廃ビルから落っこちて宙ぶらりんになってしまう。その拍子に身代金の入ったバッグが開き、紙幣が街に降り注いで、辺りは大渋滞となる。この渋滞にサミールとスハーニーは巻き込まれてしまう。
街に繰り出すことになったピントーは次から次へと個性的なキャラクターと出会う。まずピントーは楽器店でピアノを買いに来たマフィアの大ボスと出会う。大ボスはピントーの音楽の才能を認める。次にピントーはマギーと再会する。駅で会えずマヘーシュに裏切られたと考えたマギーは自殺しようとしていた。ピントーはマギーを優しくなだめる。次にピントーは、市局に連れさらわれそうになっていた仔犬を助けようとするストリートチルドレンたちに出会う。ピントーは100ルピーを渡して仔犬を助けるが、ストリートチルドレンはちゃっかりピントーの財布を盗む。次にピントーは1人のチンピラと出会う。チンピラはピントーを裏カジノの連れ込み大儲けをする。次にピントーはレーシュマー(ディヴィヤー・ダッター)と出会う。レーシュマーは大ボスの愛人であったが、振られたと思って自暴自棄になっていた。レーシュマーはピントーを家に連れ込み、悲しみと性欲に任せて逆レイプしようとする。
ところで、中ボスはアジャイとヴィジャイを巻き込んで密かに大ボス暗殺計画を立てていた。アジャイとヴィジャイは大ボスとレーシュマーの家に潜み、機会をうかがっていた。レーシュマーがピントーをベッドに押し倒したとき、突然大ボスが帰って来てしまう。しかもアジャイ、ヴィジャイ、ピントーは見つかってしまう。咄嗟に3人はレーシュマーへのサプライズギフトとして仔犬を差し出し、踊り出す。大ボスもそれに乗って怒っていたレーシュマーをなだめる。
気をよくした大ボスは、レーシュマーの他にアジャイ、ヴィジャイ、ピントーを連れて、主催のニューイヤー・パーティーへ行く。そのパーティーには、今までピントーが出会った人々が大集合していた。サミールとスハーニーもこのパーティーに来ていた。また、ピントーはここでマギーと再会する。大ボスに舞台に上げられたピントーは大ハッスルして観衆を興奮の渦に巻き込む。
中ボスは、新年になった瞬間の暗闇を利用して大ボスを暗殺しようとしていた。しかしピントーのドタバタのおかげで大ボスは命を救われ、中ボスは取り押さえられる。大ボスはピントーを命の恩人と呼び感謝する。他にもピントーのおかげでいろいろな人に人生の転機が訪れた。サミールとスハーニーは仲直りし、アジャイとヴィジャイはマフィアから足を洗うと同時に逮捕され、野良犬だった仔犬はレーシュマーの愛犬となった。そしてピントーとマギーの間に恋が芽生える予感があった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督は常に圧倒的な映像美と共に独特の世界観をスクリーン上に再現した重厚な作品を得意としており、彼がプロデュースしたこの映画には興味があった。だが、バンサーリー色は全くなく、ライトなノリの都会派コメディー映画であった。
出足は割ともたつく。導入がうまくないし、俳優たちの演技もどことなくぎこちない。もしかしたら見て失敗したかと思うだろう。しかし物語が進行すると共に徐々にグリップ力が出て来て、最後はそれなりにまとまったコメディー映画となっていた。おとぼけ天然キャラの田舎者主人公が都会で繰り広げる騒動と、それによって登場人物が抱えていたそれぞれの問題の多くがなぜか円満に収まるという展開がプロットの核である。
また、重要なテーマとなっていたのが、都会人の多忙な生活と田舎者の純粋さの対比である。サミールは田舎出身ながらムンバイーの生活に染まってしまい、自分勝手な性格になっていた。ピントーとは幼馴染みの親友であったが、彼とは長年連絡をしていなかった。フェイスブックには何百人もの「友人」がいたが、実生活での親友との久し振りの再会を喜ぶどころか、今回ピントーが1週間ほど彼の家に滞在するとのことで、サミールは「面倒くさいことになった」と考える。一方のピントーは牧師志望の純朴な田舎者で、人を疑うことを知らない。だが、そのぶん物事を次々と受け容れて行くだけの受容力があり、いろいろな事件に巻き込まれる内に人々から自然に愛されるようになって行く。また、天性の音楽の才能があり、それが随所で役立った。
純朴な田舎者がひょっこり都会の知人の家に泊まりに来るというプロットや、現代の都会人の多忙さから来る冷たさを取り上げる姿勢は、「Atithi
Tum Kab Jaoge?」(2010年)とよく共通している。だが、「My Friend Pinto」では多数の登場人物が複雑に絡み合ったプリヤダルシャン型コメディーで、しっかりした脚本がなければまとまらない作品である。その点では「My
Friend Pinto」は、複雑ながらも分かりやすかった。
ただ、俳優たちにオーバーアクティングをさせ過ぎているところが多々あり、それが前半の退屈さの大きな原因になっていた。特に悪役のキャラクターは、コメディー映画であることを差し引いても、皆極端で現実味がなく、映画の質を損なっていた。
プラティーク・バッバルは、童顔と言うか、目がキラキラしていると言うか、何だかやたらと純朴なイメージがあるため、この映画におけるピントー役はとてもはまっていた。馬鹿になり切れていないところも若干あったと思うが、適役だったことで帳消しになっていた。サミール役のアルジュン・マートゥルは「Barah
Anna」(2009年)などの演技が印象深い若手男優だ。プラティークに比べると限定的な出演になるが、やはり適役だと感じた。
カールキーは一応ヒロインということになるが、彼女の出番は意外に少ない。今回もインド人だか白人だかよく分からない役であった。もう1人のヒロインと言えるシュルティ・セートは今まで脇役でいくつかの作品に出演して来ている。今回も脇役の域を出ていないが、イライラした表情や態度の演技は非常に良かった。
他にはラージ・ズトシーがいつになくハッスルしていたのが印象的だった。アジャイとヴィジャイという双子マフィアを演じた俳優も、演技はちょっと足りなかったが、キャラクターとしては面白い。マールカンド・デーシュパーンデーもクレイジーな演技が良かった。
インド映画として途中いくつか挿入歌がある。全てピントー絡みである。最大の見所はピントーがクライマックスにおいてステージでパフォーマンスをするときに流れる曲であろう。ちなみにピントーがアボリジニーの楽器ディジュリドゥを吹くシーンなどもある。
「My Friend Pinto」は、始まりこそ退屈であるが、我慢して見ていると徐々に引き込まれて来るコメディー映画だ。満点をあげられるほどの出来ではないものの、うまくまとまっており、佳作と評価できる。
| ◆ |
10月17日(月) インド人は毎日カレーを食べているのか |
◆ |
日本人がインド人に対して抱く典型的なイメージのひとつに「インド人は毎日カレーばかり食べている」がある。これに対してはいろいろな人がいろいろな立場からいろいろなコメントをしているが、なかなか一言で強烈な説得力のある説明ができていない。僕自身もどう答えればいいのかよく分からない。日本に住んだことのあるインド人からも、「日本人のそういう問いに対してどうやって答えればいいのか」と相談を受けるほどだ。そもそもインド人自身が、外国人が好んで使う「カレー」という言葉の定義をよく分かっていなかったりする。
冒頭の質問に対してよくされるのが、「日本人の言う『カレー』はカレーライスという特定のレシピのことであるが、インドにはカレーライスはない」という説明である。日本ではオーソドックスな、何らかの肉と、ジャガイモ、ニンジン、タマネギとカレールーを使って作られるネットリとした汁と白飯の混ぜ物であるカレーライスは、インドでは日本料理レストランぐらいでしか食べられない。この点は明確であるため、それをもって「インド人はカレーを食べていない」とすることで一応質問には答えたことになる。
しかしこれでは質問者は納得しないだろう。「カレー」という言葉もより広い意味で使われることが多いし、「ではインド人は毎日何を食べているのか」という疑問が同時に浮かぶのも自然だ。そう言われたら即座に「インド人は毎日インド料理を食べている」と答えざるを得ない。もちろん都市部には様々な外国料理レストランもある。輸入食材店も増えて来た。だが、インド人が常に好むのはインド料理であり、外出先でも自宅でもほとんどの場合インド料理を食べていると断言してよく、「インド人は毎日インド料理を食べている」はほぼ正しい発言だと言える。少なくとも「日本人は毎日日本料理を食べている」よりもより真実に近い一文である。
ところが困ったことに日本には「インドカレー」または「インドカリー」なる言葉もある。「それではインド人は毎日インドカレーを食べているのか?」と再度問い掛けられる可能性がある。もしカレーライスのサブカテゴリーとしての「インドカレー」――通常のカレーライスに少し手を加えてインド風にしてみました、みたいなカレー――のことを言っているなら答えはノーだ。しかし、日本で乱立するインド料理レストランで出て来る料理のことを言っているのなら、慎重に答える必要がある。
日本であってもインドであっても「インド料理レストラン」を銘打ったレストランにおいて出て来る料理は概して「ご馳走」に分類されるものが多く、一般のインド人が家庭で「毎日」そういう料理を食べている訳ではない。一概には言えないが、家庭では意外にあっさり味の食事をしていることが多い。これは日本人が毎日寿司を食べている訳ではないのと似ている。また、日本で一般的に見られるインド料理レストランは北インド料理専門店のことが多く、バラエティーに富んだインド料理の世界の一端に過ぎない。もっとも、インド人がインド各地の様々なインド料理を毎日楽しんでいる訳ではなく、ほとんどの場合は自分が所属するコミュニティーの食事を毎日食べているだけだ。それでもインド料理の多様性は抑えておくべきであろう。最近は日本でも南インド料理レストランがちらほら出て来たようだが、それでもまだ日本のインド料理シーンはインド料理全体をカバーできていない。もし日本のインド料理レストランのインド料理をイメージして「インドカレー」と言っているのなら、この点は明確にしておかなければならないだろう。さもないと「インド人全員」が「あんな脂っこい料理を毎日食べているのか」という印象を持たれてしまう。
では「インド料理」というカテゴライズは間違っているのか?よく「多様性の中の統一性」と言われるように、インドの文化は多様でありながらどこかで共通している部分もあるのが普通だ。多様なインド各地の料理にもいくつか共通点がある。その共通点を特定の食材や調理法に求めるのは困難なのだが、食哲学とでも呼ぶべき深層部分では共有しているものが多い。
インド各地を旅行したが、まずインドの食文化に共通しているのは手で食べる料理であることはその体験から断言していいと思う。手で食べることを前提としていない料理は、一部チベット文化圏などを除けばインドには存在しない。レストランではスプーン、ナイフ、フォークも出て来るが、基本は手で食べる。よって、麺類など手で食べにくい料理はあまり発達しなかった(インドに麺状の料理が全くない訳ではない)。手で食べることはインド料理にとって非常に重要な要素だ。
それと関連し、手で掴んで食べやすいように、平たい食器(皿やバナナの葉)の上に料理を広げて食べる。乾燥地帯では小麦粉やその他の穀物から作られるローティー(パン類)、湿潤地帯では米が主食という違いはあるが、炭水化物とおかずを平たい食器の上で混ぜて口に運ぶスタイルは全国共通している。インドの中華料理もこのインド料理スタイルを受容しているので、味付けは全く違っても、また手で食べなくても、限りなくインド料理に近い印象を受ける。日本でも麻婆豆腐とカレーが融合した「麻婆カレー」なるものを見たことがあるが、もしご飯に普通の麻婆豆腐をかけてカレー的に食べるならば、それが正にインド中華である。
インドのメインディッシュには、ヴェジかノンヴェジか、ドライかグレービーかと言う共通した分類法もある。ヴェジは肉以外の食材(野菜、豆、乳製品など)を使った料理で、ノンヴェジは肉料理(主にチキンとマトン、地域によっては魚介類に加えてビーフ、ポークも)である。肉も野菜も詰め込んだような料理はインドにはなく、ひとつのレシピの中でメインとなる食材はノンヴェジならば1品、ヴェジならばせいぜい2品である。多くの場合、1回の食事で2種類以上のメインディッシュを食べることになる。また、ドライは汁気のない料理で、グレービーは汁っぽい料理のことだ。インド料理を食べる際に、ドライとグレービーをそれぞれ何品にするかは結構重要な決定事項である。少なくとも1品はグレービーが欲しい。北インドでは多くの場合、ダール(豆カレー)がその役割を担う。日本のカレーのように、ネットリとしたルーの料理はインドではあまり見ない。日本のカレーのネットリ感は、インド料理が英国経由で「カレー」として海軍に導入された際に、波で揺れる海上でも皿からこぼれないように工夫されたためであるらしい。
このように、インド人の食べる料理は東西南北多様ではあるものの根幹部分で共通のものがあり、「インド料理」というカテゴライズに問題はないと感じる。ただ、理念的な部分を越えて、実際的な調理法や料理を見ると、多様すぎてうまく一言ではまとめられない。インド料理のレシピ本を何冊か見比べてみても、同じ名前の料理であっても作り方や食材にかなり違いがあり、全く統一性はない。ましてやインド全土の料理における共通項を探し出すのは至難の業である。
ところで、「インド料理は辛い」と言う先入観も強いが、インド料理に必ずしもチリは必要としないし、辛さがインド料理の象徴だとも言えない。チリを主食にしているのはむしろインド辺境部(ノースイースト地域)やブータンの人々であり、インド料理は辛いだけではない。しかしながら、辛い料理はすぐに満腹感が生じるので、インドの貧困層が食べる料理はとてつもなく辛いことが多いのは確かである。どちらにしろ、辛さでインド料理をくくることは不可能である。
よって、以上のようなインド料理の多様性と統一性を念頭に置いた上で、「インド人は毎日カレーを食べているのか?」と聞かれたら「インド人は毎日インド料理を食べている」と答えるのが一番簡単なのではないかと思う。これはごく当然のことである。インド料理がインドでインド人に食べられていなかったら、なぜインド料理と呼ぶことができるのか?そしてもし「カレー」という言葉を、カレーライスなどの特定のレシピではなく、漠然とインド料理と同義で使っているなら、その場合に限って「インド人は毎日カレーを食べている」と言っていいのではないかと思う。しかしその際はインド料理の多様性を理解しておいて欲しいものである。
| ◆ |
10月18日(火) Mujhse Fraaandship Karoge |
◆ |
ここ10年間ヒンディー語映画を見ていると、最新コミュニケーションツールを果敢に映画のストーリーに取り込んで来たと感じる。インドで携帯電話が爆発的に普及し始めた頃、「Company」(2002年)という映画が公開され、海外から携帯電話を使ってインドに住む手下を動かすマフィアの姿が描かれた。また、「Munna
Bhai M.B.B.S.」(2003年)では、主人公のムンナーバーイーは医科大学を受験するにあたって携帯電話を駆使して答えを入手し、試験をパスしていた。「No
One Killed Jesica」(2011年)ではSMSによる大衆社会運動の広がりがストーリーのターニングポイントとして描かれた一方、「Dev.
D」(2009年)や「Ragini MMS」(2011年)ではビデオ付き携帯電話とMMSによる自家製ポルノ動画の流出問題が描かれた。これらは最新技術がストーリー上重要な役割を果たした例であるが、他にも脇役としてEメール、グーグル・サーチ、ユーチューブ、チャット、ビデオチャット、SNSなどの最新コミュニケーションツールが劇中に登場する作品はヒンディー語映画にとても多い。特に近年ビデオチャットの登場機会が増えており、最近の例だけ挙げても、「3
Idiots」(2009年)ではクライマックスの出産シーンでビデオチャットが活用され、「Mere Brother Ki Dulhan」(2011年)ではビデオチャットでお見合いが行われた。
先週より公開の「Mujhse Fraaandship Karoge」は、ポスターのデザインからも分かるように、フェイスブックを題材にしたロマンス映画である。プロダクションは、大手ヤシュラージ・フィルムスの若手育成部門Yフィルムス。ヤシュラージ・フィルムスの過去の映画に「Mujhse
Dosti Karoge!」(2002年)という映画があったが、題名はそれと全く同じ意味になる。「Friendship(友情)」が「Fraaandship」になっているのは若者言葉だと考えればいいだろう。監督は新人の女性で、キャストも若い無名の俳優ばかり。しかし予告編を見て光るモノを感じたので映画館に足を運んだ。
題名:Mujhse Fraaandship Karoge
読み:ムジュセ・フラーンドシップ・カローゲー
意味:私と友達になる?
邦題:フェイスブック
監督:ヌープル・アスターナー(新人)
制作:アーシーシュ・パテール
音楽:ラグ・ディークシト
歌詞:アンヴィター・ダット・グプタン
振付:プリヤーンジャリ・ラーヒリー
衣装:アーディル・シェーク
出演:サーキブ・サリーム(新人)、サバー・アーザード(新人)、ニシャーント・ダーヒヤー(新人)、ターラー・デスーザ、ケーシャヴ・スンダル、プラバル・パンジャービーなど
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。
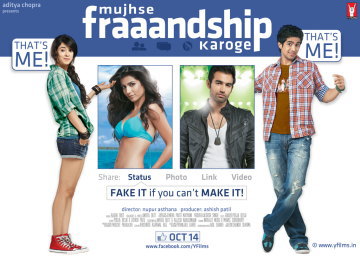
左からサバー・アーザード、ターラー・デスーザ、
ニシャーント・ダーヒヤー、サーキブ・サリーム
| あらすじ |
ムンバイーの大学に通うヴィシャール・バット(サーキブ・サリーム)は、フェイスブックを使って悪戯をするお調子者だったが、詩才があり、大学のロックスター、ラーフル・サリーン(ニシャーント・ダーヒヤー)に内緒で歌詞を提供していた。ヴィシャールは、ラーフルのコンサートで同じ大学に通うマールヴィカー・ケールカル(ターラー・デスーザ)という美人と出会い、恋に落ちる。早速フェイスブックを使ってマールヴィカーを探し、彼女に友達申請を行う。だが、念のためにラーフルのアカウントからも勝手に彼女に友達申請を行っていた。
マールヴィカーはプリーティ・セーン(サバー・アーザード)とルームメイトだった。プリーティは写真部の部長であったが、勝ち気な性格で、何かとヴィシャールとは対立していた。プリーティは密かにラーフルに恋していた。マールヴィカーのフェイスブック・アカウントにラーフルから友達申請が来たことを知り、勝手に承認し、チャットを始めてしまう。こうしてヴィシャールはマールヴィカーと、プリーティはラーフルとフェイスブック上でチャットをしていると思い込んでいたが、実際にはヴィシャールとプリーティがチャットをしていたのだった。
あるときフェイスブックのチャットの結果、ラーフルとマールヴィカーは会うことになってしまう。慌てたヴィシャールはラーフルに頼み込む一方、プリーティはマールヴィカーに頼み込み、2人は顔を合わす。お互い簡単に会話をした後、別れる。その後ももう1度ナイトクラブで会うことになったが、そのときはラーフルとマールヴィカーがそれぞれ気を利かし、ヴィシャールとマールヴィカー、ラーフルとプリーティが共に時間を過ごす。
ところでヴィシャールとプリーティは、大学の創立25周年記念イベントの出し物のために、大学で出会って結婚した25組の夫婦の取材をしなければならなかった。2人は喧嘩をしながら、卒業生夫婦の取材を続けて行く。そして家に帰ると、ラーフルに扮したヴィシャールとマールヴィカーに扮したプリーティはフェイスブック上で親しげにチャットをする奇妙な毎日を送っていた。しかしながらプリーティは徐々にラーフルを退屈だと感じるようになり、ヴィシャールを気にするようになって行く。またヴィシャールの方もプリーティに肩入れするようになる。ところがヴィシャールの友人が悪戯でアップロードしたプリーティのジョーク動画を、プリーティはヴィシャールの仕業だと考え、ヴィシャールを避けるようになる。一方、ヴィシャールはマールヴィカーに、本当はラーフルになりすましてチャットをしていたのは自分だと告白することにする。それと平行して、ラーフルとマールヴィカーは距離を縮めつつあった。
ラーフルの誕生日パーティーの日。ヴィシャールはプリーティと仲直りするものの、ラーフルとマールヴィカーがキスをしているのを見て憤慨する。そして怒りに任せてマールヴィカーに、ラーフルになりすましてチャットをしていたのは自分だと告白する。するとそれを聞いていたプリーティは、マールヴィカーになりすましていたのは自分であること、またヴィシャールに恋してしまったことを明らかにし、混乱した2人はまた喧嘩状態となってしまう。
大学創立25周年記念イベントの日。ヴィシャールとプリーティは25組の卒業生カップル発表の司会をすることになっていた。そのときまで2人はほとんど口を利くことがなかったが、壇上でヴィシャールはプリーティに愛の告白をする。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
実生活では犬猿の仲の2人が、お互いに正体を隠したネット上でのコミュニケーションでは意気投合し、最後には正体を明かし合った上で恋仲になるというプロット。Eメールが世の中を変えつつあった頃にハリウッドで作られた、トム・ハンクスとメグ・ライアン主演「ユー・ガット・メール」(1998年)をかなり下敷きにしていると思われるが(BGMも似ていた)、ストーリー自体はオリジナルで、フェイスブックの機能も存分にストーリーに活かされていた。無名の監督、無名のキャストだったが、現代のインド人大学生のライフスタイルや行動様式もよく再現されており、フレッシュなロマンス映画となっていた。もっと踏み込んで言えば、今年最高のロマンス映画の1本に数えてもいいくらいである。展開や結末は大方予想できるのだが、それでもって映画の質が損なわれていることは決してない。
「Jab We Met」(2007年)で知られるイムティヤーズ・アリー監督は、現代的なロマンス映画を作らせたら現在ピカイチである。彼が過去の作品で訴え続けて来たのは、「顔を見ただけで心臓がドキドキする人」よりも、「一緒にいて何となく居心地のいい人、落ち着く人」「一緒にいると素の自分になれるような人」こそが「運命の人」であるというメッセージである。一目惚れした人を必死になって追い掛けるよりも、いつも側にいてくれる人との関係を再評価することに重点を置いたロマンス映画がここ最近のヒンディー語映画の主流になりつつあり、「Mujhse
Fraaandship Karoge」もその一例だと言える。そしてそれだけに留まらず、登場人物の心情の変化がとても丁寧に描かれており、揺れ動く若い心をよく捉えていた。
かつてインド映画では、恋した人の名前を知るだけでも一苦労であった。そして苦労して知ったその人の名前を毎日狂ったように唱えるのが、恋に落ちたヒーローやヒロインの典型的な姿であった。ただ、名前を知っただけではそれ以上のことは不可能である。しかし現在、もし相手の名前を知ることができれば、フェイスブックでサーチして、その人の詳細情報や写真を簡単に手に入れることが出来る。それだけでなく、相手の電話番号を聞くよりも先に友達申請まで出来てしまう。もし承諾してもらえれば儲けモノだ、チャットも出来るし、友人以外には非公開のプロフィールも読めたりする。このように、「Mujhse
Fraaandship Karoge」は、フェイスブックが恋愛の手順をガラリと変えてしまったことをよく表現していた。
しかしながら、「Mujhse Fraaandship Karoge」はフェイスブック礼賛の映画ではなかった。むしろ、フェイスブックのようなSNSを使って、顔の見えないバーチャルな恋愛に没頭する現代の若者への強烈なアンチテーゼとなっていた。主人公のヴィシャールは、散々フェイスブックを使って小手先の恋愛ゲームをした後、最終的にはヒロインのプリーティの前に跪き、「I
Love You」と古典的な愛の告白をする。そういう原点回帰があったからこそ、「Mujhse Fraaandship Karoge」は一段上のロマンス映画に収まることに成功していたと言える。
僕が昔から「インド映画の良心」と呼んでいるいくつかの要素があるが、この映画にもその内のひとつが見られた。それは「嘘は必ず自ら明かす」ことである。ヒンディー語映画では多くの場合、嘘を付いていたことを自ら明かそうとしたときに別の方面からそのことが相手にばれてしまってさあ大変という筋書きが多いのだが、この映画ではそういうことはなかった。しかしながら、相手を騙しつつハッピーエンドを迎えるような、何かスッキリしない終わり方を採っていなかっただけでも良かった。この映画での嘘は、フェイスブックで他人のアカウントを使ってチャットをしていたことである。正直言って、ヴィシャールがそのことをマールヴィカーに明かし、プリーティがそれをヴィシャールに明かし、そして同時にプリーティがヴィシャールにどさくさに紛れて愛の告白までするシーンは、意外に急転直下、しかも急ぎ足過ぎて拍子抜けだったのだが、センチメンタルなシーンをサッと切り上げるところにも監督の並々ならぬセンスを感じた。
若い俳優陣は皆それぞれに最適の演技をしていたが、一番光っていたのはプリーティを演じたサバー・アーザードである。写真が趣味の、ちょっとオタクっぽい気むずかしい女の子であるが、徐々に女の子らしさを開花させて行き、土壇場でヴィシャールに一方的に告白をしてしまってからは、サバサバとした面も見せていた。どのシーンも力一杯演じており、とても好感が持てた。マールヴィカーを演じたターラー・デスーザは「Mere
Brother Ki Dulhan」(2011年)にも脇役出演していた女優であり、知名度を上げている。主演を張れるだけのオーラは今のところ感じないが、少なくとも「Mujhse
Fraaandship Karoge」の中での演技はとても良かった。
主演のサーキブ・サリームは、多少野暮ったい顔をしているが、やはりフレッシュな演技が良かった。ロックスター、ラーフルを演じたニシャーント・ダーヒヤーがもっとも鈍い演技をしていたが、「ハンサムだが話してみると意外に退屈な男」という役柄なので、よく合っていた。新人俳優のみの起用だったものの、絶妙なキャスティングでその穴を埋めていた印象である。
音楽はカルナータカ州のシンガーソングライター、ラグ・ディークシトの作曲である。ラグ・ディークシトがヒンディー語映画の音楽監督を担当したのはこれが初のことだ。2時間ほどの映画の中に多くのダンスシーンが含まれていたが、ヴィシャールとプリーティがそれぞれお互いに恋に落ちたことを悟ったときの挿入歌「Uh-Oh
Uh-Oh」が非常に良かった。他にも若者らしいパーティーソングが多く、全体的には元気な曲の詰まったサントラCDとなっている。
ところでこの映画の中にはサムスンの電子機器がたくさん登場した。ノートPC、スマートフォン、一眼レフカメラなどである。おそらく全面的にタイアップしたのだろう。映画がいい出来だっただけに、この点は日本人として残念な光景であった。
「Mujhse Fraaandship Karoge」は、スターパワーは全くないものの、フェイスブックを題材にしたフレッシュなロマンス映画である。展開はベタであるが、ロマンス映画のイロハをよく抑えてあり、楽しい鑑賞となるだろう。今年最高のロマンス映画の1本と評しても差し支えない。世間は来週公開の超話題作「Ra.One」一色で目立たないが、見て損はない。
先々週、突如として新聞にひとつの広告が出現した。「Andha Yug(盲目の時代)」。現代ヒンディー語文学者ダラムヴィール・バーラティー(1926-1997年)の有名な戯曲(作者自身は「可視詩(दृश्य-काव्य)」と呼んでいる)の名前である。ヒンディー語演劇界のみならず全インド演劇界において不朽の名作とされる戯曲で、1953年にラジオ劇として放映されたのを皮切りに、今まで多くの演劇家たちによって上演されて来た。その「Andha
Yug」が、デリーにおいて、サーヒティヤ・カラー・パリシャド(文芸評議会)とデリー州政府芸術文化言語局の共催により上演されることになり、それを告知する広告であった。しかも舞台は14世紀の城塞跡フィーローズ・シャー・コートラー。デリーで上演されるのはおよそ50年振りで、しかも当時も同じフィーローズ・シャー・コートラーにおいて上演されたと言う。50年前の公演時の監督はイブラーヒーム・アルカーズィーであった一方、今回はその弟子の1人バーヌ・バーラティーが監督をする。このような理由により、非常に特別な公演となることは必至であった。
M.A.Hindi(ヒンディー語修士課程)に在籍していた頃、「戯曲」のクラスのカリキュラムに含まれていたために、「Andha Yug」はじっくり読んだことがあった。テキストに選ばれるくらいなので、素晴らしい作品であるのは折り紙付きなのだが、同時にその世界観にも個人的に大いに感銘を受けた記憶がある。特に中心的キャラクターであるアシュヴァッターマーにはすっかり惚れ込んでしまった。しかしながら、今まで実際に舞台で上演された「Andha
Yug」を鑑賞する機会はなかった。
「Andha Yug」は、インド二大叙事詩のひとつ「マハーバーラタ」を土台にした作品である。パーンダヴァとカウラヴァの間で勃発した骨肉の争いであるマハーバーラタ戦争の最終日、勝者のいない戦争が悲惨な結末を迎えようとしている時のカウラヴァの生き残りたちを主人公にしている。アシュヴァッターマーもその1人だ。同時に、ダラムヴィール・バーラティーは、第二次世界大戦やインド分離独立時の虐殺など1940年代にインドや世界で起こった事件を背景に「Andha
Yug」を書いており、時代劇を通して現代の文脈における戦争の悲惨さが訴えられている。知る人ぞ知る、「マハーバーラタ」には核戦争を思わせる描写があるが、「Andha
Yug」ではそれが広島・長崎への原爆投下を想起させる絶好の元ネタとなっている。そのために、「Andha Yug」は反戦劇とされることが多く、実際にそのようなメッセージと共に上演されることが多かった。だが、バーヌ・バーラティー監督はひと味違った演出を試みているようで、それが非常に楽しみだった。
ところが、パスの入手に非常に苦労した。
デリーの文化行事の多くはありがたいことに無料で楽しむことができる。日本在住のインド好き日本人だった頃は、スィタールの公演やら何やらに高いチケット代を払って足を運んだものだったが、デリーに住み始めてからは、無料で巨匠のパフォーマンスを鑑賞できる幸せを享受できるようになった。特にマンディー・ハウス界隈は音楽・舞踊・演劇のメッカであり、毎日何かしら巨匠のパフォーマンスが上演されていた。まだデリーの人々がそのような文化活動に疎かった頃、そしてまだインドがそれほどテロの脅威にさらされていなかった頃、あの辺りをとりあえず散歩して、気になる公演があれば飛び込みでも割と入れてもらえた。だが、徐々にセキュリティーが厳しくなり、同時に偉大な音楽家・舞踊家・演劇家への人々の関心も高まって行った。それにつれてパスがないと入場が不可能となり、そしてパスの入手も困難になって行った。
それでもそういうイベントのパス入手には、長年の経験の積み重ねから、かなり自信があった。とにかく毎朝新聞に目を走らせ、気になるイベントがあった場合はそのパスの入手法を確認し、すぐさまその指示通りの場所へ飛んで行ってパスをいち早く入手していた。時間に自由が利く暇人だからこそ出来る技であったが、暇人が暇を活かせなかったら単なる暇人で終わってしまう。暇人は有意義な暇人を目指すべきであり、デリー生活の大部分はそういう行動に時間を費やしていた。
しかし、「Andha Yug」のパス入手には失敗してしまった。
「Andha Yug」の公演は当初10月15日~19日の5日間と発表されていた。パスは11日の午前11時より、会場となるフィーローズ・シャー・コートラーにて配布とのことだったので、11日の午前11時よりも前に現地に着くように家を出て、城塞前の特設パスカウンターに出来ていた2,30人ほどの列に並んだ。このくらいの列だったらパスは手に入るだろうと高を括っていた。懸念は1人何枚パスをもらえるかであった。どうやら1人2枚で、1枚のパスで入場は1人のみのようであった。初演日となる15日のパスを第一希望として列に並んでいた。
ところが予想もしていなかった事態が起こった。カウンターは2つあり、列も2つあった。特に明記はなかったが、自然にひとつは男性用、もうひとつは女性用となっていた。インドでは公共の場で女性を特別扱いする風潮が強く、こういう場合、女性用の列が自然と出来ることが多い。当然、男性用の列よりも女性用の列の方が圧倒的に短い。11時頃になると、係員はまず女性にパスを配り始めた。男性には全く配布されなかった。その内女性の列が終わってしまった。すると、男性用列に並んでいた人々(大部分は僕よりも後ろにいた人)が女性用列に殺到した。僕は男性用列に固執して並んでいた。ところが、列が新しく出来たにも関わらず依然として元女性用列にだけ配布が行われ続け、元男性用列は一向に進まなかった。当然元男性用列に並んでいた人々は不平の声を上げ始めた。しばらくブーイングをしていると、元女性用列への配布が一旦中止され、やっと男性用の列にパスが配られ出した。ところがこの間、配布当初の混乱を知らない人も元女性用列に並んでおり、このアンバランスなパスの配り方に文句を付け始めた。このとき、かなり喧嘩腰に不平を言う人がおり、係員と口論になってしまった。この口論で係員がかんかんに怒ってしまい、配布を放り出してどこかへ行ってしまった。よって、パスの配布は中断されてしまった。
辛抱強く待つこと1時間。やっとカウンターが再開された。このときまでにまた女性用列が復活しており、交渉の結果、男性2人に対し女性1人という割合でパスが配られることになった。一応このルールのおかげでスムーズに配布が進み、僕の番も徐々に近付いて来た。ところが僕の前の前に並んでいた人でパスが終わってしまった。暴動を恐れたのか、配り終えた途端に係員はそそくさと片付けをして去って行ってしまった。当然、パスが終わってしまったことが告げられた後、並んでいた人々からは怒声が上がったが、もうカウンターに誰もいないのでいくら文句を言っても何もならない。こうして初日にパスを入手することはできなかった。この間、2時間以上、炎天下の中列に並んで立っていた。パスが手に入ればまだしも、この残酷な肩すかしの後にはさすがにぶっ倒れそうだった。「これぞアンダー・ユグ(盲目の時代)だ」と言うニヒルなジョークがちらほらと聞こえて来たのが多少の慰みであった。
初日に配られたのは15日と16日のパスのみだった。当初予定されていた17日の公演は、フィーローズ・シャー・コートラーのすぐ近くにあるフィーローズ・シャー・コートラー・スタジアムで開催されるクリケットの試合(インド対英国戦)の影響で中止となっていた。18日と19日のパスは翌日配られるとのことだったが、初日に散々な目に遭ったため、今回はもう「Andha
Yug」を見るのを諦め、パスを入手しに行くことはなかった。
ところがその数日後の新聞に「Andha Yug」追加公演のお知らせが載っていた。大反響のため、21日、22日、23日にも公演が行われることが決まったのだった。一旦は諦めていたが、追加公演のニュースに俄然やる気が出て、追加公演分のパス配布日の15日の午前中にまたもフィーローズ・シャー・コートラーに赴いた。ところが今回は以前よりも圧倒的に多くの人々が殺到しており、配布開始30分前に到着したにも関わらず、カウンター前には長蛇の列が出来ていた。これはまたも無理かと思って並んでいたが、やはりほとんど列が進まない内にパスは終わってしまった。はっきり言って一般配布用のパスの数が少なすぎる。ほとんどのパスはお偉方に回ってしまっているのだろう。有料でもいいから、本当に見たい人が見られるようなシステムにしてもらいたいものである。
こうして2日に渡ってパス入手に奔走したにも関わらずパスが手に入らず、屈辱的な思いをした訳であるが、これは「ナンバー1」の方法、つまり正攻法であり、それに失敗しただけだった。追加公演パス入手に失敗した後、「ナンバー2」、つまり裏の道を探り始めた。国立演劇学校(NSD)に連なる人脈でパス入手を模索したところ、呆気なく手に入ってしまった。炎天下の中2時間並んで手に入らなかったものが、電話1本で手に入るこの不条理さ。決して褒められたものではない。しかしながら、土壇場で「Andha
Yug」を見ることが可能となった。初演を逃した今、出来ることなら最終公演となる23日のものを見てみたかったが、その1日前となる22日のパスが手に入ったため、贅沢は言わずにこの日の公演を鑑賞することにしたのだった。
以上、「Andha Yug」を見られることになるまでの詳しい経過であった。なぜこんなつまらない前置きを長々と書き連ねるかと言うと、最近のデリーにおけるパス入手の苦労を少しでも情報として提供したかったからである。Twitter全盛の今、ネット上において本当にインフォマティブな情報が減って来ているように感じる。演劇鑑賞でも旅行記でもグルメ日記でも、読者にとって本当に役に立つのは彼らが同様の行動を繰り返そうとする際に指針となる土台部分の情報で、僕がどう感じたかなどは二の次の情報だと考えている。この「Andha
Yug」のパス配布は近年僕が体験した中でも最悪のものであったが、今後もさらに状況が悪化することが予想されるため、デリーで文化行事を存分に楽しみたい人は心してパス入手に奔走してもらいたい。
午後6時半開場、7時開演とのことだったが、念には念を入れて早めに会場に着くようにした。既に6時頃には開場しており、中に入ることができた。フィーローズ・シャー・コートラーには、ジャーマー・マスジド(金曜モスク)、アショーカ王の石柱の立ったピラミッド、バーオリー(階段井戸)などが残っており、特にモスクをうまく利用した舞台となるのではないかと勝手に予想していたが、実際には遺跡内の広場を利用した舞台となっており、元からある遺構は、アーチ状の門が連なる壁ぐらいしか利用されていなかった。この辺りは、プラーナー・キラーで時々行われる舞踊や演劇とは大きく異なる点であった。プラーナー・キラーで行われるそれらのイベントでは概して、南門の壮大な建築が背景として使われ、圧倒的存在感を放っている。フィーローズ・シャー・コートラーでも望めばそういう演出は可能だったと思うが、おそらく遺跡保護の観点から、遺跡に悪影響を及ばさない場所でのステージ設営となったと思われる。客席は雛壇状になっており、どの席からも見やすかった。早めに行ったことが功を奏し、多少位置は高めだったが中心部のいい席に座ることが出来た。
ステージは主に3つ。左、中央、右にあり、左(下手)の舞台はカウラヴァの首都ハスティナープラの王宮をイメージ。右(上手)の舞台はジャングルをイメージ。中央は壊れたチャリオット(二輪戦車)が横たわり、戦場をイメージ。ステージと客席の周囲には照明が張り巡らされており、ステージ上の各所にはスモークを発する器械が仕込まれていた。
ダラムヴィール・バーラティーの戯曲「Andha Yug」は5幕に加えて序幕、幕間、終幕があるが、合計1時間40分の上演時間となるバーヌ・バーラティー監督の舞台劇「Andha
Yug」では、序幕プラス4幕の構成になっており、原作のいくつかの部分が省略されていた。それに伴って登場人物の数も減っており、カウラヴァ側の人物――ドリタラーシュトラ、ガーンダーリー、ヴィドゥル、サンジャイ、クリタヴァルマー、クリパーチャーリヤ、ユユツ、ヴリッド・ヤーチャクとアシュヴァッターマー――しか登場しない。原作ではパーンダヴァ5兄弟の長兄ユディシュティラなども登場する。クリシュナやヴャースは声のみの出演となっている。しかしながら、省略部分を除けば台詞に大きな変更点はなく、原作を忠実になぞっていた。

ハスティナープラのシーン
左からガーンダーリー、ドリタラーシュトラ、ヴィドゥル
原作と大きく違う部分は、アシュヴァッターマーがブラフマーストラ(古代インドの文献に登場する大量破壊兵器)を放ち、地上に破滅をもたらした場面で劇が終わるところだ(原作ではアルジュンの息子アビマンニュの妻ウッタラーの子宮にいたパリークシトめがけて発射される)。よって、アシュヴァッターマーがクリシュナの呪いによってゾンビのようになってしまうシーンは描かれない。原作ではアシュヴァッターマーがブラフマーストラを放った後にガーンダーリーがクリシュナに呪いを掛けるが、舞台劇ではこの呪いもブラフマーストラのシーンより前に来る。そのくせ台詞に変更がないために文脈がつながらない部分があったように感じた。また、盲目の王ドリタラーシュトラに戦争の様子を聞かせる役割を負ったサンジャイが原作よりもさらに重視されており、スートラダール(語り手)としての役割も担っていた。

ジャングルのシーン
父親を殺されて怒るアシュヴァッターマー
原作でも舞台劇でも、やはりもっとも迫力があるのは、父親のドローナーチャーリヤを卑怯な方法で殺されて復讐に燃えるアシュヴァッターマーが、カウラヴァの敗戦が決定的になった日の夜、森の中でフクロウがカラスを夜襲して捕えるのを目撃し、パーンダヴァに夜襲を仕掛けることを思い付くシーンである。カウラヴァ軍の大将ドローナーチャーリヤは無敵の武将であったが、武器を手に持っている時のみ無敵だとされていた。よって、パーンダヴァ側はドローナーチャーリヤを打ち負かすために、彼が武器を手放すように仕向ける必要があった。ドローナーチャーリヤはかつて、息子のアシュヴァッターマーが死んだときに武器を手放すと言っていた。そこでパーンダヴァ側は「アシュヴァッターマーが死んだ」を嘘を言う。パーンダヴァ5兄弟の長兄ユディシュティラは、ダルマプトラ(正義の息子)の異名を持つほど正直者として知られ、嘘は決して付かないとされていた。このユディシュティラが「アシュヴァッターマーは死んだ」と言ったため、ドローナーチャーリヤは信じてしまい、武器を置いてしまった。その隙を狙われてドローナーチャーリヤは殺されてしまう。実はアシュヴァッターマーという名の象もおり、ユディシュティラは「象または人のアシュヴァッターマーが死んだ」という曖昧な表現を使った。よってユディシュティラとしては嘘ではなかった。だが、アシュヴァッターマーにとってそれはアルドサティヤ、つまり半文の真実であり、不正よりも卑劣な偽善であった。この出来事によりアシュヴァッターマーが復讐の権化と化し、夜襲を決行する。そしてこの夜襲によりパーンダヴァ軍の多くの将兵が殺されてしまう。あらゆる正義が失われた瞬間であった。劇中では、ジャングルの暗闇の中で、人が扮したフクロウが、やはり人が扮したカラスを取り押さえるシーンが再現されていた。

壊れたチャリオットのシーン
ブラフマーストラ発射の後、絶望して彷徨うサンジャイ
原作にもある部分だが、ガーンダーリーがクリシュナに「獣のような死を」と呪いを掛け、それをクリシュナが受け容れるシーンは、怒りと悲しみに満ちたこの暗澹たる演劇の中で唯一、神々しいまでの救いが見られる部分である。パーンダヴァに味方し、アルジュンの戦車の御者として戦争に参加したクリシュナは、戦争によって100人の息子全員を亡くしたガーンダーリーに、「18日間のこの恐ろしい戦争の中で、他でもない、私が死んだのだ、何千万回も。兵士が倒れたときはいつでも、傷つき戦場に倒れたのは、他でもない、私だったのだ」と語り掛け、以下の言葉を言う:
जीवन हूँ मैं
तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ !
शाप यह तुम्हारा स्वीकार है ।
生は私
ならば死も私なのだ、母よ!
この呪いを受け容れよう。
そして、悲しみと怒りに任せてクリシュナを呪ったことを悔い、子なしとなったことを嘆くガーンダーリーに対し、クリシュナは付け加える――「私が生きている限り、あなたは子なしではない。」ここまで生死や許しを達観した深さはインドの文学にしか見られないのではないかと思う。
「Andha Yug」は、サティヤ(正)とアサティヤ(不正)、ダルム(善)とアダルム(不善)の葛藤の話でもある。台詞の中にはこれらの言葉が何度も登場し、それぞれの正義、善、不正義、不善の定義を披露する。しかしながら、戦争が起こるとき、そこには正も善もなくなる。どちらが勝とうと、そこには不正と不善があるのみ。そしてアシュヴァッターマーが激昂し彼を夜襲に向かわせたアルドサティヤ(半正)こそが全てのルールを破壊し、人を破滅へ導くものだとされていた。戯曲全体のメッセージはこれである。現代の世界情勢に当てはめて考えても、多くのことが思い当たる。特に911事件後に米国が世界中で行っていることや、最近「アラブの春」などともてはやされながら中東で起こっていることなどをつい考えてしまう。武器と暴力を使った解決法がある限り、問題は決してなくならない。カウラヴァ100兄弟の1人でありながらパーンダヴァに味方し生き残ったユユツの自殺は原作と舞台劇ではタイミングが違ったが、そのときに2人の衛兵が話す言葉は同じで、劇中でもっとも象徴的なメッセージである。
प्रहरी 1. युद्ध हो या शांति हो
प्रहरी 2. रक्तपात होता है
प्रहरी 1. अस्त्र रहेंगे तो
प्रहरी 2. उपयोग में आयेंगे ही
प्रहरी 1. अब तक वे अस्त्र
प्रहरी 2. दूसरों के लिए उठते थे
प्रहरी 1. अब वे अपने ही विरुद्ध काम आयेंगे
衛兵1 戦争中であろうと平和な世であろうと
衛兵2 血は流れる
衛兵1 武器がある限り
衛兵2 それは使われるだろう
衛兵1 今日まで武器は
衛兵2 他人を殺すために使われていたが
衛兵1 今では自分を殺すためにも使われる
インド人の考え方と言うととかく運命論的なイメージが強いが、「Andha Yug」はそれを否定している。それをはっきりと体現しているのは預言者ヴリッド・ヤーチャクである。ヴリッド・ヤーチャクは、未来は固定されているものだと考え、ドゥルヨーダン率いるカウラヴァ軍の勝利を約束するが、実際にはカウラヴァ軍は敗北する。ヴリッド・ヤーチャクの台詞には、「人間が今日する行為が、未来を作る」、「一瞬一瞬が歴史を変える」などがあり、以下の台詞に全てが凝縮されている。
वर्तमान से स्वतन्त्र कोई भविष्य नहीं
現在から独立した未来はない
これも「Andha Yug」の強いメッセージのひとつである。
はっきり言って、一般的に反戦劇とされて来た戯曲「Andha Yug」を新たな視点から語り直す試みがどこまで成功したかは疑問である。やはり反戦劇としてのメッセージが強く、戦争には正義も何もないことが強く訴えられた演劇だと感じた。観劇前に配られたパンフレットによると、監督はブラフマーストラのシーンの後でキャンドルを持って立つ人々を配置するオリジナルの演出を挿入することにより、どんな災厄や戦災の後でも人間は立ち直る力を持っていることを主張したかったようだ。確かに劇の副題は「A
Saga of Light in Darkness(暗闇の中の光の物語)」となっており、監督独自のメッセージがここにも込められている。光の祭りディーワーリー・シーズンにも適した副題である。だが、そのメッセージが劇中で明確になっていたとは言えなかった。それでも、監督によるその果敢な再構成・再構築のおかげで、原作では多少冗長気味な劇が、簡潔にまとまっていたと思う。そして何より俳優たちの熱演もあって、素晴らしい演劇になっていた。

キャンドルのシーン
最後になったが主なキャストを簡単に紹介する。ドリタラーシュトラを演じたのはベテラン舞台俳優のモーハン・マハリシ。精神異常者みたいなしゃべり方をしていたが、これは役作りだったのだろうか?ガーンダーリーを演じたのはやはりベテラン舞台女優のウッタラー・バーオカル。メインキャストの中では唯一の女性であったが、アシュヴァッターマーを除いてもっとも迫力のある演技をしていたのも彼女であった。サンジャイを演じたのは映画界でも活躍するザーキル・フサイン。舞台での彼の演技は初めて見たが、難解な台詞も何のその、迫真の演技であった。「Andha
Yug」の主人公と言っていいアシュヴァッターマーを演じたのはティーカム・ジョーシー。まだ若手の俳優だが、7歳の頃からステージに立っているようで、狂気の演技を堂々と演じていた。他に映画界のベテラン俳優オーム・プリーがクリシュナとして、同じく映画界で活躍するゴーヴィンド・ナームデーオがヴャースとして、声のみの出演をしていた。ちなみにほとんどのキャストはNSD関連である。
およそ50年振りにデリーのフィーローズ・シャー・コートラーで上演されたダラムヴィール・バーラティーの「Andha Yug」。パス入手では苦労したものの、それだけの甲斐があった観劇となった。
下半期に入って話題作・ヒット作が続いている2011年のヒンディー語映画界だが、その中でも今年最大の話題作が、ディーワーリー公開のシャールク・カーン主演「RA.One」であった。シャールク・カーンのホーム・プロダクション、レッドチリ・エンターテイメントの最新作であり、ラジニカーント主演「Enthiran」(2010年)を越える、インド映画史上最大予算を掛けて作られた作品であり、あらゆるメディアにまたがる大々的かつ徹底的な広告戦略も打ち出して来ており、正に「キング・オブ・ボリウッド」シャールク・カーンの一世一代を賭けた超大作となっている。ただ、予告編やサントラCDなどから内容を垣間見る限り、もしかしたらもしかして大失敗作に終わるかもしれないという不安もあった。シャールク・カーンは俳優としては成功を収めているが、彼がプロデュースした作品は必ずしも当たって来ていない。例外的に文句ない大ヒットとなったのは「Main
Hoon Na」(2004年)や「Om Shanti Om」(2007年)など、ファラー・カーン監督のシャールク・カーン主演作のみである。
言葉遊びに敏感でインドのことを少しでも知っている人なら、「RA.One」という題名を見て「ラーマーヤナ」の悪役ラーヴァンを思い起こすだろう。その通り、これは、劇中に登場する、ラーヴァンからインスピレーションを得た悪役の名前である。2010年にはマニ・ラトナム監督が「Raavan」という映画を作っているが、それに引き続きラーヴァンを題名に冠した映画の登場で、現在までラーヴァンのキャラクターが悪役ながらインド人に愛され続けて来ていることが分かる。
ヒロインはカリーナー・カプール。主演シャールク・カーンとの同一作品出演は過去に何作かあるが、カップリングは大フロップ作「Asoka」(2001年)以来となる。しかしながら、カリーナーは最近「3カーン」の中の2人――アーミル・カーンとサルマーン・カーン――と共演して大ヒットを飛ばしており、上り調子だ。シャールク・カーンにとっても彼女がラッキー・マスコットになるかどうか、見物である。悪役のRA.Oneはアルジュン・ラームパールが演じる。「Om
Shanti Om」以来、アルジュンは得意な役柄が出来、起用が多くなった。その他、サンジャイ・ダット、プリヤンカー・チョープラー、アミターブ・バッチャンなどの特別出演または声の出演があり、豪華絢爛である。その中でもサプライズは、タミル語映画界のスーパースター、ラジニカーントが「Enthiran」(2010年;ヒンディー語版題名は「Robot」)で演じたチッティー役でスーパーな特別出演をしていることである。よって、「RA.One」は、ヒンディー語映画界のシェヘンシャー(皇帝)アミターブ・バッチャンが声の出演をし、ヒンディー語映画界のキングが主演し、タミル語映画界のスーパースターが特別出演するという、これ以上にないほど豪華な作品となっており、この点だけを見てもシャールク・カーンの気合いのほどがよく分かる。
また、2D版に加えて3D版も公開となった。インドで公開された初の3D映画でも、初の国産3D映画でもないが、「RA.One」でもって初めて3D映画に触れるインド人観客は多いだろう。僕は特に2Dか3Dかにこだわりは持っていなかったが、たまたま近所の映画館が3D版を上映しており、しかも値段は据え置きだったので、迷わず3D版を見ることにした。オリジナルのヒンディー語版に加え、タミル語版、テルグ語版、ドイツ語版も同時公開されたようだが、僕が見たのはヒンディー語版である。
題名:RA.One
読み:ラーヴァン
意味:ランダム・アクセス・ヴァージョン1/ラーヴァン
邦題:RA.One
監督:アヌバヴ・スィナー
制作:ガウリー・カーン
音楽:ヴィシャール・シェーカル
歌詞:アタハル・パンチー、ヴィシャール・ダードラーニー、クマール
振付:ガネーシュ・ヘーグデー
衣装:マニーシュ・マロートラー
出演:シャールク・カーン、カリーナー・カプール、アルジュン・ラームパール、シャハーナー・ゴースワーミー、アルマーン・ヴァルマー(子役・新人)、トム・ウー、ダリープ・ターヒル、スレーシュ・メーナン、サティーシュ・シャー、ラジニカーント(特別出演)、プリヤンカー・チョープラー(特別出演)、サンジャイ・ダット(特別出演)、アミターブ・バッチャン(声の出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

シャールク・カーン
| あらすじ |
ロンドン在住でゲーム会社勤務のシェーカル・スブラマニアム(シャールク・カーン)は、妻ソニア(カリーナー・カプール)との間に出来たゲーム少年の息子プラティーク(アルマーン・ヴァルマー)の「絶対に悪役が負けないようなゲームがあれば」と言う希望を叶えるため、絶対的な力を誇る悪役を中心にした格闘型バーチャルゲームを開発する。全身を覆うコントローラーを装着したプレーヤーのモーションがキャプチャーされ、ゲーム上のキャラクターの動きに反映されるというシステムだった。当初悪役はランダム・アクセス・ヴァージョン1というコード名で呼ばれていたが、いざ悪役の名前を付けようとした際に、その略称の「RA.One」がインド神話のラーヴァンに通ずるということで、そのままRA.Oneに決まった。そしてそれがそのままゲームの題名となった。また、ヒーローの名前も当初は「グッド・ワン(善玉)」だったが、その略称G.Oneが、ヒンディー語の「ジーヴァン(人生)」に通じるということで、これもとんとん拍子に決定した。さらに、G.Oneの顔はシェーカルがモデルとなった。
「RA.One」開発チームには、中国人のアカシ(トム・ウー)やインド人のジェニー・ナーヤル(シャハーナー・ゴースワーミー)などがいた。開発中に悪役RA.Oneの異常な行動が散見されたものの、格別注意を払う者はおらず、そのまま放置され、ゲームは完成した。
「RA.One」のローンチング・パーティーに母親と共に出席したプラティークはすっかり「RA.One」を気に入ってしまい、大人たちが祝宴をしている間、アカシの好意によって「RA.One」をプレイさせてもらった。プラティークはルシファーというハンドルネームを使いゲームにアクセスし、プレイを開始する。そこでレベル2まで進んだが、途中で中断させられてしまう。だが、RA.Oneはゲームの中断を快く思わず、ルシファーに対して執拗にゲーム再開を迫っていた。異常を察知したアカシはシェーカルを呼び、バグフィックスに取り掛かり始める。ソニアとプラティークは先に家に帰していた。
ゲームのプログラムだったRA.Oneはいつの間にか自我を持っており、ルシファーとの戦闘続行のためにRA.Oneの人形にアクセスして現実世界に侵入して来た。手始めにアカシを殺し、アカシの姿形もインストールする。次にシェーカルも殺されてしまう。当初シェーカルは交通事故で死んだとされたが、プラティークは現場に残っていた特徴ある印などから、RA.Oneの仕業だと考えるようになる。プラティークはRA.One開発室へ急ぎ、そこでG.Oneを起動しようとする。もしRA.Oneが現実世界に来られたならば、G.Oneも同様に現実世界に来られるはずだった。一方、RA.Oneはプラティークがルシファーであることを知り、プラティークを追い始める。プラティークは、RA.Oneが迫って来ていたために、G.Oneの起動を待たずに脱出し、ソニアの運転する車に乗り込む。RA.Oneはソニアとプラティークを追い掛けるが、間一髪のところでG.Oneが現れ、RA.Oneを撃退する。そしてG.OneはRA.OneのHARTを入手する。HARTとは、ゲーム「RA.One」中のキャラクターの心臓部で、力の源でもあり、弱点でもあった。HARTを心臓部に組み込むとキャラクターは最大限の力を発揮できるが、レベル3でHART部に特殊な銃弾を撃ち込まれると消滅するという弱点も生じるのであった。
シェーカルの死後、ソニアはプラティークを連れて故郷ムンバイーへ帰ろうとしていた。ところがそこへ突然シェーカルの顔をしたG.Oneが現れたため、混乱してしまう。プラティークはすぐに状況を理解したが、ソニアはG.Oneをインドに連れて行くことに反対だった。しかしG.Oneは付いて来てしまう。こうしてG.ONeはムンバイーの土を踏むことになる。空港前では複数の暴徒を一網打尽にする大活躍を見せると同時に、チッティー(ラジニカーント)とも対面する。
最初はG.Oneの扱いに困っていたソニアだったが、シェーカルの顔をし、シェーカルが入力した様々なデータを持つG.Oneを徐々に受け容れるようになる。だが、RA.Oneは完全に破壊されておらず、モデルの姿を借りて自動再生し、インドへ襲来した。RA.One(アルジュン・ラームパール)はソニアとプラティークを誘拐し、G.Oneにゲームを挑む。G.Oneはまず、暴走するムンバイー近郊列車に乗せられたソニアを救出する。次にRA.Oneが待ち構えるムンバイー・エキスポへ飛び、プラティークとシンクロして、G.OneからHARTを取り戻したRA.Oneと戦い出す。中断前にレベル2まで行ったため、まずプラティークは最終ラウンドであるレベル3への移行を目指して戦う。時間切れによりG.Oneはレベル3進出に成功する。
レベル3では双方銃を与えられると同時に、1発だけ弾丸を与えられる。この弾丸を相手のHARTに打ち込めば相手は消滅する。先手を打ったのはRA.Oneの方だった。RA.Oneは試合が始まると真っ先にG.Oneに銃を撃ち込む。銃弾はG.Oneに命中し、倒れる。ところがこれはプラティークの作戦だった。プラティークは事前にG.OneからHARTを抜き取っていた。HARTを装着していない場合、銃弾で撃たれても無効となる。早速プラティークはG.Oneに隠しておいたHARTを埋め込む。復活したG.OneはRA.Oneに反撃する。RA.Oneは10体に分身してG.Oneに迫るが、プラティークは父親が生前に口にしていた「悪に落ちたら常に影が付きまとう」という諺を想い出し、10体の中から影のある1体が本物だと察知して、銃弾を撃ち込む。果たしてその通りで、RA.Oneは消滅する。同時にG.OneもRA.Oneのかけらを身に受けて現実世界から消滅する。だが、G.OneのHARTは後に残った。
後日談。ソニアとプラティークはロンドンに戻っていた。プラティークはHARTを使ってG.Oneの再生を試みていた。そしてそれに成功する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
僕は常々インド映画がハリウッドの得意ジャンルを安易に真似することに反対している。マーケットの規模が全く違い、それに伴って予算の規模も全く違うハリウッド映画と同じようなジャンルの映画をインド映画界が背伸びして作っても、ハリウッド映画には到底太刀打ちできず、最終的には呑み込まれてしまう恐れがあるからだ。よって、インド映画はインド映画の良いところを守りつつ発展して行くべきだというのが持論である。SF映画「Koi...
Mil Gaya」(2003年)公開前もこういう心配をしていたし、この「RA.One」公開前も全く同様の懸念を抱いていた。ところが、インド映画はそんな僕の心配を常にいい意味で裏切り続けてくれた。
「RA.One」は、今後インド映画がどういう方向で発展して行くかを示す、大きな指針となり得る作品のひとつである。ここ最近ヒンディー語映画界では、グローバル市場を念頭に置き、やたらハリウッド映画を意識した作品作りが行われている。その中でも、インド映画の良さを廃し、「グローバル・スタンダード」に準拠したインド映画が何本かあり、それらは失敗に終わっている。最大の失敗作がリティク・ローシャン主演「Kites」(2010年)であった。一昔前のハリウッド映画をインド人俳優で作ったような作品であり、一体誰をターゲットにしているのか分からない駄作だった。インド映画の伝統である歌と踊りを無闇に廃し、上映時間も2時間弱に収め、全体的に薄味にしてグローバル映画としているような例も少なくなく、そういう動きには今でも絶対に反対である。
しかしながら、インド映画らしさを守りながら、そのフォーマットの中で、真面目なメッセージを発信したり、世界の観客にアピールする娯楽力のある作品も多く登場しており、それらは順当にヒットを飛ばしている。その先駆けは何と言っても「Lagaan」(2001年)であるが、最近では「3
Idiots」(2009年)が好例である。「RA.One」も、このリーグに属する映画であった。
「RA.One」には、豪華絢爛な歌と踊りのシーンが目白押しであるし、コテコテのインド・ジョークも連発される。また、映画で重きが置かれる価値観もインドの文化に根ざしたものであるし、インドに関連のあるモチーフも多用される。それでいて、映画を支える技術的な部分では完全にハリウッド・レベルを実現しており、カーチェイス・シーンや戦闘シーンなど、手に汗握る見所満載である。前半はロンドンが舞台となるが、後半からはムンバイーが舞台となり、この意味でも根無し草的映画になっていない。現代のインド人観客を楽しませるインド映画として、非常にバランスの取れた作品となっていたと評価できる。
「RA.One」の最大のテーマは「悪に対する正義の勝利」である。これは「勧善懲悪」という四文字熟語と同義であり、しかもしばしばこの四文字熟語は映画の評価の際にネガティブな意味合いを持つ。だが、インド映画に限っては、勧善懲悪は欠点ではない。これは映画の歴史よりも古いインドの伝統に根ざした絶対的な方程式であり、これを動かすことはインド映画らしさを失うことになる。物語の常套手段として、「悪に対する正義の勝利」を強調するために、まずは「悪」の賛美が行われる。シェーカルの息子プラティークは、アニメやゲームなどに出て来るヒーローを「退屈」だと考えており、悪役に対して魅力を感じている少年であった。シェーカルはそんな息子に「最後に勝つのは正義だ」と言い聞かすものの、プラティークを喜ばせるために悪役が絶対的な力を持ったゲームを作ることを決める。これが映画の導入部となっており、クライマックスでは当然のことながら正義が勝利を収める。ただ、RA.Oneがどのように悪なのか、映画中では特に説明がなかったのが気になった。言わば「とにかく悪役っぽい風貌をしているので悪役」という投げやりな設定で、いい加減だったのではないかと感じた。もっとも、「ラーマーヤナ」の中のラーヴァンと重ね合わしてキャラ作りをしているため、インド人には説明は不要なのかもしれない。
ちなみに、「Ra.One」はディーワーリー祭当日に公開となったが、ラーム王子がラーヴァンを退治したのはディーワーリー祭より約20日前のダシャハラー祭であり、「RA.One」の公開もダシャハラーに合わせた方がよりメッセージが明確になったのではないかと思った。ダシャハラー祭ではラーヴァンの像が燃やされる。劇中でRA.Oneがインドに到着したのはちょうどダシャハラーの日であった。そのときRA.Oneは「なぜ毎年ラーヴァンの像が燃やされるのか?それは悪が絶対に滅びないからだ」という強烈な決め台詞も発する。また、劇中にはダシャハラー祭の約10日後に行われる、夫の長寿と健康を祈る女性の祝祭カルワー・チャウトの描写もあった。
「RA.One」のもうひとつの重要な軸は父と子の関係である。最近のヒンディー語映画で描かれる父親像が急に弱々しいものになって来ていることは何度も指摘しているが、この「RA.One」もそのひとつだと言える。序盤、プラティークは父シェーカルをドジで弱虫で情けない人物だと見下している。だが、シェーカルは人一倍プラティークのことを愛しており、自身の信念を曲げてまでして、息子の希望に沿ってゲーム「RA.One」を作る。プラティークは「RA.One」を気に入り、父親に感謝しようとするが、それを伝える前にシェーカルはRA.Oneに殺されてしまう。しかしプラティークは、バガヴァドギーター第2章第22頌にある「人間が古い衣服を捨てて新しい衣服を着るように、不滅の魂は古い身体を捨てて新しい身体を手に入れる」という一節を聞いて、突然現れたG.Oneを父親の生まれ変わりだと考えるようになる。G.Oneは百人力のパワーを誇り、正にプラティークが常々抱いていた父親像・ヒーロー像そのものであった。そしてG.OneはRA.Oneに誘拐されたプラティークを救い出し、シェーカルが果たせなかった父親としての任務を全うする。もちろん、いくらプラティークがエピローグでG.Oneの再生に成功したとしても、シェーカル自身は戻って来ない。だが、今やプラティークは父親を完全に理解し、永遠に尊敬することだろう。父親にとって、たとえ死んでしまったとしても、それは小さな話ではない。
最近は、ビデオゲームの影響で子供に「殺す」という行為に抵抗がなくなっているという話をインドでも聞く。ビデオゲームの中では敵を「殺す」行為は日常茶飯事であり、また自分が死んでもまたやり直しができる。上記のバガヴァドギーターの引用とは全く正反対となるが、劇中には「現実世界では人間は死んだら戻って来ない」という警告も盛り込まれていた。
また、オマケであろうが、禁煙のススメとも取れる1シーンもあった。喫煙シーンに厳しいインドならではの措置であろう。ちなみにシャールク・カーンはヘビースモーカーとして知られている。
全体として「RA.One」は非常に優れた娯楽作品であったが、いくつか難点も見られた。一番の難点は設定部分が分かりにくいことである。冒頭部分で説明された無線データの可視化や可触化と本筋との関連性、ゲームのキャラクターが現実世界に侵入して来る理論的裏付け、HARTの役割など、一応劇中に説明があるものの、それでも完全には理解できず、そういうものだと自分に言い聞かせてストーリーを追うしかなかった。
ハリウッドのロボット映画やSF映画の影響が大きすぎる点も、ハリウッド映画をよく見ている観客には気になる点であろう。もっとも意識していると思われるのが「ターミネーター2」(1991年)と「マトリックス」シリーズである。RA.Oneがアカシの容姿をインストールしてからルシファーを追い掛けるシーンまでの展開は「ターミネーター2」そっくりだったし、RA.Oneがソニアの運転する自動車を追い掛けるシーンは、劇中で最も迫力のあるアクションシーンだったものの、「マトリックス」シリーズにかなり似ていた。
おそらくラジニカーント主演のロボット映画「Enthiran」との比較も今後されることだろう。制作費では、2010年の時点でインド映画史上最高額だった「Enthiran」を、「RA.One」は早くも越したとされている。しかしながら、映像の迫力、ストーリーの面白さ、悪ふざけやサプライズなど、様々な点を考慮すると、「Enthiran」の方が一枚上手かもしれない。「RA.One」の方は、悪役が世界征服や大量殺人などの大それた野望を抱かず、ルシファー=プラティークの抹殺のみを追い求めるため、世界遺産チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス(元ヴィクトリア・ターミナス)破壊など一部のシーンを除きあまり外界との接点がないし、全体としてこじんまりとまとめた感じだが、「Enthiran」の方は徹底的に物語を拡大し、人類滅亡の一歩手前まで行く、観客の想像力を越える極端な展開を披露している。娯楽映画としてはやはり、破綻覚悟で徹底的な娯楽を追い求めた「Enthiran」の方が楽しさは上だ。
日本人としては、中国人エンジニア、アカシの存在も気になる。アカシは「中国人はみんなジャッキー・チェンじゃない!」が口癖で、それがお約束ギャグとなっているが、アカシという名前は日本人の名前じゃないのかというのが我々日本人の心に浮かぶ素朴な疑問である。むしろ日本人の方が、インド人から事あるごとに「ジャッキー・チェン」と呼ばれて困っているし、インド映画に根強く残る日本人と中国人の混同もどうにかして欲しいと願っている。
シャールク・カーンの演技は、はまり役とそうでない役で開きがあり、必ずしもオールマイティーの俳優ではない。だが、最近は「Om Shanti Om」(2007年)や「Rab
Ne Bana Di Jodi」(2008年)などで1人2役やそれに近い形での、全く正反対のキャラを演じ分ける特技を発展させつつあり、それが非常にうまく行っている。「RA.One」も、天然ボケの父親シェーカルと生身の感情を持たないG.Oneの演技を演じ分けており、良かった。シャールクが演じたタミル人キャラがどれだけ現実に近いか、その評価はタミル人がしてくれるだろう。
カリーナー・カプールは、一応ヒロインながら、ロマンス映画ではないため、ストーリー上ではものすごく大事なキャラでもない。しかし、ふとした拍子に見せる微妙な表情に、既にベテランの域に達した演技力の片鱗を感じさせられるところがあった。
プラティークを演じた子役アルマーン・ヴァルマーも好演。悪役RA.Oneを演じたアルジュン・ラームパールは意外に出番が少ないが、今回スキンヘッドで登場し、恐ろしさがよく出ていた。
特別出演のサンジャイ・ダットは、代表作「Khalnayak」(1993年)のパロディー、プリヤンカー・チョープラーは「Dostana」(2008年)のヒットで愛称となった「デーシー・ガール」として冒頭に少しだけ登場する。また、前述の通りタミル語映画界のスーパースター、ラジニカーントがチッティー役で少しだけ出演している。しかしあくまでオマケの出演で、ストーリーの中で重要な役割は果たしていない。アミターブ・バッチャンの声は、ゲーム「RA.One」のイントロダクションで流れる。他に、これらの特別出演に関連して、過去の有名映画音楽が少しだけ流れるシーンがいくつかある。
音楽はヴィシャール・シェーカル。正直言ってサントラCDを聞いた時点ではあまり魅力を感じなかったのだが、映画を見た後でもう一度聞き直すと、どれもストーリーにシンクロして作られており、映画の中での収まりは良かった。「RA.One」サントラCDの中の売れ筋は何と言ってもパンジャービー曲「Chammak
Challo」。「チャンマク・チャッロー」とはパンジャービー語の俗語で「セクシー・ガール」を意味する。R&Bシンガー・ソングライターのエイコン(Akon)が共同作曲し歌を歌っている。ベンEキングの有名曲「スタンド・バイ・ミー」のヒンディー語カバー「Dildaara」も目立つ曲だ。シェーカルの死後かつG.Oneとの生活スタート時に流れ、ストーリー上のアクセントになっている。「RA.One」には飛びっきりの名曲はないが、映画によく溶け込んだ良曲ばかりだと言える。
ヒンディー語版「RA.One」の言語は基本的にヒンディー語だが、面白いことに、シャールク・カーン演じるシェーカルがタミル人という設定であるため、タミル語の台詞が意外によく出て来る。逆にタミル語版がどうなっているのか興味あるところである。
「RA.One」は、インド映画史上最大予算作品かつ2011年最大の話題作の名に恥じない超娯楽大作であった。アクションシーンなどの映像はハリウッド映画レベルだが、歌と踊りやコテコテのインド・ジョークなど、インド映画らしさも失っておらず、絶妙なバランスの取れた国際派インド映画だ。押しも押されぬ今年必見の作品の1本である。完成度が低かったのに大ヒットとなってしまった「Bodyguard」に比べたら、よっぽど大ヒットする資格を持った作品である。
昨年、英連邦競技大会(CWG)のオープニングを見ることができて僕は満足していた。僕がデリーに住み始めた頃からインド中央政府やデリー州政府がずっと準備して来た国際総合スポーツ大会であり、そのオープニングを飾るスタジアムでの一大スペクタクル・ショーを現地で鑑賞できたことで、僕のデリー時代の総括となったように感じていた。僕が20代の大半を過ごしたインドとデリーの一時代――21世紀の最初の10年――の終焉と、次の新たな一時代の幕開けを感じさせてくれた。
よって、今年10月28-30日にグレーター・ノイダのブッド・インターナショナル・サーキット(Buddh International Circuit)で開催される予定の、初のF1インドGPについては、特に興味を持っていなかった。
「もっとも贅沢なスポーツ」と呼ばれるF1は、オリンピックやFIFAワールドカップなどと並んで、国威発揚には絶好のスポーツ・イベントだと考えられている。F1インドGPの構想と準備にもCWGと同じくらいの時間が費やされ、度々報道もされて来た。またこの間、インド人F1ドライバー、ナーラーヤン・カールティケーヤン(Narain
Karthikeyan)や、インド企業がオーナーのF1チーム、フォース・インディアも誕生し、F1インドGPの気運は高まっていた。
だが、F1は必ずしも当初からデリーNCR(首都圏)とは関係を持っていなかった。ブッド・インターナショナル・サーキット以前、インドにはチェンナイとコインバトールにしかレースコースがなく、インドのモータースポーツ・シーンは南インドが中心だった。その関係であろうか、F1インドGPが具体化された当初は、アーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードにサーキットが建設される予定だった。ところが、チャンドラバーブー・ナーイドゥ州首相(当時)の失脚などで二転三転し、ムンバイー、バンガロール、グルガーオンなどが候補に挙がった後、最終的に、大手インフラ開発企業ジェーピー(Jaypee)グループがデリー近郊グレーター・ノイダに建設中のスポーツ総合施設ジェーピー・スポーツ・シティーの一角ブッド・インターナショナル・サーキットを会場とすることが決まった。よって、F1インドGPは、まず首都デリー開催ありきで進められて来たイベントではない。今思うと、テランガーナ独立運動が激化するハイダラーバードをF1インドGPの会場にしなかったことは運が良かった。
また、僕自身もF1には全く疎く、関心を持ちにくかった。TVを付けたらたまたまやっていた、という理由でF1のレースをTV観戦したことは過去に何度かあるし、アイルトン・セナやミハエル・シューマッハの名前くらいは知っていたが、それだけだった。よって、F1インドGPはパスの予定だった。
ところが、開催日が近付くにつれて、F1インドGPの成功を危ぶむ声がチラホラと聞こえて来るようになった。サーキット建設の遅れ、チケットの売れ残り、税金問題、ヴィザ問題などである。「F1インドGP、大赤字確実」との報道もあった。多くの問題は何ともしがいたいものであったが、少なくともチケット売れ残りの問題に関してはデリー市民が支えることができた。
チケットが売れ残った主な原因は2つ考えられる。ひとつは、一般のインド人の間での、F1を初めとするモータースポーツへの関心の低さである。これはクリケット以外のほとんどのスポーツがインドにおいて共通して抱える問題だ。もうひとつはチケット代の高さ。3日間通しのチケットが、一般販売されている中でもっとも高いもので35,000ルピー(メイングランドスタンド)、もっとも安いもので2,500ルピー(ナチュラルスタンド)だった。ただ、2,500ルピーのチケットが早々に完売してしまったところを見ると、F1に関心を持つ層はインドにも一定数いるが、高いチケットを何枚も買う経済的余裕のある層は少ないということを示していると言える。インドではこういうイベントに1人で来る人は少なく、家族連れの割合が高いため、チケット代の高さは現実的には何倍にもなって潜在的観客層の懐を直撃する。よって、チケット代の高さがチケット売れ残りの大きな要因となったと考えられる。
しかしながら、もうひとつインド特有の理由もある。さすがに売れ残りが多すぎたためか、開催1週間前になって、最終日のみのチケットが大幅に割り引きされて販売された。35,000ルピーのメイングランドスタンド・チケットが15,000ルピーに、6,500ルピーのクラシックスタンド・チケットが4,000ルピーに、6,000ルピーのピクニックスタンド・チケットが3,000ルピーになった。そう、インドには「この料金設定では絶対に売れ残り、最終的にチケットが叩き売りされる」と予想することのできる老練な人々もおり、そういう人々の買い控えも売れ残りの大きな原因となったと考えられるのである。果たして正にその通りとなった訳である。
僕も、F1インドGP大赤字の報道とチケット安売りのニュースを聞き、腰を上げた1人である。国際舞台でインドに赤っ恥をかいて欲しくないという願いから、F1チケット入手に走り始めた。ディーワーリーの前日のことであった。
チケット入手の話の前に、ブッド・インターナショナル・サーキットの概要について簡単に説明しよう。サーキットのデザイナーはドイツ人建築家ヘルマン・ティルケ、総工費は85-90億ルピー。全長は5.137km、F1のレースではラップ60となる。高低差のあるコースとなっており、合計16のコーナーがある。第3コーナーから第4コーナーまで1.2kmの長い直線があり、ここがDRSゾーンにもなっており、ここでトップスピード320kphに達することが期待されいる。また、第5コーナーから第9コーナーにかけて小刻みにカーブが続くエリアはこのコースでもっともトリッキーであり、スキルを要求される。第16コーナーから第1コーナーのショート・ストレートもDRSゾーンとなっている。DRSゾーンでは可変リアウィングが使用でき、追い抜きがしやすいとされている。平均時速は210kph、ラップタイムは1分27秒が予想されている。全体として、テクニカルで、追い抜きしやすいコースとの評価。観客席のキャパシティーは15万人とのことである。
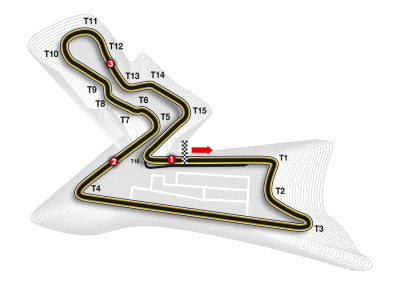
ブッド・インターナショナル・サーキット
ブッド・インターナショナル・サーキットの座席には6種類ある。スタート/ゴール地点であり、レースの中心となるメイングランドスタンド、第1コーナーや第10-11コーナーを楽しめるプレミアムスタンド、ロングストレート後の第4コーナーを楽しめるスタースタンド、その他の小さなコーナーなどを楽しめるクラシックスタンド、芝生に座る形となるピクニックスタンドとナチュラルスタンドである。チケットの値段もこの順番で高い。3日間通しのチケットで、それぞれ35,000ルピー、12,500ルピー、8,500ルピー、6,500ルピー、6,000ルピー、2,500ルピーとなっている。メイングランドスタンド、プレミアムスタンド、スタースタンド、クラシックスタンドは指定席だが、ピクニックスタンドとナチュラルスタンドは自由席となる。また、屋根があるのはメイングランドスタンドとプレミアムスタンドのみ。サーキットの観客席は東西南北4つのゾーンに分かれており、色分けもされている。赤がウエストゾーン、黄がノースゾーン、青がイーストゾーン、緑がサウスゾーンである。ゾーンごとに入口や駐車場が異なる。一旦スタンドに入ってしまうと、ゾーン間の移動ができないばかりか、クラスの異なるスタンド間の移動もできない。
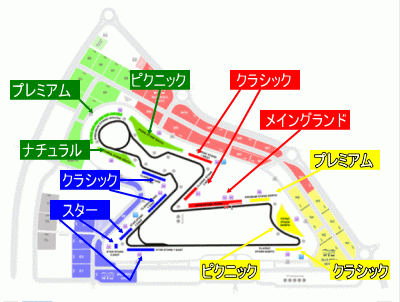
スタンド配置図
F1を生で観戦したことがなかったため、どこの席にしたらいいか分からなかった。しかしながら、全ての座席が安売りされていた訳ではなかったため、選択肢は限られていた。メイングランドスタンド(ウエスト)か、クラシックスタンド(ウエスト、ノース、イースト)か、ピクニックスタンド(ノース、サウス)である。F1に詳しい友人のアドバイスを参考にしながら、イーストゾーンのクラシックスタンド1に決めた。第4コーナーと第5コーナーの間に位置しており、向こう側の第15コーナーや第16コーナーも見えるため、4つのコーナーを一度に楽しむことができると予想したのだった。

クラシックスタンド1イーストJブロックT列からの眺め
奥に見えるのがメイングランドスタンド
左隅にクラシックスタンド1ウエストも見える
購入時にスタンドのみならずブロックも指定できた。指定席のスタンドは複数のブロックに分かれており、それぞれアルファベットが振られている。何しろ行ってみないとどこがいい席か分からない状態だったので、適当にJブロックを選んでみた。「Japan」の「J」だからというしょうもない理由だ。しかし、意外にいい選択だった。なぜならスクリーンが目の前にあったからだ。もっと多くのスクリーンが設置されるだろうと考えていたのだが、行って見てみると各スタンドひとつのみで、中央部に配置されていた。スタンドの隅の席の人はスクリーンを見にくかっただろう。サーキットは広く、補助情報がないとどこで何が起っているか分からないので、スクリーンは重要だ。よって、購入するならば各スタンド中央部が狙い目だと言える。また、列は選べなかったが、僕が買ったのはT列で、かなり高所の席だった。
ところで、3日間通しのチケットはデリー各地の特定のカフェ・コーヒー・デーなどでも販売されていたが、最終日のみの安売りチケットは、インドのオンラインチケット販売大手BookMyShowのみの販売であった。これを機に今回初めてBookMyShowを使ってみた。チケット予約や支払い(デビットカードを使った)まではスムーズに行ったが、チケット受け取りについてはあまりいい感想を抱かなかった。通常時ならばホームデリバリーもあるのだが、開催日が迫っていたために、安売りチケットは自分で指定の場所(ノイダのマハーマーヤー女学校)まで受け取りに行かなければならなかった。よって、ディーワーリーの当日にノイダまで出向いてチケットを受け取ったのだった。それはそれでいいのだが、事前のEメールで「受け取りは午前8時から」と告知されていたにも関わらず、午後8時半頃に現地へ行ってみてもまだ何も始まっておらず、結局2時間ほど待たされ、ようやくチケットを受け取ることができたのはマイナス評価だった。幸い、F1チケット購入者は比較的裕福なインド人ばかりで、担当者がいないも関わらず自主的に列を作っていたし、担当者が来てからも多少の混乱はあったが、限度を超えるようなトラブルは起きず、チケットを受け取ることができた。
安売りチケット販売に踏み切ってもまだ売れ残るぐらいだったので、今回チケット入手に大きな困難はなかった。無料の招待券などもかなり出回っていたようである。入場券入手よりもむしろ困難かつ重要だったのは、駐車券やシャトルバス・チケットを初めとするサーキットへのアクセス手段の確保であった。何しろブッド・インターナショナル・サーキットはデリーから50km以上離れた僻地にある。ジェーピー・スポーツ・シティーと言ってもまだ名ばかりで、単なる荒野が広がっているのみだ。デリー市内で開催され、デリー・メトロの恩恵に与れたCWGとは全く環境が違う。しかも、サーキットのすぐそばに駐車し徒歩で入場できるパーミット「Park
& Walk」は数が限定されている上に法外な価格設定となっていたし(四輪車は3日間有効1,500ルピー)、3枚以上入場券を買わないと四輪車用の「Park
& Walk」パーミットは買えないという縛りもあった。パーミットがない車両はサーキットに近付くことすら許されない。デリーNCR各地から発車するシャトルバス(BICバス)も事前予約必須で、かつ600ルピー(3日間往復有効)という高額な運賃設定となっていた。
僕は元々バイクでサーキットまで行く予定だったが、実はバイクがもっとも理想的なアクセス手段であった。まず、二輪車の「Park & Walk」チケットは比較的安価だった。3日間150ルピーである(1日のみの販売はなし)。四輪車が1台1,500ルピー、シャトルバスが1人600ルピーであることを考えると格安とも言えた。また、サーキットにはおよそ10万人が訪れるとされており、行き帰りは大渋滞が予想された。バイクならば渋滞にも強い。幸い、二輪車用の「Park
& Walk」パーミットも、マハーマーヤー女学校での入場券受け取り時に購入することができた。当初は、2枚以上の入場券を購入することで1枚の二輪車用「Park
& Walk」パーミット購入資格が生じるとされており、僕も念のために2枚購入したのだが、安売りの段階ではそういう縛りもなくなっていた。ただ、安売り時にも二輪車パーミットは結構余っていたものの、四輪車パーミットは残り僅かになっていた。例えば、僕が今回選んだイースト・ゾーンの四輪車パーミットは安売り時点では既に完売していた。
ついでに、もし駐車・駐輪パーミットもBICバスのチケットも手に入らなかった場合、ブッド・インターナショナル・サーキットにどうやって行けばいいのか、ということについても、今後の参考になると思うので(インドGPは今後毎年開催予定)、併せて触れておく。端的に言えば、サーキットまでのアクセス手段のひとつに「Park
& Ride」が用意されており、それを利用することになる。ノイダ・グレーター・ノイダ・エクスプレスウェイのそば、サーキットから数km離れた場所にナレッジ・パーク(Knowledge
Park)という場所があり、パーミットのない車両は皆そこに駐車・駐輪する(無料)。そしてナレッジ・パークとサーキットを往復している無料シャトルバスを使ってサーキットへ向かう。事前のインストラクションではこのパーミットもチケット購入時に同時購入することになっていたが、どうやら販売はされておらず、パーミットがなくても駐められたようである。また、ナレッジパークのシャトルバス発着所まで公共バスを使って行くことができれば、シャトルバスでサーキットにも行けるようであった。
ゾーンやスタンドの選び方についてもついでなので実際に行ってみた経験を元にアドバイスを記しておく。はっきり言ってしまえば値段相応である。高ければ高いほどいい席となる。やはり何だかんだ言ってメイングランドスタンドがもっとも楽しめたのではないかと思う。だが、僕が選んだイースト・ゾーンのクラシックスタンドに関しては、もしかしたら他のクラシックスタンドよりもコストパフォーマンスが高かったかもしれない。僕が座ったクラシックスタンド1イーストは、4つのコーナーを楽しめることについては前述の通りだが、それに加えて第4コーナーからの下り坂の目の前にあり、もっとも追い抜きがしやすい場所となっていた。よって、目の前で何度もオーバーテイクが見られた。オーバーテイクはF1の大きな見所である。また、もうひとつのクラシックスタンド2イーストは、このコースで最大の難所であり事故も多発していた第5コーナーから第9コーナーを見渡せる場所で、レース最大のドラマを目撃できたスタンドだったと思われる。さらに、イースト・ゾーンのクラシックスタンド・エリアにはグッズ販売所があった。ウエストゾーンのメイングランドスタンドの裏にはF1ヴィレッジなるものがあり、そこにグッズ販売やその他各種展示があったようだが、それはメイングランドスタンド観客のみの特典であり、その他にグッズ販売があったのはどうやらイースト・ゾーンのこのクラシックスタンド・エリアのみだったようである。フォース・インディア、フェラーリ、マクラーレン、ブッド・インターナショナル・サーキットなどの公式グッズが売られていた。ただ、フェラーリのキャップが1つ3,000ルピーなど、グッズはどれも非常に高価だった。また、このイースト・ゾーンのグッズ販売所の裏の空き地は重要な第5-7コーナーの内側で、金網の向こうに間近にコースを見ることもできた。もしスタンドを離れてこの空き地でレースを観戦していたら、フェリペ・マッサ(フェラーリ)とルイス・ハミルトン(マクラーレン)のクラッシュを眼前で目撃することができただろう。

イースト・ゾーンのグッズ販売所
また、持ち込み禁止の品物が事前にいくつも列挙され告知されていたが、当日の持ち物チェックはそこまで厳しくなかったことも付け加えておきたい。特に懸念されていたのがカメラの持ち込みについてである。「プロフェッショナル」なAV機器やカメラの持ち込み禁止が明記されており、一眼レフカメラやビデオカメラの持ち込みを意味しているのではと噂されていた。しかし現地へ行ってみると一眼レフカメラもビデオカメラも余裕で持ち込めていた。
最終日10月30日には、F1本戦の他に2つのレースがあった。ひとつはMRFデリー・チャンピオンシップ(午前11時から)、もうひとつはJKレーシング・シリーズ(正午12時から)である。前者は、1.6リットルのエンジンを搭載したレーシングカーによる、インド人エントリーレベル・フォーミュラ・レーサー育成を主眼としたレース。後者は、1.2リットルのエンジンを搭載したレーシングカーによるアジアレベルのレースで、トップスピードは230kph。ちなみに今年のF1のエンジンの排気量は2.4リットル、トップスピードは320kphとのことなので、スピードは全く異なる。F1本戦は午後3時からであった。せっかくなので、午前11時のMRFデリー・チャンピオンシップに間に合うように出掛けることにした。グレーター・ノイダにはバイクで何度か行ったことがあるので大体の距離と所要時間は分かっていたが、F1当日のため交通事情も異なるだろうと予想し、混雑を避けるためにかなりの余裕を持って午前8時半に出発することにした。

駐輪パーミット
ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)からアウターリングロードを東進し、ニューフレンズ・コロニーのフライオーバーでマトゥラー・ロードに入って南下。アポロ病院を過ぎて左に曲がり、カーリンディー・クンジからヤムナー河を渡河してマハーマーヤー・フライオーバーからノイダ・グレーター・ノイダ・エクスプレスウェイに入った。まだ朝早かったために交通は少なく、片側3レーンのエクスプレスウェイは快適な走行ができた。朝靄の中ひたすらエクスプレスウェイを進んで行くと、やがてブッド・インターナショナル・サーキットへの道順を示す看板が現れ始める。そして、ノイダ・グレーター・ノイダ・エクスプレスウェイがグレーター・ノイダへ向けてグッとカーブした後しばらくすると、サーキットへと続くフライオーバーが出現する。パーミットを持った車両のみがこのフライオーバーへ入ることができ、噴水を囲むカーブを越えて、ブッド・インターナショナル・サーキットへ向かう広い直線の道へ出る。おそらくこの道がそのままグレーター・ノイダとアーグラーを結ぶヤムナー・エクスプレスウェイ(旧名タージ・エクスプレスウェイ)になるはずである。このフライオーバーを越えてからもかなりの距離を走行しなければならなかった。まずはウエスト・ゾーンとノース・ゾーンへ向かう道が分岐し、次にパドックへ向かう道が分岐し、最後にイースト・ゾーンとサウス・ゾーンへ向かう道が分岐していた。このエクスプレスウェイを下りると、舗装はちゃんとしていたものの途端に田舎の農道のような雰囲気になり、道のすぐそこには畑があって農民が農作業をしていた。エクスプレスウェイの下をくぐり抜けるとサウス・ゾーンの入口があり、右へ向かうとイースト・ゾーンの入口があった。パーミットを何度も確認された後、敷地内に入って、二輪車用の駐輪場にバイクを駐めた。愛機カリズマをサーキット近くまで連れて来られたことにひとまず感激であった。JNUからは1時間10分かかった。時計は午前9時40分を指していた。

サーキットの駐輪場で記念撮影
裏はスタースタンド(イースト・ゾーン)
セキュリティーはそれほど厳しくなかった。チケットの確認は2ヶ所のみ。最初のチェックポイントで簡単に手荷物検査があり、2番目のチェックポイントで金属探知機による身体検査と手荷物のX線検査を受ける。一旦入ってしまえば物々しい雰囲気は全くなかった。ただ、イースト・ゾーンのスタンド裏は殺風景だった。おそらくメイングランドスタンドの辺りはより美しく整備されていたのではないかと予想する。

早朝のイースト・ゾーンの様子
時間通り午前11時からMRFデリー・チャンピオンシップが始まり、正午12時からJKレーシング・シリーズが始まった。F1に比べて排気量は劣るが、このときはこれでも十分速いと感じた。これらの前座レースはラップ10のみなのでそれぞれ30分ほどですぐに終了した。

MRFデリー・チャンピオンシップ
第4コーナー、スタースタンド方面
飲食物持ち込みは禁止されていたため、昼食は売店で購入せざるを得なかった。噂で聞いていた通り、非常に高価であった。ヴェジのメインディッシュは250ルピー前後、ノンヴェジのメインディッシュは300ルピー前後。まともな料金設定だったのは1本15ルピーのボトルウォーターのみ。しかもサンドイッチやパスタを除けばほとんどがコテコテのインド料理で、各メニューの説明は一切なし。F1のためだけにインドを訪れた外国人観客は困ってしまったことだろう。僕は「腹を壊さなければOK」という程度の気持ちでラージマー・チャーワル(250ルピー)を食べることにした。ラージマー・チャーワルはインド人の大好物のひとつで、僕も大好きである。まずはクーポン券売り場でクーポンを買い、それを料理カウンターで出して料理を注文し受け取るシステムは面倒だった。しかしながら、プラスチックの容器に白飯とラージマー(ウズラマメの料理)が別々に入っており、注文するとレンジでチンして提供してくれる。見た目はそそらなかったが、これが意外においしくて、高価でなければもっと別のメニューも試してみたかったくらいである。

ラージマー・チャーワル
ところで、JKレーシング・シリーズの終わり頃に、パドックに数々のヴィンテージ・カーが入って来ていたのが見え、気になっていた。僕の席からはパドックへ通じる道がよく見えたのである。インフォメーション・カウンターで「ヴィンテージ・カーのパレードでもあるのか?」と聞いてみたが、誰も情報を持っていなかった。しかしながら、午後1時半から「サプライズ・ショー」があるとのことだったので、おそらくそれだろうとスタンドへ戻って待っていた。すると、やはりインド人カーマニアたちが所有するヴィンテージ・カーのパレードが始まった。しかしながら主役は自動車ではなかった。なんと1台1台のヴィンテージ・カーにF1ドライバーが1人1人乗り込み、コースを1周してくれたのである。他ではあまり見られないファン・サービスであった。

王者セバスチャン・ビッテル
その後ヘリコプター・ショーなるものがあり、2台のヘリコプターがサーキット上空を飛び交っていたが、これはあまり楽しくなかった。てっきりウッタル・プラデーシュ州のマーヤーワティー州首相が到着したのかと思った。その後、メイングランドスタンドの特設ステージにレスリー・ルイス、KK、ラッキー・アリー、ダレール・メヘンディーが登場し、F1インドGPのテーマ曲と思われるヒンディー語の歌を歌っていたが、大したものではなかった。レース直前には、最近相次いで亡くなったレースドライバー/ライダー、ダン・ウェルドンとマルコ・シモンチェリのための黙祷があり、インドの国歌が上記の歌手たちによって斉唱された。
予定通り午後3時からF1本戦が始まった。やはりF1は速かった。今まで下の階級のレースを見て来てやっとF1のレースとなったが、スピードは歴然として違っていた。そして音も段違いだった。ちょうどスタンドの前は難関の第5コーナーに迫るショート・ストレートとなっており、独特の「ウィーン」という風を切るエンジン音の後に、シフトダウンをしてエンジンブレーキを掛けているのか、「ボッボッボッボ」というユーモラスな音がよく聞こえた。この「ウィーン、ボッボッボッボ」が何度も何度も繰り返されるというのが、このクラシックスタンド1イーストの特徴であった。また、レースの間中タイヤの焦げる何とも言えない匂いがサーキットを覆っており、独特の雰囲気があった。

レース開始直後、第4コーナーを曲がるマシーンたち
レースの結果は報道されている通りである。既に年間優勝を決めているセバスチャン・ビッテル(レッドブル)がポール・ポジションからスタートし、そのまま得意の先行逃げ切り独走態勢を取ってインドGP初の王座に輝いた。最速ラップもベッテルで1分27秒25。2位はジェンソン・バトン(マクラーレン)、3位はフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)。インドの視点から見れば、フォース・インディアのエイドリアン・スーティルが9位入賞、HRTのナーラーヤン・カールティケーヤンが17位の好成績でフィニッシュしたことが特筆すべきだ。一方、スタート直後に後方のマシーン数台がぶつかる事故があり、日本人の小林可夢偉(ザウバー)も巻き込まれ、0周リタイアとなってしまった。他には、前述の通りフェリペ・マッサ(フェラーリ)とルイス・ハミルトン(マクラーレン)のクラッシュがあり、マッサがリタイアとなったのが大きな出来事であった。このときフェラーリのパドックで試合を見守っていたローワン「Mr.ビーン」アトキンソンが映され、Mr.ビーンそのものの悔しげな仕草をしていたのもまた一興であった。

レース終盤
手前が第5コーナー、奥が第15コーナー
目の前にスクリーンがあり、おそらくテレビ中継と同じ映像が映っていたために、一応レースの大体の展開は追えたが、それでも全てを把握して観戦することはできなかった。今前を通っているマシーンに誰が乗っているかなど、よく分からなかった。小林可夢偉のリタイアもレースが終わって初めて確認できた。そういうことはもっとF1に慣れれば自然と分かるようになるのかもしれない。だが、生で観戦した結果、F1はむしろ五感で楽しむスポーツだと感じた。特に聴覚と嗅覚。あの音、あの匂い。テレビでの観戦とは全く違った楽しみ方になったと言える。
レース後はまた大変だった。観客が一斉に帰宅を始めたため、サーキットの駐車場やノイダ・グレーター・ノイダ・エクスプレスウェイとの合流点などで大渋滞が発生していた。しかしながら、バイクだったので隙間さえあれば前へ前へと進むことができ、渋滞による時間的ロスは最小限であった。スタンドを出てから2時間以内に帰宅することができた。しかし、「Park
& Ride」で来た人は、まずサーキットからナレッジ・パークへシャトルバスで行くまでで一苦労で、そこからまた家に帰るのに交通渋滞にはまって多大な時間を要したと聞く。予想はしていたが、こればかりはどうしようもない。

ブッド・インターナショナル・サーキット遠景
パドックへ通じる道、奥にメイングランドスタンドが見える
初のF1インドGPは成功に終わったと言っていいだろう。初日のプラクティス中にサーキット内に犬が入って来てしまっていきなりレッドフラッグが出されたことや、これまた初日にF1イベントの一環(アフターパーティー)としてグルガーオンで開催予定だったメタリカのコンサートが延期の後に中止になったことなど、全体としては完璧とは言えない運営ではあったが、最終日に限って言えば、客入りも上々であり(発表では9万人)、国際スポーツイベントとして胸を張っていいレベルの出来だった。最終日には米国の人気ポップシンガー、レディー・ガガによるアフターパーティー・コンサートもあり、盛り上がったようだ(チケット代4万ルピー、キャパシティーは1,000人のみ、ボリウッド男優アルジュン・ラームパールが仕掛け人)。よくCWGと比較する論調があるのだが、F1とCWGは運営の形態からスポーツの特徴まで全く別であり、どちらがどうだとは言えないだろう。また、CWGが失敗扱いされているのにも疑問を感じる。確かに開催までには多くの問題が発生したが、開催期間中に大きなトラブルは発生しなかった。むしろ僕の目には成功に見えたぐらいだ。
今回のF1インドGPの、インド・スポーツ界における大きな意義は、民間の国際スポーツ・イベントが成功したことである。インドのスポーツは必ず政府の委員会が管理者として関与しており、政治色が強くなる。CWGの運営委員会のトップも政治家であったし、国民的人気を誇るクリケットですら政治家のコントロール下にある。しかし、モータースポーツは例外的に政府管轄の外にある関係で、このF1インドGPは、民間企業ジェーピー・スポーツ・インターナショナル(PSI)のサミール・ガウル取締役社長が、民間団体インドモータースポーツクラブ連盟(FMSCI)の協力を受けながら、ほぼ単独で主催したイベントであった。ウッタル・プラデーシュ州政府は用地接収など基礎的な部分でしか関わっていない。レース後にマーヤーワティー州首相が登場し、ベッテルに優勝杯を渡していたが、テレビカメラがマーヤーワティーをほとんど映していなかったのは象徴的であった。
しかし、今後に向けた課題も多い。サーキットの維持・管理は最重要課題だ。インド人は一般に、造るべきものは何とか造るが、それを維持・管理することは非常に苦手だ。ブッド・インターナショナル・サーキットが来年どんな姿になっているか、心配である。コンスタントに使い道があればいいのだが、年に1回しか使わないとかなってしまうと大変だろう。サーキットは周辺の農村と直結しているので、最悪の場合、いつの間にか家畜の放牧場になっていたとか、そういう事態も予想される。
今回は初のF1インドGPとのことで何とか集客できたが、2回目以降は初物への関心を刺激する手段が使えず、集客はさらに困難となるだろう。そのときまでに一般のインド人にモータースポーツへの関心をいかに喚起できるかが、2回目以降の成否を分けるだろう。チケットの料金設定にももう少し工夫が必要だと感じた。安い席をもっと増やせばそれなりに観客は集まるのではないかと思うし、金土日3日間通しのチケットというのも見直す必要があるだろう。普通の人は金曜日には来られない。また、どうせならいろいろな位置や角度から観戦してみたいため、そういう見方ができるチケットも欲しいものだ。
デリーからサーキットが遠すぎることも不満だ。サーキットまでデリー・メトロが延伸してくれれば楽なのだが、数年内にそれが実現する見込みはない。今のままだと自家用車でサーキットへ行くのが唯一の現実的なアクセス手段であるし、そうである限りはサーキットまでの道の渋滞問題は起こり続けるだろう。
もしかしたらモトGPもこのブッド・インターナショナル・サーキットで開催されるかもしれない。どちらかと言うと四輪車のレースよりも二輪車のレースに興味があるので、モトGPインドも近い内に実現してくれたらと思う。そのときは再びこのサーキットを訪れるだろう。他にも、プラガティ・マイダーンに代わるオート・エキスポの開催地、ドライビング・アカデミーの創設、映画ロケ地としての売り込みなど、様々なプロジェクトが持ち上がっており、今後このサーキットから面白い動きが見られそうである。
最後にカタカナ表記に関する注記。Buddh International Circuitは日本語のメディアを見る限り「ブッダ・インターナショナル・サーキット」と書かれていることが多いが、英語表記に従い、ブッド・インターナショナル・サーキットとした。これはもちろん仏教の開祖である仏陀から取られているが、その前にサーキットが立地しているのがガウタム・ブッド・ナガル(Gautam Budh
Nagar)県であるためにそう命名されたのであろう。また、HRTのインド人ドライバーNarain Karthikeyanは、日本語では一般に「ナレイン・カーティケヤン」などと表記されているが、現地語に従うとナーラーヤン・カールティケーヤンがもっとも正しい。ここでもそう表記した。ちなみに、本文中には登場しないが、2人目のインド人F1ドライバーで今年チーム・ロータスの予備ドライバーを務めているKarun
Chandhokはカルン・チャンドークが正しい。カルンはFMSCIのヴィッキー・チャンドーク会長の息子である。他の固有名詞は一般的な表記に合わせたつもりである。



