| ◆ |
10月5日(水) 救世主はボージプリー映画 |
◆ |
僕が愛読しているブログ、ヒンズー語ではありません。の6月の日記に、ボージプリー映画についての記述があった。そのときは「ホントかいな」という思いで読んでいたのだが、アウトルック10月3日号にも同じようなボージプリー映画の隆盛に関する記事があり、インドの映画界でボージプリー映画が急速に見逃せない存在になって来ていることを感じた。僕はボリウッド映画以外のインド映画には疎いのだが、ボージプリー映画はヒンディー語映画と完全に切り離して考えることができず、取り上げて行かなければ潮流に乗り遅れてしまうと思い、ここで急いでボージプリー映画の紹介を行おうと思った。
まず、ボージプリーについて説明しなければなるまい。ボージプリーとは、ビハール州やウッタル・プラデーシュ州東部で話されている言語で、一般にはヒンディー語の方言に位置付けられている。1991年の国勢調査によると、インド国内でのボージプリー方言の話者は2310万2050人。当時のヒンディー語全体の話者人口が3億3727万2114人なので、統計上はヒンディー語話者の内、約7%がボージプリー方言話者ということになる。だが、ビハール州(人口約8千万人)で話されているマイティリー方言やマガヒー方言などの他の方言も、ボージプリー方言と非常に近い関係にあることを見逃してはならない。また、ネパールの人口の約7.5%に当たる137万9717人(1991年国勢調査)もボージプリー話者である。ビハール州は経済的に後進州であるため、他州の都市へ出稼ぎに出る人が多い。そのおかげで、ボージプリー話者はムンバイーに400万人、パンジャーブ州に180万人、デリーに80万人いるという。その他、コールカーターなどのベンガル地方にもボージプリー話者は多く居住している(人口の統計はなし)。さらに見逃せないのは、モーリシャス、フィジー、トリニダード・トバゴなどの国々にもボージプリー話者が多く住んでいることだ。奴隷制廃止後、英国はインドから「契約労働者」という形で安価な労働力をそれらの植民地のサトウキビ・プランテーションへ送り込んだ。契約労働者となったインド人の多くは、サトウキビ栽培の技術があり、しかも貧困地帯であったボージプリー地方の人々だった。現在、モーリシャスではボージプリー方言は公用語のひとつになっており、フィジーの公用語のひとつとなっているヒンディー語も実はボージプリー方言である。これらを考慮に入れ、世界中のボージプリー話者人口を多めに推定すると、1億2500万人に達するという。日本の人口とほぼ同数である。
文学の世界でも、ボージプリー方言は一応独自の地位を築いている。ヒンディー文学の亜流という形でボージプリー文学が確立しているし、ボージプリー方言の詩も愛好者が多い。そんな流れの中、ボージプリー方言による映画制作も近年精力的に行われるようになり、それが思いのほかヒットしているという。
ボージプリー映画の制作は昔から行われており、1961年の「Ganga Maiya Tohe Piyari Chadhaibo(ガンガー女神、お前に愛を捧げよう)」や、1970年代の「Balam
Pardesia(異国の愛人)」などが大ヒットを記録しているが、アップダウンが激しく、長らく低迷していた。だが、昨年公開されたマノージ・ティワーリーの「Sasura
Bada Paisewala(義父は大したお金持ち)」がビハール州とウッタル・プラデーシュ州東部で2000万ルピーの興行収入を上げる大ヒットを記録。続いて公開された「Daroga
Babu I Love You(お巡りさん、愛してる)」も大ヒット。こうしてボージプリー映画の黄金期が突然にして始まった。最近では、「Panditji
Batai Na Biyah Kab Hoi(坊さん、結婚はいつか教えておくんなせぇ)」という予算600万ルピーのボージプリー映画が、パトナーで50日以上のロングランを記録し、ボリウッドの今年最大のヒット作「Bunty
Aur Bubli」(2005年)の4倍以上の興行収入を上げた。また、同じくボージプリー映画「Bandhan Toote Na(関係が壊れないように)」は、ムンバイーにおいて100日のロングランを達成した。ここのところ毎年16本ほどのボージプリー映画が公開されているが、そのヒット率は98%。ボリウッド映画のヒット率が10〜12%であることを考え合わせると、脅威のヒット率である。また、平均公開週数も、ヒンディー語映画が3週前後であるのに対し、ボージプリー映画は6〜8週間だという。
ボージプリー映画の成功の裏には、比較的巨大で、かつ堅固なボージプリー話者層の市場があることは間違いない。前述の通り、ボージプリー方言を話す人々はインド各地や海外の国々にまで広がっている。よって、ボージプリー映画の支持層も同じだけの広がりを持つことは必然である。ボージプリー映画はもはやボージプル地方を越え、インド全土に、そして世界に羽ばたいている。インド国内で言えば、ジャンムー、カシュミール、ジャーランダル、ルディヤーナー、パーニーパト、クルクシェートラ、ノイダ、グルガーオンなど、ビハール州からの労働者が多数居住している地域で支持を集めているという。特にデリーのバダルプルやムンバイーのターネーなどの工業地域で受けがいい。また、フィジー、モーリシャス、西インド諸島などのインド系移民たちにも受け容れられている。
これら一連のボージプリー映画の成功を受け、ボリウッドの大手制作会社や大御所たちもボージプリー映画の制作に乗り出している。往年の名優ディリープ・クマールは、ボージプリー映画界のトップスター、ラヴィ・キシャン主演の映画を制作中で、アミターブ・バッチャンとヘーマー・マーリニーはボージプリー映画「Ganga」に出演する予定だ。アジャイ・デーヴガン、ジューヒー・チャーウラー、ナグマーは既にボージプリー映画にゲスト出演をしている。コレオグラファーのサロージ・カーンはボージプリー映画「Dil
Diwana Tohar Ho Gayi(心はあなたの虜)」を監督しており、プレイバック・シンガーのウディト・ナーラーヤンは、「Kab Hoi
Gauna Hamar(私の嫁入りはいつ?)」を監督している。ボニー・カプールは「Matribhoomi」をプロデュースし、高い評価を得たし、スバーシュ・ガイーもボージプリー映画の制作を検討中である。
ボージプリー映画の隆盛により、おそらく一番の恩恵を被っているのは、都市部の場末の映画館だろう。近年、インドでは都市部を中心に大規模なシネコンが乱立しており、小さな映画館は観客の減少に悩まされ、経営難により潰れてしまう映画館も少なくなかった。だが、それらの弱小映画館たちは、ボージプリー映画という武器を新たに手に入れた。ボージプリー映画はほとんどの場合シネコンで上映されない上、ビハール人を中心としたまとまった数の観客を見込めるドル箱コンテンツとなっている。また、ボージプリー映画はボリウッドで成功できなかった俳優たちに新たな活躍の場を提供している。リシター・バットやプリーティ・ジャンギヤーニーなど、あまりボリウッドで売れなかった女優たちは今、ボージプリー映画界で活躍しているらしい。
僕はボージプリー映画をまだ1本も見たことがないから、あまり大そうなことは言えないのだが、ボージプリー映画にはおそらく言語の他にももっと特定の地域に訴えかけるローカル性が存在しているはずだ。ボリウッド映画は多くの場合、ビハールの人々を差別的に扱っている。たまにビハール州が舞台になっても、その描写の仕方は、ビハール州の後進性をさらけ出すようなものがほとんどだ。かつて「Lajja」(2001年)という映画が公開されたとき、僕のビハール人の友人たちが、「オレたちのビハールを舞台にした映画だ!」と喜んでいたような記憶がある。この映画は全然ヒットしなかったのだが、ビハール州ではまあまあの成功を収めたと聞いている。だが、残念ながら「Lajja」の主題は、ビハール州における女性問題であり、ビハール人の自尊心を満足させるようなものではなかった。今年公開された優良コメディー映画「Ramji
Londonwaley」の序盤もビハール州が舞台であったが、やはりネガティヴな視点がチラホラと見え隠れした。ボージプリー映画は、そんなビハーリーたちの鬱憤を解消し、ビハーリー・ナショナリズムを高揚させる何かがあるはずだ。そうでなければ、ここまでヒットするとは思えない。そういう意味で、ヒンディー語映画内でのボリウッド映画とボージプリー映画の関係は、インド映画内でのヒンディー語映画とタミル語映画の関係に似ているかもしれない。ボージプリー映画の配給会社を経営するサンジャイ・メヘター氏は、ボージプリー映画の隆盛を「映画のラールー化」と呼んでいる。ラールーとは、ビハール州(のみ)で圧倒的なカリスマを誇るラールー・プラサード・ヤーダヴ鉄道大臣のことである。言いえて妙、だ。
映画がこのまま果たしてラールー化していくのかどうかは分からない。一時的な流行に終わるかもしれないし、ボリウッドの新たな潮流と位置付けなければいけない時代が近い内に来るかもしれない。だが、個人的には、場末の映画館の活路が見つかったことが嬉しい。僕はすっかりシネコン利用者だが、場末の映画館の盛り上がりを一応愛している人間である。「これこそ映画だ!」僕がかつて「ムトゥ 踊るマハラジャ」を渋谷のシネマライズの満員の映画館で見たときの震えるほどの感動を、ここインドではそういう場末の映画館へ行くことで簡単に味わうことができる(毎回それを味わってると真剣に映画を見れずに映画評が書けなくなるので遠慮している・・・)。だから、場末の映画館がどんどん潰れ、インドの映画館が全部きれいなシネコンになってしまったら、非常に悲しいと思っていた。ボージプリー映画は娯楽の王様を娯楽の王様たらしめる救世主なのかもしれない。
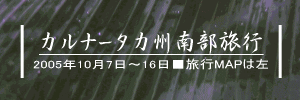
デリー大学(DU)では、インド三大祭のひとつダシャヘラーのある10月に2週間ほどの休みがあるのだが、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)にはそのような休みはない。ただダシャヘラーが休日となるだけだ。しかし、この時期は教授も学生もお祭り気分になってあまり正常に授業が行われないので、勝手に休みを取って旅行へ行くことにした。今回の目的地はバンガロール。10月8日にバンガロールで開催が予定されているARレヘマーンのコンサートが第一の目的で、そのついでに南インドを旅行しようと計画した。また、現在バンガロールにはいつの間にか多くの知人・友人がたくさんおり、今回の旅行は彼らを訪ねるというプライベートな目的もあった。
移動手段は飛行機。毎回愛用しているジェット・エアウェイズを今回も利用した。最近インドではエアー・デカン、スパイス・ジェット、キングフィッシャー・エアラインスなどの格安航空会社が続々と誕生し、航空運賃の価格破壊が進んでいる・・・イメージがあったのだが、航空運賃を調べてみたら、結局ジェット・エアウェイズの航空券を1ヶ月以上前に買う方が安かった。格安航空会社の飛行機は、早朝や深夜など、利用価値が低い便なら安いのだが、ちょうどいい時間に出ている便は高かった。
デリー発バンガロール行きの9W811は、午後5時35分離陸予定だった。ところが何らかの障害により、離陸は30分以上遅れた。バンガロールまでのフライトは2時間15分ほど。午後9時頃にバンガロールの空港に到着した。
バンガロールでは友人の家に泊めてもらったので、宿の心配はなかった。バンガロール訪問はこれで2回目になる。前回の滞在で主な観光地は見てしまっているので、市内に特に見たいものはなかった。バンガロールはデリーよりも空気が悪く、道路も狭く、過ごしにくそうな印象を受けた。ただ、気候はバンガロールの方が穏やかで、デリーの「夏暑く冬寒い」というどうしようもない気候とは比べるべくもない。
今回の旅行の目的は、上に述べた通りARレヘマーン・ライヴと知人訪問だが、その他に2つのサブミッションを用意していた。1つ目のキーワードは、「アガスティアの葉」、もう1つのキーワードは「僕だけのアイシュワリヤー」である。アガスティアの葉とは、知る人ぞ知る、人の過去、現在、未来が書かれた葉っぱのことだ。タミル・ナードゥ州カーンチープラムのアガスティアの葉が最も有名だが、偶然出会ったアガスティアの葉の研究者の方の話では、他にもっといい場所があるということなので(詳細は企業秘密)、そこで自分の運命を占ってみようと考えていた。もうひとつのサブミッションは、カルナータカ州マンガロールを中心に居住するバント族を訪ねる旅である。バント族は「インドの女神」「世界で最も美しい女性」の名をほしいままにするアイシュワリヤー・ラーイを輩出した部族であり、美男美女で知られているらしい。そこで「僕だけのアイシュワリヤー」を探そうという、全く下心丸出しのしょうもないサブミッションである。
ところで、今回の旅行ではひとつ問題が発生した。2年ほど前から愛用していたキャノンのデジカメ、IXYデジタル30の調子がおかしくなったことだ。先月25日のアルワル・ツーリングからカメラの様子が変だったのだが、ここに来て完全に故障してしまったことが発覚した。原因が全く分からなかったのだが、ちょうどタイムリーにキャノンのウェブサイトに、「デジタルビデオカメラ/デジタルカメラをご使用のお客さまへ」と題した告知が10月6日に掲載された。
平素はキヤノン製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
弊社製デジタルビデオカメラおよびデジタルカメラ製品において、製品に搭載されたCCDの一部に不具合があり、撮影画像が乱れる、映らない等の現象が発生する場合があることが判明致しました。つきましては、その内容と対応についてご案内申し上げます。対象製品(FV40, FV50, FV300, FV400, IXY DV3, IXY DV5, PowerShot A60, PowerShot A70,
PowerShot A75, PowerShot A300, PowerShot A310, IXY DIGITAL 320, IXY DIGITAL 30, IXY DIGITAL 30a)をご使用のお客さまには、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことを謹んでお詫び申し上げます。今後は、お客さまに安心してご使用いただけますよう更なる品質管理の徹底をして参りますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
対象製品を、とりわけ高温多湿環境下で保管、あるいは使用した場合、製品に搭載されたCCD内部の配線接合箇所が外れる場合があることが確認されました。この場合、撮影モード時にCCDからの信号が正常に出力されなくなるため、
撮影画像が「乱れる」、「映らない」等の現象が発生します。なお、これらの現象は撮影時に対象製品の液晶モニターの画面で確認することが出来ます。また、記録された画像にも同様の現象が発生します。
本現象が発生した対象製品につきましては、CCD内部の配線接合箇所の外れが確認された場合は弊社規定の保証期間を過ぎておりましても、無償にて修理させていただきます。なお、この不具合についての修理は11月上旬より開始する予定で準備を進めております。修理の開始時期やその他詳細につきましては、改めてご案内致します。ご不明な点につきましては、下記のデジタルビデオカメラ/デジタルカメラコールセンターまでご連絡ください。
ここに記載されている現象は、僕の持っているカメラに起こっている現象と酷似していた。確かにアルワルに行ったとき、炎天下の中でカメラを使用していたし、その後から液晶モニターに映る画像や撮影画像がおかしくなった。多分これが原因だろう。だが、あまりにタイムリー過ぎないだろうか?キャノンの誰かが僕のウェブサイトを見ていて、僕のカメラが故障したという記述を見つけて、今まで隠し通していた製品の不具合の発表に踏み切ったのではなかろうか?そんな勝手なことを考えてしまうほどだった。でもそうだとしたら、ここでキャノン関係者に告げるしかない――ちゃんと海外在住ユーザーに対してもきめ細かな対応をしてくれるんだろうなっ!デジカメの故障はそのまま「これでインディア」存続の危機につながってしまうぞっ!というわけで、以下に掲載されている写真の中には、いくつか画像が乱れているものがある。
アッラー・ラカー・レヘマーン(ARレヘマーン)と言えば、インド映画界最高の音楽監督であると同時に、英国ミュージカル「Bombey Dreams」や「Lord
of the Rings」の作曲をしたり、中国映画「天地英雄」の音楽を担当したりして、今や世界的なミュージシャンの1人としてその名を知られるようになって来ている人物である。ARレヘマーンは、ボリウッドでは最近「Mangal
Pandey - The Rising」(2005年)の音楽を担当している。僕もインド映画ファンである以上、ARレヘマーンの存在は無視できないし、何を隠そう彼のファンである。
現在レヘマーンは世界ツアー中で、今回インドではバンガロールのみで公演を行う。ARレヘマーン・ファンクラブ日本支部長の矢萩多聞氏がチケットを手配してくれるというので、僕も参加を決めた。多聞氏は世界を飛び回ってレヘマーンの追っかけをしているが、僕がARレヘマーンのコンサートへ行くのはこれが初めてだ。参加を決めた時点でチケットの値段はまだ公開されていなかった。デリーでも何度かミュージシャンのコンサートに参加したことがあり、そのときの経験からおそらく高くても2000ルピーくらいだろうと考えていた。ところが発表された料金体系を見てビックリ。安い方から、スタンディング席が499ルピー、999ルピー、シート席が1499ルピー、2999ルピー、5999ルピー、9999ルピーであった。多聞氏が手配してくれたチケットは当然のことながら最前列VVIP席の9999ルピー・・・。た、高い!はっきり言ってデリー〜バンガロール往復航空券よりも高い。だが、一生に一度のことかもしれないので、9999ルピーを払って最前列でレヘマーン・ライヴを鑑賞することにした。
ところが問題が発生した。昨日、飛行機に乗っているときから腹がギュルル・・・と鳴ったと思ったら、今日、下痢になってしまった。何がいけなかったのか・・・機内食の何かが当たったのだろうか?朝から下痢との過酷なゲリラ戦を繰り広げ、何とか停戦条約に関する会談ぐらいにまではこぎつけたが、午後になってもまだ各地で散発的な交戦が続いていた。ライヴ会場にトイレはあるだろうか・・・あるとは思うが、ちゃんとVVIP専用のトイレとかあるのだろうか・・・そんな不安を抱えてのライヴ参加になってしまった。
会場はパレス・グランドという野外広場。開場予定時刻は午後4時半、開始予定時刻は午後7時。会場で多聞氏と合流し、チケットを受け取って開場を待った。多聞氏の呼びかけで、多聞氏や僕を含む総勢8人の日本人レヘマーン・ファンが集まっていた。バンガロール在住の人、インドの他の都市在住の人、日本から遥々やって来た人など、そのバックグラウンドは様々である。多聞氏が特製レヘマーンTシャツを作成してくれていたため、みんなお揃いのコスチュームでライヴに臨むことになった。多聞氏からいただいた薬(ヒマーラヤ製薬のDialex)のおかげか、何とか腹の状態は持ち直した。多聞氏にはお世話になりっぱなしである。
インドでは普通のことだが、4時半になってもなかなか中に入れてもらえなかった。ステージでは未だに作業が行われていた。5時頃になってやっと中に入れてもらえた。チケットにはカメラ持ち込み禁止と書かれていたが、何の身体検査も持ち物検査もなかったため、簡単に持ち込むことができた。デリーではありえないことだ。最前列の席と聞いていたのだが、最前列には「レヘマーンの家族用」という豪華な椅子が2列並んでおり、その後ろからVVIP席が始まっていた。仕方なく前から3列目の席に陣取って、ライヴが始まるのを待った。
ところが時間が経つごとに次第に雲行きが怪しくなって行き、午後6時頃には雨がパラパラと降り始めてしまった。北インドはもうモンスーンは終わっているのだが、南インドはまだモンスーンの真っ最中のようだ。この時期、夕方になるとよく雨が降るらしい。そもそもそんな時期に野外コンサートを行うこと自体が間違っていたのだが、残念ながら今日も雨が降り出してしまった。傘があったので、しばらくは雨が止むのを待っていたが、雨はなかなか降り止まなかった。ふと後ろを見ると、インド人たちは椅子を頭の上に乗せて傘代わりにしていた。中にはそこら辺にくくりつけてあった看板を取り外して頭上に乗せて傘にしている集団もいた。そのユニークな工夫にはただただ脱帽だった。そこにあるもので何とかする、この精神がインド文化の根幹を形成していると僕は見ている。まだこの頃は、「この雨は『Lagaan』(2001年)の『Ghanan Ghanan』の余興か!?」と冗談を飛ばすだけの余裕があった。

椅子を傘にする人々
ところが午後6時半頃になると、雨は豪雨へと変貌して行った。ステージの裏に立っていたスクリーンが強風によって倒れるなど、舞台設備はどんどん破壊されて行った。一体コンサートは決行なのか、中止なのか?早く決断を下して欲しいと思っていたらアナウンスがあった。設備が壊れてしまったので、今回のライヴの売りだった「3Dライヴ」は不可能となったが、それでもライヴをする、というものだった。そして何を思ったのか、突然誰かが変な歌を歌いだした。神様への救いを求めるような内容の歌だと聴き取ったが、その歌が始まった途端、豪雨はさらに嵐へと変貌し、もはや会場はライヴどころではない状態と化していた。足元を見ると既に冠水しており、河のような流れが出来ているほどだった。このままここに留まっていたら、風邪を引くのは必至だし、その前に濁流に押し流されてしまう!ステージも滅茶苦茶だし、もうこれは今日のライヴは中止だろう!そう考えた我々は、一度会場を脱出することを決意した。幸い、バンガロール在住の多聞氏の自宅がパレス・グランドからすぐ近くだったため、多聞氏の家へ行って待機することにした。
家に着いた我々は、多聞氏から服を借りて着替え、暖を取った。まさかこんなことになるとは・・・とりあえず軽食をいただきながら、我々は今後の展開を話し合った。僕はこのまま延期になった方が好ましいと思っていたのだが、わざわざこのライヴを見るためだけに日本から短い休みを取って来ている人もおり、その人たちにしたらこのまま延期となるのは虚しすぎた。また、延期になると会場の使用料金が必要となるため、主催者側は意地でもライブを決行する可能性が高かった。そこで多聞氏がライヴ関係者の知り合いに電話で確認したところ、午後9時から再開されるという情報を得た。あんな状態で本当にライブを決行できるのか?そんな疑問を抱きつつも、とりあえず9時過ぎにもう一度会場へ行ってどうなっているか確認してみることになった。
9時にはもう雨は上がっていた。オートリクシャーでパレス・グランドまで向かうと、何となく音楽らしきものが聞こえてくる。ステージにはライトも灯っている。ライヴは決行されていた!我々は急いで会場に入った。ところが、そこで我々を待っていたのは、カオスという名の悪夢であった。
まず、入り口にチケットを確認する人がいなかった。よって、チケットを持っていない人でも簡単に中に入れてしまうし、本当は9999ルピーを払わなければ辿り着くことができない最前列にも誰でも侵入可能だった。それでいて、最前列の中央部は極端に厳しく立ち入りが制限されており、VVIPチケットを見せても全く中に入れてもらえなかった。ライブが始まる前まではVVIP席は空席だらけだったのに、今では満席になっている。絶対におかしい!VVIPチケットを持っていない人までVVIP席にいるはずだ!そもそも最前列の両サイドは押し合いへし合いの大混雑となっていた。この混乱の中を通り抜けてVVIP席へ行くことは困難だった。大量の警察官が警備のために動員されていたが、彼らの大半はライヴを楽しむのに余念がなく、治安維持にはほとんど貢献していなかった。記念撮影をしている警察官までいたのには呆れた・・・。
とにかくこの大混乱状態の中を通り抜けて最前列まで辿り着くことは不可能だったので、一旦戻って対策を考えてみた。見ると、楽屋裏に通じる道がステージの脇にあり、そこは全く警備がなされていなかった。そこを通って行ったら、簡単にステージ脇のすぐ下に出ることができた。しばらくそこでライヴを鑑賞した後、どさくさに紛れてステージの真ん前の真下に出ることができた。こうして紆余曲折があったものの、当初の予定通り最前列でライヴを見ることが可能となった。

ライヴの様子
今回のライヴには、ARレヘマーンの他、ハリハラン、シャンカル・マハーデーヴァン、シヴァマニ、スクヴィンダル・スィン、アルカー・ヤーグニクなどなど、インド映画音楽界で活躍しているアーティストたちが多数参加していた。ARレヘマーン自身も時々前に出てきて歌を歌っていた。バンガロールでの公演ということでタミル語の曲が中心かと思ったが、意外とヒンディー語の曲も多く演奏してくれた。僕が特定できたヒンディー語の曲で覚えているものは以下の通り。
●Aazadi "Bose : The Forgotten Hero"
●Maa Tujhe Salaam "Vande Mataram"
●Chaiyya Chaiyya "Dil Se"
●Ghanan Ghanan "Lagaan"
●Chale Chalo "Lagaan"
●Chinnamma Chilakkamma "Meenaxi : The Tales of 3 Cities"
●Taal Se Taal Mila "Taal"
●Ishq Bina Ishq Bina "Taal"
●Pagdi Sambhal Jatta "The Legend of Bhagat Singh"
●Kabhi Neem Neem "Yuva"
「Ghanan Ghanan」では、シャンカル・マハーデーヴァンが「黒い雲よ、雨を降らしておくれ」という歌詞を、「黒い雲よ、雨を降らさないでおくれ」と変えて歌っていたのが面白かった。スクヴィンダル・スィンが歌う「Chaiyya
Chaiyya」は相当盛り上がっており、タミル語ヴァージョンの「Taiya Taiya」の歌詞も混ぜて歌われていた。「Taal Se Taal
Mila」はミュージカル「Bombey Dreams」のヴァージョンとオリジナル・ヴァージョンのミックスとなっており、白人の歌手が英語版を歌っていた。この他、「Mangal
Pandey」の曲も序盤に演奏したみたいだが、聞き逃してしまった。「マンガル・マンガル・マンガル・マンガル・・・」というあの感動的な曲を生で聴いてみたかったのだが・・・!
トリの曲は「Aazadi〜Maa Tujhe Salaam」のメドレーだった。ところがこのとき観客のボルテージは最高潮に達し、後ろの席にいた人々まで前の方に出てきてしまった。しかも、この曲まではかろうじて雨が降っていなかったのだが、この曲が始まったと思ったら突如大雨が降り始めた。5m先が見えないくらいの本日最大のビッグ・スコールであった。もはや会場に秩序はなかった。人々はびしょ濡れになりながら「ヴァンデー・マータラム!」を連呼し、警察はやっと思い出したかのように治安と秩序の維持に乗り出し始めた。もう帰り支度を始める観客もいて、彼らが無理に出口に向かおうとするので、混乱は混乱を呼び、大混乱の大カオス状態となっていた。最初から最後まで、このライヴは混乱に次ぐ混乱だった。僕は最後に叫んだ・・・一体この国は何年インドをやってれば気が済むんだ!
昨夜は着て行った服がずぶ濡れになってしまい、多聞さんに貸してもらった服まで再度ずぶ濡れになってしまったので、今日は外出時に着る服がなくなってしまった。上に着る服は何着か持って来たので一応あるのだが、ズボンを1着しか持って来ていなかった。一応寝巻き用のパージャーマーがあるからそれを着ればいいのだが、もっと大きな問題は、靴がずぶ濡れになって、しかも乾かすのを忘れてしまったため、外に出るための履物がないことだった。よって、今日は服を洗濯して、乾くのを待っていた。
一方、多聞氏たちはARレヘマーンに会うために奔走していた。昨夜ライヴが終わった後にレヘマーンに会おうと楽屋へ行ったのだが、豪雨の上に警備員が厳しくて、レヘマーンに会うことは不可能に近かった。唯一、ドラマーのシヴァマニだけは至近距離で見ることができたが、それも一瞬のことだった。多聞氏はレヘマーンがメレディアン・ホテルに宿泊しているという情報を入手し、楽屋裏で会うことを諦めて直接ホテルへ行くことを決めた。だが、折からの大雨のせいでバンガロールの道路は水没しており、非常に危険な状態となっていた。僕はもう帰ってしまったのだが、多聞氏は単身メレディアン・ホテルへ行き、レヘマーンは明日(9日)にもまだバンガロールにいるという情報を得た。どうやらイスラーム教徒のレヘマーンは、6日から始まったラムザーン(断食月)の断食のせいで体調が悪いようだった。そこで多聞氏は、日を改めて9日にレヘマーンに会いに行くことを決めた。僕も誘われたのだが、メレディアン・ホテルのような高級ホテルにサンダル履きで行くわけにもいかず、また、あいにく夕方からバンガロールに駐在している知り合いの日本人たちと会食する予定があったため、レヘマーンに会いに行くのはキャンセルした。多聞氏たちは午後3時からずっと待って、数時間後にやっとレヘマーンやハリハランに会うことができたようだ。後で写真を見せてもらったが、レヘマーンの顔色はかなり悪かった。断食中にあの雨の中コンサートをするのは、さすがのレヘマーンと言えどこたえたようだ。
今日はまず、明日からの小旅行の準備のため、マジェスティックにあるセントラル・バススタンドへ行った。間違いなくインドでも一、二を争うほどシステマティックに機能している長距離バススタンドである。ここで明日の夜10時半発の夜行バスのチケットを購入した(375ルピー)。カルナータカ州陸上交通局(KSRTC)のラクジュアリー・バスである。昔ダラムシャーラーからデリーへ帰ったとき、全然デラックスじゃないデラックス・バスに乗って酷い目に遭ったことがあるが、今回はデラックス・バスよりも上のランクのラクジュアリー・バスがあるのをちゃんと確認し、購入した。
その後、RTナガルの多聞氏の家にお邪魔させてもらい、近所のアーンドラ料理レストランに連れて行ってもらって昼食を食べた。南インドに来るにあたって、僕はどうしてもミールスを食べたかった。北インドにも南インド料理レストランはあるが、バナナの葉っぱを皿にした本格的なミールスを食べることは非常に難しい。北インドの南インド料理レストランでは、大体ターリー(大皿)に乗って食事が出て来るし、プーリーが付くのも邪道のように思う。とにかく「バナナの葉っぱの上に出て来るミールスが食べたい!」と要望した。
多聞氏に連れて行ってもらったのは、RTナガルの郵便局近くにあるマードゥリー・レストラン。いかにも安食堂といった雰囲気のレストランであり、バナナの葉っぱのミールスが25ルピーで食べられる。品目名など、あまり細かいことは覚えていないが、南インド歴の長い多聞氏の指導とアドバイスを受けながらのミールスは格別にうまかった!ちなみに、現在バンガロールで一番おいしいアーンドラ料理レストランは、ビーマスというところらしい。

ミールス
多聞氏と別れた後は、バンガロール随一の繁華街、ブリゲイド・ロードへ行ってみた。2002年にバンガロールを訪れたとき、ここでモヒカン頭のインド人を見かけて驚いた覚えがある。デリーでも未だにモヒカン頭のインド人を見かけたことがないから、あれは相当レアな体験だったのではないかと思う。今回は残念ながらモヒカンを見つけることができなかったが、背中に下手な漢字で「愛」というタトゥーをしたインド人女性を見かけて満足した。どうも最近、インドの都市部を中心に漢字でタトゥーを入れるのが流行しているようだが、所詮書道はおろか漢字のことをよく知らない人が彫るので、漢字圏の人間から見たら憐憫の情が沸いてしまう程度のものでしかない。ブリゲイド・ロードは昔来たときよりも微妙に発展していたぐらいか。どうやらバンガロールのショッピングとオシャレの中心は、郊外に乱立するモールへと移行しつつあるようだ。特にコラマンガラが今一番ホットみたいだ。ブリゲイド・ロードのプラネットMで、多聞氏から勧められたARレヘマーン作曲のタミル語映画のCDを数枚購入した。

ブリゲイド・ロード
夕方からは、居候先の友人の友人、ニシャーント・シェッティー君と会った。ニシャーント君はマンガロール出身で、カンナダ人とバント族のハーフである。これからマンガロールへ行くので、彼にマンガロールの情報をいろいろ教えてもらおうと思っていた。最大の関心は、バント族とどうやったら効果的に会えるか、ということだった。今回の旅の目的のひとつは、「僕だけのアイシュワリヤー・ラーイを探す」という全くしょうもないものである。あまり知られていないが、「インドの女神」の称号をほしいままにするアイシュワリヤーはマンガロール出身であり、トゥル語を話す少数部族、バント族に属している。バント族は男性も女性も美形で知られており、ある情報筋によると、「ベンガル人女性の美人率を5人に1人だとしたら、バント族は5人に5人が美人」、つまり100%の美人率を誇る美族らしい。これは探求の価値のある部族である。ニシャーント君にとりあえず「アイシュワリヤー・ラーイの生家はどこか知ってるか?」と聞いたら、「知らない。アイシュワリヤーに会いたかったらムンバイーに行った方がいい」とそっけない返事。ニシャーント君によると、マンガロールの人々はあまりボリウッドに関心がなく、アイシュワリヤーのこともあまり知らないらしい。だが、ニシャーント君はなかなかハンサムで、バント族が美男美女ばかりだという噂は俄然信憑性を帯びてきた。ニシャーント君の実家の住所を教えてもらったため、とりあえずそこを訪れることにした。
今日はバンガロールの見所を簡単に見て回った。まず行ったのは博物館。前回バンガロールを訪れたときに見たかどうか忘れていたが、到着してみると前に来ていたことを思い出した。それでも入館料が4ルピーと安かったので、中を見てみることにした。1階は石像、2階は絵画が中心である。個人的には目を引く展示物はなかった。
次に行ったのはティープー・スルターン宮殿。マイソール王国のスルターンの夏の離宮で、1791年に完成した。同王国の首都はバンガロールとマイソールの中間点にあるシュリーランガパトナムであり、夏の間だけスルターンはこの宮殿で過ごした。木造2階建ての建築物で、ディーワーネ・アームとディーワーネ・カースが建物の表裏にある。元々壁面には繊細な模様が施されていたようだが、損傷が激しかったためにインド政府により色気のない色のペンキで塗りたくられてしまったようだ。ただ、一部だけに昔の模様を見ることができる。入場料はインド人5ルピー、外国人100ルピー。

ティープー・スルターン宮殿
バンガロールの観光地を観光するのには飽きてしまったので、繁華街をぶらつくことにした。ティープー・スルターン宮殿を見て、シティー・マーケットの喧騒をちょっと見た後は、名前を見てちょっと気になっていたコマーシャル・ストリートへ向かった。コマーシャル・ストリートはブリゲイド・ロードのすぐ北にある繁華街で、やや中流層向けの中級マーケットという感じだ。ここでファブインディアを見つけたので入ってみた。ファブインディアは元々ジョン・ビッセルという米国人が1960年にインドから海外へ織物を輸出するために設立した会社だが、1975年からインド国内向けの衣料品店へ方針を転換し、デリーのグレーター・カイラーシュに第1号店がオープンした。僕は今までファブインディアをデリーのスペシャリティーだと考えていたのだが、どうやらいつの間にやら大規模なチェーン展開が行われていたようで、ムンバイー、チェンナイ、コールカーター、ハイダラーバード、アハマダーバード、プネーなど、インド各地に支店があるようだ。ここバンガロールにも既に3店舗あるらしい(コマーシャル・ストリート店、ガルーダ・モール店、コラマンガラ店)。僕は「ファバー」として知られるほどの熱心なファブインディア・ファンであり、視察のためにファブインディアのコマーシャル・ストリート店に入ったのだが、デリーの店と何となく品揃えが違うような気がして、ついつい2着購入してしまった。ファブインディア、恐るべし。ファブインディアはなぜか手提げ袋をくれないので、買い物の後、持ち運びに苦労するのが玉に瑕である。
コマーシャル・ストリートではケンタッキー・フライドチキン(KFC)を発見したので、そこで昼食を食べることにした。僕の知る限り、KFCは今のところインドにはバンガロールにしかない。以前はデリーにもあったようなのだが、人々の反対運動に遭って焼き討ちをくらって撤退したという。だからバンガロールでKFCへ行くという行為は通過儀礼に近い重要な行為である。インドのKFCのフライドチキンには、オリジナルとスパイシーの2種類の味付けがある。以前、通に教えてもらったところによると、インド人はオリジナル味のフライドチキンを全く注文しないため、オリジナル味は冷めていておいしくないから、絶対にスパイシー味を注文すべきである、とのことだった。そういえば昔バンガロールに来たとき、オリジナル味のフライドチキンを食べてあまりおいしくなかった記憶がある。その助言を思い出した僕は迷わずスパイシー味のフライドチキンを食べてみた。なかなかうまかった!噂ではもうすぐデリーにもKFCができるという。KFCができると食事の幅が広がるのだが・・・。

2ピース・ミールス
次はバンガロール最新のモール、バンガロール・セントラルへ行ってみた。外見は立派だったが、中身ははっきり言ってあまり特徴がなかった。唯一、資生堂の店舗が出ていたことだけが特筆すべきだった。おそらくまだデリーにはないと思う。バンガロール・セントラル内は本当は写真撮影禁止だが、問答無用で1枚だけ資生堂の写真を撮ってしまった。

バンガロール・セントラル

資生堂の店舗
バンガロール観光の最後に、コラマンガラにあるフォーラムというモールへ行った。このモールには8日にも訪れたのだが、ここでまとめて記述しておこうと思う。フォーラムはおそらくバンガロールの数あるモールの中でも一番使い勝手の良さそうなモールである。その理由の筆頭は、12スクリーンのインド最大シネマ・コンプレックス、PVRバンガロールが併設されていることだ。PVRバンガロールでは、カンナダ語映画、タミル語映画、テルグ語映画、ヒンディー語映画、英語映画など、各種言語の映画が上映されている。デリーのシネコンではほとんどヒンディー語映画と英語映画しか上映されないことを考えると、多種多様な映画を見る機会に恵まれたバンガロールはうらやましい限りである。ただ、あまりに多くの映画が上映されているため、デリーに比べてひとつの映画の上映回数が限られており、見たい映画の上映時間と自分の予定を合わせるのが困難である場合が多いように見受けられる。また、フォーラムにはランドマークという本屋とCD屋が融合した店が入っており、非常に利用価値が高い。その他にもフォーラムにはスーパーマーケットがあったり、ファストフード・チェーンや喫茶店チェーンが入っていたりして、一通りのものが揃っている。

フォーラム
今夜から夜行バスに乗ってマンガロールへ出る。いつもはPCを持って旅行するのだが、天気予報によるとずっと雨に降られそうな気配なので、PCを居候先の家に置いて、軽装で旅立った。午後10時半発のラグジュアリー・バスに乗った。一体どんなバスだろうと思っていたが、AC車で、毛布が用意されており、リクライニング・シートで、おしぼりや水がサービスで出たりビデオ上映があったりして、一応ラグジュアリーな雰囲気はあった。バスの座席に横になったらすぐに寝入ってしまった。
早朝6時半にマンガロールの長距離バススタンドに到着した。マンガロールではホテル・プーンジャ・インターナショナルというホテルに宿泊。ノンACのエコノミー・ルームで600ルピー。マンガロールの中では2番目くらいにいいホテルだと思う。
マンガロールはアイシュワリヤー・ラーイの故郷。早速アイシュワリヤーみたいな美人がうろついていないかチェックしに街に繰り出した。ホテルの周辺は繁華街になっており、人がたくさんうろついている。怪しげな視線を光らせながら、道行く婦女子たちを盗み見る・・・が・・・いたってごく普通のインド人しかいない。マンガロールの街もごくごく普通のインドの街といった雰囲気である。
その代わり、街中で変なものを見かけた。熊の格好をしたり虎の格好をしたり武将(?)の格好をしたりした一団が、店を回って小金を巻き上げているのだ。おそらく明日のダシャヘラー関連の祭りの一環であろう。そういえばアジメールへヒジュラーの調査へ行ったときも、同じ時期に同じようなことして店主からショバ代を巻き上げていた。この時期は全インド的にショバ代回収の季節なのだろうか?僕もこういう格好して店を回ればお金がもらえるかもしれない。ハロウィンみたいなイベントで、見ていて面白かった。

熊と猟師?

武将?羅刹?
もしかして美人は街をうろついていないのか、と考えた僕は、今度はちょっと田舎へ行ってみようと思い立った。マンガロールの郊外に、カドリー・マンジュナータ寺院というケーララ様式の寺院がある。そこへ行ってみることにした。カドリー・マンジュナータ寺院はココナッツの木に囲まれた瓦屋根の静かな寺院で、本尊はトリローケーシュワリーという女神であった。その他にもいろいろな寺院が集まった集合体となっており、巨大なハヌマーンの像や、ガンガーの水と考えられている湧き水や、沐浴池などがあった。ところがこの寺院に到着した途端、大雨が降り出したため、しばらく雨宿りをせざるをえなかった。やはりこの寺院にも、アイシュワリヤーのような美人は参拝に訪れていなかった。

カドリー・マンジュナータ寺院
とりあえずアイシュワリヤーの実家に行ってみようと思い、今度はホテルのレセプションにアイシュワリヤーの家の住所を聞いてみた。だが「マンガロール市内であることは確かだが、詳しくは分からない。調べておく」と言われただけで、結局住所は教えてもらえなかった。アイシュワリヤーは4歳の頃にムンバイーへ引っ越してしまったので、もう彼女の実家は残っていないかもしれない。
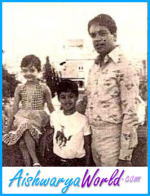
アイシュワリヤー・ラーイの公式ウェブサイトに掲載されている昔の家族写真。
父クリシュナラージ・ラーイ、兄アディティヤ・ラーイと共に。
一応背景に建物が見えるが、この頃はもうムンバイーであろうか?
こうなったらニシャーント君の実家に突撃するぞ!と思ったが、よく住所を見たらニシャーント君の家はマンガロールから北に約60kmの地点にあるウドゥピにあった。てっきりマンガロールに家があると思っていたのだが、うまく意思の疎通ができていなかったみたいだ。明日ウドゥピに行く予定なので、そのときについでに行くことにした。
アイシュワリヤーも見つからないし、マンガロールではもうやることがなくなってしまったので、マンガロールから南に12kmの地点にあるウッラール・ビーチへ行くことにした。内陸都市デリーにいると、海がやたらと恋しくなるものだ。山も恋しくなるが・・・。
ウッラール・ビーチに入るには、なぜかサマー・サンズ・ビーチ・リゾートというホテルで入場料25ルピーを支払わなければならない。そこまで美しいビーチではないが、あまり話しかけて来る人もいないので、のんびりできそうな場所ではある。ただ、ビーチが目的だったら、ゴアとかコヴァーラムへ行った方が賢明であろう。
インド留学当初から、僕は「ウドゥピ」という言葉に言い知れぬ憧れを抱いていたかもしれない。当時僕の家の近くには、ウドゥピという南インド料理レストランがあった。そのウドゥピは移転してしまい、今ではジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)近くのムニルカーにあるが、デリーの中でトップクラスにおいしい南インド料理レストランとして有名である。なぜか南インド料理レストランには「ウドゥピ」という名前が付けられることが多い。チェーン店ではないと思うのだが、いろんなところでウドゥピという南インド料理レストランを目にするにつけ、この名前には何かあるに違いないと思っていた。ウドゥピがカルナータカ州にある町の名前だと知るのには少し時間がかかったが、それを知ってからは、ウドゥピへ行って料理を食べるのがひとつの憧れとなっていた。ウドゥピはマンガロールから北に約60kmの地点にある。今日はウドゥピまで日帰り旅行をすることにした。朝10時にマンガロールのステート・バンク・バススタンドからウドゥピ行きの私営バスに乗った(30ルピー)。マンガロールからウドゥピまでの道は、亜熱帯の森林地帯と何かの工場が織り成す不思議な光景で美しかった。1時間ほどでウドゥピに到着した。
ウドゥピはクリシュナ寺院を中心とした門前町で、思っていたよりも発展した大きな町だった。バス停に着き、まずはクリシュナ寺院を目指した。クリシュナ寺院周辺にはいくつかの寺院が集合していた。一番参拝者を集めていたのは、伝説の聖者マーダヴァーチャーリヤによって安置されたというクリシュナ像を祀るクリシュナ寺院だったが、最も古い寺院はその隣のアナンテーシュワラ寺院のようだ。寺院の横には沐浴池があったり、円筒形の奇妙な物体があったり、山車が置かれていたりした。ちょうどお祭りシーズンで混雑していたのでクリシュナ寺院の中には入らなかった。

クリシュナ寺院入り口

沐浴池

これは何だ?
ウドゥピでは、矢萩多聞氏の友人で、ウドゥピの隣町マニパール在住のシュレーヤス君(19歳)と出会うことになっていた。彼に電話をしてみたらすぐに来てくれることになった。シュレーヤス君はコーンカニーであり、祖先はカシュミールから移住して来たそうだ。ただ、シュレーヤス君は典型的な現代っ子であり、あまりウドゥピの名所旧跡のことなどに詳しくなかった。そこで昨日に引き続きビーチへ行くことになり、ウドゥピから数kmの地点にあるマルペ・ビーチへ連れて行ってもらった。マルペ・ビーチはウッラール・ビーチよりも幾分美しい砂浜だった。遠くにセント・メリー島という無人島が見えたが、そこには毎日フェリーが出ていて、日帰りのピクニックができるらしい。

マルペ・ビーチ
シュレーヤス君と共に
遠くに見えるのがセント・メリー島
ビーチを見た後は、シュレーヤス君にウドゥピで一番おいしいレストランへ連れて行ってくれるよう頼んだ。ウドゥピというと菜食料理というイメージが強いのだが、住民には実はノン・ヴェジの人が多いらしく、特に魚がおいしいというので、魚料理が一番うまいレストランを紹介してもらった。バススタンドから歩いて数分のケディユール・ホテルというところで、この町では一番高級そうだがちょっと暗い雰囲気のレストランだった。ここでコネとキングフィッシュと呼ばれている魚料理を食べたが、まあまあおいしかった。僕はインドで一番おいしい魚カレーを食べられるのはアッサム州だと思っているが、その考えに揺るぎはなかった。実はこのレストランでは、ついでに頼んだチキン・スッカという鶏肉料理が一番おいしかった。

手前がチキン・スッカ
奥の2つが魚料理
昼食を食べた後は、シュレーヤス君が是非にと言うので、彼の通う大学があるマニパールへ行くことにした。ウドゥピからバスで坂道を上って30分ほどの地点にある。あまり知らなかったが、マニパールはインドで3本の指に入る医科大学、マニパール医科大学がある大学都市で、ウドゥピとは打って変わって近代的な街並みとなっていた。地元色が強くなりすぎることを避けるため、この大学への入学者はカルナータカ州以外の人が多いらしく、外国人留学生もけっこういるらしい。立派なグラウンドや図書館があり、シュレーヤス君曰く「バンガロールよりもホットな場所」だそうだ。マニパールの郊外には見晴らしのいい丘があり、学生たちのデートスポットになっているようだった。それにしてもマニパールには驚いた!

マニパール医科大学の校舎の一部

マニパール郊外からの眺め
マニパールから一旦ウドゥピに戻り、シュレーヤス君と別れ、今度はバンガロールで出会ったニシャーント・シェッティー君の実家を訪れることにした。シュレーヤス君も一緒に来てくれると助かったのだが、どうも彼は「シェッティー」という名前を恐れているようで、ウドゥピでお別れとなった。実は前々から薄々知っていたのだが、「シェッティー」という姓は地元ではマフィアと同義語なのである。インド最凶のマフィア、ダーウード・イブラーヒームの右腕の名前もシャラド・シェッティーと言う。もちろん全てのシェッティー姓の人がマフィアと言うわけではないが、シェッティー姓の人に犯罪歴のある人が多いという認識はけっこう根強いようだ。マンガロールやウドゥピの街中でも「シェッティー」という文字をよく見かけたが、少なくともシェッティー姓の人に金持ちが多いのは確かだ。シェッティーはバント族の典型的な名字であり、ボリウッド俳優のスニール・シェッティーやシルパー&シャミター・シェッティー姉妹もバント族である。
ニシャーント君の実家は、ウドゥピから数km離れたブラフマヴァラという村の郊外にあった。ブラフマヴァラにバスで向かっている間にまたも豪雨が降り始めたが、バススタンドで何とかオートリクシャーを拾って、ニシャーント君からもらった住所へ行ってもらった。住所というか、「ヴィッタル・シェッティー」という名前だけでオートワーラーは家の位置が大体分かったようだ。やはり地元ではけっこう有名な家柄のように思えた。ココナッツの木が林立する林の中に家はあった。こんなところに外国人が来るのはこれが初めてであろう。
あらかじめニシャーント君が実家に連絡を入れてくれたおかげで、僕がオートで辿り着いたときには家族が出迎えてくれた。ジョイント・ファミリーなので、ニシャーント君との関係がどうなのかよく分からないが、3世代10人以上の人がひとつの家に住んでいたと記憶している。ニシャーント君の家で英語がしゃべれるのは、ニシャーント君の従兄弟だけで、他のメンバーはトゥル語かカンナダ語しか理解しなかった。泣く子も黙るシェッティー一族を前に「アイシュワリヤーを探しに来た」なんてことは言えないので、適当に「カルナータカの村を訪ねて見たいと思っていたらちょうどニシャーント君と会って実家を紹介してもらった」と動機を説明しつつ、家の女性陣の顔を盗み見た。・・・う〜む、普通のインド人の顔だ。アイシュワリヤーほどの美人は・・・失礼だが・・・いない。だが、決して人前に出てこなかったが、チラッと見たところ、ニシャーント君のお祖母さんは長身で目鼻立ちがアイシュワリヤーに少し似ており、昔はすごい美人だったのではないかと伺われた。もういい、このお祖母さんをもって、「元アイシュワリヤー発見」ということにしておく!シェッティー家の人々は、なぜここに日本人が来たのかよく分からないながらも非常に親切にしてくれた。シェッティーという名前だけで人を判断するのはよくないだろう。

シェッティー家の人々
ブラフマヴァラのバススタンドでマンガロールまでの直行バスを拾って(36ルピー)、マンガロールまで戻った。
朝8時にホテルをチェックアウトし、ちょうど道を通りがかったバスに乗って、シュリーンゲーリーへ向かった(65ルピー)。シュリーンゲーリーはカルナータカ州のヒンドゥー教の中心的聖地で、全インドに5人いるシャンカラーチャーリヤの1人が座している場所でもある。本日の最終目的地、シモーガーへ行くちょうど途中に位置しているため、寄ってみることにしたのだった。
シュリーンゲーリーは西ガート山脈チクマガルール丘陵地帯の山の上にあり、バスから見える風景は非常に美しかった。カルナータカ州は、海も山も風景が美しくてバスの旅が毎回楽しい。だが、山道だけあって思っていたよりけっこう時間がかかり、シュリーンゲーリーには12時頃到着した。
早速シュリーンゲーリーの寺院コンプレックスを訪れた。やはりいくつもの寺院が境内に建っており、それぞれに参拝客を集めていた。最も古い寺院はシャラド寺院だが、建築的に最も面白いのはヴィディヤシャンカル寺院であろう。12星座を表した12本の柱が立っており、壁面にはジャイナ教のティールタンカラらしき像も見えた。寺院群のすぐ横にはトゥンガ河が流れ、橋を渡るとシャンカラーチャーリヤの住む場所があるようだが、ちょうど12時にゲートが閉まってしまって行くことができなかった。シュリーンゲーリー寺院群の境内には象が2頭いて、子供たちに祝福を与えていたのが印象的だった。

ヴィディヤシャンカル寺院

壁面にはジャイナ教のティールタンカラ像

子供に祝福を与える象
ちょうど昼時で、大食堂でランガル(集団会食)が行われていたため、僕もただ飯にありつこうと行ってみた。大きな広間に人々が一列にズラーッと座っている様子は壮観である。しばらく座って待っていると、ブラーフマンの格好をした人がコップや大皿を配ってくれて、流れ作業でそこにご飯や野菜などを盛ってくれた。だが、どうも配膳係の人たちは精神障害があるようで、何だか終始挙動不審で怖かった。食事は典型的ヴェジタリアン料理だったが、なかなかおいしかった。

ランガルの様子

こんな食事が配られた
もちろん手で食べる
1時半頃にこれまたちょうど道を通りがかったシモーガー行きのバスに乗り込んだ。シュリーンゲーリーからシモーガーまでがまた長かった。景色は非常に美しかったが、とんでもない田舎に来てしまったという恐怖の方が強かった。シモーガーの10km手前くらいまではただの田園と森林が続いていたくらいだ。しかしシモーガーに入ると一応市街地となって来てほっとした。シモーガーのバススタンドには午後5時半頃に到着した。シモーガーでは、ジュエル・ロックというホテルに宿泊した。オートワーラーにシモーガーで一番いいホテルに連れて行ってもらったのだが、設備はそれほどよくなかった。それでも一番高いACルームで900ルピーもした。シモーガーは特に何の見所もない退屈な街だった。
退屈なシモーガーにわざわざやって来たのは、8月24日(水)の日記で紹介した、サンスクリット語が話されている村を訪問するためだった。当時の日記では「マトゥール村」と紹介したが、どうも現地人の発音では「マットゥール」の方が近そうだ。古典語であるサンスクリット語が今でも話されている村というと、人跡未踏の僻地にポツンと位置しているような村を思い浮かべるが、マットゥール村はシモーガーのすぐ近郊にあり、ホテルからオートリクシャーをチャーターして行くことができた。
マットゥール村の第一印象は、「アレッ」というものだった。てっきり店の看板の文字などが全てサンスクリット語で書かれているかと思っていたが、カルナータカ州の言語であるカンナダ語の文字が普通に書かれていた。到着するや否や、好奇心旺盛な子供たちが寄って来たが、英語で話し掛けられた。子供たちに聞いてみると、サンスクリット語も話せるが、母語はカンナダ語らしい。「全然話と違う!」とガッカリしてしまったが、ちょっと村を散歩してみたら、いかにもサンスクリット語を話しそうなブラーフマンといった風貌の人々が多く住んでいる区画があった。また、よく目を凝らしてみると、村のあちこちに確かにサンスクリット語の看板がカンナダ語と併記されて出ていた。

村の道の清潔さは、村人の心の鏡です

寺院の神聖さを守りましょう

家の前の道を水できれいにしましょう
埃をなくせば健康が保障されます
この村の自慢は、どうやら村のそばを流れるトゥンガ河のようだ。村人たちはしきりに「河を見て来い」と言って来た。そこまで言われたら見に行かざるをえない。河ではまるで昔話のようにお婆さんたちが洗濯をしていた他、ブラーフマンの若者たちが瞑想をしていた。沈黙の行をしていたのだろうか、「写真を撮ってもいいですか?」と聞いても何も答えなかったので、1枚写真を撮ってしまった。

トゥンガ河と洗濯婆さん

瞑想するブラーフマンの若者
子供たちに連れられて一軒の家に入った。そこで1人の温厚そうな若者が迎えてくれた。彼の名はタパン・バースカル。彼の家はサンケーティーと呼ばれる、タミル地方を起源とするカルナータカ在住ブラーフマンの家系のようで、母語はサンケーティー語というタミル語の派生言語らしい。カンナダ語とサンスクリット語を話すが、ヒンディー語や英語は苦手だという。僕はサンスクリット語を1年だけ学んだことがあるのだが、全く忘れてしまっているので、彼とのコミュニケーションには困った。だが、ヒンディー語にはサンスクリット語の単語が多く入っているので、それらの知識を総動員させて、かつ英語を混ぜながら、何とか会話を成立させた。いやはや本当にサンスクリット語を日常で話している人がいた!感動!今度はタパン君に連れられて近所に住むおばさんの家へ行った。そこでも基本的にサンスクリット語で会話をした。だんだん話している内に少しずつ彼らが何を話しているのか分かってきたような気がする。マットゥール村に数ヶ月住めば、口語のサンスクリット語がすぐに身に付くかもしれない。この村の言語を調査すると非常に面白そうだ。

タパン君と共に
今日はバンガロールに帰らなければならないので、あまりマットゥール村に長居できず、帰らなければならなかった。しかし、マットゥール村はサンスクリット語をもう1度ちゃんと勉強して再訪したい場所である。

マットゥール村の入り口にあるバイタク
夕方には村人たちがここに集まって世間話をするのだろう
シモーガーのバススタンド近くの食堂で昼食を食べた後、午後2時頃にバンガロール行きのエクスプレス・バスに乗った(130ルピー)。乗る前にちゃんと「バンガロール?」と何度も確認した。そうしないと間違ってマンガロールへ行ってしまいそうだったからだ。シモーガーはどちらの都市へもアクセスできる位置にある。一体ここの人たちはバンガロールとマンガロールを間違えたりしないのだろうか?もっとも、英語をそのまま読むとバンガロールは「Bangalore」、マンガロールは「Mangalore」で「B」と「M」の違いしかないが、現地の発音だと前者は「ベンガルール」、後者は「マンガルール」になって、けっこう違いが出るかもしれない。
シモーガーからバンガロールまでは約270km。ほぼずっと平野の道で、風景は気持ちよかったが、道はよくなかった。トゥムクールという街を過ぎてからは次第に大都市へ近付いている雰囲気になって来て、車の数も増えて来た。バンガロールに着いたのは午後9時、シモーガーから7時間かかった。
夕食は播磨という日本料理レストランで食べた。バンガロールの日本食はどんなものかと偵察する目的があった。播磨はレジデンシー・ロードのデーヴァター・プラザの4階にあるが、ロケーションは初めて来た人にはちょっと分かりにくいか。店員は皆、片言の日本語をしゃべるが、完璧にしゃべりこなすインド人はいなさそうだった(デリーの日本料理レストラン「田村」にはやたら日本語がうまいネパール人がいる・・・)。メニューは豊富で、日本人の好きな料理をよく押えていたと思う。僕は牛肉ハンバーグを食べたが、ボリュームや味という観点で田村のハンバーグの方がよかったと思う。もっと本気出して作ってもらいたかった。
今日は午後4時のフライトでデリーへ帰らなければならない。バンガロールでは最新のシネコンで映画を見たいと思っていたのだが、そのための時間的余裕はなさそうだった。矢萩多聞氏にももう1度会う用事があった。
荷造りをした後、多聞氏の家に行って少し話をして、そこから空港近くにあるリーラー・パレスというホテル兼モールのような場所へ行った。リーラー・パレスには、ZENというオリエンタル料理レストランの1020ルピーの昼食ビュッフェを食べに行ったのだが、このビュッフェよりもモールの方がすごかった。デリーやバンガロールのどのモールよりも高級感が溢れており、館内ではピアノの生演奏の音楽が延々と流れていた。ゆっくり見れなかったので詳細は報告ができないが、こんなモールはインドで初めて見たと言っていいだろう。次にバンガロールを訪れたときにじっくり探検してみたい。
ZENのビュッフェは、寿司、刺身、焼き鳥などの日本料理の他、韓国料理、タイ料理、モンゴル料理などが食べられる。こういうスタイルのレストランもデリーでは見たことがない。しかし、味はあまり満足のいくものではなく、従業員のサービスも気が利いていなかった。ここでは今や世界的に有名になったインドのIT企業インフォシスに務める若い日本人たちと会食をした。現在、駐在員でもなく学生でもない、新たなタイプの在印邦人の若者がインドに増えているように感じる。彼らの多くは、インドが好きでインドに来たのではなく、英語を使える職場を追い求めた結果がたまたまインド企業だったというパターンのようだ。インドはインドが好きでないとつらい国だが、普通の駐在員のように無理矢理インドに来させられたわけでもないため、彼らはバンガロール生活を何とか楽しんでいるように見えた。ただ、そういう人たちの中でも、やっぱりインドが嫌いで嫌いで仕方なくなってしまっている人もいると聞く。そういえばインフォシスも一度行って見たい場所のひとつだった。インフォシスではインフォシス・グッズを売る店もあるらしい。インフォシス愛、という感じだ。
リーラー・パレスから空港までは車で10分ほどである。ジェット・エアウェイズのデリー行き9W816便は予定通り午後4時発だった。チェックインが遅かったために真ん中席を宛がわれたが、特にトラブルもなく、午後7時頃にデリーに到着した。ジェット・エアウェイズの機内食はおいしいというイメージがあったのだが、今回のデリー〜バンガロール間の機内食はどちらもあまりおいしくなかった。原油高によるコスト削減で味が落ちているのだろうか・・・?
今回の旅行を振り返ると、結局一番楽しかったのはサンスクリット語が話されているマットゥール村だったと思う。マンガロールやウドゥピでは、残念ながらアイシュワリヤーに匹敵するような美人を見つけることはできなかった。当初目標に掲げたアガスティアの葉は、今回は諦めた。アガスティアの葉を見てもらうにはけっこうな金額を取られるらしいが、ARレヘマーン・ライヴのチケット代が異常に高くて金欠状態になってしまったために金銭的余裕がなかったのが一番の理由だ。時間的余裕もなかった。また、前述のアガスティアの葉の研究者の方が僕のホロスコープを見てくださったところ、けっこう良さげな運勢が出てきたようなので、それで満足してしまったこともある。アガスティアの葉は人生に悩んでいる人が見るとけっこう人生の道標が見えていいようだが、今のところ僕は自分の人生に満足しているので、アガスティアの葉に頼る必要はなさそうである。アガスティアの葉には、その人が葉を見にやって来るときまでが予言されているという。僕にはまだそのときが訪れていなかったのだと思う。
今日は嫌な日に映画館に来てしまった。カルワー・チョウトである。チケット・カウンターで「チケット1枚」と頼んだら、「本当に1枚か?」と念を押された。1枚って言ってるから1枚なんだよ!
日本には1年の内に何回か、「1人でいると寂しい日」というのが巡って来るが、ここインドではカルワー・チョウトがその代表格と言えるだろう。簡単に言えば、カルワー・チョウトは妻が夫の健康と長寿を祈って日の出から月が出るまで断食をする日である。インド映画でもよく出て来る祭りのひとつで、ふるいで月を見てから夫の顔を見る動作が印象に残る。北インドで特に祝われるようだ。最近では、この日は夫婦またはカップルが水入らずで過ごす日になって来ているようで、映画館には多くの仲睦まじそうなカップルがやって来る。しかも今日僕が見た映画は、2週間前に公開されたヒンディー語映画「Main,
Meri Patni Aur Woh」だったが、結婚後の夫婦生活がテーマになっており、カルワー・チョウトの日にピッタリの映画だった。PVRアヌパムで鑑賞した。
「Main, Meri Patni Aur Woh」とは、「僕、僕の妻、そして彼」という意味。題名からも何となく内容が計り知れる。監督は「Main
Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon」(2003年)のチャンダン・アローラー、音楽はラージェーンドラ・シヴェーとモーヒト・チャウハーン。キャストは、ラージパール・ヤーダヴ、リトゥパルナー・セーングプター、ケー・ケー・メーナン、ヴァルン・バドーラー、ヴィノード・ナーグパールなど。ナスィールッディーン・シャーがナレーションを担当している。
| Main, Meri Patni Aur Woh |
 ミティレーシュ(ラージパール・ヤーダヴ)はラクナウー大学の図書館に勤める生真面目な男だった。ミティレーシュは34歳になるまで独身を通して来たが、遂に叔父(ヴィノード・ナーグパール)の説得に負けて、お見合いをすることになる。お見合い相手のヴィーナー(リトゥパルナー・セーングプター)は驚くほどの美人で、しかも彼女はミティレーシュとの結婚を承諾する。ミティレーシュとヴィーナーの結婚はとんとん拍子に進んだ。【写真は、ラージパール・ヤーダヴとリトゥパルナー・セーングプター】 ミティレーシュ(ラージパール・ヤーダヴ)はラクナウー大学の図書館に勤める生真面目な男だった。ミティレーシュは34歳になるまで独身を通して来たが、遂に叔父(ヴィノード・ナーグパール)の説得に負けて、お見合いをすることになる。お見合い相手のヴィーナー(リトゥパルナー・セーングプター)は驚くほどの美人で、しかも彼女はミティレーシュとの結婚を承諾する。ミティレーシュとヴィーナーの結婚はとんとん拍子に進んだ。【写真は、ラージパール・ヤーダヴとリトゥパルナー・セーングプター】
ミティレーシュの新しい生活が始まった。しかし結婚により彼の平穏な日常は一変してしまった。妻があまりに美人であったため、周囲の人々から注目を集め、ミティレーシュは毎日不安で仕方なかった。しかもミティレーシュは妻よりも背が低いことに劣等感を抱いていた。それでも彼は今までの真面目一徹の自分を徐々に改革し、もっと魅力的な男になるために努力する一方、妻に言い寄る男たちをあの手この手で遠ざけた。
ところが、ミティレーシュの家の前にヴィーナーの幼馴染みのアーカーシュ(ケー・ケー・メーナン)が偶然引っ越して来てからは、彼の嫉妬と劣等感はどうしようもないほど膨れ上がってしまった。アーカーシュは長身かつ社交的な好青年で、ヴィーナーとも非常に仲が良かった。ミティレーシュは疑心暗鬼を強め、遂にはヴィーナーが自分と離婚してアーカーシュと結婚しようとしていると信じ込む。
耐え切れなくなったミティレーシュは、ヴィーナーにアーカーシュと幸せに暮らすように言う。だが、それは全くの誤解だった。ヴィーナーは夫に疑われたことにショックを受け、実家に帰ってしまう。ミティレーシュは叔父に叱咤されてヴィーナーの実家へ行き、謝る。ヴィーナーも彼の謝罪を受け容れる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Main, Meri Patni Aur Woh」は、インド人にはヒットしなかったが日本人の間では評価の高い「Main Madhuri Dixit
Banna Chahti Hoon」のチャンダン・アローラー監督が、前作に引き続き、コメディアンとして有名なラージパール・ヤーダヴを主演にして作った映画だ。しかもラージパールの役柄は、生真面目で愛をうまく表現できない弱虫男という感じで、前作と非常に似ている。この映画のテーマは、ひょんなことから自分とは到底釣り合わない美人妻を娶ってしまった弱虫男の嫉妬、苦悩、劣等感、虚栄心などなどだ。
この映画は3つのパートに分けて考えることができるだろう。まずはラクナウーの美しい朝日と、ナスィールッディーン・シャーの粋なナレーションで始まる。ミティレーシュの人物像が映像とナレーションを通して面白おかしく語られ、ヴィーナーとの結婚までがとんとん拍子で描かれる。ここまでは非常に面白い。結婚後は、ヴィーナーを見ると目の色を変える男たちに悩むミティレーシュのイライラと、それを改善しようと乗り出す部分までは第2パートと言える。男としてミティレーシュの気持ちは非常に分かるのだが、しかし彼の嫉妬があまりに度を越しているため、笑っていいのか同情していいのか分からなくなって来る。第3パートはアーカーシュの登場からで、インターミッションを挟んだ後半部分全体である。ミティレーシュはヴィーナーにやたらとベタベタする親友のサリーム(ヴァルン・バドーラー)を、ラクシャー・バンダンによってヴィーナーと兄妹の仲にしてうまく対応するものの、アーカーシュの存在はサリームとは比べ物にならない脅威であった。最初はヴィーナーとアーカーシュを遠ざけようと努力するが、やがてミティレーシュはアーカーシュのスタイルを真似し始める。しかも彼は、妻が離婚を考えると誤解し、彼女を傷つけてしまう。最後のパートは、ドラえもんのいないのび太を見ているような感じでこっちがイライラして来てしまう。
「Main Madhuri Dixit Banna Chahta Hoon」もそうだったが、チャンダン・アローラー監督は、映画の導入は絶妙だが、映画の終わらせ方があまりうまくないようだ。竜頭蛇尾と表現したらいいのだろうか、映画の序盤の面白さを後半に維持できていない気がする。だが、所々で哀愁を呼ぶ爆笑シーンがあり、決して駄作ではない。例えば、背の高い妻を後ろに乗せて走ることを嫌ったミティレーシュが、自分のスクーターの座席を必要以上に高くしたり、シヴァリンガの前で人生の悩みをいろいろ打ち明けたり、ミティレーシュは、ヴィーナー、サリーム、アーカーシュと一緒に「Hum
Dil De Chuke Sanam」(1999年)を見に行って、映画中のアジャイ・デーヴガンに自分を重ね合わせたりするシーンなどが面白かった。
ラージパール・ヤーダヴは、今やインド人に大人気のコメディアンであり、シリアスな演技もできることを今作でも証明した。特にお見合いのシーンの照れ具合が好演だったのではなかろうか?リトゥパルナー・セーングプターはベンガル語映画の女優である。最初はちょっとぎこちない演技をする女優だと思っていたが、終盤に行くほど自然体になって来てよくなって来る。ケー・ケー・メーナンは後半からの出演だが、強烈な印象を残していた。やはり彼は名優である。
この映画には、インド映画の文法に従っていくつか歌が挿入されたが、その内の多くはなくてもよかったものばかりだ。いっそのこと、全くミュージカル・シーンのない映画にした方が質を保てただろう。
映画の舞台はほぼ全編ラクナウー。ウッタル・プラデーシュ州の州都で、アワド文化とナワーブ文化の中心地である。ルーミー・ダルワーザーなど、ラクナウーの見所がスクリーンに登場するため、ラクナウーを旅行したことのある人にはちょっとニンマリの映画であろう。
ミティレーシュの実家で命名式が行われるシーンが2度ある。インドのジョイント・ファミリーでは、赤ちゃんの名前を付けるのにこんな儀式をするのか、と驚いた。インドでは、パンディトジー(僧侶)が占いによって名前の頭文字を提示し、それに従って家族みんなが名前を考える。1回目の命名式では「A」が提示され、「アーユーシュ」に決定した。2回目の命名式では「K」が提示され、「カラン」が有力だったが、アーカーシュの一言によって「カビール」に決定した。カビールよりもカランの方が今風な感じだと思うのだが、なぜか赤ちゃんのお母さんはカランを「ダサい」と言って嫌がっていた。
「Main, Meri Patni Aur Woh」は、「Main Madhuri Banna Chahti Hoon」が気に入った人にはオススメの映画だ。しかし、前作ほどのドキドキ感はなく、憐憫の情の方が強いだろう。
6月6日の日記で、「アニメにもチャンスを!」と題した文章を書いた。その中で「Hanuman」というインド初の国産アニメーション映画について紹介したのだが、その映画が本日から公開された。当時の日記で僕は「Hanuman」が映画館で一般公開されることに懐疑的な見解を示したが、それは杞憂に終わったようだ。蓋を開けてみればけっこう大々的な公開となった。PVRプリヤーで鑑賞した。
監督はVGサーマント、音楽はタパス・レーリヤー。声優の中で有名なのは大人のハヌマーンの声を担当したムケーシュ・カンナー。人気TVドラマ「Shaktimaan」(1998-?)でシャクティマーンを演じた俳優である。
| Hanuman |
 猿のケーサーリとアプサラー(精霊)アンジャナーの間に生まれたハヌマーンは、風神パヴァンの息子でもあり、シヴァの化身でもあった。超人的な力と知恵を持ったハヌマーンは、自由奔放な幼年生活を送るが、やがてアヨーディヤー王国の王子でヴィシュヌの化身ラームと出会い、信仰に目覚める。ハヌマーンは森の王国、キシュキンダー王国の猿王バーリやその弟スグリーヴと仲良くなる。 猿のケーサーリとアプサラー(精霊)アンジャナーの間に生まれたハヌマーンは、風神パヴァンの息子でもあり、シヴァの化身でもあった。超人的な力と知恵を持ったハヌマーンは、自由奔放な幼年生活を送るが、やがてアヨーディヤー王国の王子でヴィシュヌの化身ラームと出会い、信仰に目覚める。ハヌマーンは森の王国、キシュキンダー王国の猿王バーリやその弟スグリーヴと仲良くなる。
王国を14年の期間追放されたラームとその弟ラクシュマンは、何者かに誘拐されたスィーター姫を探して森をうろついているとき、ハヌマーンと出会う。そのときちょうどキシュキンダー王国ではバーリとスグリーヴの間でいさかいが起き、スグリーヴは追放されてしまっていた。スグリーヴはラームたちに助けを求める。ラームはスィーター捜索に協力することを条件にスグリーヴに協力してバーリを討つ。
ところがいつまで経ってもスィーターは見つからなかった。もうすぐ追放期間の14年が過ぎてしまうところだった。ラームはスグリーヴに集中的な捜索を求める。スグリーヴは森中の動物たちに大号令を発し、スィーターを探させる。その結果、スィーターはラーヴァンの支配するランカー島に幽閉されていることが分かる。ハヌマーンはランカー島までひとっ飛びし、スィーターの無事を確認すると同時に、ランカー島に火を放って大打撃を与える。
ラームは猿や熊の軍勢を率いてランカー島に攻め込む。迎え撃つラーヴァンの羅刹軍。この戦争でラクシュマンは瀕死の重傷を負ってしまうが、ハヌマーンは薬草の生えたドローン山をヒマーラヤ山脈から根こそぎ持って来て窮地を救う。ラームは激戦の末にラーヴァンを討ち、スィーター姫を救出する。追放期間を終えたラームたちはアヨーディヤーに凱旋する。ラームの前でハヌマーンは永遠にラームに仕えることを誓う。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドの初の国産アニメということで、どんな出来に仕上がっているか楽しみだったが、やはりまだまだ日本のアニメに比べたら未熟と表現するしかない。しかし、今までのインドのアニメに比べたら格段に進歩していることは明らかであり、インドのアニメ産業の未来に希望を抱かせてくれる力作である。
インド初の国産アニメが、ハヌマーンという宗教的題材を扱ったことは、無難な選択でもあり、賢い選択でもあり、自然な選択でもあり、運命でもあろう。インド映画の歴史を紐解いてみれば、初期のインド映画の主題の多くはインドに昔から伝わる神話・叙事詩・歴史であった。「インド映画の父」と呼ばれるダーダーサーヒブ・ファルケーは、1910年に「キリストの生涯」というキリスト教を主題とした映画を見てインド神話を題材にした映画を作ることを思い付き、インド初の国産映画と言われる「ハリシュチャンドラ王」(Raja
Harishchandra:1913年)から始まり、「ランカー島炎上」(Lanka Dahan:1917年)、「クリシュナ誕生」(Shri Krishna
Janam:1918年)、「クリシュナの大蛇退治」(Kaliya Mardan:1919年)などの神話・宗教映画を次々に撮影した。これらは大いにヒットし、インド映画の隆盛の素地となった。現在はインドのアニメの黎明期と言える。この時期に大いに神話や伝承から主題を取ってアニメを作り続けることは非常に重要なことだと思う。一番の利点は、誰もが親しんでいる神話を題材にした映画は、インドでは子供から大人まで幅広い年齢層に受ける可能性が高いことだ。インド人は知ってる話を何度も見たり聞いたりすることにあまり疑問を感じない国民のようなので、「わざわざみんなが知ってる話をアニメにする必要がない」と考えるのは間違いである。知ってる話だから受けるのだ。しかも、ハヌマーンという1人のキャラクターを中心としたことがこの映画では功を奏していたように思える。「ラーマーヤナ」全体をアニメにするのは難しすぎる。インドは説話の宝庫だ。これからしばらくはこの線でアニメの制作を続けて技術を磨くべきであろう。
ただ、不思議だったのは観客の顔ぶれである。アニメを見に来るのはお子様中心かと思ったが、意外なことに20代くらいの若者が多かったのだ。今日は大学は学生自治会選挙運動の関係で授業がなかったので、正午の回を見た。普通の子供はこの時間には学校に行っていて見に来ることができなかったとしても、その観客層は僕の理解を越えていた。一番気になったのは、心なしかチンピラみたいな若者が多かったことだ。ヒンドゥー至上主義団体、世界ヒンドゥー協会(VHP)傘下の青年過激組織バジラング・ダルのメンバーだろうか、と考えていた。バジラングとはハヌマーンの別名である。ハヌマーンに格別な思い入れがあっても不思議ではない。映画に何か不都合な点があったら即刻暴動でも起こすんじゃないかと心配していたが・・・そんなことはなかった。ただ、映画が始まる前に「ジャイ・ハヌマーン!」という歓声が聞こえた。
アニメはセル画ではなく、全部コンピューターで描かれていたと思う。動きが早くなると画像が粗くなり、曲線がギザギザになったりしていたのが気になった。コンピュータの性能不足であろうか?コンピューターでアニメを描くのはいいが、設備のさらなる改善が必要のように思えた。
ハヌマーンのキャラクター・デザインは最高。特に子供の頃のハヌマーンがキュートでいい。しかしラームは何だか覇気がなかった。今回はラームは完全に脇役であった。
言語はヒンディー語。サンスクリット語の語彙が多いので、多少通常のインド映画よりも語彙力が要る。だが、頑なにアラビア・ペルシア語彙を排除しているわけでもなく、分かりやすいヒンディー語だったと思う。
実は音楽が非常によかった。特に冒頭と最後に流れる「Mahabali Maharudra」という曲はすごい。参加しているアーティストが尋常ではない。ヴィジャイ・プラカーシュ、ソーヌー・ニガム、シャーン、パラーシュ・セーン、カイラーシュ・ケール、マドゥシュリー、スネーハー・パント、サプナー・ムカルジーが一緒に歌を歌っているのだ。歌詞のベースは宗教賛歌だが、ARレヘマーンっぽい勇壮な音楽にアレンジがされており、心を高揚させる。最後のスタッフ・ロールではミュージック・ビデオも流れる。ハヌマーンに扮した子供たちが駆け回るのがいい。「Akdam
Bakdam」は子供の声で歌われるかわいい曲。サントラCDに入っている「Hanuman Chalisa」もいい曲だが、映画中では使われなかったと記憶している。
「Hanuman」は、日本のアニメのレベルを期待していくと失望するだろうが、インド初の国産アニメーション映画ということを念頭に置き、他人の子供の成長を温かく見守る気持ちで見に行くときっと面白いだろう。また、「ラーマーヤナ」をあまり知らない人にはけっこう勉強になると思う。
現代ヒンディー社会の文学と文学者の状況について調べる課題を出された。ヒンディー文学は世界の文学の中でも非常に弱い立場にある文学だと思う。ヒンディー語話者人口は4億人とも5億人とも言われ、ヒンディー語は世界の大言語の1つだ。日本ではヒンディー語の認知度は悲しいくらい低いが、それでも人口の力を背景に、これから重要度が高まっていくと思われる。一昔前に比べ、ヒンディー語のウェブサイトが激増したことはその表れだと思う。インドで最も読まれているのはヒンディー語の新聞であるし、最もよく見られているTV番組もヒンディー語のものである。ただ、ヒンディー文学の現状は決して楽観視できないように見える。ヒンディー文学はその歴史から非常に脆弱な基盤の上に成り立っており、現代においてさらにその立場を弱くしてしまっているように思える。しかし、現代のヒンディー文学と文学者の本当の現状は一体どうなのだろうか?本からはなかなか分からない。そこで、かねてから親しくしていただいている女流ヒンディー文学者ラージ・ブッディラージャー女史にインタビューしてみることにした。
ラージ・ブッディラージャー女史(1937〜)は優れた文学者であると同時に有能な教育者でもあり、東京外国語大学を初め、世界中の大学で教鞭を取った経験を持っている。また、日本とは特に親しい関係を保っており、1984年にはインド日本文化協会(Indian
Council for Japanese Culture)を設立した他、桜を題材としたヒンディー語の詩集を出版したりしている。現在ではデリー大学を定年退職し、ますます文筆活動と文化交流活動に勤しむ毎日を送っておられる。
まずはブッディラージャー女史の幼年時代や文学者になったきっかけから話を始めてみた。ブッディラージャー女史は1937年にラーホールに生まれ、ムルターン近くのコート・アッドゥーという小さな村で育ったという。これらのキーワードを聞いて質問せずにいられないのは、1947年の印パ分離独立に関する事柄だ。ちょうどブッディラージャー女史10歳の頃である。やはり、同女史も他のパンジャーブ人たちと同様、印パ分離独立時にデリーに移民してきた。このときの話は今まで一度も文学の題材にしたことがないらしいが、いつか書きたいと言っていた。少し聞いたところによると、ブッディラージャー女史の祖母はコート・アッドゥーのザミーンダール(大地主)で、当地に巨大な邸宅を構えていたという。祖父は若くして死んでしまったらしい。祖母は当時の女性には珍しく、サンスクリット語、パンジャービー語、ウルドゥー語、ヒンディー語をマスターした教養ある女性だった。また、非常に礼節にこだわる人物だったようで、村人たちを厳しく監督して村を常に清潔に保つよう心がけていた他、女性たちを組織して手織り工場を立ち上げたり、1日1回コート・アッドゥー駅に止まる列車の乗客全てに水を配らせたりしていた。おかげでコート・アッドゥーは、「パーニーワーラー・ガーオン(水が飲める村)」という名で近隣では有名になっていたという。これだけ村を愛していた祖母が、印パ分離独立時にインドへ移住することに反対することは想像に難くない。祖母はまず家族を逃がし、その後家財の全てを村人たちに分け与えてから、後でデリーにやって来たという。だが、印パ分離独立時の混乱の中、ムスリムを乗せたパーキスターン行きの列車はインド領でスィク教徒やヒンドゥー教徒の襲撃を受け、スィク教徒やヒンドゥー教徒を乗せたインド行きの列車はパーキスターン領でムスリムの襲撃を受けたことは有名である。ブッディラージャー女史や祖母は、l無事にインドへ移民できたのだろうか?恐る恐る、「列車で来たんですか?」と聞いてみると、「飛行機で来た」との答え。さ、さすがザミーンダール!失礼しました〜。
ムルターン時代のブッディラージャー女史は非常に優秀な生徒だったようだ。当時の女性の教育は3つ。計算、地理、家事であった。計算は家計を切り盛りするために重要だった。地理は、その土地の自然、文化、伝統などが中心的に教えられた。家事で教えられるのは料理や裁縫などである。ブッディラージャー女史の通っていた女学校には、月に1回くらい「アングレズィー・サーヒバー」と呼ばれる英国人マダムがやって来て、優秀な女学生を表彰したりしていたという。優秀なブッディラージャー女史はいくつもの章を受賞したそうだ。特に学校で詩や文学を学ぶようなことはなかったらしく、インド国民軍(INA)の「Kadam
Kadam」などの愛国歌や、ラーム・リーラーの挿入歌などを聞き覚えて育ったという。また、例の祖母がよくカビール(中世のバクティ詩人)の詩を詠唱していたという。ブッディラージャー女史は、文学を勉学として学んだのではなく、文学的環境の中で自然に文学的素養を身に付けたように思える。
ブッディラージャー女史が初めて作った詩は、ザクロの詩だったという。まだ子供の頃、シムラーで見た大きくておいしいそうなザクロの実を見て詩を作ったそうだ。だが、本格的に文学の世界に足を踏み入れたのは1964年、アーグラー大学の博士課程にいた頃らしい。当時のブッディラージャー女史は、リーティカール(16〜19世紀)の代表的詩人デーヴの研究をしていたという。だが、インドの女性たちの地位の低さに日頃から心を痛めていたブッディラージャー女史は、ナヴバーラト・タイムス(ヒンディー語の新聞)の事務所へ行き、女性に関してコラムを書きたいと申し出た。ただ、ブッディラージャー女史は、このとき財政的に非常に困窮していたことも新聞社の戸を叩いた大きな理由だったと正直に言っていた。当時ナヴバーラト・タイムスの編集長をしていたのはアクシャイ・クマール・ジャインという人物で、彼は「どうせファッションか何かについてでも書くのだろう」と思って、ブッディラージャー女史に「紙を渡すから、今からここで何か書いてくれ」と言ったそうだ。同女史はインドの女性問題について3ページほどの文章を書いた。ジャイン編集長はそれを読んで非常に感銘し、それからブッディラージャー女史の連載が同紙で始まったという。これが文学界に入る直接のきっかけとなったそうだ。ちなみに原稿料を聞いてみたら、当時コラム1本につき25ルピーだった一方、ブッディラージャー女史は自分の財政的困窮を訴え、特別に35ルピーにしてもらったという。その後さらに50ルピーに上げてもらったとか。当時のレートで、日本円にするといくらぐらいなのだろうか?
同女史は常日頃から大学の教育者に疑問を抱いていたという。教える才能もない人間がどうして教員をしているのか?彼らはどうやって職を得たのか?無能な教師たちを見たブッディラージャー女史は、「学生たちが一生自分のことを覚えていてくれるようないい教師になろう」と志し、教育者としての道を歩み始めた。4つの大学に履歴書を送ったところ、4つ全てから了承をもらったという。ナヴバーラト・タイムスの連載が好評を博したおかげらしい。以後、ブッディラージャー女史はインド国内の大学はもとより、世界中の大学でヒンディー語やヒンディー文学を教えることになった。今では、外国人を見るとつい誰でもヒンディー語を教えようとしてしまうほどだという。「あなたは自分を文学者だと思っていますか、それとも教育者だと思っていますか?」との質問に、ブッディラージャー女史は「私は文学者としてパワフルなのと同じくらい教育者としてもパワフルだ」と自信満々に答えていた。
ブッディラージャー女史の人生が面白くて延々と話をしてしまい、肝心のヒンディー文学と文学者の現状が後回しになってしまった。まず、昔の文学者と現在の文学者の違いについて質問してみた。すると、ブッディラージャー女史は、「サードナー」という言葉を使い、「昔の文学者は『サーヒティヤ・キ・サードナー』をしていたが、今の文学者は『アプニー・サードナー』をしている」と答えた。意訳すると、「昔の文学者は文学のために人生を捧げていたが、今の文学者は自分のために人生を捧げている」という意味だ。また、ブッディラージャー女史は文学の定義を「プレーム・キ・サードナー(愛への帰依)」と述べていた。「独立以前のヒンディー文学には、インド独立という明確な目的があった。しかし、独立を達成してからのヒンディー文学は目的を失ってしまった。近代ヒンディー文学史にはプラガティワード(進歩主義)、プラヨーグワード(実験主義)、ナイー・カヴィター(新詩)などの運動が起きたが、それが長続きしなかったのは、文学の基本である『プレーム・キ・サードナー』がなかったからだ」と自分の意見を言っていた。特に批判の対象となっていたのはプラガティワードであった。プラガティワードの文学者たちは、宗教、神、寺院に罵声を浴びせかけた。そのような傲慢な文学が人々の心を掴むはずがない、というのがブッディラージャー女史の考えである。また、現代のヒンディー文学界ではダリト文学が隆盛している。ダリトとは被抑圧民のことで、不可触民、後進カースト、後進部族などをひっくるめた言葉だ。ブッディラージャー女史は、ダリトとダリト文学に疑問を投げかけていた。「ダリトとは何か?貧しい人がダリトなのか?抑圧されているのがダリトなのか?ならば私もダリトだった。経済的に困窮した時期を過ごした。ダリト文学とは何か?ダリトが書いた文学がダリト文学なのか、それともダリトについて書いた文学がダリト文学なのか?どちらにしろ、文学者は常に強くなければならない。常に顔を上げて堂々と歩まなければならない。自分のことを弱々しい存在だと考えて書いた文学に力があるはずがない」と厳しい意見を述べていた。
「現在、文学者は文学だけで食っていけるか?」と質問してみると、ブッディラージャー女史は「不可能」とキッパリと答え、「文学者は何か別に仕事をし、経済的また文学的に自立した文学を書く必要がある」と述べた。ちなみに現在ブッディラージャー女史は、1本のエッセイを書いて新聞に投稿するごとに1000ルピーの原稿料をもらっているらしい。それも、新聞社から依頼があったときのみで、自分から原稿を送ることはないようだ。ブッディラージャー女史くらいの著名な文学者で原稿料が1000ルピーだから、他の駆け出しの文学者の原稿料はその半分以下になるだろう。それで生活していくのは確かに辛そうだ。
文学者の収入に関して、出版社の話になった。ブッディラージャー女史は現在のヒンディー文学者に対する批判をするのと同じくらい、出版社の批判をしていた。昔の出版社は、まず文学者に予めお金を渡して文章を書いてもらって本を出版していたという。それから次第に出版社は文学者に印税を支払わなくなり、支払うとしても遅れて、大体1〜2年後に払うようになったという。ちなみに印税は売り上げの10%が基本だそうだ。それからさらに状況は悪化し、本を出版するときに出版社と文学者が半分ずつお金を出し合い、共同で出資をするようになった。そして現在では、文学者が本を出版するのに文学者自身が100%お金を出さないといけなくなってしまっているという。これでは自費出版と変わらない。しかも、出版社は文学者から必要経費の全額受け取らなければ本を出版しようとせず、受け取ったら受け取ったで、当初の約束や公表する出版部数よりも少ない版数しか出版しないそうだ。文学者から出版費用を全額受け取っているので、どれだけ出版しようが出版社の勝手である。だから、なるべく必要経費を少なく抑え、収入をたくさん得ようとする。また、売れた部数も虚偽の数字を公表することが常習化してしまっている。ブッディラージャー女史の友人の文学者で、本を出版した人が、出版社からは「6冊しか売れなかった」と言われて全く印税を受け取れなかった人がいるという。だが、ブッディラージャー女史によると、デリーにある大学60校全ての図書館が2冊ずつ本を買うだけでも最低120冊は行くはずだ。6冊しか売れないというのはおかしすぎる。出版社は文学者を騙し、文学者はそれに従うしかなくなってしまっている。おかげで出版社はどんどん裕福になり、文学者はどんどん貧乏になっていっている。出版社の横暴のせいで文学は産業になってしまった。ブッディラージャー女史は、出版社の批判をすると同時に、この点でも「文学者は強くなければならない」と再度強調し、現在の弱小な文学者たちを批判していた。
「現在のヒンディー文学界で一番偉大な文学者は(あなた以外には)誰ですか?」という質問に、ブッディラージャー女史は、「心のきれいな文学者が最も偉大だ」という抽象的な答え方をしていた。具体的な返答を求めると、カムレーシュワル(1932〜)の名前を出していた。
「ヒンディー文学は世界の文学に対抗することができるか?」という問いに対し、ブッディラージャー女史は、「ヒンディー文学は非常に力がある文学だ。しかし、残念ながらヒンディー文学は世界文学の舞台まで到達していない。そのためには翻訳が最も重要な任務となる。ラヴィーンドラナート・タゴールがノーベル文学賞を受賞したのも、『ギーターンジャリー』の翻訳があったからだ」と述べた。ここでもブッディラージャー女史は、現代のヒンディー文学者を批判し、「文学者たちは自分の作品を世界に向けて発表しようとしていない。自分の世界に閉じこもって満足してしまっている。それよりは最初から英語で文学を書く方がマシだ。また、翻訳には様々な言語の知識が必要だ。現在の文学者には、世界のいろいろな言語の知識が不足している。それにヒンディー文学者には、サンスクリット語、ベンガリー語、ウルドゥー語、パンジャービー語、ブラジ方言、アワディ方言などのインド諸語の深い知識も必要だが、それを実現している文学者は少ない」と述べた。日本におけるヒンディー文学に関してもブッディラージャー女史は警鐘を鳴らした。日本語に翻訳されたヒンディー文学は数えるほどしかない上に、日本の大学教授は学生に授業の一環として適当に翻訳をさせて満足しており、日本語とヒンディー語の両方に精通した翻訳者による翻訳がなされていない。
ちょっと話題に上ったので、「英語で文学を書くインド人文学者についてどう思うか?」と聞いてみた。ブッディラージャー女史は、「英語で文学を書くのは自由だが、英語ネイティヴ・スピーカーの文学者が書く文学よりも優れた文学を書かなければ意味がない。インド人が英語で文学を書いて、文学的感興の深みに到達するのは難しいだろう」と消極的な見解を示した。
最後にズバリ「ヒンディー文学の未来は明るいか暗いか?」と聞いてみたら、ブッディラージャー女史は、「文学者の行動如何によるだろう」と曖昧な答え方をした。質問を変えて、「ヒンディー文学の読者は増えているか、減っているか?」と聞いたら、「確実に減っている」との答えだった。やはりあまりヒンディー文学の未来は明るくなさそうだ。
追記:ちょうどこの記事を書き終えた頃、現代ヒンディー文学を代表する著名な文学者ニルマル・ヴァルマー(1929-2005)が死去してしまった。なんという偶然・・・。人はいずれ死ぬものではあるが、ニルマル・ヴァルマーの死によりさらにヒンディー文学の未来が閉ざされてしまったような気分になった。ヒンディー文学の一学生として、ニルマル・ヴァルマー大先生のご冥福をお祈りいたします。
10月29日夕方、デリー市内の3ヶ所で連続爆発があった。パハールガンジ、サロージニーナガル、ゴーヴィンドプリーである。この中で旅行者にも有名なのは、デリーの安宿街パハールガンジであろう。また、サロージニーナガルは、海外有名ブランドの衣服の検品不合格品が安く手に入ることがある掘り出し物マーケットとして南デリー在住の人々に有名である。テロかどうかの断定には非常に慎重的だったが、警察の捜査によりテロであることが断定された。30日、ラシュカレ・タッイバと関係あるとされる「Inquilab
Group(革命グループ)」というマイナーな団体が犯行声明を発表したが、果たして本当に彼らがテロを実行したかはまだ不明である。
爆発当時、僕はデリーに来ていた「中村屋のボース」の著者、中島岳志氏とグルガーオンにいた。ちょうど最初の爆発があった頃にメトロポリタン・モールを出て、デリーへ向かったと記憶している。爆発発生の直後、デリーの州境が封鎖されたらしいので、もうちょっと遅かったらデリーに入れなくなっていたところだった。中島氏は、2001年12月の国会襲撃事件のときも偶然デリーにいた。中島氏がデリーに来たときはテロに注意すべし、ということか。
罪のない人々を無差別に殺すテロは決して許されるべきものではないし、僕も巻き添えになるのはゴメンだが、なぜ犯人はテロを起こさざるをえなかったのか、彼らはテロによって一体何を主張したいのか、という点も冷静になって考える必要があるだろう。テロはテロリストだけの問題ではない。
TVのニュース番組では、テロの被害にあった場所が映し出されていた。驚いたことに、テロがあった翌日にテロのあったマーケットで買い物をしているインド人がいた。インタビューでは、「人は死ぬべきときに死ぬ。テロを怖がって家に閉じこもっていてもそのときが来れば死ぬ。とりあえず私はどうしても今日買い物をしなければならないので、マーケットに来た」とか、「朝があり、昼があれば、夜もある。暗闇が辺りを覆ってしまったからと言って、怖がる必要はない。また朝が来る」みたいなことを言っていた。こういう極度に達観した考え方を持っているのがインド人のすごいところだが、いざ何かあるとパニックになって我先に逃げ惑うのもインド人である。
今日はちょっと用事があったので、近所のグリーンパークのマーケットへ行ってみた。マーケットの入り口には金属探知ゲートが設置され、カーキー色の制服を着た警官たちが多数配備されていた。だが、マーケットの店は通常通り営業をしており、ディーワーリー用のギフトなどが露店に所狭しと並べられていた。ディーワーリー直前の日曜日にしては閑散としている印象を受けたが、それでも買い物客はけっこういた。
今年に入り、今回の連続爆破テロを含め、今までのところデリーでは2回テロが発生している。5月22日にはデリー市内の2館の映画館で爆発があり、1人が死亡、40人が負傷した。この事件のおかげで、デリー市内の映画館のセキュリティーがかなり厳重になってしまって困った。おそらく今回の連続爆破テロのせいで、せっかく徐々に緩くなっていたセキュリティーがまた引き締められたことだろう。僕も死ぬときは死ぬと思っているので、テロを怖がって引きこもりになるようなことはないが、テロのせいで極度にセキュリティーが厳しくなるのだけが嫌だ。
デリーにいる限り、テロとは向かい合って生きていかなければならないが、いつ、どこで起こるか分からないのがテロなので、対策のしようがない。結局、庶民にとっては、通常通り生活するということが、テロに立ち向かうということになるだろう。
ディッリー・ナヒーン・ジュケーギー(デリーは屈しない)!



