 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
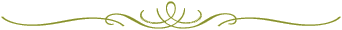

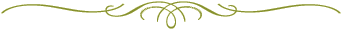
2003年に公開された映画「Pinjar」の原作ヒンディー語版からの日本語訳。著者はパンジャーブの女流作家アムリター・プリータム(1919-)。「ピンジャル」とは、「骸骨」とか「鳥かご」という意味。
|
|
|
|
埃っぽい日だった。プーローは袋の上に座って豆の皮を剥いていた。さやから豆を押し出そうとすると、白い虫が彼女の親指に飛び出た。ぬかるみに突然足を取られて驚いたときのように、プーローの身体に痙攣が走った。彼女は手をブンブン振って虫を振り落とし、両手を膝の間に押し込めた。
プーローの前には、大量の豆のさや、皮が剥かれた豆、空っぽの豆の皮が散乱していた。彼女は両手を膝の間から抜き出して、自分の胸を押さえた。彼女は、まるで自分の頭の先から足の先まで全身が、その豆のさやのように感じた。神聖な豆の代わりに、汚らわしい虫が寄生しているさやのように・・・。
プーローは吐き気を催した。彼女は自分の腹の中に巣食う虫をひねり殺したかった。彼女はその虫を自分の身体から一掃してしまいたかった。まるで刺さった棘を爪で挟んで抜き取るのように、まるでゴークルーの木の棘を引っこ抜いて捨てるように、まるで引っ付いているダニを引掻いて取り去るように、まるで吸い付いたヒルを取り外すように。
プーローは目の前の壁に視線を移した。1日また1日、彼女はそこで無為に過ごしていた。 +++
プーローはグジャラートのチャットーアーニー村のシャー(商人貴族)の娘だった。シャーとは名ばかりで、現在では没落していたが、それでも人々はシャーと呼んでいた。運の巡り合わせが悪かったせいで、シャーの家は先祖代々伝わる大鍋を売り払わなくてはならなかったほど困窮していた。生活の辛苦をなんとかするため、プーローの家族は村を出てシャム(ビルマからタイの辺り)へ行った。そこで彼らの運は、あっという間に好転した。
その当時プーローはまだ子供だった。母親の腕の中には男の子もいた。シャー一家はまた故郷チャットーアーニーに戻ってきた。プーローの父親は抵当に入れていた家を取り戻し、先祖の名誉を挽回した。新しい家を建てた方が費用は少なくて済んだが、父親は家族の反対を押し切って利子まで支払い、何とか自分の先祖の名誉を守った。
穀物、飼料、その他の品々を十分用意して、シャー一家は再びシャムへ旅立ったが、彼の家は名誉と共に故郷に残った。次に彼らが故郷に戻ったときには、プーローは14歳になっていた。プーローには一人の弟と、三人の妹がいて、さらに母親のお腹の中にはもう一人子供がいた。
シャーは帰って来てすぐに、近くのラットーワール村の裕福な家と縁談をまとめようとした。プーローの母親は、沐浴をして洗濯をしたらすぐに、プーローの結婚をまとめようと考えていた。彼女は、これで絶対に縁談をまとめ、重荷を下ろして帰るつもりで、見合い相手の家を訪れた。
プーローの将来のサスラール(義理の父親の家)には当時3匹の家畜がいた。その家は、村で唯一、レンガ製の屋上のある家だった。家の玄関には「オーム」のマークが書かれていた。見合い相手の男は容姿端麗で、知的な顔立ちをしていた。
プーローの父親は5ルピーと砂糖を渡して縁談をまとめた。当時のグジャラートでは、交差婚が行われていた。プーローと結婚する男の妹が、プーローの弟と結婚することになった。プーローの弟はそのとき12歳にも満たず、彼の花嫁に至ってはさらに幼い女の子だった。
2年ごとに続けて3人もの女の子を産んでしまったため、プーローの母親は相当イライラしていた。しかし運は上向いていた。家には十分な食べ物があり、十分な衣類があり、次に産まれてくる子供が男の子である予感もしていた。
プーローの母親はヴィディマーター(幸運の女神)のプージャー(祭祀)を行った。村の女性が数人集まってプーローの家の庭に牛の糞で人形を作り、赤いチュナリー(頭にかける布)に刺繍をして、それを人形の頭にかけた。そして小さな金製の鼻飾りを作らせ、人形の鼻に付けて、みんなで合唱した。
ヴィディマーターが怒って来なさったら、それでよし
ヴィディマーターが怒って来なさったら、それでよし
近隣の村の女性たちの間にはこんな迷信があった――子供が生まれるときには、ヴィディマーターがやって来る。もしヴィディマーターとその夫の仲がよいときに来ると、女神は急いで女の子を作って去って行ってしまう。なぜなら夫の元へ急いで帰らないといけないからだ。一方、もしヴィディマーターが夫と口論してやって来ると、家に急いで帰る必要もなく暇なので、のんびりと男の子を作って去っていく。だから、女性たちはこんな歌を歌うのだった。
ヴィディマーターが怒って来なさったら、それでよし
ヴィディマーターが怒って来なさったら、それでよし
おそらくヴィディマーターがどこか近くでその歌を聞いていたのだろう、女神はその願いを聞き入れた。15、6日後に、プーローの母親は男の子を産んだ。シャーの遠い親戚にまで祝福が届いた。ただひとつ心配事があった。それは、その男の子がテーラル(3人の女の子の後に男の子が生まれること。不吉と考えられている)だった。プーローの母親は大層不安がり、何とか神様に末の男の子を助けてもらおうとした。ヴィディマーターを信じる女性たちが再び集まり、青銅製の大きな皿の中心に穴を開け、男の子をその穴に何度も何度も通して歌った。
テーラルの呪いがかかっちまった
テーラルの呪いがかかっちまった
3人の女の子の後で神様から授かった男の吉運を祈って、やっと彼女たちは男の子が助かることを信じることができた。
15歳になったプーローの身体は急に成長した。去年まで着ていた服が小さくなってしまった。プーローは近くの市場で花柄の刺繍布を買って、新しい服を作らせた。いくつもの刺繍を施したチュナリーも用意した。
プーローの友達は、遠くから彼女の許婚のラームチャンドを指差した。プーローは、彼の美しい容姿にみとれてしまった。彼のことを思い出すだけで、プーローの顔は赤く染まるのだった。
プーローは安心して外出をすることができなかった。なぜならその村は、近隣の村からの行き来が激しかったからだ。彼女は村人たちに見られないように気をつけていた。その村の多くの人がムスリムに改宗していたことも、彼女が怯える原因だった
プーローと友達は、夕方になるまで畑で遊んでいた。プーローは幾度も畑のそばを通る獣道の辺りで立ち止まっていた。座って草をむしることもあった。ナツメの木に寄りかかって立っていることもあった。ナツメの実を落として拾うこともあった。友達とあれこれ話をすることもあった。その道は、彼女のサスラール(義理の父親の家)に続いていた。
私のあの人が今日は通らないかしら、彼がこの道を通り過ぎるのを一目見たいわ、と心の中で彼女は考えていた。プーローの心臓は、その道のそばに立っただけで激しく鼓動するのだった。そして一晩中夢の中で彼を思い描いているのだった。
ある日、プーローは新しい靴を履いていたため、靴擦れがしていた。友達と歩いている内に、彼女は遅れてしまった。プーローとその友達は、畑の中を通って帰るところだった。夕闇が、溶けたコインのように四方を覆い始めた。女の子たちは畑のあぜ道に沿って歩き、村に通じる大通りに辿り着いた。この道は広く開けた場所を通っている部分もあれば、茂みの中を掻き分けつつ通らなければならない部分もあった。女の子たちは散り散りになってこの道を歩いていた。プーローは後ろの方に取り残されてしまった。右足のかかとにマメができていた。プーローはきつい靴を脱いで手に持ち、走り出した。
友達はプーローに、彼女の右足は左足よりも大きいから、右足だけに靴擦れができるのだと常日頃言っていた。プーローの右手も、左手より大きかった。「そうね、腕輪をしたら(結婚式を挙げたら)、それがよく分かると思うわ」と言ってプーローをからかっていた。プーローは空想し始めた。本物の象牙の赤い腕輪がいくつも彼女の腕に通されつつあった。後方の大きめの腕輪は彼女の腕を通ったが、前方の小さめの腕輪が、彼女の手を通らなかった。ナーイー(床屋)は油を彼女の親指の付け根に塗って、象牙の赤い腕輪を無理に通そうとした。プーローは、その象牙の赤い腕輪が右手を通らずに壊れてしまったらどうしよう、と考えた。プーローの心臓の鼓動が激しくなった。腕輪が壊れるということは非常に不吉なことなのだ。結婚後の幸福がかかっている腕輪が、いきなり壊れてしまうなんてことがあるだろうか?プーローは自分の右手を咎めるような目で見た。神様!私の夫が長生きしますように!千年万年生きますように!プーローは心の中でお祈りをした。そのときプーローは、腕輪を通しているときに本当に腕輪が壊れてしまった女の子がいたことを思い出した。近くに立っていた女性たちは「ああ、神様」と言って、神様に彼女の夫の無事祈願をし始めた。そして宝石屋に言って、金の細い糸で壊れた腕輪を結ばせて、その女の子に再びその腕輪を付けさせた。まるで、彼女の夫の切れた生命線をつないだかのようだった。
プーローが吉兆凶兆の空想に耽っている間に、左にあったピーパルの木の後ろから、一人の男がプーローの前に立ちはだかった。プーローは、心臓を金槌で叩かれたように驚いた。見ると、それは彼女と同じ村に住むラシードだった。ラシードの年齢は22歳〜24歳に見えた。はちきれんばかりの若々しさが、彼の顔に溢れていた。
プーローは、ラシードの大きな瞳に自分の顔が映っているのを見た。その顔は震えていた。彼女はかすかな悲鳴を上げて、ラシードから逃げ出した。
プーローは走りに走って、友達のところまで辿り着いた。もう彼女は自分の家の近くまで来ていた。プーローは呼吸が収まらなかった。ラシードが彼女の手に触れなかったことは不幸中の幸いだった。彼はしゃべりもしなかった。
「いったいどうしたの?お婿さんがいたの、それとも虎にでも会ったの?」友達は彼女をからかったが、まだプーローの息は整わなかった。
「虎に会ったら、ただ引き裂かれて食べられるだけだけど、もしも熊が一人でいる女の子を見たら、その子を殺さずに連れ去るって話よ。洞穴に連れ去って、自分のお嫁さんにしちゃうのよ。」一人の女の子がそんな話を聞かせた。
プーローは今度は背筋がゾッとした。熊にさらわれた女の子の気持ちはいったいどんなだろう?それを考えただけでプーローの顔は青ざめた。プーローはラシードの大きく見開いた目を思い出した。
プーローは自宅に帰り着いた。友達はぺちゃくちゃ話をしながら遠くへ行ってしまった。
またある日、プーローとその友達は、畑でサトウキビを刈り取っていた。プーローはサトウキビの束を近くの水車のところへ洗いに行った。小さなサトウキビの茎を折って、2、3本口に含んでいた。すると、近くの木の下にラシードが立っているのを見つけた。まるで彼女は身体から命が抜き取られたかのようになった。恐怖が彼女の顔を覆い尽くした。
「おいおい、どうして怖がるんだい?俺はお前の奴隷だっていうのに。」今日はラシードが言葉を発した。そして彼はニヤリと笑った。
プーローは、今にもラシードが熊のように彼女に飛び掛ってくるのではないかと感じた。熊の爪のような、彼の長い長い指が、彼女の首をまさぐるだろう、そして彼は自分を引っ張って連れ去ってしまうだろう。そして・・・そして・・・。
幸運にも、前方から2人の農夫がこちらへやって来るのが見えた。ラシードはそのまま立っていた。プーローは赤いトマトが実っている花壇を飛び越えて、急いで友達のところまで戻った。
その日、プーローは恐怖で震え続けた。ずっと友達の手を離さず歩いた。影にすら怯え、何でもない物音に身震いした。
プーローは母親にも父親にもそのことを話さなかった。友達は、両親に話すべきだと言っていた。若い女の子が道を歩いているのを、男がじっと見るのはよくあることだ。口では自分のことを奴隷だと言ったり、召使いだと言ったり、無意味なことを口走るのもよくあることだ。男が何を言おうと、犬がほえるのを怖がって外を歩くのをやめるのは馬鹿馬鹿しい!
その日、村の6〜7歳くらいのある男の子が、狂った犬に噛まれた。近所の女性たちが集まって、男の子の傷口に赤唐辛子を塗った。唐辛子の辛味によって、犬の牙の毒が消えるのだ。プーローがこの話を聞いたとき、その赤唐辛子を粉にしてラシードの目に放り込んでやろうかと考えた。彼女はラシードの目のことを考えただけで、毒が全身に回るように感じた。
次の日、友達がプーローの腕を掴んで引っ張ったが、プーローは畑へ出掛ける勇気が沸かなかった。
プーローの結婚式も日に日に近づいていた。プーローの父親はギー(油)とマイダー(小麦粉)を集めて、家に置いていた。プーローの母親は、黄色いシルクで縁取られた赤い花の模様で、花嫁の嫁入り道具のタンスを飾った。シャムから買って来た絹をダウリー(花嫁持参金)のための白いトランクいっぱいに詰め込んだ。母親は、チュナリーの端の飾りを撚っている内に指が痛くなってしまった。奥の部屋には、プーローのダウリーのために、真ちゅう製の51個のバルタン(壺)をピカピカに磨いて置いていた。当時、田舎では手工芸の伝統があった。プーローは自分で花柄で装飾されたベッドの敷物を作った。彼女は花の刺繍を習っていた。また、自分の手でダウリーのために籠や腰掛を作った。
ある日、プーローはほうれん草の湿った葉を切っていた。プーローの母親は、より糸で作られた腰掛に座って、息子にミルクを飲ませていた。プーローは土製の鍋をバーン(草の一種)のかたまりでよく洗い、ほうれん草を水で2回洗って、鍋の中にチャンナ豆と一緒に入れた。火の上の鍋ではミルクが沸騰していた。プーローはコンロに2、3の木片を足して、その上にほうれん草の入った鍋を乗せた。
プーローの結婚式がもうすぐそこに迫っていた。プーローの母親は、サスラール(花嫁の義父の家)から誰かがプーローを見にやってくるのを、今か今かと待っていた。プーローは美しく、行儀のよい女の子だった。料理は子供の頃から身に付けていた。プーローの友達は、プーローはもう花盛りだと言っていた。プーローの白く透き通った顔はまばゆいほどだった。母親は、プーローがサスラールへ行ってしまったら、みんなすすり泣くだろうと考えながら、彼女の方を見た。すると、自然と彼女の目に涙が溢れてきた。娘を持つ母親は、娘の結婚式に泣かずにはいられない。座りながら、プーローの母親は歌いだした。
抱くなら抱いて 心をこめて
話すなら話して でもたったひとつのことだけ
長い話はいらない どうして私を娘として生んだのか教えて
今日の夜 私はあなたのもとを去らないといけない
(娘が結婚式の前に母親に対して歌う民謡)
プーローの母親の心は悲しみでいっぱいになった。プーローは台所で炊事をしながら、母親の歌を聞いていた。プーローの心に、別れのときの悲しみがもうやって来てしまった。プーローの母親は続けて歌った。
私は糸をつむぎ、水を汲み
衣服に刺繍をした
でも息子には家と土地を与え
娘には別れを与える
プーローは母親の元へ走り、彼女に抱きついた。母親も娘も大声を上げて泣いた。女の子の成熟は、母親との別れを意味するのだ。
プーローの母親は気を持ち直し、娘の肩にキスをした。夕闇が彼女たちの庭を覆いつつあった。プーローの母親は、そのとき家にもうひとつ料理を作るための食材が尽きていることに気が付いた。いつサスラールから誰かやって来るか分からなかった(サスラールからのお客さんのために、少し豪華な食事を作る必要があった)。
彼女はプーローに、妹を連れて畑へ行って、4つほどオクラを持ってくるように、そして米を一握りと砂糖を入れて、甘いご飯を作るように言いつけた。
プーローの心も今日は悲しみでいっぱいになっていた。彼女は妹を連れて外へ出た。
プーローはオクラを摘んで、2、3本のサトウキビを刈り取り、妹を連れて引き返した。家に帰る途中、プーローは、母親との別れ、妹との別れ、そしてかわいい弟との分かれについてずっと考えていた。そのとき稲妻のごとくプーローの脳裏にラシードのことが浮かんだ。もしラシードが現れたらどうしよう?
プーローは駆け出した。「プーロー姉さん、どうして走るの?」プーローの妹はすぐに息を切らしてしまった。
プーローの後ろから、一匹の馬が走ってきた。プーローが避けようとした瞬間、馬なのか馬に乗っていた人なのか分からないが、何かがプーローの右肩にぶつかった。プーローが転びそうになったとき、誰かが彼女の肩を掴んで馬の上に引き上げた。プーローの悲鳴は、飛ぶように走る馬の蹄の音と共に、一瞬の内に遠くへ消えてしまった。彼女の妹はただ震えて立ち尽くしていた。
プーローは気を失っていたため、その馬がどこから来て、誰が乗っていて、どれだけ走ったのか、全く分からなかった。
プーローに意識が戻ったとき、彼女はどこかの部屋のチャールパーイー(インド式ベッド)の上に横たわっていた。四方は壁で囲まれていた。前方には閉ざされた扉があった。
プーローは全て思い出した。彼女は壁を思いっきり叩いた。彼女は扉を思いっきり叩いた。
疲れ果てたプーローは、チャールパーイーに横たわった。そして再び意識を失った。
プーローに再び意識が戻ったとき、誰かがプーローの頭に温かいギー(油)を塗っていた。プーローは考えた。多分頭のそばに座っているのは母親だろう、そして多分私は高熱が出たのだろう。
「ああ、お母さん!」プーローの口から声が漏れた。
「俺の過ちを許してくれ、一度でいいから意識を取り戻してくれ、プーロー!」誰かが近くで言った。
高熱で身体が焼けるように熱かったプーローは、頭を起こして見た。ラシードがベッドの隅に座っていた。プーローは、アッと叫んで気絶してしまった。
プーローは、黒い毛皮で覆われた一匹の熊が、彼女の髪を爪で弄んでいるのを見た。プーローはどこかの洞穴に横たわっていた。彼女はどんどん小さくなり、熊はどんどん大きくなった。熊は毛むくじゃらの腕でプーローを抱き込んだ。
プーローは目を大きく見開いて見た。誰かが彼女の足を揉んでいた。また、誰かが彼女の肩を揉んだ。また誰かが彼女の口に手の平いっぱいの水を飲ませた。
ここは熊の洞穴なのか、ラシードの家なのか?プーローは目まいがした。そしてプーローはまた眠ってしまった。
プーローは母親や村のことなど全てを覚えていた。彼女は、この洞穴に横たわって何年も経ってしまったかのように感じていた。ラシードの顔を見るのは何とか慣れた。ラシードは彼女に何も言わなかったし、彼女もラシードを呼ばなかった。横たわっているプーローの口に、ラシードは熱いサトウキビの汁とギーを匙で流し込んでいた。ときにプーローの首の下まで垂れてしまうこともあれば、ときに吐き出してしまうこともあった。
プーローは全身に力をこめて、壁にもたれかかりつつ起き上がり、チャールパーイーの上に座った。
「私はどこにいるの?」プーローは聞いた。
「俺のそばだ。」ラシードはチャールパーイーのそばの腰掛に座っていた。ラシードはうつむいていた。今日の彼の目は、大きく見開いて彼女を見つめていなかった。
「どうして私をここに連れてきたの?」プーローは勇気を出して聞いた。
「それはまたおいおい教えるよ。」ラシードはそれだけ言って、立ち上がって外へ行ってしまった。プーローは静かにチャールパーイーの上に座っていた。
このとき部屋の扉は開いていた。扉の外には小さな中庭があり、その先に小さな玄関があり、そして外へ通じる扉があった。
プーローは震えながら立ち上がった。彼女は四方の壁を眺め渡した。彼女は、この四方の壁のどれかが突然飛び出してきて、彼女の腕を掴んで、チャールパーイーに押し倒すのではないかと恐れていた。しかし壁はピクリとも動かなかった。プーローは外の中庭にやって来た。
中庭の隅にコンロがあり、火がくすぶっていた。そばには鍋やフライパンが散らかっていた。隅には水壺が置かれていた。しかし人影は見当たらなかった。
プーローは震える足を前に進めながら、玄関まで辿り着いた。表へ通じる扉のそばに立ち、一度後ろを振り返って、また扉の方を向いた。
しかし家の扉は、プーローの運のごとく閉ざされていた。プーローは閉ざされた扉に頭を打ち付けた。しかし扉は、プーローのうつむいた頭にも、青ざめた顔にも、濡れそぼった瞳にも同情を示さなかった。
服のすそで涙を拭って、プーローは扉から引き返した。水壺から水をすくって自分の目にかけた。そしてプーローは、扉を叩けば、誰か近所の人か、通りがかりの人の耳に音が届くかもしれない、と考えた。
プーローは中庭を囲む高い壁を見上げ、今一度勇気を振り絞って、扉を叩き始めた。プーローは扉の隙間から外を覗いてみた。表は物陰ひとつない草原だった。家も倉庫も見当たらなかった。プーローは、どこだか分からないようなジャングルの中に自分がいることを考えただけで疲れ果ててしまった。
プーローが扉のそばで立っていると、外から扉が開いた。ラシードが中に入ってきて、扉を閉じ、錠をかけた。プーローはその場に座り込んでしまった。
「プーロー!どうして外に出てきたんだ!中に入って何か食べろ!もう2日も何も食べてないんだぞ!」ラシードは早口で言った。彼はプーローの手を掴むこともなく、彼女の方を大きな目で凝視することもなかった。
「私を助けて、ラシード!私を家に帰して!」プーローは彼の足元に伏して言った。
このときラシードは、棍棒のような腕でプーローを立ち上がらせ、プーローをギュッと抱きしめた。
「俺の心の炎を誰が消してくれるんだ?」ラシードは手足をばたつかすプーローを強く抱きしめ続けた。
日は沈み、また日が昇った。ラシードはまた黙り込んでしまった。扉はいつものように閉ざされていた。ラシードはいつものように見張っていた。
ラシードは時々外出をした。1、2時間すると帰ってきた。プーローはずっと閉じ込められていた。やがて、ラシードは夜になると、プーローを連れて外を散歩するようになった。その家の他にこの草原一帯には何もなかった。ラシードはこの草原のそばに庭園を所有していた。この家は多分その庭師のものだろう、とプーローは考えた。庭園には庭師がいるはずだ。しかしプーローは庭師らしき人影を一度も見なかったし、物音すら聞かなかった。プーローは幾日も幾夜もその家で過ごした。プーローが唯一満足していたのは、ラシードが彼女に嫌なことを全く言わないことだけだった。プーローの尊厳はまだ保たれていた。だが、プーローの懇願と罵声は、ラシードに何の効果も与えていないのは確かだった。
プーローの計算では、閉じ込められて既に15日が過ぎ去っていた。
ある日、ラシードは赤いシルクの布をプーローの前に置いた。以前にもラシードはプーローの気持ちを動かすため、綿の衣服を買ってきた。しかし今回ラシードは赤いシルクの布をプーローの前に置きながら言った。「明日の朝、身体を洗って準備をしろ、マウルヴィー(イスラーム教の僧侶)が来て俺たちの結婚式を挙げてくれるから。」
プーローは気を失いそうになった。今まで起こらなかったことが、遂に起こってしまう!
その日、プーローはラシードの足元にひれ伏して懇願した。
「プーロー!落ち着け!意味も無く俺に罪をなすりつけないでくれ!アッラーに誓って、俺はお前の涙を見るに耐えないんだ。」ラシードは顔を背けて言った。
プーローは、ラシードが本当にそんな思いやりのある男だったとしたら、どうして自分をこんなひどい目に遭わせるのか理解できなかった。
「ラシード、アッラーに誓うなら、どうして私にこんなひどいことをしたの?」
「プーロー!俺とお前の間には、深い因縁があったんだ。それを知ってもどうにもならない。起こったことは仕方ないだろう。俺はお前を絶対に不幸な目に遭わせたりしない。」
プーローは驚き、怯えた。いったい彼はどういう人間なのか?「プーロー!俺のシェーク家とお前のシャー家の間には、先祖の代からいざこざがあったんだ。お前の祖父は500ルピーの借金の代わりに俺たちの家を差し押さえて、家族を家から追い出したんだ。それだけじゃなく、お前の家の者は俺たちの家の女たちに罵詈雑言を浴びせ、しかもお前の祖父の長男は、俺の祖父の長女を三夜に渡って拘束したんだ。俺の祖父の目の前で全てが起こった。でも、そのときのシェーク家は、押しつぶされたサトウキビのように力がなかった。みんな血の涙を呑んで耐えていたんだ。でも、俺の祖父は、親戚一同にコーランに誓わせることを忘れなかった。この復讐を必ずすると。次の世代になって、その誓いを実現させるときが来た。お前の結婚話が村で広まったから、俺の叔父さんたちの心に、昔の復讐の誓いが蘇ったんだ。叔父さんたちは俺に、シャー家の花嫁を結婚前にさらって来るよう誓わせたんだ。」ラシードは黙った。
プーローは静かに自分の運命の話を聴いていた。
「プーロー!お前を初めて見た日、神様もご存知だろう、俺はお前に恋してしまったんだ。俺は恋に狂い、シェーク家の血に突き動かされて、お前をさらって来てしまった。でも、俺はお前の悲しみを見ていられないんだ。」ラシードは言った。
プーローは両手で頭を抱えた。
「あなたの叔母さんを私の叔父さんがさらったのは分かったわ。でもラシード!私が何をしたって言うの?ああ!私は何の関係もないのに!」プーローの顔は溢れる涙で濡れていた。
「俺もそう言ったさ。でも俺の叔父さんが俺に無理矢理強要したんだ。」
「じゃあラシード!叔父さんが怖くて私をこんな目に遭わせたっていうの?」プーローは泣きながら言った。
「プーロー!俺は死ぬまでお前の幸せのために生き続けるよ。」ラシードは声を詰まらせて言った。「俺はお前の叔父さんみたいに、3晩いいように扱って放り出すようなことはしないよ。」
「ラシード!一度でいいからお母さんに会わせて!」プーローはこれを言うのがやっとだった。
「おいおい!今頃お前の家がお前を受け容れるはずがない。ヒンドゥー教徒がお前の家をのけものにするだろう。お前はもう15日間もこの家にいるんだ。」
「でも私はただあなたの家で食べ物を食べていただけだわ。私は・・・」プーローはそれ以上言わなかったが、プーローが言いたかったことをラシードは理解した。
「そんな話、誰が信じるんだ、プーロー!これは俺のせめてもの心遣いなんだ。まず結婚式をちゃんと挙げてから・・・」ラシードは濡れた目でプーローを見た。
プーローの目の前を、許婚が通り過ぎてしまった。プーローは身体に油を塗られるはずだった、プーローはマーイー(結婚式に先祖に捧げるお菓子)を捧げるはずだった、プーローはターメリックを塗られるはずだった、プーローは本物の象牙の赤い腕輪を身に付けるはずだった、プーローは貝の首飾りをカシャカシャ鳴らすはずだった、プーローはシルクの衣服を着るはずだった、プーローは美しく化粧をするはずだった、プーローは輿に乗るはずだった、プーローは、プーローは、プーローは・・・。
プーローは無邪気だった。彼女には、母親の心が石のようになってしまうことが、父親の心が鉄のようになってしまうことが理解できなかった。父親が自分の娘を家から追い出すことが、家の扉が彼女を拒否することが、理解できなかった。
「私が家に帰って来ないのに気付いたとき、お父さん、お母さんはどんな気持ちだっただろう!妹は・・・!」プーローは運命が彼女の頭上で砕け散った気分だった。
「彼らは泣いて震えているさ、俺のお祖父さん、父さん、叔父さんが、俺の叔母さんが連れ去られたときに泣いていたのと同じように。警察も血眼になって手がかりを捜したが、遂に諦めたよ。何も手がかりは掴めなかったようだ。もっとも、どうやって手がかりが掴めるっていうんだ?警察は500ルピーも受け取っているんだ。」ラシードは笑いが止まらなかった。「お前も知っての通り、いまや俺たちの力は強大だ。村は全てイスラーム教徒になった。ヒンドゥー教徒が俺たちを責めたりできない。誰でも自分の命と財産が惜しいのさ。奴らは何も言うことができない。もし奴らの誰かが俺たちの家に指を立てたら、俺たちは奴らを生かしちゃおかない。」ラシードは笑いながら言った。おそらく彼の心には、古い復讐の炎が燃え上がっていたのだろう。
プーローは彼の顔に強い嫌悪を感じた。彼女の人生は滅茶苦茶になってしまった。人生は終わってしまった。来世までも終わってしまった。おそらく両親はチャットーアーニーに娘を残して、シャムへ帰ってしまっただろう。
「私の両親はもうシャムへ帰ってしまったの?」プーローは嗚咽しながら聞いた。
「いや、まだだ!」ラシードは答えた。
「私はどこにいるの?私の村からどれくらい遠くにいるの?」プーローは聞いた。
「お前は村の裏にあるマーゴーキヤーンの井戸の向こうの、俺の庭園にいる。多分お前は自分の村に帰ろうと思っているんだろうが、それは今は無理だ。ちょっと落ち着くまで待って、半年経ったら、お前をそこへ連れて行ってやるよ。」ラシードは微笑んだ。
プーローは黙ってしまった。ラシードは皿にプラーオ(炊き込みご飯)をよそって彼女の前に置いた。ラシードは外出するとき、誰かに食べ物を作ってもらっていた。プーローはそれを知らなかった。
その日、プーローの心に胸騒ぎが起こった。彼女は、自分の勇気が消え去ってしまうことを恐れた。だからプーローはプラーオを2、3杯掻き込み、ポットの水全てを飲み干してしまった。
その夜、プーローは勇気を振り絞って逃げ出すことを決めた。ラシードのベッドに、扉の鍵が置いてあった。プーローは静かにそれを取って、扉を開けた。今にラシードが目を覚ましてしまうのではないかと、彼女の心臓ははちきれそうだった。幸か不幸か、ラシードの目は開かなかった。
表の夜の静寂を見てプーローは身体を震わせた。一度彼女の心には、ラシードの元に戻ろうか、という考えが浮かんだ。夜道を歩いてチャットーアーニー村まで辿り着けるか不安だった。夜の闇の中、ラシードよりも危険な男に捕まってしまったら、どうなるか分からない。しかしプーローは母親の顔を思い出した。父親の顔を思い出した。兄弟姉妹を思い出した。プーローは、マーゴーキヤーンの井戸に通じていると思われる道を歩き出した。恐れで身体を震わせながら彼女は歩き続けた。
夜の深い闇が次第に薄らいできた。マーゴーキヤーンの井戸に辿り着くことができた。プーローは明け方の青い闇の中に、チャットーアーニー村の見慣れた家屋を見つけた。
その瞬間、プーローは残された力を全て振り絞って走り出した。
プーローはチャットーアーニー村に辿り着いた。自分の家へ続く道を進み、暗闇の中、自宅の扉を見つけた。
プーローは扉を叩いた。中から誰かが扉を開けた瞬間、プーローは玄関の床に倒れこんでしまった。彼女は全身の全ての力を使い果たしていた。彼女は全力で走って来て息を切らしていた。プーローの身体には少しの力も残っていなかった。
プーローの視界は暗くなっていた。彼女は、母親を、父親を見た。彼らは手に灯りを持って彼女のそばに立っていた。彼女は傷ついた小鳥のように、玄関の床の上ですすり泣き始めた。彼女は、母親の目から涙が流れているのを見た。母親はプーローを抱き上げた。プーローは母親の胸の中に自分の頭を押し付けた。まるで壊れた関係を再び結び付けようとするかのように。プーローの母親は大声で泣き始めた。
「人が集まってくるだろう!」プーローの父親は、妻の肩を揺らして言った。プーローの母親は自分の服の裾を自分の口に押し込んだ。
「娘よ、なんてことだ!もうお前のために何もしてやれない!」父親の声が聞こえたが、プーローは顔を母親の胸の中にうずくめ続けた。
「もうすぐシェーク家の者どもがやって来て、我々の子供たちを皆殺しにするだろう。」
「私をシャムに連れて行って!お願い!」プーローは母親の胸の中から口だけを離して嘆願した。
「我々はお前をどう扱えばいいんだ?お前と誰が結婚するというのだ?お前の人生はもう終わったんだ。我々が今何かしたら、我々は血の一滴まで残らず消されてしまう!」
「それなら、私を殺して、お願い!」プーローはむせび泣きながら言った。
「ああ、プーロー!お前が死んでいたらどんなによかったことか。さあ、どこかへ行きなさい。シェークが来てしまうわ。みんな殺されてしまうわ。」母親は心を鬼にしてプーローに言った。
プーローはラシードの言った言葉を思い出した。「おいおい!今頃お前の家がお前を受け容れるはずがない。」ラシードは正しいことを言ったのだろうか?
今度はプーローは許婚ラームチャンドを思い出した。婚約式は?結婚式は?私は彼の何でもなかったの?彼は私のこと何も聞かなかったの?
プーローはもうこれ以上生きたくはなかった。彼女は、全ての道が閉ざされても、死の道だけは開いていると考えた。彼女は立ち上がって外へ出た。
母親も父親も彼女を止めなかった。プーローはそのまま歩き続けた。彼女は家への道を、人生を取り戻すためにやって来た。生きるために、両親に会うために。震え怯えながら来たのだった。彼女は家から戻る道を、死に会うために歩いていた。彼女の心にはもはや何の恐れもなかった。死の他に彼女には道がなかった。
プーローは迷いなくマーゴーキヤーンの井戸の方へ歩いていた。夜明けの光が、道を浮かび上がらせていた。
前方からラシードが歩いてきていた。プーローの足が止まった。死すら彼女の前に扉を閉ざした。
プーローは、この15日間の日にちが、自分の身体から全ての肉を取り去って、後にただ骨だけが残っているように感じた。彼女の形も、心も消え去っていた。ラシードが来てプーローの腕を掴んだ。彼女は彼と一緒に歩き出した。
3日後、マウルヴィーがやって来た。2、3人の人が集まった。マウルヴィーはラシードとプーローの結婚式を挙げた。その後、ラシードはプーローに、両親は無事にシャムへ立ち去ったことを伝えた。
チャットーアーニーの名前を聞いただけでプーローは目まいがするようになった。ラシードにも彼女の気持ちが十分理解できた。プーローをチャットーアーニーへ連れて行くことは、非常に危険だった。ラシードは周辺の村のヒンドゥー教徒の怒りに火をつけることを恐れていた。だが、プーローをさらってから1ヶ月が過ぎようとしているものの、誰もそのことを取り沙汰しようとしなかった。他人の火の中に誰が飛び込むだろうか?これは先祖代々から続く復讐だった。
ラシードの母親も姉妹も既に死んでしまっていた。兄弟と叔父がいた。ラシードはプーローに、そこから数キロ離れたサッカルアーリー村へ引っ越すことを告げた。そこには縁戚のラヒームの土地があった。おそらく、ラシードの土地をラヒームの土地と交換でもしたのだろう。
今やプーローは、運命が自分にどんなひどい仕打ちをしようと、耐え忍ぶ覚悟をしていた。血のつながった両親があんな仕打ちをしたのだ。もうこの村に何の未練があろうか!こんな土地からは立ち去って、新しいところへ行きたかった。
ラシードは家のように大きなトランクと荷物を持って、プーローを連れてサッカルアーリーへ向かった。まるで目をつぶって歩いているかのごとく、プーローは大人しくラシードに従って新しい村へやって来た。村に着いてすぐ、彼らは新しい家に住み始めた。おそらくラシードが予めラヒームに頼んで用意させておいたのだろう。ラヒームの家は、彼らの家からかなり遠かった。それでもラヒームの家の女性たちが彼女に会うためにやって来た。このときプーローは初めてラシードの親類の女性と会った。
プーローは、まるで迷子の仔牛のように彼女たちのそばに座っていた。彼女たちはプーローにとやかく話しかけなかった。家事に関わる2、3の話を質問しただけだった。
ラシードはプーローをプーローと呼んでいた。結婚式の日、プーローの名前はハミーダーに変えられていたが、まだ彼は慣れていなかった。
ある日突然、ラシードは一人の男を連れてやって来た。彼は腕に名前を刺青する仕事をしていた。その日、プーローの心に鋭い痛みが走ったが、ラシードに言われた通りに彼女は腕を前に出した。彼女の左腕には「ハミーダー(ムスリムの女性名、プーローはヒンドゥーの女性名)」という文字が、深い緑色の文字で刻まれた。ラシードもその日から彼女をハミーダーと呼ぶようになった。おそらくラヒームの家の者が彼にそうするよう言ったのだろう。
プーローはハミーダーになった。しかし今でも夜眠ると、彼女の夢の中には友達が現れた。夢の中で彼女は両親と共に遊んでいた。みんな彼女のことをプーローと呼んでいた。昼の光の中では、彼女はハミーダーになったが、夜の暗闇の中では、彼女はプーローのままだった。しかしプーローは考えていた。自分はプーローでもなく、ハミーダーでもない。自分はただの骸骨なのだ。ただの骸骨・・・。何の形もなく、何の名前もないのだ。
5、6ヶ月が過ぎ去った頃に、プーローの骸骨の中に、小さな命がうごめき始めた。
埃っぽい日だった。1日また1日、無為な日がプーローの目の前を通り過ぎていった。袋を敷いて、まるで石像のようにプーローは何もせず日を過ごした。
表の扉が開き、ラシードが中庭へ入ってきて立ち止まった。プーローはまるで足音も何も聞こえないかのごとく、まるで誰が来ても何も見えないかのごとく、そのまま座り続けていた。おそらくラシードは本当にプーローのことを愛していたのだろう、彼は黙ってプーローのそばに座った。
「何を考えてるんだい?」ラシードは片腕を彼女の肩に回した。今日のプーローは極度に落ち込んでいた。動くこともできず、しゃべることもできなかった。
ラシードはずっと彼女の世話をしていた。しばらくしてプーローは口を開いた。「私のお腹の中で、何かが内臓を引掻いているように感じるわ。」
ラシードは笑って彼女を励ました。ラシードはコンロでくすぶっていた火を強くして、プーローをそばに座らせて、自らウズラを焼き始めた。
「お前はどこにも行こうとしないし、誰にも会おうとしない。そんな態度じゃあ、どんな心優しい人でも気分を悪くするよ。」ラシードは、思い出したようにポツリとつぶやいた。
「どこへ行けばいいって言うの?私はどこにも居場所がないわ。」プーローは消え去ろうとする炎のような気持ちで言った。
「お前は家の女主人なんだ。もうすぐお前の家の庭で、子供が駆け回るだろう。俺のことはどうでもいいけど、責めて子供に心を閉ざさないでくれよ。子供がお前に何をしたっていうんだ?」ラシードはもうすぐ生まれる自分の子供のことを考えた。彼は子供を引き合いに出して、プーローに心を開くよう頼んだ。
プーローは、また豆のさやの中から出てきた虫のことを思い出した。それを見て彼女は吐き気を催した。彼女はその豆の近くにある豆を全て捨ててしまいたかった。
「おい、ウズラのカレーの中に豆を入れたいから取ってくれ」ラシードはプーローの前に散らばっている豆の方を見て言った。
「豆はもう全部料理したわ。もう豆の季節じゃないでしょう。バイサーク月(4月〜5月)になる頃だわ。」プーローは今日、豆を食べることができないことを知っていた。
「ああ、そうだ!明日はバイサーク月の大きな春祭りがあるんだ。」ラシードは驚いたように言った。
「バイサーク月・・・バイサーク月・・・」彼の声がプーローの耳の中で響き渡った。彼女は皿の上に小麦粉を置いてこね始めた。
「俺は今日、サトウキビの汁の入った麺が食べたいな」とラシードは言った。プーローは黙って家の中から麺とサトウキビの汁を持ってきた。
そのときプーローは昔の思い出を思い出していた。ある日プーローの母親は座って、小麦粉で麺を作っていた。そのときプーローは言った。「お母さん、私は機械で作った麺が食べたいわ。」すぐに母親は言った。「何言ってるの、あれはムスリムが食べるものなのよ。」
プーローはそれを思い出すと目に涙が溢れて来たが、その後、ついつい笑ってしまった。
ラシードが、彼女に笑った理由を尋ねると、プーローはその話を聞かせた。聞かせている内に再び彼女は泣けてきた。ラシードは恥ずかしそうに笑っていた。
次の日の朝、プーローが目を覚ますと、村にはバイサーク月の太鼓が鳴り響いていた。プーローは家事を終えてから、屋上に上がって遠くの村の春祭りを見物し始めた。
プーローは遠くに多くの人が集まっているのが見えた。長身でがっしりとした体格の農夫が、無地の腰布を巻き、油で光っている棒を持って、楽しそうにあちらこちら行き来していた。馬に乗っている人もおり、後ろに女性を乗せ、前に子供を乗せて歩き回っていた。多くの若者たちが、若さと力を誇示しながら、歌を歌いながら、話をしながら歩いていた。遠くの広場ではクシュティー(インドの相撲)が行われているだろう、ジャレービー(甘いお菓子)の店が出ているだろう、パコーラー(インドの天ぷら)のいい匂いが辺りに広がっているだろう。サトウキビの砂糖菓子、マイダー粉のケーキ、ミターイー(甘いお菓子)が、大きな皿の上に山盛りになっているだろう。
プーローの脳裏に突然、まるで誰かが彼女の頭を金槌で打ったかのように、ある考えが浮かんだ。彼女の母親は、3人の女の子の後に息子を産んだ。そしてその子にとって、これが初めてのバイサーク月になるのだ。
プーローはずっと立っていたが、やがて屋上に座り込んだ。お母さんは今頃弟に水を飲ませているだろうか・・・。どこかの川の水でバラの花を洗って、弟の小さなピンク色の唇に宛がっているだろうか・・・。お母さんは皆からまた祝福を受けているだろうか・・・。そして・・・そして・・・お母さんは、私のことを思い出してくれているだろうか・・・。
プーローの目には、次から次へと涙が溢れてきた。彼女は両手で頭を抑えて座り続けた。
若者たちの集団が、耳に花を乗せて、歌を歌いながら楽しそうに近くを通り過ぎて行った。誰かが地元の言葉でこんな歌を歌っていた。
井戸に座って歯を磨いている女の子
一生懸命歯を白くしている女の子
お前を見初めた男がやって来て
お前を連れて行ってしまうだろう
お前を連れて行ってしまうだろう
「全く、見初められた女の子の境遇を知らずに!」プーローはつぶやいた。
プーローは考えた。ラシードは私を好きになって、私をさらった。でも許婚のラームチャンドはどうして私のことを好きにならなかったの?私のことを誰にも聞かなかったのかしら?ラームチャンドに好きになってもらいたかったわ。私はラシードを自分で探したわけでもないし、お父さんお母さんが選んだわけでもないのに。
若者たちは笑って飛び上がって歩いていた。バングラー(パンジャービー・ダンス)を踊りながら歩いていた。方言でこんな歌を歌いながら歩いていた。
お前のアクセサリーのまばゆい輝きを見て
農夫が鋤を忘れてしまった
お前の濡れたスカートを見て
鳥が歌を忘れてしまった
どうか私を悩まさないでおくれ
通りすがりのお嬢さん
プーローは考えた。全ての歌は、美しい女の子のことだけを歌っている。全てのバジャン(宗教歌)は真実の愛のことだけ歌っている。でも、私のような女の子のすすり泣く姿を歌った歌がどうしてないのだろう?神様なんていないんだと歌ったバジャンが、どうしてないのだろう?
花盛りの女の子たちの集団が、若さを謳歌しながら歩いていた。少し離れて歩いていた若者の集団は、振り向きながら彼女たちの方を覗き見して笑っていた。おそらく彼女たちについて何か冗談を言っていたのだろう。もし、この若者たちが全ての女の子を一人ずつ馬に乗ってさらって行ってしまったらどうなるだろう、プーローは考え始めた。もしこの女の子たちをさらって行ってしまったら・・・。
猛暑の季節がやって来た。燃えるタンドゥール釜のように、大地は燃え上がっていた。
プーローは座ったり、立ち上がったり、寝転がったりして過ごしていた。今日は気分がよくなかった。彼女は頻繁に水を飲んでいた。近所に住む女性は彼女に言った。「とにかく水を浴びて頭をよく洗いなさい、いつ何があるか分からないからね。何かあったらお前も生きてられないよ。」
ラシードは、プーローの身体が綿のように白くなっていくのに気が付いた。彼女は全身に痛みも感じていた。ラシードは、チャットーアーニー村の道でプーローを馬の上に抱き上げて走っているときのことを思い出した。そのときはプーローの魂から叫び声が上がっていた。今日は彼女の血と肉から叫び声が聞こえるようだった。
ラシードはラヒームの家に、自分の畑で働いている男を送った。プーローを一人残して行く勇気がなかった。ラヒームの母親が来たときには、プーローの顔が激痛でゆがむほどになっていた。ラヒームの母親は、近所に住む産婆のレーシュマーを連れてきていた。レーシュマーはラヒームの孫たちの出産を手助けしたことがあった。
産婆は来るとすぐに古い敷物を敷いて、そのの上にプーローを寝かせた。プーローは、柔らかいチャールパーイー(インド式ベッド)から固い地面に寝かされたので、うめき始めた。
ラシードは玄関の敷居のそばに立っていた。閉ざされた扉の中から、歯がきしるようなプーローの長い長いうめき声が聞こえてきた。ラシードは、プーローの身体から、せめて半分の痛みでも自分の身体に移してしまえれば、と思っていた。プーローは一人で苦しんでいた。
産婆は縁飾りのあるウチワでプーローの顔に優しく風を送っていた。ラヒームの母親は、何度も何度もプーローの口に水を注ぎ込んだ。
外に立っていたラシードは、3度の悲鳴の後、赤ちゃんの産声を聞いた。プーローの叫び声はピタリと止んだ。彼女の苦痛は終わった。ラシードは安堵の溜息をついた。彼は中に入りたかった。産婆はおそらく赤ちゃんの世話で忙しいだろう、プーローの世話を俺がしなければ。プーローはまだ続けて泣いていた。プーローはまだうめき声をあげていた。しかし中には叔母さんや産婆がいた。彼女たちが中に呼ぶまでは、中に入ってはいけなかった。
しばらく時間が経った。プーローの声がまた止んだ。ラシードは急に不安になった。プーローは無事だろうか?なぜ彼女の声が聞こえないのだろう?
30分が過ぎ去った。産婆は外に出てきてラシードに言った。「おめでとう、男の子が生まれたよ。」
「彼女は大丈夫ですか?」ラシードが聞いた。
「何も心配いらないよ。こんな風に家族が大きくなっていくのさ。子供は天から降ってくるわけじゃないんだよ。」産婆は励ましと同時に冗談を言った。彼女はこうやって、数え切れないほど多くの女性たちの苦痛を和らげてきたのだった。
ラシードが中に入ると、プーローが横たわっていた。彼女は物憂げな目をしていた。彼女のそばに、白い布に包まれた息子が、親指を吸って寝転がっていた。
ラシードの心は高揚した。彼はプーローを勝ち取ったのだった。彼は人生の賭けの中でプーローの全てを獲得したのだった。プーローは、今やただの誘拐されてきた妾ではなく、家に放り込まれた女ではなく、彼の息子の母親であった。
ラヒームの母親の言いつけに従って、ラシードは1ルピーとサトウキビの砂糖菓子を、息子の上で回した。プーローは眠たそうに目を開け、ラシードを見た。
「次は何、ラシード?私はあなたに自分自身を捧げ、息子を捧げたわ。他に私から何を取ろうというの?」プーローは消え入りそうな声でラシードに言った。そして彼女は再び目を閉じた。
熱いサトウキビ汁とアーモンドの粉を数匙飲むと、プーローの身体に生気が戻った。プーローが見ると、彼女の息子の湿った顔が、彼女の腕にくっついていた。プーローの身体に痙攣が走った。彼女は、まるで湿った白い虫が彼女の身体の上を這っているように感じた。プーローは気分が悪くなった。プーローは、自分の腕に引っ付いている虫を潰して、遠くへ放り投げてしまいたかった。プーローは、刺さった棘を爪で挟んで抜き取りたかった。プーローは、刺さったゴークルーの木の棘を引っこ抜いて捨てたかった。プーローは、引っ付いているダニを引掻いて取り去りたかった。プーローは吸い付いたヒルを取り外したかった。
ラヒームの母親は、ラシードの家に一日中いた。プーローの息子が生まれて4日が過ぎ去った。
5日目になると、プーローはおっぱいが出るようになった。今まで産婆が綿の束を作って赤ちゃんの口にミルクを飲ませていた。今日はプーローが息子に自分のおっぱいを飲ませた。
赤ちゃんはプーローの胸の中にうずくまっていた。彼女の身体の中に包み込まれていた。プーローの心に別の感情が沸き起こった。プーローは息子を抱いて大声を上げて泣きたい気分になった。この子は、私の血で出来たオモチャだ。私の肉から出来た人形だ。この広い世界の中で、この子だけが私のものだ。私は二度とお母さんの顔を見ることができないだろう、お父さんの顔を見ることができないだろう、兄弟姉妹の顔を見ることができないだろう・・・私は・・・私はただ自分の息子の顔だけを見ることができる。息子の血の中に、お父さん、お母さんの血も混じっている。両親は私を捨て去ってしまったけれど、私の身体を流れている血は捨て去ることができない。私が産んだ子供の身体には、お父さん、お母さんの血が流れているんだわ!
赤ちゃんはプーローのおっぱいを飲み続けていた。プーローは、赤ちゃんが無理矢理彼女の身体の中からおっぱいを吸い取り続けているように感じた。無理矢理・・・無理矢理・・・この子の父親も彼女を無理矢理さらったのだった。その子は父親の息子でもあった。その子の身体には、父親の血も流れていた。父親の肉も混ざっていた。父親の容姿も持っていた。無理矢理この子は彼女の身体の中に生じ、無理矢理彼女の腹の中で育ち、無理矢理彼女の身体からおっぱいを吸い続けていた。
プーローは自分の額を触った。火であぶったレンガのように、彼女の額は熱かった。おそらく産褥熱が出ていた・・・プーローの脳裏にひとつの考えがグルグルと回り始めた。この子は・・・この子の父親は・・・全ての男は・・・男は・・・男は・・・女の身体を犬が骨をしゃぶるようにしゃぶり、犬が骨を噛むように噛む生き物だ。
幼い息子はプーローのおっぱいを飲み続けた。プーローの心は、水車の柄杓のように満たされたり空になったりした。
プーローの丸々とした男の子を、皆はジャーヴェードと呼んでいた。プーローはその子を、より糸の小さなベッドに寝かせて見守っていた。赤ちゃんは足を投げ出して、かぶさった布団を跳ねのけてしまっていた。プーローは子供の足に銀製の小さな鈴を付けていた。赤ちゃんが足を動かすと、その鈴の微かな音が、ベッドに響き渡るのだった。激しく足を動かすので、赤ちゃんの顔は赤くなってしまい、しゃっくりが出始めた。
プーローは子供の手を見た。子供の手の平はとても白かった。手の平の肉は、まるでプーローが幼少の頃シャムから帰って来る途中、カルカッタの市場で買った蝋人形のように、ふっくらとしていた。プーローはその人形のために衣服を作ってあげた。小さな真珠を糸で結んで、首にかけてあげた。ジャーヴェードの手は本当にあの人形の手のようにぷよぷよしていた。あの蝋人形は今でもどこかにあるだろう。プーローは、ガラスや土で出来た物の中にも、長生きするものがあるものだ、と考えた。おそらくプーローの妹の誰かが、あの蝋人形で今日も遊んでいることだろう。
夜明けにプーローは畑へ行っていた。その間、ラシードが息子を見ていた。ある日、まだ暗いうちに、プーローは畑から戻っていた。彼女は、村の外にあるムスリム用の井戸で手足を洗って、家へ向かっていた。そのとき彼女は、近所に住むカンモーという少女を見かけた。
冬がやって来ており、寒さが増していた。カンモーは水壺を岩の上に置いて立っていた。プーローが彼女のそばを通り過ぎると、カンモーは震える手で水の入った壺を持ち上げた。おそらく彼女の力では重過ぎて持ち上げるのが無理だったのだろう、水壺が彼女の肩で傾いた。壺を下から支えていた彼女の腕が、へし折れてしまいそうになった。右手で壺を支えながらカンモーは叫んだ。「ああ!」
プーローは立ち止まった。プーローはカンモーのそばへ行った。彼女は、12、3歳のこの少女の肩から壺を下ろしてやろうと思った。壺を運ぶのを手伝ってやろうと思った。カンモーは裸足で、いつもズボンの裾をまくり上げ、縞模様のシャツはつぎはぎだらけで、髪は雑草のようにボウボウとしていた。プーローは彼女をいつも遠くから眺めていた。今日は、プーローはブリキ製の壺に押しつぶされそうになっている彼女の肩から、壺を下ろしてやろうと思った。
「大変、遅れてしまうわ」壺の重みの下から、カンモーはまるでプーローに遅刻しないよう手助けを頼むかのように言った。
「まだ日は昇ってないわ。」プーローははっきりと答えた。
少女は何とか力を振り絞って、肩の上の壺を地面に下ろした。壺の口から水が飛び跳ねて、カンモーの肩にかかった。擦り切れたシャツを伝って、水の冷たさがカンモーの身体全体に広がった。カンモーは寒さで震えた。
プーローは立ち止まった。カンモーはプーローの方を見て笑った。ちょっと前には、彼女は遅刻する恐怖と壺の重みから恐怖の表情を浮かべていた。カンモーは常に怯えたような表情をしていた。プーローはそのとき彼女の大きな唇に浮かんだ笑みを見て、彼女は笑い方を知らないのだ、と思った。彼女はまるで他人をあざ笑っているかのように、唇をひん曲げていた。
「カンモー!お前は毎日どこほっつき歩いてるんだい!」カンモーを呼ぶ声がいつも聞こえていたので、プーローは彼女の名前を知っていた。
「今日は遅れてしまうわ、きっとしごかれるわ。」カンモーは再び水壺に手をかけた。まるで彼女にとって、時間に遅れないことだけが全てのようだった。彼女の顔から笑みが消え、元の怯えた表情に戻った。
「カンモー!お前を誰が呼んでるの?」
「叔母さんよ」とカンモーは言った途端、彼女の腕が水壺の重さでガクッと下がってしまった。水壺がよほど重たかったのか、それとも叔母さんの名前がよほど怖かったのか。
「もしよかったら、手伝ってあげるわよ。」プーローは言ったが、手を出そうとはしなかった。プーローは分かっていた。人々はプーローのことをハミーダー(ムスリムの女性名)と呼んでいた。ハミーダーはラシードの妻であることも知っていた。そしてカンモーはヒンドゥー教徒の娘だった。
「水壺が不浄になってしまうわ。」カンモーはぶっきらぼうに言った。
「水は不浄にならないわ。私は水には触らないようにするから。お前は行って外で壺を洗えばいいわ。」言いながらプーローは笑ってしまった。カンモーも笑った。しかし彼女は壺を下ろそうとしなかった。
2人が少し歩いた瞬間、カンモーの足がもつれてしまった。プーローは落ちそうになった壺を掴んだが、カンモーは砂利の上の倒れてしまった。カンモーは足を挫いてしまった。
プーローは壺を抱えながら、カンモーの足を掴み、手の平で足首の辺りをさすった。手当てをしている内に、カンモーはなんとか立ち上がれるようになった。プーローは水壺を持ち上げて、彼女と一緒に歩き出した。
「ああ、お母さん!」と言ってカンモーは泣き出した。プーローは、カンモーは多くの悲しみのために自分の死んだ母親に対して嘆き訴えているのだと思った。
「産むものは産んでおいて、逝っちまった」とカンモーの叔母が言っているのを、プーローは何度も聞いた。カンモーには父親も母親もいなかった。カンモーの父親は生きているかもしれないが、しかし噂では、彼女の父親は町で愛人と暮らしているらしかった。愛人はカンモーのことなど知らなかった。だから父親もカンモーとは何の関係も持っていなかった。プーローは、母親が死んでしまうと、父親は他人になってしまう、と考えた。カンモーのことを考えているうちに、次第に自分のことを考え出した。プーローの母親はまだ生きているのに、父親は他人になってしまった。母親でさえ他人になってしまった・・・。
もう村の景色が見渡せるほど明るくなった。次第に光が強くなり、彼女たちの家に続く道の交差点まで辿り着いた。2人は、プーローが壺を持っているのを誰かに見られるのを恐れた。カンモーは壺を自分で持った。彼女の足は震えていた。プーローは急いで歩き出した。そしてカンモーとは別の道へ曲がった。
その日の昼頃だった。プーローの子供は、何か気に入らないことがあるらしく、なかなか泣き止まなかった。プーローが子供を一生懸命あやしていると、扉が開いてカンモーが入ってきた。
プーローは近寄ってカンモーを抱きしめた。プーローは、自分の息子よりもカンモーを慰める必要があると感じた。カンモーの涙を拭ってあげる人は、どこにもいなかった。
カンモーの涙がプーローの腕にポタポタと落ちていた。プーローは、ジャーヴェードだけでなく、カンモーの母親にもなりたいと思った。カンモーはしゃくり上げて泣き始めた。プーローはカンモーを抱き起こして座らせ、再び彼女を胸に抱いて、彼女にキスをした。私はジャーヴェードの母親だけど、カンモーの母親にもなりたいわ・・・全ての孤児たちの母親になりたいわ・・・。私は親孝行の娘にはなれなかったけど、子供思いの母親にはなれればいいわ・・・。
カンモーはヒンドゥー教徒だった。そしてプーローは・・・プーローはイスラーム教徒だった。だが、彼女は自分のことを今でもプーローと思っていた。カンモーはプーローの家のものを食べることができなかった。しかしプーローはカンモーに自分の手で食べ物を食べさせたかった。プーローはカンモーに自分の手でミルクを飲ませたかった。
プーローは再びカンモーの足をさすった・・・手の平で温かいギー(油)を塗りこんだ・・・綿で温めた。
カンモーは急いで家に帰ろうとした。彼女の叔母の怒号は、彼女にとって鉄の棒に等しかった。カンモーは針を買いに行ってくると言って、ここに来たのだった。
プーローはカンモーにアーモンドの入ったサトウキビ・ジュースを飲ませ、家の奥から針を持ってきて彼女に渡した。
寒さは日に日に増してきた。人々は温かい冬服を着ていた。人々は綿の黒い刺繍布のベストを着ていた。人々は厚いショールで肩を巻いていた。
カンモーは成長を止められているかのようだった。彼女の身体に若さは表れず、彼女の身体を新しい衣服が覆うこともなかった。彼女の裸の足は、寒さで震え始めた。
プーローはカンモーのために新しい靴を作った。しかしカンモーにその靴を履かせるのは容易なことではなかった。
説得に説得を重ねた後、やっとカンモーはその靴を履いてくれた。カンモーは、向かいのサトウキビ畑でその靴を拾ったと、叔母に言った。叔母はその話を信じなかった。新しい靴をそんな風に捨ててしまう人が、この村にいるはずがない。しかし叔母は何も言わなかった。カンモーは靴を履くようになった。
しかし毎日何かを拾うことはできなかった。プーローは、カンモーの震える骨を見るに耐えなかった。
ただ夜の帳だけが、プーローがカンモーの2、3の水壺を運ぶのを手伝っているのを知っていた。
カンモーはプーローの家に毎日のように来るようになった。彼女は綿を巻き軸できれいにしたり、石臼でチャンナ豆をひいたり、すり鉢とすりこ木で香辛料を砕いたりした。プーローは彼女の仕事を手伝った。カンモーの叔母は彼女にたくさんの仕事を押し付けていた。幼いジャーヴェードは、カンモーになついた。カンモーが来ない日があると、ジャーヴェードの機嫌が悪くなった。カンモーは出来る限りプーローの家に来てくれた。
今やプーローとカンモーは、母親と娘のようにお互い口論をするようになった。女友達のように、お互い寄り合って座るようになった。
プーローは何度もカンモーのために何かを作ってあげようと思った。カンモーの痩せ細った体には、微かな変化が起き始めていた。カンモーの痩せこけた頬は丸みを帯びてきた。プーローの家に来てカンモーは髪をとき、プーローは彼女の髪に油を塗って、三つ編みにしてあげた。
ある日の朝、カンモーは顔を曇らせてやって来て、プーローを掴むと大声を上げて泣き始めた。プーローは注意深く彼女の顔を見た。カンモーの顔は、潰されたサトウキビのようにくしゃくしゃになっていた。
プーローは彼女を抱き寄せ、彼女の額にキスをした。しかしカンモーは少しも泣き止まなかった。涙で彼女のショールは濡れていた。涙で彼女の手は濡れていた。
「叔母さんがね、もし私があなたの家に行ったら、私を殺すって言うの」とカンモーは言って、プーローの胸でむせび泣いた。カンモーはまるで、プーローが彼女の支えであり、手を引いて叔母から引き離してくれる存在であるかのように、心の奥底から泣いていた。
「でもどうして?私が何をしたって言うの?」プーローは聞いた。
「叔母さんが言ってたの、あなたは家から逃げて来たんだって。そして私はいつかあなたのように逃げ出すんだって。」カンモーは泣き止んで言った。夜明けの光が明るくなり始めていた。プーローはもつれた綿のようになった。
プーローの心は次から次へと傷を負っていた。彼女の心と脳は、短い間に少なくとも10年は年を取ってしまった。プーローの年齢はまだ20歳にも満たなかったが、年齢が彼女に教えなかったことを、人生の鉄槌が彼女に教えた。高齢の哲学者のように、プーローは思慮深い人間になっていた。プーローは全く違ったことを考えていた。多くのことを考えていた。しかしプーローは自分の考えを口に出せなかった。強い水流によって生じた泡が、すぐに水に消え入ってしまうように、プーローの心には多くの考えや感情が生じては消えて行った。
時々プーローは、ラヒームの家の女性たちのところを訪ねた。彼女たちの家の近所に、青白い顔をした女の子がおり、プーローはそれを見て非常に驚いた。何度もプーローは彼女に話しかけようと思った。悲しみが悲しみとして彼女の顔に表れていた。その少女の悲しそうな顔には、大きな疲れ果てた目があり、その目がプーローの方を、まるで彼女もプーローが必要であるかのように見つめていた。その内プーローは、その女の子は2年前に結婚したことが分かった。ある人は、彼女に幽霊が憑り付いているといい、またある人は、彼女は精神を病んでいると言った。彼女に一体何が起こったのか、彼女の身体は非常に衰弱しており、彼女の顔は青ざめていた。
プーローはラヒームの家を行き来しながら、その少女の情報を集めた。少女の母親にも会い、彼女にショールを作らせるついでに、少女についてそれとなく聞いた。皆はその少女をターローと呼んでいた。
数日後、プーローは、ターローに頻繁に発作が起こるということを聞いた。最近ターローは自分の実家に帰っていたのだが、もうそろそろ彼女は自分のサスラール(義父の家)に戻らなくてはならなかった。プーローが聞いたところによると、ターローはサスラールから帰って来ると、いつもこのような状態になっているらしかった。しかもサスラールから帰って来るたびに、彼女の身体の肉は以前よりも少なくなり、彼女の身体の骨は以前よりもはっきり見えるようになるらしかった。
ターローを見た者は、あと2、3回サスラールへ帰ったら彼女は死んでしまうことが分かっていた。彼女の身体は、もうこれ以上痩せ細れないほどになっていた。彼女の骨は、もうこれ以上痛々しい気分にならないほどだった。しかし誰もそのことを言わなかった。サスラールの者も、実家の者も、何も言わなかった。
ある日ターローは一人で座っていた。プーローは彼女のそばへ行って座った。以前にも彼女と多少話をしていたが、今日はもっと話し込むため座り込んだのだった。
「ターロー!年の近い私になら教えてくれるでしょ、あなたに何があったの?」
「何もないわ。」
「誰かに脈を診てもらった?」
「ジャムとアルクのジュースを飲んで疲れちゃっただけ。」
「ターロー、教えてよ、どうして自分の命を削ってるの?」
「地面の負担が少しは少なくなるからいいでしょ、お姉さん!あなたが心配する必要あるの?」
「地面にどれだけ多くの負担がかかっていることか、あなたがいなくなったって何も変わらないわよ。あなたがいなくなったら、お母さんがどうなることか。お母さんは多くの困難を克服してあなたを育てたのよ。」
「育てたでしょうよ。」ターローは無頓着に言った。「私が死んでも、2、3日泣いて、すぐに泣き止んじゃうでしょう。全くおめでたいこと!」
「そんなことないわ、お母さんに言いなさいよ、あと数日は家に残らせてほしいって。」
「何の違いがあるの!ここもあそこも同じよ!」
「でもね、女の子をいつまでも家に置いておくことはできないのよ。」
「女の子?・・・フンッ・・・」ターローは黙ってしまった。ターローは、何か気に食わないことがあり、何か言いたそうにしていたのだが、何も言うことができなかった。
「女の子が何よ、お父さんとお母さんの言いなりになるだけじゃない。」ターローはしばらく後に言った。
「あっちの水はどう?」プーローは聞いた。
「悪くたって、いいって言わなければならないでしょう。」ターローは答えた。
「多分あなたは向こうの水が合わなかったんでしょう。」プーローは何とか話を続けるために言った。
「女の子はどんな水でも飲まなければならないわ。」ターローが言うと、プーローは目を丸くした。
「ターロー、私はあなたの味方よ。どうして何も教えてくれないの?」プーローは、ターローが心を開ける家族のような言い方で言った。
「私が何を言うことができるの!神様は女の子に何かをしゃべる言葉さえ与えてくださらなかったんだわ。」
「そうね、ターロー!」
「お父さんとお母さんのところに私の居場所はないわ。なぜって女の子は結婚したら余所者になってしまうもの。私の夫のところにも、私の居場所はないわ。夫の心と家には、別の女がいるんですもの。」
「じゃあターロー、あなたの旦那さんは既に既婚だったっていうの?それならなんであなたの両親はあなたをその人と結婚させたの?」
「お父さんもお母さんもそのことを知らなかったの。彼も結婚はしていなかったわ。彼はただその女を家に住まわせていただけ。」
「でも、彼の両親は知っていたでしょう?」
「みんな知っていたわ。その女は同じカーストじゃなかったの。目下のカーストだったの。両親は、同じカーストの者じゃないと結婚してはいけないって言ってたの。」
「でも彼らは、嫁がどんな気持ちになるか考えなかったの?」
「他人の悲しみなんて誰が気にするの?食べ物と衣服があって、仕事をしなくていいなら、不満を言う嫁なんていないだろうって言っていたわ。」
「女は食べ物と衣服があればそれで満足ということ?」プーローは言った。
「私は怒りで腹が煮えくり返りそうだわ。あなたは知らないけど、みんなは知ってるわ。プーロー姉さん、2年が経ったわ、その間、食べ物と衣服のために私は自分の身体を売っているんだわ・・・見て、私はもう売春婦なのよ・・・売春婦なのよ・・・。」言いながらターローは倒れこみ、彼女の拳が縮んだ。彼女は白目を剥き、彼女の身体は竹のように曲がってしまった。
プーローは怖くなった。ターローの家にはそのときに誰もいなかった。プーローは何をしたらいいのか知らなかった。彼女は恐れ、うろたえた。彼女はターローの脚や肩を揉み、彼女の足をさすり始めた。
ターローに意識が戻った。
「私に触らないで、私は売春婦なの、あなたは知らない・・・あなたは知らないのよ。」ターローはこんなことを言い始めた。
プーローが、まだ彼女に意識が戻っていないのでは、と考えていたときに、ターローの母親がやって来た。
「ああ、なんてこと、どうしましょう、私たちは運命からひどい仕打ちを受けたっていうのに、この子はまたおかしなことを言って私たちを困らせるつもりだわ。」ターローの母親は困った顔をして座った。プーローは黙っていた。
「この子も、この子の兄も、私たちの命を縮めてしまったわ。兄はラーハウル(ラーホール)大学で勉強した挙句、妹にも訳の分からないことを教えて頭をおかしくさせてしまった。ほら、なんて馬鹿なことを言ってるんでしょう。」ターローの母親は、また悲しそうに言った。
「おばさん、可哀想に彼女はとっても不幸な境遇にいるわ。」プーローは言った。
「私たちは娘を嫁に出したんだよ。もう何の関係もないんだよ。私たちが何を言うことができるの!娘を幸せにするのも、不幸にするのも、夫の仕事だからね。」ターローの母親は言った。」
「私の顔には錠がかけられ、足には足枷がかけられているわ!神様は私を牢獄に閉じ込めてなんかいないわ!私を監禁するために神様が存在してるんじゃないわ!でも神様は私の足だけに縄をかけているんだわ!」ターローは拳を握り締めた。彼女の足はまた曲がってしまった。母親は彼女の顔に水をかけ、彼女に手で水を飲ませた。
プーローは驚いてしまった。今日彼女は人生で初めて、女の子がこんな風に考えることができ、こんな風にしゃべることができるということを知った。同じ考えがプーローの心の中にも浮かんでは消えていた。しかし彼女は口に出すことができなかった。
「これは欺瞞よ、ただの欺瞞。私はまだ結婚なんてしてないわ、お母さんは嘘をついてるのよ。私を触らないで!どっか行って!」興奮したターローは自分の足をばたつかせ始めた。
「ターロー、しっかりしなさい。なんてこと言ってるの!誰かに聞こえたらどうなるの!彼はお前の夫だよ、何か口にくわえなさい、さあ黙りなさい。」ターローの母親は、まるで正気を失っている彼女を咎めるような口調で言った。彼女の目には涙が溢れていた。
ターローは意識を失ったと思えば、また意識を取り戻したりしていた。
「向こうへ行ってそんな失礼なこと言うんじゃないよ。自分の言葉に気をつけなさい。彼が何と言おうと、神様がお前の結婚の証人なんだからね。」ターローの母親は言った。
「お母さん、もし神様が私の結婚の証人なら、嘘の証人だわ。お母さん、私はまだ結婚なんてしてない・・・」ターローは気違いのように、天井の長い梁の方を見つめていた。プーローはターローの顔を見ていた。ターローは心の中の全てを言い尽くした後も、結婚のこの巨大な欺瞞から自由にはなれなかった。むしろ、彼女の年齢は、すさまじいスピードで人生の真偽いかんを無視して前へ進んでいた。
野に出た牛たちが帰って来ていた。日が沈もうとしていた。プーローは心に重荷を背負って立ち上がった。プーローは突然、この広い世界に嫌悪を感じた。
ここ数日間、プーローは家の中に閉じこもって過ごしていた。ラシードのちょっとした冗談や、家の細々とした家事や、特にジャーヴェードの我がままが、プーローのすさんだ心を、細い細い糸で包み込んでいった。彼女の気分はだいぶよくなっていた。ところが今日ターローが自暴自棄になって話したことを聞いて、プーローの心を包んでいた糸が切れてしまったようだった。彼女の心は落ち着かなくなった。夕食の準備をしているとき、彼女は塩や香辛料の分量を間違えてしまった。ダール(豆カレー)は水っぽくなってしまった。ローティー(インドのパン)は生焼けだった。
それから数日間、彼女の憂鬱な気持ちは変わらなかった。その後何を考えたのか、プーローは日に一度しか食事を取らなくなった。そして1日中目を覚まして、瞑想をするようになった。何時間も目を閉じて、何の仕事もしなかった。まるで世捨て人になったかのようだった。
プーローはあまり眠らなくなった。めっきり少食になった。その内、彼女の食事は、乾いたもみ殻に、1枚のローティーだけだった。ローティーにはギー(油)も塗らず、ミルクやヨーグルトと一緒に食べることもしなかった。その1枚のローティーだけで1日を過ごした。数日の内にプーローの目の下には薄青いくまが浮かんできた。彼女の身体はげっそりとしてしまった。
一方、ここ数日間、ラシードはプーローを慰めるのに忙しかった。日常的に彼は冗談を言っていた。何とかプーローの心を引こうと努力していた。彼は以前にも増して彼女を愛していた。しかしラシードの全ての試みは失敗に終わった。プーローの心にも脳にも、ラシードの努力は何の影響も与えなかった。プーローの考えや振る舞いに何の変化も表れなかった。
毎日いくら頑張っても彼女の心は動かなかったため、ラシードの心は消え去ってしまいそうだった。日に日に痩せこけていくプーローの顔をラシードは見るに耐えなかった。彼の家は、人が住みながら廃墟になって行くかのようだった。ラシードの顔をも、痛々しい沈黙が支配するようになった。2人は、家の、社会の、身体の壁に囲まれていた。今や2人の間にもひとつの壁ができつつあった。
プーローは1匹の水牛を飼っていた。水牛は毎日牛乳を飲み、ヨーグルトを求めていた。ラシードの畑で働く者たちが、家畜のために飼料を持ってくると、プーローはグラス1杯のラッスィー(インドの飲むヨーグルト)に、バター1切れを入れて家畜や家畜の子供たちに与えていた。プーローは何もしゃべらなかった。ラシードも食欲がなくなってしまった。家のコンロから火が消えることはなかったが、家の団欒と生活の温もりに、もやがかかったようになってしまった。
ジャーヴェードの無邪気な顔にも、両親の不機嫌な表情の影が覆った。プーローは毎日ジャーヴェードの世話をしていたし、ラシードは息子を心から愛していたが、ジャーヴェードもあどけない表情を見せなくなった。
ある夜、眠っていたラシードを突然高熱が襲った。彼の身体が燃えるように熱くなった。朝になって、プーローがラシードの額に手を当てると、危険なほどの高熱だった。
村の医者が彼の手当てをした。ラシードの高熱が3日間続いた頃、医者はラシードがマラリアに罹っている疑いがあると診断した。
ラシードの病気は、プーローを苦行と禁欲から解放した。プーローはラシードの手当てをし、彼の身体を揉み、食べ物を食べさせた。一方で、ジャーヴェードの顔が次第に痩せてきた。昼になると、ジャーヴェードの顔には苦痛が表れるようになった。しかしプーローは息子を世話する暇がなかった。数夜が過ぎた。数日が過ぎた。だが、ラシードの熱は下がらなかった。
「プーロー!俺の犯した罪を許してくれ!俺の間違いを許してくれ!プーロー・・・プーロー・・・」ラシードは熱にうなされて叫んだ。真夜中だった。プーローはハッとして目を覚ました。ここ数日間気の休まる暇がなかったことと、夜通し起きていたことで、プーローは疲れ切っていた。彼女は立ち上がって急いでラシードのベッドのそばに座った。ラシードの額に手を当て、彼の足を揉んだが、ラシードは意識を取り戻さなかった。
「もういい、プーロー、俺は行くよ、俺のプーロー・・・」とラシードは言葉にならない声でつぶやき続けた。プーローの心臓ははちきれそうになった。
「もうやめて、ラシード、私をこれ以上悲しませないで!」プーローは苦しそうに声を上げた。しかしラシードは昏睡状態だった。彼ははっきりしない言葉をうめくだけだった。プーローが理解できる言葉もあったが、多くの言葉はラシードの喉から飛び出て、唇のところで消えてしまっていた。
世界の終わりのように暗い夜だった。プーローは家に一人だった。しかしまるで広い世界に一人でいるように感じた。ラシードの他に、彼女の傷口にガーゼを当てる者は他にいなかった。
プーローはラシードの額に、冷たい水を染み込ませた布切れを置いた。彼の額は、コンロのレンガのように熱かった。彼女は布切れを濡らし続けた。水壺の水はたちまちの内ににごってしまった。プーローは水を替えた。彼女の目からは涙がポタポタとラシードの額の上に落ちた。
夜が明ける頃までに、冷たい水が効いたのか、温かい涙が効いたのか、ラシードの熱は引いた。プーローはラシードの身体を洗った。彼の昏睡は、安らかな眠りに変わった。
ラシードが目を開けたとき、彼は自分の身体が軽いように感じた。今日は彼の額に痛みがなかった。ラシードは安堵の溜息をつき、寝返りを打った。プーローは、ラシードのベッドの脚にもたれかかって、地面に座って寝ていた。彼女の片手にはまだ布切れが握られていた。彼女の足のそばにはまだ水壺が置かれていた。
プーローを見て、ラシードは嬉しい気持ちでいっぱいになった。彼は彼女の顔の方を見た。彼女のやつれた顔は、深い眠りに沈んでいた。
自分の病気とプーローの看病は、ラシードの心を混乱させていた。プーローの顔と布切れから、ラシードは、夜通しの看病はどんなに大変だったかと心配になった。ラシードは自分の弱々しい右手をプーローの頭に乗せた。プーローのボサボサの髪の中を、ラシードの指が動き回った。彼の指はプーローの耳を、額を優しく触った。プーローは全身を眠りに委ねていた。ラシードの目の隅から涙があふれ出てベッドを濡らした。ラシードは、不思議な充足感を感じながら起きていた。
ラシードはプーローの身体を獲得していた。しかし彼は、プーローの魂も完全に自分のものにしたいと思っていた。プーローの悲しみは、彼の心を消耗させた。このときプーローは、マスタードの木の枝のように、ラシードのチャールパーイー(ベッド)に横たわっていた。
ラシードは身体に力が入らなかったが、プーローを抱きしめたいという気持ちになった。ここ数日間の絶望的悲しみのせいで、ラシードの心はひどく傷ついていた。このときラシードはプーローの顔から、プーローにはラシード以外何もないということがはっきりと読み取れた。ラシードは腕を伸ばし、プーローを胸に抱いた。おそらく強く抱きしめてしまったのだろう、プーローは目を覚ました。彼女は驚いた。しかしラシードはもう回復していた。彼の熱は引いていた。ラシードは弱った目でプーローを見つめていた。
ラシードは10日間ベッドに寝ていた。熱は引いたが、彼はとても衰弱していた。しかし彼はとても幸せだった。プーローはラシードを愛するようになっていた。ラシードのそばに座って、プーローは1日中世話をした。プーローはジャーヴェードをあやしながらラシードのそばに座らせた。ジャーヴェードはハイハイができるようになり、他人の真似をするようになり、母親から教えられた片言の言葉を話すようになった。ラシードの心は満開だった。彼の身体は花のように軽かった。彼は心の中で、自分の病気に感謝した。彼の家には、幸せが2倍、3倍になって帰ってきた。
プーローは、ラシードが自分に行った過ちを全て許してしまおうという気持ちになった。彼女はラシードを本当に愛するようになった。ラシードは彼女の夫だった。ラシードは彼女の息子の父親だった。これだけが真実だった。他は全て欺瞞だった・・・。
その後、しばらくの間、ラシードはサッカルアーレー村とチャットーアーニー村との間を行き来していた。彼は兄弟と共同で経営していた土地の収穫物を売り払った。しかしプーローはサッカルアーレー村に来てからというものの、一度も村の外に足を踏み出していなかった。ラシードが外出を提案しても、プーローは微かに笑って言うのだった。「私は自分の意思でこの村に来たのではないわ。自分の意思でこの村から外に出ることもしないでしょう。」
ジャーヴェードは今や元気に駆け回るようになっていた。ラシードは変わらぬ愛情をプーローに注いでいたが、それにも増してジャーヴェードを溺愛していた。ジャーヴェードにいくらキスしても、いくら愛を注いでも、満足しないほどだった。ジャーヴェードは何か口ごもりながら言葉を話すようになった。アッバー、アッバー(「パパ」という意味)と言って、ラシードの足にしがみついていた。
プーローがコンロに粘土を塗りつけていると、ジャーヴェードが走ってやって来て、濡れた土をペタペタと塗りつけ始め、プーローのコンロを台無しにしてしまうのだった。プーローがラッスィー(飲むヨーグルト)に塩を混ぜて飲み出すと、ジャーヴェードはターメリックと唐辛子を彼女のラッスィーのコップに入れてしまうのだった。ジャーヴェードがドアの後ろに隠れると、ラシードは彼を探し回るのだった。ジャーヴェードの小さな小さな悪戯によって、ジャーヴェードのあどけない笑顔によって、ラシードはトウモロコシの実のように笑い続けることができるのだった。
ある日、一人の女が路地で「フクロウと馬(オモチャの名前)」を売り歩いていた。ジャーヴェードは土で出来た小さな人形や、アシで出来たガラガラを見てしまった。プーローの服の裾を引っ張り始めた。プーローは一握りの穀物と、古い布を与えて「フクロウと馬」を買った。プーローがそのまま路地に座っていると、遠くから頭の狂った女がやって来た。
近所の女性たちは、急いで自分の子供を隠し、扉を閉め、何が起こったか分からない子供たちは泣き叫び始めた。パグリー(狂った女性)は、ふくらはぎが丸見えのサルワール(ゆったりとしたパンツ)をはいている他は、上半身に何も着ていなかった。彼女の身体は、おそらく日焼けして黒くなったのだろう、もしくは元々黒かったのかもしれない。彼女の髪はぐちゃぐちゃで、埃だらけになっていた。まるで生まれたときから一度も身体を洗ったことがないかのようだった。彼女は足を変な風に曲げ、手を変な風に広げ、歩いているのに走っているかのようだった。彼女の顔を見ると、気味の悪い笑みの中に潜む、バラバラな方向に突き出した歯の方に目が行ってしまうのだった。彼女のしわだらけの、焼け焦げた体からは、誰も彼女の年齢を予想することができなかった。彼女はただの骸骨だった。走り回る骸骨だった。
プーローは立って見ていた。パグリーは、走ってやって来ると、オモチャを売る女の籠の中から、両手で「フクロウと馬」を掴んで逃げ出した。彼女の気味悪い、叫び声に似た笑い声は、しばらくの間、路地裏にこだましていた。
パグリーは一日中走り回っていた。畑の中を駆け回っていた。畑の作物から野菜をもぎ取って食べていた。誰かが座り込んでいる彼女の前に数枚のローティーを投げると、彼女はそれをむさぼり食った。また誰かが彼女に破れかけた古いクルター(丈の長いブラウス)を着せると、パグリーはゲラゲラ笑って、数日と経たない内にボタンを引き抜き、クルターを歯で引き裂いてしまうのだった。しばらくの間ズタズタになった布切れが彼女の上半身に残っているが、それすら彼女は引き裂いて捨て去ってしまうのだった。時々彼女は素っ裸になることもあった。すると、村の女性たちは再び古いサルワールやクルターを彼女に着せるのだった。
パグリーは今やサッカルアーリー村の住人のようになっていた。彼女を毎日見るのにも慣れっこになっていた。時々村の小さな男の子たちが、彼女の後ろから、手を打ち鳴らして追いかけ回すことがあった。すると通りがかりの大人が、子供たちを叱り付けるのだった。男の子たちは仕方なく彼女を追いかけ回すのを止めるのだった。
小さな子供たちは、我がままを言わなくなった。母親たちは、パグリーの名前を出して子供たちを脅かすのだった。「パグリーが来てお前をさらって行ってしまうよ。」それを聞くと子供は怖がって黙りこんでしまうのだった。
パグリーはある麦わらの山の下に住んでいた。時々誰かが彼女のそばに水の入ったコップを置いていった。またあるときは誰かがローティーの切れ端を彼女の枕元に置いていった。情に厚い誰かが、破れかけた掛け布団を麦わらの山の下に敷いてあげた。パグリーは夜になるといつもそこへ行って寝ていた。
パグリーはただ走り回り、笑っていた。誰かの子供に何かを言うこともなかったし、誰かの物を盗むこともしなかった。地面に落ちているローティーの切れ端を拾い、地面に落ちている食べ物を食べていた。
ある日、村の全ての人は、また驚きと共にプーローも、パグリーのむき出しになったお腹が膨らんでいるのを発見した。村の全ての女性は、誰かの恥知らずの行為に、穴があったら入りたい気持ちになった。しかしパグリーは何も言わず、何も話さなかった。
パグリーのお腹は日に日に膨らんできた。
村の女性たちは、パグリーの身体を覆っておきたかった。彼女をどこかの地下室に閉じ込めておきたかった。パグリーは何も理解していなかった。彼女は以前のように笑っていた。以前のように走り回っていた。
ある日、村の男たちが集まって、パグリーを村の外に放り出した。真っ暗闇の夜だった。その夜、誰もパグリーを見なかった。皆は、パグリーが村から出て行ってしまったのだと思った。彼女はもはや誰の目も届かないほど遠くの、誰の心からも遠くの村へ行ってしまったのだと思った。
次の日の昼頃になると、パグリーは以前と全く同じように村の路地を走り回っていた。以前と全く同じように、畑の中で笑っていた。
「いったいどこの男だろう!その男は獣だよ、全く!この哀れなパグリーをこんな目に遭わせるなんて!」全ての女性は口々に声を荒げていた。パグリーのことを考えただけで、彼女たちは吐き気を催すのだった。
「彼女には美しさもなければ若さもない。肉もなければ、自意識もない。彼女はただ骨で出来た生きた骸骨・・・。狂った骸骨・・・。トビはその骸骨すらついばんで食べてしまったんだわ・・・。」プーローはそう考えるだけで疲れてしまった。
パグリーのお腹はどんどん大きくなった。
夜明け前の暗闇の中、プーローはいつものように畑へ歩いていた。プーローが郊外の道を歩いていると、ある木の根元に、人間の形をしたものが横たわっているのが見えた。プーローは震え上がったが、彼女はそこまで臆病な女性ではなかった。ゆっくりと彼女は倒れている身体の方へ近づいた。プーローは、すぐにそれが誰であるか分かった。パグリーが石像のように身動きひとつせず、木の根元に横たわっていた。彼女の足の近くには、生まれたばかりの男の子の身体があった。その子供のへその緒は、まだパグリーとつながっていた。
プーローはハッと息の呑んで立ち尽くした。彼女の目の前が暗くなった。そして全く気が動転してしまった。
プーローの背筋に突然震えが走った。彼女は足をもつれさせながらラシードのもとへ走り、彼を連れてきた。
プーローは破れたショールの切れ端でパグリーの遺体を覆った。ラシードはパグリーの脈を診た。しかし脈を診るまでもなく、パグリーの顔には死の印章がはっきりと映し出されていた。髪の束が彼女の額を覆っていた。
自然はパグリーの息子の中で力いっぱい躍動していた。赤ちゃんは自分の右手の親指を口にくわえていた。
「ああ、アッラー!」ラシードの口から嘆息が漏れた。彼はナイフで子供のへその緒を切った。
プーローは子供を自分の頭にかけていたショールで覆った。二人は家に戻った。
朝もやのように、この話は村中に広まった。小麦粉をこねていた女性たちは、皿をひっくり返してしまった。ローティー(インド式パン)を焼いていた女性たちは、火のついたタンドゥール釜をそのままにして、プーローの家にパグリーの赤ちゃんを見に来た。
綿の玉のように白くて穢れのない赤ちゃんを、プーローは洗って小さなベッドの中に寝かせていた。温かいミルクで浸した小さな布切れを、プーローは赤ちゃんの唇にあてがった。赤ちゃんは一生懸命ミルクを吸い始めた。ジャーヴェードは家に来た小さなお客さんを、しゃがみ込んで見ていた。
「赤ちゃんに神様のご加護がありますように!」「赤ちゃんが長生きしますように!」「なんて幸運なこと!」村の女性たちは口々にこの孤児に祝福を与えては去っていった。
数人の男性が、パグリーの遺体を火葬した。
夜になっていた。プーローは赤ちゃんの世話にかかりっきりだった。ラシードはランタンをきれいに掃除してから火をつけた。赤ちゃんは、大きな瞳でランタンの方を見た。まだ赤ちゃんの目はよく見えていなかった。すぐに赤ちゃんは他の方向を向いた。
プーローは考えに耽っていた。
どんな男がパグリーの黒い体に手を出したのだろう。パグリーの方から望んだのか、それとも無理矢理犯されたのか!その男はパグリーに対してどれだけ重い犯罪を犯したのか、少しも気付かなかった。その男はパグリーのそばに横たわっていた赤ちゃんのことも、少しも気にかけなかった。
おそらくパグリーは、自分が子供を生むことすら分かっていなかったのだろう。出産の苦痛を彼女はどうやって我慢したのだろう!産婆も彼女を手助けしてやれなかった。夜の暗闇の中で泣き叫んだことだろう!吹きっさらしの風が彼女の身体を突き刺したことだろう!冷たい大地の上でもがいていたことだろう!それでいながら、厳しい自然の掟に従って、彼女の子供は痛みを我慢して自らこの世界に飛び出て、この大地の上に生まれ落ちたのだろう!そして激痛に蝕まれたパグリーの命の糸が切れてしまったのだろう!
さらにプーローは考えた。たとえパグリーが生きていたとしても、何の得があったろう!彼女が自分の息子の世話をすることができただろうか!彼女は死んだ方が幸せだったかもしれない。彼女の息子はなんてかわいいことか。黒く醜い骸骨の中で、どうしてこんなに美しい子供が育ったのだろう!なんて大きな大きな瞳だろう!なんてかわいい身体だろう!完璧に男の子の身体をしている!いったいこの子の父親は誰なのだろう!
考えながらプーローは眠り込んでしまった。プーローは夢を見た。ラシードが彼女を馬の上に乗せて連れ去っていた。ラシードはどこかの小さな倉庫にプーローを3日間閉じ込めた後、彼女を外に出した。プーローは気が狂ってしまった。彼女は路地を走り回り始めた。彼女のお腹の中で子供がうごめくようになった。そして・・・そして・・・ある日どこかの木の陰で彼女は男の子を産んだ。その子の容貌はジャーヴェードにそっくりだった。その赤ん坊は彼女の胸にしがみついて、ミルクを求めて泣いていた。しかしプーローのおっぱいは出なかった・・・。
震えながらプーローは目を覚ました。目の前のベッドの中で、彼女の新しい子供が泣いていた。彼女は赤ちゃんを抱き起こした。そして恐る恐るジャーヴェードの方を見た。ジャーヴェードは既にそばのチャールパーイー(インド式ベッド)で寝ていた。今度はプーローは恐る恐る表のコンロのそばに座っているラシードの方を見た。ラシードはまだ彼女を残してどこにも行っておらず、彼女を追い出してもいなかった。彼女は家をきちんと管理していた。ラシードは彼女の慈悲深い夫だった。ジャーヴェードは彼女のちぢれっ毛のかわいい息子だった。近所に住むカンモーも、こっそりとやって来ては彼女とあれこれ話をし、既にプーローの家族同然の存在になっていた。プーローの家族はさらに大きくなった。神様は彼女の家にもう一人の男の子を送ったのだった。彼女は新しい赤ちゃんの額にキスをした。
プーローは立ち上がって白いクミンの実を一握り食べた。ジャーヴェードは2年間プーローのおっぱいを飲んでいたが、最近プーローのおっぱいが出なくなっていた。彼女は、白いクミンの実を食べると、おっぱいが出るようになるという話を聞いていた。プーローは新しい赤ちゃんの口に自分の乳首をあてがった。
3日後、本当にプーローのおっぱいが出るようになった。村の女性たちはそれを見て驚いた。その子はプーローの第二の息子として育てられることになった。
火にかけられた石の中にゆっくりと熱が伝わっていくように、村の中でじわじわと噂が広まって行った。「パグリーはヒンドゥー教徒なのに、彼女の息子をムスリムが持って行ってしまった。村人たちが見ている前で、奴らはヒンドゥー教徒の息子をムスリムにしてしまった・・・。」
猫が自分の子供をひた隠しておくように、プーローも小さな赤ちゃんを胸に抱いて、家の一番奥の部屋に閉じこもっていた。それでもなお、噂話は壁を通り抜けて彼女の耳にまで届いた。
最初の内は、数人のヒンドゥー教徒が家に集まって話し合っていた。
「パグリーがヒンドゥー教徒だというのは本当だろうか?」誰かが言った。
「俺が聞いたところによると、パグリーはラールムーセー村のある良家の娘だったという話だ。だが夫の妾が、彼女に死体の灰を食べさせてからというものの、彼女は気が狂ってしまったんだ」と誰かが言った。
「こんな話もある。パグリーの両親が彼女を家の中に閉じ込めておいたんだが、不幸なことに逃げ出してしまったんだ」と誰かが言った。
「俺は自分の目で見たんだ。パグリーの腕に『オーム』の刺青がしてあった」と誰かが地面を叩きながら言った。
「世も末だ、イスラーム教徒が目の前で我々の名誉に泥を塗るとは・・・。」
「これは我々に対する冒涜だ、ヒンドゥーの赤ん坊をムスリムが一瞬のうちにイスラーム教徒にしてしまうとは・・・。」
「もうこの話は止めにしようじゃないか、あの子供がいったい誰の迷惑となるって言うんだ。こんな小さなことで深刻になる必要はない」と言う人も中にはいた。
「何を言うか!問題は今、宗教に関わっている。明日には奴ら、全ての村をムスリムにしてしまうに違いない。お前はそれを指をくわえて見ているつもりか?」数人の人々が同時に大声を張り上げた。
密室の中で、空気はまるで沸騰したかのようになった。
「あの子を取り戻そうじゃないか。誰が我々の邪魔をするか、見てやろうじゃないか。」
「実際これは金の問題だろう?寄付金を集めて乳母に渡して、あの子を育てさせればいい!」誰かが身を乗り出して叫んだ。
「村全体で協力すれば、一人の男の子を育てることなどわけない。」
「あの子もパグリーのように聾唖(ろうあ)になってしまわないとも言えないだろう・・・。」誰かがつぶやいた。
「だからどうしたっていうんだ。ダルムシャーラー(巡礼宿)で掃き掃除させればいい。1日2枚ローティー(インド式パン)を食べさせれば十分だ。」
両者の中間にたって意見を述べる者もいた。
「まずは乳母に聞いてみよう。」誰かが言った。
「待て待て。乳母が拒むはずないだろう?まずは銀の靴を彼女の頭に置こう、それから彼女と話をしよう。」
「おいおい、赤ん坊はどうする?ダルムシャーラーで仕事する者に不足はしてないよ。」
「赤ん坊にどうしてそんなに気を遣うんだ、世話しなくても勝手に育つだろう。まずは・・・」
「お前たちは何を言ってるんだ?宗教の名のもとにこれっぽっちの仕事もできないなら、めくらは井戸に飛び込めっていうことだ。」
「お前の畑の水を誰かが自分の畑に引いたら、お前はそいつの頭をかち割るっていうのに、ヒンドゥー教徒の赤ん坊をムスリムがさらって行っても何も言わないのか?」
部屋の空気は、まるで石炭の煙が混ざったかのようになった。
ラシードが畑へ行くと、通り過ぎるヒンドゥー教徒たちは彼に冷たい視線を投げかけるようになった。そんなときラシードは、下を向いて足早に立ち去るのだった。
2、3回ラシードはプーローに言った。「村の空気がよくない。この問題の渦中にいて俺たちは何の利益があるっていうんだ?問題はもっと大きくなるだろう。奴らが望むんなら、子供を渡そうじゃないか。あとはその子の運任せにすればいい。」
プーローは何も答えなかったが、彼女の心は不安でいっぱいになった。彼女は小さな骸骨を昼も夜も胸に抱いて、6ヶ月間過ごした。その赤ん坊は今やジャーヴェードのようにふっくらとしてきた。子供の目はプーローを認識するようになった。プーローがどこかへ行くと、その方向を見つめるのだった。その子はラシードを見ると手を広げるようになった・・・。
プーローは考えていた。子供が生まれた日にどうしてヒンドゥー教徒たちは気が付かなかったのだろう?彼らは子供を引き取ることができた。育てることができた。母親のように胸に抱くことができた。父親のように愛情を注ぐことができた。6ヶ月間プーローは夜通しで子供の世話をし、クミンの実を頬張っては自分の血液からミルクを引き出していた。子供の糞尿を洗って、自分の爪を削っていた。
プーローは赤ちゃんに蜂蜜を塗って、近所のムスリムの家にスパイスを配った。子供が大きくなったときに、自分の出生について何も疑念を抱かないようにするためだった。
ある日、村のヒンドゥー教徒の長がラシードを呼んだ。プーローは胸騒ぎがした。プーローは考え込んでしまった。子供を拾って育てたのは私だが、彼らはラシードに対して罵詈雑言を浴びせかけるだろう・・・。
プーローは、ラシードと一緒に自分も行くと主張した。彼女こそが、この問題の張本人だった。彼女は自分で行って、彼らに子供を育てることを懇願しようと考えていた。しかしラシードは拒否した。彼は一人で呼ばれた場所へ行ってしまった。
村のある有力なヒンドゥー教徒の家の庭に、3つのチャールパーイー(インド式ベッド)が置かれていた。その上に、村のヒンドゥー教徒の長老たちが座っていた。彼らは、もしラシードが数人の仲間を引き連れてやって来たり、もしくは来なかったりした場合は、別の方法で解決しようと話し合っていた。だがラシードは一人でやって来た。ラシードは挨拶をして彼らの前に座った。
「どうだ、考えはまとまったか?子供を返すか否か?」フッカー(水タバコ)の管を口から離して、彼らの中の一人が太い声で言った。
「私に何の権利があるでしょう。全てはアッラーの授かり物です。与えるのも授かるのもアッラー次第です。」ラシードは片手で額を触って空を仰いだ。
「言い訳をするな!必要なことだけを話せ!」一人の男が怒った声で言った。
「私はアッラーのご慈悲によってあの子を拾い上げたのです。あと少しあそこに辿り着くのが遅れたら、あの子を野良犬が食べてしまったかもしれません。アッラーのおかげで、あの子の命があるのです・・・。」
「分かった。もし神様と人間とを結ぶ糸が長ければ、その糸を切ることは誰にもできない。しかしお前は、あの子の母親がヒンドゥー教徒であったことと、お前がヒンドゥー教徒の子供を拾って連れ去ったことに対して、我々が我慢できないことを、よく理解しなければならない。」
「いいえ、私は彼女がヒンドゥー教徒だったことなど知りませんでした。彼女はヒンドゥーの家からも食べ物をもらっていましたし、ムスリムの家からも・・・」
「しかしあの女は気違いだった。お前は気違いではない。」彼の言葉をさえぎって誰かが言った。
「分かりました。でもあなたたちが初めからあの子を拾って育てていれば、私には何の問題もありませんでした。あの子は拳ほどの大きさの骸骨でした。私の妻が6ヶ月間命を削ってあの子の世話をしたんです。赤ん坊の命が助かった今になってやっと、あなたたちは子供を引き取ろうとしている。アッラーの恐れを知らない人たちよ!どうか神の名において、あの子を育てて下さい。私は神の名においてあの子を育てているのですから。そうでなかったら、私は何のために生きましょうか・・・。」ラシードがこのようなことを言うと、数人の人々の顔に憐憫の情が浮かび始めた――もう言い争いはやめにしようじゃないか、育てたければ育てればいいが、無意味な不幸を背負い込んで何の得があるっていうんだ・・・。
「いいか、我々は問題を大きくしたくない。あの子は我々のものでもなく、お前のものでもない。問題は宗教だ。お前は宗教の問題に関わるべきではない。お前は無意味に命を危険にさらすことになるだろう。誰かがお前に何かをしても、我々は責任を取れない。だから平穏に暮らすためにも、あの子を我々に渡しなさい。そしてもし今まで育てるのに費やしたお金を望むなら、数ルピー持っていけばいい。」一人が言った。
「異議なし!異議なし!」全員が声を上げた。
「アッラー・・・アッラー・・・」ラシードは両手で耳をふさいだ。
「乳母の用意はできている。我々と共に数人の若者が同行して、お前の家から子供を連れてくることにする。子供の浄化儀式は我々が自分で行う。」
「これが最後のお願いです。どうかあの子に慈悲をかけてやってください。そしてあの子が今いる場所にそっとしておいてやってください。私の妻は、腹を痛めた実の息子のように育てているんです。」ラシードは両手を合わせて懇願した。
「我々はお前に正しい道を教えた。もしお前が幸せを望むなら、そのようにしろ。そうでなければ、我々もいつまでも甘いことばかり言ってはいられない。」2、3人の男がチャールパーイーから立ち上がった。
家の中から乳母がショールを巻いて出てきた。ラシードは立ち上がらざるをえなかった。全員がラシードの家に向けて歩き出した。
プーローは家の玄関に立って、路地の様子を伺っていた。ラシードがうつむいて数人の男と共に歩いてくるのを見つけた途端、彼女の鼓動が激しくなった。
プーローの目の前にあの日のことが浮かんで来た。母親が彼女に別れを言い渡した日、父親が彼女を追い出した日、彼女の兄弟姉妹と別々になってしまった日・・・。その子は既に彼女の心の支えになっていた。その子との別れは、家族との別れと同じくらいの苦しみだった。
プーローは走って子供を抱きしめた。ラシードが自宅の庭にやって来て、呆然と立ち尽くした。
ラシードは何も言う必要がなかったし、プーローは何も聞く必要がなかった。
乳母も一瞬立ち尽くした。プーローの胸から、子供を引き離すのは困難に思えた。
「早くしろ、急がなくちゃならんのだ。我々にも仕事がある。」ラシードと共に来た男たちが声を荒げた。
乳母は両手を伸ばしてプーローの手から子供を引き離した。その子は小さな拳でプーローのショールを掴んでいた。プーローは、まるでその子が自分の心までも掴んで離さないかのように感じた。プーローのショールが引っ張られていった。
乳母は子供の拳を開いて、ショールを離させた。赤ん坊は泣き叫び始めた。おそらく手が空になってしまったからだろう。
プーローは折れた木の枝のように、玄関に寄りかかって座り込んだ。路地裏から子供の泣き声が聞こえた。
暗くなってもプーローの乳首からミルクが流れ出て、彼女の服がぬれてしまっていた。プーローは言っていた。あの子はきっとお腹を空かしていることでしょう、だから私のおっぱいが流れ出ているんだわ。
夜になってもプーローの家では、誰も料理をせず、誰も何も食べなかった。
ジャーヴェードがいつもの口調で聞いた。「お父さん!弟はどこへ行っちゃったの?」「お父さん!弟はいつ戻ってくるの?」プーローとラシードは無言でジャーヴェードの方を見て、屈辱からうつむいてしまうのだった。
プーローの目に、カンモーの顔が浮かんで来た。カンモーの顔が次第にあの子の顔に変わった。プーローは考えた。枯れた花をどうして大事にしまっておくのだろう?枯れた花にどうして水をやっているのだろう?全ては他人だった。誰も自分のものにならなかった。ラシードだけは違った。ラシードは彼女と共に過ごしていた。たとえ全ての関係を断ち切る原因になったのが彼だったとしても、彼は自分のものだった。ジャーヴェードの父親だった。
3日が過ぎ去った。4日目に村中をひとつの噂話が駆け巡った。「あの子は助からないだろう。あの子は死の床にいる。あの子は重病だ。もう長くはないだろう。ミルクを飲ましてもすぐに吐き出してしまう・・・。」
プーローは玄関にしがみついて泣いていた。彼女の乳房は乳で満たされて垂れ下がっていたのに、子供の口は乳がないために乾ききっていた。子供の口と、乳房の乳の間には、果てしない空間ができてしまっていた。
「子供から母乳を奪ったんだから、子供が苦しむのは当たり前だわ。」
「もしあの子が死んでしまったら、村中の不名誉になるでしょう。」
「私は夫にいつも言ってるわ、正直者になって、子供をどこからも拾って来るなって。」
「私たちも子持ちだわ、誰かの悲しみを見てられないわ。」
「私の夫は自分のことしか考えていないわ。私だって最初から、他人の火の中に飛び込んでどうするのって言ってあるわ。」
「噂によると、昨晩乳母が子供に冷たいミルクを飲ませたそうよ。それから子供の調子がおかしくなったみたい。」
「水牛の乳をあんなに小さな子供が飲めるはずがないわ。子供は何度も吐いたそうよ。」
「そうじゃないわ、あの子は寂しがっているのよ。生まれたときから彼女の顔を見て育ったんだから、今さら他の人になつくはずがないわ!」
「ああ、かわいそうに!」
村のヒンドゥー教徒の女性たちは、このようなことを噂しあった。プーローはそれを聞くと居ても立ってもいられなくなった。彼女は今すぐダルムシャーラーまで走って行って、彼らに懇願しようと思った――どうかこんな風にあの子を死なせないでください!子供を私に返してください、そうすればあの子はすぐによくなります!
しかしプーローはそれをする勇気がなかった。彼女の足は動き出さなかった。プーローは、神様が彼女の祈りを聞き届けてくれるか、希望が持てなかった。
次の日は何の噂話も立たなかった。
すると突然、ラシードの家の庭の数人の男がやって来た。
「さあ、この子の命はお前に託された。救えるなら救ってやれ。」彼らは白い布に包まれた、瀕死の状態の子供をラシードに手渡した。
ラシードは、拳で彼らの顔をぶん殴ってやろうと思った。「6ヶ月間の必死の世話に対して4ルピーの金を出しておきながら、今度は墓に入りかけた子供を俺に手渡そうというのか!恥を知れ、どっか行け!」
プーローの嬉しそうな顔を見て、ラシードは全てを我慢した。
1週間の内に村中の人々が、その子供がプーローの家の庭を元気に駆け回っているのを見た。
ラヒームの年老いた母親の目が日に日に悪くなっていった。ラヒームの最初の妻は、7ヶ月の幼い娘を残して死んでしまった。次の妻は、姑と仲がよくなかった。ラヒームの母親は自分の目のことを嘆き悲しんでいた。今まで彼女は台所の仕事をし、綿を紡ぎ、河から水を運んでいた。美しい刺繍の入った壁飾りで、家中を飾っていた。今まで彼女は皺だらけの手でもみ殻をあおぎ分け、小麦粉を挽き、綿をより分けていた。朝には攪乳器でヨーグルトをかき混ぜていた。それでも嫁は粗探しをしては文句を言っていた。老婆は、もし目暗にでもなったら、嫁は水すらくれないだろうと考えていた。
ラヒームの母親は不安を抱えたまま日々過ごしていた。ある日彼女はプーローにお願いして言った。「どうか15日間私と一緒に来ておくれ。目の治療をしてみたいんだ。もしかしたらよくなるかもしれない。」
「お母さん!その医者はどこに住んでるの?」プーローは聞いた。
「医者じゃないんだよ!ある階段井戸があってね、聖者の魔法がかかってるんだよ。聞くところによると、その水で毎朝、礼拝した後に目を洗うと、数日の間に目がよくなるっていうんだよ。目暗ですらそこへ行って目が見えるようになったそうだよ。階段井戸の土も目にいいみたいなんだよ。」
「お母さん!その階段井戸はどこにあるの?」
「ラットーワール村だよ。ある聖者がそこに住んでいてね、やって来る患者たちのためのテントを用意してるそうだよ。」
プーローの耳に、まるで誰かが鉄の棒を突き刺したようだった。ラットーワール・・・ラットーワール・・・チャットーアーニー村の畑に立って、ラットーワール村に通じるでこぼこ道をプーローはどきどきしながら眺めていたいたのだった。その道で、誰かがプーローをさらいに馬に乗ってやって来たのだった。その道を、輿の乗って嫁入りに行くはずだった。ラットーワール・・・ラットーワール・・・
プーローはその村に足を踏み入れたこともなければ、見たこともなかった。プーローは、遠い記憶の彼方に消え去った名前を思い出した・・・ラームチャンド・・・ラームチャンド・・・
プーローの心の中に、一筋の煙が立ち上がった。彼女の心にひとつの望みが生まれた。一度彼の顔を見てみよう、どんなだろう、一度彼の村を見てみよう、どんなだろう・・・。
「いいわ、お母さん!私、お母さんと一緒に行くわ。」プーローは突然答えた。そして恥ずかしげに彼女の顔を見た。プーローは、まるでラヒームの母親に、心の中で考えていたことを知られてしまったかのように感じた。
「ありがとう、お前の子供が長生きするように、子孫が繁栄するように。」ラヒームの母親の心から祝福の言葉が湧き出た。彼女は、自分の嫁がこんな優しい言葉のひとつやふたつでも知っていれば、と考えた。
「お母さん!ジャーヴェードの父親をあなたが説得してちょうだい。私は何も言わないから。」プーローは恥ずかしそうに言った。
「分かった。ラシードは私の息子だよ、断れるはずがない!私のためなら何でもするだろうよ。」ラヒームの母親は自慢げに言った。
プーローは、ラシードが彼女の頼みを断らないことを知っていたが、ラシードの前でラットーワールの名前を出すことは難しかった。
その夜、プーローの心の中で、いくつもの対立する考えが浮かんでは消えていた。彼は私のことを誰だと思うだろう?私は彼の方を決して見ないようにしよう。全く他人の男なのだから、彼の村から何も得るものはない・・・彼が村に住んでいたとしても別にいいではないか、お母さんは自分の治療に専念すればいい、それが終わったら帰ってくればいい。・・・お前の心は俄かに沸き立っているけれども、彼の心には、悪夢に等しいお前のことなど何の興味も沸かないだろう・・・。
プーローは考えた。あの村に行って夜中に誰かの墓を掘るのか?その中に横たわっている男を起こすのか?彼の経かたびらを脱がして何の利益があろう?ラットーワールには行かないでおこう。ラットーワールの道は通らないようにしよう。
プーローは、是とも非とも言わなかった。
ジャーヴェードは父親を放そうとしなかった。ラシードは息子を同行させなかった。2人の女性の警護役として、ラヒームの家で古くから働いているアシュラフを同行させた。プーローは幼い息子を連れて行った。
アシュラフは馬車使いと共に前に座った。全ての荷物を裏に置いて、プーローと母親は裏の席に向かい合わせに座った。馬車が動き出すや否や、プーローの子供は胸の中で眠ってしまった。前に座っていたアシュラフは、プーローの子供を抱きかかえた。馬車はラットーワールの道を進んでいた。
馬のいななきは、まるでプーローの頭を金槌で叩きつけているかのようだった。プーローは馬車の端にもたれかかった。彼女は眠ってしまった。・・・美しく装飾された輿の中で、銀の飾り房のついた大きな枕に頭を乗せて、プーローは横になっていた。腕輪の重みで彼女の両腕は動かせないくらいだった。風が吹くと、輿のカーテンが少しだけめくれ上がった。その隙間から漏れた光の中で、プーローは自分の手のメヘンディーが光っているのを見た。なんてまずいメヘンディーだろう、彼女の友達は、隙間もないほどのメヘンディーで彼女の手を覆ってしまっていた。そしてこの輿担ぎたちの下手なこと、いったいどうやって歩いているのだろう?輿に座っているうちに、プーローの腰が痛くなってしまった。輿はひどく揺れていた。プーローの頭からショールが滑り落ちてしまった。プーローは手でショールをかけ直した。彼女の手の装飾品の、チャンチャンという音が輿の中に響き渡った。プーローはだんだん気が沈んできた。昨日から何も食べれなかった。プーローの母親は、マトリー(お菓子の一種)の入った籠を袋の中に入れていた。プーローはマトリーを一切れ食べたくなった。彼女は我慢できなくなった・・・。
ラヒームの母親は、プーローの肩を揺らして言った。「太陽が頭の上まで来たから、何か食べようじゃないかい。」
馬車使いは馬を止めた。道中のある小さな村の近くで、食事のために彼らは止まった。プーローはビクッと目を覚ました。輿も装飾品もメヘンディーも腕輪もなかった。プーローは馬車の裏の席で母親の前に座っていた。
プーローは弁当のために、ギー(油)を塗ったパラーター(インド式パン)を作って持って来ていた。母親はその包みを開けた。アシュラフに4枚のパラーターを与えた、馬車使いにも与え、自分の分も取って、プーローの前に置いた。
プーローはあまり食欲がなかった。パラーターのギーで気持ち悪くなってしまった。
「まだ先はあるから、急いで食べてしまってください。夜に馬を休ませて、次の日には帰らなければなりませんので」と馬使いは言った。食事が済んだ後、彼らは元のように馬車に座った。プーローはまた馬車にもたれかかった。プーローは夜通しで旅行のための荷造りをしたため、眠たかった。
・・・輿がまた揺れだした。ラットーワールに到着しようとしていた。突然大きな太鼓と笛の音がした。輿の周囲で太鼓が鳴り響いていた。プーローは、ラットーワールに到着したことに気が付いた。・・・太鼓がさらに大きな音で鳴り始めた・・・すると誰かが一人の小さな男の子を彼女に抱かせた。子供は見知らぬ人の胸の中に来たため、泣き出した。女性たちは大声で笑っていた。その子供の長寿を祈っていた。
ラヒームの母親が彼女の肩を揺らしていた。「今日のお前はよく眠るね、見なさい、子供が泣いてるよ。」
プーローはまた震え上がって目を覚ました。馬車の裏の席に座っていた母親が、彼女に話しかけていた。
「さっき盛大なバーラート(結婚式パレード)が通り過ぎて、太鼓の音がドンドン鳴ってましたが、全く気が付きませんでした?」アシュラフが言った。
「アシュラフは眠ってるお前に子供を抱かせて、お前も子供を抱いたんだが、それでもお前は目を覚まさなかったよ・・・」と言って母親は笑った。
馬車はラットーワールの近くまで来た。階段井戸の近くまで来て皆が馬車から降りると、前方に聖者の家が見えた。テントの代わりに聖者は最近2、3の小屋を建てていた。その中には、遠くから来た旅人が滞在していた。彼らは階段井戸の土や水を目に塗って治療をしていた。
聖者は彼ら新しい訪問者にひとつの小屋を与えた。アシュラフは全ての荷物を小屋の中に入れ、母親を連れて聖者の元へ行った。プーローは小屋の中にあったチャールパーイー(インド式ベッド)の上に布を敷いて、子供を寝かした。そして彼女は入り口に立って、目の前の畑の向こうに広がる村の家々を眺めた。
・・・私はラットーワールに来た。誰も私を呼んだわけでもなく、誰か男が私を連れてやって来たわけでもなく、誰かが笛を鳴らしたわけでもなく、誰かが歌を歌ったわけでもなく、誰かが私の手に腕輪を通したわけでもない。ひとつの貝飾りも私の手になく、メヘンディーの一滴すら私の手にはついていない・・・
村の郊外にあるこの階段井戸は静寂に包まれていた。プーローの欲望が膨らんできた。彼女は走ってあの村まで行ってしまおうと思った。ここから逃げ出してしまおうと思った。この村の人々はどんなだろう、とプーローは考えた。誰も彼女に「座りなさい」とも言わなかった。誰も彼女に「長生きしなさい」と言わなかった。誰も彼女に・・・
プーローは幾分落ち着いた。プーローは、自分が少しおかしくなっていることに気が付いた。パグリーのように村の路地を走り出しはしないか、自分の服を引き裂いてしまわないか、奇声を張り上げて話し始めはしないか、と思った。
聖者は母親に、一日中そこにいるように行った。アシュラフは次の日、サッカルアーリー村に戻った。小麦粉や豆を彼女は自分で持って来ていた。プーローと母親は自分のローティー(インド式パン)を自分で作っていた。もし望めば、聖者の住居で食べ物を食べることもできた。
プーローは村の方を見なかった。村のことをプーローは誰にも何も尋ねなかった。1日、また1日と過ぎていった。村に行く用事もなかった。何か必要なものがあると、聖者の召使いが買ってきてくれた。村のすぐ近くまでやって来て村も見ずに戻ることになると考えると、プーローの心は不安になった。プーローは何とかして村中を見てみたいと思った。彼の家も見て、彼も見て、でもそのことは誰にも知られないように・・・だが彼の家がどれなのか、誰かに聞くとしてもどうやって、家が分かったとしても、中をどうやって見ようか・・・しかし彼の家を見たところで何の得があろうか、彼の家とは何の関係もない、どうしてそんなこと考えなければならないのか・・・。
プーローは落ち着かない気持ちになった。次々に日にちは経っていった。暇を持て余したプーローは、昔覚えた歌を思い出した。
詩(保留)
何度もプーローは涙を流したが、彼女はそれを飲み干した。
息子を母親のそばに寝かして、彼女は畑へ散歩に出掛けた。
プーローは、一度でも見れば分かるだろう、と考えていた。
しかしこうもプーローは考えた。あれからだいぶ月日が経ってしまった、彼がどんな容姿になっているだろうか全く分からない。でももし彼がそばを通ったら、絶対に彼だと気付くでしょう!
畑の中でプーローは数人の農夫に尋ねた。「ねえ!この畑はだれのもの?2本ほどニンジンが欲しいんだけど。私たち旅行中なの。」農夫は誰かの名前を答えることもあれば、また他の誰かの名前を答えることもあった。ラームチャンドの名前は出てこなかった。
次の日、誰かが本当にラームチャンドの名前を答えた。プーローの足はまるで地面に沈み込んだかのようになった!
プーローは目まいがした。プーローは地面の上に倒れこみそうになった。地面の上の土になってしまいそうだった・・・
プーローはアカシアの木の下で立ち尽くした。彼女の足から誰かが力を吸い取っているかのようだった。彼女の足はひとかたまりの氷になってしまった。地面はプーローを掴んで離そうとしないかのようだった。
プーローは、自分がザクロの木となってそこで育ってきたように感じた。彼女の赤いザクロの実を誰かが取りに来ると、彼女は石炭となって地面に落ちるのだった。もしラームチャンドが取りに来ると、ザクロの赤い実は血液になって彼の服に染み付くのだった。そしてそのザクロの木から声が聞こえて来るのだった。
詩(保留)
農夫は刈り取ったチャンナ豆が入った袋を頭に乗せた。プーローはハッと気が付いた。彼女は、お姫様がザクロの木になって育つという、子供の頃に聞いたお伽話を思い出した。プーローはお姫様でもなく、ザクロの木でもなかった。
「ご主人様がやって来なさる・・・」と言って農夫はチャンナ豆の袋を持って井戸の方へ向かった。
プーローの目から涙が流れ出した。ラームチャンドは、プーローのそばを通るときに彼女の方を見た。プーローの顔は涙で濡れていた。
プーローはアカシアの木陰に隠れることも、ショールの端で涙を拭うこともできなかった。もしかしたら涙のせいで、ラームチャンドの顔も見えていなかったかもしれない。
「君は誰だい?いったいどうしたの?」ラームチャンドは立ち止まった。
プーローは何も言えなかった。
「何か悲しいことでもあったの?」プーローの耳に、再びラームチャンドの声が入ってきた。プーローの舌は、まるで裏から誰かが引っ張っているようになってしまい、石像のように立ち尽くしていた。プーローの心の中は洪水のようになっていたが、彼女の口からは一言も言葉が出なかった。
ラームチャンドは困ってしまった。彼は辺りを見回した。彼は誰か農夫に助けを求めに行った。そのときプーローの足に力が戻り、無言で、静かに畑を抜け出した。
プーローは何も言わずに自分の部屋に倒れこんだ。その日の夕方、サッカルアーリー村からアシュラフがやって来た。次の日の夜明けに、プーローたちは村に帰らなければならなかった。
その夜プーローは眠ることができなかった。プーローは考えていた。一言もしゃべることができなかった・・・何も言うことができなかった・・・彼が「君は誰だい?」と聞いていた・・・私は自分が誰か、何て答えればいいの!・・・私の苦痛を誰も知らないのに!・・・寝ているときでも、起きているときでも、座っているときでも、私の泣き顔を彼が思い出してくれたら、「あの娘はだれだったのだろう?」と考えるでしょう・・・そしたら彼は忘れ去った話を思い出すだろうか・・・彼の死んだプーローのことを思い出すだろうか・・・そして彼の目から2、3滴の涙でもこぼれ落ちるだろうか・・・!もし私もあのお姫様のようにザクロの木になることができたら、彼の畑で育ちたいわ、彼は私のザクロを取るでしょう、そして私はザクロで話をするでしょう・・・・・・私はいったいいつの時代のことを考えてるのかしら・・・今時人間は木になることなんてできないわ・・・。
深夜を過ぎたが、まだ夜は明けていなかった。誰かがプーローの手を掴んでチャールパーイーから起き上がらせたかのようだった。プーローは表の畑へ出た。夜の暗闇の中でも、プーローは昨日ラームチャンドと出会った場所を、あのアカシアの木を識別することができた。プーローはかがみ込んで、彼が立っていたその地面から砂をすくい、その砂を自分の閉じた目にかけた。
目を覆っていた彼女の両手を誰かが掴んだ。プーローは驚いて目を開けた。ラームチャンドが彼女の目の前に立っていた。
「お前はプーローかい?」ラームチャンドが聞いた。「一晩中そのひとつの名前が私の頭の中を巡っていたんだ、本当のことを言ってくれ、お前の名前はプーローかい?」
プーローは、ラームチャンドの足元に倒れこもうと思った。思いっきり泣いて、自分がプーローであることを話そうと思った。泣き叫びながら、自分がプーローであることを伝えようと思った。私があなたのプーローであることを、私があなたに馬で連れ去られるべき女であったことを、私があなたと結婚するはずだったことを、私があなたの家に輿に乗って行くはずだったことを・・・私がそのプーローだということを・・・
プーローの舌は今回も誰かが引っ張っていた。プーローは一言もしゃべれなかった。彼女は自分の手をラームチャンドの手から離した。プーローは前回のように、黙ってそこから走り去った。
「お前がプーローだったら、一度でいいから私に言ってくれ!」ラームチャンドはプーローを追いかけながら言った。「私は一晩中この畑を歩き回っていたんだ!お前がもう一度やって来ることがなぜ分かったのか分からない、でも私の心は、お前がプーローだと言って止まないんだ!」
「プーローはもう死んだわ!」プーローの口からなぜか勝手に言葉が出た。彼女は後ろを振り向きもせず、遠くへ去って行ってしまった。
母親は、階段井戸の聖者にミターイー(甘いお菓子)を渡した。母親とその同伴者たちが乗った馬車は、太陽が昇る前にサッカルアーリー村へ続く道に辿り着いた。
一日また一日、一月また一月、そして一年また一年と月日が過ぎて行った。
ミルクで満たされた鍋をコンロにかけ、プーローは乾いた牛糞をくべた。牛糞はゆっくりと燃えながら、一日中くすぶり続けるのだった。それを見てプーローは、自分の胸の中に、長い間くすぶり続けている何かがあるのに気が付いた。
プーローは最近、食べたり飲んだしたものが、胸のところで止まっているように感じた。自分の喉に何か障害物があるように感じた。2、3回、彼女は水と共にヒメウイキョウの実を食べた。プーローは身体を冷やすため、1日に3、4回ラッスィー(飲むヨーグルト)を飲んだ。プーローは時々、お母さんの調子はどうだろう、と考えた。なぜそんな考えが彼女の心に浮かんだんか、分からなかった。
そんなある日、ラシードが家に帰って来ると、彼の顔はまるで重病患者のように青ざめていた。
ラシードは家の中で何も言わなかった。プーローと何でもない話をし、ジャーヴェードと学校の話をし、小さな息子と遊んだ。食事のとき、プーローはラシードの顔をじっと見つめた。ラシードは水を呑み込んだ瞬間、それを地面に吐き出した。ラシードは、自分の不安をプーローに隠すことができなかった。
チャールパーイー(インド式ベッド)に横たわった後、プーローはラシードに調子を尋ねた。
「今日俺の村から、畑で働いてる一人の男がやって来たんだ。」ラシードは一瞬黙り込んでから言った。
「チャットーアーニー村から?」
「そうだ。」
「それで?」
「彼が言うには、俺たちの畑で採れた作物の山があったんだ。穀物が山のように積まれてたんだ。」
「それで?」
「誰かが真夜中、それに放火したんだ。」
「まあ!」
「一握りの作物すら残らなかった。」
「誰かがわざとやったのかしら?」
「そう疑ってる。」
「いったい誰でしょう?」
「炎が空を赤く染めるほどだったそうだ。」
「どうしましょう!私たちの分け前もあったでしょうけど、可哀想に彼らはどうするんでしょう?」プーローが言う「彼ら」とはつまり、収穫を分け合っていたラシードの兄や、彼の叔父さんたちのことだった。
ラシードは黙り込んだ。プーローも考え込んだ。子供は既に眠っていたが、ラシードとプーローは眠れなかった。
でも、他人の家のものに放火して何の得があるのだろう?プーローは何度も何度も考えた。ラシードは黙っていた。プーローは、ラシードが何度も寝返りを打っているのを見ていた。彼は目を閉じていたが、眠気はやって来なかった。何度も彼は起き上がって水を飲んだ。
「息子を別のチャールパーイーに寝かせてくれ、俺は今夜こいつのそばで眠ることができない。」ラシードは言った。
ジャーヴェードはいつも父親のそばで寝ていた。幼い子供はプーローのそばで寝ていた。ラシードがこんなことを言ったのは初めてだった。プーローは驚いたが、黙ってジャーヴェードを抱えて、別のチャールパーイーに寝かした。
それからどれだけの時間が過ぎ去っただろう。ラシードは依然として寝返りを打ち続けたが、一向に眠たくならなかった。
「馬鹿げた話を聞いたんだ。本当のことか、デタラメかは知らないが!」ラシードは横になりながら言った。
「何?」プーローは驚いて聞いた。
ラシードは再び黙り込んでしまった。まるでその話をプーローに話すべきか否か、決めかねているかのようだった。
ラシードは長い間黙り込んでいた。プーローは自分のチャールパーイーから起き上がって、ラシードのチャールパーイーに座った。
「聞くところによると、村に一人の見知らぬ若者がやって来たそうだ。彼は村の誰とも関わりがなかった。村の奴らは、それが・・・それがお前の弟だって言ってる。」
「私の弟?」プーローは青天の霹靂だった。
「詳しいことは分からない。俺があの村に行ったのはだいぶ前だからな。全部村からやって来た男が言ってた話だ。」ラシードは再び黙り込んでしまった。
プーローは訳が分からなくなった。
私の弟?・・・弟はもういい年になってるだろう。もう弟を10年以上見てないわ。どんな容貌になっているだろうか。見てもすぐには分からないだろう。髭も生えていることだろう。10年前の弟は、ちょうど今のジャーヴェードと同じ年頃だったわ。プーローの心の中にいろいろな考えが浮かんだ。
ラシードは、プーローの古い家のことについて、その若者が「この家は誰のものか」と誰かに聞いたが、その若者は自分のことを誰にも話さなかった、という話を付け加えた。ただ人々は疑っていた。誰も自分の耳で何も聞かなかった。
本当に弟が村に来たのだろうか?彼は私のことを思い出したのだろう、自分の姉のことを、血を分けた実の姉のことを・・・!」プーローの心は散り散りに乱れ始めた。彼女の目から涙がこぼれ落ちた。
彼女は、作物が火事になった悲しみを忘れ、燃えた穀物の灰の中から、実の兄弟姉妹たちへの愛情が生まれた。愛の炎が彼女の心で燃え上がった。
本当に彼が放火したのだろうか?おそらく彼は心に満たされた悲しみをどうしようもなくなって、このように復讐をしたのだろう!彼の若い身体の中に新しい血が流れているのだろう。彼は姉のことでそんなに心配しているのだろうか・・・一度でも彼の顔を見ることができたら!いったい私はどんな運命の下に生まれてきたのか!彼女をこんなことを考えていた。
彼女は弟のことが気掛かりになった。少し前には、プーローは燃えて灰になった作物のことで心を痛めていた。今のプーローは、その作物に火を放ったと思われる人物に同情していた。
放火した人が私の弟じゃなければいいのだけれど!・・・誰か他の人が放火したのであったら・・・そしてその人が捕まってくれれば!・・・プーローの心配はさらに増大した。どうであれ、プーローは弟の幸せと無事を願っていた。プーローは、弟が心の中に燃えている悲しみと愛の炎の火の粉を、畑の作物に放ったのではないかと考えた。おそらく弟は、ラシードがチャットーアーニー村にいないことも知らなかったのだろう。
プーローはバッタリと自分のチャールパーイーに倒れこんだ。いろいろな考えが彼女の心に浮かんでは消えた。
プーローの目には、地面の草からピーパルの木まで、全てが燃えに燃えている情景が浮かんで来た。そして、燃え盛る炎のそばで、一人の美しい若者が、火で手を温めているのを見た。
プーローは驚いて目を覚ました。プーローはこの上なく悲しい気持ちになった。
プーローは、ここ数日の間、胸の中でくすぶり続け、ヒメウイキョウの実を食べたり、ラッスィーを飲んだりする原因となっていた炎が、今日になって彼女の身体を焦がしているように感じた。しかし、プーローには、自分の心の中の炎が本当に自分の身体を焦がしているのか、それとも弟の愛の炎が燃えているのか、理解できなかった。
まるでメロンが切られていくように、町が、村が、人が分割されていった。
まるで風と共に砂埃が運ばれてくるように、周りの村々から噂が流れてきた。次々に人が殺され、家々が燃やされていた。隣人が隣人を殺していた。道を歩いていた人が、道を歩いていた人に切り殺された。人々の命も、人々の財産も、もはや安全ではなかった。
プーローは全てを自分の目で見、全てを自分の耳で聞いていた。プーローの村や、その周辺の村々では、人々が鉄をかき集めていた。家の天井にレンガを集めていた。槍を自分の家に閉まっていた。
「ここに我々の国ができるだろう、ここに我々の政府ができるだろう。」人々はそのことばかりを話していた。「ヒンドゥー教徒は一人残らず追い出そう。」人々は交差点に立って話し合っていた。
今までこんなことがあったろうか!プーローは何度も考えた。こんな多くの人々がいったいどこへ行くというのだろう!
「人々は興奮して正気を失ってるだけだわ。4日もすれば、すぐに治まるでしょう。」プーローは言っていた。
しかし人々はたとえ正気を失っていたとしても、ただ悪い話ばかりをしていた。どこからもいい知らせは届かなかった。プーローは、町の道という道が血で赤く染まり、市場という市場が死体で埋まり、腐った死体から悪臭がたちこめているということを聞いた。誰も死体を焼く者がおらず、誰も死体を埋める者がいなかった。人々は、死体の悪臭によって、国中に疫病が広がるだろうと噂した。
その年の8月15日が過ぎ去った(1947年8月15日は印パ分離独立の日)。村には太鼓が響き、月と星の入った緑色の旗が立った(パーキスターンの国旗)。毎日マスジド(モスク)で人々が集会を開いた。村のヒンドゥー教徒の顔は、まるで誰かがターメリックを投げつけたかのようになっていた。
プーローはどこかの町で国境が造られつつあることを聞いた。その町には全てのイスラーム教徒が残った一方で、その町から全てのヒンドゥー教徒が去って行ってしまったという。その一方で、向こう側からイスラーム教徒が死に物狂いで逃れて来ているという話を聞いた。多くの人がそこで殺され、多くの人が道で殺され、多くの人がこちらに辿り着いてから死んだという。
プーローの耳は、あちこちの噂を聞くうちに鼓膜が破れてしまいそうになった!プーローは、イスラーム教徒がヒンドゥー教徒の女の子をさらい、ヒンドゥー教徒がイスラーム教徒の女の子をさらっているという話を聞いた。彼女たちを自分の家に閉じ込めた者もいれば、彼女たちを殺した者もいれば、彼女たちを裸にさせて道や市場を歩かせている者もいた。
グジャラート地方の、プーローの住む村の周辺では、一番最後に暴動が発生した。プーローの村の者も、彼女の兄弟も、ラシードの親戚一同も、ラシードを除いて全ての人々が暴徒となって駆け回った。プーローにもラシードにも、彼らを説得するできるような状況ではなかったし、そんな勇気すら起こらなかった。
彼らの周辺の村々のヒンドゥー教徒が逃げ始めた。彼らの牛は杭につながれたまま取り残され、彼らの水牛はモ〜モ〜鳴き始めた。彼らの住み慣れた家は空き家となり、彼らの畑は主人を失った。彼らは夜通し逃げたが、村の境で殺された。村から30km離れた場所でも、彼らの死体が見つかった。
プーローの村の全てのヒンドゥー教徒は、ある大きなハヴェーリー(邸宅)に閉じこもった。もし誰かが窓や戸を開けて外に出ると、一瞬の内に殺された。ハヴェーリーには穀物が蓄えこまれていると言われていた。一人のヒンドゥー教徒も表を歩いていなかった。表を覗くヒンドゥー教徒の女性もいなかった。
プーローの村には、ただムスリムだけが残った。村のヒンドゥー教徒は動物のようにハヴェーリーの中に閉じこもった。ある日、彼女の村の者たちが集まってハヴェーリーを攻撃した。彼らは、ハヴェーリーに住む者たちの名前を全て消し去ってしまうことを決めていた。彼らは閉ざされた家々の錠を破壊して、それぞれの家を占領した。もし夜中に誰かがこっそりハヴェーリーから出てくると、次の日プーローは村にその人の死体が転がっているのを見つけるのだった。
ある日彼らはどうやったか知らないがハヴェーリーの戸や窓に油をかけて火をつけたとき、ヒンドゥー教徒の軍隊のトラックが村にやって来た。
ハヴェーリーの中から、炎と同じくらいの大きさの悲鳴が聞こえていた。軍隊は火を消しとめ、中から人々を救い出した。彼らは被害者たちをトラックに座らせた。大火傷を負った人も3人救い出された。彼らの身体からは脂が流れ出ており、彼らの肉は焼け焦げて骨にぶら下がっていた。肘と膝から彼らの骨が外に突き出ていた。3人はトラックに乗せられたが、そのまま息を引き取った。3人の死体はその場に捨て去られ、トラックは去って行ってしまった。彼らの家族は泣き叫んでいたが、軍隊には彼らを火葬する時間がなかった。
プーローの村は空になってしまった。他の国の誰も残らなかった。ただ3つの死体だけが、ハヴェーリーの外に横たわっていた。残っていた彼らの肉や骨を、1日の内に村の犬やカラスがついばんでしまった。
プーローの目は、まるで誰かがガラスの破片で差し込んだかのようになった。ある日プーローは、10人ほどのちゃらちゃらした若者たちが、一人の若い女の子を追いかけて手を打ち鳴らしながら、村のそばを通っているのを見た。彼らがどの村から来て、どの村へ行くのか分からなかった。
プーローは、まるでこの世界では生きること自体が重荷になってしまったように感じた。まるでこの時代では、女として生まれたこと自体が罪のように感じた。
その日の午後、プーローはサトウキビ畑の中に隠れている一人の少女を見つけた。プーローは彼女を夜の暗闇の中自分の家に連れ込んだ。
その少女がプーローに語ったところによると、近くの村でキャンプが作られており、村のヒンドゥー教徒が集まって、軍隊がそこからヒンドゥスターンへ連れて行ってくれるのを待っていた。パーキスターン側の軍隊がそのキャンプを警護していたが、毎晩数人のムスリムがこっそりやって来ては、キャンプにいる若い女の子をさらい、次の日の朝に彼女たちを返していた。
その少女もさらわれた一人で、毎晩別の男のところへ行かなければならなかった。さらわれて9晩が過ぎた昨晩、彼女は何とかして自分を連れて行こうとした男をだまして逃げ出したという。走りに走って、彼女はこの村に辿り着いた。朝になって明るくなると、彼女はどこまでやって来たのか分からなくなっていた。彼女は昼中サトウキビ畑の中に隠れて過ごしたという・・・。
プーローはその話を聞いて、気が変になってしまうかと思った。彼女はこれ以上聞くことができなかった。プーローはその話を信じることができなかった。プーローはその女の子を家の一番奥の部屋に住まわせた。そこにはプーローの家の麦や水牛の飼料が貯蔵されていた。
次の日、2人の男が走ってやって来た。彼らは村中の人々に、ある少女を見なかったか聞いて回った。彼らは村人たちの庭の中まで覗いたが、その女の子のことはばれなかった。
プーローの心には多くの問いが沸き起こったが、彼女はその答えを考えることはしなかった。彼女には、この地上に人々の血が流れた今、以前のように金色の麦が実るかどうか、この地上に腐った死体が転がる今、以前のようにトウモロコシからあの香りが立ち上るかどうか、分からなかった。女性に対してこのような犯罪を犯した男たちのために、女性たちはこれからも子孫を産むのだろうか・・・彼女には分からなかった。
ヒンドゥスターンへ向かう一団が、プーローの村のそばに来て留まった。男も女も全ての人々が徒歩で移動していた。牛車には子供たちを乗せていた。数人の兵隊が隊列の前方に、数人の兵隊が後方にいた。旅人たちの目は虚ろだった。道の砂埃が彼らの顔や頭に山積していた。
プーローの村の近くまでやって来たところで日が沈んでしまった。彼らはそこで一晩過ごさざるをえなかった。
プーローは落ち着いていられなくなった。彼女にはひとつの考えが浮かんでいた。この道はラットーワール村に続いている。この旅団の中に、必ずあのラームチャンドがいるはず・・・最後に一度だけ・・・たった一度だけ・・・最後に一度だけ彼に会えたら・・・もう彼がこの国に住むこともないだろう・・・この機会を逃したら、私はもう二度と彼の消息を知ることができないだろう・・・今後二度と彼の村から私の村に風も吹いてこないだろう・・・。
隊列の人々は、残った装飾品やお金で、道中の村々の人々から作物を買っていた。村の人々はそこへ行って、彼らと交渉して、兵隊の監督の下、自分の穀物などと金を交換していた。それを理由にして、プーローもその旅団に近づいた・・・。
プーローは、旅団の中に、座っているラームチャンドを見つけた。ラームチャンドは、ラットーワール村の畑の中で、涙を流して立っていたプーローに気付いた。
ラットーワール村の畑では、プーローの顔を臆病な気持ちが閉ざしてしまっていた。今日の彼女の顔は、近くに立っていた兵隊が隠してしまっていた。プーローは何も言うことができなかった。
「何か欲しいものはある?」プーローはラームチャンドの方を向いて言った。
「ああ。」ラームチャンドの目は、プーローの顔をじっと見つめていた。おそらく今でも彼は彼女の正体をあばこうとしていたのだろう。
「分かったわ、お金を用意しておいて、私は夜に来るわ。」そばに立っていた軍隊の方をチラリと見て、プーローは再びラームチャンドの方を見た。そして彼女は家に帰った。
プーローはラシードに、「家に隠れてる女の子をあの旅団に預けたいの」と言って、小麦粉とギー(油)の入った壺を布に包んで、夜の暗闇の中女の子を連れて、眠り込んでいる旅団の方へ向かって歩き出した。
一日中歩いたことにより、人々は疲れ果てて眠っていた。彼らの頭上には常に恐怖がコウモリのように飛び回っていたにも関わらず、彼らは安穏に眠っていた。
「私は夜に来るわ。」ラームチャンドの耳に、プーローの声が夕方から響き渡っていた。ラームチャンドは、夜の静けさの中に、誰かの足音を聞いた。
兵隊は巡回して警護に当たっていた。プーローは忍び足で歩きながら旅団に辿り着いた。
彼女は頭から包みを下ろしてラームチャンドの前に置いた。そして女の子に座るように言った。
「お前はプーローだね?」今日もラームチャンドはラットーワール村の畑でしたのと同じ質問をした。
「まだ聞くつもり?」プーローは不満げに言った。人生の中で、これが彼女のラームチャンドに対する、最初で最後の不満だった。ラームチャンドは頭を下に下げた。
「私のお父さんお母さんは元気?」プーローは大きく息を吸ってから言った。
「彼らは結婚した後、帰ってないが・・・」ラームチャンドは口をつぐんだ。
「結婚?誰の結婚?」プーローは聞いた。
「お前がいなくなった後、彼らはある晩何も言わずにお前の妹と私の結婚をさせたんだ。そしてお前の弟と、私の妹の結婚も。それ以来、彼らは村に帰ってないよ。今頃彼らはシャムにいるはずだ。でも・・・」ラームチャンドはまた黙ってしまった。
「私の妹・・・ということは、妹がこの旅団にいるの?」プーローにとって、ラームチャンドと自分の妹の結婚の話は初耳だった。
「いや、つい先日お前の弟が来て、私の妹を我が家に返し、私の妻を一緒に連れて行ってしまった。彼女がここにいたなら彼女も・・・」ラームチャンドの目が涙で溢れた。
「彼女も・・・何が起こったの・・・」プーローはよく理解できなかった。
「よく分からない、いつの間にか、誰かが私の妹を連れ去ってしまったんだ。家から出たときは、彼女は一緒だった。私は老いた母親を背負って旅団に来たんだ。そのとき妹は私の後をついて来ていた。でも今、旅団にはいない・・・」ラームチャンドは叫びたい欲求を抑えつつ、小さな声で言った。彼は泣き叫びたかったが、ターバンを口に押し込んでこらえた。「母さんの悲しみは救いようがないほどだ!」ラームチャンドは言った。
プーローのハラワタは煮えくり返るようだった。
「何とかしてくれ、何か分かるかもしれない。生きているのか、死んでいるのか・・・。」ラームチャンドは言った。
プーローは腹の中の苦痛のため、何も言うことができなかった。
「彼女の名前は多分ラージョーでしょ?」プーローは思い出した。自分の婚約式の日、彼女は弟の許婚の名前を聞いていた。
「そう、彼女の腕にも彼女の名前が彫ってある。」ラームチャンドは言った。兵隊が巡回していた。寝静まった人々の間で、ラームチャンドとプーローは座って小さな声で話をしていた。
「この子を私はあなたに託そうと思って来たの。彼女を旅団に入れてあげて。ヒンドゥスターンに行ってから、彼女の両親を探してあげて。もし見つかったらだけど・・・。」プーローは少女の腕をラームチャンドに掴ませた。
「私の弟が来ていたそうね・・・一度でいいから会いたかったわ・・・」プーローは自分の望みを口に出した。
「ついこの前・・・お前のチャットーアーニー村の畑で火事があったのを知ってるかい・・・」ラームチャンドは言った。
「火事?・・・ええ、知ってるわ。私の弟が放火したっていうのは本当なの?」プーローは、ラシードがその噂話を聞かせたときのことを思い出した。
「そうだ、彼が放火した。彼にはお前がどこにいるのか分からなかった。怒りから彼はラシードの畑に火を付けたんだ。」
プーローは震え上がった。彼女の弟は今や成長し、彼の心には復讐の炎が燃え上がり、姉のことを思い出していたのだ。同時に彼女には、弟の妻が行方不明になった不幸を思い出した。誰かが無理矢理さらって行ったのか、今彼女はどんな状態なのか・・・私のラームチャンドの妹・・・
「私に、このサッカルアーリー村の住所宛てに手紙を書いて、自分の住所と一緒に。ラージョーのことで何か分かったら、私も手紙を送るわ・・・」プーローは言った。
夜はまだ明けていなかった。兵隊は旅団の人々を起こし始めた。旅団は前進しなければならなかった。プーローは立ち上がった。
プーローはラームチャンドの手を掴んだ。彼女は何も言うことができなかった。
プーローが旅団から離れようとすると、一人の兵士が彼女を棒で止めた。「お前は誰だ?どこへ行く?」
「私は作物を売りに来ただけです。」
「いくらで売った?金を見せろ。」兵士は叫んだ。
プーローはショールの中に手を入れて、自分の銀製の腕輪を見せた。そして急いで村のほうに走り去った。
おそらくその兵士は、ヒンドゥー教徒が銀製の装飾品をほとんど付けないことを知らなかったのだろう。この女性が作物の代わりにどこから銀の腕輪を手に入れたのか、考えもしなかった!
夜、プーローはチャールパーイーに横たわりながら、天井の黒い梁を見つめていた。プーローは、誰かの娘、姉妹、妻たちが閉じ込められている閉ざされた部屋のことを思い浮かべていた。その中の一人がラージョーなのだ。ラージョーは、ラームチャンドの妹であり、自分の義理の妹だった。まだ見たことのないラージョーの顔が、プーローの目の前に浮かんで来た。その顔はまるで破れた葉っぱのようだった。まるで抜け落ちた羽のようだった。
ラージョーは既婚なのだから子供もいるだろう、とプーローは考えた。彼女の心はどんなだろう、彼女の身体に何が起こっただろう。いったい彼女は今どこにいるのだろう!私は彼女をどうやって探せばいいのだろう?どうやって見分ければいいのだろう?あの日サトウキビ畑の中に隠れていた少女はラージョーだったらよかったのに・・・私は彼女を旅団に合流させ、ラームチャンドに引き合わせることができたなら・・・。
プーローは全てのことをラシードに話し、彼の足元にひれ伏した。
「どうか私の言うことを聞いてください。私は今まで一度もあなたに何も求めなかったわ。だからどうか私のために、ラージョーのことを調べて来てください。お願いだから・・・」プーローの目から流れる涙は止まらなかった。ラシードは、できることは何でもすると約束した。
ラシードは考えに考え抜いた末、ひとつの結論に達した。ラージョーが生きているなら、きっとラットーワール村にいるだろう、と。彼は自分の兄弟と共に出掛けたが、旅団の中に彼女はいなかった。旅団の混乱の中で、彼女は誰かにさらわれてしまった可能性があった。
ラシードはラットーワール村をグルリと回ったが、他人の家の中を覗くことは不可能だった。彼は村の店で何度も買い物をしたが、ラージョーを見つけ出すことはできなかった。彼は、村の数人の若者が、移動中の旅団から2、3人の女の子をさらって来たという話を耳にした。ラシードは、その中の一人がラージョーであると信じて疑わなかった。
その村の人々はラシードのことを知らなかったし、その村にラシードの知り合いも住んでいなかった。彼は誰かのところで4日間過ごし、誰かから村の様子を聞いた。
プーローはいいことを思いついた。彼女は階段井戸の聖者を知っていた。彼らは子供たちを2人連れて聖者のところへ行き、そこの部屋に滞在した。昼も夜も心配し続けていたため、プーローの目は慢性的に疲れるようになっていた。プーローは毎朝礼拝をしてから井戸の水で自分の目を洗い、聖者にミターイーを献上していた。昼になると、彼女は刺繍布を包んで村へ行き、それを売り歩いた。
その時間には、村の男たちは畑へ行っており、女性たちは家の中で家事をしている頃だった。プーローは全ての家へ行って売っていた。プーローは刺繍布を、すぐには売れないような高い値段で売っていた。元々村人たちは自分で作った敷物や刺繍布などをたくさん持っていた。それに加えて、略奪によって村人たちの倉庫は潤っていた。プーローから何かを買う必要などなかった。しかしプーローは図々しい商人のように彼らの家の中庭まで入って込み、中を覗いたり、女性たちとおしゃべりしたりした。彼女はうまく略奪のことに話を持って行き、誰か何を得たかを聞き出した。ヒンドゥー教徒が残して行った家のことも聞き出した。プーローはラームチャンドの家を知らなかったが、村人たちとの会話によって、彼の家を見つけることができた。ラシードとプーローは、ラージョーをさらった人は、ラージョーの家まで占領しているのではないかと疑った。プーローはその家にも何度も行商に訪れたが、その度に一人の老婆が出てきて、「うちは何も必要ないよ」と言って彼女を玄関のところで追い返してしまうのだった。
他の人の家に無理矢理入り込んでいたように、プーローはある日やっとその家の中に入り込むことに成功した。
「ちょいと、何も必要ないのは分かってるけど、見るだけは見ておくれよ。見物料は取らないからさ」と言って、プーローは刺繍布の包みを地面に下ろして、商品を広げ始めた。中庭には、その老婆の他に誰もいなかった。
「アッラーの慈悲あれ!私に一杯水をくださいな、朝から喉が渇いて仕方ないんですよ。」プーローは思い切って老婆に言った。
「水よりもラッスィーを飲んで行きなさい。お前、ショールや刺繍布を売りたいなら、どこかの町へ行った方がいいよ。誰も綿を紡いだり、布を織ったりしてない場所じゃなきゃね。村のどの家にも刺繍布の不足なんてあるもんかい!」老婆はプーローに助言を与え、家の中に顔を向けて声を上げた。「これお前、一杯ラッスィーを持ってきな!」
プーローは心臓が高鳴り始めた。中から出てきた少女の顔は、本当に破れた葉っぱ、抜け落ちた羽のようだった。プーローは、彼女こそラージョーだ、と心の中で飛び上がった。
ラージョーの居所が分からなかったとき、プーローは何とかしてラージョーに会えたらと願っていた。ラージョーと思われる少女に会えた今、どうやってその仮説を確かめたらいいのか分からなくなった。
「あんたの娘さん、大丈夫かい?」プーローは老婆に同情を込めて言いながら、女の子からラッスィーの入ったコップを受け取った。
「大丈夫さ・・・ただちょっと・・・。」老婆は口ごもった。
「ちょっと塩ちょうだいな、ラッスィーに混ぜたいから。」プーローはラッスィーを一口飲んだ後、コップを手に持った。
少女は黙って塩を持って来て、プーローの前に出した。彼女の手から塩を取るときに、プーローは彼女の指を押してみた。少女はハッとプーローの方を見たが、その唇に笑みはなく、その口から一言の言葉も出なかった。少女はサトウキビの皮のように暗い表情をしていた。
プーローは、この少女がラージョーであれ、誰であれ、無理矢理連れてこられた女性であることは確実だと思った。この家がラームチャンドのものであったことは既に知っていた。プーローはこの少女がラージョーであると信じて疑わなくなった。
ラッスィーを飲んだ後、コップを地面に置きながらプーローはその少女の腕を掴んだ。
「こっちに来な、私がお前の脈を見てやるよ。お前の顔色はターメリックのようになってるからね。」プーローは片手を取って、彼女の袖を少しまくった。少女の腕には、ヒンディー語で彼女の名前が彫ってあった、「ラージョー」。それでも彼女は何も言わなかった。彼女の唇は、冬の霧のような沈黙で閉ざされていた。
「何とかしてくれるかい!この娘が家に慣れるように。家の男とも口を利こうとしないんだよ。」老婆は困った顔をして言った。
プーローは平静を保つのが難しくなっていたが、急いで答えた。「私のところに、この女の子が数日間の内にトウモロコシの実のように明るくなるジャンタル(魔除けのお守り)があるよ。」
「そんならいくらでも出すから、そのジャンタルを持って来ておくれ。」老婆はプーローのショールを掴んで言った。
「こんないい話はないよ、明日にでも持って来ますから。アッラーがお望みなら・・・」と言いながら、プーローは刺繍布を包み込んだ。少女は聾唖者のように彼女の方をじっと見つめていた。
刺繍布の包みの重みで、プーローの腰は痛むようになってきた。痛みをこらえてなんとか階段井戸の自分の小屋まで戻ってきた。
「今日は大きな収穫があったわよ。」プーローはラシードに全てを話した。
「何か計画を立てねば・・・」ラシードは考え込んだ。
「私を馬でさらったのと同じように、思い切って・・・」プーローはラシードをからかって笑った。
プーローとラシードはいろいろ方法を考えたが、いい考えが浮かばなかった。ラシードは、ここから逃がして連れて行くことは難しくないが、そこから向こうへ連れて行くのは難しいだろう、と言っていた。
プーローの心にひとつの不安が浮かんだ。それは今まで考えてもいなかった不安だった――私の両親が私を自分の娘と認めなったのだ、彼らは自分の嫁を受け容れるだろうか?もし万一彼らが拒否したとしたらどうなろうだろう?・・・
ラシードはプーローに、政府から発表された知らせのことを教えた。その知らせは、無理矢理連れさらわれた女の子を見つけ出して返しなさい、なぜならその代わりに向こうの国から同じように探し出された女の子たちを返してもらえ、彼女たちの両親の元に再び帰ることができるから、と呼びかけられていた。
プーローの心は痛んだ。彼女がさらわれたとき、世界の全ての宗教は彼女の進む道に棘となって突き刺さった。両親は彼女を受け容れなかった。サスラール(嫁ぎ先の家)の人々も彼女を受け容れなかった。今や全ての宗教に対する信頼感を失っていた。今や・・・
プーローは自分のことを考えるのをやめた。ラージョーのことを考え始めた。
その夜、プーローは星を数えながら過ごした。朝になるや否や、彼女はあの老婆が畑で働く息子のためにローティーを持っていくのを見張った。彼女はまた数枚の刺繍布を頭において、布切れに灰を少量くるんで出掛けていた。
ラージョーの家の閉じた扉を自分の手で押して開けるとき、プーローは全ての聖者に祈った。あるときから忘れ去ってしまった神々のことも思い出した。以前のプーローは、神の名を口に出すときにはいつも、「神は私の義理の父親で、義理の娘だった。どの神も私の苦しみを救ってくれなかった」と言っていた。しかし今日、プーローは心の中で、まごつきながらも、「なんとかしてラージョーと2人っきりで会うことができますよに!」と神様に祈っていた。
プーローがラージョーの家に着いたとき、正午になっていた。老婆は息子にローティーを届けるために外出していた。ラージョーは中庭に一人で、シーツも敷かずにチャールパーイーに横たわっていた。
「お母さんはどこ?」プーローは中庭に踏み込みながら聞いた。
「畑へ行ったわ。」ラージョーは、昨日来た刺繍布売りの方を見て言った。ラージョーの心の中で、刺繍布売りに対して以前にはなかった興味が沸いてきた。彼女の顔にはその興味が表れていた。ラージョーは起き上がってチャールパーイーに座った。
一瞬の内に、プーローはラージョーの顔の仕草の中に、自分の母親、妹、そして義妹の顔を見つけた。プーローはラージョーに抱きついた。
プーローは思った。私は泣いてしまうだろう、大声で泣いてしまうだろう、その泣き声は壁を通り抜けて、畑まで届いてしまうだろう、私の泣き声は村中に響き渡るだろう、私の泣き声は町よりも遠く、もっともっと先へ届くだろう・・・
プーローは泣き声を喉から外へ出すまいとこらえた。
「お前はラージョーね・・・私の義妹・・・」プーローは自分の心で吹きすさぶ嵐を押さえ込みながら言った。
「あなたはプーロー?」ラージョーは少し彼女の胸から離れて彼女の顔を見た。ラージョーはプーローを一度も見たことがなかったが、それでもラージョーは、プーローの顔は、彼女の弟のように、自分の夫のように思えた・・・ラージョーの心の中には、まるで自分の夫の顔の方をまっすぐ見れないように、恥じらいの気持ちが生じた・・・ラージョーはプーローの胸の中に飛び込んだ。
ラージョーの心にそのとき沸き起こっていた感情は、おそらくプーローの心の中にも染み込みつつあった。プーローは何も聞く必要がなかった。プーローは彼女を力いっぱい抱きしめた。
「誰か来てしまうわ、ラージョー!私の話を聞いて。」プーローは時間のことを気にし始めた。ラージョーの嗚咽は止まらず、彼女の息は整わなかった。
「お婆さんはいつまでに戻ってくるの?」プーローは聞いた。
「何も知らないわ。私を連れて行って。」ラージョーは泣き止まず、ただプーローにしがみついていた。
「お前を連れにやって来たのよ、他に何があるっていうの!私の話を聞いて。」プーローはラージョーの肩を掴んで言った。
「ああ、私を連れて行って!」
「しっかりして、誰かが来ちゃうわ・・・」
「私を連れて行って。私は一生あなたの奴隷になるから。」
「馬鹿なこと言うんじゃないの!このままお前を連れて行くことなんてできないでしょ。とにかく私の話を聞いて。」
「そんな!私はどうすればいいの、私はここでもがき苦しんで死んじゃうわ。」ラージョーは泣き続けた。プーローは、まともに話ができないまま、あの老婆が来てしまうのではないかと恐れた。プーローは自分のショールの端で彼女の顔を拭き、何とかして彼女を黙らせた。
「たまには家の外に出てるの?」
「出てないわ。」
「でも朝には畑へ行ってるでしょう!」
「あの人が一緒よ。」
「今日はちょうど新月の日だわ、今夜お前は外にある井戸のところまで来れる?そうしたらラシードがお前を馬に乗せて行ってくれるわ。」
ラージョーはうつむいて黙り込んでしまった。夜中に一人で井戸のところまで行くのは、この上なく難しいことに思えた。しかも彼女はラシードを知らなかった。もし万一誰かに見つかったら、命の保証はなかった。
「私はどうやって家の外に出ればいいの?」
「夜になって、みんな寝てしまったら、隙を見て外に抜け出しなさい。」
「彼はお酒を飲むわ。夜に2、3杯多めに飲ませればぐっすり眠るでしょう、でも外の庭にはあの老婆が・・・」
「老婆は阿片とか吸ってないの?」
「私は吸ってるところ見たことないわ。」
「何とかしてあそこまで辿り着けたら・・・」
「でも・・・私はその人を知らないし・・・そこにあなたがいてくれれば・・・。」
「彼は夜通し待ってるわ、もし私がいたら、お前と私を乗せて走らなくてはならなくなっちゃうでしょ。」
「私は彼を一度も見たことがないわ。」
「私を信じて。お前のためを思ってやってるのよ。そうだ、この指輪を見て。これを彼の指につけさせるわ。見て、ラージョー。」
「今夜抜け出せれなかったら・・・?」
「そうしたら明日の夜。彼は3日間お前を待ち続けるわ。」
「表から足音がするわ、多分誰か来てる。」
プーローはチャールパーイーから立ち上がって床に座った。チャールパーイーの足元に刺繍布を置いて、プーローはショールに結んであった灰の包みを見た。もし老婆が来たら、いつでもジャンタルと灰を与えられるようにした。
しかし老婆はまだ帰って来なかった。
「このジャンタルを言い訳にして、私を毎日どこかの井戸に連れて行って、そこでもし機会があったら・・・」ラージョーは小さな声で言った。
「そんなことしたら私が疑われるわ。まず彼がお前を連れて村を出るわ、その後も私は2、3日同じように村を行商して歩くわ。誰にも疑われないようにするためにね。」
「道の途中で誰かに捕まったら・・・私、怖いわ。」
「自分の運命を信じて。このままここにいても何の得もないでしょう。」
「でも、私のせいであなたに迷惑がかかってしまうわ!」
「その話は後よ、今はそんな時間ないわ。もう私は行った方がよさそうね。あのお婆さんに見つからないようにした方がいいわ・・・」
「そんな!私も連れて行ってよ。」プーローが立ち上がると、ラージョーは子供のように彼女にしがみついた。プーローは扉の方を見ながら、ラージョーを力強く抱きしめ、そして言った。「今夜・・・深夜・・・駄目だったら明日・・・でも怖がっちゃだめよ。」プーローは刺繍布をまとめて、家の外に出た。
チャールパーイーの上にラージョーは両足を伸ばして横になった。今日、彼女は自分の身体の隅々に何か不思議な力がみなぎっていくのを感じた。すると、ラージョーは家の壁の中から声がするのを聞いた。「今夜・・・深夜・・・」ラージョーは回廊のひとつひとつのレンガを見た。「ここが私の家だった。ここで生まれ、ここで育った。ここで私は大きくなった。この家から私の輿が出て行った。私はこの家に戻ってきた。皆はこの家から出て行ってしまった、でも私の死体はここに残った。私は自分の家の中で余所者になってしまった。この家が私を生み、この家が私を呑み込んだ。」ラージョーは家の四方の壁を見渡した。「この壁たちも恥知らずだ、私が辱めを受けるのを見たのに、私の尊厳が奪われたのを見たのに・・・でも今日・・・今夜・・・深夜・・・全ての壁は崩れ落ちるでしょう、全ての戸が外れるでしょう・・・私は・・・」
老婆が閉まっていた戸をあけて中庭に入ってきた。
「いいときに来てくれた。」ラージョーは心の中で言った。
「今日あの刺繍布売りは来なかったかい?」老婆は帰ってきてすぐにそう聞いて、手に持っていた野菜の入った壺を地面に置き、ラージョーが寝ていたチャールパーイーの端に座った。
刺繍布売りのことを聞かれて、ラージョーの顔が一瞬ピクリと動いた。ラージョーは頭を振って言った。「来なかったわ。」そして彼女は考え始めた――プーローはどうして私がここにいることが分かったのだろう?彼女はどうして私を探しに来たのだろう?彼女はどこの村に住んでいるのだろう?私は彼女に何も聞かなかった。聞く時間すらなかったわ――そして、彼女の耳の中で、「今夜・・・深夜・・・」という言葉が浮かんでは消え始めた。
「言っただろう、一握りのモート豆を入れて、米を炊くようにって。ああ、疲れちまったわ」といいながら、老婆はチャールパーイーの上にグッタリと横になった。
最後の仕事を何とか早く終わらせようとする人のように、ラージョーは起き上がって豆を選び、米を選び、コンロに2、3本の木片を入れて、キチュリー(インド式お粥)を作り始めた。いつもは老婆が小麦粉をこねていたが、今日はラージョーは自分で小麦粉をふるいにかけ、こねた。
今日という日は、まるで壊れた靴のようになかなか進まなかった。やっと夜がやって来た。老婆の息子がやって来たとき、今日のラージョーは辛い気持ちがしなかった。以前、ラージョーは彼を見るといつも、まるで何百ものお椀が自分の額で弾けるような思いがしていた。
鍋の中をヒシャクでかき混ぜているとき、今日は3度もラージョーはヒシャクを落としてしまった。2度も彼女の手からローラーが滑り出してしまった。1、2度彼女は銅製のコップを落としてしまった。
「ちゃんと仕事しな。」老婆はいらいらして怒鳴った。
「その目は節穴か!」老婆の息子も叫んだ。
しかし今日のラージョーは、老婆の言葉がちっとも罵声には聞こえなかった。老婆の息子の話は耳に入ってすらこなかった。まるで家の全ての財産も、今日は老婆とその息子の顔をいらつかせているように感じた。
ラージョーには今日、いまだかつてないほどの勇気が沸き起こっていた。彼女の心は恐怖でおびえていなかった。彼女の頭に何の心配もなかった。ただ、決行の時のみが、刻一刻と近づいてきていた。もうすぐ夜中になるだろう、もうすぐ皆寝静まってしまうだろう、そして石鹸をつけた手から腕輪がスルリと抜け出すように、彼女はこの家から抜け出すだろう。
以前のラージョーは、ムカムカする気持ちを抑えながら酒のボトルを老婆の息子の前に置いていた。しかし今日のラージョーは、自ら中から酒の瓶を取り出した。それは老婆の息子がカルダモンの実を混ぜて特別強くした酒で、他の酒とは別にして置いてあるものだった。
老婆の息子は考えていた。今日のラージョーはモート豆のキチュリーをスープみたいにしてしまった。今日のラージョーは酒の瓶を自分から取り出してきた。今日のラージョーは機嫌がいい。ということは・・・
老婆はうたた寝をしていた。
「庭は寒くなったから、あなたのチャールパーイーを中に入れておきました。中に行って寝てください。」ラージョーは家の女主人のように老婆に言った。老婆は目を見開いてラージョーの方を見た。
「今日は天地がひっくり返っちまったみたいだ。今日はこいつにジャンタルを着けさせようとしていたところだったが、着ける前から効果が出たみたいだ」と老婆は心の中で考え、中には行って横になった。
夜の暗闇はますます暗さを増して行った。老婆の息子は酒に酔っ払って、ラージョーの腕を引っ張っていた。・・・
いつの間にか3時間が過ぎ去った。老婆の息子は酔っ払ってチャールパーイーの上で眠っていた。
その家の壁たちは、その家の窓たちは、その日の深夜に、ラージョーが忍び足で玄関の戸を開けて、外に出て行く様子を見守った。
ラージョーは少し進むと、誰かが裏から追いかけて来るのではないか、という恐怖に駆られた。誰かが私を肩に乗せてしまうのではないか、誰かが私の首を切ってしまうのではないか。冬の真夜中の寒さの中でも、ラージョーの額には汗が滴り落ちていた。
新月の夜だったが、ラージョーには空にまたたく星の光すら明るく感じられた。自分の家の壁を乗り越えた後、隣の家の入り口に着いたところでラージョーは突然立ち止まった。ラージョーは振り返って自分の家の高い壁の方を見た。霧のように全ての路地は静まり返っていた。それでもラージョーは大きな通りを避け、狭い路地裏の道を歩き始めた。
家並みが途切れた。郊外にある井戸に辿り着くためには、広大な平地の中の道を進まなければならなかった。ここでラージョーの裸の足から震えが生じ、彼女の頭の先まで広がった。ラージョーは後ろを振り向いて、墓のように寝静まっている家々を見た。今まで何も起こっていなかった、今まで墓の中から死体が起き上がっていなかった。ラージョーは、自分の息の音がまるで鍛冶屋のふいごのように聞こえていた。しかしラージョーにそんなことを考えている暇はなかった!ラージョーは一度、霧のような星が散らばる空を見上げ、平地の中に足を踏み出した。
ラージョーの心は、平地を歩いているときに誰かが自分を見やしないかと恐れていた。ラージョーは白っぽい服を着ていた。彼女は、深い暗闇の中で、自分の服の白さにすら恐れを覚え始めた。しかし今やラージョーは平地を通り抜けることができた。彼女は振り返った。平地には誰もいなかった。井戸の方を見て、彼女は不安になった。井戸には誰もいなかった。ラシードもいなかった。彼女はうろたえてしまった。村に帰ることは彼女にとって不可能だった。彼女は井戸を一周した。彼女は、この世界のどこにも安住の地がないなら、この井戸の中に身を投げ出そうと決意したかのようだった。
近くの茂みの中から、毛布に身を包んだ一人の男が出てきた。「お前がラージョーかい?」その男はラージョーのそばに来て、毛布の中から顔を出した。
「私に印を見せて。」ラージョーはラシードの方をチラリと見た。ラシードの顔は、まるで憐れみの印が押されたかのようだった。ラージョーは落ち着いた。ラシードは自分の手の指輪をラージョーの前に出した。
「お前を送ってから、明日か明後日にプーローを連れてくる。子供は彼女のところにいる。」ラシードは井戸の囲いから降りると、茂みの中に結んでいた馬を連れてきた。
「ヤー・アッラー!」ラシードは一度声を出して、ラージョーを片腕で馬の上に持ち上げた。
ラシードは、一度馬に拍車を当てた途端、チャットーアーニー村のでこぼこ道からプーローを持ち上げて自分の馬に乗せたときのことを思い出した。ラシードは、自分がもう一度同じように馬を走らせていることに、もう一人の村の女の子をさらっていることに、驚いた。若い興奮は、今日のラシードの腕にはなかった。しかしラシードは考えていた。プーローをさらったときは、馬を走らせれば走らせるほど、自分の魂に重りの石が次々と置かれていくようだった。今日、ラシードはラットーワール村の境から馬を走らせれば走らせるほど、自分の魂を抑え付けていた重みが、次第に取り除かれていくように感じた。馬はまるで羽を持ったかのように、軽やかに走っていた。
夜明けの光と共に、ラージョーの失踪の知らせは村中に広まった。ヨーグルトに攪乳器が入れられる頃には、全ての家でラージョーの噂話がされていた。
周辺の村々にはヒンドゥー教徒の名札すらなかった。ムスリムがどうしてこんなことをするのか!人々は当惑してしまった。
太陽の光はすぐに勢いを増した。牛糞のコンロで豆が調理されていた。女性たちはタンドゥール釜を温めていた。その中から燃えかすの匂いと煙の輪が出て、村中を覆っていた。そのときプーローは村に入った。
今日、ラージョーの家の扉は、死んだ動物の口のように開いていた。プーローがその家の玄関に足を踏み入れると、中庭には、昨夜料理に使った鍋が散らかっており、そこにハエがたかっていた。プーローは、今朝から誰も何も食べたり飲んだりしていないことを知った。
「ああ、お前、どこかであのアバズレを見たかい?」老婆の額には、まるで誰かが素焼きの壺を叩きつけたかのように、多くの皺が寄っていた。
「誰のことです?」プーローは頭から刺繍布を下ろして中庭に置きながら聞いた。
「ほら、あの奴隷女だよ、アッラー、どうにかしてください。」老婆は再び嫌悪を自分の額に寄せて言った。
「あらまあ?嫁さんはどこです?」
「あの恩知らずが逃げちまったのさ。」
「なんてこったい、でもいったい誰と?せっかく彼女のためにジャンタルと灰を持ってきたのに。」
「ジャンタルと灰なんて燃やしちまいな!いったいどこの幽霊が連れ去ったんだか。」
「何を言ってるんです!村に彼女を連れ去る人なんていやしません!外の畑に行ったんでしょう、すぐに帰って来ますよ。」
「ちょいと!畑に行ったなら、もう正午になったってのにどうして帰って来ないんだい。」
「でも、あの娘はローティーの切れ端じゃないんだから、カラスがつまんで持って行くなんてこともないし。」
「だから言ってるだろう。どっかの井戸に落ちて死んだのか、どっかの池にでも落ちたのか。・・・私は初めっからあいつを信用してなかったのさ。ただ息子があいつにちょっかいを出してたんだ。息子は『今頃どこへ逃げるって言うんだい、身寄りがるわけでもないし!』なんて言ってたけどね。」
「彼女の両親はどこの村の人なの?」
「両親なんて糞喰らえさ。私は初めの日に言ったよ、見知らぬレンガで家は建たないってね。でも息子はすっかり舞い上がっちまってて、老婆の言うことなんて、聞こうともしなかったのさ。・・・まあお前に隠してもしょうがないしね、村中みんな知ってるんだ、あいつはヒンドゥー教徒の娘だったんだよ。村からヒンドゥー教徒が逃げ出したとき、息子がどっかからかっぱらって来たのさ。アッラーはご存知だろう、私は最初っから言ってたんだよ、娘や嫁がこんなことじゃあ手に入らないってね。アッラーディッター(息子の名前)は意味もなく罪を背負い込んぢまったよ。いつこの罪を償えることやら・・・。」
「大体話は分かったわ!だから彼女はあんなに落ち込んでたんだね。でも逃げたとしてもどこへ行くって言うの?ここにはあの娘の知り合いもいないんだよ。カラスから逃れたとしても、トンビに喰われてお終いでしょう。多分今頃どこかの井戸に落ちてるんでしょうよ、たとえ自ら飛び込んだとしても、うっかり落ちてしまったとしても。」
「うちから汚点は消えた。でも息子は私をいじめるんだよ。息子は言うんだ。『母さんがボヤッとしてるから、逃げられたんだ。奴は小鳥じゃない、きっと誰かが奴をさらって行っちまったんだ』ってね。」
「彼女は前にも一人で外出してたの?」
「どこへ行くってんだい!あの世へ行くとでも言うのかい?以前は私が息子にローティーを届けに出掛けるときには、家の外から錠をかけて行ってたんだよ。でも息子も私も、あいつにはどこにも逃げ場がないと考えたんだ。四六時中乗っかってれば、家のことも忘れるだろうってね。あいつは昼には1、2時間家に一人でいたよ。昨日も私はローティーを届けて来たんだ。あの娘はおとなしくここに座ってたよ。夜にはモート豆のキチュリーを作って、香味野菜のカレーを作って、ローティーを温めて、私たちに食べさせたんだ。自分も食べたよ、そんで私のチャールパーイーを中に入れて、『庭は寒くなりました』って言ったんだ。息子は少しお酒を飲み、私は寝ちまったよ。それからいつ何がどうなったのか、朝になって目が覚めて、あいつを呼んでみても声がしない・・・」
「私が言った通り、井戸や池を探させてみました?一緒に逃げ出す人なんていさそうになかったし。」
「いったい誰と一緒に逃げたって言うんだい!」老婆は頭を膝に乗せた。
「全く不思議な話だね。肉のかけらも落っこちてないから、犬や猫がくわえて持ってっちまった訳でもないし。村の中は探させたんでしょうね?」
「ああ、朝から村の男を一人一人ここに呼んだよ。村の者どもは隅から隅まで探し回った。今頃息子のアッラーディッターが、村の若者と一緒に井戸の方へ行ってるよ。どこかで死体でも見つかったなら、息子もいつまでも探し回らなくて済むんだがね。息子に何事もなけりゃいいけど・・・。」
プーローの顔には今にも笑いが込み上げそうになっていたが、そのとき3人の男が外から帰って来た。
「俺たちは全ての井戸や溝を見てきたが、どこにも奴の骨すら見つからなったよ」と言って、3人は庭のチャールパーイーの上に座った。
「この恥さらしが!お前はどうして自分を狂わせるんだい!幽霊か化け物の仕業だろう!」老婆はアッラーディッターの方を見て、愛情を込めながら言った。プーローは、彼がアッラーディッターであることを知った。
プーローは、ラージョーの落胆した顔を思い出した。ラージョーの顔は、まるで狡猾なトンビの鋭い足に数日間捕まえられていた小鳥の骨のようだった。
「俺が思うに、その女は真夜中に起き上がって外に出て、そこを何かの動物が持ち去ってしまったんだろう。」その中の一人が、アッラーディッターの方を見て言った。
「ジャッカルも狐もどこにもいないし、この村の近くにどんな動物がいるって言うんだ!」他の男が座りながら言った。
「どうせ泥棒でも来て連れ去っちまったんだろう。お前、少しは何か食べな。」老婆は自分の息子を落ち着かせるために言って、立ち上がってローティーの準備をしに行った。
「それじゃあ、私は行くとするわ!アッラーのご加護がありますように。」プーローは刺繍布を包んで包みを頭の上に乗せた。
「おい、お前は誰だ?」アッラーディッターはプーローの方を睨んで言った。村の女性たちがプーローのことを既に知っていたので、アッラーディッターは今まで彼女のことに注意しなかったが、刺繍布を持ち上げている彼女を見て、彼は大声を上げて質問した。
「誰だって?刺繍布を売ってるんだよ、その他に何だって言うのさ?」そばにいた老婆が答えた。
「俺はお前をこの村で見たことないぞ?」アッラーディッターは疑わしい目で聞いた。
「いったいいつからこの娘はここで売り歩いていることか!」老婆はまた息子を叱りながら言った。
「しかしお前、どこの村から来た?」アッラーディッターはプーローの方を見て言った。
「2人の子供がいて、村を回って日銭を稼いでいるだけよ。」プーローは、羽を生やしてそこから飛び去りたい気分だった。どうして村に残ってしまったのだろう?夜に私も一緒に立ち去ってしまえば、誰も私のことを知る者はいなかったのに!
「お前はヒンドゥーか、ムスリムか?」アッラーディッターはまだ疑っていた。彼の仲間はニヤニヤし出した。
「おいおい、どういうこった?今度はこの女を家に放り込むつもりか?」アッラーディッターの仲間が彼をからかって言った。
「何言ってるんですか!ヒンドゥー教徒がどこから来たって言うんですか?」と言って、プーローは隅に脱いであった靴をはいて、包みを頭に乗せて外へ出ようとした。
「ヒンドゥーの名前は額には書いてないからな。」アッラーディッターは再び大声で怒鳴った。
「まだ疑ってるんですか?これを見ておくんなさいな、私の名前はハミーダーです。」プーローは玄関に立ちながら、自分の左腕に彫られた名前を見せた。
「行きなさい、息子は興奮してるんでね。」老婆が言った。
「何か分かったら、教えに来ますわ!と言いながら、プーローは急いで歩き出した。階段井戸の小屋に2人の息子を残して来ていた。ジャーヴェードはもうしっかりしていたので、彼が小さな息子をあやしていてくれた。
プーローはその夜、そわそわしながら過ごした。次の日の朝、ラシードがラージョーをサッカルアーリー村の自分の家に置いて、プーローのところへ戻ってきてくれるはずだった。その夜が、ラットーワール村でのプーローにとっての最後の夜だった。プーローは星を数えながら、2人の息子を抱えてチャールパーイーに寝ていた。
今日、ラットーワール村で、プーローの全ての望みが叶った。プーローは、前回ラットーワールに来たときのことを思い出した。畑の中を散歩していたときのことを思い出した。そしてラームチャンドと出会った最後の夜のことを思い出した・・・あのときプーローはラームチャンドの畑を見た・・・今回プーローはラームチャンドのあの家、あの中庭も見た。それらは、彼女が何年もの間見たいと思っていたものだった。プーローは考え出した。自分が嫁として嫁ぐはずだった家に、自分の妹が嫁いだ。この家に弟がバラート(結婚パレードの群集)を引き連れてやって来た。しかし彼女は、その家の顔も見ることができなかった。家に住む者の影すら見ることができなかった。家の中で、彼女はただラージョーの骸骨を見た・・・幸い、今やラージョーの悲しみは消え去った。プーローは、今日、あの家の骸骨の中に自らはまり込んだことを思い出した。そのとき彼女を救ってくれたのは、「ハミーダー」という名前だった。
いつプーローの目が閉ざされたのかは分からなかった。夜の暗闇が、ゆっくりと色を薄めて行った。
ラシードはとんぼ返りにラットーワール村に取って返し、プーローを連れてサッカルアーリー村に到着した。
ラージョーの大きな大きな両目は、まるで閉ざされた戸にくっ付いてしまったかのようになっていた。プーローが到着する直前、その物音がしただけで、、ラージョーは閉ざされた戸を開けた。ラシードは村の誰にも疑われないように、外から錠をかけていた。玄関の戸を中から閉じて、プーロー、ラージョー、そしてラシードは家の一番奥の部屋に、まるでライオンに怯える鹿の群れが、どこかに安全な洞穴でも見つけたかのように閉じこもった。
ラージョーとプーロー、この2人は、まるで共に遊び、共に育ち、魂を共有していたにも関わらず、何かの間違いによって何年も離れ離れになっており、今日、何らかの豪雨の後、何らかの砂嵐の後、再び再会することができたようだった。そして長い別離と人生の出来事が、2人の唇を固く閉ざしてしまったかのようだった。2人は自分のことを話すのを躊躇し、2人は相手の話を聞くのに躊躇していた。
食事を取ることにより、次第に緊張は解けてきた。2人が話しやすいように、ラシードは席を外して彼女らを2人っきりにさせてあげた方がいいことを知っていた。実際、最初からラシードは悪い人間ではなかった。彼は仕方なくプーローをさらったのだった。でなければ、道を歩いている誰かの大事な娘を無理矢理馬に乗せてさらうような悪いことはしなかった。プーローを自分の妻にした後も、ラシードは決して他の女性に浮気をしたことはなかった。
2人の息子を寝かしてから、プーローとラージョーは奥の部屋にチャールパーイーを入れて寝ていた。ラシードはベランダで寝た。
「ラットーワール村の旅団がこの村を通ったの。」プーローが話し始めた。
「あなたは見たの?」ラージョーとプーローは今でも打ち解けていなかった。ラージョーは、プーローがどうして、どうやって自分を探し出したのか全く分からなかった。
「私はお前のお兄さんと会ったの、そのときお前のことを知ったのよ。」
「え?」
「本当よ。」プーローの目に、旅団の中にいたラームチャンドの顔が浮かんだ。
「どうやってお兄さんに気付いたの?あなたは彼を一度も見たことないはずだわ!」ラージョーの脳裏に多くの記憶が浮かんで来た。プーローと兄の婚約式が行われたこと、兄の結婚が間近に迫っていたこと、プーローが突然いなくなってしまったこと、そしてプーローの妹と兄の結婚が行われたこと・・・。
「私は彼を前にも一度見たことがあったの。」プーローはラットーワール村の畑の話をラージョーに聞かせた。プーローはそのときまで、ラームチャンドが自分の妹と結婚したなんて知らなかったことも語った。
「私はそれまで何も知らなかったの。ある日旅団がこの村を通ったわ・・・私の身に起こったことを家族は思い出しているでしょう、私の葬式も行われたことでしょう、時々家の誰かが私の名前を口に出しているでしょう。」プーローは声を詰まらせた。
ラージョーは、プーローの父親が死んで2年になることと、彼女の母親が折に触れてプーローの名前を口に出しては泣いていることを伝えた。
「母さんは何て可哀想なんでしょう、生きてる内に娘を失い、今度は嫁まで・・・」プーローは言った。プーローとラージョーは揃って泣き出した。
牛舎の牛のように、2人は自分のチャールパーイーにうつ伏してした。
「お前があっちに行ったら、母さんに言ってちょうだい、一度私の顔を見てって・・・」プーローはさらに激しく泣き出した。
「私・・・私あっちに行くの・・・?」
お前は自分の家に帰るのよ、自分の夫のところへ、自分の兄弟のところへ。」
「私はもう死んだも同然だわ、今さら私を受け容れてくれないでしょう?」
「いいえ、ラージョー、私が生きてる内は、そんな間違い誰にもさせないよ。お前は必ず自分の家に戻るのよ。お前に何の罪があるっていうの?」
「でもあなたに何の罪があったの?今日まで誰も家族はあなたを呼ばなかったわ!」
「私の話は別よ、ラージョー!」
「どうして別なの?あなたは自分からここに来たの?あなたも同じように・・・」
「そうね、ラージョー!でもあのとき私は一人だった。私の両親は世間の目に耐える勇気がなかったの。彼らは愛情を捨ててしまったの。今は一人じゃないわ。多くの人に同じことが起こってるの。」
「いいえ、プーロー!私の運がよかったら、最初からこんな目には遭っていないはずだわ。きっと私を連れに誰も来ないでしょう。」
「お前のお兄さんから必ず手紙が来るわ。そしたらお前のことを伝えましょう、そして彼らはお前を連れに必ず来るわ。・・・ところで、私の弟はどんな顔してるの?」プーローは興味深そうに聞いた。
ラージョーは自分の夫のことを思い出した。私はどうやって夫に顔向けできようか、私はどうやって家族の前に出て行こうか、ラージョーは考えた。しかし彼女は、誰も自分を連れにやって来ないと信じていた。心の中に生じる希望のラッドゥー(お菓子)を次から次へと捨ててしまうかのようだった。
「いいえ、ラージョー!誰かが必ず連れに来るわ。今では誰も文句は言ってないわ、みんな自分の娘や姉妹を連れにやって来てるのよ。ラシードが言ってたけど、あっちからも人々は自分の女性たちを探し出して連れ帰ってるのよ。子供が出来た人までいるのよ。」そして2人は黙り込んで、女性のこの無力さを考え始めた。
ラージョーは、何の罪か、今日まで自分の家に一人も子供が生まれなかったことを考え出した。今日、その罪が形となって現れたのだ、そうでなかったら、この不幸の説明がつかなかった。
「今まで一人のために泣いてたのよ、私が行ったら2人のために泣くことになるわ。私はどこにも行かないわ、プーロー!私はどんな顔して行けばいいの!私はあなたの子供たちの世話をしてローティーを食べて過ごすわ。」
「なんでそんなこと言うの、ラージョー!傷に塩を塗りこむような話をしないで。ここはあなたの家よ。でもラージョー!彼らはお前を連れに必ずやって来るわ。私が世界を敵に回してでも彼らを連れてくるから。」
プーローはラージョーを抱きしめた。
「あなたはこの家にいて幸せなの、プーロー!」
「ラシードに聞こえるわ。確かに彼は最初私に罪深いことをしたわ、でもその後彼は私に少しも悪いことをしなかった。彼がいなかったら、あなたを見つけることもできなかったでしょう。」
「彼は命がけで私を連れに来てくれたわ。でもあの悪魔にこのことが知れたら、私の骨から血をすするでしょう・・・」
「彼らが血をすするはずないでしょう!彼らはただ地面に埋めるだけよ。」
「それはそうだけど、プーロー、この村のことがばれてしまったらどうしよう!」プーローはラージョーに、彼女がいなくなった後、老婆とその息子と会ったことを話した。
「以前も私はこの奥の部屋に、何日間も一人のヒンドゥー教徒の女の子をかくまっていたのよ。誰も彼女の息の音すら聞くことができなかったわ。それから私は、彼女を旅団に合流させたのよ。お前もこの中に隠れてなさい、村人に知れないようにね。手紙が来たら、お前をラーハウルに連れて行ってあげるから。誰にも何も知れることはないわ。」
「もし手紙が来なかったら・・・」
「私は絶対の自信があるわ、ラージョー!お前のお兄さんは必ず手紙を送ってくれるって。」
日は昇り、また沈み、次々に日は過ぎて行った。ラージョーのことは家の外には知られず、ラージョーの家族から何の便りもなかった。プーローとラージョーはいつも一緒に過ごしていた。夜になって2人を眠気が襲うと、2人を夢が悩ますのだった。夜明け前に2人は目を覚まして、夢の吉凶の話をし出すのだった。彼女たちはイライラすることもあれば、落ち着くこともあった。何度もラージョーはコンロから炭を拾い上げて、座りながら地面に絵を描いていた。夢は吉兆のこともあれば、凶兆のこともあった。ラージョーは話をしながら涙を流すこともあれば、プーローの子供たちと遊んで気を紛らわすこともあった。ラージョーはいい予感がしなかった。彼女は誰かから頼りが来るとは信じていなかった。しかしプーローはなぜかは知らないが、いつか突然誰かがやって来る、あいつか突然手紙が来て、ラージョーが幸せを取り戻せると固く信じていた。プーローは出来る限りのことをラージョーにしてあげた。プーローにとってラージョーは、自分の失われた過去の、2度と戻らない過去の顕現だった。ただラージョーの顔の表情だけに、プーローは家族の顔を見出すことができた。誰も彼女の家に滞在するために来ない、誰も彼女に会いに来ない!プーローの知り合いの中で、ただラージョーだけが最初の客であり、最後の客だった。
昼の光の中でラージョーは決して玄関から表に出なかった。夜の暗闇はラージョーの秘密を慎重に包み隠した。しかし村の郵便局員から、3ルピーの手紙(ヒンドゥスターンからの手紙)も彼女の家の庭に届かなかった。
ラージョーとプーローの顔に不安がよぎるようになった。ラージョーは、ただプーローとラシードが自分を落胆させるようなことを決してしなかったことだけに満足していた。しかし毎日毎日隠れて過ごすラージョーには、自分の頭に山のような時間がのしかかって来ているように感じた。いつこの忍耐の時が終わるのだろう!
プーローは他人の家に頻繁に出入りすることはなかった。ラージョーは奥の部屋で生活していた。昼になると時々2人は玄関に錠をして、チャルカー(紡ぎ車)を回していた。日は過ぎて行ったが、それがいつ終わるかは誰にも分からなかった。
冬は過ぎ去った。ファーグン月(2月−3月)も終わろうとしていた。水も冷たくなくなった。ある日の昼下がり、ラシードは玄関から家の中に入ってくると、ラージョーとプーローを見るなり目に涙を浮かべた。
驚いた2人は彼の元へ駆け寄った。しばらくの間彼は何も言わなかった。ラージョーは、誰かが彼の心を外へ引っ張っているように感じた。ラージョーは、あの老婆とその息子に自分の居所が知れることだけを恐れていた。自分を無理矢理引きずって連れ去ってしまわないか、プーローに何か迷惑がかからないか。
ラシードはチャールパーイーの端に座り、上着の裾で両目を拭って、ラージョーの背中を愛情を込めてポンと叩いた。それはまるで、年老いた父親が、娘をサスラール(婚家)へ送るときのような愛情に満ちた仕草だった。ラシードはたまらない気持ちになった。彼は自分の心を落ち着かせて言った。「今日ラームチャンドが来た。」
「ここに?」ラージョーとプーローは同時に言った。
「ああ、ヒンドゥスターンの警察と、パーキスターンの警察も一緒だった。彼らは村や町で行方不明になった女性を探している。ラームチャンドと俺は2人っきりで話をした。」ラシードは言った。
「本当に私を連れに来てくれたの?」ラージョーは突然大声で言ったが、すぐに自分で自分に恥じ入ってしまった。
「そうでなかったら、何のために来たっていうんだ?」ラシードは言った。
プーローは黙って聞いていた。彼女は今までにない喜びを感じていた。なぜなら彼女の信じていたことが実現したからだ。彼女はラームチャンドが来ることを知っていた。彼女は自分の義妹が然るべき場所に戻れることを知っていた。ラージョーは意味もなく落ち込んで過ごしていた。ラシードも不安になっていた。だがプーローは、まるで誰かが約束でもしたかのように、ラームチャンドが必ず来ると信じて疑わなかった。今日、待ち焦がれていた日がやって来た。ラームチャンドは本当にやって来たのだ。
「一人で来たの?」ラージョーは聞いた。
ラシードは、ラージョーがその質問で何を聞きたかったかを理解した。彼は言った。「ああ、今のところ一人で来た。でも心配するな!お前の家族みんながお前を名誉にかけて迎えに来るだろう。」
ラージョーは幾分安心した。
「お前の名前を聞いて、お前の様子を聞いて、ラームチャンドは泣いていたよ、彼の涙は止まらなかったよ。彼を見ていたら、俺まで泣けて来ちまったよ。」ラシードの目が再び濡れてきた。ラージョーとプーローは泣き出した。
「俺は彼らによく言い聞かせた。今日お前をここで引き渡したら、村中にその噂が広まるだろう。噂がラットーワール村まで届いてしまうかもしれない。俺は彼らに、とりあえずラーハウルに戻るように言った。俺がラージョーを連れてラーハウルへ行って、そこで彼らに引き渡すことにした。」
「それはいい考えだわ。」プーローは言った。
「俺たちはそこへ今日から5日後に行く。それまでに彼はアムリトサルからプーローの弟も呼んでくる。一度プーローも自分の弟に会えるようにと考えたんだ。」ラシードはラージョーの背中を撫でながら言った。
プーローの押さえ込んでいた涙が溢れ出た。ラージョーはプーローの胸に頭を埋めた。2人はお互いに我を失い、お互いに悲しみを分かち合った。2人の涙は混ざり合った。
ラーハウルまでせいぜい1日半の道のりだった。出発日まであと3日あった。
次の日プーローはグラム粉を買い、貯蔵してあった水牛のミルクのバターを取り出し、アーモンドとドライフルーツを入れて一日中ラッドゥー(お菓子)を作っていた。それはまるで、娘をサスラールへ送るときのようであった。プーローはシルクの布を取り出した。ラージョーを何度も何度も抱きしめ、涙を流した。
3日目、2人の息子を連れたプーローは、ラージョー、ラシードと共に夜明け前に村を出て、列車に乗り込んだ。
この4日間プーローの心には多くの考えが浮かんでいた。彼女は考えを巡らせながら夜を過ごした。プーローは心の中で決めていた、私はラージョーに言うんだ、お母さんに、私のお母さんに、一度でいいから私の顔を見て、と言うように、ラージョーに言うんだ・・・。考えている内にプーローは泣き出しそうになった。考えている内にプーローには多くの伝えたいことが浮かんだ。考えている内にプーローの口は何も言えなくなってしまった。
ラージョーには、自分の兄や夫に会うことが奇跡のように思われていた。まるで来世で離れ離れになった人々と会うことを望んでいるかのように思えた。たとえラージョーが家族から引き離されて5、6ヶ月しか経っていなかったとしても、一度死んで再びこの地上に生まれ変わったように感じていた。
道中、2人の心は絶え間なく揺れ動き続けた。
警察の監視の下、彼らは再会した。ラージョーはまぶたを開けることができなかった。プーローは弟の顔を見た。このひとときの再会の前には、長い長い別離があった。このひとときの再会の後には、限りない別離が目に浮かんだ。誰も涙を止めることができなかった。
人々の心はバラバラになっていた。運命の壁は崩れ落ちていた。誰も誰にも何も聞くことができなかった。彼らは泣きながら自分の手を濡らし、自分の服を濡らした。
「聞いてちょうだい!間違ってもラージョーを辛い目にあわせては駄目よ。」まずはプーローが言った。
ラージョーの夫はうつむいていた。ラージョーの兄はうつむいていた。
「プーロー、私たちを恥ずかしがらせないでくれ。」ラージョーの兄が言った。
ラージョーの夫は何も言わなかった。おそらく彼は何も聞くことができなかった。今日彼は、自分の行方不明になった妻と再会しただけでなく、物心つく前に失踪した自分の姉とも再会したのだった。何年間も彼の心の中には炎が燃えていた。その火の粉を彼はラシードの畑に放ち、全てを灰にしてしまったのだった。何年も彼はあるお姫様のお伽話のことを考えていた。一匹の悪魔がその姫をさらい、東の国の王子が魔法の矢で悪魔を退治して姫を救う話だった。幼年時代に彼は何度もサードゥ(遊行者)やサント(聖人)に、その魔法の矢を求めたのだった。大きくなってからは、プーローのことを考えるだけで気が狂いそうになったのだった。今日、何年にも渡って行方が分からなくなっていたプーローが目の前にいた。この瞬間、彼はラシードが彼の妻を救ったことを忘れ、ていた。このひととき、彼はただラシードが彼の姉をさらって行ったことを思い出していた。
警察のトラックの準備ができた。ヒンドゥスターンの警察が知らせた。「あちらへ行くヒンドゥー教徒は集まって下さい。トラックの準備ができました。」
ラームチャンドはラシードを何度も抱きしめ、何度も言った。「兄弟よ、なんとお礼を言っていいのか、私はこの恩を一生忘れない。」ラシードの顔には、この恩に対する喜びこそあったものの、ラージョーを助けた後も後ろめたい気持ちがあった。彼は、プーローをさらって来たときのことを思い出していた。それでも彼は、自分の頭を抑え付けていた業が幾分軽くなったように感じた。
再び声がした。「あちらへ行くヒンドゥー教徒は集まって下さい。」
プーローはシルクの布とグラム粉のラッドゥーの包みをラージョーに渡し、ラージョーを力いっぱい抱きしめた。そしてプーローは自分の弟のところへ行き、彼に抱きついた。
「プーロー・・・!」プーローの弟はただそれだけしか言えなかった。そして彼はプーローの腕を握り締めた。
「俺の話を聞いてくれ、今・・・」プーローの弟は勇気を出して言ったl。プーローは弟の言いたいことを理解した。プーローの心に一瞬だけひとつの考えが浮かんだ。もし今、私はヒンドゥー教徒だと言えば、私はみんなと一緒にあちらへ行くことができるだろう。私も戻ることができる、ラージョーのように・・・国の何千もの女性たちのように・・・
プーローの目には、抑えていた涙が溢れ出した。彼女はゆっくりと弟の手から自分の腕を放し、近くに立っていたラシードのそばへ行って、自分の息子を胸に抱いた。
「ラージョーが自分の家に戻るわ。ラージョーの中に、私もいると思って。私はもう、この国の人間なの。」プーローは穏やかな声で、トラックに乗り込んだ弟に言った。
ラームチャンドはお辞儀をしてプーローに手を合わせた。おそらく心の中の苦痛が彼の唇を閉ざしてしまったのだろう、彼は何も言うことができなかった。
ヒンドゥーであろうとムスリムであろうと、自分の家に戻る女の子たちと共に、プーローの魂も家に戻ったのだ。プーローは心の中で言った。そして視線を地面に落として、ラームチャンドに最後の挨拶をした。
トラックは動き出した。道に砂煙が舞い上がった。
完
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



