 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
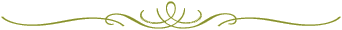

Phanishwarnath Renu
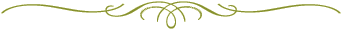
近代ヒンディー文学の黄金期である20世紀前半には、なぜか文学の基本である恋愛をテーマにした小説がほとんど書かれなかった。「第三の誓い」は、パニーシュワルナート・レーヌ(1921-1977)がインド独立から約10年後、ナイー・カハーニー(新短編)運動の最中の1956年に書いた、近代ヒンディー文学の最初の恋愛小説のひとつである。原題は「Maare Gaye Gulfam(殺されてしまったグルファーム)」。レーヌの小説には、マイティリー語(ビハール州北部の方言)と口語調の文が多用されるという特徴がある。また、映画的筆致も特筆すべきである。「第三の誓い」は1966年にラージ・カプールとワヒーダー・レヘマーン主演で映画化もされた(「Teesri
Kasam」;DVDあり)。
|
|
|
|
牛車乗りのヒラーマンの背中はムズムズしていた・・・。
ヒラーマンが牛車に乗り始めて20年が経っていた。ネパール国境の向こうのモーラング村から米と木材を積み込む仕事はもうやめていた。コントロールの時代(イギリス植民地時代)に、ヒラーマンは密輸品をネパールからインドへ運んでいた。しかし、これほど背中がムズムズしたのは初めてだった。
コントロールの時代!ヒラーマンはあの時代を決して忘れることができない。ヒラーマンはあるとき、セメントと衣類の荷物で一杯の牛車を、ジョーグバニー村からビラートナガル村まで届けたことがあった。ファールビスガンジ村の密輸業者たちは皆、ヒラーマンを真の牛車乗りと認めていた。界隈の商売を取り仕切るセート氏が彼の牛たちを手放しで賞賛していたくらいだった。
あるとき、国境近くの平野で彼の牛車は捕まってしまった。これで5度目だった。
高利貸しのムニーム氏は、ヒラーマンの牛車の積荷の中に隠れていた。警部の持っている懐中電灯の光がどれだけ眩しいか、ヒラーマンは知っていた。少しでも目に入ったら、1時間はめくらになってしまうほど眩しいのだ!光と共に、怒鳴り声も聞こえた。「おいこら!車を止めろ!この野郎、銃をぶっ放すぞ!」
20台の牛車がギシギシ言いながら同時に止まった。ヒラーマンは最初から「20台は多すぎる!」と言っていた。警部は彼の牛車の中に隠れているムニーム氏に光を当てて、悪魔のように笑った。「ハッハッハ!ムニームじゃあねぇか!ヒッヒッヒ!おい、野郎、牛車乗り、何見てやがるんだ!この袋の口の毛布を外せ!」手に持った警棒でムニーム氏の腹を小突きながら言った。「この袋は何だ!この野郎!」
警部とムニーム氏の間には何やら古い因縁があるのだろう。そうでなかったら、これほど多くの金をせしめても警部が許さないのはおかしいだろう。ムニーム氏は即座に4000ルピーを手渡したが、警部はもう一度警棒で小突きながら言った。「5000!」再び小突いた後、言った。「まずは車から降りろ!」
ムニーム氏が車から降りると、警部は彼の目に光を当てた。そして2人の部下と共に彼を道端の茂みの中に連れ込んだ。牛車と牛車乗りのそばには、銃を持った警察官が5人ついて見張っていた。今回ばかりは助からないだろう、ヒラーマンは覚悟した。・・・牢屋?ヒラーマンは牢屋に入ることを恐れていなかった。しかしオレの牛たちはどうなる?いったい何日間、飲まず食わずで役所の門につながれるだろうか、水も飼料もなしで。挙句の果てには競売にかけられてしまうだろう。これじゃあ全く兄と兄嫁に合わす顔がなくなる・・・。競売の掛け声が彼の耳の中で鳴り響き始めた・・・1、2、3!警部とムニーム氏の話はまだ終わらなかった。
ヒラーマンの牛車のそばに立っている警察官が、他の警察官に自分の村の方言でそっと聞いた。「どうなってるかな?話は丸く収まったかな?」そして噛みタバコを渡しにその警察官にところへ行ってしまった。
1、2、3!ちょうど3、4台の牛車の影に隠れていた。ヒラーマンは決断した。彼は静かに牛たちの首の縄をほどき、車の上に座りながら2匹を結びつけた。牛たちも即座に何をすべきか理解した。ヒラーマンは車から降りると、牛たちの肩から牛車のくびきを外した。2匹の牛の頭を撫でると、彼は心の中で叫んだ。「行くぞ、バイヤン(兄弟)、命さえ助かれば、こんな車いくらでも手に入るさ!」1、2、3!それ!
道は牛車の群れで一杯で、道の両側は深い茂みで覆われていた。3つの影が息を潜めて茂みを掻き分けて音もなく走った!いくつもの茂みを抜け、2匹の牛は深いジャングルの中に入り込んだ。道のにおいを嗅ぎ、川を渡り、尻尾を立てて走った。その後ろからヒラーマン。2匹と1人は夜通し走り続けた・・・。
家に着くや否や、ヒラーマンは2日間無意識のまま倒れ込んだ。意識が戻ると、彼は誓いを立てた――もう2度とこんな荷物は運ばないようにしよう!密輸品の積荷?くわばら、くわばら!・・・ムニームの旦那はいったいどうなっただろう!屋根付きの牛車は惜しかった!本物の鉄製の軸だったし、片方の車輪は新品だったのに。せっかく車に色とりどりの飾り房を取り付けたんだが・・・。
彼は2つの誓いを立てた。ひとつは密輸品の運搬を2度としないこと。もうひとつは竹。彼は客に最初に質問することにした。「荷物は密輸品じゃないだろうね?それと竹でもないだろうね?」竹を届けるために50ルピーを用意しても、ヒラーマンは首を縦には振らなかった。他の車を当たりな!
竹を積んだ車!竹が車の前にも後ろにも飛び出していて、車体はいつも不安定だった。不安定な積荷とカライヒヤー市の話!客が付き添わせた間抜けな下男が、竹の先っぽを掴んで歩きながら、女子校の方に気を取られたその瞬間、曲がり角で幌馬車とぶつかってしまった。ヒラーマンが牛の手綱を引いたときには、積荷の竹の先が馬車の屋根に突き刺さってしまった。馬車乗りはヒラーマンを鞭でひどく打って罵声を浴びせかけた。
やがてヒラーマンは竹の積荷だけではなく、カライヒヤー市の積荷を運ぶのも止めてしまった。そして彼はファールビスガンジ村とモーラング村の間で貨物と旅客の運送を始めた。が、牛車を借りる必要があった。何年もヒラーマンは半分の収入で牛車を走らせていた。車の持ち主の取り分が半分だったから、牛車乗りの取り分も半分になってしまう。しかし半分の収入では牛たちの腹は膨らまなかった。そんな中、去年彼は自分の牛車を作らせたばかりだった。
女神様、あのサーカス団の虎に祝福を!去年のことだった。サーカス団の虎を運ぶ車を引いていた2匹の馬が突然死んでしまった。サーカス団がチャンパーナガル村からファールビスガンジ村の祭りへ移動するとき、マネージャーは牛車乗りたちに呼びかけた。「運賃は100ルピー出すぞ!」2、3人の牛車乗りが手を挙げた。しかし、彼らの牛たちは虎の入った檻に近づこうともせず、恐れおののいて遠くで「バァン!オォン!」と足踏みするだけだった。しかも縄を引きちぎって逃げ出す有様だった。ヒラーマンは自分の牛たちの背中を撫でながら言った。「いいか、バイヤン、こんな機会はもう2度とないぞ。牛車を作る金を手に入れる絶好の機会だぞ。今やらなくちゃ、また半分の収入で働かなきゃならねぇ。おいおい、檻の中に入った虎なんてちっとも怖くねぇぞ。モーラング村の原っぱで、グルグル唸ってる虎を見たばっかじゃねぇか。後ろにはオレもいるんだし・・・。」
牛車乗りたちから一斉に拍手が沸き起こった。ヒラーマンの牛たちは、牛乗りたちの名誉を守ってくれた。牛たちはのろりのろりと動いて、虎の乗った車に1匹ずつ結ばれた。異変と言えばただ、結ばれた直後に右の牛が長々とおしっこをしたぐらいだった。だが、ヒラーマンは2日間ずっと鼻を布で覆わなければならなかった。セート氏のように鼻の覆いをしなければ、虎の体臭を我慢することはできなかったのだ。
・・・虎車を引いたヒラーマン。いくら彼でも、このようなムズムズを背中に感じたことはかつてなかった。今日の彼の車の中からは、チャンパー花の香りが立ちのぼっていた。背中がムズムズするので、ヒラーマンは何度もタオルで背中を叩いていた。
ヒラーマンは考えていた――どうやらここ2年あまり、チャンパーナガル村のバグワティー女神のご加護があるようだ。去年は虎を運ぶ仕事が手に入った。100ルピーの運賃の他、必要経費、チャーイ、ビスケットや、猿と熊とジョーカーのショーを無料で見ることができた。
そして今回の乗客はこの娘さん。人間の娘だろうか、それともチャンパー花?彼女が乗り込んでからというものの、牛車は何ともいい香りで包まれていた。
ガタガタ道の穴ぼこに車の右車輪が突然はまってしまった。ヒラーマンの車から、「アッ!」というかすかな声が聞こえた。ヒラーマンは右の牛を革のひもで打ちながら言った。「この野郎!何してやがんだ!」
「ねぇ!叩かないで!」
見知らぬ女の声が、ヒラーマンを驚かせた。子供の声のような、高くガラスのような声!
マトゥラーモーハン劇団でライラー役を演じるヒーラーバーイーの名前を知らぬ者がいようか!しかしヒラーマンだけは違った。彼は7年間祭りの荷物を運ぶ仕事をしていたが、演劇やバイオスコープ映画を一度も見たことがなかった。ライラーやヒーラーバーイーの名前も聞いたことがなければ見たこともなかった。だから、祭りが終わる15日前の真夜中に、黒いショールに身を包んだ女性を見て、彼の心が動揺するのも無理はなかった。荷物を積み込んだ下男が運賃の交渉をしようとすると、ショールの女は頭を振ってそれを止めた。ヒラーマンは牛と車をつなぎながら下男に聞いた。「密輸品か何かじゃねぇだろうな?」荷物を積み込んだ下男は、指を振って車を出すように指示し、暗闇の中に忽然と消えてしまったので、ヒラーマンは驚いた。彼は、祭りでタバコを売る老婆の黒いサーリーを思い出した。
こんな状態で誰が車を走らせられるってんだ!
ひとつに背中がムズムズするし、ふたつにチャンパー花が牛車の中で咲いてるし、みっつに牛を叱るとこの乗客はあれこれ言ってくるし。・・・いったいどんな乗客だろう!女が一人で・・・タバコを売る老婆でもない!彼女の声を聞いてからというものの、彼は何度も何度も振り返って幌の中をチラチラと覗いていた。タオルで背中を叩きながら・・・。神様は今回、どんな運命を用意してくださったんだろう!車が東の方向を向いたとき、月の一筋の光が車の中に差し込んだ。乗客の鼻の鼻飾りがキラリと光った。ヒラーマンは摩訶不思議な気分になった。眼前にはチャンパーナガル村からスィンディヤー村まで広々と広がる平野があった。・・・もしかして妖怪じゃあるめぇな?
ヒラーマンの乗客は寝返りを打った。月の光が顔全体を照らし出すと、ヒラーマンは叫んだ。「なんてこった!こりゃあ妖精だ!」
妖精の目が開いた。ヒラーマンはパッと前を向いて、牛たちに舌打ちを始めた。彼は舌をうわあごにつけて、ティティティティという音を出そうとした。が、ヒラーマンの舌はいつの間にか乾ききって木の枝のようになっていた。
「バイヤー(お兄さん)、あなたの名前は何?」
全くガラスのような声・・・!ヒラーマンの全身の毛が逆立ち、口からは一言も言葉が出なかった。彼の2匹の牛も、この声に聞き耳を立てた。
「オレの名前!・・・オレの名前はヒラーマンだよ。」
乗客は微笑んだ。・・・微笑みから芳香が沸き立った。
「じゃあミーター(親友)って呼ぶことにするわ、バイヤーじゃなくて。・・・私の名前もヒーラーって言うの。」
「何っ!」ヒラーマンは訳が分からなかった。「男と女の名前ってのは違うんだよ。」
「一緒よ。私の名前もヒーラーバーイーなの。」
ヒラーマンとヒーラーバーイー?全く違うじゃないか!
ヒラーマンは牛たちを叱り付けた。「こそこそ耳を立てて話を聞きやがって、そんなことしてたら、100kmの道のりはいつまでたっても終わらねぇぞ!この左の野郎はちっとも言うこと聞きやしねぇ!」ヒラーマンは左の牛を革のひもで軽く打った。
「打たないで!ゆっくり行きましょうよ。急ぐ必要なんてないわ。」
ヒラーマンの心に疑問が沸き起こった。いったいどんな言葉でヒーラーバーイーと話をすればいいのだろう?標準語では、2、3の会話をするのが精一杯だ。心を開いて世間話するには、村の言葉じゃなければ駄目なのだ。
アーシュヴィン月からカールティク月(9月〜11月)の夜明けに立ち込める霧に、ヒラーマンは嫌な思い出がある。今まで何度も道に迷ったことがあったのだ。しかし今日の夜明けのこの深い霧の中でも彼は上機嫌だった。川岸の方から田んぼの稲の匂いで満ちた風が吹いて来ていた。この時期の村では、このようないい匂いが立ち込めるものだった。そして彼の車の中にはチャンパー花が咲いていた。その花の中に、一人の妖精が座っている。バグワティー女神様、万歳!
ヒラーマンは横目で乗客を見た・・・ミーター・・・ヒーラーバーイーの目は彼を見つめていた。ヒラーマンの心の中で、聞いたことのないような音が鳴り響いた。全身が痺れたままだった。彼は言った。「牛を打つと心が痛むのかい?」
ヒーラーバーイーは、ヒラーマンが本当にヒーラー(ダイヤモンド)であることに気付いた。
40歳のたくましく黒い身体をしたこの村の男は、自分の車と牛のこと以外、世界のどの事象にも大した関心を示していなかった。家には兄がいて、農業をしていた。純粋無垢な男だった。ヒラーマンは兄よりもむしろ兄嫁を尊敬していた。恐れてもいた。ヒラーマンも結婚式は挙げたが、幼年時代にガウナー(花嫁を家に連れてくる儀式。インドでは結婚式だけまず挙げて、数年後にガウナーが行われるのが一般的)を挙げる前に花嫁は死んでしまった。ヒラーマンは花嫁の顔をよく覚えていなかった。・・・再婚?再婚しない理由はいくつかあった。兄嫁は、初婚の花嫁とヒラーマンを結婚させることを主張していた。初婚の花嫁、つまり5、6歳の女の子。誰も法律なんか気に掛けなかった。男ヤモメに自分の娘をやすやすと与える親などいなかったが、兄嫁は主張を曲げようとしなかった。兄ですら兄嫁にはかなわなかった。・・・とうとうヒラーマンは決意した――もう結婚なんてしねぇ。誰がわざわざ無駄な結婚するってんだ?結婚したところで、牛車乗りがいったい何するって言うんだ?何が起こったとしても、牛乗りの仕事だけは手放すことはできねぇ。
ヒーラーバーイーはヒラーマンのように実直な男をほとんど見たことがなかった。彼は聞いた。「あんたの家はどの地方にあるんだい?」カーンプルの名前を聞いた途端、彼は笑い出した。彼の笑いを聞いて牛たちは飛び上がった。ヒラーマンは笑いを必死でこらえようとした。笑いが収まった後、彼は言った。「カーンプル(耳の町)とはね!だとしたらナークプル(鼻の町)なんてのもあるんだろう?」ヒーラーバーイーが「ナークプルもあるわ」と答えると、彼は腹を抱えて大笑いした。
「なんて世の中だ!いろんな名前があるもんだなぁ!カーンプル、ナークプル!」ヒラーマンはヒーラーバーイーの耳飾りをじっと見た。そして鼻飾りの宝石を見て震え上がった――まるで血みたいだ!
ヒラーマンは今までヒーラーバーイーの名前を聞いたことがなかった。劇団の女性を彼はアイドルとは思っていなかった。・・・彼は以前、劇団で働く女性と会ったことがあった。サーカス団の女主人は、2人の娘と共に虎の乗った車のそばに来ていた。虎に餌をやったりしていたし、虎をたいそうかわいがってもいた。長女はヒラーマンの牛たちにローティー(インドのパン)やビスケットを食べさせてくれたりもした。
ヒラーマンは賢い男だった。霧が晴れるや否や、自分のショールを幌にかけてカーテンの代わりにした。「あと2時間!その後は進むのは難しくなるだろう。カールティク月(10月〜11月)の朝の光をあんたは我慢できないだろう。カジュリー河の岸辺に車を止めて、テーガチヤー村の近くで昼休みして・・・。」
前方からやって来る牛車を見て、彼は警戒した。道と牛に気を配りながら彼は座り直した。その牛車乗りは道を通り過ぎながら聞いた。「祭りはもう終わったのかい?」
ヒラーマンは答えた。「オレは祭りのことなんざ知らねぇ。オレの車にゃ、花嫁が乗ってるのさ。チャッタープル・パチーラー村へ行くところさ。」ヒラーマンは適当な村の名前を出した。
「チャッタープル・パチーラー村ってどこだい?」
「どこだっていいじゃねぇか。それを知ってどうするってんだい?」ヒラーマンは自分の賢さにほくそ笑んだ。カーテンを閉めたというのに、背中はまだムズムズした。
ヒラーマンはカーテンの穴から中を覗いた。ヒーラーバーイーはマッチ箱ほどの大きさの鏡で自分の歯を見ていた。・・・ヒラーマンはマダンプル村の祭りで牛たちのために小さな貝殻の首飾りを買ってやったことを思い出した。小さな可愛らしい、貝殻の列!
テーガチヤー村の3本樹は遠くからでも目立った。ヒラーマンはカーテンをちょっと寄せながら言った。「見てみな、あれがテーガチヤー村。2本の樹が甘松(カンショウ)の樹で、もう1本が・・・あの花の名前は何て言うか知らねぇが、あんたの上着に同じような花の模様があるだろ、多分それさ。いい匂いがするんだ。5km先からでも匂うんだぜ。ここいらの村のやつは、あの花をタバコに混ぜて吸ったりもするのさ。」
「あのマンゴー畑の向こうにいくつか建物が見えるけど、あれはどこかの村なの?それともお寺?」
ヒラーマンはビーリー(巻きタバコ)に火をつけようとした手を止めて言った。「ビーリー吸うかい?あんた、煙を気にはしないかい?・・・ああ、あれかい、あれはナーマルガル寺院さ。今、オレたちが後にしてきた祭りを取り仕切ってる王様の守護神のお寺さ。・・・古き良き時代だったな!」
ヒラーマンは、「古き良き時代だったな!」と言って、話をもったいぶった。ヒーラーバーイーは幌のカーテンを無造作に引っ張った。・・・ヒーラーバーイーの歯が光った。
「何の・・・時代?」彼女は頬杖を付いて興味深そうに聞いた。
「ナーマルガル寺院の時代!いったい何がどうなったことか!」
ヒラーマンは物語りの要領を心得ていた。ヒーラーバーイーは言った。「あなた、その時代を見たの?」
「見たことはねぇよ、聞いただけさ。・・・王様がどうなってしまったか、とっても悲しい物語さ。聞くところによると、王様の家に神様が生まれたそうだ。とは言え、神様は結局神様さ。そうじゃないかい?神様が天界を去って人間界に生まれたら、その威光を誰か抑えられるか!ヒマワリみたいな光が、おでこのそばで始終輝いてたんだ。でも、不幸なことに誰もそれに気付かなかった。あるとき、白人の旦那がマダムと一緒に飛行機に乗ってやって来たんだ。旦那もそれに気が付かなかったが、マダムの方は気が付いた。マダムはヒマワリみたいな光を見て言ったんだ。『オーマイ!王様、ちょっと、これは人間の子供じゃないわ、神様よ!』」
ヒラーマンは白人のマダムのしゃべり方を面白おかしく真似た。ヒーラーバーイーは身をよじらせて大笑いした。
ヒーラーバーイーはショールを直した。そのとき、ヒラーマンは思った・・・思った・・・
「それで?その後どうなったの、ミーター?」
「あれ!物語を聞くのが大好きみたいだな?・・・でも、黒い人間は、王様だろうが大王様だろうが、結局黒い人間なのさ。白人の旦那みたいに物分りがよくなかった。みんな笑ってその話を信じようともしなかったのさ。そしたら、神様がお后の夢に現れるようになった。『私の面倒を見れないようだったらそれでいい、こんなところにはもう住まない!』その後、神様の悪戯が始まったんだ。まず最初に、立派な牙の象が二頭とも死んじまって、それから馬が、それからパトパターングが・・・。」
「パトパターングって?」
ヒラーマンの心は刻一刻と変わっていた。心の中に、七色の傘がゆっくりと開いていくかのようだった。・・・彼の車に、天界の女性が座っているように思えた。神様は結局神様なのだ!
「パトパターング!つまり、財産、穀物、家畜、全て消え去っちまったってことさ。そして神様は天界に戻って行ってしまった。」
ヒーラーバーイーは通り過ぎていく寺院の屋根の方を見て溜息をついた。
「でも、神様は立ち去るときに言ったんだ。『この王国には2度と息子が生まれないだろう。我々は富を持ち去っていくが、徳だけは残して行く。』その神様と一緒に全ての神々は去って行っちまった。ただ、サラスワティー女神(=バグワティー女神)だけが残ったんだ。それがあの寺院なのさ。」
馬にジュートを乗せた商人の群れがやって来るのを見て、ヒラーマンは幌のカーテンを閉めた。牛たちを叱りつけながら、ビデーシヤー(ビハール州の舞踊劇)の歌を歌い始めた。
サラスワティー女神様、お願い申し上げます
我らにお恵みを、女神様、我らにお恵みを
馬に乗った商人にヒラーマンは陽気に問いかけた。「いくらでジュートを買ったんだい、大将?」
びっこ気味の馬に乗った商人は通り過ぎながら答えた。「下は27〜28ルピー、上は30ルピーだ。質の通りの値段さ。」
若い商人が聞いた。「祭りはどんな様子だい?どの劇団の劇をやってるかな?ラウター劇団かい、それともマトゥラーモーハン劇団?」
「祭りのことは祭り屋に聞きなよ!」ヒラーマンはまたチャッタープル・パチーラー村の名前を出した。
太陽はもうだいぶ上まで昇っていた。ヒラーマンは牛たちと会話を始めた。「あと3kmくらいだ!もうひとふんばりだぞ!だいぶ喉が渇いたろうな!覚えてるか、あのときテーガチヤー村の近くで、サーカス団のジョーカーと猿回しがケンカしたっけな。ジョーカーの奴、まるで猿みたいに歯をひんむいてキーキー叫び始めたな。・・・世の中にゃ、いろんな奴がいるもんだな!」
ヒラーマンは再びカーテンの穴から覗いた。ヒーラーバーイーは紙切れを見ながら座っていた。今日のヒラーマンは上機嫌だった。いろんな歌が頭に浮かんだ。20〜25年前は、ビデーシヤー、バルワーヒー(舞踊の一種?)、チョークラー・ナーチ(児童舞踊)、みんな同じような歌を歌っていたものだった。今では、スピーカーからプープープープーいったい何の歌を歌ってることか!古き良き時代だったな!ヒラーマンはチョークラー・ナーチの歌を思い出した。
愛しい人、私の敵になってしまったの、愛しい人・・・
ああ、手紙だとみんなに読まれてしまう、手紙だと・・・
ヘイ!愛しい人、ヘイ、愛しい人・・・
誰も読まないよ、オレたちの手紙、・・・愛しい人・・・
車の手すりを指で打ち鳴らしながら歌っていたヒラーマンは、ふと歌うのを止めた。チョークラー・ナーチの踊り子の顔は、ヒーラーバーイーにそっくりだった。・・・あの古き良き時代はどこへ行ってしまったのだろう?毎月舞踊団が村にやって来ていた。チョークラー・ナーチが来るといつも、ヒラーマンは兄嫁の罵声を聞いていた。兄は兄嫁に、出て行け、と言っていた。
今日のヒラーマンにはサラスワティー女神の恩恵があるように思えた。ヒーラーバーイーは言った。「わぁ!素敵な歌声ね!」
ヒラーマンの顔が赤くなった。彼はうつむいて笑った。
今日はテーガチヤー村に祀られているマハーヴィール(ジャイナ教の教祖)もヒラーマンを手助けしているようだ。テーガチヤーの3本樹の下には一台も車が止まっていなかった。ここには車と車乗りがたむろっているのが常だった。ただサイクルリクシャー乗りが一人だけ座ってのんびりしていた。マハーヴィールの名前を心の中で唱えつつヒラーマンは車を止めた。ヒーラーバーイーはカーテンを開けようとしたが、ヒラーマンは彼女に目で合図した。彼女に目で合図をしたのはこれが初めてだった――サイクルワーラーがこっちをじっと見てる。
牛を解く前に、車輪止めを車輪の下に置いて車を固定した。そしてサイクルワーラーの方をチラチラと見ながら聞いた。「どこへ行くんだ?祭り?どっから来た?ビサンプル村から?すぐ近くじゃねぇか、もう疲れちまったのか?・・・ほら、もう行けよ、若いんだからよぉ!」
やせ細った若いサイクルワーラーはブツブツ言いながら、ビーリーに火を付けて立ち上がった。
ヒラーマンはヒーラーバーイーを世間のあらゆる視線から守ってやりたかった。彼は四方を見回した――どこにも車や馬はなかった。
カジュリー河の細い流れは、テーガチヤーの3本樹のそばで東の方へ湾曲していた。ヒーラーバーイーは水の中で座っている水牛と、その背中に止まっているサギを見つめていた。
ヒラーマンは言った。「さあ、河で顔と手を洗って来なよ!」
ヒーラーバーイーは車から降りた。ヒラーマンの心臓がドキッとした。・・・いやいや!足はまっすぐだ、曲がってやしない。それなのに足がこんなに赤いのはなぜだろう?ヒーラーバーイーは河岸の方へ行った、村の女のように頭を下にしてゆっくりと。誰が劇団の女だと気付くだろう?・・・女じゃない、女の子だ。多分まだ未婚だろう。
ヒラーマンは車の上に座った。彼は幌の中を覗いた。一度辺りを見回してから、ヒーラーバーイーの枕に手を触れた。そのまま肘を突いてみた。いい香りが彼の身体を覆った。枕のカバーに刺繍されている花を手で触って匂いを嗅いでみたら、わぁ!なんていい匂いだ!まるで大麻を5回吸った後のように目が覚めた。ヒーラーバーイーの小さな鏡で彼は自分の顔を見た。オレの歯がこんなに赤いのはなぜだろう?
ヒーラーバーイーが戻ってくると、彼は笑って言った。「じゃあちょっと、今度はあんたが車を見ててくんな、オレはすぐ来るからよ。」
ヒラーマンは自分の旅行袋から下着を取り出した。タオルを一振りして肩にかけると、バケツをぶらさげて彼は歩き出した。牛たちが代わる代わる「フンク、フンク」と鳴いた。ヒラーマンは歩きながら振り返って言った。「ああ、分かってるとも、みんな喉が渇いてるんだ。すぐ戻ってくるからよ、そしたら草をやるから、いい子にしてるんだぞ!」
牛たちは耳を振った。
ヒラーマンがいつ一浴びして帰ってきたのか、ヒーラーバーイーは知らなかった。カジュリー河の流れを見ているうちに、彼女の目に夜の眠気が舞い戻ってきた。ヒラーマンは近くの村から食事のためにヨーグルトとチューラー(焼き飯)と砂糖を買ってきた。
「さあ、目を覚まして!ちょいと腹ごしらえをしよう!」
目を覚ましたヒーラーバーイーは驚いた。片方の手にはヨーグルトの入ったカップとバナナの葉っぱ、もう片方の手は水の入ったバケツ。目には親愛の情!
「これだけのもの、どこから持って来たの?」
「この村のヨーグルトは有名なんだ。・・・チャーイ(茶)はファールビスガンジ村で飲むといい。」
ヒラーマンの背中のムズムズは消えていた。ヒーラーバーイーは言った。「あなたも葉っぱを敷いて・・・どうして?あなたが食べないなら包んで袋の中にしまってちょうだい。私も食べないわ!」
「えっ!」ヒラーマンは照れながら言った。「分かったから、まずはあんたが食べなよ。」
「先も後もないわ。あなたも座って!」
ヒラーマンは遂に折れた。ヒーラーバーイーは彼のために葉っぱを敷いて、水を振りかけ、チューラーをその上に乗せた。ああ!ありがたや、ありがたや!ヒラーマンは、バグワティー女神が食べ物をよそってくれるのを見た。赤い唇にヨーグルトが触れる!・・・山のオウムが食事をするところを見た者があろうか!
夕日が赤く燃えていた。
幌の中で眠っていたヒーラーバーイーと、地面に敷物を敷いて寝ていたヒラーマンは同時に目が覚めた。・・・祭りへ向かう車がテーガチヤーの3本樹のそばで止まったのだ。子供たちがキャッキャと騒いでいた。
ヒラーマンは急いで起き上がった。幌の中を覗いて、目配せで言った――もうすぐ日が沈んじまう!彼は車乗りたちの質問に答えもせずに、急いで車に牛たちをつなげた。そして車を進めながら言った。「スィルプル市場の病院のお医者様さ。病人を診に行くところだ。近くのクルマーガーム村にね。」
ヒーラーバーイーはチャッタープル・パチーラー村の名前を忘れてしまった。車がしばらく進んだところで、彼女は笑いながら聞いた。「パッタープル・チャピーラー村はどうしたの?」
ヒラーマンは大笑いし過ぎて腹が痛くなってしまった。「パッタープル・チャピーラー村だって!ハッハッハ!あいつらはチャッタープル・パチーラー村の車乗りだったのさ。奴らにそんなこと言えるはずないだろう!ヒッヒッヒ!」
ヒーラーバーイーは微笑みながら村の方を見た。
道はテーガチヤー村の中を通っていた。村の子供たちは、カーテンのかかった車を見て、手を打ち鳴らしながら、童謡を歌いだした。
赤い赤い御輿の中で
赤い赤い花嫁が
パーン(噛みタバコ)を食べている・・・!
ヒラーマンは笑った。・・・花嫁・・・赤い赤い御輿!パーンを食べて、花婿のターバンで口を拭っている花嫁。おお、花嫁、テーガチヤー村の子供たちを忘れないで。戻って来るときは、ナツメの汁でできたラッドゥー(ボール状の甘いお菓子)を持ってくるのを忘れないで。何万年も、お前の花婿が生きるように!・・・この願望をかなえるのに、ヒラーマンは何年待ったことだろう!このような夢を、今まで何度見たことだろう!彼は自分の花嫁を乗せて村に戻っていた。男も女も皆聞いて来るのだ。「どこの車だい?どこへ行くんだい?」彼の花嫁は、御輿のカーテンを少しだけ開けて見ている。こんな夢を彼は幾度となく見たものだった・・・
村を抜けた後、彼は横目で幌の中を見た。ヒーラーバーイーは何か考え事をしていた。ヒラーマンも考え事を始めた。しばらく後に、彼は口ずさみ始めた。
愛しい人よ、嘘をつかないで、神様のところへ行くなんて
象でもなく、馬でもなく、車でもなく
そこには歩いて行くなんて。愛しい人よ・・・
ヒーラーバーイーは聞いた。「ねぇ、ミーター?あなたの村の言葉で何か歌はないの?」
ヒラーマンは今や躊躇なくヒーラーバーイーの目を見て話していた。劇団の女は皆こうなのだろうか?サーカス団の女主人もこんなだった。しかしヒーラーバーイー!村の方言の歌を聴きたいとは。彼は微笑んで言った。「あんたは村の言葉が分かるのかい?」
「ええ!」ヒーラーバーイーは首を振った(肯定の仕草)。耳飾りが揺れた。
ヒラーマンはしばらく黙って牛たちを進めた後に言った。「どうしても歌を聴きたいのかい?どうしても?・・・そうかい!あんたはよっぽど村の歌に興味があるようだなぁ!ならこの道を外れなきゃなんねぇ。人通りの多い道じゃあ歌を歌うことなんざ、できやしねぇからな。」ヒラーマンは左の牛の手綱を引いて、右の牛を道から外れさせて言った。「そうなってくると、ハリプル村には寄らないことになるな。」
ヒラーマンの車が道を外れるのを見て、ヒラーマンの後ろから車を走らせていた車乗りが叫んだ。「どうしたんだい、道を外れてどこへ行くんだい?」
ヒラーマンは革ひもを振り回しながら答えた。「道を外れたって?この道はナナンプル村には行かんだろう。」そして一人でつぶやいた。「この辺りの奴らの悪い癖だ。道を行くだけであれこれ質問してきやがる。他人のことは気にするなってんだ。・・・村の奴らは馬鹿ばっかさ。」
ヒラーマンは車をナナンプル村へ続く道に乗り上げ、牛たちの手綱を緩めた。牛たちは駆けるのを止め、ゆっくり歩き出した。
ヒーラーバーイーは、ナナンプル村へ続く道は本当に静かであることに気付いた。ヒラーマンは目を見ただけで彼女の気持ちを察した。「心配しなさんな。この道もファールビスガンジ村へ行くよ。途中の村人たちはいい奴ばかりさ。夜までには到着するだろう。」
ヒーラーバーイーは急いでファールビスガンジ村に到着する必要はなかった。今や彼女は何の心配や恐怖も感じないほどヒラーマンを信頼していた。ヒラーマンはまずは照れ笑いをした。どの歌を歌えばいいかな!ヒーラーバーイーは歌と物語を聞くのが大好きだ。・・・そうだ!『渡し守の娘マフアー』はどうだ?彼は言った。「よし、あんたがそんなに望むんなら、『渡し守の娘マフアー』の歌を歌おう。これは歌あり、物語ありだからちょうどあんたにいいだろう。」
・・・バグワティー女神は彼のこの願いすらかなえてくれた。バグワティー女神万歳!今日のヒラーマンの心は天にも昇ってしまうだろう。彼はヒーラーバーイーの微笑みを見つめた。
「それじゃあ始めるぜ!今でもパルマール河には渡し守の娘マフアーゆかりの河岸が残ってる。マフアーはこの地方の女だった!渡し守の娘だったが、その信心深ささは人並み外れていた。彼女の父親は大酒飲みで、昼も夜も酔っ払って寝転んでいた。継母は悪鬼羅刹のような女だった!そして稀代の詐欺師!夜な夜な大麻、酒、阿片を盗んでは売るような輩どもと継母は幼少の頃からの知り合いだった。マフアーは独身だった。しかし羅刹女の継母は、マフアーをこき使って働かせてたから、彼女の身体はボロボロだった。どこからも結婚の話は来なかった。そんなある晩のこと!」
ヒラーマンは小声で喉の調子を確かめるようにして口ずさみ出した。
アァア〜、サーヴァン月(7〜8月)、バードーン月(8月〜9月)の増水した河
恐ろしげな夜、ゴロゴロ唸る雷
小さな女の子がどうやって河岸まで行けるだろうか
しかも他国の商人に買われるために
継母は家の扉をピッタリと閉ざしてしまった
空には暗雲が立ち込め、轟音と共に雨が降り出した
マフアーは泣き出した、自分の母親を思い出して
母親が生きていたら、今日のような怖い日には
マフアーは母親の胸に抱きしめられていたことだろう
お母さん、この日のため、こんな目に遭わせるために、
あなたは私を生んだの?
マフアーは母親に怒りが込み上げた
どうして一人、死んでしまったの?
心の底から憎んで言った・・・
ヒラーマンが見ると、ヒーラーバーイーは枕に肘を付いて、歌に聴き入りながら彼の方を見ていた。・・・歌に没頭したその姿は何とも無邪気だった。
ヒラーマンは喉を震わせた。
なんてひどいお母さんなの
私のことをほったらかしにして死んでしまうなんて
この日のために娘を生んで
私にミルクを飲ませてウトガンを塗ったの・・・
ヒラーマンは息を吸いながら聞いた。「歌の意味は分かるかい、それとも単に歌だけを聴いてるのかい?」
ヒーラーバーイーは答えた。「分かってるわ。ウトガンっていうのはつまりウブタン、身体に塗るウコンと油と香水の練り物のことね。」
ヒラーマンは「へぇ」と驚きながらも歌を続けた。
今さら泣いても何にもならない
商人はマフアーの代金を耳を揃えて払ったのだ
彼はマフアーの髪を引っ張って、引きずりながら舟に乗り
船頭に、舟の縄をほどいて帆を畳むよう命令した
帆船は小鳥のように岸を飛び出した
マフアーは泣き喚めき続けた
商人の部下たちは彼女を脅した
静かにしろ、でないと水の中に放り込むぞ
そのときマフアーは決意した
夜明けの星が雲の切れ間からチラリと現れ消えてしまった
マフアーも黙って水の中に飛び込んだ
商人の部下の一人がマフアーを見た途端恋に落ちてしまっていた
マフアーの後を追って彼も飛び込んだ
流れに逆らって泳ぐのは簡単ではない
しかもバードーン月の増水した河なのだ
マフアーは生粋の渡し守の娘だった
魚が水の中で溺れるだろうか!
マフアーは魚のように水を掻き分けて逃げて行った
その後ろから商人の部下が叫んで言った
マフアー、ちょっと待っておくれ
君を捕まえようとしてるんじゃないよ
僕は君の味方だよ
僕たち一生一緒に住もう
しかし・・・
これはヒラーマンのお気に入りの歌だった。『渡し守の娘マフアー』を歌っている間、彼の目の前にはサーヴァン月、バードーン月の荒れ狂った河が浮かんで来るのだった。新月の夜、垂れ込めた雲の中で雷が光っていた。その雷の中、波と戦う小さな少女マフアーの姿がチラリと見えるのだった。魚の動きはさらに速くなった。彼は、自分自身がマフアーに恋した商人の部下であるように感じた。マフアーは話を聞こうとしなかった。気にもしなかった。振り返ろうともしなかった。彼は泳いで泳いで、とうとう疲れてしまった・・・
今日のヒラーマンは、マフアーが掴まってくれたように思えた。自分で掴まりに来たのだ。彼はマフアーに触れることができた。得ることができた。彼の疲れは消え去った。15〜20年間、増水した河の流れに逆らって泳いでいた彼の心は、岸辺を見つけた。至福の涙は止めどもなく流れ落ちた・・・
彼はヒーラーバーイーに自分の濡れた目を見られないようにした。しかし彼女は彼の心の中に座って、ずっと前から全てを見ていた。ヒラーマンは震える声を振り絞って牛たちを叱り付けた。「この歌に何があるか知らねぇが、この歌を聞くと2匹ともなぜかゆっくりになるんだよ。まるで誰かが何千kgもの荷物を載せたみたいにな。」
ヒーラーバーイーは長いため息をついた。ヒラーマンの身体中が熱くなった。
「あなたはウスタード(先生)だわ、ミーター!」
「何だって!」
アーシュヴィン月からカールティク月(9月〜11月)の太陽はすぐに沈んでしまう。太陽が沈む前にナナンプル村に着かなければならない。ヒラーマンは牛たちに言い聞かせていた。「足を速めろ、気合を入れろ・・・エイ・・・チッチッ!バイヤン、もっと速く!レーレーレーヘイ!」
ナナンプル村まで彼は牛たちを急かし続けた。牛たちを急かすときには、彼は必ず昔話をするのだった。「なぁ、覚えてるか、チャウドリーの娘のバラート(結婚パレード)に何台の車が集まったことか。オレたち、全部の車を追い抜いてやったっけなぁ!そうだ、あんな速さを出すんだ。レーレーレー!ナナンプル村からファールビスガンジ村まで10km!あと2時間!」
ナナンプル村の市場では最近チャーイ(茶)も売られるようになった。ヒラーマンはコップにチャーイを満たして持ってきた。・・・劇団の女のことを彼はよく知っていた。一日中、何度も何度もチャーイを飲んでいるのだ。チャーイだけが人生みたいに!
ヒーラーバーイーは笑って言った。「まぁ、あなたに誰が言ったの、独身の男性がチャーイを飲んじゃいけないなんて?」
ヒラーマンは顔を赤らめた。何て言えばいいのだろう?・・・恥ずかしい話だ。しかし彼は一度だけチャーイを飲んだことがあった。サーカス団の女主人からチャーイをもらったことがあったのだ。ひどく熱い飲み物だった!
「飲んでちょうだい、グルジー(先生)!」ヒーラーバーイーは笑った。
「へっ?」
ナナンプル村の市場では既に灯火が付いていた。ヒラーマンは携帯用ランタンに火をつけて後部にぶら下げた。最近は町から15km離れた村に住む村人たちも自分のことを都会人だと思っている。灯りを付けていない車を捕まえては警察に突き出すのだ。
「あんた、オレのこと、グルジーって呼ぶのはよしてくれ。」
「あなたは私のウスタードよ。経典にも書いてあるわ、文字を教える者はグルであり、音楽を教える者はウスタードだって。」
「へぇ!経典や神話のことも知ってるのかい!・・・でも、オレが何を教えたってんだい?オレが何だってんだい・・・?」
ヒーラーバーイーは笑いながら口ずさんだ。「アァア〜、サーヴァン月、バードーン月の増水した河・・・」
ヒラーマンは驚いて言葉を失った。・・・なんて賢いんだ!全く渡し守の娘のマフアーそのものだ!
車はスィーターダール河の乾いた河の底にギシギシ音を立てながら下りた。ヒーラーバーイーはヒラーマンの左肩を片手で掴んだ。しばらくの間、彼女の指はヒラーマンの肩に触れていた。ヒラーマンは横目で何度もその肩を見ようと努力した。車が坂を上り始めると、ヒーラーバーイーの指に再び力が入った。
前方にファールビスガンジ村の灯りが見え始めた。町から少し離れた場所に祭りの灯り・・・ランタンの光の中、影があちこちで踊りを踊っていた。・・・涙に濡れた目で見ると、それらの光はヒマワリのように見えた。
ファールビスガンジ村はヒラーマンの庭みたいなものだった。
何度彼はファールビスガンジ村に来たことか。祭りの荷物を運んでいた。誰か女性と一緒に?たった一度だけ。兄嫁と共に、彼女が結婚して家に来た年に一度。このように布で車を四方から覆って簡易の部屋を作ったものだった。
ヒラーマンは車乗りの広場で車を布で覆っていた。早朝、ラウター劇団のマネージャーと話をして、ヒーラーバーイーを引き渡すのだ。明後日に祭りは始まる。今回の祭りでは、キャンプ場はだいぶ混雑していた・・・たった一晩。今晩は一晩中、彼女はヒラーマンの車の中で過ごすのだ。・・・ヒラーマンの車の中?・・・いや、これは彼の家なのだ!
「どこの車だい?・・・誰だ、ヒラーマン!どの祭りから?積荷は何だい?」
村の車乗りたちは、お互いに声を掛け合って、車を寄せ合ってテントを張るものだ。ヒラーマンは、自分と同郷の車乗り、ラールモーハル、ドゥンニーラーム、パラトダースらを見て驚いた。一方、パラトダースはヒラーマンの車の幌の中を覗いて、まるで虎と目が合ったかのように「ヒャッ!」と奇声を上げた。ヒラーマンは口に人差し指を当てて皆を黙らせた。そして車の方にウィンクして囁いた。「静かに!劇団の女だ。」
「劇団の・・・?」
「??・・・??・・・!」
1人じゃない、今や4人のヒラーマン!4人はお互いの顔を見合わせた。・・・劇団の名前はそれほど影響力があるのだ。ヒラーマン以外の3人は、驚きのあまり3人とも魂が抜けてしまったかのようになった。ラールモーハルは、ちょっと遠くへ行って話をしよう、と身振り手振りで皆に知らせた。ヒラーマンは幌の方を向いて言った。「もう飯屋は閉まっちまったろう。駄菓子屋から何か買って来るから待ってな!」
「ヒラーマン、ちょっとこっちに来て。・・・私はまだお腹減ってないわ。あなただけ食べなさい、はい、これ。」
「これは何だ?金?チッ!」・・・ヒラーマンはファールビスガンジ村でお金を払って食べ物を食べたことがなかった。村の仲間がこんなにいるのは何のためか?彼はお金に触ることもできなかった。彼はヒーラーバーイーに言った。「祭りの日にこんなよそよそしいことはよしてくんな。金は持っててくれ。」この隙を利用してラールモーハルも幌の近くまで忍び寄って来た。ラールモーハルは彼女に挨拶をして言った。「4人分の食事に2人増えたところでどうってことありませんぜ。オレのテントでもう食事を作ってるところです。ヘッヘッヘ。オレたちゃおんなじ村のもんで。同郷の友をほっぽりだして、ヒラーマンがどうして飯屋や駄菓子屋で食事しましょうや?」
ヒラーマンはラールモーハルの手をつねった。「汚ねぇしゃべり方すんじゃねぇ!」
車から遠くへ歩きながら、ドゥンニーラームは不満を暴露した。「全く!おめぇは本当に果報者だよ、ヒラーマン!去年はサーカス団の虎、今年は劇団のべっぴんさんと来たもんだ!」
ヒラーマンは声を抑えて言った。「お前たち、聞けよ、あの娘はオレたちの地方の者じゃねぇ、訛った言葉で話しかけるんじゃねぇ。西方の女だし、それに劇団の女ってこと忘れるな!」
ドゥンニーラームは疑り深げに言った。「でもよ、劇団の女はよ、聞いたとこによると、売春婦らしいぜ。」
「馬鹿野郎!」皆が一斉に彼を罵った。「なんて奴だ!劇団の女が売春婦なはずねぇだろ!何考えてやがんだ!・・・見たこともねぇくせに、聞いただけで話をしやがる!」
ドゥンニーラームは自分の過ちを認めた。パラトダースはいい案を思いついた。「ヒラーマン兄貴、女の子が一人で車で夜を過ごすのかい?いくら劇団の女だからって、女は女だからよ。多分何か必要になることがあるんじゃねぇか?」
彼の発言には皆が納得した。ヒラーマンは言った。「その通りだ。パラト、お前は戻って、車のそばにいろよ。あと、いいか、話はよく考えてするんだぞ、いいな!」
ヒラーマンの身体からバラの花の香りがした。ヒラーマンは働き者の果報者だ。去年は何ヶ月も身体から虎の臭いが抜けなかった。ラールモーハルはヒラーマンのタオルの匂いを嗅いだ。「ウヘッ!」
ヒラーマンは急に立ち止まった。「どうしたもんか、ラールモーハル兄貴、何とかしてくれ!あの娘、わがまま言って聞かないんだ、劇を見て行けってな。」
「無料で?」
「村まで噂が広まんねぇかな?」
ヒラーマンは言った。「やっぱ駄目だ!一晩劇を見て、一生後ろ指指されるのは御免だ。・・・村の奴らはずっとオレたちを笑い者にするだろうぜ。」
ドゥンニーラームは聞いた。「無料で劇を見ても、お前の兄嫁は怒るのか?」
ラールモーハルのテントのそばには、屋台を載せてやって来た車乗りたちのテントがあった。テントの主のミヤーンジャーヌー翁が、携帯用の水タバコを吸いながら聞いた。「なぁ、ミーナー市場の積荷積んで来た奴はどいつだ?」
ミーナー市場!ミーナー市場と言ったら売春街のことだ。・・・この老翁は何を言い出すのか?ラールモーハルはヒラーマンにそっと耳打ちした。「お前の身体はプンプン匂うんだよ、ホントに。」
レヘサンワーンはラールモーハルの下で働く車乗りだった。年は一番若かったが、初めて祭りに来たからといってどうってことない。彼は幼少の頃から既にいろんな場所で働いており、状況を鼻で嗅ぎ分け、耳で聞き分ける術を心得ていた。ヒラーマンは、レヘサンワーンの顔が赤らむのを見て取った。・・・誰だ、ドタバタこっちに来るのは?「ん、パラトダース?どうした?」
パラトダースはやって来ると、黙って立ち尽くした。彼の顔も赤らんでいた。ヒラーマンは聞いた。「どうした?なんで黙ってるんだ?」
何と答えようか、パラトダースは!ヒラーマンは彼に、話はよく考えてするように忠告しておいた。彼は車へ行って、黙ってヒラーマンの席に腰を下ろした。ヒーラーバーイーは聞いた。「あなたもヒラーマンの仲間なの?」パラトダースは首を振って肯定した。ヒーラーバーイーは再び横になった。・・・彼女の表情を見て、話し方を聞いて、パラトダースの心は異常なほど震え上がった。そうだ!ラームリーラー(「ラーマーヤン」を主題とした劇)の中で、スィーター姫はちょうどこんな風に疲れて横になっておられた!スィーター姫の夫、ラームチャンドラ王、万歳!・・・パラトダースの心の中で万歳三唱が沸き起こった。彼はヴィシュヌ派のブラーフマン(僧侶)だった。彼は疲れたスィーター姫のお御足を揉んで差し上げたい願望を露にした・・・まるでハルモニウム(鍵盤楽器)を弾く手のように指を動かして。ヒーラーバーイーは飛び上がって怒った。「きゃあ、何するの?どっか行って!」
パラトダースは、怒りの震えた劇団の女の目からパチパチと火の粉が飛び散っているように思った。彼は逃げ出した。
パラトダースは何と答えようか!彼は祭りからも逃げ出す口実を考えていた。彼は言った。「何でもない!客が見つかったんだ。今から駅まで行って、荷物を積まなきゃなんねぇ。食事をするにはもう遅くなっちまった。また戻って来るから、じゃあな。」
食事中、ドゥンニーラームとレヘサンワーンはパラトダースの悪口をありったけ叩き合った。小心者だ。悪人だ。ケチンボだ。食事が終わった後、ラールモーハルの一団はテントをたたんだ。ドゥンニーラームとレヘサンワーンは車を牛につなげて、ヒラーマンのテントまで先に車を走らせて行った。ヒラーマンはラールモーハルと歩いていたが、急に立ち止まって彼に言った。「ちょっとオレのこの肩の匂いを嗅いでくんな。やっぱり匂うかい?」
ラールモーハルは彼の肩の匂いを嗅いで目をつぶった。口から言葉にならない言葉が漏れた。「ウヘッ!」
ヒラーマンは言った。「ちょこっと手を置かれただけでこの通りプンプンの香りだ!・・・全く!」
ラールモーハルはヒラーマンの手を掴んだ。「肩に手を置いたのか?ホントに?・・・いいか、ヒラーマン、こんな風に劇を見る機会は2度と巡って来ねぇだろう。2度とな!」
「お前も見るか?」
ラールモーハルの歯が交差点の光の中できらめいた。
テントまで戻ると、ヒラーマンは、幌のそばに誰かが立ってヒーラーバーイーと話をしているのを見た。ドゥンニーラームとレヘサンワーンは同時に言った。「どこ行ってたんだい?ずっと探してたんだぜ、劇団の・・・」
ヒラーマンは幌のそばへ行って見た――おや、こいつは箱を積み込んだ下男じゃねぇか、チャンパーナガルの祭りでヒーラーバーイーを車に座らせて暗闇の中に消えちまった、あの・・・。
「ああ、来てくれた、ヒラーマン!よかった、こっち来て!・・・これ、運賃、それとこれ、心付けよ!25ルピーと25ルピーで、50ルピー。」
ヒラーマンは、誰かに空中から地面に突き落とされたかのように感じた。誰かに、と言う必要はない・・・この、荷物を積んだ男に。お前、どこから来たんだ?彼の舌まで来た言葉は、舌で止まってしまった。・・・何だって!心付け!彼は黙って立ち尽くした。
ヒーラーバーイーは言った。「さあ、受け取って!それから、いい?明日の朝、ラウター劇団まで私に会いに来て。パスを作らせるから。・・・どうして黙ってるの?」
ラールモーハルは言った。「おい、マダムが運賃とバクシーシ(喜捨銭)をくれるってよ、受け取れよ、ヒラーマン!」ヒラーマンはラールモーハルを睨みつけた。・・・全く話し方を知らない奴だ、ラールモーハルは!
ドゥンニーラームの独り言を皆が聞いた、ヒーラーバーイーも――車乗りが車と牛をほっぽり出して祭りで劇を見られるかってんだ。
ヒラーマンはお金を受け取りながら言った。「何て言うかその・・・」彼は笑おうと努力した。・・・劇団の女が劇団に去って行ってしまう。ヒラーマンが何だってんだ!荷物を積んだ男は、道を示しながら前へ進んだ。「こっちです。」ヒーラーバーイーは足を止めた。彼女はヒラーマンの牛たちに声を掛けて言った。「じゃあ、私はもう行くわね、バイヤン!」
牛たちは、「バイヤン」という言葉に反応して耳を振った。
「?・・・?・・・!」
「聞いてらっしゃい、見てらっしゃい!今晩、ザ・ラウター歌劇団のステージで、グルバダン(同名のヒロインを主人公とした劇の名前)を見てらっしゃい!なんとマトゥラーモーハン劇団のかの有名な女優、何千人もの観客を虜にしたミス・ヒーラーデーヴィーが、今回我々の劇団に来てくれました。一生の思い出に、今宵、ミス・ヒーラーデーヴィーのグルバダンを・・・!」(ヒーラーデーヴィー=ヒーラーバーイー)
劇団のこの告知によって、祭りの会場はどこもかしこも大騒ぎとなっていた。・・・ヒーラーバーイー・・・ミス・ヒーラーバーイー?ライラー(これも恋愛劇のヒロインの名前)、グルバダン・・・?映画女優が色あせるほどの女だ!
(宣伝の歌)
・・・君のその仕草に僕はすっかりまいってしまった
君への欲望をどのように巧く言葉にしようか!
たったひとつの願い、君よどうか僕を見ておくれ
そして、愛しい人よ、僕は君を見続けられるように
キルルルル・・・キルルルル・・・ダン、ダン、ダーン!
人々の心は太鼓のように鳴り響いた。
ラールモーハルは息せき切ってテントまで走って来た。「ハァ、ハァ、ヒラーマン、ここで何座ってるんだ、ちょっと見てみろよ、みんなが万歳万歳してるぞ!楽隊の演奏と一緒に、ヒーラーバーイーの万歳してるんだ!」
ヒラーマンは急いで立ち上がった。レヘサンワーンは言った。「ドゥンニーおじさん、あんたはテントにいてくれ、オレも見に行ってくる。」
ドゥンニーラームの呼びかけを誰が聞いていようか!3人は宣伝をして歩く劇団の一団の後ろを歩き出した。街角で立ち止まっては、太鼓を打ち鳴らして宣伝をしていた。宣伝文句の言葉ひとつひとつに、ヒラーマンの身体は喜びで打ち震えた。ヒーラーバーイーの名前、そしてその名前を飾る数々の言葉を聞いて、彼はラールモーハルの背中を叩いた。「全くすごいな!そうは思わねぇか?」
ラールモーハルは言った。「さあ、どうだ!これでも劇を見ねぇのか?」朝からドゥンニーラームとラールモーハルは彼を説得していたのだが、ヒラーマンは劇を見ようとしなかったのだ。「劇団に行って会って来いよ。お前のこときっと待ってるぜ。」しかしヒラーマンは同じ言葉を繰り返すだけだった。「へん、誰が会いに行くもんか!劇団の女は劇団に行っちまったんだ。もう何の関係もねぇさ!オレのことももう忘れちまっただろう!」
彼はすっかりすねていたのだが、その宣伝文句を聞いて、すっかり心変わりした。彼はラールモーハルに言った。「こりゃあ是非とも見なきゃなんねぇ、そうだろ、ラールモーハル?」
2人はあれこれ相談しながらラウター劇団の方へ向かった。テントのそばに着くと、ヒラーマンはラールモーハルに合図した。質問するのはラールモーハルの仕事になっていた。ラールモーハルは標準語を知っていた。ラールモーハルは一人の黒いコートを羽織った男に話しかけた。「旦那、ちょっといいですか!」
黒コートの男は顔をしかめて言った。「なんだ?どうしてここに来た?」
ラールモーハルの標準語はしどろもどろになってしまった。しかめっ面を見ながら言った。「ええっと・・・ブル・・・ブル・・・あ、あの・・・グル・・・グル・・・」
ヒラーマンは急いで取り繕った。「ヒーラーデーヴィーはどこにいるか、知ってますかい?」
その男の目はみるみるうちに赤くなった。前に立っていたネパール人の門番を呼んで言った。「こいつらをどうして中に入れた?」
「ヒラーマン!」・・・あのガラスのような声、どこから?テントのカーテンが開き、ヒーラーバーイーが顔を出した。「こっちに来て、中に!・・・いい、バハードゥル(ネパール人に対する呼称)!彼を覚えておいて。彼は私のヒラーマンなの。分かった?」
ネパール人の門番はヒラーマンの方を見て少し微笑み、去って行った。黒コートの男のところに行って言った。「ヒーラーバーイーの知り合いです。中に通すように言われました!」
ラールモーハルはネパール人門番のためにパーン(噛みタバコ)を持って来て渡した。「まぁ、食べなって!」
ヒラーマンは戻ってきてラールモーハルに言った。「驚いたよ!1枚ばかりか5枚もパスくれた!5つとも50パイサー席だ!祭りにいる間は、毎晩来て見ろってさ。それにみんなことを考えてくれたよ。お前のと仲間の、みんなのパスを持ってけってさ。劇団の女の考えることは違うな!そう思うだろ?」
ラールモーハルは赤い紙切れを手にとって見た。「パ〜ス!やったぜ、ヒラーマン兄貴!・・・でも5枚もパスをもらってどうするんだ?パラトダースはまだ戻って来ねぇし。」
ヒラーマンは言った。「あの馬鹿はほっとこう。運がなかったってことさ。・・・そうだ、まずはみんな、神様に誓わなきゃなんねぇ。村でも家でも、このことは誰にも漏らさねぇってな。」
ラールモーハルは鼻息を荒くして言った。「誰が言うもんか、村に戻って?パラトダースの奴がもし間違った真似でもしやがったら、もうあいつとは絶交してやる。」
ヒラーマンは自分の荷物袋をヒーラーバーイーのところへ預けた。祭りでは何があるか分からない。あらゆる種類のスリたちが毎年やって来るのだ。自分の仲間ですら信用できない。ヒーラーバーイーは快諾してくれた。ヒラーマンの布製の黒い袋を彼女は自分の革製の箱に閉まってくれた。箱は表面が布で覆われ、裏地も光沢のあるシルクだった。まるで心が洗われるかのように美しかった。
ラールモーハルとドゥンニーラームは共にヒラーマンの賢さを賞賛した。彼の幸運を何度も何度も褒め称えた。そして婉曲に彼の兄と兄嫁の批判もした。ヒラーマンのような立派な弟がいたからだ!他の弟だったら・・・。
レヘサンワーンは今にも泣きそうな顔をしていた。劇団の宣伝隊を追いかけて彼はどこかへ行ってしまっており、夕方になってやっと戻ってきた。ラールモーハルはご主人様らしく彼に罵声を浴びせて叱った。「どこをほっつき歩いてやがった、この役立たず!」
ドゥンニーラームはコンロの火にキチュリー(インド式お粥)の入った鍋をかけながら言った。「まずは、車の番を誰がするか決めねぇとな!」
「車の番って、このレヘサンワーンがいるじゃねぇか?」
レヘサンワーンは泣き出した。「ヘ〜エ〜エ〜、ご主人様、お願いです。一目だけ!たった一目だけでも!」
ヒラーマンは同情して言った。「分かった、分かった、一目じゃ物足りんだろ、1時間は見ろよ。オレが戻って来るから。」
劇が始まる2時間前に太鼓が鳴った。そして太鼓が鳴るや否や、人々は会場に雪崩れ込んだ。チケット売り場の前に出来た人だかりを見て、ヒラーマンは笑いが込み上げた。「ラールモーハル、あれを見てみろよ、押し合いへし合い大変そうだな、みんな!」
「ヒラーマン兄貴!」
「ん、誰だ、パラトダース!どこに荷物運んで来たんだ?」ラールモーハルは赤の他人のように聞いた。
パラトダースは手をこすり合わせながら許しを乞うた。「オレが間違ってたよ・・・どんな罰でも受け容れるさ。でも、正直言ってスィーター姫の・・・。」
ヒラーマンの心は、太鼓のリズムのおかげで既に高揚していた。彼は言った。「いいか、パラト、彼女はオレたちの村や家の女じゃねぇ、勘違いするな。さあ、お前のパスもここにあるぜ。1枚持ちな、一緒に劇を見ようじゃねぇか。」
ラールモーハルは言った。「しかしパスをもらうにはひとつ条件がある。途中でレヘサンワーンと交替すること・・・」
パラトダースは全部知っていた。ついさっき、レヘサンワーンと話をしてきたばかりなのだ。
ラールモーハルは2つ目の条件を出した。「村でもしこのことが知れたら、どうなるか・・・」
「ラーム・ラーム(神様に誓って)!」パラトダースは宣誓した。
パラトダースが言った。「50パイサー席の入り口はこっちみたいだ。」入り口に立っていた門番は、パスを受け取ると彼らの顔をジロジロと見て言った。「これはパスだ。どっから手に入れた?」
今こそラールモーハルの標準語の出番だ!彼の怒った表情を見て、門番は萎縮してしまった。「どっから手に入れたかですって?劇団まで行って確認してください。4枚だけじゃなくて、もう1枚持っているんです。」ラールモーハルはポケットから5枚目のチケットを取り出して見せた。
1ルピー席の入り口には、ネパール人の門番が立っていた。ヒラーマンは彼を呼んだ。「おい、門番の兄ちゃん、朝会ったのにもう忘れたのかい?」
ネパール人門番は言った。「みんなヒーラーバーイーの知り合いだ。通していいぞ。パスがあるのに引き止める必要もないだろう?」
50パイサー席!
4人ともテントの中を見たのは初めてだった。最前列には椅子やベンチの席が並んでいた。幕には「ラーム王子の亡命」の絵が描いてあった。パラトダースはそれに気が付いた。彼は手を合わせて、幕に描かれたラーム王子、スィーター姫、ラクシュマン王子らにナマスカール(挨拶)した。「万歳!万歳!」パラトダースの目に涙が溢れた。
ヒラーマンは言った。「ラールモーハル、幕の絵は立ち止まってんのかな、それとも歩いてんのかな。」(幕が風で揺れていたため、絵の中のラームたちが歩いているように見えたようだ)
ラールモーハルは近くに座っていた観客に知り合いを見つけた。彼は言った。「劇は幕の裏でやるんだよ。今はただ音を鳴らしてるだけさ、観客を退屈させないようにな。」
太鼓の心得があったパラトダースは、太鼓の音を聞いて首を揺らしながら、マッチ箱を打ち鳴らしていた。ヒラーマンも周囲の観客とビーリー(巻きタバコ)を分け合いながら、2、3の友人を作った。ラールモーハルの知り合いの男は、毛布にくるまりながら言った。「劇が始まるまでまだ時間があるから、それまでちょいと一眠りするとしよう。・・・50パイサー席は最高だな。一番後ろの一番高い場所、地面には温かい藁が敷いてある!ヘッヘッヘ、この寒い中、椅子やベンチの席の奴らは可哀想に。今に寒さに耐えかねてチャーイを飲みに席を立つだろうよ!」
その男は自分の仲間に言った。「劇が始まったら起こしてくんな。い〜や、劇が始まったらじゃねぇ、ヒーラーちゃんが舞台に現れたらオレを起こしておくんな。」
ヒラーマンは少しカチンと来た。・・・どうも無礼な男のようだ。ヒラーマンはラールモーハルに目配せしながら言った。「こいつとは話さなくていいさ。」
ダン、ダン、ダン、ダーン!幕が上がった。ピューピュー!ヒーラーバーイーがいきなり舞台に現れた!テントの中は騒然となった。ヒラーマンの顔は一気に明るくなった。ラールモーハルはなぜか笑みが止まらなかった。ヒーラーバーイーの歌の一小節一小節に彼は理由もなく嬉しくなってしまった。
グルバダン(ヒロインの名=ヒーラーバーイー)は宮廷で座って告知をしている――タクトハザーラー(マリーゴールドの花の玉座)を作って持って来た者は、思いのままに褒美を取らそう!・・・もしそのような芸術家がいるならば、準備をしなさい、タクトハザーラーを持って来なさい!キルキルキル・・・!素晴らしい踊りだ!歌声もすごい!知ってるか、噂だとヒーラーバーイーはパーン(噛みタバコ)も食べないし、ビーリーやタバコも吸わないらしいぜ。・・・噂は本当だったな。かなり名の知れた娼婦だってな。・・・誰だ、娼婦なんて言う奴は!ミィッスィー(歯を着色する化粧品)は使ってないって話だ。パウダーで歯を磨いてるに違いない。・・・誰だ、変なこと言う奴は!劇団の女を娼婦だって言ったのはどいつだ!おめぇが何で怒るんだよ?ポン引きはどいつだ?この野郎!畜生!貴様・・・
騒ぎの中、ヒラーマンの声がテント中に響き渡った。「やい、コラ、一人一人首をちょん切ってやるぞ!」
ラールモーハルは革ひもで前に座っていた観客を殴っていた。パラトダースは一人の男に馬乗りになっていた。「この野郎、スィーター姫の悪口を言いやがって、さてはイスラーム教徒だな?」
ドゥンニーラームは初めから黙っていた。暴動が起こるや否や、テントから外へ逃げ出した。
黒コートの劇団マネージャーがネパール人門番と共に走ってやって来た。警部が警棒を振り回しだした。警棒で叩かれると、ラールモーハルの目から火が飛び出た。彼は標準語で演説を始めた。「警部の旦那、殴るのなら殴って下さい。何の文句もございません。しかしその前にこれを見て下さい、パスです、もう1枚ポケットにあります。分かりますか、旦那?チケットじゃありません、パスです!・・・私たちの目の前で劇団の女性の悪口を言う奴がいたら、どうしてそのまま野放しにすることができましょうか!」
劇団のマネージャーは全てを理解した。彼は警部をなだめて言った。「旦那、分かりました。この騒動はマトゥラーモーハン劇団の奴らの差し金です。劇の最中にケンカを始めて、劇団の名に泥を塗ろうとしたんです・・・旦那、彼らを放してやって下さい。ヒーラーバーイーの知り合いなんです。彼女の命は、可哀想に、危険にさらされているんです。前にも申しましたよね!」
ヒーラーバーイーの名前を聞いて、警部は3人を放した。しかし3人から革ひもを取り上げた。マネージャーは3人を、1ルピー席の椅子に座らせた。「あなたたちはここに座って下さい。今、パーンを持って来させます。」テントは静かになり、ヒーラーバーイーは舞台に戻って来た。
太鼓が再び鳴り出した。
すると、3人は同時にドゥンニーラームがいないことに気付いた――あれっ、ドゥンニーラームはどこ行った?
「ご主人様、ねぇ、ご主人様!」レヘサンワーンがテントの外から呼んでいた。「ねぇ、ラールモーハル様!」
ラールモーハルは大声で返事をした。「こっちから、こっちから!1ルピー席の入り口から!」観客は皆、ラールモーハルの方を見た。ネパール人門番が、レヘサンワーンをラールモーハルのところへ連れて来た。ラールモーハルはポケットからパスを出して見せた。レヘサンワーンはやって来るや否や聞いた。「ご主人様、オレのこと忘れちゃったんですか?ずっと待ってたんですよ。ヒーラーバーイーの顔だけでもどうか、一目だけ!」
人々はレヘサンワーンの開いた平たい胸元を見た。こんな真冬にこんな薄着!・・・こんな薄汚ない小僧も一緒なのか、この連中は!
ラールモーハルはレヘサンワーンを黙らせた。
・・・この牛車乗りたちに劇で何を見たのか聞いても無駄だ!彼らが話を理解できようか!ヒラーマンは、ヒーラーバーイーが最初から彼の方を見つめながら歌い踊っているように感じていた。ラールモーハルはラールモーハルで、ヒーラーバーイーが彼の方を見ているように感じていた。彼女もやっと理解しただろう、ラールモーハルはヒラーマンよりも偉い男だって!パラトダースだけは物語を理解していた。・・・物語と言っても、彼が知っているのは「ラーマーヤン」だけだ。ラーム王子、ラクシュマン王子、そして羅刹ラーヴァン!スィーター姫をさらうため、ラーヴァンはいろんな姿に変身してやって来るのだ。ラームとスィーターも姿を変える。ここでも、タクトハザーラーを作る庭師の息子の名前はラームだ。グルバダンはスィーター姫だ。庭師の息子の友達はラクシュマンで、スルターン(皇帝)はラーヴァン・・・。ドゥンニーラームは高熱が出ていた!レヘサンワーンはジョーカー役が一番気に入った・・・小鳥よ、お前を連れて、ナルハトの市場へ行こう!彼はあのジョーカーと仲良くなりたかった。・・・友達になってくれませんか、ジョーカーの旦那!
ヒラーマンはある歌の一節が心に残った――殺されてしまったグルファーム!グルファームとは誰のことだろう!ヒーラーバーイーは泣きながら歌っていた。「ああ、殺されてしまったグルファーム!」ティリリリ・・・可哀想なグルファーム!
警部は、3人に革ひもを返しながら言った。「革ひもを持って踊りを見に来てるのか?」
次の日、祭りはこの噂で持ちきりだった――ヒーラーバーイーはマトゥラーモーハン劇団から逃げ出して来た、だから今回はマトゥラーモーハン劇団は祭りに来なかったんだ。・・・だが、マトゥラーモーハン劇団の暴徒がやって来た。・・・ヒーラーバーイーも負けちゃいない。肝っ玉の座った女だ。村人を自分の護衛に付けてたんだ。・・・全く天晴れな女だよ!大した勇気だ!
10日間祭りは続いた・・・
ヒラーマンは1日中積荷を運んでいた。夕方になると劇団の太鼓が鳴り始めた。太鼓の音を聞くと、ヒーラーバーイーの声が耳のそばで飛び回った――バイヤー・・・ミーター・・・ヒラーマン・・・ウスタード・・・グルジー!1日中、何か得体の知れない音が彼の心の耳で鳴り響いていた。あるときはハルモニウムの音、あるときは太鼓、あるときはヒーラーバーイーのパイジニー(鈴付きの足首飾り)!それらの楽器の演奏に伴って、ヒラーマンは立ち上がったり座ったり、歩いたり止まったりしていた。劇団のマネージャーから幕係りまで、彼のことを知っていた。・・・彼はヒーラーバーイーの護衛だ!
パラトダースは毎晩劇が始まると、恭しい仕草で両手を合わせて舞台にナマスカールをしていた。ラールモーハルは、ある日自慢の標準語をヒーラーバーイーに聞かせに行った。だが、ヒーラーバーイーは彼が誰だか分からなかった。その日から彼は自信を失ってしまった。彼の部下だったレヘサンワーンは彼の下で働くのを辞めて、劇団に入団した。ジョーカーと友達になったのだ。一日中、水を汲みに行ったり、服を洗ったりしていた。村に何の未練があるもんか!ラールモーハルは落ち込んでいた。ドゥンニーラームは病気になって家に帰ってしまった。
ヒラーマンは、今日3回も積荷を積んで駅に来ていた。なぜか今日は兄嫁のことが頭に浮かんでいた。・・・ドゥンニーラームは口を滑らせてないだろうか、熱にうなされて!ここにいたときからブツブツうわ言を言ってたな――グルバダン、タクトハザーラー!・・・レヘサンワーンはいい暮らししてるみてぇだ。毎日ヒーラーバーイーを見てることだろう。昨日言ってたな、ヒラーマン兄貴、あんたのおかげでオレはウハウハさ。ヒーラーバーイーのサーリーを洗った水は、まるでバラの香水みたくなるんだ。その中に自分のタオルを浸しておくんだ。なぁ、これ嗅いでみなよ?・・・ヒラーマンは毎晩誰かがヒーラーバーイーのことを娼婦だの売春婦だの言うのを聞いた。何人とケンカをしたことだろう!何も知らずに人々はあれこれ知った口を叩くものだ!王様のことでさえ、人々はこそこそ悪口を言っている!・・・今日こそヒーラーバーイーに会って言おう、劇団にいると人々の悪評の的になってしまう。サーカス団になんで行かないんだ?・・・みんなの前で踊る彼女を見ると、ヒラーマンの心は不安になった。サーカス団には虎がいる・・・誰も虎に近づこうとしないだろう!だからヒーラーバーイーは安全だ!ん、こっちに来るのはどの車だ?
「ヒラーマン、おい、ヒラーマン兄貴!」ラールモーハルの声を聞いて、ヒラーマンは振り返った。「何積んで来たんだ、ラールモーハル?」
「ヒーラーバーイーがお前を待ってるぜ、駅で。どっかへ行っちまうってよ。」一息で彼はまくし立てた。彼女はラールモーハルの車で駅まで来たのだった。
「どっかへ行く?どこへ?ヒーラーバーイーは列車で行くってのか?」
ヒラーマンは牛からくびきを外し、倉庫の門番に言った。「バイヤー(兄ちゃん)、ちょっと車と牛を見ててくれ。すぐ来るからよ。」
「ウスタード!」ヒーラーバーイーは女性用待合室の入り口の近くで、ショールで顔を隠しながら立っていた。預かっていたヒラーマンの袋を差し出しながら言った。「これを!ああ、神様!あなたに会うことができてよかった、もう諦めかけてたのよ。もうあなたに会えないかと思ってた。・・・私、もう行っちゃうの、グルジー!」
箱を積み込んだ男は、今日はコートとパンタロンを着て紳士風になっていた。ご主人様っぽく、ポーターたちに命令を出していた。「女性席に載せるんだ、いいな?」
ヒラーマンは袋を受け取って黙って立ち尽くしていた。ヒーラーバーイーは上着の内側から袋を取り出して彼に渡した。・・・袋は小鳥の身体のように温かかった。
「もうすぐ列車が来るぞ。」箱を積んだ男が顔をしかめてヒーラーバーイーの方を見た。彼の表情は語っていた――大きな袋だ、何が入ってるんだ?
ヒーラーバーイーは焦って言った。「ヒラーマン、ちょっと来て、中に。私、またマトゥラーモーハン劇団に戻るの。自分の故郷の劇団よ・・・バナイリー村の祭りに来てくれるでしょ?」
ヒーラーバーイーはヒラーマンの肩に手を載せた・・・今度は右肩に。そして自分の袋からお金を取り出して言った。「これで、あったかいショールでも買って・・・」
ずっと黙っていたヒラーマンはやっと口を利くことができた。「ちっ!いつもいつも金のことばっか!・・・ショール買ってどうしろってんだい?」
ヒーラーバーイーは手を止めた。彼女はヒラーマンの顔をじっと見つめて言った。「あなた、怒ってるの?どうして、ミーター?・・・渡し守の娘のマフアーを商人が買い取ったのよ、グルジー!」
ヒーラーバーイーは声を詰まらせた。箱を積んだ男は外から呼びかけた。「列車が来たぞ。」ヒラーマンは部屋から外に出た。箱を積んだ男は舞台劇のジョーカーのように顔をしかめて言った。「プラットフォームから出て行け。チケットなしで捕まったら、3ヶ月の禁固刑だぞ・・・」
ヒラーマンは黙って外に出て立った。・・・ここは駅だし、列車の縄張りだ!そうでなかったら、ヒラーマンは箱を積んだ男をこてんぱんにしていたところだ。
ヒーラーバーイーは目の前の車両の中へ乗り込んで行った。へんっ!あんな顔しやがって!列車の中に座っても、彼女はヒラーマンの方を見つめていた、じっと・・・。ラールモーハルはそれを見て嫉妬していた。いつもオレが脇役なのはどうしてだ・・・!
列車は汽笛を鳴らした。ヒラーマンは、自分の中から何かの音が汽笛と一緒に抜け出て天へ昇っていくかのように感じた。ク〜ウ〜ウ〜イッシュ!
・・・チィ〜イ〜イ〜イック!列車が揺れた。ヒラーマンは右足の親指を左足のかかとにぶつけた。心臓の鼓動は正常に戻っていた。・・・ヒーラーバーイーは手に持った紫色のハンカチで涙を拭っていた。ハンカチを振って彼女は合図した・・・もう行って。・・・遂に列車は行ってしまった。プラットフォームには何も残っていなかった・・・何も・・・倉庫は空になっていた!まるで世界が空になってしまったかのようだった!ヒラーマンは自分の車のところまで戻った。
ヒラーマンはラールモーハルに聞いた。「オレはもう村に帰るよ。お前、いつ頃村に戻るつもりだ?」
ラールモーハルは言った。「今、村に帰ってどうするんだ?今こそ金の稼ぎどきじゃねぇか!ヒーラーバーイーは行っちまった、祭りももうすぐ終わるだろう。」
「そうか。家に何か言伝でもあるかい?」
ラールモーハルはヒラーマンを説得しようとしたが、その甲斐なくヒラーマンは自分の車を村に続く道に向けた。・・・もう祭りに何があろうか!空っぽの祭り!
列車の線路のそばを、牛車のガタガタ道がずっと続いていた。ヒラーマンは一度も列車に乗ったことがなかった。彼の心には、昔から抱いていた願望が浮かんで来た。彼は、いつか列車に乗って、歌を歌いながらジャガンナート寺院まで行けたらと考えていた。・・・彼には、振り返って空っぽの幌を見る勇気がなかった。今日も背中がムズムズしていた。今日もチャンパー花が彼の車の中で花開いていた。何度も何度も同じ歌の一節と太鼓の音が聞こえてきた・・・!
彼は思い切って振り返った。積荷もない、竹もない、虎もいない・・・妖精・・・女神・・・ミーター・・・ヒーラーデーヴィー・・・渡し守の娘マフアー・・・誰もいない。葬式のときのような嗚咽が漏れそうになった。ヒラーマンの唇は震えていた。おそらく彼は3つ目の誓いを立てているのだろう・・・劇団の女なんて二度と乗せるもんか・・・
ヒラーマンは突然2匹の牛を革ひもで打って言った。「なに線路の方を見てやがるんだ?」2匹の牛は駆け足になった。ヒラーマンは口ずさんだ。「ああ、殺されてしまったグルファーム・・・」
−完−
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |


