 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 印度文学館 印度文学館 
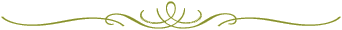

Mahadevi Varma
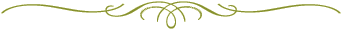
|
|
20世紀初頭の女流文学者マハーデーヴィー・ヴァルマーの代表作「レーカーチットラ」から「ビンダー」を日本語に翻訳。 |
|
ビンダーは私の幼年期の友達だった。その頃私は生と死の区別すらついていなかった。祖父と祖母の死去の報を聞いて、私は真剣な顔で無邪気に家族にこう話したことがあった。「私の頭がタンスの上まで届いたら、一度おじいちゃん、おばあちゃんに会いに行って来るわ。」私のこの無垢な決意に反対する人はおらず、そのとき私は、一度死んだら二度と戻って来れないという事実を知るに至らなかった。このように無邪気だった私に、幼い子供を後に残して死んでしまう母親がいるということを理解する力があるわけがなかった。私の経験も非常に限られていた。私の仲間だった白い雌犬が、階段の下の暗い部屋の中で、まだ目が開いていない仔犬たちを、異常なほどまでの警戒心と共に守っているのを私は見た。その犬の唸り声は、私との長年の深い友情に水を差すほどのものだった。茶色の猫も、ネズミのような自分の子供たちを、鋭い歯でもって、しかし噛んでしまわないような優しさと共に持ち上げ、あちこちへ連れて行っていた。屋上の隅にあった鳩の巣や、大きな額縁の後ろにあったスズメの巣の中で、小さな小さな何かの部品や、注意深く集められた穀物や虫たちを何度も目にしていた。仔牛を遠ざけると、モ〜と鳴いて家中にこの知らせを知らせるシュヤーマーという名の牝牛の心の不安は、私にも理解できた。子供を肩に乗せ、1本の指を掴んでドアからドアへ廻る女乞食は、子供のためだけに乞食をしていた。つまり、私は世界の全ての仕事は、子供たちに食べ物を食べさせ、飲み物を飲ませ、寝かせたりするためにあるのであり、その重要な仕事は、「母親」という名の生き物に与えられた忘れることのできない仕事であることを、はっきりと理解していた。
そしてビンダーにも母親はいた。彼女を私たちは「パンディターインおばさん」と呼び、ビンダーは「ナイー・アンマー(新しいお母さん)」と呼んでいた。彼女は自分の白く太った身体をカラフルなサーリーで着飾り、チャールパーイー(インド式ベッド)の上に座って、膨らんだ頬とつぶれた鼻の両側にあるガラスのボタンのように輝いている目で、四六時中モーハンにオイル・マッサージをしていたのだった。特に彼女の、髪の分け目にベットリとインクのように塗られたスィンドゥール、眠たそうな目に黒い糸のように塗られたカージャル、輝きを放つ耳飾り、首飾り、色とりどりのチューリヤー(バングル)やグングルー(アンクレット)、その全てが私はとても気に入っていた。なぜならそれらの装飾は私の持っていた人形とそっくりだったからである。
これらはよかったのだが、彼女の振る舞いはおかしなところがあった。冬に私は日が昇ってから起こされ、お湯で手と顔を洗った後はストッキング、靴そしてウールの衣服を着せられ、無理矢理温かいミルクを飲まされていた。ところが隣の家では、パンディターインおばさんの大声が常に響き渡っていた。もしその大声の意味が分からなかったら、私はそれをシュヤーマーの鳴き声と同じく愛情の表現だと理解していただろう、しかしその言葉の意味が分かってしまっていたことから、不安な気持ちにならざるをえなかった。「起きるのかい、それとも私がひっぱたきに行こうかい?」「あんたは牛よりも怠け者だよ」「モーハンのミルクはいつできるんだい?」「あの不幸者は死にもしないね」など、言葉の隅々まで、幼い私にも分かるほどの暴力性で溢れていた。
時々私は屋上へ上って、隣の家で起こっていることを理解することに努めていた。そのとき私には汚ないドーティー(インドの衣服)を着たビンディーが、庭から台所までコマのように踊り廻っているのが見えた。時に掃き掃除、時に火起こし、時に庭の用水路から水を汲み、時にナイー・アンマーにミルクを渡しに行き、私はまるで手品ショーを見ているようだった。なぜなら私にはそれら全ての仕事が不可能だったからだ。しかし、その驚くべき早業を全く無視したパンディターインおばさんの恫喝声が上がったとき、そしてその恫喝声には時々パンディトジー(パンディターインおばさんの夫)の怒声も混じることがあったのだが、そのとき私はなぜか悲しい気分でいっぱいになるのだった。私はビンダーの行儀のよさを例に出されて、自分の悪戯ぶりを叱られることが多かったのだが、当のビンダーはいったい家でどんな悪さを密かにしているのか、彼女をおだてて聞きただしても全く理解することができなかった。私は何も家の仕事を手伝わず、朝から晩まで遊びまわっていたが、私の母親は私に「死ね」と言ったり、目をむいて脅したりするようなことはしなかった。一度私はこんなことを尋ねたことがある。「パンディターインおばさんはお母さんみたいじゃないの?」母親に私の質問の意味がどれだけ理解できただろうか、私には分からない。彼女の「そうね」という答えによってビンダーの問題は解決できず、私の不安も解消されなかった。
ビンダーは私よりも若干年上だったが、彼女はまるで誰かが上から抑え付けて縮めてしまったかのように背が低かった。彼女は2パイサーのカジュリー(弦楽器)の上に張られた皮のように薄い皮をしていたので、皮の下を流れる青い血管を彼女の痩せた手や足に見ることができ、私は知らず知らずの内に怖くなるのだった。どこかから物音がすると彼女は異常なまでに敏感に反応し、パンディターインおばさんの声が聞こえて来るや否や、彼女の全身は震えだすのだった。それを見て私は驚きというよりも恐怖を覚えた。そのときのビンダーの目は、まるでカゴに閉じ込められた小鳥のようだった。
あるとき彼女はひとつひとつ星を数えながら、ひとつのある明るい星を指差して言った。「あれが私のアンマー(ママ)よ」そのとき私は驚きの感情すら起こらなかった。いったい1人のアンマーは星にいて、もう1人は家にいるものなのだろうか?質問するとビンダーは自分の知識の中から少しだけ私に教えてくれた。そのとき私は、神様が呼んだアンマーは星になって空の子供たちの世話をして、豪勢に着飾って家に来るアンマーはビンダーのナイー・アンマーのようであることを理解した。私の理解力はすぐにそれを受け容れることができなかったため、私はよく考えてから言った。「ナイー・アンマーをプラーニー・アンマー(古いお母さん)と呼べばいいと思うわ、そうすればもう新しくないから、あなたを叱ることもないでしょう。」
ビンダーは私が考えた解決法を聞いて喜ぶようなことはなかった。なぜなら彼女はプラーニー・アンマーが屋根のないパールキー(つまり死体を運ぶ担架)に横たわって家を出て行くのと、ナイー・アンマーが閉ざされたパールキー(担いかご、輿)に乗ってやって来るのを見ていたからだ。誰にもそれを入れ替えるのは困難だった。しかし彼女の講義で私の心は本当に不安になってしまい、その夜私は母親に真剣に言った。「お母さん、絶対に星にならないでね、たとえ神様がどんなにきれいな星にしてくれても。」母親は私のおかしなお願いに驚いて、何も言うことができなかった。私は一生懸命自分の言いたいことを説明した。「そうじゃなかったら、パンディターインおばさんのようなナイー・アンマーがパールキーに乗ってやって来ちゃうわ。そして私のミルク、ビスケット、ジャレービー(ミターイーの一種)、みんな食べられなくなっちゃうわ。そして私はビンダーになっちゃうわ。」母親がなんと答えたのか、私は覚えていない。しかしその夜、母親のドーティーの裾を握りしめながら眠ったことだけはよく覚えている。
ビンダーがどんな悪戯をしているのか、私には分からなかったが、パンディターインおばさんの裁判所で下される刑罰の全てを私は知っていた。夏の日中に、私はビンダーが庭の灼熱の土壌の上で、何度も何度も足を上げたり下げたりしながら何時間も立っているのを見たし、台所の柱に1日中縛り付けられているのも見た。彼女は自身の失敗だけでなく、無実の罪でのお仕置きも受けなければならなかった。パンディトジーのターリー(皿)の中に、パンディターインおばさんの黒くて太い、巻き毛の髪の毛が入っていたことがあったが、そのときも罰せられたのはビンダーだった。彼女の小さな手では到底洗うこともできない、ボサボサの油の少ないビンダーの髪の毛を私は気に入っていた。私の髪の毛は生まれたときから茶色で柔らかかったからだ。パンディターインおばさんのハサミが彼女の髪をゴミの山にし、まるで猫の縞模様のような髪型にしてしまったとき、私には涙が溢れてきたほどだ。しかしビンダーは、その髪の毛があたかもナイー・アンマーのものであるかのように静かに座っていた。
またある日、ビンダーはチュールハー(コンロ)でミルクを熱していたことがあった。そのときミルクが吹きこぼれそうになったので、ビンダーは小さな手で鍋を掴んだ。と、その瞬間、ビンダーの指から鍋は離れ、彼女の足の上に落ちてしまった。沸騰したミルクで足に火傷をしたビンダーが、扉のところで立って泣いているのを見て、私は驚いてしまった。どうしてパンディターインおばさんに薬を塗ってもらわないのだろう、私には全く理解ができなかった。ビンダーが私の手を自分の激しく動悸する心臓に当てて、どこかへ隠れないといけないと言い出したとき、私には全く訳が分からなかった。
私は彼女を自分の家へ引っ張って来たものの、上の階にいる母親のところへ連れて行くわけにもいかず、隠れる場所を見つけることもできなかった。壁の向こうからパンディターインおばさんの怒声が聞こえてきたとき、私たちは恐怖で立ちすくんでしまった。私たちは焦りに焦って牛のための飼料が貯蔵されていた倉庫へ転がり込んだ。草の先がチクチクして痛かったし、倉庫の暗闇が一層私を不安にさせていたが、ビンダーは火傷した足を草の中に隠して、冷たい両手で私の両手を握って、まるでチクチク突き刺さる草の山がシルクのベッドになったかのように座っていた。
私は多分眠ってしまったのだろう、飼料を運び出すためにやって来た牛飼いが、奇妙な光景を伝えるため大声を上げたとき、私は目をこすりながら質問した。「朝になったの?」
母親がビンダーの足にゴマ油とライム汁を塗って、言伝を託した使用人と共に彼女を家に帰した後、彼女に何が起こったかは知る由もない。しかしパンディターインおぼさんの審判に容赦も慈悲もなかったことだけは確かである。
その後しばらくの間、私はビンダーが家や庭で働いている姿を見なかった。母親は私に彼女の家に行くのを禁止した。しかし母親はたびたびブドウとリンゴを持ってそこへ通っていた。なんとかしてルキヤー(使用人の名)から聞き出したが、彼女は「隣の家に女王様が来たんです」としか教えてくれなかった。もうビンダーは私に会えないのだろうか?そう質問するとルキヤーは口を布で覆って笑いをこらえるのだった。どうにも我慢できなくなったある日の昼、私は誰にも見つからないようにビンダーの家にこっそり入った。1階はひっそりと静まり返っており、ビンダーが1人でチャールパーイー(ベッド)に横たわっていた。両目は窪んでいた。何が起こったのか、顔は吹き出物だらけになっており、汚ない布団に包まれた身体はベッドの一部となってしまったかのようだった。医者、薬の瓶、頭に手を乗せる母親、そしてベッドの周りをグルグル廻る父親がないにも関わらず、病気だけは存在していた。これは私には全く理解できないことだった。だから私は1人で寝ているビンダーの傍に立って、驚いて四方を見回していたのだった。ビンダーは指差しながら、かすれた声と共に私に言った。「ナイー・アンマーはモーハンと上の階にいるわ、多分天然痘を避けるために。」朝晩、バラウニー(新しく来たメイド)がビンダーの代わりに仕事をしていた。
ある日の朝、ルキヤーが母親に何かを言うと、母親はラーマーヤンを閉じて何度も目を拭いながらビンダーの家へ行った。行くときに母親は私に外に出ないよう命令するのを忘れなかった。だから私は家のあちこちから隣の家を覗き込まなくてはならなくなった。ルキヤーは私にとって物知り博士的存在だった。しかし彼女はよっぽど頼み込まないと何も教えてくれなかった。ルキヤーに懇願することは私の自尊心が許さなかった。窓から覗き込んだだけでは、ビンダーの家の玄関に集まった人々の他は何も見ることができなかった。そしてこのような人込みは結婚式ぐらいしか私には考えられなかった。隣の家で結婚式が行われているのだろうか、そうだとしたらいったい誰の?神様は私の知恵を試し始めた。パンディトジーの結婚式は2番目のパンディターインおばさんが死んで星になったときに行われるだろう、かと言ってまだ座ることもできないモーハンの結婚式は不可能だ、そう考えた私は、遂にビンダーの結婚式が行われているという結論に達した。そして彼女が私を結婚式に呼ばなかったことにすっかりすねてしまい、私は人形を証人に立てて、ビンダーをもう絶対に祝いの席に招待しないことに決めたのだった。
数日間私はビンダーの家を覗き込んでいたが、ある日母親に彼女がいつサスラール(夫の家)から帰って来るか聞いた。そのとき私は、彼女が空に住む母親のところへ行ってしまったことを知った。その日から私はよく夜空の明るい星を取り囲む小さな小さな星の中から、ビンダーを探していた。しかし遠すぎてどれがビンダーなのかを見極めることはできなかった。
そのときからどれだけの時間が過ぎ去ったことだろう、だがビンダーと彼女のナイー・アンマーの話は終わっていない。いつか終わるのだろうか、誰も答えることはできない。
|
|
|
|
|
|
−完−
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |

