|
|
8月後半から少しずつ家具を買い揃え、部屋の模様替えをしていた。現在洋服が散乱している状態なので、それを収納する棚か引き出しを買えば完了する。一昨日、昨日とそのミッションを完遂しようと南デリー中を駆けずり回ったが、僕の求めるものは見つからなかった。おそらくデリーの学生の部屋に必ずある、タケヒゴ細工の安い棚を買うと思う。
机と椅子を買ったことにより、勉強が格段にしやすくなった。しやすくなったとは言え、別に勉強はそれほどしていないが。代わりにパソコンに向かう時間が増えた。やはり床に座って低い机で何かをするよりは、椅子に座って勉強机の上で勉強なりパソコンなりした方が遥かに能率がよい。去年1年間は何となく時間と労力を無駄にしたような気分になった。床に座って勉強をすると、立ち上がるのが億劫になる。立ち上がるのが億劫になると、すぐに寝転んでそのまま眠ってしまう。また、その席の周りに必要な物を並べるようになる。そうすると部屋が散らかったままになる。片付けると返って非効率的になってしまう状態だ。だから掃除をしないということが正当化される。さらに汚なくなる・・・という悪循環を去年は辿っていたように思える。それに椅子に座った方が疲れが少ない。本当に机と椅子は買ってよかったと思っている。こればっかりは西洋の発明に軍配が上がると思う。
部屋の模様替えと平行してるのかどうか自分でもよく分からないが、このウェブサイトの模様替えも行った。日曜日に集中的に行ったが、今日は仕上げとして、上のイスラーム建築風の飾りを、凝り性な性格を存分に発揮して装飾した。参考にしたのは、タージ・マハルのメイン・ゲートだ。タージ・マハルの美しさは改めて述べるまでもないが、その門の美しさもかなりのものだと思う。僕が最初にタージ・マハルを見に行ったときは、まず門を見て感動して、中に入らずに早速その門のスケッチを始めたものだった。そのスケッチを1時間ほどで終わらせて中に入ったが、やはりタージ・マハル本体の美しさにも息を呑み、再びスケッチをした。それでも足りずに、次の日もまたタージ・マハルを訪れ、さらにスケッチをした。あのときはタージ・マハルの入場料に外国人料金がなかったので、とても気軽に入れた覚えがある。世界遺産に気軽に入ってくつろげる雰囲気が、いかにもインドっぽくて好きだったのだが・・・。今は昔の物語だ。
それにしても、ますますこのサイトがイスラーム色を帯びてしまった。別に僕はムスリムが嫌いなわけではない。インドにはまる前はもともとアラビア方面に興味があったので、イスラームにも思い入れがある。だが、なんとなくインドというとヒンドゥーが強い国なので、ヒンドゥー色を強くしたいという欲求がどこかにある。左側にあるミナレットなんか、いかにもアザーンが流れてきそうだ。このデザインそのものは、自分で言うのもなんだが、かなり「してやったり」と思っている。だが、心の中で何か引っ掛かるものがある。元のデザインに戻すことはないと思うが、ヒンドゥー側の反撃を現在頭の中で考えている最中だ。そんな細かいことにこだわっているのは僕だけかもしれないが。
今日は授業がなく、午後5時から学校に来なさい、と言われた。何が行われるか全く知らされないままの突然の通達だったので、生徒たちは大いに混乱していた。金曜日にそれを言われたのだが、月曜日のことだと勘違いして、昨日午後5時から来た人もいれば、すっかり忘れてて今日の朝に学校へ来てしまった人もいた。
昼頃、ユスフ・サラーイを歩いていたら、そこの寺院の周りにブラスバンド隊が大集合しており、演奏を行っていた。垂れ幕に「クリシュナの何たらかんたら」と書いてあったので、今日はまた何かの祭りなのか、と思った。おそらく今日の学校のイベントも、それと関係あるのだろうと思いつつ通り過ぎた。
午後5時頃学校へ行ってみると、ホールにはきれいに椅子が並べられ、正面の長机の上には花瓶まで置かれて、かなり気合の入った準備がなされていた。隅にはサラスヴァティーの絵が飾られていた。忙しく立ち回っている先生に「今日はクリシュナのプージャーですか?サラスヴァティーのプージャーですか?」と聞いてみたら、「一番最初にガネーシャのプージャーが行われるのよ」と言われた。ますます頭の中がクエスチョン・マークでいっぱいになった。
次第に人が入ってきた。サンスターンで学んでいる外国人の学生はあまり多くなく、代わりにインド人がたくさんやって来た。隣に座ったインド人に話を聞いてみて、やっと今日が何なのか合点が行った。僕たち外国人学生は10時半〜3時10分まで授業があるが、その後、5時〜7時半まで、主にインド人を対象に別のクラスが開講されるらしい。ジャーナリズムや翻訳のクラスがあるそうだ。その夕方クラスが今日から始まるらしく、その始業式が行われていたのだった。つまり僕たちは出席する必要なんて全然なかったのだ。しまった、騙された・・・。
始業式にはけっこう偉そうな人たちがやって来た。確かに一番最初にガネーシャのプージャーが行われた。そしてひとりずつ長々とスピーチが始まった。その内容はヒンディー語の地位向上、またはヒンディー語の素晴らしさを讃えるような、非常に狂信的なもので、「インドの公用語はヒンディー語であり、英語ではない」「全てのインド人がヒンディー語を話せるようになるべきだ」「ヒンディー語はスリナム、モーリシャス、フィジーに至るまで使われている、国際的で偉大な言語だ」「ヒンディー語はもっとも合理的で科学的な言語だ」「中国語が世界で最も話者人口の多い言語とされているが、実際には中国語にも多くの方言があり、それは正しくはない。ヒンディー語の方が多くの人々に話されている」などと延々と述べられていた。
年配のサンスターンの教師には、ヒンディー語を国語とする理想に燃えていたような人々が多い。インド独立後、ヒンディー語が国語としての地位を確立すべく、かなり集中的に研究、辞書編纂、普及活動などが行われたらしい。しかし1960年代末あたりから次第に英語や地方言語も法律上の地位を確保してきて、おかげでヒンディー語は絶対的な国語ではなく、相対的な第一公用語としての立場に転落してしまった。そんな状態にあった1970年代、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンはインド各地に次々と設立されているので、まだ当時はヒンディー語をインド中に普及させようという理想があったのだろう。だが、どうも1990年代に入ってからインド政府も当時ほどヒンディー語普及に力を入れなくなってしまったようだ。ところが、2000年代に入り、ヒンドゥー教至上主義が政府に浸透しつつあるので、ヒンディー語もヒンドゥー教と結びつき、再び力が入れられ始めたような印象を受ける。サンスターンが新しい校舎に移転できたのも、それと無関係ではないように思われる。今回の移転には、政府からかなり莫大な予算がつぎこまれているそうだ。
サンスクリト語起源の言葉を交えつつ、延々と長話が繰り返されたので、非常に退屈してしまった。4、5人の人が話を終えたときには既に7時半頃だった。最後にミターイーと軽食が出たので、それを食べて帰った。納得のいかない1日だった。
いつの間にか気付くとデリー市民たちの間に携帯電話が爆発的に普及していた。使用人レベルの人まで携帯電話を持っており、まさに猫も杓子も携帯電話という状態だ。インド人というと、「映画評論家?」というくらいみんな映画に詳しいことはよく知られているが、最近はそれに加えてみんなやたらと携帯電話に詳しくなった。お互いに携帯電話を見せ合って自慢したり、値段を聞きあったり、新機種の噂をしてみたり、と皆にわかに携帯電話評論家になってしまったかのようだ。
携帯電話が普及した要因は、携帯電話本体の値段の下落と、通話料の下落、それに家庭用電話に比べてすぐに使用可能という便利さなどだと思われる。現在中古品だったら1000ルピーぐらいから手に入るようになっており、通話料もかなり安くなった。インドの携帯電話というと、かけた方だけでなく、かかってきた方にも課金されるということで、日本の携帯電話とは少し使い勝手が違ったのだが、最近同社間の通話だったら、受け側は課金されなくなった。その内受け側の課金は廃止されるのではなかろうか。
もちろんデリー在住の日本人も、ほぼ全員携帯電話を持つようになってきている。駐在員はもともと必ず持っていたが、学生にとってもいつの間にか携帯電話は生活必需品の地位を確立してしまったようだ。気付いてみたら、持っていないのは僕だけという状態になって来た。
今まで僕は自宅で常時接続のインターネットができるということで、かなりの優位に立っていた。インドにおいて自宅でインターネットができ、しかも時間を気にしなくていい、というのは、1年前の日本人社会では、駐在員もビックリの環境だった。ところが1年経ってみたらどうだ。周囲を見渡せば、僕と同じような環境でインターネットをしている人が増え、僕の優位性は揺らいでしまった。逆に携帯電話を持っていないことから、「アナログな人間」というレッテルを貼られてしまいそうだ。インドで自宅インターネットをしているようなマニアックな人間がアナログなはずないだろ!との反論もしたくなるが、だんだん他の人とコミュニケーションをとるのが困難になって来たのは事実だ。
という訳で、ついに携帯電話を買うことを決心した。
まずは下調べということで、デリー最大の携帯電話市場があるカロール・バーグへ出掛けてみた。デリーに携帯電話が登場したとき、一番最初に売り出されたのがこの市場だったらしい。現在ではデリーのどこでも携帯電話を買うことができるようになったが、古くからの携帯電話ユーザーは依然としてカロール・バーグに携帯電話を買いに出掛けるようだ。
カロール・バーグでは中古から新品まで、多くの携帯電話が軒先に並べられていた。また、携帯電話グッズも豊富で、修理も承っている。まさに市場全体が携帯電話のためにあるようなものだった。店はスィク教徒が経営していることが多い。
とりあえず中古から見てまわると、やはり旧型でデザインが武骨なものは1000ルピー代だった。テレビのリモコンのような携帯電話もあった。その旧式ぶりがアンティークな雰囲気を醸し出していて逆にちょっといいかな、とも思ったが、携帯電話でもっとも重要な部分はバッテリーであることから、あまりに古い携帯電話には手を出すのはやめた。
新品になると、さすがに洗練されたデザインのものが多い。ソニー、パナソニック、サムスン、ノキアあたりの携帯がけっこういけてた。こちらはいくら安くても5000ルピーぐらいだ。上は限りがないが、1万ルピー出せば人に自慢できるようなデザインのものが手に入る。
僕のこだわりはまず、韓国企業のはやめよう、ということだ。周囲の韓国人にいちいち突っ込まれる様子が目に思い浮かぶし、日韓親善大使を気取るつもりはないので、サムスンなどは最初からパス。しかし生意気にもサムスンの携帯電話はかっこいいわりに安い。それは認める。しかし僕にも意地はあるので、韓国企業には手を出さない。一番いいのは日系企業のものだが、やはり少し値段が高くなる。パナソニックの携帯で、6000ルピーでけっこういいデザインのものを見つけた。これはいちおう要チェックだ。世界最大の携帯メーカー、ノキアのものもいろいろバラエティーがあってよさそうだった。
中古でも新品でも、バッテリーの持ちが一番の懸念だ。下手に安い携帯電話を買ってしまうと、バッテリーがすぐに切れたり、バッテリーの寿命がすぐに来たりする恐れがある。また、インドで簡単に修理可能な機種を選ぶというのも重要かもしれない。なるべくみんなが持ってる携帯を選んだ方が、修理してもらいやすいだろう。
今日は下調べだったので、特に何も買わずに帰った。ちょっとカロール・バーグは秋葉原に似た怪しい雰囲気だったので、新品を買っても本当に新品かどうか怪しい。買うときは別のちゃんとした場所で買った方がいいかもしれない。
同じクラスに香港人の青年がいる。彼は建築家&インテリア・デザイナーらしく、10年の間、アフリカ、南米、オセアニアなどを渡り歩いて仕事をし、挙句の果てにインドにやって来たそうだ。今日は彼に連れられてアマル・コロニーへ行った。
彼の情報に寄ると、アマル・コロニーに中古家具の市場があるらしい。その情報に沿って以前アマル・コロニーのマーケットへ行ったのだが、発見できなかった。そこで今回彼に連れて行ってもらったのだった。実際にはその家具市場はマーケットにはなく、少し外れた場所にあった。僕はムニルカーが南デリー最大の家具市場だと思っていたが、アマル・コロニーもなかなかの規模の家具市場だった。中古家具だけでなく、新しい家具も売られていた。彼はこの市場で家具をオーダー・メイドしたらしい。
僕の希望商品は相変わらず衣服を入れるのにちょうどいい3段くらいの引き出しが付いた棚だ。インドでは木材が高いらしく、木製家具は高価なのだが、プラスチックで同じものを作った方がさらに値段が張るそうなので、仕方なく木製の棚を探した。文房具を入れるのにちょうどいいような棚はいくつかあったが、底の深い棚を見つけるのは困難だった。だが、市場の隅でちょうどいいくらいの棚を発見。引き出しは3段、底が厚くて衣服を入れることもできそうだ。早速値段を交渉してみる。残念ながら現物は既に売約済みだったが、新しいのを作ってくれるらしい。言い値は2000ルピーだったが、1500ルピーまで下がった。本当は1000ルピーが予算の上限だったが、1000ルピーだと安い木で作ることになってしまうため、あまり見栄えがよくなくなるそうだ。売るときのことも考え、1500ルピーで立派なものを作ってもらうことにした。家具をオーダー・メイドするのは初めてだ。1週間後に出来上がるらしい。もちろんそんな時間の話は信じてないが。
その後、香港人の家に連れて行ってもらった。彼の家はグリーン・パークにあり、門番付きの立派なフラットだった。日本人の駐在員の家と同じくらい広い上に、さすがインテリア・デザイナーだけあって内装もセンスが光っていて驚いた。電化製品に目を向けてみると、ソニーのテレビ、ソニーのDVDプレイヤー、ソニーのノートPC・・・ぐわ、ソニーだらけだ!一応日本人としてお礼を言っておいたが。
はっきり言って、平均するとデリーに住む先進国の外国人の中で、日本人が一番質素な生活をしている。これは確固たる事実だ。駐在員ならまだしも、学生ともなるとインド人と同じレベルで生活している人が少なくない。よく言えば倹約主義だが、悪く言えばケチだ。対照的なのは韓国人である。韓国人の駐在員のことはよく知らないが、学生でもかなり高い家賃の家に住み、豪遊生活を送っている人が多いと聞く。ようするに本国で生活するのと同じだけの金をデリーで使って生活すれば、にわか成金の生活ができるという考え方だ。東京に住むのと同じ金銭感覚でデリー生活をしようと思ったら、仮に少なく見積もって1ヶ月10万円としても、3万〜4万ルピーの生活レベルになる。家賃1万ルピー、生活費1万ルピー、遊び代1万ルピー、使用人代(コック、ドライバーなど)1万ルピーの生活と考えれば、東京では普通の学生生活でも、デリーでは確かに一気に上流階級の仲間入りだ。日本だったら普通の人はこういう生活はできないだろう、というレベルの生活ができる。今のインドでしか体験できないような豪遊生活を体験しておく、という考え方をする外国人がいても不思議ではないかもしれない。
夕方からIIC(India International Centre)でマニプリー・ダンスの公演を見に行った。どうもビピン・スィンというマニプリー・ダンスの大御所の82歳の誕生日を祝って、サンジーブ・バッタチャリヤという人がビピン・スィンが作曲した音楽に合わせ、同じくビピン・スィンが創作したダンスを踊るというものだった。もちろん無料である。
IICに来たのは2回目だった。IIC一帯にはいろんな建物が建っており、どこが会場なのかよく分からないという欠点があるのだが、幸い以前来たのと同じホールで行われていたため、少し迷っただけで辿り着けた。観客はリタイアした老年の上流階級インド人、という感じの人が多く、インドらしからぬ落ち着いた雰囲気だった。最初は空席が目立ったが、演目が終わる頃にはけっこう埋まっていた。
マニプリー・ダンスがいったいどういうものなのか、僕は全く知識がないので偉そうなことは語れないが、見たままの印象と感想を書いておく。
今回は先にも述べた通り、サンジーブ・バッタチャリヤというダンサーの一人舞台で、最初から最後まで彼が1人で踊っていた。6つの演目があり、ダンサーは演目ごとに衣装を着替えていた。全てヒンドゥー色の強い踊りばかりで、最初は神様に祈る短いダンスから始まり、クリシュナを題材としたダンス、ヴィシュヌの10化身を題材としたダンス、手拍子を打ちながら踊るクラップ・ダンスなどがあり、最後にフィルミー・ダンスっぽい現代風のダンスを踊って終わった。カタックと同じように足に鈴を付けており、その鈴の音と床を足で打ち鳴らす音でリズムを取っていた。動きは滑らかで穏やか。表情にも重きが置かれていたかもしれないが、踊り手は東洋人系の顔をしていたため、インド人ほど目鼻立ちがくっきりしておらず、表情の変化は乏しかった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
サンジーブ・バッタチャリヤ |
● |
右足に付けていた鈴が踊っている途中で次々と外れて吹っ飛ぶというアクシデントに見舞われており、落ちた鈴を踏んづけて転ばないかと心配していたが、特に問題はなかった。なんか中途半端なハンサム顔のダンサーの、ナヨナヨした踊りだったので、オカマ・ダンスを見ている気分になった。僕はどちらかというと、ビピン・スィンという人の踊りを見てみたかったので、まだ若いサンジーブの踊りを見ても別にそれほど感動しなかった。まあ無料だったし、いい経験になったので、損したとは思わなかったが。
その後、ディッリー・ハートで食事をした。今までアルナーチャル・プラデーシュ州、スィッキム州のチキン・スティームド・モモを食べたので、今日はナーガーランドのスペシャル・ターリーに挑戦しみた。やはりあちらの方の料理もインド料理の一部という感じで、サブジーあり、ダールあり、しかも辛かった。味付けは少し異質な感じがした。このまま全ての州の料理をディッリー・ハートで食べ歩いてみようと計画している。ディッリー・ハートは頑張れば自宅から徒歩圏内だし、バスで行くのも簡単だ。いろんな州の名産品を見れるのもいい。何か珍しいものを見つけたら、必ず店の人に、それがどこの州のものか聞くようにしている。思わぬところから、次の旅行の動機が生まれるかもしれない。今はマディヤ・プラデーシュ州の物産品にかなり興味が沸いているところだ。
食事をし終わった後、いろんな店を見てまわっていると、僕がシュリーナガルで買った皮バッグと同種のものが売られていた。聞いてみるとやはりシュリーナガルから来た人だった。しばらくシュリーナガル話に花が咲く。僕が泊まったハウス・ボートの主人のことも知っていた。僕がそのバッグをシュリーナガルで250ルピーで買ったと言うと、店の人に「180ルピーで売ってるぜ」と言われた。う〜む、けっこう値切ったはずなのだが、やはりまだ下限ではなかったか。カシュミール商人、恐るべし。
僕は今までけっこうインド中いろんなところを旅行して来たので、だんだん各地から来たインド人たちと地方話ができるようになってきた。各地の名所、旧跡、名産品や、雰囲気、衣装、気候、言語などなど。一方、ふと振り返ってみると、日本旅行はほとんどしたことがないので、地方出身の日本人とは、同郷人以外そういう話ができた覚えがほとんどない。だんだん自分の中でアイデンティティーのドーナツ化現象が起こっているような気がしてきた。それはそれで「これでインディア」として、ディッリー・ハートで店を構えている人たちと話すと、彼らはインド各地からはるばるやって来ているので、インド旅行経験の豊富な人にとっては案外楽しめるかもしれない。
先週は雨ばっかだったが、今週に入りほとんど雨が降らなくなった。それと同時に気温が上昇し、再び水シャワーが気持ちいい気候となった。歩けば汗が出るし、部屋に帰ってまずすることはパンカーのスイッチを入れることだ。とは言え灼熱の暑さではなく、本当にちょうどいいくらいの気温、湿度である。夜はパンカーがあってもなくてもいいくらいの涼しさ。パンカーをつけなければ裸で寝るし、パンカーをつけたら腹に軽く掛け布団をかけるか、服を着て寝ればよい。その日の気分によって違う。僕はこのくらいの気候が一番好きだ。これが俗に言うセカンド・サマーだろうか?去年の今頃は、7月のぶり返しのように暑かったように記憶しているのだが。
ヒンディー語で「anguuThaa dikhaanaa(親指を見せる)」というイディオムがある。「〜を禁止する、やめさせる」という意味だ。拳を握り、親指だけ上に上げて、指の腹を相手に見せるジェスチャーを言う。そのジェスチャーは、意味は全く反対になってしまうが、ちょうど欧米人がよくやる「ベリー・グー」と似ている。それを見てふと思ったのだが、日本でも子供を叱るときに同じジェスチャーをして「メッ!」と言ったりする・・・のは僕の出身地だけかもしれないが、少なくとも僕の幼少時に、そういうジェスチャーをして叱られたような記憶がある。こういうふとした拍子に発見されるインド文化と日本文化の共通点はとても興味深い。
また、クラスにはいろんな国の人がいるので、インドと日本だけでなく、それらの国との対比もできる。例えば北枕という習慣が日本にはある。北向きに枕を向けて寝ると縁起が悪い、というアレだ。その習慣は実はインドにもある。おそらくインドから仏教と共に伝わっていたと思われる。しかし驚いたことに、フランスにも北向きに頭を向けて寝るのはよくないとされる迷信があるらしい。もしかして世界共通の習慣だったのだろうか?
また、インドでは明日からピトル・パクシュという一種の祭りが始まる。いわゆる祖先崇拝だ。明日から15日間、9月21日から10月6日まで祖先が現世に戻ってくるらしい。この間はあまり縁起のよい期間ではなく、何か新しいことを始めたり、祝いごとをしたりするのは好ましくないらしい。これって日本のお盆に似ている。また、中国、台湾、韓国などにも同じような先祖崇拝の祭りがある。このレベルに来ると、文化が底でつながっているというよりも、人間はどこでも同じことを考えて同じようなことをしている、ということにした方が適切だろう。それにしても、こういう先祖崇拝は、ヒンドゥー教の重要な教義のひとつである輪廻転生と矛盾するような気もするのだが・・・。
一番不思議なのは、インドとロシアの文化の共通点である。今までこのことについて触れられた文献があるかどうか知らないが、どうもロシア人やウクライナ人に聞いてみると、ロシア人とインド人の文化基盤や考え方はかなり似ているらしい。もちろん、キリスト教が入る前の原ロシア文化のことについて述べている。キリスト教がロシア地方に普及する前は、ヒンドゥー教とそっくりな自然崇拝&多神教の宗教があったそうだ。ドゥルガーそっくりの女神の像などもあるらしい。僕はロシア(またはソビエト連邦)とインドの結びつきは、政治的な利害が一致したことによる、政治的友好関係ぐらいとしか思っていなかったので、ちょっと今見直しているところだ。そういえばロシア人は、外見では白人の中でもいかにも白人、という感じだが、内面は案外東洋人に近いものを持っているような気がする。今までそんなに多くのロシア人に会ったわけではないので一概には言えないのだが。
僕はもともと映画好きで、1年間で映画を100本見たこともあった。もちろん映画館で。かつて大学で「映画論」という授業があり、教授が「映画好きを自称するからには、映画を1年間で最低100本は見ないとね〜。僕が若い頃は1年間で300本は見てたよ。映画は映画館で見られることを前提に作られているからね、なるべく映画館で映画を見るようにしなきゃ駄目だよ〜。映画館で見た映画以外は軽々しくあ〜だこ〜だ論じるべきじゃないね〜。」などと偉そうに言っていた。その言葉が僕の心に深く刻まれ、「映画は映画館で見るもの。1年間に100本見てこそ映画好き」というポリシーが形成された。それから1年間映画館に通い詰め、1年間映画館で映画100本を達成したわけだが、日本では映画の料金が高すぎる!単純計算するとその1年間で学生料金1500円×100=15万円もの金を映画につぎこんだことになる。そのときは何とか100本達成したくて、見たくもない映画まで見漁って、1日に映画5本とかにも挑戦したりして、本当に狂っていた。その後、さすがにそれは馬鹿馬鹿しいことに気が付いたので、見たい映画だけ厳選して見るようになった。ところが、最近になってまたその映画熱が再燃しつつあるように思われる。対象はもちろんヒンディー語映画だ。去年もよく映画を見ていたが、今年はさらにひどい。インドでは金曜日が映画の入れ替え日なのだが、木曜日には上映されてるヒンディー語映画を全部見つくしている状態でないと気がすまなくなっている。ノルマのような感じだ。現在インドに住んでる日本人で、僕よりヒンディー語映画狂の人っているのだろうか・・・。
今日は朝からPVRナーラーヤナーへ新作映画「Shakti」を見に行った。早く着いてしまったので、映画が始まるまでPVRナーラーヤナーの辺りを散策していたのだが、未だにこの辺りはほとんど開発されていない。せめてマクドナルド、いや、ニルラーズぐらい作ったらどうかと思うのだが。
「Shakti」は「力」という意味。ナーナー・パーテーカル、カリシュマー・カプール、サンジャイ・カプール主演、シャールク・カーンがゲスト出演、アイシュワリヤー・ラーイとプラブデーヴァがダンス・シーンだけ特別出演、という密かに豪華な俳優陣の映画だった。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Shakti |
● |
| Shakti |
ナンディニー(カリシュマー・カプール)はカナダ生まれのNRI(在外インド人)。両親は幼い内に亡くなってしまい、叔父たちと共にカナダで悠々自適の生活を送っていた。やがてナンディニーは天涯孤独のインド人、シェーカル(サンジャイ・カプール)と結婚し、幸せに暮らしていた。彼らの間にはラージャーという男の子も生まれた。
ところがある日突然、シェーカルはインドに帰ると言い出す。彼の母親が病気になったというのだ。シェーカルに家族がいたとは知らなかったナンディニーは面食らうが、とにかくラージャーも連れて一緒にインドへ赴くことになった。
初めて訪れたインドは、カナダ育ちのナンディニーにとって非常に過酷だった。人、人、人、の大喧騒、埃、悪臭、オンボロのバス・・・。それらに閉口しながらも、ナンディニーたちはシェーカルの生まれ故郷であるラージャスターンの片田舎へと向かっていた。
ところがそのバスへ突然暴徒が襲い掛かる。彼らは手に手に刃物や銃を持ち、シェーカルを探し出して彼を殺そうとする。間一髪で他の武装集団が現れてシェーカルたちを救う。ナンディニーは何が何だか分からずに呆然とするしかなかった。
シェーカルを救った武装集団は、シェーカルの家の兵隊たちだった。シェーカルの父ナルシンハー(ナーナー・パーテーカル)は村落の首長で、要塞のようなハヴェーリー(邸宅)に住み、多くの兵士たちを養っていた。彼の力は絶大で、警察も手を出すことができない上に、州首相も彼の手下同然だった。彼は隣村の首長と争いを繰り返しており、シェーカルを襲ったのもその首長の息子だった。
シェーカルは、生まれ故郷で繰り広げられていた、復讐が復讐を呼ぶ殺し合いに嫌気が差してカナダへ逃げて来たのだった。今回の帰郷は実に8年振りだった。両親は彼を喜んで迎え、その妻ナンディニーと息子のラージャーも歓迎する。ナンディニーは凶暴な性格のナルシンハーや、暴力の支配する村に怯えながらも、シェーカルの母親には深い愛情を感じる。
ところがシェーカルが帰ったハヴェーリーで起こったのは、8年前と全く変わらない殺し合いの連続だった。それに加えてナルシンハーはラージャーに爆弾を投げさせて、人殺しに育てようとする。それを見てナンディニーはカナダに帰りたいと主張する。しかしシェーカルの誕生日が数日後に迫っていたことから、母親のたっての願いでそれまでは村に滞在することになった。
それが仇となってしまった。シェーカルは外出中に敵対村落の暴徒たちに無残にも殺されてしまう。ナンディニーは耐えられなくなり、ラージャーを連れて何度も逃げ出そうとするが、失敗を繰り返した。遂にナルシンハーは彼女を捕まえて倉庫に閉じ込める。
母親たちの助けによりナンディニーは脱出に成功し、ラージャーを連れてハヴェーリーを飛び出す。ナルシンハーはすぐに追っ手を差し向ける。今にも捕らえられそうになったナンディニーを助けたのは、流れ者の男(シャールク・カーン)だった。男は追っ手を1人で蹴散らし、ナンディニーと共に空港へ向かう。
次に彼らを襲ってきたのは、敵対村落の首長たちだった。彼らの目的はラージャーの殺害。シェーカルが死んだ今、ラージャーだけがナルシンハー一族の正統な跡継ぎなのだ。流れ者の男は列車にナンディニーを乗せて、一人で首長たちを殺害した後、自分も力尽きる。
やっとのことで空港に着いたナンディニーだったが、そこにはナルシンハー自身が武装集団を連れてやって来た。しかしハヴェーリーを出る前にナルシンハーは妻から必死の説得を受けていた。ナルシンハーは怯えるナンディニーに祝福を与え、カナダ行きを許す。「オレが死んだら、ラージャーの手で葬ってくれ」と言い残して・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
まず、この映画はいろんな要素が詰まった正統派インド映画だった。踊りあり、ロマンスあり、笑いあり、悲劇あり、アクション・シーンあり、暴力シーンあり、海外ロケあり、インドの田舎の描写あり、ありとあらゆる要素が詰まっており、インド映画的に非常にバランスのとれた作品だった。それに加えて社会問題にも、嫌味にならない程度に軽〜く足を踏み込んでおり、ただの娯楽映画に終わらせていなかった。この辺りの匙加減が絶妙だった。カメラ・ワークにも工夫が見られた。
上記の通り、キャストも演技派揃いで、各人の演技力、ダンス力も素晴らしかった。残酷で凶暴な父親を演じたナーナー・パーテーカルを筆頭に、恐怖に震え、息子を守り抜くために戦うカリシュマー・カプール、無教養だが夢だけはでかくてやたら強い飲んだくれを演じたシャールク・カーンの3人が特に素晴らしかった。シャールク・カーンはゲスト出演なのに少し目立ちすぎているような感じもしたが・・・。プラブデーヴァやアイシュワリヤー・ラーイのダンスも映画を盛り上げていた。アイシュワリヤー・ラーイは、流れ者の男(シャールク・カーン)の夢の中に出てくるアイシュワリヤー・ラーイという、そのまんまの役だった。ラージャーを演じた子役は、少し演技力不足だったかもしれない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左からサンジャイ・カプール
カリシュマー・カプール
子役のジャイ・ギドワーニー |
● |
|
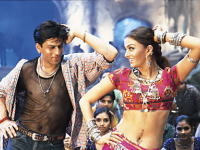 |
|
| ● |
夢の中でアイシュワリヤー・ラーイと
踊る流れ者(シャールク・カーン) |
● |
ラージャスターンのド田舎という設定だったので、人々のしゃべる言葉もバリバリのラージャスターニー語。つまり訛りに訛ったヒンディー語と考えていい。特にナーナー・パーテーカルとシャールク・カーンのしゃべり方は年季が入っていた。おかげで聴き取るのに苦労した。他のインド人は理解できる範囲なのだろうか?あと、ロケ地はジョードプルのようだ。数箇所、見覚えのある風景を見つけることができた。映画のロケ地を後から訪問するようなマニアックなことは僕の趣味ではないが、僕が訪れた場所が映画に出て来て、それに気付くことができると嬉しい。特に普通の観光客が行かないような場所だと嬉しさ倍増だ。インドを旅行すればするほど、インド映画の楽しみも増えて行く・・・。これだからやめられん。
音楽は「ミモラ(Hum Dil De Chuke Sanam」「Devdas」と同じイスマイル・ダルバール。CDを買って聞いていたときは、上記ふたつの映画の相の子のような音楽で、イスマイルの才能の限界が知れたような気になっていた。ところが映像を伴って見てみると、やっぱりいいな、と思えた。それほど典型的インドっぽい音楽でもないのだが、映画に挿入されると、インドの雰囲気にピッタリ来る。土臭いインドにも合うし、宮殿インドにも合う。彼の音楽には、インド映画にインド風味をさらに加える不思議な力があると思う。
さて、題名の「Shakti(力)」だが、これは何を意味しているだろうか?一見すると、暴君である父ナルシンハーの絶対的権力を表しているように見える。しかしヒンディー語で「シャクティ」と言った場合、それは一般的な「力、パワー」の意味も表すが、狭義には自然の持つ力(無常の人間や生物とは違う、永遠に存在し続ける力)か、女性の持つ力(新しい命を生み出す力)のどちらかだ。この映画では後者、女性の力を示していたと思う。ナルシンハーの支配する村では暴力による恐怖政治が行われていたが、息子を守るために超人的な力を発揮するナンディニー、そしてナンディニーとラージャーを助けるために、自らに火を放ってまで夫を説得したシェーカルの母。この2人のシャクティが、ナルシンハーの心を動かしたのだった。現にナルシンハーの家に祀られていたのは、シャクティの女神であるドゥルガーだった。
暴力シーンが多かったのが子供や家族のためによくなかったかもしれない。また、この映画をインドについて何も知らない外国人が見たら、「インドってやっぱり怖くて汚ない国なんだな」と再認識してしまう怖れもある。ナンディニーが初めてインドにやって来るシーンなんか、全ての外国人が一斉に「そうだ、そうだ」とうなずきそうだ。それでも、日本で公開するのに足る作品に思えた。今のところ、僕の中の勝手な日本公開待機中ヒンディー語映画は「Lagaan」「Devdas」そしてこの「Shakti」だ。
ちなみに、この映画のタイトルはポスターでは「Shakti」と綴られていたのだが、映画のプリントではなぜか「Shakthi」だった。いわゆる姓名診断のような習慣がインドにもあり、綴りをわざと変えたりすることが時々ある。例えば去年「Asoka」という映画があったが、「Ashoka」という綴りは占い師によって好ましくないとされ、わざわざ「Asoka」に変えたらしい。「Shakti」もそれと同じようなものかもしれない。それか、南インドの言語で歯音の「t」をアルファベットで書き表すときに「th」を使うので、それかもしれない。結局推測だけで詳しい理由は分からないので、一応「Shakti」と綴ることにしておいた。
「インド映画にはナヴァラサ(9つの情感)が込められている」と最初に言い出したのは、アジア映画研究家の松岡環さんらしい。もともとインドの芸術理論に、8つ、または9つのラサ(情感と訳されるが、原義はジュース)という考え方がある。芸術とは、鑑賞者に恋愛、喜笑、悲哀、憤怒、勇猛、恐怖、嫌悪、驚嘆の、8つの感情を想起させ、それらをミックスさせることによって、最後に9つ目の平安の情感に昇華させることが目的である、という概念だ。ところがどうも実際はインド映画監督はラサのことなど全くお構いなしに作っているらしい。作ったものが自然とその9つの情感が盛り込まれた作品となっているだけのようだ。インド映画監督に「インド映画にはナヴァラサの要素が含まれてますね」と聞いたところ、「そういえばそうですね」と答えられた、という話を聞いたことがある。
昨日「Shakti」を見ていたときに、「この映画は恐怖や嫌悪の情感が強いなぁ」となんとなく思ったことから、ふと思いついて、今まで日記に綴っていたヒンディー語映画鑑賞記に、その映画のナヴァラサのバランスの評価も加えてみることにした。以下、それらの説明。
| 各ラサの特徴 |
 |
シュリンガール・ラサ。ロマンス。男女の恋愛。 |
 |
ハーシャ・ラサ。コメディー。笑い。爆笑シーン。 |
 |
カルン・ラサ。悲劇。同情を誘う悲しみ。 |
 |
ラウドラ・ラサ。怒りと憎悪の念。 |
 |
ヴィール・ラサ。アクション・シーン。ヒーロー的行動。 |
 |
バヤーナカー・ラサ。ホラー。スリル。 |
 |
ヴィーバッサ・ラサ。悪役の憎たらしさ。残虐シーン。 |
 |
アドブト・ラサ。どんでん返し。斬新さ。意表を突くシーン。 |
 |
シャーント・ラサ。ハッピー・エンド。映画の総合評価。 |
| 4段階評価 |
 |
0。全くその要素に欠けているということ。 |
 |
1。その要素があるにはあるが、それほど目立っていないということ。 |
 |
2。その要素が物語を構成する上で重要な位置にあるということ。 |
 |
3。その要素が映画のもっとも特徴的な情感であるということ。 |
9つ目の情感であるシャーント・ラサについては、映画を見終わった後の満足度であると同時に総合評価であると考えてもらっていい。あとは大体パッと見れば、上のような説明書きをしなくても直感的に理解できるだろう。
もちろん、映画の評価はこれだけで決まるわけではないので、従来通り思ったことをいろいろ書いていくつもりだ。また、僕の全くの独断と偏見によって決定されるので、他の人が見たら全然違う評価になることも十分ありうる。ただのオマケだと考えてもらいたい。うまくいくといいのだが。
また時間割の変更があった。学校が始まって1ヶ月が経ったが、未だに時間割がしっかりと固定されないみたいだ。しかし、おかげで300クラスの教師陣や授業の質が高まったように思う。去年の200クラスはどちらかというと内容が簡単過ぎて退屈だった。ヒンディー語の聴き取りを磨いていたようなものだ。しかし、今年は300クラスに進んだこともあるが、内容も難しくなったし、生徒のレベルも高い。ヒンディー語の文学、言語学、インドの文化などの授業があり、とても興味深い。
特に言語学の授業が始まったのは嬉しい。もともと僕は言語学を専攻していたので、一番得意で興味のある分野だ。先生は去年から教えてくれていたラリト・モハン・バフグナー先生。彼はヒンディー語の複合動詞についての研究論文も出しており、言語学に精通している。
現在、音韻論を勉強している。語学の授業ではなく、言語学なので、ヒンディー語を科学的に分析して紹介してくれてて、いろいろ新しい驚きなどもある。例えばヒンディー語の母音について。ヒンディー語を習い始めると、ヒンディー語の母音には短母音・長母音とそれぞれに鼻音があり、合計20個、それプラス特殊な発音である「リ」が加えられて21個とされることが多い。しかし言語学的には、短母音と長母音の区別はそれほど重要ではなく、調音方法の違いに重点が置かれている。「イー」はただ単に「イ」を長く伸ばしただけではない。「イー」が一番口の前方&高い位置で調音され、「イ」それよりも少し後ろ&低い位置で発音される。その違いが、何となく長母音と短母音に聞こえるだけのようだ。これは薄々感じていたことだが、ちゃんと表でもって説明されると納得がいく。
ヒンディー語では一応サンスクリト語からの伝統に従って母音に数えられている「リ」だが、音声学的にはもちろん母音ではない。サンスクリト語が話されていた時代には、アメリカ英語の語末の「r」(carのr)に近い発音がされていたと考えられているそうだ。
というわけで、結局ヒンディー語には鼻母音も含めて母音が20あるということになる。
また、ヒンディー語の「w」の発音について。僕は今まで、ヒンディー語の「w」は、「w」と「v」のどちらで発音してもいいと思っていたのだが(文字の区別はない)、実際にはヒンディー語の固有な音声は「w」らしい。「v」はペルシア語や英語からの借用語に使われるそうだ。よって、「Saraswati」は「サラスワティー」とカタカナ化した方がより正確ということになる。僕は今まで「サラスヴァティー」と綴っていた。なぜならこっちの方が何となくかっこいいからだ。また、そうすると同じように「Shiv(Shiva)」は「シウ(シワ)」と綴らなければならなくなる。「シヴァ」の方がかっこいいんだけどなぁ・・・。僕は何でも統一しなければ気が済まない、完璧主義な性格なので、こういう細かいところがかなり気になる。ちょっと今、どうしようか考えている。
それから、言語学の祖といえば、一般的にはソシュール(1857〜1913)やチョムスキー(1928〜)などが挙げられるのだが、インドではやっぱりパーニニ(B.C.5世紀頃)が登場する。サンスクリト語の文法体系を確立した人だ。そしてインド人からすれば、現在の言語学は全てパーニニの業績の上に成り立っている、ということになる。とは言え、彼は現在の括りから言うとインド人ではない。現在のアフガニスタンにある、カンダハール出身だ。しかし当時の世界地図では、アフガニスタンもインド世界の一部だったので、インド人ということになっている。現在のアフガニスタンで、古代インドを代表する言語であるサンスクリト語が作られたと思うと不思議な気分もする。そして現在の国境の線引きがいかに無意味で、国際化社会と呼ばれて久しいながら、逆に非国際化になっているという矛盾の現実に引き戻される気分だ。
ここ数日間、8月の暑さが戻ってきたかのようだ。この2週間の日記の題名を「秋声編」にして失敗した。この題名は次のページの題名にすべきだった。命名したときは、雨が続いて一時的に涼しくなっていたのだが、今ではすっかりセカンド・サマーだ。涼しい日など一日もない。
例によって今日もヒンディー語映画を見に行った。見た映画は先週の金曜日に封切られた新作映画「Gunaah(罪)」。PVRアヌパム4で見た。
「Gunaah」は、今年上半期大ヒットした映画「Raaz」と監督&主演俳優が一緒だ。監督はムケーシュ・バット、主演はディノー・モーリヤーとビパーシャー・バス。2匹目のドジョウを狙って、果たして吉と出るか、凶と出るか?
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左がディノー・モーリヤー、
右がビパーシャー・バス |
● |
| Gunaah |
プラバー(ビパーシャー・バス)は腐敗した警察機構の改革に情熱を燃やす女警官。同僚で、悪徳警官のパーンデーイと何かと対立していた。
ある日プラバーは殺人事件の捜査に携わり、見事な推理で犯人を突き止める。容疑者の青年(ディノー・モーリヤー)は警察に踏み込まれると間一髪で逃げ出す。プラバーは彼の後を追い、屋根の上に上がる。しかし足を滑らせて下に落ちそうになる。容疑者の青年はそれを見て、とっさにプラバーを助ける。しかし当然のことながらそれが原因で御用となってしまう。
逮捕された青年は、どんなに拷問を受けても一言もしゃべろうとしなかった。青年の名前はアディティヤといった。プラバーはアディティヤに惹かれるものを感じ、なんとか彼に共感してもらおうと自分の過去を語りだす。
プラバーは実は売春婦の娘だった。ある夜警官が買春しに母親の元を訪れたのだが、プラバーはその警官が母親に乱暴を働くのを見てとっさに金属の燭台を持ち、殴り殺してしまったのだった。それがトラウマとなり、今でも彼女を悪夢となって時々襲うのだった。
それでもアディティヤは口を開こうとしなかった。そんなこんなしている内にアディティヤは仲間の助けにより脱走してしまう。プラバーもその責任を取らされ、この事件から外されることになった。
アディティヤはパルシュラームという男が率いる革命組織のメンバーだった。そして彼の父は有名な革命小説家だった。しかし彼はパーンデーイによって辱められた挙句に撃ち殺されたのだった。その事実を知ったプラバーはパーンデーイを裁判にかけ、退職処分にさせる。このときにはプラバーとアディティヤは、警察と犯人という関係ながら、相思相愛になっていた。
退職となって怒ったパーンデーイはプラバーの自宅に押しかけてプラバーを痛めつけ、銃を撃つ。プラバーは一命を取り留めたが、今度はアディティヤが怒り狂い、パーンデーイ殺害宣言をする。怖くなったパーンデーイは警察署に逃げ込んで助けを求める。アディティヤは警察署へ自動車ごと突っ込んで、暑全体を火の海にさせる。そしてパーンデーイと一対一の殺し合いを繰り広げる。
いざアディティヤがパーンデーイを殺そうと銃を構えたときにやって来たのが、病院から必死の思いで駆けつけてきたプラバーだった。アディティヤは「お前を殺そうとした男を救って何になる?」と言うが、プラバーは「理由はどうあろうと市民を守るのが警官の役目」とアディティヤを止める。しかしアディティヤはパーンデーイに銃を撃つ。それを見たプラバーは涙を流しながらアディティヤを撃つ。こうしてパーンデーイとアディティヤは死んでしまう。1人残されたプラバーは泣き崩れる。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
見ていて頭痛がしてくるような映画とはこのことだ。ストーリーがお粗末、登場人物の性格も曖昧で一貫性がない。音楽も並以下だし、音楽の使い方に必然性がない。終わり方も気持ち悪い。何の取り得もない。
ビパーシャー・バスはセクシー女優として華々しくデビューしたが、本人はセックス・シンボルに甘んじるよりはやはり演技派として脱皮したがっているようだ。この映画では製作者側の「ビパーシャーはセックス・シンボル」という思考と、ビパーシャー本人の「私は演技派」という思考が見事にぶつかって、何が何だか分からなくなっていた。意味もなくセクシーな服を着て登場する割には、顔は真剣に演技をしているのだ。ビパーシャーは僕のお気に入りの女優。先月リリースされた「Chor Machaaye Shor」でも、女警官役を演じていたが、やっぱり訳の分からない役柄だった。頼むから手当たり次第に変な役を引き受けないでもらいたい。女優としての質が下がってしまう・・・。
ディノー・モーリヤーは、アルジュン・ラームパールに匹敵するほどのハンサム・ガイだ。しかしこの映画では大半をずっと黙って過ごすという、特殊な役柄だった。初めて口を開いたときに出て来た言葉は、「I Love You」だった。それはそれでいいのだが、なんかこちらもうまく生かされていないような気がした。
この映画がヒットする理由はどこにもない。おそらく今週限りの命だろう。チケット代150ルピーを無駄にした。客入りも最低に近かった。存在そのものが「Gunaah(罪)」の映画だった・・・。
人間は生活しているといろいろな出来事が起き、それに伴って心にいろいろな感情が沸き起こるものだ。愛、嫌悪、恐怖、悲しみ、怒りなど。一方、舞台劇や映画、小説、詩などの文学作品によっても、それらの感情は沸き起こる。しかし、実生活で沸き起こる感情と、文学によって沸き起こる感情にはひとつの違いがある。実生活で起こった感情というのは直接的なものだ。喜びは喜びであり、悲しみは悲しみである。しかし、文学によって沸き興された感情はそうではない。悲しみでも、怒りでも、それは本当のものではなく、最終的に歓喜の感情へと昇華される。これがラサ(情感)である。
これは今ちょうど授業で習っている文章のまとめだが、こういう哲学理論を読むと、インド人ってすごいなぁと思ってしまう。確かにその通りだ。映画などを見て沸き起こる感情は、結局自分とは直接関係ないものを対象としている。感情の疑似体験をしているだけだ。疑似体験をした後に残るのは、すっきりとした爽快感だけだ。そんなこと、誰でも何となく分かっているのだが、改めて理論立てて説明するのは案外難しい。こういうことをさせたらインド人の右に出る民族はいないだろう。
そのラサと同じく、自分とは全く関係ない事件のニュースを聞いたときも、そういう感情が沸き起こるような気がする。例えば昨年の9月11日にアメリカで起こった同時テロ。あの事件で多くの人々が死んで、少しは悲しい気持ちになったが、僕と関係のある人が被害に遭ったわけでもないので、その感情は最終的には「いやはやすごいことが起こったな」という、一種の爽快感に変わったような気がする。現代の人々はテレビで遠隔地の全く自分とは関係ない悲劇を見慣れてしまっているため、実際の出来事にもラサが沸き起こるようになっているかもしれない。
そういえば昨日グジャラートで寺院襲撃事件が起こった。何十人もの人が死んだようだが、もはやテロ事件では何の感情を沸き起こらなくなって来た。同じインドで起こった事件だが、あまりに日常的だし、デリーで起こったことではないので、全く当事者気分がしない。まるで同じ映画を何度も何度も見尽くして、飽きてしまったかのようだ。敢えて言えば、「まだグジャラート旅行は危険かな」という感情が沸き起こったくらいである。
現代は情報があまりに早過ぎて、そして世界各地から情報が無意味に集まり過ぎて、ひとつの事件に長い間かまっていられなくなっている。だから、あたかも映画を見ているような気分になり、ラサが沸き起こってしまう。ラサが沸き起こるということは、結局事件を見て楽しんでいるということになっていまう。また、日常生活があまりにルーチン・ワークになってしまっていると、実生活で何の感情も起こらなくなって来る。そうなると、テレビ番組などからやって来る情報だけが感情を沸き興す媒体となってしまう。しかしそれは実際の感情ではなく、ラサである。
おそらく昔は、何かの事件といえば、大体自分と関係のある範囲で起こったものだっただろう。だから当事者として真の感情が沸き起こったのではないか。実際の感情の中で生きていたのではないか。どうも現代人は、ラサという幻の世界に生きているかもしれない。
そういうラサの世界から抜け出すには、旅行が一番だ。旅行中は全ての出来事が実体験となって自分に迫ってくる。リアルな感情を存分に味わうことができる。旅行中の喜びは喜びだし、悲しみは悲しみだし、恐怖は恐怖だし、怒りは怒りだ。自分=自分という関係になれる。自分が旅行好きな理由を今までよく考えたことがなかったが、インド人的に理論立てて考えてみると、どうも実生活をラサから切り離したいみたいだ。そしてついでに映画好きな理由も考えてみると、ラサをラサの世界だけに封じ込めたいのかもしれない。
旅に出たくなった。
9月23日が秋分の日だったので、もう過ぎてしまったのだが、気になることがある。日本の法律では、秋分の日は「先祖をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日と決められているということを知った。これはちょうどインドのピトル・パクシュと主旨が全く同じだ。
秋分の日は太陽が真東から出て真西に沈む日で、昼と夜の長さが同じ日である。秋分の日は仏教的には「彼岸の中日」とも呼ばれ、彼岸7日間の真ん中の日ということになっている。ただ、秋分の日が彼岸の中日と決められたのは19世紀半ばで、それ以前は、日取りの決め方は一定していなかったようだ。また、秋分の日は秋季皇霊祭として、宮中でも先祖を祭る日とされてきたようだ。
祖先を祀る祭りで、9月21日頃から15日間続くピトル・パクシュは、最初は8月のお盆に似ていると思っていたのだが、同じ時期に日本でも同じ祭りが行われていたとは驚きだ。十中八九、仏教と共にインドから日本に伝わった習慣だろう。しかし、今のところピトル・パクシュだからと言って何か大々的にプージャーをしているのを見たことがない。祖先崇拝の祭りなので、寺院で行うのではなく、各家庭でプージャーをしているのだろう。
いつもラディカルな主張をして生徒たちを驚かすマンジュ先生だが、今日は飛びっきりぶっ飛んだことを言ってくれた。ちょうど今、インドの宗教に関する授業で、イスラーム教にも触れることになった。イスラーム教の聖地と言えばメッカである。日に5回ムスリムはメッカのある方向(キブラ)に向かって礼拝をする。メッカにあるのがカーバ神殿だ。カーバ神殿は黒い布で覆われた四角い建物で、中には「何か」があるらしい。一説では隕石とも言われているが、マンジュ先生はなんとその中にヒンドゥー教のシンボルであるシヴァ・リンガが入っていると言い放った!非常にびっくりした。
聞くところによると昔ある人が密かにそのカーバ神殿の中身を見たらしい。そこにはシヴァ・リンガそっくりの偶像が安置されており、その人は気が狂ってしまったらしい。そして死ぬ前にその事実を書き記したそうだ。
カーバ神殿の中にシヴァ・リンガがあるという話の信憑性は限りなく低いと思う。また、シヴァ・リンガとは要するに男根崇拝であり、人間の考えることはどこもそう違わないことから、偶然似たものが偶像として作られたということも十分考えられる。しかし、もし万が一、万に一つ、イスラーム教徒が崇拝して止まないカーバ神殿の中にシヴァ・リンガがあったとしたら、それは特にインドとパーキスターンにおいて、驚嘆と脱力を持って受け止められるだろう。いったいこれまで数々の悲劇を生み出してきたヒンドゥーとムスリムの争いは何だったのか?お互い崇拝していたものは、蓋を開けてみれば同じものだったのだ。「ヒンドゥー、ムスリム、バーイー、バーイー(ヒンドゥーもムスリムも兄弟さ)」というキャッチ・フレーズがあるが、本当の意味で兄弟だったらそれはなんと嬉しく、また悲しいことか。お互い憎みあい、殺しあってきた2人が実は兄弟だった、という映画のストーリーまで浮かんでくる。
しかし、もしカーバ神殿の中にシヴァ・リンガがなかったとしても、この話はある意味宗教の本質を暗示している。結局一神教であれ多神教であれ、創始宗教であれ自然宗教であれ、人間が信じるものである以上、それぞれの宗教に違いはない。本質はひとつだ。ただ外見が異なるだけである。どの宗教の聖典を読んでも、人を殺していいと書かれたものはないし、皆が幸せに平穏に暮らしていくにはどうしたらいいのかが考え抜かれ、様々な形で記されている。誰だって殺し合いの世の中よりは平和を愛しているだろう。宗教はいつの時代も対立などしていない。対立しているのは政治だ。政治家が宗教を利用して、信心深い人々を煽動し、わざと宗教間で衝突を起こさせているのだ。
1週間前に注文しておいた引き出し付き棚が出来上がった。授業が終わった後、アマル・コロニーの家具マーケットへ行って出来上がりぶりを見てみた。もう1週間前の話なので、頭の中の完成予想図があやふやになってしまっていたが、実際に見てみたらなかなかの出来である。ちょうどいいサイズだ。木の色も少しオシャレだし、取っ手も見た目高級そうなのを付けてくれた。細かいところを見ていくと、ところどころに傷が付いていたりするのだが、どうせ家の階段を持って上がるときにあちこちぶつけて傷が付いてしまうので気にしない。1500ルピーという値段が高いか安いかは分からないが(多分高いのだろうが)、一応満足。オート・リクシャーに載せて持って帰った。
この棚で部屋の模様替えはほぼ完了である。早速棚を予め予定していた位置に設置する。本当にちょうどいいくらいの大きさで大満足。中に服などを入れたら、部屋の中がみちがえるほどスッキリした。ついでに部屋の掃除も始める。最近忙しくてあまり掃除をしていなかった。今まで本棚に衣服なども置いていたので、それらを新しく買った棚の引き出しに収納したら、本棚がガラガラになるほどすっきりした。家具ひとつで部屋の中がガラッ変わってしまうなぁ。
その以前ムニルカーで買った本棚だが、買った当初からある問題に悩まされていた。隅の部分にきな粉のような木の粉が溜まるのだ。最初は原因が何だかよく分からなかったが、聞くところによると木の中に住んでいる虫が原因らしい。今日掃除したついでによ〜く本棚を点検してみると、あちこちに小さな穴が開いているのを発見した。小さすぎて今まで気付かなかった。おそらくこの穴の中に虫が住んでいるのだろう。試しに針でその穴をほじくってみたが、別に何も出てこなかった。それとも針で押しつぶして殺してしまったのだろうか?
一応溜まった木の屑を全てきれいに拭き取り、いくつかの穴に針を突っ込んでみたのだが、今日の夜にはもう下に木の粉の山ができていた。まだ虫は生きているようだ。まだ虫の姿を見たことがないので、まさに見えない敵、テロリストとの戦いである。
夕方からニザームッディーンへ出掛けた。友人たちとニザームッディーンにあるカリームというレストランで食事をすることになった。ニザームッディーンと言えば知る人ぞ知る、オールド・デリーを除いてデリーで最もムスリムが多く住んでいる地域だ。僕はフマユーン廟には行ったことがあったのだが、ニザームッディーンに足を踏み入れたことはなかった。今日が初訪問である。
まずニザームッディーンに着いた途端驚いたのが、トルコ帽をかぶったムスリムの多さ。道の隅々までムスリムで溢れかえっている。そういえば今日は金曜日、イスラーム教では金曜日はモスクへ礼拝する日とされている。みんな一様に白いトルコ帽をかぶっており、みんな一斉に僕の方へ視線を投げかけてくるので、まるで運動会の帽子取りで白組の中に混じりこんでしまった赤組の人のようだ。しかも道には乞食も多い。この辺りは一応観光地でもあるため、旅行者慣れした乞食たちが一目散に僕の元へ駆け寄ってきてお金を無心する。食堂の前でタンドゥール釜の前に座っている兄ちゃんは、陽気に僕に話しかけてくる。まるで旅行者になった気分だ。デリーで生活していると、もう僕は現地人にかなり溶け込んでしまっているので、外国人扱いを全くされない。北東インド人か、チベット人だと思われているのだろう。だが、ここでは僕は一人前に外国人として扱われる。なんだか懐かしい感覚だ。しつこくしつこく付きまとってくる乞食にすら、僕は懐かしみを感じた。あまりにみんなに注目されるので、カメラを構える余裕もなかった。
しかし依りによって今日ニザームッディーンで食事をするとは・・・あまりタイミングのいい日ではなかった。なぜなら先日グジャラート州で起こったヒンドゥー寺院テロ事件のほとぼりが冷めていない金曜日だったからだ。もしヒンドゥー至上主義者たちがデリーでムスリムを対象に報復攻撃をするとしたら、ニザームッディーンは格好の標的になるし、モスクに一番人の集まる金曜日が最も適している。というわけで、ニザームッディーンに来てしまってからそれらの考えが浮かんできて少し後悔したわけだが、当然のことながら特に何も起こらなかったので結果オーライだ。
ニザームッディーンの高級レストラン、カリームは、けっこうマスコミにもよく取り上げられている有名なムガル料理屋である。ニザームッディーンを歩いてみると、安くておいしそうな食堂が何軒も並んでいて、ついつい匂いに連れられてそちらへ足が進んでしまうのだが、もし財布に余裕があるならばやはり高級レストランの味を確かめたくなるのが人情というもの。カリームはこじんまりとしてはいるが、周囲の安食堂とは全く一線を画した高級感溢れるレストランで、値段も一流。あまり覚えてないが、バター・チキン・ボーンレスが300ルピー、普通のナーンが1枚60ルピーする。羊の脳みそや内臓のカレーなども食べれる。しかし僕はバター・チキンが最も好きだし、この店の中のカレーの中でも特においしかった。9人で腹いっぱい食べて、1人200ルピーほどだった。
| ◆ |
9月28日(土) モバイル購入/日本人学校夏祭り |
◆ |
念願のモバイル購入を果たした。
昼頃ムニルカーから750番のバスに乗り、カロール・バーグへ。今のところ僕の住んでいる地域からカロール・バーグへ直行するバスはこれしか知らない。カロール・バーグに着いたその足でグッファー・マーケットへ行く。携帯電話の市場だ。ここ最近グッファー・マーケットに立て続けに来ているので、もう大体どこで何が売られているのか分かっている。何度も足を運んでいる内にターゲットは絞られていた。パナソニックのGD−75(シルバー)だ。早速値段の調査を始める。やはり僕の顔を見て高めに値段を言ってくるところもあり、安いところで6000ルピー、高いところで6500ルピー、ちゃんとした店舗を構えているところで6200ルピーだった。1週間前に来たときは5900ルピーが底値だったのだが、携帯電話の値段は変動相場制なので、日に日に値段が変わるそうだ。
もちろん6000ルピーの値段を提示してくれたところで交渉を始める。一度買いかけたのだが、よくよく話を聞いてみるとなんだかおかしい。まず、パッケージが付いていないというのだ。しかも、説明書は原本をコピーして束ねたものだった。携帯電話本体は問題なく動きそうなのだが、怪しさ満点だったのでそこで買うのはやめた。
次にちゃんとした店舗を構えており、店内は冷房が効いている、グッファー・マーケットの中でも比較的信頼できそうなところで交渉をしてみた。ここはパッケージ付き、本物の説明書付きだったのだが、保証が付いてなくて6200ルピーらしい。保証付きの商品は7000ルピー以上するらしいが、入手が難しく在庫はないそうだ。
どうやらグッファー・マーケットで売られているモバイルは、パッケージ付きかなしか、説明書がオリジナルかコピーか、保証付きかなしかでも値段が変わるようだ。ブラック・マーケットと合法マーケットの中間、グレー・マーケットと呼ばれている所以だ。ここで売られている携帯電話たちは、いったいどこからやって来たのだろうか?謎は深まるばかりである。
どうせ保証があっても壊れないから必要ないみたいだし、パッケージ付き、オリジナルの説明書付きで6200ルピーならいい値段だろうということで、その店でモバイルを買った。その他には何も買わずにカロール・バーグを後にした。
インドの携帯電話は、本体にSIMカードという小さなチップを組み込んで初めて使えるようになる。SIMカードの中には電話番号や電話帳などの情報が登録されている。そのSIMカードは家の近く、ユスフ・サラーイにあるエア・テル(Air Tel)のオフィスで購入した。エア・テルのSIMカードには2種類ある。1つはプリペイド・カード用、もう1つは月払い用である。料金体系をいろいろ比較した結果、あまり頻繁に携帯電話を使用しないならプリペイドで十分と見極め、300ルピーでプリペイド・カード用のSIMカードを購入した。外国人はちゃんとフォームを提出しないといけなくて、写真1枚とパスポートのコピーが必要となる。本当は住所証明も必要みたいだが、僕は提出しなくても何も言われなかった。けっこう適当らしい。同時に315ルピーのプリペイド・カード(エア・テルのはマジック・カードと呼ばれている)を買った。これで193.80ルピー分話すことができる。
プリペイド式携帯電話の料金は現在のところ以下の通り。
|
日中
8:00am〜10:00pm |
夜間
10:00pm〜8:00am |
| 送信 |
Rs 1.35/30秒 |
Rs. 0.67/30秒 |
| 受信 |
Rs. 0.99/30秒 |
Rs. 0.49/30秒 |
インドの携帯電話は受信にも料金が発生するので、日本の携帯電話と使い勝手は違う。また、エア・テルの携帯からエア・テルの携帯へのコールだったら受信料金はただになる、というような話も聞いたが、それはどうやらプリペイド・ユーザーには適用されないらしい。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
パナソニック GD−75 |
● |
GD−75の機能を見てみよう。まず、呼び出し音が20種類くらいあり、録音した音声で呼び出しすることも、自分で作曲した音楽で呼び出しすることもできる。バイブ機能も付いている。時計、アラーム、計算機、通貨換算機能もある。スケジュール機能やゲームまであるし、メールやi−modeのようにブラウザ機能もある。日本の携帯電話に比べたら原始的機能ばかりかもしれないが、インドではやっとデジカメ付き携帯が売り出されたぐらいだ。これらの機能だけでも十分自慢できる。何しろ時計すら付いてない携帯も堂々と売られているのだ。
日本には一昔前、携帯電話を持っていることがステータスの時代があった。万人携帯ユーザー時代が訪れた後は、持っている携帯の機種や機能が自慢の種である時代がやって来た。しかしその時代もすぐに終わってしまい、現在では携帯電話を持っていることは特別なことでもなく、機種で自慢することも困難となった。しかしインドは違う。まず携帯電話を持っていれば、一定のステータスが保証される。そして機種、機能やデザインで大いに自慢できる。日本の携帯電話はインドで使用できない(と思う)が、あの美しい呼び出し音をインド人の前でわざとらしく鳴らせば、絶対にヒーローになれるに違いない。「なんだ、このCDみたいな音楽は!」という感じだろう。ムービー写メールを見せたら、まるで原始人にコンピューターを見せたかのごとく怒涛の反応を示されることだろうな。「インド人もビックリ」というフレーズがあるが、インド人は確かに驚かしがいのある民族だと思う。僕が逆に驚かされることの方が実際は多いのだが・・・。
今日は年に一度の夏祭りの日。デリー中の富が、ヴァサント・クンジのニューデリー日本人学校に集まる日だ。ユスフ・サラーイでユーザー登録やSIMカードの購入を済ませ、その足で日本人学校へ向かった。もちろん携帯電話持参で。
ちょいと道に迷ってしまったが、遠くから聞こえる日本語の放送を頼りに歩いていくと日本人学校に辿り着いた。去年の夏祭りから実に1年ぶりの来訪だ。去年と雰囲気は全く同じで、運動場の中心には盆踊り用の台が築かれ、隅には出店が立ち並び、運動場に面した教室は古本屋となっていた。サンスターンやデリー大学、JNUなどの友達、知り合いや、その他いろいろ面識のある日本人たちもこぞって来ていた。
日本人学校夏祭りは、僕たち学生にとっては戦争に等しい。日常では決して手に入らないような日本食が手に入る上、日本語の本も破格の値段で売られている。効率よく買っていかないと、すぐに売り切れてしまう。5時50分、全ての店が一斉に開店。まずはおにぎり(1つ20ルピー)を集中的に購入、その後散らし寿司(30ルピー)、うどん(80ルピー)、ヤキソバ(30ルピー)などを買って僕はひとまず安心。古本屋にももちろん行く。3冊10ルピーで、6冊日本語の本を買った。「インドへ」(横尾忠則)、「身体にやさしいインド」(伊藤武)、「マンガ聖書物語」(樋口雅一)、「インド入門」(辛島昇)、「焼かれる花嫁」(ジャミラ・ヴァルギーズ)、「インド放浪」(藤原新也)。ほとんどインド関連の本だ。なかなかの収穫だった。
盆踊りも始まったが、上記の通りいろいろ忙しくて僕は踊らなかった。早速友達に携帯電話を披露し、電話番号も教えた。これからさらに忙しくなりそうだ。
朝から新作映画「Road」を見にPVRアヌパム4へ行った。意識していなかったのだが、モーニング・ショーということで、普段は150ルピーのチケットが朝一番の回に限って90ルピーだった。早起きは三文の徳、という気分。11時からの回だったので、それほど早起きでもないのだが。
「Road」は、今年の前半に「Company」をリリースして話題をさらったラーム・ゴーパール・ヴァルマーの新作で、期待度も高い。主演は「Company」で衝撃のデビューを果たしたヴィヴェーク・オーベーロイ、同じく「Company」でゲスト出演したアンタラー・マーリー、そしてマノージュ・バージペーイー。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
アンタラー・マーリー(左)と
ヴィヴェーク・オーベーロイ(右) |
● |
| Road |
デリー。アールヴィンド(ヴィヴェーク・オーベーロイ)とラクシュミー(アンタラー・マーリー)は恋仲だったが、両親の反対にあって結婚できずにいた。そこで2人はRV車(TATA社のサファリ)に乗ってデリーを飛び出し、新天地を求めてラージャスターンの荒野を突っ走っていた。
道の途中で2人はヒッチハイクしていた男を乗せる。彼の名前はバーブー(マノージュ・バージペーイー)。しかし実はバーブーはマフィアの一員で、銃でアールヴィンドを脅して道端に置き去りにし、ラクシュミーをさらって行ってしまった。バーブーは怯えるラクシュミーに問いかける。「もし大学でオレとアールヴィンドがいたら、どっちを選ぶ?」ラクシュミーは「アールヴィンド」と答える。
一方、アールヴィンドは後ろから来たトラックに乗せてもらってバーブーを追いかけ、うまいことバーブーを追い払ってラクシュミーと自動車を奪い返した。
ところが今度はそのトラックをバーブーが奪い、アールヴィンドたちの自動車目掛けて後ろから激突してくる。アールヴィンドは逃げ回るが、砂にタイヤがはまってしまい、抜け出せなくなる。そこへバーブーのトラックが爆走してくるが、間一髪のところで抜け出し、逆にトラックのタイヤがはまり、アールヴィンドたちは何とか逃げ出すことに成功した。
夜になった。アールヴィンドたちは途中の町の宿に泊まる。翌朝、再び自動車に乗って走り出すが、バーブーが後部座席で銃を持って待ち伏せしていた。バーブーはアールヴィンドを再び自動車から降ろし、ラクシュミーをさらって行ってしまう。アールヴィンドは警察署に駆け込んで道の検問をしてもらうが、バーブーは途中で自動車をTATA車のスモーに変えており、まんまと抜け出すことに成功する。逆に、道の途中でバーブーが殺した死体が発見され、アールヴィンドが警察に疑われることになる。アールヴィンドは警察のジープを奪って逃走する。
再び夜になった。バーブーは道の途中にあった金持ちの邸宅に車を止め、そこのチャウキーダール(警備員)を殴り倒して留守中だった家の中に入る。そこでバーブーは再びラクシュミーに問う。「もし大学でオレとアールヴィンドがいたら、どっちを選ぶ?」ラクシュミーは「あなた」と答える。バーブーは乱暴だが、心は案外純粋だった。バーブーはいつの間にかラクシュミーに人生初めての恋をしていたのだった。ラクシュミーが自分の恋人となったことにバーブーは狂喜する。
一方、バーブーは警察の追っ手を振り切り、バイクに乗り換えてバーブーを追跡していた。翌朝になり、通報を受けた警察がバーブーたちの潜む邸宅を急襲する。バーブーとラクシュミーも、裏口に置いてあったバイクに乗り込んで逃げ出す。道の途中でアールヴィンドとバーブーは出会い、そこからバイク・チェイスとなる。2人ともバイクが駄目になると今度は走り出す。バーブーはラクシュミーと共に丘の陰に隠れる。バーブーは銃を構えながらラクシュミーに言う。「これが最後の一発だ。」そこへゆっくりアールヴィンドが歩み寄ってくる。バーブーはアールヴィンドに照準を合わせる。いざ撃とうとした瞬間、ラクシュミーはバーブーに蹴りを食らす。ラクシュミーはやはりバーブーなど好きではなく、アールヴィンドのことを愛していたのだった。
銃を失い、ラクシュミーに裏切られたバーブーは、ただアールヴィンドの攻撃を受け続けることしかできなかった。アールヴィンドはバーブーを徹底的に痛めつけ、荒野の真ん中に置き去りにして、ラクシュミーと共に去って行った。バーブーは最後につぶやく。「ラクシュミー、お前はオレよりも汚ない人間だぜ・・・。」 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Company」と似たテイストの映画で、非常に楽しかった。まず最初のクレジット・シーンから凝っていてよかった。エンジンをふかす音やら、クラクションを鳴らす音やらが大音響で映画館中響き渡り、音響設備のいいPVRで見たのは正解だった、と思わせた。映像もなかなか凝っていて、この映画の第4の主人公――ヒーロー、ヒロイン、悪役の次に来る主人公――である「道」が中心的に映し出されていた。まるで全ての物語の語り部のごとく・・・。
舞台はラージャスターンの砂漠地帯だが、どうやらオーストラリアでもロケが行われたようだ。オーストラリアの荒野をインド国産TATA社のサファリやスモーが疾走するとは、なかなか痛快だ。トラックが後ろから追いかけてくるシーンは、スティーブン・スピルバーグ監督の「激突!」を思い起こさせ、最後のバイク対バイクのシーンはジョン・ウー監督の「ミッション・インポッシブル2」を想起させた。道の他に影の主人公を挙げるとしたら、アールヴィンドやバーブーが次々と乗り換える乗り物たちだろう。
音楽はサンデーシュ・シャーンディリヤ。「Road」の音楽はアップ・テンポ調の曲が多く、普通のインド映画音楽の感覚からすると変な曲が多かった。踊りも思わず首を傾げたくなるような、斬新過ぎというか、狙い過ぎというか、変な踊りが多かった。「Road」のCDは持ってないし、買う気になれないが、なかなかの売れ行きのようだ。
どちらかというと、マノージュ・バージペーイの演技が一番光っていた。図々しく、殺人鬼ながら、実は純粋な心を持っている哀れな男を気味悪いくらいうまく演じていた。こんなインド人がそばにいたら嫌だな〜、でも現実にいそうだな〜と思いながら見ていた。ヴィヴェーク・オーベーロイは主人公ながら途中から登場機会がめっきり減り、演技の見せ所にも欠けていた。彼の顔はスニール・シェッティーに少し似ている。特に目の辺りが。今回初めて主役をはったアンタラー・マーリーは、顔はそれほど美人でもないが、セクシー女優路線を爆走しそうなパワーに溢れていた。
この映画のひとつの大きなポイントは、ラクシュミーが本当にバーブーを愛してしまったかどうかだろう。途中から、演技で愛している振りをしているのか、本当に愛しているのか分からなくなってくる。最後のシーンでアールヴィンドとバーブーが戦うところがあるのだが、そこで彼女がどちらの味方をするのか、ドキドキしてしまった。
スリルに満ちた映画だったのだが、笑えるシーンもところどころに用意されていた。特にいろんな映画のパロディーがたくさん盛り込まれていた。分かりやすいところでは「Company」のパロディー。アールヴィンドが自動車の中で「Company」のCDを聴いていると、ヒッチハイクで乗り込んできたバーブーが「オレはこの歌好きじゃないから消してくれ」と言う。他に、「Devdas」のパロディーがあった。また、いろんな映画の有名なセリフをバーブーが時々口にしていたような気がしたのだが、これは確信が持てない。
荒野の中で果てしなく続く道、その半密室状態の中で繰り広げられる、少数の登場人物による追跡劇、RV車、ジープ、トラック、バイクなどの乗り物の数々、そしてちょっとしたお色気シーン。男による男のための映画という感じがした。ヒットしてもおかしくない。
| ◆ |
9月30日(月) American Desi |
◆ |
明日10月1日から10日まで、「The 33rd International Film Festival of India 2002」という映画祭が家の近くのスィーリー・フォート・オーディトリアムで行われる。デリー情報誌「Delhi
Diary」を買ったが、「詳しい情報は次号」とのことだった。次号の発売日は4日(金)だから、既に映画祭が始まってるではないか。使い物にならん!学校から帰った後、自分で情報を集めにスィーリー・フォート・オーディトリアムまで歩いて行ってみた。
スィーリー・フォート・オーディトリアムでは飾りつけの真っ最中だった。僕がのこのこ中に入って行っても、誰にも文句を言われなかった。こういう適当なところが僕は好きだ。会場入り口の広間にはインド映画の歴史がパネル写真と共にズラーッと紹介されており、各時代の有名な映画の写真が並んでいた。
僕が欲しかったのはプログラムである。会場にいた人に聞いてみたが、皆忙しいようで、そっけない返事。「向こうにプレス用のカウンターがある」と言われたのでそこへ行ってみると、一応掲示板に映画のスケジュールが載っていた。スィーリー・フォート・オーディトリアムの他に、コンノート・プレイスのオデオン・シネマも会場になってるみたいだ。オデオンの方はどうやら一般にチケットが販売されるようだが、スィーリー・フォートの方は主にプレス関係者やバイヤー中心らしい。映画のタイトルを見てみたが、「Devdas」が何度も上映される予定になっていた。しかもベンガリー語やテルグ語など、インド各地の言語で。他に「Kabhi Khushi Kabhie Gham」や「Raaz」などのヒンディー語映画の他、インドの地方言語の映画が何本か上映されるようだ。全部メモしようかと思ったが、明日の新聞に掲載されるらしいので、それを買った方が早いと思い、そのまま帰った。
夕方からPVRアヌパム4へ「American Desi」という映画を見に行った。この映画は、僕が勝手に命名したヒングリッシュ映画の新作で、アメリカに住むNRI(在外インド人)が主人公のため、全編ほとんど英語、ところどころにヒンディー語が入る、という言語構成の映画だった。キャストやクルー、プロデューサーなどに顔なじみの人はいなかった。「Desi」とは日本語の「〜人」にあたるヒンディー語だ。
| ● |
|
● |
|
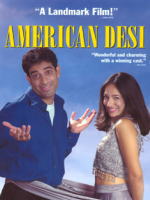 |
|
| ● |
American Desi |
● |
| American Desi |
アメリカ合衆国はニュー・ジャージー州。クリスはアメリカで生まれ育ち、バスケットやロックンロールの好きな普通のアメリカ人だった。唯一、両親がインド人であることを除けば。彼の本当の名前はクリシュナ・ゴーパール・レッディーだったが、彼はインドの文化を毛嫌いしており、自分の名前をクリスで通していたのだった。
インド文化の塊である両親から逃げるため、クリスは州立工科大学で寮生活を始める。ところがルーム・メイトとなったのは不幸にも全員インド人。芸術家志望ながら親の命令で泣く泣く工学を勉強しているスィク教徒ジャグジット・スィン、厳格なムスリムであるサリーム・アリー・カーン、お調子者のヒンドゥー教徒であるアジャイ・パーンディヤの3人だった。部屋にはマサーラーとお香の匂いがたち込め、テレビからはヒンディー語映画がひっきりなしに流されていた。これでは実家にいたときと全く変わらない生活だ。クリスは3人を避け、自分だけの世界に閉じこもる。
新入生パーティーでクリスはニーナーという美しい女の子と出会う。クリスはニーナーに話しかけるが、なんと彼女はインド人だった。ニーナーは流暢なアメリカ英語を駆使したが、自分がインド人であることに誇りを持っていた。また、クリスはニーナーを狙うキザなインド人ラーケーシュ・パーテールに目を付けられることになる。
そんな中、大学のインド人学生会でナヴァラートリーの祭りを企画することになる。音楽係にニーナーが立候補したのを見てクリスとラーケーシュも手を上げる。そこで3人が共同して祭りの音楽を決定することになった。しかしクリスはヒンディー語映画の知識が全くなかった。クリスはインドに対する嫌悪の気持ちを秘めながらも、ニーナーの気を引くために次第にインド世界に入り込んでいく。ルーム・メイトのインド人たちとも心を通わすようになる。
ニーナーにガルバー(スティック・ダンス)を個人指導してもらったりして、だんだんいい仲になってきたのだが、最終的なところでインドの伝統に捉われているニーナーと、インドの文化からは何も学ぶことがないと思っているクリスの間ではそりが合わず、喧嘩別れしてしまう。クリスは結局考え直し、アジャイからスティック・ダンスを教えてもらう。
ナヴァラートリーの祭りがやって来た。会場にはたくさんのインド人の他、外国人も多く詰め掛けていた。みんなでインド流に踊り、最後にガルバーの時間がやって来る。ガルバーは2列の輪になって互いに棒を打ち鳴らしてグルグル周り続ける踊りで、クリスはニーナーと踊る機会が数回巡ってきた。ニーナーはクリスのスティック・ダンスの腕が上がっていることに驚く。面白くないのはラーケーシュである。ラーケーシュはニーナーを外に連れ出し、追いかけてきたクリスに急にパンチを喰らわす。そこへジャグジットらが救援に駆けつける。クリスはラーケーシュをノック・アウトし、ニーナーとも仲直りする。こうしてインディアン・ナイトは最高潮に達したのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
前半はインド文化の特異性が、インド人なのにインド嫌いな主人公の視点から、自虐的なギャグと共に描かれる。ヒンドゥー式の旅立ちの儀式、手で食事をとる習慣、時間を守らないインド的時間感覚などなど・・・。しかし後半を過ぎると、主人公の心にインド文化に対する理解と自覚が芽生え、それと同時に描写の仕方も次第にインドに対してポジティブになって来る。最後の祭りのシーンになると、「やっぱインドっていいなぁ〜」と改めて思ってしまう。日本人の僕がそう思うんだから、他のインド人観客はきっとさらにインド人であることに誇りを持ったのではないだろうか?特にPVRの観客は金持ちインド人ばかりだ。この映画を見て心当たりがあったのではないだろうか?インド人にアイデンティティーを自然と見直させる巧妙さのある映画だった。
インド人はインド文化に対してあまり興味がないのに、その周りの外国人はインド文化にやたらに興味を示し、うらやましがるという構図が映画中に登場し、こちらは僕自身に心当たりがあった。しまった、今日はクルター・パージャーマーを着て来てしまった。映画館を出るときにインド人から、「こいつもインド好きな外国人だな」と思われたかもしれない。
言語は正真正銘のアメリカ英語。インド英語を聞き慣れてしまっているので、最初の内はアメリカ英語特有のレロレロと流れていく発音が頭に入ってこなかった。ただ、クリスのルーム・メイトたちはきれいなインド英語を話してくれたので、聴き取りやすかった。また、インド人の登場人物が時々ヒンディー語を話すのだが、それが逆になんだか英語訛りしていたくらいだ。もしかしたら俳優陣のインド人はほとんど本当のNRIかもしれない。
基本的にギャグ映画だったので、ほぼ満席の会場は爆笑の渦に巻き込まれていた。やはりインド人はアメリカ英語でも十分聴き取ることができるようだ。英語のギャグで笑うこともインドではステータスのひとつだ。
どういう目的で作られたのかは知らないが、特に英語を解する上流階級インド人向けのハイソなコメディー映画という感じがした。既にNRIの多いイギリスやアメリカでは上映されたらしい。この映画がインド中でヒットすることはまず有り得ないが、都市部を中心に一定の成功は収めそうだ。そういえば先行ヒングリッシュ映画である「Bend It Like Beckham」(12週)や「Everybody Says I'm Fine!」(10週)は未だにPVRで上映され続けている。やはりデリーともなると、インド人が作った英語の映画を楽しめる能力と金銭的余裕のある人が多いのだろう。そしてインドでもこの種の映画がある程度の収入を見込めることが証明されつつある。この傾向が続けば、さらに良質のヒングリッシュ映画が今後増加すると思われる。
|
|



