| ◆ |
6月1日(水) インド系Jリーガー、インドへ? |
◆ |
6月1日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に、「日本で育った、インドの血を引くサッカー選手」と題した記事が掲載されていた。それは、アルビレックス新潟に所属するイズミ・アラタ選手のことであった。さぶずぃや庵によると、実際にはアルビレックス新潟ではなく、アルビレックス新潟がシンガポールのSリーグに送っているアルビレックス新潟Sというチームに所属する和泉新選手のことであった。いったい彼のことをJリーガーと呼んでいいのか分からないが・・・。僕はサッカーには詳しくないので、和泉選手のことはこの記事を読んで初めて知った。
記事によると、和泉選手の父親はインド人、母親は日本人。和泉選手は1982年7月31日、山口市で生まれたが、彼が8歳の頃に父親はどこかへ逃げてしまい、その後、和泉選手は母親に育てられてきた。「彼の容貌は日本人のようで、日本語しか話せない」という記述もあった。ポジションはフォワード。シンガポールのSリーグでは、両翼での活躍、抜群の加速力、優れたボール・コントロールなどで注目を集めているとか。なかなか有望な選手のようだ。
タイムズ・オブ・インディア紙のインタビューで、和泉選手はインドでのプレイに対する野望を明らかにした。「私が初めてインドチームを見たのは、ワールドカップ一次予選のインド対日本戦だった。日本ではインドのサッカーについて全く報道されていないので、日本人は、インドのサッカーのことをほとんど何も知らなかった。私はインドでプレイしたいと思っている。私はインドの国内リーグのことを聞いたことがある。それこそが私にとってインドチームに加入するための理想的な場だと考えている」と和泉選手は語っている。和泉選手は18歳の頃にインドに来たことがあるようで、1週間デリーで過ごしたらしい。インドについては、「摩訶不思議な雰囲気に感動した。もしチャンスがあったらまた訪れたい」と述べている。
和泉選手は「スバ抜けてハンサム(strikingly good looks)」で、特に女性にモテモテ、との記述もあったのだが、それは本当だろうか・・・。アルビレックス新潟Sのウェブサイトに写真が掲載されていた。タイムズ・オブ・インディア紙に掲載されていた以下の似顔絵とそっくりであった。

Izumi Arata選手の似顔絵
去年は、偶然にもワールドカップ一次予選で日本とインドが同じ組に入った結果、日本対インドの試合が実現した。僕もコールカーターで行われた試合を観戦しに行ったので、思い出深い出来事となった。その様子は、2004年9月7日からの日記に詳述した。だが、あれは一時的なもので、日本とインドのサッカー界の交流に寄与する性格のものではなかった。もしそれが起こりうるとしたら、インドのエース・ストライカー、バイチャン・ブーティヤーのJリーグ移籍くらいではないかと考えていた。だが、もしこの和泉選手がインドの国内リーグに移籍することがあれば、インドのサッカー界が日本人の注目を集めることが増えるかもしれない。それがたとえわずかなものであったとしても、現在の「ほぼゼロ」の状態と比較すれば、大きな前進と言えるだろう。
しかし、インドのサッカー界はまだまだ発展途上であるため、Jリーグの恵まれた環境から突然インドのサッカーチームに入ると、戸惑うことが多いと思う。どうせなら、Jリーグで才能を磨き、名声を獲得してから、インドサッカー界を啓蒙する目的でインドに移籍してもらった方が、彼自身にとっても、インドにとっても、いいのではないかと思う。
現在インドではジョージ・ルーカス監督「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」が公開されている。やはり「スター・ウォーズ」は思い入れの深い特別な映画なので、普段はほとんどインド映画しか見ない僕も見に行った。シリーズ最高傑作と言われるだけあって、確かによく出来ていた。アナキン・スカイウォーカーがいかにダース・ヴェイダーになったかが、「スター・ウォーズ」シリーズで最も緻密な心情描写重視と共に描かれていた。「スター・ウォーズ」シリーズは当初から9部作の予定だったようで、まずは1977年〜1983年まで、第4部〜第6部が公開され、その後、1999年から2005年まで、第1部〜第3部が公開されている。
ところで、今日は新作ヒンディー語映画「D」をPVRアヌパムで見た。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーがプロデュースするギャング映画であるが、ちょうど彼自身が監督したギャング映画「Company」(2002年)に出てきたマフィアのドン、マリク(アジャイ・デーヴガン)が、ドンになるまでを描いたような作品であった。よって、アナキン・スカイウォーカーがダース・ヴェイダーになるまでを描いた「スター・ウォーズ エピソード1〜3」を思い出し、冒頭の前振りを置いたわけだ。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは「Satya」(1998年)でもギャングを主人公にしており、これら3作品を彼のギャング三部作と呼ぶことができる。
監督はヴィシュラーム・サーワント、音楽はプラサンヌ・シェーカルとニティン・ラーイクワール。キャストは、ランディープ・フダー、ゴーガー・カプール、チャンキー・パーンデーイ、ヤシュパール・シャルマー、スシャーント・スィン、ルクサール、イーシャー・コーッピカルなど。ラージパール・ヤーダヴが特別出演。
| D |
 警察官の息子で、無為に人生を過ごしていたデーシュー(ランディープ・フダー)は、ある日、自ら志願して、ムンバイーのマフィア、ハーシム・バーイー(ゴーガー・カプール)の下で働くようになる。元々警察の訓練を受けたデーシューは拳銃の扱いに長けており、また政治的センスも持ち合わせていた。デーシューの活躍により、ハーシム・バーイーはライバルのマフィアを次々と打ち破り、勢力を広げる。デーシューは仲間からも尊敬を受けるようになり、特にラーガヴ(チャンキー・パーンデーイ)は彼の親友となった。また、デーシューは女優バクティー(ルクサール)と恋仲になる。【写真は、ランディープ・フダー】 警察官の息子で、無為に人生を過ごしていたデーシュー(ランディープ・フダー)は、ある日、自ら志願して、ムンバイーのマフィア、ハーシム・バーイー(ゴーガー・カプール)の下で働くようになる。元々警察の訓練を受けたデーシューは拳銃の扱いに長けており、また政治的センスも持ち合わせていた。デーシューの活躍により、ハーシム・バーイーはライバルのマフィアを次々と打ち破り、勢力を広げる。デーシューは仲間からも尊敬を受けるようになり、特にラーガヴ(チャンキー・パーンデーイ)は彼の親友となった。また、デーシューは女優バクティー(ルクサール)と恋仲になる。【写真は、ランディープ・フダー】
ところが、ハーシム・バーイーの息子、シャッビール(ヤシュパール・シャルマー)とムカッラム(スシャーント・スィン)は、デーシューばかりが注目を集めるのが面白くなかった。2人は父親にデーシューの悪い噂を吹き込み、デーシューの勢力を一掃する許可を得る。ムカッラムはラーガヴとその愛人(イーシャー・コーッピカル)を殺害するが、デーシューとバクティーは刺客を巻いて逃げ出す。ハーシム・バーイーの親友で、グジャラートのマフィア、ガンガーラームは、デーシューの力を高く買っており、ハーシム・バーイーのマフィア内で起こった内紛を解決しようと努力する。しかし、デーシューは和解の場において容赦なくムカッラムを撃ち殺す。
もはやハーシム・バーイーのグループ内での内紛は避けられなくなった。だが、デーシューの方が才能も人望も上で、すぐにハーシム・バーイーの息のかかった者たちは始末された。こうして、デーシューはマフィアのドンにのし上がった。こうして、誰も彼のことを「デーシュー」と呼ぶ者はいなくなり、デーシューは畏敬の念と共に「D」と呼ばれるようになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
1人の男がマフィアの中で実権を握るまでを淡々と描いたハードボイルドな映画。映像や表現技法が工夫されており、かっこいい映画に仕上がっていたが、ストーリーは一直線で、人物の心情描写にも深みがない。デーシューの圧倒的な強さと賢さも、警察の息子であること以外、最後まで何ら説明や言い訳がされることがなかったので、現実感がなかった。ミュージカル・シーンの中途半端な挿入もマイナスに働いていた。「インドのクエンティン・タランティーノ」と呼ばれるラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、なぜ執拗に同じようなプロットのギャング映画を撮り続けるのだろうか・・・。
映画の題名「D」とは、主人公デーシューのことである。しかし、ムンバイーで頭文字「D」から始まる実在のマフィアと言ったら、誰しもが思い浮かべる人物がいる。ダーウード・イブラーヒームである。ダーウードはドバイにいながらムンバイーを支配した有名なマフィアで、1993年3月12日のムンバイー連続爆弾テロの首謀者とされており、インドの最重要指名手配犯となっている。現在はパーキスターンに匿われているとか。「Company」も、ダーウード・イブラーヒームとその腹心チョーター・ラージャンとの間の抗争を基にした映画と言われている。ダーウードとデーシューの間には、頭文字以外にも多くの共通点がある。例えば、デーシューの父親は警察官であるが、ダーウードも警察官の息子である。デーシューはハーシム・バーイーというマフィアの下でギャングとしてのキャリアをスタートさせたが、ダーウードも1983年にカリーム・ラーラーというマフィアの下で働き始めてドンまで登りつめた。ダーウードの愛人は、「Ram
Teri Ganga Maili」(1985年)で有名なボリウッド女優、マンダーキニーだったが、デーシューも映画女優バクティを恋人にした。デーシューは、ハーシム・バーイーの2人の息子、シャッビールとムカッラムにライバル視されるが、ダーウードもカリーム・ラーラーの親戚、アーミルザーダーとアーラムゼーブと激しい内部抗争を繰り広げた。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、「D」とダーウード・イブラーヒームの関連を否定しているが、明らかにこの映画は、インドで最も有名なマフィアがドンにのし上がるまでを描いた映画である。聞くところによると、ラーム・ゴーパール・ヴァルマーのもとには、既にマフィアから脅迫の電話がかかって来ているとかいないとか・・・。故伊丹十三監督のようにならなければいいが・・・。
デーシューを演じたランディープ・フダーは、「モンスーン・ウェディング」(2001年)でデビューした男優。本作が2回目の出演作となるが、いきなり主役に大抜擢された。およそマフィアのボスにのし上がる男とは思えない、細身で優男の風貌だが、そのギャップが逆によかった。脇役陣の演技も素晴らしかった。ハーシム・バーイーを演じたゴーガー・カプール、デーシューの親友ラーガヴを演じたチャンキー・パーンデーイなど、あまり名前に馴染みのない俳優がいい演技をしていた。なぜかいつも裏切り者を演じ、僕が勝手に「裏切り者男優」というレッテルを貼っている、ヤシュパール・シャルマーが、やっぱり今回もズルイことをしていて密かに満足。ジョニー・リーヴァルに次ぎ、最近のボリウッドを代表するコメディアンに台頭したラージパール・ヤーダヴは、なんとアイテム・ボーイ(挿入歌のみダンス出演)として登場。女優陣の活躍の場は少なかったが、イーシャー・コーッピカルが印象的であった。
ラーム・ゴーパール・ヴァルマーが制作・監督する映画の中には、インド映画のトレードマークであるミュージカル・シーンを一切排したものがいくつもあるが、この「D」にはいくつかのミュージカル・シーンが強引な形で挿入されていた。全体のハードボイルドな雰囲気からすると、これらのミュージカル・シーンは相容れなかった。
インドのギャング映画は概して言語が難しい。マフィア独特の言い回しや俗語などがあるからだ。だが、この映画のヒンディー語は、標準ヒンディー語に比較的近いもので、分かりやすかった。「D」独特の技法として、登場人物同士の会話が途中で音楽にかき消されるというものがあった。そのような手法が何度も使用されていた。手抜きにも思えたが、「映画らしい工夫」としておこう。
一般に「映画らしい映画」と言った場合、「インド映画らしくない映画」ということになってしまうのだが、「D」は、「映画らしい映画」かつ「インド映画っぽい映画」であった。実在の大物マフィアの半生をベースにした作品として見ても面白い。
インドでは10年ごとに国勢調査が行われており、最新の国勢調査は2001年2月に行われた。そのデータによると、インドの全人口は10億2861万328人とのことである。
ところが、6月2日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に、人口に関して気になる記事が載っていた。「6億7千万人の有権者の内、2500万人は偽物」という題名である。この記事の根拠は、簡単な算数に基づいている。
2001年2月の国勢調査では、15歳以上の人口は6億6500万人となっている。ところが、3年後の2004年に行われた下院総選挙の有権者(18歳以上)の数は、6億7100万人に増えていたのだ。インドでは、1000人中8人の人が毎年死亡し、その内4分の3が15歳以上の人であることを計算に入れると、有権者の登録が完了した2004年2月の時点で、インドの有権者数は約6億4600万人になっていなければおかしい計算になる。つまり、約2500万人の有権者がどこかから沸いて出たことになる。この数字を仮に「偽有権者数」としておく。
さらに、1999年に行われた下院総選挙のときのデータも加えてみると、インドの人口の不可解さがさらに浮き彫りになる。1999年の時点で、有権者の数は6億2千万人だった。1999年のときに投票権を持っていた18歳以上の人は、2001年の国勢調査の時点では20歳以上のグループになっていなければならない。だが、2001年の国勢調査で20歳以上の人口は5億6500万人と、大幅に減少している。
州別に見ると、国勢調査の人口と有権者数のギャップが最も激しいのはウッタル・プラデーシュ州。2001年の国勢調査の人口と2004年の下院総選挙の有権者数のデータ比較から算出された偽有権者数2500万人の内、実に1540万人がウッタル・プラデーシュ州に属している。ビハール州がそれに次いで多いが、それでも偽有権者数は370万人。カルナータカ州、オリッサ州、マディヤ・プラデーシュ州などがそれに続くという。
国勢調査の人口と有権者数のギャップの原因を移民に求める考え方もあるが、偽有権者数の多い州の多くは、出稼ぎ労働者や移民を他州に送り出している州であり、この説には説得力がない。ひとつの原因として考えられるのは、2004年の下院総選挙の前に、選挙委員会が有権者の数を徹底的に調査したことだ。2001年の国勢調査で人口のカウントに漏れた人々が、2004年の下院総選挙時の有権者のカウントに入った、と考えることもできる。しかし、1999年の下院総選挙時の有権者数が、2001年の国勢調査のときに大幅に減っていることは、この説の反証となってしまう。結局、国勢調査の人口が正しく、選挙時の有権者数はどこかで不正に水増しが行われていると考えるしかないのだろうか。だが、国勢調査の人口のカウント方法はかなり適当だという話を聞いたことがある。本当かどうか知らないが、人口調査をする人は、手間を省くために村の村長に、「お前の村の人口は何人だ?」と聞いて、「えっと・・・300人くらいじゃな」みたいに適当に答えた数字をそのまま足していくだけらしい。また、まだまだインドには交通が不便な場所に住む人々がたくさんいるし、政府が入っていけない危険地域というのも存在するので、そういう場所の人口を隅々まで数え上げることは不可能に近い。そう考えると、国勢調査で示された人口は、予想されうる最小限の数字と受け止めるしかないように思える。もしかしたら有権者数の方が、国勢調査よりも実際的な問題に関連しているため、より正確な数字に近付いているかもしれない。それでも、既にインドの人口が中国の人口を越えている、なんてことはないとは思うが・・・。
ただ、国勢調査の人口と有権者数のギャップの原因において、僕がひとつ仮説として挙げたいのは、インド人の年齢に対する考え方の曖昧さである。経験上、インド人は複数の年齢を使い分けていることがけっこうあるように思う。実際の生年月日と、パスポートなどの公式文書に載っている生年月日に開きがある場合があるのだ。ある人にその理由を尋ねたら、「父親が、私に教育を早く受けさせるために、実際よりも年上の年齢を公的な年齢とした」と答えていた。農村部ではこういうことがよく行われるらしい。インドには戸籍がないので、年齢などは自己申告制になってしまわざるをえないようだ。また、不幸なことだが、自分の生まれた正確な年や月日が分からない人なんて、インドにはたくさんいる。そういう人は、適当に好きな数字を自分の生年月日にしてしまっている。それを考えると、年齢別に緻密にデータを比較していく上記の方法は、インドではあまり役に立たないことになる。インドの正確な人口を測ることは困難である上に、年齢別の比較も大して役に立たないことは、データによるインドの概観がいかに難しいかの一例となるだろう。それにしても、インド人の年齢を言い当てるのは非常に難しかったりする・・・。「その顔で二十歳かよ!」とか・・・。
| ◆ |
6月5日(日) Koi Mere Dil Mein Hai |
◆ |
暑くて暑くて何もやる気が出ない最近だが、時々夕方ににわか雨が降るようになったので、そういう日はちょっと涼しくなる。今日も午後に雨が降ったため、ちょっと涼しくなった。よって、グルガーオンのPVRメトロポリタンまで映画を見に出かけた。今日見た映画は、新作ヒンディー語映画「Koi
Mere Dil Mein Hai」である。
「Koi Mere Dil Mein Hai」とは、「誰かが私の心の中にいる」という意味。監督はディーパク・ラームセー、音楽はニキル・ヴィナイ。キャストは、プリヤーンシュ・チャタルジー、ディーヤー・ミルザー、ラーケーシュ・パーパト、ネーハー、カダル・カーン、リーマー・ラーグー、サダーシヴ・アムラープルカル、イムラーン・カーン、ヒマーニー・シヴプリー、リター・バハードゥリー、ディネーシュ・ヒーングなど。
| Koi Mere Dil Mein Hai |
 大企業ヴィクラム・インダストリーズの御曹司、ラージ(プリヤーンシュ・チャタルジー)はプレイボーイな生活を送っていた。父親のヴィクラム(カダル・カーン)と母親(リーマー・ラーグー)は、ラージの縁談を、友人でやはり大富豪のゴーレー氏(サダーシヴ・アムラープルカル)の一人娘、シムラン(ディーヤー・ミルザー)と取りまとめる。最初は拒否するラージであったが、母親の説得に負け、シムランと結婚することを了承する。ところが、ラージは妹ソーニーの家庭教師としてやって来たアーシャー(ネーハー)に一目惚れしてしまう。だが、アーシャーはラージを無視し続けていた。【写真は左から、プリヤーンシュ・チャタルジー、ディーヤー・ミルザー、ラーケーシュ・バーパト、ネーハー】 大企業ヴィクラム・インダストリーズの御曹司、ラージ(プリヤーンシュ・チャタルジー)はプレイボーイな生活を送っていた。父親のヴィクラム(カダル・カーン)と母親(リーマー・ラーグー)は、ラージの縁談を、友人でやはり大富豪のゴーレー氏(サダーシヴ・アムラープルカル)の一人娘、シムラン(ディーヤー・ミルザー)と取りまとめる。最初は拒否するラージであったが、母親の説得に負け、シムランと結婚することを了承する。ところが、ラージは妹ソーニーの家庭教師としてやって来たアーシャー(ネーハー)に一目惚れしてしまう。だが、アーシャーはラージを無視し続けていた。【写真は左から、プリヤーンシュ・チャタルジー、ディーヤー・ミルザー、ラーケーシュ・バーパト、ネーハー】
一方、ドバイでプレイガールな生活を送っていたシムランは、歌手を目指す純朴な若者サミール(ラーケーシュ・バーパト)に恋をする。シムランはあの手この手でサミールを誘惑するが、全て失敗に終わった。シムランはサミールを追ってインドに帰ることを決意する。
空港にシムランを迎えに来たラージ。シムランはサミールと共に空港に降り立った。しかし、サミールが到着ロビーに現れた途端、アーシャーが飛び出してきて2人は抱きつく。実はサミールとアーシャーは婚約を交わした仲だった。その様子を見て、ラージとシムランはショックを受ける。お見合いで出会ったラージとシムランは、お互いの好きな人が偶然に恋仲であることを知る。そこで彼らは、自分たちの結婚を破談にし、サミールとアーシャーの仲を裂く策略を立てる。まずは第一作戦が成功し、ラージとシムランの結婚はなかったこととなる。
次に、ラージは、アーシャーの家が貧しいことに目を付け、無職だったアーシャーの兄を自分の会社に就職させ、アーシャーに高価な贈り物をし、彼女の家族を味方にする。そしてアーシャーに結婚を申し込む。ところが、アーシャーは頑なに拒否していた。一方、シムランは友人の音楽プロデューサーにサミールを紹介し、彼のCDデビューを決定させる。サミールはシムランの誘惑を何とか拒みながらも、自身の成功に酔い始める。アーシャーは、シムランと一緒にいるサミールの姿を見て不信感を募らせ、やがてサミールと絶交する。そしてラージとアーシャーの結婚が決まった。
ところが、作戦が成功したと同時に、ラージもシムランも不思議な焦燥感に駆られるようになる。実はラージはシムランのことが好きであることに気付き、シムランもラージのことが好きであることに気付いた。だが、お互い言い出せなかった。ラージとアーシャーの結婚式の日が来てしまった。落ち込んだサミールは、最後の別れを言いにアーシャーを訪ねる。アーシャーはサミールに罵声を浴びせかけるが、そこで彼はシムランが泣いているのを見つける。
ラージとアーシャーの結婚式は完了する。だが、ラージはその夜アーシャーに、自分は実はシムランのことが好きであることを打ち明ける。と、実はアーシャーだと思っていた花嫁は、シムランだった。そこへラージとシムランの家族が現れる。ラージとシムランの本心を聞いた家族は、密かにアーシャーとシムランを入れ替えたのだった。こうして、ラージとシムラン、サミールとアーシャーはお互いにお互いの好きな相手と結婚することができた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
近年稀に見る駄作。駄作だろうとは思っていたが、ここまで僕の怒りを買ったインド映画は久し振りだ。なるべく駄作は見ないように、最近は見る映画をよく選んで来たのだが・・・。
序盤は古風なインド映画のノリ。大富豪の御曹司と、これまた大富豪の娘が、両親から結婚話を持ちかけられる、という出だしである。僕は、これだけでは最低の評価は与えない。なぜなら、使い古されたプロットではあるが、インド映画の一番インド映画らしい魅力が引き出されることが多いからだ。インターバル直前には、ラージとシムランの結婚が破談となり、いよいよ2人はサミールとアーシャー仲を裂く計画に乗り出すところとなる。この時点では、もしかしたら楽しい映画かも、と思い始めていた。しかし、後半は見ていてムカムカしてくる最悪の展開だった。ラージとシムランの手口が卑怯であるし、サミールとアーシャーがあまりに簡単に罠に引っかかってしまうからだ。そして、サミールとアーシャーの仲が計画通り破綻すると、今度はラージとシムランは、やっぱりお互いのことが好きだったと思い始める。他人の恋愛をぶち壊しておいて、なんと身勝手な・・・。主人公に共感できないインド映画は、最低の評価を下さざるをえない。
ラージとシムランは上流階級、サミールとアーシャーは中流階級という設定になっていたが、サミールの身寄りはいないし、アーシャーの家庭では毎月の家賃支払いにも困るほどだったので、後者2人は下位中産階級ぐらいの生活レベルであろう。この映画は、上流階級による貧しい男女への執拗ないじめとしか言いようがなかった。サミールとアーシャーの仲を裂く計画を立てているときの、ラージとシムランのセリフは酷かった。「私たちは上流階級、あの2人は中流階級。私たちが貧しい人たちと結婚してあげることで、彼らの救済にもなるでしょう。」
役柄が役柄であったため、主演のプリヤーンシュ・チャタルジーとディーヤー・ミルザーは、はっきり言って悪役に近い印象を受けた。しかも悪役よりも悪い悪役だ。自分が悪いことをしているという自覚がほとんどないからだ。ただ自分の自尊心を満たすためだけに、他のカップルの仲を裂くとは、今までのインド映画のヒーロー・ヒロインのモラルからは考えられない。インド映画のヒーロー・ヒロインは、両親や社会慣習の妨害に遭いながらも、それに敢然と立ち向かうはずではなかったのか。プリヤーンシュとディーヤーは、演技力云々前に、この映画に出演することで株を下げてしまったと思う。一方、悲劇の貧乏人カップル、サミールとアーシャーを演じたラーケーシュ・ブーパトとネーハーは、ほとんど無名の俳優であるし、あまり将来性がなさそうだった。
ディーヤー・ミルザーの不必要なお色気シーンが多かったのも気になった。洗車しているときに、水や洗剤を自分の身体にかけて「ウッフ〜ン」とか・・・。ちょっとディーヤーの将来に不安を感じた映画であった。
ミュージカル・シーンにはけっこう力が入っていたと思う。ただ、最後のラージとアーシャーの結婚式では、なぜか「Dilwale Dulhania
Le Jayenge」(1995年)の有名な曲「Mehendi Laga Ke Rakhna」に合わせたミュージカルがあった。どういう効果を狙ったものか不明だった・・・。
「Koe Mere Dil Mein Hai」はおそらく1週間で上映終了となる運命であろう。全く見る価値のない映画である。
インドのアニメ産業がかなり成熟しつつあることは、最近時々取り沙汰されている。インドは、高いIT技術力、英語話者の多さ、安い人件費などの理由から、人海戦術にならざるを得ないアニメーションのアウトソーシング先として注目を集めている他、世界最大の映画大国という土壌があるため、アニメーション生産国/消費国としても、急成長が期待されている。2005年の世界のアニメーション産業の規模は500億〜700億USドルになるとされている。2004年の時点でインド国内のアニメーション産業はわずか5億5千万USドルだった。だが、インドのアニメーション産業は2008年までに飛躍的に成長し、150億USドル規模にまでなると予想されている。インドのアニメというと、日印合作「ラーマーヤナ」(1999年)や、2005年アカデミー賞アニメ部門ノミネート作品候補に選ばれた「The
Legend of Buddha」(2004年)などが思い浮かぶ(2004年12月6日の日記を参照)。
最近少し話題になっているのが、「Hanuman」というアニメである。題名の通り、「ラーマーヤナ」で大活躍する猿の将軍ハヌマーンを主人公にしたアニメだ。制作はサハラ・ワンとパーセプト・ピクチャー・カンパニー。サハラ・ワンは大手TV局で、映画制作にも進出しており、最近では「Netaji
Subhash Chandra Bose : The Forgotten Hero」(2005年)を制作している。パーセプト・ピクチャー・カンパニーは、「Phir
Milenge」(2004年)などを制作した会社だ。実際にアニメを担当したのは、VGサーマント氏率いるアニメ会社、シルバートゥーンズ社。予算は4000億ルピー。どうやら、この「Hanuman」は初のインド国産アニメということになるらしい。上に挙げた「ラーマーヤナ」や「The
Legend of Buddha」は外国から財政的・技術的援助を受けており、純国産とは言いがたい。
「Hanuman」は、ハヌマーンの子供時代から、ラーム王子の軍勢に加わってランカー島を攻略するまでを描いた90分の作品のようだ。特に子供時代のハヌマーンが見所で、まるでベイビー・クリシュナのように愛らしい悪戯っ子として描写がされるらしい。

6月5日付けのサンデー・エクスプレス・アイに掲載されていた
「Hanuman」のベイビー・ハヌマーンの絵
ハヌマーンは一般に、風神バヴァンとアプサラー(天女)アンジャナーの間に生まれたとされ、マールティ(風の子)と呼ばれている。だが、このアニメの中ではサーマント監督の意向によりシヴァ神の化身とされるようだ。ハヌマーンは、「大きな潜在能力を持っていながら、それに気付いていない」存在の象徴とされる。ハヌマーンは、海を越えて羅刹王ラーヴァンの住むランカー島に行くだけの超人的力が自分にあることを知らなかったし、そういう自信もなかった。しかし、瞑想することによりハヌマーンは自身の力に覚醒し、ランカー島へ渡って大活躍することになる。こういう経緯があるため、ハヌマーンは本番に最大限の力を発揮しなければならない戦士やスポーツ選手の信仰を受けると同時に、航海の安全を司る神ともされる。「Lagaan」(2001年)でも、クリケットの試合が始まる前に「ジャイ!バジラングバリ!」とハヌマーンへの祈りが捧げられていた(バジラングもハヌマーンバリの別名)。ハヌマーンが「西遊記」の孫悟空のモデルになったという説は有名である。
ケーララ州を拠点とするトゥーンズ・アニメーションが、「The Adventures of Hanuman」という似たようなTV向けアニメ・シリーズを制作したというニュースも見つけたが、これは別のアニメのようだ。絵柄から判断する限り、「Hanuman」の方がキュートだ。

「The Adventures of Hanuman」
瞑想するハヌマーン
他に、クリシュナを主人公にした「Gopal」というアニメも制作中のようだ。アニメを制作しているのはバンガロールを拠点とするジャードゥーワークス社。こちらもTV向けで、米国で放映されるとか。2003年12月のニュースなので、もう放映されているかもしれない。

「Gopal」のクリシュナ
現在のところアニメ産業のアウトソーシング先として注目を集めつつあるインドは、神話、民謡、童話の宝庫であり、アニメのネタは国内で事足りるという強みがある。だから、アニメ生産国として急浮上してくることは容易に想像できる。だが、僕はインドが将来アニメの巨大市場となることには懐疑的である。なぜなら、インド人はアニメにほとんど親しみがなく、「アニメは子供の見るもの」ぐらいにしか考えていないからだ。日本人はアニメを芸術の域にまで磨き上げたと言っていいが、インド人の大半はアニメの芸術性などほとんど理解しないだろうし、理解しようともしないだろう。ハリウッドの「ファインディング・ニモ」(2003年)などのCGアニメ映画を除けば、デリーの映画館でアニメ映画が上映されたのを見たことがない。冒頭に挙げた「The
Legend of Buddha」は、オスカーのノミネート候補作品にまでなったが、デリーでは一般公開されなかった。「Hanuman」が映画館で上映されるかどうかも微妙である。インドの映画館は、アニメに対して堅く門戸を閉ざしている。もし上映されるとしたら都市部のシネコンであろうが、そういう場所で映画を見られる人は、ある程度の経済力のある家庭に限られる。VCDなどで見ることも可能だろうが、どうせそれらは海賊版なので、それでは表経済にほとんど貢献しないだろう。
一応、ケーブルTVでは多くのアニメが放映されている。カートゥーン・ネットワークでは米国のアニメが放映され、ディズニー・チャンネルではディズニーのアニメが放映され、アニマックスでは日本のアニメが放映されている。子供の頃からTVでアニメに親しんできた世代が大人になれば、インドのアニメ産業が大きく発展することはありうる。子供の頃からアニメを見ていれば、アニメ産業で働くことを志す人が増えるだろうし、大人になってもアニメを普通に見続けるような土壌が形成されるかもしれない。また、大人がアニメを見なくても、巨大な未成年人口を抱えるインドなら、完全に子供のみを対象としてしまってもいいだろう。だが、今のところインドのアニメ産業はアウトソーシングに限られており、国産アニメを国内市場で売って採算が取れるようになるまでは、まだまだ時間がかかると思われる。
ひとつ言えるのは、インドのアニメ産業の発展にはボリウッドの協力が不可欠であることだ。最近の傾向として、ボリウッド映画の途中にアニメが挿入されることが徐々に増えてきた。「Abhay」(2001年)や「Karam」(2005年)では露骨なアニメの挿入があったし、冒頭のクレジット・シーンでアニメを利用していた映画がいくつかあったと記憶している。また、ハリウッドのアニメ映画のヒンディー語吹替版の声優をボリウッドの俳優が務めるということも出てきた。だが、まだまだボリウッドはアニメ産業の発展を全面的にバックアップしているとは言えない。どちらかというとアニメの勃興に慎重な態度を取っているのではなかろうか。
こうして見てみると、インドでは一昔前に比べてアニメに接する機会は大幅に増えているものの、まだまだ「アニメは子供のもの」という固定観念が強く、映画館ではほとんどアニメ映画を上映できない状態となっている。アニメ先進国日本としても、インドのアニメ産業の行く末は気になるところだ。僕ももちろん昔からアニメに親しんできたので、インドでアニメにチャンスが与えられることを期待している。
5月30日〜6月6日まで、1週間の予定でパーキスターンを親善訪問していたインド人民党(BJP)のラール・クリシュナ・アードヴァーニー党首が、カラーチーにてパーキスターン建国の父にして初代大統領ムハンマド・アリー・ジンナー(1876-1948)を「政教分離主義者」と表現したことにより、インドで批判の的となっている。
元々、アードヴァーニー党首のパーキスターン訪問は、パーキスターンからの招待による親善目的のものだった。現在はパーキスターン領となっているカラーチーで生まれたアードヴァーニー党首のパーキスターン訪問は26年振りだった。アードヴァーニー党首は首都イスラマーバードで、パルヴェーズ・ムシャッラフ大統領、シャウカト・アズィーズ首相、クルシード・メヘムード・カスーリー外相らと会談した他、自身の生誕地カラーチーでジンナー廟を訪問した。自分が通った学校や生家の訪問をせずに、ジンナー廟を訪れたというのだから異常である。また、パーキスターン訪問中、アードヴァーニー党首はジンナー元大統領を賞賛する発言を何度かしたと伝えられている。ジンナーは、インドでは「印パ分離独立の元凶」と評価されており、特に「アカンド・バーラト(統一インド)」をスローガンに掲げるサング・パリワール(BJPの親団体)は、ジンナーこそが、ヒンドゥーとムスリムの対立を促し、印パ分離独立の悲劇を生み出した張本人だと考えている。BJP切ってのタカ派として知られるアードヴァーニー党首自身、ジンナー暗殺を謀ったとされ、逮捕状を出された経緯まである。そのアードヴァーニー党首が、ジンナー廟を参拝した上に、ジンナーを賞賛する発言をしたことは、サング・パリワールにとって寝耳に水どころの事件ではなかった。サング・パリワールに所属する民族義勇団(RSS)、世界ヒンドゥー協会(VHP)の指導者や、BJPの政治家たちは、一斉にアードヴァーニー党首を「裏切り者」として糾弾し始めた。元々BJPは、2004年の下院選挙で野党に転落して以来、政治的失敗を何度も重ねてきており、危機的状況を迎えていた。それに加えて、党首自身がジンナーというパンドラの箱を開いてしまったことにより、現行の印パ友好ムードの立役者だったBJPの功績を今一度主張したい考えだったアードヴァーニー党首のパーキスターン訪問は、一転してアードヴァーニー党首の政治生命やBJPの存亡に関わる問題にまで発展してしまった。

パルヴェーズ・ムシャッラフ大統領(左)と、
ラール・クリシュナ・アードヴァーニー党首(右)
ジンナーの略歴は以下の通りである。ムハンマド・アリー・ジンナーは1896年にカラーチーで生まれ、英国に留学して弁護士の資格を取得した。帰国後はボンベイで弁護士として働くが、1906年にダーダーバーイー・ナオロージー(1825-1917)の秘書を務めたことにより、政治の世界に入る。国民会議派に参加し、1913年にムスリム連盟に加入したジンナーは、1916年にムスリム連盟の議長となり、国民会議派とも協調するが、マハートマー・ガーンディー(1869-1948)の反英サティヤーグラハ運動に反対して会議派を脱退した。その後ロンドンに長く滞在したが、1934年にインドに帰国し、分裂していたムスリム連盟の再建に努めた。1940年のラーホール大会で、ジンナーは「ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒は文明も歴史的伝統も全く異なる2つの民族である」という「ニ民族論」を唱え、ムスリム多住地域の分離独立を決議させた。俗に言う「パーキスターン決議」である。ジンナーの尽力によりムスリム連盟の発言力は国民会議派に匹敵するものとなり、第二次世界大戦後、インド総督マウントバッテンにより、インドとパーキスターンの分離独立案が発表され、それが受理された。パーキスターンは、インド独立の1日前、1947年8月14日に独立し、ジンナーが大統領に就任したが、ジンナーは翌年病死してしまう。ジンナーは、パーキスターン建国の功績を讃えられ、「カーイデ・アーザム(偉大なる指導者)」と呼ばれている。

ムハンマド・アリー・ジンナー
アードヴァーニー党首のジンナー発言を巡る論争は、印パ問題が単純に解決できるものではないことを改めて示している。印パ分離独立は両国にとって未だに完全に過ぎ去った歴史ではなく、現在進行中の問題なのだ。アードヴァーニー党首の発言の中で問題となったのは、「ジンナーは政教分離国家パーキスターンの立役者」という言葉と、「印パ分離独立は変更不可能な歴史の現実」という言葉だと思われる。アードヴァーニー党首が本当にそういうニュアンスで発言したのかどうかは今のところ分からないが、少なくともインドではそのような受け止め方をしている。焦点は、ジンナーが政教分離主義者で、かつパーキスターンが政教分離国家か否か、ということと、印パ分離独立の正当性を認めるか否か、ということであろう。ちなみに、「secularism」は時々「世俗主義」と訳されているが、日本語としてあまり意味が伝わってこないので、僕は「政教分離主義」と訳している。
アードヴァーニー党首がジンナーを「政教分離主義者」と呼んだ根拠は、ジンナーが1947年8月11日にカラーチーにおいて行われたパーキスターン憲法制定会議で行った演説である。演説の中でジンナーは、「諸君はパーキスターンにおいて、自由に寺院、モスク、その他の宗教施設へ行くことができる。諸君はいかなる宗教にも、カーストにも、主義にも属することができる。国家がそれに干渉することはない・・・宗教は各人の信条に依るものであるから、宗教的意味合いではなく、国家の一員という政治的意味合いにおいて、時の流れと共に、ヒンドゥーはヒンドゥーであることを意識しなくなり、ムスリムはムスリムであることを意識しなくなるだろう」と述べている。この部分は明らかにジンナーの政教分離主義的思想を表している。だが、ジンナーは一生の内で何度か自身の立場を転換しており、また、パーキスターン建国後すぐに死亡してしまったことで、どういうビジョンを持って国造りをして行きたかったのかが曖昧となってしまったため、彼の評価は一定していない。一定していない、と言うより、ジンナーの思想は時の為政者に、いいように利用されてきたと言っていいだろう。特にパーキスターンがイスラーム国家化した1977年〜88年のジヤーウル・ハク政権時代には、1947年8月11日のジンナーの演説から、彼の政教分離主義的思想が汲み取れる上記の部分が省略されてしまい、「ジンナーはイスラーム国家樹立を望んでいた」とする説が意図的に流布された。だが、現在のムシャッラフ政権は、米国との関係を強化し、対テロ戦争を推進する中で、イスラーム国家としてよりも政教分離国家としてのアイデンティティーを強調したい考えのようだ。よって、アードヴァーニー党首の発言を歓迎している。
一方、インドでのジンナーの評価は、パーキスターンに比べると一定している。ジンナーは庶民の間では、「ラーマーヤナ」に出てくる羅刹王ラーヴァンと同一視されており、一般的な見解においても、自身の権力欲のために、マハートマー・ガーンディーやジャワーハルラール・ネルー(1889-1964)が推し進めた政教分離主義と統一インドの理想をぶち壊した張本人だとされている。インドの政教分離主義が成り立つためには、パーキスターンが政教一致主義の国でなければならない。よって、今まで1947年8月11日のジンナーの演説は無視され、ジンナーはイスラーム至上主義者だとされてきた。アードヴァーニー党首が「ジンナーは政教分離主義者である」と述べたことがいかにインドの潮流に反するものであるかは、以上のことを考えれば容易に納得がいくだろう。
だが、一般の評価がどうであれ、学会ではジンナーを政教分離主義者と捉える見方は既に定着している。その転機となったのは、1985年にアーイシャー・ジャラールによって出版されたジンナーの伝記「The
Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan」である。同書の中で彼女はジンナーを政教分離主義者とは定義していないものの、彼の真の目的はパーキスターン分離独立ではなく、インド国内でのムスリムの発言力強化のためにパーキスターンを言わば脅しのネタとして使用しただけだったと主張した。元々、ムスリム国家建設は、詩人ムハンマド・イクバール(1877-1938)によって提唱され、ケンブリッジ大学に留学していたあるムスリム学生によって「パーキスターン」という名前が与えられたのだが、ジンナーに政治的な切り札として利用されることにより、それがジンナーの思惑以上の迫力と現実味を帯びてしまい、遂には印パ分離独立という結果となってしまったというのが大体の流れのようだ。アードヴァーニー党首の発言も、オリジナルな見解ではなく、学問的潮流に乗っ取ったものだったのだが、サング・パリワールのイデオロギーとは相容れず、今回の問題を引き起こしてしまったようだ。BJPの政治家たちの中にも、アードヴァーニー党首を擁護する者はほとんどいない。ヴァージペーイー元首相のみが「ジンナーは政教分離主義者だ」と党首の発言を支持している。また、国民会議派は「触らぬ神に祟りなし」の慎重な態度を取っている一方、他の政党は各種各様の反応を示している。インド共産党マルクス主義派(CPI(M))のジョーティ・バス元西ベンガル州州首相は、「1947年8月11日のジンナーの演説のことはともかく、1946年8月にカルカッタで発生し、何千人もの人々が惨殺されたコミュナル暴動の責任はジンナーにある。私はこの目でその暴動を見た」と述べている。
印パ分離独立に対するスタンスも、インドとパーキスターンでは違いがあり、アードヴァーニー党首はジンナーの評価と連動する形で、そのデリケートな問題に触れてしまった。インドは、印パ分離独立を「不幸な出来事」と考えており、いつかその不幸を克服してインドが再統一されるという夢を少なからず持っている。特にサング・パリワールは「アカンド・バーラト(統一インド)」のスローガンを掲げている。一方、パーキスターンは当然のことながらムスリムのための国家であるパーキスターン建国を「輝かしい成果」として捉えている。パーキスターンはインドと比べると、そのアイデンティティーの歴史は短く、どうしても建国の正当性と国家の独自性を強調していかなければならないという弱みを持っている。アードヴァーニー党首の「印パ分離独立は変更不可能な歴史の現実」という発言は、パーキスターンの正当性を認めるものであり、サング・パリワールのイデオロギーに反する。よって、サング・パリワールの指導者たちは、アードヴァーニー党首を「裏切り者」呼ばわりし、「パーキスターンに帰れ」とまで罵った。
第三者の目でアードヴァーニー党首の発言を見ると、その中におかしなことはないばかりか、印パ平和プロセスが進展する中で、隣国パーキスターンを思いやった、非常に積極的で革新的な発言だと評価できる。しかし、ジンナーと印パ分離独立の正当性を評価してしまうと、印パ分離独立時に発生した暴動の責任をジンナーとパーキスターンになすりつけることができなくなったり、ジャワーハルラール・ネルー元首相の評価にも影響が及んできたり、カシュミール問題にも関係してきたりと、いろいろ連鎖的な問題も抱えているので、インドにとって、できることなら触れたくなかった非常に厄介な議論が沸き起こってしまったという感じだ。現在を重視し、未来へ向かっていくためには、過去を完全に過去としてしまわなければならないこともある。だが、言うのはたやすいが、過去が現在と結びついている以上、それを実現するのは困難なようだ。この種の問題は、日本にとっても他人事とは言えないだろう。
ラヴィーンドラナート・タゴールと並んで有名なベンガルの文学者、シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーイ(チャタルジー)といえば、「Devdas」の原作者として有名である。「Devdas」は何度も映画化されてきたが、最近では2002年のシャールク・カーン主演「Devdas」が有名だ。そのシャラトチャンドラの文学が、再び映画化されて本日より公開された。「Parineeta」である。やはりこの作品も過去に何度も映画化されてきており、ヒンディー語では、1953年にビマル・ロイ監督が同名の映画を発表している。ビマル・ロイ監督は、ディリープ・クマール主演の「Devdas」(1955年)も監督している。今日は早速「Parineeta」を見にPVRアヌパムへ行った。話題作のようで、映画館は久々に隅から隅まで満席だった。
「Parineeta」とは、「既婚の女性」という意味。監督は新人のプラディープ・サルカール、プロデューサーと脚本は、「Munnabhai MBBS」(2003年)で脚本を担当したヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー、音楽はシャーンタヌ・ミトラ。キャストは、ヴィディヤー・バーラン(新人)、サンジャイ・ダット、サイフ・アリー・カーン、ディーヤー・ミルザー、ライマー・セーン、サビヤサチ・チャクラバルティー、アチユト・ポートダルなど。レーカーがアイテム・ガールとして特別出演。
| Parineeta |
 1962年、カルカッタ。大富豪ナヴィーン・ロイ(サビヤサチ・チャクラバルティー)の一人息子、シェーカル(サイフ・アリー・カーン)は、ミュージシャンになることを夢見て仲間と共に音楽に没頭していた。シェーカルは、隣のグルチャラン(アチユト・ポートダル)の家に住むラリター(ヴィディヤー・バーラン)と幼馴染みだった。ラリターは幼い頃に両親を亡くし、親戚のグルチャランの家に引き取られてきた。グルチャランは、ラリターを実の娘コーヤル(ライマー・セーン)同様かわいがっていた。ラリターは、シェーカルの口利きにより、ナヴィーン・ロイのオフィスで秘書として働いていた。シェーカルとラリターの仲は、兄妹以上の結びつきで、シェーカルは自分の小遣いを自由に使うことをラリターに許していた。【写真は、サイフ・アリー・カーン(左上)、サンジャイ・ダット(右上)、ヴィディヤー・バーラン(下)】 1962年、カルカッタ。大富豪ナヴィーン・ロイ(サビヤサチ・チャクラバルティー)の一人息子、シェーカル(サイフ・アリー・カーン)は、ミュージシャンになることを夢見て仲間と共に音楽に没頭していた。シェーカルは、隣のグルチャラン(アチユト・ポートダル)の家に住むラリター(ヴィディヤー・バーラン)と幼馴染みだった。ラリターは幼い頃に両親を亡くし、親戚のグルチャランの家に引き取られてきた。グルチャランは、ラリターを実の娘コーヤル(ライマー・セーン)同様かわいがっていた。ラリターは、シェーカルの口利きにより、ナヴィーン・ロイのオフィスで秘書として働いていた。シェーカルとラリターの仲は、兄妹以上の結びつきで、シェーカルは自分の小遣いを自由に使うことをラリターに許していた。【写真は、サイフ・アリー・カーン(左上)、サンジャイ・ダット(右上)、ヴィディヤー・バーラン(下)】
ロイ家では、シェーカルの結婚話が持ち上がっていた。ナヴィーン・ロイは、大富豪ターティヤー家の娘ガーヤトリー(ディーヤー・ミルザー)とシェーカルの縁談を勝手に進める。だが、シェーカルはこの結婚に乗り気ではなかったし、傲慢な素振りのガーヤトリーのことも好きではなかった。
グルチャラン家の近所に、ロンドンから帰って来た実業家ギリーシュ(サンジャイ・ダット)がやって来た。陽気なギリーシュはすぐに近所の人気者となり、ギリーシュはラリターに一目惚れする。
一方、グルチャランの家では、借金が大きな問題となっていた。グルチャランは古いハヴェーリー(邸宅)に住んでいたが、ナヴィーン・ロイに1万5千ルピーの金を借りるときに、少なくとも20万ルピー以上の価値があるそのハヴェーリーを担保にしていた。グルチャランはナヴィーン・ロイの人柄を信じていたが、ナヴィーン・ロイはビジネスマンであった。彼は、グルチャランの家をヘリテージ・ホテルにする計画を密かに進めていた。その計画を知ったラリターは、グルチャランに早く借金を返すよう促すが、お人好しのグルチャランは真剣に受け止めなかった。
困ったラリターは、シェーカルに金を借りに行く。だが、シェーカルは忙しくて取り合ってくれなかった。グルチャラン家の借金の話を耳に挟んだギリーシュは、グルチャランを自分の会社の重役にし、数年分の給料を先払いした。そのお金でグルチャランは借金を返済することができた。だが、シェーカルはその話を聞いて、元々ギリーシュに抱いていた嫉妬心を爆発させる。だが、ラリターはシェーカルの前で泣き出し、彼が勘違いしていることを伝える。シェーカルもラリターの涙に怒りを沈め、彼女を抱きしめる。その夜は、結婚式を挙げた夫婦が必ず幸せになれる吉日だった。2人はお互いに首飾りを掛け合い(結婚の契りの印)、ベッドに横たわる。
てっきりグルチャランは借金を返すことができないだろうと考えて、勝手にヘリテージ・ホテルの計画を進めていたナヴィーン・ロイは、借金を返したグルチャラン家を恨み、ギリーシュを敵視するようになる。彼はラリターがギリーシュに身体を売って金をせしめたのだと考え、ラリターに対し、「この売奴女め!」と罵声を浴びせかけ、彼女をクビにする。さらに、ナヴィーン・ロイはグルチャラン家との間に高い壁を作らせる。これを見たグルチャランは心臓発作を起こし、倒れてしまう。全てはシェーカルが仕事のためにダージリンへ行っていた間に起こった。
ダージリンから帰って来たシェーカルは、父親から、ギリーシュがグルチャラン一家をロンドンへ連れて行くつもりであることを聞く。グルチャランの病気を治せるのはロンドンの医者だけだという。また、これを機にギリーシュとラリターの婚約が決まったとの話も聞く。絶望するシェーカル。ギリーシュとグルチャラン一家は、ロンドンへ向けて旅立つ。その後、グルチャランはロンドンで死去し、ギリーシュとラリターが結婚したとの知らせが入ってきた。ラリターを失ったシェーカルは、本格的に父親の仕事を手伝うようになり、ガーヤトリーとの結婚も承諾する。
シェーカルとガーヤトリーの結婚式の日。シェーカルはまだ悶々とした気持ちに苛まれていた。その日、ラリターたちもロンドンから戻って来た。シェーカルはラリターと会うが、「私に何で触ってくれないの?私が結婚しているから?結婚しているから私には何の恥らいも恐れもないわ・・・」と誘惑する彼女の恥知らずの発言に怒り、彼女を殴って立ち去る。だが、シェーカルを訪れたギリーシュから真実を聞く。ギリーシュはラリターに何度もプロポーズしたが、彼女は「私は既婚者です」と言って拒んだという。だから、ギリーシュは仕方なく妹のコーヤルと結婚したのだった。ギリーシュはラリターが誰と結婚したか分からなかったが、彼女がグルチャラン家の権利書をシェーカルに渡そうとしたことから、それが誰だか悟ったという。シェーカルも彼女を殴ってしまった自分の過ちに気付く。そこを訪れたナヴィーン・ロイは、グルチャラン家の権利書を手に入れたことに喜ぶ。だが、シェーカルは「あなたは全てを手に入れたが、自分の息子を失った」と言い、気が狂ったように、グルチャラン家との間に造られた壁を壊し始める。ナヴィーン・ロイは必死で止めるが、他の皆はシェーカルを応援する。「シェーカル、壁を壊せ!壁を壊すんだ!」壊れた壁の先には、ラリターが待っていた。こうして、シェーカルはラリターと改めて結婚式を挙げたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
新人監督の作品とは思えないほど完成された映画。ストーリーの細かい部分で不明な点がいくつかあったものの、「Devdas」に匹敵するほど感動できた。特に、「Devdas」がアンハッピー・エンドである一方、「Parineeta」はハッピーエンドで終わるので、見終わった後の爽快感がより強い。1960年代のカルカッタの雰囲気も、忠実な再現かどうかは置いておいて、ユニークでよかった。もちろん、シャラトチャンドラの生没年は1876年〜1938年なので、原作では20世紀初頭の英領インド時代のカルカッタが舞台となっている。
やはり「Parineeta」は「Devdas」との比較なしでは語れないだろう。隣家同士の幼馴染みの男女の恋愛という点で、「Devdas」と非常によく似た設定であるし、主人公の男女や、その家族の性格にも共通点が多い。顕著に違う点と言えば、「Devdas」では、デーヴダース、パーロー、チャンドラムキーという男1人、女2人の三角関係が主軸となっている一方、「Parineeta」では、シェーカル、ラリター、ギリーシュという男2人、女1人の三角関係が主軸になっていることが挙げられる。また、デーヴダースは最後、死ぬ間際にパーローの嫁ぎ先に辿り着くが、パーローを一目見ること叶わず一人孤独に死んでしまう。だが、シェーカルは、全身の力を振り絞って壁を破壊し、ラリターを手に入れる。デーヴダースはパーローを失った悲しみに自暴自棄になってしまうが、シェーカルは我を失わず、またギリーシュの助言を得ることができたために、恋愛を成就させることができたと言っていいだろう。ただ、最後、シェーカルが壁を破壊しているとき、破片が飛んでラリターの顔に傷が付くのは、「Devdas」を意識しすぎだと思った。「Devdas」では、デーヴダースがパーローの額にわざと傷を付け、自分たちの思い出の印とする。
ストーリーの中で一番不明だったのは、ギリーシュがグルチャラン家の借金の問題を知る過程である。ギリーシュは姉からその話を聞くのだが、姉は一体誰から聞いたのだろうか?また、借金を払わないとグルチャランのハヴェーリーがナヴィーン・ロイに取られてしまうというタイミングでギリーシュがそれを知るのも話が出来すぎだ。その他にも、強引な展開がいくつかあった。だが、見事だったのは、ラリターの「既婚」の意味合いが、ストーリーの冒頭と最後で180度変わることだ。
この映画の最大の見所は何と言ってもヒロインのラリターを演じたヴィディヤー・バーランである。彼女はこの映画がデビュー作となるのだが、既に大女優の風格が漂っていた。ヴィディヤーは40本以上のTVCMに出演した経歴を持つCM女優であり、既に一部では名の知られた存在だったようだが、この映画により大ブレイク間違いなしだ。どうやら早くも数本の映画のオファーを受けているとか。ヴィディヤーの演技で特に光っていたのは、シェーカルに「シャーディーシュダー・フーン・・・イスリエ・トー・・・ナ・シャルム・ハェ・ヤー・ナ・ダル・・・(私は既婚よ・・・だからこそ・・・恥らいもなければ恐れもないわ・・・」とつぶやくシーンだ。このシーンでの彼女の目の使い方や、セリフの間の開け方などは、並みの女優とは思えなかった。これから絶対に急成長する女優であろう。ちなみに、ヒロインの名前は「Lolita」とベンガリー語風に綴られているが、ヒンディー語風に「ラリター」にした。
サイフ・アリー・カーンは、ヴィディヤー・バーランに押され気味ではあったが、貴公子風の風貌を活かしてなかなかの演技をしていた。サンジャイ・ダットは、はっきり言って不必要だったのではなかろうか?ギリーシュの役を彼が演じる必要性を感じなかった。ディーヤー・ミルザーは、タカビーなお嬢様を生意気に演じていた。ライマー・セーンも脇役ながら存在感を示していた。あと、レーカーが、ミュージカル「Kaisi
Paheli Zindagaani」でダンス出演していた。レーカーの踊りは・・・ちょっと気持ち悪かった・・・・。
「Parineeta」の音楽と歌詞はかなり心に残るものだった。シェーカルとラリターが共同制作する「Piyu Bole」、シェーカルがダージリンへ行く途中のトイ・トレインで歌う「Kasto
Mazza」、レーカーが踊る「Kaisii Paheli Zindagaani」など。「Piyu Bole」では、シェーカルとラリターが歌詞の掛け合いをする。「心の話は、心の話は」→「心に置いておきなさい」→「唇を閉じたら、唇を閉じたら」→「目が全部しゃべっちゃったわ」など。「Kasto
Mazza」では、冒頭に謎の言語の歌詞がある。ダージリン付近で話されている言語だと思われる。その次にヒンディー語の歌詞が続き、「風よ、轟け、あの人はどこにいるか、僕に聞いてくれ、あの人は花に、つぼみに、そして僕の夢の中の隅々にいるんだ」などという意味になっている。
映画中、ギリーシュたちが日本のこっくりさんみたいな遊びをしていたのが驚いた。インドにもこっくりさんがあるのか・・・!もしかして万国共通なのか?ギリーシュがやっていたのは、机の上にアルファベットを書いた紙を敷き、その上にコインを置いて、魂を呼び寄せる。魂がコインに宿ると、質問に答えてくれる。だが、結局そのとき行われていたこっくりさんでは、ギリーシュが机の下から磁石を使ってコインを操作していた、というオチだった。
60年代ということで、エルビス・プレスリーの曲が何度か登場した。その他、ラヴィーンドラナート・タゴールの楽曲が印象的に使われていた。
「Parineeta」の舞台はカルカッタで、ダージリンが少しだけ出てくる。カルカッタのヴィクトリア・メモリアル、ハーウラー橋、カーリー寺院や、ダージリンのトイ・トレインなどが出てきた。ギリーシュたちがムーラン・ルージュというダンス・クラブへ行くシーンがあったが、それは実在のものであろうか?
カルカッタが舞台になっているものの、言語はヒンディー語。時々ベンガリー語が出てきたが、基本的に登場人物がしゃべるのはヒンディー語オンリーである。ディーヤー・ミルザーだけは見栄を張って英語をよくしゃべる。
シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーイ原作の「Parineeta」は、60年代のカルカッタの雰囲気と、驚異の新星ヴィディヤー・バーランの演技が見所の優れた映画である。
もうすぐスターTVで「Kaun Banega Crorepati 2」が始まるらしい。「Kaun Banega Crorepati(誰か億万長者になるか)」は、日本で人気を博した「クイズ・ミリオネア」のインド版である。アミターブ・バッチャンが司会進行とクイズ出題役を務め、インド人にも大人気の番組だったが、数年前に何らかの理由により打ち切られた。バッチャンは当初、家族からこの番組への出演を断るように言われていたらしいが、それを押し切って出演したという。そのおかげでバッチャンは庶民と接する機会が生まれ、「私の人生の中で最良の失敗だった」と発言している。また、同番組のおかげで、当時落ち目だったアミターブ・バッチャンは人気を取り戻し、現在も国民的な人気を維持している。「Kaun
Banega Crorepati 2」でももちろんアミターブ・バッチャンが出演する他、視聴者による電話を使った投票という新オプションが導入されたり、賞金額が増額されたりして、パワーアップして帰って来るようだ。噂によると8月から始まるようだが、既に電話投票は実験的に始まっている。
ところで、アミターブ・バッチャンと言えば、インドに住む人なら誰でも知っている有名人である。それは日本人などの外国人にも当てはまる。インドに来てすぐの日本人でも、「背が高くて白髭の人」と伝えるだけで、すぐに「ああ、あのおっさんね」と思い付く。僕の父親がインドに旅行しに来たとき、ホテルのTVにちょうどアミターブ・バッチャンが映ったので、「これがインドで一番人気のある俳優だよ」と教えたら、「この白髭がか?」と返答された憶えがある。アミターブ・バッチャンの白髭はそれほど目立つのだろう。彼の髭は既になくてはならないトレードマークとなっている。だが、アミターブ・バッチャンの髭には、大きな秘密が隠されていると言ったら驚くだろうか?その秘密は、インド最大の秘密と言っても過言ではない。
まずはアミターブ・バッチャンの写真を見ていただきたい。

アミターブ・バッチャン
次に、インド初代首相ジャワーハルラール・ネルーの写真を見ていただきたい。

ジャワーハルラール・ネルー
バッチャン家とネルー・ガーンディー家の間に親交があったことは有名である。その話は2004年11月4日の日記に詳述したが、ここで再び簡単に説明しておく。アミターブ・バッチャンの「父親」、ハリヴァンシュラーイ・バッチャン(1907-2003)は有名な文学者であり、ジャワーハルラール・ネルーとも親しかった。その親交は1942年に女流作家で独立運動家のサロージニー・ナーイドゥ(1879-1949)が2人を引き合わせてから始まったと言われている。ハリヴァンシュラーイ・バッチャンは1926年にシヤーマーという女性と結婚しているが、彼女は1936年に死亡しており、1942年にスィク教徒の26歳の女性、テージー・スーリーと再婚した。テージーは美人で、年齢がほぼ同じだった、ネルーの娘のインディラー・ガーンディー(1917-1984)と親しく、ネルーの家によく出入していたという。ハリヴァンシュラーイ・バッチャン夫妻は1942年3月26日に行われたインディラーとフィーローズ・ガーンディーにも出席した。ハリヴァンシュラーイとテージーの間には2人の息子が生まれる。アミターブとアジターブである。アミターブは1942年10月11日に生まれ、アジターブはその5歳年下、つまり1947年生まれだった。一方、インディラーとフィーローズも2人の息子をもうかる。1944年に長男のラージーヴが、1946年に次男のサンジャイが生まれた。アミターブ、アジターブ、ラージーヴ、サンジャイは、ちょうど年齢が近かったこともあり大の仲良しとなった。ネルー・ガーンディー家とバッチャン家は家族ぐるみの付き合いをするようになった。やがてアミターブは映画スターに、アジターブはロンドンへ渡って実業家に、ラージーヴはインディアン・エアラインズのパイロットに、サンジャイは政治家になったが、4人の友情は変わらなかった。
ここで、1942年という年に注目してもらいたい。この年にハリヴァンシュラーイ・バッチャンはネルーと出会い、テージーと結婚している他、インディラーとフィーローズの結婚も行われ、しかもその年の10月11日にアミターブが生まれている。参考までに、人間の一般的な妊娠期間は40週、つまり8〜9ヶ月である。また、ネルーの妻カムラーは1936年に死去している。さらに、ネルーはインディラーとフィーローズの結婚に反対していたと言われている。残念ながら、ハリヴァンシュラーイとテージーの結婚が1942年の何月だったのかは情報がないが、ハリヴァンシュラーイとネルーが初めて出会ったのは、インディラーの結婚式の約1ヶ月前だったと言われている。
ここで再び、アミターブ・バッチャンとジャワーハルラール・ネルーの写真を見比べていただきたい。

アミターブ・バッチャン(左)とジャワーハルラール・ネルー(右)
次に、ハリヴァンシュラーイ・バッチャンの写真と、アミターブ・アジターブ兄弟の写真を見ていただきたい。

ハリヴァンシュラーイ・バッチャン

長男アミターブ(左)と次男アジターブ(右)
次男のアジターブは非常に父親に似た顔をしているが、アミターブはどうだろうか?
また、バッチャン家とネルー・ガーンディー家の対立が表面化した際、アミターブ・バッチャンは以下のような意味深な発言をしている。「ガーンディー家はラージャー(王)であり、バッチャン家はランク(民)である。王のみが貧しい者とどういう関係を持つか決定できる。」
これが、アミターブ・バッチャンの髭に隠された秘密である。
ラールー・プラサード・ヤーダヴと言えば、インドで最も有名な政治家の1人である。国民党(RJD)の党首で、ビハール州の州知事を長く務め、現在では中央政府の鉄道大臣に就任している。「老練」という言葉がピッタリの政治的手腕と、ビハール訛りの独特の口調で、庶民から畏敬と失笑の対象となっている稀な人材である。僕は、インドで最も面白い政治家は、ダントツでこのラールー・プラサードだと思っている。「面白い」という言葉にもいろいろ意味があるが、文字通り見ていて面白い政治家である。例えば、今年2月に「Padmashree
Laloo Prasad Yadav」という映画が公開された(映画評はコチラ)。ラールー・プラサードの名前をそのまま題名に使用した、言わばラールーをからかうような映画だったのだが、なんとその映画にラールー自身が特別出演してしまった。頭の堅い政治家にはできない芸当である。以下、僕も畏敬と失笑の念を込め、彼のことをラールージーと呼ばせてもらう。
今年2月にビハール州で州議会選挙が行われたときは、連日ラールージーのニュースが新聞やTVを賑わせていた。しかし最近ラールージーのニュースが減ってしまって退屈な毎日を過ごしていた。そんな中、ラールージーの人形が発売されたという吉報が届いた。ラールージー・ドール!本日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙にラールージー人形の写真が掲載されたことにより、居ても立ってもいられなくなった。欲しい!ラールージー・ドールが欲しい!でもどこに売ってるんだ?

6月14日付けデリー・タイムズ紙
インドで何か特定の物を買うのは、実はけっこう難しい。日本のように流通網や宣伝網が発達していないので、どこの店でも同じ物が手に入るわけではない。勘と経験だけが頼りである。まずは、バサント・ロークのアルチーズへ行ってみた。アルチーズはインド全国にチェーン展開しているギフト・ショップで、誕生日カードやヴァレンタイン・カードなどの他、映画スターのポスター、人形、アクセサリーなどなど、いろいろなギフトを取り扱っている。アルチーズの店舗にもいろいろな規模のものがあるが、近所で一番大きいのはバサント・ロークのものであったため、まずはそこを見てみることにしたのだ。だが、そこにはラールージーはいなかった。
こうなったら玩具屋しかない。デリー・タイムズ紙に載っていた写真でも、ラールージーの背景にはバービーらしき人形が写っていた。バービーを売っているような玩具屋へ行く必要がある。どこへ行ったら確実に手に入るか熟考した結果、グルガーオンの玩具屋へ行くことにした。ひとつ思い当たる玩具屋があった。DTシティーセンターにあるMaya'sという店である。その玩具屋は主に輸入玩具を扱っているが、そこで昔、「Koi...
Mil Gaya」(2003年)に出てきたジャードゥーの人形を買ったことがあった。ジャードゥー人形があったということは、ラールージー人形もある可能性が高い。グルガーオンまでは遠いが、ラールージーに会いたい一心でバイクを走らせた。
僕の直感は正しかった。Maya'sですぐにラールージー人形を発見することができた。ラールージーは透明なビニール袋の中に入っていた。ビニール袋には赤と青の2種類があったが、中身は一緒のようだった。だが、記念に赤と青両方買うことにした。値段は1匹、もとい1ラールージー144ルピー。

赤ラールージーと青ラールージー

ラールージー人形のドアップ
ラールージー人形はかわいい(?)赤ちゃんの姿をしており、白いクルター・パージャーマーを着ている。髪は白髪とも金髪とも取れる色。だが、ラールージー本体に、ラールージーと識別できるようなものはない。袋に「Laluji」と書いてあるだけだ。これでは、人形と袋を常にセットにしておかなければ、この人形をラールージーだと気付く人が少なくなってしまうだろう。

袋に「Laluji」と書かれている
・・・しかし、ラールージー人形にはアレがない!アレが!ラールージーのトレードマークとも言えるアレが見当たらない!これはかなりの欠陥である。何がないかというと、耳毛がないのだ。ラールージーと言えば、あの猛々しい耳毛抜きには語れないのではなかろうか!それともまだ赤ちゃんだからないのか?

本物のラールージーと耳毛の様子
また、ネットに掲載されていたラールージー人形の写真には、気になるものがいくつか写っていた。

ネットで拾ったラールージー人形の写真
まず、ラールージーがランタンを持っている。ランタンは、ラールージー率いる国民党のシンボルマークである。僕の買ったラールージーにはランタンは付いていなかった。また、鉄道大臣を務めていることを暗示するかのように、機関車の玩具が横に置かれている。これはナイスなコンビネーションだ。だが、ラールージーと機関車の裏にいるのは誰だ?やはりインドの政治家だろうか?ラールージー人形に引き続き、これからも政治家の人形が発売されて行くかもしれない。マハートマー・ガーンディー人形とか、けっこう人気が出そうだ。
今年2月にビハール州で州議会選挙が行われたが、獲得議席数が過半数を越える政党や連立党がなく、政治的混乱が続いたため、結局ビハール州は大統領直轄となってしまった。つい最近、ビハール州の州議会選挙のやり直しが行われることが決定された。今年10月〜11月に再選挙が行われる。2月の選挙では敗北してしまったが、次のチャンスで巻き返しを図る老練なラールージーは、このラールージー人形を選挙に大活用する意向を示しているとか。子供たちにこの人形を配って親近感を出すと同時に、子供の頃からラールージー洗脳を始めるようだ。さらに、「しゃべるラールージー人形」の製造まで計画されているという。僕の買ったラールージー人形はしゃべらないが、「しゃべるラールージー人形」は、どこかを押すと「僕はラールー・プラサード・ヤーダヴ。国民党に投票してネ」みたいなことをしゃべるようになるらしい。
ところで、このラールージー人形の売れ行きはそれほど芳しくないらしい。「ラールージー人形は本物ほど売れていない」と題した新聞記事もあった。144ルピーというのは、普通のインド人にとってジョークで買える値段ではないだろう。2匹、もとい2ラールージーも買ってしまった僕はかなりの変人だ。実は買うときちょっと恥ずかしかった。いつかこれがプレミア物になるといいのだが。
| ◆ |
6月15日(水) シャーリーマール・エクスプレス |
◆ |

僕は今まで列車で旅行に出るときは、必ず予約された切符と共に列車に乗り込んでいた。「予約された切符」というのは、「ちゃんと席が確保された切符」という意味だ。インドの鉄道では、外国人旅行者のために各列車各等級に席が数席留保されており、外国人は比較的簡単に鉄道切符を取得することができる。ただし、外国人留学生はこの制度を利用できないことになっている。ニューデリー駅の外国人用鉄道予約オフィスでは厳しくヴィザをチェックされるので、外国人留学生がここで外国人用切符を予約するのは至難の業である。ただし、不可能ではない。うまく交渉すれば切符を売ってくれることもあるし、運よくヴィザがチェックされないこともある。要は交渉力と運次第だが、僕の経験から言えば、女性の方が圧倒的に成功率が高い。男性はここでは、男尊女卑社会の逆差別を味わうことになるのが通常である。
なぜ外国人用切符にこだわるかというと、インドでは列車のチケットを手に入れるのが非常に困難だからだ。デリー〜ムンバイーや、デリー〜コールカーターなど、主要都市を結ぶ列車は数ヶ月前に予約しないと席が取れない状態であるし、他の路線にしても同じような状態である。僕は今まで、観光ヴィザやビジネスヴィザでインドに来ている日本人に代わりにチケットを予約してもらうという裏技を利用していたが、今回旅行に出ようと思った際、ほとんどの知り合いは帰国してしまっており、また日本人の観光シーズンでもないため、裏技利用は困難な状態であった。最近はインターネットで列車の予約状況を調べることができるが、僕が利用しようと思っていたシャーリーマール・エクスプレスは、既にウェイティング・リスト、つまりキャンセル待ちの状態だった。外国人用鉄道予約オフィスに駄目元で行ってもみたが、ちょうど欧米の旅行シーズンであるため、大変混雑しており、面倒になってやめた。
だが、インド鉄道は急な列車移動が必要な人々のために、タトカールというサービスを行っている。「タトカール」とは「即時」みたいな意味であり、各列車各等級の座席の内、数席が列車出発の前日に売り出されることになっている。しかし、こんな難しい状態なので、みんなタトカールの切符を狙っているのは当然のことである。鉄道予約オフィスが開く朝8時には、このタトカールを目当てにした人々が列をなす。僕も旅行出発の前日の午前7時半から、サロージニー・ナガルの鉄道予約オフィスに行って列に並び、タトカール席入手を図った。窓口が開いてから、窓口に辿り着くまで、30分くらいかかっただろうか。しかし、タトカールにはいろいろと制約があるようで、僕が行こうとしていたパンジャーブ州パターンコートまでのタトカールの切符はない、と言われてしまった。仕方なく、普通のチケットを予約した。行きも帰りもシャーリーマール・エクスプレス。行きのウェイティング・リストの番号は40。つまり、僕の前に39人が順番待ちしていることになる。帰りのシャーリーマール・エクスプレスの番号は24だった。
ウェイティング・リストの切符で座席が手に入るかどうかは、順番待ちの番号の数と、列車出発までの時間と、人脈に依る。もちろん、番号が少なければ少ないほど座席が手に入る可能性は高いし、時間に余裕があれば余裕があるほどゆっくり待つことができる。だが、最も重要なのは人脈である。人脈さえあれば、どんなにウェイティング・リストの番号が大きくても、「割り込み」で座席を入手することができてしまう。もちろん、コミッションを払う必要があるが。僕にもそういう人脈があるので、それに頼ってみることにした。・・・だが、時間に余裕が少なかったことが災いし、座席を手に入れることはできなかった。ウェイティング・リストの座席が確定するのは、列車出発の2時間前。座席が確保できたかどうかも、インターネットで確認ができる。2時間前まで粘ってみたが、ウェイティング・リストの番号は19番まで下がったものの、結局座席は手に入らず、座席が確定してしまった。確定後はどうあがいても無理らしい。「人脈」によると、帰りの列車の座席は何とかなるようだと言うので、そちらは頑張ってもらうことにした。
座席が手に入らなかったらどうするか?実はウェイティング・リストの切符でも列車に乗ることができてしまう。とりあえず列車に乗り込んで、T.T.(車掌)と交渉したり、何らかの事情で空いた座席を譲ってもらったりすればいい。今までインド各地を旅行して来たものの、ウェイティング・リストの切符で列車に乗るのは初めてだったが、これもひとつの経験だと思い、ニューデリー駅に向かった。
4645シャーリーマール・エクスプレスは、午後4時5分、ニューデリー駅発。ウェイティング・リストの乗客の座席がどうなったかは、プラットフォームにも貼り出される。一応確認してみたが、やはり僕の座席は取れていなかった。・・・よく見ると、僕よりもウェイティング・リストの番号が後の人が座席を取れている。僕よりも強力な人脈を持つ者がいたか・・・!
僕が買った切符はAC3段寝台の車両であったため、とりあえずその車両のテラスに座っていた。T.T.はまだ見当たらなかったので、念のために通りがかりの乗務員に「座席が手に入らなかったんだ」と顔を売っておいた。発車時刻になり、列車は動き出した。と、やはり座席が手に入らなかったおじさんも同じようにテラスに乗り込んできた。同じ境遇の仲間ということで自然と会話が始まった。おじさんの番号は16。僕よりも若い番号だ。すると、乗務員の1人が僕たちにアドバイスしてくれた。「AC車両の乗客はみんな終点のジャンムー行きだ。ここにいても座席が手に入る見込みはない。寝台車両(ACなし)へ行って、T.T.と早く交渉した方がいい。ガーズィヤーバード駅に来たら、大勢の乗客が乗り込んできて、二度と座席は手に入らないだろう。」そこで、おじさんと僕は寝台車両へ行ってT.T.を探した。T.T.は忙しそうにおり、「S6へ行って待ってろ」と言われた。S6というのは車両の番号で、寝台車両の6番目である。言われた通りS6へ行った。寝台車両と言っても、昼間は普通の座席扱いになり、短距離移動の乗客が座っている。空いている座席に座って、T.T.が来るのを待った。
実は久し振りに寝台車両(スリーパー・クラス)に乗った。昔は寝台車両ばかり使っていたが、一度デリーからアッサム州のグワーハーティーへ行くのに寝台車両を利用したとき、かなり疲労困憊して散々な目に遭ったので、それ以来ACクラス以上の列車で移動するようにしている。ACクラスで最も便利なのは、毛布やシーツなどがもれなく支給されることである。スリーパー・クラスではそのようなサービスはない(有料で毛布を借りることができるときもある)。冬や、朝晩冷え込む地域を移動するときなど、スリーパー・クラスを使うと必然的に自分で毛布などを持参しなければならなくなり、荷物が増えてしまう。なるべく軽装で旅行するのがモットーなので、ACクラス利用が癖になってしまった。だが、やはりスリーパー・クラスにいる人々は、裕福ではないが、好奇心旺盛で親切なインド人が多く、そういう人たちとの交流に久し振りに触れることができた気がした。インドの列車では、等級が上がるにつれて、乗客のレベルは上がるものの、何となく余所余所しい人が増える傾向にある。もちろん、中にはフレンドリーな人もいるが、何だか日本の新幹線に乗っているときと同じような、人間と人間の言い知れない距離がある。それに、スリーパー・クラスだと景色を眺めながら移動できるのがいい。ACクラスの車両のガラスは黒く塗られており、景色があまり見えない。
S6に座ってしばらくするとT.T.が通りかかったので、「あの、席が欲しいんですけど」と言ってみた・・・が、「遅すぎる」と全く相手にしてもらえなかった。自分でここにいろと言った癖に!と怒ると逆効果なので、「もし席が手に入ったら教えて下さい」と言っておいた。これは真剣に困った・・・。夜寝る場所がないから、ずっと起きていないといけないか・・・。
列車は、ガーズィヤーバード、メーラトなど、ウッタル・プラデーシュ州北西部の都市を通過し、パンジャーブ州に入った。既に日が沈み出している。なぜか同じコンパートメントにいる子供から指を差して笑われる。なぜだ・・・。僕が頭をなでると逃げてしまう。なぜだ・・・。時計は6時を回った。
すると、1人の乗務員が僕に話しかけてきた。確か、僕が列車に乗り込んだときに少し話した奴だ。「席が欲しいか?」思わず首を傾げる(インドではイエスの意味)。「AC2段寝台でもいいか?」AC2段寝台とは、俗に言うセカンドACで、AC3段寝台よりも1ランク上の座席である。「OK」と答えると、次にその男は急に声を潜め、僕にこっそりと耳打ちした。「200ルピーかかるがいいか?」つまりコミッションということである。200ルピーで寝床が手に入るなら背に腹は代えられない。ふたつ返事でAC2段寝台の車両に移った。結局、AC3段寝台とAC2段寝台の差額310ルピー+コミッション200ルピーをT.T.に支払い、めでたく一夜の寝床を確保することができた。当然、その乗務員にもチップを弾んでおいた。僕に宛がわれた寝台は、どうやら車掌用座席の余りのようだ。それにしてもあのとき、乗務員と少し会話をしておいて本当によかった。この国では、例え一期一会でも人脈を構築することが大切である。
寝台が手に入ったら急に腹が減ったので、カツレツを食べた。通路側の上の段の寝台だったため(インドで列車を利用したことがない人には分からない表現だろう)、ここに寝てしまったらもうどこを走っているか全く分からないし、カーテンを閉めてしまえば完全に1人だけの世界である。AC2等寝台は、誰とも会話せずに列車移動ができてしまうという、インド人嫌いには打ってつけの、またインド人好きには非常に退屈な車両である。こうしてパンジャーブの夜は汽笛と共に更けて行った・・・。
| ◆ |
6月16日(木) 閑静な避暑地、ダルハウジー |
◆ |
今回の旅行は、ヒマーチャル・プラデーシュ州のチャンバー谷の観光地を巡ることが主な目的である。チャンバー谷へは、パンジャーブ州北端の街パターンコートからバスで行くのが最も近い。
列車がパターンコート駅に到着したのは午前4時25分、予定よりも20分遅れだった。もっと遅れるかと思っていたので意外だった。駅を出て、サイクルリクシャーに乗り、バススタンドまで行った。言い値通り10ルピー払ったが、駅からバススタンドまではけっこう近く、5ルピーが相場だったかもしれない。まあ、サイクルワーラーにとって僕がファースト・カスタマーだろうから何も言わないでおいた(インドでは、その日最初の客の良し悪しに1日の商売の縁起を担ぐ)。
最初の目的地はダルハウジー。ダルハウジーは標高2036mにある避暑地で、他の避暑地と同じく、英領時代に開発された。当時は主にラーホール(現在はパーキスターン領)の人々が避暑に来ていたようだ。ちなみに、ダルハウジーとは1846年〜56年まで在任したインド総督の名前である。ダルハウジー行きの始発バスは4時に出ているとのことだが、なぜか今日はそのバスがバススタンドに来なかったという。そのバスを待っていたのだが、いつまで経っても来なかった。途中でパンクでもしたのだろうか?そこで、午前5時半発チャンバー行きのバスに乗ることにした。途中のバニーケートで乗り換えれば、ダルハウジーまで行ける。パターンコートからバニケートまで45ルピー、バニケートからダルハウジーまで5ルピーだった。パターンコートまでは平野だが、ヒマーチャル・プラデーシュ州に入るとすぐに山道になり、バスはエンジンを唸らせながらグングンと登って行った。ダルハウジーには午前9時20分頃到着した。
ダルハウジーは、今まで訪れたインドのどの避暑地(シムラー、マナーリー、ダージリン、マーテーラーン、ウーティーなど)よりも静かな場所だった。シムラーなんかでは、ハイシーズンの5月〜6月には文字通り身動きが取れないほど多くの避暑客が訪れるが、ダルハウジーは避暑客らしき人々の姿よりも地元の人々の往来の方が目立つ、小さな山の町だった。外国人も全くと言っていいほど見かけなかった。ホテルの部屋が見つかるか不安だったが、1軒目に当たったヒマーチャル・プラデーシュ州観光局経営のホテルは満室だったものの、2軒目に適当に入ってみたホテルには空き室があった。山道を歩くのは疲れるので、ここに泊まることに決めた。ホテルの名前はホテル・スーパー・スター。ダブルルーム、ホットシャワー、TV、石鹸、タオル付きで700ルピー。やはり避暑地なので、このくらいの値段はする。

ダルハウジー
午前中はダルハウジーを散歩してみた。標高が高いだけあり、気候は非常に涼しくて快適。空気も澄んでいる。日中は半袖でもいいくらいだが、朝晩はセーターがないと凍えるくらい冷え込む。ダルハウジーは、ガーンディー・チャウクとスバーシュ・チャウクの2つの交差点が、山頂を挟んで中心的な広場となっており、この2つのチャウクを、ガラム・サラク(ホット・ロード)とタンダー・サラク(コールド・ロード)という道がつないでいる。どちらの道もほぼ水平であるため、これらの道や広場を歩き回るのは楽だ。一方、タンダー・サラクから一段低いところにバススタンドがあり、ここと上記のチャウクを結ぶ道は急な傾斜となっている。北インドの他の避暑地と同様に、ダルハウジーにも多くのチベット人難民が居住しており、バススタンドの近くには小さなチベッタン・マーケットがある。チベッタン・マーケットにあった小さな食堂でマトン・モモを食べてみたが(1皿20ルピー)、かなりおいしかった。

ガラム・サラク

スバーシュ・チャウク
ダルハウジーは小さな町なので、午前中散歩しただけで大体把握してしまった。町の中には特に見所はないので、ここでは適当に散歩ぐらいしかすることがない。そこで、ダルハウジーから約22kmの地点にあるカッジヤールという場所へタクシーで行ってみることにした(バスでの往復は本数が少ないので困難)。昼食を食べた後、ガーンディー・チャウクのタクシースタンドでタクシーをチャーターした。ダルハウジーのタクシースタンドでは、料金は全て定価になっている。ダルハウジーからカッジヤールへの往復は510ルピーだった。
ダルハウジーからカッジヤールまでは1時間弱だった。カッジヤールは「ミニ・スイス」と呼ばれている風光明媚な地である。・・・だが、「ミニ・スイス」という呼称を聞くと、何だか嫌な予感がするのは僕だけではあるまい。「東洋のスイス」とか「インドのスイス」とか、そういう勝手な名前を名乗っている場所で、本当にスイスほど美しい場所はほとんどない。あるとしたらカシュミールぐらいだ。この「ミニ・スイス」も、行ってみてガックリの代物ではないか・・・?そういう疑念と偏見を抱くことは罪ではなかろう。だが、驚くなかれ、なんとこの「ミニ・スイス」という呼称は、1992年7月7日に、スイス大使によって正式に承認されたのだ。それだけでなく、ここカッジヤールの石がスイスの首都ベルンに移送され、駅前の彫像となったらしい。おそらく世界に「〜〜のスイス」を名乗る土地は多いだろうが、スイスから正式に承認された場所は、けっこう少ないのではないだろうか?
と言うわけで、怖いもの見たさの好奇心を胸にカッジヤールに着いたわけだが、第一印象はかなりよかった。不覚にもちょっとだけ感動した。延々と続く森林地帯の中に突然、広々とした草原と池が現れるのだ。スイスと比較したくなる気持ちは分かる。遠くの方で牛や馬がのどかに草を食んでいるし、さらに遠くにはヒマラヤスギの鬱蒼とした森林が美しい曲線を描いている。・・・ただ、ここはインド。何だか変なものが草原のあちこちに見受けられ、そっちの方に目が行ってしまう。特に目を惹いたのは・・・なんだあの巨大なボールは!透明で巨大なボールが、草原の斜面をゴロゴロ転がっているのだ。どうやら人が中に入って遊ぶ遊具のようだ。これでは景観が台無しではないか!しかも、草原の中心にある池は、ゴミが無造作に投げ捨てられていて汚ない泥池となっていた。昔は青空を映す美しい湖で、地元の人々の信仰の対象にもなっていたらしいが、観光による汚染により現在のような惨状になってしまったらしい。もったいないことだ。

カッジヤールの風景

湖に浮かぶコテージ
写真で見るときれいだが・・・

人を中に入れて転がる巨大ボール
カッジヤールは、その景色と共に、12世紀に建立されたというカッジーナーグ寺院でも有名だ。カッジーナーグ寺院に祀られているのはナーグ(蛇神)である。また、寺院には「マハーバーラタ」に出てくるパーンダヴァの5兄弟の像もある。だが、寺院は好ましくない形で補修が行われており、まるで新しい寺院のようだった。

カッジーナーグ寺院

珍しくご神体の写真撮影を許してくれた
ナーグ(蛇神)だが、人間の姿をしている

パーンダヴァ5兄弟の1人、アルジュンの像
カッジヤールは確かに美しい景観の場所であり、ピクニックにはもってこいの場所だ。クリケットをして遊んでいるインド人たちがたくさんいたが、その気持ちはすごい分かる。乗馬をすることもできるし、情報によるとパラグライディングの設備もあるようだ。だが、ここにいるよりもダルハウジーに戻った方が時間を有効に使えると思い、1時間ほどカッジヤールで適当に時間を潰した後、ダルハウジーに戻った。
ダルハウジーに戻ったのは4時頃。午前中にダルハウジーを一周したものの、まだ行っていない道があったので、それらの道を散策することにした。すると偶然、「ネータージー・スバーシュ・チャンドラ・ボース・メモリアル」とヒンディー語で書かれた建物を発見した。実はダルハウジーに着いたときから、町の至る所にあるチャンドラ・ボースの肖像や彫像がずっと気になっていた。僕が宿泊しているホテルはスバーシュ・チャウクの近くにあるが、そのスバーシュ・チャウクにはその名の通り、大きなチャンドラ・ボースの彫像が立っている。その謎が解けるかもしれないと思い、その建物の中に入って行った。

タンダー・サラクで見つけたチャンドラ・ボースの看板

スバーシュ・チャウクにあるチャンドラ・ボースの彫像
「メモリアル」と書かれていたので、てっきり博物館か何かかと思ったのだが、それは学校であった。職員室では先生たちがPCでソリティアをして遊んでいた。1人の先生に質問してみたら、チャンドラ・ボースの謎が解けた。ダルハウジーには、1937年5月から10月まで、チャンドラ・ボースが療養のために滞在していたのだ。その関係で、町のあちこちにチャンドラ・ボースの肖像があるという訳だ。しかし、たった5〜6ヶ月滞在しただけで、これほどまで土地の人々から尊敬を集めるチャンドラ・ボースは、やはりカリスマ的指導者であったのだろう。スバーシュ・チャウクにあるチャンドラ・ボースの彫像には彼の没年が刻まれておらず、「チャンドラ・ボース生誕百周年1897年1月23日−1998年1月23日」とだけ記されていた。
その学校で、ダルハウジーの郊外にチャンドラ・ボースが毎日のように通った井戸があるという情報を得たので、そこへ行ってみた。その井戸はスバーシュ・バーオリーと呼ばれている。ガーンディー・チャウクに通じる道のひとつを、10分ほど歩いていくと、そのスバーシュ・バーオリーはある。井戸と言っても、現在ではちょっとした記念堂みたいになっていた。英国政府に逮捕され、獄中で体調を崩したチャンドラ・ボースは、ダルハウジーのこの水を飲むことで健康を回復したという。

スバーシュ・バーオリー
また、スバーシュ・チャウクの奥には、サダル・バーザールと呼ばれる古いマーケットがあった。英領時代からあると思われる古い建物が並んでおり、当時の様子が偲ばれた。だが、現在ではそれほど繁盛しているマーケットではない。

サダル・バーザール
ところで、暑いところから急に涼しいところへ移動すると、無性に腹が減るような気がする。食べても食べても何だか腹がいっぱいにならない。夕食は肉が食べたくなって、サダル・バーザールの入り口付近にあるレストランの一軒に入った。「Sher-e-Punjab(パンジャーブのライオン)」という、シムラーにもある有名なレストランに入ったつもりだったが(シムラーの店と関係あるのかは不明)、間違えてその隣にある「Shan-e-Punjab(パンジャーブの栄光)」に入ってしまった。紛らわしすぎる!というか、本物は文句言え!だが、ここで食べた「Shan-e-Punjab
Special Chicken」(110ルピー)は、バターチキンにパニールの粒が混じったようなカレーで、紛らわしい店名を差し引いてもうまかった。ダルハウジーの料理は、空気と水が清浄なためか、基本的にどこでもおいしいように思われる。
今日はダルハウジーを発ち、次の目的地チャンバーへ向かう。チャンバーは、チャンバー谷の中心都市で、西暦920年から1000年以上に渡ってチャンバー王国の首都だった古都である。チャンバー王国は、北インドで最も長く続いた王朝だとされている。
ダルハウジーのバススタンドから、朝7時にチャンバー行きのバスが出ているので、それに乗り込んだ(40ルピー)。昨日行ったカッジヤールを経由してチャンバーまで行くルートもあるが、このバスは一度バニーケートまで戻って、そこからダルハウジーのある山の北側をグルッと回って行くようなルートを取っていた。おそらく、こちらの方が道が整備されていて、短時間で移動できるのだろう。バニーケートからチャンバーまでの道の風景は非常に美しかった。ヒマラヤ杉に覆われた峻険な山々、雄大なラーヴィー河、そして山の斜面に点在する村々・・・。この道をバイクで走ったら、どんなに気持ちいいだろうと考えていた。
チャンバーには朝9時半頃に到着した。チャンバーは想像していたよりも大きく騒々しい街だった。人口は約2万人。だが、想像していた通りの美しい街だった。ラーヴィー河の河畔に南北に細長く街が伸び、山腹には宮殿やハヴェーリー(邸宅)が並び、ヒマーチャル・プラデーシュ州特有の木造屋根を持った寺院が所々頭を覗かせていた。標高は996m。気候は少し暑いぐらい。寒いよりも暑い方が好きな僕には快適だった。チャンバーでは、アロマ・パレス・ホテルに宿泊した。おそらくチャンバーで最もいいホテルだ。シングルルームで400ルピー。バストイレ、ホットシャワー、石鹸、タオル、TV、スリッパなどが完備されており、部屋は小さいが清潔。レセプションの応対も非常に礼儀正しく好感が持てた。

チャンバー
まず訪れたのは、ブーリ・スィン博物館。チャンバー地方などの文化や風俗に関する展示がしてある博物館である。入場料やカメラ料には外国人料金があったが、博物館の館長と話をして、デリーで勉強している旨を伝えたら、入場料を無料にしてくれた。けっこう気合の入った博物館で、チャンバー名物の刺繍ハンカチをはじめ、細密画、石像、寺院の一部、民俗衣装、金属製の契約書、手紙、古写真、古銭、マハーラージャーの写真、肖像画、遺品などなど、多岐に渡る展示物があり、またほぼ全ての展示物にヒンディー語と英語の解説が添えられていた(当たり前のことだが、この当たり前ができていない博物館がインドには多すぎる)。特に、噴水板(Fountain Slab)のコレクションに力が入れられていた。噴水板とは、自然の源泉が注ぎ出る口やその周囲などに彫刻が施されたもので、チャンバー谷には多くの噴水板が残っているという。

ブーリ・スィン博物館

刺繍ハンカチ
表と裏の模様が同一
クリシュナとゴーピー(牧女)のラース・リーラーが描かれている

噴水板
その次に、チャンバー最大の見所であるラクシュミー・ナーラーヤン寺院群へ行った。この寺院群には、10〜19世紀に渡って建立された6つの寺院が横一列に並んでいる。ヒマーチャル・プラデーシュ州の寺院の多くは、砲弾型の本殿(ガルバグリハ)に、キノコのような傘がかぶせられており、独特の形状をしている。ヒマーチャル・プラデーシュ州は特に多雨地域であるため、雨を防ぐために寺院の上に木製の屋根がかぶせる習慣が定着したという。ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群の寺院も全て傘をかぶっている。まるで傘子地蔵のようだ。

ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群
ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群の中で最大かつ最古のものは、門を入って正面にあるラクシュミー・ナーラーヤン寺院である。御神体はヴィシュヌ神。本殿の裏には、ヴィシュヌ神の化身であるナルスィンの赤い像があった他、クリシュナや、乳海攪拌の像などがあった。ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群はなぜか写真撮影禁止で、「もし写真を撮影したら罰金500ルピー」と壁に書かれていた。念のためにラクシュミー・ナーラーヤン寺院の御神体の前にいたパンディト・ジー(僧侶)に聞いてみたら、「見つからないように急いで撮れ!」と言われた。・・・誰に見つからないようにすればいいのか分からなかったが、とにかく適当に写真を撮りまくった。

ラクシュミー・ナーラーヤン寺院
ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群のすぐ隣には、立派な建物が建っている。元々王宮(オールド・パレス)だった建物だが、現在は大学になっている。オールド・パレスの上階から、ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群の俯瞰的な写真が撮れそうだったので、こちらにも行ってみることにした。ちょうど大学では入学試験が行われていたが、簡単に中に入れてもらえた。王宮を無理矢理校舎にしてしまったため、教室の形状や配置がかなりいびつで不便そうだった。だが、建物の重厚さや中庭の美しさは、さすが元王宮という感じだった。これはヘリテージ・ホテルならぬ、ヘリテージ・カレッジだ。ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群の写真もうまく撮影することができた(上に掲載)。

旧王宮

教室の様子
チャンバーには無数の寺院が点在するが、次はチャンバーを見下ろす山にある3つの寺院を目指した。急な階段を登って行かなければならないのでヘトヘトになったが、何とかまずは3寺院の内の1つ、バジュレーシュワリー女神寺院に辿り着いた。バジュレーシュワリーはドゥルガー女神の一種であり、谷を見下ろす山腹に位置していた。やはり木製屋根を頭に抱いた形をした寺院であり、壁面には無数の彫刻が施してある。だが、いまいち面白味に欠けた。
次に向かったのは、スーヒー女神寺院。スーヒーとは、チャンバーの女性たちから信仰されている女神である。スーヒー女神寺院には、以下のような寺院の縁起話が掲示されていた。
西暦920年、チャンバー王国のマハーラージャー、サーヒル・ヴァルマンによって王国の首都はバルマウルからチャンバーに遷都されたが、水不足に悩まされていた。ある日、マハーラージャーの夢に氏神が現れ、「もし王族の誰かが命を捧げるならば、水を授けよう」と神託を下した。そこで、王妃スナーイナーが犠牲になることが決まった。チャイトラ月(3〜4月)に王妃は輿に乗り、楽隊を引き連れてバロートという場所まで行き、そこで命を捧げた。その瞬間、その場所から水が湧き出た。ところで、王妃は死ぬ前に、道中休息した場所で女性たちによる祭りを15日間開くように言い残した。そのときから、チャイトラ月15日〜30日まで、チャンバーの全ての女性は、この場所に集まって王妃を祀る祭りを行って来た。
水不足も何も、すぐ近くにラーヴィー河が流れているので、水が不足することはなかったのではないか?また、王妃を犠牲にする必要があったのか?どうして王妃が死んだ場所ではなく、王妃が休憩した場所に寺院を作るのか?など、いろいろ疑問点があるが、民話というのはこんなものだろう。スーヒー女神寺院は、寺院というよりも祠に近い小さな建物であった。

スーヒー女神寺院の内部
チャンバーの町を一望のもとにできる場所に立地しているのが、チャームンダー女神寺院である。この寺院は王国の首都がチャンバーに遷都される前からあったとされるが、現存しているのは後世の再建らしい。この寺院の御神体がかなり素晴らしい彫刻らしいのだが、僕が辿り着いたときには本殿は閉じていた。だが、木製の天井などの彫刻は見ることができた。この寺院には多くの鐘が吊り下げられていた。
これら3つの寺院を見終わった後、麓に下って行った。その途中、赤い色をしたラング・マハルに立ち寄った。これも元々王宮だったようだが、現在では政府機関などが入っている。チャンバー名物の刺繍ハンカチを売るエンポリアムもあったが、あまり質のいいものは売られていなかった。やはり博物館の展示物を見てしまうと、売るために作られた製品は全て見劣りしてしまう。
他にもチャンバー市内に点在するいくつかの寺院を訪れた。だが、どれも似たような形をしており、特筆すべき寺院はなかった。ちなみに、チャンバーには入場料などが必要な寺院はひとつもなかった。
昼食を食べた後、ラクシュミー・ナーラーヤン寺院群のスケッチでもしようかと考えながらホテルの部屋で休息していたら、突然雨が降り出した。雨は1時間ほど降り続いた。おかげで少し予定が狂ってしまった。スケッチをするのはやめにして、チャンバーをブラブラと散歩することにした。チャンバーの路地裏は歩くと面白い。木造の伝統的な住宅がたくさん残っており、日本の古い民家と同じ匂いがする。チャンバーの中心部にはチャウガーンという広場があり、住民はそこでクリケットをしたり走り回ったりして遊んでいる。チャウガーンの向こう側には、ヒマーチャル・プラデーシュ州観光局が経営するカフェ・ラーヴィー・ビューという小さなレストランがある。名前通り、このレストランからは、ラーヴィー河の急流を眺めることができる。チャンバーのマーケットは、メインロードに沿って細長く続いている。一通り見て回ったが、売られているものにそれほど特徴のあるものはなかった。ダルハウジーにいたときから思っていたが、ヒマーチャル・プラデーシュ州はもしかしたら飲酒に対して寛容な州かもしれない。酒屋が朝っぱらから開いているし、ビールを出すレストランやバーがけっこう多かった。

チャウガーンとチャンバーの街並み
緑色の屋根と白い壁の大きな建物は旧王宮
| ◆ |
6月18日(土) 天国を抱く村、バルマウル |
◆ |
チャンバー王国の首都は、チャンバーに遷都されるまでは、チャンバーからさらにラーヴィー河を約65km遡った地点にある、バルマウルにあった。バルマウルには、チャンバーにある寺院よりもさらに古い寺院がいくつか残っている。今日はバスでバルマウルを目指す。
早朝、午前6時半発バルマウル行きのバスに乗り込んだ(48ルピー)。バスはひたすらラーヴィー河の上流へ向かった。河沿いの道なので、それほどアップダウンは激しくないが、右に左にグニャグニャと曲がる、断崖絶壁の危険な道である。道も1車線〜1.5車線しかないので、対向車両とすれ違うのも大変である。上流へ向かうにつれて、周囲を取り囲む山は高さを増して行った。途中には大きなダムがあり、水力発電が行われていた。チャンバーに滞在中は一度も停電がなかったが、このダムのおかげであろうか。この辺りの道は土砂崩れや落石などの頻発地帯であり、応急処置程度しか対策が施されていないので、非常に危険である。特に、途中にあるカラームクという町の近くの道路は、次から次へと上から石が転がり落ちて来る超危険地帯であった。まるで誰かが上からわざと石を落としているみたいだ。カラームクとは、「上を見上げる」みたいな意味だと思う。うまく名付けたものだ。こんなに落石の多い場所は人生で初めて見た。主に落石が起こっていたのは対岸であったが、いつ道路側に落石が起こってもおかしくない状態であった。常に石の除去作業を行わないといけない。

カラームクの落石頻発地帯
バルマウルには10時過ぎに到着した。バルマウルの標高は2195m。雪を抱いた峻険なヒマーラヤの山々に囲まれながらも、なだらかな山の斜面に広がる美しい村であった。民家は、木と石を組み合わせたヒマーチャル・プラデーシュ州の伝統的な建築様式がよく残っていた。バススタンドに着いて、まずはホテルを探した。バルマウルにはいいホテルがないと聞いていたが、確かにそれは本当だった。ホテルと呼べるような宿泊施設はなく、ゲストハウスしかなかった。おそらく一番趣のある部屋があるのは、チャウラースィー寺院群へ続く道の途中にあるチャウラースィー・ホテルである。レストランの2階が客室となっており、見晴らしがよくて広い部屋が400ルピーだった。しかしここには泊まらなかった。僕が泊まったのは、メイン・ロード沿いにあるカールティカ・ゲストハウスである。小さなギザ(電気温水器)付きのバストイレが付いた部屋が300ルピー、バストイレ共同の部屋が200ルピー。カールティカ・ゲストハウスに宿泊したのには特別な理由があったが、それは後述する。

バルマウル
ホテルを決めた後は、早速チャウラースィー寺院群へ行ってみた。「チャウラースィー」とは「84」という意味で、ここには大小様々な寺院が思い思いの方向を向いて乱立している。チャンバーのラクシュミー・ナーラーヤン寺院のように、横一列にはなっていない。最も目立つのが、マニーマヘーシュ寺院と、ナルスィン寺院である。どちらも木製屋根をかぶった砲弾型の石造寺院で、建立は9〜10世紀。だが、それらよりももっとすごいのが、マニーマヘーシュ寺院の隣にあるラクシュナー女神寺院。このドゥルガー女神を祀った小さな寺院は、インドに現存する寺院としては珍しく木造で、建立は700年。北インドで最も古い木造寺院のひとつだろう。寺院の門や内部の天井などに刻まれた彫刻は絶品の一言。元々インドでは木造の寺院が主流だったと言われるが、厳しい気候や度重なる戦乱により、現存しているものはほとんどない。それらの失われた寺院の多くにも、このような素晴らしい彫刻が施されていたのだろうか・・・。

マニーマヘーシュ寺院

ラクシュナー女神寺院

ラクシュナー女神寺院の入り口の素晴らしい木彫

入り口の木彫の拡大
ミトゥナ像などが彫られている
実は、宿泊したホテルのオーナー、ラーム・プラサード氏がけっこう土地の歴史に詳しくて(どこにでもこういう自称郷土研究家みたいな人はいるものだ)、チャウラースィー寺院を案内してくれた。ラーム・プラサード氏の語った話を総合すると、チャウラースィー寺院群の重要性がさらに浮き彫りになった。まず、このチャウラースィー寺院群は、実は「天国」だと言う。高所にあるから、とか、風景が美しいから、とか、そういうしょうもない理由ではない。地元の人々の信仰によると、文字通りこのチャウラースィー寺院群は、死後の魂がやって来る天国だと言う。チャウラースィー寺院群の一角には、ダルマラージ寺院がある。ダルマラージは天国を支配する神で、魂に天国に住む資格があるかどうか、審判を下す役割を担っている。ダルマラージを祀る寺院はインドでもここだけしかないとか。そして、ダルマラージ寺院の正面には赤い柵で囲まれた一角がある。これはチトラグプタ寺院と呼ばれている。ただし、寺院と言ってもただ単にシヴァリンガと足跡があるだけだ。チトラグプタは人間の業と寿命を司る神である。死後の魂がダルマラージ寺院の前までやって来ると、チトラグプタがその魂の生前の所業を読み上げ、ダルマラージが審判を下す、という形になっているらしい。また、チャウラースィー寺院群の中央部には、アルド・ガンガージー(半分のガンジス河)という小川が流れている。これはつまり、三途の川みたいなものみたいだ。この話を聞くと、チャウラースィー寺院群は非常に面白い場所に思えてきた。

ダルマラージ寺院(奥の緑色の寺院)と
チトラグプタ寺院(手前の柵の中)

ダルマラージ寺院内部

チトラグプタ寺院
チャウラースィー寺院群の隅には、アルド・ガンガージーの源泉となっている泉がある。この泉の水量は一年を通して一定しているが、例外的に2日だけ、水量が増加するという。ジャナマーシュトミー(クリシュナの誕生日)とラーダーシュトミー(ラーダーの誕生日)の日である。今でもこの不思議な現象は続いているそうだ。

アルド・ガンガージー
上記の2日には、水量が排水口の位置まで達する
また、「チャウラースィー」が「84」という意味であることは上に述べたが、どう数えても寺院群に84個もの寺院があるとは思えない。しかし、ラーム・プラサード氏の話によると、寺院群の地下にもまだたくさんの寺院が埋まっていると言う。今までに2度、それら埋もれた寺院の発掘作業が行われた。しかし、1度目は、発掘を始め、地下の寺院のてっぺんが見えた途端、豪雨に見舞われて寺院は土砂に埋もれてしまい、発掘作業は中止されてしまった。2度目の発掘作業が行われたとき、今度はアルド・ガンガージーの源泉である泉の水が急に溢れ出して寺院群一帯が洪水になってしまい、やはり発掘は中止された。これら2度の試みが超自然的な力によって中断されたことにより、発掘は神の意思に反するということになり、以後発掘は行われていない。以前は寺院群の敷地内は芝生になっていたが、美化の名のもとに石が敷き詰められてしまった。
昼食を食べた後は、マニーマヘーシュ寺院を2時間ほどかけてスケッチした。ヒマーチャル・プラデーシュ州の寺院は傘をかぶっているのでユニークな印象を受けるが、スケッチをしている内に、これら初期の寺院は、ヒンドゥー教の最も基本的な寺院形態である砲弾型寺院に傘をかぶせただけであり、実は造形的にあまり面白くないことに気付いた。
バルマウルの最大の見所はチャウラースィー寺院だが、それに匹敵するほど興味深いのが、民家の建築である。木と石をうまく組み合わせた民家は、ブータンの民家と構造的に非常に似ているように思えた。おそらく昔は、ヒマーチャル・プラデーシュ州の民家は全てこのような建築になっていたのだろうが、田舎にも徐々に浸透しつつある経済発展の影響で、レンガ造りの味気のない民家が増えてきている。だが、バルマウルには昔ながらの伝統的な民家が多く残っており、古い住宅地を歩くと非常に面白い。バススタンドの上の方に、古い町並みを残す住宅地の一群が見えたので、そこまで歩いて行ってみた。一口に木と石を組み合わせると言ってもいろいろな融合の仕方があった。一番特徴的なのは、木の板と石を積み上げて家屋の柱にする独特の建築法である。チャウラースィー寺院群の寺院にもこのような建築法で建設されている寺院がいくつかあった。普通のレンガとコンクリートの家に、木製のベランダが付け足されているような家もあった。

バルマウルの古い住宅街

石と木を組み合わせた民家

木の板と石の柱
この村ではまだデジカメがあまり知られていないようで、1人の子供の写真を撮って、画像を見せてあげたら大変なことになった。次から次へと、「僕も撮って!」「私も撮って!」と、子供たちがやって来た。最初の内は「はいはい」と写真を撮って、その写真を見せてあげていたが、だんだんこの写真熱が大人にまで広がってきて、切りがないので逃げ腰になって来た。ちょうどそのときポツポツと小雨が降り出したので、それを言い訳に何とか逃げ出すことができた。それにしても、デジカメでこんなに盛り上がってくれるところは、インドの観光地では絶滅危惧種的に急減している。何しろインド人観光客がデジカメを持っている時代だからだ。

村の子供たちの写真
インドの子供は子供らしいはつらつさがあってかわいい
バルマウルよりさらに山を登った地点にはバルマーニー女神寺院がある他、バルマウルから33kmの地点にはマニーマヘーシュ湖という聖なる湖と、マニーマヘーシュ・カイラーシュ山という聖なる山がある。だが、どちらも時間がなかったため、行くのは諦めた。
今まで旅行してきたダルハウジー、チャンバー、バルマウルは、チャンバー谷の都市であった。今日はチャンバー谷の南側にある、カーングラー谷を目指す。具体的な目的地は、チベット亡命政府の本拠地として知られるダラムシャーラー(マクロード・ガンジ)である。ダラムシャーラーには2002年に一度行ったことがある。
実は、カールティカ・ゲストハウスのオーナー、ラーム・プラサード氏が、ちょうど今日、ダラムシャーラーに用事があって自家用車で行くところだった。よって、僕もそれに便乗させてもらうことにした。こういう訳もあり、カールティカ・ゲストハウスに宿泊することにしたのだった。バルマウルはチャンバー谷のどん詰まりにあるため、チャンバーまで戻って、カーングラー谷へ回り込まなければならない。
自動車はマールーティ・スズキの軽ワゴン車、オムニ。朝8時にホテルを出発した。坂道を下って、麓にあるカラームクまで行き、そこからラーヴィー河の流れに従ってチャンバーへ向かった。カラームクの落石地帯を通り抜け、断崖絶壁の道を慎重に進んだ。3時間半ほどでチャンバーに到着。ここまでは主に下り坂か平らな道だったので順調に進んだのだが、チャンバーから今度は上り坂になった。と同時に、自動車のポンコツさが目立ってきた。ローギアにあまり力がなく、今にも止まってしまいそうなスピードでしか坂を登ることができなかった。そして終いにはオーバーヒートしてしまった。河が流れているところに車を停めて、エンジンと冷却水を冷やした。30分ほど休憩して、再び坂を登り出した。しかし坂道の登る力にそれほど変化はなく、ひいこらひいこら言いながら何とか峠まで辿り着いた。そこの食堂で昼食を食べた。東の方に白く険しい山々が延々と連なっているのが見えた。
峠を越えたら、後は下り坂なので今度は一転してスピーディーな移動となった。カーングラー谷は、チャンバー谷とはだいぶ違う景色だった。カーングラー谷はビアース河に流れ込む無数の河によって形成された谷だが、谷というよりは平野に近かった。多少のでこぼこはあるものの、チャンバー谷の断崖絶壁の道と比較すれば、平野と言ってしまってもいいだろう。カーングラー谷には空港まであるくらいだ。パターンコートとマンディーを結ぶ幹線に出ると、チャンバー谷との違いはより鮮明になった。道路の脇には食堂や露店が立ち並び、自動車の往来もせわしない。「人を寄せ付けない孤高の威厳に満ちたブラーフマン」のような雰囲気を持つチャンバー〜バルマウル間の閑散とした道路と比べると、カーングラー谷は「他者に迎合し金儲けを追及するヴァイシャ(商人)」の顔をしていた。簡単に言えば、観光地化されていた。
ところで、インドの山道にはよく「Don't Mix Drive & Drink」「Na Pahunchne Se Der Hona
Achcha Hai(着かぬより遅れるほうがマシ)」みたいな標語が掲げられ、飲酒運転やの速度超過を戒める努力がなされている。それらを見ていくと時々面白い標語があったりするのだが、カーングラー谷の幹線でひとつ目に留まったものがあった――If
Married, Divorce to Speed(結婚したならスピードとは離婚せよ)。なら独身者はスピードを出してもいいのか、と突っ込みたくなるが、この標語から、この谷をハネムーンで訪れる新婚カップルが多いことが伺われた。さらに、何となくこの標語は、もっと深い含蓄を含んでいるような気になった。「結婚したら、人生の速度を緩めろ」みたいな意味にも取れるのではないかと思ったのだ。こういう標語はインドのいろいろな場所にあるが、スィッキム州の州都ガントクへ行くまでの道の途中にあった標語が一番面白かった記憶がある。
カーングラー空港がある街ガガルから、ダラムシャーラーまで通じる道が伸びている。既に時計は4時を過ぎていた。一刻も早くマクロード・ガンジまで行きたかったが、ラーム・プラサード氏は途中で修理屋に停車して、車を修理し出した。もうダラムシャーラーまですぐそこなので、僕を下ろしてから修理してもらいたかったが、便乗させてもらっている身としては文句は言えない。だが、修理にはそれほど時間がかからず、10分ほどで完了した。僕はてっきり、ローギアの馬力が出なかったり、オーバーヒートしやすいから修理してもらっているのだと思っていた。だからものすごく時間がかかるのではないかと考えていた。あまりにあっけなく修理が終わってしまったので、「直ったんですか?」と聞くと、「ほら、音楽が鳴ってるだろ?」と言われた。確かに、道中は全く無音楽のまま来たが、今は音楽が鳴っている。どうやらラジカセの配線に不具合があり、それを修理してもらっただけのようだ。そんなもの後から直せばいいのに・・・。
ガガルから上り坂になり、山の中腹部にあるダラムシャーラーまで登って行った。ラーム・プラサード氏とはダラムシャーラーのバススタンドで別れた。バススタンドでマクロード・ガンジ行きのバスに乗り、さらに山の上にあるマクロード・ガンジへ向かった(7ルピー)。
マクロード・ガンジは、1850年代中頃、カーングラー谷管轄の英国軍の駐屯地として開発された。しかし、1905年にこの地域を襲った大地震により町は崩壊し、英国軍は駐屯地を移動せざるをえなかった。マクロード・ガンジが再び脚光を浴びるのは、1960年にダライ・ラマがチベットから亡命して来て、ここにチベット亡命政府を樹立したときからだ。現在では多くのチベット難民がマクロード・ガンジに住んでおり、バックパッカーや避暑客が集まる観光地としても栄えている。一般にダラムシャーラーの名前でよく知られているが、チベット亡命政府の政庁トゥグラグカンがあるのは、ダラムシャーラーよりも4km高所にあるマクロード・ガンジである。町の名前は、パンジャーブ州(当時)のデーヴィッド・マクロード副州知事の名前から命名された。「ガンジ」とはヒンディー語で「市場」という意味である。
マクロード・ガンジには午後5時半頃に到着した。バルマウルから9時間半かかった計算になる。長い移動だった。マクロード・ガンジの標高は1770m。標高1219mのダラムシャーラーはまだ暑いくらいだったが、マクロード・ガンジの空気はひんやりとしており、強い日差しと混ざり合って快適な気温となっていた。しかし、驚いたのはその混雑振り。3年前に訪れたときは、白人バックパッカーとチベット難民の群集がたむろっているだけだったが、今回特に目立ったのはインド人避暑客であった。パンジャーブ州などの平野部から避暑にやって来たと思われるインド人が、自家用車で狭いマクロード・ガンジに乗り付けているため、やっと1台車が通れるくらいの幅しかない道路では、しばしば対向車と対向車がにらめっこしてしまい、渋滞を引き起こしていた。また、以前来たときは交差点にバススタンドがあったのだが、現在では渋滞解消のためか、旧バススタンドよりも一段低い場所に広場が造られ、そこに駐車するようになっていた。これは賢明な判断だったと思う。

マクロード・ガンジ
マクロード・ガンジは今回の旅行の最後の宿泊地となるため、いいホテルに泊まりたかった。この混雑を見て空き室があるか不安になったが、最初にあたってみたホテル・インディアン・ハウスで部屋が空いていたので、ここに泊まることにした。マクロード・ガンジに数あるホテルの中でも高級な方のホテルである。マクロード・ガンジの中心部にも近くて便利だ。スタンダード・ルームが880ルピー。バストイレ、ホットシャワー、タオル、石鹸、トイレットペーパー、冷蔵庫などが完備されている。スタッフの応対も礼儀正しい。
マクロード・ガンジに着いた途端、モモ(チベット風餃子)が食べたくなった。ロンリー・プラネットに「マトン・モモがおいしい」と書かれていた、スノー・ライオン・レストランへ行って、迷わずマトン・モモを注文した(35ルピー)。・・・が、注文してから出てくるまでやたら時間がかかった上に、具が少なくておいしくなかった。悔しかったので、路上で販売されているモモを食べてみた。・・・が、今度はチリが効きすぎている上に、やっぱり具が少なかった。チベット亡命政府のお膝元でこんなまずいモモを出していていいのか?それともモモまで観光地化されてしまったのか?非常に情けない気分になりながらも、明日から徹底的にモモの味の調査を行うことを決意した。
今日はタクシーをチャーターして、マクロード・ガンジから日帰りで行ける観光スポットを3〜4ヶ所見て回ることにした。昨夜ホテルのレセプションでタクシーのアレンジを頼んでおいた。
朝9時にホテルを出発。自動車はターター社のセダン車、インディゴ。ドライバーの名前はサンジュー。ダラムシャーラーの麓のガガル出身。陽気でおしゃべりな人だったので、楽しくドライブをすることができた。ヒマーチャル・プラデーシュ州で話されているパハーリー方言を少し教わることもできた。ただ、一口にパハーリー方言と言っても、谷ごと、町ごとにかなり異なっているようだ。
タクシーの値段は、昨夜オーナーと交渉して、1500ルピーで決着が着いた。インディゴは高級な自動車の部類に入るし、山道の走行なので、妥当な値段だろうと判断した。だが、今日になって僕の運と判断は想像以上によかったことが実感された。ちょうど本日、全インド石油業者組合の全国一斉ストライキが行われ、全てのガソリンスタンドが終日閉業となってしまっていた。これを受け、ダラムシャーラーやマクロード・ガンジ一帯のタクシーの値段が2倍に跳ね上がってしまったのだ。インドのタクシーは、大体客を獲得してからガソリンを入れる。だからガソリンスタンドのストライキはもろにタクシーにも影響を与える。だが、サンジューは賢明にも昨夜ガソリンを給油しており、ストライキの影響は全くなかった。
マクロード・ガンジを下り、下界に下りた。まず目指すはカーングラー。その名の通り、カーングラー谷の中心都市である。カーングラーとは、「カーン(耳)」+「ガル(砦)」が語源となっているそうだ。ジャランダルという巨人が神々との戦いに敗れて倒れたとき、耳があった場所に砦が立てられたために、「カーンガル」と呼ばれるようになり、それが訛って「カーングラー」になったと伝えられている。カーングラーはナガルコートとも呼ばれていた。カーングラーの標高は734m。もはやこのぐらいの高度だと、北インドの酷暑を軽減することは不可能である。しかもここ数日間、北インドを熱波が襲っているため、暑さは雨季を前にして極限に達している。
カーングラーで有名なのは、バジュレーシュワリー女神寺院。バジュレーシュワリー女神はドゥルガー女神の一種である。インド神話には以下のような有名な話がある――シヴァ神の妻サティーが、父親ダクシャ王の夫シヴァ神に対する侮蔑に抗議して焼身自殺をすると、シヴァ神は悲嘆にくれてサティーの屍を抱いて世界を滅茶苦茶に荒らしまわった。ヴィシュヌ神はシヴァ神の悲しみを軽減するために、サティーの屍をチャクラ(円盤状の武器)で切り刻んだ。サティーの身体は51片に分かれ、インド各地に落ちた。それらの場所はスィッドシャクティピートと呼ばれ、ヒンドゥー教の重要な聖地となった――バジュレーシュワリー女神寺院は、サティーの左乳房が落ちた場所だとされており、スィッドシャクティピートのひとつである。

バジュレーシュワリー女神寺院
バジュレーシュワリー女神寺院は昔から多くの信者と寄進を集めた寺院のようで、その富は常に侵略者の標的となっていた。例えば、1009年にはメヘムード・ガズナヴィーが、1360年にはムハンマド・ビン・トゥグラクが寺院を略奪したが、寺院は略奪の度に復興し、現在でもカーングラー谷の中心的な寺院として権威を誇っている。この寺院は完全に生きた寺院であり、現存する寺院からはあまり古さを感じなかったが、寺院の各所にけっこう古そうなヒンドゥー教の神々の像が見受けられ、寺院の歴史を物語っていた。本殿入り口の正面には、女神に自分の頭を切って捧げたデャーヌーという狂信的信者の頭像が祀られている。デャーヌーは女神を崇拝するあまり、自分の頭を切って女神に捧げた。すると女神は彼の前に姿を現し、頭と胴体をくっつけた。生き返ったデャーヌーは、再び自分の首を切って女神に捧げた。またも女神が現れ、彼の首をつなげた。しかし今度は女神は彼に、「3度目に首を切ったときはもう戻りません」と忠告した。それでもデャーヌーは首を切ってしまった。今度ばかりはもうデャーヌーは生き返ることはなかった。こんななんとも言えない伝承があるデャーヌーの頭像だが、雨が降らないときは、この頭に牛乳、牛糞、ガンガーの聖水、ヨーグルト、蜂蜜の5品を捧げて祈祷すると、雨が降り出すと言われているそうだ。
カーングラーの中心街から2.5kmほど離れた場所には、カーングラー砦がある。伝説によるとこの城塞は、マハーバーラタ戦争の後、スシャルマー・チャンドラによって建造されたという。よって、カーングラーは昔、スシャルマープル(スシャルマーの街)と呼ばれていた。また、カーングラー砦を中心とする地域はカトーチ地方と呼ばれていた。だが、カーングラー砦が歴史に登場するのは、1009年にメヘムード・ガズナヴィーによって奪取されてからである。以後、カーングラー砦は波乱に満ちた歴史を経験する。メヘムードはカーングラー砦に駐屯軍を置いて去って行ったが、1043年にはデリーのトーマル王朝が砦を奪い返し、カトーチ地方の王族に返還した。その後、イスラーム勢力のインドへの侵入が繰り返される度にカーングラー砦も攻略され、1337年にはムハンマド・ビン・トゥグラクが、1357年にはフィーローズ・シャー・トゥグラクが、1372年にはアクバルの将軍カーネ・ジャハーンが、1615年にはジャハーンギールの将軍スィカンダル・ムルタザーがこの砦を陥落させた。しかし、すぐにヒンドゥーの地元勢力に奪い返され、これらムスリム王朝の支配は永続的には続かなかった。そこで、1621年にジャハーンギールが自ら軍勢を率い、14ヶ月に渡る攻防戦の末にカーングラー砦を陥落させ、サイフ・アリー・カーンをこの地方の太守に任命した。この後、カーングラー砦は約150年間ムガル朝の支配下に置かれた。1786年にカトーチ王朝のサンサール・チャンド2世がムガル朝衰退の隙を突いてカーングラー砦を奪取すると、カーングラー谷は最盛期を迎え、芸術や工芸が大いに発展した。サンサール・チャンド2世は領土欲の強い藩王で、近隣の王国に攻撃を繰り返し領土を拡張した。しかし、その栄華は長く続くかなかった。1805年にネパールのアマル・スィン・ターパーの攻略を受けたのだ。サンサール・チャンド2世に苦汁を舐めさせられていた近隣の山岳王朝もネパール軍に加勢し、篭城戦は4年間に渡って続いた。1809年、窮地に陥ったサンサール・チャンド2世は、かつて敵対関係にあったパンジャーブ王国の藩王ランジート・スィンに救援を要請し、アマル・スィン・ターパーの軍勢を追い返すことに成功すると、条約に従ってカーングラー砦はランジート・スィンに譲渡された。その後、1846年に英国の支配下に入ると、カーングラー砦は軍の駐屯地として重要な拠点となったが、1905年4月4日にヒマーラヤ地域を襲った大地震により、城塞は崩壊し、以後廃墟となってしまった。

カーングラー砦
カーングラー砦は断崖絶壁の頂上に位置する城塞であるが、ラージャスターン州やマハーラーシュトラ州に多く残る圧倒的規模の城塞や、ハイダラーバード近くにあるゴールコンダー砦などと比較すると、小じんまりとした印象を払拭できない。入場料はインド人5ルピー、外国人100ルピー。いくつかの門をくぐり抜け、坂を上って行くと、すぐに宮殿部に辿り着く。内部は完全に廃墟となってしまっており、どこに何があったかを識別するのは今や困難である。カーングラー砦最大の見所はヒンドゥー寺院跡であろう。ほとんど壁しか残っていないが、繊細な彫刻を見ることができる。カーングラー砦のそばには小さな博物館があり、カーングラー砦から出土した石像や、カーングラー派の細密画のコレクションを見ることができる。

城塞内部

寺院跡の壁に残る繊細な彫刻
次に向かったのは、カーングラーから南に34kmの地点にあるジュワーラームキー。地元の人々からはジュワーラージーと呼ばれている。ここもサティーの身体の一部が落ちたスィッドシャクティピートの1つであり、ドゥルガー女神の一種を祀った寺院がある。この寺院のご本尊は、面白いことに「自然に燃え続ける火」である。油やロウソクなどもなくても燃え続ける火が祀られているのだ。こう聞くと不思議だが、何てことはない、天然ガスが地中から噴き出しているのだ。何だか面白そうなので行ってみることにした。カーングラーも暑かったが、ジュワーラームキーはさらに標高が低く、もはやデリーと変わらぬ灼熱であった。これでは避暑に来た意味がないと嘆きながらも、ジュワーラージーの門前町を通り抜けて、寺院の境内に入った。境内は小さな山の上にあった。

ジュワーラー女神寺院
ジュワーラージーの本殿は、黄金の屋根を抱いた小さな建物だった。この屋根は、ムガル朝のアクバルやパンジャーブ王国のランジート・スィンによって寄進されたらしい。12時過ぎに着いたが、本殿の入り口は閉まっていた。12時半に開くという。既に参拝者の長い列ができていた。僕も他の参拝者と一緒になってその列に並んだ。一応列に沿って布製の屋根が設置されていたが、影になっているところ以外は強い日差しにより、熱せられた鉄板のように熱くなっていた。インドの宗教施設の大半は靴を脱いで裸足で上がらなければならないが、床が歩けないくらい熱せられていることが多く、裸足に慣れていない外国人にはきつい試練となっている。その灼熱の床の上を、インド人たちは平気で裸足で歩いていくので、「インド人の足の皮は厚いのだなぁ」と驚くものだが、このジュワーラージーの床は、そのインド人にとっても耐えられないくらいの熱さだったようで、日向を移動するときはみんな悲鳴を上げながら走っていた。いかに暑かったかがうかがい知れることだろう。
本殿の門が開くと同時に、参拝客は我先に中に突入せんと押し合いへし合いをし出した。インドでは参拝客の群集が将棋倒しになって死傷者が出る事件がときどき報道されるが、それに思わず納得してしまうほどの大混雑である。門が開いて数十分後にようやく本殿の中に入ることができた。中央部は一段低くなっており、パンディトジー(僧侶)たちが信者たちから供え物を受け取っていた。よく見ると、その低くなった部分の壁に煌々と青い火が燃えている。これがジュワーラージーのご本尊である。本殿内は写真撮影禁止だったので、写真を撮ることはできなかった。
ジュワーラージーの霊験に関して、以下のような伝承が伝わっている。少し長いが引用する。
アクバルの時代。ナドーン村のデャーヌーは女神の信者であり、千人の信者を連れてジュワーラージーまで巡礼の旅に出掛けた。ムガル王朝の兵隊たちは、それら巡礼者の大群集をデリーのチャーンドニー・チャウクで見かけて呼びとめ、デャーヌーをアクバルのもとへ連行した。
アクバルは尋ねた。「お前はこんなに多くの人々を引き連れてどこへ行く積もりか?」
デャーヌーは手を合わせて答えた。「私はジュワーラー女神を参拝しに行くところです。私と共にいる人々も女神の信者で、同じ場所へ巡礼に行くところです。」
アクバルはそれを聞いて言った。「ジュワーラー女神とは何か?そこへ参拝すると何かいいことがあるのか?」
デャーヌーは答えた。「ジュワーラー女神はこの世界を創造し、見守る女神です。女神は信者たちの誠意に満ちた祈りを受け入れ、願い事をかなえてくれます。女神の寺院では、油もロウソクもないのに火が燃え続けています。我々は毎年女神の参拝に行っています。」
アクバルは言った。「それだけでジュワーラー女神とやらの偉大さを信じることがどうしてできようか。我が目の前で何か奇跡を起こしてみよ、そうすれば我もその話を信じようではないか。」
デャーヌーは答えた。「私は女神の一信者に過ぎません。どうして奇跡を起こして見せることができましょうか?」
アクバルは言った。「もしお前の信仰が純粋かつ真実ならば、女神はお前を見捨てることはないだろう。お前のような信者を見守ることがないならば、女神を信仰して何の利益があろうか?女神が偽物か、それともお前の信仰が足りないかだろう。我がお前と女神に試練を課そう。我はお前の馬の首を斬らせる命令を出す。お前は女神に馬を生き返らせるように頼んで来い。」
命令通り、馬の首は斬られた。
デャーヌーはアクバルに1ヶ月の猶予をもらい、馬の首と身体を保存しておくようお願いをした。アクバルはデャーヌーの願いを聞き入れ、ジュワーラージー巡礼の許可も出した。
デャーヌーは巡礼者の群集と共にジュワーラージーを訪れ、一晩中礼拝を行った。早朝、デャーヌーは手を合わせて女神に呼び掛けた。「女神様!あなたは全てお見通しです。皇帝が私の信仰心を試しています。私を助けて下さい。私の馬を蘇らせて下さい。奇跡を見せて下さい。もし私の願いが聞き届けられないならば、私も自分の首を切って死にます。なぜなら、恥を忍んで生きるよりは死んだ方がましだからです。これが私の願いです。どうか聞き届けて下さい。」
デャーヌーはしばらく黙っていた。
だが、何も起こらなかった。
その後、デャーヌーは剣で自分の首を切って女神に捧げた。
そのとき、ジュワーラー女神が現れ、デャーヌーの首を身体にくっつけ、彼を生き返らせた。女神はデャーヌーに言った。「今、デリーでも馬の首と身体がくっつきました。迷うことなくデリーへ行きなさい。何も恥じることはありません。他に何か願い事があれば言いなさい。」
デャーヌーは女神の足元にひれ伏して言った。「女神様!あなたこそ全能の神です。我ら人間は無知で、信仰の方法も知りません。それでも私はあなたにお願いをしたいと思います。女神様!どうかもうご自分の信者たちにこのような困難な試練を与えないで下さい。全ての信者があなたに首を捧げることはできません。どうか、女神様、もっと簡単な供え物で信者たちの願望をかなえて下さい。」
女神は言った。「承知しました!これより私は首の代わりにココナッツの供え物と誠意のこもった祈祷によりなされた願い事をかなえることにしましょう。」そして女神は消えてしまった。
そのとき、デリーでは死んだはずの馬の首と身体が自然にくっついた。アクバルの王宮の全ての人々は女神の奇跡に驚いた。アクバルは兵士たちをジュワーラージーに送った。兵士たちは戻って来るとアクバルに言った。「ジュワーラージーでは、地中から光が湧き出ています。おそらく女神の奇跡によるものでしょう。もし命令を下されるならば、我々がそれを閉ざしてしまいます。このようなヒンドゥー教徒たちの信仰の地は潰してしまうべきです。」
アクバルはそれを承諾した。アクバルの兵士たちはまず、分厚い鉄板を置いて女神の炎を塞ごうとした。しかし、聖なる炎は鉄板を突き破って出てきた。今度は小川の水を引いてきて、炎の上にかけ、火を消そうとした。しかし、炎は水の中でも消えなかった。そこで兵士たちはアクバルに伝えた。「あらゆる努力をしましたが、炎を消すことはできませんでした。いかがいたしましょうか?」
アクバルはこの伝言を受け取ると、王宮の学者や僧侶たちを集めて助言を求めた。僧侶たちはアクバルに、自分でジュワーラージーまで行って女神の奇跡を見て、慣わしに則って供え物を捧げ、女神を喜ばせるべきだと助言した。アクバルはその助言を受け入れ、純金製の傘を自らの肩に担ぎ、裸足で寺院まで参拝した。アクバルは聖なる炎を見て自然とひれ伏し、純金製の傘を女神に捧げようとした。ところが、傘は地面に落ちて砕け散ってしまった。そのとき、純金で造らせたはずの傘は、鉄でも真ちゅうでも銅でもガラスでもない、見たこともない金属に変質していたという。つまり、女神はアクバルの供え物を受け容れなかった。
この奇跡を見たアクバルは、あらゆる種類の儀式を行って女神の怒りを静めようと試み、デリーへ帰って行った。デリーに到着すると、アクバルは兵士たちに、女神の信者たちを尊重するよう命令を出した。
今でも、アクバルによって捧げられ、砕け散ってしまった傘が、ジュワーラージー寺院の境内に残っている。
この縁起話は、バジュレーシュワリー寺院の門前町に売られていたヒンディー語の小冊子「カーングラー観光とバジュレーシュワリー女神の話」(25ルピー)から抜粋したものだ。インドの大きな寺院の門前町には、必ずこの種の、寺院の縁起話や地域に伝わる伝承をまとめた小冊子が売られており、よく読むと面白い。ただ、英語版が用意されているのは、外国人も訪れるような大きな寺院のみであり、ローカルな寺院になると、現地語の小冊子しかないことが多い。この小冊子を読んだのはホテルに戻ってからであり、残念ながらアクバルの傘を見ることができなかった。暑すぎてバテバテになっていたので、本殿の炎を見た後は一目散に寺院を出てしまった。それにしても、バジュレーシュワリー女神に頭を捧げた信者デャーヌーの話と、ジュワーラー女神に頭を捧げた信者デャーヌーの話が酷似しているのは興味深い。この話を読むと、おそらくこれらの寺院では昔、首狩りと人身供養が行われていたであろうことが推測される。ヒンドゥー教の寺院では、よくココナッツが捧げられるが、あれは人頭の代替物なのだろう。また、ジュワーラージーのこの話は、アクバルが人身供養を禁止した出来事の変形と読み取ることも可能であろう。
ところで、ジュワーラージーの門前町で面白いものを見つけた。「コンピューター占い師」と書かれており、説明書きには「このコンピューター製の人形は、インド占星術に従って、過去、現在、未来の簡潔な占いと、人生に起こる重要な出来事を、簡単な口語により伝えます」と書かれていた。このような占いマシーンは他の場所でも見たことがあったが、試したことはなかった。ここではおじさんが退屈そうにしていたので、ちょっとやってみることにした。1回5ルピー。ヘッドフォンを耳に当てると、怪しいおっさん声でヒンディー語による占いの読み上げが始まった。細部は忘れたが、まとめると「今年はいいことがあるけど、心身清く正しくして頑張るともっと吉だよ」みたいな当たり障りのない内容だった。また、「1、3、5」の3つの数字が僕のラッキーナンバーだそうだ。う〜ん、ラッキーナンバーにしてはちょっと多すぎないだろうか・・・。仕掛けは簡単で、人形の正面に付いたいくつかのスイッチの内、おじさんが適当にひとつをONにすると、音声が流れ出すという仕組みだ。

コンピューター占い師
ジュワーラージーの次はマスルールへ行った。マスルール村の近くにある山の上には、エローラのカイラースナート寺院のような石彫寺院が残っている。誰が造ったかは明らかになっていないものの、8〜9世紀の建立だと推定されており、北インドに唯一現存する石彫寺院として重要な遺跡となっている。入場料はインド人5ルピー、外国人100ルピー。マクロード・ガンジやカーングラー砦と同じく、1905年4月4日の大地震で崩壊してしまっているが、それでも寺院がどのような形をしていたのかは、かろうじて感じ取ることができる。元々15のシカラ(砲弾状の尖塔)があったようだが、今では10個ほどしか残っていない。ラーム、スィーター、ラクシュマンを祀った本殿は完成していたと見られるが、両翼の部屋はまだ掘られておらず、未完成のまま放置されたのだろう。寺院の各壁面には繊細な彫刻が部分的に残っている。また、寺院の前には大きな貯水湖があり、魚が威勢良く泳いでいた。

マスルールの石彫寺院

本殿入り口の彫刻
マスルールを見た後はマクロード・ガンジに戻った。マクロード・ガンジに着いたのは午後4時半頃。午前9時に出たので、合計7時間半ほどの日帰り旅行であった。
マクロード・ガンジに戻ってからは、バーザールを散歩した。急にひとつ欲しいものが思い付いた。延々と「オーム・マニ・パドメ・フム、オーム・マニ・パドメ・フム・・・」と繰り返されるチベット音楽のCDが欲しかったのだ。一度友人の家で聞いて、これはかなりトリップする音楽だと思い、ずっと欲しいと思っていた。マクロード・ガンジではチベット関係のものがたくさん売られているのできっと手に入るはずだと思い、露天のCD屋で聞いてみたら、海賊版であったがすぐに見つかった。CDの題名は「Tibetan Incantations」で、僕が欲しかった曲の名前はそのまま「Om Mani Padme Hum」だった。海賊版CDを買うのはポリシーに反するのでオリジナルがあるか聞いてみたが、どうやらインドにこのCDのオリジナルは1枚しかないらしく、購入は困難で、チベッタン・マーケットなどで売られている「Tibetan Incantations」のCDは全て、その1枚のオリジナルからコピーされた海賊版らしい。本当かどうか知らないが、そういう事情なので海賊版CDを買うことにした。一応調べてみたら、このCDは1998年にチベットで発売されたもののようだ。チベット音楽のCDが欲しかったら、このCDはオススメである。

Tibetan Incantations
ついでなので、そのCD屋の兄ちゃんにおいしいマトン・モモの店を聞いたら教えてくれた。早速教えてもらった店へ行って、メニューも見ずにマトン・モモを注文した。しかし、ここのマトン・モモもイマイチであった。ダルハウジーで食べたような、皮を噛むと汁がジュワーと溢れ出てくるようなジューシーさを持つマトン・モモは、ここにはないのだろうか?経験上、ひたすらモモだけを作っているような店が一番うまいのだが、マクロード・ガンジにはそのような店は見当たらなかった。一応、ジョーギーバラー・ロードで、チベット人やインド人が道の隅でモモ蒸し器を置いてモモを売っているが、ほとんどヴェジ・モモだった。やはりチベット仏教最高指導者のお膝元なので、菜食主義者が多いのかもしれない。ダライ・ラマは肉を食べていると専らの噂だが。・・・そこで、方針を転換して、ヴェジ・モモを食べてみることにした。もしかしたらマクロード・ガンジの名物はヴェジ・モモなのかもしれない、と思い付いたからだ。ジョーギーバラー・ロードの適当な露店で、ジャガイモとほうれん草が入ったヴェジ・モモを買ってみた。5個で6ルピーという格安の値段だった。そのモモは、餃子というより饅頭に近く、皮がふかふかしておいしかったが、具は野菜だけなのでやっぱりピンと来ない。もはやマクロード・ガンジでモモを食べるのは諦めた。
ところで、これは後から聞いた話だが、どうやらマクロード・ガンジで一番おいしいチベット料理屋は、ホテル・チベットのレストランのようだ。また、現在日本人女性がホテル・トーキョーというゲストハウスをマクロード・ガンジで開いており、日本人の手作り親子丼を食べることができるそうだ。あと、マクロード・ガンジでは多くのイタリア料理レストランが開業しているが、おいしいイタリア料理を食べられる場所は皆無に近いと思われる。僕もある店でスパゲッティーを試してみたが、ただ腹を膨らませるだけの料理という程度だった。しかし何よりマクロード・ガンジで最も美味だったのは、「マナーリー」というブランドのミネラル・ウォーターである。インドにはビズレリ、アクアフィーナ、キンレー、ヒマーラヤ、キャッチ、エビアンなど、いろいろなブランドのミネラル・ウォーターが売られているが、その中でも最もおいしいのがこの「マナーリー」だと思った。ヒマーチャル・プラデーシュ州の特産水なのだろう。こんなうまい水があるのか、と驚いたほどだった。
今日はデリーに戻る日である。しかし、旅行記の初めにも述べたように、僕の帰りの列車のチケットもウェイティング・リストだった。昨日からネット・カフェでインド鉄道のウェブサイトにアクセスして状況を確認していたのだが、僕の番号はやっとウェイティング・ナンバー5まで上がっただけだった。僕の前に4人、席が空くのを待っている人がいる状態である。微妙な数字であった。この列車は、現在インド人避暑客が押し寄せているシュリーナガルへ通じており、特に座席入手は困難である。今日の午前にもチェックをしてみたが、やはり5番のまま。列車はパターンコートを午後11時5分に出て、デリーには翌日午前11時5分に着く予定だった。
だが、考えてみたらマクロード・ガンジからは多くのデラックス・バスがデリーへ行っている。調べてみたら、午後7時に出発して、翌日午前6時にはデリーに到着するらしい。もちろん列車の寝台で一夜を明かす方が格段に楽なのだが、一度わざわざパターンコートまで戻って(3時間かかる)、そこから席があるかどうか不確かな列車を深夜に待つのは面倒に思えてきた。そこで即決を下し、列車のチケットはキャンセルして、デラックス・バスでデリーに戻ることにした。マクロード・ガンジからデリーまでは400ルピーだった。
この決断を下したのは午後1時頃だった。今日中に列車のチケットをキャンセルすれば、料金は全額戻って来る。もし明日になると、半額になってしまう。マクロード・ガンジやダラムシャーラーには鉄道が通っていないが、ダラムシャーラーに鉄道予約オフィスがあるとの情報を得たので、そこでキャンセルをすることにした。オフィスは午後2時に閉まってしまうとのことなので、急いで向かうためにタクシーに乗ってダラムシャーラーへ向かった(100ルピー)。
鉄道予約オフィスの窓口はひとつしかなかったが、そこには2人が並んでいるだけだった。閉業時間まであと30分ほどある。これなら余裕でキャンセルできるだろう、と胸をなで下ろした。が、ここはインド。安堵の溜息をついた途端に、失意の金槌は容赦なく振り下ろされる。係員はノロノロと作業をし、窓口の裏に座っている人と呑気に談笑していて、全く仕事が進んでいなかった。やっとのことで、並んでいた人の1人の人のチケットの発券が済んだが、その人は3枚のチケットを頼んだのに、2枚しかもらえなかった。よって、その人は「あと1枚くれ」と窓口にそのまま居座った。係員は次の人のチケットの予約作業に入った。すると、突然コンピューターの予約システムが故障してしまったようで、窓口には「System
Fail」との札が掲げられた。もう閉業まであと10分ほどしかない。また、新たに数人の人が列に並んだ。みんなで故障が直るのを待っていたが、遂に閉業時間までコンピューターは復帰しなかった。係員は「また明日の朝来い」と言ってスタスタと立ち去ってしまった。・・・呆然と取り残される人々・・・。インドによくある風景とは言え、腹が立った。どうか、外国人が多く訪れるような場所でこんなことを行わないでもらいたい。インドの恥をさらすことになる・・・。
せっかくダラムシャーラーまで下ってきたので、ここでも懲りずにおいしいモモを探してみることにした。モモしか作っていない店かつノン・ヴェジのモモも作っている店を探したが、なかなかそのようなところは見つからなかった。雨が降り出してしまったので、近くにあったモーナール・レストランに入ってマトン・モモを注文してみた(30ルピー)。それが大正解。ダルハウジーのモモには及ばなかったが、具がいい具合に味付けされていた。やっとおいしいモモにありつくことができた。
ダラムシャーラーでは、バススタンド近くにあるカーングラー美術館にも行ってみた。入場料は10ルピー。カーングラー地方から出土した石像、カーングラー派の細密画、チャンバーの刺繍ハンカチ、カーングラー砦の模型、武器などが展示されていた。また、地元の画家のものと思われる絵画の展示もあった。しかし、それほど面白い美術館でもなかった。
バスでマクロード・ガンジまで戻ったときには午後4時になっていた。既にホテルはチェックアウトしてあり、荷物をホテルに預けてあった。バスの出発時刻まで暇なので、インターネット・カフェでネットをして時間を潰した。マクロード・ガンジのような有名な観光地では、インターネットの設備が整っており、しかも日本語が使えるようになっているところが多いので便利である。ノートPCをそのままネットにつなげる設備があるネット・カフェもあった。
午後6時半頃、ホテルに預けていた荷物を受け取って、いざバスのところまで行こうとしていたところ、携帯に電話があり、列車の席が取れた旨が知らされた。どうもタイミングが悪い。だが、もうパターンコートまで3時間かけて行く気はなかったので、列車チケットは断った。
ところで、インドで「デラックス」という言葉を信じてはならない。インド人はやたらと「デラックス」という形容詞をつけたがるが、その言葉が示すイメージを、その形容詞によって修飾された事物が実現していることは稀である。僕が買ったデリー行きのバスも、デラックス・バスであった。僕はこの「デラックス」という言葉の罠を知っていたが、しかし不覚にもこの「デラックス」が、「ACバス」という意味を含むと勘違いする初歩的なミスを犯してしまっていた。確かに公営のバスよりは席が広かったが、ACがない上に、窓際に設置されたなけなしの小さな扇風機まで作動しないというデラックス振りであった。窓を開けて、天然のクーラーに頼るしかない。マクロード・ガンジはまだマシだが、下界に下りたらこの天然のクーラーが天然のドライヤーに一変することは目に見えていた。しかし窓を開けざるをえなかった。唯一救いだったのは、隣に座ったのが日本人の女の子の旅行者だったことだ。おかげで日本語で話をしながら行くことができ、苦痛を紛らわすことができた。他に、バスの乗客の半分ほどは外国人で、半分ほどはチベット人、少しだけインド人が乗っていた。
案の定、高度が下がるにつれて窓から流れ込んでくる風は熱風に変わって行った。持参したボトル・ウォーターはすぐに空になってしまった。夕食を食べていなかったので、早く食事休憩にならないかと思っていたが、9時を過ぎ、10時を過ぎてしまったので、もう諦め、ウトウトしていた。そうしたら、ヒマーチャル・プラデーシュ州の平野近くの街ウナーで食事休憩があった。既に時計は11時半を回っていた。目の前には「デリーまであと320km」の看板があった。「ディッリー・ドゥール・ハェ(デリーは遠い)」という諺が思い起こされた。本当に午前6時にデリーに着くのだろうか?
まずくて量が多い最悪のチョウメンを食べ、再びバスに乗り込んだ。パンジャーブ州に入り、大きなダムがあったのを憶えているが、そこからは記憶がない。気付いたときには明るくなっていた。バスはデリーの北端まで到達していた。チベット人の大規模な難民キャンプがあるマジュヌ・カ・ティッラーで一旦停車し、そこからパハール・ガンジまで行ってくれた。外国人旅行者に対する配慮だろう。僕はそこでオート・リクシャーを拾って自宅まで戻った。
| ◆ |
6月22日(水) Bachke Rehna Re Baba |
◆ |
旅行から帰って来たばかりであると同時に、デリーの殺人的暑さにまいっているところであったが、僕の映画に対する情熱は疲労と暑さを吹き飛ばすほどで、すぐに映画をPVRアヌパムまで見に出かけた。今日見た映画は、先週の金曜日から公開の「Bachke
Rehna Re Baba」。題名の意味は、「気を付けなさい」みたいな意味。映画のストーリーから判断して、「恋に要注意」みたいな意味が暗示されている。監督はゴーヴィンド・メーナン、音楽はアヌ・マリク。キャストは、レーカー、マッリカー・シェーラーワト、サティーシュ・シャー、パレーシュ・ラーワル、カラン・カンナー(新人)である。
| Bachke Rehna Re Baba |
 ルクミニー(レーカー)とその姪のパドミニー(マッリカー・シェーラーワト)は、美貌とチームワークを武器に結婚詐欺を行って、金持ちの独身男性から大金をせしめることを生業としていた。2人は、パンジャービーの富豪モンティー(パレーシュ・ラーワル)を騙したばかりだった。手順は以下の通りだった。まずルクミニーがモンティーを誘惑し、結婚まで行き着く。結婚式の初夜にパドミニーがモンティーを誘惑し、2人が自動車の中でもつれ合っているところにルクミニーがタイミングよく現れる。怒ったルクミニーは離婚を宣言すると同時に、彼から慰謝料をガッポリ頂く。こうして2人はモンティーから250万ルピーを手に入れていた。しかし、パドミニーはもうこんな詐欺はしたくないと考えており、最後の大仕事をして、結婚詐欺業から足を洗おうと決めた。二人は大物を捕まえるため、モーリシャスに飛ぶ。【写真は、左からカラン・カンナー、マッリカー・シェーラーワト、パレーシュ・ラーワル、レーカー】 ルクミニー(レーカー)とその姪のパドミニー(マッリカー・シェーラーワト)は、美貌とチームワークを武器に結婚詐欺を行って、金持ちの独身男性から大金をせしめることを生業としていた。2人は、パンジャービーの富豪モンティー(パレーシュ・ラーワル)を騙したばかりだった。手順は以下の通りだった。まずルクミニーがモンティーを誘惑し、結婚まで行き着く。結婚式の初夜にパドミニーがモンティーを誘惑し、2人が自動車の中でもつれ合っているところにルクミニーがタイミングよく現れる。怒ったルクミニーは離婚を宣言すると同時に、彼から慰謝料をガッポリ頂く。こうして2人はモンティーから250万ルピーを手に入れていた。しかし、パドミニーはもうこんな詐欺はしたくないと考えており、最後の大仕事をして、結婚詐欺業から足を洗おうと決めた。二人は大物を捕まえるため、モーリシャスに飛ぶ。【写真は、左からカラン・カンナー、マッリカー・シェーラーワト、パレーシュ・ラーワル、レーカー】
モーリシャスで、ルクミニーはスィンド人大富豪マンスカーニー(サティーシュ・シャー)に目を付ける。一方、パドミニーは、ホテルのレストランでウェイターで、その実はそのレストランのオーナーの息子であるラグー(カラン・カンナー)と出会う。ルクミニーはパドミニーに、「仕事に恋は厳禁」と戒めるが、パドミニーはラグーへの恋に落ちていってしまう。
ルクミニーは首尾よくマンスカーニーの気を引き、プロポーズまで受けるが、そのときマンスカーニーは突然ポックリと死んでしまう。ルクミニーとパドミニーは、マンスカーニーの遺体を彼の家に運ぶが、ルクミニーのことが忘れられないモンティーがモーリシャスまで追いかけて来ており、ルクミニーは見つかってしまう。ルクミニーとパドミニーが詐欺師であることを見抜いたモンティーは、自分から騙し取った250万ルピーを12時間以内に返すよう求める。モンティーは、さもなくば警察に訴えると脅した。
2人のもとにそんな大金はなかった。ルクミニーは刑務所に入ることを決めるが、パドミニーは、モンティーに「ラグーを騙して金を手に入れるまで待ってほしい」と頼む。パドミニーはラグーのことを本心から愛していたが、そうしなければ2人とも刑務所行きになってしまうので仕方がなかった。モンティーも彼女たちと一緒になってラグーを騙し、パドミニーとラグーは婚約する。
パドミニーとラグーの結婚式の日。ルクミニーはラグーを誘惑し、自分の部屋に誘う。だが、ラグーは真面目な男だった。ルクミニーの誘惑には乗らなかった。そこで彼女は酒の中に睡眠薬をこっそり混ぜ、裸にして一緒にベッドに寝た。心中ではラグーが自分を裏切るはずはないと思っていたパドミニーは、その様子を見てショックを受ける。離婚は成立し、パドミニーはラグーから大金を手に入れる。しかし、パドミニーの将来を案じたルクミニーは、彼女に、本当はラグーは誘惑に乗らなかったことを打ち明ける。それを聞いたパドミニーはラグーのもとに走り、もう一度結婚して欲しいと頼む。ラグーは笑って応じる。また、ルクミニーもモンティーにもう一度結婚を申し込む。こうしてルクミニーとパドミニーは一緒に結婚式を挙げた。と、そこへマンスカーニーそっくりの男がやって来て2人は驚くが、実はそれはマンスカーニーの双子の弟だった。マンスカーニーは死ぬ前に、全ての財産をルクミニーの名義にしていたのだった。こうしてルクミニーとパドミニーは、大金も手に入れ、夫も手に入れることができた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
現在のボリウッドのセックス・シンボル、マッリカー・シェーラーワトのお色気全開のコメディー映画。しかも共演するは、「永遠の美貌と色気」を持つ伝説的女優レーカー。この2人のコンビが金持ちの男たちを次々と騙していく様子は、痛快と言えば痛快だが、男としては恐ろしい限りであった。映画のストーリーははっきり言ってしょうもない。
映画の最も成功している部分はキャラクター設定であろう。レーカー演じるルクミニーは、人生の酸いも甘いも知り尽くした大人の女性で、どうしたら男の心を操作することができるかを心得ていた。映画中のレーカーのファッションはオシャレと奇天烈の中間ぐらいで面白かった。また、レーカーがこんなコミカルな演技のできる女優だとは思ってもみなかったので驚いた。一方、マッリカー演じるパドミニーは、ルクミニーから男の操作法を学びながらも、まだ自分の心をコントロールする方法を完全にマスターしていなかった。彼女はルクミニーに対する競争心を燃やし、遂にはラグーと恋に落ちてしまう。マッリカーはやたらと胸元を強調したセクシーな服を着ており、セックス・シンボルの名をほしいままにしている。
この2人に騙される哀れな男役は、ボリウッドを代表するコメディー男優が演じた。サティーシュ・シャーは、常にグトカー(噛みタバコ)を噛み続けている気味の悪い大富豪を演じ、パレーシュ・ラーワルはルクミニーに騙されながらも盲目的恋から抜け出せない可哀想な男をキュートに演じていた。その他、パドミニーと恋に落ちるハンサムな青年役を演じていたのが、この映画がデビュー作となるカラン・カンナー。それほど出番が多くなかったが、無難な演技をしていたと思う。だが、やはりこの映画の主人公は、レーカーとマッリカー以外に考えられない。

セクシーなマッリカーと変な衣装のレーカー
映画中、いくつも爆笑スポットがある。例えば、マンスカーニーがオークションで落札しようとしていた「裸の労働者」という石像。チンコ丸出しの変な像である。ルクミニーは、自分のことを印象付けてもらうためにわざとオークションで値段を上げるが、誤って彼女が落札してしまう。落札額ほどの大金を持っていない彼女は、わざと「裸の労働者」のチンコを折り、「こんな不良品はいらないわ!」と投げ出す。また、マンスカーニーと会食することに成功したルクミニーが、「私はおフランス生まれですの」と言うと、マンスカーニーは「それは素晴らしい。ちょうど今日はフランス料理デーなんだ」ということで、フランス語でフランス料理を彼女に注文させる(モーリシャスではフランス語が話されている)。「ウイ(イエス)」と「ボンジュール(こんにちは)」ぐらいしかフランス語を知らないルクミニーは焦りながらもウェイターに適当に「ウイウイウイウイ」言って注文する。すると出てきたのは生タコ料理。ルクミニーは「ウッ」と一瞬顔をしかめながらも、「これ私の大好物ですの、オホホホホ」と言ってタコの足を口に放り込む(インド人は基本的にグロテスクな魚介料理を好まない)。しかもルクミニーはステージの上でフランス語で歌を歌わされ、ヒンディー語とフランス語を適当に混ぜた変な歌を歌う。何となく日本のギャグ漫画に似たノリのコメディー映画であった。
映画の4分の3以上はモーリシャスでのロケ。美しい海はもちろんのこと、その美しいビーチで観客を挑発するマッリカーの野性的なボディーも見所であろう。
音楽はアヌ・マリク。数あるミュージカル・シーンで最も印象的なのは、マッリカーの登場シーンに挿入される「Sharafat Chod De」であろう。SMの女王様みたいな格好をしたマッリカーが、腰をくねらせながら自分のお尻をペンペンするという、斬新なダンス。マッリカーのエロさ爆発である。しかも、最近いろいろな映画のダンスシーンによく出てくる東洋人顔のダンサーがけっこう活躍していて気になった。
ゴーヴィンド・メーナン監督は、際どい性描写で話題となった映画「Khwahish」(2003年)で有名となった監督で、以後マッリカー・シェーラーワトとタッグを組み続けている。
「Bachke Rehna Re Baba」は、視覚的には男性向け、ストーリー的には女性向けの映画のように思えた。レーカーとマッリカーのファンの人に特にオススメしたい映画であるが、あくまで理屈抜きで見なければいけない映画のひとつであろう。
今日は、先週から公開の新作ヒンディー語映画「Silsiilay」をPVRアヌパムで見た。「Silsiilay」とは「連鎖」とか「シリーズ」みたいな意味。3人の全く関係のない女性の話で構成されたオムニバス形式の映画である。監督は、「Fiza」(2000年)や「Tehzeeb」(2003年)のカーリド・ムハンマド監督、音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。なにげにオールスターキャストの映画で、ラーフル・ボース、ジミー・シェールギル、アシュミト・パテール、ケー・ケー・メーナン、カラン・パンタキー(新人)、タッブー、セリナ・ジェートリー、リヤー・セーン、ナターシャー、ブーミカー・チャーウラー、ディヴィヤー・ダッター、プリヤー・バドラーニーなど。シャールク・カーンがナレーションとして特別出演している。
| Silsiilay |
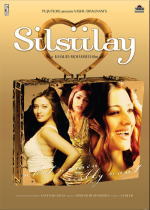 ズィヤー(ブーミカー・チャーウラー)は人気女優で、富、名声、欲しいものは全て手に入れていたが、たったひとつだけ手に入らなかったものがあった。それはニール(ラーフル・ボース)であった。ズィヤーとニールは相思相愛の仲であったが、忙しいズィヤーのスケジュールにより次第に疎遠となり、破局してしまったのだった。それでもズィヤーはニールのことを愛していた。ニールの子供が欲しいと思っていた。一方、ニールは同じ職場に勤めるナンディター(プリヤー・バドラーニー)と付き合っており、結婚間近だった。ズィヤーはある日、ニールを家に呼ぶ。彼女の家にはまだニールの荷物が置いてあったからだ。ニールのことを愛してやまないズィヤーだったが、彼の前ではわざと冷たい態度を取る。ニールは適当に受け流すものの、成り行きにより2人はベッドを共にする。次の日の朝、ズィヤーはニールに「ありがとう」と言う。ニールはその意味が分からなかった。ズィヤーと同居していた妹のディヤーは、ズィヤーが彼に1枚のDVDを渡さなかったのを見ていた。ズィヤーはそれを手に入れるために大金を費やしていたのだが、彼には渡さなかった。それを見たディヤーはニールのもとを訪れ、「あなたはいい人だけど、女性の心の痛みが分からない人よ」と言ってそのDVDを渡す。そのDVDは、ナンディターが出演するAVだった。ニールはナンディターと別れる。それからしばらく後、ズィヤーは妊娠していることに気付き、ニールに電話をする。【写真は、左からリヤー・セーン、ブーミカー・チャーウラー、タッブー】 ズィヤー(ブーミカー・チャーウラー)は人気女優で、富、名声、欲しいものは全て手に入れていたが、たったひとつだけ手に入らなかったものがあった。それはニール(ラーフル・ボース)であった。ズィヤーとニールは相思相愛の仲であったが、忙しいズィヤーのスケジュールにより次第に疎遠となり、破局してしまったのだった。それでもズィヤーはニールのことを愛していた。ニールの子供が欲しいと思っていた。一方、ニールは同じ職場に勤めるナンディター(プリヤー・バドラーニー)と付き合っており、結婚間近だった。ズィヤーはある日、ニールを家に呼ぶ。彼女の家にはまだニールの荷物が置いてあったからだ。ニールのことを愛してやまないズィヤーだったが、彼の前ではわざと冷たい態度を取る。ニールは適当に受け流すものの、成り行きにより2人はベッドを共にする。次の日の朝、ズィヤーはニールに「ありがとう」と言う。ニールはその意味が分からなかった。ズィヤーと同居していた妹のディヤーは、ズィヤーが彼に1枚のDVDを渡さなかったのを見ていた。ズィヤーはそれを手に入れるために大金を費やしていたのだが、彼には渡さなかった。それを見たディヤーはニールのもとを訪れ、「あなたはいい人だけど、女性の心の痛みが分からない人よ」と言ってそのDVDを渡す。そのDVDは、ナンディターが出演するAVだった。ニールはナンディターと別れる。それからしばらく後、ズィヤーは妊娠していることに気付き、ニールに電話をする。【写真は、左からリヤー・セーン、ブーミカー・チャーウラー、タッブー】
アヌーシュカー(リヤー・セーン)は、デヘラードゥーンからムンバイーに出てきて働く純朴な女の子だった。アヌーシュカーはニキル(アシュミト・パテール)という男と恋に落ちていたが、なかなか彼に貞操を捧げる決心がつかなかった。ルームメイトのピヤー(ナターシャー)はそんなアヌーシュカーと違って男好きな性格で、「そんなものいつまでもとっておいたって何の得にもならないわよ」と彼女を促す。ある日、ニキルとアヌーシュカーはホテルに泊まるが、アヌーシュカーはニキルのデリカシーのない態度に呆れ、また恐怖から逃げ出してしまう。一方、アヌーシュカーの勤める会社で働くタルン(ジミー・シェールギル)は、アヌーシュカーに恋していた。タルンは毎日彼女にバラを送っていたが、彼は彼女に恋人がいるのを知っていた。アヌーシュカーはタルンの気持ちを知りながらも、ニキルへの愛を止めることはできなかった。しかし、ニキルが他の女とホテルにいるところを見てしまい、アヌーシュカーの気持ちは一変する。そのときタルンの米国転勤が決まり、彼はアヌーシュカーに結婚を申し込むが、彼女はそれを拒否して言う。「私は初めて私自身に会うことができた気がするの。だから私はここにいたいの。」アヌーシュカーは米国へ旅立つタルンを空港で見送る。
リーハーナ(タッブー)はムスリムの大富豪アンワル(ケー・ケー・メーナン)の二番目の妻だった。最初の妻は死去しており、前妻の間にはイナーヤト(カラン・パンタキー)という息子がいた。アンワルは7年間に渡ってスチュワーデスのプリーティ(セリナ・ジェートリー)と不倫していたが、それを薄々感じながらリーハーナは黙って孤独な生活を耐えていた。また、密かに年頃のイナーヤトはリーハーナに恋をしていた。同時に、リーハーナを放っておいて不倫をしている父親に憎悪を燃やしていた。結婚記念日、リーハーナは夫の背広から指輪を見つける。自分へのプレゼントだと思ったリーハーナは幸せな気持ちになる。しかし、アンワルは「今夜も仕事で遅くなる」と言って出勤してしまった。それでもリーハーナは夫のことを信じていたが、イナーヤトはそんな義母の姿に耐えられなくなり、彼女を父親とプリーティの不倫現場まで連れて行く。その指輪は、プリーティへの贈り物だった。不倫現場を押えられたアンワルは、リーハーナと離婚をしようとし、「タラーク、タラーク・・・」まで言いかけるが、その瞬間リーハーナは、「私があなたを離婚するわ。私は絶対にあなたのために泣いたりしない」と言って出て行く。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
僕より以前にこの映画を鑑賞した、ある日本人女性のボリウッド映画ファンから、「この映画は女心の分からない人には分からない」と釘を刺された。僕の映画批評は、女性心理の理解に欠如があるとよく批判を受けるので、それを念頭に置いた忠告だったと思われる。よって、なるべく「女心」とやらの動向に気を遣って映画を見た。確かにこの映画は女性心理の複雑さを巧みに描いた映画であった。ここまで女性の共感を得られる映画を撮れるのは女性しかいないだろうと思ったが、なんと監督は男性。その割に、この映画に登場する男性はステレオタイプなキャラクターが多かったように思える。男性中心の映画は女性キャラクターがステレオタイプになるし、女性中心の映画は男性キャラクターがステレオタイプになるのは宿命なのだろうか?
まずはシャールク・カーンが登場し、この映画が「どこにでもいるような3人の女性のストーリー」であることが観客に伝えられる。「あなたの隣に座っている女性の話かもね」なんて言って観客を沸かしていた。その後もシャールク・カーンは、軽いノリで登場してシャレたことを口走って映画を進行させており、なかなか面白い工夫だと思った。テーマソングに合わせてシャールク・カーンがおかしなノリの踊りを踊るのも見所と言えば見所であろう。
基本的にズィヤー、アヌーシュカー、リーハーナのストーリーは全く独立したものである。だが、微妙な部分でリンクされており、最後にはズィヤーが外で産気づいてしかも交通事故に遭ったとき、たまたまアヌーシュカーとリーハーナもその場に居合わせる設定になっていた。しかし、3本のストーリーのリンクのさせ方は中途半端であり、全く独立させるか、それとももう少し深くリンクさせるか、どちらかにした方がよかったのではないかと思った。
3人の女性の話ということだが、その質にはばらつきがあった。おそらく女性の心理の複雑さを最も適格に描いたのは、最初のズィヤーのストーリーである。愛している男性の前でわざと強気かつ冷たい態度を取るという女性の性質が描写されていたし、愛する男性が自分のもとを永遠に去っていくのを潔い気持ちで見送るときの表情がうまく表されていた。また、演技の点ではタッブーが主演したリーハーナのストーリーが最も優れていた。夫の不倫現場を目の当たりにしながらも、夫の前で涙を見せずに離婚を言い渡すその演技は、タッブーが一流の演技派女優であることを存分に証明していた。一方、アヌーシュカーのストーリーは、プロットや演技の面から、この映画の中で最も弱い部分となってしまっていた。
監督はムスリムなので、映画にはムスリム色が強かったように思える。例えば、ズィヤーはウルドゥー語の中心地のひとつ、ハイダラーバード出身という設定で、彼女のことを「ジヤー」と呼ぶ人に対し、「ジヤーじゃなくてズィヤーよ」と注意していた。「Zia」の「Z」の発音は、アラビア語特有の発音で、実際には日本語の「ジ」でも「ズィ」でもないが、便宜的に「ズィヤー」と書いておいた。また、リーハーナのストーリーはムスリムの上流家庭が舞台となっており、話す言語もウルドゥー語であった。ちなみに、イスラーム教では、夫が妻の前で「タラーク(離婚)」という言葉を3回唱えると離婚が成立する。イスラーム法に女性から離婚する方法はない。アンワルはリーハーナの前で「タラーク」を2回まで言いかけた。だが、それを遮ってリーハーナは夫に離婚を言い渡した。
「Silsiilay」をまとめると、悲しみを乗り越えて自立していく3人の女性を描いた映画ということになるだろう。残念ながらヒットしておらず、一瞬の内に公開が終了しそうだが、隠れた名作だと思う。
今日から待ちに待った映画「Paheli」が始まった。この映画を見るために、死人が出るほどの暑さの中、インドに留まっていたようなものである。PVRプリヤーで鑑賞した。
題名の「Paheli」とは「なぞなぞ」みたいな意味。監督はアモール・パーレーカル、音楽はMMカリーム。原作は、ラージャスターン州に伝わる民話を基にヴィジャイ・ダーン・データーが書いた小説である。キャストは、シャールク・カーン、ラーニー・ムカルジー、アミターブ・バッチャン、ジューヒー・チャーウラー、スニール・シェッティー、アヌパム・ケール、ディリープ・プラバーカル、ラージパール・ヤーダヴなど。他にナスィールッディーン・シャーとその妻ラトナー・パータク・シャーが、声優出演。
| Paheli |
 美しいラージャスターニーの女の子ラッチー(ラーニー・ムカルジー)は、ナワルガルの豪商バンワルラール(アヌパム・ケール)の息子キシャン(シャールク・カーン)と結婚した。しかし、キシャンは金儲けしか頭にない男で、結婚式の翌日、商売のために5年間の予定でラッチーを残して旅立ってしまった。ラッチーは悲嘆に暮れていた。【写真は、シャールク・カーン(左)とラーニー・ムカルジー(右)】 美しいラージャスターニーの女の子ラッチー(ラーニー・ムカルジー)は、ナワルガルの豪商バンワルラール(アヌパム・ケール)の息子キシャン(シャールク・カーン)と結婚した。しかし、キシャンは金儲けしか頭にない男で、結婚式の翌日、商売のために5年間の予定でラッチーを残して旅立ってしまった。ラッチーは悲嘆に暮れていた。【写真は、シャールク・カーン(左)とラーニー・ムカルジー(右)】
そのとき、ラッチーの美しさを見て一目惚れした幽霊は、キシャンの姿に化けてバンワルラールの家にやって来た。幽霊は巧みにバンワルラールを言いくるめ、家族の中に入り込む。夫が帰って来たことを知ってラッチーは喜ぶ。ところが、幽霊は自分が本当はキシャンではなく、幽霊であることを彼女に打ち明ける。ラッチーは幽霊の愛と優しさを感じ、彼を受け容れる。
一方、自分の偽物が家にやって来たとは知らない本物のキシャンは、旅先で商売に精を出していた。彼は幾度も実家に手紙を書くが、配達人の機嫌を損ねたため、その手紙は実家には届かなかった。
ある日、毎年恒例のラクダレースが行われることになった。バンワルラール家は、7年前に叔父スンダルラール(スニール・シェッティー)がレースに敗北して、その恥と悔しさのために失踪して以来、ラクダレースには参加していなかった。だが、今年はキシャンの説得もあり、レースに参加することになった。バンワルラール家が出走させた2頭のラクダはレースに負けそうになるが、そのときキシャンは魔法を使って他のラクダを妨害し、バンワルラール家を勝たせる。
しかし、公衆の面前で魔法を使ったことをラッチーは面白く思わなかった。もしキシャンが幽霊であることが他の人にばれたらどうするのだろうか?ラッチーは幽霊に、今後絶対に人前で魔法を使わないように約束させる。
結婚から数年後、ラッチーは幽霊の子供を身ごもる。幽霊とラッチーは、その子供が女の子であることを祈り、名前も2人で決める。だが、ラッチーがいざ産気づいたときに、本物のキシャンが家に帰って来てしまう。バンワルラール家では2人のキシャンが鉢合わせし、人々は困惑する。キシャンは必死に自分が本物であることを訴えるが、バンワルラールは信じなかった。そこでマハーラージャーに審判してもらうことになり、村の長老たちは2人のキシャンと共に宮殿へ向かう。
ところが、その途中、彼らは1人の老羊飼い(アミターブ・バッチャン)に出会う。老羊飼いは、村人たちの問題を聞いて知恵を働かせ、どちらが本物のキシャンか確かめることにする。老羊飼いは、いくつかの題を出すが、最後には水袋を取り出して、「この袋の中に入った者こそがラッチーの夫である」と言う。袋は人間の入れる大きさではなく、もしその中に入るには魔法を使うしかなかった。だが、幽霊はラッチーに、公衆の面前で魔法を使うことを禁じられていた。・・・しかし、ラッチーに対する愛を試された幽霊は、仕方なく魔法を使い、その袋の中に入る。老羊飼いはすぐにその袋の口を閉め、幽霊を閉じ込めてしまう。こうして、本物のキシャンを特定することに成功した。
ラッチーは、幽霊が閉じ込められてしまったことを聞いて悲しむ。夜、寝室にやって来たキシャンに対し、自分は本当は幽霊のことを幽霊だと知って暮らしていたことを明かす。キシャンはその話を聞いても驚かず、ラッチーが産んだ女の子の名前を口にする。それは、幽霊と一緒に考えた名前だった。ハッと振り返るラッチー。実は幽霊は袋を脱出しており、キシャンに取って代わっていたのだった。こうして幽霊とラッチーは再び結ばれることになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
カラフルでメロディアスなラージャスターン州の魅力が存分に詰まったお伽話映画。人間と幽霊の恋愛という非現実的なストーリーを、極彩色の衣装と、美しい壁画が踊るハヴェーリー(邸宅)、そして適度なCGと共に丁寧に紡ぎ出していた。まるで「アラビアン・ナイト」の世界に迷い込んだかのようだった。もちろん、ボリウッドのスクリーン上のベストカップルとも言えるシャールク・カーンとラーニー・ムカルジーの絶妙のコンビネーションと演技も、この映画の成功に不可欠であった。原作のラストはもっと悲しいようだが、映画化する際に「パブリックのデマンド」に応える形で、ハッピーエンドに改変されたようだ。それも僕は成功していると思う。
僕は何度も映画評の中でラージャスターン州の魅力について言及してきた。どんなつまらない映画でも、ラージャスターン州のシーンが出てくるだけで、なぜか素晴らしい映画のように思えてしまうだけの魅力がある。「Paheli」も、ともすれば駄作になる寸前だったと言ってもいいかもしれない。物語の展開が必要以上にゆっくり過ぎるし、脇役があまり活かされていなかったし、基本的に大人の鑑賞に耐えうるようなストーリーではない。だが、3時間の上映時間の内の大半がラージャスターン州の美しい文化と風景で埋め尽くされているため、映画館を見終わった後は、万華鏡を見終わったかのような、遊園地で1日中遊んだような、そんな気分になることができる。「Paheli」で主に舞台となったのは、シェーカーワーティー地方のナワルガル。カラフルな壁画で彩られたハヴェーリーがたくさん残っている街である。僕はまだ行ったことがないが、いつか行きたいと思っている街のひとつだ。日本の映画祭で公開されたインド映画「ハリ・オム」(2004年)でも、ナワルガルのハヴェーリーが出てきた。階段の手すりに沿って象の鼻の絵が描かれていたり、窓の上にクジャクの絵が描かれていたり、細部を観察すると本当に面白い。また、ラージャスターン州名物である操り人形も存分に活かされていた。王様と王妃の人形が、ストーリーの端々に現れてお互いに進展について話し合う。これらの声を、インドを代表する演技派男優ナスィールッディーン・シャーと、その妻のラトナー・パータク・シャーが担当している。他に、ラクダレースのシーンはダイナミックで、映画のアクセントになっていた。ちょっとカメラ回しが悪くてレースの進行の様子が把握しづらかったが、カラフルなターバンを巻いたおっさんたちがラクダを走らせる姿はかっこよかった。
この映画で最も重要なセリフは、キシャンがラッチーに自分が幽霊であることを告白した後に、ラッチーが言うセリフであろう。「私に選択する権利を与えてくれたのは、あなただけよ。」妻の尊厳を全く考えないキシャンとの対比により、幽霊の人間性がより鮮明になるセリフである。
ラッチーに恋した存在は、映画中では「ブート(幽霊)」と呼ばれている。だが、日本人の感覚からすると、死んだ人間が死に切れずに現世に現れる幽霊とは程遠く、どちらかというと狐、狸とか妖怪の類であろう。しかし、幽霊でも子供が作れるとは・・・驚きである。
「Asoka」(2001年)では長髪に挑戦して、ファンの目を丸くさせたシャールク・カーンは、この映画で初めて髭を生やしたキャラクターを演じ、再びファンを驚かせた。しかも巨大なターバンまでかぶっている。ラージャスターン州の男たちは皆立派な髭を生やしており、髭のないキャラクターはラージャスターンの風景には適応しないとのことで、シャールク・カーンは髭を付けることにしたようだ。シャールクは、金儲けのことばかりを考えているキシャンと、人間に恋した幽霊の二役を演じた。いつものようにオーバーリアクション気味であったが、二役を見事に演じ切っていた。最後、キシャンと幽霊が鉢合わせするシーンでは特撮になっていたが、違和感を感じない出来であった。その代わり、幽霊がカラスやオウムに化けたりするシーンに使用されていたCGは、まだまだハリウッドに比べると、子供の遊び程度のレベルにしかない。
今年のラーニー・ムカルジーは無敵だ。「Black」、「Bunty Aur Bubly」と大ヒット作を連発し、ここに来て再び大ヒットが見込まれる「Paheli」に出演である。「Paheli」のヒロイン、ラッチーは、「Black」ほど高度な演技力を要する役ではなかったが、ラージャスターンの純朴な女性を説得力のある演技で演じていた。ラーニーの踊りも存分に楽しむことができる。
この映画では、ボリウッドの大スターたちが何人も端役で出演していた。キシャンの兄で、7年間失踪中のスンダルラールをスニール・シェッティーが、その妻ガジュローバーイーをジューヒー・チャーウラーが、最後で突然登場して活躍する老羊飼いをアミターブ・バッチャンが演じていた他、アヌパム・ケールやラージパール・ヤーダヴも出演していた。だが、残念ながらそれらの人材がうまく活かされていたとは言いがたい。別に彼らがわざわざ出てこなくてもよかったのではないかと思った。印象的な演技をしていたのは、アヌパム・ケールとラージパール・ヤーダヴくらいか。
ラージャスターン州が舞台になっているだけあり、言語は標準ヒンディー語ではなく、ラージャスターニー語ミックスのヒンディー語である。よって、標準ヒンディー語のみの知識では、セリフの隅々まで理解することは難しいだろう。僕も通常のヒンディー語映画より理解度が落ちた。
題名の「Paheli」は、アミターブ・バッチャンが演じる老羊飼いが2人のキシャンに出す3つの問題のことを言っているのだろう。まず彼は、熱せられた石を取り出して、「これを手で掴んだ者が本物だ」と言う。次に彼は、「羊を捕まえられた者が本物のキシャンだ」と言う。そして最後に水袋を取り出して、「この袋の中に入った者がラッチーの本物の夫だ」と言う。ラッチーの名前を出された幽霊は、それを見過ごすことができず、思わず袋の中に入ってしまう。「西遊記」の金閣銀閣の話を思い出した。
音楽はMMカリーム。振り付けはファラハ・カーン。どの曲もどの踊りも隙がなかった。ラージャスターン州のプロのダンサーが踊っているものもあり、迫力があった。ラージャスターン風音楽に合わせてシャールク・カーンとラーニー・ムカルジーが操り人形になって踊るコミカルなミュージカル「Phir
Raat Kati」は、最後のスタッフロール時に流れる。
この酷暑期は話題作が続くが、「Paheli」もその一角を担う重要な作品となるだろう。また、この映画は、国内の古い民話を基にしたことに大いなる意義があると思う。なぜなら、インド映画界はハリウッド映画などの真似をしなくても、国内に数千年の歴史の中で培われた膨大な数の神話・伝承・民話のストックがあり、それらからも十分に現代的な面白い映画を作ることが可能であることが証明されたからだ。



