今まで全く知らなかったのだが、1月10日は世界ヒンディー記念日(विश्व हिन्दी दिवस)であるらしい。1975年1月10日にマハーラーシュトラ州ナーグプルにおいて第一回世界ヒンディー会議が開催されたことを記念して毎年開催されているようだ。メディアもほとんど取り上げないので、毎年どんなことが行われているのか全く分からないのだが、今年はジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)オールド・キャンパス内にある外務官僚学校(Foreign
Service Institute)において、デリーやアーグラーでヒンディー語を学ぶ外国人学生が招待されての式典となった。突然僕も行くことになった。主賓はアーナンド・シャルマー副外相であった。
実はヒンディー語に関するこういう集まりはあまり好きではない。口では「ヒンディー語万歳」を唱え、皆盛大な拍手を送るが、真剣にヒンディー語のことを考えている人はほとんどいないからだ。少なくとも日本における日本語の地位を見て来ていると、インドにおけるヒンディー語を巡る環境はほったらかしと言っていい状態だ。本当に力のある言語は政府の後援のあるなしに関わらず自然に広まって行くものだし、現にヒンディー語が今享受している力と人気も、市場の自然な需要に応える形で得て来たものである。だが、難解な公用語ヒンディーを万人向けのシンプルな言語に改善し、インドのあらゆる問題の病巣である英語のヘゲモニーを打破するには、政府の積極的な介入が必要不可欠だ。ヒンディー語の将来を話し合う場では必ず「ヒンディー語を国連公用語に」という議論がなされるが、インド国民の言語になっていない言語が世界の言語になるはずがない。空虚な意見交換と自虐的なジョークを飛ばすだけの集会なら、最初からやらない方がマシであろう。
ヒンディー語を学ぶ外国人学生が招待されたのも、ヒンディー語の現状のカモフラージュを目的にしたものに思えて来る。ヒンディー語を学ぶ外国人学生に片言のヒンディー語で何かをしゃべらせて「よくできました」と喝采しておけば、一応ヒンディー語の普及のために何か有意義なことをした気になれるものだ。ヒンディー語を外国語として学んでいる人がいる以上、こういう場が用意されるに越したことはない。しかし、それは日本語スピーチコンテストのように別のイベントして行われるべきで、世界ヒンディー記念日のメインイベントのひとつにするようなことでもないだろう。
それでも、今回の式典に、インド留学初期の頃に通っていたケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)の先生たちが来ることが分かっていたので、旧交を温めるためだけでも出席していいだろうと思ったのだった。また、どんな国の人々がどんな目的でヒンディー語を学んでいるのかということは、常に興味のある事柄である。そして、ヒンディー語を学んでいる外国人たちとの交流はとても刺激的なものだ。それもひとつの動機であった。ヒンディー語学科のチャマンラール学科長の顔を立てる意味もあったのだが。
午前10時半からとのことだったのだが、インドのイベントが時間通りに始まるはずがない。と言うより、会場で配られたプログラムには、なぜか11時からと書かれていた。そして実際に始まったのは11時半からであった。こういう示し合わせたかのような遅延は何年インドに住んでいても面白くないものである。思っていたほど外国人の数は多くなかったが、それでも、日本、韓国、中国、スリランカ、アフガーニスターン、ポーランド、アルメニア、フィジー、トリニダード・トバゴなどの国々から学生が来ていた。多くはケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンのデリー校またはアーグラー校の学生であったが、JNUのヒンディー語学科からも、僕を含め4人の外国人が参加していた。
まずは主賓などの挨拶があり、次に、いつの間にか行われていたヒンディー語エッセイ・コンテストの表彰があり、その後、外国人学生によるスピーチがあり、最後に詩の朗読会があった。
僕は何もする予定ではなかったのだが、なぜかトップバッターでスピーチをさせられた。事前に準備したわけではなかったが、何とか無事にこなすことができたと思う。他の人々のスピーチを聞いていて面白かったのは、ヒンディー語に興味を持ったきっかけがボリウッド映画だと言う人がけっこういたことである。僕にとってボリウッド映画はヒンディー語を学ぼうと決めた直接の原因ではなかったが、それでもヒンディー語を習い始めたときは、ヒンディー語ができるようになればボリウッド映画を生で楽しめるようになれるからお得だと考えていたのは確かである。ヒンディー語の普及に対するボリウッド映画の貢献度の高さを改めて思い知った。
詩の朗読会では、コメディー番組によく出演している詩人スレーンドラ・シャルマーが司会になり、数人の詩人が思い思いの詩を披露していた。スレーンドラ・シャルマーは、ハリヤーナー州の方言であるハリヤーンヴィー方言を駆使し、妻をネタにしてポーカーフェイスでギャグを言うスタイルが人気の詩人兼コメディアンである。他にアショーク・ヴァージペーイー、アショーク・チャクラダル、シェールジャング・ガルグなどが来ていた。
今回もいろいろなことが話し合われたが、その結果、ヒンディー語にとって特に何かプラスになるようなことが今後すぐに行われることはないだろう。このまま馴れ合いが続いて行くのだと思われる。
| ◆ |
1月10日(土) ヒンディー語紙の怪しげな広告 |
◆ |
ヒンディー語の新聞を読んでいると、最後のページなどに変な広告がよく載っている。日本の週刊誌などにもよく精力増強剤の広告が掲載されているが、あれと全く同じような具合の広告がインドでも普及しているのである。一番気になるのは以下のものだ。

商品名は「ジャーパーニー・テール」。ズバリ、「日本油」である。広告自体にはどんな効用があるのか書かれていないが、パッケージ写真から精力増強剤の一種であることが分かる。「21歳から71歳まで心配無用、ジャーパーニー・テールの素晴らしさを塗った後に体感して下さい。効力抜群、副作用なし、アーユルヴェーダ薬品」と書かれている。日本でもよく、「中国4千年の歴史の・・・」「インド古来より伝わる・・・」など、エキゾチックさを前面に押し出した宣伝文句と共に怪しげな薬品の広告があったりするが、それと全く同じ思考で、日本の名を冠したオイルがインドで売られているのである。なぜ日本なのか、それは謎であるが、きっと日本のものは何でもいいというイメージがインド人の心の中に常識として存在するのであろう。
そう思っていたら「ジャーマン・テール(ドイツ油)」なる商品もあった。

どうやら自動車と間違えているようだ・・・。
日本の広告でも、「利用者」の体験談を載せる手法はよく使われるが、インドでも変わらない。例えば下の広告。

これは「プリンス・ティッラー」という商品の広告である。ヒンディー語で長々と文章が書かれているが、これはいわゆる体験談である。全文を翻訳してみよう。「子供の頃に過ちを犯さない者がいるでしょうか、私も過ちを犯しました。そのため、私は1人で悔やみつつも、数年の内に全てを使い果たしてしまいました。家族は結婚するように圧力をかけて来ていました。しかし私は、自分の結婚生活がどんなものになるかと恐れていました。ある日私はプリンス製薬のプリンス・ティッラーの広告を読み、溺れる者が藁を掴んだような気持ちになりました。私は毎日朝晩3-4滴のプリンス・ティッラー・オイルでもって、前の部分を除き、後ろの部分を軽くマッサージしました。プリンス・ティッラー・オイルを数日使った後、私の血管に血流が正常に流れるようになりました。私と私の血管は新たな人生を得ました。数ヶ月後に私の結婚式があります。あなたも血管の問題を抱えているなら、一度プリンス製薬のプリンス・ティッラー・オイルを是非使ってみて下さい。全国の薬局で発売中です。」これもつまりは精力増強マッサージ・オイルの一種のようで、先ほどのジャーパーニー・テールの類似品だということが分かる。体験談風の文章ながら、使い方もしっかり解説してある。ちなみに、文中の「血管」とは、ヒンディー語「नस」の訳であるが、もっと直接的な訳は「男根」になる。
ところで上の体験談の中で、冒頭の部分がとても気になる。この筆者は子供の頃にどんな過ちを犯してしまったのだろう?何を使い果たしてしまったのだろう?ジャーパーニー・テールの別のバージョンの広告にも同じようなことが書かれている。ジャーパーニー・テールは毎日違った種類の広告を熱心に掲載している。

題名は「あなたの妻は他の男に惹かれていませんか?」というショッキングなもの。その内容は写真とプロフィール付きの体験談となっており、プリンス・ティッラーよりも手が込んでいる。全文訳は以下の通り。「私はPKチャトゥルヴェーディー、45歳、衰弱体質と子供の頃の過ちのせいで、私は結婚生活の喜びを得ることができませんでしたし、妻に結婚生活の喜びを与えることもできませんでした。そのため、私たちの結婚生活はうまく行っていませんでした。結婚直後から私は妻を満足させられないため、恥ずかしい思いをしなければなりませんでした。最初は彼女も何も私に不満を漏らしませんでした。しかし、後でこれが原因で家で喧嘩が起こるようになりました。そして私は、自分の弱さのせいで妻が他の男に惹かれつつあるのではないかと思うようになりました。私はとても悩むようになりました。しかし私に何ができたでしょう、私は自分の妻を満足させられないのですから。そこで医者の助言に従ってジャーパーニー・テールを塗るようになりました。ジャーパーニー・テールを塗り始めて以来、私は何となく落ち着くようになりました。私はジャーパーニー・テールを朝晩毎日塗り始めました。すると自信が増して来て、1ヶ月の内に、妻との不仲の原因となっていた何年も前からの問題をジャーパーニー・テールのおかげで解決することができました。ジャーパーニー・テールは私にとってとても有用でした。私と妻は結婚生活を幸せに過ごしています。弱点を克服した今日でも私は進んでジャーパーニー・テールを使っていますし、他の人々にも幸せになるように助言をしています。詳しい情報が欲しければ、この電話番号で医者と話すことができます。」
結婚生活を破壊する、子供の頃の過ちとは一体どんなものなのか?さらに別の広告を見てみると、その詳細がよく分かる。

これはオイルではなくカプセルのようだが、効能は似たようなものである。広告主は再びプリンス製薬。題名には「名前通りの効果」と書かれている。この広告では体験談ではなく、普通に説明がなされている。その訳は以下の通りである。「昔から若い男性は美しい女性を見ると心の中でいろいろなことを考え、妄想をして来た。その結果、カームデーヴ(愛の神)の矢に影響され、自分の手で熱情を鎮めようといろいろな行為をする。無知と無理解のため、器官と血管の発達を止めてしまい、いろいろな病気、例えば夢を見ているときに身体のもっとも大切な成分を出してしまったり、痩せてしまったり、排尿の前後に粘着物質が見えたり、尿関係の病気など、いつの間にか呼び寄せてしまう。これら全ての障害にかかったときには、プリンス製薬によって開発されたCPゴールド・カプセル&シロップを毎日朝晩服用することで治療できる。CPゴールド・カプセル&シロップは器官に再び新たな力を漲らせ、仕事ができるようにする。CPゴールド・カプセルは、夢の中で起こる損害を止める効果がある。」どうもインドでは子供の頃に自慰をするとEDになるという迷信があるようである。本当にそう思っているのかと友人に聞いてみたが、そんなこと信じているのは無学な奴だけだと言っていた。だが、そういう迷信自体はあるようであった。そうでなければこんな広告がまかり通っていないだろう。
この「子供の頃の過ち」をネタにした類似品の広告はヒンディー語紙に非常に多い。英語紙ではあまり見掛けないところを見ると、やはりヒンディー語がかろうじて読めるぐらいの無学な層をターゲットにして騙そうとしているのであろう。精力増強剤系の広告の他には、身長を伸ばす薬、頭が良くなる薬、ハゲを直す薬、マッチョになる薬、アルコール中毒を治す薬、美白になる薬などがよく見られる。ずっと広告がなくならないところを見ると、ある程度の宣伝効果と売り上げがあるのであろう。
| ◆ |
1月11日(日) The President Is Coming |
◆ |
現在インドの映画界では、昨年末公開された「Rab Ne Bana Di Jodi」と「Ghajini」の旋風がまだ続いている。この間いくつか映画が公開されたが、ほとんど巷の話題にも上らない小品ばかりである。その中で、1月9日に公開されたインド製英語映画「The
President Is Coming」だけはそこそこの評価を得ていたので、これだけは見ておこうと思い、映画館に足を運んだ。2006年のブッシュ大統領訪印を題材にしたドキュメンタリー風フィクションである。米国で大統領が交代する節目の時期に公開となったのは、きっと前からの計画なのであろう。
題名:The President Is Coming
読み:ザ・プレジデント・イズ・カミング
意味:大統領が来る
邦題:大統領が来る!
監督:クナール・ロイ・カプール(新人)
制作:ローハン・スィッピー
音楽:ゴールド・スポット
出演:コーンコナー・セーン・シャルマー、ナミト・ダース、イラー・ドゥベー、ヴィヴェーク・ゴンベール、シェールナーズ・パテール、サトチト・プラーニク、イムラーン・ラシード、シヴァーニー・タンクセール、アーナンド・ティワーリー、ポール・ノックス
備考:サティヤム・ネループレイスで鑑賞。

上から順に、ナミト・ダース、
サトチト・プラーニク、アーナンド・ティワーリー、
コーンコナー・セーン・シャルマー、
ヴィヴェーク・ゴンベール、イラー・ドゥベー、
シェールナーズ・パテール、シヴァーニー・タンクセール
| あらすじ |
2006年、米国のジョージ・ブッシュ大統領が訪印することになった。ブッシュ大統領は、訪印中にインドの若者と握手をしたいと提案して来た。そこで在ムンバイー米国総領事のマイケル・フライン(ポール・ノックス)は、大統領と握手をする若者を公募することにした。その責任者に選ばれたのが、総領事館に勤務するサーマンター・パテール(シェールナーズ・パテール)とリトゥ・ジョンソン(シヴァーニー・タンクセール)であった。
公募により、6人のインド人が選ばれた。ベンガル人女流小説家のマーヤー・ロイ(コーンコナー・セーン・シャルマー)、アメリカ英語教師のローヒト・セート(ヴィヴェーク・ゴンベール)、投資家のカピル・デーヴ(アーナンド・ティワーリー)、バンガロールのIT企業勤務ラメーシュS(ナミト・ダース)、社会活動家のアジャイ・カールレーカル(サトチト・プラーニク)、化粧品会社を経営する女社長アルチャナー・カプール(イラー・ドゥベー)であった。
サーマンターとリトゥは、ムンバイーの総領事館に集った6人の若者をテストする。その中で、ローヒトとアルチャナーが実は恋人で、過去に2人のセックスビデオが流出していたことが分かったり、ラメーシュが実は同性愛者であることが発覚したりと、いろいろな事件が起こる。もっとも賢明に立ち回っていたのはマーヤーで、アジャイを色仕掛けで失格にさせたり、ラメーシュの同性愛趣味を暴露して失格にさせたりした。また、ローヒトとアルチャナーはよりを戻して2人で揃って失格になる。
残ったのはマーヤーとカピルであった。カピルはリトゥを買収して何とか勝ち残ろうとするが、それがサーマンターにばれ、カピルも失格になる。こうしてマーヤーが大統領と握手することになったのだが、実は彼女は大統領暗殺をもくろむテロリストであった。サーマンターは彼女も失格にせざるをえなくなる。
そうこうしている内に大統領が来てしまった。そこでリトゥは機転を利かし、総領事館に勤務する警備員ムハンマド・アスラム(イムラーン・ラシード)を抜擢する。
後日談。アジャイは多国籍企業に勤務し、マーヤーは相変わらず反政府運動を続けていた。ローヒトとアルチャナーは結婚してヒンディー語の学校を運営していた。カピルは株式取引での不正がばれて服役中、ラメーシュはカモフラージュのために女性と結婚しながらも、本命の男性の恋人と緊密な関係にあった。サーマンターはPR会社を立ち上げ、リトゥはブータンでオーガニック野菜を栽培していた。ムハンマド・アスラムは大統領と握手をしたことで人生が変わり、現在モテモテの生活を送っていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
基本的にはコメディー映画で、所々面白いシーンもあったが、ストーリーは非常に下らなく、特別なメッセージが込められている訳でもない。通常、英語の映画はある程度の質が保証されているものであるが、このような駄作を見てしまうと、英語映画だからと言って無条件で見るという態度は改めざるをえなくなる。
大統領と握手をするインドの若者代表を選考する過程を描いた物語であるが、選考する責任者も、候補に選ばれた人々も、まともな人間が1人もいない。それが大衆娯楽映画のように開き直った馬鹿馬鹿しさならまだ許せるが、なまじっか英語を言語とし、コジャレた雰囲気を出そうとしているため、かえって脚本の粗が目立ってしまう。結局最後に選ばれたのは警備員だったというオチだけは意外性があってよかったが、そこまでのドタバタ劇は、ボリウッドのB級コメディー映画にも劣る。
キャストの中ではコーンコナー・セーン・シャルマーがトップの知名度であろう。イラー・ドゥベーは女優リレット・ドゥベーの娘で、ネーハー・ドゥベーの妹である。シェールナーズ・パテールも主に舞台での活躍で有名な女優で、映画では神経質なおばさん役を演じることが多い。だが、他の俳優は見覚えがなかった。
映画では、ブッシュ大統領訪印時の実際の映像が使われており、マンモーハン・スィン首相、アブドゥル・カラーム大統領(当時)などが映っていた。
言語は完全に英語である。ヒンディー語などの現地語も所々に入っていたが、全て英語字幕が付いていたので、英語映画と言って差し支えがないだろう。
「The President Is Coming」は、一見都市部のマルチプレックス観客層向けのコジャレた映画に見えるが、実際はほとんど見所のない駄作である。見ても時間と金の無駄になるだけだと忠告しておきたい。
| ◆ |
1月15日(木) Chandni Chowk To China |
◆ |
興味深いことに、故意か偶然か、2008年12月から2009年1月にかけて、ボリウッドのトップスター3人が真のトップの座を巡って競り合うことになり、映画ファンを熱中させている。その3人とは、「Rab
Ne Bana Di Jodi」(2008年)のシャールク・カーン、「Ghajini」(2008年)のアーミル・カーン、そして「Chandni
Chowk To China」(2009年)のアクシャイ・クマールである。昨年12月に公開済みの「Rab Ne Bana Di Jodi」と「Ghajini」は既に大ヒットを記録している。残るはアクシャイ・クマールだけであった。アクシャイ・クマールはここ数年絶好調で、出演作のほとんどは大ヒットとなっている。その勢いが果たして2009年も続くか、そしてシャールク・カーンとアーミル・カーンという強大なライバルとの直接対決にどれだけ成果を上げられるのか、今年最初の話題作「Chandni
Chowk To China」に注目が集まっていた。
「Chandni Chowk To China」はいろいろな意味で歴史的な作品である。まず、この映画はハリウッド資本の入った映画である。ボリウッドでは2年前からハリウッド資本の入った映画が作られるようになっており、今まで「Saawariya」(2007年;ソニー・ピクチャーズ・エンターテイメント)、「Saas
Bahu Aur Sensex」(2008年;ワーナー・ブラザーズ)、「Roadside Romeo」(2008年;ウォルト・ディズニー)が公開された。「Chandni
Chowk To China」はワーナー・ブラザーズ出資ボリウッド映画第2弾ということになる。
題名からも察せられる通り、この作品では中国ロケが行われている。中国でロケが行われたインド映画はおそらく初めてのはずであるが、香港なども含めるともしかして正確には初とは言い切れないかもしれない。しかし、アジアの二大国であるインドと中国が映画によって本格的に結ばれたことの意義は大きい。さらに、この映画は「インド初のカンフー・コメディー」を謳っており、それも注目である。
「Chandni Chowk To China」は1月16日より公開であるが、最近インドでは話題作に限ってペイド・プレビューという有料試写会が事前に行われる習慣が定着しつつあり、一般公開より1日前に鑑賞することができた。
題名:Chandni Chowk To China
読み:チャーンドニー・チャウク・トゥ・チャイナ
意味:チャーンドニー・チャウクから中国へ
邦題:チャンドニー・チョーク・トゥ・チャイナ
監督:ニキル・アードヴァーニー
制作:ラメーシュ・スィッピー、ローハ・スィッピー、ムケーシュ・タルレージャー
音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ、カイラーシュ・ケール、パレーシュ、ナレーシュ、バッピー・ラーヒリー
歌詞:カイラーシュ・ケール、ラジャト・アローラー、シャイリー・シェイレーンドラ、ボヘミア
振付:ポニー・ヴァルマー
スタント:ディー・ディー・クー
出演:アクシャイ・クマール、ディーピカー・パードゥコーン、ミトゥン・チャクラボルティー、ランヴィール・シャウリー、ゴードン・リュー、ロジャー・ヤン
備考:PVRアヌパムで鑑賞、プレビュー、満席。

アクシャイ・クマール(左)とディーピカー・パードゥコーン(右)
| あらすじ |
スィッドゥー(アクシャイ・クマール)は捨て子だったが、チャーンドニー・チャウクで安食堂を経営するダーダー(ミトゥン・チャクラボルティー)に拾われ、育てられた。小麦粉をこね、野菜を切る毎日だったが、人生一発逆転を信じ、占いに頼ったり、宝くじを買ったりしていた。中国の風水とインドのヴァーストゥ・シャーストラの両方をマスターしたと自称する詐欺師チョップスティック(ランヴィール・シャウリー)は、そんな頭の弱いスィッドゥーを騙しては小銭を巻き上げていた。
ある日、チャーンドニー・チャウクに中国人がやって来る。彼らの村は、ホージョーという名のカンフーの達人が率いるマフィアに支配されていた。占いによると、ホージョーを打倒できるのは、中国を異民族の手から守った英雄劉勝(リューシェン)の生まれ変わりだけで、それはデリーにいるとのことであった。彼らはスィッドゥーを劉勝の生まれ変わりだと断定する。中国語ができるチョップスティックは金儲けの臭いを感じ、スィッドゥーを騙して、とにかく中国へ行くことを承諾させる。チョップスティックも通訳として同行することになる。
中国へ行くため、スィッドゥーはヴィザを取りに中国大使館へ行くが、そこでサキー(ディーピカー・パードゥコーン)というTVCM女優に出会う。だが、このときサキーに一杯食わされたため、スィッドゥーは恨みを抱いていた。スィッドゥーは中国行きを反対するダーダーを説得し、チョップスティックと共に中国へ飛ぶ。
空港では村人たちが劉勝の生まれ変わりを待っていた。スィッドゥーは何が何だか分からないまま村人たちの期待を一身に背負う。また、空港でスィッドゥーはサキーに似た美女を見掛け追いかける。だが、彼女はホージョーの手下のミャオ(ディーピカー・パードゥコーン)であった。ミャオはダイヤモンドの密輸をしていたが、スィッドゥーのせいでそれがばれてしまい、逃亡する。ホージョーは、劉勝の生まれ変わりが中国にやって来たことを知り、刺客を差し向ける。
一方、サキーも中国に来ていた。サキーは、中国の発明会社TSMのブランド・アンバサダーになっており、本社を表敬訪問する目的で中国を訪れたのだが、彼女には別の目的もあった。実はサキーは中国人の父親とインド人の母親の間に産まれたハーフであった。父親のチャンは優秀な警察官であったが、ホージョーに殺され、母親はサキーを連れてインドに逃げて来たのであった。サキーには双子の姉妹スージーがいるはずであったが、彼女の生死は不明であった。サキーは父親を供養するため、父親が死んだ万里の長城を一度訪れたいと思っていたのであった。
万里の長城には、スィッドゥーの一行も来ていた。なぜなら劉勝の死んだ場所もここだったからだ。ミャオとホージョーの手下たちはスィッドゥーを殺そうとするがうまく行かなかった。また、サキーは指名手配されたミャオと間違えられ、警察に追われることになった。サキーはスィッドゥーの姿を見つけ、彼の車に隠れて逃げる。車は、ホージョーの支配する村へ向かった。村では村人たちによって歓迎会が行われたが、ホージョーの手下たちも送り込まれた。だが、酔っぱらったスィッドゥーは何が何だか分からない内に手下たちを撃退する。村人たちの期待はさらに高まった。
夜になった。ミャオはスィッドゥーを暗殺しようと忍び寄るが、スィッドゥーとチョップスティックに気絶させられてしまう。その前にサキーも気絶させられていた。意識を取り戻したサキーは、自分とうり二つの人間がいるのを見つけ、双子の姉妹スージーだと直感する。だが、縛られていたために彼女と話すことはできなかった。また、次に意識を取り戻したミャオは、考え直してチョップスティックを連れてアジトへ戻る。スィッドゥーだけ注目を浴びて面白くなかったチョップスティックは、スィッドゥーは実は劉勝の生まれ変わりではないとホージョーに暴露する。そのとき、インドへ調査に送り込んでいた部下も戻って来た。彼もスィッドゥーが劉勝ではない証拠を掴んで来ていた。安心したホージョーは、翌朝村に総攻撃をかける。
未だに何が何だか分からないスィッドゥーは、ホージョーと共に村に戻って来たチョップスティックから初めて事情を聞き、ショックを受ける。また、そこにはダーダーも連れて来られていた。スィッドゥーはダーダーの命乞いをするが、ホージョーはダーダーの命を奪ってしまう。スィッドゥーもコテンパンにやっつけられ、万里の長城から放り投げられてしまう。だが、スィッドゥーを救った1人の男がいた。彼は乞食のような身なりをしていたが、実は彼こそがホージョーに殺されたはずのチャン、つまりサキーとスージー(ミャオ)の父親であった。ホージョーにやられたときに頭に受けた傷がもとで記憶喪失であったが、インド人の妻といたときに覚えたヒンディー語はまだ覚えていた。スィッドゥーはチャンの看病もあって回復するが、ダーダーを殺したホージョーに復讐することを決めていた。スィッドゥーとチャンが生きていることを知ったホージョーによって送り込まれた刺客を倒した後、スィッドゥーは演劇鑑賞中のホージョーを殺そうとするが成功しなかった。一転して追われる身となったスィッドゥーだったが、その場にはサキーも駆けつけており、TSM社の発明品のおかげで脱出に成功する。サキーは父親のチャンと再会し、チャンも記憶を取り戻す。チャンは警察に復職するが、スィッドゥーの願いを聞き入れ、彼にカンフーを教え込むことを決める。スィッドゥーは厳しい訓練を重ね、カンフーをマスターする。
チャンとスィッドゥーはホージョーの秘密工場を襲撃し、チョップスティックを救出すると同時に手下の1人を捕まえる。チャンは娘のスージー(ミャオ)がホージョーの手下になっていることを知り、ホージョーに人質とスージーを交換することを提案する。だが、ホージョーはミャオに、彼女の父親を殺したのはチャンだと吹き込む。解放されたスージーはチャンのところへ駆け寄るが、そのままチャンに刃物を突き刺す。だが、スージーはサキーの姿を見て、ホージョーが嘘を付いていたことを悟る。スィッドゥー、チョップスティック、サキーは怪我をしたチャンを連れて村へ逃げる。
村ではチャンの治療が行われた。そこへホージョーの手下たちが襲って来る。スィッドゥーは雑魚たちを一網打尽にするが、その隙を突いてサキーがさらわれそうになる。だが、サキーを助けたのはミャオであった。最後にホージョーがスィッドゥーと対決しにやって来る。やはりホージョーは強力で、一度スィッドゥーはやられそうになるが、チャーンドニー・チャウクで鍛えた料理人の技とカンフーを合体させ、究極の格闘技を編み出してホージョーを倒す。
その後、スィッドゥーは中国でインド料理屋を開いた。だが、そこへアフリカからピグミー系の部族が救世主スィッドゥーを訪ねてやって来る。今度はスィッドゥーはアフリカへ行かなければならないのか? |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドと中国を股に掛けた映画とのことで、スケールの大きな作品を期待していたのだが、案外こぢんまりとまとまっていて残念であった。カンフー・コメディーという看板に嘘はなく、カンフーもコメディーも十分楽しめるレベルのものであったが、いかんせん編集が雑で、冒頭部分やラストを含め、端折り過ぎに思える部分が散見された。ダンス・シーンやミュージカル・シーンも短縮されたりぶつ切れになっており、純粋に歌と踊りを楽しめるようなものではなかった。映画の上映時間は2時間半ほど。「Ghajini」のようにいっそのこと3時間の映画にして、もう少し丁寧にシーンとシーンをつないで行けば、もっと完成度の高い作品になったのではないかと悔やまれる。ハリウッド資本が入ったことと、編集の乱雑さはもしかして無関係ではないかもしれない。もしかしてワーナー・ブラザーズが上映時間の短縮を要求し、そのせいで多くの重要なシーンを削らなければならなかったのではなかろうか?もしそうだとしたら、ハリウッド資本がボリウッドに入り込むことは必ずしも歓迎できない。ハリウッドの下らない哲学に屈して映画の完成度を低めるよりは、インド人が作品を完全にコントロールし、インド人が楽しいと思える映画をとことん追求して行ってもらいたい。今後の課題を感じた映画であった。
少々外し気味のギャグも多かったのであるが、この映画の最大のギャグは何と言っても、主人公スィッドゥーがラストの悪役ホージョーとの対決シーンで編み出した「デーシー・カンフー(インド風カンフー)」であろう。スィッドゥーはカンフーの師匠チャンから、「誰にでもその人にしかできない動きが何かある」という言葉を教え込まれており、自分の独自の動きとは何かと考え続ける。絶体絶命のピンチに陥ったとき、彼の脳裏に浮かんだのは、子供の頃からやって来た、野菜を切ったり小麦粉をこねたりずた袋を持ち上げたりする動作であった。その動作をカンフーと融合させ、スィッドゥーは最強の「デーシー・カンフー」を編み出す。正にカンフー・コメディーの名にふさわしいクライマックスであった。カンフーですらインド臭く料理してしまうところは素直に感心する。
主演のアクシャイ・クマールは、実際にチャーンドニー・チャウクのパラーンテーワーリー・ガリーで生まれ育った経歴を持っている。また、子供の頃からマーシャルアーツを習っており、ほとんどのスタントを自分でこなせるほどスポーツ万能で、ボリウッドでもっともアクションが得意な俳優として知られている。よって、「Chandni
Chowk To China」は彼の自伝的映画だと言える。アクシャイ・クマールは今や全てのインド人若者のアイコンとなっており、特に今回は下層の人々の共感を呼びやすい役であったことから、彼1人の人気で多くの観客を映画館に呼び込むと思われる。
次期トップ女優候補の1人ディーピカー・パードゥコーンは、今回1人2役に挑戦。しかもアクション・シーンにも果敢に取り組んでいる。だが、本作はロマンスの要素が弱かったためか、彼女からデビュー作「Om
Shanti Om」(2007年)のような輝きは感じられなかった。舞台が中国のため、今回ディーピカーはチャイナドレス(旗袍)など中国風衣装を着ており、それがとても色っぽかった。
悪役ホージョーを演じた中国人俳優ゴードン・リューは、クエンティン・タランティーノ監督「Kill Bill」シリーズにも出演していたベテラン俳優で、「Chandni
Chowk To China」でもずば抜けて迫力のある演技とアクションを見せていた。チャンを演じたロジャー・ヤンも好演していた。中国人俳優のキャスティングは素晴らしかったと言えるだろう。敢えて言うならば、もし中国人女優が絡んでいればもっと面白くなっていただろう。
キャスティングで弱かったのはむしろインド人脇役である。ミトゥン・チャクラボルティーが演じたダーダーも、ランヴィール・シャウリーが演じたチョップスティックも、キャラクターがうまく描き切れていなかったし、2人とも中途半端な演技であった。
音楽は、シャンカル・エヘサーン・ロイやカイラーシュ・ケールなどの合作となっている。特筆すべきは、インド映画音楽におそらく初めて中国語の歌詞が本格的に挿入された「India
Se Aaya Tera Dost」であるが、この曲については以前取り上げたのでそちらを参照していただきたい(参照)。スィッドゥーの紹介曲である「S.I.D.H.U.」はカイラーシュ・ケールが歌うカッワーリー風ナンバーで、歌詞もチャーンドニー・チャウクの路地裏の食堂の光景が浮かんで来るようでとてもよい。エンディングのスタッフロールで流れる「CC2C」は、パーキスターン/パンジャーブ系アメリカ人ボヘミアが参加しているラップ調ソングで、彼自身も映像に登場する。アクシャイ・クマールが歌声を披露しているのにも注目。その他、タイトル曲「Chandni
Chowk To China」や、ラブソング「Tere Naina」など、ひとつひとつはいい曲が多い。だが、前述の通り、概して映画ではこれらの曲が上手に挿入されておらず、歌って踊ってなんぼのインド映画としては残念な編集の仕方となっている。
映画は、実際にオールドデリーのチャーンドニー・チャウクやデリーの各名所、例えばクトゥブ・ミーナール、フィーローズ・シャー・コートラー、ウグラセーン・キ・バーオリーなどでロケが行われた他、中国の万里の長城や故宮などで撮影が行われている。また、途中でなぜかタイでロケが行われたシーンも出て来る。日本人が見れば明らかに中国ではないことが分かるだろう。
言語は基本的にヒンディー語だが、中国語もたくさん出て来る。いくつかの中国語の台詞には英語の字幕が付くが、全てではない。サキーがブランド・アンバサダーを務める中国企業TSM社は自動翻訳器を開発しており、それをサキーが装着しているという設定なので、ストーリー進行に必要な中国の台詞はその機械を通して音声でヒンディー語に翻訳される。インドは英語字幕もヒンディー語字幕も万人向けにはならないので、字幕よりも音声翻訳に頼る方法の方がより親切であろう。また、ストーリー進行上重要ではない台詞にはいちいち字幕は付かない。ちなみに、映画の最後で、クリック音を多用したアフリカの言語らしきものも出て来るが、多分いい加減なものであろう。
日本ロケが行われたインド映画「Love in Tokyo」(1966年)のおかげでインド人の間に「さよなら」という日本語が広まったことは有名な話だが、「Chandni
Chowk To China」ではそのようなことはなさそうだ。「ニーハオ」や「シェシェ」のような簡単な挨拶が映画中に出て来ないことはなかったのだが、インド人観客がつい覚えてしまうような方法での使われ方ではなかった。唯一、ミャオが終盤で「ウォ(我)」という短い台詞をしゃべり、英語字幕で「I
will」と出て来たとき、インド人観客の多くが反応し、あちこちから「ウォ」「ウォ」「ウォ」と復唱が聞こえて来た。そういえば、耳を凝らしているとアクシャイ・クマールが中国人に対し「さよなら」という日本語をしゃべるシーンがある。どうもやっぱり中国語と日本語を間違えているようである・・・。
「Chandni Chowk To China」は決してつまらない映画ではない。ヒットする可能性も十分ある。だが、予告編があまりによく出来ていたためか、期待が大きすぎて落胆することになった。どうもハリウッド資本が入ると予告編だけはうまく作るようだ。そういうせこい技術だけはボリウッドには学んで欲しくない。実は中国ロケのハリウッド資本インド映画ということで、話題性も十分で、もしかして日本一般公開も狙えるのではないかと淡い期待を抱いていたのだが(実際に公開予定ありのようだ)、日本の一般の観客の鑑賞に堪えうるだけの完成度はお世辞にも満たしてない。あまり大きな期待を抱かず、一般的なインド娯楽映画として楽しむのが吉であろう。
| ◆ |
1月23日(金) Raaz - The Mystery Continues |
◆ |
2002年、「Raaz」という映画が公開された。この映画は、高い露出度(いわゆるスキンショー)とホラーという2つの意味において、その後しばらくボリウッド映画のトレンドを決定付けた重要な作品である。それまでボリウッドには「Raaz」ほど際どい露出シーンのある映画はなく、また、ホラー映画というジャンルも一般的ではなかった。だが、「Raaz」のヒットにより、ボリウッドはホラー映画に真剣に取り組むようになり、また、女優のスキンショーさえあればどんな映画でもヒットするという妄想にも取り憑かれてしまったのであった。さらに「Raaz」は、2001年に「Ajnabee」で衝撃のデビューを果たしたモデル出身女優ビパーシャー・バスの第2作という意味でも重要である。彼女は、「Ajnabee」での新人賞獲得に続いて「Raaz」で一気に知名度を高め、スターダムを駆け上がった。その後、「Jism」(2003年)などにより彼女はセックス・シンボルとしての地位を確立するのであるが、彼女自身はその称号を不名誉に思っており、演技派への転向を模索するようになる。そうこうしている内にセックス・シンボルの称号は「Murder」(2004年)のマッリカー・シェーラーワトによって奪取されることになるが、21世紀のボリウッドにおける元祖セックス・シンボルは本人が望もうと望むまいとビパーシャー以外におらず、その影響は計り知れない。今でも「ビパーシャー」という名前はセックス・シンボルやセクシーな女性の同義語として使われることがある。「Raaz」は、音楽のヒットが映画のヒットに大いに貢献した映画としても記憶されている。当時、「Raaz」のヒットにより、ボリウッド映画における音楽の重要性が再認識されたと言えるだろう。
その「Raaz」の続編が本日より公開された。一般に「Raaz 2」と呼ばれているが、正式名称は「Raaz - The Mystery Continues」であり、プロデューサーのマヘーシュ・バット以外、キャストにもストーリーにも前作とのつながりは一切ない。おそらく題名は「Raaz」のヒットにあやかっただけであろう。ところで現在インドはダニー・ボイル監督の「Slumdog
Millionaire」(2008年)で持ち切りで、不幸にも「Raaz - The Mystery Continues」は同作品のインド一般公開と公開日が重なってしまったが、それでも「Raaz」の頃の異常な盛り上がりを知る者としては「Slumdog
Millionaire」以上に興味ある作品であった。「Slumdog Millionaire」は後日鑑賞する予定である。
題名:Raaz - The Mystery Continues
読み:ラーズ・ザ・ミステリー・コンティニューズ
意味:秘密-ミステリーは続く
邦題:お前は穢れている
監督:モーヒト・スーリー
制作:マヘーシュ・バット、ムケーシュ・バット
音楽:ラージュー・スィン、トシ/シャリーブ、プラナエMリジヤー、ゴウラヴ・ダースグプター
歌詞:サイード・カードリー、クマール
出演:イムラーン・ハーシュミー、カンガナー・ラーナーウト、アディヤヤン・スマン、ジャッキー・シュロフ(特別出演)
備考:PVRバンガロールで鑑賞、満席。

イムラーン・ハーシュミー(上)とカンガナー・ラーナーウト(下)
| あらすじ |
モデルのナンディター(カンガナー・ラーナーウト)は、テレビ番組のプロデューサー、ヤシュ(アディヤヤン・スマン)と付き合っていた。ヤシュは、「アンドヴィシュワース(迷信)」という、インドに伝わる迷信の嘘を科学の力で暴くドキュメンタリー番組を制作して受賞しており、絶好調であった。ナンディターはかねて自分の家が欲しいと願っていたが、ヤシュは彼女にマンションを買い与え、彼女のその夢を叶える。ナンディターも幸せの絶頂期にあった。
ところが、ナンディターは自分を付け回す不気味な男の影に怯えるようになる。その男はプリトヴィー(イムラーン・ハーシュミー)という名の画家であった。数ヶ月前から彼女の顔が脳裏に浮かんで来るようになり、狂ったようにナンディターの絵を描いていた。そして最近、彼はナンディターが手首を切って倒れる絵を描いてしまい、それが未来を予知するものだと考え、彼女に警告しに来たのであった。ナンディターは不気味に思ってプリトヴィーから逃げ出すが、その後彼女は入浴中に得体の知れない力に襲われて手首を切り、病院へ搬送される。そのときからナンディターの身の回りで恐ろしい現象が起こるようになり、彼女の奇行は周囲にも知られるようになる。彼女に悪魔が取り憑いたと噂する者もいた。迷信を暴く番組を制作していたヤシュは、ガールフレンドが迷信に取り憑かれてしまい、面目丸つぶれであった。ヤシュはナンディターの奇行を精神異常と決め付け、彼女にもそう説明するように強要する。
だが、ナンディターは依然恐ろしい目に遭い続けていた。その中で、「トゥム・アシュッド・ホー、サル・チュケー・ホー(お前は穢れている、腐り切っている)」という言葉が彼女を悩ますようになる。その言葉は、プリトヴィーの絵の中にも登場していた。プリトヴィーはインターネットでその言葉を検索する。すると、ヒマーチャル・プラデーシュ州のカーリンディーという村で起こった奇怪な事件に行き着く。カーリンディー村では、村の僧侶や外資系工場のオーナーが同じような状態に陥って死亡する事件が続発していた。プリトヴィーは当初、ナンディターとは一切関わらないようにしようと決めるが、ナンディターがあまりに危険な状態に陥っていたため、彼女を助けざるをえなくなる。プリトヴィーとナンディターはカーリンディー村へ向かう。一方、ヤシュはナンディターにプロポーズをして彼女の精神を落ち着かせようとするが、彼女はそれを振り切ってプリトヴィーと共に去って行ってしまう。ヤシュは密かに2人の後を追いかける。
カーリンディー村は聖河の畔にある村で、河で沐浴する大祭が行われようとしていた。プリトヴィーとナンディターは事件の関係者に会って話を聞くが、真相ははっきりしなかった。だが、ナンディターはひとつの井戸に行き着き、その中に落ちることで、真実を知る。全ての怪奇現象の原因は、プリトヴィーの父親ヴィール・プラタープ・スィンであった。
第3次印パ戦争の英雄ヴィールは、カーリンディー村の河の水質調査の結果、上流にある外資系工場によって河が汚染されており、巡礼者がここで沐浴をするのは危険であると知る。だが、村の経済は大祭に依存しており、僧侶も警官も工場オーナーもその事実の公表を望んでいなかった。ヴィールは彼らに捕まり、暴行を受け、最後に井戸に落ちて死んでしまう。だが、彼は死ぬ前にある人物に電話をかけていた。それはテレビ番組プロデューサーのヤシュであった。カーリンディー村に駆けつけたヤシュは、ヴィールが殺される一部始終をカメラに収録する。だが、彼は工場のオーナー、デーヴィッド・クーパーと取引をし、その映像を報道しない代わりに番組のスポンサーになるように要求する。ヤシュの成功の裏には、こんな秘密があったのだった。だが、亡霊となったヴィールはその映像の公表を望んでおり、事件に関わった者を呪い殺すと同時に、ヤシュに報道を訴えかけていたのであった。ナンディターはヤシュの強欲の原因ともなっていたため、怨念を受けていたのだった。
ナンディターはカーリンディー村まで追って来たヤシュに対し、映像を公表するように求める。だが、ヤシュはそれを拒絶し、彼女を殺そうとする。プリトヴィーが助けに来るが、彼は隙を見せた瞬間に大怪我を負わされてしまう。絶体絶命のピンチとなるが、そのときヴィールの亡霊が現れ、ヤシュを惨殺する。こうして河の汚染とヴィールの死の真相が公表され、カーリンディー村の祭りは中止となり、多くの人々が犠牲となるのが防がれたのであった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画の冒頭と最後で、中世の詩人カビールの以下のドーハー詩が引用される。
बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई।
जो मन खोज आपणा, तो मुझसे बुरा ना कोई॥
burā jo dekhan main chalā, burā nā miliyā koī
jo man khoj āpnā, to mujhse burā nā koī
悪を探しに出掛けたが、どこにも悪はいなかった
自身を振り返って見ると、自分よりも悪い者はいなかった
この詩はつまり、「人の振り見て我が振り直せ」という日本の諺に近い意味になる。主人公ナンディターは、自身に降りかかる数々の心霊現象の原因を突き止めに遠くまで出掛け、遂にその原因は自分のボーイフレンド、ヤシュの過去の行動にあることを知る。だが、ヤシュがそのような行動をするに至ったそもそもの原因は、彼女自身の、成功のためなら何でもやっていいという考え方にあった。ホラー映画でありながら、カビールの詩を引用し、それをもとにストーリーを構築することで、含蓄があり、しかもインドの地に根ざした映画に仕上っていた。さらに、ヒンドゥー教の聖典バーガヴァト・ギーターや、大祭クンブメーラーを彷彿とさせるヒンドゥー教祭典などもさりげなく物語に織り込んであった。インド製ホラー映画にまたひとつ傑作が生まれたと言える。ちなみに今まで個人的に殿堂入りしたインド製ホラー映画傑作は、「Om
Shanti Om」(2007年)と「Bhool Bhulaiyaa」(2007年)である。
それでも、細かいところではまだまだ未熟な部分が散見される。「Raaz - The Mystery Continues」が売りとする怖さは、日本映画が「リング」シリーズなどで完成させたような精神的恐怖には到底及ばず、まだ音や映像で物質的に観客を怖がらす段階からも脱却できていない。ナンディターの身の回りに起きる超常現象も、種明かしを見た後にもう一度考え直してみると整合性の低いものが多い。しかし、インド映画の永遠の命題である、ホラー映画とミュージカルの融合は、何とか相互反発現象を起こさない程度に調和されており、ひとまず失敗ではないと言えるだろう。また、ホラー映画とヌードは古来より相性がいいが、カンガナー・ラーナーウトの(比較的)大胆な入浴シーンもあり、映画のひとつの見所となっている。
イムラーン・ハーシュミーは着実に名優の道を歩んでいる。イムラーンらしさを維持しながら、それでも映画ごとに違った魅力を見せるのが彼の持ち味である。「Raaz
- The Mystery Continues」では影のある落ち着いた演技に徹していて良かった。カンガナー・ラーナーウトも、もっぱら得意とする狂気をちらつかせた演技をしており、素晴らしかった。イムラーンとカンガナーの共演は「Gangster」(2006年)以来だが、この2人のスクリーン上のケミストリーはアクシャイ・クマールとカトリーナ・カイフに劣らないほど良い。イムラーンもカンガナーもパーソナリティーの中にどこか破滅へ向かう狂気じみた要素があり、それが映画に狂おしさを加えるのに役立っている。
もう1人の主演アディヤヤン・スマンはあまり名の知られていない俳優であるが、「Haal-e-Dil」(2008年;未見)でデビューした新人である。今回は主役に見せかけておいて実は悪役に近い役であったが、今後は主役として活躍しそうだ。ジャッキー・シュロフが特別出演していて驚いたが、彼にはすっかりこういう役しか回って来なくなってしまって同情を禁じ得ない。だが、少ない出番をしっかりとこなしていた。
「Raaz」(2002年)はヴィクラム・バットが監督だったが、「Raaz - The Mystery Continues」はモーヒト・スーリーが監督である。モーヒト・スーリーは、「Zeher」(2005年)、「Kalyug」(2005年)、「Woh
Lamhe」(2006年)、「Awarapan」(2007年)などの監督であり、イムラーン・ハーシュミーやカンガナー・ラーナーウトとも相性がいい。「Raaz
- The Mystery Continues」の成功は、イムラーン、カンガナー、モーヒトのタッグの賜物とも言えるだろう。
音楽はラージュー・スィン、トシ/シャリーブ、プラナエMリジヤー、ガウラヴ・ダースグプターなどの合作となっている。中でもトシ/シャリーブ作曲「Maahi」はヒットとなっており、映画中この曲が登場したときも歓声が上がった。それ以外はそこそこの曲しかないが、ストーリーとの相性は悪くなかった。また、サントラCD/カセットはソニーBMGが配給している。
「Raaz - The Mystery Continues」は、話題性では同時公開となった「Slumdog Millionaire」の影に隠れてしまっているところもあるが、もしかしたら興行収入ではこちらの方が上を行くかもしれない。「Raaz」(2002年)と同様に、ホラー映画ながらインド映画らしい万人向けの娯楽映画に仕上がっており、広い客層に受け容れられるだけの要素がある。一般的な日本人の趣向には必ずしも合致しないだろうが、インド製ホラー映画のひとつの完成形を見る目的ならオススメできる。
| ◆ |
1月24日(土) デカンのデリー、グルバルガー |
◆ |
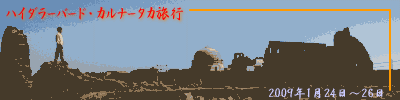
僕は公式にはヒンディー語とウルドゥー語の言語問題を研究テーマに、デリーのジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のヒンディー語学科博士課程後期コースに在籍しているが、デリーに長年住んでいる内に、デリーという都市自体に興味が生じ、非公式にデリーの研究をするようになった。研究というより趣味に近いものであるが、その成果は「これでインディア」上でも折に触れて書き記して来たつもりである。デリーに関することなら基本的に何にでも興味を惹かれるのだが、特にデリーの歴史に大きな魅力を感じている。当初はヒンディー語とウルドゥー語の研究とデリーの研究を完全に平行して行っていたのであるが、次第にこの2つは相互に関係するテーマだと気付き始めた。そもそも現在一般的に標準ヒンディー語・ウルドゥー語と呼ばれている言語は、デリー周辺で話されていた言語が発展したものであり、元々無関係ではないことは重々承知していたのだが、それだけでなく、デリーの破壊と再生の歴史と、ヒンディー語・ウルドゥー語の発展・伝播の歴史は非常に密接な関係を持っていると感じるようになったのである。ヒンディー語・ウルドゥー語の文学が現れ始める時代とデリーが歴史の表舞台に登場する時代はほぼ一緒であるし、ヒンディー語・ウルドゥー語がインドの広範な地域で理解される理由も、デリーに興った王朝の領土拡大の歴史を見て行くと自然に納得できる。そしてこれは大いなる皮肉であるが、歴史上、デリーの力が弱まったときにヒンディー語・ウルドゥー語の文学が黄金期を迎えるという現象が繰り返されて来た。デリーに13世紀にイスラーム政権が興って以来、インドの公用語はペルシア語であり、デリーはペルシア語文化の中心地だった。デリーの衰退はペルシア語文化の衰退を意味し、そのおかげでペルシア語に比べてステータスの低かったヒンディー語・ウルドゥー語が文学を発展させる機会を得られたのである。
ちなみに、一般にはブラジ語(マトゥラーやアーグラー周辺の言語)やアワディー語(ラクナウー周辺の言語)などもヒンディー語の一方言として考えられ、「ヒンディー語文学」には必ずこれらの言語の文学が内包されるが、僕はその立場には反対である。文学的伝統という見地からはブラジ語文学やアワディー語文学は無視できないが、現在俗に言う「ヒンディー語」とはデリーの言語の標準形であり、その文学史は、少なくとも19世紀に入るまで、現在「ウルドゥー語」と呼ばれている言語の文学史と異なるものではない。歴史的要因からアラビア語・ペルシア語の語彙が多用されていたデリーの言語から、それらを取り出して、代わりにサンスクリット語の語彙を代用して人工的に作り出されたのが現在のヒンディー語であり、換言すれば、ヒンディー語の方がウルドゥー語の傍系であると言っていいだろう。だが、インド独立後のヒンディー語はインドの連邦公用語として政治的バックグランドを得、さらに国連公用語の地位も狙っているたため、逆にウルドゥー語を傍系扱いして呑み込もうとしているように見える。
デリーの歴史散策は当然のことながらデリーでのみ可能であり、デリー在住というアドバンテージを利用して、今までおよそ2年の歳月をかけてデリーに残る数々の遺跡をボチボチと見て来た。まだ全てを網羅したわけではないが、重要なものはかなり制覇したと言える。しかし、デリーの研究を続ける内に、デリーが持つ歴史的特殊性から、デリーの外にもデリーがあることにも気付くようになった。つまり、デリーに何らかの関連のある都市がインド各地に(国外にも)けっこうあるのである。元々旅行は趣味であり、行ったところを挙げて行くよりまだ行っていないところを挙げて行った方が手っ取り早いほどインド中を旅行した。行って見たい未知の場所、もう一度再訪したい場所は山ほどあり、おそらくいつか行くことになると思うのだが、デリー愛が高じて、最近はデリーをテーマにした旅行を優先して行う方針を採りつつある。昨年3月のサルダナー・ツーリングや昨年10月のアジメール・ツーリングはその一環であった。
また、アジメール・ツーリングやデリー散歩バーバー・ファリードの祈祷所でも触れたが、デリー散歩を続ける中でスーフィー聖者(イスラーム教神秘主義者)たちの活動にも興味を持つようになり、それがデリー外デリー旅行やヒンディー語・ウルドゥー語とも関連付けできると思うようになった。スーフィズムにはいくつかの派閥があるが、デリー史の中で特に重要なのはチシュティー派である。デリー外デリー、チシュティー派聖者、ヒンディー語・ウルドゥー語の3つのキーワードを並べ、アジメールの次に行くべき場所を考えていると、自然にデカンのグルバルガーとその周辺都市が候補として浮上して来た。
デカン地方は、デリーから遠く離れているが、デリーの王朝史、またヒンディー語・ウルドゥー語の言語史・文学史と意外なまでに密接な関係を持っている地域である。デカン地方がデリーの王朝の支配下に入ったのはアラーウッディーン・キルジー(在位1296-1316年)の時代で、ムハンマド・ビン・トゥグラク(在位1325-1351年)の時代にはデカン地方に一旦首都が置かれたこともあった。だが、ムハンマド・ビン・トゥグラクの治世にデカンでは独立政権が興り、デリーとデカンは再び政治的に切り離されることになる。しかし、ムガル朝時代に入るとデカン遠征が度々行われるようになった。第6代皇帝アウラングゼーブ(在位1658-1707年)に至っては生涯の大半をデカンで過ごした。また、ムガル朝が衰退すると、今度はデカンに興ったマラーターが北上してデリーに影響を及ぼすようになる。このように、デリーとデカンの歴史は地理的な距離に比べて近い関係を持っている。
また、現在一般にヒンディー語圏と言われている地域は、デリー、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ハリヤーナー州、ウッタラーカンド州、ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州、ジャールカンド州、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州であるが、実はデカン地方のいくつかの都市、つまり現在のマハーラーシュトラ州、アーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州の一部地域でもヒンディー語・ウルドゥー語がよく通じる。それにもデリーとデカンを結ぶいくつかの歴史的事件が絡んでいる。もっとも大きな事件は、前述のムハンマド・ビン・トゥグラクによる遷都である。ムハンマド・ビン・トゥグラクは1327年からデカンの都市ダウラターバード(現マハーラーシュトラ州アウランガーバード近く)に宮廷を移し始め、1329年にデリーの全市民を強制的にダウラターバードに移住させた。だが、ムハンマド・ビン・トゥグラクは1334年にデリーに新都市ジャハーンパナーを建設し、再び首都をデリーに戻した。それでも全ての住民はデリーには戻らず、ダウラターバードにデリーの言語を話す人々がまとまって定住することになった。1347年にはデカン太守ハサン・ガングーが独立政権バフマニー朝を興したが、バフマニー朝の支配者層も元々デリー在住の人々であり、デリーの言語を話していたと想像されるし、実際にデリーの言語が公用語として使用された。バフマニー朝は1518年以降に小王国に分裂するが、それらの各王国でもデリーの言語が公用語として使用されていたと見られている。もうひとつの大きな事件は1398年のティームールによるデリー侵略である。当時のデリーは元から後継者争いによって混乱していたが、ティームールによって虐殺が行われたため、多くのデリー住民がデリーから難民となって流出することになった。このときにも多くの人々がデカンへ移住したと考えられる。これら一連の歴史的事件により、デカン地方にはデリーの言語を話す人々が住むようになり、現在までその伝統が残っている。具体的には、マハーラーシュトラ州のアウランガーバード、カルナータカ州のビージャープルやグルバルガー、アーンドラ・プラデーシュ州のハイダラーバードなどで、主にイスラーム教徒によってヒンディー語・ウルドゥー語が話されている。彼らは、元々デリー在住で何らかの理由でデカン地方へ移住して来たイスラーム教徒支配者層の子孫だと考えられる。ただし、彼らのヒンディー語・ウルドゥー語はデリーの言語とは異なった発展をして来たため、区別してダキニー語と呼ばれることも多い。
グルバルガーの名前が出て来たが、グルバルガーは長らくバフマニー朝の首都が置かれていた都市であり、ティームール侵略後に衰退したデリーの王朝に代わり、当時インドでもっとも栄えた都市のひとつであった。もうひとつ、グルバルガーが重要なのは、チシュティー派聖者のバンダー・ナワーズ・ゲース・ダラーズ(1321-1422年)のダルガー(聖廟)があることである。バンダー・ナワーズは、チシュティー派聖者ナスィールッディーン・チラーグ・デリー(参照)の後継者である。インドのチシュティー派聖者の系譜は、インドにスーフィズムを初めて伝えたモイーヌッディーン・ハサン・チシュティーから、クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー、ファリードゥッディーン・ガンジシャカル、ニザームッディーン・アウリヤー、ナスィールッディーン・チラーグ・デリーと綿々と続いて行き、バンダー・ナワーズ・ゲースー・ダラーズで途絶えている。なぜバンダー・ナワーズ以降チシュティー派聖者の系譜が途絶えたのかはよく分からない。「ゲースー・ダラーズ」とは「長い髪」という意味であり、師から与えられた称号である。伝承によると、彼が他の弟子と共に師ナスィールッディーンの乗った輿を運んで下ろしたとき、彼の長い髪が輿の下敷きになって引っ張られたことがあった。だが、師への敬愛の念から彼はその痛みに耐えた。後にその逸話を聞いた師は喜び、彼に「ゲースー・ダラーズ」の称号を与えたのであった。
デリーを主な拠点として来たチシュティー派最後の聖者としてもゲースー・ダラーズは重要なのだが、彼の生涯はデリーの衰退期を象徴するものとなっており、興味深い。デリー生まれのバンダー・ナワーズは、幼い頃にムハンマド・ビン・トゥグラクによる遷都と強制的移住の影響により、ダウラターバードへ移住することになった。だが、すぐに父親が急死し、バンダー・ナワーズは母親に連れられてデリーに戻り、教育を受ける。フィーローズ・シャー・トゥグラク(在位1351-1388年)の治世にデリーは再び繁栄し、教育も大いに振興されていた。デリーでバンダー・ナワーズはナスィールッディーン・チラーグ・デリーの弟子となり、後継者に任命される。だが、フィーローズ・シャー・トゥグラク死後の混乱またはティームール侵略を受けて彼はダウラターバードへ逃れ、後にバフマニー朝の首都グルバルガーに拠点を移して、そこで死を迎える。それまで北インドを拠点としていたチシュティー派聖者がデカンに移住したことは、スーフィズムやヒンディー語・ウルドゥー語のデカン伝播に一定の役割を果たしたと思われる。また、歴代のチシュティー派聖者たちと違い、バンダー・ナワーズは多くの著作を残している。ほとんどはペルシア語やアラビア語で書かれているが、ヒンディー語・ウルドゥー語の作品もあり(信憑性については異説あり)、ヒンディー語・ウルドゥー語の文学史上でも重要な人物である。バンダー・ナワーズは、ダルガーこそデリーから遠く離れたデカン地方にあれど、その生涯は14世紀のデリーそのものであり、デリー散歩の一環として是非とも抑えて置かなければならない人物であると同時に、彼のダルガーは、ヒンディー語・ウルドゥー語の研究者としても是非詣でておかなければならない場所であった。
グルバルガーはカルナータカ州の北部に位置しており、同名県(District)の県庁所在地となっている。かつてはエヘサーナーバードとかカルブルギーとか呼ばれていたようだが、グルバルガーが正式名称である。バンガロールから617kmもあり、どちらかというとアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードからの方が近いし(220km前後)、歴史的にもハイダラーバード藩王国の領土だった時代もあり、ハイダラーバードとの方が関係が深い。実際、グルバルガーを中心としたカルナータカ州北東部の3州(グルバルガー、ビーダル、ラーイチュール)は、俗にハイダラーバード・カルナータカと呼ばれている。グルバルガーへはバンガロールから1月23日午後9時3分発の夜行寝台バスを利用して移動した(685ルピー)。翌朝目が覚めたときには既にグルバルガー県に入っており、ショーラープル、シャープルなどを経由して午前9時半頃にグルバルガーのセントラル・バススタンドに到着した。
グルバルガーは歴史上無名の都市ではないが、観光という観点では知名度が低そうだ。旅行ガイドブックのフットプリントには記載があるものの、大手のロンリー・プラネットでは全く無視されている。よって、宿探しもほとんど手探り状態であった。さらに追い打ちをかけるように、グルバルガーは外国人旅行者にフレンドリーな町とは言いがたかった。共和国記念日前という微妙な時期の関係もあったかもしれない。いくつかの良さそうなホテルでは「満室」と言われて宿泊を拒否された。だが、オートワーラーが精力的に宿探しに協力してくれたため、バススタンドからそれほど遠くない場所にあるホテル・ラージ・ラージェーシュワリー(Hotel
Raj Rajehwari)に部屋を見つけることができた。ただ、A/Cデラックスルームのみしか空いておらず、料金は725ルピーであった。ホテル・ラージ・ラージェーシュワリーへは、電話をして空室を確認してから行ったのだが、もしかしたらグルバルガーで宿を見つけるときはそれがコツなのかもしれない。また、バススタンド近くのホテルは比較的門戸が広そうな感じもあった。ただ、グルバルガーでもっともいいホテルはホテル・アーディティヤ(Hotel
Aditya)で、このホテルに泊まれればそれに越したことはないだろう。
ホテルで軽食を取ってから、早速グルバルガー観光に出掛けた。まず向かった先はバンダー・ナワーズ・ゲース・ダラーズの聖廟である。グルバルガーでは「ダルガー」と言えば自動的にバンダー・ナワーズ廟を指す。ダルガーはグルバルガー市街地の東部に位置していた。

遠くに見える白いドームがダルガー
残念ながら聖廟では参拝客に対するボッタクリや乞食たちによるバクシーシ(喜捨)攻勢が横行しており、ゆっくりと見て回れるような雰囲気ではなかった。ましてや外国人は珍しいので、彼らの格好の標的になる。大きなダルガーはどこでも少なからずそのような状態となるのであるが、ゲースー・ダラーズ廟はデリーのニザームッディーン廟やアジメールのガリーブ・ナワーズ廟と比べても度を越してひどい印象を受けた。境内には、バンダー・ナワーズ・ゲースー・ダラーズの廟の他に彼の子孫の墓廟が並んでいた。

ダルガーの入り口

境内

バンダー・ナワーズ・ゲースー・ダラーズ廟
ダルガーの建築物の外壁は真っ白に塗られていた。青空とのコントラストは視覚的に美しいのであるが、無造作なカラーリングの印象も否めない。しかし、いくつかの墓廟の内壁には素晴らしい壁画や装飾が残っており、美術的価値を感じた。建築的にはデリーの同時代の墓廟建築と非常に似通っており、デリーの影響を感じずにはいられない。ただ、デリーのスーフィー聖者の墓廟は至ってシンプルなものばかりで、ゲースー・ダラーズ廟のような壮大な墓廟は王侯貴族に限られる。チシュティー派は一般に権力とは距離を置いた派閥と言われており、特にニザームッディーン・アウリヤーは皇帝との癒着を頑なまでに避けた逸話で有名であるが、先日亡くなられた荒松雄氏はその通説に異議を唱えておられた。デリーのニザームッディーン廟に残る、ニザームッディーン存命中に建設されたと考えられる建築物は皇帝の庇護なしには実現不可能な規模のものであるし、フィーローズ・シャー・トゥグラクの即位にもナスィールッディーン・チラーグ・デリーが関与した可能性があり、それらが異議の根拠となっている。それらの真偽はともかくとして、少なくともインド・チシュティー派の系譜の最後の聖者とされているバンダー・ナワーズ・ゲースー・ダラーズは、確実にバフマニー朝の王から厚い庇護を受けていた。彼がグルバルガーにやって来たときは、時の王タージュッディーン・フィーローズ・シャー(在位1397-1422年)が大いに歓迎したと言うし、彼の死去は、フィーローズ・シャーを廃位して即位した弟のシハーブッディーン・アハマド・シャー1世(在位1422-1436年)に多大な衝撃をもたらし、バフマニー朝の首都がグルバルガーからビーダルへ移転する原因ともなったようである。ゲースー・ダラーズ廟もアハマド・シャー1世によって建設された。
ダルガーには、墓廟の他に図書館もあり、ウルドゥー語やペルシア語の書物が所蔵されている。残念ながら訪れたときは閉館していたが、図書館周辺の建築はユニークかつ壮大であった。

図書館周辺の建築
ダルガーの近くにはハフト・グンバズと呼ばれるバフマニー朝王族の墓廟群もある。だが、ハフト・グンバズの入り口は閉まっており、外からしか見られなかった。ここにはムジャーヒド・シャー(在位1375-1378年)からフィーローズ・シャーまでの墓廟が並んでいて壮観である。

ハフト・グンバズ
グルバルガーのもうひとつの見所は、バフマニー朝の王宮が置かれたグルバルガー城塞である。グルバルガー市街地の中央部に位置しており、シャラババサヴェーシュワラ湖の湖畔にそびえ立っている。上空から見るとΩをひっくり返したような形をしている。

グルバルガー城塞
グルバルガー城塞の大部分は荒野となっているが、一部には今でも人が住んでおり、遺跡と生活が混在している。城塞内で特筆すべき建築物はジャーマー・マスジド(金曜モスク)である。第2代のムハンマド・シャー1世(在位1358-1375年)が建設した、140本の柱を持つ巨大なモスクで、ドームの配置などにユニークな特徴が見られる。

ジャーマー・マスジド
城塞の中央部には塔のような小高い建築物があった他、城壁のブルジ(稜堡)には大砲が残っていた。また、西側の入り口は7重の堅固な門となっており、壮観であった。

7重の門
だが、グルバルガー城塞の建築でもっとも興味深かったのは、デリーのトゥグラク朝様式の建築の影響が随所に見られたことである。トゥグラク朝様式の建築物には壁に微妙な傾斜角があったり、三角屋根があったりして非常に特徴的なのだが、それがそのままグルバルガー城塞でも見られた。デリー南郊に残るトゥグラク朝時代の城塞トゥグラカーバードは城壁以外ほとんど廃墟となってしまっているのだが、グルバルガー城塞はもう少し保存状態が良く、トゥグラカーバードのかつての姿を想像するのに役立つ。明らかにグルバルガー城塞は、ダウラターバードと同様に、デカンの地にデリーを再現しようとする、元デリー住民によるノスタルジー・プロジェクトの一環である。グルバルガーはデリーを観光してから来るととても面白い場所だと感じた。

三角屋根
おそらく市場跡であろう

傾斜角を持つ壁
トゥグラカーバード城塞のビジャイ・マンダルと同等の建築物か
グルバルガー城塞の北部にはシャー・バーザール・マスジドという、ジャーマー・マスジドよりも古いモスクが残っているので、そこまで歩いて行ってみた。ところがこちらのモスクは金曜日以外は入り口が閉ざされており、中を見ることができなかった。代わりにシャー・バーザール・マスジドの西にある塔建築を見た。これは門なのか何らかの建築物の一部なのか不明だったのだが、現在では中規模のダルガー(ゲースー・ダラーズのダルガーとは別)の一部となっていた。塔の上まで上れるようになっており、涼むのに最適であった。差し詰めグルバルガーのクトゥブ・ミーナールと言ったところか。

塔建築
他にもグルバルガーには大小様々な遺構が残っており、その様子は古都と呼ぶにふさわしい。西郊外にはチョール・グンバズと呼ばれる墓廟が孤立して残っているのだが、そこまでは行かなかった。これは元々ゲースー・ダラーズの廟として建設されたにも関わらず、結局使われずに放置されたもののようであるが、詳細は不明である。また、同じく西郊外にはセ・グンバズと呼ばれる墓廟群があるはずで、そこにはバフマニー朝創始者ハサン・ガングーの墓廟もあるはずだが、見つけることができなかった。グルバルガーは観光情報に乏しく、町の人々もそれらの遺跡にほとんど関心を払っていないため、観光はスムーズに行かないことが多いのではないかと思う。よって、観光しやすい町とか、居心地のいい町とはお世辞にも言えないが、それでもグルバルガーに残るダルガーや遺跡は、宗教史や建築史の観点からとても重要で興味深い。
バフマニー朝の首都は、ゲースー・ダラーズの死をきっかけに、1425年にグルバルガーからビーダルへ移された。バフマニー朝滅亡後もビーダルを首都にバリード王朝が存続し、ビーダルの繁栄は続いた。ビーダルもカルナータカ州北部の都市のひとつで、同名県の県庁所在地となっている。グルバルガーから北東へ116kmの地点にある。かつてはムハンマダーバードと呼ばれた。グルバルガーの次の目的地はこのビーダルであった。ロンリー・プラネットで紹介されているものの、「誰もビーダルに行こうとしないが、その理由ははっきりしない」と半ば憤慨気味に書かれている。だが、同時に「警告」として「ビーダルでは外国人ウォッチングが人々の暇つぶしになっているから、特に女性は注意されたし」と書かれており、こんな記述があっては旅行者は寄り付かなくなってしまうだろう。それでも、ビーダルはグルバルガーよりも観光に力を入れている様子で、観光地の所在地を示した標識も随所にあり、観光に不便はなかった。折りしもビーダル・フェスティバル2009なる催し物が間近に迫っており、町はその準備に沸いていた。
グルバルガーから午前8時発のバスに乗り、午前11時にはビーダルのニュー・バススタンドに到着した(65ルピー)。ビーダルではマユーラ・バリード・シャーヒーというカルナータカ州観光振興局(KSTDC)運営のホテルに宿泊した。やはりデラックス・ルームしか空いておらず、宿泊費は650ルピーであった。ホテルにはバー&レストランが併設されており、夜は地元の人々で賑わっていた。
ビーダルの最大の見所はやはり城塞である。ビーダル旧市街も城壁で囲まれているのだが、それに隣接して、巨大な城塞が残っている。今までインドでいくつもの城塞を見て来たが、ビーダル城塞はその中でもトップクラスに堅固かつ巨大な城塞建築と言える。周囲を5.5kmの城壁で囲まれ、しかもその城壁は何重にも張り巡らされており、深い堀も巡らされている。6つの門があり、南東にメインの入り口グンバド・ダルワーザーがある。

ビーダル城塞のグンバド門
保存状態も良く、特に一部はきれいに整備されていた。庭園が非常に美しく、その遺構から高い治水技術も見られた。ただ、残念ながら建物の中には入れないようになっていた。宮廷部には小さな博物館もあった。

宮廷部
正面はガガン・マハル(空の宮殿)、
右はソーラー・カンブ・マスジド(16柱のモスク)
城塞はかなり広大で、日中に歩いて回るのはたとえ冬季であってもかなり辛い。城塞内には道路が通っており、自動車やバイクを乗り入れ可能で、地元の人々は乗り物に乗って走り回っていた。この遺跡の中をバイクで走り回れたらどんなに爽快であろうか。城塞内にはヴァルコーティー・バヴァーニー寺院というヒンドゥー寺院があり、その寺院に参拝に来ている人もいたのだろうが、ほとんどは日曜日の暇つぶしに何となくドライブに来ている感じであった。

モスク跡か

タクト・マハル(王座の宮殿)

タクト・マハルの裏側

カーラー・ブルジ(黒の稜堡)
この上には巨大な大砲が置かれていた

城壁
次にビーダル旧市街にあるメヘムード・ガーワーンのマドラサへ向かった。メヘムード・ガーワーンはイラン人で、15世紀中頃にビーダルにやって来て重用された人物である。メヘムード・ガーワーンは宰相と将軍を兼任した他、学者としても一流で、教育の振興も努めた。彼が1472年にビーダル旧市街に建設したのがメヘムード・ガワーンのマドラサと呼ばれる大学で、インドでは他に例を見ないイラン風の建築が特徴的である。メヘムード・ガーワーンは反対派の謀略によって死刑にされてしまうが、その後も彼の創設した大学は存続し続けた。だが、アウラングゼーブの時代に弾薬庫となり、落雷によって大爆発が起こったようで、大学の半分は崩壊してしまっている。現在はミーナール(塔)が1本残っているが、かつては4本立っていたようである。

メヘムード・ガーワーンのマドラサ
奇しくもビーダル・フェスティバルの一環としてマドラサでは教育会議が開かれており、中を見て回ることができなかった。だが、東側の外壁やミーナールに残っているタイルは見ることができ、それらから、かつては青を基調とした美しい建築物であったことが窺われた。上部にはコーランの文句が記されていた。

青いタイルの残る外壁
メヘムード・ガーワーンのマドラサの南の交差点にはチャウバーラーと呼ばれる時計塔が残っており、それが旧市街の中心地となっている。道路拡張工事の真っ最中で閑散としていたが、かつては賑わう市場の中心地だったのだろう。

チャウバーラー
チャウバーラーでオートに乗り、ビーダル西郊にあるアシュトゥールへ向かった。アシュトゥールにはバフマニー朝時代の王族の墓廟群が東西に並んで残っている。東部にあるもっとも巨大で白色の墓廟が、ビーダルに遷都したアハマド・シャーのものである。ドームが半壊した墓廟があるが、これはフマーユーン・シャー(在位1458-1461年)のもの。半壊したおかげで造形的魅力が増している。このフマーユーン・シャー廟は上部へ上がることができた。これらの墓廟はデリーの墓廟の建築ともよく似ている。

アシュトゥール
アシュトゥールの墓廟群の中で興味を引かれたのは、西部にある小さな墓廟たちである。これらはバフマニー朝末期の王アハマド・シャー4世(在位1518-1520年)、ワリーウッラー・シャー(在位1523-1526年)、カリームッラー・シャー(在位1526-1527年)のものであるが、トゥグラク朝様式風の三角形の屋根をいただいている。王国に力があったときはドーム屋根を持った巨大な墓廟が建造されたのに、衰退期に入るとまるで時代が回帰したような古い様式の建築になっているところは面白い。

アシュトゥールの西の墓廟群
アシュトゥールもビーダル市民の休日のピクニック場となっており、多くの人々がくつろいだりクリケットをして遊んだりしていた。ただ、交通は不便なのでビーダルでオートリクシャーをチャーターして来るべきであろう。帰りには、カリールッラー・シャーのダルガー、通称チャウカンディーに立ち寄ることもできる。丘の上に立つ八角形をした白亜の立派な建築である。

チャウカンディー
やはりビーダルも町の至る所に古い遺構が点在する古都であり、しばらく滞在して散策すると面白そうな町であった。他にバリード王朝時代の墓廟、スィク教教祖グル・ナーナク関連のグルドワーラー、古いヒンドゥー教寺院、ダルガーなどがある。
インドにおいて1月26日は、1950年同月同日にインド憲法が施行されたことを記念する共和国記念日であり、デリーなどで式典が開催される他、昨今はテロの影響で1年でもっとも警備が厳重となる日である。デリーに住んでいると共和国記念日は無用なトラブルを避けるためになるべく外出しないようにしようと思うものであるが、デリー以外の都市ではそれほど緊迫感はなく、割と普通の日常がそこにあって新鮮であった。交通機関も通常通り運行されており、おかげで支障なくハイダラーバードへ向かうことができた。ハイダラーバードへ向かった第一の理由は、この後バンガロールに帰るために接続がいいからである。ビーダルはバンガロールから733kmも離れているが、ハイダラーバードまで行けばバンガロールまで560kmほどであり、しかも交通手段のオプションも多い。
ビーダルのニュー・バススタンドで午前7時15分発のハイダラーバード行きバスに乗り込んだ(73ルピー)。ビーダルからハイダラーバードまでは130kmほどであり、3時間半ほどで着くことが期待されたが、途中で立ち寄ったザヒーラーバードという町でバスが故障の修理のためにガレージに入ってしまい、30分間待たされた。だが、午前11時15分にはハイダラーバードのマハートマー・ガーンディー・バススタンドに到着した。
バススタンドに着いた直後に、翌日のバンガロール行きのバスを予約した。日中のバスで行こうと思っていたが、ほとんどのバンガロール行きバスは夜行で、朝出発して夕方着く旅程のバスは、カルナータカ州陸上交通局(KSRTC)が運行する午前6時半発の1便のみであった。そのバスを予約し、宿探しに向かった。翌朝早いこともあり、ハイダラーバードではバススタンドから徒歩の距離にあるホテル・ヒルタワー(Hotel
Hill Tower)に宿泊することにした。バススタンドで客待ちしていたオートワーラーに連れて行かれたホテルで、宿泊費も法外に高く(最初2000ルピーを提示されたが1200ルピーまで値切った。おそらく実際はもっと安いだろう)、あまり雰囲気のいい場所ではなかったので他人にオススメはできないが、1泊しかしないので妥協した。
ハイダラーバードは以前に来たことがあり、チャール・ミーナールやゴールコンダ城塞など、主要な見所は既に見たことがあった。しかも、共和国記念日ということもあり、街ではシャッターを閉じている店が多く、観光もあまりできそうになかった。よって、チャール・ミーナールを中心とした旧市街を散策することにした。

ハイダラーバードの象徴、チャール・ミーナール
まずはチャール・ミーナールの上に上った。と言っても塔に上ることはできず、2階部分までしか行けない。インド人の入場料は5ルピーだが、外国人は100ルピーを取られた。観光客なのか地元客なのか、多くのインド人がチャール・ミーナールに来ていた。
チャール・ミーナールから西に延びるラール・バーザールを散策していると、チャウクと呼ばれる地域に出た。この辺りは書店が多い。その中でハズィーク&モヒーという珍古書店を見つけ、店も開いていたので入ってみた。埃にまみれ、虫に浸食された本の並ぶ、古墳のような本屋であったが、店主の太ったおじさんの知識は確かで、興味あるテーマを言うとそれに関連する本を次々と抜き出して見せてくれた。いくつか重要な本があったのだが、自分の研究に関するもっとも貴重な文献である「A
Defence of the Urdu Language and Character (Being a reply to the pamphlet
called "Court Character and Primary Education in N.-W. and Oudh")」という小冊子があったのでこれを購入した。1900年発行の本であるが、ヒンディー語とウルドゥー語の分離の歴史の中で1900年という年は非常に重要であり、この本は両言語の政治的抗争の軌跡を物語る資料となっている。この店の主人は日本人研究者ともコンスタントに商売をしているようで、親日的な人であった。だが、本の値段設定は容赦なかった。
夜はチャール・ミーナールのライトアップを見た。チャール・ミーナールは白を基調としているのだが、夜はカラフルな光によってライトアップされており、雰囲気がガラリと変わっていた。

ライトアップされたチャール・ミーナール
ハイダラーバードでは食事にも期待していた。残念ながらカルナータカ州北部では南インド料理も北インド料理も並程度のものしか食べられず、グルメの希望は捨てていたので、ハイダラーバードには余計に期待していたのだった。ハイダラーバードと言ったらまずはビリヤーニーなのだが、残念ながら旧市街パッタルガッティーにあるホテル・ナヤーブで昼食に食べたビリヤーニーはおいしくなかった。また、夕食はチャール・ミーナールのそばにあるファラーシャー・カフェで食べたのだが、やはり注文した全ての料理がうまいという訳ではなかった。デリーの料理のレベルが高すぎるのか、それともたまたま入ったレストランが行けていなかったのか。とりあえずデリーの方がハイダラーバードよりもおいしいビリヤーニーが食べられると思っておくことにする。
1月27日は移動の1日であった。世界最大のバススタンドを自称するハイダラーバードのマハートマー・ガーンディー・バススタンドから、予定より10分ほど遅れて、バンガロール行きのバスが午前6時40分頃に出発した。午前8時前後に朝食休憩を挟み、午前11時15分にクルヌールに到着。午後2時にはアナンタプルを経由し、午後3時頃にやっと昼食となった。午後5時45分頃にチクバッラプルで再び小休止となったが、この時点で既にカルナータカ州に入っていた。午後7時30頃にはバンガロールの市街地に到着。ハイダラーバードから13時間ほどかかった計算になる。
一応今は灼熱のデカン高原を旅行するのにもっとも適したシーズンなのだが、それでも日中はとても暑く、日差しも強烈であった。特に城塞遺跡などでは日陰がないことが多いので、日差しの影響をモロに受ける。日中にハイペースで観光していると身体がもたない。それでいて日は短いので、日が傾くのを待っているとすぐに日が暮れてしまう。時間と体力の配分に苦労した小旅行であった。しかし、グルバルガーとビーダルという、前々から行ってみたかった場所を訪れることができたため、満足である。残念ながら今回訪れた都市ではいずれもホテルに恵まれず、しかも観光客を歓迎するような雰囲気がほとんど感じられなかったのだが、これは共和国記念日前の警戒態勢のためだと思いたい。もしこんな状態が年中続いているとしたら、いつまでもマイナーな観光地で終わってしまうだろう。ちなみに、今回はグルバルガーとビーダルを主に巡ったが、これらにビージャープルとゴールコンダを加えるともっと充実した旅になるだろう。両方ともバフマニー朝から分離独立したデカン・サルナタト諸王国の中心都市であり、壮大な歴史的遺構が残っている。どちらも以前に行ったことがあったため、今回は足を伸ばさなかった。
半ば予想していたのだが、今回訪れた都市では普通にヒンディー語・ウルドゥー語が通じた。多少特徴的な訛りがあったが、会話する上で支障はない。バンガロールのオートワーラーよりもよっぽど流暢なヒンディー語を話す。この辺りはマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州の境目にあるため、多くの人々はヒンディー語・ウルドゥー語、マラーティー語、テルグ語、カンナダ語など、近隣の言語をある程度理解するようだ。ウルドゥー語の看板や、ウルドゥー語メディアムの学校も多く見掛けた。地元言語にヒンディー語・ウルドゥー語が上からかぶさっているような印象を受けた。
| ◆ |
1月29日(木) Slumdog Millionaire |
◆ |
ダニー・ボイルと言ったら、新感覚の映像を引っさげて登場した映画「トレインスポッティング」(1996年)の監督として有名だ。同映画は当時若者の間で大いに流行し、映画好きだった僕も完全にその世代の人間である。そのダニー・ボイル監督が、インド人作家ヴィカース・スワループの小説「Q
and A(邦題:ぼくと1ルピーの神様)」を原作に、インドをテーマにした映画「Slumdog Millionaire」を撮ったということで、何か幼馴染みにインドで出会ったかのような嬉しい奇遇感を覚え、期待せずにはいられなかったのだが、僕の期待以上にこの映画は世界中で注目を集め、絶賛され、現在までゴールデン・グローブ賞をはじめ、数々の賞を受賞している。アカデミー賞にも10部門でノミネートされており、各部門での受賞が期待されている(追記:8部門で受賞)。「Slumdog
Millionaire」は英国人監督による英国映画であるが、キャストもストーリーも完全にインド一色であり、音楽もインド映画界が誇る音楽家ARレヘマーンが担当している。さらに、ダニー・ボイル監督は、インドやインド映画の持つエネルギーを高く評価しており、それらに対する愛情を惜しみなくこの映画に注ぎ込んだと言われている。よって、「Slumdog
Millionaire」は、外国映画ながら限りなくインド映画に近い映画とされており、アカデミー賞8部門を受賞したリチャード・アッテンボロー監督の名作「ガンジー」(1982年)とも比されている。2008年初公開の作品であるが、インドでは2009年1月23日に公開された。英語版と同時に、ヒンディー語版「Slumdog
Crorepati」も公開されたが、僕が見たのは英語版の方である。通常、インド映画以外の評はここでは掲載しないのだが、「Slumdog Millionaire」の特殊性と重要性を鑑みて、評論してみようと思う。ちなみに、原作は読んでいない。
題名:Slumdog Millionaire
読み:スラムドッグ・ミリオネア
意味:スラムの犬、億万長者に
邦題:スラムドッグ$ミリオネア
監督:ダニー・ボイル、ラヴリーン・タンダン
制作:クリスティアン・コルソン
原作:ヴィカース・スワループ「Q and A(ぼくと1ルピーの神様)」
音楽:ARレヘマーン
出演:デーヴ・パテール、フリーダ・ピント、マドゥル・ミッタル、アニル・カプール、イルファーン・カーン、サウラブ・シュクラ、マヘーシュ・マーンジュレーカル、アンクル・ヴィカル、ラージ・ズトシー、アーユーシュ・マヘーシュ・カーデーカル、タナエ・チェーダー、ルビーナー・アリー、タンヴィー・ガネーシュ・ローンカル、アズハルッディーン・ムハンマド・イスマーイール、アーシュトーシュ・ロボ・ガージーワーラー
備考:PVRバンガロールで鑑賞、ほぼ満席。

デーヴ・パテール(左)とフリーダ・ピント(右)
| あらすじ |
2006年、ムンバイー。世界最大のスラム、ダーラーヴィー出身で、コールセンターでチャーイボーイをして生計を立てるジャマール・マリク(デーヴ・パテール)は、警察署で警部補(イルファーン・カーン)とシュリーニワース巡査(サウラブ・シュクラ)から拷問を受けていた。ジャマールは、プレーム(アニル・カプール)が司会を務める人気クイズ番組「Kaun
Banega Crorepati(誰が億万長者になるか)」で全問正解して1千万ルピーを獲得し、翌日2千万ルピーを賭けた最後の問題に望むところであったが、詐欺を疑われて警察に逮捕されたのであった。拷問は一晩中続いた。
だが、ジャマールは詐欺をしたわけではなかった。偶然にも出題された問題は彼の過去の人生に関わるものばかりであり、その経験をもとに解答していたのだった。警部補は昨晩の番組の録画を再生し、ジャマールはそれらについてひとつひとつ説明し出す。
最初の問題は映画「Zanjeer」(1973年)の主役に関わるものだった。答えは、スーパースター、アミターブ・バッチャンであり、インド人なら誰でも答えられるものであったが、特にジャマールはアミターブ・バッチャンの大ファンで、かつて彼のサインをもらったこともあった。だが、兄のサリームにそれを売り飛ばされるという苦い思い出も持っていた。
次の問題はインドの国章に刻まれた文句「サティヤメーワ・ジャヤテー(真実は勝利する)」についてであった。それもインド人なら誰でも知っているものであったが、無学なジャマールは答えられず、ライフラインの「オーディエンス」で何とか乗り切った。「サティヤメーワ・ジャヤテー」も知らない青年が1千万ルピーを獲得したということで、ますます疑いは募った。どんな知識人でも今までそんなところまで行けた者はいなかった。
次の問題はヒンドゥー教の神ラームが右手に持っている品物についてであった。ジャマールの脳裏には、1993年のボンベイ暴動の悲劇がよぎった。イスラーム教徒のジャマールは、スラムのイスラーム教徒居住区に母親や兄サリームと共に住んでいたが、バーブリー・マスジド破壊事件を受けてボンベイ(現ムンバイー)で発生した一連のコミュナル暴動の中で、彼らの居住区はヒンドゥー教徒の暴徒による襲撃を受け、母親を殺されてしまったのだった。このとき彼はラームの姿をした少年が右手に弓矢を持っているのを目撃しており、そのシーンが恐怖と共に脳裏に刻み込まれていた。だが、このとき新たな出会いもあった。暴動の中を逃げ惑う内に、ジャマールはラティカーという女の子と出会う。サリームはラティカーを無視しようとしたが、ジャマールは彼女を仲間にする。こうして3人はスラムで一緒に暮らし始めたのであった。
次の問題は、バジャン(宗教賛歌)「Darshan Do Ghanshyam(クリシュナ神よ、姿を見せておくれ)」の作者についてであった。その歌もジャマールの人生にとって大きな意味を持ったものだった。ゴミ拾いをして何とか生計を立てていたサリーム、ジャマール、ラティカーは、突如として現れたマーマン(アンクル・ヴィカル)という男に拾われ、孤児院のような場所へ連れて行かれる。そこではご飯をたらふく食べることができ、スラム暮らしの彼らにとって天国のようであった。ただ、マーマンは子供たちに乞食をさせると同時に、「Darshan
Do Ghanshyam」を歌うレッスンを課していた。上手に歌えるようになったら、子供たちはプロの歌手になれると信じていた。しかし現実は残酷であった。サリームは、アルヴィンドという子供がその歌を上手に歌えるようになったがために、目を潰されて盲目の乞食にされるところを目撃してしまう。サリームはジャマールとラティカーと共に逃げ出す。サリームとジャマールは何とか逃げ切るが、ラティカーは逃げ遅れてしまった。以後、ラティカーとはしばらく音信不通となる。
その後、サリームとジャマールは列車で物売りをして生計を立て始めた。彼らは列車でインドのいろいろな場所を旅行する。最終的にはアーグラーのタージ・マハルに辿り着き、そこで今度は観光客の荷物を盗んだりガイドをしたりして生計を立てるようになる。一儲けした2人は、ムンバイーに戻って来る。ジャマールはラティカーのことが忘れられず、彼女を見つけたいと思っていたのだった。
次の問題は、米国の100ドル札の肖像は誰かというものであった。それも彼の人生と関わるものであった。アーグラーで米国人観光客から100ドル札をもらっていたからだ。だが、そこに描かれた人物が誰かということまで彼は知らなかった。ムンバイーに戻った2人は、厨房で働きながら暇を見つけてはラティカーを探す。その中でジャマールは、かつてマーマンに盲目にされたアルヴィンドと出会う。アルヴィンドは歌を歌って乞食をしていた。ジャマールは彼に100ドル札を渡す。アルヴィンドは声ですぐにそれがジャマールだと気付く。アルヴィンドは100ドル札に描かれた人物がベンジャミン・フランクリンだと教える。また、彼はラティカーの居所も知っていた。彼女は現在、チェリーという名前で呼ばれており、売春街で踊りのレッスンをさせられていた。サリームとジャマールはラティカーを探しに行く。そこでラティカーと再会するが、宿敵マーマンにも遭遇してしまう。だが、サリームはどこからか銃を入手しており、マーマンを射殺して復讐を果たす。3人は逃げ出す。
元々性根が曲がっていたサリームは、次第に悪の道に走り出す。彼はダーラーヴィーを支配するマフィア、ジャーヴェード(マヘーシュ・マーンジュレーカル)の部下になると同時に、ラティカーをジャマールから奪い、彼を追い払ってしまう。以後、ジャマールはサリームやラティカーと連絡が途絶えてしまう。いつしかジャマールはコールセンターでチャーイボーイとして働くようになる。
次の問題は、ケンブリッジ・サーカスが英国のどの都市にあるかというものであった。コールセンターでの経験により、彼はそれがロンドンにあることを知っていた。また、コールセンターのコンピューターで電話番号を検索することで、サリームの連絡先を突き止める。久し振りに再会したサリーム(マドゥル・ミッタル)は、ジャーヴェードの片腕としてすっかりマフィアの一員となっていた。ジャマールはラティカーの居場所を聞くが、サリームは、ラティカーは遠い昔に死んだと答える。だが、それを信じられないジャマールはサリームを尾行し、ジャーヴェードの邸宅にラティカー(フリーダ・ピント)がいるのを発見する。ラティカーはジャーヴェードの愛人になっていたのだった。ラティカーはジャマールとの再会を喜び、彼と駅で待ち合わせをして逃げ出そうとするが、サリームらに捕まり連れ去られてしまう。以後、ジャーヴェードは邸宅を引き払ってどこかへ行ってしまい、彼女の行方は分からなくなってしまうが、ジャマールは、彼女がクイズ番組「Kaun
Banega Crorepati」を欠かさず見ていることを知っており、この番組に出演すれば彼女に見てもらえると考え、出演を決めたのであった。
次の問題はクリケットに関するものだった。史上もっとも多くファーストクラス・センチュリー(ファーストクラス形式の試合における100ラン)を記録した選手は誰か、という質問だった。ジャマールには、Aのサチン・テーンドゥルカルでないことは分かっていたのだが、答えは分からなかった。そこで一旦休憩となり、ジャマールはトイレに行く。そこで司会者プレームは彼に「答えはBだ」と教える。だが、ジャマールは騙されているのではと考えた。彼はライフラインの「50:50」を使うが、不幸にも残ったのはBとDであった。ジャマールは思い切ってDを選ぶ。それが正解だった。それによって、ジャマールは1千万ルピーを獲得したが、そこでその日の収録は終了となってしまい、翌日最終問題が出題されることになった。だが、プレームはジャマールが詐欺をしていると思い込み、警察に通報して逮捕させる。そのときからジャマールは警察署に拘束されていたのだった。
彼の話を聞いた警部補は、その話に嘘はないと結論を出し、彼が番組に出ることを許す。既に世間ではスラム出身の貧しい青年が番組で1千万ルピーを獲得した話題で持ち切りで、彼は一躍時の人となっていた。人々に見送られながらジャマールはテレビ局へ向かう。一方、サリームとラティカーもジャーヴェードの隠れ家でその番組を見ていた。ジャマールの成功を見たサリームは、ラティカーに自動車の鍵と携帯電話を渡し、彼女を逃がす。ラティカーはテレビ局へ向かうが、渋滞に巻き込まれてしまい、路上で番組を鑑賞することになる。
番組が始まった。ジャマールに出題された最後の問題は、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説「三銃士」に出て来る3人目の主人公の名前であった。「三銃士」は、サリームとジャマールが子供の頃に学校で読まされた小説であり、2人は教師からアトス、ポルトスと呼ばれていたが、3人目の名前は分からなかった。ジャマールは最後のライフラインである「テレフォン」を使用する。彼は兄サリームの携帯電話を登録していたが、電話に出たのはラティカーであった。元々ラティカーと連絡を取るために番組に出場していたジャマールは、彼女と話ができただけで満足であった。ラティカーは答えの代わりに「神のご加護を」と言う。ジャマールは無心になって答えるが、偶然にもそれが正解で、彼は2千万ルピーを獲得する。
深夜の駅・・・そこはかつてラティカーと待ち合わせをした場所だった。ジャマールはそこで彼女をひたすら待っていた。やがてそこにラティカーは現れ、2人は再会を喜び、抱き合う。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
アミターブ・バッチャン、クリケット、タージ・マハル、コールセンター、コミュナル暴動、スラム再開発、乞食ビジネスなど、インドの様々な側面をクロスカッティングを多用した見事な手法でひとつのまとまりあるストーリーの中に詰め込んだ傑作。さらに、「トレインスポッティング」を彷彿とさせる独特の映像美も、ストーリーを邪魔しない程度に程よく織り込まれており、ダニー・ボイルの映画監督としてのスキルの熟成も感じさせられた。ただ、ストーリーがあまりにインドの文化に深く食い込んでおり、インドのことを知らない人が見たら理解できないであろう部分も散見された。それは例えば映画「Zanjeer」やアミターブ・バッチャンに関する下りであったり、ファーストクラス・センチュリーというクリケットの専門用語であったりする。ボンベイ暴動に関するシーンも、子供の頃の記憶のひとつとして済まされており、何の解説もなかった。インドのことをよく知っている人ならすぐに気付くが、そうでない一般の観客にはその意味がいまいちピンと来ないのではなかろうか?主人公の兄弟がイスラーム教徒で、ヒロインはヒンドゥー教徒であるという点も、インドに造詣の深い人なら名前だけで自然に察することができるが、一般人にそこまで期待できないだろう。このような極度にインド向けの映画が国際的に高い評価を得たことは多少驚きである。また、あまりにインドの汚ない部分が前面に押し出されており、それが一般の外国人が想像するインドのネガティブなイメージを助長するものであるため、インドをよく知らない人々への悪影響が心配される。スラムでの便所管理とか列車の中での物売りとかならまだしも、タージ・マハルでの靴泥棒とか置き引きなどは、僕もインドで少なからず盗難被害に遭ったことがあるため、見ていて心が痛んだ。こんなのを見せられては、せっかくインドを旅行したいと思っている人も二の足を踏んでしまうだろう。
映画で題材となっていた「Kaun Banega Crorepati」は、実際にインドで放映されているクイズ番組であり、日本の「クイズ$ミリオネア」と同系列の番組である。オリジナルの英国版の題名は「Who
Wants to Be a Millionaire」で、英セラドール社からライセンス提供を受けた番組制作会社が世界各国で同様のクイズ番組を制作している。インド版での初代司会者はアミターブ・バッチャン、2代目司会者はシャールク・カーンで、どちらもボリウッド映画界のスーパースターだ。90年代一時停滞期に入っていたアミターブ・バッチャンは、この番組で司会をすることで人気を取り戻したという経緯もあり、インド映画史上でも一定の意義を持ったテレビ番組だと言える。
「Kaun Banega Crorepati」は、基本的に四択式のクイズ番組であるが、解答者はライフラインと呼ばれる3種類のヘルプを各1回ずつ使用することができ、展開に起伏を持たせてある。それは、観客にアンケートする「Ask
The Audience(オーディエンス)」、四択をランダムで二択にする「50:50」、予め登録した電話番号に電話をかけ、知り合いに質問する「Phone
A Friend(テレフォン)」である。「Slumdog Millionaire」で優れていたのは、番組の特徴であるこれらライフラインのシステムを効果的にストーリーの中に組み込んであったことだ。「オーディエンス」は解答者ジャマールが一般常識のない人間であるということを示すために使われ、「50:50」は司会者プレームの傲慢な策略を暴くのに使われた。そして映画のハイライトは、最終問題で「テレフォン」を使うシーンである。ジャマールは賞金を獲得するためではなく、子供の頃から思いを寄せていた女性ラティカーと連絡を取りたいがために番組に出場していた。ジャマールは「テレフォン」を使って兄サリームと話そうとしたが、偶然電話はラティカーにつながる。彼女と話せたことで彼の目的は叶ったのであり、もはや彼にとってクイズの解答はどうでもよかった。その無心な気持ちで選んだ選択肢が偶然正解となり、彼は見事2千万ルピーを獲得することになったのである。
ただ、賞金の使い道は映画では描写されておらず、観客の想像に任せる形となっている。だが、十分その後の幸せな展開を予想できるものとなっていた。それと関連し、最後にジャマールとラティカーが駅でボリウッド風のダンスを踊るシーンがあった。必ずしも映画の雰囲気と合っておらず、しかも2人ともあまり踊りがうまくなかったが、これはダニー・ボイル監督のボリウッド映画に対するオマージュと受け止めればいいだろう。ダンスシーンで駅の時計が1時頃を指していたが、おそらくこれはムンバイーのローカル列車の終電時刻を示していると思われる。
「Slumdog Millionaire」は、ジャマールとラティカーのロマンスと見ればハッピーエンドであるが、もうひとつ映画の重要なテーマは、ジャマールと兄サリームの人生の対比である。サリームは、ジャマールがアミターブ・バッチャンからもらったサインを勝手に売り飛ばした幼少時のエピソードが象徴するように、性根の曲がった人間であった。一方ジャマールは、暴動で両親を失い、雨の中立ちすくむラティカーを屋根の下に招き入れた幼少時のエピソードが象徴するように、まっすぐで心優しい人間であった。サリームは、かつて自分たちを騙そうとしたマーマンを射殺し、マフィアのボス、ジャーヴェードの部下となって、悪の道へ進むが、ジャマールは、コールセンターのチャーイボーイをしながら地道に生計を立てる。ジャマールが「Kaun
Banega Crorepati」に出演したのもラティカーへの一途な思いからであり、その正直な気持ちが結果的に彼に成功を呼び込む。一方、サリームはジャマールの成功を見て、自分の命を捨てる覚悟でジャーヴェードの愛人となっていたラティカーを逃がし、札束で満たされた浴槽に入って最期を迎える。それはジャマールの2千万ルピー獲得との悲しい対比であり、おそらく、正しくない手段で手に入れた金や権力には何の意味もなく、一途な気持ちで正直に取り組めば、金を含め、何事もうまく行くということを暗示したかったのだろう。最期にサリームが口にした言葉は「神は偉大なり」であった。ただ、サリームがジャーヴェードの手下となったのも、マーマンの部下の復讐から身を守るためであり、ジャマールを追い払ったのも、弟のことを思っての行動だったのかもしれない。そう考えると、最後にラティカーを逃がしてジャマールの元に送ったのは、基本的に彼が弟思いの性格だったからだと言えそうだ。悪の道に進みながらも、完全に良心は失っていないことを最期に見せたかったのだろう。この勧善懲悪的展開や登場人物の心変わりは、ボリウッド映画の方程式とも共通する。
アニル・カプール、イルファーン・カーン、サウラブ・シュクラ、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ラージ・ズトシーなど、ボリウッド映画界では名の知れた渋い俳優たちが脇役として出演しており、ボリウッド映画ファンとしてはそれだけでも嬉しい。だが、主役はデーヴ・パテールとフリーダ・ピントという全く無名の若い俳優たちである。デーヴ・パテールはインド系英国人で、テレビドラマぐらいにしか出演経歴がなく、今回は大抜擢だったと言えるだろう。名演とまでは行かないが、悪くない演技をしていた。フリーダ・ピントはマンガロール・クリスチャン系のモデルで、やはり「Slumdog
Millionaire」以前に大した経歴を持っていた訳ではない。フリーダ・ピントの方が出番は少なかったものの落ち着いた演技をしていたように感じた。また、サリームを演じたマドゥル・ミッタルは、声に渋みがなく、キャラクターに合っていなかったのではないかと思われる。さらに、幼少時代のジャマール、ラティカー、サリームを演じるため、子役俳優もキャスティングされていたが、皆とてもいい演技をしていた。
音楽はARレヘマーン。既に彼はこの映画の音楽でゴールデン・グローブ賞を受賞しており、アカデミー賞でもオリジナルスコア賞と楽曲賞の2部門でノミネートされている。しかし、長年彼の音楽を聴き続けて来た者の耳には、「Slumdog
Millionaire」の音楽は彼の最高傑作ではないように聞こえる。最後のダンスシーンで流れる「Jai Ho」などいかにもレヘマーンらしい音作りだが、これらの曲は彼のディスコグラフィーの中では平均レベルの出来である。これで国際的に権威のある賞を受賞したりノミネートされたりするのだったら、今まで彼が作って来た音楽はいったいどうなってしまうことか。世界がようやくレヘマーンに追いついたと言っていいだろう。
前述の通り、インドではこの映画の英語版とヒンディー語吹き替え版が公開されている。だが、英語版でもかなりの数のヒンディー語の台詞が出て来た。主要な台詞にはスタイリッシュな形で英語字幕が付いていたが、全てではなかったし、映画の情緒を理解するのに重要ないくつかのヒンディー語台詞が字幕を伴っていなかった。特に最後、ラティカーが「テレフォン」でジャマールと話したときに彼に対して投げかけた「神のご加護を」という言葉の言いかけの形が映画のもっとも美しい部分だったのだが、字幕が付いていなかった。
細かい点になるが、クイズで出題されていた「Darshan Do Ghanshyam」の作者について。映画中では中世バクティ詩人スールダースが正解になっていたが、実はこれは彼の詩ではない。映画「Narsi
Bhagat」(1957年)に出て来た曲で、ゴーパール・スィン・ネーパーリーによって書かれた詩である。ジャマールがスールダースと答えたのは、スールダースが盲目の詩人として知られているからだ。スールダース作と言われるブラジ語(マトゥラー地方の言語)で書かれたクリシュナ神の賛歌の数々は、盲目の詩人のものとは信じられないほど情景豊かなものが多い。「Darshan
Do Ghanshyam」を上手に歌えるようになった少年アルヴィンドはマーマンによって盲目にされてしまったが、これは盲目の乞食がスールダースの歌を歌うことで人々の同情を買いやすいという計算に基づいてのものである。これらのつながりからスールダースが解答として浮かんだという設定である。
ついでになるが、「Slumdog Millionaire」ではインドの乞食ビジネスに対しても深く切り込まれていた。よく、インドの乞食は、乞食としての稼ぎをよくするために、自分の子供の手足を切り落としたりすると言われるのだが、映画「Traffic
Signal」(2007年)を見ても明らかのように、そんなことはありえない。たとえ乞食であろうとも自分の子供は自分の子供であり、実の親が何の罪もない自分の子供に対してそのような酷い仕打ちをするとは、インドの文化からしたら普通ありえない。むしろ、乞食が組織的ビジネスになっていることの方が問題であり、もし人工的に不具者が作られているとしたら、彼らは残酷な両親によってではなく、そのビジネスの餌食となったと考えた方が自然である。映画中に出て来たマーマンは、路上生活者の子供たちを集めて来て、寝食を保証する代わりに乞食をさせる乞食ビジネスの元締めであった。しかも、彼は歌のうまい子供を麻酔で眠らせて目を潰し、盲目の乞食として路上で歌を歌わせて喜捨銭を稼がせていた。さらに彼は、少女ラティカーに踊りを仕込ませて売春婦として売り飛ばそうともしていた。このように、インドの乞食は「貧困」の一言で片付けられるような単純な問題ではなく、そのインドの社会の暗部を先入観に囚われずに適切に取り上げていた点で、「Slumdog
Millionaire」は意義ある映画である。ただ観客に感動を安売りするためにインドの貧困を利用したような安易な映画ではない。
ちなみに、クイズの中に出て来たファーストクラス・センチュリーとは、ファーストクラス形式のクリケットの試合において1人で100ランを得点することである。クイズで出題されたのは、史上もっとも多くのファーストクラス・センチュリーを獲得したのはどの選手か、というもので、その解答はDのジャック・ホッブスで間違いない。1963年に死去した伝説的英国人クリケット選手ジャック・ホッブスは、現役時代に199回のファーストクラス・センチュリーを記録している。現在クリケットの国際試合で一般的なテストマッチは、ファーストクラス・マッチの一形式であるが、一般にファーストクラス・マッチという用語は国際試合には適用されない。現在ファーストクラス・マッチは英国の国内試合ぐらいでしか行われていないため、今後も彼の記録は破られにくいとされている。
「Slumdog Millionaire」は、英国映画でありながら極度にインドを感じさせられる映画であり、インドを旅行した者が見たら必ずインドが懐かしくなるだろう。つい「ああ、こんな子供たち、いたな」と思うこと請け合いである。つまり、インドを知っていれば知っているほどこの映画は面白くなる。ダニー・ボイル監督のインド愛もヒシヒシと感じる。だが、ここまで国際的に高い評価を得ているということは、インドを実際に体験していない観客にも受けているということであり、そこまで一般的なアピールのある作品だと認められていることに多少の驚きと疑問を隠せない。おそらく「想像通りのインドがそこにある」「見たかったインドがそこにある」という点がもっとも受けているのではないかと思うが、そうだとしたらインドにとって決して名誉なことではないので注意が必要だ。インドの要素を抜きとしたら、クイズ番組「Kaun
Banega Crorepati」の特徴をうまくストーリーに組み込んだ脚本とダニー・ボイル印の映像美のみが突出して優れており、それ以外は特に何の変哲もないシンデレラ・ファンタジーということになる。もっとも、インド映画ファンも含め、全ての映画愛好家必見の映画であることには変わりがない。日本では「スラムドッグ$ミリオネア」という題名で4月から一般公開のようである。



