デリーが誇る3つの世界遺産のひとつ、ラール・キラーの観光を終えた後、ラーハウル門を背に西へ向かって歩いて行くと、もうそこはオールドデリーの目抜き通りチャーンドニー・チャウクだ。とりあえず左側に巨大なジャイナ教寺院やヒンドゥー教寺院がそびえ立っているのが見える。チャーンドニー・チャウクと三叉路を作っている大通りは、ネータージー・スバーシュ・マールグと呼ばれている。元々チャーンドニー・チャウクはラーハウル門のすぐそばから続いていたのだが、1857年のインド大反乱の後、防衛上の理由から英国人によってラール・キラー周辺の建物の大部分は破壊されてしまい、チャーンドニー・チャウクも削られてしまった。ネータージー・スバーシュ・マールグも大反乱後に作られた新しい道である。この道を越え、チャーンドニー・チャウクに入る。寺院群とは反対側の北側の道を西に向かって歩いて行くと、やがて右手にマクドナルドが見えて来る。ムガル朝時代から続く繁華街にマクドナルドの店舗が進出したのはひとつの事件であった。日本で言うならば、浅草の仲見世にマクドナルドが出来るぐらいの衝撃である。だが、その戦略的立地が功を奏し、オールドデリーを観光する外国人観光客で賑わっている。マクドナルドのすぐそばに路地がある。その路地の中に入ると、そこは照明器具や医療器具のマーケットとなっている。北インド最大の電子機器卸売り市場である。道は曲がりくねり、人と物と車でごった返しているが、方向を見失わないように北へ北へと進むことを心掛けると、やがてヨーロッパ風の邸宅がマーケットの建物に埋もれているのを発見する。それがベーガム・サムルーの邸宅である。現在ではバギーラト・パレスと呼ばれており、インド中央銀行のオフィスとなっている(EICHER「Delhi
City Map」P59 A3)。

ベーガム・サムルーの邸宅
ベーガム・サムルーは、18世紀末から19世紀初めの北インドで重要な働きをした女性である。その人生は波乱万丈と表現するにふさわしい。出自は諸説あるが、彼女は元々はデリーの踊り子に過ぎなかった。だが、当時北インドで最強の混合傭兵部隊を率いていたヨーロッパ人隊長ウォルター・ラインハルトと出会い、彼女の運命は一変する。以後、彼女はウォルターと共に戦場を駆け巡る生活を送る。ウォルターはムガル朝皇帝から功績を認められ、メーラト近くのサルダナーの領主になる。ウォルターが死去すると、ベーガム・サムルーはサルダナー王国の女王に即位し、軍団の指揮を引き継いで、ムガル朝の絶体絶命の危機を救うまでの活躍を見せる。皇帝シャー・アーラム2世はベーガム・サムルーを実の娘として扱い、可愛がったと伝えられる。彼女の邸宅がチャーンドニー・チャウクの一等地にあるのもそのためである。当時、彼女の邸宅の周辺は広大な庭園となっていたようだが、時の流れと共に風景は変わり、現在ではゴミゴミした市場となっている。ベーガム・サムルーの人生は文学作品の題材にもなっており、例えばプラタープ・シャルマーが「Begum
Sumroo」という演劇を書いている。

外観を見渡せる場所は限られている
ベーガム・サムルーとウォルター・ラインハルトの生涯についてもう少し詳しく見てみよう。ウォルター・ラインハルトは、1720年頃、ルクセンブルグ大公国統治下のトリーア(現在はドイツ領)またはフランス統治下のストラスブールで生まれたとされている。資料によってウォルターはフランス人とされたり、ドイツ人とされたり、スイス人とされたりしているが、どちらにしても、現在のドイツとフランスの国境付近が生まれ故郷であることは確かなようで、ドイツ語とフランス語を理解したことが容易に想像される。ウォルターは1754年頃にチャンスを求めてインドの地を踏む。この頃のウォルターの経歴には諸説があってはっきりしないが、まずはイギリスまたはフランスの東インド会社で私兵として働き出したようだ。18世紀当時のインドは、衰退期に入ったムガル朝、それに乗じて勃興した地方政権、そしてヨーロッパでの覇権争いに連動してインドで抗争を繰り広げるヨーロッパ列強が入り乱れた戦国乱世であり、ウォルターのように多くの冒険心旺盛なヨーロッパ人が一獲千金を求めてやって来ていた。その頃はまだ国籍という概念も希薄だったようで、かなり自由にいろいろな国の組織に雇用されていた。彼らはヨーロッパの組織で働くだけでなく、インドの土着の王国に仕えることもあったし、インド側の軍隊を率いてヨーロッパの軍隊と戦うこともあった。
ウォルターはイギリス式兵法とフランス式兵法の両方をマスターしていたとされる。しかも彼の人生を見てみると、特に後半は反英国的な行動が多い。当初はヨーロッパの軍隊に勤務していたウォルターはやがてベンガル太守に仕えるようになり、軍隊を西洋式に訓練する任務を引き受ける。この頃から彼は「サムルー」と呼ばれるようになる。彼は「サマー(Summer)」という名字を持っていたが、色黒だったために同僚から「ソンブル(Sombre)」とあだ名されていた。「サムルー」は「ソンブル」のインド訛りである。
1760年からベンガル太守に就いていたミール・カースィムは、当初イギリスの操り人形に過ぎなかったが、次第にイギリスとの仲が険悪になり、遂に1763年に戦争が勃発する。このときのベンガル太守軍の司令官がウォルター・ラインハルトであった。英国軍は過去類を見ない強烈な攻撃を受け、敗北する。それだけでなく、捕虜となった英国人は惨殺される。その惨殺を指揮したのもウォルターだったとされる。英国もすぐに報復に出るが、ミール・カースィムは、亡命中のムガル朝皇帝シャー・アーラム2世やアワド太守シュージャーウッダウラーと組んで英国に立ち向かった。だが、1764年のバクサルの戦いで、ムガル・ベンガル・アワド連合軍は決定的な敗北を喫し、これを機に英国東インド会社はインド東部の支配権を確固たるものとする。
しかし、サムルーが率いた部隊は敗戦の中でも見事な退却を見せ、そのまま英国の支配の手が及んでいないインド西部へ向かった。以後7、8年間、サムルーはヨーロッパ人とインド人から成る精鋭傭兵部隊を率い、ジャイプル王国やバラトプル王国などに仕えて数々の戦争に参加した。当時アーグラーはバラトプル王国の支配下にあったが、ウォルターはアーグラー城の城主に任命されるほど戦績を上げていた。
バクサルの戦いでの敗戦後、イラーハーバードで英国から年金を受け取って生活していたムガル朝皇帝シャー・アーラム2世は、1772年にマラーターの力を借りてデリーに帰還し、ムガル朝再興を開始する。だが、当時のデリーは、現ウッタル・プラデーシュ州西部を拠点としたアフガン系のローヒラー勢力や、パンジャーブ地方のスィク教徒勢力など、常に周辺の勢力によって危機にさらされていた。シャー・アーラム2世と苦難の亡命生活を共にした名将ナジャフ・カーンはウォルターと旧知の仲であり、彼をデリーに呼び寄せる。ムガル朝に鞍替えしたウォルターは、反乱を起こしたローヒラーのザブター・カーンを敗走させ、その功績によりドアーブ地方(ヤムナー河とガンガー河の間の地域)の領有権を与えられる。ウォルターは1773年にメーラト近くのサルダナーを首都とし、サルダナー藩王国を興す。ウォルターはかつての雇い主であったバラトプル王国とも戦い、アーグラーを奪い返す。ウォルターは再びアーグラー城の城主に任命され、1778年に死去するまでその地位に留まった。ウォルターの墓はアーグラーのローマン・カトリック共同墓地にある。
ベーガム・サムルーの出自にも諸説がある。カシュミール人の血筋だという説もあれば、アラブ人の血筋だという説もある。本名はファルザーナーとされている。1753年頃、メーラト近くのコーターナーで生まれ育ったが、幼い頃に父親を亡くし、母親と共にデリーに移り住んだ。母親はタワーイフ(踊り子または娼婦)として生計を立てたようで、ファルザーナーも幼い頃から高級娼婦としての素養を身に付けた。
ウォルターとファルザーナーの出会いは1765年頃のようである。当時バラトプル王国のジャワーハル・スィンに仕えていたウォルターは王のデリー遠征に従ったが、そのときファルザーナーに一目惚れし、そのまま共に戦場を連れ歩くようになった。ウォルターとファルザーナーが正式に結婚したか否かについては議論があるが、ここでは便宜上夫婦として扱う。ファルザーナーは美しいだけでなく聡明かつ勇敢な女性であった。ウォルターが育て上げた北インド最強の軍隊を、夫の死後も立派に指揮し、ムガル朝の危機を度々救った。
例えば1783年。スィク教軍団のサルダール・バゲール・スィンがデリーを占領したことがあった。このときバゲール・スィンはデリーのスィク教関連地にグルドワーラーを建設するが、最後までラール・キラーの中には入れなかった。なぜならファルザーナーがしっかり守護し、巧みな交渉を行ったからである。皇帝と講和をしたバゲール・スィンはパンジャーブへ戻って行った。
1787年には、ザブター・カーンの息子のグラーム・カーディルが反乱を起こし、デリーを占領する。このときファルザーナーはパーニーパト近辺でスィク教勢力と戦っていたが、この知らせを聞くや否やデリーに取って返し、グラーム・カーディルを敗走させる。シャー・アーラム2世はファルザーナーの忠誠を喜び、彼女にゼーブンニサー(女性の中の宝石)という称号を与えた。
この頃のムガル朝は毎年のように危機を迎える。1788年には名将ナジャフ・カーンの養子ナジャフ・クリー・カーンが反乱を起こす。シャー・アーラム2世は自ら軍勢を率いて討伐に向かったが、奇襲を受けて命の危険にさらされる。しかしファルザーナーは混乱に陥ったムガル軍を立て直し、反撃を開始する。ナジャフ・クリー・カーンは敗北し、降伏する。シャー・アーラム2世はファルザーナーを「もっともいとおしい娘」と呼んで実の娘扱いし、彼女に新たな領土を与えた。
このような輝かしい戦績を重ねている内に、いつしか彼女はベーガム・サムルー(サムルー女王)と呼ばれるようになり、北インドの最重要人物に数えられるまでになった。あまりの強さに、人々の間では、ベーガム・サムルーは魔法を使って敵を撃破する魔女だと実しやかに囁かれるようになった。噂では、ベーガム・サムルーが布を広げるだけで敵が殲滅されるとされた。
ベーガム・サムルーは元々イスラーム教徒であったが、1781年にカトリックに改宗し、ジョアンナという洗礼名を受けた。これは、フランスの英雄ジャンヌ・ダルクにあやかって付けられた名前であった。しかし、彼女は改宗後もイスラーム文化を捨てようとせず、彼女の宮廷ではヨーロッパ文化とイスラーム文化の混交文化が花開いた。サルダーナー藩王国に仕えたヨーロッパ人の中には逆にイスラーム教に改宗する者もおり、ファラスーのように、ヨーロッパ人でありながら一流のウルドゥー詩人に数えられるまでになった変り種の人物も登場した。
ベーガム・サムルーは夫の死後、一時の恋に身を任せ、命を失いかけたことがあった。ベーガム・サムルーが夫を亡くしたときにはまだ20代で、若さの盛りであった。ベーガム・サムルーの軍隊の中では、彼女の心を射止めようと多くの仕官がつばぜり合いをしていた。その中でももっとも彼女に近い存在だったのがアイルランド人のジョージ・トーマスであった。ところが、1790年頃にル・ヴェソという若くてハンサムなフランス人が入隊した。たちまちベーガム・サムルーは彼と恋仲になった。2人は1793年に結婚もしたと言われているがはっきりしない。だが、ル・ヴェソに対するベーガム・サムルーの寵愛によって軍隊内の規律は乱れ、反抗の動きが次第に高まった。ジョージ・トーマスもベーガム・サムルーの軍隊を去ってしまう。ベーガム・サムルーの息子ザファル・カーンも母親の恋愛を好まず、反乱を起こして全権を掌握することを画策する。その動きを察知したベーガム・サムルーは、全てを投げ出し、ル・ヴェソと愛の逃避行をすることを決断する。ところが、2人は追っ手に迫られ、絶体絶命の危機に陥る。もはやこれまでと観念したベーガム・サムルーは短剣で自分の胸を刺し、ル・ヴェソも拳銃で自分の頭を打ち抜く。ル・ヴェソの方は即死したが、ベーガム・サムルーの傷は致命傷ではなく、生き延びた。だが、自軍の反乱分子によって捕まり、サルダナーへ連れ戻される。ベーガム・サムルーは砲台に括り付けられ、7日の間、炎天下飲まず食わずで放置される。だが、その虐待の様子を伝え聞いたジョージ・トーマスはベーガム・サムルーを救出し、ザファル・カーン率いる反乱分子を打ち負かして、彼を幽閉する。こうしてベーガム・サムルーは再び軍団の指揮権を取り戻した。彼女はこのことがあって以来、決して恋愛に身を任せないことを決心し、サルダナー藩王国の繁栄に全力を傾けるようになった。彼女は特に農業に力を入れ、サルダナーの農業生産力を北インド有数のレベルまで高めた。
ベーガム・サムルーは優れた外交センスも持っていた。19世紀初頭のデリーの事実上の支配者はマラーターであったが、彼女は英国の優位性を敏感に感じ取っていた。彼女はマラーターと英国の両方とコンタクトを取りつつ、状況を伺った。1803年にパトパルガンジの戦いが勃発し、英国軍とマラーター軍が激突したが、このとき彼女は勝者である英国の側にいた。以後、ベーガム・サムルーは英国人からも一目置かれた存在となる。
1806年にシャー・アーラム2世は死去し、息子のアクバル・シャー2世がムガル皇帝に即位した。アクバル・シャー2世は父親と同様にベーガム・サムルーを尊敬しており、即位を記念し、彼女にチャーンドニー・チャウクの一等地にある庭園を与えた。ベーガム・サムルーは1823年にその庭園に宮殿を建造した。それが現在バギーラト・パレスと呼ばれる建物である。地元ではチューリーワーリー・キ・ハヴェーリー(腕輪の女性の邸宅)と呼ばれているようだ。チューリーワーリーとは踊り子を暗示する言葉である。おそらくそれは、ベーガム・サムルーの過去と関係しているのだろう。

邸宅のベランダ
ベーガム・サムルーは1837年に死去した。サルダナー藩王国は英国に接収されたが、邸宅を含む彼女の莫大な財産は主に養子のデーヴィッド・オクタロニー・ダイス・ソンブルが相続した。ダイスは1842年に英国に移住し、1847年にチャーンドニー・チャウクの邸宅をデリー銀行に売却した。デリー銀行は1850年に正式に営業を開始し、ベーガム・サムルーの邸宅は銀行頭取の住居となった。1857年のインド大反乱で邸宅は多大なダメージを被るものの改修され、1859年からデリー銀行のオフィスがこの邸宅に移された。以後、この建物は銀行として利用され続け、帝国銀行やロイズ銀行などがここにオフィスを構えた。今でも建物の正面にロイド銀行の文字を確認することが出来る。前述の通り、現在ではインド中央銀行のオフィスとなっている。

上にロイズ銀行の文字が見える
邸宅周辺にはかつて庭園が広がっていたが、時代の変遷と共に市場に変わってしまった。邸宅とラール・キラーの間には、ラージパト・ラーイ・マーケットという電化製品の市場があるが、ここは元々サッカー場だった。1947年の印パ分離独立時にデリーに流入したパンジャーブ人難民のためにサッカー場は市場へと姿を変えた。
ベーガム・サムルーはインド大反乱前のデリーの社交界の中心人物であり、この邸宅では毎晩のように豪華絢爛なパーティーが催されたと言う。豊かな領土からは莫大な富がもたらされたため、彼女の生活は贅沢そのものであった。ヨーロッパ人の演奏隊を抱え、美しい馬を揃え、美しい踊り子を養い、最高の訓練を施された軍隊を所有していた。そして彼女の邸宅を訪れる者は、必ず高価な品物をお土産として渡された。ベーガム・サムルーはインドとヨーロッパの両方の習慣を熟知しており、ヨーロッパ人の客には洋食と共にヨーロッパ風の対応をし、インド人の客にはパルダーの習慣(顔を隠す習慣)を守りながらインド風の接客をしたとされている。ベーガム・サムルーが社交界の中心であったと同時に、チャーンドニー・チャウクの彼女の邸宅はシャージャハーナーバードのランドマークとして何十年も君臨した。だが、残念ながら現在の建物からは、当時の栄華を偲ぶことは難しい。インド考古局(ASI)の管理下にも入っていないし、ここまで密集した市場になってしまっては修復も難しそうで、このまま朽ち果てていく運命にあるのだろう。
次の日記では、ベーガム・サムルーの本拠地であるサルダナーへ向かう。
本日の日記は、昨日の日記の続きとなる。
かつてデリーでもっとも豪華かつユニークな存在として名を馳せた女王ベーガム・サムルー。その実像に迫るには、彼女が首都を置いたサルダナーを訪れる必要性を感じた。サルダナーはウッタル・プラデーシュ州のメーラト(英語ではMeerutと書くが、読みはメーラト)のすぐ近くで、デリーからならバイクで日帰り圏内であった。そうとなったら行動は早い。すぐにツーリングの計画を立てた。メーラトまでの道は、かつてリシケーシュやバドリーナートへツーリングに行ったときに通ったので、よく知っている。距離も片道100kmほど、つまり往復200kmぐらいだ。経験上、インドでのツーリングは1日300kmが境目となる。これを越える距離を1日で走ろうとすると、難易度が上がる。200kmは余裕の距離である。また、途中メーラトのバイパス上にカフェ・コーヒー・デーという絶好の休憩スポットもある。国道沿いのダーバー(安食堂)で休憩してもいいのだが、マクドナルド、カフェ・コーヒー・デー、A1プラザなどの大手が経営しているドライブインがあると、冷房が効いていたり、トイレが清潔だったりして、いろいろ都合がいい。つまり、サルダナーはツーリングの目的地としては初心者向けコースである。ちょうどデリー・ツーリング・クラブに新参者(バジャージのパルサー180)が入って来たので、彼にインドでのツーリングの経験を積ませるため、同行してもらうことにした。
午前9時にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を出発。オーロビンド・マールグ、カーン・マーケット、プラーナー・キラーなどを通り過ぎて、リングロードに出た。メーラトへ向かう国道58号線(NH58)は、ヤムナー河の向こう側のガーズィヤーバードから出ている。南デリーからそこまで行くルートはいくつかあるのだが、行きは分かりやすさを重視し、カシュミーリー・ゲート長距離バススタンド(ISBT)のそばから出ている橋を渡ってヤムナー河を越え、東へ向かうことにした。そのままスィーラムプル、シャーダラー、サーヒバーバードを通り抜け、ヒンダン河を越えてすぐの交差点を左に曲がると、そこはもうNH58である。ガーズィヤーバードからメーラトまでの道は市街地が続き、交通量が多いので、快適な道とは言えない。だが、中央分離帯があるために走行は楽な方である。
南デリーから2時間弱でメーラトの入り口に到着した。道はふたつに分かれており、右へ行けばメーラト市街地、左へ行けばバイパスになっている。今回メーラトに用はないので、迷わずバイパスを使う。バイパス上にはカフェ・コーヒー・デーがあり、そこでコーヒーを飲んで休憩した。
カフェ・コーヒー・デーを出ると、すぐに大きな交差点がある。ここを直進し、しばらく行くと、再び大きな交差点に差し掛かる。この交差点を左に曲がって20分ほど走ると、サルダナーの町に到着する。デリーから110kmほどであった。サルダナーは一目でイスラーム教徒の多い町であることが分かった。だが、サルダナーの名を有名にしているのは、ベーガム・サムルーが建造した教会である。教会までの道筋は多少複雑なので、道を聞きつつ行った方がいいだろう。「チャーチ」と言えば誰でも分かってくれる。正式名称は「Our
Ladys of Graces Basilica Shrine Sardhana」と言う。ここでは便宜的にサルダナー聖堂と訳しておく。

サルダナー聖堂
この教会の設計者はイタリア人のアントニー・レゲリーニという人物で、その建築はバロック様式とムガル様式の折衷となっている。建設時期については諸説がある。教会の入り口の碑文には1822年という数字が見られるが、これが完成の年なのか建築開始の年なのかははっきりしない。また、いくつかの証拠から1825年になっても教会は完成していなかったことが分かっており、完成は1820年代としておくのが妥当だろう。碑文によれば、1957年11月7日に「The
Shrine of Our Lady of Graces」つまり「聖母マリアの巡礼地」としての称号を受け、1961年12月19日にローマ法王から「Basilica」つまり「聖堂」の称号を受けたようだ。カトリックでは、聖堂を称することを許されるのは、歴史的に重要かつ美しい教会に限られるようで、北インドで「Basilica」と付く教会は稀である。

正面
サルダナー聖堂は観光地となっており、中を見学するには1ルピーのチケットを買わなければならない。だが、チケット売り場の人は僕たちの顔を見てノースイースト人だと思ったようで、「お祈りに来たなら入場料は要らない」と言った。1ルピーをケチるのも嫌なので、「お祈りもするけど、はっきり言って見学に来たんだよ」と入場料を支払おうとしたが、「いいからいいから」と言ってチケットを売ってくれなかった。

祭壇
教会はインドの寺院やモスクと同様に靴を脱いで入るようになっていた。神父さんらしき人が入り口にいて、「チケットはどうした?」と言うので、「チケット売り場の人が、お祈りに来た人はチケットはいらないと言って売ってくれなかった。必要なら買って来る」と答えたら、「まあいい」と言われた。だが、後から「君たちを見ていると観光客と変わらない」と愚痴を言われ続けたので、いっそのことチケットを買っておけばよかったと思った。キリスト教徒でない人は素直に1ルピーを支払って見学した方がいいのかもしれない。

ホール
祭壇の左側には、ベーガム・サムルーの墓もある。元々彼女の遺体は付属礼拝堂に安置されていたが、養子のデーヴィッド・オクタロニー・ダイス・ソンブルがイタリアで発注した大理石製の墓石が届いた1870年に、現在の位置に移された。この墓石はイタリア人彫刻家アダモ・タドリーニが彫ったもので、上部にはベーガム・サムルーの彫刻もある。中央部には4体の大きな彫像が彫られているが、正面向かって左側の人物がデーヴィッド・オクタロニー・ダイス・ソンブルである。右側の人物は、ベーガム・サムルーの大臣ディーワン・ラーイ・スィンである。どうもモーティーラール・ネルーの母方の曽祖父に当たる人物のようである。

ベーガム・サムルーの墓
この教会で興味深かったのは、ペルシア語の詩やウルドゥー語の碑文が見受けられたことだ。宗教と文字は基本的には関係がないとは理解しながらも、どうしてもインドにいると、デーヴナーグリー文字=ヒンドゥー教、アラビア・ペルシア文字=イスラーム教、グルムキー文字=スィク教、ラテン文字≒キリスト教という構図が頭にこびりつく。だから教会にアラビア・ペルシア文字の碑文があると異様な印象を受けてしまう。だが、19世紀前半という時代背景と、ベーガム・サムルーの人生を見てみれば、それは当然のことなのだろう。

ペルシア語の詩(上)やウルドゥー語の碑文(下)
サルダナーにはベーガム・サムルー関係の見所がいくつか残っているが、サルダナー聖堂の他に見応えがあるのは、ベーガム・サムルーの宮殿である。現在宮殿はセント・チャールズ・インター・カレッジという学校の校舎となっている。サルダナー聖堂から西へちょっと行った場所にある。門をくぐり、大きな運動場のそばの道を通ると、左手に美しい建物が見えて来る。だが、こちらからだと裏側である。正面に回るとその素晴らしさがよりはっきりと分かる。

ベーガム・サムルーの宮殿
この宮殿の設計者も、サルダナー聖堂を設計したイタリア人建築家アントニー・レゲリーニである。教会完成後に建設に着手したとされ、1833年に完成した。パヴァンKヴァルマー&ソンディープ・シャンカル著「Haveli
of Old Delhi」には、「デリーの邸宅はサルダナーの宮殿をモデルに建造された」と書かれているが、デリーの邸宅の完成が1823年であることを考えると、その記述は誤りである。その保存状態は比べるまでもないが、サルダナーの宮殿の方がより洗練されているように感じる。

正面
日曜日だったので学校は休みで、建物の鍵は全て閉まっていた。だが、平日に来ればもしかしたら中も見学させてもらえるかもしれない。

ベランダ
ちなみに、サルダナー聖堂の売店で、ベーガム・サムルーの生涯やサルダナーの見所についてかなりよくまとめられた小冊子が売られている(英語版とヒンディー語版あり。値段は10ルピー)。これをじっくり読めばサルダナーの見所を余すところなく観光できるだろう。
サルダナー観光を終えて帰路に着いたのは午後1時半頃。午後2時過ぎにメーラト・バイパス上のカフェ・コーヒー・デーの隣にあるレストラン・チェーンのナトゥースで昼食を食べて休憩し、デリーには午後4時半時までに到着した。思っていた通り、とても簡単なツーリングであった。サルダナーは、デリー周辺の日帰り観光地としてオススメのスポットである。ベーガム・サムルーによってデリーと少なからず関係を持つ場所でもあるため、デリー在住者にとって特に魅力的な場所になりうるだろう。
| ◆ |
3月7日(金) 恐怖のバーンガル・ツーリング1日目 |
◆ |

Q.日没後にバーンガルへ行ったことのある人はいますか?
A.こんにちは、皆さん。この質問に答えさせて下さい。私は一度バーンガルへ行ったことのある幸運な人間の1人です。しかし、不幸にも私たちは日の出の数時間後に現地に到着しました。私は自分の体験談を皆さんに話したいと思います。私は5人の親しい友人たちとそこへ行きました。私の名前はマニーシュ・デーヴです。私はそこへ、ジャスミート、彼の妻のネーハー、ハールディク、シシル、クナールと共に行きました。私たちはグルガーオンのビジネスプロセス・アウトソーシング(BPO)企業インフォヴィジョンに務めていました。私たちは皆、アドベンチャー・スポーツが大好きです。ある日ジャスミートがネット上でバーンガルのことを見つけ、数分後に私たちは、その気味の悪い場所へ日没後に行くことを決めました。日曜日は休日だったため、私たちは土曜日の夜に出発しました。バーンガルへ行く間、私たちは異常な出来事を体験しました。まず、私たちはガス欠になってしまいました。そして私たちは2台の車で移動していましたが、途中で道に迷ってしまいました。さらに私は命の危険にもさらされました。車が谷へ落ちそうになったのです。そうこうしている内に不幸にも日が昇ってしまいました。適切な時間に到着することができなかったため、私たちの冒険は台無しになってしまいました。それでも旅行を続けることを決めました。バーンガルの廃墟に入ると、私たちは皆、言葉では言い表せないような異様な雰囲気を感じました。体験したことのひとつひとつは一生忘れないでしょう。私たちは今ではバラバラになってしまい、違う組織で働いていますが、今でも私たちはバーンガル旅行のことをよく話しています。
ジャイプルとアルワルの間に位置する廃墟の町バーンガル。知る人ぞ知る、北インド随一のオカルトスポットである。呪われた町と言われており、ここで一夜を過ごした者は二度と帰って来ないと専らの噂である。遺跡なのでインド考古局(ASI)の管理下に入っており、宿直する管理人が置かれているが、呪いを避けるため、管理室は遺跡の外に置かれている。ASIの規定では管理室は遺跡内に作られなければならないことになっており、これは異例の処置のようである。
バーンガルには先史時代から集落があったようだが、現存している廃墟の町は1574年に建造されたとされている。建造者は、マハーラージャー・バグワーン・ダースジーとも、ラージャー・マドー・スィンとも言われている。バーンガルが呪われた理由を説明する伝説にはいくつかの種類があるが、筋が通るように勝手にまとめると以下のような流れになる。
バーンガル王国のラトナーワティー姫は絶世の美女として知られていた。18歳になった彼女のもとにはインド中の王子たちから結婚の申し込みが殺到した。スィンド王国のスィンギヤー王子も、ラトナーワティーの美しさに正気を失った者の1人だった。しかし、スィンギヤーの申し込みはあえなく断られてしまった。そこでスィンギヤーは王国を飛び出し、何としてでも姫を手に入れるため、黒魔法の修行をし始めた。邪悪な黒魔法を習得すると、彼は身分を隠してバーンガル王国に忍び込み、黒魔術師として王宮に登用された。だが、ラトナーワティー姫はスィンギヤーの邪悪な心に気付いていた。
ある日、スィンギヤーは市場でラトナーワティー姫の侍女が姫のために香水の買い物をしているのを見つけた。これは好機とばかりにスィンギヤーは香水に黒魔法をかけた。呪文を込められたその香水に触れた者は催眠術にかかり、即座に彼のもとへやって来て体を差し出すのであった。だが、不審に思ったラトナーワティー姫はその香水を石にぶつけて壊してしまった。するとその香水に触れた石は動き出し、スィンギヤーの方へ向かって突進し始めた。スィンギヤーはその石に潰されて死んでしまった。
だが、スィンギヤーは死ぬ直前にバーンガル全体に呪いをかけた。宮殿に住む者全てが死に絶えるように、そして彼らの魂が輪廻転生せずに何百年もそこに留まるように。バーンガルには誰も住む者がいなくなるように、そしてバーンガルに住もうとする者は死ぬように。寺院以外、全ての建物の屋根は崩壊するように。
その後、バーンガルの人々は、呪いを恐れて一晩の内に引っ越したとも、近接した王国アジャブガルとの戦争に負けて皆殺しにされたとも言われている。
こうしてバーンガルは、誰も近寄らない廃墟となって現在でも残っているのである。
その他、バーンガルは黒魔術の中心地として栄えたが、黒魔術師同士の黒魔術合戦の末に人間の住めない場所になってしまったという言い伝えもある。とにかく遺跡を盛り上げるマサーラーには事欠かない場所のようである。いつか訪れてみようと思っていた。
バーンガル(Bhangarh)はEICHER「Road Atlas India」やLonely Planet「India & Bangladesh
Road Atlas」などのメジャーな地図には載っていなかったが、バーンガルの近くにあるというアジャブガル(Ajabgarh)の方は掲載されており、大体の位置は掴むことができた。デリーから日帰りだと苦しい距離にあるので、1泊2日または2泊3日の日程で行く計画を立てた。宿泊拠点としてもっとも便利なのは、有名ホテルチェーン、アマングループのアマンバーグ(Amanbagh)である。アマンバーグはアジャブガルの郊外に位置しており、バーンガル観光には理想的な立地である。アジャブガル自体にも古い城が残っている。だが、高級リゾートなだけあって貧乏学生には手が出せない宿泊料だ。それに代わる宿泊拠点を探すと、ちょっと離れてはいるものの、サリスカー(Sariska)のタイガー・デン(Tiger
Den)がなかなかいい位置にある。ラージャスターン州観光局経営のこのホテルは、サリスカー虎保護区のサファリ・ベースとして利用する人がほとんどだが、周辺には密かな見所が多く、それ以外にも利用価値のあるホテルである。既に2回訪れたことがあり、場所や設備は熟知していた。宿泊料も、年々値上がりしているものの、何とか手の届く範囲内である。そこで、タイガー・デンを拠点にバーンガルなどをバイクで観光することにした。デリー・ツーリング・クラブのメンバーと相談して日程を決めた。現在クラブのメンバー数は5人で、できたら5人全員で行きたかった。
バーンガルは数々の怪奇現象を巻き起こす場所のようなので、現地でメンバーの1人や2人は神隠しに遭うかと思っていたが、バーンガルの呪いの威力は予想を超えるすさまじさで、出発前からメンバーが消滅するという事態に陥った。数々のやむをえない事情により、2人のメンバーが参加できないことになったのである。よって、バーンガル・ツーリングの参加メンバーは、アルカカット(ヒーロー・ホンダのカリズマ)、新デリー☆OK牧場(旧チベOK)の牧場主さん(ヒーロー・ホンダのCD-Dawn)、インド1年目新入りの大将さん(バジャージのパルサー180)となった。全員ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の日本人留学生である。また、日程は余裕を持って2泊3日となった。3月7日(金)正午出発、3月9日(日)帰宅である。
本当はタイガー・デンに2泊できれば楽だったのだが、あいにく8日(土)は予約がいっぱいだった。調べてみたら、その日は蒸気機関車フェアリー・クィーン号ツアーが入っていた。フェアリー・クィーン号の詳細については2006年11月26日の日記をご覧いただきたい。一方、7日(金)は空き部屋があった。そこで、1泊目はサリスカーのタイガー・デンに宿泊し、2泊目はアルワルまで戻って泊まることにした。念には念を入れて、デリーのラージャスターン州観光局(ビーカーネール・ハウス)でタイガー・デンの予約をしておいた。アルワルにはたくさんホテルがあるので予約をしなくても問題ないが、サリスカーはタイガー・デンぐらいしか泊まれる場所がないので、予約をしておいた方が安心である。
3月7日(金)の午後1時40分頃にJNUキャンパスを出発。ヴァサント・クンジを抜けて、デリーとジャイプルを結ぶ国道8号線(NH8)に乗った。デリー・グルガーオン・エクスプレス・ハイウェイに料金所が設置されてから初めてこの道を通った。バイクも通行料金を徴収されるかと思ったが、無料であった。ただし、エクスプレス・ハイウェイのあちこちにはバイク通行禁止を知らせる標識が立っていた。どうもいつの間にかエクスプレス・ハイウェイはバイクの通行ができなくなったようだ。だが、余裕でバイクが走っていたし、誰にも何も言われなかったので、そのままエクスプレス・ハイウェイを走行した。しかし、将来的には完全にバイクが締め出されるかもしれない。そうなるとジャイプル方面へのツーリングは多少不便になりそうだ。一応エクスプレス・ハイウェイの脇に下道があるが、こちらの道ではスピードが出せず、大幅なタイムロスになる。
マーネーサルには午後2時40分頃に到着。ここのマクドナルドで昼食を食べた。午後3時にはマクドナルドを出て、ひたすらNH8を南下。ダールヘーラーでNH8を降りて東へ向かい、町の外れで南に折れて、アルワルへ続く道に乗った。また、今までデリー、ハリヤーナー州を通り抜けて来たが、ダールヘーラーを過ぎるとラージャスターン州になる。この辺りの風景は農村と畑に囲まれており、とてものどかだ。交通量も少なく、道もきれいに舗装されており、快適な走行ができる。デリー周辺のツーリング・ルートの中ではもっとも爽快な道と言える。次第に道往くラクダ車の数も増え、アラーヴァリー山脈のいかつい山々が見えて来る。グジャラート地方から端を発するアラーヴァリー山脈は、インド亜大陸がまだゴンドワナ大陸の一部だった時代、大陸の背骨となっていた山脈と言われる。ステゴザウルスの背中のような険しい山々が連なる姿は、とてもダイナミックでかっこいい。「竜の山脈」と名付けたくなる。このアラーヴァリー山脈の最北端、ヤムナー河にぶつかる地点にデリーがある。デリー市民にとっても心の山である。

アラーヴァリー山脈
デリーからアルワルまでの道は何度も通ったことがあるため、何の問題もなくアルワルに到着した。時計は午後5時を回っていた。そのまま市街地を一直線に突っ切ると、モーティー・ドゥーンガリーと呼ばれる巨大な城砦跡に出る。モーティー・ドゥーンガリーを越えてしばらく進むと、道は二手に分かれる。直進するとラージガルへ、右手の坂道を上って行くとサリスカーへ通じる道である。サリスカー行きの道へ針路を取って峠を越えると、道は途端に悪くなり、穴ぼこだらけになる。だが、一応舗装道なのでインドの道の中では最低ランクには入らない。サリスカーまでは35kmほどだが、マーネーサルのマクドナルドを出てから2時間以上経っていたため、一度ダーバー(安食堂)で休憩を取った。既に日はアラーヴァリー山脈の裏に隠れており、夕闇が迫っていた。インドの道路は夜になると危険度が格段に上がるため、暗くなるまでのホテル到着をツーリングの鉄則としている。ジャヤンティーというラージャスターン州特有の炭酸飲料を飲んで身体を簡単に休めた後、すぐに出発した。
サリスカーのタイガー・デンには午後6時半頃に到着した。予約を入れていたため、スムーズにチェックインすることができた。ちなみに料金は、ダブルルーム(エアコンなし)1泊1,075ルピー、エキストラベッド300ルピーである。部屋の設備はインドの中級ホテルのレベルに十分達しており、しかも広いため、快適である。ホテルの敷地内に気持ちのいい芝生があるのもよい。虎保護区の森林の中にあるホテルなので、周囲の環境も抜群である。密猟者の暗躍によってサリスカー虎保護区から虎は全くいなくなってしまったが、動物たちの楽園であることには変わりがなく、いろいろな動物と間近で遭遇するチャンスのある場所だ。最も間近なのは悪戯好きな猿だが・・・。
本日の走行距離は190.8km。
| ◆ |
3月8日(土) 恐怖のバーンガル・ツーリング2日目 |
◆ |
ホテルの周辺を散策し、朝食を食べ、チェックアウトし、午前9時にホテルを出発した。今日の第一目的地はバーンガルである。
サリスカーから西へ向かうと、すぐにターナー・ガーズィーという町に出る。崩れかけの古城に見下ろされた町なのですぐに分かる。このターナー・ガーズィーで道は二手に分かれる。右へ行くとNH8に通じ、左へ行くとアジャブガルに通じている。バーンガルがアジャブガルのさらに先にあることは事前に把握していたため、アジャブガル方面へ向かった。ここからは一車線のみの農道となる。だが、交通量が少ない上に道が意外にきれいに舗装されており、走行には問題がなかった。ただ、途中いくつかの農村があるのだが、村ごとに分かれ道があったりするので、ちゃんと方向を確かめながら進む必要がある。ヒンディー語のみではあるが、分岐点には道標が立っていたため、人に道を尋ねながら行く必要はなかった。
午前10時頃にアジャブガルに到着した。アジャブガル村の入り口には古い門や城壁ががあり、趣がある。アジャブガルの道は工事が行われており、迂回をしなければならなかったが、特に問題はなかった。村を抜けると右手の山の上に城砦が見えた。また、左手には広大な農地が広がり、所々に雰囲気のいいチャトリー(東屋)が立っていた。この農地はかつて貯水湖だったと思われる。下流にはダムもあった。非常に豊かかつ歴史のある村であることが伺われた。とりあえずアジャブガルの観光は後回しにし、バーンガルに向かった。

アジャブガルの入り口の城壁
アジャブガルを抜けてしばらく一本道を進むと、やがて三叉路に出る。ここを右に曲がると道は二車線の舗装道となる。さらに道なりに進んで行くと、やがて遠くに遺跡らしきものが見え始める。しばらくすると右へ折れる道がある。そこには一応ヒンディー語で「→バーンガル」と書かれている。それに従って進んで行くと、すぐに正面にバーンガルの遺跡が見えて来る。遂に憧れのバーンガルを発見することができた。午前10時20分頃であった。
以前、ジャイサルメール周辺の砂漠で捨て去られた村を見たことがあり、てっきりバーンガルもそのような種類の遺跡だと思っていた。人影ひとつなく、聞こえるのは風の音のみ、朽ちるに任せられた住居が物寂しげに並ぶ様子を勝手に想像していた。だが、まずバーンガルで目に飛び込んで来たのは、駐車場に並ぶ数台のバイク、自転車、自動車と、鉄格子がはめられた門をくぐる多数の人間の姿であった。最初はだいぶ観光地としてメジャーになってしまったのかと思ったが、すぐに来訪者のほとんどは地元の人間であることが分かった。バーンガルの中にはいくつか寺院があり、彼らの多くは参拝に来る人々であった。また、貯水池もあり、そこで泳いだり洗濯したりしている人もいた。もちろん観光客もいたが、どちらかと言うと地元の人々の憩いの場となっていた。ちなみに入場料は無料であった。

バーンガルの入り口
そんな訳で若干拍子抜けしたが、それでもかなり壮大な遺跡であることが見て取れたため、胸が高鳴った。門をくぐり、石畳の道に従って奥へ向かった。

門をくぐると石畳の道が続く
まずは基部しか残っていない住居跡が残っていた。そしてしばらくすると、小さな建物が密集する通りが現れる。市場跡と思われる。こちらは壁も残っていたが、どの建物にも屋根はない。寺院以外の建物の屋根は崩壊するという呪いのためだろうか。このバーザールの一角に香水屋があり、ラトナーワティー姫の侍女は香水を買ったのだろうか。

市場跡か
ある資料には、黒魔術師は山の上にある小屋に住んでいたと書かれていた。確かに山の上に小屋が今でも建っていたが、どう見ても見張り小屋にしか見えなかった。だが、とても見晴らしがいいため、市場の様子も丸見えであろう。そこから市場で侍女が買った香水に呪いをかけたと考えると、物語としてはとても面白そうだ。

崩れたアーチの先の山の頂上に小屋が見える
市場を越えると、樹木と遺跡が一体と化している部分があり、カンボジアのアンコール・ワットを思い出した。この辺りは猿の溜まり場にもなっていた。そしてその先には三連アーチの立派な門が見え始めた。

三連アーチ門前
三連アーチ門をくぐると、その先は緑の芝生が広がる心地の良い公園となっていた。敷地内にいくつか建物が建っていたが、目立つのは2つの寺院であった。他の建物は全て屋根が崩壊してしまっているのに、寺院だけはほぼ完全な形で残っている。あの呪いのせいであろうか?この広場には宗教に関連する施設が多いので、便宜的に寺院コンプレックスとでも呼んでおこう。そしてこの寺院コンプレックスの奥の山の斜面に、王宮と思われる壮大な遺跡がそびえ立っていた。

宮殿
いろいろ見てみたい建物が盛りだくさんだったが、とりあえず王宮へ向かった。王宮の門をくぐってジグザグの坂道を登ると、第二の門があり、それをくぐると本格的に王宮に入ることになった。ガイドなど全くいなかったので各部屋の詳細は不明だが、ザナーナー(女性居住区域)と思われる部分は大理石でできており、ハンマーム(浴場)らしきものが残っていた。王宮の中心部には寺院があったが、こちらは大部分が崩壊してしまっていた。また、王宮の地面には水路が巡らされているのが分かった。一部では壁画の残っているところもあった。

宮殿の細部
最近、インドの遺跡は整備が進んでおり、久し振りに訪れると見違えるほど立派に修復されたものが少なくない。バーンガルの遺跡も修復が行われた形跡があったが、まだ完成はしていないようで、あちこちに瓦礫が散らばっていた。中にはけっこう考古学的な価値があるのではないかと思われる彫刻の入った瓦礫もあった。かつてのインドの遺跡はどこもこんな感じでほとんどほったらかし状態だった。だが、いざ整備が進むと、やけにほったらかし状態の遺跡が恋しくなるものだ。バーンガルの遺跡にはまだ、古き良きインドの遺跡の雰囲気が感じられた。古き良きインドの遺跡・・・その言葉を聞くと必ず嗅覚が刺激される。そう、あのコウモリの尿の匂いである・・・。昔はアーグラー城も、アジャンター石窟寺院群も、コウモリの尿の匂いが充満していたものだ。だが、いつの間にか遺跡を巣窟とするコウモリたちは締め出され、あの匂いを嗅ぐ機会はほとんどなくなってしまった。バーンガルの遺跡では、その懐かしい匂いを嗅ぐことができた。無論、単体では気持ちのいい匂いではないのだが、若かりし頃の思い出が混じると、不思議と陶酔感が沸き起こる。この匂いを嗅ぐと、遺跡に「こんな辺鄙なところまで来てくれてありがとう」とお礼を言われているような気分になるのである・・・。

まだ修復は不完全
また、最近のメジャーな遺跡の多くは観光客の立ち入れるエリアが制限されている。かつて余裕で行けた場所が、今では鉄格子や扉が設置され、行けなくなっているということはよくある。その理由は、崩壊や落下の恐れがあって危険だからとか、遺跡の劣化を防ぐためとかだと思うが、かつて行けた場所に行けず、かつて撮れた写真が撮れず、かつて体験できた冒険が体験できなくなっているのを知ると、せっかくの再訪も損した気分になるものである。だが、バーンガルではまだそこまでASIの手が及んでおらず、どこまでも自己責任で行くことができた。もちろん、王宮の屋上にも上ることができた。そこからの眺めは当然のことながら絶景であった。次にここに来たときには、もう上れなくなっているかもしれない・・・。

王宮屋上からの風景
屋上から見下ろすとバーンガルの町の構造がよく理解できた。バーンガルは、山と山に挟まれた扇形の平地に築かれた城砦都市で、二重の城壁に守られている。外側の城壁は左側と右側の山の裾野を結ぶように大きく巡らされており、その内側に市民の居住区と思われる地域が広がっている。内側の城壁も山と山を結ぶように築かれており、その内側に寺院コンプレックスが広がっている。そして一番奥の山の斜面に王宮が建造されている。正面からの攻撃にはある程度持ちこたえられそうだが、裏山から奇襲されると一気に王宮を攻め落とされそうな気がする。

屋上ではないが、王宮からの俯瞰図
王宮内の一角には祠のようなものがあり、地元の人々の信仰対象となっていた。壁の凹みを神様に見立てたりしていた。デリーのフィーローズ・シャー・コートラーのジン(精霊)信仰と似た信仰の仕方であるように感じた。どちらかというと、バーンガルが廃墟になった後、誰かが思い付いて始めたような祠である。だが、もしかしたらバーンガルを呪いで滅ぼした黒魔術師と何か関連があるのかもしれない。祠の周辺では、おじいさんやおじさんがチラム(煙管)を吸ってまったりしていた。

祠
王宮を一通り見て回った後は、寺院コンプレックスにある寺院を簡単に見学した。この広場には宗教施設と思われる建築物がいくつか建っているが、完全に原型を留めているのは2つの寺院のみである。王宮側にある寺院は、緑色の沐浴池に隣接しており、人々が気持ち良さそうに水浴びをしたり洗濯をしたりしていた。ホールにはナンディー像が置かれ、聖室には大理石製のシヴァリンガが祀られていたため、シヴァ寺院である。だが、パンディト(僧侶)らしき人は見当たらなかった。

シヴァ寺院
シヴァ寺院からは沐浴池を挟んでもうひとつの寺院がよく見えた。

シヴァ寺院からの風景
次に、もうひとつの寺院を見てみた。こちらは聖室にご神体が存在しない。どうも盗まれてしまったようだ。だが、彫刻などからこちらもシヴァ寺院であることが予想できた。こちらの方が繊細な彫刻が見られた。

ガランドウの聖室
呪われたゴーストタウンとして僕の想像を掻き立ててやまなかったバーンガル。だが、実際に訪れてみた結果、むしろとても心地のいい遺跡だという感想を抱いた。寺院コンプレックスは公園と表現しても差し支えないし、王宮の上から眺める風景は絶景であるし、その気になればシヴァ寺院のそばにある沐浴池で泳ぐこともできる。樹木が遺跡に絡みつく様子からは、「インドのアンコール・ワット」と愛称を与えてもいい。昨日の日記の冒頭で、ネットで発見したQ&Aを転載したが(オリジナルは既に消滅)、彼らはバーンガルの遺跡から異様な雰囲気を感じたと語っていた。しかし、彼らは廃墟そのものに異様さを感じ取っているだけなのではないかと思う。このような廃墟の遺跡はインドには他にいくらでもあり、それらをいくつか見ていれば特に異様な感じはしないだろう。もっとも、僕たちは昼間に訪れただけで、これだけの体験で伝説を笑い飛ばすのはフェアではない。日没後、この遺跡がどんな雰囲気になるのかは全く予想が付かない。もしかしたら幽霊の晩餐会みたいなすごいことになっているかもしれない。

遺跡を呑み込む樹木
だが、城塞跡や都市跡の廃墟に幽霊や呪いの伝説が生まれるのは、盗難盗掘防止と関係がありそうだ。どこの国にも、本当か嘘か分からない埋蔵金を目当てにしたトレジャー・ハンターがいるもので、彼らは真夜中に遺跡のいろいろな場所を掘り起こしては遺跡を破壊する。それを防ぐために、近隣の村人たちは幽霊や呪いの伝説をでっち上げて広め、侵入者の防止に努めたのではないかと思われる。住民が一晩の内にいなくなった都市や村というのも、戦争の他、自然災害や疫病の流行などで説明が付きそうだ。ただ、寺院だけ屋根が崩壊せずに残っているという事実だけは何とも科学的解釈が思い付かない。しかし、総じてバーンガルは、呪いや祟りとは無縁の爽快な遺跡だと言うことができる。

屋根のない家屋
バーンガルの周辺には、小さな遺跡がいくつか散在していた。一番目立ったのは大理石製のチャトリーであった。何のために建てられたのか分からないが、今では周辺の村人たちの涼み場所となっていた。我々はバーンガル観光に2時間ほど時間を費やしたが、ここだけで1日を費やしても十分楽しい場所だと思った。ただし周辺に昼食が取れる場所はなさそうなので、弁当持参が望ましい。だが、食べ物を持っていると遺跡に住み着いている猿たちから集中攻撃を喰らうかもしれない。

チャトリー
正午12時にバーンガルを出発し、来た道を戻って今度はアジャブガルを観光した。アジャブガルに到着したのは12時15分頃であった。アジャブガルも寺院やチャトリーなど大小の遺跡が点在する村だが、メインとなるのは山の中腹にそびえ立つ砦であろう。四方を小塔で囲まれた正方形の城塞である。

アジャブガルの砦
全く整備されていない石だらけの道を登って行くと、砦の門に辿り着く。一瞬、扉が閉まっているように見えたが、幸運なことに、紐で縛ってあるだけだった。紐を解いたら中に入ることができた。多分管理人がいるのだろうが、我々が訪れたときには中に誰もいなかった。中心部には貯水タンクがあり、城壁が四方を取り囲んでいた。谷側の壁には大理石の柱が埋め込まれており、彫刻はなかなか保存状態がよかった。窓からはアジャブガルの村を一望の下にすることができた。

砦の内部
アジャブガルの砦を見終わって麓に下りて来たときには既に午後1時になっていた。先を急ぎたい気持ちもあったが、バーンガルとアジャブガルの観光を連続でこなして身体が火照っていたので、ここらでコールドドリンクをグイッと飲みたい気分であった。しかしここは辺鄙な場所にある村。冷蔵庫でキンキンに冷やした飲み物がそう簡単に手に入るとは思えなかった。ところが、駄目元で聞いてみたアジャブガルの市場の食堂に、冷蔵庫で冷やした各種コールドドリンクが取り揃えられていた。こんなところにもコールドドリンクがあるとは・・・。インドの経済発展の影響が田舎まで行き渡りつつあるのを感じた瞬間だった。文明の浸透は、ツーリング時にはとてもありがたいものである。
アジャブガルの食堂ではやっと昼食の準備が始まったぐらいでまだ時間がかかりそうだったので、ここで昼食を食べるのはやめにして、先に進んで途中で適当なダーバーを見つけ次第そこで昼食休憩を取ることにした。ターナー・ガーズィー辺りまで行けば何かあるだろうと漠然と考えていた。だが、ここからが今回のツーリングの本当の山場であった・・・。
午後1時半頃にアジャブガルを出て、2時ぐらいにはターナー・ガーズィーに到着できるだろうと考えながら走行していたところ、突然トラブル発生。大将さんのパルサーの後輪がパンクしてしまったのである。よりによってこんなところでパンク・・・。周囲を見渡しても畑が広がるだけで、パンク修理屋のようなものは見当たらない。下手すると20km先のターナー・ガーズィーまでバイクを押して行かなければならなくなるかもしれない。大幅な旅程変更を余儀なくされそうだった。だが、インドの「必要な場所に必要なものがある」はこんなところでも健在であった。パルサーがパンクした地点から2,3km先のビーカムプル村にパンク修理屋があったのである。修理工もテキパキと仕事をしてくれた。驚いたのはその応用力の高さ。今回のパルサーのパンクは、パンクの中でもかなり深刻な部類に入っていた。チューブに穴が空いていた他、プラグが破損していたのである。本当ならばチューブを交換しなければならなかった。だが、さすがにこのような辺鄙な村ではチューブの在庫はなかった。もし応用力がなかったらチューブの手に入るところまで買出しに行く必要があったところだが、彼はチューブに空いた穴を補修した他、手元にあった別のプラグ(バイク用のものではない)をチューブに接着して応急処置をしてくれた。これでしばらくは持つだろうとのことであった。実際、今日1日パルサーは問題なく走行することができた。
こんなこともあり、ターナー・ガーズィーに到着したときには予定より1時間遅れの午後3時頃であった。昼食の食べれそうな場所を探したが、いい雰囲気の場所は見つからなかった。仕方ないので冷たいミネラルウォーターを買って、牧場主さんが持参したクッキーを食べて空腹を満たした。
今日はもう1ヶ所行きたい場所があった。それはターナー・ガーズィーから西へ20km弱行ったところにあるヴィラートナガル(別名バイラート)である。ヴィラートナガルは古代インドに興隆し、「マハーバーラタ」にも記録されているマツヤ王国の首都があった古い町である。ここには、紀元前3世紀の仏教遺跡が残っている。石窟寺院ではなく、独立して建っている仏教遺跡の中ではインドでもっとも古いものとなるらしい。だが、デリーやジャイプルの近くにありながら、それほど有名ではない。ヴィラートナガルを知ったきっかけはタージマハルであった。タージマハルの内部のトイレの近くには、超メジャーなものから超マイナーなものまで、インド中の遺跡を網羅したパネル展示がしてある(少なくとも僕が最後にタージマハルを訪れた2007年2月まではしてあった)。今までインドのいろいろな遺跡を見て来たつもりだったが、そのパネルを見て、まだまだインドには見なければならないものが多すぎることを思い知らされた。その中にヴィラートナガルの仏教遺跡の写真も展示されていたのである。ほとんど基部しか残っていない寂しい遺跡だったが、きれいな円形をしており、なぜか惹かれるものがあった。バーンガルやアジャブガルと併せて観光できる位置にあったため、今回のツーリングに組み込んだというわけである。
ターナー・ガーズィーの分かれ道を今度は右(西)に向かい、ヴィラートナガルを目指した。途中峠を越したが、それが県境にもなっていたようだ。今までずっとアルワル県を観光して来たが、この先はジャイプル県である。
しかし、ヴィラートナガルに到着する寸前に本日2度目のトラブルに見舞われた。またパンクである。しかもパンクしたのは僕のカリズマの後輪。ツーリング中にパンクしたことなど今まで1度もなかったし、ここ1年以上パンクとは無縁だったので、かなりショックであった。見ると巨大な釘が刺さっていた。安物のチューブは何もしなくても自然に破裂してパンクしてしまうことがあるが、これではどんなに質のいいチューブでもひとたまりもない。峠を越した辺りから何か変だなとは思っていたが、パンクに気付いたのはヴィラートナガルに到着してからだったので、すぐにパンク修理屋を見つけることができた。チューブを抜いて見てみると、釘がブッスリと刺さっただけではなく、先っぽがチューブの数ヶ所を突付いて裂傷のような裂け目を作っていたため、カリズマの場合もチューブ交換が最善の策であった。あまり質の良さそうなチューブではなかったが、修理屋が持っていたものに変えてもらった。これでまた30分ほどタイムロスが生まれ、既に4時になってしまっていた。もし今日中にアルワルへ行こうとすると、明るい内に到着できない可能性が出て来た。
一応、アルワル宿泊予定を変更してNH8上にあるシャープラー辺りでホテルを探して宿泊する代替手段も考えたが、メンバーと相談した結果、ヴィラートナガルを簡単に観光して予定通り急いでアルワルへ向かうことに決まった。
ヴィラートナガルには博物館があるはずで、まずはそこを見学しつつ、周辺の遺跡に詳しそうな人を捉まえて情報収集をしようと思っていた。だが、ヴィラートナガルのメインロード上に博物館の存在を示す看板は、僕が注視していた限りではひとつも見当たらず、博物館を見つけるのに苦労しそうな予感がした。また、僕が尋ねた限りでは博物館の存在を知っている人も皆無だった。だが、予め、ヴィラートナガルの遺跡はビージャク・パハーリーという場所にあることを調べ上げていたため、博物館は諦め、町の人に「ビージャク・パハーリーはどこか?」と聞いてみた。そうしたらこちらは有名のようで、すぐに教えてくれた。アルワル方面からヴィラートナガルへ入ると、町の中を突っ切って、警察の検問を越えた先の左へ曲がる未舗装道が、ビージャク・パハーリーへ通じる道であった。一応ヒンディー語の道標があったのですぐに分かった。このダート道をずっと直進すれば、岩山の麓に着く。そこからは石段が続いていた。バイクを降りて石段を登って行くと、5分ほどで変わった形の石を抱いたハヌマーン寺院がある。仏教遺跡の発掘現場は、ハヌマーン寺院の向かい側の囲いの中である。岩山の上に2段に渡って遺跡が残っている。

ビージャク・パハーリーのハヌマーン寺院
発掘現場の入り口には一応遺跡について解説文の書かれた看板が立っていたが、錆び付いていて解読不可能であった。だが、その看板のすぐ裏に、タージマハルで見た円形の仏教遺跡があった。これはチャイティヤと呼ばれる礼拝堂跡のようである。もしかしたら中心部にストゥーパが建っていたのかもしれない。これこそがインド最古の独立した仏教遺跡である。中心の円の形は歯車のようにも見える。焼きレンガで建造されているのも特徴的である。タージマハルで見た写真はもっと整備されていなかったような気がする。

チャイティヤ跡
このチャイティヤより一段高いところにも遺跡が残っているが、こちらは僧院跡のようである。

僧院跡
また、ここにも奇妙な形の岩を積み重ねたような構造物(?)があった。

巨石文化?
この辺りには、アショーカ王の石柱跡がいくつか残っている他、詔勅文を刻んだ碑文もあるらしい。だが、ガイドもなしに碑文を見つけることは不可能だった。タイムリミットも迫っていたので、後は岩山からの景色を楽しんだだけだった。

チャイティヤ跡で記念撮影
ビージャク・パハーリーで本日の観光の日程を終え、午後5時にアルワルへ向けて出発した。ツーリング時、道の状態や交通量にも寄るが、大まかな目安として、1km=1分という計算が成り立つ。ヴィラートナガルからアルワルまでは60kmほどであり、順調に行けば日没前の6時過ぎにはアルワルに到着するはずだった。だが、本日3度目のトラブルが我々を襲った。またもパンクである。パルサー、カリズマと続けてパンクしたので、次はCD-Dawnの番なんじゃないかと冗談を言い合っていたのだが、まさかのまさか、それが現実のものとなってしまった。しかもただのパンクではなく、チューブ破裂とでも言うべき壮絶なパンク。後輪のチューブがタイヤの内部でちぎれ、破片が外にベロンと飛び出すという、今まで見たこともないような奇妙なパンクであった。当然、新しいチューブを購入する必要があった。幸いにもパンク地点から500mほど行った場所にパンク修理屋があったが、そこにチューブの在庫はなかった。だが、修理屋の兄ちゃんによれば隣町まで行けば手に入るとのことであった。よって、兄ちゃんと一緒に隣町にチューブを買出しに行くことになった。後輪のチューブに応急処置を施しただけのパルサーに2人乗りするのは危険だったため、チューブを交換しもっともまともな状態のカリズマが出動することになった。修理屋の兄ちゃんを後ろに乗せ、峠を越して、隣町まで行った。確かにそこにはまともな修理屋が並んでいた。その内の1軒でチューブを購入し、元の場所まで戻った。すぐにチューブ交換をしてもらえたが、30分以上のタイムロスが発生した。もはや日没前にアルワルに到着するのは難しい。だが、ここまで来たらもう前進するしかない。明るい内に可能な限り距離をかせごうと、先を急いだ。
峠を越え、ターナー・ガーズィーを過ぎた。辺りは刻一刻と暗くなって来る。だが、意外にもこの時間に走って面白かったのはサリスカーであった。サリスカー虎保護区の大部分は入場料を払わなければ見れないようになっているが、アルワルとターナー・ガーズィーを結ぶ公道が虎保護区の一角を通っており、ここを走っているだけで様々な動物に遭遇することができる。行きのときはニールガーイを目撃したが、夕闇が迫った帰りのときには、ありとあらゆる動物たちが道路に出て来て、まるで人間の時間の終了を告げるように、我が物顔でのさばっていた。時間さえあれば動物たちを間近で観察しながらゆっくり通り抜けたかったが、アルワルまで行くことを考えると、スピードを緩めることはできなかった。やはりサリスカー2泊が一番理想的な旅程であった。
とうとう真っ暗になってしまった。街灯もない本当に真っ暗な道。ヘッドライトだけが頼りだが、対向車が来るとハイビームで目がくらみ何も見えなくなる。しかも反射板なしの自転車が道の隅をノロノロと走ったりしていて、不用意にハンドルを切ることもできない。条件は皆同じのはずなのに、なぜか夜になってもスピードを落とさないインド人ドライバーたち。彼らはもしかして我々よりも夜目が利くのだろうか?これは夜だけの話ではないが、夜には特にインドの路上に何が落っこちていても不思議ではない。もはや路面の凸凹を事前に避けるような余裕もなく、全ての窪みを甘んじて受け入れざるをえない。夜間走行はなるべく避けて来たが、今回はパンクに次ぐパンクでやむを得ない状態に追い込まれてしまった。だが、アルワルはもうすぐそこだった。市街地に着けばさすがに街灯があるので走行の危険性は格段に減る。何とか午後7時頃にアルワル市内に入ることができた。3人とも無事であった。
アルワルでは、マヌ・マールグにあるホテル・アルワルに宿泊した。オーナーはやたらと英語が流暢で、ホテルの設備や客室の細かい配慮などから、国際経験のあるセンスのある人だと感じられた。宿泊料は決して安くなく、ダブルルーム1泊1,450ルピー、エキストラベッド300ルピーであった。ほとんど昼食抜きの状態だったため、夕食は激辛のタンドゥーリー・チキンやチキン・カレーなどを3人でガツガツと平らげた。
さて、今日は3台連続で後輪パンクという前代未聞の不幸に見舞われた1日だった。今まで僕はインドで15回ほどツーリングをこなして来たが、自分のバイクがパンクしたことも、仲間のバイクがパンクしたことも、一度もなかった。いや、正確には一度だけ仲間のバイクがパンクしたことがあったが、デリーを出る直前でパンクしたため、近くに修理屋があり、それほど大変な事態にはならなかった。よって、ほとんどパンクとは無縁のツーリング人生を送って来たと言える。それが1日で3台、しかも参加者全員のバイクが全てパンクするのは異常な出来事としか言いようがない。・・・やはり脳裏に浮かぶのはバーンガルの呪いとの関連性である。もしかしたらバーンガルを訪れたこととこの連続パンクは関係があるのではないだろうか?これはバーンガルの祟りなのではないだろうか?しかし、祟りだと考えると、パンクなんて小学生の悪戯みたいなかわいい祟りに思えて来る。夜の走行で怖い思いはしたものの、命は助かったので何よりであった。是非パンクをもって憑き物は落ちたことにしていただきたいものである。
本日の走行距離は196.3km、本日までの総走行距離は387.1km。
| ◆ |
3月9日(日) 恐怖のバーンガル・ツーリング3日目 |
◆ |
今回のツーリングのメインディッシュはバーンガルで、昨日は十分バーンガルの素晴らしさと恐怖を味わったため、今日はデザートのような楽な日程を組んでいた。具体的にはアルワル観光である。僕と牧場主さんは既にアルワルを観光済みだったが、大将さんは初訪問。バイクで来たことによる機動力を活かし、アルワルの見所をつまみ食いして回ることにした。
朝食を食べ、午前9時にホテルを出発した。ところがすぐにパルサーがパンク。昨日応急処置した後輪である。やはり応急処置に過ぎなかったようで、一晩経ったら空気が抜けてしまったようだ。近くにパンク修理屋があったのでそこに持ち込んだ。今度こそ新しいチューブに交換する必要があったが、元々自転車修理をメインにしているところで、バイクのチューブはどこかから買って来なければならなかった。ちょうど修理屋のおじさんの息子がバイクでやって来たため、彼がお使いを頼まれ、チューブの買出しに向かってくれた。だが、まだ朝早く、開いている店が少なかったと見え、なかなか帰って来なかった。パルサーのチューブ交換が終わったときには午前10時になっていた。
さて、気を取り直して再出発。アルワルでまず向かったのは、デリーからサリスカーへ向かう途中に必ず目の当たりにする巨大な城塞跡モーティー・ドゥーンガリー。ホテル・アルワルの従業員に聞いてみたところ、モーティー・ドゥーンガリーの上には寺院があるだけだとのことだったが、どう見てもただの寺院建築には見えなかった。まず麓でバイクの記念撮影をしてから、上へ向かった。砂利道ではあるが、バイクでも十分通れる道が上まで続いていた。ここは僕も牧場主さんも初めてであった。

モーティー・ドゥーンガリーで記念撮影
最上部は・・・ただのだだっ広い平地だった。中心部に崩れかけた建物が残っていたが、古いものではなさそうだ。不思議な空間であった。

モーティー・ドゥーンガリー最上部
この平地より一段低いところには寺院があった。しかしこの寺院、よく見てみるとなかなか興味深い特徴を備えていた。

モーティー・ドゥーンガリーの寺院
イスラーム聖者廟とラーム寺院が同じ敷地内に併設されていたのである。ここに葬られている聖者はサイード・バーバーと言われている。この辺りで信仰されているイスラーム聖者のようである。

手前にイスラーム聖者廟、奥にラーム寺院
次に訪れた博物館で、モーティー・ドゥーンガリーの正体が分かった。やはりここにはかつて宮殿があったようである。ランズダウン・パレスとも呼ばれていたようだ。1882年に建造され、アルワル藩王国の国王がここに住んでいた。マハーラージャー・ジャイ・スィンは1928年に宮殿の再建を計画して一旦取り壊しを行った。そして宮殿の材料をヨーロッパから取り寄せたらしいのだが、輸送船が沈没してしまい、そのまま放置されることになったらしい。古いポストカードに在りし日のモーティー・ドゥーンガリーを見ることができた。

モーティー・ドゥーンガリー宮殿
アルワルの博物館やシティーパレス・コンプレックスは、かつて訪れたことがあるのでここでは詳しく書かない。2005年9月25日の日記を参照していただきたい。ただ、現在シティーパレスや博物館は改装作業中であったことは付記しておきたい。完了までまだ少し時間がかかりそうであった。

左が2005年9月、右が現在の写真
見違えるほど綺麗になったのが分かる
シティーパレスのそばには高い山が連なっているのだが、そこにはバラー・キラーと呼ばれる山城がある。かつてアルワルを訪れた際、そのバラー・キラーまで歩いて登って行こうとして失敗したことがあった。だが、後に自動車でも行ける舗装道があることを知り、一度バイクで上まで行ってみたいと思っていた。舗装道はシティーパレスの近くから出ていた。曲がりくねった峠道になっており、ここをバイクで走行するのは非常に快適だった。しかし、バラー・キラーは警察の施設になっており、パーミッションがないと中を見せてもらえなかった。そのことは昔から知っていたが、警察に見つからなければ見て回れるようなことを聞いていたため、ちょっと期待していたのだが、運悪くモロに警察が監視の目を光らせていた。写真撮影もさせてもらえなかった。
アルワルで行こうと思っていた場所は全て行き尽くしたため、デリーに帰ることにした。アルワルの出口でガソリンを給油し、12時45分頃にアルワルを出た。来た道をそのまま引き返してもよかったのだが、少し時間に余裕があったため、ニームラーナーに寄って行くことにした。僕は何度もニームラーナーを訪れたことがあったが、他の2人はまだ行ったことがなかった。距離的にもそんなに変わらない。アルワルから北西方面へ向かった。
こちらの道は初めて通ったが、アラーヴァリー山脈を貫くトンネルを発見したのが大きな収穫だった。こんなところにトンネルがあるのは全く知らなかった。インドでトンネルはけっこう珍しいのである。おそらくデリーからもっとも近いトンネルになるだろう。日本のトンネルと違うのは、ライトがないため中が真っ暗なことである。短いトンネルではあったが、面白い発見をすることができた。

トンネル
途中、午後1時半頃、ジンドーリーの辺りのダーバーで昼食を食べた。ここはトラック野郎ぐらいしか来ないような本格的なダーバーであった。椅子ではなくチャールパーイーに座って木の板の上で食事をするタイプ。ラージュマー・チャーワル(ウズラマメのカレー)を注文したはずだが、なぜかニンジンのカレーや謎のカレーなど、フルセットの料理が出て来た。値段は高めだったが、味はけっこういけた。

ダーバー
ダーバーを出たのは午後2時20分頃であった。そのまま北西へ向かう道を進むと交差点があり、それを直進するとタタールプルという町に出た。ここにもちょっとした城があった。この辺りには古い城がゴロゴロ転がっているようである。デリーからそんなに遠くない地域なのだが、毎回訪れる度に何か新たな発見のあるところだ。ひとつひとつ調べて行ったらとても面白いことだろう。

タタールプルの城
そのまま道なりに進んで行くと、ベヘロールという町でNH8に出る。NH8を右折してしばらく直進すれば、ニームラーナーに到着する。ニームラーナー・フォートパレス・ホテルについても既に何度も紹介したので、ここでは詳しい説明をしない。だが、今回見てみたらさらに増築している最中だった。元々、元からの城塞である旧館と、ホテル開業時に後から増築した新館に分かれていたが、さらに新館を増築して部屋数を増やすつもりのようだ。確かに日曜日の午後だというのに宿泊客の数はとても多かった。知名度が上がって手狭になってしまったのだろう。初めて僕がニームラーナーを訪れたときには宿泊客は無ではないにしてもまばらだったことを思うと、隔世の感がある。
ところでこのニームラーナーで、トラブル続きのパルサーにまた故障が生じた。今度はガソリン漏れである。原因は不明。だが、サイドスタンドでバイクを立てたときのみ漏れて来る状態で、走行中や、センタースタンドで駐車しているときは特に漏れはない。緊急に修理が必要な故障ではないと判断し、そのままデリーへ向かうことに決めた。
ニームラーナーを出発したのが午後5時頃だった。ニームラーナーからデリーまで120km。だが、デリーの基点は中央デリーのラージガートである場合が多く、南にあるJNUへ行こうとした場合、残り距離数はそれよりも低くなる。さらにNH8はスムーズに高速走行することができるため、思ったよりももうデリーは近い。途中いくつか工事中のところがあり、減速を余儀なくされたものの、午後7時頃にはJNUに帰還することができた。
本日の走行距離は213.7km、本日までの総走行距離は600.8km。バーンガルは普通の地図に載っていない場所なので、今回のツーリングの略式地図を以下に掲載しておく。
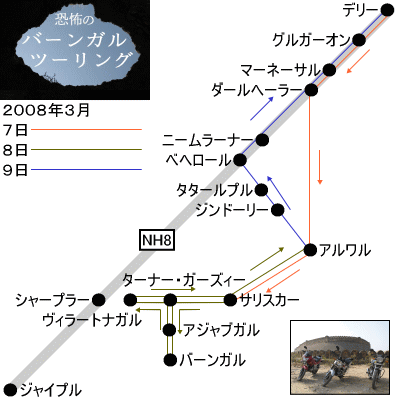
| ◆ |
3月11日(火) Black & White |
◆ |
「Jodhaa Akbar」以来、しばらく新作ヒンディー語映画が公開されずにいたが、3月に入ってひとつ傑作が公開された。「Black &
White」。公開直後からタックスフリーになっており、質の高さが十分伺われた。
題名:Black & White
読み:ブラック&ホワイト
意味:黒と白
邦題:ブラック&ホワイト
監督:スバーシュ・ガーイー
制作:スバーシュ・ガーイー
音楽:スクヴィンダル・スィン
作詞:イブラーヒーム・アシュク
出演:アニル・カプール、アヌラーグ・スィナー(新人)、アディティー・シャルマー、シェーファーリー・シャー、ハビーブ・タンヴィール、スクヴィンダル・スィン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アヌラーグ・スィナー(左)とアニル・カプール(右)
| あらすじ |
8月1日にデリーにやって来たヌマイル・カーズィー(アヌラーグ・スィナー)は、実はアフガニスタンでイスラーム原理主義の教育を受けた自爆テロリストだった。8月15日のインド独立記念日にラール・キラーで行われる首相演説で自爆テロを起こすために送り込まれていた。ヌマイルは地元のイスラーム教徒たちの助けを借り、ウルドゥー詩人ガッファール・ミヤーン(ハビーブ・タンヴィール)の家に居候し始める。
ヌマイルは、デリー大学ザーキル・フサイン・カレッジでウルドゥー文学を教えるラージャン・マートゥル教授と知り合う。ラージャンはチャーンドニー・チャウクで生まれ育ったヒンドゥー教徒で、皆から尊敬を集めていた。妻のローマー(シェーファーリー・シャー)は活動家で、やはりチャーンドニー・チャウクで一目置かれる存在だった。また、ガッファールの近所に住む女の子シャグフター(アディティー・シャルマー)はヌマイルに一目惚れし、彼に近付こうとするが、ヌマイルはあまり相手にしなかった。
ヌマイルは8月15日までの期間デリーで生活する内に、いろいろなものを目にする。一方で彼は、インドのイスラーム教徒が酒を飲み、政治家を買収し、ヒンドゥー教徒の巡礼ツアーのビジネスをしていることを知って、その堕落に憤慨する。他方、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融和のために全力を傾けるマートゥル夫妻の行動を見る。彼の考えに、白と黒ではない、いろいろな色が混じって来た。
一方、中央情報局(CBI)や警察は独立記念日を前にテロリスト対策を強化していた。その中でテロの首謀者の1人の逮捕状を発行する。彼はヌマイルに独立記念日式典へのエントリーパスを調達する役目を負っていた。だが、警察に逮捕される前に首謀者は拳銃自殺をしてしまう。一気に自爆テロ計画は中止に危機に追い込まれるが、ヌマイルはマートゥル夫妻に気に入られ、何とかエントリーパスを発行してもらうことに成功する。
独立記念日には、ガッファールが作詞した国民融和の詩が演奏される予定になっていた。だが、ガッファールはその日を待たずに他界してしまう。死因は心臓発作であった。だが、その本当の理由は誰も知らなかった。実はガッファールは、かわいがっていたヌマイルが自爆テロリストであることを偶然知ってしまい、ショックのあまり心臓発作を起こしたのであった。また、8月14日の夜には、自爆テロ計画の要員によってローマーが殺害されてしまう。ラージャンは、ローマーが近所のイスラーム教徒に殺されたと考え、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の抗争を避けるため、独立記念日式典が終わるまでローマーの死を伏せることにした。
8月15日。ヌマイルはラージャンと共にラール・キラーのVIP席に座った。ヌマイルはペン型の爆弾を所有していた。そして時間が来たら爆弾を爆発させようとしたが、短い間デリーで体験した事柄が頭をよぎり、何もすることができなかった。一方、CBIはヌマイルが自爆テロリストであることを突き止め、警察を動員する。ヌマイルは逃亡する。ラージャンは何が起こったか理解できずにいたが、ヌマイルに自爆テロ未遂の容疑がかけられていることを知ると、彼をかばう。ラージャンのおかげでヌマイルは逃亡に成功するが、ラージャンはテロリスト幇助の容疑で逮捕されてしまう。
ラージャンの裁判が行われようとしていた。近所の人々やラージャンの教え子たちは皆ラージャンを擁護する。そこへヌマイルからCBIへ手紙が届く。ヌマイルは、ラージャンと出会ったことが自爆テロを思い留まらせたとつづっていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
映画の冒頭でお決まりの「この映画はフィクションです・・・」の断り書きがナレーション付きで表示されたが、明らかにこの映画は2001年12月13日の国会議事堂テロとそれに付随するアブドゥル・レヘマーン・ギーラーニー教授(デリー大学ザーキル・フサイン・カレッジ)逮捕という実際に起こった事件をベースにしている。だが、「Black
Friday」(2004年)や「Shootout At Lokhandwala」(2007年)のように、事件の真相に迫るドキュメンタリー・タッチの映画ではなく、自爆テロリストの心理の変化を中心に据えて、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融和の重要性が主張されていた。今まで娯楽映画メーカーのイメージが強かったスバーシュ・ガーイー監督がシリアスな映画に挑戦したことも大きな見所だ。
主人公のヌメイル・カーズィーは、アフガニスタンで戦火を潜り抜けて生きて来た青年であった。幼い頃からイスラーム教原理主義を叩き込まれており、インド独立記念日に自爆テロをして殉死することに誇りを感じていた。グジャラート暴動で両親を失った不幸な若者として、彼はデリーに送り込まれる。彼の世界は黒と白のみで塗り分けられていた。彼にとってイスラーム教のみが絶対の真理であった。だが、自爆テロ決行の8月15日までの2週間、デリーのチャーンドニー・チャウクで様々な人間模様を目の当たりにすることで、彼は次第に黒と白以外にも色があることに気付き始める。最終的に彼は自爆テロを思い留まる。
ヌメイルの考え方にもっとも大きな影響を与えたのは、老齢のウルドゥー詩人ガファール・ミヤーンと、マートゥル夫妻であった。3人ともチャーンドニー・チャウクで生まれ育ち、地域の人々から多大な尊敬を集める人物であった。ガッファールは昔ながらの詩人で、色鮮やかな現代の文壇の中では次第に忘れ去られつつある存在だったが、最後の力を振り絞って、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融和を謳い上げた詩をインドに捧げる。だが、皮肉なことに、彼の孫には、祖父のヒンドゥー教徒に対する融和の態度が弱腰の態度に映り、自爆テロの幇助に手を染めることになってしまう。
ラージャン・マートゥル教授は、大学でウルドゥー文学を教えるヒンドゥー教徒である。多くの人々は、ヒンディー語・ヒンディー文学=ヒンドゥー教徒、ウルドゥー語・ウルドゥー文学=イスラーム教徒という図式で理解してしまうが、実際にはそのようなことはない。ヒンドゥー教徒でもウルドゥー文学者はいるし、イスラーム教徒もヒンディー語でものを書く人がいる。特に19世紀からウルドゥー語を使いこなして来たヒンドゥー教徒コミュニティーとして、カーヤスト、カシュミーリー・ブラーフマン、パンジャービー・カトリーの3種が挙げられる。マートゥルという名字はカーヤストのものである。彼の存在自体が宗教融和の象徴であった。
ラージャンの妻ローマーも、チャーンドニー・チャウクにおいてヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間に芽生えつつあるコミュナルな感情に危機感を感じる社会活動家である。彼女は人々に、「チャーンドニー・チャウクでは人をヒンドゥー教徒とかイスラーム教徒と言って呼んだりはしない。相手の名前で呼ぶのよ」と言って説得する。
一方で、政治が宗教を利用するインドの病巣も描き出されていた。チャーンドニー・チャウクにはヒンドゥー教徒多住地域とイスラーム教徒多住地域があり、それぞれにリーダーがいて、お互いにいがみ合っているように見えるが、実は「同じ酒屋で酒を飲む」仲間であった。地元の政治家の都合に合わせて彼らはコミュナルな対立を煽り、報酬を得ているのであった。
しばしばインドは「多様性の中の統一」と表現される。インド人全てが必ずしも多様性を受け入れている訳ではなく、時々コミュニティー間の対立や暴動が発生する。だが、そんな中にも融和を諦めない人々がおり、その人たちのおかげでインドがインドとして成り立っていることが映画の中で強く主張されていた。ラージャン・マートゥル教授は最後、シャグフターに対し、ヌメイル・カーズィーの逃亡を助けたことについて、こんなことを語っていた。「イスラーム原理主義者たちは自分たちの考えを世界に知らしめるためのメッセンジャーとして我々に自爆テロリストを送り込んだ。それなら我々も彼らにメッセンジャーを送り込もうではないか。ヌメイルは我々と共に生活し、新しい考えを得たはずだ。彼がきっと、彼らに我々の考えを伝えるメッセンジャーとなってくれるだろう。」
ストーリーも素晴らしかったが、主演の俳優陣の演技も素晴らしかった。まず特筆すべきは、著名な演劇作家ハビーブ・タンヴィールがウルドゥー詩人役で出演していることである。彼が銀幕に登場するのは、「Mangal
Pandey」(2005年)以来だ。既に老齢のため、所々台詞が聴き取りにくかったが、その存在感は映画の核として十分であった。
ラージャン・マートゥル教授役を演じたアニル・カプールも、朗らかかつ情熱のある人柄をうまく演技で表現していた。ここ数年でベストの演技と言える。妻ローマーを演じたシェーファーリー・シャーは、「Monsoon
Wedding」(2001年)や「Gandhi My Father」(2006年)に出演していた女優である。多少オーバーアクティング気味のときもあるが、迫力のある演技ができる女優だ。
主人公ヌメイル・カーズィーを演じたアヌラーグ・スィナーは、本作がデビュー作。目付きが悪いが、その暗い表情が自爆テロリストにピッタリであった。スバーシュ・ガーイーは人材発掘屋としても有名なので、これから注目を集める男優になって行くかもしれない。
映画の大部分がデリーで撮影されているだけでなく、デリーに住む人々の調和と団結が巧みに描き出されており、デリー市民には嬉しい作品である。ラール・キラー、チャーンドニー・チャウク、ジャーマー・マスジド、インド門、大統領官邸、国会議事堂、クトゥブ・ミーナールなど、デリーのメジャーな見所の多くが網羅されていた。最近デリー・ロケの映画が急激に増えて来たが、ムンバイーで撮影された一般のボリウッド映画とは違った味が出るのがいい。
ヌメイルはアフガニスタンから送り込まれたという設定になっているため、パシュトー語と思われる台詞がいくつかあった。その部分は英語字幕付きだった。登場人物の多くはチャーンドニー・チャウクで暮らす人々であり、ウルドゥー語、ヒンディー語、パンジャービー語など、多岐に渡った言語が使用されていた。
「Black & White」は、黒と白、善と悪、イスラームと非イスラームという二元的な見方しかできなかった自爆テロリストが、「色彩の国」インドで様々な色を体験することで、多元的な考え方に影響されて行く過程を追った、考えさせられる映画である。昨年12月に公開された「Taare
Zameen Par」、今年1月に公開された「Halla Bol」に続く、質の高いクロスオーバー映画だと言える。
| ◆ |
3月12日(水) 空席のキャノピーと戴冠公園 |
◆ |
デリー市民の憩いの場で、観光地のひとつでもあるインド門。英領インドの首都デリーが完成した1931年に建造された堂々たる門である。計画都市ニューデリーを設計したエドワード・ルティヤンスは巨大記念碑のデザインを得意としており、インド門も彼の設計である。インド独立前は全インド戦争記念碑(All
India War Memorial)と呼ばれていたが、今ではインド門(India Gate)と呼ばれている。第一次世界大戦で戦死した6万人のインド人兵と、第一次アフガン戦争で戦死した13,516年の英国人・インド人兵を追悼して建てられた。毎年1月26日には、このインド門を中心に共和国記念日式典が開催される。インドの国家的威信を象徴する場所であり、テロの標的にもなりやすいため、警備は厳重である。

インド門
インド門の東側には、四本の柱で支えられた屋根を持つ東屋が建っている。ヒンディー語ではチャトリー、英語ではキャノピー(canopy)と呼ばれている。また、キャノピー周辺の広場はニューデリーの中心を成す、象徴的に重要なエリアであり、セントラル・ヴィスタ(Central
Vista)と呼ばれている。

キャノピー
キャノピーの建築自体、単品でけっこう完成されているので、ほとんどの観光客はキャノピーを見ても何の疑問も抱かないかもしれないが、ニューデリー完成から5年後の1936年から、インド独立後20年以上経った1968年まで、実はこのキャノピーの中には英国王ジョージ5世(在位1910-1936年)の像が立っていた。このキャノピーは、インドの支配権を象徴するために設計された帝国主義的建築物なのである。今はもろもろの事情があって空席となっている。
その事情を解説する前に、かつてキャノピーに置かれていたジョージ5世の像がどうなったかを先に見てみよう。ジョージ5世の像は今でもデリーに残っている。だが、かつてインドのもっとも輝かしい玉座に座していた像は、今では北デリー郊外のうら寂しい公園の中に、鳥の糞まみれになってひっそりと立っている。その場所は一般に戴冠公園(Coronation
Park)と呼ばれている。公園の中央部にはオベリスク風の戴冠記念碑(Coronation Memorial)が立っている。EICHER「Delhi
City Map」ではP12のE6, F6になる。その戴冠記念碑の南側に、英領時代にデリー各地に立てられた英国人の彫像と共に、ジョージ5世の像も立っている。

戴冠公園に立つジョージ5世の像
戴冠公園は、今でこそ近所の子供たちのクリケット場でしかないように見えてしまうが、英領インドの新首都ニューデリーの歴史の出発点となった重要な場所である。

戴冠記念碑
英領インドの首都は当初ベンガル地方のカルカッタにあった。ベンガル人たちはそのおかげでいち早く西欧式教育に恵まれ、様々な分野でインドの他の地域の人々よりも先進的な考えを持つに至った。中には植民地主義の弊害と不正に気付く者も現れ、次第に民族運動が高まって行った。英国政府はベンガル地方をヒンドゥー教多住地域の西ベンガルとイスラーム教徒多住地域の東ベンガルに分割してその動きを弱体化させようとし、1905年にベンガル分割令を制定したが、それが余計にベンガル地方の民族運動を活発化させた。また、元々商都として発展した街であるため、カルカッタは英国人貿易商の影響力も強かった。次第にカルカッタは英国政府にとって植民地政策の拠点としては不適合な場所となって行った。
英領インドの首都移転に関する審議は過去何度も行われたが、デリーへの遷都が初めて本格的に審議され始めたのは、1911年6月17日にインド総督諮問委員の1人ジョン・リーヴァイス・ジェンキンスがインド総督チャールズ・ハーディングに提出した提案書がきっかけだった。ちょうど年末には、英国王ジョージ5世とメアリー王妃がインドを訪問することになっており、ハーディング総督もそれに併せて何か歴史に残るような大きな発表をしたいと考えていた。ハーディングはジェンキンスの提案に賛成し、8月25日に本国インド省に「ニューデリーへの首都移転」と題したメモを送った。インド省のクルー大臣もそれを支持した。長い間インドの中心として栄えて来たデリーへの遷都は、英国植民地政府の正統性をインド人に知らしめる絶大な効果が期待された。クルー大臣は短い言葉でそれを端的に表現した。「デリーに残された古い城壁は、ローマやコンスタンティノープルと比肩するような帝権の伝統を秘めている。」デリー遷都案は、カルカッタ・ロビーなどからの反対があったものの、すぐに採用された。
1911年6月22日にロンドンのウェストミンスター寺院で戴冠式を行ったジョージ5世は、それをインド人民にも知らせるため、英国の国王として初の(そして唯一の)インド訪問を決定した。ジョージ5世はメアリー王妃と共に同年12月2日にボンベイに上陸し、数日間滞在した。5日にはエレファンタ島を観光し、その夜にデリー行きの特別列車に乗った。ジョージ5世一行を乗せた列車は7日の朝にデリーに到着し、英国人官僚やインド人王侯貴族、そして一般人民から熱烈な歓迎を受けた。
以後、デリーで「デリー・ダルバール」と呼ばれる一連の儀式が執り行われた。デリー・ダルバールとは「デリー謁見式」という意味で、ヴィクトリア女王がインド皇帝に即位した1877年、エドワード7世が英国王兼インド皇帝に即位した1903年にも行われた。だが、英国王が自ら参加したのは1911年の第3回デリー・ダルバールのみであった。英領インドの首都カルカッタで一度も謁見式が行われず、当時パンジャーブ州の一都市に過ぎなかったデリーでこのような重要な儀式が行われたのは、やはりカルカッタが政治的に不穏だったことと、デリーが伝統的にインドの帝権を象徴して来たからであろう。
第3回デリー・ダルバールでもっとも重要な行事は、1911年12月12日に行われた。この日、インド中の英国人将校・官僚や王侯貴族合計4,000人が臨席する中で、ジョージ5世の英国王・インド皇帝即位が宣言されたと同時に、いくつかの決定が発表された。その中でもっとも重要なのが、デリー遷都とベンガル分割令撤回である。このふたつは表裏一体であった。ベンガル分割令の失敗は明らかであったが、無条件での撤回は英国植民地政府の威信に関わった。よって、英領インドの首都をデリーに移転することで、ベンガル地方とその周辺部の行政区分を再構成する正当な口実を作り出し、事実上のベンガル分割令撤回を行ったのである。
我々は国民に喜びと共に以下の発表を行う。大臣の助言の下、評議会の総督と審議した結果、我々は、インド政府の首都をカルカッタから古都デリーに移転することを決定した。同時に、その移転の結果として、ベンガル管区知事職、ビハール、チョーター・ナーグプル、オリッサを統治する副知事職、アッサムの主管職をなるべく早期に創設することも決定した。また、評議会の総督が近日中にインド省大臣の承認の下に行うであろう決定に基づいて、州境の再編も行う。我々は、これらの改革がインドの統治を効率化し、最愛の国民たちにさらなる繁栄と幸福をもたらすことを期待する。
デリー遷都決定は、デリー・ダルバールのときまで極秘とされた。一部の高官を除く全ての人々は、このとき初めて英領インドの首都がカルカッタからデリーへ移転されることを知った。ハーディング総督は、ジョージ5世がデリー遷都を発表したときの会場の様子を「My
Indian Years, 1910-1916: The Reminisceneces of Lord Hardinge of Penhurst」にこう綴っている。
国王は、4,000人の参列者全てがはっきりと聞き取れるような明瞭な声で、声明文を読み上げた。それはまるで爆弾のようであった。まず、心底からの驚きから来る深い沈黙があった。その数秒後、けたたましい歓声が一斉に沸き起こった。
ジョージ5世はハーディング総督に対し、新首都の定礎式を執り行うことを提案した。だが、この提案は関係者を困惑させた。なぜなら、デリーのどこに新都を建設するかまだ決定していなかったからである。結局礎石はシャージャハーナーバード(オールドデリー)の北に置かれることになり、12月15日にジョージ5世の臨席の下に定礎式が行われた。しかし、後にニューデリーはシャージャハーナーバードの南西に建造されることになった。ハーディング総督は後に回想している。
国王と王妃が礎石を置いた場所は新都に選ばれなかった。1年後、私はそれらの石を密かに新都の省庁舎建設予定地へ移動させた。
北デリーに残る戴冠公園は、正にこの第3回デリー・ダルバールが開催された場所である。ニューデリーがシャージャハーナーバードの南西に建造されたことにより、この辺りはデリーの中でも相対的に辺境に分類されることになってしまった。現在公園の中央に立つ戴冠記念碑のみが、ニューデリーの始まりを告げている。記念碑には、英語とウルドゥー語で、1911年12月12日にこの広場でジョージ5世の戴冠式が行われたことが記されている。

戴冠記念碑の碑文
既にデリー・ダルバールのときに、ジョージ5世の像がニューデリーに設置されることが決定されていた。ジョージ5世の訪印とデリー遷都発表を記念するためで、グワーリヤル藩王国のマハーラージャーがその責任者に任命された。それとつながりがあるかは不明だが、1936年、エドワード・ルティエンスは全インド戦争記念碑(現在のインド門)の東側に、15mの高さのジョージ5世の大理石製の彫像を設置した。ジョージ5世の像は、英国の王権の象徴である王冠、宝珠、ローブを身に着け、インドの王権の象徴である星の紋章を持ち、そして東洋の文明の象徴である水で装飾されており、全体で帝国主義と植民地主義の正統性を象徴していた。

ジョージ5世像
インド独立時、デリーにはジョージ5世像を含め、英国人総督や将校の像が13体立っていた。英領時代に立てられた像に対する処置は各州政府に委ねられたが、デリーは首都という特殊なステータスを持っていたため、デリーに立っている像に関してインド全土の政治家が関心を払った。特にセントラル・ヴィスタは国権の象徴であり、時代ごとに数々の議論を巻き起こした。
初代首相ジャワーハルラール・ネルーは、英領時代にデリーに立てられた彫像を強行に除去しようとはしなかった。彼は、不快な印象を与える像を真っ先に取り除くべきだと主張したものの、英国との関係を悪化させないように徐々に除去作業を行うべきだとの姿勢を取った。いくつかの像は撤去されて行ったが、ネルー首相が1964年に死去するまで、ジョージ5世像を含めた4体の彫像がそのまま残ることになった。ジョージ5世像を巡る議論は次第に熱を帯びて来た。1965年5月、ある国会議員がジョージ5世像の撤去を議題として持ち上げた。
インドが独立してから17年、18年が過ぎ去り、国民による政府が樹立してから十分な時間が経った。今日までジョージ5世像が大統領官邸の正面に立っていることは非常に恥ずべきことである。少なくともこの像は撤去されるべきであり、他の外国人の像も撤去されるべきである。
1965年8月13日、何者かがジョージ5世像の鼻と両耳を破壊するという事件が起きた。そして1968年の末になってやっとジョージ5世像はセントラル・ヴィスタのキャノピーから撤去されることになった。撤去されたジョージ5世像はしばらくオールドデリーの倉庫に保管されていたようだが、後に戴冠公園に設置された。戴冠公園にはジョージ5世像以外にも4体の小さな英国人彫像が立っているが、これらもきっとかつてデリーの重要なエリアに立てられていたものであろう。

ジョージ5世像アップ
鳥の糞尿が頭からしたたり落ちている・・・
さて、晴れてジョージ5世像はキャノピーから取り払われたわけだが、今度は空席となったキャノピーの扱いが問題となった。次第に、独立の父マハートマー・ガーンディー像をキャノピーに設置しようという動きが強まって行った。一応、1969年2月までに下院にて、ガーンディー像を公費で制作してインド門近くのセントラル・ヴィスタに設置することが決定されたが、ガーンディー像はジョージ5世像が立っていた位置に置かれるのか、それとも別の場所に置かれるのか、ガーンディー像のデザインはどんなものなのかなど、それ以上の詳細は決まっていなかった。
ガーンディー像をキャノピーに置くことに対しては多くの反対の声が挙がった。その主な理由は、英領政府に対し非暴力・非協力運動を提唱・推進したガーンディーの像を、帝国主義の象徴であるキャノピーに置くのは不適切であるというものだった。幾度も国会で議論が行われたが、結局最終的な決定は下せないまま10年が過ぎ去った。1977年、モーラールジー・デーサーイー首相率いる人民党が国民会議派から政権を奪取すると、再びガーンディー像問題が取り上げられた。やはりガーンディーのイメージとキャノピーはマッチしないということになったが、今度はキャノピーを取り払うべしとの提案が出された。このときガーンディー像のサイズも問題となり、等身大の7倍の大きさの像を制作することが提案された。1980年にインディラー・ガーンディーが政権を奪回すると、ガーンディー像に関してまたも再考が行われ、議論の末、結局キャノピーの下に約5mの高さのガーンディー像が設置されることになった。政府から任命された彫刻家は、瞑想のポーズを取るガーンディー像の制作を開始した。
1989年、青銅製のガーンディー像が完成した。ところが、完成した像は大きすぎてキャノピーの中に収まり切らないことが発覚した。そこで急遽キャノピーの屋根と4本の柱が除去されることになった。しかし、このことをメディアが報じたことで、デリーの民間組織や教養層の間から反対の声が挙がった。その先頭に立ったのが、デリーの非公式遺跡保護団体、デリー保護協会(CSD)であった。CSDは、キャノピーを含むセントラル・ヴィスタは保護区域に指定されていると主張し、キャノピーの破壊に反対した。世論に反対に遭い、またもガーンディー像計画は暗礁に乗り上げてしまった。1992年になると、ナラスィンハ・ラーオ政権はこの問題について公聴会を開いたが、やはりキャノピーは破壊されるべきでないとの総意に達した。このとき、遺跡保護活動を行うNGO、インド芸術文化遺産基金(INTACH)は、キャノピーを空白のままにすることで、帝国主義に対するインド国民の勝利が象徴されるとのユニークな意見を発表した。
キャノピーはそのままにしておくのが一番いい。空白は帝国主義に対するインド国民の勝利を象徴的にハイライトするからだ。キャノピーの空白はいついかなるときも、英国帝国主義の退去とインド国民への民主主義の約束を表現する。適切にデザインされた銘板をキャノピーの基部に設置してもいい。そこにはヒンディー語と英語で、建築学的解説、帝国主義の象徴としての英国人によるジョージ5世像の設置、1960年代にそれが撤去されたときの状況、マハートマー・ガーンディー像の設置に関するジレンマ、空白のキャノピーが象徴するもの、マハートマー・ガーンディー像が別の場所に最終的に設置されたことの理論的根拠などが記されるべきである。数年後、数十年後、数百年後、インド門を訪れるインド人や外国人観光客はこの銘文を読んで、この問題に関してインドが直面した大きなジレンマを知ることができるだろう。よって、空席のキャノピーは、破壊されたキャノピーや調和しない事物が置かれたキャノピーよりも多くのことを語るのである。
結局、キャノピーの中に置かれるはずだったマハートマー・ガーンディーの坐像は、国民の感情に配慮して、代わりに国会議事堂の敷地内に置かれることになり、セントラル・ヴィスタのキャノピーは現在に至るまで空席のまま残されている。国会議事堂は一般人の立ち入りができないため、このガーンディー像を実際に見たことはないのだが、ネット上で写真を拾うことができた。

国会議事堂のガーンディー像
こんなものがキャノピーの中に座っていたら、人気観光地のインド門もだいぶ雰囲気が違っていたに違いない・・・。帝国主義云々は別にして、純粋に美観という観点から、今のままが一番無難だと言っていいだろう。なにはともあれ、インド門の東側にオマケのように立つあのキャノピーには、これだけ長いストーリーが隠されていたのであった。
インドでは数々の宗教が共存しているが、今日はその多様性を象徴する日になった。イエス・キリストの命日であるグッド・フライデー、ムハンマドの生誕日かつ命日であるイード・ミラードゥン・ナビー、拝火教徒の新年であるナヴローズが重なったのである。しかも明日はヒンドゥー教の祭りホーリーで、その前日の今日はチョーティー・ホーリー(小ホーリー)と呼ばれ、前夜祭のような祝われ方をする。インドのほとんどの宗教の人々にとってめでたい日であった。
そのお祭りシーズンを狙い、2008年のボリウッドの期待作の1本が公開された。「スリラーの帝王」の名をほしいままにする監督ドゥオ、アッバース・マスターンの「Race」である。
題名:Race
読み:レース
意味:レース
邦題:レース
監督:アッバース・マスターン
制作:ラメーシュ・タウラーニー、クマール・タウラーニー
音楽:プリータム
作詞:サミール
振付:ボスコ・マーティス、カエサル・ゴンザルヴェス、ガネーシュ・アーチャーリヤ
出演:アニル・カプール、サイフ・アリー・カーン、アクシャイ・カンナー、ビパーシャー・バス、カトリーナ・カイフ、サミーラー・レッディー、ダリープ・ターヒル、ジョニー・リーヴァル
備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、カトリーナ・カイフ、アニル・カプール、サイフ・アリー・カーン、
アクシャイ・カンナー、ビパーシャー・バス、サミーラー・レッディー
| あらすじ |
南アフリカ共和国ダーバン。ランヴィール・スィン(サイフ・アリー・カーン)は競馬が生き甲斐の大富豪実業家で、自分の競走馬やファームも所有していた。一方、弟のラージーヴ・スィン(アクシャイ・カンナー)は酒にしか興味のない飲んだくれだった。ランヴィールには、ファッション・モデルのソニア(ビパーシャー・バス)というガールフレンドがいたが、彼の秘書ソフィア(カトリーナ・カイフ)はランヴィールのことを密かに想っていた。
あるとき、ランヴィールは大事故に遭うが、一命を取り留める。しばらくの入院の後、ランヴィールは退院する。ラージーヴは退院パーティーを開催する。このとき初めてランヴィールはラージーヴにソニアを紹介する。ソニアに一目惚れしてしまったラージーヴは、もしソニアが自分のものになったら禁酒すると宣言する。ラージーヴの暴飲を心配していたランヴィールは、ソニアをラージーヴに譲ることを決める。ランヴィールはソニアに、自分には実はガールフレンドがいると嘘を付く。ショックを受けたソニアだったが、ラージーヴとデートを重ねるようになる。
ところがラージーヴはソニアの過去を前々から調べ上げていた。彼女には前科があり、インドから南アフリカ共和国に逃げて来たのであった。それを暴露されるとソニアは居直り、ラージーヴに「何が目的なの?」と聞く。実はラージーヴは密かにランヴィール暗殺計画を立てていた。彼らの父親は2人に100万ドルずつの生命保険を掛けており、もしどちらかが死ねば、100万ドルの保険金が手に入ることになっていた。ラージーヴはその計画への協力を求める。ソニアもその話に乗る。ランヴィールは、ケープタウンへの出張から帰って来た後、会社のビルのテラスから突き落とされて死亡する。最初は事故と見られたが、この事件を担当することになったインド人刑事ロバート・デコスタ(アニル・カプール)は真相は別だと考えていた。ロバートはアシスタントのミニ(サミーラー・レッディー)と共に捜査を始める。当然、最も疑わしいのは保険金の受取人になっているラージーヴであった。
だが、ここで事件に新展開が出て来る。ランヴィールが死ぬ直前に秘書のソフィアと結婚していたことが明らかになったのである。ケープタウンへの出張中に2人は役所に婚姻届を届けていた。ランヴィールはダーバンに帰って来た後にサプライズとして発表しようとしていた。つまり、保険金の受取人はラージーヴではなく、ソフィアになってしまったのである。だが、婚姻届に不審な点を発見したロバートは、ミニと共にケープタウンへ飛ぶ。そこで発覚したのは、役所にソフィアと共に婚姻届を出しに現れたのはランヴィールではなく、ラージーヴだったという事実だった。実はラージーヴはソニアより前にソフィアと通じていたのである。ロバートはラージーヴとソフィアを追及する。ラージーヴは仕方なく保険金の4分の1を賄賂として彼に渡すことになる。
保険金受け取りの日になった。ソフィアはラージーヴの乗る自動車で保険会社へ行き、保険金100万ドルを受け取った。ラージーヴの行動を不審に感じたソニアはラージーヴを尾行していたが、それはラージーヴの罠であった。誘い出されたソニアは、雇われた殺し人に殺されそうになるが、それを助けたのが死んだはずのランヴィールであった。
ランヴィールは、以前入院したときに偶然、自分の遭遇した事故が、ただの事故ではなく、ラージーヴの計画したものだったことを知ってしまう。その後、ラージーヴの部屋を探ったところ、ソニアの経歴をまとめた書類を発見し、弟が何を考えているのかを知るため、故意にソニアをラージーヴに会わせたのだった。ラージーヴが再度の暗殺計画を立てていることを知ったランヴィールは、その計画を逆手に取り、200万ドルのゲームを遊ぶことに決めた。つまり、自分の死を偽装して100万ドルの保険金を引き出し、さらにラージーヴを殺して彼の分の100万ドルの保険金もせしめようとしたのだった。ランヴィールはロバートと協力して死を偽装し、ソニアを使ってラージーヴの行動を逐一把握していた。その中で、ラージーヴは子供の頃から自分に劣等感を持っており、何とか兄を負かそうと躍起になっていたことを知る。ランヴィールはソニアと共にラージーヴとソフィアの前に姿を現し、全ての種明かしをする。
だが、ランヴィールはラージーヴに最後にチャンスを与えた。自動車でレースをして、勝った方が全てを手に入れるというものだった。ラージーヴもそれを受け入れる。ラージーヴとソフィアは青いスポーツカーを用意してランヴィールを待った。ランヴィールとソニアは黄色いスポーツカーに乗って現れる。ラージーヴが兄の車を見て、「これなら誰でも勝てる」と言ったため、ランヴィールはラージーヴの車と交換してレースをすることにした。レースは始まった。だが、すぐにラージーヴの姑息さが明らかになる。青いスポーツカーのブレーキは故障していたのだ。だが、ランヴィールも負けてはいなかった。ランヴィールはラージーヴに電話し、黄色いスポーツカーには爆弾が仕掛けられており、時速100km以下になったら爆発することを伝える。こうして、ブレーキなしの死のレースとなった。だが、最後にはラージーヴとソフィアの乗った車はタンクローリーとぶつかって大破炎上してしまう。ランヴィールとソニアの乗った車は何とかスピードを殺して止まることが出来た。実は黄色いスポーツカーには爆弾など仕掛けられていなかった。卑怯な手段を使った弟に、嘘で対抗しただけだった。
こうして、法律上ラージーヴの妻であるソニアは100万ドルの保険金を受け取った。ランヴィールとソニアはこのまま誰も知らない場所へ向かった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
アッバース・マスターン監督らしい、二転三転の展開が楽しい娯楽映画であった。保険金を巡って兄弟間で繰り広げられる仁義なき騙し合いがテーマである。インド映画のスリラーにありがちではあるが、各どんでん返しに理論的整合性はほとんどない。脚本の都合で何度も話がひっくり返ってしまう。騙し騙されの連続で、最終的にはとんでもなく複雑で高度な騙し合いになってしまっている。あまり計画性のないインド人がこんな練りに練った犯罪計画を立てるかと疑ってしまう。だが、その点に目をつむりさえすれば、十分楽しめる作品である。
目まぐるしく展開する映画の中で重要な軸となっていたのは、ランヴィールのモットーである。競馬に全身全霊を捧げるランヴィールは、勝負に対してひとつのモットーを持っていた。それは、「負かそうと思う者は勝てない。勝とうと思う者が勝つ」というものである。つまり、真剣勝負のレースにおいて、卑怯な手段を使って勝とうとする者は必ず負けるというのが彼の自論であり、むしろ彼はそういう卑怯者を容赦なく打ち負かして来た。ランヴィール暗殺計画を立てて失敗したラージーヴも、最後にチャンスを与えられながら、真剣に勝負をせず、卑怯な手段に頼ったため、負けてしまうのだった。卑怯者は、自分が卑怯な考えを持っているだけあって、相手も卑怯な手段を使って自分を負かそうとして来ると考える傾向にあり、それが結局勝負事で命取りになってしまう、という主張が映画から感じられた。エンディングでランヴィールはロバートに、「オレが一番苦手なのは正直者だ」と呟くシーンがあるが、それはそのモットーの裏返しである。
主演の男優3人は、昔からボリウッドで活躍していながら、いまいち芽の出なかった人々である。だが、ここ数年でだいぶ彼らの評価も急激に変わって来た。頭ひとつ飛び抜けたのはサイフ・アリー・カーン。「Kal
Ho Naa Ho」(2003年)などの娯楽大作で人気を再燃させることに成功したばかりでなく、「Omkara」(2006年)などの比較的シリアスな作品での演技は高く評価された。「Race」のサイフの演技も素晴らしかった。アクシャイ・カンナーも、サイフに比べたら出遅れているものの、「Gandhi
My Father」(2007年)などで重要な役を演じ、かなり信頼できる俳優になって来た。サイフとのスクリーン上の相性もよく、映画を盛り上げていた。アニル・カプールは、時々迷走して変な役を引き受けたりする癖があり、「Race」での彼の役も微妙であったが、先日公開された「Black
& White」で見せたように、真面目な演技もできる俳優である。彼が「Race」で演じたロバート・デコスタ刑事は、毎回果物を食べながら捜査するという、苦笑もののキャラクターであった。
一方、女優3人の現在の立ち位置はだいぶ異なっている。ビパーシャー・バスは、アッバース・マスターン監督「Ajnabee」(2001年)でデビューし、しばらくセックス・アイドルとしてインド中にビパーシャー旋風を巻き起こした女優である。だが、いつしか演技派転向を口にするようになり、次第に映画への露出も肌の露出も限られて来た。現在でも活躍中だが、一時期のホットさに比べたら、だいぶ落ち着いてしまったと言わざるをえない。サミーラー・レッディーは、デビューはビパーシャーと同じ頃だが、今に至ってもなかなかブレイクできないでいる。比較的勢いがあったのはサンジャイ・ダットと共演した「Musafir」(2004年)の頃だが、残念ながら今でも二流三流のままだ。期待作「Race」への出演が彼女のキャリアの突破口になるかもしれないと思っていたが、彼女に与えられた役は、ロバート・デコスタ刑事のアシスタントながら頭のねじが外れた半分コミックロールみたいな役で、いてもいなくてもあまり変わらなかった。男優の数に女優の数を合わせるために作り出された役という感じがした。カトリーナ・カイフは、今もっとも勢いのある若手女優である。「Race」では、無邪気な秘書と見せかけて実は曲者という、けっこう高度な役を演じていた。客寄せパンダ的な女優から徐々に脱皮しつつあるのを感じる。
その他、一瞬だけ名コメディアン、ジョニー・リーヴァルが登場し、あのギョロ目とマシンガントークを披露してくれる。
音楽はプリータム。スリラーの雰囲気を盛り上げるテーマ曲「Race Saanson Ki」、ディスコナンバー「Dekho Nashe Mein」などの踊れる曲や、アーティフ・アスラムの歌うバラード「Pehli
Nazar Mein」、誘惑の歌「Zara Zara Touch Me」など、バラエティーに富んだナンバーが揃っている。サントラは買いである。
「Race」は、どんでん返しに次ぐどんでん返し、スピーディーな展開、美女とダンス、クライマックスの死のレースなど、見所盛りだくさんの娯楽大作である。暇潰しや気晴らしには最適の作品だ。
| ◆ |
3月21日(金) イード・ミラードゥン・ナビーの行進 |
◆ |
オールドデリーにイスラーム教徒の友人ができ、祭りがあると誘ってもらえるようになった。ヒンドゥー教の祭りであってもイスラーム教の祭りであっても、デリーで祭りを祝うのにオールドデリーほど適した場所はない。デリーの市街地拡大に従ってデリー各地で独立していろいろな祭りが祝われるようになったが、やはりオールドデリーが持つ祭りの権威は衰えていない。それに地域住民の参加度もオールドデリーにかなう場所はないだろう。
今日は、キリスト教、イスラーム教、拝火教の3つの祭りが重なるという稀な日となった。ヒンドゥー教のチョーティー・ホーリー(小ホーリー)を含めれば4つの祭りになる。オールドデリーで、イスラーム教の祭りイード・ミラードゥン・ナビーに関連した行進が行われると聞いたので行ってみた。
イード・ミラードゥン・ナビーとは、イスラーム教の開祖ムハンマドの誕生日かつ命日である。ヒジュラ暦(イスラーム教の暦)第3月ラビーウル・アッワルの第12日目に当たる。人々にイスラームの教えを広めたムハンマドがこの世にやって来たと同時に、この世から去って行った日であるため、人々は喜びと悲しみの入り混じった感情でこの日を祝う。
イード・ミラードゥン・ナビーは、エジプトを支配したシーア派王朝ファーティマー朝(909-1171年)の時代に始められた祭りで、それ以前はムハンマドの誕生日と命日を祝う習慣はほとんど見られなかったようである。アラブ世界ではほとんど祝われていないようだが、元々聖人信仰の土壌があった南アジアでは大いに受け入れられ、現在でも盛大に祝われている。
午後3時半頃にジャーマー・マスジドの1番ゲートへ行ってみると、既に多くの人々が集まっており、治安部隊も配備されていた。門の脇にはテントが張られ、小さなステージが設けられていた。午後4時過ぎになると壇上にイスラーム教徒の正装をした十数人の人間が上がり、集まった人々に挨拶を始めた。主賓は、デリー州議会議員(マティヤー・マハル選出)のショエーブ・イクバールであった。そして、アルビノっぽいお爺さんが、ムハンマドを讃える歌を歌い出した。

賛歌を歌うお爺さん
その内、ジャーマー・マスジドの西、チャーウリー・バーザールの方から行進の先頭がやって来るのが見え始めた。行進はバーラー・ヒンドゥー・ラーオの辺りから始まり、ジャーマー・マスジドは終着点に当たるようである。ひどい混雑だったが、マッカ(メッカ)のカーバ神殿やマディーナ(メディナ)のムハンマド・モスクなど、イスラーム教や預言者ムハンマドに関連するモチーフが行進して来るのが見えた。

マッカのカーバ神殿

マディーナのムハンマド・モスク

ラクダの行進

ベイビー・ムハンマド?

旗振る集団
一通り行進が終わると、集まった人々は一斉にジャーマー・マスジドの中に入って、ナマーズ(祈祷の言葉)を読んでいた。ナマーズ中はジャーマー・マスジドは非イスラーム教徒立入禁止となる。

ジャーマー・マスジドへナマーズを読みに行く
行進がバーラー・ヒンドゥー・ラーオを何時に出発したのか分からないが、ジャーマー・マスジド前で見物していた限りでは1時間ほどで行進は終了した。デリーで祝われる行進系の祭りの中では小規模な方ではないかと思うが、デリーのフェスティバル・スピリットを味わうには十分の盛り上がり方であった。
| ◆ |
3月23日(日) ブッダ・ジャヤンティー・パーク |
◆ |
北京オリンピックの開催の年である2008年、チベット問題で中国が、世界が揺れている。中国共産党政府による長年の抑圧に耐えかねたチベット人たちが起こした独立運動なのか、それとも五輪聖火のチョモランマ到達前に中共政府が反政府組織を一網打尽にするために扇動した暴動なのか、はたまた別の真相があるのか、よく分かっていないが、チベットと隣接し、チベット亡命政府を抱えるインドにとって、決して他人事ではない事件である。インドと中国は今のところ表向きは友好路線を取っているため、インドはチベット問題を外交カードに使おうとせず、中共政府寄りの慎重な姿勢を見せている。そしてインド在住のチベット人による暴力的または違法な抗議運動は徹底して取り締まられている。インドも、カシュミール問題やノースイースト問題など、完全に同様ではないにしても似通った問題を抱えているため、表立ってチベットの独立運動を支持できないという理由もあるだろう。また、日頃人権侵害問題にうるさい左翼政党や左翼団体が、チベット問題に対しては無視を決め込んでいるのは日本の状況と共通している。だが、インドは決して手をこまねいて見ているだけではなく、インド副大統領のハーミド・アンサーリーがデリー入りしたダライ・ラマと会談予定である。インドでは大統領は国事を司る役職で、副大統領ともなると要職中もっとも政治色の薄い人間となる。チベット問題に対して何もしないという批判と、チベット問題に政治的に関わったという批判の両方を交わすための苦肉の策だと思われる。
中共政府はダライ・ラマを暴動の主導者に決め付けているが、亡命政府を率い、外交力だけで国際社会の中を生き延びて来たダライ・ラマの方が一枚上手のようで、暴力を完全に否定し、オリンピック中止やチベット独立は求めていないことを予め訴えている。もし暴力が続くならば引退する覚悟もあることすらほのめかし、常に中共政府より先手を打っているように思われる。
中国とインドはアジアの二大国で、様々な共通点と様々な相違点があるわけだが、この二国に関わると必ずチベットのことを考えさせられることになるという点では共通しているように思われる。中国を旅行するのが好きな人にとってチベットは憧れの土地であるし、ラサの現状を見て心を痛めない人はいない。一方、インドを旅行する人にとっても、チベット亡命政府のお膝元であるダラムシャーラーは人気の目的地であるし、たくましく生きるチベット難民やその二世、三世の姿に励まされたり、会話の中でチラリと見せる故郷への愛着や自由の利かない身分に対するもどかしさに心を打たれたりする。また、チベット文化圏に入るラダック地方やラーハウル・スピティー地方は、少々マニアックな旅行先を求め始めた人の目に必ず留まる場所である。それらの土地を訪れると、比較的純粋な形で残っているチベット文化を目の当たりにすることができる。
チベット難民たちは、ダラムシャーラーだけでなく、インド各都市に散らばっている。元々高地に住む民族であるためだろう、彼らは避暑地や標高の高い都市に住み着くことが多いようだが、ここデリーにもチベット難民のコロニーがある。一般にはマジュヌーン・カ・ティッラーと呼ばれている(EICHER「Delhi
City Map」P24 H5, H6、表示なし、ヤムナー河沿いの住宅地)。マジュヌーン・カ・ティッラーのチベット料理は、さすがに本場の人々が作っているだけあって定評がある。それだけでなく、時代の変遷を反映しているのか、マジュヌーン・カ・ティッラーは実はデリーでもっとも充実した中華食材市場ともなっているようだ。四川料理の火鍋の材料も大体ここで手に入るらしい。
しかし、デリーの意外な場所に、チベット仏教関連のモニュメントが存在する。それは、大統領官邸の西側、セントラル・リッジの中央部にあるブッダ・ジャヤンティー・スマーラク・パークまたはブッダ・ジャヤンティー・パークである(EICHER「Delhi
City Map」P78 F6, P95 B1)。ブッダ生誕記念公園またはブッダ生誕公園という意味になる。1956年、ブッダのマハーパリニルヴァーナ(涅槃)から2500年を記念して建設された公園で、かなり広大な敷地を有している。ホーリーの1日後に訪れたところ、強烈な色彩の花々があちこちで咲き乱れており、まるで自然がホーリーを祝っているようであった。

ブッダ・ジャヤンティー・パーク
ブッダ・ジャヤンティー・パークに入って適当に歩いていると、「Buddha Statue」と書かれた道標があるので、それに従って歩いて行くと、チャトリー(東屋)の中に鎮座するブッダの銅像が現れる。金ぴかに輝いており、かなり神々しい。だが、チャトリーは、形こそ仏教建築を念頭に置いているものの、色はニューデリーのイメージカラーに合わせたスタイリッシュなもので、周辺にチベット仏教寺院にありがちな旗やら石やらもなく、不思議な雰囲気に包まれている。

ブッダの銅像
1983年、ダライ・ラマはデリーにブッダの像を寄付したいとの願望を述べた。それは、ブッダの国インドへの寄進でもあり、チベット亡命政府をかくまってくれたインドへのチベット人コミュニティーからの感謝の気持ちでもあり、インドとチベットの共通文化としての友好の印でもあった。ブッダの銅像を安置するのにブッダ・ジャヤンティー・パークが最適だということになり、以後、関係諸機関からの許可を取るための手続きが始まった。また、ダラムシャーラーから名匠が呼ばれ、1年の歳月をかけてブッダの銅像が制作された。最終的にブッダ・ジャヤンティー・パークにブッダの銅像が安置されたのは1993年であった。

ブッダのポーズはブーミスパルシュ・ムドラー
ブッダの銅像の近くには、ダライ・ラマの署名入りのメッセージがチベット語、ヒンディー語、英語で刻まれた石が置かれていた。

ダライ・ラマのメッセージが刻まれた碑文
人類は、真に人道的で、全ての人々が自由にそして何にも恐れることなく繁栄する世界を創造し、未来の世代へ託す力を持っている。だが、無視、貪欲、憎悪が、その達成までに立ちはだかっており、世界自体もそれらの要素によって危機にさらされている。
同情と忍耐、穏健と環境に対する尊敬というブッダのメッセージや、全ての生き物の協調的相互依存を重視する仏教思想は、現在根本的な妥当性を有している。
このブッダを記念する場所において、この比類のないブッダの像が捧げられた。
これは、インドに対する我々の深い尊敬と愛情の印であると同時に、ブッダによって導かれた、世界平和と恒久的幸福へとつながる道のシンボルでもある。
ビクシュ・テンジン・ギャツォ
ダライ・ラマ14世
仏教暦2537年
1993年10月2日
また、ブッダの銅像の周辺には、仏教のメッセージが刻まれた碑文があちこちに散在していた。平和、非暴力、学習などの大切さが説かれていた。そのおかげで、ブッダ・ジャヤンティー・パークはただの公園ではなく、訪れる者を啓蒙する公園になっていた。

仏教のメッセージ
死を恐れない者がいようか?
生を愛さない者がいようか?
私のように、皆が自分の生を愛している
だから殺してはいけないし、
他人に殺させてもいけない
チベット人がいくら虐殺に遭っても頑なに非暴力を貫くダライ・ラマの姿勢が、何となく感じられた。チベットで起こっていることは、いろいろな意味でダライ・ラマの非暴力の戦いの危機であるが、彼が言うように、それらを乗り越え、全ての人々が自由にかつ何にも恐れることなく繁栄して行けるような、真に人道的世界の創造が達成できたら素晴らしいことであろう。

ブッダ像の周辺はアヒル天国になっていた
| ◆ |
3月27日(木) インドへ馬鹿がやって来た |
◆ |
先日、日本文芸社から待望の「インドへ馬鹿がやって来た」が届いた。
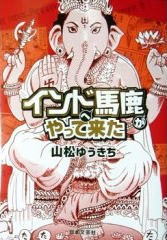
「インドへ馬鹿がやって来た」
「インドへ馬鹿がやって来た」は、漫画家山松ゆうきち氏が、インドで日本の漫画をヒンディー語に翻訳して出版するという途方もない計画を実行した体験談をもとにして描かれた漫画である。元々「月刊漫画ゴラクネクスター」2005年9月号~2006年12月号、2007年3~12月号に連載されていたものを単行本化したものだ。
山松ゆうきち氏のその計画には僕も翻訳者として加担している。平田弘史著「血だるま剣法」をヒンディー語に翻訳した。その顛末は、姉妹ブログこれでインディア エクスプレスで度々報告して来た。関連記事は以下の通りである。
翻訳に関わった身であるため、「インドへ馬鹿がやって来た」には僕も実名で登場してしまうのである。また、紹介文みたいなものの執筆を依頼されたので、ギャグ漫画の雰囲気を損なわないように頑張ってふざけた文章を書いて送っておいた。それはそのまま漫画の途中に挿入されていた。漫画には、僕だけでなく、デリーの有名日本人が軒並み登場するので、デリー在住日本人には密かに受けそうだ。
早速一通り読んでみたが、正直に言ってしまうと、期待していたよりも面白くなかった。おそらくその理由は、山松氏の失敗談を生で見聞きしていたためであろう。失敗談から来るおかしさは既にそのときリアルタイムで大部分を味わってしまっていたため、僕にとってはもはや「昨晩の夕食の残り」くらいの価値しかなかった。だが、初めて読む人には新鮮な面白さや驚きがあると思われる。
また、山松氏がインド人のしゃべることをほとんど理解していないこともじれったい部分だ。ある程度理解していて、敢えて分からなさをギャグにするのならまだ高度な笑いになったかもしれないが、本当に理解していない場面があまりに多すぎた。それはそれで面白いことには面白いのだが、そればかりだとだんだんイライラして来る。描いている人が理解していないのだから、読者には全くもってチンプンカンプンであろう。しかし、インドに長年住んでいるためか、勘で「ここではインド人たちはこういうことを言いたかったのでは」と予想できるところもある。善意でアドバイスしていたり、おそらく正しいことを言っているのだろうと思われるところもあるのだが、山松氏はやっぱり全く理解しておらず、冷淡に反応してしまっているので、だんだん彼に関わったインド人たちがかわいそうに思えて来てしまう。読み方によっては、インド人は全員悪どくてどうしようもない奴という印象を受ける読者もいることだろう。基本的な情報の間違いも多く、インド、デリー、ヒンディー語などを理解しようと思ったら、この漫画をテキストにしてはならない。あくまでお馬鹿なギャグ漫画として読むべきである。また、はっきり言って山松氏が漫画の中でしていることのいくつかは違法行為であるので、「真似しないで下さい」みたいな注意書きくらいは入れるべきだったと思う。昔からインドを旅行して来た人の中には、インドは何でもありだと思っている人がけっこういるのだが、近年違法行為の取り締まりは厳しさを増しており、10年、20年前の感覚で違法行為を行うと痛い目に遭うだろう。
しかし、山松氏の画風とインド人の行動や表情が妙にマッチしているところもあり、そういうところではやけに笑える。果たしてインドに来たことのない日本人にそういう微妙な味が理解できるかどうかは分からないが、少なくともインドを長期間旅行したことがあったり、インドにしばらく住んだことのある人にとっては、爆笑できる場面がいくつかあると思われる。
巻末には、インドで出版されたヒンディー語版「血だるま剣法」の見本が数ページ掲載されている。日本語からヒンディー語に翻訳したのは僕だが、その翻訳のまずさには僕自身が文句を言いたくなる。実物をもらったときも思ったが、今また改めて見て、なぜこんなひどい翻訳なのか・・・と頭を抱えたくなった。翻訳した時期を考えてみると、2004年の下半期。ヒンディー語修士2年目だ。あの頃の僕のヒンディー語はこの程度のものだったのか?確か時代劇っぽい雰囲気を出そうと思って、単語の選択にはいろいろ苦労した記憶があり、結果的に翻訳として全く適さない言い方や完全に誤った単語にしてしまったような気がする。だが、僕の関与していない写植の時点でミススペリングになってしまった部分もかなりたくさん見られるようだし、手書きの原稿を渡したため、正しく読んでもらえなかったものもあるのかもしれない。今となっては、どんな翻訳を自分がしたのかほとんど覚えていないが、山松氏に急かされる形で不完全な原稿を渡してしまったことだけは覚えており、それがいつまでも完璧主義者の僕には心残りになっている。
「インドへ馬鹿がやって来た」には、「血だるま剣法」ヒンディー語版出版顛末記だけでなく、インド滞在中に山松さんが挑戦したいくつかのことも取り上げられている。手品グッズやテープカッターを売ろうとしたり、競馬に挑戦して大穴を当てたり、デリーの赤線地帯GBロードへ行ったり、そちらのレポートも面白い。インド旅行を題材にした漫画はいくつかあるが、インドで何か事業を立ち上げる際に味わう苦労をここまで生々しく描写した漫画は今までなかっただろう。だから、インドで何かをしようと思っている人は、その前にこの漫画を読んでおくと、ある程度苦労のほどが想像できるようになるだろう。と言うか、この本のおかげで、これ以上インドに馬鹿がやって来なくなるかもしれない・・・。
| ◆ |
3月28日(金) One Two Three |
◆ |
先週公開された「Race」がとても調子いいようだ。「Jodhaa Akbar」と共に今年のヒット作の1本に数えられることになるだろう。今週公開の新作ヒンディー語映画は「One
Two Three」。低予算のコメディー映画である。
題名:One Two Three
読み:ワン・トゥー・スリー
意味:1、2、3
邦題:ワン・トゥー・スリー
監督:アシュワーニー・ディール
制作:クマール・マンガト
音楽:ラーガヴ・サーチャル
作詞:アーディティヤ・ダール、ムンナー・ディマン
振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ
出演:スニール・シェッティー、パレーシュ・ラーワル、トゥシャール・カプール、イーシャー・デーオール、サミーラー・レッディー、ニートゥー・チャンドラ、ウペーン・パテール、タニーシャー、ムケーシュ・ティワーリー、ヴラジェーシュ・ヒルジー、マノージ・パフワー
備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、イーシャー・デーオール、ウペーン・パテール、パレーシュ・ラーワル、
スニール・シェッティー、トゥシャール・カプール、タニーシャー、
サミーラー・レッディー、ニートゥー・チャンドラ
| あらすじ |
この物語では、3人のラクシュミーナーラーヤンが登場する。便宜的に1、2、3と数字を振って紹介する。
2億ルピー相当のダイヤモンドが盗まれた。マフィアのドンは、ダイヤモンドを盗んだポンディチェリーのマフィア、パパ(ムケーシュ・ティワーリー)に刺客を送る。選ばれたのは、駆け出しのマフィア、ラクシュミーナーラーヤン1(トゥシャール・カプール)であった。ラクシュミーナーラーヤンは、宿泊先のホテル、ブルー・ダイヤモンドで、ターゲットの写真を受け取る手はずになっていた。
サラリーマンのラクシュミーナーラーヤン2(スニール・シェッティー)は、ボスの命令に従って、ポンディチェリーに行くことになった。与えられた任務は、ビンテージカーの商談をまとめることであった。ラクシュミーナーラーヤン2は、宿泊先のホテル、ブルーダイヤモンドで、購入すべき自動車の写真を受け取る手はずになっていた。
チャーンドニー・チャウクで下着を売って生計を立てるラクシュミーナーラーヤン3(パレーシュ・ラーワル)は、息子の依頼に従ってポンディチェリーへ行くことになった。ポンディチェリーに住む下着デザイナーの下着を見るためであった。ラクシュミーナーラーヤン3は、宿泊先のホテル、ブルーダイヤモンドで、下着デザイナーの写真を受け取る手はずになっていた。
こうして3人のラクシュミーナーラーヤンは、同じ日にポンディチェリーのホテル、ブルー・ダイヤモンドに宿泊することになってしまった。レセプションが混乱したため、それぞれに違う写真が手渡されてしまう。まず到着したのはラクシュミーナーラーヤン3であった。彼は下着デザイナーの写真を受け取るはずだったが、受け取ったのはビンテージカーの写真だった。だが、その写真には水着を着たディーラーのライラー(サミーラー・レッディー)の姿も写っており、その女性に会うのだと理解した。次に、ラクシュミーナーラーヤン2は、パパの写真を受け取った。これはラクシュミーナーラーヤン1が受け取るはずの写真だった。だが、ちょうどパパは自動車に乗っていたため、ラクシュミーナーラーヤン2はその自動車を購入すればいいのだと理解した。一方、ラクシュミーナーラーヤン1は、下着デザイナーのジヤー(イーシャー・デーオール)の写真を受け取った。彼はこの女性を暗殺すればいいのだと理解した。
ところで、ダイヤモンドは実はライラーのディーラーで働くチャンドゥー(ウペーン・パテール)とチャーンドニー(タニーシャー)が持っていた。だが、彼らはほとぼりが冷めるまでダイヤモンドを隠しておこうと、ショールームに展示してあったビンテージカーのオイルタンクの中にダイヤモンドを入れた。だが、そのビンテージカーこそ、ラクシュミーナーラーヤン2が購入するはずのものだった。既にその自動車が売約済みであることを知った2人は、購入者がショールームを訪れられないようにしようと画策するがなかなかうまくいかない。
ラクシュミーナーラーヤン1は、ジヤーの経営するレストランを訪れた。ジヤーはラクシュミーナーラーヤン1のことを下着のディーラーだと勘違いし、自分のデザインした下着を渡す。一方、ラクシュミーナーラーヤン1はそれをダイヤモンドだと勘違いする。また、ジヤーが置かれた境遇に同情したラクシュミーナーラーヤン1は、彼女を殺すのではなく、守ることを決意する。そこへボスがやって来る。ボスはラクシュミーナーラーヤン1が全く仕事をしていないことを知って絶望する。このとき初めて間違った写真を受け取っていたことに気付いたラクシュミーナーラーヤン1は、ボスと共にパパの隙を見て暗殺しようとする。
ラクシュミーナーラーヤン2は、パパのアジトを訪れる。パパはラクシュミーナーラーヤンという名の刺客が送られて来ることを事前に察知しており、ラクシュミーナーラーヤン2を捕まえて拷問する。ラクシュミーナーラーヤン2は何のことだか分からないが、どうも人違いであることに気付き、ホテルにもう1人ラクシュミーナーラーヤンが宿泊していたことを伝える。それはラクシュミーナーラーヤン3のことであった。パパとその一味は、ブルー・ダイヤモンドへ忍び込んでラクシュミーナーラーヤン3の様子を伺う。
ラクシュミーナーラーヤン3はライラーのディーラーを訪れる。ライラーは、彼が自動車を購入しに来たと思って歓待するがどうも話が通じない。そこで2人はホテルの部屋へ行くことになる。下着を見せろとしつこいラクシュミーナーラーヤン3に対し、ライラーは仕方なく服を脱ぎ出す。だが、そのとき息子が部屋に入って来てしまう。ラクシュミーナーラーヤン3は窮地に陥るが、ライラーはそれに乗じて勝手に自動車の売買契約をまとめてしまう。ラクシュミーナーラーヤン3は、前金として10万ルピーを支払い、残りの90万ルピーは後でショールームへ持って行くことにする。
一方、ライラーはチャンドゥーとチャーンドニーから、ビンテージカーの中に2億ルピーのダイヤモンドが入っていることを知る。ライラーはダイヤモンドを取り出そうとし、ラクシュミーナーラーヤン3に1時間待つように電話で伝える。
90万ルピーを持ってホテルを出ようとしていたラクシュミーナーラーヤン3とその息子は、その電話があったため、90万ルピーの入ったカバンをレセプションに預ける。それを見たパパたちは、そのカバンを爆弾が入った同じカバンと取り替えることを思い付く。部下のピント(マノージ・パフワー)は爆弾作りのディプロマを持っていた。その計画を裏で聞いていたラクシュミーナーラーヤン1とそのボスは、さらにそのカバンを取り替えて90万ルピーを横取りしようとする。こうしてカバンは数度取り替えられた。
やがて1時間が経ち、ラクシュミーナーラーヤン3とその息子はカバンを持って外に出た。パパとその一味、そしてラクシュミーナーラーヤン2が後に続き、その後をラクシュミーナーラーヤン1とそのボスが尾行した。ラクシュミーナーラーヤン3はライラーのショールームへ入って行った。そこにはライラーの他、チャンドゥー、チャーンドニー、そしてジヤーもいた。なぜならそのビンテージカーは元々ジヤーのものだったからだ。だが、ラクシュミーナーラーヤン3の息子はジヤーのことを知っており、やっと父親の持っていた写真が間違いだったことに気付く。また、そこで初めてラクシュミーナーラーヤン2も、ボスから頼まれたビンテージカーがそこにあることを知って出て行く。ラクシュミーナーラーヤン1もやって来て、これでやっと3人のラクシュミーナーラーヤンが揃った。
ところで、爆弾が爆発するはずだったが、乾電池が切れていたために爆発しなかった。そこでパパの部下アルバート(ヴラジェーシュ・ヒジュリー)が乾電池を買いに出掛けた。一方、ショールームでは、ビンテージカーの中にダイヤモンドが入っていることが明らかになり、みんなで協力してダイヤモンドを取り出すことになった。やっとダイヤモンドは飛び出たが、今度はその場の人々の間でダイヤモンドの取り合いが起こる。だが、爆弾の乾電池を市場で買っていたアルバートを、警察官マーヤーワティー・チャウターラー(ニートゥー・チャンドラ)が捕まえ、ショールームに乗り込んで来る。乾電池を入れ替えても爆弾は爆発しなかったが、そのときピントは爆弾がリモート操作ではなく時限爆弾だったことを思い出す。爆発まで3秒しかなかった。あっと言う間に爆弾は爆発し、その場の人々は真っ黒になって、ダイヤモンドは粉々になってしまう。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
お馬鹿な笑いに特化したコメディー映画。細かいことを言うのは野暮であろう。何も考えずに笑うためにある映画である。同名の人間が3人も偶然一ヶ所に揃ってしまったために繰り広げられる大混乱という、半ば古典的なネタであるが、笑いの切れは鋭く、大爆笑は間違いなしである。
パレーシュ・ラーワルとスニール・シェッティーは、大ヒットコメディー映画「Hera Pheri」(2000年)や「Phir Hera Pheri」(2006年)で既にコンビを組んでいる。パレーシュ・ラーワルの方は生粋のコメディアン俳優であり、ボリウッドのお笑いレースを独走していると言っても過言ではない。本当に面白い俳優である。スニール・シェッティーは元々はヒーロー俳優で、恐ろしいマフィア役なども得意なのだが、「Hera
Pheri」シリーズのおかげですっかりコミックロールも板についた。「One Two Three」では生真面目すぎのトラブルメイカーを演じている。
この映画で意外に頑張っていたのはトゥシャール・カプールだ。彼も今まで何度もコメディー映画に出演して来たが、はまり役だったためかベストと言っていいコメディー演技をしていた。マフィアの家系に生まれながら気弱でおっちょこちょいな性格のためなかなか最初の殺人ができずにいる若者の役で、彼の性格をうまく反映していた。期待の新人ウペーン・パテールも出演していたが、本作ではオマケ程度の役割だった。彼が出る必要性を感じなかった。
女優陣はほとんど飾り程度である。イーシャー・デーオールはまだヒット作に恵まれており、「One Two Three」の中でも比較的出番の多い役を与えてもらっていたが、残りのサミーラー・レッディー、ニートゥー・チャンドラ、タニーシャーの3人はあまり芽の出ていない女優たちであり、本作でも彼女たちの運命に変化はなさそうであった。
音楽はラーガヴ・サーチャル。タイトル曲以外、耳に残るものはなかった。
シリアスな映画を吹っ飛ばすほどコメディー映画にパワーのあった2007年に比べると、今年のコメディー映画はまだ気合の入ったものが少ない。「One
Two Three」も、笑える映画ではあるが、決して質の高いコメディー映画ではない。一見どれも五十歩百歩に見えるコメディー映画にも質の良し悪しがあり、インド映画の批評をする際はそれらを見分ける鑑識眼は重要である。だが、まだ焦ることはない。きっと今年も完成度の高いコメディー映画が登場するであろう。
インドはしばしば世界最大の映画大国と称される。市場規模ではハリウッドの足元にも及ばないが、制作本数では世界一だと言われる。その制作本数の多さの秘密はインドの多言語性にある。各地の有力言語がそれぞれ映画産業を有し、毎年多くの映画を制作するため、それらを合計してインド映画全体の制作本数を算出すると自ずとその数は多くなる。ただしノリウッドと呼ばれるナイジェリアのビデオ映画産業の制作本数も驚異的で、一説ではインド映画よりも多いとされる。世界三大映画大国と言ったら、通常、アメリカ合衆国、インド、ナイジェリアになる。
インドの映画産業を代表するのはヒンディー語映画産業だ。その拠点はマハーラーシュトラ州の州都ムンバイー。かつてボンベイと呼ばれていたこの都市の頭文字「B」とハリウッドを掛け合わせ、ヒンディー語映画産業は一般にボリウッドと呼ばれている。ボリウッドは愛称であると同時に蔑称でもあり、その呼称は当事者たちの間で必ずしも好まれているわけではないが、通りのいい言葉なので「これでインディア」でもヒンディー語映画産業のことをボリウッドと呼び習わしている。だが、実はムンバイーはヒンディー語圏ではない。かと言ってムンバイーはヒンディー語が全く通じない都市ではなく、様々な事情によりむしろよく通用する都市に数えられるが、ヒンディー語が生まれ育った土地でもなければ、人々に愛される土壌のある土地でもない。ヒンディー語は北インドの言語であり、現在の州区分で言えば、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ウッタル・プラデーシュ州、ハリヤーナー州、デリー、ラージャスターン州、ビハール州、ジャールカンド州、マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州がヒンディー語圏になる。ヒンディー語の普及におけるボリウッド映画の貢献は多大なものがあり、もしボリウッドがなかったら今ほどヒンディー語はインド人全体に理解されていなかっただろうと思われる。もしかしたらムンバイーというメトロポリタンシティーでインド全体を市場として考慮しつつヒンディー語映画が制作されて来たから、多言語国家インドの中途半端な国語としてのステータスしか持ち得なかったヒンディー語が、かろうじて全インド的な広がりを持つことができたのかもしれない。だが、ヒンディー語の本拠地にヒンディー語映画産業の拠点がないことは、同時にヒンディー語の不幸の原因のひとつにもなっていると言わざるをえない。ボリウッドの映画人の大半にとってヒンディー語は最も効率的に大衆から利益を吸い上げることができる言語というだけで、そこに尊敬や愛情はない。だからヒンディー語自身が世界の偉大な言語に対して誇ることができるような本当に質の高い映画がボリウッドから出て来ることは稀である。その点では、その言語が話され愛されている場所で制作されている映画――例えばベンガリー語映画やマラヤーラム語映画など――は芸術的に質の高い映画がコンスタントに制作されているし、地元の人々がテルグ語やタミル語の映画に対して持つ熱狂をヒンディー語圏の人々に見出すことは難しい。
デリーはヒンディー語の中心地のひとつである。「ヒンディー」という言葉が指す意味は時代や場所によって異なる上に微妙な類義語が多く、しかも日本人の中には「ヒンドゥー」、「ヒンズー」と混同している人が多くてさらに話がややこしくなるが、もし便宜的に現在一般的なヒンディー語映画の台詞や歌詞で使われている言語をヒンディー語と定義するなら、それは一般にウルドゥー語と呼ばれ、現在パーキスターンの国語になっている言語もかなりの範囲まで含む大きな概念となる。そしてそのヒンディー語を育んで来た土地は他ならぬデリーということになる。もしヒンディー語圏にヒンディー語映画の拠点が出来るはずだったとしたら、それはデリーだっただろう。
デリー出身の映画人は案外少なくないものの、今のところデリーに映画産業の拠点はない。ムンバイーがヒンディー語映画産業の拠点になった理由はいくつか挙げられるが、まず前提として押さえておかなければならないのは、無声映画時代には言語別映画制作の習慣がなかったことである。トーキー映画が主流になって初めてインド映画は多言語映画制作の時代に入った。だが、それまでにインド各地には映画産業の拠点が複数出来ており、それらが地域ごと言語ごとの映画産業の下地となった。トーキー映画が主流となった1930年代半ば、ボンベイ、カルカッタ(現コールカーター)、コーラープル(現マハーラーシュトラ州の一都市)、プネー(またはプーナー)、ラーハウル(またはラホール)、マドラス(現チェンナイ)などが映画産業の拠点だった。1931年公開のインド初トーキー映画「Alam
Ara」以来、数年の内にインド映画のトーキ化、多言語化が進展し、カルカッタでは主にベンガリー語の映画が制作され、プネーはマラーティー語映画の中心地となり、マドラスではタミル語映画が作られるようになった。ヒンディー語映画は、ボンベイ、カルカッタ、プネーの三都市で主に制作されていた。映画は外来の技術であったため、映画産業の発展は英国人との交流や西洋文化との接触の多寡と密接な関係がある。当時映画産業の拠点となった都市は、昔から英国人が貿易や統治の拠点として来た都市がほとんどである。それらの都市に比べたらデリーは、いくら中世に首都としての権威を長らく誇っていたとしても、パンジャーブ地方の片隅の一地方都市に過ぎない状況になっていた。既に1911年にはデリー遷都が宣言され、英領インドの首都はカルカッタからデリーに移されていたが、新都ニューデリーが正式に開都されたのは1931年であり、しかも元々限られたエリートのみが住む政治首都として設計されたため、都市としての賑わいはカルカッタ、ボンベイ、マドラスの足元にも及ばなかった。よって、映画産業が育つ土壌に乏しかった。だが、もしヒンディー語圏にヒンディー語映画の拠点ができるなら、デリーが最有力候補地であろう。
デリーに映画制作の拠点が誕生したことはないが、過去に一度だけ、デリーはヒンディー語圏の教養層のための高品質なヒンディー語映画制作を推進する運動の拠点となったことがある。インド映画史に記される価値もないような小さく短い盛り上がりだったが、デリーがかつてボンベイの商業主義映画に立ち向かったことがあることは記憶の片隅に留めておいても損はないだろう。今日の記事の主要部分は、僕の指導教官でもあるジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のヴィール・バーラト・タルワール教授の小論文「‘सेवासदन’ पर फिल्म:
राष्ट्रीय आन्दोलन का एक और पक्ष(映画『セーワーサダン』:国民運動のもうひとつの側面)」に拠っている。
件の運動の中心となったのは、リシャブチャラン・ジャインというデリー在住の人物と、彼がデリーで発行していたヒンディー語の週刊映画情報誌「チトラパト(चित्रपट)」である。1933年から発行が始まった「チトラパト」は現在でも路上で売られているが、既に発行者や方針は完全に変わってしまっており、名前のみが原型を留めているに過ぎない。だが、発刊当初「チトラパト」が目指していたのは、ヒンディー語文学とヒンディー語映画の融合という高尚なものだった。よって、「チトラパト」には映画関連記事の他、連載ヒンディー語小説やヒンディー語文学の批評なども掲載されていた。時代を反映し、映画を通じた反帝国主義運動、独立運動、国民運動も推進されていた。
リシャブチャラン・ジャインは事あるごとにボンベイで制作される下品でいやらしくて低俗なヒンディー語映画を批判し、ボンベイの映画人たちに芸術的で高品質の映画制作に方針転換するように要求し続けた。デリーや連合州(≒現ウッタル・プラデーシュ州)を中心とした北インドは自ずとヒンディー語映画の主要な市場となっていたが、そこから遠く離れたボンベイで制作されるヒンディー語映画は、北インドの人々の文化、価値観、現実に基づいていなかった。リシャブチャラン・ジャインはそれを解決するため、ヒンディー語文学を題材にしたヒンディー語映画制作を提案し始める。この頃には既に、カルカッタのベンガリー語映画界や、プネーのマラーティー語映画界では、地元の著名な作家の主要な傑作を題材にした優れた映画が制作されていた。だが、ボンベイの映画監督やプロデューサーは、ヒンディー語文学に全く疎い人々ばかりで、ベンガリー語映画やマラーティー語映画のような状況は到底望めなかった。彼らの多くは二束三文の書生に適当に脚本を用意させて興行収入最優先の娯楽映画を撮影し、それで満足していた。むしろカルカッタの映画人の方が、ベンガリー語映画制作の片手間に、質の高いヒンディー語映画を送り出していた。リシャブチャラン・ジャインはボンベイの映画人たちに対し、まずヒンディー語文学を勉強するように促した。さらに「チトラパト」の代表団をボンベイに派遣し、ヒンディー語文学の中から映画化に適した作品のいくつかを映画制作会社に紹介することまでした。その尽力の結果、1933年末までにヒンディー語・ウルドゥー語文学の巨匠プレームチャンドの長編小説「セーワーサダン(सेवासदन)」の映画化が正式に決定した。
「セーワーサダン」の映画化に乗り出したのは、ボンベイのマハーラクシュミー・シネトーンというプロダクションである。監督はナーヌーバーイー・ワキール、主演はマスター・モーダク、ズベーダー、ジャッダン・バーイー。1934年2月5日からプロジェクトは始動し、5月には完成して、6月に公開された。原作「セーワーサダン」のウルドゥー語版題名は「バーザーレ・フスン(بازار حسن)」だったため、映画の題名は「Sevasadan Ya Bazaar-e-Husn」になった。ちなみに「セーワーサダン」とは「奉仕所」、「バーザーレ・フスン」とは「美の市場」というような意味である。1人の女性が恵まれない結婚を経て売春婦へと転落して行く様を描いた作品で、インド社会の病巣のひとつである持参金問題が主に取り上げられている。
だが、「Sewasadan Ya Bazaar-e-Husn」に関わった監督や俳優たちは、残念ながら一流に数えられる人材ではなかった。ナーヌーバーイー・ワキール監督はまだ2作しか監督経験のない新人監督であった。主演男優のマスター・モーダクもまだまだ若く、ほとんど無名の男優だった。当時、インド人女優は娼婦や芸妓がほとんどであったが、ヒロインのズベーダーも例に漏れずデリーの娼婦の娘で、彼女もまだ経験が浅かった。「Alam
Ara」(1931年)などに出演した大女優ズベーダーとは別人だが、それでも一応当時彼女は期待の新人の1人とされていたようだ。また、ジャッダンバーイーはカルカッタの有名な歌手で、「Mother
India」(1957年)のナルギスの母親に当たる人物である。ジャッダンバーイーが演じたのは、ヒロインを売春婦の道に導くきっかけを作った芸妓であり、小説の中ではとても重要な役だが、映画の中では今で言うアイテムガール的な役割に過ぎなかった。当時はプレイバックシンガーの習慣がなく、女優自身が歌も歌わなければならなかったため、ジャッダンバーイーのようなプロの歌手や踊り子が映画によく起用されていた。
「Sevasadan Ya Bazaar-e-Husn」は、ヒンディー語映画とヒンディー語文学の融合というリシャブチャラン・ジャインの夢の実現であったが、出来上がった映画はすっかりボリウッド色に染まってしまっており、売春婦となったヒロインの境遇に必要以上にスポットが当てられた低俗な映画になってしまっていた。プレームチャンド原作の映画ということでヒンディー語文学界では一定の注目を集めたが、反応は失望交じりのものがほとんどであった。興行的にも大失敗だった。その後、プレームチャンド自身もバナーラス(現ヴァーラーナスィー)からボンベイに移住してボリウッドの映画制作に関わったが、彼一人の力でボリウッドの商業主義を変えることはできず、数ヶ月の後に失望のままヴァーラーナスィーに戻って来てしまう。
リシャブチャラン・ジャインはその後も「チトラパト」を介してヒンディー語映画の質向上に努め、1942年には配給業にも手を出すが、ニティン・ボース監督の「Paraya
Dhan」(1943年)の興行的大失敗によってすぐに行き詰ってしまう。その後、倉庫が火災で焼失するなどの不幸に見舞われた。彼はカラーチーやラーハウルにもオフィスを持っていたが、1947年の印パ分離独立を機にそれらはパーキスターン側に組み込まれてしまい、さらに大きな痛手を被る。次から次へと不幸な災難に見舞われたリシャブチャラン・ジャインは遂に精神に異常をきたしてしまい、生涯回復しなかった。デリーを中心に一瞬だけ盛り上がったヒンディー語映画改革運動は、主導者の発狂という悲劇で幕を閉じたのである。
ヒンディー語映画界が現在まで抱える大きな問題のひとつは、ヒンディー語の本拠地で映画が制作されていないことである。映画に携わる人々の多くも、ヒンディー語を母語としていない。ただ単にヒンディー語で映画を作ると最も利益を出しやすいために映画の主要言語をヒンディー語にしているだけで、ヒンディー語の発展に寄与しようとか、ヒンディー語文学界との相乗効果を試みようとか、そういった考えを持った人はいない。もしインドの英語理解者人口が今の何倍にも増えて、採算の見込みが付けば、彼らは何の躊躇もなく映画の言語を英語に切り替えるだろう。実際にその動きは2002年に起こり、英語のインド映画が多数制作されたが、まだ時期尚早だったようで、すぐにそのトレンドは下火となった。だが、最近のボリウッド映画を見ると、ヒンディー語映画を自称しつつも台詞に占める英語の割合はかなり高くなっていることに気付く。ボリウッドでは、ヒンディー語地域の文化や伝統に興味を示す制作者も稀である。そのため、ヒンディー語映画はヒンディー語圏の地域の人々の文化や意識から常に遠い位置にある。舞台となるのはムンバイーばかりで、ひどい映画になると、ヒンディー語を満足に話すことができない俳優たちがアルファベットで書かれた台本を見て行き当たりばったりの演技をしている。
ただし、最近は新たな潮流も見られ、デリーで大部分の場面または重要な場面のロケが行われる映画が増えて来た。21世紀の映画の中で、デリーの特徴を捉えることに成功した映画はまず「Monsoon
Wedding」(2001年)になるが、デリー・ロケ流行の発端は「Lakshya」(2004年)だったと考えている。その後、「Rang De
Basanti」(2006年)、「Khosla Ka Ghosla」(2006年)、「Cheeni Kum」(2007年)、「Chak De!
India」(2007年)、「Sunday」(2008年)、「Black & White」(2008年)など、デリーを舞台にしたり、デリーでロケが行われたりしたボリウッド映画がコンスタントに公開されるようになった。デリーが登場する映画はムンバイーを舞台にした映画と一味違う雰囲気になる傾向があるのだが、それはおそらくデリーの緑の多さと、風景に古都としての味を加える中世から近代の歴史的建築物のおかげであろう。デリー・ロケは現在のボリウッドで一種の流行とも言える盛り上がりを見せているが、今までデリーがボリウッドから無視されて来たのが不思議なだけであり、それほど驚くことでもないだろう。またすぐにトレンドが移って行ってしまう可能性も十分ありうる。そもそも、ロケが行われることと、映画産業の拠点となることは全く異なる。
インド随一の演劇学校、国立演劇学校(NSD)がデリーにあることは、デリーにとってひとつの誇りとなっている。ヒンディー語映画界で活躍しているNSD出身者は多い。ナスィールッディーン・シャー、オーム・プリー、ラージ・バッバル、パンカジ・カプール、スィーマー・ビシュワース、イルファーン・カーン、ヤシュパール・シャルマーなどが有名であろう。だが、デリー自体に映画産業の拠点がないことには、人材はムンバイーへ流出するばかりである。一応、隣のノイダにフィルムシティーなるものがある。ウッタル・プラデーシュ州の映画産業をテコ入れするため1988年に建設された映像作品制作所だが、現在では主にTVドラマの撮影などに使われているようで、ここで撮影されたヒンディー語映画というのはあまり聞いたことがない。
昨今のボージプリー語映画の隆盛は、ムンバイー中心のボリウッド映画産業への警鐘と受け止めることができるだろう。ウッタル・プラデーシュ州東部からビハール州で話されているボージプリー語はヒンディー語の一方言に組み込まれているが、その話者は日本の人口と同じくらいおり、決して無視できない力を持っている。現在のボリウッド映画は、題材や展開があまりに都市中産階級向けになってしまったため、農村部に住む単純明快な娯楽映画を求める層にそっぽを向かれてしまった。その空白を埋める形で、地元の人々の趣向を最大限に汲み上げ、地元の言語で制作されたボージプリー語映画が、ボージプリー語地域で人気を博すようになった。ボージプリー語映画の典型的なテーマは恋愛と結婚で、作りはひと昔もふた昔も前のボリウッド娯楽映画とそっくりである。初のボージプリー語映画は1961年公開の「Ganga
Maiya Tohe Piyari Charaibo」だが、ボージプリー語映画がボリウッドの脅威となるほど支持を集めるようになったのは2005年になってからのことである。ほとんどのボージプリー語映画は低予算ながら、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州などでボリウッドの大予算映画を遥かに凌ぐ興行収入を稼ぎ出している。実際のところ、ボージプリー語地域では超期待作を除き、ボリウッド映画は映画館で上映すらされないようだ。アミターブ・バッチャンやアジャイ・デーヴガンなど、ボージプリー映画に出演するボリウッド・スターが増えて来たこともその影響力の強さを物語っている。ただ、ボージプリー語映画の大半は、パトナーなどのボージプリー語地域の都市ではなく、ムンバイーで制作されているようである。監督や制作者も必ずしもボージプリー語話者ではないようだ。つまり、ボージプリー語映画の隆盛は、ボージプリー語地域の映画人たちがボリウッド映画に対抗して自発的に盛り上げたものというよりも、元々ムンバイーの映画界で娯楽映画を作っていた人々が、ボージプリー語話者という娯楽映画の格好の顧客層を発見し、彼らの趣味に合った古風な娯楽映画を作ったのが成功しただけなのかもしれない。そうなると、ヒンディー語映画の構造とそう変わらない。
もしデリーにヒンディー語映画産業の拠点ができれば、ボリウッドに倣って「デリウッド(Delhiwood)」または「ディリウッド(Dilliwood)」などと呼ばれるようになるだろう。だが、デリウッドは過去一度たった一瞬の輝きを見せただけで、その後デリーはずっとボリウッドの娯楽路線とムンバイー中心主義の完全な支配下にあり、今のところ再起も不能な状態にあると言っていい。ヒンディー語映画の中心地がヒンディー語圏の外にある内は、ヒンディー語映画から真の芸術映画が誕生することは困難かもしれない。



