|
|
2008年まで、出演映画をかなりの高確率でヒットさせ、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進して来たスター男優アクシャイ・クマール。彼の2009年はとりあえず「Chandni
Chowk to China」という失敗作で始まり、好ましいものではなかった。4月に入り、今年2番目の主演作となる「8x10 Tasveer」が公開された。アクシャイの快進撃は2009年も続くのか、試金石となる一作である。
また、この映画はナーゲーシュ・ククヌール監督の作品でもある。「Hyderabad Blues」(1998年)や「Iqbal」(2005年)で知られた、ボリウッドの中では新進気鋭の映画監督であるが、僕は個人的に高く評価して来なかった。それでも彼の映画を見続けるのは、いつか彼の作品の良さが分かるときが来るのではないかと期待しているからである。
さて、ナーゲーシュ・ククヌールとアクシャイ・クマールの取り合わせは吉と出ただろうか?
題名:8x10 Tasveer
読み:エイト・バイ・テン・タスヴィール
意味:8×10インチの写真
邦題:タスヴィール
監督:ナーゲーシュ・ククヌール
制作:シャイレーンドラ・スィン
音楽:サリーム・スライマーン、ニーラジ・シュリーダル、ボヘミア
歌詞:イルファーン・スィッディーキー、サミール、ボヘミア
出演:アクシャイ・クマール、アーイシャー・ターキヤー、シャルミラー・タゴール、ギリーシュ・カールナード、ベンジャミン・ギラーニー、アナント・マハーデーヴァン、ルシャード・ラーナー、ジャーヴェード・ジャーファリー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
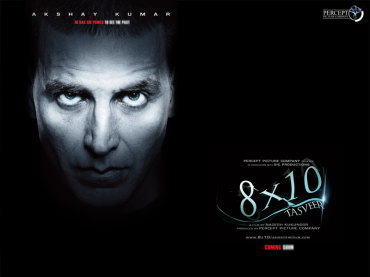
アクシャイ・クマール
| あらすじ |
カナダで森林レンジャーEPSを経営するジャイ・プリー(アクシャイ・クマール)は、写真の中に入り込み、それが写されたときの様子を知る特殊能力を持っていた。彼は滅多にその力を使わなかったが、人助けのためには使用していた。ジャイには、シーラー・パテール(アーイシャー・ターキヤー)というガールフレンドがいた。
あるとき、ジャイの父親ジャティン・プリー(ベンジャミン・ギラーニー)が急死する。ジャティンは実業家で、一人息子のジャイに会社を継いでもらいたいと考えていたが、ジャイはビジネスには全く関心がなかった。ジャティンは、死ぬ直前にもジャイに会いに来ていたが、ジャイは彼を冷たく追い返していた。ジャティンは、ボートから転落して心臓発作を起こして死亡したとされていた。その場には、母親のサーヴィトリー(シャルミラー・タゴール)、叔父のスンダル(アナント・マハーデーヴァン)、重役のアディト(ルシャード・ラーナー)、弁護士のアニル・シャルマー(ギリーシュ・カールナード)もいた。
父親の遺言に従い、遺産は全てサーヴィトリーに託されることとなった。ジャイは元から遺産を期待していなかったので何とも思わなかった。だが、そこへハビーブッラー・パーシャー、通称ハッピー(ジャーヴェード・ジャーファリー)という奇妙な探偵が現れ、父親は事故死したのではなく、殺されたのだと言い出す。最初ジャイは彼を相手にしない。だが、父親の死の直前に撮影された写真が存在するのを知り、写真に入り込む特殊能力を使って死の真相を確かめたところ、確かに奇妙な点があった。その結果、叔父のスンダルが父親に薬を飲ませていたことが分かる。だが、スンダルはその後、自殺しているのが発見される。
一見事件は解決したかのように思えたが、ジャイとシーラーが黒塗りの自動車にひき殺されそうになるという事件があり、まだ事件に関与した人物が存在することが分かる。また、ジャイは母親とアニルが抱き合っているところを目撃してしまう。ジャイには誰が犯人だか分からなくなる。そこでジャイは、もう一度特殊能力を使い、父親が死ぬ直前の様子を調査する。それによって、アディトも殺害に関与していたことが発覚する。
特殊能力を使って衰弱していたジャイは、アディトに殺されそうになるが、ハッピーの活躍により何とか危機を脱する。だが、アディトには逃げられてしまう。今度はアニルから、母親が父親の遺産を全額EPSに寄付するという話を聞き、ジャイは母親の命が危ないと直感し、駆けつける。案の定、そこには黒幕の男が来ており、母親を刺したところだった。幸い、母親の命に別状はなかった。
ジャイは、母親がつぶやいた言葉を頼りに、家の屋根裏部屋を調べる。そこからショッキングな写真が出て来る。それは、ジャイに双子の弟がいるという新事実を示すものであった。また、ジャイが特殊能力を身に付けた理由は、弟を失った悲しみであったこともこのとき分かる。両親はジャイの精神を刺激しないために弟の形見を全て片付け、カナダへ移住し、弟が最初からいなかったように装ったが、ジャイの潜在意識の中では常に何かの欠乏が訴えられていたのだった。
ジャイは、何か見逃した部分がないか確かめるため、もう一度写真に入り込むことを決める。それによって、父親が殺されたとき、ボートにはもう1人の人物が乗っていたことが分かる。それが黒幕の男であった。ところが、ジャイが特殊能力を使っている間に、ジャイのところに黒幕の男がやって来て、写真を燃やしてしまう。写真に入り込んでいるときにその写真が消滅すると、ジャイは二度と現実世界に戻って来られなくなるのだった。そしてその男は、ジャイと瓜二つの双子の弟ジート(アクシャイ・クマール)であった。さらに、ジートと一緒にいたのは、ジャイの婚約者であるはずのシーラーであった。実はシーラーはジートの恋人であり、ジートをジャイと入れ替わらすためにジャイに近付き、チャンスを窺っていたのであった。
だが、間一髪でジャイは写真から抜け出していた。だが、ピンチには変わりなかった。その絶体絶命の危機を救いに来たのはやはりハッピーだった。しかし、彼は2人のジャイを見て戸惑う。その隙にハッピーはシーラーに刺されて殺されてしまう。
ジャイは手足を鎖で縛られ、夜中にボートから湖中へ突き落とされた。だが、その前に突き落とされたハッピーの死体から銃を見つけ、それによって鎖をほどき、反撃に撃って出る。ジャイはシーラーを人質に取ってジートと交渉する。もう一度幸せな家族に戻るために。ジートはその言葉に心を動かされるが、シーラーはジャイを殺すように言う。結局、ジートはシーラーを撃ち、シーラーの撃った弾がジートを打ち抜いた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ナーゲーシュ・ククヌール監督と言えば、従来のボリウッド映画とは異なったテーマや手法の映画を作ることで知られている映画監督である。その彼が、「8x10
Tasveer」において、得意とするマルチプレックス向けクロスオーバー映画の手法を踏襲しながらも、かなり娯楽に徹したサスペンス映画に挑戦したことは新鮮な驚きであった。主人公には、写真を通して過去を見る特殊能力が備わっている。それはちょうど、先日公開された「Aa
Dekhen Zara」の逆である。だが、ストーリーをその特殊能力中心に持って行かずに、むしろ父親殺害の犯人を追うサスペンスの部分を主軸とし、その特殊能力はあくまでサイドにキープしたところに、この作品のユニークさがあった。しかも、特殊能力が備わった理由と、劇中に起こる殺人事件の黒幕とが関連付けられており、結果としてまとまりのある作品になっていた。
もちろん、サスペンスの部分のみに注目すると、真犯人が当初登場する人物の中に含まれておらず、ルール違反ということになる。だが、冒頭において、ジャイの子供の頃の記憶が伏線として提示されており、全く見当外れの脚本とも言えない。ジャイの持つ特殊能力とのバランスによって、この作品はひとつのまとまりある娯楽映画として成り立っていた。
しかし、映画から登場人物がインド人である必然性が全く感じられず、インド映画としては好ましくない進化の方向だとケチを付けることもできるだろう。映画の中でインドの要素が登場したのは、父親の遺体の司法解剖が宗教的理由で拒否されたことと、遺灰が湖に流されたことくらいである。
また、映画を最後まで見終わってから、いちいち思い返していくと、合点の行かない部分もいくつか思い付く。例えば、中盤でジャイとシーラーが黒塗りのジープにひき殺されそうになるシーンがあるが、もしそれがジートの仕業だとすると、彼の恋人であるシーラーまで傷付けようとする必要性があったのか、疑問である。
アクシャイ・クマールは、得意のアクションを織り交ぜながら、ダブルロールにも挑戦し好演していた。アーイシャー・ターキヤーはヒロインと思いきや悪役で、終盤には般若の形相で殺人を犯すシーンもある。先日アブー・アーズミーという実業家と結婚したため、クレジットはアーイシャー・ターキヤー・アーズミーとなっていた。ジャーヴェード・ジャーファリーは今回も変なしゃべり方をする変な役で、映画の笑いを一手に引き受けていた。相変わらず彼の台詞は聞き取りにくい。ボーパール弁らしいが。他に、劇作家ギリーシュ・カールナードや往年の女優シャルミラー・タゴールが出演していたことが特筆すべきである。
音楽はサリーム・スライマーンなど。挿入歌はほとんどなく、エンディングのクレジット・ロールでボヘミアの「I Got The Picture」のみがキャッチーな曲となっている。この曲ではナーゲーシュ・ククヌール監督も一瞬ながら登場する。
「8x10 Tasveer」は超能力サスペンスとでも呼ぶべき特殊なジャンルの作品だが、本筋であるサスペンスの部分は一応よく練られており、十分楽しむことができる。ただ、インドらしさに欠ける点が惜しく、典型的インド映画を求める人にはあまり勧められない。
| ◆ |
4月9日(木) プロデューサー対マルチプレックス |
◆ |
映画評のついでに度々触れて来たが、現在インドでは、映画プロデューサーやディストリビューターの組合とマルチプレックス(複合スクリーン型映画館)の間で紛争が起こっている。論点となっているのは興行収入のシェアである。
1997年、デリーのサーケートに、インド初のマルチプレックス、PVRアヌパムが開館して以来、インド全国で急速にマルチプレックスが普及した。現在インド全国に合計250館のマルチプレックスがあるとされている。マルチプレックスの登場は、おそらくトーキー映画以来最大のインパクトを映画そのものに与えた。スクリーン数が増えたことで、今まで映画祭でのみ日の目を浴びていた芸術映画、社会派映画、実験的映画も一般公開の機会が得られるようになり、それらのいくつかは娯楽映画と比べても遜色ない興行収入を稼ぎ出した。それに勇気づけられた映画メーカーたちは、興行を目的としながらも高品質の映画の制作に挑戦するようになり、芸術映画と娯楽映画の垣根は徐々に取り払われていった。芸術映画と娯楽映画の中間を行く映画は、クロスオーバー映画やマルチプレックス映画などと呼ばれている。マルチプレックスの普及に伴い、マルチプレックスで常に映画を鑑賞するマルチプレックス層と呼ばれる新たな観客層も生まれた。彼らの正体は都市在住の上位中産階級であり、新興富裕層(ニューリッチ)とかモールマニアなどと呼ばれる層と合致する。彼らはハリウッド映画やその他の外国映画もよく見ており、映画に都会的センスと斬新なストーリーを何より求める敏感な観客層である。従来の大スター中毒型観客とは根本的に異なる。また、一般的映画館に比べてマルチプレックスのチケットは高価であるため、興行収入も自然と多くなる。現在、ボリウッド映画の興行収入の65%はマルチプレックスから来ているとされる。よって、マルチプレックスでヒットした映画は、単館でそっぽを向かれようと、ヒット映画として記録される。最初からマルチプレックス専用に映画を作っても問題ない環境が整った。メーカーと観客の利害は一致し、こうしてマルチプレックス層のためのマルチプレックス映画がボリウッドの主流となった。
だが、マルチプレックスがインド映画ビジネスの中心に君臨するようになるに従い、プロデューサーやディストリビューターと、エグジビターであるマルチプレックスの間で摩擦も生まれるようになった。要は、興行収入の何%がマルチプレックスの懐に入り、何%がプロデューサーやディストリビューターの取り分になるか、という争いである。マルチプレックスの力は一部で「マフィア」と形容されるほど強大なものとなっており、通常のプロデューサーはマルチプレックス側の要求を呑む以外に方法がない。しかし、ヤシュラージ・フィルムスやヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーなどのような大手プロダクションはマルチプレックスに対して強気に出ることが多く、交渉が決裂した場合、当然のことながらその新作はマルチプレックスで公開されなくなる。話題作がマルチプレックスで公開されないということは実際に過去に度々あった。「Fanaa」(2006年)や「Lage
Raho Munnabhai」(2006年)などがその犠牲となったし、最近では「Delhi-6」(2009年)もギリギリまで交渉が行われていたようである。インドの伝統的な封切り日である金曜日を前にした、プロデューサー、ディストリビューター、マルチプレックスの間の攻防はもはや日常茶飯事になっており、その状況を正すために、今回プロデューサーやディストリビューターが一丸となって具体的な抗議活動に出たというのが経緯である。彼らは4月以降、マルチプレックスに新作を提供しないことを決定した。映画のボイコットである。おかげで、今後数ヶ月間、話題作がほとんど公開されない可能性がある。
プロデューサーやディストリビューター側が要求しているのは50:50のシェアである。つまり、税引き後の興行収入の半分をマルチプレックスの取り分とし、残りの半分をプロデューサーとディストリビューターの取り分とするというシステムである。興行収入は純粋に映画のチケット売り上げから発生する収入で、映画館内での飲食物の売り上げなど、付加的な収入は含まれていない。今までは、第一週の興行収入の48%がプロデューサーやディストリビューターの取り分となり、客の入りに従って第二週は35~65%、第三週は25~75%の範囲で決定されるのが通例であったようだ。どうも、プロデューサー側が50%以上の配分を要求するとマルチプレックスが「ノー」を突き付け、交渉が難航するというのは今までのパターンだったようだ。
プロデューサー側のその要求に対し、マルチプレックス側は、興行収入に応じたフレキシブルなシェア配分を要求している。つまり、映画がヒットした場合はプロデューサー側の取り分も多くなるが、フロップに終わった場合は取り分を減らしてマルチプレックスの損失をなるべくカバーするというシステムである。しかし、具体的な数字には言及しておらず、どうフレキシブルになるのか不透明である。
元々4月には話題作公開の予定がなかったこともあり、双方まだ余裕の態度で、現在歩み寄りはほとんど行われていない。
この論争の根源を探っていくと、それはおそらく現代の観客の趣向の多様化に行き着くのではなかろうか?プロデューサーもエグジビターも、どのような映画がヒットするのか全く予想できない時代が到来したと言っていい。かつてはスターが観客を呼び込むための最大の要素だった。今でもそれは完全には過去のものとなっていない。だが、マルチプレックス時代において、スター・パワーだけでは映画はヒットしない。ここ最近アクシャイ・クマールは大当たりで、彼が人気女優ディーピカー・パードゥコーンと共演した「Chandni
Chowk to China」(2009年)は大ヒットが予想されていた。だが、この作品は大コケしてしまった。その一方で、意外な低予算映画がサプライズ・ヒットを飛ばすことも増えて来た。「Khosla
Ka Ghosla」(2006年)や「Bheja Fry」(2007年)がその一例である。それでも、全ての高品質低予算映画がヒットするわけでもなく、公開してみなければ分からないという状況が続いている。昔から映画は博打と言われていたが、多様な観客を扱うマルチプレックスはさらに映画産業を困難なギャンブルに突き落としているように感じる。そのような状況の中で、プロデューサーやディストリビューターは興行収入の安定確保を求め、マルチプレックスは興行のリスクを減らそうとしている。双方の利害が激突することで、今回の紛争が勃発したのだろう。
この新作空白期間、各マルチプレックスはそれぞれ対策を練っているようだ。ハリウッド映画新作の公開を拡大するところもあれば、過去のヒンディー語映画のリバイバル上映や、映画祭受賞作品の公開を行うことを計画しているところもある。スクリーンをIPL(クリケット・リーグ)の生中継に使うところもあるようだ。インド映画ファンにとっては何とも退屈な期間になりそうである。

デリーの歴史を紐解く内に、様々な時代において、ハーンスィー(Hansi)とヒサール(Hissar/Hisar)という町の名によく出くわした。どちらも、デリーから北西方向に伸びる国道10号線(NH10)を150~180kmほど行った地点にある町で、現在ではハリヤーナー州に属している。ヒサールの方は同名県の県庁所在地であり、2001年の国勢調査によれば人口25万人ほどの中都市であるが、ハーンスィーの方はヒサール県内の小さな田舎町である。ハーンスィーからヒサールにかけての地域は鉄鋼業や綿工業が有名らしいが、観光マップの中では目にすることはない。そもそもハリヤーナー州自体、観光地に乏しい州である。だが、ハーンスィーとヒサールは歴史の中では非常に重要な地位を占めている。なぜなら、これらの都市は古代からの北インドの大動脈である幹線上にあったからだ。つまり、これらの都市は、西アジア、中央アジア、ガンダーラ、ラーハウル(ラホール)、ムルターンなどパンジャーブ以西の地域と、デリー、マトゥラーなどパンジャーブ以東の地域を結ぶ重要なルート上に位置していたのである。インド亜大陸への侵略者の多くはこのルートを通って進撃して来ていたため、防衛側としては首都デリーを守るための最後の防衛拠点として、侵略側としては北インドにくさびを打ち込むための攻撃拠点として、非常に重要な場所だった。とは言っても、インドでは、かつて栄華を誇っていた都市が今ではただの田舎町に凋落し、見るべきものもほとんど残っていない、ということも少なくない。だが、調べてみたところ、ハーンスィーもヒサールも観光するに値するものが今でも一応いくつか残っていることが分かり、いつか足を伸ばしてみたい場所として記憶されていた。足を伸ばす、というのはつまりバイクで行くということだ。デリー近辺のツーリング・スポット開拓は、インドでバイクに乗り出して以来、ライフワークのひとつとなっている。
デリーとハーンスィー・ヒサールの接点は大まかに考えれば4点にまとめられるだろう。ひとつはプリトヴィーラージ・チャウハーン3世の時代、つまり12世紀。「ディッリー・ナレーシュ(デリーの王)」と称されるプリトヴィーラージ王が建造したとされる城塞がハーンスィーに残っている。ふたつめはデリー・サルタナトのトゥグラク朝第3代皇帝フィーローズ・シャーの時代、つまり14世紀。ヒサールはデリーの皇帝フィーローズ・シャーによって築かれた町で、トゥグラク朝時代の建築物が残っている。みっつめはチシュティー派聖者同士の交流である。ハーンスィーにはチシュティー派スーフィー聖者の一大拠点があり、デリーを拠点としたスーフィー聖者たちともコンスタントに交流があった。時代で言えば13世紀~14世紀である。よっつめはアングロ・インディアンの英雄ジェームズ・スキナーの時代、つまり19世紀。ジェームズ・スキナーは、「スキナーズ・ホース」と呼ばれる軽騎兵隊を組織し、19世紀に北インド各地で起こった戦争で縦横無尽の活躍をした軍人であった。ジェームズ・スキナーは主にムガル朝末期のデリーで暮らしていたが、ジェームズ・スキナーの荘園や別荘がハーンスィーにあり、彼が没したのもこの地で、所縁が深い。ハーンスィーやヒサールはデリー近郊の最重要軍事拠点だったため、他にも歴史上デリーとの接点はいくつもあるが、観光できるものを挙げて行くとこれだけになる。
しかし、ハリヤーナー州観光局はあまり積極的にハーンスィーやヒサールの辺りをプロモートしていないようで、これらの都市に関する観光情報はほとんどなかった。外国人が宿泊するのを嫌がらない宿泊施設があるのかも不明であった(テロの影響で最近外国人に冷たい宿が増えて来た)。距離にして片道150~180kmというのは、観光と合わせると日帰りツーリングには過酷な旅程となる。どうしてもどこかで宿泊しなければならない。ガイドブックに載っているような有名な観光地だったら、何も考えずに飛び込んでも宿はピンからキリまで見つかることがほとんどだが、近年僕が精力的に旅行しているマイナー観光地では、宿探しに多大な労力を要することが常である。なるべくなら予約できるようなホテルがハーンスィーかヒサールに欲しかった。ツーリングに絶好の場所にありながら、今まで二の足を踏んでいたのは、ひとえに宿の心配からであった。
4月に入り、ぐんぐん暑くなるかと思われたが、季節外れの雨が数日間続けて降り、デリーの気温はそれほど上昇しなかった。この時期の雨は農作物に悪い影響を与えるのだが、都市在住の一般市民にとって酷暑期の雨は自然からの思いがけないサプライズ・ギフトであり、心地よい気候の日が続いた。さらに、デリーでは4月に入ってからやたらと祝日が続き、ちょうど日本のゴールデンウィークのような状態となっていた。俄然、ツーリングへの欲求が沸いて来た。ラーム・ナヴミー(ラーム生誕祭)のおかげで形成された3連休(4月3日~5日)は下痢で寝込んでいて潰れてしまったのだが、グッド・フライデー(聖金曜日)のおかげで形成された3連休(4月10日~12日)はどこかへ行けそうだった。
ツーリングの目的地を思案しながらネットサーフィンをしていたところ、偶然ハーンスィーにあるヘリテージホテル(古い城塞、宮殿、邸宅などを改造したホテル)に目が留まった。ハーンスィーのような観光マップ空白地にヘリテージホテルがあるのは意外であった。しかもそれほど高くない。リーズナブルなヘリテージホテルに宿泊するのも僕の長年の趣味のひとつであり、このホテルのおかげで、ハーンスィー・ヒサールへのツーリングとヘリテージホテル宿泊を一挙両得できる可能性が出て来た。ホテルの名前はシェークプラー・コーティー。ヘリテージホテル・チェーンウェルカム・ヘリテージのプロパティーである。しかし、このホテルを発見したのは3連休の前日であり、空き室があるか不明であった。よく見たら、オフィスの住所はジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)から目と鼻の先のバサント・ローク。まずは電話で問い合わせたが、インドでは日常茶飯事の「調べてコールバックします→いつまで経っても電話なし」の痛恨コンボを喰らったので、直接オフィスに出向いて状況を確認してみた。そうしたら宿泊できることになり、急遽3連休を利用したツーリングが決定したのであった。ちょうど、4月1日から9月30日までの間、サマーパッケージが提供されており、2泊3日がお得な料金で宿泊できた。全食付き、税込みで7500ルピーであった。このホテルを拠点にハーンスィーとヒサールを観光することにした。
グッド・フライデーで祝日の4月10日(金)午前7時半にカールカージーの自宅を出た。折からの涼しい気候のおかげで、この時間にバイクで走行するとまだ震えるほど寒い。リングロードを使ってデリーを時計回りに回り、パンジャービー・バーグの交差点で国道10号線(NH10)に乗って、そのまま西を目指した。デリー・メトロの工事が行われており、祝日の早朝にも関わらず混雑していたが、何の問題もなくデリーを抜けてハリヤーナー州に出ることが出来た。
午前8時半頃にバハードゥルガルを通過した。バハードゥルガルは、グルガーオン、ファリーダーバード、ノイダ、ガーズィヤーバードなどと共にセントラルNCR(中央首都圏)を構成する衛星都市のひとつであるが、まだ発展は立ち後れていた。だが、メトロが延び、道路が整備されれば、今後グルガーオン並の発展をする可能性は秘められている。バハードゥルガルまでは交通量の多いゴミゴミとした道であったが、バハードゥルガルを越えると、田舎の国道の風景となった。
午前9時頃に、道端にあったカナク・ダーバーという安食堂で休憩を取った。この時間になってもまだ風は冷たく、まるで2月にツーリングしているような気分であった。チャーイで身体を温めた。
午前9時半に出発し、NH10を進んだ。この辺りは道路の拡張工事の真っ最中であった。片側1車線、中央分離帯なしの危険な道だが、道路が拡張されれば、片側2車線、中央分離帯ありのマシな道になりそうだ。対向車に注意しつつ慎重に走行して行くと、午前10時頃にはロータク(Rohtak)に到着した。ロータクは同名県の県庁所在地で、ハリヤーナー州中部の中心的な中規模都市である。ロータクにはバイパスがあるため、市中を通らずに通り抜けることができた。
午前10時45分頃、メヘム(Maham)という町を通りかかった。崩れ掛けの古いモスクが残る歴史のありそうな町であった。このメヘム周辺から、怒濤のスピードブレーカー村落地帯が始まった。この辺りのNH10上に位置する村々は、お互いに競い合うようにハードなスピードプレーカーをいくつも設置しており、通行する車両を困らせていた。スピードブレーカーを設置すること自体は文句ないのだが、スピードブレーカーの作りが悪いため、四輪車も二輪車も底をガリガリとやられてしまうのである。しかも、底をガリガリ言わして通って行く車を村人たちが面白がって見物していた。バイクはまだ脇を通ればダメージを最小限に抑えられたが、軽自動車などはスピードブレーカーごとに苦労しなければならず、大変そうだった。何かNH10を通行する車両に恨みでもあるのだろうか?スピードブレーカーができるまでは、国道を猛スピードで走行する車両によって多くの村人たちが命を奪われていたのかもしれない、などと村人寄りの妄想しつつ、ガリガリと通過した。
午前11時半には、本日の目的地ハーンスィーに到着した。ハーンスィーに着けば看板などがあってシェークプラー・コーティーまでの道筋は自然に分かるかと期待していたが、そのようなものは全く見当たらないままハーンスィーの町を通り抜けてしまった。こんなこともあろうかと、シェークプラー・コーティーの電話番号をネットで見てメモして来ていた。早速電話を掛ける。しかし、「この電話番号は現在使われておりません」のアナウンス。こうなったらと、そこら辺の人に聞いてみる。「シェークプラー・コーティー」はどこかと聞いてもいまいち反応は鈍いが、「シェークプラー」はどうも有名な地名のようで、それなら誰でも道を教えてくれた。ちなみに、「シェークプラー・コーティー」とは、「シェークプラーの邸宅」みたいな意味である。このホテルはその名前からシェークプラーにあることが予想されたので、まずはシェークプラーへ行くことにした。
シェークプラーはハーンスィーの郊外にある村であった。デリー方面から来た場合、ハーンスィー市内へ入る手前、町から2kmほどの地点で右折しなければならない。その道はやがて二手に分かれ、左はバルワーラーへ、右はジーンドへ行く道となっているが、シェークプラーへ行くには右のジーンド行きの道へ進路を取る。そのまま用水路に沿って行って出会う最初の集落がシェークプラー村であるが、シェークプラー・コーティーは、シェークプラー村に入る前に右手に見える邸宅のことである。村人に「コーティーはどこか?」と聞いたらすぐに教えてもらえた。

シェークプラー・コーティー遠景
しかし、ヘリテージホテルであることを示す看板はここまで一切なし。邸宅の入り口にも何もなかった。唯一、「アルヴィンド・チャウドリー」という表札があった。よって、最初は私有地なのかホテルなのか釈然としなかった。恐る恐る建物の近くまで行ってみたが、人の気配がない。しかし、目の前にある建物は、ウェブサイトで見たものと同一のように思えた。そこで、ウェルカム・ヘリテージの担当者に電話を掛けて確認したところ、ここがシェークプラー・コーティーに間違いないことが分かった。ドアを開けて呼んでみたら、ちゃんと給仕もいた。どうやら今のところ誰も宿泊客がいないようだった。この時点で既に正午を過ぎていた。

シェークプラー・コーティー 側面玄関
ウェルカム・ヘリテージのウェブサイトによると、シェークプラー・コーティーは築150年のようだが、なぜこのような田舎にこのようなフランス・シャトー式の大邸宅が存在するのかには全く触れられていない。ジェームズ・スキナーとの関連も不明である。ただ、マネージャーとの会話の中から、現在この邸宅を所有しているのは表札の通りチャウドリー一族で、この一家はハーンスィー一帯で強大な権力を握っていることだけは分かった。現在アルビンド・チャウドリー氏はデリーのニューフレンズ・コロニーに住んでいるらしい。シェークプラー・コーティーがヘリテージホテルとしてオープンしたのは3年ほど前のことのようだ。

シェークプラー・コーティー 正面玄関
シェークプラー・コーティーは客室6室のみの小さなホテルである。早い者勝ちベースなのか、それとも外国人びいきなのか、客室の中で一番大きな部屋に宿泊させてもらえた。しかし、まだホテルとしての運営に慣れていないのか、ホテルに宿泊していると言うより、裕福な家庭に居候させてもらっているような感じだった。邸宅の至る所にチャウドリー家の私物と思われるものが置かれており、バスルームを含め、ホテルとしての設備も整備が不足していた。掃除も行き届いていない部分が多かったし、給仕のサービスも全く洗練されていなかった。それでも、このような不慣れなヘリテージホテルは逆に言えばフロンティアのような価値を持っており、発見の喜びの方が大きかった。外国人宿泊客が過去にいなかった訳ではないだろうが、マネージャーとの会話から、仕事でハーンスィー周辺に来てここに泊まった外国人はいれど、やはりわざわざここに宿泊しに来る物好きな外国人観光客はほぼ皆無であることがうかがわれた。

大理石の階段
とりあえず昼食を出してもらえることになったが、全く準備がなかったようで、出て来るまで非常に時間がかかった。それでも、長距離を走行して来て疲れていたので、昼食までいい休憩になった。料理も家庭料理ならではのマイルドな味付けで好感が持てた。特にラーイター(野菜入りのヨーグルト)がおいしかった。スパゲッティーなどのコンティネンタル料理も出すようだが、そういう料理が作れそうな雰囲気が感じられなかったので、宿泊中は朝食を除き常にインド料理を注文した。多分正しい選択だっただろう。

客室の一室
金曜日から土曜日にかけては、他にもインド人の宿泊客が泊まっていたが、立ち入った会話をする機会がなかったために、彼らがどういう人たちなのかは分からずじまいだった。土曜日から日曜日にかけては他に宿泊客がおらず、広い邸宅を独占することができた。しかし、夜の大邸宅はどうしてもお化け屋敷を想像してしまう。ちなみに、マネージャーや給仕は、邸宅の東側にある離れに住んでいる。

1階応接間
娯楽施設としては、ビリヤード台と卓球台がある。しかし、ビリヤードのボールや卓球用具は見当たらず、遊ぶことはできなかった。他にボードゲーム類がいくつかあったが、これらもチャウドリー氏の私物のような感じであった。ホテルのハイライトとして「蔵書数豊富なライブラリー」と書かれており、実は結構期待していたのだが、子供向けの本が多く、大した本はなかった。しかし、1940年代ぐらいに発行された古い本がいくつかあり、例えばマハートマー・ガーンディーの75歳誕生日を記念して編集された「Gandhiji」という本はとても貴重であった。結局、シェークプラー・コーティーにおける、頼りになる暇つぶしの娯楽道具はテレビのみということになる。停電が多かったものの、電気が来ているときはテレビはちゃんと映った。ちなみに、2階のビリヤード室には巨大なソニーのテレビが設置されていた。ソニーの大型テレビをしっかり持っているところは、インドの金持ちの典型だ。

2階ビリヤード室
シェークプラー・コーティーは、道標から客室まで、今のところホテルとしての環境が全く整っていないため、至れり尽くせりの滞在を求めるハイエンドのツーリストには向かないだろう。まだ外国人宿泊客を受け容れる態勢も万全ではない。ヒンディー語ができないと辿り着くことも出来ないかもしれないし、たとえ辿り着いたとしても、スタッフとの意思疎通に苦労しそうだ。築150年のフランス式邸宅と言えば聞こえはいいが、このような豪奢な家屋はデリーやグルガーオンに住むパンジャービー成金たちが好んで建てており、実は取り立てて珍しい訳でもない。だが、豪邸に居候しているような疑似体験を楽しむことができるのは、他のプロフェッショナルなヘリテージホテルにはない特徴だと言えるだろうし、ハーンスィー・ヒサールの観光をしようと思ったら、現在のところシェークプラー・コーティーぐらいしか宿泊施設のまともな選択肢がないことも強みになっている。

サーバント・クォーター
さて、昼食を食べ終えた後はハーンスィー観光に出掛けた。まず向かったのはアスィガルである。ハーンスィーの北郊に位置している。アスィガルとは「刀剣の城塞」という意味で、ハーンスィーがかつて刀剣製造の一大拠点だったことと関連していると考えられるが、アスィガルがいつ誰によって最初に築かれたのかについては諸説あってはっきりしない。紀元前4世紀頃に活躍したとされる文法家パーニニが既にアスィまたはアスィカーの地名を記述している上に、アスィガルからはその時代と矛盾しない出土物も発掘されていることから、紀元前からこの地が名の知られた町だったことは確実だと思われる。だが、一般に信じられているのは、12世紀の英雄プリトヴィーラージ・チャウハーン3世によって建造されたという伝説である。
シェークプラーからアスィガルまでは、バルワーラー・バイパスを使って容易にアプローチできる。バルワーラーとジーンドへ行く二手の道が分かれていた場所まで戻り、バルワーラー行きの道へ行けば、アスィガルの裏手に回ることができるのだ。そのまま旧市街の中を道を、なるべく上へ上へと傾斜している道を取りながら進んで行った。旧市街の一番高い所に城塞があるだろうとの勘を働かせたのだが、いつの間にか門をくぐって旧市街の外に出てしまった。だが、振り返って見るとそれはバルスィー門であった。ハーンスィーの旧市街はかつて城壁で囲まれており、5つの門があるのだが、バルスィー門はその中でもっとも壮麗な門で、ハーンスィーの観光名所のひとつとなっている。デリー・サルタナトのアラーウッディーン・キルジーによって1304~05年に建造された。

バルスィー門
バルスィー門周辺で道を尋ねてみたところ、やはりアスィガルは門をくぐった旧市街の中にあるようだった。来た道を引き返し、そのまま言われた通りに進んで行くと、目の前に土の壁が見えて来た。それがアスィガルだ。観光地として整備中のようで、歩道の舗装作業が行われていた。

アスィガルの城壁と門
アスィガルの内部はほとんど平らな更地となっている。その広大な荒れ地の中に、貯蔵用または避暑用と思われるテヘカーナー(地下室)、雨水を蓄える貯水池、モスクなどがポツポツと建っていた。近年補修されたようで、保存状態は良い。

テヘカーナー
中でも興味深かったのはモスクである。デリーのクッワトゥル・イスラーム・モスク(通称クトゥブ・モスク)やアジメールのアラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーなどと同様に、ヒンドゥー教またはジャイナ教の寺院の建材が流用されていた。第2次タラーイーンの戦いでプリトヴィーラージがムハンマド・ガウリーに敗れた後、デリー、アジメール、ハーンスィーなど北インドの重要都市はイスラーム教勢力の支配下に置かれた。よって、ハーンスィーに残る建築物に、デリーやアジメールと共通の特徴が見られても不思議ではない。モスクは明らかに13世紀以降のいわゆるイスラーム時代のものだが、ガイドを買って出たお爺さんはこの建物を「プリトヴィーラージの宮殿」と解説していた。また、モスクの裏手には井戸があり、その上に石の梁が渡してあった。それもおそらくイスラーム時代以前のものであろう。その梁の上には馬のひずめのような跡があり、地元の言い伝えではプリトヴィーラージと関連づけられているようであった。

モスク
左下は馬のひずめの跡とされる
アスィガルにはもうひとつジャイナ教関連の史跡が残っている。城塞の西の端に、ポツンと柱、足跡、小さな像の3点セットが残っているのである。プリトヴィーラージ以前の時代からこの高台の地にはジャイナ教寺院があったのだろう。

ジャイナ柱
アスィガルを見終えた後、今度はダルガー・チャール・クトゥブへ向かった。ダルガー・チャール・クトゥブはハーンスィー旧市街の西に位置している。ここは、アジメールに定住したスーフィー聖者モイーヌッディーン・ハサン・チシュティー(1141-1230年)から始まるインド・チシュティー派と所縁の深いダルガー(聖廟)で、ジャマールッディーン(1187-1261年)、ブルハヌッディーン(1261-1300年)、クトゥブッディーン・マヌワル(1295-1358年)、ヌールッディーン(1325-1397年)ら4人のスーフィー聖者が埋葬されている他、ファリードゥッディーン・ガンジシャカル、通称バーバー・ファリード(1173/88-1266/80)のチッラーガー(祈祷所)が残っている。バーバー・ファリードは、モイーヌッディーンの弟子でデリーを拠点とした聖者クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー(1173-1235年)の弟子で、彼の聖廟はパーキスターンのパンジャーブ州パークパッタンにある。チャール・クトゥブに埋葬されているジャマールッディーンはバーバー・ファリードの一番弟子で、後継者に目されていた人物だったが、バーバー・ファリード存命中に没した。そのため、デリーのニザームッディーン・アウリヤー(1238-1325年)がバーバー・ファリードの後継者となり、チシュティー派指導者の座を継いだのだった。チャール・クトゥブに埋葬されている他の3人の聖者はジャマールッディーンの子孫である。バーバー・ファリードはクトゥブッディーンが死去する前にハーンスィーに12年間滞在しており、彼が祈祷を行っていたとされるチッラーガーがチャール・クトゥブの境内に残っている。ちなみに、バーバー・ファリードの祈祷所とされる場所は各地に残っているようで、デリーにも存在する(参照)。また、ニザームッディーンや、彼の後継者に当たるナスィールッディーン・チラーグ・デリー(1274-1356年)もハーンスィーのチャール・クトゥブを訪れたことがあった。このように、ハーンスィーのチャール・クトゥブはデリーのスーフィー聖者たちと深い関係にある場所なのである。ダルガーの隣には、フィーローズ・シャー・トゥグラクによって建造されたモスクも残っている。

ダルガー・チャール・クトゥブ
深緑色のシェルターの下にあるのがバーバー・ファリードの祈祷所
ダルガー・チャール・クトゥブを見終えた後はシェークプラー・コーティーに帰った。本日の走行距離は183.7km。
「ヒサール」はアラビア語で「城」という意味である。ヒサールは1354年にデリー・サルナタトのトゥグラク朝皇帝フィーローズ・シャーによって築かれた要塞であり、元々「ヒサーレ・フィーローズ(フィーローズ城)」と呼ばれていた。ムガル朝時代にそれが短縮されて「ヒサール」と呼ばれるようになったようだ。今でもヒサールにはフィーローズ・シャーの時代の建築物が残っている。ヒサールはハーンスィーから西に25kmの地点にある。
また、ヒサールからさらに25kmほど先へ行った場所にアグローハー(Agroha)という町があり、そこにアグローハー・マウンドの名で知られる古い遺跡があるとの情報も得ていた。ヒサール観光前にまずはアグローハーを見てみることにした。
シェークプラー・コーティーで朝食を食べた後、午前9時半に出発した。ハーンスィーの市街地を通り抜け、NH10を西へ進んで行くと、まずはヒサール・カントンメントが現れる。英領時代にこの辺りは軍の駐屯地になり、独立後もそのままミリタリー・エリアとして利用されている。ヒサール・カントンメントを過ぎるとやがて馬に乗ったプリトヴィーラージ・チャウハーン3世の銅像が現れる。ヒサールの向こうのアグローハーへ抜けるバイパスもあったが、敢えてヒサールの町中に入って様子を見ることにした。さすがにヒサール県の県庁所在地だけあって、ハーンスィーとは比べものにならないほど都会であった。まずはショッピング・コンプレックスやモダンな住宅街などが並ぶ新市街があり、それを抜けると旧市街に出た。旧市街を越えると既にヒサールの外に出ており、バイパスと合流していた。そのままNH10を走行し、午前11時頃にアグローハーに到着した。
アグローハー・マウンドは、巨大な寺院コンプレックスの隣、アグローハー医科大学の目の前にある。入り口は分かりにくいが、一応ヒンディー語の看板があった。アグローハーはタクシュシラー(タキシラー)とマトゥラーを結ぶ幹線上に位置しており、かつてはここに大きな町があったとされる。アグローハー・マウンドでは城壁、仏教ストゥーパ・僧院跡、砦などの遺構が残っている他、発掘調査により、紀元前2~3世紀から紀元後13~14世紀にかけての様々な出土品が見つかっている。

厚い壁と稜堡を持った四角形プランの遺構
アグローハー・マウンドは、一応歩道が整備され、遺跡も修復されており、観光客を迎え入れる準備が出来ていたが、辺り一面には土器の欠片や古いレンガなどが散乱しており、少し地面を掘ればまだいろんなものが出て来るのではないかと思われた。言わば、まだ発掘途中のような雰囲気であった。このような中途半端な状態で一般開放してしまっていいのか、ちょっと心配になった。

仏教ストゥーパ・僧院跡
アグローハー・マウンドを見終わった後はNH10を引き返し、正午頃にヒサールに戻って来た。ヒサールの最大の見所はフィーローズ・シャー・トゥグラクが建造した宮殿・城塞跡である。地元ではグジュリー・マハルの名で知られている。ヒサール市内を通るNH10上にあるので、バイパスを通らずにヒサールを通り抜ければ、旧市街エリアにグジュリー・マハルを見つけることができるだろう。

フィーローズ・シャーの宮殿
この遺跡がグジュリー・マハルと呼ばれるのには理由がある。言い伝えによると、狩りが大好きだったフィーローズ・シャーは、ヒサールの辺りに狩りに来ていたときに、地元のグッジャル(酪農民)の娘と恋に落ち、結婚した。彼女はその出自からグジュリー・マハルと呼ばれた。だが、グジュリー・マハルは皇帝と共にデリーに行くことを拒んだため、フィーローズ・シャーはヒサールに宮殿を建て、彼女を住まわせたのだった。そのため、フィーローズ・シャーの宮殿と城塞はグジュリー・マハルとして知られている。ただし、何度も繰り返すように、ハーンスィー~ヒサール~アグローハーは古代からの主要幹線上に位置しており、フィーローズ・シャーがこの地に城塞を築いたのも、軍事的・経済的な目的からだったと容易に推測される。また、アグローハー・マウンドからの出土品はフィーローズ・シャーの時代までで途絶えており、ヒサールが開かれてからこの地域の中心地はヒサールに移ったと考えられる。さらに、灌漑にも類い稀な関心を示したフィーローズ・シャーはヒサールのために用水路まで引いている。グッジャルの娘との恋物語は、話としては面白いが、フィーローズ・シャーがもっと現実的な目的のためにヒサールを築いたことは明らかで、おそらく民間伝承の域を出ないだろう。
フィーローズ・シャーの宮殿ではガイドが案内してくれた。宮殿の大部分は日光の届かない迷宮となっており、ガイドに懐中電灯で照らして案内してもらわないと迷いそうだ。柱が林立する謁見の広間、水を利用した空冷設備、馬に乗りながら上階まで上ることができる物見台など、非常に興味深い遺構が残っていた。また、宮殿の近くには現在よく整備された公園が広がっているが、そこはかつて巨大な貯水湖だったと言う。そうだとしたら、湖を吹き抜ける涼風が吹き込むとても心地の良い宮殿だったことだろう。

謁見の間
また、宮殿の隣には、ラート・キ・マスジド(石柱のモスク)と呼ばれるモスクがある。この建築もとてもユニークだ。モスクのレイアウトは基本的に長方形なのだが、境内の西側と北側をL字型の建物が、南側と東側をL字型の貯水池が囲むような形になっている。ミフラーブ(メッカの方向を示す窪み)は中央に位置しているが、ミンバル(説教壇)はL字の角に設置されている。このようなプランのモスクはインドには他に類がない。また、モスクの境内には塔が立っており、貯水池を見おろすようにドームを乗せた廟のような建物も建っている。この塔は実はアショーカ王の石柱で、元々アグローハーに立っていたものをここに持って来たようだ。歴史オタクのフィーローズ・シャーはデリーにも2本のアショーカ王の石柱を他の場所から運んで来て立てている。

ラート・キ・マスジド
フィーローズ・シャーがどのような意図でラート・キ・マスジドを設計したかは分からないが、このモスクを見た瞬間、デリーのクトゥブ・コンプレックスを想起せざるを得なかった。これはデリーのミニチュアなのではなかろうか?塔はクトゥブ・ミーナール、廟に見える建物はアラーイー・ダルワーザー、モスクはクッワトゥル・イスラーム・モスクに対応させられる。また、L字型プランは、デリーのハウズ・カースにフィーローズ・シャーが建造したマドラサー(大学)にも適用されており、関連性を考えることも可能だ。
ムガル朝時代にもヒサールは地方行政の主都として栄えた。また、特にヒサールが歴史上重要なのは、皇太子がヒサール太守に任命される習わしがあったからである。例えばシャージャハーンやダーラー・シュコーも王子時代にヒサール太守に任命されており、ヒサール太守に任命されることが、次期皇帝として公式に認められることとされていた。
グジュリー・マハルを見終えると昼食の時間となっていた。ヒサールでどこか適切なレストランはないかとグジュリー・マハルのガイドに聞いてみたら、サンシティー・モールの名前が挙がったので、そこへ行くことにした。田舎のモールがどんな案配か見てみたかったし、NH10上にあって、帰る途中に寄るためにも都合が良かったのである。だが、やはり田舎のモールは田舎のモールであった。マルチプレックスが併設されているのはよかったが、モールに入っているのはいけてない店ばかりで、ゆっくりくつろげる場所もなかった。もちろん、デリーのモールの定番であるマクドナルド、KFC、バリスタ、カフェ・コーヒー・デーなどは一切なし。それでもヒサールの人々にとっては憧れの場所なのだろう。一応サンシティー・モールの中にロイヤル・フードというレストランがあったので、そこで軽く昼食を取った。
午後2時過ぎにヒサールを出て、午後2時半頃にハーンスィーに戻って来た。昨日一応ハーンスィーの観光はしたのだが、ひとつ行き残した場所があった。それはジェームズ・スキナーの邸宅である。シェークプラー・コーティーのマネージャーに、ハーンスィーにジェームズ・スキナー関連の史跡が残っていないか聞いてみたら、ハーンスィー市内に彼の旧邸があるとの情報が得られた。それは現在、地元の人々にメームサーブ・カ・バーグ(マダムの庭園)として知られており、NH10上のカチュハリー・チャウクにある。メインロードに面して立派な門が建っているのですぐに分かった。現在でもジェームズ・スキナーの子孫がここに住んでいるらしい。

メームサーブ・カ・バーグの門
ここでジェームズ・スキナーと、ついでにジョージ・トーマスについて簡単に解説しておこう。ジェームズ・スキナーは1778年にカルカッタで生まれた。父親は英国東インド会社に勤めるスコットランド人ヘラクレス・スキナー中佐で、母親はラージプートの領主の娘だった。つまり、ジェームズ・スキナーはいわゆるアングロ・インディアンである。インド人との混血だった彼は英国東インド会社に上官として入社することを許されず、マラーター同盟旗下のフランス人部隊に入隊する。そこでジェームズは天才的軍事能力を開花させる。

ジェームズ・スキナー
ジェームズはインド生まれであったが、当時、冒険心旺盛なヨーロッパ人の若者が一攫千金を狙って群雄割拠状態のインドに来ており、英国やフランスだけでなく、地元の王国に仕えて活躍していた。その内の1人がジョージ・トーマスである。1756年頃アイルランドに生まれたジョージ・トーマスは、当初英国海軍に属しており、1780年頃にインドに来たが、マドラス駐屯中に除隊処分となり、職を求めてデリーまで北上して来た。そこでサルダナー王国の女王ベーガム・サムルーに登用され、寵愛されたが、べーガムの愛情がフランス人ル・ヴェソに移ったことで彼女の元を去り(参照)、マラーター同盟のスィンディヤー家に仕えるようになる。ジョージ・トーマスは華々しい業績を上げ、ジャッジャルを中心に現ハリヤーナー州の広大な領地を与えられる。だが、成功に酔ったジョージ・トーマスはスィンディヤー家から独立し、ジャッジャルやハーンスィーを拠点に非公式の独立王国を打ち立てた。彼はヒサールにジャハーズ・コーティーと呼ばれる邸宅を建てたり、ジャッジャル近くにジョージガルと呼ばれる城塞を建築したりしており、この地域の歴史には欠かせない名前となっている。人々からは「アイリッシュ・ラージャー」と呼ばれた。
だが、そのままおめおめと引き下がるスィンディヤー家ではなく、ジョージ・トーマスの討伐に打って出た。1801年にジョージ・トーマスはスィンディヤー軍との戦争に敗れる。その戦争で活躍したのが、フランス人将校ピエール・クリエ・ペロンと、その指揮下にいたジェームズ・スキナーの軽騎兵隊であった。捕虜となったジョージ・トーマスは1802年に失意の内に没する。だが、ジェームズ・スキナーとスィンディヤー家の仲もすぐに悪化する。1803年に英国とマラーター同盟の間で第2次アングロ・マラーター戦争が勃発し、英国人の血を引いていたジェームズ・スキナーは敵性と判断され解雇されてしまったのだ。その後、スキナーは部下たちと共に英国東インド会社に鞍替えすると同時に、ハーンスィーを拠点に、インド人やアングロ・インディアンから成る軽騎兵隊を正式に立ち上げる。この非正規軽騎兵隊は「スキナーズ・ホース」という名称だったが、人々からは「イエロー・ボーイズ」と呼ばれた。なぜなら隊員は黄色のユニフォームを着用し、戦争時には顔を黄色に塗っていたからである。黄色はインドでは殉死の色であり、それはラージプートの母親からの影響だとされる。「ヒンマテ・マルダーン、マダデ・クダー(勇気ある者を神は助ける)」の雄叫びを上げ、ラージプート譲りの「勝利か死か」と言う決死の覚悟で突進するスキナーズ・ホースは、すぐに北インド最強の部隊のひとつとして知られるようになり、英国東インド会社軍の非正規軍として大活躍した。また、彼はインド人の文化や気質をよく理解していたため、相談役としても重宝された。ジェームズ・スキナーは、混血の出自を理由にしばらくは傭兵扱いであったが、1828年にようやくその功績を認められて正式に東インド会社の士官となり、後には大佐まで昇進している。

スキナーズ・ホース
「The Golden Calm」より
ジェームズ・スキナーはムガル皇帝からも認められ、ナスィールッダウラー・バハードゥル・ガーリブ・ジャングという称号を与えられた。シャージャハーナーバード(オールドデリー)内に邸宅も持っており、14人の妻とムスリム貴族風の豪奢な生活を送っていたとされる。ペルシア語にも堪能で、ペルシア語の著作も残している。ジェームズ・スキナーは19世紀前半のデリーの英国人社交界の中心人物の1人であり、インド人からも慕われていた。1857年のインド大反乱のとき、スキナーの子孫が、スキナーの子孫であるという理由だけで地元の人々から殺されるのを免れたほどである。人々はジェームズ・スキナーを畏敬を持って「スィカンダル・サーハブ」と呼んだ。スィカンダルとはアレクサンダー大王のことであり、ジェームズ・スキナーの武勇を端的に示す称号だと言える。ジェームズ・スキナーは1841年に没したが、彼が育て上げた最強の軽騎兵隊スキナーズ・ホースはその後も存続し続け、現在でもインド陸軍の一部隊となっている。
メームサーブ・カ・バーグは通常の観光地とは違って個人の敷地なので、果たして勝手に入っていいのか分からなかった。だが、門の近くで客待ちをしていたサイクルワーラーに聞いてみたら、なぜか彼が門の鍵を持っていて、開けてくれた。ただ、この邸宅に住んでいるジェームズ・スキナーの子孫は一昨日どこかへ行ってしまったところらしく留守であった。邸宅を外側からでも見てみようと、メームサーブ・カ・バーグの中へ入って行った。「マダムの庭園」と言われているものの、庭園は管理が行き届いておらず、草木がボウボウの状態であった。邸宅も、本当に人が住んでいるのか疑いたくなるような状態だった。しかし、その建築は、歴史あるコロニアル様式のバンガローであった。ライオンの彫像が2体置いてあったが、これはジェームズ・スキナーの武勇を現代まで伝える形見なのであろうか。ちなみに、メームサーブ・カ・バーグと呼ばれているのは、ジェームズ・スキナーの妻の1人アシュラフィー・ベーガムが庭園を管理していたからだと思われる。

ジェームズ・スキナーの旧邸
本日の走行距離115.2km、本日までの総走行距離298.9km。
今日は単に来た道を戻るだけである。午前9時半にシェークプラー・コーティーをチェックアウトし、NH10をデリーに向けて走った。午前11時45分頃に、行きにも立ち寄ったカナク・ダーバーで休憩し、軽く食事を食べた。一昨日は10時頃でもまだ涼しかったのだが、既にデリー周辺の気候は例年並みに戻っており、正午前後になると猛暑となっていた。とにかく喉が渇く気候である。水を飲んで水分を補給した。午後12時15分頃にカナク・ダーバーを出て、1時間もしない内にデリー市内に入った。
そのまま家に帰っても良かったのだが、ついでにデリーに残るジェームズ・スキナー関連の史跡に寄って行くことにした。ジェームズ・スキナーはイスラーム教徒のようなライフスタイルを送っていたのだが、宗教的には敬虔なキリスト教徒で、シャージャハーナーバードにセント・ジェームズ教会という教会を建てている。1836年に完成したこの教会はデリーでもっとも古い教会のひとつであり、「スキナーの教会」という異名も持っている。カシュミーリー門のすぐ近くにある(EICHER「Delhi
City Map」P58 H1)。十字架型プランであるが、奥ではなく中央の交差部分にドームを頂いており、ユニークな建築となっている。

セント・ジェームズ教会
この教会の建設には興味深い裏話が伝わっている。1800年、マラーター同盟に仕えていたときにウニアラーの戦いで瀕死の重傷を負ったジェームズ・スキナーは、3日間戦場に身動きが出来ないまま倒れていた。死との戦いの中で彼は、もし生き延びることがあれば教会を建てると神に誓った。神のご加護のおかげか、死体漁りをしていた地元の女性に救われ、スキナーは九死に一生を得る。彼は、その命の恩人の女性を一生母親として敬った他、そのときの誓いを忘れず、自己の資金を投じて、シャージャハーナーバード内の自分の荘園の中にこの教会を建設したのだった。元々ダーラー・シュコーの荘園があったこのエリアには、ジェームズ・スキナーの邸宅もあったはずだが、現在では残っていない。おそらく1857年のインド大反乱時に破壊されてしまったのだろう。
セント・ジェームズ教会の敷地内には、19世紀前半のデリーで活躍した3人の重要な英国人の墓がある。教会の建設者であるジェームズ・スキナーの墓の他、ウィリアム・フレーザーとトーマス・メトカーフである。ジェームズ・スキナーはハーンスィーで没し、一度はそこで埋葬されたのだが、すぐに遺体はデリーに運ばれ、この教会に埋葬されたと言う。トーマス・メトカーフについてはデリー散歩初期に取り上げたことがあった(参照)。ウィリアム・フレーザーについてはまたどこかで触れたいと思う。これらの人物の墓の他、ジェームズ・スキナーの妻や子供たちの墓がまとまって教会の北にある。14人も妻がいたというだけあり、墓も大所帯となっている。

スキナー家の墓
カールカージーの自宅には午後3時頃に到着した。本日の走行距離は174.8km、3日間の総走行距離は473.7km。
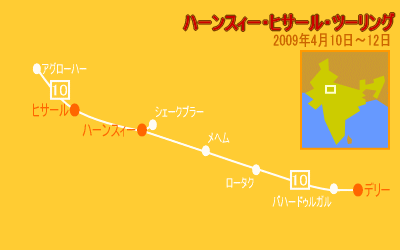
今回、初めてデリーの西方面にツーリングをした。ハーンスィーやヒサールは、1泊2日または2泊3日のツーリングには最適な距離にあり、デリー西方面のツーリング先として価値が高い。ウェルカム・ヘリテージのヘリテージホテル、シェークプラー・コーティーがハーンスィーにあるおかげで、宿泊にも一応困らない。だが、この地域に残っている旧所名跡は見た目のインパクト勝負をすることはできず、デリーの歴史や史跡に造詣が深くないと魅力を感じないものが多いかもしれない。デリーとハーンスィー・ヒサールを結ぶ国道10号線も、まだ道路拡張の真っ最中で、今のところ片側一車線、中央分離帯なしの危険な道路であり、デリーとアーグラーを結ぶ国道2号線や、デリーとジャイプルを結ぶ国道8号線に比べて、純粋に走る楽しさは感じられないだろう。シェークプラー・コーティーにしても、あるだけマシというレベルで、プロフェッショナルな接客は全く望めない。よって、ハーンスィー・ヒサールのツーリング・コースは、距離的には困難はないが、他の様々な要因によって玄人向けの難易度の高いコースになっていると言えるだろう。だが、ハーンスィーやヒサールの人々は皆とても純朴かつ親切で、地元の人々との接触の中で嫌な思いをしたことは全くなかった。それはこの地域の何よりの魅力だと感じた。
様々な要因が重なり、現在ボリウッドでは未曾有の新作不足に陥っている。その代わりハリウッド映画が大々的に上映されたり、普段は公開されないような低予算マイナー映画が公開されている。そんな中、昨年南インドで大ヒットしたタミル語映画「Dasavathaaram」のヒンディー語吹き替え版「Dashavtar」が公開された。これは嬉しい展開である。南インド映画がヒンディー語吹き替えされて北インドで公開されることは稀なのだが、こういうことが増えて行ってくれると、デリーにいながら理解できる言語で南インドの映画シーンも垣間見ることが出来て参考になる。
「Dasavathaaram」は、タミル語映画界の重鎮カマル・ハーサンが1人10役という野心的な多重演技をしたことで話題になった映画だ。さらに、監督は、日本でカルト的人気を博したタミル語映画「ムトゥ:踊るマハラジャ」(1995年;原題「Muthu」)のKSラヴィクマールである。タミル語オリジナル版の題名「Dasavathaaram」もヒンディー語吹き替え版の題名「Dashavtar」も、サンスクリット語の「dashāvatāra」がそれぞれ訛った形で、ヴィシュヌ神の十化身のことだ。ヴィシュヌ神は人類を救うために化身して地上に現れるとされており、一般的には彼の10の化身が認められている。すなわち、マツヤ(魚)、クールマ(亀)、ヴァーラハ(猪)、ナラスィンハ(人獅子)、ヴァーマナ(矮人)、パラシュラーマ(斧人)、ラーマ、クリシュナ、仏陀、カルキである。仏陀の代わりにクリシュナの兄バララーマが入ることもある。カマル・ハーサンが1人10役を演じたのも、ヴィシュヌの十化身から着想を得たのだと思われる。ヒンディー語吹き替え版ではタミル語版と比べて登場人物の名前が多少変更されていたようだが、ストーリーは同一である。
題名:Dashavtar
読み:ダシャーヴタール
意味:十化身
邦題:ザ・テン
監督:KSラヴィクマール
制作:ヴェーヌ・ラヴィチャンドラン
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー
歌詞:ヴァイラムットゥ、ヴァーリ
出演:カマル・ハーサン、アシン、マッリカー・シェーラーワト、ジャヤプラダー、ナポレオン
備考:デライトで鑑賞。

全員カマル・ハーサン
| あらすじ |
12世紀、シヴァ派の王(ナポレオン)がヴィシュヌ派根絶に打って出たことがあった。王はシュリーラームプルの寺院からヴィシュヌ神のご神体を奪い去ろうとするが、ヴィシュヌ派のランガラージャ・ナンビー(カマル・ハーサン)はそれに反抗する。王はご神体共々ナンビーを海に沈めてしまう。そのとき、ナンビーの妻(アシン)も頭を自ら割って死ぬ。
2004年12月20日。米国の研究所に勤めていた生物学者ゴーヴィンド(カマル・ハーサン)は、人類を滅亡させる恐れのあるバイオ兵器NACLを開発してしまう。所長はそれをテロリストに売り渡そうとするが、ゴーヴィンドはそれを奪って逃走する。最初ゴーヴィンドは研究所の友人を頼る。だが、彼は所長と通じていた。元CIAで殺し屋のフレッチャー(カマル・ハーサン)が送り込まれ、友人とその日本人の妻ユカは殺されてしまうが、ゴーヴィンドは何とか逃げ出す。ゴーヴィンドはNACLをFBIに届けようとするが、手違いによりNACLの入った封筒はシュリーラームプルに送られてしまう。フレッチャーの追撃を振り切ったゴーヴィンドは、気絶している内に貨物と共に飛行機に積み込まれ、インドへ飛ぶ。フレッチャーは、表向きバーダンサーその実パーキスターンの諜報部員であるジャスミン(マッリカー・シェーラーワト)を通訳に雇い、インドへ飛ぶ。
ゴーヴィンドは飛行機内で逮捕され、空港でベンガル人諜報局員バルラーム・ナーダル(カマル・ハーサン)に取り調べを受ける。だが、バルラームが席を外している間にゴーヴィンドはフレッチャーとジャスミンに捕まってしまう。ちょうどそのとき空港にはパンジャービー・ポップシンガー、アヴタール・スィン(カマル・ハーサン)が妻のランジーター(ジャヤプラダー)と共に到着していた。だが、アヴタールが突然血を吐いたことで空港は騒然となっており、その隙にフレッチャーとジャスミンはゴーヴィンドを連れ出す。NACLがシュリーラームプルに送られたことが分かっていたため、3人はシュリーラームプルを目指す。また、バルラームも彼らがシュリーラームプルへ向かったことを突き止め、後を追う。
道中でフレッチャーらから逃げることに成功したゴーヴィンドは、シュリーラームプルで配達人がNACLの入った封筒を届けるのを待つ。その封筒は、95歳の老婆クリシュナヴェーニー(カマル・ハーサン)に届けられる。ゴーヴィンドはそれを取り返そうとするが、クリシュナヴェーニーはNACLをゴーヴィンドラーラー神の神像の中に入れてしまう。神像の奪い合いが始まり、その中でジャスミンは死んでしまう。ゴーヴィンドはフレッチャーを振り切ることに成功したものの、クリシュナヴェーニーの孫娘ラーダー(アシン)がいつまでも神像を掴んで離さなかった。
NACLは低温で保存しなければならなかったため、ゴーヴィンドは一旦神像を砂の中に埋め、氷を探しに行く。そのとき自分がテロリストとして指名手配されていることを知る。また、神像を埋めた場所は違法に砂を採掘する業者の縄張りとなっており、神像も砂ごと持って行かれそうになっていた。ゴーヴィンドはそれを止めようとするが、逆に違法業者たちに暴行を受け、ラーダーもレイプされそうになる。それを救ったのがダリト(不可触民)の活動家ヴィンセント(カマル・ハーサン)であった。ヴィンセントはマスコミと共にその場に駆けつけ、違法業者たちの悪行を暴露した。その騒動の中でゴーヴィンドとラーダーは神像を取り返し、トラックを奪って逃走する。
だが、途中でトラックはヴァンと衝突し横転してしまう。そのヴァンに乗っていたのはイスラーム教徒一家であった。その一家の長男カリフッラー(カマル・ハーサン)は巨人であった。カリフッラーの母親が事故で怪我をしてしまったため、近くの病院へ運ばれる。そこでとりあえず神像は冷却ボックスの中にしまわれる。その病院ではちょうどアヴタール・スィンが診断を受けていた。アヴタールは喉に癌を患っており、手術が必要であった。アヴタールは最後のコンサートを行った後に手術を行うことを決める。アヴタールは医者から冷却ボックスに入った薬をもらう。
ゴーヴィンドは冷却ボックスをバルラームに届けようとするが、途中でそれはアヴタールの冷却ボックスと取り違えられてしまう。また、フレッチャーは病院まで辿り着いており、カリフッラーとラーダーを人質に取ってカリフッラーの家にゴーヴィンドを呼び寄せる。ゴーヴィンドは冷却ボックスと共にカリフッラーの家に来るが、中身はNACLではなかった。そのとき、バルラームが家宅捜索にやって来る。その混乱の中でゴーヴィンドとラーダーはフレッチャーから逃げ出すことに成功する。彼らは薬をアヴタールに届け、中身を交換してもらうことにする。そのときちょうどアヴタールはコンサート会場にいた。
アヴタールは血を吐きながらもコンサートを決行していた。ゴーヴィンドとラーダーは休憩中のアヴタールに薬を届け、神像を返してもらう。だが、そこへフレッチャーが現れる。アヴタールは喉を撃たれて重体となるが、ゴーヴィンドとラーダーは再び逃亡する。フレッチャーは後を追う。
3人は工事現場にやって来て、そこで神像の奪い合いをする。時は12月26日の朝になっていた。ゴーヴィンドは神像からNACLを密かに抜き出し、フレッチャーに渡して逃げる。ゴーヴィンドはNACLを冷やすために塩を取りに行こうとするが、フレッチャーに止められ、NACLを奪われる。ゴーヴィンドにも既に反撃の力は残されていなかった。そこへ登場したのが日本人のナラハシ・シンゲン(カマル・ハーサン)であった。シンゲンはユカの兄で、妹の仇を討つためにインドに来ていた。当初はゴーヴィンドを仇だと勘違いしていたが、真の仇はフレッチャーだと悟り、この場に現れたのだった。シンゲンは武術の達人で、フレッチャーを追い込む。ところが、敗北寸前のフレッチャーは自暴自棄になり、NACLを呑み込んでしまう。それにより、危険なウィルスが周囲に充満し始めた。
と、そのとき、沖から大津波が押し寄せ、NACLを呑み込んだフレッチャーもろとも全てを洗い流してしまう。津波による大混乱の中、ヴィンセントは子供たちを助けようとして溺死する。だが、カリフッラーとその隣人たちは、モスクで警察から取り調べを受けていたために死を免れる。ゴーヴィンド、ラーダー、シンゲンも運良く舟に乗り込んでおり、救われた。津波の去った海岸でゴーヴィンドとラーダーはいつしかお互いに恋し合っていたことを確認し合う。また、海岸には12世紀に海に沈められたヴィシュヌの像が打ち上げられていた。一方、病院ではアヴタールの手術が終わっていた。銃弾で撃たれたおかげで癌が消え去っており、彼は完治後再び歌えるだろうと診断されていた。
現代。米国のジョージ・ブッシュ大統領(カマル・ハーサン)がインドを訪問しており、マンモーハン・スィン首相やタミル・ナードゥ州のカルナニディ州首相と共に壇上に立っていた。ゴーヴィンドが司会を務め、12世紀から2004年までに起こった不思議な出来事を語っていた。ブッシュ大統領も上機嫌でインド人向けのリップサービスをしていた。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
テクニカルな部分では何と言っても、主演のカマル・ハーサンが1本のまとまったストーリーの映画の中で独立した10役を演じるという、世界の映画史上類を見ない偉業に挑戦したことに注目せざるをえないだろう。それぞれ独立した小話の中で合計10役を演じた訳ではなく、1話の完結した長編の中で、主役から悪役まで、ストーリー進行上それぞれに重要な役割を果たす役を10役演じた。よって、カマル・ハーサン演じるキャラクターが2人以上同時にスクリーンに登場する場面もいくつもあるのだが、そのような特殊効果・特殊演技はカマル・ハーサンが昔から得意とするお家芸であり、全く不自然を感じさせなかった。
だが、脚本上興味深かったのは、ヴィシュヌ神の十化身の特徴がカマル・ハーサンの演じる10役の設定に反映されていたことと、2004年12月26日にインドを襲ったインド洋津波という実際の出来事がストーリーに組み込まれていたことである。十化身と「Dasavathaar」「Dashavtar」の登場人物の対応は以下の通り。
| 十化身 |
「Dasavathaar」/「Dashavtar」 |
| マツヤ |
ランガラージャ・ナンビー |
| クールマ |
ジョージ・ブッシュ |
| ヴァーラハ |
クリシュナヴェーニー |
| ヴァーマナ |
カリフッラー |
| ナラスィンハ |
ナラハシ・シンゲン |
| パラシュラーマ |
フレッチャー |
| ラーマ |
アヴタール・スィン |
| バララーマ |
バルラーム |
| クリシュナ |
ヴィンセント |
| カルキ |
ゴーヴィンド |
この中で、クールマとジョージ・ブッシュ、ヴァーラハとクリシュナヴェーニーはつながりが薄いが、それ以外はある程度明確である。例えば12世紀のシーンでランガラージャ・ナンビーは海に沈められるが、それはマツヤ(魚)と対応する。カリフッラーは巨人であったが、それは悪魔に一泡吹かせるために矮人から一気に巨人になったヴァーマナと対応する。殺し屋のフレッチャーは片っ端から人を殺していくが、その様子はクシャトリヤを殲滅したパラシュラーマと一致する。アヴタール・スィンは癌を患い、喉を撃たれながらも最後で復活した。それはどちらかというとラームの弟のラクシュマンに対応する。ラクシュマンはランカー島の戦いで重傷を負うが、ハヌマーンの活躍により一命を取り留めたのだった。ヴィンセントは肌が黒く、最後は足を鉄棒で串刺しにされて溺死するが、それは肌の色が黒く、アキレス腱を射られて死んだクリシュナと酷似している。カルキは世界の終わりに現れるとされるが、それはこの映画の主人公ゴーヴィンドを彷彿とさせる。また、ナラスィンハはナラハシと、バララームはバルラームと名前が一致している。
タミル語版オリジナル「Dasavathaaram」とヒンディー語吹き替え版「Dasavtar」の間で大きな違いはなかったが、唯一バルラームの設定だけ異なった。タミル語版ではバルラームはテルグ人であるが、ヒンディー語版では彼はベンガル人ということになっていた。バルラームのキャラクターには、訛ったしゃべり方をおちょくるようなところがあった。タミル語版ではテルグ人の話すタミル語をおちょくったが、ヒンディー語吹き替え版ではそのままテルグ人にしてもしっくり来ないため、バルラームの設定をベンガル人に変更し、ベンガル人の話すヒンディー語をおちょくろうとしたのであろう。
カマル・ハーサン演じるジョージ・ブッシュも気になるが、日本人にとって一番気になるのは何と言っても日本人ナラハシ・シンゲンである。武術の達人で、妹の仇討ちにインドにやって来るという設定は非常に格好いいし、クライマックスで悪役のフレッチャーと格闘するのもシンゲンで、かなりおいしいキャラクターだ。しかも、シンゲンは日本語の台詞をしゃべる。インド映画にしてはなかなか本格的な日本語だ。日本語の台詞のところでは字幕が出る。クライマックスで米国人のフレッチャーに「広島を覚えているか?」と聞かれ、シンゲンが「真珠湾を覚えているか?」と問い返すところもニヤリとさせられる。これは、「ムトゥ:踊るマハラジャ」の日本での大ヒットで気をよくしたKSラヴィクマール監督の、日本へのオマージュなのであろうか?
また、クリシュナヴェーニーとヴィンセントについて一言触れておくべきであろう。クリシュナヴェーニーはブラーフマンの家系に生まれ育った老婆で、ヴィンセントはダリト(不可触民)である。通常ならこの2人が互いに関わり合うことはない。だが、クリシュナヴェーニーは息子の死を受け入れられずにいるという設定で、最後に津波が発生し、ヴィンセントの遺体が海岸に打ち上げられると、クリシュナヴェーニーはそれを息子だと勘違いし、嘆き悲しむ。それによって彼女は「息子は死んだ」という現実に直面し、正気を取り戻すのだが、それは津波によってカースト間の壁が取り除かれたことを示しているのかもしれない。
よって、実は「Dasavathaaram/Dashavtar」は、3時間という「インド映画サイズ」の大長編映画ながら、その中に3時間では収まりきらないほど多くの要素が詰め込まれた映画である。このような難しい脚本と難しい演出・演技を要する野心作に挑戦したKSラヴィクマール監督とカマル・ハーサンは賞賛に値する。だが、あまりに展開が急速かつごちゃごちゃし過ぎていて、見るのに疲れる映画だった。アクションやスリルは一級だったが、緩急の「緩」の部分が欠けており、ゆっくり見ていられなかった。娯楽映画なので、少しぐらいは先の展開を予想する心の余裕を持ちながら鑑賞したいのだが、そういうことを許してもらえず、次々とストーリーが進行して行き、それに追い付くだけで精一杯だった。
カマル・ハーサンは今回10役を1人で演じた。全く別人にしか見えないような顔に変貌させてしまうメイク技術には驚かされたし、映画の最後に映されるメイクの「メイキング」シーンも面白かったが、メイクをしているのが分からないほど自然なメイクというレベルには達しておらず、変な顔のキャラが登場したらいちいち「これもカマル・ハーサンなのだな」と分かってちょっと興醒めであった。特にジョージ・ブッシュ、クリシュナヴェーニー、カリフッラー、ナラハシ・シンゲン、フレッチャー、ヴィンセントのメイクが変だった。つまり10役の内6役は不自然だった。果たしてカマル・ハーサンは1人で10役を無理に演じる必要があったのだろうか、そういう根本的問いを投げかけずにはいられない。それでも、こういうユニークな挑戦はどんどんして行ってもらいたい。
ヒロインは「Ghajini」(2008年)でボリウッド・デビューしたアシン。「Ghajini」のアシンはフレッシュで良かったのだが、「Dasavathaaram/Dashavtar」は甲高い声でマシンガントークをしてドタバタするうるさい女であり、げんなりであった。ボリウッド女優のマッリカー・シェーラーワトがサブヒロイン(正確には悪役)として登場するが、これが彼女のタミル語映画デビューとなる。登場機会は前半のみであったが、彼女が演じたのは、アイテムナンバーでのダンスを含め、自分のもっとも得意とする役柄であり、アシンよりも好感が持てた。他に、往年の女優ジャヤプラダーが端役で登場する。
音楽は主にボリウッドで活躍する音楽家ヒメーシュ・レーシャミヤー。しかし、「Dasavathaaram/Dashavtar」において彼の持ち味は全く活かされておらず、挿入歌の中に魅力的なものはほとんど見出されなかった。南インド映画にしては、ダンスシーンに気合いが入っていない部類に入る映画だと言えるだろう。ストーリーが急展開過ぎるので、ダンスシーンを適度に織り込んで緩急を付けることもできただろうが、時間不足のためか、端折り気味のダンスシーンばかりであった。特筆すべきは、エンディングで流れる曲(タミル語版では「Ulaga
Nayagan」)でKSラヴィクマール監督自身が登場してダンスを披露することである。
タミル語映画では、やたらとタミル語に対する愛が語られる。それは時に、登場人物が、非タミル人も含め、皆タミル語を理解し、タミル語を話す言い訳にもなっている。ヒンディー語吹き替え版では当然流れからそれはヒンディー語に対する愛に置き換えられるのだが、ヒンディー語映画では通常そういう台詞は出て来ないため、非常に違和感を感じる。タミル語版も同時制作された「Guru」(2007年)でもそれを感じたのだが、この「Dasavtar」でもヒンディー語、ヒンディー語とうるさかった。この点は、吹き替え版の弱点だと言える。
最近、上映時間が短めで薄口の映画がヒンディー語映画界では多くなって来ているのだが、「Dasavtar」はコテコテのインド娯楽映画路線を行っており、久々にマサーラーを腹一杯詰め込んだ気分である。皿からはみ出るほどの大盛りで、必ずしも見た目は美しくなかったが、とにかく3時間観客を存分に楽しませようという気概に満ちあふれており、その旺盛なサービス精神は買いたい。ヒンディー語という自分が得意とする言語で鑑賞できたのも嬉しかった。願わくは、このような南インド映画の典型的娯楽映画のヒンディー語吹き替え版公開が少しずつ増えてくれればありがたい。
現在インドは下院総選挙の真っ最中である。インドの今後最大5年の方向性を決める重要な選挙だ。既に政党同士の党争本能むき出しの駆け引きは佳境を迎えているが、今回はハング(どの政党や連立党も過半数議席を得られない状態)の可能性が高いため、本当のタマーシャー(ショー)は開票後に見られるだろう。
各党が、いかにも最大限の有権者を魅了するような、当たり障りのないマニフェストや公約を掲げる中で、ウッタル・プラデーシュ州を拠点とする社会党(Samajwadi
Party;SP)はかなり個性的なマニフェストを公表し、話題になった。それは、英語とコンピューターの禁止である。
社会党のマニフェストは同党のウェブサイトで閲覧することができる。英語とヒンディー語のページがあるが、ウェブサイト上で公開されているマニフェストはなぜかヒンディー語版のみである。その中から、該当の部分を抜き出してみた。
まずは英語禁止の部分。
शिक्षा, प्रशासन और अदालतों में अंग्रेजी का चलन समाप्त कर देशी भाषाओं का
प्रयोग हो। (p.7)
訳:教育、行政、司法において英語の使用を禁止し、地元言語を使用するようにする。
4月12日付けのサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙には、マニフェスト発表時に記者とのインタビューで、ムラーヤム・スィン・ヤーダヴ党首がこの部分についてさらに踏み込んで解説した発言が掲載されていた。それによれば、社会党が反対しているのは、教育、行政、司法における英語の強制的な使用であり、地元言語の中でも特にヒンディー語の使用を推進して行くとのことである。英語禁止は今に始まったことではなく、社会党が前々から主張している政策のひとつである。
次にコンピューター禁止の部分。その前後で、コンピューター禁止の他にも面白いことを言っているので、それらも併せて取り上げる。
पिछली सरकारों ने फारवर्ड ट्रेडिंग, शेयर बाजार और बाजार की 'मॉल संस्कृति'
को बढ़ावा दिया है। समाजवादी पार्टी की मदद से जो भी सरकार बनेगी, उसे कम करेगी
या रोक देगी। आदमी के श्रम को महत्व दिया जायेगा और जो काम आदमी के हाथ से
हो सकेगा, उसे कम्प्यूटर और मशीन का गुलाम नहीं बनाया जायेगा। समाजवादी पार्टी
जानती है कि अब ट्रैक्टर का युग आ गया है। किसानों के दरवाजे से बैल गायब
हो गये हैं और बैल, गाय के बछड़े गाँव के बाजार से कलकत्ता के कमेलो के हाथों
में चले गये। समाजवादी पार्टी जानती है कि हार्वेस्टर का जमाना आ रहा है,
फसल की कटाई करके गाँव का मजदूर पाँच-छः महीने के लिये अपनी रोटी का इंतजाम
कर लेता है। हार्वेस्टर आने के बाद मजदूर बेरोजगार हो जाएगा और भूखों मर जाएगा।
यही काम दफ्तरों में कम्प्यूटर कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को दोहराती
है कि जो काम हाथ से हो सके उसके लिये मशीन के प्रयोग पर रोक लगायी जाए। समाजवादी
पार्टी ऊँची तनख्वाहों, सुविधाओं पर रोक की पक्षधर है। ऊँचे वेतन और न्यूनतम
वेतन में एक तर्कसंगत संतुलन से ही राष्ट्र में पूँजी का निर्माण हो सकता
है। पूँजी निर्माण विकास की कुंजी है। (p.5)
訳:今までの政府は先物取引、株式市場、そして市場の「モール文化」を推進して来た。もし社会党の支持により政府が樹立したなら、その政府はそれらを減退させるか、あるいは停止させる。人間の労働を重視し、人間の手で行える仕事はコンピューターやマシーンに頼らないようにする。社会党は、今やトラクターの時代が到来したことを知っている。農家の戸口から牛が消え、仔牛が村の市場からカルカッタの屠殺業者に送られている。社会党は、刈り取り機の時代が到来しつつあることを知っている。作物の収穫のために労働者は5~6ヶ月生活費を稼ぐことができるが、刈り取り機が来た後は労働者は職を失い、餓死してしまう。同様のことがオフィスにおいてコンピューターによって起こっている。社会党は繰り返し主張するが、手で行える仕事においてマシーンの使用を禁止すべきである。社会党は、高額な給料や施設を禁止することを支持する。高額賃金と最低賃金の間に理に適ったバランスをもたらすことでのみ、国の資本形成が可能となる。資本形成こそ発展の鍵である。
これらの文章から読み取れる社会党の基本理念は「人間が出来ることは人間が」であり、それに則ってコンピューターやマシーンの使用に反対するマニフェストを掲げていると言える。同時に、「モール文化」なるものや、高額賃金にも言及し、それを規制する方針を打ち出している。
社会党のこれらの主張は、かつてマハートマー・ガーンディーが言っていたことを思い出させる。ガーンディーも、英語をインドの国語または公用語にすることや、労働者から職を奪う形でのマシーンの導入に反対していた。英語については、憲法によって英語の使用は排除されることが規定され、猶予期間終了後はヒンディー語がインドの唯一の公用語として適用されるはずだったのだが、未だにヒンディー語への完全な移行は実現していない。教育の場ではまだしも、行政や司法の場における英語の排他的使用は実は憲法違反なのであるが、誰もそれを気に留めようとしない。社会党の主張は、憲法を盾にすれば十分通用するものだと思われる。また、ガーンディーのマシーンに対する嫌悪は独立後のインドの工業に少なからず影響を与えており、インドが第二次産業に弱い原因とされることもしばしばである。モール文化についても、左寄りの人々が度々槍玉に挙げる事項であり、レッド・キャンパスの異名を持つジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では特に目新しいトピックではない。JNUを舞台にした小説「Sumthing
of a Mocktale」でも、モール文化についてこんな一節があった。
別の日、彼(教授)はモール文化がいかに富裕者と貧困者の格差を拡大するかを指摘した。彼によれば、アンサル・プラザ(デリー最初のショッピングモール)は全ての人に開かれているように見えるが・・・
「そこにどれだけの下位中産階級や下層階級の人々を見出すことができるだろうか?どれだけのスラム住民が、『買える人専用』と無言で訴えるガラス張りの建物に足を踏み入れることができるだろうか?建物の建築自体が既に威圧的であり、訪れる貧困者を嫌な気分にさせ、阻害することで、階級差を固定化しようとしている。モールの発明によって、古き良きバーザールはどうなってしまうだろう?バーザールでは、階級差は溶解し、億万長者は他の群衆の中に埋もれ、富裕者は貧しい大衆と肩を寄せ合いながら屋台の食べ物を食べていた。今や、億万長者の子供たちは、彼らと同年齢の子供たちが、少しの間立っているのも我慢ならないくらい不衛生な場所でチャーイをサーブしていることなど知ろうともしない。」(p.13-14)
賃金格差については、社会党マニフェストの別の部分でも少しだけ触れられていた。
नये अध्ययन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की 84 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन प्रति
व्यक्ति 20 रुपया या उससे कम पर गुजारा करती है। इसका भी काफी बड़ा हिस्सा
तो महज 9 रुपया औसत प्रतिदिन कमाता है और इसके उलट दुनिया के 10 खरबपतियों
में भारत का चौथा स्थान है।(p.2)
訳:最新の調査によると、農村地域の84%の人口は毎日1人あたり20ルピー以下の生活をしている。その中の大半は毎日平均9ルピーしか稼いでいない。その一方で、世界の億万長者トップ10の中で4位にインド人が入っている。
インドにおいて貧富の差は今に始まったことではなく、その格差是正は全ての政党が必ず触れるトピックであるが、社会党のマニフェストがユニークなのは、貧困を撲滅するのではなく、所得の上限を公務員の給料体系に従って規定し、高額所得者の所得を制限しようとしているところである。
当然、マニフェスト中のこれらの主張に対し、多くの人々が反対の声を上げた。中には嘲笑とも取れるものもある。例えば、4月12日付けのサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙は、「タイムズ・ビュー」という小さな囲み記事の中で社会党のマニフェストを痛烈に批判している。
社会党はインドを何十年も過去に引き戻そうとしているように見える。だから同党は英語を教育言語から排除しようとしているのだ。英語の知識こそが、発展途上国の中でインドを優位に立たせる役割を果たしたにも関わらず、である。現在、中国は英語教育を大急ぎで行っている。それだけでなく、マシーンの排除により雇用が促進されるという理論は道理に反している。もしそうなら、どうしてウッタル・プラデーシュ州やビハール州のようなマシーン不毛地帯から何百万人もの人々がデリーやムンバイーへ職探しのために移民しているのか?もし国を発展させたいのなら、同党は馬鹿げた経済理論を弄ばず、どのように生産性を増加させるか真剣に考えるべきである。
タイムズ・オブ・インディア紙の批判はそれだけでは収まらず、その後もあの手この手を使って社会党のマニフェストを狙い撃ちしている。英語禁止運動におけるヤーダヴ党首のアキレス腱は、彼自身の息子である。ヤーダヴ党首は息子を英語ミディアムの学校で学ばせており、マニフェストと矛盾している。社会党はボリウッドともつながりが深く、今回はサンジャイ・ダットが党の広告塔に立っている他、バッチャン一家も社会党とつながりが深いが、彼らも英語ミディアム学校卒である。また、読者アンケートでも、社会党の時代遅れな政策を嘲笑する内容が多く掲載されていた。英語教育やモールを禁止しようとする社会党を、イスラーム法による統治を掲げるターリバーンと同一視するような記事もあった。これらの意見はごもっともであるが、インドにおいて英語の使用が減少した場合に被害を被るのはタイムズ・オブ・インディア紙をはじめとした英語紙であり、その利害関係から、少しヒステリックになって批判している部分もあるのではないかと思う。インドの英語紙を読んでいると、インドにおける英語の発展を礼賛する一方で、反英語的政策や意見に敏感に反応する傾向が時々顕著に見受けられる。いかに「インドを代表する大衆紙」としばしば称されるタイムズ・オブ・インディア紙と言えど、大手ヒンディー語紙と比較したら発行部数は桁違いに少ない。さらに、タイムズ・オブ・インディア紙の読者層と、コンピューターを駆使し、モールへ行き、マルチプレックスで映画を見る層はかなり重なっていると考えることができる。タイムズ・オブ・インディア紙は、「英語」「IT」「モール」などのキーワードでつながる、小さな、だが強力なコミュニティーの代弁者であり、それらの「外来文化」に対する攻撃に自然に防衛反応が働くのだろう。実際、ヒンディー語紙では不思議と社会党のマニフェストはほとんど触れられていなかった。
新聞は新聞でいろいろ言っているが、やはり選挙シーズンなので、ライバル政党もここぞとばかりに社会党のマニフェストを槍玉に挙げている。国民会議派は社会党を「インドを石器時代に引き戻そうとしている」と批判し、インド人民党(BJP)は「社会党は19世紀に住んでいるようだ」とおちょくっている。
ノーベル経済学賞を受賞した著名な経済学者アマルティヤ・セーンも黙っていなかった。「英語は既に十分インドの言語である」と主張するセーン教授は、1970年代に西ベンガル州で共産党政権が英語を排除しベンガリー語教育を推進しようとして失敗したことを引き合いに出し、社会党の英語禁止運動を批判した。西ベンガル州での英語排除が成功しなかったのは単純な理由からである。誰もベンガリー語の学校へ行きたがらなかったし、子供を通学させたがらなかったからだ。もし社会党が与党の一員となっても、ムラーヤム・スィン・ヤーダヴはインドの商業、産業、法律、さらには公共の場から英語を完全に排除することはできないはずで、そうした場合、英語教育の禁止は、逆に現在の格差を固定する方向に働き、逆効果であると述べている。
批判にさらされたムラーヤム・スィン・ヤーダヴ党首は結局火消しに回ることになり、「英語の使用そのものを禁止するのではなく、英語が必須である状態を変えたい」と多少表現を和らげたが、英語への反対姿勢は一貫している。
果たしてセーン教授の言う通り、既に英語がインドの言語の一員となっているのか否か、そして教育、行政、司法の場での英語の使用を排除または制限しようとする政策がインドにとって有害なのか否かについては、ここでは議論しないでおく。ただ、僕は前々から英語がインドの貧困撲滅や格差是正の最大の障害になっていると考えており、インドが本当に発展したいならば、英語のヘゲモニーを何らかの手段で打破して行かなければならないと考えている。また、英語はまだ完全にインドの言語にはなっていないし、これからもならないだろうと考えている。インドの社会では、英語の能力が一種の足切りとして不当に働いており、それは日本では見られない現象なので、日本人としてつい注目してしまう。だから、社会党のマニフェストは、手段の部分ではなく理念の部分でよく理解できる。だが、それに対する批判も同じくらいよく理解できる。
それでも、これは選挙であることを忘れてはならない。社会党は端から、英語を話し、会社に勤め、コンピューターを使って仕事をし、高給を稼ぎ、休日はモールへ行ってリラックスするような都市在住上位中産階級層を支持者層として相手にしていない。社会党の支持者層は、ヤーダヴ(牛飼い)カーストをはじめとしたその他の後進階級(OBC)とイスラーム教徒であり、農村の貧しい人々である。社会党の時代を逆行するようなマニフェストは、もしかしたらインドの経済発展から取り残されつつある彼らの心を掴むことになるかもしれない。ただ、今回社会党は、元インド人民党(BJP)の政治家で、バーブリー・マスジド破壊事件の責任者の一人として目されているためにイスラーム教徒たちから嫌われているカリヤーン・スィンを公認候補として擁立したため、イスラーム教徒の票を失う可能性がある。人気スターのサンジャイ・ダットを書記長に任命し、大衆の支持を集めようとしているが、それもどこまで功を奏するか不明である。
ちなみに、今回社会党のマニフェストを調べるために社会党公式ウェブサイトを訪問したことをきっかけに、各政党の公式ウェブサイトに興味が沸いた。気になったのは職業柄その言語である。社会党は英語とヒンディー語のページを用意している。だが、他の政党はどうだろうか?国民会議派ウェブサイトは英語をメインとしながらも、ヒンディー語とウルドゥー語のページも用意されていた。だが意外だったのは、インド人民党(BJP)のウェブサイトがほとんど英語のみだったことである。一応マニフェストはヒンディー語でも読むことができるが、ウェブサイトのメイン言語は英語で、ヒンディー語ページは用意されていない。ヒンドゥー教至上主義の政党とされ、いかにもコテコテのヒンディー語のページを用意していそうなイメージであったが、実際のBJPのウェブサイトは以下の画像に象徴されるような、何かとてつもない未来を予感させる先進的なデザインであった。イメージチェンジを計っているのであろうか?

最近は面白そうな新作映画がないので映画館から足が遠のいているが、ほぼ毎週のように映画を見に行っているため、いかにも映画好きだと思われることが多い。だが、自分はどうも世間一般の映画好きとは違うような気がしてならない。まず、僕が好んで見ているのはヒンディー語映画、いわゆるボリウッド映画である。それ以外の映画を見に映画館へ行くことは滅多にない。デリーでも時々映画祭が行われるが、日本とインド以外の映画にはほとんど興味が沸かない。映画好きを自称しボリウッド映画を敬遠する人々は、インドにいるとよっぽど退屈するようで、映画祭ではここぞとばかりに片っ端から世界各国の映画を見るようであるが、僕の興味の範囲はせいぜい南アジア止まりである。高校・大学の頃は、映画館、ビデオ、テレビなどを通してよく映画を見ていたものだったが、現在自分が映画好きを自称する権利があるかと問われたら、もしかしてないのではないかと思う。本当に映画好きの人はもっと満遍なくいろいろな映画を見ている。
また、一般的なヒンディー語映画ファン、または広く見積もってインド映画ファンとも、どこか話が合わない部分があるような気がしてならない。一番困る質問が、「好きな俳優は誰ですか?」「好きな監督は誰ですか?」という質問である。一応プロフィールにも好きな男優・女優を載せているが、それはどちらかと言えば応援しているくらいのニュアンスであり、基本的には中立である。いい映画を撮った監督を高く評価するし、いい演技をした俳優を賞賛するだけだ。俳優や監督に会いたいとも思わない。一方、ボリウッド好きな日本人は、どうも俳優中心主義で映画を見ている人が多いような気がして、孤立感を感じることがある。ただし、俳優中心主義は全く問題ない。好きな俳優ができると、その人の出演作を中心にボリウッドに入って行くことができるため、そういう楽しみ方はあって当然だと思う。それだけになってしまっては、逆に視野を狭めてしまうが。
結局、僕は「映画」も「ヒンディー語映画」も好きなわけではないのだと思う。それなのになぜここまでヒンディー語映画を見続けているかと言えば、職業柄「ヒンディー語」に注目せざるをえないからである。ヒンディー語を学習・研究する上で映画の影響力は無視できない。また、ヒンディー語映画には必ずと言っていいほどインド独自の要素が出て来る。それは文化であったり、歴史であったり、社会であったり、政治であったりする。それらと言語は切っても切れない関係にあり、ヒンディー語映画を見る際はその部分も重視している。よって、まずヒンディー語があり、インドがあり、その次にヒンディー語映画があると言って過言ではないだろう。ヒンディー語映画ファンを自称するのもはばかられる。
だから、日本でヒンディー語映画が広まればいい、インド映画専門映画館が出来れば素晴らしいとは常日頃思っているものの、ヒンディー語映画自体の魅力をみんなに分かってもらおうとはあまり考えていない。ヒンディー語映画が日本で普及することで、インドに対する理解やヒンディー語学習への気運が高まればいいと考えているだけで、あくまでヒンディー語映画は手段に過ぎない。インドでヒットしたヒンディー語映画が日本人一般に受けるとも思っていないし、ヒンディー語映画が日本で公開される際の売り出し方にも疑問を持っている。「これでインディア」で書いている映画評にしても、いわゆるネタバレな上にその内容はかなりマニアックであり、ヒンディー語映画普及のためというより、ヒンディー語映画に元々興味のある人が作品を通してインドをより深く理解するのに役立つように発信しているつもりである。
しかし、ヒンディー語から離れ、「映画」の部分で僕が執着している点がある。それは「娯楽映画とは何か?」という命題の追求である。
2001年にインド留学して以来、映画を見るたびに日記を付けて来たが、それが評論と呼んでもいいレベルになったのはせいぜい数年前である。それまでは単なる備忘録みたいなものだった。ただのメモではなく、真剣に批評をしようと思い立ったきっかけは、インド映画に対するある屈辱的な言葉であった。インド映画をロクに見ていない、年配のいわゆる「映画愛好家」の方から、「インド映画の批評なんてできるのか?」と嘲笑されたのである。その言わんとするところはつまり、歌って踊ってのインド映画は批評にも値しないということである。そのときから、インド映画の、特に娯楽映画の批評をしよう、娯楽映画評の方法論を確立しようと決心したのであった。
世界でインド映画産業ほど娯楽映画を徹底して追求しているところは他にない。やはりハリウッドが様々な意味で最大のライバルとなり得るが、娯楽映画のひとつの完成形であったミュージカルをほぼ完全に捨て去ったハリウッドに、もはやインド映画に真っ向から立ち向かう力は残されていないと考える。娯楽映画批評法の確立のために、インドはもっとも適した場所なのだ。
インド娯楽映画を数多く見ていると、一口に「歌って踊って」と言っても、とんでもなく楽しい傑作もあれば、全くの失敗作も少なくないことに気付き始める。子供の頃、夕方になるまで公園で心ゆくまで遊んで家に帰って来たときのような充足感を、映画館を出るときに感じさせてくれる優れた娯楽映画がある一方で、冒頭数分から胸がムカムカして落ち着かなくなるような酷い駄作もある。しばしば「どれも同じ」と揶揄されるインドの娯楽映画に、こうも差が出来てしまうのはどうしてだろうか?また、どうしてもインド娯楽映画に馴染めない人がこの世に存在する一方で、言葉が分からないのにインド娯楽映画が大好きという人もいる。一体この差は何なのだろうか?娯楽映画追求のそもそもの出発点は、この2つの疑問点であった。
はっきり言ってまだ結論は出ていない。もうしばらくインドに住む予定なので、その間に何らかの結論が出ればと思っている。だが、今まで映画評を書き続けて来た中で、いくつかのヒントは得られたし、折に触れて提示して来たつもりである。それらを一度まとめてみようと思う。
●1.映画館で見なければ娯楽映画の良さは分からない。
映画は第一に映画館で上映するために作られるものであり、正当な評価をするためには映画館で見ることが最重要である。特に娯楽映画は、自宅では到底真似できない音響設備や、映画館という特別な場に宿る力を必要としている。よって、映画館で映画を見ていない人は、その作品を評価する権利を持たないことを肝に銘じるべきである。違法ダウンロードや海賊版などの手段を使って見るなど言語道断だ。
●2.娯楽映画には娯楽映画の評論の仕方がある。
社会派映画には社会派映画の評論の仕方があるし、芸術映画には芸術映画の評論の仕方がある。それと同様に、娯楽映画には娯楽映画の評論の仕方があり、異なるカテゴリーの映画と同じ方法や見方で娯楽映画を評価するのは無意味である。また、娯楽映画の正当な鑑識ができなければ、映画評論家としてはまだ未熟だと言わざるをえないだろう。
●3.インドにおける映画は、日本における漫画・アニメである。
社会における映画の立ち位置は、日本とインドにおいて異なる。インドにおける映画の立ち位置にもっとも近いメディアは、日本では漫画やアニメである。よって、日本の漫画・アニメを評価する目でインドの映画を評価するとちょうどいい。大衆の間での人気や、生活への密着度も、インドの映画と日本の漫画・アニメはとてもよく似ている。インド映画音楽と日本アニメ主題歌の各世代における浸透度も、かなり近いものがあると言っていい。
●4.インドにおける娯楽映画は、遊園地のアトラクションに等しい。
漫画からもう一歩踏み込んで、インドの娯楽映画を日本人が理解する鍵になるものを考えると、それは遊園地のアトラクションになる。遊園地に1人で行く人がいるだろうか?おそらくいないと思う。それと同様に、インドでも1人で映画館に行く人は稀である。インド人にとって映画は、家族や友達と共にワイワイガヤガヤと楽しむものである。遊園地のアトラクションに現実を求めるだろうか?むしろ現実からの逃避を求めるだろう。東京ディズニーランドは、敷地外の風景を訪問者に見せないようにどれだけ努力していることか。それと同様に、インドでも映画に現実性は求めない。遊園地のアトラクションから出るとき、悲しい気持ちになっていたいだろうか?そんな人はいないだろう。ファンタジー、ノスタルジー、スリル、サスペンス、恐怖、笑い、そしてそれらを親しい人々と共有する幸福感、それらの感情が混ざり合い、昇華して出来た満足感を求めて、人は遊園地へ行く。インドでも、人はみんなで楽しい気持ちになるために映画館へ行く。遊園地での楽しい思い出がある人なら、インド娯楽映画を理解することは難しくないはずだ。
●5.優れた娯楽映画を作るのはもっとも難しい。
芸術映画、社会派映画、ドキュメンタリー映画などなど、娯楽映画と対極にある映画の数々は、限られた観客をターゲットに作られている。だが、娯楽映画が対象とするのは、大袈裟に言えば老若男女全ての人々である。特にインドは様々な意味で格差の激しい国だが、娯楽映画の制作者の多くはなるべく全ての人々に楽しんでもらえるような映画作りをしている。そのためには、都会のインテリ層を唸らせると同時に、農村の無教養層の人々でも理解できるようなプロットにしなければならない。ターゲットが広ければ広いほど、映画作りが困難になることは容易に想像が付く。さらに、娯楽映画は関わる人数も多い。大スターを起用すれば、彼らの身勝手な振る舞いに耐えなければならないし、プロデューサーやスポンサーが口出しをしてくるような人物だったら、それらにもいちいち耳を傾けなければならない。大衆娯楽映画の制作者は、創造性だけでなく、あらゆる能力を要求される。実は娯楽映画の制作がもっとも難しいのではないかと思う。
●6.娯楽映画の核は、感情のコントロールである。
最高に面白い娯楽映画を見ているとき、ふと無理をして客観的になり自分を眺めてみると、映画によって感情がうまくコントロールされているな、と気付く。その現象は感情移入という言葉で置き換えることも可能かもしれないが、特定の登場人物に自分を同化させるというよりも、スクリーン上で起こっている出来事によって自分の感情がいいように操られているという感覚の方が強い。「インド映画を見るときは脳みそを家に置いて行くべし」とよく言われるが、むしろ優れたインド娯楽映画は、観客の感情を完全に掌握し、脳みそを使わせる暇を与えないのである。途中で歌と踊りが入っても、舞台が突然スイスに移ったとしても、感情は自然にそれを受け容れる。むしろ歌と踊りは感情を高ぶらせ、感情のコントロールを助長する。また、娯楽映画で重要なのは、ラストを必ず観客の期待する方向へ持って行くことである。観客に、「こうなればいい、こうなってほしい」と散々思わせ、一旦それは実現不可能だと提示して、その洪水のように押し寄せる希求の念をせき止めておきながら、ラストギリギリで観客が切望する通りの終わらせ方に持って行くことで、ダムから一気に大量の水が放出されたかのように、観客は怒濤の満足感を得ることができる。優れた娯楽映画というのは、観客の感情を上手にコントロールして巨大なダムに誘導し、目一杯ため込んで、絶妙なタイミングでそれを鮮やかに解放させることに成功した映画だと言える。よって、「観客の予想を裏切る衝撃の大どんでん返し」みたいな仕掛けは、ホラーやサスペンスのような特殊なジャンルを除き、娯楽映画には必要ない。予定調和という言葉がインド娯楽映画の批判によく使われるが、それはむしろ娯楽映画にとって欠かせない要素であり、褒め言葉であるべきだ。
それと関連し、インドに特有の現象かもしれないが、インドの娯楽映画では、伝統的な価値観や道徳観に沿った展開が好まれる。それは神様への信仰とその果報であったり、結婚の神聖性であったり、非暴力主義であったりする。観客の価値観や道徳観に沿った展開を見せることで、感情のコントロールは容易になる。それは端的に言えば「正義は勝つ」であり、これは勧善懲悪と置き換えても問題ないだろう。ただし、正義は広義で捉えるべきで、たとえ主人公がマフィアであっても、マフィアなりの正義を貫けば、それは観客も受け容れる。インドの宗教用語で言えば、「ダルマ」の遵法が観客の感情のコントロールの重要な要素になる。
逆に、つまらない娯楽映画は感情のコントロールで失敗していると言える。感情は行き場を失い、現実に引き戻され、理性が働くため、退屈になってしまう。あたかも空に放たれた凧が風を得られずに地上に落下するかのように。また、娯楽映画を楽しめない人は、感情のコントロールを映画に任せていないのではないかと思う。言語や文化の違いが壁になっている可能性もあるし、偏見や先入観などの他の要素が邪魔していることもあるだろう。娯楽映画を楽しむ際に、感情を完全に解放することはとても重要だ。
最近、インドの娯楽映画の本質を追求する上で興味深い材料を与えられた。それは「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)である。「これでインディア」でも、既に映画評と考察を発表した。4月18日から日本でも一般公開が始まったようで、日本でのこの映画のレスポンスに大いに注目している。
周知の通り、「スラムドッグ$ミリオネア」は英国人監督ダニー・ボイルによる、インドを舞台とした英国映画である。だが、ダニー・ボイル監督はインド娯楽映画をかなり研究しており、インド娯楽映画の持つ徹底した娯楽性を取り入れながら、自分のスタイルも併存させるという離れ業をやってのけている。「歌って踊って」のボリウッド・スタイルの映画なんて、ハリウッドの映画監督なら、作ろうと思えば簡単に作れるだろう、と言う人もいるかもしれないが、やはりインドの娯楽映画には独自の文法があり、それはインド娯楽映画を見て育って来た者でなければなかなか真似できない。以前、米国の監督がボリウッド映画のスタイルを真似、サルマーン・カーンを主演に据えて撮った「Marigold」(2007年)という映画があったが、誰の記憶にも残らないような完全失敗作に終わった。スタイルだけ真似ても全く楽しくないのである。それを考えると、ダニー・ボイルの天才振りがよく分かる。彼は完全にインド映画のエッセンスを使いこなしている。よって、インドを愛する英国人監督が、インド人作家の小説を原作に、インドを舞台にして、インド人キャストやスタッフを使って仕上げられた「スラムドッグ$ミリオネア」は、インド娯楽映画と言い切っても完全に不適切ではない。
ダニー・ボイルは日本でも人気の監督であり、おまけに「スラムドッグ$ミリオネア」はアカデミー賞まで受賞した。通常のインド映画だと、日本で一般公開されても、「インド映画だから」というバイアスと共に見られ、不当に扱われたり無視されたりすることが多いのだが、「スラムドッグ$ミリオネア」なら、それらの偏見からフリーになることは必至で、まとまった数の公平な評価が得られるのではないか、そういう期待があった。インドの娯楽映画がどこまで日本の観客に理解されるか、または日本の観客がインドの娯楽映画をどこまで理解できるか、「スラムドッグ$ミリオネア」はそれを知るための絶好の試金石となり得た。
どうやら日本での「スラムドッグ$ミリオネア」の興行収入は、公開規模から見たら上々のようである。現在誰が日本の映画評論家の中心なのか知らないのだが、ネットで見られる範囲で確認した限り、概ね好評だ。だが、やはり特殊な映画であるためか、正確な評価をしている人は皆無である。また、様々なウェブサイトで一般人によるレビューも読むことができるのだが、インドのことはまだしも、映画の内容や娯楽映画の見方を理解していない人が少なくないように思えた。もちろん、映画は各人によって好きに受け止めていいのだが、話のついでによくある問題点に触れてみたいと思う。
まず、「スラムドッグ$ミリオネア」に関する日本人のレビューを見て感じたのは、「映画に国境はない」ことはないということである。つまり、映画に国境はどうしても存在する。インドのような大国では、州の境すら越えられない映画も多い。映画評で詳述したが、「スラムドッグ$ミリオネア」を理解するにはインドの知識が必須である。この映画は元々一般公開を念頭に作られたものではないため、特に観客を突き放している。日本一般公開時にどこまでそれが補足されたかは不明である。日本の映画館にはパンフレットと言う独自の伝統があるため、もしかしたらそれで補われている情報があったのかもしれないが、「スラムドッグ$ミリオネア」の批評や感想を読む限り、そういう感じでもなかった。「オレはインドを知っているからこの映画を完全に楽しめた、だが、インドを知らない奴らは到底この映画を理解できないだろう」そういう傲慢なことを言っているように聞こえてしまうかもしれないが、これはどうしようもない事実である。僕が日本とインド以外の映画をあまり見ないのも、インド映画を長らく見ている内に、「映画に国境はある」ということを痛感するようになったからだ。その国のことを知らずに、映画の正当な批評はできない。もちろん、そういう予備知識なしに普通に映画を楽しめている人も多いのだが、感情のコントロールという点では、どうしても映画中の出来事と距離が出来てしまい、流れに乗れていない部分が多かったのではないかと思う。
また、それとは逆に、「スラムドッグ$ミリオネア」をきっかけに、日本人の間で、インドの文化、伝統、社会問題や、インド人俳優やキャストへの関心が少しでも増えるかと期待した。前の文章と矛盾するようだが、映画はその国への関心を引き起こす絶好のツールでもある。映画産業が盛んな国ほど、その国の理解は容易になると言ってもいいだろう。「スラムドッグ$ミリオネア」がインドを舞台にしていることは、誰にも隠されていない。だが、「スラムドッグ$ミリオネア」をきっかけにインドの注目度アップとか、そういう現象も起こっていなさそうだった。多分、元から「スラムドッグ$ミリオネア」はそういう売り出し方をされていないのだろう。敢えて言うならば、「やっぱりインドは貧困の国だ」という印象のみが残ってしまったようだ。これはインド人自身が恐れていたことである。
だが、「スラムドッグ$ミリオネア」がインドの貧困を必要以上に強調して描写している云々の批判は的外れである。インド人自身がそういう声を上げるならまだしも、外国人である日本人がそういう感想を持つのはちょっとおかしい。インドで間違いなくもっとも美しいのは貧しい人々である。インドを旅行した人なら誰でも、つい貧しい人々にカメラを向けてしまったことはあるはずだ。モールにいるリッチなインド人をわざわざ写真に写そうとは思わないし、彼らを主人公にした映画が果たして「スラムドッグ$ミリオネア」ほど魅力的な映画になり得ただろうか?インドへの愛情は、自然に貧しい人々への同情へと向かい、彼らと直接接することで、それは彼らに対する尊敬に変わる。おそらくダニー・ボイル監督の心もそういうプロセスを経たのだと思う。「スラムドッグ$ミリオネア」からは、インドの貧困を強調してインドを貶めてやろうというような魂胆は微塵も感じられない。あるとしたら、それはインドを理解し、映像化しようとする真摯な心である。
インド人のレビューにもよく見られ、映画に批判的な日本人のレビューの中にもあったのが、「非現実的」という言葉である。過去の経験に関わることが、時系列に沿って、そのままクイズ番組のクイズとなって出題されるのは不自然で、幻滅したみたいな意見だ。そういう感想を持つ人々は、一体何をしに映画館へ行っているのだろうか?また、スラム出身の若者がクイズ番組で大金を掴むストーリーなどと言ういい加減なあらすじも散見されたが、そういう記述を見るにつけ、日本公開版の字幕に何か問題があるのではないかと疑ってしまう。「スラムドッグ$ミリオネア」は基本的にはラブストーリーである。もちろん、正確に内容を読み取っている人もおり、おそらく字幕などの問題ではないだろう。しかし、陳腐なラブストーリーに終結させてしまって失望したみたいな意見も見られた。なら同性愛でも描けば良かったのか?これらの読み間違いの多くは、娯楽映画の根本を理解していないことから起こるのだと思う。そしてそういう感想を持つ人々は、インド娯楽映画を無条件に馬鹿にする人々とかなり重なっているのではないかと推測する。
「スラムドッグ$ミリオネア」の音楽は多くの人々から絶賛されている。だが、そのクレジットのほとんどはダニー・ボイル監督へ行ってしまっており、作曲家のARレヘマーンの名前が滅多に出て来ない。それも残念なことである。
だが、まだ「スラムドッグ$ミリオネア」は日本では公開されたばかりであり、骨のある批評はこれから出て来るのだろうと期待される。娯楽映画とは何か、それを解く鍵がその中から見つかればと思う。
|
|



