 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
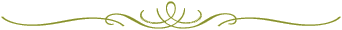
2003年6月
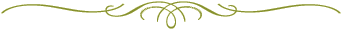
|
|
|
|
※旅行地図を用意しました。左の「旅行MAP」をクリックして下さい。
| ◆ |
6月1日(日) ボールプル&シャーンティニケータン |
◆ |
スィリーグリーからベヘラムプルまで、コールカーターに通じる国道34号線をずっと南下してきたのだが、これからは少し寄り道して、南西の方角へ向かう。今日の目的地はシャーンティニケータン。アジアで初めてノーベル賞を受賞したラヴィーンドラナート・タゴールが自分の理念を実現するための学校を建てた場所である。現在ヴィシュヴァバーラティーという大学になっている。ヴィシュヴァバーラティー大学の教育理念は自然との共存。自然と自由な雰囲気の中でのびのびと学ぶことができると聞いている。世界各国から留学生も多く学びに来ており、日本人の留学生も多いそうだ。
朝ホテルをチェック・アウトしてバススタンドへ向かった。ベヘラムプルのバススタンドは他のインドのバススタンドと同じく混乱を呈している。カオスである。四六時中バスが出入りし、車掌たちの叫び声があちこちから聞こえてくる。しかし不思議なことにこの混乱状態の中でバスはキチンと運行されているのだ。混乱の中の秩序とでもいうのだろうか。インドの合言葉「多様性の中の統一性」とも近いものがある。そして僕の想像は宇宙の誕生シーンまで飛んでしまう。宇宙が誕生する前もこんな状態だったのだろう・・・。そういうバススタンドの混乱ぶりを見ると僕はなぜか安心する。このバスの中のどれかが目的地へ行く、という妙な信頼感がある。道が通じている限りどこへでも行くことができる、という勇気が沸いて来る。逆にブータンの閑散としたバススタンドを見たときは、非常に不安になったものだ。
バススタンドでベヘラムプルからシャーンティニケータンまで直通で行くバスを探したがどうも直通バスはないようので、まずはサーンイーティヤーという町まで行くバスに乗った(29ルピー)。サーンイーティヤーは英語では「Sainthia」と表記されているが、これもベヘラムプルと同じくイギリス人が強引にアルファベット化してしまったもので、ベンガリー語ではサーンイーティヤーになる。
ベヘラムプルからサーンイーティヤーまでの道は幹線ではなく、ベンガルの村々や田園を横切るような田舎道だった。ベンガルの村の様子を見ていると本当に面白い。デリー周辺では見ることのできないようなものを見ることができる。家は藁葺きの屋根に泥を固めて造った壁。不思議な形をした小屋があったり、水瓶を埋め込んだ泥の隆起物があったり・・・通り過ぎていくだけなのでそれが何なのかを調べることができなくて残念だ。
8時半にベヘラムプルを出たバスは、11時にサーンイーティヤーに到着した。サーンイーティヤーのバススタンドの人々はなぜかフレンドリーで、僕を日陰に呼び込んでいろいろ質問してきたり、僕が持っていたミネラル・ウォーターを「ちょっと飲ませてくれ」と言ってきたりと、田舎的友好空間という感じだった。外国人、というか外部の人間を恐れることなく、ガバッと取り込む懐の広さがあった。こういうところからインド人の民度の高さを感じる。ちなみにサーンイーティヤーにはナンデーシュワリー寺院という古い寺院があり、そこはサティーの鎖骨が落ちた場所と言われているそうだ(サティーの神話についてはグワーハーティーのカーマーキャー寺院参照)。サーンイーティヤーには乗り換えのために立ち寄っただけだったので、観光はしなかったが、地元の人はしきりにそこへ行くことを勧めていた。
サーンイーティヤーから今度はボールプルという町を目指した。ボールプルへ行くバスは超オンボロバスで、半分木造、内部は山手線風の座席配列になっていた。サーンイーティヤーからボールプルまで14ルピー、11時半に出発して、ボールプルには1時半過ぎに到着した。バスの中が地獄の暑さだったことは言うまでもない。
ボールプルはシャーンティニケータンの隣町だった。そしてシャーンティニケータン観光のための拠点となる。ボールプルにはたくさんホテルがあるため、泊まるところには困らなかった。僕は西ベンガル州観光局経営のツーリスト・ロッジに泊まった。シングルが236ルピー。テレビ、タオル、石鹸などがあって、快適な宿だった。ただシャワーが天然ホットシャワーになってしまうのが駄目だった(屋上の貯水タンクが太陽の熱で高温化する)。
現在ヴィシュヴァバーラティーは夏休みで、キャンパスを歩いても面白くないだろうことは予想していた。ただシャーンティニケータンがどんなところが見てみたくて来たようなものだった。やっぱり大学のキャンパスに人影はまばらで、どこの建物も閉まっていた。幸いラヴィーンドラ博物館だけは開いていたので、そこを見てみることにした。ラヴィーンドラ博物館は名前の通りインドが生んだ万能の天才ラヴィーンドラナート・タゴールに関する博物館で、タゴールの住んでいた家の一部に展示物が並べられている。入場料は5ルピーで、カメラやバッグなどの持ち込みは禁止されている。
博物館にはラヴィーンドラナート・タゴールの生い立ちや業績の説明、彼の遺品や彼に関する物品の展示が中心だった。タゴールというと白髭モジャモジャの姿がイメージされるが、彼の若い頃の写真を見てみると、細身で長身なハンサム・ガイで驚いた。彼に関していろいろと書かれていたのだが、文字が小さすぎて読む気にならなかった。もっと分かりやすい展示を心掛けるべきだと感じた。展示品の中には世界各国から贈られた品物が多く並べられており、日本からのプレゼントもあった。彼が生きたのは19世紀後半から20世紀初めだが、その頃からタゴールは国際人として各国を遍歴して国際的名声を得ていたことに改めて驚かされる。また、近代史における日本とインドの関係も、タゴール1人の存在から始まったと言って過言ではないだろう。
シャーンティニケータンは広大な公園のような雰囲気だった。学生らしき人影は全く見当たらず、インド人観光客がちらほら訪れていただけだった。おそらく皆猛暑を避けてどこかへ行っているのだろう。学期中はどんな活気を呈しているのだろうか・・・。
一方、ボールプルは村というより町だった。シャーンティニケータンの近くにあるボールプルの町を歩いてみたがけっこう面白かった。昔ながらの伝統的な泥造りの家と、近代的なレンガ造りのオシャレな家が並んで建っていて、不思議な雰囲気だった。シャーンティニケータンはコールカーターの金持ちベンガル人の別荘地として人気があるという話を聞いた。おそらく泥造りの家の中に建っているオシャレな建物は別荘なのだろう。また、ボールプルからシャーンティニケータンに至る道にはお土産屋が並んでいた。大学なのに観光地、というのも不思議といえば不思議である。
夜になってホテルで偶然5年前にシャーンティニケータンでベンガリー語を勉強していたという日本人に出会った。今回は旅行でインドに来ているそうだ。シャーンティニケータンで日本語を勉強しているインド人と日本語で会話をしていたので、日本人だと分かった。おかげでヴィシュヴァバーラティーについていろいろ知ることができた。
ヴィシュヴァバーラティーの学費は以前はただ同然だったようなのだが、現在では外国人料金が設定され、1年間1500ルピーほどに値上がっているそうだ。大学の学費に外国人料金が設定されたのはデリーでも同じで、これはインド全土に共通の現象みたいだ。だが、年間1500ルピーという学費はデリーの大学に比べて非常に安い。家賃も平均1月1500ルピーを出せば満足のいく部屋を借りることができるそうだ。何より、シャンティニケータンでは金の使い道がないので、非常に安く生活することができるらしい。授業時間は朝9時〜11時と非常に短い。インドの大学では、先生が授業に来ないという事態がよく発生するが、ここでは先生はちゃんと教室に来ると言っていた。
一時日本人留学生は20人ほどここで勉強していたようだが、今はなぜか減少し、4、5人ほどのようだ。ヴィシュヴァバーラティーは音楽と絵画の教育で非常に有名で、芸術を学ぶために留学している人が多い他、ヒンディー語、ベンガリー語、オリヤー語などの言語を習得するために留学する人もけっこういるようだ。
シャーンティニケータンは「平穏の地」という名の通り、非常にのんびりとした雰囲気の場所だ。だからのびのびと芸術を学びたい人にはすごいいい場所だと感じた。しかし言語などの学問を学ぶにはちょっとのんびりしすぎかな、とも思った。僕はやはり、公害都市、人口爆発、政治都市などと悪口を言われても、現在インドで最も急速に発展しつつあるエキサイティングな街デリーに住むのが一番好きだ。
| ◆ |
6月2日(月) テラコッタの町ビシュヌプル |
◆ |
今日はシャーンティニケータンからさらに南西にあるビシュヌプルへ向かう。ビシュヌプルはテラコッタの町として知られ、テラコッタ(赤土の素焼き)で装飾された寺院がたくさん残っている遺跡の町である。16世紀から19世紀までマッラ朝の首都として栄え、歴代の王によって芸術が保護育成されたと言う。
昨日はボールプルのバススタンドであらかじめビシュヌプルへ行くバスに関しての情報を仕入れておいた。どうも現在はボールプルからビシュヌプルへ直接行くバスはないようで、何本もバスを乗り換えなくてはならないらしい。面倒だが、そうしなくてはならないならそうしなくてはならないだろう。地図で見るとシャーンティニケータンとビシュヌプルは100kmくらいかと思ったが、嫌な予感がしたので思い切って朝早く起きてバススタンドに向かった。
まずは朝一番の5時20分発のバスに乗ってイラームバーザールへ(8ルピー)。このバスは人を運ぶのか貨物を運ぶのかよく分からない状態になっており、大量の素焼きの壺を持った人や、魚の入った容器を持った人などが乗り込んで来て、バスの中はゴチャゴチャ状態だった。6時半頃にイラームバーザールへ到着した。
イラームバーザールは3本の道の交差点になっており、バススタンドなど存在しなかった。道端に立って今度はドゥルガープル行きのバスが来るのを待った。このときから既に、朝早く移動を開始したのは大正解だったと思っていた。同じことを日中やったら暑くて死ぬところだった。まだ日差しは柔らかくて、日向に立っていても汗ばんで来ない。
イラームバーザールからドゥルガープルへ行くバスは本数が少なく、道端には多くの人がバス待ちをしていた。30分ほど待っていたらやっとドゥルガープルへ行くバスがやって来た。ロケット・サービスというデラックス・バスで、ダージリンから夜行でやって来たようだ。何でもいいからとにかくドゥルガープルへ行かなくてはならない。インド人をも蹴散らす勢いでバスに乗り込んだ。席はなく、ほとんどずっと立っていた。イラームバーザールからドゥルガープルまで20ルピーだった。
イラームバーザールからドゥルガープルまでは案外近くて、30分ほどでドゥルガープルのバススタンドに到着した。ところが全然バスがない。ドゥルガープルの鉄道駅前が主要なバススタンドになっているようだ。そこでちょうど乗客を呼び込んでいたミニバスに乗って、ドゥルガープル駅まで行った(4.5ルピー)。
ドゥルガープル駅前のバススタンドにはビシュヌプルへ行くバスがあった。ところが非常に遠回りして行くようで、バーンクラーへ行ってからビシュヌプル行きのバスに乗ることを勧められた。というか半ば強引にバーンクラー行きのバスに乗せられた。このバスは8時過ぎに出発し、9時半にバーンクラーに到着した(15ルピー)。
バーンクラーから今度はコールカーター行きのバスに乗った。自分が現在どこをどう廻ってどこに来ているのか全くチンプンカンプンだったが、どうもビシュヌプルよりも西の地域へ来てしまっているようだ。バスは10時頃に出発し、11時過ぎにやっとビシュヌプルに着いた(14ルピー)。ボールプルからビシュヌプルまで行くのに、合計5本のバスを乗り継いだことになる。次の目的地まで行くのに乗り継いだバスの数の自己最高記録を達成した。
どうも西ベンガル州のバス網は、コールカーターを中心に放射線状に伸びており、地方都市⇔コールカーター間の交通は便利だが、地方都市間の移動は非常に不便だ。ベンガルというとインドを代表する文学と芸術の花開いた地域である。ラヴィーンドラナート・タゴール、ラヴィ・シャンカル、サタジット・レイなど、インドにあまり興味のない人でもピンと来る偉大な芸術家たちを輩出したのがベンガルだ。だから僕もベンガルに一目置いていた部分があるのだが、今まで実際に見てきた経験から言わせてもらうと、ベンガルは相当田舎で貧しい地域だと結論づけざるをえない。コーチ・ビハール地方に入ったときから気になっていた、ブラウスを着ていない女性の姿も、結局西ベンガル州全土で目にした。
ビシュヌプルでも西ベンガル州観光局経営のツーリスト・ロッジに宿泊した。シングル1泊250ルピー。部屋は広くて清潔。テレビ、石鹸、タオル、ギザルなどが完備されている。この他にも近くにいくつかホテルがあったので、宿泊するには困らない町だろう。
さすがに何度もバスを乗り換えて疲れたので、日中は昼寝をして休んだ。3時過ぎから行動を開始し、まずはホテルの近くにあるラース・マンチへ行った。予想していた通り、ここも外国人料金が設定されており、外国人旅行者は100ルピーを払わなければならなかった。しかし僕はヒンディー語で「デリーから来た」と言って押し通し、5ルピーで入った。しかしいちいちビシュヌプルの遺跡はあちこちに散らばっている。それらの遺跡に入る度に入場料を払わなくてはならないのだろうか・・・。
ラース・マンチは、インドで唯一というピラミッド型をした建築物である。1600年にマッラ朝の王ビール・ハンビールによって建造されたと言う。基壇部分の柱はよく保存されていたが、壁の表面の彫刻はくっきりとは残っていなかった。写真を撮るにも柵の外から撮った方が全体像を写すことができるため、わざわざ入場料を払って入るべき建築物ではない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ラース・マンチ |
● |
3時を過ぎてもまだ暑くて、この遺跡を見ただけで汗ビッショリになった。もう少し休もうと決めて、市場でマンゴーを買ってホテルへ帰った。明日は1日使ってビシュヌプルを観光する予定なので、急ぐ必要はない。
5時頃になって外に出てみると、空に暗雲が立ち込めていた。冷たい風がさっと吹く。さっきまでの猛暑が嘘のように涼しくなっていた。雲はゴロゴロと唸り声を上げている。まるで「Lagaan」の「Ghanan Ghanan」のイントロ・シーンのようだ。雨が降る・・・!ちょっと通りの様子を見てみると、インド人たちも外に出て涼んでいる。なんだかみんな嬉しそうだ。この雨がどんなに嬉しいか、酷暑期のインドをずっと耐え忍んできた者にしか分からない嬉しさだ。僕も思わず嬉しくなった。さすがに「Lagaan」のようにはいかず、期待通り間もなく堰を切ったように大雨が降り始めた。今酷暑期初の雨だ。すさまじい雨量、激しい風、そして耳をつんざく雷。まるで大地の全てを洗い流そうとするかのような嵐だった。しばらく呆然として外の様子を眺めていた。この自然の脅威の前には何の言葉も意味をなさない。ただただひれ伏すしかないだろう。僕はちゃんとした屋根のある建物の中にいるからいいが、ベンガルの田舎で見た泥の壁と藁葺きの屋根の家に住んでいる人はどうしているのだろうか・・・とふと心配になった。ちゃんと大丈夫なように造ってあるとは思うが。
そういえば、酷暑期と雨季の境目、雨が1回降った後のマンゴーが一番おいしいと聞いたことがある。マールダーのマンゴーは今頃どうなってるかな・・・と未練がましく考えを巡らしながら、さっき買ったマンゴーを口にほうばった。このマンゴーも十分うまい。
マッラ朝は695年から西ベンガル州バーンクラー地方を中心に栄えた歴史のある王朝だったが、ビシュヌプルが首都となったのはビール・ハンビール王の治世(16世紀)からである。ビール・ハンビール王の息子ラグナート・スィンハーの時代にビシュヌプルはサンスクリト語研究、音楽(ビシュヌプル・ガラーナーと呼ばれる)など、芸術と学問の中心地となり、また多くの優れた寺院が建築された。マッラ朝の繁栄は続いたが、18世紀初頭にマッラ朝の王となったラグナート・スィンハー2世はラール・バーイーというムスリムの女性に恋をして国事を忘れ、ラール・バーイーの誘惑に乗ってムスリムに改宗する寸前にまで至った。ところが彼の王妃がラグナート・スィンハー2世を殺害し、自身も火の中に飛び込んで自殺した(サティー)。ラール・バーイーもバーンドと呼ばれる人造湖に身を投げて自殺したと言う。この後マッラ朝には混乱期が訪れ、マラーターや近隣地域の侵略を受けることになる。1805年には財政難からマッラ王国の土地はイギリス東インド会社に売却され、こうしてマッラ朝と繁栄とビシュヌプルの栄華は終焉を迎えた。だが、マッラ朝時代に培われた芸術は今に至るまで伝わっており、ビシュヌプルはテラコッタ、金属製品、シルクやコットン製品などでも有名である。
ビシュヌプルには合計30の寺院が建っている他、マッラ朝時代の遺跡が散在している。大きな町ではないので全て徒歩圏内だが、日中の猛烈な日差しの中歩くのはかなり辛い。だから朝の涼しい内になるべく見ておこうと思い、朝5時頃に朝飯前の散歩に出掛けた。
ツーリスト・ロッジでもらったビシュヌプルの地図を見てみると、ビシュヌプルの遺跡は大まかに分けて3つのグループに分かれると思う。もっとも多くの遺跡が集中し、また重要な遺跡も固まっている城砦部分(ビシュヌプル中央部)、南部の遺跡群、そして北部の遺跡群である。ビシュヌプル・ツーリスト・ロッジは遺跡の観光に便利なロケーションにあり、ビシュヌプル中央部と南部の遺跡群には余裕で歩いていける。唯一北部の遺跡群だけは城砦部分を越えてけっこう歩いていかなければならない。
まずは城砦部分の主要な遺跡を見に行った。シャーム・ラーイ、ジョール・バーングラー、ラーダー・シャーム、ラールジー、パッタル・ダルワーザーなどなど数多くの遺跡が残っている。この中で入場料が必要なのはシャーム・ラーイとジョール・バーングラー。ラース・マンチと同じくインド人5ルピー、外国人100ルピーである。やはり群を抜いて素晴らしいのも上記の2つの寺院である。
シャーム・ラーイは1643年にラグナート・スィンハーによって建てられたラーダー・クリシュナ寺院である。ビシュヌプルの寺院の中でも最も美しい形をしており、壁面にビッシリと埋め込まれたテラコッタも非常に保存状態がいい。四角形の基部の上に、パンチ・ラトナ様式と呼ばれる五本の塔が建っており、ベンガル独特のデザインであるチャール・チャーラーが基部と3本の塔に施されている。
| ● |
|
● |
|
 |
|
|
シャーム・ラーイ |
|
|
 |
|
| ● |
シャーム・ラーイの壁の装飾
クリシュナとゴーピーのダンス |
● |
ジョール・バーングラーは本名をケーシュト・ラーイと言う。2軒のベンガル風民家をくっ付けたような変わった形をしており、この寺院も壁面のテラコッタが非常にいい状態で残っている。1655年にラグナート・スィンハーによって建てられた。中にはチャイタニヤが祀られているそうだ。ジョール・バーングラーもビシュヌプルを代表する個性的な寺院である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ジョール・バーングラー |
● |
ちなみに城砦といっても、別に城砦があるわけではない。昔は城砦になっていたのだろうが、今では野原となっている。ただ、盛り上がった丘のような隆起がいくつもあり、かつては壁だったのだろうと思わせるだけだ。唯一、パッタル・ダルワーザー(石の門)と呼ばれる城砦の北門だけは残っており、今でも地元の人々が門を通過して行き来している。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
パッタル・ダルワーザー |
● |
城砦地域を越えて北群の寺院にも足を伸ばしてみた。道を尋ねながら路地裏を通り抜けて北へ向かうとマダン・モーハンへ着く。この寺院は入場料はなかった。マダン・モーハンはマッラ王家の氏神を祀った寺院で、1694年にドゥリジャナ・スィンハーによって建築された。四角形の基部に1本の塔を持つエーク・ラトナ様式の寺院である。壁面のテラコッタは南側の壁にしか残っていないが、やはり保存状態はよい。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
マダン・モーハン |
● |
|
 |
|
| ● |
壁面のテラコッタ装飾 |
● |
ビシュヌプルの寺院はインドの他の地域では見られない独特の特徴がある。形が面白いことと、壁一面に埋め込まれた細かいテラコッタの装飾である。寺院の大きさはそれほど大きくなく、置物のようにちょこんと立っているような印象を与えるのだが、それがまた魅力的だ。ビシュヌプルは文句なく西ベンガル州でもっとも訪れる価値のある遺跡の町である。町の雰囲気ものんびりしていて観光客ずれもしていない。
昨日見たラース・マンチを含め、僕にスケッチしてみたいと思わせる建築物はシャーム・ラーイ、そしてジョール・バーングラーの2つだった。城砦部と北群の遺跡を見終えた後、ホテルで朝食を食べてまずはシャーム・ラーイへもう一度行った。シャーム・ラーイの周りは木で囲まれているため、日陰には困らない。アングルを決めて、レンガの破片に腰掛けてスケッチを始めた。7時45分頃だった。ところが8時を過ぎるとだんだん気温が上がってきて、とてもじゃないが落ち着いて絵を描ける環境ではなくなってきた。昨夜雨が降ったので少しは涼しくなるかと思っていたが、あんまり変化はないようだ。9時半頃にギブアップしてホテルに戻った。また明日の早朝スケッチすることにした。
ホテルの近くにはジョーゲーシュ・チャンドラ・プーラー・キルティー・バヴァン博物館という長ったらしい名前の博物館があった。昼食を食べた後にその博物館へ行ってみた。だが昨夜の大雨の影響からか電気が来ておらず、館内は暗くてパンカー(天井のファン)も回っていなかった。僕の泊まっているホテルにはジェネレーターがあるので電気には不自由していないが、どうもビシュヌプル全土は停電中のようだ。この暑さの中停電とは・・・。しかし博物館にもジェネレーターはあり、僕が訪れたことにより発電してくれることになった。
博物館の入場料は2ルピー。ビシュヌプル近辺から出土した石像、石器、金属器などが展示してあった他、2階はフォーク・アート・ギャラリーとなっており、地元のアーティストたちによる作品が展示してあった。この2階のギャラリーの方が見て面白かった。ナショナル・アワードを受賞したテラコッタのパールキー(御輿)は一見の価値があるだろう。また、バーンクラー地方の建築物の写真が展示してあり、ビシュヌプル以外にも多くの興味深い建築物がこの辺りに散在していることを知った。残念ながら多くの展示物にはベンガリー語でしか説明がしていなかった。あまり外国人は来ないのだろうか・・・。
ここのところ外に出て帰ってくる度にシャワーを浴びている。少し表を歩いただけで汗ビッショリになるからだ。博物館から帰ってからは暑いのでずっとホテルに缶詰だった。テレビを付けても昨夜の大雨でラインが切れたのか、何も映らない。暇なので、今日撮った写真を見ながらジョール・バーングラーの絵を描き始めた。ジョール・バーングラーの周りには適当な日陰がなく、スケッチは無理だと判断していた。だが是非描いてみたい建物だったので、原則には反するが写真を見てのスケッチをした。今まで現物を見て苦労して描いて来たが、写真を見て絵を描くと非常に楽である。だが完成した絵を見ると、どうも正確すぎて人間味がない。写真とあまり変わらない。やはり現場で現物を見て描いた方が、絵に揺らぎが出て魂のこもった絵になると思った。
5時頃になってやっと外を出歩けるくらいの気温になった。今度は南にある遺跡群を見てみることにした。南にはジョール・マンディル、ラーダー・ゴーヴィンダー、ナンドラール、ラーダー・マーダヴ、カーラーチャンドなどの寺院がある。この辺りは平野になっており、ポツンポツンと寺院が建っている。ひとつひとつの寺院は大したことないが、寂寥感あふれる平野の雰囲気がとてもよかった。国敗れて山河あり、というか人家が消滅して寺院だけ残っているのが不思議だった。やはりかつては壁だったと思われるなだらかな丘がなんとなくあちこちに残っていた。日が沈むまでそれらの寺院をブラブラと見て廻った。ラーダー・マーダヴとカーラーチャンドはインド考古学局のオフィスの敷地内にあり、オフィスではビシュヌプルのガイドブック(英語)を買うことができた(9ルピー)。
| ◆ |
6月4日(水) 斜陽の混沌都市コールカーター |
◆ |
早朝5時からシャーム・ラーイへ行ってスケッチを完成させ、ジョール・バーングラーの絵も実物を見て仕上げを施した。両方とも旅を締めくくるのにふさわしい絵になったと思う。その後ホテルへ戻って朝食を食べ、チェック・アウトしてバススタンドへ向かった。目的地は、今回の旅の終着点に選んだコールカーター(旧名カルカッタ)。インド4大都市のひとつにして、東インドの中心的都市である。コールカーターを訪れるのはこれで3回目、前回の訪問から3年以上が過ぎている。あれからどれだけ発展しただろうか、楽しみである。
ちょうどコールカーター行きのバスがバススタンドの前に停まっていたので、首尾よくバスに乗ることができた。ビシュヌプルからコールカーターまで54ルピー、152kmの道のりである。7時半頃にバスは出発した。
バスから見える風景は田園、農村、町、農村、田園、農村、町・・・というサイクルでもって変化していき、コールカーターに近付くにつれて次第に町が切れ目なく続くようになる。フーグリーの町を越えるともうそこはコールカーター圏内だ。コールカーター北部でフーグリー河を越え、ダクシネーシュワル寺院方面から市街地へ入った。さすがにコールカーターは大都会で、今回の旅で見てきたどの都市よりも交通渋滞がひどかった。コールカーターのバススタンドであるエスプラネードには11時半に到着した。
コールカーターの安宿街といったら何と言ってもサダル・ストリートだ。ホテル、レストラン、ネット・カフェ、旅行会社、古本屋など、旅行者に必要なものは何でも揃っている。そして当然のことながら旅行者をカモにすることを生業としている輩たちも大集合している。今までサダル・ストリートにしか泊まったことがなかったが、今回は敢えてサダル・ストリートを避けて、少し北のチットランジャン・アヴェニューあたりでホテルを探すことにした。しかしチェック・アウト・タイムの正午頃に訪れたにも関わらず、どこのホテルも満室で、あちこち彷徨った挙句、サダル・ストリートのホテルとあまり変わらないような喧騒の中にある小汚いホテルに泊まることになった。チャーンドニー・チャウクにあるホテル・サンシャインという名前で、シングルが250ルピー。あまり外国人が泊まりに来るようなホテルではないようで、ホテルの人も親切で、安全そうだった。
ホテルはサダル・ストリートを避けたものの、やはり一番訪れてみたいのもサダル・ストリートだった。ニューマーケットからサダル・ストリート辺りがコールカーターの一番の繁華街で、やはりすごい混雑だった。昔よりはオシャレな店舗が増えたような気がする。サダル・ストリートは案外閑散としていて、旅行者の数も少なかった。今は酷暑期なので、わざわざ灼熱のコールカーターに長居する旅行者は少ないのだろう。
今日はインド博物館を見てみることにした。今まで何度もコールカーターを訪れたにも関わらず、サダル・ストリートの入り口にあるインド博物館は一度も入ったことがなかった。インド博物館はインドで最初に造られた博物館であり、インド最大の博物館でもある。だが博物館のくせに入場料に学生料金はなく、外国人は問答無用で150ルピー払わされた。
インド博物館は3階建ての巨大な建物で、中心部は吹き抜けになっており、中庭がある。建築自体は贅沢な空間の取り方がしてあるのだが、展示物は所狭しの並べられており雑多な印象を受ける。だが展示物は広範なジャンルを網羅しており、さすがインド最大を謳うだけはある。ただ、現在改装中で、いくつかの部屋は入ることができなかった。
個人的に一番面白かったのは、1階の奥にあったインドに住む各種部族についてのコーナー。稚拙なジオラマと共に、いくつかの部族の紹介がしてあった。インドには未だにほとんど文明社会と接せずに暮らす部族がたくさんいる。今回の旅で見ることができたカースィー族やジャインティア族も部族だが、どちらかというと文明に順応している人々である。解説を読んでみると、部族の中にはけっこう母系社会の習慣を持っている人々が多いことに気が付いた。メーガーラヤ州やブータンなどで母系社会を目の当たりにしたので、母系社会は今回の旅のテーマになっている。現在の世界を見てみると、基本的に父系社会の習慣を持った民族が幅を利かせているように思われる。だからどうしても父系社会を基準に物事を考えてしまうが、もしかしたら母系社会の方がより自然に近い形なのかもしれないと思い始めた。また、展示されていたインドのトライブの中でも一番興味深かったのはアンダマン・ニコーバル諸島に住む人々だった。人種はネグロイドに分類され、裸族であり、人口は150人ほどしかいないらしい。アンダマン・ニコーバル諸島もいつか訪れなければならないだろう。
インド博物館で気に入らなかったのは、複製品に「複製品です」という説明が全然なされていなかったことだ。インド各地の遺跡や博物館を制覇してきた僕の目から見て明らかに複製品だと分かるものが、あたかも本物であるかのように堂々と展示されているので、インド人の中にはそれが本物だと信じてしまう人もいるのではなかろうか。また、順路が非常に分かりにくい。150ルピーを払って入場する外国人には、博物館の地図が印刷されたチケットが渡されるので、それを見て廻れば見逃すことはないだろう。だが、インド人は地図もなしに行き当たりばったりで巡っているので、2階の奥にある魚やテキスタイルのコーナーなど見逃す人が多いのではないかと思った。
インド人もたくさん訪れていたのだが、彼らに一番人気があったのは、面白いことに動物学の標本コーナーだった。いろんな哺乳類の標本が展示してあって、なぜかインド人はひとつひとつじっくりと標本を見て廻る。そんなに動物が好きだったら動物園に行けばいいのに・・・。
■博物館で耳にしてちょいウケした会話
子供「マミーはどこ?」
母親「何言ってるの、私はここよ」
子供「マンミー(お母さん)じゃなくてマミー(ミイラ)!」
インド博物館にはエジプト・コーナーがあり、ミイラが展示されている。ここもインド人には人気のコーナーのようだ。ほとんど偽物ばかりだったけど(ミイラは本物かも)。
| ◆ |
6月5日(木) バッチャン寺院を訪ねて三千里 |
◆ |
以前からコールカーターで是非目にしておきたいと思っていたものがあった。インド映画史上最大の映画スターにして、現在でも現役で活躍中の白髭ノッポおじいさんアミターブ・バッチャンを祀った寺院がコールカーターに存在すると言うのだ。いったい世界中のどこに現役映画俳優が寺院に祀られるような国があるだろうか?とにかくインド映画ファンとしては一度は参拝しておかなければならない場所だと心をくすぐられていた。
アッサム州を旅行していたときから、コールカーターの人に会う度にアミターブ・バッチャンの寺院についてそれとなく尋ねてみていた。ところがどの人も口を揃えて「そんなものはコールカーターにはない」と言う。中には「アミターブ・バッチャンは自分のために金を稼いでいるだけだ。そんな奴を祀るような馬鹿がどこにいる?」とか「外部の人が勝手に噂を流しているだけだ。全く馬鹿馬鹿しい。」と怒りを露にする人までいて、実在性が疑われてきた。しかしデリーでは本当にまことしやかに「コールカーターにアミターブ・バッチャン寺院がある」とささやかれているのだ。火のないところに煙は立たぬ、という諺もある。何らかの噂の火種はあるはずだと確信していた。
コールカーターに来て、さてどうやって探そうかと思案を巡らせてみた結果、やはり旅行者の集まるサダル・ストリートに情報は集まるだろうと思い、今日も朝サダル・ストリートへ足を運んでみた。コールカーターを訪れたことがある人で知らぬ者はいないと思われるほど有名なバックパッカーの溜まり場、ブルー・スカイ・カフェに入り、朝食を食べながら店の人にふと聞いてみた。すると日本語も少ししゃべれるフレンドリーなウェイターがいきなり有力な情報をくれた。「ベーハーラーにアミターブ・バッチャンの像があって、寺院のようになっているみたいだよ。」それだ!
ベーハーラーはコールカーター南部にある町の名前のようだ。行き方も教えてもらったので、ダラムタッラーから市バスに乗って、南コールカーターを目指した。ジャワーハルラール・ネルー通り(旧名チョウロンギー通り)に沿ってまずは南下して行ったが、この通りはやはりコールカーターの背骨にあたるだけあって、通り沿いには多くのモダンな店や銀行、会社のオフィスなどが続いていた。途中高級住宅街のような地域も通り抜け、バリスタも発見した。30分ほどでバスはベーハーラーに到着した。
とりあえず見回してみたところ、アミターブ・バッチャンの像らしきものはない。そこで土地の地理にもっとも詳しいであろうオート・ワーラーたちに聞いてみた。だが、彼らも口を揃えて「そんなものはここにはない」と言う。店の人などにも聞いてみたが、やはり「そんなものはここにはない」という答え。代わりにベーハーラーにはクリケットのインド・チーム主将サウラヴ・ガーングリーの家があるという情報は得た。だがあまり興味はない。
くじけずに情報収集を続けたところ、あるオート・ワーラーがふとつぶやいた。「もしアミターブ・バッチャンの像があるとしたらキャンサー・ホスピタルだ。バッチャンらボリウッドのスターたちが建設費用を寄付したから。」それか・・・!?
キャンサー・ホスピタルはベーハーラーからそう遠くはなかった。バスに乗って3Aバススタンドというところまで行き、そこで乗り合いオートに乗ってキャンサー・ホスピタルと呼ばれる病院に辿り着いた。名前の通り、ガンの研究・治療に取り組んでいる病院のようだ。しかしここにもアミターブ・バッチャンの像はなかった。受付で質問してみてが、質問が馬鹿馬鹿し過ぎたのか、あまり相手にしてもらえなかった。確かに病院でそんなことを聞くのはなんだか不謹慎である。
これで手掛かりは尽きてしまい、結局アミターブ・バッチャンの寺院を見ることは適わなかった。サダル・ストリートまで戻り、ブルー・スカイ・カフェの店員にベーハーラーにはなかったことを告げた。彼もそれ以上は知らないようで、お手上げ状態だ。店で食事をしていたインド人にもやっぱり「そんなものはコールカーターにない」と一笑に付されてしまった。「アミターブ・バッチャンに会いたかったらムンバイーに行け」とも言われた。別にファンだから探しているわけでもないのだが・・・。
いったいアミターブ・バッチャン寺院がコールカーターにあるという噂はどこから生じたものなのだろうか?デリーでは多くの人が知っていた既成事実だったのだが、当のコールカーターでは全く相手にしてもらえない。不思議な都市伝説である。インド7不思議のひとつにカウントしてもいいくらいかもしれない。もしこのホームページを見ている人で何か情報を持っている人がいたら是非連絡してもらいたい。
1ヶ月以上旅行をしていて、見たい映画がかなり溜まっている。数週間前に封切られた、傑作っぽい雰囲気だった「Armaan」はどうやら駄作だったようで、ロング・ランしていない。残念ながら見逃してしまったかもしれない。しかし同じくらいの時期に封切られた「Andaaz」はまだ上映されているので、いい映画だということが予想された。また、ちょうどコールカーターでは、市内で最も高級映画館と言われるパラダイス・シネマで「Andaaz」が上映されていたので、コールカーターの高級映画館観光と映画鑑賞を兼ねて、「Andaaz」を見ることにした。チケットはバルコニーで60ルピー。デリーに比べたら半分以下の値段だ。平日の3時の回にも関わらず映画館は満員御礼状態。「Andaaz」がよっぽどいい映画なのか、コールカーター人は暇で映画好きなのか、はたまたただ単に涼みたいだけなのか。
「Andaaz」のキャストはアクシャイ・クマール、プリヤンカー・チョープラー、ラーラー・ダッター、ジョニー・リーヴァルなど。プリヤンカー・チョープラーは2000年度のミス・ワールド、ラーラー・ダッターは2000年度のミス・ユニヴァースという豪華女優陣である。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Andaaz |
● |
| Andaaz |
ラージ(アクシャイ・クマール)とカージャル(ラーラー・ダッター)は幼馴染みの親友だった。ラージは飛行機のパイロットになるのが夢で、パイロットになった暁には上空でカージャルにプロポーズをしようと心に決めていた。ラージは空軍に入隊し、1年半の訓練を受けて帰ってくる。
ところが1年半の間にカージャルには恋人ができていた。カランという大金持ちで、ヘリコプターやセスナ機を所有しており、彼はカージャルに上空でプロポーズをした。カージャルはただラージに聞いてから返答すると答えていた。ラージが空軍から帰ってくると、カージャルはラージをカランに引き合わせる。カランはラージに、カージャルに対する気持ちを打ち明けて、どうか結婚する許可を与えて欲しいと頼む。自分の幸せより他人の幸せを選ぶ性格だったラージは、ついそれを承諾してしまう。
カージャルとカランの結婚式の日。ラージは何とか気持ちをこらえて2人を祝福するが、最後には耐え切れなくなって会場を去る。それを見たカージャルは、ラージが自分を愛していたことに気が付く。しかしもう遅い。カージャルはラージに言う。「1人の大事な人が去ってしまったからと言って、人生が終わるわけではないわ。自分の幸せのために生きて、ラージ。」
傷心のラージは、誰とも結婚する気にはなれず、ただ空軍の訓練に打ち込むだけだった。あるときラージはアメリカへ特別訓練を受けに行く。そこのディスコでジーヤー(プリヤンカー・チョープラー)という遊び好きなインド人の女の子と出会う。ジーヤーはラージに惚れ込むのだが、ラージは全く受け付けない。しかしジーヤーは諦めない。必ずラージを自分のものにしてみせると決意する。
アメリカでの訓練を終えてインドに帰ったラージは、自宅に新しくペイング・ゲストが住み始めたことを知る。なんとそれはジーヤーだった。ジーヤーは既に家族の心を掴んでおり、ラージはジーヤーとの結婚を迫られる。家族の説得に折れたラージはジーヤーとの結婚をOKする。
ところが、偶然にもジーヤーは実はカランの妹だった。カランとカージャルの結婚式にはたまたま試験のために来ていなかったのだった。そして知らない間に大事件が起こっていたことをラージは知る。カランとカージャルは悪天候の中ヘリコプターで飛び立ってコントロールを失って墜落し、カージャルは助かったもののカランは死亡してしまった。だが、カランが死んだことを知ったカージャルは精神に異常をきたして植物人間同然になってしまっていた。
カランはカージャルを必死に看病し、かつてカージャル自身がカランに言った言葉「1人の大事な人が去ってしまったからといって、人生が終わったわけではない」と語りかけ、彼女を正気に返らせた。カージャルはカランとジーヤーが結婚することを知って喜ぶが、ラージの心は既にカージャルへと向かっていた。それを見たジーヤーはショックを受け、一計を案じる。
ジーヤーはカージャルをパーティーに招待し、赤色の派手なサーリーを着て、精一杯着飾ってくるように頼む。カージャルは「インドでは、未亡人はこんな派手なサーリーを着ることは許されない」と拒むが、ジーヤーは強引に彼女を着飾らせる。パーティーで派手に着飾ったカージャルを見た年配の女性たちは眉をひそめる。だがジーヤーは彼女たちに「夫が死んだからといって未亡人の人生が終わったわけではない」と言い放ち、さらに「今日のパーティーはカージャルの再婚のためのものだ」と突然宣言する。驚くカージャルの前に、花婿が現れる。カージャルが拒否するとジーヤーは叫ぶ。「あなたはラージを愛しているから再婚しようとしないんだわ!」
それを聞いたカージャルはむきになってその花婿から結婚指輪を受け取ろうとするが、それをラージが止めた。ジーヤーはラージに「あなたとカージャルはどういう関係だっていうの!?」と言うと、ラージは「こういう関係だ!」と言ってカージャルの額にスィンドゥールを付ける。そして言う。「オレはカージャルを愛している!」
実はジーヤーは、ラージとカージャルを結びつけようとして全てのことを企画したのだった。ラージとカージャルが結婚するには、みんなの前で全てをさらけ出すしかなかった。他の人々も2人の結婚を祝福し、こうしてラージとカージャルは結ばれたのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インド映画にしかありえない強引なストーリーだったが、泣ける映画だった。前半がもっとも盛り上がり、後半の序盤は退屈で、終盤で「やれやれ何とかまとまった」という流れだった。
まずは子供時代のラージとカージャルの出会いからストーリーが始まる。最初ラージは補助器を付けないと歩くことができない足の弱い子供だったが、カージャルの励ましのおかげで走れるようになり、やがてサッカー・チームのエースにまでなるという設定だった。この辺りは完全に「フォレスト・ガンプ」のパクリでちょっと白ける。そういえば「Rishtey」という映画でも同じようなシーンがあった。もういい加減あのガンプが走り出す感動的シーンの二番煎じはやめようよ・・・。
ラージは子供の頃からカージャルに恋していたようで、空軍に入ったのもカージャルにプロポーズするためだった。ラージは、カージャルも自分のことを愛していることを疑っておらず、「『I Love You』の言葉がなくてもオレたちは愛し合っているんだ」と思っていたようだ。この辺りにアジアの男の心理の共通性を感じた。ところがどっこい、カージャルはどうも別にラージと結婚したいと思っていたわけではないようだ。空軍から帰って来たラージに、カランとの出会いからプロポーズまでを無邪気に語るカージャルにはムカッと来てしまった。ラージはいわゆる「いい人」だったため、ついついカランとカージャルの結婚を許してしまう。
カランとカージャルの結婚式は前半のクライマックスであり、映画中もっとも泣けるシーンだ。インド映画の定型通り、結婚式シーンはミュージカルになるのだが、そこで歌われる歌がとてもいい。「恋をしたらすぐに気持ちを表すべきだよ、手遅れにならない内にね」というフレーズが繰り返される。涙をこらえながらラージがその歌を歌うのだ。また、カージャルがラージに言う「大事な人が去ってしまったからといって人生が終わったわけではない」というセリフもいい。この言葉は後半でラージがカージャルに返すことになり、物語の中で最もテーマ性のあるセリフだ。
ジーヤー役のプリヤンカー・チョープラーが登場する後半になって急に映画は安っぽくなってしまうのが残念だ。今回プリヤンカーはアメリカ在住のイケイケ・ギャルを演じていたが、彼女にこういう役はあまり似合わない。インテリジェントな役をやらせた方がいいと思う。ジーヤーはラージのストーカーとなって彼を悩まし、やがてラージの実家にまで押しかける。こんなことするインド人女性が果たしているのだろか?現実味がない。
ジーヤーがカージャルの夫の妹だったことが発覚してから物語は再び悲劇性を増し面白くなる(それにしても強引過ぎる!)。カージャルはカランを失った悲しみのあまり植物人間になってしまっていたが、ラージはかつて彼女が自分を励ました言葉をそのまま返して彼女を回復させる。だが同時にジーヤーの嫉妬が始まり、三角関係が発生する。
インド人の観客が一番盛り上がったのは、このラージ、カージャル、ジーヤーの三角関係を象徴的にミュージカルにした「Ishq Na Ho Jaye」だ。このミュージカル・シーンはテレビでもよく流れており、ヒットしている。カージャルへ向かうラージ、どうしていいのか分からず立ち尽くすカージャル、そしてラージを我が物にしようとするジーヤーが砂漠や海岸で踊りを繰り広げ、けっこうかっこいい。
ジーヤーは、ラージを手に入れるためなら手段を選ばない悪女のようなキャラクターへと変貌して行くが、最後の最後で、実はジーヤーはラージの幸せのために自分の幸せを捨てる決意をしていたことが分かる。ラージとカージャルが結ばれたのはよかったのだが、ジーヤーの決着は着いてない。第二のラージが生まれてしまったことになり、物語としては完結性に欠ける。
映画の中で、インド社会における未亡人へのタブーについての批判がなされていたが、ちょっと唐突過ぎて蛇足だった。インド人の女性は、夫が死ぬと真っ白なサーリーを着ることしか許されず、装飾品も一切身に付けてはならない。未亡人の再婚も認められていないことになっている。だが、都市部を中心にこれらの習慣は次第にルーズになって来ている。
「大事な人がいなくなったことは、人生の終わりを意味しない」という言葉は、インドの未亡人に向けられた言葉なのかもしれないが、どちらかというと失恋して落ち込む人への励ましの言葉と受け取った方が無難だろう。全体としてとてもいい映画なので、ブロークン・ハートな人々にオススメである。
パラダイス・シネマはコールカーターで最も高級な映画館とのことだったが、デリーの高級映画館と比べたら全然格下だった。音響がよくないのと、バルコニー席がスクリーンに遠すぎるのと、トイレや椅子が汚ないことがマイナス要因だった。コールカーターはやはり斜陽の都市のようだ。
| ◆ |
6月6日(金) プールヴァー・エクスプレス |
◆ |
今回の旅行を振り返ってみると、ほとんど全て予定通りに進行し、行きたかったところは全て行ったという満足度の極めて高い旅になった。ダージリンで思わぬ足止めをくらったのと、ブータンでトンサへ行けなかったのと、コールカーターのバッチャン寺院は発見できなくてことぐらいが心残りなだけだ。今日はデリー行きの列車に乗る。
列車のチケットはあらかじめスィリーグリーで取っておいた。コールカーターのハーウラー駅を朝9時10分に発車し、24時間後にデリーに到着するプールヴァー・エクスプレスである。ハーウラー駅はフーグリー河の対岸にあり、非常に混雑する橋を渡っていかなければならないので早めにホテルを出た。まだ朝早かったため、全く道路も橋も混んでいなくて、20分くらいでハーウラー駅に着いてしまった。
ハーウラー駅に着いてみると、どうも不穏な雰囲気。プラットフォームに列車がほとんど停まっておらず、電光掲示板にも数本の列車の発車時刻しか出ていない。しばらく待っているとアナウンスが流れ、プールヴァー・エクスプレスは2時間20分遅れの11時半に出発と知らされた。明後日には日本に発つので、なるべく早くデリーに到着したかったのだが、これで2、3時間遅れることが決定した。溜息が漏れる。
それでもちゃんと11時半に列車は出発してくれたので、それだけでもありがたいと思わなければならない。今回利用したのはAC3ティアーズという等級の車両で、エアコン付きの寝台車両の中でもっとも安いものだ。エアコンなしの車両に比べて運賃は2倍ほど違うので、乗客層もだいぶハイ・クラスになり、安心して乗ることができる。エアコンなしの寝台車両と比べて微妙に清潔になっており、各乗客には無料で毛布、枕、シーツ、タオルなどが配られる。乗務員のサービスも微妙によくなる。列車のクラスが上がるにつれて微妙にサービスもよくなっていくこのシステムが非常にインド的で面白い。
インドの列車の旅ではいろいろな出会いがあって楽しいのだが、今回出会った中で一番印象に残ったのは自称ヨーギーのおっさん。突然朝になると列車の寝台でヨーガを始め、宇宙の真理について講釈を始めた。予言者じみたことも口走っており、僕に向かっていきなり「お前は遠くから何かを探しにこんなところまで来たようだが、お前の求めるものはここにはない。お前は別の方向行きのバスに乗っている」と語り出した。「お前が探すのをやめたとき、既にそれは手に入っていたことを悟るだろう」僕はインドで求めるもとを手に入れることはできないのだろうか・・・。何か気の遠くなるような思いになった。
プールヴァー・エクスプレスはドゥルガープル、パトナー、アリーガルなどを通過し、翌日の12時頃にニューデリー駅に到着した。なぜかデリーは非常に砂っぽくて、空は薄黄色い雲で覆われていた。これがルーと呼ばれる砂埃の風だろうか?
自宅のあるガウタム・ナガルに着いてみると、なんと全ての道路が舗装されており、ちょっと高級な住宅街になっていた。ビックリ!しかし僕の部屋は一面砂だらけになっており、ガックリ・・・。しかも部屋に着いた途端停電になって、ポックリ逝きそうになった・・・。
2002年度の大ヒット作となった「Raaz」以来、ボリウッドではホラー映画作りが流行している。2003年1月公開の「Kuch To Hai」は失敗作に終わり、「Darna Mana Hai」がカミング・スーン状態の中、本命の「Bhoot」が現在公開されており、大人気を博しているようだ。これは日本に帰る前に是非見ておかなければならないと思い、今日旅行から帰って来たばかりなのにも関わらず、映画館に直行した。
やはり「Bhoot」は大ヒットしているようで、上映時間30分前に行ってもチケットは取れなかった。そこで最終回夜10時からのチケットを買った。ホラー映画を真夜中見るという最も恐ろしい選択をしたことになる。映画館はラージパト・ナガルの3CS。どうもサウンド・エフェクトが相当怖いらしいので、絶対に音響のいい映画館で見なければ見た意味がないと思った。
「Bhoot」とはズバリ「オバケ」という意味。監督はラームゴーパール・ヴァルマー。「Company」の監督や「Road」のプロデューサーをしている、今もっとも注目されている映画監督・プロデューサーである。主演はアジャイ・デーヴガン、ウルミラー・マートーンドカル、ナーナー・パーテーカル、レーカー、ファルディーン・カーンなど、個性派俳優が揃っている。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左からファルディーン・カーン、レーカー、
アジャイ・デーヴガン、ウルミラー・マートーンドカル、
ナーナー・パーテーカル |
● |
| Bhoot |
証券会社勤務のヴィシャール(アジャイ・デーヴガン)は妻のスワーティー(ウルミラー・マートンドカル)と住むためのマンションをムンバイーで探していた。彼はとあるマンションの12階にいい物件を見つけるが、その部屋には忌まわしい過去があった。先住者のマンジートという女性がベランダから飛び降りて死んでしまったというのだ。しかし現実主義のヴィシャールはそんなことには頓着せず、その部屋に住むことに決めた。マンジートのことは妻には言わなかった。
すぐにマンジートの死についてはスワーティーの知るところとなるが、それ以来スワーティーは女性の幽霊に悩まされることになる。やがてスワーティーは夢遊病者のようになり、夜な夜な眠っている間に外へ歩き出すようになる。ヴィシャールは心理学者に相談するが、解決しなかった。
その内にスワーティーはヴィシャールの目の前で眠りながら歩き出し、1階にいた門番の首をひねって殺してしまう。刑事(ナーナー・パーテーカル)は事件の捜査をし、ヴィシャール一家が怪しいことに勘付く。また、それ以来スワーティーは別の人間のようになって凶暴化し、手が付けられなくなる。そこでヴィシャールは霊能者(レーカー)に相談する。
霊能者はスワーティーにマンジートの霊が憑依していることに気付き、彼女の死についての真実を聞き出すことに成功する。実はマンジートは気が違って飛び降りたのでも、自殺したのでもなく、マンションの大家の息子サンジャイにベランダから突き落とされたのだった。そしてサンジャイは門番を買収して、残されたマンジートの子供すらもベランダから突き落としたのだった。ヴィシャールらはサンジャイを呼び出し、マンジートが乗り移ったスワーティーと引き合わせる。サンジャイは白を切って逃げ出すが、スワーティーは彼を追いかけて殺そうとする。しかし霊能者は「スワーティーの身体を使って殺人をするのはやめなさい」と説得し、サンジャイに自白をさせる。するとスワーティーの身体からマンジートは消え、彼女は正気を取り戻す。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
非常に怖い映画だった。インド人もやればここまで怖い映画を作ることができるんだなぁと感心したと同時に背筋が凍りっぱなし、ドキッとさせられっぱなしの2時間だった。今まで公開された「Raaz」や「Kuch To Hai」にはミュージカル・シーンがあったり、お笑いの要素が少し入っていたりして、インド映画の定型から抜けきれておらず、ホラー映画としては失格だったのだが、この映画は観客を怖がらせることに徹底しており、一切お笑いなし、ミュージカルもなしである。
この映画の優れた点は、まずは先述の通りインド映画の定型から抜け出せたことにある。第二の点は、カメラ・ワークと音の使い方について、ハリウッドのホラー映画の手法がよく研究されていることにある。普通だったら何でもないようなシーンが非常に怖さを煽っている。エレベーターが昇ってくるシーン、ヴィシャールがマンションを出て行ってしまうシーン、スワーティーが鏡を覗き込むシーンなどなど・・・。薄っすらと笑みを浮かべる人形がストーリーの要所要所に映し出されるところや、スワーティーが夜キッチンに水を飲みに行くシーンなどはとても怖い。また、効果音もオーバーなくらいに使われており、オバケが出現するときに鳴る驚き音の他、ありとあらゆる音が恐怖を煽り立てる。
俳優の演技も素晴らしい。アジャイ・デーヴガンは「Company」辺りでシリアスな役柄に活路を見出してからあっという間にボリウッドで一二を争う演技派男優に成長を遂げ、この映画でも存分に演技力を発揮している。だが何と言ってもウルミラー・マートンドカルの体当たり演技は、ボリウッドの女優には今まであまり考えられなかったくらいのレベルだ。霊に憑りつかれてからの演技はオーバー過ぎるような気もしたが、その前の恐怖に怯えるシーンなんかは文句なく素晴らしかった。
よく出来た映画だったが、厳しい目で見れば少し足らない部分もあった。ヴィシャールらの部屋の隣に住んでいる、ずっと数珠を回し続けているお婆さんがいったい何者なのかは遂によく分からなかった。サンジャイのキャラクターについてもう少し時間を割いて説明すべきだった。心理学者の娘の死がどういう意図でストーリーに絡んで来たのか説明不足だった。マンジートの死の真相が明らかになるシーンはあっけらかん過ぎた。また、子供の幽霊もちょっと蛇足だったような気がする。だが細かい部分を気にする必要がないほど、映画館を出るときには背筋が冷たくなっているので、インド製ホラー映画としては突然変異的に大成功を収めた映画だと思った。
それにしてもホラー映画をインド人の観客と共に見ることほど面白いことはないのではなかろうか?ビックリ・シーンの前にはあちこちから「来るぞ来るぞ」みたいな予想の声が飛び交い、「ウギャー!」となった後はみんなで「怖かった〜」と大笑いしてホラー映画を遊園地的に楽しんでいる。前半は背後からワッと驚かすようなタイプの恐怖シーンが多いが、後半はウルミラーの迫真の演技と脚本で、ストーリーにグッとのめりこむような恐怖が多い。よって、後半はインド人もけっこう息を呑んで鑑賞していた。この映画はロング・ランするだろう。作品の完成度が高いことが一番の理由だが、映画館で見ることに価値がある映画なので、普段ケーブルTVで映画を見ている人たちを映画館に呼び込むことにも成功するだろう。また今年のインドは暑いので、ホラー映画は流行りやすいと思われる。超低予算映画なのは明らかなので(俳優の出演料は別として)、大幅黒字になる可能性も高そうだ。今年の重要な映画となるかもしれない。
| ◆ |
6月8日(日) Jajantaram Mamantaram |
◆ |
日本に帰る前にあとひとつだけ映画を見ておくことにした。「Ishq Vishq」「Khwahish」「Nayee Padosan」など是非見ておきたいヒンディー語映画があった中で僕が選んだのは「Jajantaram
Mamantaram」。子供向けのヒンディー語映画で、「Monsoon Wedding」や「Bend It Like Beckham」など良質のインド映画を連発しているiDream Productionの作品である。PVRナーラーイナーで朝10時半からの回を見た。
「Jajantaram Mamantaram」とは特に意味のない言葉で、映画中で合言葉としてよく出てくるフレーズである。主演はグルシャン・グローヴァー、ジョイ・フェルナンデス、ジャーヴェード・ジャーフェーリーなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Jajantaram Mamantaram |
● |
| Jajantaram Mamantaram |
典型的なムンバイーっ子のアディティヤ(ジャーヴェード・ジャーフェーリー)はアラビア海で遭難して小人の島に漂着する。島にはシュンディーという王国があり、ブーパティという国王によって統治されていた。小人たちもアディティヤもお互いの存在に驚くが、アディティヤは持ち前のユーモアでシュンディーの人々と仲良くなる。
一見平和そうに見えたシュンディーにも悪の権化がいた。将軍チャラン・スィン(グルシャン・グローヴァー)は王国を乗っ取ろうと画策しており、巨人ジャームンダー(ジョイ・フェルナンデス)を使ってシュンディーの人々を恐怖に陥れていた。アディティヤはジャームンダーを退治してますます村人たちの信頼を得る。
アディティヤの一番の親友は一般兵のジェーラーンだった。ジェーラーンはアディティヤに励まされてアモーリー姫と恋仲になるのだが、それを見たチャラン・スィンは国王に密告してジェーラーンを追放の刑にさせる。そしてチャラン・スィンの王国乗っ取り計画は本格的に始動する。アディティヤはパワーアップしたジャームンダーによって重傷を負わされ、国王らはチャラン・スィンによって幽閉される。
しかしジェーラーンを中心にシュンディーの人々は団結し、アディティヤを看病すると同時にジャームンダーに対抗するための武器を作った。ジェーラーンは国王救出に成功し、アディティヤも再度ジャームンダーと対決して打ち負かす。こうして王国に平和が訪れ、アディティヤはムンバイーに帰るために海へ去っていくのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
どうしても「ガリバー旅行記」が連想されるが、映画のウェブサイトを見ると原作はグジャラート地方に伝わるおとぎ話「バカースル」だと言い張っている。小人の国に迷い込むという設定なので、SFXがふんだんに使用されていたが、ハリウッド映画と比べるとまだまだ幼稚である。しかしインド映画のヴァラエティーが広がることはいいことだ。このような子供向けのファンタジー映画もインドで製作されるようになってくると、映画界全体にもいい影響が出ると思う。
ストーリーには脈絡のない部分がいくつもあった。アディティヤがシュンディーへ漂着するまでの過程がほとんど説明されていなかったり、途中意味のないキャラクターが出てきたり、アディティヤがどうやってムンバイーに帰るのかよく分からなかったりと、細かいところでもどかしいところはたくさんあった。だが子供向け映画ということであえて批判は避けておこう。主人公のアディティヤのキャラクターは賛否両論あるだろうが、面白かったのでこれも目をつむっておく。悪役のおっちょこちょいぶりは子供たちに非常に受けていた。
わざとやっているのか知らないが、セットはなんだか安っぽくて幼稚だった。学芸会の劇のような家や衣装をみんな着ていた。それらのデザインはインドのトライブの風俗が参考にされていると思う。
僕としてはあまり楽しめなかったのだが、まあこういうインド映画もたまにはいいかな、と思わせる映画だった。この路線でもどんどん映画を作っていくといいと思う。
少し時間が経ってしまったが、5月〜6月初めにかけての旅行中に考えたことをまとめておこうと思う。
今回の旅行でもっとも収穫だったのは母系社会の実例をいくつか目の当たりにすることができたことだ。メーガーラヤ州の部族はもっとも有名だが、その他アッサム州の田舎やブータンなどで見ることができた。母系社会と一口に言っても定義は様々だと思うし、僕自身もあまり理解せずに使ってしまっているところがあるが、僕個人の定義では、「結婚後に花婿が花嫁の家に入る習慣を持っている社会」で「遺産相続は女性構成員によって行われる社会」を母系社会と呼んでいる。必ずしも家族の家長が女性であることを意味しない。と言うより、母系社会でも家長は年上の男性が受け持つことが多いようだ。
地球上の部族、民族が全て父系社会か母系社会、どちらかのカテゴリーに分類されるのかどうかは知らないが、普通に日本で生まれて日本で成長してきた僕の目から見たら、父系社会が一応「当たり前のもの」として記憶されている。結婚したら花婿側の家に入るのは基本であるし、姓も花婿側のものに統一されるのが一般的だ。インドも結婚後にどちらがどちらの家へ入るかを見た場合、父系社会と定義することができるし、欧米の社会も基本的に父系社会だと言っていいだろう。
父系社会では財産は基本的に男性に相続され、家長も男性、社会の要職も男性で占められることが一般的だ。女性は家事を分担し、社会に参画する機会は男性に比べたら圧倒的に少なくなる。世界中で20世紀に入り、女性の社会進出が重要な変化となって表れたものの、男性中心の社会が根本から変わったかと言えばそうは言えないだろう。男は外で働き、女は家で家事をする、という考え、また男らしいことは何か、女らしいことは何か、という観念もあまり変わっていない。
だが、昔から母系社会の習慣を持っていた人々は、ごく自然に女性が社会を「構成」していた。僕が見た母系社会の中の女性たちは、積極的に社会に関わり、商売をし、サービスをし、起業していた。母系社会では女性に対するタブーもルーズなようで、彼女たちは非常にのびのびと生活している印象を受けた。一方、男性の方も負けず劣らず社会に参画しているのだが、それは都市に限られ、田舎へ行くと赤ちゃんをおんぶして子育てをしている男性の姿が目立った。話に聞くところでは、やはり母系社会では男性が家事を受け持つことが多いようだ。
そうなって来ると、父系社会の中で培われた男性観、女性観というのはいったい何だったのか、と自分のアイデンティティーを揺るがされる思いがする。いったい男性は本当に社会的・政治的な生き物だったのか、女性は家事・子育てをするのに適した生き物だったのか。父性、母性とは何か。社会が変われば簡単にひっくり返ってしまうものでしかなかったのではないか。
やがて僕は、もともと人類は母系社会だったのではないか、と考え出した。まず、遺伝子の流れから見たら母系社会がもっとも自然だ。夫婦に子供ができた場合、母親がその子供の母親である確率は100%である(代理母などの現代の特例は除く)。なぜならその母親からその子供が生まれたからだ。しかし父親がその子供の父親である確率は100%にはならない。現代では血液検査やDNA検査をすれば100%の実証ができるかもしれないが(それでも科学も所詮信用ならないから100%にはならないだろう)、昔の状況を考えてみたらそうはいかない。男にとってこれはとてつもない恐怖である。自分の子供が本当に自分の子供なのか、誰も確実な答えをくれないのだ。残されたのはただ「愛」という不確かなものへの信頼しかない。それがさらに恐怖を増大させる。これは感情としての恐怖というより、もっと本能的な、遺伝子の恐怖感だ。この恐怖が今までどれだけ男性を女性の圧迫へと駆り立ててきたか、女性はあまり理解できていない。妻を家に閉じ込めるような習慣を作り上げたり、なるべく多くの女性に遺伝子を注入しようと努力したり・・・。しかし残念ながら、遺伝子の流れは全て女系である。男性がいくら頑張っても、自分の遺伝子から自分の完全なる後継者を作り出すことはできない。だから自然の成り行きとして、人間の社会は母系社会が選ばれたと考えられる。母系社会の縦の連なりは、続いている限り確実に同じ遺伝子の連なりである。
また、人類が農耕を始めた段階でも女系社会の方が都合がよかったと思われる。農耕社会で重要なのは土地だ。農耕をするということはその土地に定住するということに等しい。だから代々土地を守っていかなければならないと同時に、土地の分割をなるべく抑えなければならない。家畜などだったらどんどん増えるので、分割しても構わないが、土地はそう簡単に増えるものではない。男系社会の場合だと、遺産相続の場合にその土地分割が発生しやすい。母系社会の場合も土地分割は起こりうるかもしれないが、少なくとも僕がインドやブータンで見た社会では工夫がなされていた。メーガーラヤ州の部族は一番年下の娘が遺産を相続し、ブータンでは一番年上の娘が遺産を相続することになっている。この遺産分割の観点から見たら、父系社会は家畜などが主な遺産となる遊牧民族向け、母系社会は土地が主な財産となる農耕民族向けだと言うことができると思う。
また、戦乱の多い地域でも母系社会の方が有利だろう。男は兵士として戦争に行って死ぬことが多いが、女は敵軍に蹂躙されない限り生き延びる。家族の系譜をつなげていくためには、いつ死ぬか分からない男を中心にするよりも、女を中心にした方がいいと思う。母系社会では女性の再婚にも絶対に寛容なはずだ。
日本もかつては母系社会だった、というのは一種の通説だろう。「源氏物語」の時代の貴族の妻問婚は有名だが、それ以前の古代日本、例えば邪馬台国もイメージとしては女性中心の社会だし、神話時代まで遡れば天照大神などの女神が想起される。和式の結婚式には母系社会の名残が見られるし、また現代でも家計を握るのは女性である場合が多いのは母系社会の残骸かと思われる。少し前に「愛子さま」の登場で女性が天皇になれるのかが取り沙汰されていたが、せいぜい2000年未満の日本の歴史を振り返れば可能、というよりそろそろなければおかしい、というぐらいだろう。だがあまり詳しくないので深くは言及しない。
インドの場合を見ても、どうも母系社会っぽい習慣が残っているような気がする。シヴァリンガ崇拝や女神信仰は母系社会の特徴のように思えるし、ダウリー(結婚持参金)も元々は母系社会の名残なのではないかと思える。元々母系社会だったところに、父系社会の習慣を持つ民族がやって来て、母系社会の上に父系社会をバンと無理矢理据えてしまったように思えてきた(これはアーリヤ民族のインド侵略説のイメージにピッタリだ)。
前述した通り、必ずしも世界中の民族が父系・母系に分かれるとは思えない。例えばブータンでは、結婚後に夫婦が花婿の家に住むか花嫁の家に住むか、また独立して住むかは、全く本人たちの自由のようだ。遺産相続にのみ母系社会の特徴が見られる。しかしこの世に男と女しかいないということは、すなわち父系社会か母系社会か、ということになると思う。そして概して父系社会よりも母系社会の方が人間を縛るタブーが少ないように思える。皆のびのびと暮らしている印象を受ける。現代の社会を見ると、少し前に比べて次第に女性が力をつけつつある。今の日本を見てみると、かえって男性よりも女性の方が好きなことができる社会になっていると思う。これは父系社会の崩壊と母系社会の復活を暗示しているような気がする。別に男性が権威を失っているのではなく、元の状態に戻りつつあるのだろう。
アッサム州、メーガーラヤ州、スィッキム州そしてブータンを旅行していたときによく目にしたのがオンブだった。背中で赤ちゃんを背負っている人が多かったのだ。何も用いず、空手で赤ちゃんをオンブすることもあれば、布などを使って赤ちゃんを背中にくくりつけてオンブすることもある。もし日本から直接それらの地域に行ったのなら別に変に思えなかっただろうが、インド平野部からそこへ行くと非常に新鮮に思える。なぜならインド人はオンブをほとんどしないからだ。
インド人の赤ちゃんの一般的な抱き方は、左右の腰骨の上に赤ちゃんの股をひっかけて、片腕で支える方法である。だから最大2人まで抱くことができる。ここでは仮に横抱っこと命名しておこう。横抱っこを一番よく目にするのは、赤ちゃん連れ乞食たちと会ったときだ。1人の赤ちゃんを横に抱えて、空いた手で喜捨金を要求する。乞食だけでなく、一般の人ももちろんその抱き方をする。インド人がオンブをしない理由は分からないが、僕は以前、インド人の女性は太っているからオンブしにくい一方で、腰の出っ張りが比較的大きいので、横抱っこしやすいのだろうと推測しておいた。インド人がオンブをするときは、かなり大きな子供を持ち上げるときくらいしか見ない。
なぜインド人はオンブをせず、東北部の人は横抱っこをしないのだろうか。これは旅行中ずっと頭を悩ませ続けた問題だった。しかしあるものを見たときにピンと来た。アッサム州、メーガーラヤ州、スィッキム州、ブータン(ネパールも)などの人々は、物を運ぶときに特徴的な籠を使う。籠の形状は地域で様々だが、共通なのは籠に紐が縛り付けてあり、その紐を頭に引っ掛けて固定するようになっていることだ。これに似た籠はアイヌ人も使っていると聞いたことがある。ちょうど肩掛けカバンを頭に引っ掛けて歩く中学生のような感じだ。実はインド平野部でも、ゴミ集めの人などが同じようにしているのを見たことがあるが、それでも平野部ではあまり一般的ではない。
その籠の利点と言えば、まず両手がフリーになること。そして山登りに適していることである。おそらく山の民族がその籠を積極的に使用していると予想できる。そう考えると、オンブもやはり山に住む民族特有の赤ちゃんの抱き方なのではないかと思われる。山を歩くのに両手がフリーでないのは危ないし、低い木や草の中を通り抜けていくのにも、オンブなら赤ちゃんをガードすることができる。
一方、横抱っこの利点と言ったら、着脱のスムーズさと通気性のよさだろうか。暑いインドだと、オンブをするより横抱っこをした方が肌を接する面積が少なくて涼しいし、サーリーの端などで赤ちゃんを日差しから守ってあげることも容易だ。またインド平野部では頭の上に荷物を乗せることが多いため、片手で頭の上の荷物を抑え、もう片手で赤ちゃんを抱く、という姿も見られる。
つまり、最終的な結論は、オンブは山の民族、横抱っこは平野の民族ということになる。日本はオンブの民族だ。とするとやはり起源は山の民族なのだろうか。
よく「インド全土でヒンディー語は通じない」とか「英語が通じるからヒンディー語は必要ない」などといった論を聞く。そういう話を聞くと、ヒンディー語を習っている僕としては悲しい気分になる。だが、本当にインド全土でヒンディー語は通じないのか、英語の方がインド全土で通じるのか、それを確かめるには実際にインド全土を巡って確かめてみなければならない。実はその使命を僕は勝手に自分に負わせて旅行をしているのだ。
一般に「ヒンディー・プラデーシュ」「ヒンディー・ベルト」などと呼ばれる、インドでヒンディー語が公用語として通用している地域は、北インドのみである。それらの地域では、多少の方言差はあれ、一応ヒンディー語が通じる。問題となるのはそれ以外のインドの地域であり、また最近では南アジアのインド隣接国である。僕が今まで確認した中で、口語レベルで十分ヒンディー語が通じた非ヒンディー・プラデーシュ(都市名で挙げていく)は、ジャンムー・カシュミール州のシュリーナガルとジャンムー、アーンドラ・プラデーシュ州のハイダラーバード、カルナータカ州のハイダラーバード、そしてケーララ州のティルヴァナンタプラムぐらいだった。今回は全く非ヒンディー語圏の旅行となったので、どれだけヒンディー語が通じるか楽しみだった。
結果は非常に満足のいくものとなった。アッサム州、メーガーラヤ州、西ベンガル州、スィッキム州の都市部ではヒンディー語がよく通じた。メーガーラヤ州のジョワイは英語もヒンディー語も通じなくて焦ったが、ある程度の大きさの街になれば、バススタンドや駅周辺、ホテルでは確実にヒンディー語が通じる。旅行者が集まる場所では、呼び込みなどもヒンディー語で行われていることが多い。さらにはブータンでもかなりの片言ながらヒンディー語が通用した。教養の高いインド人は別として、学校で習った程度の英語、ヒンディー語を知っている人なら、英語よりもヒンディー語が得意な人の方が多い(これはヒンディー語映画の普及のおかげだと思われる)。また、非ヒンディー語圏でも、英語で話すよりもヒンディー語で話す方が親しみを持ってもらえることは確実である。インド人にとって英語は外来語に過ぎないが、ヒンディー語は例え母語でなくても「我々の言語」という意識があると思われる。
また、インド東北部ではネパーリー語が案外通用していることに驚いた。西ベンガル州北部、スィッキム州、そしてブータンにはネパール系の人々が多く住んでおり、公用語もネパーリー語になっている。ネパーリー語はヒンディー語に似ており、文字も共通であるため、これがさらにヒンディー語受容を容易にしているとも考えられる。
インド東北部にはモンゴロイドが多く住んでいる。スィッキム州のレプチャ族、ネパール人、ブータン人、ノース・イーストの諸部族など。東北インド旅行は、アーリヤ民族の海からモンゴロイドの海の中にジャンプして飛び込むようなものでもあった。
不思議なのは、それらの各地域で、必ず日本にいてもおかしくない顔をした人々がいることだ。もちろんその中には知人にそっくりな顔をした人も発見する。ついついじっと見てしまって、相手を困惑させてしまうことも多々あった。
日本に帰ってきて今度は逆に、「ああこの人はあの辺の顔だな」とか「この人はあそこで見たな」とか、日本人を勝手に僕が今まで見てきた民族に分類して見てしまう。
アジアを旅行して面白いのは、「日本人って何だろう」という問いのヒントが所々で断片的に見つかることだ。民族の顔からもそれは感じるし、伝統的建築、ふとした習慣、言語、宗教などからも感じる。ただ、それらのヒントを正しく取捨選択してつなぎ合わせるのは非常に難しいことだ。ただ環境が似ているから、そこに住む人間も似てきただけなのかもしれないし、何の因果関係もなく偶然に似てしまった可能性も十分ある。素人や駆け出しの学者が「この民族は日本の祖先だ」とか「この言語が日本語の起源だ」と軽々しく提唱することは、「太平洋にムー大陸があった」「ノストラダムスの大予言によると1999年に地球が滅びる」と提唱するに等しいことである(蛇足だが、個人的にノストラダムスのあの有名な予言「1999年7の月・・・」は、2年2ヶ月遅れで的中したと思っている)。だが、直感から言えば、多くの人々が提唱している通り、インド東北部から中国雲南省辺りが、日本人の直接の故郷だと思われてならない。あんなに顔の似ている人たちがいる地域は、他にはないだろう。それと同時に、日本人には比較的多くの民族の血が混ざり合っているとも思われる。新しいところでは朝鮮人の混血があっただろうが、それ以前、日本人が日本人になる前には、かなり多くの民族との混血をくぐり抜けてきたはずである。アジアのどこへ行っても、全く別の国に来た感じがしないのはそのためだと思う。本当に日本人って何だろう・・・。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年7月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



