 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 これでインディア これでインディア 
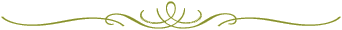
2003年7月
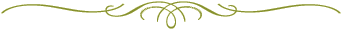
|
|
|
|
■FM豊橋出演
この「これでインディア」を作っていたおかげで出会うことのできた人というのはけっこういる。そういう出会いがあるたびに、ホームページを作っていてよかったなぁと思う。実はブータンを個人旅行できたのも、元をたどっていけばこのホームページがあったからなのだ。インドにモロ関係のあるサイトだけあって、インド関係者との出会いが多いのだが、今回は偶然にもインドとは全く関係ない人と出会うことができた。
僕の出身地は愛知県豊橋市である。愛知県というと名古屋がすぐに浮かぶ人が多いが(愛媛県とごっちゃにする人も案外多いが)、もともと名古屋のある尾張地域と、豊橋のある三河地域は別の文化圏だったと言って過言ではなく、概して豊橋市民は名古屋と一緒にされることを嫌う。方言もかなり違う。三河弁というと「じゃん・だら・りん」が有名だ。文末にとりあえず「じゃん」「だら〜」「りん」をつければ、三河弁になる。「じゃん」は今では割と全国的に通用するようになったが、もともと三河地方の方言だったものが、東海道を通って静岡、神奈川と上京し、東京まで達したと思われる(文献では長野で「じゃん」が最も早期に使用されている、という話を聞いたことがある)。新幹線が止まるので、豊橋の名はまあまあ認知度があるのではないか、と自負している。
いつ頃からか豊橋にはブラジル人が多く住むようになった。豊田と浜松という日本の二大工業地域の中間点にあり、また大きな港もあるため、工場などで働く外国人労働者に都合のよい土地だから、という説を聞いたことがある。そうでなくても豊橋は日本の住みやすい街の上位にランクインされることが多いので、外国人にとっても住むには都合のいい場所なのかもしれない。ただ、外国人の流入と時を同じくして豊橋は急速に凋落しつつあり、特に駅前の閑散ぶりには悲しくなることが多い。
そんな豊橋のローカル・ラジオ局であるFM豊橋から、ある日突然出演依頼が舞い込んだ。ラジオ局の人がこのサイトに偶然漂着し、僕が豊橋出身であることを知って思いついたそうだ。僕はどちらかというと口下手な部類に入るので、ラジオかぁ・・・と最初考え込んだが、ラジオに出演したことなんてなかったので、楽しそうだと思い快諾した。豊橋に帰って来て早速その機会がやって来た。
ラジオなのでもちろん生放送で、昼頃の登場だった。30分と言われたときは長いと思ったが、話してみると30分というのは案外短かった。話の内容はやはりインドに関することが中心で、僕自身の個人情報の質問はなんとかそらしておいた。名前もアルカカットとして登場した。なんだか覆面レスラーみたいな気分だった。
だが、DJと話してみて明らかになったのは、普通の人がいかにインドに対して無関心、無知識であるか、ということだった。ひとつのことに熱中しすぎると、どこが常識だったか分からなくなるものだ。僕も普通の日本人がインドに対してどこまで知っているか、ということが分からなくなりかけていた。思い返してみると、僕の周りの友人知人は、僕の存在のおかげで少しはインドについて情報が入っていたと思う。だからそれほどひどい偏見をもってインドが語られることはなかった。ましてやインドに住んでいる友人や、インドに関わっている人々と話すときは、共有されたインド的常識がかなりの部分あった。そういうこともあり、頭では「普通の人はあまりインドについて知らない」と分かっていたものの、その中にも「でもこのくらいは知ってるよね」という理想的観測が大いに入り込んでいた。実際は絶望的なほどインドは知られていなかった。やはり普通の日本人にとって、インドは縁もゆかりもない外国中の外国であり、全く日常生活とは関係のない国であり、偏見に満ちた固定観念をもって語られるものでしかなかった。
特に「インドに住んでいる日本人」というのはかなりの偏見を持って見られている。ヒッピーなどの悪いイメージの残存だろうか。確かにインドには尋常ではない滞在をしている外国人も多い。だが、普通に滞在している人の方が多いのは当然のことだ。どうしてインドだけ特殊な人々がクローズ・アップされて映るのだろうか?インド留学というのも未だに世間の感覚でいったら普通ではない。だが、少し前までオーストラリア留学をする人も変人と見られていたことを考えると、そういう先入観も時代と共に変化していくものだと思う。あと10年後には、インド留学というのも一般に認知されるであろう(希望的観測)。しかしそうなったら僕はインドには留学していなかったかもしれない。とにかく多くの人がやっていることが嫌いなだけかもしれない。インドが好きになって、たまたまインド留学が割と一般に認知されていなかったから、こういう方向に向かっていっただけなのかもしれない。インドは僕にとってちょうどいい冒険対象だっただけかもしれない。「そこに山があったから」という格言があるが、まさに「そこにインドがあったから」僕はインドへ行ったのだと思う。ああ、全てを説明してくれるいい言葉だ。よく「なぜインドが好きになったんですか?」と聞かれるが、いちいち答えるのが面倒だから、これからこうやって答えよう。今度からホームページの題名を「そこにインドがあったから」にしようか。
話がだいぶそれてしまったが、今回のラジオ出演を通じて、僕はもっと日本人にインドを知ってもらいたいと強く感じた。多分アフリカ好きな人は「もっと日本人にアフリカを知ってもらいたい」と思うだろうし、ドイツ好きな人は「もっと日本人にドイツを知ってもらいたい」と思うだろうし、それはどこでも同じだと思うのだが、日本人にインドを知ってもらうことを推進するための強力な言い訳が存在する。インド文化が日本文化に長年間接的または直接的に与えてきた影響だ。特に仏教の存在は重要だろう。また日常の語彙や慣用句の中にもインド起源の言葉は少なくないし、20世紀前半の英領インドと日本の結びつきは重要であるし、またインド東北部から中国雲南省にかけての地域は日本人にとって非常に興味深い地域のはずだ。これだけ深い結びつきがあるのに、日本人のインドに対する見方のレベルは悲しいほど低い。せめて日本人が中国に対して持っている興味と同程度のものがインドに向けられるまで、僕はがんばろうと思う。
ちなみに僕はFM豊橋インド支部局長に任命された。やったね!
■Joggers' Park
インド東北部の1ヶ月以上に渡る旅行を終えてデリーに帰って来て、その次の日に日本に帰るというハード・スケジュールを決行したので、デリーではものすごい忙しかったのだが、その忙しい合間を縫って3枚の音楽CDを買って日本に持ち帰っていた。コールカーターで鑑賞してけっこう楽しかった「Andaaz」のサントラと、当時プラネットMのチャートで1位を獲得していたシャールク・カーンの「Chalte Chalte」のサントラと、もう1枚は適当に選んで買った当時最新CDだった「Joggers'
Park」のサントラである。
「Andaaz」は映画を見て、このCD欲しいな、と思ったので、問題はなかった。4曲目の「Rabba Ishq Na Hove」がお気に入りだが、その他にも映画のシーンに合ったいい曲が多かった。「Chalte
Chalte」の音楽は初めて聞いたときにはあまり印象に残らなかったのだが、テレビなどで何度も聞いているうちに欲しくなった。僕が日本滞在中に上映されてしまったため、どうやらこの映画を映画館で見る機会は失われてしまったようだ。残念。1曲目の「Tauba Tumhare Ishare」が好きだ。
これらのCDはよかったのだが、最後の「Joggers' Park」のCDのケースを開けてみて驚いた。1枚の紙切れが入っており、そこには「このCDはコピー防止機能付きです」と書かれていた。海賊行為を防ぐため、CDをCD-Rに焼いたり、MP3に変換したりすることができないようになっている、と書かれていた。しかも一部のパソコン、ゲーム機、プレイヤーなどでは再生できないことがある、とも書かれていた。そういえば日本でも浜崎あゆみなどのCDがこういうコピー防止機能付きで発売されたことあった(今でもあるのか知らないが)。まさかインドでこんなことがされるとは・・・。非常にショックを受けた。
僕はいつも音楽CDをMP3に変換してハードディスクに保存して聞いている。いちいちCDを入れ替えたりするのが面倒だし、いろんなCDから曲を選んで再生したりできるので、重宝している。しかし、もしこのコピー防止機能がインドで普及してしまったら、それもできなくなるということなのだろうか・・・。
ただ、試しに「Joggers' Park」のCDをパソコンに入れてみたらちゃんと再生することができ、MP3変換も難なくできた。この分だったら手先の器用なインド人なら簡単に今まで通り海賊版CDを作ることができるだろう。だが、なるべくならこのコピー防止機能はインドでは廃止の方向に向かってもらいたいのだが・・・。僕はちゃんと金払ってCD買って、インドの音楽業界に貢献しているんだけどな・・・。
「Joggers' Park」はインド初(?)のフュージョン・ミュージックという鳴り物入りで、あまりインド映画っぽくない曲がたくさん入っている。しかしこういう方向も僕はあんまり好きじゃない。インドの音楽業界がどういう方向に向かってしまうのか、少し不安になった一枚だった。
■講演「インドに魅せられて」
某外語大学で講演をすることになった。これもこの「これでインディア」から発生した縁である。講演をするような偉い人間でもないのだが、ヒンディー語の未来のために少しでも役に立てるならと引き受けた。
題名は「インドに魅せられて」という捉えどころないもの。自由に話してもらいたい、と言われた。だが、こういうのが一番困るものだ。聞き手は外大のヒンディー語科・ウルドゥー語科の1、2年生が中心。ということは基本的なインドの情報は持っていると考えていいだろう。だが、どこまでが基本的なインドの情報だろうか・・・。結局こういう場面でも、どこまでが常識で、どこまでが新鮮な情報か、見極めることができない。インドやパーキスターンなどの南アジア諸国へ実際に行ったことのある人も聞いてみたら半分くらいだった。ますます難しい。テーマが曖昧で、インド・レベルの設定も曖昧だったため、後から振り返ると非常に駄目な講演になってしまった。しかもインド人の客員教授も聞いていたので、インドに対していい意味でも悪い意味でも好き勝手なことを言いづらかった。
座談会みたいなものをイメージしていたのだが、普通に講義様式だった。50人くらい来たので仕方ない。あまり聞く価値のない講演になってしまって本当に罪悪感を感じたのだが、まあプロじゃないしいいか、と開き直っておいた。ただ、終わってみてやはり現地の生の情報が一番求められているように感じた。本で手に入るような情報は割とみんな知っているような気がした。インド各地の旅行情報や思い出話ならいくらでも話せるのだが・・・。
そういえば「インドに魅せられて」という題名は、講演を主催してくれた人が適当に考えてくれたのだが、当初からこのニュアンスに少し違和感があった。僕はインドに受動的に魅せられたわけではなく、インドを積極的に愛したのだと思っている。インドはこちらから愛さなければ、決して優しい表情を見せてくれない国だと思う。インドに旅行しようと思ったのも自分の意思だし、インドに留学しようと思ったのも自分の意思だった。もし他人にいやいや連れて来られたら、インドはきっと違う表情をしていただろう。インドに生活していると、やはりときどきインドが嫌になることがある。そんなとき「もうインドは嫌だ!」と考えてしまうと、途端にインドは僕に対してさらに過酷な試練を課して来る。インドを「好きになってしまった」わけではなく、何度も挫折しそうになりながらも「好きでいようと努力した」結果が、現在の自分のインドの対する愛情だと思っている。『地球の歩き方:インド』の冒頭に以下のような文があった。
深い森を歩く人がいるとしよう。
その人が、木々のざわめきを、小鳥の語らいを心楽しく聞き、
まわりの自然に溶け込んだように自由に歩き回れば、
そこで幸福な1日を過ごすだろう。
だがその人が、たとえば毒蛇に出会うことばかり恐れ、
歩きながら不安と憎しみの気持ちをまわりにふりむけば、
それが蛇を刺激して呼び寄せる結果になり、
まさに恐れていたように毒蛇に噛まれることになる。
この深い森こそがインドである、という喩え話だった。まさにそうだと思う。そしてこれはインドだけでなく、人生における重要な教訓だと思う。インドに魅せられる人は一人もいない。インドを愛する人が、インドを楽しむことができる。
■伊勢神宮と大相撲
日本にいるよりも海外にいた方が、自分のアイデンティティを見つめなおす機会が多いのは想像に難くない。僕も海外旅行をするようになってから、自分が日本人であることを意識し始めた。ましてやインドに住むようになってからは、皮肉にも僕はますます日本から離れることはできなくなり、日本の看板を背負って生きているように感じることもしばしばある。だが、同時に気付かされるのは、自分の日本文化に対するどうしようもない無知さであった。その無知さは、日本文化に対しての根本的な勉強不足と、明治維新後または戦後の急速な西洋化による、日本文化に対する幻想の2つに起因していると思う。
まず日本文化に対する勉強不足であるが、そもそも文化というのは勉強するものではなく、自然に身に付いて行くものなので、勉強しなくては、と思った時点でもうすでに手遅れだと言っていいだろう。また、文化は常に変化していくものなので、いちいち過去に立ち返って懐古主義に浸るのも馬鹿馬鹿しい。今の自分こそ、現代の日本文化の体現である、と開き直ってしまうのが一番手っ取り早い。しかし、外国に住んでいると必ず日本文化を紹介しなければならない場面に出くわす。出会った人から日本について質問されたり、ときには公衆の面前で何かをしなくてはならなくなる。そういうときに初めて僕は自分の日本度の低さを感じる。他の国の人はその点すごい。どうもGNPが低い国ほど国民ひとりひとりが独自の文化を継承しているのではないか、と思えるくらい、玄人じみた芸を持っていることがある。そういうときに僕は激しく赤面する。日本は確かにテクノロジーを発達させ、世界有数の経済大国にのしあがった。しかし日本国民一人一人は、日本独自の芸能をほとんど継承できていない。童謡を歌ったり、盆踊りを踊るのが精一杯だ。
そういう屈辱感が関係してか、今回の日本滞在中に2つほど、日本文化に関係するアクションを起こすことができた。ひとつは伊勢神宮参拝、もうひとつは大相撲観戦である。伊勢神宮は豊橋から日帰りで行けるし、大相撲はちょうど名古屋場所が行われており、これも日帰り圏内だった。
一生に一度は参るべきと言われている伊勢神宮だが、現代の日本人で参拝したことがある人はいったい何%ぐらいなのだろうか?僕は初めて伊勢神宮へ行った。前情報によると伊勢神宮には外宮と内宮があり、外宮から参拝するのがマナーらしいので、まずは豊受大御神が祀られている外宮から参拝した。
外宮にはあまり参拝客がおらず、ひっそりと静まり返っていた。原生林みたいな鬱蒼と茂った林の中の砂利道を進んでいくと、外宮の正宮があった。だが、中に祀られているものを拝むことはできない上に、正宮の建物自体も影に隠れていて全貌が見えず、手前の建物で賽銭を投げて手を合わせることしかできない。だが建築様式はいかにも古代日本という雰囲気で、かつ迫力があり、オリジナリティーを感じた。
外宮から御幸道路を歩いて内宮を目指した。バスで行くこともできるし、御木本道路というもっと直線的に結んだ道路もあったのだが、なんとなく道の雰囲気からして直感的に御幸道路を歩くのがもっとも正しい参拝方法のような気がした。道の両脇に石灯篭が立っていたのは御幸道路だけだったし、道に沿っていくつか別の神社も建っていたし、地図で見てみたら、御幸道路は外宮から内宮まで時計回りにぐるっと円を描くようにして結ばれていたからだ。この時計回りという概念はインドの寺院参拝でも重要である。それが染み付いていたためにそう行動してしまったのだが、多分何か深い意味があると思う。
御幸道路を歩いていくと、思ったよりも外宮から内宮までは遠かった。途中で昼食をとって休憩しつつ、雨が降ってきたのでコンビニで傘を調達しつつ、内宮に辿り着いた。
内宮は外宮と比べるとたくさんの参拝客が来ていた。内宮だけ参拝して帰る人も多いのだろうか?川を渡って境内に入る構造は外宮と共通しており、全体的な雰囲気も似通っていたが、内宮の方が混雑しているので、少し神秘度が落ちるように感じた。内宮の正宮は石段の上にあり、やはり一般の参拝客は中を見ることができなかった。なんでそういうケチなことをするのだろうか?せっかく来たのに。もしかして神道ってニラーカール(非偶像崇拝)なのだろうか?神様の姿があまり具体的に表されないような気がする。
その他気になったのは、主な神社の入り口の前に必ず立てられている敷居のようなもの。風水にも同じようなものがあったのを覚えている。気の流れを一旦せき止めて流す役割を果たしていたと思う。ここに鏡などをかけるとさらにいいらしいが。やはり日本でも古いものを見ると、アジアのかけらをふと感じることがある。ただ、20年に一度新しい建物を建て直すという風習は、他の国にはない独特のものだと思う。おかげで2000年前の木造建築様式が、今まで残っているそうだ。インドの昔の木造建築物はほとんど残っていないから、これはすごいことだろう。
大相撲名古屋場所は、3日目の取り組みを見に行った。名古屋城近くの愛知県体育館で行われており、升席での観戦だった。相撲観戦は日本のもっとも有名な文化を実際に見るという目的以外に、果たして相撲をインドでやることが可能かどうか、ちょっと考えてみたかったのもある。やはり日本の文化を海外に紹介するにあたり、相撲はキラー・コンテンツと言って過言ではないだろう。相撲ほど外国人が見たがっているものはない。インド人ですら知っているし、とても興味を持たれている。インドで相撲が行われる日はまだまだやって来ないとは思うが、実現したら非常に面白いだろうと思う。
相撲会場に入ったのは3時頃だったが、もう既に土俵の上では取り組みが始まっていた。午前中から下っ端の力士たちの取り組みがずっと続いているようだ。土俵の上に釣り下がっている巨大な屋根は伊勢神宮の建築様式と似ていた。客席は鉄骨で組み立てられており、これだったら広場さえあればどこでも相撲会場になりそうだ、と思った。だがテレビで見ているときよりも土俵も力士も全体的に小さく見えた。席に着くと、早速ビール、お茶、弁当、お土産などが配られた。ビール・・・なぜビール・・・。インドの感覚が抜けないと、問答無用でアルコールが配られることに違和感を感じる。特に伝統芸能の鑑賞の場でアルコールがさも当たり前のように配られるのか・・・。これも文化の内なのだろうか?せめて日本酒だったらまだ納得できたのだが・・・。
だが、会場全体の雰囲気はなんとなくインドと似ていた。相撲は既に始まっており、佳境に入っていく内に次第に客が入ってくる様などはインド古典音楽のコンサートと似ているし、真剣な眼差しで一試合一試合を注視するのではなく、観客が思い思いに連れと雑談などしながら肩の力を抜いて観戦している様は、インドの映画館を想起させた。幕内の対戦になってくると場内はかなり加熱して来て、客席からはいろいろな掛け声が飛ぶ。横綱武蔵丸が負けると噂どおり座布団が飛び交う。この場内の一体感は、インドの映画館と酷似していた。しかも近くにやたら相撲に詳しいお婆さんがいて、友達にあれこれ力士のプロフィールやら裏話やらを解説していたのだが、その解説が聞こえてきたおかげで詳しい情報を得ることができた。こういうところもインドでよくある風景だ。・・・と今までインドと比較してきたが、ようするにそういう諸々の事象はインド特有のものではなく、結局日本にもあったものだということが分かった。なぜ日本から直接こういう世界に入って行けなかったのか、なぜインドを遠回りして日本文化に入らなければならなかったのか、これは僕だけの責任ではないと思う。
現在大相撲は人気が低下しているようだが、観客たちの話を盗み聞きすると、必ず焦点は朝青龍をはじめとする外国人力士の話になる。今回僕が見た中では、モンゴル人、グルジア人、韓国人などの力士がいた。そして概して観客はそういう外国人力士に対して冷たい。特に横綱が外国出身力士に占められている現状を憂いている。だが一方で日本人がメジャーリーグに挑戦する日本人を応援しているのであり、これは明らかに矛盾している。僕は大いに外国人力士歓迎の立場だ。特にアジア各地にはインドのクシュティーなど相撲と同じような伝統競技が残っているので、まだまだいろんな国から角界に挑戦する人が出てきてもおかしくないと思う。
冒頭で挙げた日本文化に対する幻想は、長くなってしまったのでまたの機会に書くことにする。
■時間の計り方
インドに暮らして以来、時間に対する考え方が変わったように感じる。1日に2つ以上のアクションを起こすことに恐怖を覚えるようになったのだ。
インドでは事務手続きなど非常に時間がかかる。例えば外国人登録などは、インドに住む外国人が最初にぶつかる壁である。まず外国人登録局(FRRO)へ行かねばならない。最近場所が移転したので、それを知らないとまずFRROに辿り着くのに苦労するだろう(ちなみにハイアット・リージェンシーの近く)。FRROに着いたとしても、4時には業務が終了してしまうので、もしかしたら時間切れで次の日に来ないといけなくなってしまうかもしれない。無事業務を取り次いでもらったとしても、あれが足りない、これが足りないと不備を指摘され、すごすごと帰されることもある。そしてその不備を補完して再び訪れたとしても、また新たに別の書類が足りない、と言われてまたまた帰されることもありうる。なぜ一度に「これとこれとこれが足りないよ」と言ってくれないのか、と憤慨することもあるが、オフィサーを怒らせると後が怖いので逆らえない。ときにはそれらの必要書類を集めるために、さらに同じような面倒な手続きを踏まないといかず、時間がかかることもある。ある人のサインが必要なのに、その人がカシュミールへ避暑に行っていて当分帰ってこない、という事態も起こる。デリー中を駆け巡らないといけないこともある(デリーに住んでいるだけマシかも)。コピーが必要な場合など、オフィスでコピーはとってもらえず、「外でとってこい」と冷たく言い放たれる。外のコピー屋に行ってみると停電でコピー機が動かず、今日はもうやめだやめだ諦めた、という状況に陥ることもある(悲しいが、全て実体験である)。こういう苦労があるため、やっと必要書類をかき集め、手続きを終えたときにはまるで鬼の首でも取ったかのような勝ち誇った気分になる。外国人登録はまだ難易度が低い方であるが、一昔前の電話線架設などは、手続きが完了されてから実際に電話線が敷かれるまで果てしなく待たないといけないことがあったりしたので、これはもう忍耐力云々の問題ではなく、さらに次元の高い試練なのかもしれない。
というわけで、いつの間にか僕の脳裏に「事務手続きは最低3日、なるべく1週間の余裕を持って行動」という基準が出来上がってしまっていた。そのまま日本に帰って来て、今回自動車の運転免許を更新したのだが、やはりなんとなく「更新には最低3日はかかるだろうなぁ」と思っている自分がいた。実際にやって見たら半日で終わってしまい、呆気に取られてしまった。日本って便利だなぁ・・・。感動モノである。
だがやはり手こずったものもあった。それはジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の入学許可証である。今年から僕はJNUへ行く予定で、インドを去る前に申請書を提出して来た。オフィサーの話では6月中旬に日本に入学許可証が届くとのことだったので、ずっと待っていた。ずっと。しかし7月に入っても届かない。入学許可証がないと学生ヴィザを取ることができないので、つまりはインドに行けないことになってしまう。僕は合格したのだろうか、オフィサーはちゃんと送ってくれただろうか、途中で郵便事故に遭っていないだろうか、だんだん不安になってきていろいろ現地の友人などに動いてもらって確認したところ、なんてことはない、なんとインドの僕の家に届いていた。確かに申請書にパーマネント・アドレスとポスタル・アドレスの欄があり、僕はうっかりインドの住所をポスタル・アドレスに記入してしまったが、しかしオフィサーに「日本に送ってくれ」と念を押しておいたはずだ。それなのにインドに届くとは・・・。結局FAXで送ってもらって、それでヴィザを申請して発行されたので事なきを得たが、やきもきしていた2〜3週間を損した気分である。
こう書くといかにもインドは暮らしにくい国のように映る。だが、あまり認めたくはないのだが、そういう面倒さが逆にツボにはまったというか、そういう困難さを楽しんでいる自分がいるのも事実である。何か困難に直面すると、そこから物語が始まる。日本で暮らしていると毎日あまりにもスムーズ過ぎて、なんだか生きている実感が沸かない。それでいて日本の生活は徐々に肉体も精神も蝕まれているような不気味な不快感もある。一方、インドでは困難が極端な形で立ちはだかり、それを克服することで大量の経験値が入り、大きく成長しているような感じだ。誰が言ったか「インドはドラクエである」という格言もある。まるで毎日がロールプレイング・ゲームのようだ。道路を歩いているだけでも何かしらイベントが発生し、それを克服するためにいろんな人の助けを借りたり、新たな出会いがあったり、全知全能全体力を駆使しなければならなかったり、いろんな偶然に助けられたりして、それを克服したときには、より成長した自分がいる、という按配だ。少しインドを馬鹿にしたような表現だが、当たらずとも遠からずだと思う。
昨日の夕方7時にデリーに到着した。
6月8日にデリーを発ったので、1ヶ月半ぶりのデリー、そして1ヶ月半ぶりのインドである。つまり1ヶ月半日本にいた。
1ヶ月半という時間は僕にとってけっこう長い時間だった。1〜2ヶ月日本に滞在してしまうと、腰が落ち着いてしまう。腰が重くなってしまい、少しインドへ向かうのにエネルギーがいるようになってしまう。早くインドに行きたい、と思いながら、身体が日本にネットリと張り付いてしまったような感じだ。
1ヶ月半の間に、なんとなくデリーも様変わりしてしまったようだ。公共バスのペイントの色が新しくなっていたり、いくつか新しい店がオープンしていたり、道路の舗装が着々と進んでいたり・・・。映画も僕がいない間にけっこう入れ替わったようだ。デリーの変化から取り残されたような気分になり、ちょっと寂しい気分だ。
現在デリーは雨季のため、雨がよく降る。緑が勢いを増し、道は泥沼と化している。インドでは自然の自己主張も人に負けないくらい強い。
昨日今日とインドでの生活を安定させるために必死である。周りの環境や自分の身体を、インドを去る前までの水準に戻すのには時間がかかりそうだ。まずは部屋の掃除。少し空けただけで砂まみれになるのにはもう驚かない。あらかじめ家具などの上に新聞紙や布をかぶせておいたので、それほど大変でもない。今回の大きな損害は、壁の一部が真っ黒になっていたことである。どうも雨漏りしていたようだが、原因はよく分からない。おかげでただでさえ貧乏くさい部屋がさらに貧乏くさくなった。
インターネットもつながらなくなっていた。今日はインターネットのケーブル会社に出向いて接続を復旧させるのに1日を費やした。いろいろ大変だったが、最終的に復旧してもらえた。だが、雨の中歩き回ったからか、この湿気が原因なのか、気付くとドッと疲れていた。インド初日はこうも疲れるものなのか、と改めて実感した。
昨日はネットの復旧に1日を費やしたが、今日はジャワーハルラール・ネルー大学(以下JNU)の手続きに1日を費やした。やはりインドではアクションが1日単位になってしまう。JNUの入学手続き方法はおそらくこれからJNUに入ろうとする人の参考になると思うので、自分の経験も踏まえて、かつデリー大学と比較しながら順を追って書いていくことにする。ちなみに僕はICCRなどの奨学金留学ではない、セルフ・ファイナンスであり、M.A.(文学修士)である。だから他のコースはまた手続きが違うかもしれない。ICCRは合格さえすればおそらく比較的簡単に手続きを済ますことができるだろう。
だいたいデリーの大学の入学願書が配られ始めるのは2月頃である。その時期に大学のアドミニストレーション・オフィスか何かへ行って入学願書をもらわなければならない、というか買わなければならない。自分で実際に行って願書をもらうのが最上の方法だろう。電話やFAXなどで願書を無事に取り寄せることができるかどうかは知らない。JNUのウェブサイトで願書をダウンロードすることができたが、それは使用できない、と言われた(何のこっちゃ)。JNUの場合、入学手続きを行う場所はアドミニストレーション・ブロックと呼ばれ、JNUのキャンパスのけっこう奥まったところにある。入学願書はインド人用と外国人用があり、外国人は25ドル(または1250ルピー)もの大金を払わされる。ちなみにインド人は220ルピーである。
入学願書の提出期限は大学によってまちまちだが、JNUの場合4月の中旬であることが多いようだ。今年は4月15日だった。デリー大学の入学願書締切は案外ルーズらしいが、JNUはその日を過ぎたら一切受け取ってもらえないと聞く。入学願書と一緒に提出しないといけない書類がいろいろ書かれているが、この時点では全然チェックされなかったので、もしかしたらとりあえず願書だけ出せばいいのかもしれない。この願書にポスタル・アドレス(現住所)とパーマネント・アドレス(本籍)を書くところがあるのだが、ここで注意しなければならないのは、入学許可証が届く6月〜7月にどこにいるかをあらかじめ考えて書かなければならないことだ。何も言わないと書類はポスタル・アドレスに届く。僕はうっかりインドの住所をポスタル・アドレスに書いてしまったため、面倒臭いことになった。
外国人の場合、デリー大学に入る際は特に試験を受ける必要はないようだ。だが、JNUでは制度上、外国人は試験を受けてもいいし、受けなくてもいいことになっている。JNUの試験は5月の末にあり、インド各地の会場で行われる。これは外国人も対象になっている。しかし、外国に住み、その時期にインドに来れない外国人留学生希望者のためへの便宜として、欠席合格という制度がある。つまり、試験を受けなければ自動的に合格、という制度だ。だが、この欠席合格が適用されるには、試験の時期にインドにいてはいけない、という条件が付いている。ネパールとバングラデシュにも試験会場があるので、おそらく正確には5月末にインド、ネパール、バングラデシュにいてはいけない、ということだろう。これはパスポートなどでちゃんとチェックされるようで、これに引っかかって入学許可が取り消された人もいると聞く。また、他のインド人と同じように試験を受けて入ろうと思っても、入学案内には詳しい試験日程が載っておらず、オフィスに問い合わせるように、と書かれているだけであり、問い合わせてみると、「試験のある時期にインドにいるなよ」と言われるだけなので、結局JNUも外国人は試験を受けなくていい、ということなのかもしれない。また、無理矢理試験を受けたとしても、外国人は必ず受かるようになっている、との疑いも指摘されている。インドの大学の授業料には法外な外国人料金が設定されており(インド人料金はただ同然である)、金儲けのために基本的に外国人をなるべく入学させようとしている、というのが実態のようだ。
入学許可証が届くのは6月中旬から7月上旬あたりのようだ。デリー大学の方が授業開始時期が早いので、願書が届くのも少し早い。経験上、7月10日頃になっても届かなかったら、少し焦って対策をとるべきだと感じた。また、ICCR奨学金の学生は、入学願書が届くのがセルフ・ファイナンスの学生に比べて遅い、との話も聞いた。この入学許可証があれば学生・研究ヴィザを取得することができる。
JNUの場合、インドへ行く前に日本で用意すべき書類を挙げていくと、まずは大学の学位・卒業証明書と成績証明書である。英文でなければならない。実物を要求されるのだが、そもそも英文の卒業証明書や成績証明書の実物など日本の大学では存在しないと思うので、、日本人は特に気にしなくていいだろう。また、JNUでは人柄証明書(Character Certificate)というのが必要になるが、適当に親しい教授などに一筆英語でしたためてもらえば内容はどうだっていいようだ。その他、英文の健康診断書も必要である。JNUの場合チェック事項は特に指定されていないので困るが、HIV検査だけは必ずやっておくべきだと思う。インド政府はなぜかエイズに対して厳しい態度をとっており、外国人登録局(FRRO)での外国人登録のときに必須となる。健康診断はインドでやれば安く上がるが、どうも国営の病院で検査をしなければならないようなので、やはり日本でやって来た方がいいと思う(国営じゃなきゃ駄目だ、と言われても「日本の病院は全て民営なんだ!システムが違うんだ!」とかごねれば通る)。インド到着後の手続きで、パスポート、ヴィザ、そして各書類のコピーを何枚も要求されるので、あらかじめ日本でそれぞれ5、6枚コピーをとっておくと楽だと思う(パスポートとヴィザは1枚の紙に載るように工夫してコピーすると吉)。パスポート・サイズの写真もたくさん要求されるのであらかじめ2、30枚用意しておくといいのだが、インドの方が遥かに安く済むと思うので、インドで調達してもいいだろう。
ヴィザを取得し、航空券を買い、無事にインドに到着することができたら、早速入学手続きを行わなければならない。以下、JNUの情報オンリーになる。JNUの場合、アドミニストレーション・ブロックへ行って、外国人用受付で用意した書類のチェックを受ける。不備があると容赦なく付き返される。一通り揃っていることが確認されると、記入用の書類を山ほど渡される。それらにいちいち名前やら生年月日やらコース名やらを腱鞘炎になるくらい書きなぐって、各用紙に顔写真を貼らなければならない(ノリを持参するといいだろう)。何を書いたらいいのか分からないところはとりあえず空欄にしておく方がいいだろう。また、ここで授業料を払わなければならない。JNUの外国人の授業料は半年で600ドルまたは850ドル。理系の学科は授業料が高い。ちなみにインド人は1年間400ルピー以下である。会計窓口で払うのだが、窓口の前には長蛇の列ができていることが多い。だが、外国人は払う額が多いため、会計の部屋に直接入って行って払うことができる。授業料を払ったらレシートをもらう。
書類を全て記入して、授業料も払ったら、それらを再び外国人用の入学窓口に出す。不備があるところなどを指摘されるので、それらを直してまた見てもらう。チェックが済んだらオフィサーのサインが入り、写真に印章が押され、これで晴れてJNUの正式な学生として登録される。この際、決め台詞としてオフィサーは必ず「Welcome to JNU」と言うようだ。ここまでがまず一苦労なので、この一言にウルウル来る人もいるのかもしれない・・・?
しかし残念ながらまだ入学手続きは終わっていない。さらに手続きは残っている。実はJNUのキャンパスは広大で、しかもほとんどジャングルに包まれているようなものであり、建物はあちこちに分散している上に道標など一切ないので、ここからはおそらくJNUのことをよく知っている人に案内してもらわないと大変だと思う。まずはDean of Students(学生監督官、とでも訳そうか)のところへ行かなければならない。どうも学生の生活などを司っているところみたいだ。寮に住みたい人はここで申請する。寮に住まなければここでの手続きは簡単に終わるが、寮に住むとなるとまた1、2枚書類を書いて提出しなければならない。
次に図書館で書類を提出し、図書館利用ナンバーをもらう。それから今度は自分が通う学部(school)へ行って手続きをし、IDカードを発行してもらわなければならないが、僕の通う言語文学文化学部の手続きは25日からだと言われてしまったので、今日はできなかった。でもとにかく今日できることは今日中に終えることができた。ひとまず満足感に浸った。
振り返ってみると、本当にJNUの手続きはJNUをよく知っている人にいろいろ手助けしてもらわないと不可能じゃないかと思った。僕はもうデリーに住んで2年経ったのでJNUに知り合いも多く、助けてもらうことができたからよかったが、全く何の人脈もなくJNUに来る人はいったいどうしているのか不思議なくらいだ。ただ、一見非合理的で不親切に見えるこの手続きも、終えてみれば何となく一通りJNUのキャンパスを廻ることができ、何となく地理が掴めるので、もしかしたらこれはこれで理に適っていると言うこともできるかもしれない。
| ◆ |
7月24日(木) Main Prem Ki Diwani Hoon |
◆ |
6月下旬に封切られ、是非見てみたいと思っていたヒンディー語映画「Main Prem Ki Diwani Hoon」が、うれしいことにまだ上映されていた。最近低迷しているヒンディー語映画の中で1ヶ月続く映画はあまりない。けっこうヒットしているようだ。入れ替わってしまわない内に今日見に行くことにした。チャーナキャー・シネマで見た。
「Main Prem Ki Diwani Hoon」とは「私は恋の虜」という意味。「Prem」とは「愛、恋」という意味の他に登場人物の名前がかけてあり、「私はプレームの虜」と読むこともできる。リティク・ローシャン、カリーナー・カプール、アビシェーク・バッチャン、映画カースト出身の3人が主演である。他にジョニー・リーヴァル、パンカジ・カプール、ヒマーニー・シヴプリーなど個性俳優が脇を固める。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
左からリティク・ローシャン、
カリーナー・カプール、アビシェーク・バッチャン |
● |
| Main Prem Ki Diwani Hoon |
風光明媚の地スンダル・ナガルに住むサンジュナー(カリーナー・カプール)は女子大を卒業したてのイマドキの女の子。お見合い結婚なんて時代遅れ、女も自分の生きたいように生きるのよ、と考えていた。しかし母親(ヒマーニー・シヴプリー)はサンジュナーのいい結婚相手を見つけようと焦っていた。
そんなときアメリカに住むサンジュナーの姉ルーパーから連絡が入る。なんと大物実業家のプレーム・クマールがスンダル・ナガルを訪れると言うのだ。プレームは結婚相手を探しており、サンジュナーの写真を見て気に入ったと言う。そこでルーパーはプレームをスンダル・ナガルの自宅へ滞在するようアレンジしたのだった。思いがけないところからいい縁が転がり込んだ両親は喜び、プレームを迎えるための準備にオオワラワとなる。しかし面白くないのは当の本人のサンジュナーだ。サンジュナーはプレームを追い返すために案を練る。
空港に現れたプレーム(リティク・ローシャン)は陽気でスポーティーな男だった。サンジュナーはプレームに意地悪をするのだが、プレームは飄々とした性格でどうもうまくいかない。その内にサンジュナーはプレームの前で自然と笑顔を見せている自分に気付くのだった。サンジュナーはプレームに恋をしていた。両親もプレームのことを非常に気に入っていた。
ところがルーパーから意外なメールが届く。なんとプレームは急用ができてインドではなく日本に行っていたと言うのだ。では、今家に泊まっている男は何者なのか?調べた結果、その男はプレーム・キシャン。プレーム・クマールの会社の会社員で、プレームの代わりにインドに来ていたのだった。だが、既にサンジュナーとプレーム・キシャンは相思相愛になっていた。父親はプレーム・キシャンでもいいじゃないか、と言うが、金にこだわる母親は、何としてでも娘をプレーム・クマールと結婚させることを決める。
やがて本物のプレーム(アビシェーク・バッチャン)がスンダル・ナガルにやって来た。プレーム・クマールはプレーム・キシャンとは対照的な物静かで知的な男だった。元からサンジュナーの写真を見て見初めていたプレーム・クマールは、実際にサンジュナーに会って本格的に恋をしてしまう。プレーム・クマールの母親も一緒に来ていたため、縁談はとんとん拍子に進む。しかしサンジュナーはプレーム・キシャンのことを愛しており、父親もサンジュナーの気持ちを尊重したいと思っていた。一方、プレーム・キシャンは自分のボスがサンジュナーに恋をしていることを知って身を引く決意をし、一人デリーへと去ってしまった。
プレーム・クマールとサンジュナーの婚約式が執り行われていた。サンジュナーはプレーム・キシャンをずっと待ち続けたが彼は現れなかった。失意の中、式は進んでいく。ずっと会場の出入り口を見つめ続けるサンジュナー。そして指輪交換が終わった瞬間、プレーム・キシャンは会場に現れる。サンジュナーは彼に抱きつく。
全てを理解したプレーム・クマールは、プレーム・キシャンにサンジュナーを譲る。こうしてプレーム・キシャンとサンジュナーはめでたく結婚することになった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
日本の時代劇には一定のパターンがあるが、インド映画にも一定のパターンが存在する。この映画はまさにその黄金パターンそのものだった。愛する二人の男女、しかし親の決めた結婚により二人は引き裂かれる。しかし結婚式の土壇場で愛する二人は結ばれる、という何度も何度もインド映画で使い古されたプロットである。しかし批判する気は毛頭ない。この男女の愛と家族の愛の葛藤こそがインド映画の永遠のテーマなのだ。インド映画にこの黄金パターンが見られなくなったら僕は声高らかに叫ぼうと思っている。「インド映画は死んだ」と。
このパターンのインド映画では、最後の結婚式のシーンでどうどんでん返しが巻き起こるかを楽しむのが通の見方だが、この映画ではちょっとパンチ不足だった。プレーム・キシャンの左腕に彫られた「サンジュナー」というタトゥーをプレーム・クマールが見て、彼の本当の気持ちを知る、というものだった。これがもっとひねってあったら、いい映画だと言うことができるのだが。
この映画で工夫が見られたのは2人のプレームが登場して、勘違いから事がこんがらがることだ。とはいえこういう筋もインド映画では割と一般的ではあるのだが、この2人のプレームを対比させて「結婚は金じゃない」という主題を浮き彫りにしていたのは特徴だと言うことができるだろう。
カリーナー・カプールはいつも通り俗に言う「シェヘリー・ラルキー(都会の女の子)」役である。派手好きで、わがままで、西洋化された思考を持ち、男に挑戦的な女の子だ。彼女がもっとも得意とする役であり、ほとんど地でやってると思うので、さすがに非の打ち所がないほど板に付いている。物語が進むにつれてお転婆度が下がっていき、中盤からは悲恋のヒロインに様変わりするのもいつものパターンである。映画中に出てくる、リバー・ラフティング、乗馬、バンジー・ジャンプ、シュノーケルなどいろんなスポーツに対しての体当たりの挑戦や、コミカルな2枚目半の演技は、現在のところカリーナーをおいて他に真似できる女優はいないだろう。僕は彼女は大女優になっていくと思っている。
リティク・ローシャンもかつてのサルマーン・カーンが得意だったような、リッチでマッチョなお調子者役が定番となっている。無意味に上半身むき出しにして筋肉を見せびらかすのも同じだ。でも踊りが天才的にうまいので、サルマーン・カーンを越えることはたやすいと思う。リティクの右手の親指が2本あるのはインド映画ファンの間では常識だが、彼の映画を見ているとどうもずっとその親指が気になって映画に集中できないことがある。一時期に比べてあまりその親指を隠さないようになってきた。
相変わらずヒット作に恵まれないスモールBことアビシェーク・バッチャンは、だんだん昔のアジャイ・デーヴガンのような、無口で不器用な男役オンリーになって来た。今回はダンス・シーンもほとんどなし。俳優として崖っぷちに立たされているのではなかろうか。顔はアミターブ・バッチャンにますます似てきたように感じる。
この映画にはあまり悪役らしき人物は登場しなかったのだが、唯一サンジュナーの母親役のヒマーニー・シヴプリーが憎まれ役だった。娘を何としてでも金持ちと結婚させようと躍起になり、プレーム・キシャンに意地悪する姿は醜い。でも彼女がいなかったらこの映画のストーリーは成立しなかったため、重要な役柄だった。いい演技をしていたと思う。
人間の他、この映画ではオウムと犬がサブキャラとして登場した。犬などの動物を隠し味として使うのは、最近のインド映画の流行である。おかげで現在デリーでは上流階級の家でペットが大流行中である。犬のジョニーは怒ると顔がアニメになるという変わった演出。オウムのラージャーはインド映画のタイトルで会話をするCGキャラだった。映画のウェブサイトでラージャー君のデスクトップ・マスコットをダウンロードすることができるのは調子に乗りすぎだと思った。確かにペットがいると映画全体に多少ぬくもりが出ていい。頼りすぎるのはよくないが。
音楽はアヌ・マリク。「Main Prem Ki Diwani Hoon」のCDはけっこう売れているみたいだ。僕はまだ買っていないが、買ってもいいかな、と思うぐらいのレベルだった。テレビなどでよく流れていた「Sanjana I Love You」という曲は結局映画中では使われていなかった。歌詞が安易過ぎてあまり好きではなかったので、賢明な判断だと思った。CDに入っているのに映画では使われなかった曲、プロモに使われただけの幻の曲というのもインド映画ではよくあるのだ。
前回(22日)の手続きでJNUの学生にはなれたものの、まだ学部(School)と学科(Centre)には登録されていない。今日からその登録が始まると聞いたので、朝から再びJNUへ足を運んだ。
どうもこの登録の主な目的は、履修する単位の登録のようだ。掲示板に科目番号、科目名、単位数などのリストが載っているので、それを紙に写して提出する。僕はインド言語学科(CIL)のMAヒンディー語コースを学ぶ。科目を見てみると、「ヒンディー語の起源と発展」「ヒンディー語文学の歴史」「初期ヒンディー語の詩」「ヒンドゥスターンの文学と伝統文化」「ウルドゥー語、ウルドゥー文学の基礎」が必修科目となっていた。授業の質はまだ分からないが、科目名だけから判断するとちゃんと一通り揃っている。特にウルドゥー語も併せて学べるのが嬉しい。ヒンディー語とウルドゥー語は姉妹言語というか双子の言語なので、両方知っているのが望ましい。ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンに足らなかったのは、まさにこのウルドゥー語の授業である。そもそもサンスターンはヒンディー語の普及のために設立された機関であり、ウルドゥー語や他のインド諸言語はどちらかというと排除の方向へ向かわせようとしているので仕方ないのだが。一方、ウルドゥー語科でも逆にヒンディー語の授業が1科目必修になっていた。その他、オプションで語学のクラスもあるようだ。ヒンディー語を母語としない人のための措置だろう。
履修届けの紙に学科長(Dean of School)のサインがもらえると、学部のオフィスでIDカード用紙をもらえる。それに写真を貼り、必要事項を記入するのだが、写真を貼るスペースが小さくて、パスポート・サイズの写真でははまりきらない。ハサミはないか聞いてみたが、「ない」と言われてしまった。オフィスにハサミがないはずないだろうが・・・。でも本当になさそうだった。ちょっと周囲で聞き込みをして探してみたが、ハサミを持っている人はいなかった(インドではハサミはあまりポピュラーな文房具ではないかもしれない)。このハサミのためだけに僕は家まで帰らないといけなかった。
写真を切ってIDカードに貼りつけ、それを学部のオフィスに提出する。そのIDカードにも学部長のサインが必要である。その後ラミネートもしてくれるようだ。IDカードができるのは来週の月曜日か火曜日だと言われた。つまり今週中には手続きはまだ完了しなかったということだ。やっぱりこの手の手続きはインドでは1週間かかってしまう。まだいつから授業が始まるかもよく分からないので、あと何回もJNUへ行かないといけない恐れもある。
ちなみに今日アドミニストレーション・ブロックを見てみたら、アドミッション・アシスタントという名札を付けた学生がたくさんうろついていた。前回来たときは、あまりの不親切さに不安になったものだったが、どうやら彼らが入学手続きを手伝ってくれるようだ。僕が手続きをしたときには彼らはいなかったのだが・・・。とにかく、入学手続きは非常に面倒で分かりにくいだけあって、それをサポートする組織もちゃんと学生内で作られていることは感心である(ただどうも政治団体っぽかったが)。
インド人はよく他人の持ち物の値段を聞く。インド人同士なら「オレはこんないい品物をこんな安く買ったんだぜ」「いや、あそこならもっと安い」という、言わば買い物の自慢と情報交換に発展して行ったりしてそのまま流れていくが、外国人相手だとそうもいかない。インド人からしたらとても珍しい品物だったりする場合があり、そういうときにインド人は執拗に値段を聞いてくる。一般に、そういうインド人の態度は外国人にあまり好まれていない。
大家さんの息子のスラブ君も、当初は僕の持ち物の値段をよく聞いて来た。パソコン、デジカメ、時計、バッグ、ペン、靴などなど・・・僕の持てる物全ての値段を知り尽くそうとしているかのようだった。あるとき僕はちょっとムッと来たので「なぜそんなに値段を気にするのか。あまりいい気分がしない」と言ったところ、「いつか自分も買うかもしれないから、そのときのために相場を知っておきたい」と答えた。彼の言葉を補うならば、インドではまだ商品の値段は交渉で決まることが多いので、なるべく相場を知っておきたいという欲求があるということだろう。また、持ち物で相手の社会的地位をはかっていることも考えられる。もっとも、それ以後スラブ君はあまり値段を聞いてこなくなった。
そういえば昔、隣の部屋にウガンダ人が住んでいたことがあった。僕がウガンダ人の部屋で話をしていたときに、下の階に住んでいたインド人が僕を訪ねてやって来た。ウガンダ人の部屋には、けっこういいブランドのテレビやCDプレーヤーが置いてあった。それを見てそのインド人はやっぱり値段を聞いていた。やはりウガンダ人もインド人のその習慣を好ましく思っていなかったようで、適当に「100ルピー」とか明らかに嘘と分かるような安い値段を答えてあしらっていた。インド人は「そんな安いなら、俺に200ルピーで売ってくれよ」とか言っていたのを覚えている。
人それぞれ対応の仕方はあると思うが、僕はそういう場合、あまり嘘のつけない性格も手伝ってか、正直に値段を答えてしまう。円で言ってもほとんどの場合分からないので、ルピーに換算して答える。そうこうしている内に話題は円とルピーの話に移行する場合が多い。こういうときが一番面倒なのだ。
質問の内容は大体こうである。「日本の1ルピーはインドのルピーでいくらだ?」とか、「日本の1ドルはインドのルピーでいくらだ?」とか、まずお金の単位がよく分かっていない人が多い。世の中の貨幣単位はルピーしかないと思っている人や、外国のお金は全てドルだと思っている人が多い。まあこういう場合は、日本では貨幣単位は円であることを教えれば済む。
すると質問はこうなる。「1イェンはインドの何ルピーだ?」こういう答え方は少し面倒なので、前後を入れ替えて僕は「1ルピーは3円ぐらいだ」と答える。そうすると大部分のインド人は首を傾げる。「日本円よりもインド・ルピーの方が強いのか?」ここからが大変なのだ。
日本人の感覚からすると、このインド人の貨幣概念は俄かには理解しづらい。だが、こう考えてみると分かりやすい。例えば1日に働いて稼ぐお金が100貨幣単位であるとする。するとインドで1日働けば100ルピー、日本で1日働けば100円、アメリカで1日働けば100ドルである。外貨為替相場は1円=0.33ルピー、1USドル=48ルピーとする。これをインド・ルピーに換算すると、インドでは1日100ルピーもらえて、日本では33ルピー、アメリカでは4800ルピーになる。これがインド人の貨幣概念である。つまりインド人の感覚からすると、日本で働いたら、インドよりも稼ぎが少ないということになってしまうのだ。逆にアメリカで働いたら、1日で大金持ちである。
もちろん、この計算方法は間違っている。しかし僕が多くのインド人と話した結果、ある程度学識のある人でも、この間違った計算方法をしていることが多いと実感した。おそらく一度でも南アジア以外の外国へ行けば、すぐに間違いに気付くと思うのだが、なかなかまだ海外旅行はインド人にとって雲の上の話であり、正確な知識を得るには時間がかかりそうだ。
前文で「南アジア以外の国へ行けば」と限定した理由は、おそらく南アジア諸国とインドの外貨為替相場が、インド人に間違った計算方法を植えつけている原因だと思うからだ。例えばインド・ルピーとネパール・ルピーの関係を見てみると、1インド・ルピーが約1.6ネパール・ルピーになる。つまり、インドで100ルピー稼ぎ、ネパールに持っていけば160ルピーになる計算である。インドとネパールではそう物価が違わないので、ネパールで働くよりもインドで働いた方が得である。よってインドにはネパール人の出稼ぎ労働者が多くいるし、一般的にインド人はネパールを旅行すると得した気分になると言う。
ネパールだけでなく、他の南アジア諸国とインドの為替相場を比較してみると、1インド・ルピー=1.56スリランカ・ルピー=1.39パーキスターン・ルピー=1.09バングラデシュ・タカ=1ブータン・ヌルタム=0.28モルディブ・ルフィアーである。こうして見てみると、モルディブを例外として他の国々は全てインド・ルピーよりも数字上の価値が低くなっている(ただ、ブータンのヌルタムはインド・ルピーと同価値に設定されている)。これらの国々であまり数字上の物価も変わらないことから(例えばコーラ1瓶の値段がどこの国でも10〜15貨幣単位ということ)、実際に南アジア諸国の中でインド・ルピーは一番強いということになる。
ところがどっこい、その計算方法を日本などの全く別の国に当てはめてしまったら大きな誤解が生じる。確かに1ルピー=2.5〜3円である。この為替相場は、どの南アジア諸国に比べても数字上の価値が低くなる。インド人式に考えると、日本は南アジアの国々よりも貧しい国ということになる。だが、日本では10円でコーラは買えない。ミネラル・ウォーターも買えない。実際の物価も、数字上の物価も全く違うのだ。
こういうことをいちいちインド人に教えるのは面倒であり、理解するだけの知能を持っていない人もいるのだが、基本的に僕はコーラの値段などを使って根気強く説明している。ときどき自分のことが「円とルピーの親善大使」のように思えてくるくらいだ。少なくともスラブ君は、僕の努力の甲斐あって、今では「円÷3=ルピー」であることを完全に理解している。
| ◆ |
7月27日(日) Jhankaar Beats |
◆ |
インド人によって作られた英語の映画、ヒングリッシュ映画が次第に1ジャンルを築きつつある。そのヒングリッシュ映画によく顔を出し、個人的に最も注目している、ラーフル・ボースという俳優がいる。メジャーなインド映画にはほとんど出ないのだが、癖のある顔、癖のある演技、癖のある役柄からすぐに顔と名前を覚えてしまい、また彼の出ている映画は極めて高い確率で良作であることが多いことから、彼の映画なら是非見てみたいと思ってしまう、いい俳優である。
そのラーフル・ボースが遂にヒンディー語映画に登場。その名も「Jhankaar Beats」。なかなか好評を博しているようだ。主演はサンジャイ・スーリー、ラーフル・ボース、シャヤン・ムンシー(新人)、ジューヒー・チャーウラー、リンキー・カンナー、リヤー・セーン。監督はスジョーイ・ゴーシュ。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
Jhankaar Beats |
● |
| Jhankaar Beats |
ディープ(サンジャイ・スーリー)とリシ(ラーフル・ボース)は広告代理店に勤める親友。お菓子好きのディープは妻のシャーンティ(ジューヒー・チャーウラー)に厳しく栄養管理をされながらも、円満な家庭を築いていた。一方、リシは妻のニッキー(リンキー・カンナー)と離婚の危機にさらされてブルーな日々を送っていた。
そんなディープとリシにはひとつの夢があった。それは年に1回開催される「ジャンカール・ビーツ」という音楽祭で優勝すること。ディープはキーボードとヴォーカル、リシはドラムを演奏しており、R.D.ブルマンを「ボス」と尊敬しており、毎晩クラブなどで演奏して腕を磨いていた。ところが彼らはもう2度も敗退していた。今年こそはと奮起するものの、「ジャンカール・ビーツ」はリシとニッキーの離婚危機の直接の原因になっており、またギタリストも見つかっておらず、前途は多難だった。
仕事の方もうまくいかなかった。ディープとリシはコンドームの広告を担当することになるが、いいキャッチ・フレーズが思い浮かばない。おかげで顧客をフイにしてしまい、クビの危機にさらされる。
そんな中、ギタリスト志望の青年が現れる。彼の名はニール。ギターの腕は上々で、彼らはニールの加入を認めるが、実はニールは広告代理店の社長の息子だった。ニールも広告代理店で彼らと共に働き始める。
ニールにはひとつの悩みがあった。ニールはプリーティ(リヤー・セーン)という女の子に恋をしていたのだが、まだ一度も話しかけたことがなかった。シャーンティはディープとリシに、ニールの手助けをするように命令する。ニールはプリーティの前に出ると訳の分からないことを口走ってしまい、なかなか成功しなかったが、3回目のときに歌で彼女の心を射止める。
リシもニッキーと寄りを戻そうとするのだが、ニッキーはハンサムな弁護士と親密な関係になっており、近寄ることもできなかった。そんなときリシにアメリカ行きのチャンスが巡って来る。ニッキーから逃げるため、リシはアメリカへ行くことを決意する。しかしアメリカへ行く日は、ちょうど今年のジャンカール・ビーツと重なっていた。それでもリシはアメリカへ行くことに決めた。
ディープたちはリシを止めるものの、リシの決意は固かった。リシは長年の夢を諦め、心の友を捨てて空港へ去って行ってしまう。しかしリシは空港へ向かうタクシーの中で、「ボス」の名曲「Yeh Dosti Hum Nahin Todenge(この友情は永遠に)」を聞くのだった。リシは急遽ディープたちのもとへ戻り、共にジャンカール・ビーツへ乗り込む。
ジャンカール・ビーツにはシャーンティとプリーティも応援に駆けつけていた。いよいよディープたちの出番が廻ってきた。彼らは「ボス」の曲を演奏するが、その途中で妊娠中だったシャーンティが急に産気づき、ディープとリシは演奏を中断して彼女を病院へ運ぶ。
病院でシャーンティは元気な男の子を産む(「ボス」の名を取ってラーフルと命名)。と同時にジャンカール・ビーツで優勝したことが分かる。ディープたちは喜びの絶頂に達した。しかもひょんなことから「Better Safety Than Worry」というコンドームのキャッチ・フレーズまで思い浮かぶ。また、リシはニッキーにひたすら謝って何とか寄りを取り戻し、こうして6人はそれぞれの全ての問題を解決してハッピー・エンドを迎えるのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ヒンディー語映画と言いながらも、セリフの4割ぐらいは英語が入っており、半ヒングリッシュ映画というさらに新しいジャンルを確立させてしまいそうな映画だった。つまり、ヒンディー語と英語の両方が理解できないとストーリーを追うのに少し苦労するという、インドの言語状況を如実に反映させた映画であった。確かに英語だけでインド人が映画を作るのも違和感があるし、ヒンディー語だけで映画を作るのもまた現実離れしているので、これからこういうタイプの映画も増えていくかもしれない。
さすがにラーフル・ボースが出ていただけあって、後味のいいさわやかな映画に仕上がっていた。ストーリーの筋は3組のカップルの恋愛・家庭模様が横糸、ジャンカール・ビーツに優勝するという男たちの夢が縦糸になっており、一般的なインド映画の手法とそう変わらなかった。終わり方も予定調和的オール・ハッピー・エンドである。ただ、インド映画音楽界の巨匠R.D.ブルマン、コンドームの広告作り、バンド活動、おかしな脇役といった隠し味が効果的に散りばめられており、退屈しなかった。
ところでこの映画をさらに楽しむためにはR.D.ブルマンのことについて少し知っておいた方がいいだろう。ラーフル・デーヴ・ブルマンは、有名な音楽家でプレイバック・シンガーのサチン・デーヴ・ブルマンの息子として1939年に生まれてから1994年に死ぬまで、インド映画に数々の名曲を提供してきた天才的作曲家である。アリー・アクバル・カーンから幼年時代にサロードを習ったり、9歳で作曲を始めたり、ほとんど全ての楽器を演奏することができたりと、彼にまつわる伝説は多い。死後から10年経った今でもインド人の心の中に彼の作った歌は相当根付いているようで、R.D.ブルマンの作品のベスト集やリミックス集が今でもけっこう売れるほどだ。映画中ではディープ、リシが彼のことを「ボス」と呼んで尊敬し、彼らの練習部屋に巨大な彼の肖像画が描かれていたり、生前彼が住んでいた家を「マンディル(寺院)」と呼んで参拝に訪れたり、ディープとリシの間に入った亀裂を修復したのが彼の曲だったりと、これでもかというほどR.D.ブルマンに対する尊敬が払われていた。
なぜかコンドームに対しても異様なこだわりがあり、ところどころにコンドーム絡みのギャグがあった。現在インドでコンドームがどれくらい普及しているのか、それはよく分からない。だが、依然としてコンドームはいろいろな要因から買いにくい商品にとどまっていることは確かだと思う。薬屋で買うにしてもインドの薬屋はカウンターで欲しい薬の名前を言って出してもらう方式だし、屋台などで売っているコンドームは品質に疑問が残るし、スーパーマーケットなどで売っているコンドームも怪しげで割高である。また、映画にも出ていたが、貧しい庶民からしたら「コンドーム?ハリウッド・スターの名前だろ」というぐらいの認識しかないかもしれない。このままインドは人口世界一の大国へ突っ走るのだろうか。
シャヤン・ムンシーという新人が出ていたが、リティク・ローシャン・タイプのハンサムでダンスのうまい男優で、これからの活躍に期待ができそうだった。ハンサムな男優ではアルジュン・ラームパールを応援しているのだが、アルジュンはなかなかヒット作に恵まれず、くすぶっているので、その内シャヤン・ムンシーに乗り換えるかもしれない。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
シャヤン・ムンシー |
● |
けっこうお気に入りの女優ジューヒー・チャーウラーを久々にスクリーンで見ることができたのは嬉しかった。結婚後、最近めっきり出演の機会が減り、またお母さん役が増えてきたが、それでも美しさに衰えはそんなにないと思う。このままレーカーのような感じになっていくのだろうか。リンキー・カンナーとリヤー・セーンには全く興味なし。
音楽が主題の映画だったのだが、案外音楽はあまりよくなかった。音楽監督はヴィシャール&シェーカルというあまり聞いたことのない人。ただ、音楽の平凡さが気にならないくらい内容が面白い映画だったので救われていた。インド映画お約束のミュージカル・シーンも、そんなにしつこく入っていなかった。
僕の住んでいるガウタム・ナガルのすぐ近くにはAIIMS(All India Institute of Medical Science、通称メディカル)という全インド的に有名な大学病院がある。政府系の病院なので、無料で治療を受けることができ、デリーは元より他の州からもはるばる患者がやって来ている。やはりインドでも医科大学に入学するには相当優秀でなければならず、AIIMSはさらに南にあるIIT(Indian
Institute of Technology)と共にインド最大の理系難関大学となっている。
こういう事情もあって、実はガウタム・ナガルには多くの医者または医者の卵が住んでいる。街のレベルは他の高級住宅街に比べたら低いかもしれないが、人のレベルはけっこう高かったりするのだ。
僕の住んでいるアパートにも以前若い医者が住んでいた。名前はマニーシュ。いかにも頭のよさそうなインド人、という感じで、物腰の柔らかい人だった。僕に会うといつもニコニコしていたのを覚えている。いつの間にか彼は結婚し、AIIMSの敷地内にある既婚者用の宿舎に引っ越してしまった。どうも独身の医者は宿舎を宛がわれないため、マニーシュのようにAIIMS周辺で下宿したりしているようだ。
そのマニーシュがなんと交通事故に遭い、AIIMSで入院しているという話を聞いた。マニーシュがAIIMS構内をスクーターに乗って走っていたところへ、横から別のバイクが突っ込んできて、左足を骨折してしまったらしい。大家さんがお見舞いに行くというので、僕も連れて行ってもらうことにした。AIIMSは僕の家の目と鼻の先にありながら、まだ一度も中へ入ったことがなかった。興味はあったが、病院に用もなくブラブラと入るのはあまりいい趣味ではないと思っていたのだ。この機会にお見舞いと同時にAIIMSの中を少し見てみようと思っていた。
朝行くと聞いていたのだが、結局いろいろあって夜に訪れることになった。大家さんと、屋上に住んでいる警察官のオーム・プラカーシュさんと僕の3人でAIIMSへ入った。どうもAIIMSにはパブリック用の病棟と、プライベート用の病棟があるそうだ。パブリック用の病棟では無料で治療が受けられるが、その代わりに医療施設はよくないらしい。一方、プライベート用の病棟では個室が宛がわれ、上質の治療が受けられるが、1日1500ルピー以上のお金がかかるらしい。マニーシュはAIIMSで働く医者であったため、プライベート用病棟で特別に無料で治療を受けることができると言う。
微妙なオンボロさのエレベーターに乗って5階へ行き、病室に入った。ベッドにマニーシュが横たわっている。しかしその顔はいつものマニーシュではなかった。すさまじく不機嫌な顔をしていた。こんなに怒りを露にしているところは見たことがない。ちょっと威勢をくじかれ、「どう、元気?」と言ったきり僕は黙ってしまった。今日手術が終わったところらしい。
プライベート用病棟の病室を見回してみると、やっぱり微妙な清潔さ、微妙な汚なさである。インド映画に出てくるような、あらかじめ想像していた「インドの病院」よりも遥かにきれいだったことは確かだが、日本の病院のレベルからしたら「汚ない」と言わざるを得ない。最近の日本の病院は、病院らしさを消してホテルっぽい雰囲気にしようと努力しているように思われるが、インドの病院はいかにも病院という感じの、いかにも患者を「自分は患者なんだ」と思わせてしまうような、不思議な圧迫感がある。それでもこの部屋は他のパブリック用の病室に比べたら数倍いいのだろう。
マニーシュは相変わらず不機嫌で、僕は二言三言話しかけたが、彼はかすれた声で言葉を転がすだけで何を言っているのか聞き取れない。彼の左足全体にはギブスが痛々しく巻かれており、自分の足まで痛くなってくるほどだった。部屋にはマニーシュの奥さんと、母方の叔父と、彼のルームメイトだった若者がいた。
重苦しい空気が流れる中、30分ほど病室にいただろうか。誰ともなく立ち上がって病室を後にした。その後家に帰って専ら話題に上ったのは、なぜマニーシュがあんなに怒っていたか、である。大家さんもあんなに怒っているマニーシュは見たことがないと驚いていた。大家さんの息子のスラブは、「ぶつかって来たバイクの運転手に怒っているんだろう」と言い、奥さんは「よっぽど足が痛いんだろう、かわいそうに」と言い、オーム・プラカーシュ氏は「医者ってのは本で学んで他人の治療しているだけで、理屈では分かっていても患者がどれだけ痛みを感じているか分からないから、いざ自分が重症を負ってみると、その痛みの大きさに気付いて不機嫌になるのだろう」と言っていた。それらの意見を聞いた後、大家さんはゆっくりと自分の意見を述べた。「普通患者ってのは医学のことについて何も知らないから、医者の言うまま従っていればいい。でもマニーシュは医者だから医学のことをよく知っており、どう治療すればいいのか自分で判断できる。しかし主治医には主治医のやり方がある。おそらくその主治医のやり方が気に入らなくてすねているのだろう。」確かに僕たちが病室にいた間にも、医者がやって来てマニーシュと何やら口論をしていた。さすが大家さん、最も的確な分析をしていた。
とにかくAIIMSを見て、インドでは絶対に交通事故に遭いたくないと思った。もちろん日本でも遭いたくないが・・・。インドラプラスタ・アポロ病院などは世界水準の医療施設を備えているとは言うものの、無病息災でインド生活を送れるに越したことはない。
| ◆ |
7月30日(水) Chalte Chalte |
◆ |
日本でも人気のある映画男優シャールク・カーンがジューヒー・チャーウラーやアージズ・ミルザーらと共に立ち上げた映画制作会社、ドリームズ・アンリミテッド。金儲けのためではなく、個性的で本当に優れた映画を作ろうという高尚な夢と共にスタートしたのだが、第1作目の「Phir Bhi Dil Hai Hindustani」は、個人的には大好きな映画ではあるものの興行的には外れ、2作目の「Asoka」は莫大な制作費をかけて鳴り物入りで公開されたにも関わらず大コケし、シャールク・カーンの会社は「夢は限られていた!(Dreamz Limited!)」と揶揄されるまでになってしまった。最近のシャールクは資金集めのためにか、狂ったようにCMに出まくっている。「Devdas」の成功により男優としての面子は保たれたが、やはりここらで一発大ヒット作を自らの手で生み出しておきたい。「痩せ蛙/負けるな一茶/ここにあり」の情を持つ僕は、弱い立場に立たされたシャールクを密かに応援しているのであった。
そのドリームズ・アンリミテッドが「Asoka」の失敗に懲りずに(めげずに)新作を公開した。「Chalte Chalte(このままずっと)」である。6月13日に封切られた映画で、そんなにロングランせずに終わってしまったので、もう見逃したと思っていた。ところが調べてみたらグルガーオンに新しくできたシネマ・コンプレックス、DTシネマで1日1回だけ上映されていたので、終わってしまわない内に見ることにした。
「Chalte Chalte」のキャストはシャールク・カーン、ラーニー・ムカルジー、ジョニー・リーヴァルなど。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ラーニー・ムカルジー(左)と
シャールク・カーン(右) |
● |
| Chalte Chalte |
ラージ(シャールク・カーン)はトラック運送会社を経営するお調子者の男。プリヤー(ラーニー・ムカルジー)はギリシア育ちでインドにやって来たファッション・デザイナー。一見何の接点もないこの2人が運命の悪戯で出会い、ラージはプリヤーに恋してしまう。しかしプリヤーは幼馴染みのサミールと結婚する運命にあった。サミールとの婚約式に出席するためにプリヤーはギリシアへ向かうことになった。ラージとプリヤーは住む世界が全く違う。ラージは自分にチャンスがないことは分かっていた。しかし「あのとき止めていれば」と後で後悔しないためにラージは仕事を投げ打ってプリヤーを追いかける。
ギリシアに着いたラージとプリヤーは、乗り換えの飛行機の遅れから二人でギリシア観光をする。その間にプリヤーは次第にラージに心を開く。ラージは「君が幸せでいることで、幸せになれる男がこの世界のどこかに一人いることを覚えておいて」と言い残してプリヤーと別れる。自宅に戻ったプリヤーは、サミールではなくラージと結婚することを告げる。両親も最初は反対するものの、プリヤーの信念とラージの人柄に押されて二人の結婚を許すのだった。
結婚から1年後。ラージとプリヤーは喧嘩を繰り返しながらもインドで仲良く暮らしていた。ところがラージの会社のお得意先の会社が倒産したことにより、ラージの会社も多額の負債を抱えることになる。1週間以内に250万ルピーを揃えなければ会社は差し押さえられてしまう。ラージは他人の力を借りることを潔しとしない性格で、何とか自分の力で解決しようとするが、八方塞がりだった。それを見ていたプリヤーは、サミールにお金を借り、それを内緒にしてラージに渡した。
ひとまずラージの会社の倒産は免れたものの、ラージにサミールからお金を借りたことがばれてしまう。ラージは烈火の如く怒り、サミールの前でプリヤーを侮辱する。プリヤーはそれに怒って家を出て行ってしまう。
ラージは酔っ払ってプリヤーと話をしに行く。だがプリヤーの叔母に追い返される。暴れるラージは警備員に取り押さえられ、もう少しで警察に連れて行かれそうになるが、プリヤーが止める。しかしプリヤーは、ラージと一緒に住むことも難しく、ラージと離れて住むことも難しいことを痛感し、いっそのことギリシアへ行ってしまうことを決めた。
プリヤーがギリシアへ行くことを知ったラージは、空港まで彼女を追いかける。どさくさに紛れて空港内に入り、飛行機に乗り込もうとするプリヤーを見つけて必死で説得をする。しかしプリヤーは飛行機に乗り込んでしまった。
絶望のどん底で自宅に戻るラージ。誰もいない家の灯りをつけると、なんとそこにはプリヤーがいた。プリヤーはやはりラージがいなくては生きていけないと思い直して帰って来ていたのだった。抱き合う二人だが、すぐに小さなことでまた口喧嘩を始めるのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
シャールク・カーンお得意のストーキング・ラヴストーリーと、最近ボリウッドで流行の「結婚後の夫婦の実態話」をミックスさせた映画だと感じた。スタンダードなインド映画で、「Asoka」などよりはリラックスして作られている。普通に楽しめる映画ではあるが、シャールク・カーンの映画には少し期待をかけてしまう分、普通だとちと物足りない気持ちもある。
好きな女の子を追いかけて追いかけて追いかけまくって物にするというストーカーに等しい求愛行動はインド映画の基本だが、その大御所と言えばやはりシャールク・カーンだろう。日本でも公開された「Anjaam(邦題:アシュラ)」などはひどかった。そういう古典的なシャールク映画を、この映画の前半で久々に見ることができる。
一方、後半では結婚後のラージとプリヤーのつばぜり合いが描かれる。インド映画でもおとぎ話でも、ヒーローとヒロインが結婚してめでたしめでたしで終わることが多いが、最近のインド映画では結婚後の理想と現実のギャップも正直に描写されるようになって来た。2002年末に公開された「Saathiya」などは最もうまくできていた「結婚後」映画だった。「Chalte Chalte」の前半では、まるで恋愛小説のようなラブストーリーの主人公だったラージとプリヤーも、後半では醜い争いを繰り広げるありきたりな夫婦となってしまう。結婚後の夫婦が描かれるようになったのは、ボリウッドが新しいテーマを求め始めたこともあるだろうが、僕はもうひとつ理由があると思う。90年代のヒンディー語映画黄金期を担ったスターたちが、次第に独身のヒーロー、ヒロインでは通用しない年齢になって来ており、それでいて彼らに代わるようなカリスマを持った新人がなかなか現れないことが、映画中の主人公の高年齢化・既婚化の原因となっていると思われる。
割と有名な話だが、ヒロインは元々ラーニー・ムカルジーではなく、アイシュワリヤー・ラーイだった。しかし元恋人で本当にストーカーと化したサルマーン・カーンとのドンパチによって降ろされてしまったのだ。だが、ラーニー・ムカルジーよりもアイシュワリヤー・ラーイの方が絶対に適役だったと思う。「タイタニック」のような階層を越えたラヴストーリーなので、天女のような美しさを誇るアイシュワリヤーの方がその階層差をより感じさせてくれるだろう。ラーニー・ムカルジーはちょっと高嶺の花という感じではない。一方のシャールク・カーンも、もはや庶民という顔をしておらず、トラックの運ちゃん姿は全然似合っていなかった。少し配役に難があったか。
ギリシアというのは目新しかった。おそらく本当にギリシアでロケが行われていただろう。アテネのパルテノン神殿らしきものも映っていた。ギリシアにもインド人移民がいるのかどうかはあまりピンと来ないものの、いくつかのミュージカル・シーンで見られた真っ白に塗られた建物と真っ青な空とのコントラストは美しかった。一昔前のインド映画の海外ロケと言ったらスイスやカナダだったが、最近だんだん海外ロケがマイナー所を狙うようになって来たように感じる。日本は物価の関係で難しいだろうが、いつかまた「Love In Tokyo」のように日本ロケのインド映画にも挑戦してもらいたい。
インド随一のコメディアン俳優ジョニー・リーヴァルの役柄も毎回気になるところだが、今回は「Chor Machaye Shor(1974年)」の「レ〜ジャ〜エンゲ〜、レ〜ジャ〜エンゲ〜、ディルワ〜レ〜ドゥルハニャ〜ンレ〜ジャ〜エンゲ〜」という歌をいつも歌っている変な飲んだ暮れという役だった。好きだった女の子が別の男と結婚して去っていってしまい、「あのとき止めていれば」と後悔している内にこうなってしまったという。彼の哀れな状況を見て、ラージはプリヤーを追いかけてギリシアまで行くことになるから、ストーリーにはけっこう関わっているが、なんとなく中途半端な役だった。ジョニー・リーヴァルと一緒にいた三毛犬は高級な犬と見た。
ちなみにグルガーオンとは、デリーの南西部にあるデリーの衛星都市である。「サトウキビの村」という名前からすると、おそらく一面にサトウキビ畑が広がっていた地域なのだろう。デリーが東京だとしたら、グルガーオンは横浜にあたる。グルガーオンはハリヤーナー州なのだが、デリー首都圏を構成しており、あまりハリヤーナーという感じでもない。グルガーオンへは実は初めて行ったのだが、デリーではまだ見受けられないような巨大なショッピング・モールが林立しており、びっくり仰天驚いた。デリーも急速に発展しているが、グルガーオンの発展はそれを上まる勢いだ。DTシネマはシティー・センターというモールの中にあり、その向かいにはメトロポリタンというモールがあって、中にはこれまた高級シネマ・コンプレックス、PVRグルガーオンがあった。この辺りはグルガーオンのホット・スポットになっているようだ。デリー・ウォーカーもグルガーオンの情報収集に乗り出さねばならないと感じた。一応以下グルガーオンの豆情報。
◆デリーからグルガオーンへバスで行く場合、ダウラー・クンアーかメヘラウリーでグルガーオン行きのバスに乗るか、サラーイ・カーレー・カーンISBTなどからジャイプル行きのバスに乗るのがいいだろう。ただ、グルガーオンは街の発展に見合うほど交通機関が発達していないので、自家用車で行ったりタクシーをチャーターして優雅に買い物を楽しむのがグルガーオンの正しい遊び方のように思えた。
◆メヘラウリー・グルガーオン・ロードにいくつか大きなショッピング・モールが建っている。ただ、薬屋の横に別の薬屋ができるようなインド人の悲しい習性からか、それぞれのモールに入っている店舗はあまり変わり映えしない。マクドナルド、ニルラーズ、サブウェイ、ピザハット、アールチーズ・ギャラリーなどなど・・・。はっきり言って同じ内容のモールがいくつあっても意味ないだろう。その中で、シティー・センターとメトロポリタンは映画館を併設しているので一歩抜きん出ている。ちなみに、まだ完成していなかったが、PVRグルガーオンの前にはヨーロッパ映画専門の映画館ができるようだ。これはすごいことになりそうな予感。
◆インドの近代建築コンセプトに足りないところはいくつもあるが、僕が一番改善してもらいところはエスカレーターだ。日本のデパートは客が利用しやすいようにエスカレーターを配置する工夫がなされていることが多いが、インドのエスカレーターはわざと客をたくさん歩かせるように配置してあるように思える。だからエスカレーターを使って上の階へ行くのにけっこう疲れる。もっとも、インドではまだエスカレーターが一般化していないので、エスカレーターの横に「How to use Escalator」というインストラクションが立っていたりする。おばさんや小さな子供などはエスカレーターが苦手のようだ。
| ◆ |
7月31日(木) Darna Mana Hai |
◆ |
ホラー映画はインド映画の最近の流行である。世界一の映画大国インドで今まであまりホラー映画が作られてこなかった方が不思議なくらいだ。お化けとか妖怪という概念はインドにもあり、ブートと言えばお化け、ラークシャスやピシャーチュと言えば鬼とか妖怪、アートマーやパルマートマーと言えば魂など、いろいろな分類もある。今日PVRアヌパムで見た「Darna Mana Hai(恐怖は禁止)」はインド製ホラー映画の最新作である。
副題は「Six Stories One Ending」。オムニバス形式の映画で、6つの小話で構成されている。ただ、見てみて思ったのは、この映画はホラー映画というよりは、「世にも奇妙な物語」のような、不思議で面白い話を集めたような映画だった。映像で語っていくタイプの話の運び方だったので、ヒンディー語が分からなくてもけっこう楽しめる映画だと感じた。簡単にあらすじを書いておく。
| Darna Mana Hai |
ムンバイーからゴアへ向かおうと、7人の若者たちが真夜中林道を車でに乗って走っていた。ところが途中でタイヤがパンクしてしまう。修理道具を持って来なかったため、他の車が通りかかるのを待つが、何も来る気配はない。車を降りると空気は非常に冷たい。その内一人が森の中に家の灯りらしきものを見つけたので、助けてもらおうと1人を車に残して6人はその灯りを目指して森の中を歩いた。
たどり着いた先には廃墟があった。そこで6人は焚き火を囲んで怖い話を語り始める。ひとつのストーリーが終わるごとに1人ずつ車の方へ去っていくが、誰も帰ってこなかった。6つのストーリーが終わったとき何かが起こる・・・! |
6つのストーリーを簡単に説明すると、「真夜中人気のない森をドライブするカップルの話」「愛煙家が禁煙狂ホテルに宿泊する話」「ある日突然宿題をちゃんとやって来るようになった生徒を恐れる教師の話」「食べるとリンゴになってしまう不気味なリンゴの話」「墓場で乗り込んできた幽霊の話」「神様から超能力を授かったさえない男の話」である。それぞれの小話では割と有名な俳優が出演していたりして、密かに豪華キャストだった。一応有名なキャストの名前を挙げておくと、アーフターブ・シヴダーサーニー、ナーナー・パーテーカル、シルパー・シェッティー、サイフ・アリー・カーン、ヴィヴェーク・オーベローイ、アンタラー・マーリー、イーシャー・コーッピカル、ラージパール・ヤーダヴ、サンジャイ・カプールなどなどである。
| ● |
|
● |
|
 |
|
| ● |
ヴィヴェーク・オーベローイ(左)と
ナーナー・パーテーカル(右) |
● |
ひとつひとつの小話ははっきり言ってしょうもない内容なのだが、ヒンディー語映画でこういうオムニバス形式の映画というのは目新しかったのでよしとする。敢えてお気に入りの小話を挙げるとすれば、サイフ・アリー・カーンが出ていた喫煙狂ホテルの話と、サイコな教師の話だろうか。ただ、小話ではなく全体の話の最後のまとめ方は最悪だった。確かにまとめるのは難しいとは思うのだが、もっとインド映画的な解決方法を模索してもらいたかった。
ちなみに、ホラー映画にミュージカル・シーンは必要ないとやっと理解してもらえたようで、「Bhoot」に引き続きノー・ミュージカルの映画だった。ただ、こうなって来ると音楽CDが売れないため、少し映画制作のシステムを変えないといけなくなってくるのではないかと別の心配をしてしまう。
|
|
|
|
|
NEXT▼2003年8月
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



