 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 �@����ŃC���f�B�A�@ �@����ŃC���f�B�A�@
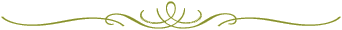
�Q�O�O�R�N�X��
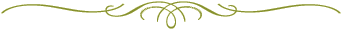
|
|
|
|
�@�O��W���R�P���̓��L�ŁA�a�@�ł̐f�f�̌��ʁA���t�܂��͊̉��ɂȂ����Ə������B�Ƃ��낪���܂�ɊȒP�ɐf�f����Ĕ[���������Ȃ��������߁A����̓C���h�ō��̎{�݂����C���h���v���X�^�E�A�|���a�@�֍s�����B�A�|���a�@�͔��ɍ����Ȃ̂����A��҂̃��x���͍����B�f���[�ŊO���l�������d�a����������d�������肵���Ƃ��͂����������̕a�@�ɗ��邱�Ƃ������B
�@����͐��m�Ȍ��������邽�߂ɁA���t�����Ƃw�����������Ă�������B���t�����ł͂Ȃ����R�A�S���C�ɍ̌����ꂽ�̂ŁA���Ȃ肮������Ƃ��Ă��܂����B�P���Ƃ�ΑS�������邾�낤�ɁE�E�E�B
�@�A�|���a�@�̈�Â̎��͂����炭�]���ʂ�C���h�ō����Ǝv���̂����A������a�@�̂��߁A�s�ւ�����B����������̂ɂ��������炱�����֕������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������肷��B�܂��A�f���[�ɂ̓��b�`�ȃC���h�l�������̂ŁA���҂̐������Ȃ葽���B�҂����Ԃ��������Ƃ�����B�ҍ����̃G�A�R������������̂���_�ł���B�������Őf�f���I�������A�l�̕a��͑O�����������Ă��܂����B
�@�����̈�҂������ɂ́A�l�͊̉��ł����t�ł��Ȃ��������B����ς�E�E�E�B���t�ɂȂ�����ڂ�܂����F�ɂȂ�͂������A�l�̐g�̂ɂ��̂悤�Ȓ���͔��o���Ȃ��B�����}�����A�̉\��������Ƃ����B�E�E�E���������R�A�S�����O�ɃA�b�T���𗷍s���Ă����̂ŁA�n�}�_���J�Ɏh���ꂽ�\���͂���B�f���[�ɂ��}�����A���҂�n�}�_���J�����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B���x�͈�C�Ƀ}�����A�C���ɂȂ����B�����`�^�̉���������A�������ꂽ�E���R��H�ׂ����ƂɂȂ�̂ŃJ�b�R�������A�}�����A���������r�I���h���̂����a�C�ł���B�Ƃɂ����������ʂ͂P����ɏo��̂ŁA���̓��͂���ʼnƂɖ߂����B
�@������������}�����A�ɂȂ����C���ōēx�a�@��K��Č��ʂ����Ă݂�ƁA���lj��t�ł��}�����A�ł��Ȃ������B���Ⴀ���������̂��A�Ƃ����b�����A�ʂɉ��ł��Ȃ��悤���B�a�����͂����肵�Ȃ��B�����g�̂̍R�̂����Ȃ����Ă���A���ꂩ��E�C���X��ۂɊ������鋰�ꂪ����炵���B���̂��ߍR���������������ꂽ�B
�@�����ɂȂ��ĂȂ�ƂȂ��̒������Ă����̂ł悩�������A�܂��g�̂ɗ͂�����Ȃ��������B�̉����}�����A��狰�낵���a��������ꂽ���Ƃɂ�鐸�_�I�V���b�N���傫�������B��̐肢�t�̗\�������Ǔ������Ă��Ȃ��悤���B�ĊO�C���h�ɂ��Ă���a�ɂ͜��Ȃ����̂Ȃ̂��E�E�E�B
�@�C���h�����E�Ɍւ����̂͂���������B�A�[�O���[�̃^�[�W�E�}�n����������A���E�꒷��ȏ������}�n�[�o�[���^��������A���y�║�x�Ȃǂ̌ÓT�|�\��������A���E�Ŋ���h�s�Z�p�҂�����������A�l�ɂ���ċ�������̂͗l�X���낤�B���ꂾ���C���h�ɂ̓��j�[�N�Ȃ��̂����݂���ʔ������ł���B���̒��ŁA�I�[���h�E�����N�̖���������l�����Ȃ��炸����̂ł͂Ȃ��낤���H
�@�I�[���h�E�����N�Ƃ́A�C���h�Y�̃������̖��O�ł���B�C���h�̎��Ƃ����ƁA���{�̃C���h�������ɂ悭�u���Ă���}�n���W���E�r�[���Ȃ�r�[�����v�������ׂ�l�������������瑽����������Ȃ����A�}�n���W���E�r�[���̓f���[���ӂł͎�ɓ���Ȃ����A�l�͍��܂ŃC���h�Ō������Ƃ��Ȃ��B�C���h�̃r�[���̉����Ƃ�������A�L���O�E�t�B�b�V���[�����Ȃ��B�������L���O�E�t�B�b�V���[�̖��Ɋ���Ă��܂��ƁA���{�̃r�[�����ØI�̂悤�ɂ��܂�������Ƃ������炢�̖��Ȃ̂ŁA�l�̓L���O�E�t�B�b�V���[���C���h�̎��̑�\�ɂ������Ȃ��B��͂�C���h�Y�����̌���ŁA�I�[���h�E�����N���\�I��Ƃ��Đ����������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�I�[���h�E�����N |
�� |
�@�l�̓C���h�ɗ��w����܂Ń����̖���m��Ȃ������B���R�ƁA�������Ƃ����̂͑D��肪�D����̎���Œ��Ԃ����ƃ|�[�J�[�ł����Ȃ������ł���悤�ȏa�����ݕ����낤�Ǝv���Ă����B�C���h�ɗ��Ď��W�ł܂��������̂́A�C���h�l�̓r�[���ɕX�����Ĉ���ł��邱�Ƃ������B���̎��ɒm�����̂́A�ǂ����C���h�l�̓��������D�����Ƃ������Ƃ������B�E�B�X�L�[���W�����E�H�b�J�������ނ��A��Ԃ̓����Ƃ����������B���ɌR�l�̓����D���������炵���B�������A�I�[���h�E�����N�Ƃ�����������Ԉ����Ă��܂��悤���B�l���C���h�l�ɂ���ă���������������ł݂���A�v���Ă��������Â��āA�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��f�B�[�X�����̖��������B��������̂͂��A�����̓T�g�E�L�r����ł��Ă���B���̃����ɃR�[���������Ĉ��ނƔ��ɂ��܂����Ƃɂ������ɋC���t�����B���Ȃ݂ɃC���h�ł̓��C���͏��̈��ݕ��ƌ��Ȃ���Ă��邽�߁A��̒j�����C�������ނ��Ƃ͏����I�J�}���ۂ��s�ׂɎv����i�㗬�K���ł͂܂��ʂ����j�B
�@�I�[���h�E�����N���烉���ɓ������̂ŁA�l�ɂƂ��ă������I�[���h�E�����N�������B�o�J���f�B�[��X�B�b�L���E�����ȂǁA���̖����������Ă͂��邪�A�I�[���h�E�����N�ɓK�������͂Ȃ������B�C���h�ɗ��āA�l�͂������胉���D���A�Ƃ������I�[���h�E�����N�D���ɂȂ��Ă��܂����B
�@�����Ȃ��Ă���ƁA���{�ɋA���Ă����������݂����Ȃ�B�����A�A���Ă݂ċC�t�����̂����A������u���Ă��鋏�����Ƃ����͓̂��{�ɂ͈ĊO���Ȃ����̂��B�C���h�Ń����̒u���Ă��Ȃ��o�[�͍l�����Ȃ��̂����A���{�ł͑����C�̗������Ƃ���֍s���Ȃ��ƃ����ɂ͂�����Ȃ��B�܂��A�������Ƃ��Ă��A���̃������܂����E�E�E�I�܂������C�̔��������ł���B�I�[���h�E�����N�������ɂ��܂��������A�܂������{�̃���������Ŏv���m�炳�ꂽ�B
�@�N�z�̃C���h�D�����{�l�ɂ����̓I�[���h�E�����N�D���͑����B�u�I�[���h�E�����N�������E��̃������v�ƌ����l�����āA�l�́u��͂�v���������ꂽ�B�������Ȃ��I�[���h�E�����N�͂���Ȃɂ��܂��̂��H�P���b�g���Q�O�O���s�[���炸�̎����A�ǂ����Ă���قǃn�C�E�N�I���e�B�[�̖��������o�����Ƃ��ł���̂��H�S���s�v�c�ł���B�܂��A��x�R���p�ɐ������ꂽ�i�I�[���h�E�����N�������Ƃ�����B���ꂪ��ʎs�̗p�̃I�[���h�E�����N��������ɔZ���Ȗ������āA����ɋ������L��������B���̃I�[���h�E�����N���A�C���h�P�O���l�����R�l�����̗͂̌��ɂȂ��Ă���̂��E�E�E�I
�@�I�[���h�E�����N�̕r�̌`�������B�I�[���h�E�p�[�̃p�N���ƎU�X���Ȃ���Ă��邪�A����ł��l�͍D�����B�����ɂ��������ۂ����x�����\���Ă���̂��ꋻ�B�Ƃ��ǂ����̃��x�������Ȃ肸��Ă����肷�邪�A���ɖ��͂Ȃ��B�ςȂ�������̊G�������Ă��邪�A������������͒N�Ȃ̂��낤�H
�@���{�ɋA��Ƃ��̓I�[���h�E�����N������ł��y�Y�ɂ��悤�ƌv�悷��̂����A�����o���ԍۂ͂��Ȃ�Z�����Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�����ɍs���Ď����Ă���ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���܂Ŕ����Ă��������Ƃ͂Ȃ��B��`�ŃI�[���h�E�����N��̔����Ă��Ȃ��̂́A�C���h���{�̍ő�̃~�X���Ǝv���Ă���B�Ȃ��C���h�����E�Ɍւ�I�[���h�E�����N����`�œ��X�Ɣ���o���Ȃ��̂��낤���H�N���^�[�E�p�[�W���[�}�[�𒅂āA�A���o�T�_�[�ɏ���Ă��Ă��A�I�[���h�E�����N��n�܂Ȃ�������A�^�̃C���h�l�Ƃ͔F�߂��Ȃ����낤�B�܂��ɃC���h���\������A�I�[���h�E�����N�B���{�ʼnʂ����Ď�ɓ���ꏊ������̂��낤���H
| �� |
�X���U���i�y�j�@�f���[���{�l���w���𗬉� |
�� |
�@���������f���[�ɂ͉��l�̓��{�l���w��������̂��낤���H����ȑf�p�ȋ^�₩��n�܂����f���[���{�l���w���𗬉�A���N�͂Q��ڂ��}�����B���N�͖Y�N��V�[�Y���ɍs�������A���N�̓C���h�̑�w�Ȃǂ̐V�w���J�n�P������ɂ�����X���̍����s�����Ƃɂ����B���͑O��Ɉ��������A���@�T���g�E���B�n�[���ɂ�����{�������X�g�������ނ�B�P�l�P�T�O���s�[�œ��{�H�r���b�t�F�H�ו�����ݕ���Ƃ����i���̒l�i��ݒ肵�Ă����������B
�@����͗��w���Ƃ̌𗬂���]����Љ�l�̐l�����l�Q�����Ă���āA�܂��C���h�l��؍��l�Ȃǂ����l���Ă���A���v�R�X�l���𗬉�ɎQ�������B���{�l�̗��w���Ɍ���ƁA���̐��͂Q�W�l�ɂȂ�B����̓W�����[�n�����[���E�l���[��w�i�i�m�t�j�̊w�����P�T�l�A�f���[��w�̊w�����T�l�A�P�[���h���[���E�q���f�B�[�E�T���X�^�[���̊w�����S�l�A���̑����S�l�ł���B���݂̗��w������ƁA��͂�i�m�t�ɗ��w������{�l����ԑ����Ƃ������ƂɂȂ�B�����A����̓f���[��w�ɐV�����������l���Q�����Ă��Ȃ������B�����������甭���ł��Ȃ�����������������Ȃ��B�f���[��w�̃L�����p�X�̓o���o���ɂȂ��Ă���̂ŁA���肷��ƈ�l�̓��{�l�ɂ���킸�ɗ��w�������I���Ă��܂��l�����邩������Ȃ��B
�@��L�̒ʂ�A���̑��ɂ����{�l���w��������\���͏\���ɂ���̂����A�Q�O�O�R�N�x�̃f���[�ł̓��{�l���w���̐��́A��R�O�l�Ƃ������Ƃɂ��č����x���Ȃ����낤�B���N�����{�l���w���̐��͂R�O�l�������̂ŁA�����ϓ��͂Ȃ��B
�@�O��̗��w���𗬉�͕K�����������Ƃ͌��������������̂����A����͊��Ɛ���オ�����Ǝv���B���ɐV���Ƀf���[�ɗ����l�X�ɂ́A�R�l�N�V�����̗ւ��L���邢���@��ɂȂ����Ǝv����B
�@�l�̂��̃z�[���y�[�W���f���[�ݏZ�̐l�ɂ悭�ǂ܂�Ă��邽�߁A�u�̒��͂���������ł����H�v�Ƃ��u�̉��͎�������ł����H�v�Ƃ��u���O�����������H�ו��͐H�ׂȂ��v�Ƃ��A���낢�뎿�₳�ꂽ�B�����ł�����x�����Ă������B�l�͕ʂɊ̉��ł��}�����A�ł��Ȃ��A�����P�ɍ��M���o�đ̒�������������������B�̉��Ɛf�f���ꂽ�̂͌�f�������B�}�����A���\��������ƌ���ꂽ�����ŁA���t�����̌��ʁA�}�����A�����͔�������Ȃ������B��T�̐��j�������肩�獂�M���o�����A�P�T�Ԍ�̍��T�̐��j���ɂ͂����ԉ��A���͂������ʂɐ����ł��Ă���B���낢��Ȑl�ɐS�z�������Ă��܂������Ƃ����̏����Ă��l�ѐ\���グ�܂��B
�@�ŋ߃f���[�̍����f��ق͏T���ǂ����卬�G�ł���B�������̂܂܍s���ă`�P�b�g�����̂�����Ƃ������s�\�ɂȂ��Ă����悤�Ɋ�����B�ȑO�̓q�b�g��ȊO���������f���ԂP�O���O�ɍs���Ă���ɓ����Ă����̂����A���ł̓q�b�g��͂܂��^����ɖ��ȂɂȂ�̂͂������̂��ƁA����ɂ���đ��̍�i�ɂ��ϋq�����ꍞ�ނ̂ŁA�T���͂ǂ̉f����K�����ȂɂȂ�B�f��ّ����炵�����ׂ����낤�B
�@�����͍ŐV��uKuch Naa Kaho�v���A�p�e�[���E�i�K���̍����V�l�}�E�R���v���b�N�X�A�T�e�B�����E�V�l�v���b�N�X�Ō����B�����̍��G�Ԃ�������Ȃ��̂ŁA�o�u�q�n��̉f��ق������ԏ�̐����������Ă��Ȃ����߁A�o�����͓����Ȃ����炢�a�ƂȂ��Ă���B
�@�uKuch Naa Kaho�v�Ƃ́u��������Ȃ��Łv�Ƃ����Ӗ��B�剉�̓A�C�V���������[�E���[�C�ƃA�r�V�F�[�N�E�o�b�`�����B���Ɋ��҂����Ă����킯�ł͂Ȃ����A�A�C�V���������[�E���[�C���o�����Ă������߂Ɍ��Ă݂����Ǝv�����B��͂�C���h�̎���͋���ȃX�N���[���Ŋy���܂Ȃ���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�A�C�V���������[�E���[�C�i���j��
�A�r�V�F�[�N�E�o�b�`�����i�E�j |
�� |
| Kuch Naa Kaho |
�@�j���[���[�N�ŕ�e�Ƌ��ɏZ��ł������[�W�i�A�r�V�F�[�N�E�o�b�`�����j�́A�]�o���̌������ɏo�Ȃ��邽�߂Ƀ����o�C�[�ւ���ė����B���e�̂��Ȃ����[�W�ɂƂ��āA�f���̃��[�P�[�V���i�T�e�B�[�V���E�V���[�j�͕�����̑��݂������B����̓��[�P�[�V���̒����̌������̂��߂Ƀ��[�W���Ăъ��킯�����A���̑��Ƀ��[�W�̂���������������ړI���������B
�@���[�W�͌�������C�ȂǂȂ��������A���[�P�[�V���͉�Ђ̕����̃i�����^�[�i�A�C�V���������[�E���[�C�j��t�Y���l�ɂ��ă��[�W�̂�������������s������B���[�W�͂������������K���ɂ��킵�Ă��߂������A���̓��i�����^�[�ɗ������Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪�i�����^�[�͊����ŁA�A�f�B�e�B���Ƃ������q�������B�����A�v�̃T���W�[���̓A�f�B�e�B�������܂��O�Ɏ��H���Ă���A�V�N�ԃi�����^�[�͏����l�ŃA�f�B�e�B������ĂĂ����̂������B�A�f�B�e�B���̓��[�W���C�ɓ���A�����̂�������ɂȂ��Ă����悤�ɗ��ނ��A���[�W�̋C�������������i�����^�[�͔ނ������悤�ɂȂ�B
�@���[�W�̓i�����^�[�������ł���ƒm��Ȃ�����A�ޏ��ƌ������邱�Ƃ����ӂ���B�i�����^�[�����ɔނ̔M�ӂɕ����A���[�W�ƍč����邱�Ƃ����߂�B�������̂Ƃ��ɓˑR�v�̃T���W�[���������B�T���W�[���͋���ׂ��邽�߂ɃA�����J�֍s���Ă����̂������B�����i�����^�[���A�f�B�e�B�����A�T���W�[��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�T���W�[���͎��������Ȃ��Ԃɕ��e�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m���������[�W�ɑ��Ď���ɋ��d�Ȏp�����Ƃ�悤�ɂȂ�B
�@�]�o���̌������̓��B���ɃT���W�[���A���[�W�A�i�����^�[�̕��G�ȊW����G�����̏�ԂƂȂ�B�����Ńi�����^�[�̓��[�W�Ƌ��ɏZ�ނ��Ƃ��T���W�[�����͂��ߊF�̑O�Ő錾����B�T���W�[���̓i�����^�[�ƃA�f�B�e�B�������[�W�ɑ����A���̏�������Ă����B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�f��̑薼�ʂ�A�����R�����g�������Ȃ��قǑދ��ȉf�悾�����B�A�r�V�F�[�N�E�o�b�`�������o��f��͂ǂ����Ă������܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤���H�ʂɔނ����̐ӔC�ł͂Ȃ��Ǝv���̂����A�Ȃ����ނ̂����ł܂�Ȃ��Ȃ������̂悤�Ɏv���Ă��܂��͖̂Ƃ��������B
�@�ꉞ�l�͂ǂ�ȉf��ł������Ƃ���������ď����悤�ɂ��Ă���̂ŁA������������悤�B�܂��A�ŏ��̃X�^�b�t�E���[���͂Ȃ��Ȃ��ʔ��������B�e���b�v�Ŕo�D��N���[�̖��O���Љ��̂ł͂Ȃ��A�f���̒��̃I�u�W�F�N�g�ɂ��̂܂ܖ��O���f���o����Ă����B�������Ă�����A�C�V���������[�E���[�C�̓����V�[�����Ǝv�킹�Ă����āA���̓A�r�V�F�[�N�E�o�b�`�����̂������Ƃ����̂͋q�������傭��߂����Ǝv���B
�@�A�r�V�F�[�N�E�o�b�`�����̉��Z�́A���\��Ŗق��Ă���V�[�����炢�����J�߂�ׂ��Ƃ��낪�Ȃ��B�A�C�V���������[�E���[�C������͂��܂薣�͓I�ɕ`����Ă��Ȃ������B����ɂ��Ă��V�̎q���̕�e���ɂȂ��Ă��܂��Ă����̂��낤���A�A�C�V���́H�܂����ꂳ�D�ɓ]������̂͑�������Ǝv���̂����E�E�E�B
�@�f��̒��ŁA���y�̗ǂ������͍ۗ����Č����Ă����B���y�ē̓V�����J���E�G�w�T�[���E���C�̃g���I�B�uDil Chahta Hai�v�̉��y�ēŁA���j�[�N�ȉ��y�����̂Ŗl�͂��������D�����B�uKuch
Naa Kaho�v�̉��y�ł̓e�[�}�E�\���O�́uKuch Naa Kaho�v�A�V���o�f�B�X�R�E�\���O�uTumhe Aaj Maine Jo Dekha�v�Ȃǂ��悩�����B���Ȃ݂ɁuABBG�v�Ƃ����Ȃ����邪�A����͉f������ď��߂Ăǂ������Ӗ������������B�̎��͉p��̃A���t�@�x�b�g���ꌩ������ɕ���ł���B�u�`�a�a�f�@�s�o�n�f�@�h�o�j�h�@�t�o�n�f�v�̂悤�ɁB����͂悭������p��̍��������q���f�B�[��ɂȂ��Ă���A�u������Ɖ�����A����������ł��������ȁA���͈���ŗ��܂����A���Ȃ�������ł��������v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă���i�G�[�A�r�[�r�[�E�W�[�A�e�B�[�i���j�@�s�[�I�[�E�W�[�A�A�C�i���j�@�s�[�P�@�A�[�C�[�A���[�i���Ȃ��j�@�s�[�I�[�E�W�[�j�B���̋Ȃ̌��t�V�тɂ͒E�X�B
�@����Ɉ��������������f������ɍs�����B���T�̖{���͎��͂��́uCalcutta Mail�v�ł������B�������O����\���҂��s�u�Ȃǂŗ���Ă����̂����A����ƌ��J�ƂȂ����B�o�u�q�A�k�p���S�Ŋӏ܁B
�@�uCalcutta Mail�v�Ƃ́A�ʂɎ莆�̂��Ƃł͂Ȃ��A��Ԃ̖��O�ł���B���ׂĂ݂����A���̂悤�Ȗ��O�̗�Ԃ͌�������Ȃ������̂ŁA�ˋ�̗�Ԃ��Ǝv����B�剉�̓A�j���E�J�v�[���A���[�j�[�E���J���W�[�A�}�j�[�V���[�E�R�[�C���[���[�B���W���[�����a���o�D�������Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���[�j�[�E���J���W�[�i���j��
�A�j���E�J�v�[���i�E�j |
�� |
| Calcutta Mail |
�@��l�̒j���R�[���J�[�^�[�̃n�[�E���[�w�ɍ~�藧�����B�j�̖��̓A���B�i�[�V���i�A�j���E�J�v�[���j�B�A���B�i�[�V���͉����̈��h�ɏh�����邪�A�����Ńu���u���i���[�j�[�E���J���W�[�j�Ƃ��������Ǝu�]�̏��̎q�Əo��B
�@�A���B�i�[�V���̓��J���E���[�_���Ƃ����j���N�ɂȂ��đ{���Ă����B�����ǂ����֏o�|����A���B�i�[�V�������ĕs�v�c�Ɏv�����u���u���́A�A���B�i�[�V���̔閧��T�낤�Ƃ��낢�낿����������o���B���̓��A���B�i�[�V���́A�U�����ꂽ�����̑��q��T���ɃR�[���J�[�^�[�֗������Ƃ�ł��������B���������J���̕����A���B�i�[�V�����E�����߂Ɏh�q�𑗂�A�A���B�i�[�V���͕m���̏d�����Ă��܂��B
�@�a���ŃA���B�i�[�V���̓u���u���ɑS�Ă����B�A���B�i�[�V���͓������R�ɃT���W���i�[�i�}�j�[�V���[�E�R�[�C���[���[�j�Ƃ��������ɏo������B�T���W���i�[�̓r�n�[���̗L�͎҃X�W���[���E�X�B���̈�l���ŁA���\�҂̃��J���E���[�_���Ɩ��������������ꂻ���ɂȂ�A���J�����瓦���Ă����B�A���B�i�[�V���̓T���W���i�[�������A���̂܂ܔޏ��ƌ������Č̋��ŕ�炵�Ă����B��l�̊Ԃɂ͑��q�����܂ꂽ�B�Ƃ��낪�ނ�̓X�W���[���E�X�B���Ɍ�����A�T���W���i�[�̓��J���ɎE�Q����A���q�͗U������Ă��܂����B�����ŃA���B�i�[�V���͒P�g�R�[���J�[�^�[�֑��q��T���ɂ���ė����̂������B
�@���q�̋~�o�ɏł�A���B�i�[�V���̌��ɁA�X�W���[���E�X�B�����R���^�N�g������Ă���B�X�W���[���E�X�B���������E�������J��������ł���A�܂����J���͑��q�̐g�����v�����Ă����B������X�W���[���E�X�B���̓A���B�i�[�V���ɗ͂����킹�đ��q�����߂����ƒ�Ă��ė����B
�@�g�����p�ӂ����A���B�i�[�V���́A���J�����w�ɌĂъ�B����������̓��J���ƃX�W���[���E�X�B�������d����㩂������B���̓T���W���i�[���E�����̂��X�W���[���E�X�B�����g�������B㩂̒����c�����A���B�i�[�V���̓X�W���[���E�X�B���̓@��ɔE�э���ő��q�����߂��A�܂��X�W���[���E�X�B���̓��J���ɎE�����āA���J�����x�@�ɎE�������B�������ăA���B�i�[�V���͍Ăё��q�Ƌ��ɓc�ɂŕ�炵�n�߂��B�ނ�̌��Ƀu���u���������������ɂ���ė���B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@���҂��Ă������ɂ͈ĊO�債�����Ƃ̂Ȃ���i�ŃK�b�J�������B�Ȃ���l���̒j�̓R�[���J�[�^�[�ɗ����̂��A���ꂪ������Ȃ��O���͊��ƃT�X�y���X�ɖ����Ă��Ĉ����t�����邪�A�v�̓}�t�B�A�ɗU�����ꂽ���q�̋~�o���ł���A��ʓI�ȃC���h�̃A�N�V�����f��̉������s���Ă����B
�@�薼�̒ʂ�A�w���Ԃ��d�v�ȕ���ƂȂ�f��ŁA�C���h�̉w�̗l�q���Ԃ̗l�q�����X�����`����Ă����̂͂悩�����B���ʂ̃C���h�f��͈ĊO��Ԃ̗��Ȃǂ̃V�[�����f���Ȃ����Ƃ������B�ړ�����Ƃ��͑S����s�@�Ńr���[���ƍs���Ă��܂����Ƃ��قƂ�ǂ��B�������C���h�̍����ړ��Ƃ������牽�Ƃ����Ă���Ԃ̗��ł���B�u���[�̃V�[�g�����ԐQ��Ԃ��X�N���[���ɏo�Ă���ƁA�����ɗ��ɏo�����Ȃ�B
�@����܂��薼�ʂ�A�R�[���J�[�^�[�i�J���J�b�^�j����ȕ���ɂȂ��Ă����B�R�[���J�[�^�[�Ƃ����x���K���[��̖{���n�B���̉f��̓q���f�B�[��f��Ȃ���A�x���K���[��������������Ă����B�C���h�f��̂������Ƃ���́A���̌��ꂪ�o�Ă��Ă������Ȃ��ł��̂܂܂��߂����Ă��܂��Ƃ��낾�B�q���f�B�[��ƃx���K���[�ꂭ�炢�������牽�Ƃ������͗����ł��邭�炢�̋��ʐ�������悤�ŁA�ϋq���x���K���[��𗝉����Ĕ������Ă����悤�������B�q���f�B�[�ꌗ�̐l�ɂƂ��ăx���K���[��́A�����قɑ�����ق��炢�̈Ⴂ�Ȃ̂�������Ȃ��B���̕ӂ̊��o�͓��{�l�̖l�ɂ͖����ɂ悭������Ȃ��B���Ȃ݂ɃR�[���J�[�^�[�����̃h�D���K�[�E�v�[�W���[�������Ɖf��̉B�����Ɏg���Ă����B�R�[���J�[�^�[�̎G�����悭�\������Ă����Ǝv���B
�@��l���̃A���B�i�[�V�����R�[���J�[�^�[�Ŕ��܂������h�́A�p�n�[���E�K���W�̈��h�i�������O�E�z�e����u���C�g�E�Q�X�g�n�E�X�Ȃǂ��v���N���������B�l���C���h�ɗ����Ă̍��͂���ȏh�ɔ��܂��Ă����Ȃ��Ɖ��������C���ɂȂ����B����ɂ��Ă��P�����T�O�O���s�[�̏h�����͈����I�����ƃC���h�Ɠ��̗���̂���f�悾�����Ǝv���B
�@�剉�̃A�j���E�J�v�[���͍ŋ߃q�b�g��Ɍb�܂�Ă��Ȃ��B���̉f�������ȂɃq�b�g�͂��Ȃ����낤�B�����������炩�A�j���E�J�v�[���͎q�����̒j���������������Ȃ��Ă����悤�Ɏv����B�����o�D���Ǝv���̂ŁA�����P�A�Q�{���炢��q�b�g��ɏo�����Ă����Ă��炢�����B
�@�}�j�[�V���[�E�R�[�C���[���[�������Ȃ�o�����Ă������A�}�j�E���g�i���ḗu�{���x�C�v�̍����v�킹��悤�Ȑ��^�ȕ��͋C���Y���Ă���A�ߔN�̃}�j�[�V���[�f��̒��ł͈�Ԉ�ۂ��悩�����B����̃��[�j�[�E���J���W�[�͐L�єY��ł��銴���������B�u���u���Ƃ��������œ_����܂��Ă��Ȃ��֊s�̂ڂ������ŁA������Ǝ��s�̂悤�ȋC�������B
�@�i�m�t�̃q���f�B�[��Ȃł́A�E���h�D�[���b�̎��Ƃ��K�C�ƂȂ��Ă���B����Č��ݕ�������E���h�D�[�������Ă���Ƃ��낾�B�����A�q���f�B�[����K�������l�ɂƂ��āA�E���h�D�[����w�ԂƂ������Ƃ́A�S���قȂ����O������w�Ԃ��ƂƂ͑S���ʂȑ̌��ɂȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��͂قƂ�Ǔ������ꂾ���炾�B
�@�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̊W���ꌾ�Ō����\���͓̂���B�܂���ʂ̔F���Ƃ��āA�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��́u��v�̖��̂��Ⴄ�̂�����S���ʂ̌��ꂾ�Ǝv���Ă��邱�Ƃ������B�q���f�B�[��̓C���h�̑����p��ƂȂ��Ă���A�E���h�D�[��̓p�[�L�X�^�[���̌��p��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�����̌��ꂪ�S���ʂ̌���ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ����߂Ă��邵�A������������q���f�B�[��ƃE���h�D�[�ꂪ�قƂ�Ǔ������@�\������������ł��邱�ƂȂǑz�������Ȃ����낤�B
�@�����A���ۂ̂Ƃ���A�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��͂قƂ�Ǔ�������ł���B�q���f�B�[����w�ׂC���h�͓��R�̂��ƁA�p�[�L�X�^�[���֍s���Ă���Ȃ��ӎv�a�ʂ��ł��邵�A�E���h�D�[���m���Ă���p�[�L�X�^�[���l�Ƃ����łȂ��A�C���h�l�Ƃ���b���ł���B�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̕��@�͂قƂ�Ǔ����ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̂��Ƃɂ��Ċw�ԂƁA���x�͂��������l�������悤�ɂȂ�B�q���f�B�[��̓q���h�D�[���k���g������ŁA�E���h�D�[��̓C�X���[�����k���g������ł͂Ȃ����E�E�E�H�m���ɃE���h�D�[��̓C���h�ł��g���Ă���A�Ⴆ�C�X���[�����k�������Z�ރI�[���h�E�f���[�ɍs���ΊX�̊Ŕ̓E���h�D�[�ꂾ�炯�ł���B�������A�C���h�̃C�X���[�����k���S���E���h�D�[����g���Ă��邩�Ƃ�������͊ԈႢ�ŁA�x���K���n���̃��X�����̓x���K���[���b�����A�J���i�[�^�J�B�̃��X�����̓J���i�_���b���B�܂��A�p�[�L�X�^�[���ł��E���h�D�[�����Ƃ���l�͂킸���ŁA�قƂ�ǂ̃p�[�L�X�^�[���l�̓E���h�D�[��Ƃ͕ʂɂ��ꂼ����������Ă���B���̗�������Ă݂悤�B�`�D�q�D���t�}�[���Ƃ����L���ȉ��y�Ƃ�����B�ނ͌��X�q���h�D�[���k�ŁA�����`�D�r�D�h�D���[�v�E�N�}�[���Ƃ��������A�C�X���[�����ɉ��@���A���O���ς����B�ł́A�C�X���[�����k�ɂȂ����r�[���t�}�[���̓E���h�D�[���b���n�߂��̂��낤���H�����͔ہB�ނ̓^�~���l�ł���A���̓^�~����ł���A���Ƃ��C�X���[�����ɉ��@���Ă����̓^�~����̂܂܂ł���B�܂�A����Ə@�������т��čl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����Ə@��������ѕt���悤�Ƃ���̂͐����I�Ӑ}�����邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B����͊��S�ɒn���I�v���ɍ����������̂��B�u�P�Q�}�C���s���ƌ��t���ς��v�Ƃ������͐��藧���Ă��A�@�����ς��ƌ��t���ς��Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B
�@�����A�m���Ƀq���f�B�[��̌�b�ɂ̓T���X�N���g�ꂩ��̎ؗp�ꂪ�����A�E���h�D�[��̌�b�ɂ̓y���V�A���A���r�A�ꂩ��̎ؗp�ꂪ�����Ƃ�������������B���̓������Ăя@���Ɍ��т��āA�T���X�N���g�ꁁ�q���h�D�[���A�y���V�A��A�A���r�A�ꁁ�C�X���[�����Ƃ���̂��ԈႢ���B�T���X�N���g�ꂪ�����������Ƀq���h�D�[���͑��݂��Ȃ��������A�C�X���[���������E���y�ȑO����A���r�A����y���V�A����b����Ă������̂��B�����Ŗ��ƂȂ�̂́A��b�̈Ⴂ������̈Ⴂ�̊�ɂȂ邩�A�Ƃ������Ƃ��B���{��ōl���Ă݂�ƕ�����₷���B���ɂR�̕���p�ӂ����B
�@�@���݂͂�ȂƉ���ĂƂĂ��K���Ȏ����߂�����
�@�A���͏W��ɎQ�����Ĕ��ɍK���Ȏ��Ԃ�����
�@�B���̓p�[�e�B�[�ɃW���C�����ăn�C�ȃt�B�[�����O�ɂȂ邭�炢�G���W���C����
�@�R�Ƃ��Ӗ��͂قƂ�Ǔ��������A�g���Ă����b���Ⴄ�B�@�͂������܂Ƃ��Ƃ��Ȃ�ׂ��g���A�A�͂����钆����R���̊�����ۂ���b���g���A�B�͉p��������ĕ\�������B�ʂ����Ă����͉���ɂȂ�̂��낤���H�@�͓��{��A�A�͒�����A�B�͉p��H����A�S�ē��{��ɕς��Ȃ����낤�B�p��̌�b�ōl���Ă݂Ă������B�p��̌�b�̒��ʼnp��ŗL�̂��̂ƌ�����̂͑S�̂̂Q�O���ɉ߂����A���̓��e����A�M���V�A��A�t�����X��Ȃǂ���̎ؗp�ꂪ�唼���߂Ă���B�������p��͉p��ł���B�܂�A��b�͌��ꂻ�̂��̂ɉe�����y�ڂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̌�b���Ⴄ����ƌ����āA�ʂ̌���ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������q���f�B�[��ƃE���h�D�[��Ō�b���Ⴄ�Ƃ������Ƃ���������B�q���f�B�[��̒��ɂ������̃A���r�A��A�y���V�A��N���̌�b�������Ă���A�t���܂��R��ł���B
�@����A�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̕����̈Ⴂ�́A���o�Ɋւ�邾�������đ傫�ȈႢ���B�q���f�B�[��̓T���X�N���g��̕\�L�Ɏg�p����Ă����f�[���i�[�O���[�����i�f�[���@�i�[�K���[�����Ƃ������j��K�p���ĕ\�L����A�E���h�D�[��̓A���r�A���������ǂ��ĕ\�L����Ă���B�ǂ���̕������\�������ł��邱�ƂƁA�s���S�Ȍ`�̉��ߕ����ł��邱�Ƃ͋��ʂ��Ă��邪�A�����ڂ͑S���Ⴄ���A�����̕\�L�̕������t�ł���B�ł́A�����̈Ⴂ�͌���̈Ⴂ�̍����ƂȂ邩�H��������{���p��ɓ��Ă͂߂Ă݂�ΈĊO����Ȃ�Ɨ����ł���B�Ⴆ�Ή��̂S�̕�������B
�@�@���͍����w�Z�֍s���܂���
�@�Awatashiwa kyou gakkoue ikimashita
�@�B�A�C�@�E�F���g�D�[�@�X�N�[���@�g�D�f�C
�@�CI went to school today
�@�@�ƇB�͓��{��̕����ŏ�����A�A�ƇC�͉p��̃A���t�@�x�b�g�ŏ�����Ă���B����������͇@�ƇB�����{��ł���A�A�ƇC���p��ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��B�����炭��ʂ̐l�Ȃ�A�@�ƇA�����{��ŁA�B�ƇC���p��ł���ƔF�߂邾�낤�B�v����ɁA�����̈Ⴂ�͌���Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ�������B
�@�ł́A�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��͑S����������ł���ƌ����Ă����̂��Ƃ����ƁA�����ł����ЂƂ̖�肪�����͂�����B�����̈Ⴂ�ł���B�E���h�D�[��Ŏg���邢�����̉��ɂ́A�q���f�B�[��b�҂���ʂ����Ă��Ȃ���������B�Ⴆ�u�U�`�W���v�̉��B�E���h�D�[��ɂ͂����Ȏ�ނ́u�U�v�u�W���v�̉�������A�E���h�D�[��̕����ł͂�������ʂ��Ă��邪�A�q���f�B�[��b�҂́u�U�v�Ɓu�W���v�̉��̋�ʂ�����Ȃ���Ԃł���B�܂�œ��{�l���ur�v�Ɓul�v����ʂ��Ă��Ȃ��悤�ɁA�u�U�v�Ɓu�W���v���Ƃ����b���Ƃ�����ʂ��Ă��Ȃ��B����̓C���h�l�ƈꏏ�ɃE���h�D�[��̎��Ƃ��Ă��Ď����������Ƃ��B���{�l�Ȃ班�Ȃ��Ƃ��u�U�v�Ɓu�W���v�̋�ʂ��炢�͂��̂ŁA���̓_�Ŗl�̓E���h�D�[����w�ԍۂɑ��̃C���h�l�ɑ��ėD�ʂɗ����Ă���B�����悤�ɃE���h�D�[��ɂ͕����́u�T�v�̉�������̂����A�n���ɂ���Ă̓q���f�B�[��b�҂́u�T�v�Ɓu�V���v�̋�ʂ���B���ȏ�Ԃł���B���ɂ��u�^�v�A�u�J�v�A�u�n�v�ȂǁA�E���h�D�[��ł͂Q�̉��̕\�L������Ȃ���A�q���f�B�[��ł͑S����ʂ����ɕ\�L�A��������Ă��鉹������B
�@�����������̉��̋�ʂ����d�v���Ǝv�����̂́A�q���f�B�[���b���l�X�����̈Ⴂ�̃R���Z�v�g��S���������Ă��Ȃ����Ƃ��B�O�q�̒ʂ�A�q���f�B�[��ɂ��E���h�D�[��̌�b�i�܂�A���r�A��A�y���V�A��N���̌�b�j������B�����A�u�U�v�u�W���v�u�T�v�u�V���v�u�^�v�u�J�v�u�n�v�Ȃǂ̂��ꂼ��̉��̈Ⴂ�͈ӎ������ɂЂƂ̉��Ƃ��Ĕނ�͎q���̍����炻���̌�b���g�p���Ă����B���ꂪ�ˑR�E���h�D�[��̎��ƂɂȂ��āA�u���̒P��Ɏg���Ă��邱�́w�U�x�̉��ƁA���̒P��Ɏg���Ă��邱�́w�U�x�̉��͕ʂ̉����v�ƌ���ꂽ���Ă����ɂ͗����ł��Ȃ��ē��R�Ȃ̂��낤�B�܂����{��ɋA���čl���Ă݂�ƁA����l�ɂƂ��ĉ��������̈Ⴂ�������ɉe�����Ȃ����Ƃɓ��Ă͂߂Ă݂�Ƃ����̂�������Ȃ��B���㉼�������ł́u���v�Ɓu���v�A�u���v�Ɓu���v�A�u���v�Ɓu�Áv�̑��A����I�Ɂu��v�Ɓu�́v�A�u���v�Ɓu�ցv��\�L���ʂ��邪�A�����ł͋�ʂ��Ă��Ȃ��B�����A�����͂��ċ�ʂ���Ă��������B����ɕ������㍠�̗��j�I���������ł́u���v�u�Ёv�u��v�A�u���v�u�ցv�u��v�ȂǂȂǂ̋�ʂ�����A�ޗǎ���ȑO�̓��{���\�L��������ꉼ�������Ƃ��Ȃ�u���E���E���E���E�ƁE�́E�ЁE�ցE�݁E�߁E��E��E�i���j�v�̂P�Q�`�P�R�̉����Q��ނ��������ƌ����Ă���B�\�L���Ⴆ�A����͔������Ⴄ�A�܂��͂��Ĉ�������Ƃ��Ӗ�����B����Đ̂̓��{�l�͂����̉�����ʂ��Ĕ������Ă����Ƃ������Ƃ��B�������A�����̋�ʂ�������{�l�ɂ����Ȃ�˂����Ă��������邾�����B����Ɠ������ۂ��A�E���h�D�[��̃N���X�ŃC���h�l�̊w���ɋN�����Ă���悤�Ɋώ@�����B�q���f�B�[��b�҂ɂ́A�E���h�D�[��̔����Œ������Ȃ����̂����������݂���B
�@�ł́A�����̈Ⴂ�͌���̈Ⴂ�̍����ƂȂ邾�낤���H�Ⴆ�A�����J�p��A�C�M���X�p��A�I�[�X�g�����A�p��Ȃǂ́A��b�̈Ⴂ�ȏ�ɔ����̈Ⴂ�����������A�����͓����p��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�����������Ƃ������ނ��������ނȂ�A�����̉p��͌��ꃌ�x���ł͂Ȃ��������x���ł̈Ⴂ�������ƂɂȂ�B�������ǂ��܂ł�����ƌ���̋��E���ŁA�ǂ��܂ł������ƕ����̋��E���Ȃ̂����K�肷��͍̂�����A�����ł͂����܂ŋc�_���Ȃ��B�����A�A�����J�p��A�C�M���X�p��A�I�[�X�g�����A�p��Ƃ������ނ��������Ȃ�A�q���f�B�[��ƃE���h�D�[����������x���œ���O���[�v�ɕ��ނ���A�������x���ňႤ�O���[�v�ɕ��ނ���鎑�i�������Ă���Ǝv����B
�@�����A�{���ɃE���h�D�[��b�҂�������ňႢ�̂��鉹�𐳊m�ɔ����ł���̂��͂͂Ȃ͂��������Ǝv���Ă���B���p��Ƃ��ăE���h�D�[����w�K����p�[�L�X�^�[���l�͂����̉��𐳊m�ɕ��������Ĕ������Ă���̂��낤���H�E���h�D�[��̕��������������Ŗ��I�[���h�E�f���[�ݏZ�̃C���h�l�����́A�ʂ����ăE���h�D�[��̐��m�Ȕ��������Ă���̂��낤���H���N�i�E�[�o�g�ŁA�����̕��̓E���h�D�[�ꂾ�Ǝ咣����l�̃E���h�D�[��͂ǂ����낤���H�E���h�D�[��ŋ�ʂ���A�q���f�B�[��ł͋�ʂ���Ă��Ȃ����́A���X�O����̉��ł���B�E���h�D�[��̋��t�⌤���҂Ȃǂ̓���ȐE�ƂɏA���Ă���l�Ȃ�Ƃ������Ƃ��āA����I�ɃE���h�D�[���b���Ă���l�X�̃E���h�D�[��͖{���ɕ����ʂ�̔��������Ă���̂��A���ɋ^��ł���B��͂茾��͒n��ɍ��������̂ł���A�Ƃ���ς��Δ������ς��̂����ʂ��낤�B�����甭���Ńq���f�B�[��ƃE���h�D�[�����ʂ��邱�Ƃɂ��T�d�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@���ǁA�q���f�B�[��ƃE���h�D�[��́A���@�����ʂ��Ă��鑼�́A�����̑���_��������̂́A���@�̋��ʓ_�݂̂ɂ����āA��������ł���ƌ������Ƃ��ł��������B���@����������̈Ⴂ���K�肷��B�Q�̌���Ԃŕ��@��������������A�����͓���̌���ƌ����Ă������낤���A���@���������Ⴄ���ꂾ�ƌ����Ă������낤�B�����A���@�ɂ����낢��Ȏ�ނ�����A�u���@���Ⴄ�v�ŊȒP�ɍς܂�������ł��Ȃ����Ƃ͖��L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��q���f�B�[��ƃE���h�D�[��́A���@�������ł���A��������ł���ƌ����č\��Ȃ����낤�B
| �� |
�X���P�Q���i���j�@�q���f�B�[�ꂪ�����Ȃ��C���h�l |
�� |
�@���͍����͑������e�X�g���ŁA���T���炩�̃e�X�g������B�������ɍςe�X�g������A���ʂ��Ԃ��Ă������̂�����B
�@��T�s��ꂽ�e�X�g�́A���傤�Ǖa�C�ŐQ����ł��������Əd�Ȃ��Ă����B���Ƃ����������ăe�X�g�������A�����ƐQ����ł��ĂقƂ�Ǖ������Ă��Ȃ��������A��̕���p�Ȃ̂��肪�s���s��Ⴢꂽ��Ԃœ��Ă������Ă����̂ŁA�U�X�Ȍ��ʂ�\�z���Ă����B�����N���X�ōʼn��ʂ��낤�A�ƁB���Ȃ݂ɂP���Ԃ̃e�X�g�ŁA�P�̃e�[�}�ɂ��ăq���f�B�[��ŕ��͂������`���̃e�X�g�������B�������Ԃ��Ă�����]���͂`�A�a�A�b�X�i�K�]���i���ꂼ��v���X�A�I�����[�A�}�C�i�X������j�̂����̂a�I�����[�ŁA���傤�ǐ^�������B�����N���X�̃A�����J�l�����]���������̂ŁA�������ɂ��̂��炢�Ȃ��o�����A�ƈ��S�����B
�@���̃e�X�g���s���������͓��e�ȏ�ɕ��@��Â�Ɍ������l�ŁA�u�Ⴆ�C���h�l�ł����Ă��O���l�ł����Ă��A�q���f�B�[��C�m�ɂ���҂��������q���f�B�[��������Ȃ��悤�ł́A�C�m�Ŋw�Ԏ��i�͂Ȃ��v�Ǝ��B���Ă����B������l���������q���f�B�[��̊ԈႢ�𐔉ӏ��ׂ����w�E����Ă����B
�@��͂蓯���N���X�̃C���h�l����ԋC�ɂȂ�̂́A�l�����O���l���ǂ̒��x�̕]��������������A��������Ȃ̂����Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ炵���A���i�͂��܂�b�������Ƃ̂Ȃ��l�܂ł��l�̂Ƃ���ւ���ė��ĕ]�����Ă����B�������ɂ`�̕]������������C���h�l�w��������A�O���l���������]�������炦�Ĉ���S���Ă���l���������A�C���h�l�̕Ȃɂb�}�C�i�X����������l�����āA���Ȃ藎������ł����B�ǂ����b�]�������炤�C���h�l�́A���e�]�X�����q���f�B�[�ꂪ����ۂǏ����Ă��Ȃ��悤���B
�@�Ƃ���ŃC���h�̊w�Z�ɂ́A�p��Ŏ��Ƃ�������Ƃ���ƁA�q���f�B�[��Ȃǂ̌��n��Ŏ��Ƃ�������Ƃ��낪����A��w�ł����̋�ʂ�����B�l�̗F�l�i���{�l�j���f���[��w�w�m��ʋ��{�ߒ��́A�q���f�B�[��Ŏ��Ƃ��s����R�[�X�ɒʂ��Ă��邪�A���̐l�̏،��ɂ��ƁA����ς�q���f�B�[�ꂪ�S�R�����Ă��Ȃ��C���h�l�w����������������炵���B���̐l�̕�������ۂǐ��m�ȃq���f�B�[�ꂪ������悤���B�C���h�l�������Ƀq���f�B�[�ꂪ������悤�ɂȂ�����A����͂���łȂ��������C���ɂȂ邾�낤�B
�@�C���h�ɂ͂����Ȍ��ꂪ����A�q���f�B�[�ꌗ�ȊO���痈�Ă���w�����q���f�B�[�ꂪ�ł��Ȃ��͔̂[���ł���B�������q���f�B�[�ꌗ�ɂ��Ȃ���q���f�B�[��𐳂����������Ƃ��ł��Ȃ��l�Ƃ����̂����݂��A���������ɋꂵ�ށB
�@�Ⴆ�Ώ㗬�K���̂��q�l�Ȃ�A�ƒ�ł����ʂɉp����g���Ă���A�q���f�B�[�ꂪ�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��\�����肤��B�u�q���f�B�[�ꂪ�ł��Ȃ��v���Ƃ��t�ɃX�e�[�^�X�̍����������Ƃ����A���Ώ��b�ɋ߂���ԂɂȂ��Ă���̂��A���݂̃C���h�̓s�s���̌���ł���B
�@����������͂���Ƃ͂܂��b���ʂ̂悤���B�Ȃ��Ȃ�q���f�B�[��Ŏ��Ƃ��s�����w��A�q���f�B�[��ȂȂǂɓ��w����w���́A�\������㗬�K���̎q���ł͂Ȃ����炾�B�������̎q���͉p��Ŏ��Ƃ��s����w�Z�A��w�֍s���A�����Ǝ��p�I�Ȋw����w�сA�ʂĂ̓A�����J��C�M���X�ɗ��w���Ă��܂��P�[�X���قƂ�ǂł���B�q���f�B�[��ƊW�̂���w�Z�ɍݐЂ��Ă��鐶�k�́A�h�c�ɂ��痈���l��A�����K���ȉ��̐l�I�����[�ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ����낤�B����ł��q���f�B�[�ꂪ�����Ȃ��̂��B����A���̏ꍇ���A����䂦�q���f�B�[�ꂪ�����Ȃ��Ə����ׂ����B
�@�Ȃ��q���f�B�[����������Ƃ��ł��Ȃ��C���h�l������̂��B����ɂ͂܂��q���f�B�[��Ƃ�������̈Õ����W���Ă���ƍl������B���݁u�q���f�B�[��v�ƌĂ�Ă��錾��́A��ʓI�����ł͖k�C���h�̊e�B�Řb����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���B���������ےn���n���ł��Ȃ�̕�����������A�������q���f�B�[��̕����Ƃ͂����ɁA�ʂ̌���Ƃ��ׂ����Ƃ���l��������قǂ��B���͑O��̓��L�ŏ������q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̈Ⴂ�����A�q���f�B�[������̊e�����̑���̕��������ƕ��G�ŏd�v�Ȗ�肾�Ƃ�������B�����̌����S�ĂЂ�����߂Ė�����ЂƂ́u�q���f�B�[��v�Ƃ��Ă��܂����̂ɂ́A���R�̂��ƂȂ��琭���I�ȗ��R�����݂���B
�@�����A�����n���̃q���f�B�[���ʂ̌���Ƃ���Ȃ�A���ݖl�̃N���X���C�g�ɂȂ��Ă���C���h�l�����͊F�q���f�B�[��̃l�C�e�B�u�E�X�s�[�J�[�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�F�A�r�n�[���B��[�W���X�^�[���B�́A�d�C�����Ă��邩���Ă��Ȃ���������Ȃ��悤�ȕГc�ɂ������ė����l���肾���炾�B�ނ�̘b�����t�������a���Ă���A�������Â炢���Ƃ����X����B����ȏ�Ԃ�����A�W���q���f�B�[����������Ƃ͔ނ�ɂƂ��Ď��͂���������V�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B�����A�܂���Ȃ�ɂ��q���f�B�[��ȂɍݐЂ��Ă���̂�����A���m�ȃq���f�B�[���b���A�������Ƃ͍Œ�������낤�B
�@�܂��A�������q���f�B�[�ꂪ�����Ȃ��Ƃ����̂́A�����P�Ɏ������̖��ɘA�Ȃ��Ă�����Ȃ̂�������Ȃ��B�܂��܂�����ǂ菑�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�̓C���h�ɂ͂��܂�Ƃ���B����̎��̖��Ƃ��ւ�肪����̂�������Ȃ��B������������Ƃ����āA��͂��w���炢�̍�������@�ւɗ���l���A�q���f�B�[��������Ȃ��悤�ł͂����Ȃ����낤�B
�@�O�q�̒ʂ�A���݃C���h�ł͓s�s���𒆐S�ɁA���ł���q���f�B�[��Ȃǂ̒n���ꂪ�̂�ɂ���A�O����ł���p�ꂪ���Ă͂₳���X�����ǂ�ǂ�������Ă���B����ŁA�ێ�I�Ȑl�X����̓q���f�B�[���ی삷�铮���������ɂȂ��Ă���B�q���f�B�[��Ȃɂ���悤�Ȑl�X�́A��͂�q���f�B�[��ی�̗���ɗ����Ă���l�������B�m���ɂ��낢��ȗ��R����q���f�B�[����������Ƃ��ł��Ȃ��C���h�l���������錻�������ƁA�p��ɑ���C���h�l�̎p�͊��m���댯�Ȗ����̂悤�ɂ��v����B�������l�Ԃ͑��Ɍo�ϓI���R�Ŋ������邱�Ƃ������B�C���h�l���p��D���`�ɑ���̂́A�ʂɃq���f�B�[���̂�ɂ������킯�ł��Ȃ��A�p��𐒔q���Ă���킯�ł��Ȃ��A�����P�ɉp���m���Ă�������E�ɂ��Ă���������������\���������Ƃ����P���Ȑ��m�h�����R�ɂ����̂��Ǝv���B���K��������ɂ̓y���V�A�ꂪ���݂̉p��Ɠ����n�ʂɂ������킯�����A�����Ƒk��A�T���X�N���g�ꂾ���ăC���h�l�ɂƂ��Ă͊O���ꂾ�����킯���B���݂̃C���h�̌���́A�����������R�Ȃ��̂̂悤�Ɏv����B������l�͕ʂɃq���f�B�[�ꏧ��̗���ł��Ȃ��A�q���f�B�[��r�˂̗���ł��Ȃ��A�����T�ς��Ă��邾�����B
�@���������Γ��{�ł����������{�ꂪ�����Ȃ���w���E�Љ�l�Ƃ��A������肪���邩��A�C���h�̂��̌��������I�ɔᔻ���邱�Ƃ͋؈Ⴂ��������Ȃ��B���ł��l�Ȃ͕��͂������̏�ɂ��炵�Ă���̂ŁA�q���f�B�[�ꂪ�����Ȃ��C���h�l�w���ᔻ�̂��̕��͂ɓ��{��̊ԈႢ����������A���ꂱ���p���炵���ȁE�E�E�B
�@�C���h�ōL���ǂ܂�Ă���G���Ɂu�C���f�B�A�E�g�D�f�C�v������B�p��ŁA�q���f�B�[��ŗ������o�ł���Ă���A�����K���`�㗬�K�����炢�̃C���h�l���悭�ǂ�ł���G�����B�l�͕ʂɖ��T�w�ǂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���T���i�X���P�T�����j�͂��������Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ���W���uThe Sex Report�v���������炾�B�p���p���ƓǂƂ���A�����Ă��邱�Ƃɔ��ɋ^����������̂œ��ɋC�ɂ��Ă��Ȃ������̂����A��͂�J�Ŋ��Ƙb��ɂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�����ł����グ�邱�Ƃɂ����B���e�����e�Ȃ����ɁA������Ɛ��l�����̋L���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����e�͊肢�����B
�@����̂��̃Z�b�N�X�E���|�[�g�́A�C���h�l�̏����̐��Ɋւ���ӎ��𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ������̂ŁA�C���h�ʼnߋ��ő�K�͂̒������s��ꂽ�Ə�����Ă����B�C���h�̎�v�P�O�s�s�ɏZ�ނP�X�`�T�O�܂ł̒����K���`�㗬�K���̓Ɛg�^�����^�����^�ʋ��������Q�R�O�T�l�ɃC���^�r���[���s��ꂽ�������B�قڑS�Ă̕ԓ��҂̓J���[�s�u�����L���A�T���̂S���Ƃ������A�P�T�����g�ѓd�b�������A�Q�T���������Ԃ������Ă���A�Ƃ�������Ă����B
�@���̎��_�ŁA���Ɂu�C���h�l�����v�Ƃ������t�͎g���Ȃ����낤�B�悭������i���Ɂu�C���h�ɕ��ς͂Ȃ��v�u�C���h�ŕ��ς��o���ȁv�Ƃ������̂�����B�C���h�͂��܂�ɏ㉺�̊i�����傫�����߁A���ς��o���Ă����̖��ɂ������Ȃ��������Z�o����邾�����B���̒����ł͓s�s���ɏZ�ޒ����`�㗬�K���̏����Ɍ��肳��Ă���B���肵���̂͐������Ǝv���B�C���^�r���[����̑��������肷�����قǂ��̃f�[�^�͐��m�x���������炾�B���������̒������C���h�l�����̐��ɑ���l�����\���Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B
�@�C���f�B�A�E�g�D�f�C�ɍڂ��Ă����f�[�^�[����A�����[�����̂��������f�ڂ��ăR�����g�����Ă݂��B
�Z�b�N�X�͂��Ȃ��̐l����
�ǂꂾ���d�v�ł����H |
| �d�v |
�S�R |
| ���ɏd�v |
�Q�R |
| �W�Ȃ� |
�Q�T |
| �d�v�ł͂Ȃ� |
�X |
���Ȃ��͎����̂f�X�|�b�g��
�ǂ��ɂ��邩�m���Ă��܂����H |
| �͂� |
�S�Q |
| ������ |
�Q�X |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�Q�X |
�@�l���̒��ŃZ�b�N�X�ɏd����u���Ă��鏗�����S�̂̂U�U�����߂��B�܂����̂��炢�Ȃ̂��낤�B����ɂ��Ă������Ȃ�f�X�|�b�g�ƌ����ē�������C���h�l����������̂��낤���H���{�l�ł������Ǝv���̂����B
���Ȃ��̍D���ȑO�Y��
���ł����H |
| �L�X |
�T�T |
| �}�b�T�[�W |
�P�U |
| �g�̂����� |
�P�S |
| ����E������ |
�P�P |
| �|���m�f������� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�Q�V |
���Ȃ��͎��̂ǂ��
���������Ƃ�����܂����H |
| �I�[�����E�Z�b�N�X |
�Q�V |
| �A�i���E�Z�b�N�X |
�P�R |
| ������ |
�P�U |
| ���� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�S�P |
�@���̃f�[�^�[�̓C���h�f����ۂ����}���`�b�N�ȏ�i�������Ԃ��A�E�̃f�[�^�[�͉₩�ɐM���������B�I�[�����E�Z�b�N�X������C���h�l�́A�}�j�v���[�Ȃǂ̃m�[�X�E�C�[�X�g�̕��̐l���������炠�܂肢�Ȃ��Ƃ����C���[�W������B���������ǂ�Ȑl�ɃA���P�[�g��������̂��낤�H
�������Ȃ��̗F�l�����Ȃ���
�|���m�f���n������ǂ����܂����H |
| �����ɕԂ� |
�R�V |
| �p�[�g�i�[�ƈꏏ�Ɍ��� |
�Q�W |
| �Q���ň�l�Ō��� |
�P�P |
| ���̗F�l�ƌ��� |
�W |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�U |
�Z�b�N�X���̂��Ȃ����g�̉�����
�ǂꂾ���d�v�ł����H |
| �p�[�g�i�[�Ɠ������炢�d�v |
�T�Q |
| �p�[�g�i�[���͏d�v�ł͂Ȃ� |
�P�O |
| �p�[�g�i�[�����d�v |
�X |
| �d�v�ł͂Ȃ� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�Q�R |
�@���̎���͂ȂςȎ��₾�B���������V�`���G�[�V�������C���h�ł��肦��̂��낤���H
�������Ȃ��̃p�[�g�i�[��
�I�[�����E�Z�b�N�X��
���ۂ�����ǂ����܂����H |
���ꂪ�����ɂƂ���
�d�v�ł���ƒm�点�� |
�P�W |
| �I�[�����E�Z�b�N�X������̂���߂� |
�P�U |
| �������点�� |
�P�P |
| �ނƂ̃Z�b�N�X�����ۂ��� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�S�X |
�ǂꂮ�炢�̕p�x��
�Z�b�N�X�����܂����H |
| �T�ɂP��ȏ� |
�Q�X |
| �Q�T�ԂɂP��`�Q�����ɂP�� |
�Q�X |
| �P�T�ԂɂP�� |
�Q�R |
| ���Ȃ� |
�P�P |
| ���� |
�W |
�@���̍��̎�����ςȎ��₾�B�C���h�l��������������I�[�����E�Z�b�N�X�����悤�Ƃ���V�`���G�[�V�������z���ł��Ȃ��B�p�x�̕��́A���ނ���܂������Ă��܂�Q�l�ɂȂ�Ȃ��悤�ȋC������B
���Ȃ��̓}�X�^�[�x�[�V������
���܂����H |
| ���Ȃ� |
�V�T |
| ���� |
�X |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�U |
���Ȃ��͕��C���������Ƃ�
����܂����H |
| ������ |
�W�P |
| �͂� |
�V |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�Q |
�@�N���V���i�ƃ��[�_�[�̊����ғ��m�̗���������������Ă��邾�������āA�C���h�ł͕��C���ӊO�Ƒ����ƕ����Ă����̂����A���̃f�[�^�[���������ł͏��Ȃ��ƌ����Ă����̂��낤���H����A�V���Ƃ��������͑����̂��H
| ���Ȃ��̍D���ȑ̈ʂ͉��ł����H |
| �j����� |
�T�R |
| ������� |
�P�O |
| ���� |
�V |
| ���� |
�R |
| �o�b�N |
�Q |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�Q�T |
���Ȃ��̃p�[�g�i�[�����C��������
���Ȃ��͂ǂ����܂����H |
| �b�������ĉ������� |
�U�V |
�ނɎ������������Ƃ�����
����������Ɠ`���� |
�W |
| �W���I��点�� |
�U |
| �����A�Y��A����ɖ߂� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�R |
�@�C���h�l�͉�����肪�N�������Ƃ��ɁA�Ȃ�ׂ������ғ��m�Řb�������ĉ�������Ƃ����K��������I�ɂ�������B���ꂪ�x���z���āA�{���ɓ����ғ��m�����ŏ���ɘb�������Ď���i�߂Ă�������������B
| �Z�b�N�X�ɂ��ĒN�Ƒ��k���܂����H |
| ���F�B |
�T�Q |
| �N�Ƃ����k���Ȃ� |
�Q�X |
| �e�ʁ^���e�^�Z��o�� |
�P�O |
| �j�F�B |
�T |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�Q |
�j���̂ǂ̕�����
���I���͂������܂����H |
| ���� |
�S�Q |
| �y�j�X |
�Q�W |
| �ؓ����ȑ� |
�P�Q |
| �K |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�Q |
�@���ɏo���I��͂�C���h�l�̏����̑����͒j���̋��тɐ��I���͂������Ă���悤���B���ł��Ȃ����тɒj�̐F�C��������l���S�Q��������Ƃ�����A����͓��{�Ɣ�ׂĂ��Ȃ荂���������ƌ����Ă������낤�B���Ăł͓��R��������Ȃ����E�E�E�B�����C���h�ł͖ѐ[���قǂ��Ă�Ƃ������ƂȂ̂��낤���E�E�E�B���т̔Z�������̏����́A���тɐ��I�~�]��������悤�ɂł��Ă���̂�������Ȃ��B�_�l�͂��܂��l�Ԃ���肽���������̂��B
| �����̌������܂������H |
| ������ |
�W�T |
| ��w���� |
�V |
| ����� |
�T |
| ���Z����ȉ� |
�R |
| ���̂Ƃ��ɏ��̌������܂������H |
| �P�W�`�Q�P�� |
�R�Q |
| �Q�P�`�Q�R�� |
�Q�W |
| �Q�R�`�Q�V�� |
�P�X |
| �P�W�Έȉ� |
�W |
| �Q�V�Έȏ� |
�U |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�V |
�@�s�s���̏����ւ̃A���P�[�g�Ƃ̂��Ƃ����A�������̃f�[�^�[���M�p�ɒl����Ȃ�A������s��ɏZ��ł��Ă��C���h�l�̏����͈ӊO�ɕێ�I�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����ƌ����邾�낤�B���O��������C���h�l�͖����ɂ����������Ȃ��̂��낤���H�f��uDil Se�v�ɂ����O���ɂ��Ęb���V�[�����������ȁE�E�E�B���Ȃ݂ɏ��̌��̕��ϔN��͂Q�Q�炵���B
���������ł��Ȃ��̓Z�b�N�X��
�O���Ă��܂����H |
| ������ |
�V�S |
| �͂� |
�W |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�P�W |
���Ȃ��͈����Ă��Ȃ��l��
�Z�b�N�X���ł��܂����H |
| ������ |
�U�S |
| �͂� |
�P�T |
| �m��Ȃ��^�����Ȃ� |
�Q�P |
�@���̂�����͒�ԂȎ��₩�����ȓ�����������Ȃ��B
�@�S�̓I�Ɍ��āA�����C���h�l�����͂��Ȃ肢���q�Ԃ��ĕԓ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����߂�������B�����A���ꂪ���ۂ̂Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��B�������̗�����Ă��A�قƂ�ǂ̃C���h�l�����͂Q�P���I�̌���ɂ����āA�܂��������������Ă��Ȃ�����������Ǝv���B����ʼnߌ��ȕԓ�������킯�ŁA����ς�Ȃ����ς��o�����ƂɈӖ����Ȃ��悤�Ɋ�����B
�@�l�I�ɁA�R���h�[���Ɋւ��ẴA���P�[�g��m�肽�������̂����A�c�O�Ȃ���R���h�[���Ɋւ��Ă͑S���G����Ă��Ȃ������B�C���h�Ŕ�D���Ă���J�b�v���͐�]�I�ȂقǏ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���Ɨ\�z�����B�Ƃ�����荥�O�������Ȃ�������Ȃ��̂��낤���E�E�E�H
�@��͂�A���P�[�g�����̂ɂ͔��ɋ�J���������悤�ŁA�C���^�r���A�[���Z�b�N�X�Ɋւ��ẴC���^�r���[���n�߂������ŁA�ԓ��҂͓{��o������A�s�R�ȖڂŌ�����A����������ƁA�l�K�e�B�u�Ȕ���������l�����Ȃ肢���悤���B�悭�Q�R�O�O�l���������邱�Ƃ��ł����Ɗ��S����B�C���h�ł͂܂��܂������������ʂ̒����͐l�X����S�ʓI�ȋ��͂������Ȃ����낤�B�����Ă⑺�ɍs���đ��̏����ɂ���Ȃ��Ƃ����₵����A�C���^�r���A�[�͐����ċA���ė���Ȃ���������Ȃ��B���ȋ��낵��B
�@����ɂ��Ă��C���h�l�̐��Ɋւ��Ă͓䂾�炯�ł���B�����̐l��������𖾂��悤�Ɠw�͂��Ă���i�H�j���A�����ɑS�e�͉𖾂���Ă��Ȃ��B�����A�L���ȁu�J�[�}�X�[�g���v��A�J�W�����[�z�[�̎��@�Q�Ɍ�����^���g���Y���ȂǁA���Ƃ��Ɛ��Ɋւ��Ă͂Ȃ�������Ȃ����i��ł���悤�ȃC���[�W�̃C���h���A���ۂ̂Ƃ���͐��E�ł���ʂɐH�����ނ��炢�ێ�I�ȍ����ƌ����Ă������낤�B�����{���ɂ��������ێ�I�Ȏv�l���c���Ă���Ƃ�����A�l�̓C���h�l�ɐ�����ێ����Ă����Ă��炢�����Ǝv���Ă���B���܂艢�Ă̓ŁX���������ɉe������Ȃ��悤�ɁE�E�E�B
| �� |
�X���P�S���i���j�@�����o�C�[�s�u�b�l�B�e���s�L |
�� |
�@�W�����{���炢����A�f���[�̓��{�l�Љ�ɉ����ь����Ă����B�����̎B�e�̂��߂ɓ��{�l���K�v�ŁA�K���Ȑl��T���Ă���A�ƁB������ɂ��ƃ{���E�b�h�f��̂��Ȃ�d�v�Ȗ��ɓ��{�l���K�v�Ƃ����b�ŁA�܂��ʂ̏��ɂ��Ɠ��n��Ƃ̃e���r�b�l�ɏo��������{�l��T���Ă���Ƃ����b�ŁA�S����������Ă����B�����o�C�[�ɏZ��ł���ƁA���X���{�l�ɉf��o���̘b���������ނ��Ƃ�����炵�����A�f���[�ł�����Ȃɕp�ɂł͂Ȃ����A�����������Ƃ͂���B�ȑO�C���h�̃e���r�b�l�ɏo���������f���[�ݏZ�̓��{�l�j����m���Ă��邵�A���̃��W�j�[�J�[���g�̉f��ɏo����������܂����f���[�ݏZ�̓��{�l�����Ƃ���������Ƃ�����B
�@�l�I�ɋ������������̂ŒT������Ă݂��Ƃ���A���ǂǂ����ʁX�̃v���_�N�V����������R�����ɁA�{���E�b�h�f��o���̘b�ƁA�e���r�b�l�o���̘b���i�s���Ă���悤�������B�܂��͂�͂�{���E�b�h�f��̕��ɋ������������̂ŁA�R���^�N�g���Ă݂邱�Ƃɂ����B���{�l���K�v�ȃ{���E�b�h�f��ƕ����Đ^����Ƀs���Ɨ����̂��A�V���[���E�x�l�K���ē����ݐ��쒆�Ƃ����X�o�[�V���E�`�����h���E�{�[�X�̓`�L�f��uNetaji
- The Last Hero�v�ł���B�{�[�X�̐l���Ɠ��{�̊Ԃɂ͖��ڂȊW������A���ɓ��{�R�ƃ{�[�X������C���h�����R�̋������ł���C���p�[�����͂��܂�ɂ��L�����B������l�̃{�[�X�A�V�h�������ɓ��{�ŏ��߂ăJ���[���Љ�����[�X�E�r�n�[���[�E�{�[�X�̓o������҂����i�Q�l�̃{�[�X�͌����W�ł͂Ȃ����A�Q�l�͓��{�ŏo��������Ƃ�����j�B�C���p�[�����ŋʍӂ�����{�R�̓��̖��ł����ł���������A�x�l�K���ē̉f��ɏo�Ă݂����Ǝv�����B����������͏������Ƃ��肾�����悤�ŁA�A����̐l���ɓd�b�����ĕ����Ă݂��Ƃ���A�ǂ��������̒�\�Z�Y���f�悩�T�X�y���X�f��ɏo��������{�l���������B�Ȃ���Ȃ��E���������ۂ��B���̂Ƃ��������Ƀf���[�ŎB�e�����Ă���Ƃ̂��Ƃ������B�������ǂ������̓d�b�ɏo���j�̘b�������}�t�B�A���ۂ��āA�l���u���{�l��T���Ă���ĕ������̂ł����ǁA�l���菕���ł��܂����v�ƌ������Ƃ���A�����Ȃ�u������K�v���H�v�Ɨ���ꂽ�̂ň����Ă��܂����B�܂�Łu�o���܂P�������肽�����v�u������K�v���H�v�Ƃ����悤�Ȗ����o������̉�b�����Ă���悤�������B�C���h�f��E�ƃ}�t�B�A�E�ɖ��ڂȂȂ��肪����̂͌��R�̔閧�ƂȂ��Ă���B���̒j�̘b�������������ŁA������Ƃ��̘b�͊댯�Ȃ����肪���邩��p�X���Ă������Ǝv�����B���Ȃ݂Ɂu������K�v���v�ƕ�����āu������ł������v�Ɠ������Ƃ���A�u�P���U�O�O���s�[�łǂ����v�ƌ���ꂽ�B�B�e�͂T���Ԃ���Ƃ������獇�v�R�O�O�O���s�[�̃M�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����ЂƂ̃e���r�o���̘b�̕��́A���������炱����ɃA�v���[�`���������B�����o�C�[����X�J�E�g�}�����f���[�ɗ��Ă���A�i�m�t�𒆐S�ɓ��{�l�̎�҂�T���Ă������炾�B�ڍׂ��ƁA������n��Ƃ̃e���r�b�l�̂��߂ɁA�}�j�v���[�⒆���l�Ȃǂł͂Ȃ��A�����̓��{�l�i�j�Q�l�A���P�l�j��T���Ă���A�B�e�̓n�C�_���[�o�[�h�̃��[���[�W�[�E�t�B�����E�V�e�B�[���A�����o�C�[�̃t�B�����E�V�e�B�[�ōs����炵���B��������s�@��A�z�e����A���H��S�Č����������B��������V�͓��{�̃A���o�C�g�̃��x���ōl���Ă����z�Ȓl�i�B����Ȃ��������b�����x����������A�C���h��������߂�Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������炢�������B�������N�ł������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ʐ^�R�����������B�f���[�ݏZ�̓��{�l���l�̎ʐ^������ꂽ�B�l���ꉞ�ʐ^���d���[���ő����Ă݂��Ƃ���A�Ȃ�ƈꔭ�łn�j���o���B���R�́u�u���[�X�E���[�Ɏ��Ă��邩��v�������炵���B�u���[�X�E���[���č��`�l�Ȃ��ǁE�E�E�B����ɂ��Ă��l�͂悭�C���h�Łu�u���[�X�E���[�Ɏ��Ă���v�ƌ�����B�Ƃɂ����l�̓u���[�X�E���[�̈Ќ��̂������Ńe���r�b�l�o�������܂��Ă��܂����B
�@�������ꂩ�炪���ɒ��������B�����͎��Ƃ����邽�߁A�T���ɎB�e�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����̂����A�����������x�����x���X�P�W���[����ύX���Ă���̂ŁA���T���T���̎B�e�̓����ɐU����i�D�ɂȂ����B�u���x�̏T���ɎB�e���v�ƘA��������A���̂���ő҂��Ă���ƁA���O�ɂȂ��ĉ��炩�̗��R�łP�T�Ԍ�ɉ����ɂȂ�A���ꂪ�܂��P�T�Ԍ�ɉ����ɂȂ�E�E�E�Ƃ��������������B���̓��u�ǂ������T�̎B�e���������낤�v�ƍl����悤�ɂȂ����͎̂��R�̐���s���ł���B��������X�T�ɁA�l�̑��ɍ̗p���ꂽ���{�l�����Ƀn�C�_���[�o�[�h�֍s���ĎB�e���s�����Ƃ̘b�������߁A�B�e�̘b�͂ǂ����{���ŁA�������҂��邱�Ƃ��ł��A��V�������Ƃ��炦�邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����Đ��ɍ��T���A�l�������o�C�[�֍s�����Ƃ��{���Ɍ��肵���B�y�j���̗[���Ƀf���[���o�āA���j���ɎB�e�����A���j���̖�Ƀf���[�ɋA���Ă�������������B
�@�P�R���̓y�j���̒��A�w�����ꂽ�ʂ�C���f�B���[�E�K�[���f�B�[��������`�̃W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�i�C���h�̍��������̎��c�q���Ёj�̃I�t�B�X�֍s���Ă݂��B����ꂽ�ԍ����J�E���^�[�ɒ��Ă݂�ƁA�{���Ƀ`�P�b�g�����s���ꂽ�B�������悭���Ă݂�Ƃ��̃`�P�b�g�̓����o�C�[����f���[�֍s����s�@���\��Ă���A���������O���Ԉ���Ă����B�Ȃイ���������ȃA�����W���I���̏�Ńf���[���烀���o�C�[�֍s���ւɕύX���Ă��炢�A���O�̌����`���Ă������̂Ŏ��Ȃ������A���Ȃ�s����������̂͌����܂ł��Ȃ��B�������Ƃɂ��������o�C�[�s���̍q�͎�ɓ������B���悢��e���r�b�l�o���������̂��̂ƂȂ����������������B���Ȃ݂ɃC���h�̍������̔�s�@�͊����ŁA�f���[�`�����o�C�[�Ԃ͂W�R�S�T���s�[�i��Q���T��~�j������B
�@�[���W�����̃t���C�g���������߁A���������ĂV�����ɍĂы�`��K�ꂽ�B�W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�𗘗p����̂͏��߂ĂȂ̂Ń��N���N����B�������Ɏ��c�̉�ЂȂ��������āA�葱���̓e�L�p�L���Ă���B���ς�炸�̌��d�ȉו���������蔲���Ĕ�s�@�ɏ�荞�ށB��s�@�͎��Ԓʂ�ɏo�������B���U�l�����̔�r�I�����Ȕ�s�@���������A�@���H�̓I�[�x���C�E�z�e�������Ă��邾�������Ă��Ȃ�����B�W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�͂����q���Ђ��Ǝv�����B�P���Ԕ��قǂŃ����o�C�[�̃`���g���p�e�B�E�V���@�[�W�[��`�֓��������B
�@�G�R�m�~�[�E�N���X���������̂́A�W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�������������K���������߁A��`�ɒ������Ƃ��ɂ͊��ɃX�^�[�C���ɂȂ��Ă����B������������x���c���҂��Ă��邩�A�Œ�ł����h��̃A���o�T�_�[�i���{�̗v�l�p�j���҂��Ă��邾�낤�A����Ȗϑz�̒��ɂ悬�点�Ȃ����`���o��ƁA�f���[�ʼn�����X�J�E�g�}���̃T���W���C���l���}���ɗ��Ă���Ă����B�������l��҂��Ă�����蕨�́A�Ȃ�Ɣޏ��L�̃X�N�[�^�[�B�K�N�b�I�Ȃ��b������Ă������A�Ɠ��S�v�����ނ̃X�N�[�^�[�̌��ɂ܂������č���h������z�e�����������B�����o�C�[�̋C��̓f���[�Ƃ���Ȃɕς��Ȃ������B
�@�T���W���C����̃��b�Z�[�W�ɂ��ƁA�u�N�̂��߂ɂ����z�e����\���v�Ƃ̂��Ƃ������B�u�����z�e���v�ƌ����Ε��ʂɑz������̂͂T���z�e���B����A���̍ۂR���A�S���z�e���ł�����͌����܂��A�Ǝv���Ă����B�T���W���C�̃X�N�[�^�[�͋�`�߂��̊X�𑖂蔲���Ă����B��͂��`�̋ߕӂɂ���͍̂����z�e�����������A����͑f�ʂ�B����z�e���X�̂悤�ȏꏊ�ɂȂ��Ă��āA�����z�e��������������ł������A������f�ʂ�B���ǒH�蒅�����̂́A�z�e���X�̃z�e���̒��ł���Ԉ������Ȃ�����܂�Ƃ����z�e���������B���O�̓V�����O�����B���O�����͗��h���B�T���W���C�̘b�ɂ��ƁA���̕ӂ�ɊO���l�𔑂߂Ă����Ƃ��낪���܂�Ȃ������炵���B�T���Ȃ�m���ɔ��߂Ă���邾�낤�ƐS�̒��Ŕ��_���A���������Ă݂�ƈꉞ�z�b�g�E�V�����[�ƃe���r�Ƃ`�b�t���B�����l�̊ӎ���ɂ��ƁA�P���T�O�O���s�[�͉z���Ȃ����낤�Ɨ\�z����邭�炢�̃��x���̕����������B�����A�����o�C�[�̓z�e���オ���̃C���h�̊X�ɔ�ׂĈ��|�I�ɍ����̂ŁA����ȃz�e���ł������������邩������Ȃ��B����ɂ��Ă����ꂪ�C���h�l�̌����u�����z�e���v�Ȃ̂��E�E�E�B�ނ̐������x�����߂������Ȓm��Ă��܂��B
�@�T���W���C�͑����u�o�[�Ɉ�t���݂ɍs�����v�Ɩl��U�����B�o�[�Ƃ����ƃf���[�ł͊��ƍ����Ȉ��H�X�ɕ��ނ���A�f�B�X�R�ƈ�̂ɂȂ��Ă���o�[������B�l�͂܂��܂��߂��Ă��Ȃ������̂ŁA�u�{���E�b�h�E�X�^�[�ɉ�邩�ȁv�Ɣނɖڂ��P�����Ęb���Ă����B�Ƃ��낪�������Ƃ���͏ꖖ�̎���̂悤�ȏꏊ�B�P���̎d�����I������Y�ǂ����Ђ��߂������ċC�����悳�����Ɏ�������ł����B�܂�����ȂƂ���Ƀ{���E�b�h�E�X�^�[�͖K��Ȃ����낤�B�f���[�ł̓��X�g�����ŃA���R�[�����o���̂ɍ��z�Ȑŋ����K�v�Ȃ̂ŁA�������߂郌�X�g�����Ƃ����Ƃǂ����Ă��������X�g�����ɂȂ��Ă��܂��̂����A�ǂ��������o�C�[�ł͕��ʂ̈��H���ł������o�����Ƃ��ł��邭�炢�K�����ɂ��悤���B�����悤�Ȉ����ۂ��o�[���z�e���X�ɂ���������ł����B�������ނ���������悤�ɁA���̃o�[�̃`�����i���͔��ɂ������������B���̖�̓I�[���h�E�����N������ő��X�ɐQ���B
�@���j���̎B�e�͒��̂P�Q������U���܂łƂ̂��Ƃ������B����ČߑO���l�̓z�e���ɕ��������ĕ�������i���̓��e�X�g�������j�e���r�������肵�ĉ߂������B�P�P�����߂��ɃT���W���C������Ɠ����X�N�[�^�[�Ŗl���}���ɗ����B����͖钅�����̂ł��܂�����������Ȃ��������A�����ɃX�N�[�^�[�Ń����o�C�[�̊X�𑖂��Ă݂�ƁA�u�C���h����̑�s����o�C�[�ɗ����ȁI�v�Ƃ����C���ɂȂ�B�썑�̖A����A�l�g�i���o�[�i�}�n�[���[�V���g���B�j�̎����ԁA�Ԃ��o�X�A�����Ɍ����鍂�w�r���E�E�E�B�z�e���E�V�����O��������R�O���قǂŁA�{���E�b�h�f��̎q�{�A�t�B�����E�V�e�B�[�ɓ��������B
�@�f��̎B�e���Ƃ����Ɠ��{�ł͂����炭�����Ƃ����ɂ��f����B�邽�߂̂���Ƃ�����{�݂��ї����Ă���悤�ȏꏊ�Ȃ̂��낤�i�Ⴆ�]�ˎ���̊X���݂��Č������悤�ȎB�e���Ȃǁj�B�����A�t�B�����E�V�e�B�[�͍L��ȃW�����O�������̂܂ܕ~�n�ɂȂ��Ă���B�n�C�_���[�o�[�h�̃��[���[�W�[�E�t�B�����E�V�e�B�[���������������L���~�n�ɎB�e�{�݂��_�݂��Ă���B�ǂ����C���h�ł̉f��B�e���Ƃ����̂́A�L���~�n����������̂��낤�B�����\�ɂ��Ƃ��̃t�B�����E�V�e�B�[�̃W�����O���ɂ͌Ղ�`�[�^�[���Z��ł���A��ɂȂ�Ǝ��X�o�v����炵���B�������A�A�[�f�B���[�X�B�[�i���Z���j�������ɂ��̃W�����O���̒��Ő��������Ă���Ƃ����B���������Ƃ��낪�C���h�̖�̂킩��������Ƃ��낾�B�W�����O���̂��������ɂ͉f��̃Z�b�g����������Ă����B�t�B�����E�V�e�B�[�̒����X�N�[�^�[�ŋ삯������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�t�B�����E�V�e�B�[�̃W�����O��
�����ɂ̓����o�C�[�s�s���̃r���Q |
�� |
�@�����ō���̂s�u�b�l�̃R���Z�v�g���Љ�Ă������B�e�[�}�́uMade In Japan, Entertainment For The World�v�B�������̃o�[�W�����������悤�����A�l���o������̂̓p���W���[�r�[�E�_���X�҂ł���B�p���W���[�r�[�������o���O���[�E�_���X�i�p���W���[�u�n���̗x��j��x���Ă���ƁA���̒��ɓˑR��̒j����т��݁A�������o�[���O���[��x��ڗ����܂���B���������̒j�̊�͌����Ȃ��B�U�X�x��������A�Ō�ɂ��̒j�����������ƁA����͂Ȃ�Ɠ��{�l�������B�����Ŗ`���́uMade
In Japan, Entertainment For The World�v�Ƃ����i���[�V�������e���b�v������Ƃ������@���B�ǂ��炩�Ƃ����ƁuEntertainment For India�v���Ǝv���̂����A�܂������Ƃ��悤�B�Ƃɂ����A���̃p���W���[�r�[�E�_���X��x����{�l�����l�ł���B�Ƃ͌����Ă��x������ۂɗx��̂̓X�^���g�}���ŁA�l�͍Ō�̊猩���̃V�[������������������B���ɂ������悤�ȃv���b�g�Ń^�u���[�E�o�[�W������o���^�i�[�e�B�����E�o�[�W�����Ȃǂ����삳��Ă���悤�ŁA�����ɂ��ʂ̓��{�l���o������B
�@�X�N�[�^�[����Ԃ����ꏊ�ɂ́A�悭�f��X�^�[�����P�n�őҋ@����悤�ȁA�T�����J�[�i���ƌĂԂ̂��m��Ȃ��j����܂��Ă����B���̒��ɍ����Ă���悤�Ɏw�������B�����A����ȍ��ȍT��������������Ƃ̓X�^�[���A�Ǝv���Ă����̂����̊ԁA���̍T�����̒��ɂǂ�ǂ�ƃp���W���[�r�[�̊i�D�������C���h�l��������荞��ł���B�ȂA�l��l�̂��߂̍T��������Ȃ��̂��E�E�E�B�܂��܂��K�b�N���B�������Ȃ�قǁA�ނ炪�p���W���[�r�[�E�_���X��x��o�b�N�E�_���T�[�����B�����Ă݂�Ƃǂ����ނ�̓_���T�[�̎d�������Ă���l�����ŁA���i�̓_���X�E�V���[�Ȃǂɏo�������肵�Đ��v�𗧂ĂĂ���悤���B�R���I�O���t�@�[�i�_���X�w���ҁj���j����l�����Ă����B�ē�Ƃ����A�����킵���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�T�����J�[ |
�� |
|
 |
|
| �� |
�T�����J�[���� |
�� |
�@�T�����J�[�������o���A�t�B�����E�V�e�B�[�̏������u�̏�ɂ��郍�P�n�ɓ��������B�����o�C�[�̊X�ƃt�B�����E�V�e�B�[����]�̉��ɂł����D�̃��P�[�V�����ł���B�����ɂ͊��Ƀp���W���[�u�̓c�ɕ��̃Z�b�g���g��ł���A�@�ނ���ʂ�o����Ă����B�l�̏o�Ԃ͍Ōゾ���Ȃ̂ŁA��{�I�ɕ����Ă����ꂽ�B���炭����ƁA�p���W���[�r�[�̊i�D�������_���T�[�����̎B�e���n�܂����B�l�̑���ł���C���h�l�������B�ǂ����l�Ɏ�����̐l���I�ꂽ�悤�ŁA��u���݂��̊�������ƌ��߂č����Ă��܂����B�m���Ɏ��Ă��Ȃ��͂Ȃ��B�������̐F������I�ɈႤ�B�f���̗͂ʼn��Ƃ��Ȃ�̂��낤���B
�@�s�u�b�l�ɂ���f��ɂ���A�C���h�̎B�e�Ƃ����ƂЂ�����m���r���Ɛi�ރC���[�W�����邪�A�Ȃ��Ȃ��ǂ����Ĕނ�͊F�v���t�F�b�V���i���Ɏd�������Ă����B�U���܂łƂ������Ԑ��������������Ƃ����邵�A�������ɎB�e���I��炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���������������������������A���O���P�ň�Ԗ��ƂȂ�̂͑��z�ł���B�������ނ܂łɎB�e���I�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���Ă��ē��Ɋ撣���Ă����̂͊ēƃR���I�O���t�@�[�ŁA�ނ�̎d���Ԃ�̓v���������������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�����_���T�[�̔��������� |
�� |
|
 |
|
| �� |
�B�e���̗l�q |
�� |
|
 |
|
| �� |
�N���[���E�J�������g�p |
�� |
|
 |
|
| �� |
�����_���T�[�����͈�x�� |
�� |
�@�Q�������Ƀ����`�x�e�ƂȂ����B�P�[�^�����O�E�J�[�����Ă���A���P�n�͉₩�ɉ��O�C���h�����r���b�t�F���ƂȂ����B���[�e�B�[�A���C�X�A�_�[���A�_�q�[�i���[�O���g�j�A��J���[�A�`�L���E�J���[�A�t���C�h�E�t�B�b�V���ȂǂȂǂ��p�ӂ���Ă���A���ꂪ�܂����܂��ċ������B����Ȃ��������H�����H�ׂ���Ƃ́A�C���h�f��ƊE�œ����l�X�͂Ȃ�čK���Ȃ̂��낤���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�P�[�^�����O |
�� |
�@�����`�E�^�C���͂P�T���݂̂ŁA�����B�e���ĊJ���ꂽ�B���������ɖl�̏o�Ԃ͂Ȃ��A�����B�e�����w����݂̂������B�t�B�����E�V�e�B�[�ւ͈�ʂ̊ό��q���K��邱�Ƃ��ł���悤�ŁA�O���̐l���B�e�����ɗ����肵�Ă����B�c�O�Ȃ���f��X�^�[�͋߂��Ń��P�����Ă��Ȃ��������A�ߑO���ɂ͂����߂��ŃA�~�^�[�u�E�o�b�`�������V��f��uKhaki�v�̃��P�����Ă����������B�uKhaki�v�̃��P�n�ɂ̓g���b�N���Ђ�����Ԃ��Ă����B�܂��A�X�^�b�t�̐����ɂ��ƂȂ����A�t�K�j�X�^���̊O����b���B�e�����w���ɗ��Ă����B�������O����b�iForeign Minister�j�Ƃ����̂͌��ŁA������g�̂��Ƃ��Ǝv���B�A�t�K�j�X�^���̊O����b���C���h�ɗ��Ă����炯��������ςȂ��Ƃ��B
�@�S�����悤�₭�l�ɒ��ւ����߂��o���B�����T�����J�[�ɓ����ĐF�̃p���W���[�r�[�ߑ��𒅂�B�\�߃T�C�Y��m�点�Ă������̂ŁA�l�̐g�̂ɍ����悤�Ɏd���Ă��Ă����B�����č��x�̓��C�N�A�b�v�E�J�[�ɓ����Ċ�Ƀ��C�N���{���Ă�������B���ς������̂͂��ꂪ���܂�ď��߂Ă��B�Ƃ�����TVCM�ւ̏o�����̂����܂�ď��߂Ă��B����ْ����Ă���B
�@�����A�ЂƂ̌��O���������B�ߑ��͖l��p�Ɏd���Ă��Ă������A�p���W���[�r�[�̒j���̈ߑ��ł����Ƃ��d�v�ȃp�[�g�ł���p�O���[�i�^�[�o���j���A�X�^���g�}���Ƌ��L���������Ƃ��i�����^�C�v�̃p�O���[�ł͂Ȃ��A�J�|�b�Ƃ��Ԃ�^�C�v�̃p�O���[�������j�B�C���h�l�̓��̃T�C�Y�Ɠ��{�l�̓��̃T�C�Y���Ⴄ���Ƃ��ē͂ǂ����v�Z���Ă��Ȃ������悤���B�����p�O���[�����Ԃ��Ă݂�ƁA���炩�ɋ����ł���B�������A�p�O���[�̎��������{�l�Ƃ����̂͌o����H���B���ł������ȓ��{�l�̊�ɂ͂Ȃ��Ȃ��t�B�b�g���Ȃ��B�l�̊���p�O���[��������Ȃ����ނɓ���B�����Č���I�ɃX�^���g�}���ƈقȂ����͔̂��^�������B�l�͂��̎B�e�̂��߂ɂ����Ɣ���炸�ɂ����̂ł������������ɂȂ��Ă������A�X�^���g�}���̔��^�͐����̃C���h�l�X�^�C���ŁA�Z���������B�l�̔����p�O���[�̒��ɉ������ޓw�͂��s��ꂽ���A�����ł��������ȃp�O���[�������̂Ŗ����������B���Ɋē���u�����v���߂��o���B�Z�����ɂ���̂̓J�c�������Ȃ����A������Z���ɂ���Ȃ������̂ŊȒP���낤�Ǝv���A�b�l�o�������܂����Ƃ����炸���Ə����֍s���Ȃ������B�������ǂ����B�e���I�������낤�Ǝv���Ă����̂ň�Γ������B�������ӂƋC���t���Ă݂�ƁA����ł���l���A����ł���X�^���g�}���̔��^�ɍ��킹��Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃ��H���������Ėl�̕�������������Ƃ������Ƃ��H����A�������X�^���g�}���͊炪�f��Ȃ����A�l�͉f��B��͂�l�̕���������A�Ȃǂƍl���Ă���Ԃɖl�̔��̓w�A�E�h���b�T�[�ɂ���ăo�T�o�T�Ɛ��Ă��܂����B�p�O���[����������ɂ͂ߍ��߂�ꂽ�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�l�̑���Ƃ̂Q�V���b�g |
�� |
�@�T�����ɂȂ��Ă悤�₭�l�̓o�ꂷ��V�[���̎B�e���n�܂����B�l���o������V�[���͂������̂Q�V�[���B�܂��́A�������ŃW�����v���Ē��n���āA���ʂ݂̏Ƌ��ɐU��Ԃ�A�Ƃ����V�[���̎B�e���s��ꂽ�B���́u���ʂ̏݁v�Ƃ����̂�����āA�ē���u�N�̏Ί�͋U�����ۂ��B�����ƐS������Ă���v�Ƃ��u�N�̎����ŃC���h�l�S���̃n�[�g���ˎ~�߂�v�Ƃ��u�ǂ����ČN�̏Ί�͈������Ă���A�s�N�s�N�����Ă��邼�v�Ƃ��u�J�����̌������ɌN�̗F�B������Ǝv���āv�Ƃ��u���Ƃ��ɂ܂�������ȁv�Ƃ��A����Ƃ����鏕���Ǝ��ӂ��āA���x�����x���B�蒼���ꂽ�B�Q�O��͎B�蒼�����Ǝv���B���ꂾ�����x���B�蒼���Ă���ƁA���M�������Ă��āA���̒����^�����ɂȂ�B�悤�₭�n�j���o���Ƃ��ɂ́A��̋ؓ���Ⴢ�Ă����قǂ��B
�@�Q�Ԗڂ̃V�[���́A�����J�����Ɍ������ē��{���̂����V�����邾���������B����͊ȒP�ŁA���e�C�N�B���������łn�j���o���B����ɂĖl�̏o�Ԃ͏I���B���Ԃɂ��ĂR�O���ɂ������Ȃ������Ǝv���B���̂��߂����ɖl�͔�s�@�ɏ���Ă͂�郀���o�C�[�ɗ����̂��Ǝv���Ə����������C�����ɂȂ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�l�̓o��V�[���B�e�� |
�� |
�@����ɂ��Ă����Z������̂�����قǓ�����ƂƂ͎v��Ȃ������B�l�͍��܂ŃC���h�f������āA�U�X�u���̔o�D�̉��Z�͑S���ʖڂ��v�Ƃ������Ă������A���ꂩ��͂���Ȃ��Ə����Ȃ��Ȃ肻�����B���̂s�u�b�l�����������Ƀ{���E�b�h�E�X�^�[�Ƃ��Ẳh���̊K�i���삯��邩�Ǝv���Ă������A���������ɉ��Z�̍˔\���Ȃ����Ƃ��������������������B�Ăіl���J�����̑O�ʼn��Z�����邱�Ƃ́A�l���̒��ł�����x�ƖK��Ȃ����낤�B
�@�l�̎B�e���ς�����������B�e�͑�����ꂽ�B�������̕ӂ肩��͖{���ɓ��v�Ƃ̎��ԏ����ŁA�ē��N���[���݂�Ȍ���ɂȂ��đ����Ĉړ����đ�}���ŎB�e�����Ă����B�������ނV���O�ɂ͂߂ł����p�b�N�E�A�b�v�i�B�e�I���j�ƂȂ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�_���T�[�ƃR���I�O���t�@�[�̏W���ʐ^
���Ȃ݂ɂ��̒��ɂ���l�͑���ł��� |
�� |
�@�ǂ����C���h�f��̎B�e�̎d���Ƃ����͓̂��ق��J���ƕς��Ȃ��悤�ŁA�f��̎B�e���I���Ɗe�X�̃M�����̎x�����̎��ԂƂȂ����B�l�͌��ɌĂ�Ă����ƌ����Œz�ʂ�̕�V�����A�̎����ɃT�C���������B���̐l�̗̎������������̂Ŕ`�������Ă݂�ƁA�d���ɂ���đS����V��������B�R�O�O���s�[���炢�̐l�������B���낵���قǂ̃q�G�����L�[���B
�@�A��̔�s�@�́A�s���̃W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�Ƃ͑ł��ĕς���āA�[��Q�F�S�O���̃G�A�E�C���f�B�A�̃t���C�g�������B�����h���A�j���[���[�N�s���̍��ې������A�r���f���[�ɂ��������̂ō����ړ��ɂ����p�ł���B�l�i��������U�T�R�R���s�[�������B�f���[���烀���o�C�[�֗���Ƃ��ɗ��p�����W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�����Q�O�O�O���s�[�قLj����B�����ړ����s�@�ł���ہA�������𗘗p����������ې��𗘗p�������������Ȃ�Ƃ������Z������悤���B���������ԑт͍ň����B�[��P�Q�����ɋ�`�֍s���āA�Q�������ɔ�s�@�ɏ��A�S�����f���[�ɓ�������Ƃ�����J���ރR�[�X�ł���B�B�e���n�܂�܂ł̑ҋ��ɂ��^�₪���������A�B�e���I����Ă���̑ҋ��͂܂��Ɏ�̕���Ԃ������̂悤�ɕς�����悤�Ɋ������B�܂�l�͗p�ς݂Ƃ������Ƃ��E�E�E�B
�@�X�J�E�g�}���̃T���W���C�̉Ƃ���`�̂����߂��������̂ŁA�B�e���I�������͔ނ̉Ƃɍs���Ĕނ̉Ƒ��Ɖ�A�[�H�����y���ɂȂ��āA���ԂɂȂ������`�܂ő����Ă�������B�G�A�E�C���f�B�A�͖{���ɍň��ŁA���ԑт͈������A�Z�L�����e�B�[�̂��߂Ɋ�ʐ^���B�e����邵�i�W�F�b�g�E�G�A�E�F�C�Y�ł͂���Ȃ��Ƃ͂���Ȃ������I�j�A�Ȃ͋��������A�@���H�͂܂������A�قƂ�ǖ���Ȃ����ŁA�S���߂��Ƀf���[�ɒ������Ƃ��ɂ̓w�g�w�g�ɂȂ��Ă����B��`���玩��ɖ߂����Ƃ��ɂ͂T���ɂȂ��Ă����B
�@�l�⑼�̓��{�l���o�����邻�̂s�u�b�l�́A�����Ƃ���ɂ��ƂP�T���`�P������ɕ��f����邻�����B���������{�ł͕��f����Ȃ��B�C���h�݂̂ł���B����������ɂ��Ă��l�̋U���������Ί炪�d�g�ɏ���đS�C���h�ɓ͂��Ǝv���ƒp���������C�����ł����ς��ɂȂ�B�����f���f�O�ɗ������b�l�ɁA�l���o�������b�l������X�N���[����Ƀo�[���Ɨ����悤�Ȃ��Ƃ���������A�l�͂��炭�̊ԉf��ق֍s���Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B���ꂩ��͐�X���X�̖������B�l�͋��Ɩ��_�ɖڂ������ŁA�����Ȑ����������ɍ����o���Ă��܂����悤���E�E�E�B
�@�����A�����o�C�[�Ńe���r�b�l�̂��߂̎B�e�ɎQ���������Ƃ́A�l�̃C���h�؍݂̒��ł������o���A�����v���o�ɂȂ����B�����̎�A���b�̎�����������Ƃ����A�K�������̓C���h�Ȃ̂ŁA���{�����f�R�C���y���B�ɂ��ނ炭�́A�p�O���[�����Ԃ邽�߂ɕςȔ��`�ɂ���Ă��܂������Ƃ��E�E�E�B���Ȃ�Z������Ă��܂������߂ɂ�����悤���Ȃ��B�܂������L�т�܂ʼn䖝���邵���Ȃ����낤�B������w�ŃN���X���C�g����u�Ȃ��̔��^�́H�v�Ƃ��炩���Ă��܂����B
�@���݃C���h�l�ږ��͐��E���ɏZ��ł���B��r�I�V�����Ƃ���ł̓C�M���X�A�A�����J�A�I�[�X�g�����A�ȂǂɈڏZ�����l�X�A�Â��Ƃ���ł͓�C���h����}���[�����ɈڏZ�����l�X�Ȃǂ��L�����낤�B���̒��ŁA�C�M���X�A���n����ɂP�X���I�`�Q�O���I�ɂ����Đ��E�̂��������ɈڏZ�����C���h�l�͂����炭���܂��ʓI�ɒm���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H
�@�P�X���I�͂܂��ɐ��m�̒鍑��`���A�W�A��N�H�����鎞�ゾ�����B�C���h�ł����ɃC�M���X�̓��C���h��Ђ��x�z�n����C���h�S�y�ɍL���Ă���A�P�W�T�V�N�̃C���h�唽�����@�ɃC���h�̓C�M���X���{�̒��ړ������ɒu���ꂽ�B�����̃C�M���X�͐��E���ɐA���n�������Ă���A�����̔��W�Ɨ��v�̂��߂����ɃT�g�E�L�r�Ȃǂ̃v�����e�[�V�������\�z���Ă����B�����̓A�t���J����̍��l�z����v�����e�[�V�����̘J���҂Ƃ��Ďg�p���Ă����̂����A�z�ꐧ�x���֎~�����ƁA���x�̓C���h����u�_��J���ҁv�Ƃ������ڂŘJ���͂�⋋����悤�ɂȂ����B�P�W�R�W�N�`�P�X�P�V�N�̊ԁA�T�O���l�ȏ�́u�_��J���ҁv���t�B�W�[�A���[���V���X�A�g���j�_�[�h�E�g�o�S�A�X���i���A�ԓ��M�j�A�Ȃǂ̃C�M���X�A���n�̃T�g�E�L�r�E�v�����e�[�V�����֘A��čs���ꂽ�B�ނ�͂̌_��͈�ʓI�ɂT�N���������A�_����Ԃ��I���������C���h�ɋA�炸�ɂ��̒n�ɗ��܂�҂����Ȃ肢���B�ނ�͂��ꂼ��̓y�n�Ő������A�����A�q����ɉh�����A���ł͏�L�̍��X�̐l���̑唼���C���h�n�ږ�����߂Ă���B���{�l�ɂƂ��Ă���قǓ���݂̂Ȃ����������̂����A�t�B�W�[�Ȃǂ͂���ł���r�I�|�s�����[�ȃ��@�J���X��Ȃ̂ŁA�t�B�W�[�֍s���ď��߂Ă����ɃC���h�n�ږ����₽�瑽�����Ƃɋ����l�������ƕ����B
�@�u�_��J���ҁv�͈�ʓI�ɃM���~�e�B���[�J���҂ƌĂ��B�_��J���҂Ƃ��ĊC�O�֏o�čs�����C���h�l�̑唼�̓{�[�W���v���n���i�r�n�[���B����E�b�^���E�v���f�[�V���B�����j�̐l�ł���A�M���~�e�B���[�͉p��́uagreement�v���A���̒n��̕����ł���{�[�W���v���[�����a�����P��ł���B�܂��A�ނ�͎��������̂��Ƃ��u�W���n�[�W�[�E�o�[�C�[�v�ƌĂԂ悤���B�u�C��D�œn���Ă����Z��v�݂����ȈӖ��ł���B
�@�����͂����M���~�e�B���[�̃C���h�n�ږ��̒��ł����ɃJ���u�C�̍��X�i�g���j�_�[�h�E�g�o�S�A�X���i���A�ԓ��M�A�i�j�Ɉږ������l�X���ނƂ����h�L�������^���[�f��uJahaji Bhai�v�̃v���~�A���ʉ�X�B�[���[�E�t�H�[�g�E�I�[�f�B�g���A���ōs���A�l���Ђ��Ȃ��Ƃ���U��ꂽ�̂ōs���Ă݂��B���͖l�̓t�B�W�[�̃C���h�n�ږ����������Ƃ�����̂ŁA�����M���~�e�B���[�E�C���h�l�ɂ͋���������B������܂�Ƃ������ʉ�������A�g���j�_�[�h�E�g�o�S�ƃ��[���V���X�̍����ٖ����i�p�A�M�̍��X�ł͑�g�̂��Ƃ������Ăԁj�A�X���i���̑�g�ɉ����A�������ȑ�b�̃����B�E�V�����J���E�v���T�[�h���o�Ȃ��Ă����B
�@�͂����茾���ĉf��͑債�����Ƃ��Ȃ������̂����A�f���f�̑O�ɕo�q�������b�������Ƃ������[�������B�܂��͑�b�̃����B�E�V�����J���E�v���T�[�h���b�������B�ނ͂��傤�ǃ{�[�W���v���n���o�g�̂悤�ŁA�����̌̋�����C�O�ֈڏZ�����C���h�l�̂��Ƃ𑼐l���Ǝv�����A�o�Ȃ����߂��ƌ����Ă����B�ނ͌_��J���҂����̂��Ƃ��u�z��v�ƌĂ�ŃC�M���X�̂������Ƃ���A�Ȃ��{�[�W���v���n�����瑽���̃C���h�l���A��čs���ꂽ���ɂ��Ď����̈ӌ����q�ׂĂ����B��͂�r�n�[���̐l�X�̓A�V���[�J���̎���܂Ńr�n�[�����C���h�̒��S�������Ƃ������Ƃ���������X���ɂ���B�������C�M���X���C���h��A���n�Ƃ����Ƃ��ɂ́A�C�M���X�ɂƂ��ďd�v�Ȓn��̓f���[�A���N�i�E�[�A�J���J�b�^�A�{���x�C�A�}�h���X�ł���A�{�[�W���v���n���͂����̓s�s�����Ԓʂ蓹�ɉ߂����A�d�v�Ȓn��ł͂Ȃ������B�܂��A�{�[�W���v���n���̐l�X�͖�����Ȑl�������������߁A�z�ꈵ�����Ă����̒�R�����Ȃ����낤�ƕ����Ă����B������{�[�W���v���n�����瑽���̕n�����C���h�l�����@�I�z��Ƃ��ĊC�O�֘A��čs���ꂽ�ƌ����Ă����B
�@����ɔ��_�����̂����[���V���X�̍����ٖ����������B�����������B�E�V�����J���E�v���T�[�h�����Z�̂��ߑސȂ����ゾ�������A�ނ͎����̗�������đ�b���q�ׂ����Ƃ͑S�������Ⴂ�ł���Ǝ咣�����B�ނ͂܂��_��J���҂͓z��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����������B�l�̈ӎv�ŘJ���ҕ�W�ɉ��債�āA�_���l�X���_��J���҂ƂȂ�A�܂��ނ�͂����Ƌ�����������Ă����B�����ĂȂ��{�[�W���v���n������唼�̃C���h�l���_��J���҂ƂȂ����̂��Ƃ������ɂ��G��Ă����B�{�[�W���v���n���̃C���h�l�͌�����T�g�E�L�r�͔|�����Ă���A���ɐ������ꂽ�T�g�E�L�r���J���҂ƂȂ肦���B������{�[�W���v���n������W���I�ɘJ���҂���W���ꂽ�ƌ����Ă����B
�@���ꂾ���ɗ��܂炸�A���[���V���X�̍����ٖ����́A�P�X�P�T�N�ɓ�A�t���J����C���h�ɋA��r���Ƀ��[���V���X�ɗ���������}�n�[�g�}�[�E�K�[���f�B�[�̂��Ƃɘb��i�߂��B�K�[���f�B�[�̓��[���V���X�Ɉږ������C���h�l�ɂR�̂��Ƃ�b�����Ƃ����B�P�́u���[���V���X�͊��ɕꍑ�Ȃ̂�����A�C���h�l���C���h��������悤�Ƀ��[���V���X�������邱�Ɓv�A�Q�߂́u������[�������邱�Ɓv�A�R�߂́u�����ɐϋɓI�ɎQ�����邱�Ɓv�B����Ȍ�A���[���V���X�̃C���h�n�ږ������̓K�[���f�B�[���猾��ꂽ���Ƃ𒉎��Ɏ��A���������̕������������I�������������Ă������Ƃ����B
�@����Ƀ��[���V���X�ɂ���K���K�[�ɘb���ڂ�ƁA�ނ͂܂��܂��`��ƂȂ����B�Ȃ�ƃ��[���V���X�ɂ��K���W�X�͂�����Ƃ����B�C���h�n�ږ������[���V���X�̃W�����O���̒���T�����Ă���ƁA���ꂢ�Ȍ������B���̔������ɐS��D��ꂽ�ږ������́A���̌̔ȂɃV���@�����K������ăv�[�W���[���n�߂��B���̃V���@�����K�����@�ƂȂ�A�₪�ă��[���V���X�̃C���h�l�����łȂ��A�t���J�̃C���h�n�ږ��������Q�q�ɖK���قǗL���Ȏ��@�ƂȂ����B�����č������P�O�N�O�ɁA�N�����C���h�{���̃K���K�[�̐�������ŗ��āA���̌ɗ������B����ɂ���Ă��̌ƁA���̌��痬���͂��K���K�[�ƂȂ����Ƃ����B�����ٖ����́A���̃��[���V���X�̃K���K�[�̓C���h�̃K���K�[�����������Ɛ����炩�ɐ錾�����B
�@���[���V���X�̃K���K�[�̓C���h�̃K���K�[�����������\�\���̌��t�ɂ͐[���Ӗ�������B���ۂɃ��[���V���X�̃K���K�[�̓S�~���̂Ă��蟔�������肷�邱�Ƃ��֎~����Ă���A�{�Ƃ̃K���K�[�������|�I�ɐ����Ȃ悤���B��������͕\�ʏ�̈Ӗ��ł���B�ނ̓C���h�{���̃C���h�l���A���������̕�����Y����邱�Ƃ�Q���Ɠ����ɁA�܂������̃C���h�l���A�C���h���牓��������A�C���h�̕�����厖�Ɉێ����Ă��邱�Ƃ��ւ��Ă��̌��t�����̂������B�ނ̓q���f�B�[����g�킸�ɉp������b���C���h�l�������Ă��܂�������Ɍx����炵�Ă����B
�@�l�͈ȑO�ɂ��������ʂ�A���ꂩ�珫���C���h���p��Ɍ������đ��葱����̂��A�q���f�B�[��։�A����̂��ɂ��ẮA�T�ς̗�����Ƃ��Ă���B�m���ɃC���h�l���C���h���\���錾��ł���q���f�B�[����̎��ɂ��ĉp�ꎊ���`�ɑ����Ă����̂�����͎̂c�O���B�������A�A�W�A�e���̐l�X�Ɣ�r���ĉp��͂̂��邱�Ƃ��A�C���h�̗L���ȓ_�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͔F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�q���f�B�[��ی삪���ڂɉp��͂̒ቺ�������Ƃ͎v���Ȃ����A���{�̉p�ꋳ������Ă��܂��ƁA���܂�Ƀq���f�B�[���ی삵������̂���肩������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�p��͍��̂܂܂��ێ����āA�����ƃq���f�B�[��w�K�̈Ӌ`�ƁA�q���f�B�[��w�K�ɂ�闘�v�i�܂�q���f�B�[����w�Ԃ��Ƃɂ���ĐE���ȒP�ɓ�����悤�ɂ��邱�Ɓj��n�o���Ă������Ƃ��d�v���낤�B
�@�����A���������ӎ����v�́A�C���h�l��������ӎ��ɖڊo�߂Ă���Ă����ׂ����Ƃ��ƍl���Ă����B����������ł��������̂͋ɂ߂Đ����I�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������E�������Ă����B���̍ň��̌`��������`���B�����������A���[���V���X�̍����ٖ����̘b���āu���ꂾ�I�v�Ǝv�����B�P�X�`�Q�O���I�ɊC��n�����C���h�n�ږ����������A�C���h�{���ɕ����ی�������咣�ł���l�X�ł͂Ȃ��낤���B�ނ�͂���Ӗ��O���l���B������C���h�������ŋq�ϓI�ȖڂŌ��邱�Ƃ��ł���B����������Ŕނ�̓C���h�l���B�C���h�����R�Ȉ���Ƌ��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�{���̃C���h�l���A�S���W�̂Ȃ����̐l�̌��t�ɂ͎���݂��Ȃ��Ă��A�ނ�̌��t�Ȃ�X�b�ƐS�ɓ����Ă���͂����B���Č_��J���҂����́A�̋��������č����C��n�낤�Ƃ���Ƃ��A�u���[���`�����g�E�}�[�i�X�v�u�n�k�}�[���E�`���[���[�T�[�v�����ăK���K�[�̐�����������������ė��������Ƃ����B�܂�A�ނ�͂����ЂƂA�@����S�̎x���Ƃ��ĊC��n�����̂������B�����ĖړI�n�ɒ����A�i�Z�����߂�����A�����C���h�ɗ��ł���Ȃ���A�C���h�̕�����厖�ɑ厖�ɕی삵�Ă����B�ނ�ږ������̍��́A����Ε�Ȃ�C���h�̎q���������B�q�������͗��h�ɐ��������B��������e�͍��A�������ȕ��������Ă���B�܂�ŕa�C�ɂȂ��Ă��܂������̂悤���B���������Ƃ������A�q���������͂����킹�ĕ�e��������ׂ����B
�@���E�e���̋��A���n���ɎU���C���h�n�ږ������́A�s�K�ȗ��j�̐����ؐl�Ƃ�������B�������A�ʂ̌���������A�C���h�͐��E�e�n�Ɂu�W���n�[�W�[�E�o�[�C�[�v�Ƃ����S�����q�����������A�q��Ɍb�܂ꂽ�����Ƃ�������B�ނ炪�e�F�s����Ƃ��͍����Ǝv���B���������ݖډ��A�u�n���[�C�[�E�W���n�[�W�[�E�o�[�C�[�i��s�@�ŊC��n�����Z�킽���j�v�����B�����B��������Ƒ���`���ƃC���h�I
�@�����Q�T�ԂقǖZ�����Ă��܂�f������ɍs���Ȃ������̂����A�����͎��Ԃ��������̂ŃT�b�e�B�����E�V�l�v���b�N�X�ŐV��f������邱�Ƃ��ł����B�����f��͍��������J����n�߂�����́uBoom�v�B�C���h�f�旣�ꂵ���ߌ��ȕ\���ƁA��ȃt�@�b�V�����Œ��ړx�̍���������i���B
�@�剉�̓A�~�^�[�u�E�o�b�`�����A�O���V�����E�O���[���@�[�A�W���b�L�[�E�V�����t�A�W���[���F�[�h�E�W���[�t�@���[�A�Y�B�[�i�g�E�A�}�[���A�X�B�[�}�[�E�r�V�����[�X�A�p�h�}�[�E���N�V���~�[�A�}�h�D�E�T�v���[�A�J�g���[�i�E�J�C�t�B�O�ҎO�l�i�A�~�^�[�u�A�O���V�����A�W���b�L�[�j�̓{���E�b�h�f��ɂ悭�o�Ă��邨����݂̔o�D���B�W���[���F�[�h���}���`�E�^�����g�ŁA�s�u�ɉf��ɉ��y�ɂ����ȍ˔\�����Ă���B�Y�B�[�i�g�ƃX�B�[�}�[�͂����������̔��ꂽ���D�̂悤�ŁA��ҎO�l�i�p�h�}�[�A�}�h�D�A�J�g���[�i�j�͖{���̃��f���ł���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
Boom |
�� |
| Boom |
�@�V�F�[���[�i�p�h�}�[�E���N�V���~�[�j�A�A�k�i�}�h�D�E�T�v���[�j�A���[�i�[�i�J�g���[�i�E�J�C�t�j�̓C���h�̃g�b�v�E���f���Ń��[�����C�g�������B����������o�C�[�̃C���h��O�ōs��ꂽ�t�@�b�V�����E�V���[�̃X�e�[�W�̏�łR�l�͑��̃��f�������ƌ��܂�����B���̂Ƃ����f���̔����炢�����̃_�C�������h���U������B���̃_�C�������h�͓��i�ŁA�h�D�o�C�ɏZ�ޑ啨�}�t�B�A�A�o���[�E�~���[���i�A�~�^�[�u�E�o�b�`�����j�֖��A�����\��̂��̂������B�_�C�������h�͎G���̒��ŕ������Ă��܂����B
�@�_�C�������h�̖��A�����d���Ă����̂́A�`���[�e�[�E�~���[���i�W���b�L�[�E�V�����t�j�Ƃ����}�t�B�A�������B�ނ̕ʖ��̓t�B�t�e�B�[�E�t�B�t�e�B�[�B�K���T�O���̃}�[�W������邱�Ƃ��疼�t����ꂽ���O�������B�`���[�e�[�E�~���[���͕����̃u�[���E�V�����J���i�W���[���F�[�h�E�W���[�t�@���[�j�ɁA�R�l�̃��f���̕ߊl�𖽂���B�V�F�[���[�����͏����g���̃o�[���e�B�[�i�X�B�[�}�[�E�r�V�����[�X�j�Ƌ��ɕ߂炦����B
�@����A�h�D�o�C�ł̓o���[�E�~���[�����{�q�̃~�f�B�A���E�~���[���i�O���V�����E�O���[���@�[�j�Ƀ_�C�������h�D��𖽂��Ă����B�~�f�B�A���E�~���[���̓����o�C�[�̃`���[�e�[�E�~���[���Ƀ_�C�������h�D��𖽂��A�`���[�e�[�E�~���[���̓u�[���E�V�����J���ƕ߂܂����R�l�̃��f���Ƀ_�C�������h�D��𖽂����B
�@�u�[���̓V�F�[���[�A�A�k�A���[�i�[�ɏe��n���A��s�����𖽂���B�Ȃ������̕ӂ肩�珢�g���̃o�[���e�B�[���}�ɍ�m�ƂȂ��č��ɎQ�����n�߂�B�o�[���e�B�[�̋@�]�Ńo���O�i�喃�j�����R�l�̓n�C�e���V�����̂܂܋�s�ցA�����Ńo���[�E�~���[���̕����`���[�g�D�[���[������_�C�������h��D�����Ƃɐ��������i���̕ӂ̃X�g�[���[���������Ă����j�B
�@�R�l�͏��g���̃o�[���e�B�[�Ƌ��Ƀu�[���E�V�����J�����o�������ăh�D�o�C�֓n��A�o���[�E�~���[���A�~�f�B�A���E�~���[���ƐڐG����B�����ă_�C�������h�̎�����a�ɂ��āA�o���[�E�~���[���A�~�f�B�A���E�~���[���A�`���[�e�[�E�~���[���̂R�l����ӏ��ɌĂяo���A�R�l�𒇈Ⴂ�����đ������ɂ������B�������ău�[���A�V�F�[���[�A�A�k�A���[�i�[�A�o�[���e�B�[�́A�R�l�̃}�t�B�A���狐�z�̋�����ɓ��ꂽ�B�܂��A�u�[���E�V�����J�����Ō�ɂ͗����ĊC�ɕ���o���ꂽ�B
�@���̏o�����̌�A�o�[���e�B�[�A�V�F�[���[�A�A�k�A���[�i�[�͎�ɓ��ꂽ���ŗI�X���K�̐����𑗂����Ƃ����B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�܂��S�̓I�Ȋ��z���珑���ƁA�͂����茾���Ċ��ҊO��̉f�悾�����B�n���E�b�h�f����ۂ��{���E�b�h�f�����낤�Ƃ��Ă���͕̂�����̂����A�X�g�[���[���悭������ɂ��������B�܂��A�C���h�f��̃��x�������G���`�b�N�ȃV�[���A��_�ȃt�@�b�V�����A�����Ďc���V�[���������āA����̓C���h�l�̊ϋq�ɂ͎�����Ȃ����낤�Ǝv�����B
�@�i���@���T�]�̇@�������ō��]���̂R�ɂ����̂́A�ʂɃ��}���e�B�b�N�ȉf�悾��������ł͂Ȃ��A�ɓx�ɃG���`�b�N�ȉf�悾�������炾�B�C���h�Łu�V�������K�[���i�����j�v�ƌ������ꍇ�A�j���̗����ɉ����ăG���e�B�V�Y���̃j���A���X������B���f�������̒��Ă��镞�͋�������_�ɂ͂����Ă��ċ����ۏo�����������A�`���[�e�[�E�~���[���̊��̉��œ����Ă��鏗���i�������邽�߂��͂����ł͏����܂��j�Ȃǂ͍ۂǂ�����\���������B
�@�A�~�^�[�u�E�o�b�`����������o���[�E�~���[���̃o�J�a�I�L�����N�^�[��A�W���[���F�[�h�E�W���[�t�@���[������u�[���̌��ȁu�A�C���C���C���C���`�v�Ȃǂ͂��������Ă悩�����B���̑��j�q���ȃR���f�B�[�������ɎU��߂��Ă����B����ćA��̃��T���R�ɂ��Ă������B
�@�G�������R�Ȃ̂́A���܂�ɖ\�̓V�[���A�c���V�[���������������炾�B���ɏ��w���~�V���Őؒf����V�[�����o�Ă���̂����A���̌����L���V�[���ɂ͉�ꂩ�猙���̐������������B�l���v�킸��������߂Ă��܂����B
�@�}�t�B�A�̋ƊE�p�ꂪ�p�o���A�}�t�B�A�����̂���ׂ���������̂ŁA�f����قڑS�ė������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂�����܂��B���ՂŃX�g�[���[���������Ă��܂����B�����S�������ł�����A���������]���͏オ������������Ȃ����A�A��ۂɃC���h�l���u���̖��ʌ������v�ƌ��X�Ɍ����Ă����̂ŁA��͂��O�͂��Ȃ��Ǝv����B
�@���ƁA�ǂ����R�l�̃��f�����N���N�����悭������Ȃ������B�l���l�̊���o����̂����Ȃ�����������Ȃ����A����������Ɍ��̂���R�l���L���X�e�B���O���Ă��ꂽ�������������x���オ������������Ȃ��B�O���V�����E�O���[���@�[�ƃW���[���F�[�h�E�W���[�t�@���[�̊���Ȃ�ƂȂ����Ă��č��������B
�@���͂��̉f��̃T���g���́A�^�����B���E�X�B����T���f�B�[�v�E�`���E�^�[�Ȃǂ̗L���ȃA�[�e�B�X�g���Q�����Ă���A���݃C���h�̃q�b�g�E�`���[�g�̃i���o�[�P�ł���B�������uBoom�v�͂Q���Ԃ̉f��ŁA�~���[�W�J���E�V�[���͂قƂ�ǂȂ��A�����̉��y����������邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�ׂ����Ƃ���Ŗʔ����������������f�悾�������A�G���E�V�[���A�O���E�V�[�������������邱�ƂƁA�r�{�̐������̂Ȃ��̂����ŁA�l�͂��܂�I�X�X���ł��Ȃ��f��ł���B�薼�ʂ�̃u�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�l�c�A�l�o�R�A�b�c�|�q�A�c�u�c�|�q�ȂǁA�L�^�Z�p�̐i���ɏ]���ĂX�O�N�ギ�炢����}���Ɂu���쌠�v�Ƃ������t�����y�A�f��A�R���s���[�^�[�E�\�t�g�E�F�A�Ȃǂ̋ƊE�̐l�X�̌����甭������������Ă����B���ꂾ���łȂ��A���쌠�͂��܂╶�w��|�p�Ɋւ��l�S�Ă����ʂ�����ƂȂ����B����Ȓ��A�C���h�ł͈ˑR�Ƃ��āu���쌠�v�Ƃ������t�͎s�����Ă��Ȃ��B�܂�C���ł̉��y�A�f��A�\�t�g�E�F�A�A�{�A�ߕ��A�H�i�ȂǂȂǁA����Ƃ����鏤�i�ɒ��쌠�����̂��̂�������B���쌠�����Ƃ������A���X���쌠�ȂǑ��݂��Ȃ����̂悤���B
�@�C���h�̒��쌠�N�Q�̗�������n�߂��疇���ɉɂ��Ȃ��B�Ⴆ�Ζl�͂悭�C���h�f��̉��y�b�c���悭�����B���������̂b�c���Ő��K�ɔ����Ă���b�c�ł���B����������������������Ƃ̑��q�̃X���u�͖l�Ɍ������B�u�Z����͂ǂ����Ă����������ʂȔ���������́H����Ȃ́i��@�R�s�[�́j�l�o�R�őS����ɓ���̂ɁB�l�������X�������v�l�͂����A�u�l�������Ɣ������ƂŁA�C���h�f��E�̔��W�ɍv�����Ă�v�Ɠ������������������A�X���u�͂悭�������Ă��Ȃ��悤�������B
�@�f��E�ł����쌠�����͐�]�I�ȂقǐZ�����Ă���B�V��f��̂u�b�c�����ؑO�Ɏ�ɓ�������A�P�[�u���s�u�ɏ�f���̐V��f�悪���f���ꂽ��ƁA������肽������ł���B
�@�C���h�Ŕ����Ă���p�\�R����\�t�g�E�F�A�͂����ƂЂǂ��B�l�̓C���h�ŊC���ŃE�B���h�E�Y�ȊO�œ����Ă���p�\�R�����������Ƃ��Ȃ����A�\�t�g�E�F�A���P���̐��K�łb�c���牽����̊C���łb�c�����Y�����Ƃ�����Ԃ��B
�@�����܂낤�Ǝv���Ă��A�����܂�l�Ԃ���ʏ����Ɠ������C���Ń��f�B�A�̉��b������Ă���l���낤����A�{�i�I�Ɏ����܂邱�Ƃ͕s�\���낤�B�܂��A���{�@�ւ̃p�\�R���œ����Ă���E�B���h�E�Y�����āA�唼���C���łł��邱�Ƃ��e�Ղɐ��������B�C���h�ł͂����ǂ����悤���Ȃ��قǒ��쌠�͐N�Q����܂����Ă���B
�@�����A�l�͎��͒��쌠�Ƃ����l�����������ł���B�ꉞ�@�������璘�쌠�͐N�Q���Ȃ��悤�ɐ����Ă�����肾���A�Ƃ��ɃC���h�l�̒��쌠�ɑ���ԓx���ɉ��Ɏv���邱�Ƃ�����B�Ȃ����쌠���������B����͂ЂƂ̍����I�₢���l�̐S�̒��ɂ��邩�炾�B���쌠���咣����l�Ƃ����̂́A��T�|�p�Ƃ��ƂȂǁA�m�I�n�����̑n�o�ƂƂ��Ă���l�X���B�����đ�T�Ȃ������������E�ƂƂ����̂͂����������C���[�W�����܂Ƃ��A�{�l�������傫�Ȋ�����Ă���l�������肾�B�������ނ�̎d���͉ʂ����Ē��쌠�]�X���咣���Ă���قLĵ��E�ƂȂ̂��낤���H�l�Ԃ��������ŕK�v�s���ȈߐH�Z�Ɋւ��d��������l���В���͔̂[���������Ƃ��āA�Ȃ���Ȃ��ł������悤�ȃG���^�[�e�C�����g�Ɋւ��悤�Ȑl���A���������o�������̂Ɏ������āA�����������ꂪ���������̂��̂ł��邩�̂悤�ɐU�����̂�����͍̂D���ł͂Ȃ��B�ނ�̎d���͑��ɐl������邱�Ƃł���B��y���m���ɐl�Ԃ��������ŕK�v�s���Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͔F�߂�B�������A���������l���������Ȃ��Ă��l�͎��R�Ɍ�y�������邱�Ƃ��ł��邾�낤���A��y�ŋ����ɋ������悤�ȏ����ɂ͋^���������B�G���^�[�e�C�����g�Ɋւ��d��������҂́A�l������ĂȂ�ڂ��B��V�͂����܂ł��̂��q����̊���������ɂ���Č��߂���ׂ����낤�B�����A�l�����z�Ƃ���|�p�Ƃ̐������́A�C���h�̓��[�ɐ�����哹�|�l���B���ꂱ���|�p�Ƃ̖{���̎p���Ǝv���B�����Ă��ă}�n�[���[�W���[�̋{��ɏZ�ݍ���Ō|�p�̒Nj��ɑł�����ł����Ƃ����������̌|�p�Ƃ����B�ނ���}�n�[���[�W���[�̊��y�̂��߂ɍ�i�ݏo���A����ɂ��J������������蒞�������肵�Ă����Ƃ����Ӗ��ŁA�{���̌|�p�Ƃ��Ǝv���B��y�Ɋւ��҂Ƃ����͖̂{��������Ɣڂ������݂������̂ł͂Ȃ����B
�@�C���h�̕��w�j��R�����Ă݂�ƁA��͂蒘�쌠�Ƃ����ϔO�͊F�����������Ƃ�Ɋ���������B�Ⴆ�o���������̐��T���F�[�_�B�����������l�̓��F�[�_�ɂ��Ă������������������Ƃ�����B�u���F�[�_�Ƃ����̂́A�N������������̂ł͂Ȃ��A���X���݂��Ă������̂ł���B��C����������A���̒���������A�������̑̓���������A�Ƃɂ������̐��E�̎��鏊�Ɍ��X���݂��Ă������̂ł���B�������ʂȔ\�͂��������l�����t�ɂ������̂����F�[�_�ł���B�v���F�[�_�����łȂ��A�u���[�}�[���i�v��u�}�n�[�o�[���^�v�A���̑��̃C���h�̌ÓT���w�̐����ɂ��Ă������悤�Ȑ������Ȃ���邱�Ƃ������B�v����ɂ����̍�i�̍�҂͎��ۂɂ��̍�i��������̂ł͂Ȃ��A�_�̐������������m��Ȃ����A�������X���������̂��u���������v�܂��́u�ҏW�����v�������Ƃ����̂��B���X���������̂Ȃ�A���쌠�Ȃ�čŏ����瑶�݂��Ȃ��B
�@�����A�̂̕��w�Œ��쌠���C�ɂ��Ă����҂Ȃǐ��E�Ɉ�l�����Ȃ����낤�B�C���h�����Ɍ����ďq�ׂ�悤�Șb�ł��Ȃ���������Ȃ��B�������A�̂̃C���h�̕��w�҂������A��i���������g�ō�������̂ł͂Ȃ��A�����̌[�����Č��t�ɂ����Ǝ~�߂Ă��邱�Ƃ͔��ɖʔ����Ǝv���B�m���Ɍ���̍�Ƃ�|�p�Ƃł��A�悭�u�ˑR�C���X�s���[�V�����������Ĉ�C�ɍ��グ���v�Ƃ��u���N������Ȃ������̒��ɃC���[�W���ł��������Ă��āA������`�ɂ��������������v�ƌ����l�������肷��B�����Ă��Ă��Ă��������ˑR�̂Ђ�߂��ɂ���č��ꂽ���͖̂���ƂȂ邱�Ƃ������B�C���h�l�̍l����Ƃ���A�^�̌|�p��i�Ƃ����͖̂{���͌l�̗͂őn�o�������̂ł͂Ȃ��āA������ӂɕY���Ă��鉽�����L���b�`���Č`�ɂ��������̂��̂�������Ȃ��B
�@��i�����̎��_�Œ��쌠���Ȃ��ƂȂ�ƁA�����Ȍ�̉��ς��N���邱�Ƃ͕K�R���B�C���h�ł͌������w�̓`�����������������Ƃ�����A���肩�����֎p����Ă������Ƃɂǂ�ǂ�`���ς���Ă����Ƃ������Ƃ����������B�܂������ɕς���Ă��܂��̂͌���ł���B�������w�Ƃ��ē`�������i���A�L�^�҂����̐l�̕����ōD������ɋL�^���Ă��܂����ƂȂǓ��풃�ю��ł��������߁A�㐢�Ɏc���Ă����i�̌��ꂩ��I���W�i���̍�҂̌�������邱�Ƃ͎��͓���B�܂��A�R�s�[�@�ȂǂȂ������̂ŁA�����ŋL�^���ꂽ��i�ł����Ă��A���ʂ������ɕς���Ă��܂����Ƃ͑����B����ɉ����A�㐢�̐l���I���W�i���ɏ���ɕ���͂�lj����Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ������B�u���[�}�[���i�v�̑�V�̓E�b�^���[�J���h���㐢�ɒlj����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ͗L���ł���B�܂��A�ߋ��̍�i���ނɂƂ��ĐV���Ƀ��~�b�N�X��i�����Ƃ����`�����C���h�̕��w�ł͂悭������B�܂��Ⴊ�u���[�}�[���i�v�ɂȂ��Ă��܂����A�g�D���X�B�[�́u���[���`�����g�E�}�[�i�X�v��P�[�V�����́u���[���`�����h���J�[�v�ȂǂȂǁA�u���[�}�[���i�v�̋���ɂ��Č㐢�ɍ��ꂽ���w��i�̓C���h�ɂ͕���قǂ���i�C���h���O�ɂ�����j�B���{�̘a�̂ł��u�{�̎��v�Ƃ����Z�I�����邵�A�����ł��u�O���u�v����Ɂu�O�����Z�v�����ꂽ�肵�Ă��邩��A��͂肱����C���h���L�̎��ۂł͂Ȃ������Ƃ����邾�낤�B���ǒ��쌠�Ȃ�Ă����l�����́A���ŋߐ��������̂����A���܂荪���̂Ȃ����̂̂悤�Ɏv����B�����|�p�ƂȂǂƌĂ�錳�X��H�������R�̐l�����̕��������߂̌�����Ȃ��̂��B
�@���w�ł��|�p�ł��A���{�I�ɂ́u�݂�ȂŊy���ނ��́v�ł���A�N�������L�����咣����悤�Ȑ��i�̂��̂ł͂Ȃ������Ǝv���B���Ă̕��w�j���ǂ����������͒m��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A�W�A�̗��j�ł́A��x���ɕ��y������i�́A�݂�Ȃ̎�Ŏ��R�ɉ��ς���čs���I�[�v���E�e�L�X�g�������ƌ����Ă������낤�B����Ō����t���[�\�t�g�̂悤�Ȃ��̂��B�E�B���h�E�Y���N���[�Y�h�E�e�L�X�g�Ƃ���A���i�b�N�X�̓I�[�v���E�e�L�X�g���B���������`���I�ȍl�������C���h�l�̐S�ɍ��t���Ă��邩��A���쌠�Ƃ����l�����͂��܂������Ȃ��ƍl����̂͂�����Ɛ[�ǂ݂��������낤���H�����P�ɋƎ҂ׂ͖��邩��C���ł�A����҂͋���ߖ邽�߂ɊC���ł��Ă���ɉ߂��Ȃ��Ƃ����̂����ǂ̌��_���낤���B
�@�ŋ߂�����Ɗ������������Ƃ��������B
�@�l���w��ł��鋳���͂قƂ�Ǒq�ɂ̂悤�ȏꏊ�ŁA��ꂽ�֎q�╶���ՂȂǂɎg�����Ǝv����ŔȂǂ����ɒu����Ă���A�O�ւȂ���V���b�^�[�܂ł��Ă���B�����炭�ȑO�͑q�ɂ��K���[�W�Ɏg���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�����G����w�Ԃ��߂ɗ��Ă���Ȃ�A�Ȃ�ƂȂ��A�g���G�Ƃ������͋C�ł�����Ƃ��������Ȃ̂����A�c�O�Ȃ��炻���ł͂Ȃ��B�u�`�u���邽�߂ɗ��Ă���̂��B����A���̋�����`���Č���ƁA���ʂɋ����Ƃ��������̕����ɂȂ��Ă���B�܂�l�`�q���f�B�[��R�[�X���������̂悤�ȕ��u�����������������Ă���̂��B�C���h�̑�w�ɂ�����q���f�B�[��Ȃ̒n�ʂ����ƂȂ��m��Ă���B
�@���Ƃ͂قږ����X��������n�܂�B�l�̓L�����p�X�̊O�ɏZ��ł��邱�Ƃ���A���ߑ��߂ɏo�����Ă��邽�߁A���������������B�����A�����̔��͏����������ĕ܂��Ă���B���J���W�̐l���ЂƂЂƂ��������ċ����̔����J���Ă����̂ŁA�����҂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����J�����璆�ɓ���A�d�C��������p���J�[�i�V��̃t�@���j�����葋���J�����肷��B���ꂪ�l�̓��ۂł���B������������̒��A�����̑����J���Ă���ƁA�ӂƋ����̋��ɓ������̂��������B�����I
�@�����̒��ɔ������荞��ł����B������炸���Ƒ��������܂��Ă������낤����A����̂�����ɓ����Ă��Ă��̂܂܂����Ƃ��̋����ɕ����߂��Ă������ƂɂȂ�B������܂茳�C���Ȃ������ł���B���������H�ɋ���������Ă��鍑���B�����炱��Ȃ��Ƃŋ����Ă��Ă̓C���h�ݏZ�҂̌������ɏ������B�l�͋C�ɂ����ɂ��̂܂ܐȂɒ������B
�@���̂܂��Ƃ��n�܂�A���̂��ƂȂǂ�������Y��Ă��܂����B���������Ƃ����Ƃ��Ă����悤�ŁA���̑��݂ɋC�t���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������悤���B���̂܂܂S���ԖڂɂȂ�A�����������Ă����B���̋����̓q���f�B�[��w�Ȃ͂��Ƃ��i�m�t���Ɋ댯�l���Ƃ��Ēm����قnj������l�ł���B�F�̊�ɋْ�������B���̂Ƃ��ɉ����v�������A���炭�����Ƃ��Ă��������H�����������̂��B����ł��̋����ɔ��̑��݂��m���Ă��܂����B
�@���̏u�ԁA�l�̔]���Ɉ�u�ɂ��āA���̋������������Ăǂ���������������̂��̗\���V�~�����[�V�������������p�p�p�b�ƕ����B�u�Ȃ����v�ƋC�ɂ����߂Ȃ����A�u���Ƃ̎ז����A�N�����̔���ǂ��o���v�Ɩ��߂��邩�A�u���O�烏�V�ƈꏏ�ɍu�`��������肩�A�Ȃ߂�Ȃ�v�Ɠ{��o�����A�͂��܂������l�^�ɃK�U���i���j���r���������A���̂ǂꂩ���Ǝv�����B�������A���̋������Ƃ����s���͂��̂ǂ�ł��Ȃ������B
�@�u�N���A�p���J�[�̃X�C�b�`���Ȃ����v
�@�����̓V��ɂ͋���ȃt�@������������]���ĕ��𑗂�o���Ă���B���������̃t�@���͎��͔�s���鐶���ɂƂ��ēV�G�ŁA��ȂǂɁA�����̖�����ɂ��ĕ����̒��ɓ����Ă������Ȃǂ��A�t���t���b�ƃp���J�[�̕��߂Â������̂Ȃ�A�u�p���I�v�Ƃ������Ƌ��ɍ�����]����p���J�[�̉H�ɂ͂�����A����ꂠ���Ȃ����ɗ������ė�������B����̓C���h�̉Ă̖�ɂ悭���镗�i�ł���B���̃p���J�[�Ɍ���Ď��˂�����ł��܂�����ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ������Ƃ����͎����ς݂ŁA�����B�����l�������̏㒅�𒅂悤�Ǝv���đ��Ɏ��ʂ��Ă����Ƃ���A���r����ɏグ�Ă��܂��A�����ɂ������p���J�[�Ɏ������Ԃ��Ă��܂����B�l�͂Ă�������悪�����ꂽ���̂Ǝv���ē��]�������A�������̐悪���ꂽ�����ŁA���͖����������B�ǂ����p���J�[�ɂ͐l�Ԃ��E������قǂ̗͂͂Ȃ��悤���B��]���ˑR�������ė�����E���͂����邩������Ȃ����E�E�E�i������C���h�ł͂��蓾�Ȃ��b�ł͂Ȃ��炵���j�B
�@�b�����ɂ���Ă��܂������A�Ƃɂ��������ɂ����������Ă��̋��������������t���A�u�p���J�[�̃X�C�b�`���Ȃ����v�������̂��B�����p���J�[�ɓ������Ď�������̂�h�����߂̎w���������B
�@�J�G�������A�Z�J���h�E�T�}�[�ƌĂ�鎞���ɂȂ��Ă���̂ŁA�ŋߓ��������������������������B�G�A�R���ȂǂȂ��A�B��̔������u�ł���p���J�[����Ă��܂�����A�����Ȃ�͕̂K��ł���B���������̂܂܃p���J�[�������Ă�����A���̃p���J�[�ɔ������˂��Ė��𗎂Ƃ��Ă��܂���������Ȃ��B�m���ɂ���͋N���肤��B�����̐l�Ԃ̉��K�������A��C�̓����̖������E�E�E���̍��ׂȏo��������l�̓C���h�̑f���炵�������߂Ď��������B�����Ėl�͒����̔����������Ƃ��ɁA���̂��ƂɋC�t���Ȃ������̂�p�����B�����̃p���J�[�͑S�ăX�C�b�`�E�I�t����āA�����̒��͏����Ȃ����B�ł������̂��A���̖�����邽�߂Ȃ�E�E�E�B
�@�����ɂ���C�����Ƃ����̂́A���E�̂ǂ��ɂł�����Ƃ͎v�����A��͂�C���h�͑����ɔ�ׂĈ�����������o�Ă���Ǝv���B������ɖ����ɂ��鍑���e���ɂ��鍑�����߂�͓̂���B�������l�͂ЂƂ̊��m���Ă���B����͖�nj��ł���B��nj������鍑�͐l�Ԃ̉��K�����������S�ʂ̖����ɂ��鍑���Ǝv���Ă���B��nj������Ȃ����́A�l�Ԃ����������ŕ֗��ň��S�Ȃ悤�ɁA���C�Ŏז��Ȑ����E���邱�Ƃ��ł��鐸�_���������������̍��ł���B���������Ӗ��ŁA�C���h�l�͖����ɂ��A���{�l�͖����y�����Ă���Ǝv���B����A�y������悤�ɂȂ����ƌ����ׂ����B�l���q���̍��Ȃǂ͖�nj��Ȃ�Ă�������������ӂ�����Ă������̂ł���B���ꂪ���̊Ԃɂ��قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����a�Ȃǂ̗\�h�̂��߂ɕی����ɘA��čs����ĎE�Q���ꂽ�̂��낤�B����̂͋�������ĉ����炿�̃y�b�g�̌������ł���B����Ȃ̌��Ƃ͔F�߂��Ȃ��B��͂��nj��������^�����̌��ł���B��nj�����r�����Ă����āA�u���̑���𗝉����܂��傤�v�Ƃ��u���R�ɐG�ꍇ���܂��傤�v�Ȃ�Đ�������̂͋U�P�ł���B��nj��̂��Ȃ����̍�����M����ȁA������̂ɖ����č��ۉ��Љ�������ׂ��i�H�j�B
�@���Ȃ݂ɗ�̔��́A�p���J�[���~�܂��Ă��炭��ɁA���S�����̂����̕��֔�ї����A���̊i�q�̌��Ԃ���O�ɏo�čs�����B�����Ƀp���J�[���I���ɂ����̂͌����܂ł��Ȃ����A�����ɒ�d�ɂȂ��Ă܂��~�܂��Ă��܂����E�E�E�B
�@�ȑO�z���_�̂`�r�h�l�n���C���h�ɗ����Ƃ����j���[�X���������A�܂��C���h�ɑ؍݂��Ă����悤�ŁA�����̓X�B�[���[�E�t�H�[�g�E�I�[�f�B�g���A���ŁuASIMO MEGA SHOW�v���������B�`�P�b�g����ɓ������̂ōs���Ă݂��B
�@�`�r�h�l�n�̂��Ƃ̓j���[�X��s�u�b�l�Ȃǂŏ\���m���Ă������A���ۂɌ���̂͏��߂Ă������B�C���h�ɂ��Ȃ�����{�̍ŐV�e�N�m���W�[��ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ͉������s�v�c�ȋC�����B���ς�炸�X�B�[���[�E�t�H�[�g�E�I�[�f�B�g���A���̌x���͌��d�ŁA�������������Ă������J������A�g�ѓd�b�ȂǁA�S�ē�����ŗa���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������ߕq�Ȍx�����f���[�̌��ȂƂ��낾�B�������z���_�W�̐l�̂������ň�ԑO�̗\��Ȃɍ��邱�Ƃ��ł����B
�@�ߌ�V������n�܂�\�肾�������A�C���h�Ŏ��Ԓʂ�Ɏ����i�ނ悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A��͂�R�O���قǒx��Ďn�܂����B�������O���ŕςȃ_���T�[�������ςȉ��y�Ƌ��Ƀ_���X��������A�z���_�̂b�l�����X�Ɨ����ꂽ��ƁA���Ȃ肶�炳�ꂽ�B�₪�Ă`�r�h�l�n�̊J����b�r�f�I��������A����Ƃ`�r�h�l�n�ɉ�邩�Ǝv������A�܂��_���X���n�܂�A���������ɂ���Ɠ{�肪���_�ɒB�����Ƃ���ł���Ƃ`�r�h�l�n�̓o��ƂȂ����B
�@�����`�I�s�u�Ō����`�r�h�l�n��������̂`�r�h�l�n�������Ă����I����͊����I�����������͎v���������R���p�N�g�ŏ����������i�g���P�Q�O�����j�B�e���݂₷���f�U�C���ɂ��邽�߂ɏ����߂ɐv�����悤���B�`�r�h�l�n�͗�������킹�āi���S�ɍ��킳���Ă��Ȃ��������j�u�i�}�X�e�[�v�ƈ��A���A���Ƃ̓q���f�B�[��̍��������p��Ŏi��̂��o����Ɖ�b�����Ă����B�����ȓ��������邱�Ƃ��ł��āA����͂����C���h�l���r�b�N�����낤�B���{�l���r�b�N�����Ă��܂����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�`�r�h�l�n |
�� |
�@�`�r�h�l�n�̈Ӗ��́uAdvanced Step in Innovative Mobility�v�̗��炵���B�E�E�E�Ȃɂ�����Ȗ����ɂ������Ȃ��Ă��E�E�E�B���{��́u���v�Ƃ������낤�ɁE�E�E�B�Q�P�N�̍Ό��ƂR�O�O�O���~�̎����𓊓����Đ��삳�ꂽ�炵���A���݃C���h�ɗ��Ă���`�r�h�l�n�̓^�C�̒��݈����������B�܂蕁�i�̓^�C�œ����Ă���A���̓C���h�ɏo���ɗ��Ă���Ƃ����킯���B
�@�`�r�h�l�n�����̊K�i��艺�����I����A���̃C���h�l�̃{���e�[�W���ō����ɒB�����Ƃ���ŁA�ϋq�Q���^�̃C�x���g�ɂȂ����B�������C���h�l�͐ϋɓI���B���̂�����������q���������X�e�[�W�삯��B�܂��͐��l�̊ϋq���X�e�[�W�ɏオ���āA�`�r�h�l�n�ƈꏏ�Ƀ_���X��x�����B���y�́uDil Chahta Hai�v�́uWoh Ladki Hai Kahan�v�B���̋Ȃ̃_���X�Ƃ����A���r�����ɍL���Ē��̂悤�Ƀp�^�p�^�������̂��L�����B�������`�r�h�l�n���x�����̂̓n���C�̃t���_���X�̂悤�ȓ����������B������ƐU��t�����Ⴄ���A�`�r�h�l�n�I���̌�A�ϋq�ƈꏏ�ɕБ��łǂꂾ�����Ă邩�Ƃ��A�ꏏ�Ɏʐ^���B������Ƃ��A���낢��A�g���N�V�������������B
�@�C���h�ɏZ��ł���ƕ��i�A�C���h�l���Ă������Ȃ��A�Ƃ��A�C���h�l���đʖڂ��Ȃ��A�Ƃ��v�����肷����̂����A��������́A���{�l���Ă������Ȃ��A�Ǝv�����B�����炭����������C���h�l�����������v�������낤�B�`�r�h�l�n�������q�������̒����珫���C���h�̃��{�b�g�H�w��S���l���o�Ă��邩������Ȃ��B���݂̃C���h�̃��{�b�g�Ƃ����Ƃ��ꂾ����ȁE�E�E�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�C���h���{�b�g�H�w�̌���
�u�_���X�L���O�v |
�� |
�@�������A�`�r�h�l�n�����Ď��������{�l�ł��邱�Ƃɏ����ւ���������B���x�P�P���ɂh�b�b�q�iIndian Council for Cultural Relations�j��Â̊O���l���w�������𗬃C�x���g������A���{�l���w���������o���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B�ꉞ����ɖ~�x��ł����悤���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A�`�r�h�l�n�ɗx���Ă������������Ɏ�̂����E�E�E�B
�@�Ƃ���ŕςȘb�ɂȂ邪�A�`�r�h�l�n�����Ă��ĂӂƎv�������Ƃ�����B�Ȃ����{�b�g�Ƃ����̂͊�{�I�ɒj�Ɍ�����̂��낤���H�`�r�h�l�n�̐��͒j�̎q�̐��ŁA�i��̂��o��������̋^����Ȃ��Ɂu�K�[���t�����h�͂���̂��ȁH�v�u�Ƃ��Ă��n���T���ˁv�Ƃ������Ă����B�`�r�h�l�n���j�ł���Ƃ́A�`�r�h�l�n���E�F�u�T�C�g�ɂ��ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��Ǝv���̂����B�܂��A��̃��{�b�g���o�Ă��閟������Ă��A�j�^�̃��{�b�g���嗬�ŁA���^�̃��{�b�g�͒j�^�̃��{�b�g�Ƀ��{������������A�����ς���������A�s���N�F�ɂ����肵�ĂȂ�Ƃ����̂悤�Ɍ����Ă��邾�����B�`�r�h�l�n���͂��߁A���낢��ȃ��{�b�g���o�ꂵ���邪�A�l�^���{�b�g�Ƃ����̂́A�ǂ���̐��ʂ��Ƃ����قڑS���j�Ƒ��ꂪ���܂��Ă���悤�ȋC������B�܂胍�{�b�g�Ƃ����̂͂Ȃ����j����{�`�ł���B����A���R�E�ł́A������̔����̉ߒ��ōŏ��͑S�����ŁA�j�̈�`�q�������͓̂r������j�ɕω�����B�܂莩�R�E�ł͏�����{�`�Ȃ̂��B�l�H�̐��E�Ǝ��R�̐��E�̈Ⴂ�̍��{�������ɂ���悤�ȋC�������B
�@��i���قǓ��ɓ�֎Ԃ������ƌ����邪�A�C���h�ɂ��X�N�[�^�[��o�C�N�Ȃǂ̓�֎Ԃ������B��̑O�܂ł͓�֎Ԃ͒����K���̏ے��A�l�֎Ԃ͏㗬�K���̏ے��ɂȂ��Ă������A�ŋ߂ł͒����K�����l�֎ԂɎ肪�͂��悤�ɂȂ�A��֎Ԃۗ̕L�҂̑w�����̕��ւƂ��Ȃ�L�����Ă����B���Ɏ�҂ɂƂ��ăo�C�N�̓X�e�[�^�X�E�V���{���ł���B�������̗L���Őg�����͂����鍑�Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����o�C�N������Δޏ����ł���Ƃ����b�����������Ƃ�����B
�@�������o�C�N�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����A�ŋ߂̃C���h�̓s�s���ł́u�����Ă��邩�����Ă��Ȃ����v�Ƃ������l�����A�u���������Ă��邩�v�Ƃ������l��ɂ���ƈڍs������Ɗ����Ă���B�Ⴆ�Γ��{�ł��e���r�A�①�ɁA����@���O��̐_��ƌĂꂽ���オ�������B���̍��̓��{�ł͂����炭���L���Ă��邱�ƂɈӖ�������A�X�e�[�^�X�����������낤�B�C���h���������������A�_���ł͂܂��������낤�B�����A�f���[�����Ă݂�ƁA�ǂ�ȕn�����Ƃɂ��i���Ƃ��X�����X�̏Z�l�ł��j�I���{���ł��Ƃ肠�����e���r��①�ɂȂǂ��������肵�āA����ɏ��L���Ă��邱�ƂɈӖ����Ȃ��Ȃ��Ă����B�����Ńf���[�Ȃǂ�����Ǝ��̃X�e�[�W�A�u�ǂ�Ȑ��\�̂��̂������Ă��邩�A�ǂ�ȃX�^�C���̂��̂������Ă��邩�v�Ƃ����A�@�\���A�f�U�C�����ɉ��l����ڍs���Ă����B�܂�A�������\�̂��̂�A�������������̂������Ă���l���X�e�[�^�X��̂ł���B���ꂪ�߂���A���x�͓��{�̌��݂̂悤�Ɂu�ǂ̉�Ђ̐��i���A�ǂ̃u�����h���v�Ƃ����u�����h��`�ֈڍs����̂��낤�B
�@������ƑO�܂ł̃C���h�̃o�C�N�Ƃ����Ɗ��S�Ɏ��p��`�������B�C���h�l�̃o�C�N�̕]����͂܂����ɔR��ł���A��R��̂P�O�O�����ȉ��̃o�C�N���嗬�������B�V�[�g�͕���ɂȂ��Ă���A�R�`�S�l������₷���悤�ɂł��Ă�����̂��l�C���B�������^�]���A���ɍ��������ꂳ��Ƃ̊ԂɎq�����P�l���Q�l����A�܂��q���������炨������̑O�ɂ���l�q��������Ƃ����u��Ƒ����Ă��o�����X�^�C���v�̓C���h�̔��܂������i�ł���i�@���ł͂R�l���ȏ�͈�@�����j�B�������Q�P���I�ɓ����Ă���C���h�̃o�C�N��Ёi�q�[���[�E�z���_�A�J���T�L�E�o�[�W���[�W�A�s�u�r�X�Y�L�A���}�n�A�k�l�k�Ȃǁj���A�P�O�O�����I�[�o�[�̋@�\�d���A�f�U�C���d���̃o�C�N���ǂ�ǂ����Ă����B��C�Ƀo�C�N�s��͂P�O�O������ւƈڍs���A�f�U�C�������{�l�̍D�݂ɂ��Ȃ��悤�Ȃ��̂��o�Ă����B
�@�l�͉Ƃ���P�O�������ꂽ��w�ɒʂ����߂Ƀo�C�N�����Ǝv���Ă���A���Ӑ[���C���h�̃o�C�N�s������Ă����B�_���͂�͂�P�O�O�����䂾�����B���݂̃C���h�̔���o�C�N�͉��ƌ����Ă��J���T�L�E�o�[�W���[�W�̃p���T�[�ł���B�P�T�O�����ƂP�W�O����������A���ɂP�W�O�����̓X�e�[�^�X�E�V���{���ƂȂ��Ă���B�p���T�[�̃q�b�g�̂������Ńo�[�W���[�W�͋}���ɃV�F�A���L������B�����o�[�W���[�W�̃G���~�l�[�^�[�̓A�����J���E�^�C�v�̃o�C�N�ŁA������P�W�O�����B�����_�ŃC���h�ň�ԍ����o�C�N�ɂȂ��Ă���A��͂肱����X�e�[�^�X�E�V���{���ł���B����A�q�[���[�E�z���_�̂b�a�y�͗��j�̒����P�T�O�����o�C�N�ł���B�s�u�r�X�Y�L���t�B�G���e�Q�Ƃ����P�T�O�����o�C�N���o���Ă���B����������ׂ������Ŕ���Ă���̂͂k�l�k�Ƃ�����Ђ̂P�P�O�����o�C�N�A�t���[�_�����B�ŋ߂ɂȂ��ă��j�N�����݂̃J���[�U���ɏo�Ă��āA�s���N�Ƃ��I�����W�Ƃ��N���[���F�Ƃ��A�Z���X���^���悤�ȐF�̃t���[�_�����C���h�̓��Ɉ���悤�ɂȂ����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
|
Kawasaki Bajaj - Pulsar180 |
|
|
 |
|
|
Kawasaki Bajaj - Eliminator |
|
|
 |
|
|
Hero Honda - CBZ |
|
|
 |
|
|
TVS Suzuki - Fiero F2 |
|
�@�����������Ƃ��C�ɂȂ��Ă����̂́A�q�[���[�E�z���_�����M�������č��N�V���ɑ���o�����A�C���h���̂Q�O�O�����I�[�o�[�o�C�N�A�J���Y�}�ł���B�r�C�ʂQ�Q�R�����A�ō������P�Q�T�����A�����ăX�|�[�e�B�[�ŃX�^�C���b�V���ȃf�U�C���́A���ݔ����Ă���C���h�̂ǂ̃o�C�N�������킷��B�s�u�b�l�ł̓C���h�f��̑�X�^�[�A���e�B�N�E���[�V��������`�����Ă���A�q�[���[�E�z���_�̋C���̓�������f����B
�@�Ƃ���ŁA��ɋ������o�C�N�̑��ɁA�C���h�ɂ͂����ЂƂ́u�嗬�v�����݂���B�C���h�̎l�֎ԊE�ɃA���o�T�_�[�Ƃ������삪����悤�ɁA�C���h�̓�֎ԊE�ɂ̓��C�����E�G���t�B�[���h�Ƃ����J���X�}�I�o�C�N��Ђ�����B�G���t�B�[���h�̃o�C�N�͂ǂ���N���V�b�N�Œj�炵���O�ςł���A�r�C�ʂ��R�T�O�����`�T�O�O��������o�C�N���肾�i��ŃJ���Y�}���u�C���h���̂Q�O�O�����I�[�o�[�o�C�N�v�ƕ\���������A����̓C���h�l�̕\���ł���B�G���t�B�[���h�͕ʊi�̂悤���j�B�G���W����������ƃh�h�h�h�h�Ƃ����剹�ʂ��A���ȃ��b�O�K�[�h�͑����Ђǂ��]�|������^�]��ƃo�C�N�{�̂����B�������̏Ⴕ�₷���̂���_�ŁA���ɓd�C�n���������ɂ�����邻�����B�����A�A���o�T�_�[�Ɠ����Ō̏Ⴕ�₷�������₷���Ƃ����o�C�N�Ȃ̂ŁA���������Ɏ����Œ����Ă��܂��Ƃ���������Ƃ��낾�B���{�ɂ��G���t�B�[���h�̃}�j�A�͂�����������悤�ł���B���˂Ă���A�C���h�ɗ����琥��G���t�B�[���h�̃o�C�N�����Ă݂����Ǝv���Ă����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
Royal Enfield - Thunderbird |
�� |
�@�ŋ߂ɂȂ��ăJ���T�L�E�o�[�W���[�W���E�C���h�P�Q�T�Ƃ����P�Q�T�����̂����������\�̗ǂ������ȃo�C�N���o������A�܂����}�n����r�C�ʂ̃A�����J���E�o�C�N�A�h���b�O�E�X�^�[��N���ɏo���Ƃ����\�����ꂽ��A�J���Y�}�ɑR����`�ŃJ���T�L�E�o�[�W���[�W��s�u�r�X�Y�L���Q�O�O�����I�[�o�[�̃X�|�[�c�E�o�C�N���������Ă���Ƃ����b�������ɋ���ƁA�ǂ�ɂ��悤���A�҂��������������A���ɖ����Ă����B�������A�s�u�b�l�B�e�Ŏv�������Ȃ��Վ����������������ƂɌ㉟������A�J�G���������̂��ЂƂ̌_�@�Ƃ��āA���Ƀo�C�N�w���ɓ��ݐ����B�{���ɂ��낢����������l���ŏI�I�ɑI�̂̓q�[���[�E�z���_�̃J���Y�}�ł���B
�@�J���Y�}��I����ł́A�����̃M�A�y�_���������B���{�̃o�C�N�͂ܐ�݂̂ŃM�A���グ��������悤�ɂȂ��Ă��邪�A�C���h�̃o�C�N�́A�T���_���𗚂��Ă��Ă����삵�₷���悤�Ɂi�H�j�A�M�A�A�b�v�̂Ƃ��͂����Ƃ��g���悤�ɂȂ��Ă���B�z���_�̃J�u�Ɠ����^�C�v���B�l�͂��̃C���h���̃M�A�y�_���������������̂ŁA���{���̃M�A�y�_�����������J���Y�}�ɐS�������ꂽ�i���̂Ƃ��늮�S�ɓ��{���̃M�A�y�_�����������o�C�N�̓J���Y�}�����ł���j�B�܂��A�C���h�̃o�C�N�ɂ͕K�����b�O�K�[�h���t���Ă��邪�A�J���Y�}�ɂ͕t���Ă��Ȃ��B������J���Y�}�̂����������Ƃ��낾�B
�@�J���Y�}�̊O�����A�l���̎����Ă����o�C�N�Ɏ��Ă������Ƃ��w���̓��@�ɂȂ����B�l�͓��{�ł̓��}�n�̂e�y�S�O�O�Ƃ����S�O�O�����̃o�C�N�ɏ���Ă������A�C���h�ɗ���O�ɔ����Ă��܂����B�P�X�X�V�N�`�P�X�X�X�N�̊Ԃɂ��������Ȃ��������̃o�C�N�ł���A���������������������̂ŁA���̖ʉe���c��J���Y�}�ɂ͈�ڍ��ꂵ���B
�@�J���Y�}�̓C���h���ꂵ���f�U�C�������Ă���̂ŁA���Ŕ��ɖڗ��B�܂��V�����o�C�N�Ȃ̂ŁA�݂�Ȃ��璍�ڂ����B���̖ڗ��_���}�C�i�X�E�|�C���g�ɂ��Ȃ�A�v���X�E�|�C���g�ɂ��Ȃ�ƍl�����B�}�C�i�X�E�|�C���g�́A���Ԓ��Ɉ��Y���ꂽ��x�^�x�^�G��ꂽ�蓐��̕W�I�ɂȂ����肵�₷�����Ƃ��B�������v���X�E�|�C���g�͑��s���ڗ����߁A���ӂ��Ă�����Ď��̂ɑ����\�����������邩���A�Ƃ������Ƃł���B����ɑ������炻���Ŗl�̃o�C�N�l�����ЂƂ܂��I���Ȃ��������A��ʎ��̂ɑ�������l�����̂��̂��I����Ă��܂��B�C���h�ł͂Ƃɂ����ڗ��o�C�N�������ƍl�����B
�@���Ȃ݂Ɂu�J���Y�}�iKarizma�j�v�Ƃ������O�́A�p���charisma�i�J���X�}�j�ƁA�q���f�B�[��̃J���V���}�[�i��Ձj�������č��ꂽ���ꂾ�Ǝv���邪�A����ȊO�ɂ����{��̃C�i�Y�}�i��ȁj���W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ[�ǂ݂��Ă���B�ǂ���ɂ���A���������������������O�ł�����C�ɓ����Ă���B�����A�ɂ��ނ炭�̓C���h�l�̒��ɃJ���Y�}�̂��Ƃ��u�J���W���}�v�Ɣ�������l���������Ƃ��B
�@�o�C�N�͌��܂������A�F�ł������ɖ������B�J���Y�}�ɂ͐ԁA�A���A���A��A���A���̂V�F���������B�l�������Ă����e�y�S�O�O�͋�F�������̂ŁA��F�̃J���Y�}���܂�����₾�������A�悭���Ă݂�ƃJ���[�����O�̓_�ŏ��������������Ƃ��낪����A��͎~�߂邱�Ƃɂ����B�����Ă����͂�͂�C���h�f��t�@���Ƃ��āA�s�u�b�l�Ń��e�B�N�E���[�V����������Ă���Ԃ��J���Y�}�����Ƃɂ����B������e�B�N�E���[�V�����E���f���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�C���h�ŊO���l���o�C�N���w������Ƃ��ɂǂ�ȋK��������̂��A�悭������Ȃ��B�l�̗F�l�ʼn��l�����o�C�N�������A���ꂼ��K�v���������ނ͂܂��܂����B���ɂ͑�Ƃ���̃R�l�ŁA�قƂ�lj��̏��ނ��v�����ꂸ�Ƀo�C�N�����l������B�l�̏ꍇ�͑�g�ق���̃��^�[��v�����ꂽ�B�܂��A�f���[�ł̓C���h�l�ł��O���l�ł��o�C�N�w���ɐ��{����̎w���ŏZ���ؖ������K�v�ł������ŁA�ׂ̃n�����[�i�[�B�ɍs�����炨����������ΊȒP�ɔ����Ă��܂��炵���i�n�����[�i�[�E�i���o�[�ɂȂ邪�j�B���Ȃ݂Ƀn�����[�i�[�E�i���o�[�̎����Ԃ͌x�@�ɕ߂܂�ɂ����Ƃ����b�����������Ƃ�����B�x�@���̓n�����[�i�[�o�g�̐l���������炾�B�{�����낤���H
�@���傤�Ǎ����̓_�V���w���[�̂X���O�A�i�����[�g���[�̑����ڂ������B�X��������ɂ̓s�[�g���E�p�N�V���Ƃ������Ԃ�����A���̎����ɐV�������Ƃ��n�߂���V�������̂����肷�邱�Ƃ͕s�g���ƐM�����Ă��邽�߁A�C���h�l�͍��������������Ȃ��B�������i�����[�g���[�ɂȂ�ƁA�C���h�l�̎U���V�[�Y���ɓ˓�����B�i�����[�g���[����_�V���w���[�A�����ăf�B�[���[���[�܂ŁA���̎����̃C���h�l�͒��ϋɓI�ȏ���s��������B�����Ƃ��Ă����̎�������N�ň�Ԃ̉҂����Ȃ̂ŋC��������B�܂��A���z�̌�����������������A�Ƃɒu���Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�D�_�A�X���A����������̂����̎����ł���B�l�͕ʂɉ����C�ɂ����Ƀq�[���[�E�z���_�̃V���[���[����K��ăJ���Y�}�����̂����A���܂��܃i�����[�g���[�̑��ڂ������̂ŁA��������̐l���V���[���[���ɗ��Ď��X�ƃo�C�N���čs���Ă����B�J���Y�}����Ԃ悤�ɔ���Ă����B�����x��������Ԃ��J���Y�}�������Ă��܂��Ƃ��낾�����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
Hero Honda - Karizma |
�� |
�@�����J���Y�}�ɏ���ăf���[�𑖂����Ă݂��B�S�O�O�����̃o�C�N�ɔ�ׂ�ƃp���[�͗�邪�A�ł����{�̃o�C�N�Ɠ������o�ŏ�邱�Ƃ��ł��邢���o�C�N���Ǝv�����B�����A�V�[�g�������̂ŁA������x�g�����Ȃ��Ə�肱�Ȃ��Ȃ����낤�B���̃^�C�����r�C�ʂɔ�ׂčׂ����ƂƁA�~���[�̈ʒu���Ⴂ���Ƃ������C�ɂȂ������x�������B�܂����炵�Ȃ̂Ŏ����T�O�����ȉ��ő��s���Ă���Ƃ���ł���B
�@���N�X�����{�ɂȂ�ƁA���@�T���g�E�N���W�ɂ�����{�l�w�Z�ʼnčՂ肪����B���N�����R�̂��ƂȂ���J�Â���A���R�̂��ƂȂ���l���s���Ă݂��B���{�ɏZ��ł���l�ɂƂ�����A�u�X���ɉčՂ�Ƃ͂��ꂢ���ɁH�v�Ƃ����������낤���A��x�čՂ�ɗ��Ă݂�A�u�X���ɉčՂ�Ƃ����̂������Ȃ��v�Ǝv�����낤�B�čՂ�̓��A���{�l�w�Z�̕~�n�ɑ��ݓ��ꂽ�u�Ԃ���A�ˑR���{�Ƀ��[�v�����悤�ȍ��o�Ɋׂ�B���ɂ͓��{�̍ŐV�q�b�g�Ȃ�����A�����ɂ͖~�x��̘E���������A�f���[���̓��{�l���W�����Ă���B��N�͂W�O�O�l���K�ꂽ�������B
�@���{�l�w�Z�čՂ�ɂ����āA�w���Ƃ��Ă����Ƃ��C�ɂȂ�̂͌Ö{�̔��ł���B�čՂ�ł͓��{��̖{���i���Ŏ�ɓ���B���N�͑�l�����̖{���R���Q�O���s�[�������B�w���͊J�X�Ɠ����ɌÖ{�̔��̂Ƃ���֑���ׂ��B�������c�O�Ȃ��獡�N�̌Ö{���͋��N�ɔ�ׂĕi�������悭�Ȃ������B�C���h�W�̓��{��̖{�����X�g�E�����e�b�h�������̂����A�قƂ�nj�������Ȃ������B�C���h�ɊW�Ȃ��{���肾�B���ʂ̐l�ɂƂ�����A�C���h�ɗ��Ă܂ŃC���h�̖{�Ȃ�ēǂ݂����Ȃ����Ă��Ƃ��낤���H
�@�čՂ�̂����ЂƂ̊y���݂Ƃ�������A�i�w���́j���i�H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����{�H��H�ׂ��邱�Ƃ��B�������A�ӂƋC���t���Ă݂�ƁA���{�H�ޓX�x�����������|�������ł��Ă���A���܂���{�H�ɑ��銉�]�����Ȃ��Ȃ��Ă����B���N�ɔ�ׂē��{�H�ɂ������@��i�i�ɑ��������A���X�l�͕a�C�ɂł��Ȃ�Ȃ�����C���h���������ł��������Ă�����̂ŁA����̉čՂ�ł͐H�ׂ���ɂ��܂�_�o�������Ȃ������B����f���[�ݏZ�̓��{�l�̐��������サ�Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@�~�x����ɂ��Q�����A���Ɛ^���ɗx���Ă݂���Ȃ��Ȃ����������������B������������������猩���ʍӂ����B���Ȃ�S�����̂����A�P�C���߂�Ȃ������B���̑��A�t���[�L�b�N���{�[���˓I���A�y�����A�g���N�V�������������B�čՂ�͌ߌ�T���`�W���܂łȂ̂����A���������x���܂ł���Ă������̂ł́A�Ǝv�����B
�@�čՂ蒆�A�x�����������|��������`������A�V���Ȓm�荇�����ł����肵�āA���N���l�I�ɗL�Ӌ`�ȃC�x���g�������B
�@�Q�V���ƂQ�W���̗����A�`���[�i�L���[�v���[�ɂ���^�C��g�قŃ^�C�����t�F�X�e�B�o���uAmazing Thai Taste�v���J�Â���Ă����B�^�C�l�̗F�B�ɗU���Ă������A�^�C�����͑�D���Ȃ̂ŁA���R�K�ꂽ�B��������͍s�����̂����A�p���������ĂP���Ԃ�������Ȃ������B�����͂Q���`�U���܂ł����ƃ^�C��g�قɂ����B
�@�^�C�����t�F�X�e�B�o���ɂ́A�u���[�E�G���t�@���g�A�X�p�C�X�E���[�g�A�o�[���E�^�C�A�o���R�N���P�ȂǂȂǂ̃f���[�ɂ���^�C�������X�g�����������o�X���Ă������A�^�C�̎G�݂�A�����i�Ȃǂ��̔�����Ă����B�����͏������߂ŁA�ǂ̐H�ו������������P�O�O���s�[�O�ゾ�����B���������̖��͖{�i�I�B����H�ׂ������Łu����߂��`�I�v�Ƌ��Ԃقǂ������B����ς�^�C�����͂��܂��B�C���h�����Ɣ�ׂ�ꂽ�獢�邪�A��ʘ_�Ƃ��Ă�͂���{�l�ɂ̓C���h���������^�C�����̕������ɍ����̂��낤�B���̑��A�����u�[�^���A�}���S�X�`���A�O�@�o�Ȃǂ̃^�C�̃t���[�c�������ŐH�ׂꂽ��A�^�C�����V���n�E�r�[�����U�O���s�[�Ŕ̔�����Ă����B
�@�����H�ׂĈ���Ŕ��������łȂ��A�������C�x���g���p�ӂ���Ă����B�Q���Ԃ��Ƃɍs����̂����b�L�[�E�i���o�[�B���ꌔ�i�W�O���s�[�j�Ƀi���o�[���L�ڂ���Ă���A���ꂪ���I�ԍ��ƈ�v����ƁA�V���c�A�V���[����A�^�C�������X�g�����ł̃f�B�i�[���Ȃǂ����炦���B�������l�̔ԍ��͓�����Ȃ������B����ȂƂ���ʼn^���g���Ă��d���Ȃ��̂ł܂������Ƃ��悤�B
�@�^�C�̌ÓT���x�̃p�t�H�[�}���X�Ȃǂ��������B���ł��ʔ��������̂́A�^�C�̃}�[�V�����E�A�[�c�B��l���_�������A������l���g���t�@�[�������āA�g�ݎ�̂悤�Ȋ����Ŗ͋[�I�ɐ키�̂����A�R���f�B�[�d���ĂɂȂ��Ă���A���������y���������B�^�C�����̎��������Ȃǂ��������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�^�C�̃}�[�V�����E�A�[�c |
�� |
�@��������͕������ς��H�ׂ܂���A���̌㕠�̒��q�����������Ȃ����قǂ������B�ł����낻��^�C�ɂ������s�������Ȃ��Ă����ȁE�E�E�B
�@���܂Ńo�X��I�[�g�E���N�V���[�𗘗p���ăf���[�s�����ړ����Ă����̂����A�o�C�N����ɓ������̂ŁA�ړ����i�i�Ɋy�ɂȂ����B�I�[�g�̔����̎��ԂŖړI�n�ɒ������Ƃ��ł��邵�A�ړ���̐ߖ�ɂ��Ȃ�B����Ƀo�C�N�ő���Ƃ܂�������f���[�������Ă�����̂��B
�@�C���h�Ŏ����Ԃ��^�]����Ƃ����ƁA�Ƃɂ����댯�ȃC���[�W������B�C���h�l�͌�ʃ��[�������Ȃ��A�Ƃ������m��Ȃ����A�^�]�Ƌ����x�͋@�\���Ă��Ȃ��ɓ������̂Ŕނ�̉^�]�Z�p������ӂ₾���A������������Ƃ肠�����˂����ނƂ������i�̐l�������̂ŁA�m���ɓ��{�ʼn^�]����Ƃ��Ƃ͈�����N�w�������ĉ^�]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��Ⴄ�̂́A�N���N�V�����̎g�p�p�x���낤�B���{�ł̓N���N�V�������g���@��͂��܂�Ȃ����A�C���h�ł͂Ƃɂ����N���N�V�������g���Ď��Ȏ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ���Ƃ����������̂̓E�C���J�[�����N���N�V�����ł���B�u���荇���v�Ȃ�Ă��̂��C���h�̓��H�ɂ͑��݂��Ȃ��B�Ƃɂ����s����Ƃ���܂őO�i���A�ǂ���������Ȃ��Ȃ����炻���ŏ��߂Ăǂ����邩�l����Ƃ����K���ɂȂ��Ă���B���ɐM������d�ɂȂ��ď������Ƃ��Ȃǂ͂Ђǂ��B�M�����������u�ԁA�l���̓�����M���҂������Ă����Ԃ���C�Ɍ����_�����։����A�哱���̎�荇��������B�l�����{�ŖƋ���������Ƃ��́A�u���낤�^�]�v�ł͂Ȃ��u��������Ȃ��^�]�v�����Ȃ����ƌ���ꂽ���A�C���h�ł́u���낤�^�]�v��y���ɗ��킵���u������^�]�v�ł���B�Ƃɂ����{�f�B�[�����đΌ��Ԃ��낤���㑱�Ԃ��낤���A�������~�߂Đi�ނƂ����^�]�@���B�l�͓��{�̉^�]�@���g�ɐ��ݕt���Ă���̂ŁA���{���̈��S�^�]�����Ă�����肾���A�C���h�ł͂��ꂪ�������Đg�̊댯���������Ƃ����肤��B
�@�������A�����̂��Ƃ��l���ɓ���Ă��A���ǃf���[�͉^�]����̂ɉ��K�ȊX���Ǝv���B���ɖl�̏Z�ޓ�f���[�́A��{�I�ɔ��ɉ��K�ȃh���C�u�����邱�Ƃ��ł���B���������������Ĉ��S�Ȃ��炢���B��f���[�̎�v�����͓������L���A�ܑ��������Ƃ���Ă���Ƃ��낪�����B�������̂��������A�����̓��Ɍ��⋍�����邱�Ƃ͋H�ł���B��ʗʂ����b�V���E�A���[����������قǂЂǂ��͂Ȃ��B���������т�t���C�E�I�[���@�[�Ȃǂ����X�Ɗ����������B�����̂������łt�^�[�������ɂ����ƃf�����b�g�͂�����̂́A���S���͊m���ɑ������B�`���[�i�L���[�v���[����C���h��ɂ����Ă̒n��Ȃ͌����_�Ƀ��[�^���[���ݒu����Ă���̂ŁA�������������₷���̂����A�����m���X�g�b�v�ł����Ƒ��s���邱�Ƃ��ł���B��f���[�ł��Ђǂ����͂��邪�A����I��ňړ�����Δ��ɉ��K�ȑ��s�����邱�Ƃ��ł���B����ȗ��h�ȓ��H�̂����s�́A���ɂ��܂�Ⴊ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������炢���i���ǃC�M���X�l�̒u���y�Y�Ȃ̂����j�B�C���h�l�̂Ђǂ��^�]�����������Ă��A�����Ԃ̉^�]�͐�ɓ����̕�����Ȃ��B�C��t����ׂ��Ȃ̂́A�C���h�l�̉^�]�ƁA�Ƃ���ǂ���ɂ���X�s�[�h�E�u���[�J�[�ƁA�ˑR���H�ɊJ���Ă��錊�݂̂��B
�@��f���[�ɔ�ׂ�ƁA�k�f���[�͂܂��܂��Ђǂ��B���H�����܂�ܑ�����Ă��Ȃ��̂œ��������Ƃ��낪�������A�����ԁA���]�ԁA�T�C�N���E���N�V���[�A���ԂȂǂ����R��̂ƂȂ��Đi�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������������肷��̂ŁA�_�o���g���B��ԂЂǂ��̂̓f���[�E���g���̌�����ł���B�n���S�����߂̋������̃J�o�[�̏�𑖍s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��낪����̂����A�c���c������̂œ�֎Ԃ͂��Ȃ��Ȃ��B�������������Ă��炢�������̂��B�k�f���[�ɂ͂��܂�s�������Ȃ��Ƃ����̂��{�����B
�@�܂��A�f���[�̓��Ŋy�����̂́A���[�ɂ��낢��Ȉ�Ղ�����A�����̈�Ղ��y���݂Ȃ��瑖�s���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��B�Ⴆ�h�r�a�s�߂��̃����O�E���[�h�B���[���E�L���[�̂������𑖂邱�Ƃ��ł��邵�A���[���E�L���[�Ɨׂ̃T���[���K���E�t�H�[�g�̊Ԃɉ˂��郀�K�������z���ۂ����������蔲���邱�Ƃ��ł���B�v���K�e�B�E�}�C�_�[���߂��̓��ł̓v���[�i�[�E�L���[�̈Зe���ԋ߂Ɍ��Ȃ��瑖�邱�Ƃ��ł��邵�A�t�}�[���[���_�̑O�ɂ��郍�[�^���[�́A�_���K�[�����̂܂܃��[�^���[�ɂȂ��Ă���B�����O�E���[�h���牓���Ɍ�����t�}�[���[���_�͗[�����ɔ������B�܂��A������ʂ��Ă���Ǝv��ʂƂ���ňӊO�Ȉ�Ղɏo���킵���肷�邱�Ƃ�����A�Ȃ��Ȃ��y�����B
�@�����������̂������B�X�s�[�h�ᔽ�ł������^�]�ł��m�[�w���ł����Ƌ��^�]�ł��M�������ł��A�x�@�ɕ߂܂����由���ꗥ�P�O�O���s�[�ł���i�C���h�l�����ɂƂ��Ă͈����Ȃ����j�B�ŋߔ����卑�����i�ޓ��{�Ƃ͑�Ⴂ�ł���B�������x�@�͊O���l�ƌ���ƂP�O�O�O���s�[�ȏ�̔�����v�����Ă��āA�قƂ�ǂ����ɂ��܂����ނ̂����A�P�O�O���s�[���������Ă����Ε���͌�����؍����͂Ȃ��B�ᔽ�^�]������ȂɋC�y�ɂł��鍑�����ɂȂ����낤�i�ʂɈᔽ�͂��Ă��Ȃ����j�B
�@�Ƃ���ŁA���̂Ƃ���l�̃J���Y�}�͒��q�悭�����Ă���Ă���B���݂Q�O�O�����قǑ��s�����B�J���Y�}��I��ł悩�����ƐS��v���Ă���B�J���Y�}���̂ɖ��͂Ȃ��̂����A�����Ă���͍̂����ł���B�P���O�ɒu���Ă����������ō����܂邯�ɂȂ�B����A�ܑ�����Ă��Ȃ����ԏ�ɒ�߂Ă�������A�������R���ԂŊ��ɍ����炯�ɂȂ��Ă����B�����͍������A�ƕ�������������Ȃ�قǂ��B�C���h�l�͑����A�Ƃ̑O�̓���|���|������K��������̂����A����ɂ���Ċ����オ�������o�ł��o�C�N�͍����炯�ɂȂ�B�Ƃɂ������ɂ͋�������Ă���B
�@�����͋v�X�ɂo�u�q�A�k�p���S�ʼnf��������B�l���ۛ��̒j�D�A���[�t���E�{�[�X�剉�́uMumbai Matinee�v�B��T�̋��j�����畕��ꂽ�V��f��ł���B�L���X�g�̓��[�t���E�{�[�X�A�p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[���A���B�W���C�E���[�Y�A�T�E���u�E�V���N���ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
Mumbai Matinee |
�� |
| Mumbai Matinee |
�@�����o�C�[�̍L���㗝�X�ɋ߂�f�[�u�[�i���[�t���E�{�[�X�j�͂R�Q�̓���ŁA��������Ȃ�Ƃ�������̂Ă邱�Ƃ�����l���Ă����B������f�[�u�[�͋��R����`���V����ɓ����B���̃`���V�ɂ́A�ǂ�ȔY�݂ł���������o�[�o�[�E�q���h�D�X�^�[�j�[�̍L�����ڂ��Ă����B
�@�f�[�u�[�̓o�[�o�[�E�q���h�D�X�^�[�j�[�ɑ��k���邽�߂Ƀz�e���E�s�J�f���[��K���B�����̂P�K�ŏo������̂́A����Ȃ��f��ēj�e�B���E�J�v�[���i�T�E���u�E�V���N���j�������B�f�[�u�[�ƃj�e�B���͂����ɒ��ǂ��Ȃ邪�A�j�e�B���ƂQ�K�ɏZ�ރo�[�o�[�͌����̒��������B�j�e�B���̓o�[�o�[�ɑ��k���邱�Ƃ����߂Ȃ����A�f�[�u�[�͂Q�K�ւƏオ���čs���B
�@�o�[�o�[�E�q���h�D�X�^�[�j�[�i���B�W���C�E���[�Y�j�͕������ɏ���ϐl�������B�o�[�o�[�̓f�[�u�[�ɕςȖ��n���B���̖������}�Ƀf�[�u�[�̓I�t�B�X�̃Z�N�V�[�E�K�[���A�A�k�[�V���[�ɂ��Ă�悤�ɂȂ������A����͊��Ⴂ�������B�����������悤�Ƃ�����f�[�u�[�̓r���^�����B
�@�Ăуf�[�u�[�̓o�[�o�[�̌���K���B���x�̓o�[�o�[�̓f�[�u�[�t�h�֘A��čs�����A�^�����x�@�̎����ɏo���킵�Ă��܂��A�ނ͑ߕ߂���Ă��܂��B�j�e�B���̋@�]�ɂ��f�[�u�[�͂Ȃ�Ƃ��ߕ������B
�@����A�f�搧��ōs���l���Ă����j�e�B���́A�ь������Ă����o�[�o�[�E�q���h�D�X�^�[�j�[�̌��֑��k�ɖK���B���̂Ƃ��o�[�o�[���j�e�B���ɒ�Ă������Ƃ́A����ׂ��v�����������B
�@�O�x�o�[�o�[�̌���K�ꂽ�f�[�u�[�́A�o�[�o�[�Ɍ�����܂ܗ��ɂȂ��ĉ^��������B�����������������̂��߂��͕�����Ȃ������B
�@���ꂩ�炵�炭��A�f�[�u�[�̓j�e�B�����ē����f�悪���J���ꂽ���Ƃ�m��A�F�l�ƈꏏ�ɉf��ق��ɍs���B����������͂Ȃ�ƃ|���m�^�b�`�̉f��ŁA�j�D�͂Ȃ�ƃf�[�u�[�������B�o�[�o�[�̂Ƃ���ŗ��ʼn^���������Ƃ��ɁA�����Ƀr�f�I�J�����ŎB�e����Ă���A�����ŏ���Ƀ|���m�f��ɏo���������Ă��܂����̂��B�������^�̈������Ƃɂ��̉f��͑�q�b�g���A�f�[�u�[�͈��Z�b�N�X�E�X�^�[�Ƃ��ėL���ɂȂ��Ă��܂��B����Ȃ̂ɃZ�b�N�X�E�X�^�[�Ƃ́I�f�[�u�[�͓{���ăz�e���E�s�J�f���[�։��������邪�A�j�e�B�����o�[�o�[�����ɂ��Ȃ������B�f�[�u�[�͐E�������A��Ƃ���Ƃ�ǂ��o����Ă��܂����B
�@�x���`�ɍ����Ă��傰�Ă���f�[�u�[�̌��ֈ�l�̏����������B�W���[�i���X�g�ŁA�Z�b�N�X�E�X�^�[�̃f�[�u�[�ɃC���^�r���[�����ɗ����̂������B�ޏ��̖��O�̓\�[�i�[���[�i�p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[���j�Ƃ������B�\�[�i�[���[�͉Ƃ̂Ȃ��f�[�u�[������ɔ��܂点�āA�ނ̘b���B�b���Ă�����Ɏ���ɓ�l�͗��ɗ�����B�������f�[�u�[�͋��������Ƃɂ́A���͔ޏ��������������B�₪�ē�l�͂߂ł����x�b�h�C������̂ł������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@��{�I�ɉp��̉f�悾�������A�q���f�B�[���x���K���[����Ƃ���ǂ���Ŏg�p�����q���O���b�V���f�悾�����B�X�g�[���[�͂ƂĂ�������₷���A�܂����V��ł���B�T�Ȓ��ɏ�������悤�ȃe�C�X�g�̉f�悾�B�Q�O�O�Q�N�ɃC���h�Ō��J���ꂽ�C�M���X�f��uThe Guru�v���v���N��������悤�ȃv���b�g�������B
�@�R�Q�Γ���j�̓���r������Ƃ����A�C���h�f��ɂ��Ă͏����ۂǂ��e�[�}���������A�y���ȃ^�b�`�������̂ŋC�y�Ɋy���߂�f��Ɏ��܂��Ă����B�Ō�̓��}���e�B�b�N�ɒ��߂������Ă���̂ŁA�J�b�v���Ō��Ă����Ȃ��Ǝv���B�uBoom�v�̃h���h���Ƃ����G�����Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA�y���q�b�g���邩������Ȃ��B
�@���[�t���E�{�[�X�̉��Z�͂������ŁA�����������ǂ��ǂ����\������ɂ��Ƃ��������������B���̑��ɂ��ɂ߂Č��I�ȃL�����N�^�[�����l���o�ꂷ��B���̕M���̓o�[�o�[�E�q���h�D�X�^�[�j�[�����������B�W���C�E���[�Y�B�ނ̊�͎��X�{���E�b�h�f��Ō���B�}�b�h�Ȉ����̂��Ƃ��������A����͎����H���قǂ̃}�b�h�Șe���������B
�@�f�[�u�[�̖{���̓f�[�o�[�V�V���E�`���^���W�[�Ƃ����B����͓T�^�I�ȃx���K���l�̖��O�ł���B�f�[�u�[���x�@�ɑߕ߂���ď��ɘA�s�����V�[��������̂����A�����̏������x���K���l�ŁA�f�[�u�[���x���K���l�ł��邱�Ƃ�m��ƈ�]���ăx���K���[��Ŏ��B����Ƃ����V�[��������B�Ȃ������̃V�[�����n�����Ă����B�ނ�̓x���K���[��𗝉����A�x���K���[��̓��e������ۂǖʔ��������̂��A�q���f�B�[�ꌗ�̐l�ɂƂ��ăx���K���[�ꎩ�̂��}�̓I�Ȃ̂��A���̗��R�͓�ł���B�l�͍��܂ŁA�q���f�B�[��f��̒��Ńx���K���[�ꂪ�o�Ă���ƕK���ϋq���甚�������N����Ƃ������ۂ������Ă����B������������^�~����f��������Ƃ����q���f�B�[���b���l���o�Ă������A����͋t�]���Ă���A���������q���f�B�[���b���Ĕ���U���Ă����B�C���h���̌���ԂŌy�����C������̂�������Ȃ��B
|
|
|
|
|
�m�d�w�s���Q�O�O�R�N�P�O��
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



