 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 �@����ŃC���f�B�A�@ �@����ŃC���f�B�A�@
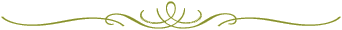
�Q�O�O�S�N�P�O��
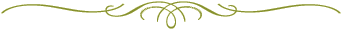
|
|
|
|
�@�C���h�̃f�B�X�R�ŕK������Ă���ȂƂ����̂�����������A�f�B�X�R�ɂ悭�s�����肵�Ă���ƁA�N�̋Ȃ��m��Ȃ��Ă����R�Ɓu���A���̋Ȓm���Ă�ȁv�Ƃ����̂������Ă���B���Q�G�̉��l�ƌ�����V���M�[�̋Ȃ��A�C���h�ɗ��Ă��炻��Ȋ����Őe����ł����B���̃V���M�[�̃R���T�[�g�������A�f���[�ōÂ��ꂽ�B
�@�Q���V���i�y�j�Ƀf���[�̃l���[�E�X�^�W�A���ōs��ꂽ�u���C�A���E�A�_���X�̃R���T�[�g�ł͎U�X�Ȗڂɑ������̂ŁA�������������R���T�[�g�ɂ͓�x�ƍs���܂��Ɛ����Ă����B�����A�f���[�ŃR���T�[�g�����Ă����C�O�A�[�e�B�X�g�͔��Ɍ����Ă���A�V���M�[�̓u���C�A���E�A�_���X�ɑ����A�f���[�������s�����N�Q�l�ڂ̑啨�A�[�e�B�X�g�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A�f���[�ł͊C�O�A�[�e�B�X�g�̃R���T�[�g�͔��N�ɂP��̃y�[�X�ł����s���Ă��Ȃ��ƌ����Ă������낤�B�ǂꂾ���h���ڂɑ����Ă��A���ꂾ�����Ԃ��ƁA���̃A�[�e�B�X�g�̃t�@���ł��낤���Ȃ��낤���A�u�܂��s���Ă݂悤���ȁv�Ƃ����C���ɂȂ��ė���B�t�ɍl����A���N�ɂP��̃y�[�X�����炱���A�f���[�Ō������Ă��ꂽ�A�[�e�B�X�g��Ђ��[���猩��]�T���ł��A���ꂼ��̃A�[�e�B�X�g���D���ɂȂ�`�����X�Ɍb�܂��Ƃ������Ƃ��B���ꗿ�����{�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�����B����ɁA�C���h�ōs����R���T�[�g���ǂ̂悤�ȏ�ԂȂ̂��A�ώ@����̂����͊y�����B
�@�V���M�[�̃R���T�[�g�̑薼�́uLucky Day Live�v�B�Q�O�O�Q�N�ɔ������ꂽ�A���o���uLucky Day�v�̖��O�����������C�����B�V���M�[�͍���łR�x�ڂ̃C���h�K��Ƃ̂��ƁB�O��͂Q�N�O�Ƀ����o�C�[�ŃR���T�[�g���s�����Ƃ����B�R���T�[�g�̓��ꗿ�͂U�O�O���s�[�܂��͂S�O�O���s�[�B�u���C�A���E�A�_���X�̃R���T�[�g�Ŏ����������A�C���h�ōs����R���T�[�g�́A�Ȃ�ׂ������`�P�b�g���Ɍ���B�Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ͉ʂĂ��Ȃ����̕��ɂȂ��Ă��܂����炾�B�`�P�b�g�͑�艹�y�X�`�F�[���̃v���l�b�g�l�Ŕ����Ă����̂ŁA���킸�U�O�O���s�[�̃`�P�b�g���w�������B
�@�R���T�[�g�̏ꏊ�́A�f�B�b���[�E�n�[�g�E�O���E���h�Ə����Ă������B�f�B�b���[�E�n�[�g�ƌ����A��f���[�̂h�m�`�}�[�P�b�g�߂��ɂ���`���H�|�i�}�[�P�b�g�ŁA�l�̉Ƃ��炷���߂������E�E�E�悭���Ă݂�ƁA�����ł͂Ȃ������B�s�[�^���v���[�Ə�����Ă���B�n�}�Œ��ׂĂ݂�ƁA�s�[�^���v���[�͖k�f���[�̕Ӌ��n�т������B����ȂƂ���ɂ��f�B�b���[�E�n�[�g�Ȃ�Ă������̂��A�Ǝv�������A�R���T�[�g���̓f�B�b���[�E�n�[�g���ݗ\��n�̋n�������B������������f�B�b���[�E�n�[�g�ړ]�v�悪����̂�������Ȃ��B�R���T�[�g�̓m�L�A�A�y�v�V�A���}�m�t�A�l�s�u�Ȃǂ����^���Ă������A�Ȃ�ƃf���[�ό��ǂ����ʋ��^���Ă����B���̂悤�ȃR���T�[�g�Ƀf���[�ό��ǂ��ւ��̂͏��̂��Ƃ炵���B
�@�ߌ�T��������J��Ƃ̂��Ƃ��������A���i���܂�s���Ȃ��n�悾�����̂ő��߂ɍs�����Ƃɂ����B�����O���[�h���O���ɖk�サ�A�i�[���[���i�[�A���W���E���[�E�K�[�f���A�p���W���[�r�[�E�o�[�O�Ȃǂ��z���čs�����B�R���T�[�g���́A�f���[���g���̃l�[�^�[�W�[�E�X�o�[�V���E�v���C�X�w�̂����߂��A�}�b�N�X�E�z�X�s�^���̑O�ɂ���A��O�X�e�[�W���g�܂�Ă����̂ł����ɕ��������B���ԏ�͂قƂ�ǓD����Ԃō������B���̎��_�ŊJ��܂łQ���Ԃقǂ������̂ŁA�U�����Ă�߂��ɂ������s�U�n�b�g�Ŏ��Ԃ�ׂ����B
�@�T�����炢����Q�[�g�̑O�ɕ���ł����B�u���C�A���E�A�_���X�̃R���T�[�g�̂Ƃ��͂ƂĂ��Ȃ����ւ̗ł��Ă����̂����A����͂���قǍ��G���Ă��Ȃ������B�������x���͑��ς�炸�ŁA�J�[�L�[�F�̐����𒅂��x�@�����X�����x�����s���Ă����B�Q�[�g���J�����̂͂U�����������B�����A�����ő傫�Ȗ�肪�N�����B����̃R���T�[�g�̌x����Ԃ͍ō����x���ŁA�J�����͋����A�n���h�o�b�O�ȂLj�؎������݂��֎~����Ă����B�m���Ƀ`�P�b�g���ʂɏ�����Ă������ӎ����ɂ́A�������֎~�i�ڂƂ��ăn���h�o�b�O�����L����Ă����B�����A�Ⴆ�n���h�o�b�O�������֎~�ł��A�����܂Ō����Ɏ������݂��֎~����C�x���g�͍��܂Ōo���������Ƃ��Ȃ������B�������ɃJ�����͎����ė��Ȃ��������A����^�]�Ƌ�����ꂽ�����ȃo�b�O�������ė��Ă����̂ŁA��������ۂ���Ă��܂����B�Q�[�g�ɂ���͉̂����[�̐l�ԂȂ̂ŁA�����ʼn��������Ă��ނ�́u�ʖڂȂ��̂͑ʖڂ��v�ƕ������������Ȃ��B�d�����Ȃ��̂ŁA�o�b�O�̒��g��S�ďo���āA�o�b�O�������o�C�N�̃V�[�g�̉��ɓ���ē��ꂵ���B��������A���ɂ���l�̑������]�T�Ńo�b�O����������ł����B�ǂ����ʂ̃Q�[�g�ł͂���قǃZ�L�����e�B�[���������Ȃ������悤���B���������ǂ��Ȃ��Ă�E�E�E�B
�@�R���T�[�g�͂W������n�܂����B�܂��̓C���h�l�_���T�[�ɂ��O���̃_���X�B���݃q�b�g���̃q���f�B�[��f��uDhoom�v�́uDhoom Machale�v����n�܂�A�m�y�̃_���X�i���o�[�Ȃǂ𐔋ȗx���Ă����B�ŏ��͐���オ���Ă������A�����������炾��Ƃ����������̂ŁA�����͂���u�V���M�[���o���`�I�v�Ƃ����{���ɕς���Ă����B�V���M�[�͂W�������o��B��ꐺ���u�����o�C�[�I�v�������̂̓W���[�N���A����Ƃ��{�C�̊ԈႢ���E�E�E�B
�@�V���M�[����I�����Ȃ́uMr Lova Lova�v�uBoombastic�v�uHey Sexy Lady�v�uAngel�v�uOh Carolina�v�uStrenght of Woman�v�uIn the Summertime�v�uHotshot�v�uLuv Me�v�uGet
My Party On�v�uIt Wasn't Me�v�ȂǂȂǁB�܂��A���N�R�������\��̐V�Վ��^�\��̐V�Ȃ��A���E�ɐ�삯�ĉ̂��Ă��ꂽ�B�V���M�[�͂��܂�_���X�����ӂł͂Ȃ��悤�ŁA�����������p�^�[�����������A�Ɠ��̂˂��Ƃ�Ƃ������͖��͓I�������B
�@�q�̓���̓u���C�A���E�A�_���X�̂Ƃ��Ɣ�ׂĔ������炢�B���̂Ƃ��͐g�������Ƃ�Ȃ����炢�r�b�V���Ƌl�܂��Ă������A����͂����ԋ�Ԃɗ]�T���������B�P�O���R���t���̃G�R�m�~�b�N�E�^�C���X���ɂ��ƁA��Î҂͂P���T��l�̗���Ґ���\�z���Ă����悤�����A���ۂɂ͂��̔������炢�������Ƃ����B�ϋq�������Ȃ������̂́A�V���M�[�̒m���x���Ⴂ�Ƃ��������A��翂ȏꏊ�����ɂ������炾�Ǝv����B�R���T�[�g�ʼn��t���ꂽ�Ȃ̓f�B�X�R�ł悭����Ă���i���o�[�������������߁A���͋���ȃf�B�X�R�̂悤�ɂȂ��Ă����B�ϋq�̑S�̓I�Ȑ���オ��̓u���C�A���E�A�_���X�̂Ƃ��̕����悩�������A�e�l�̔M���x�̓V���M�[�̕����悩�����悤�Ɏv�����B�V���M�[���u���ꂪ�Ō�̋Ȃ����I�v�ƌ������u�ԁA�����̃C���h�l���A��n�߂��͎̂c�O�������B�C���h�l�͉������I����ۂ�A�Ȃ���ڎU�ɋA�肽����̂��낤���E�E�E�B�����ɂ��̓������Ȃ��ł���B
�@���d������x���ɕs���Ȏv�����������A�I����Ă݂�Ȃ��Ȃ��y�����R���T�[�g�������B�R���T�[�g���̗������X�ʂ�߂���K���K���̃��g�����A�V���[���ȕ��͋C�������o���Ă����B
�@��T����ʂɐV��f�悪���J���ꂽ���A���T���q���O���b�V���f��Q�{�A�q���f�B�[��f��S�{�������A�C���h�f��t�@���Ƃ��Ă͖ڂ����悤�ȖZ�����ł���B��T���J�̉f����S�Č����킯�ł͂Ȃ��B�S�����s�����قljɐl�ł͂Ȃ��̂ŁA�T�d�ɑI�����Ċӏ܂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���܂Ŕ|�����I���������Ƃ������悢�旈���Ƃ����������B���̒�����A�����̓i�V���i���E�A���[�h����܂����q���O���b�V���f��uDance Like A Man�v���o�u�q�A�k�p���Ŋӏ܂����B
�@�uDance Like A Man�v�́A�}�w�[�V���E�_�b�^�[�j�[�ē̕��䌀���f�扻������i�ŁA�ē̓p�����E���b�N�X�B�L���X�g�́A�V���[�o�i�[�A�A�[���t�E�U�J�����[�A�A�k�[�V���J�[�E�V�����J���A���[�n���E�A�K�[�V�F�[�A�T�~�[���E�\�[�j�[�ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�A�k�[�V���J�[�E�V�����J���i���j��
�T�~�[���E�\�[�j�[�i�E�j |
�� |
| Dance Like A Man |
�@�W���C���[�W�i�A�[���t�E�U�J�����[�j�ƃ��g�i�[�i�V���[�o�i�[�j�͋��Ƀo���^�i�[�e�B�����̕��x�Ƃŕv�w���������A���ɉߋ��̐l�ƂȂ��Ă����B���̃��^�[�i�A�k�[�V���J�[�E�V�����J���j���o���^�i�[�e�B�����̕��x�Ƃ�ڎw���Ă���A�f�r���[�̕��䂪�ߕt���Ă����B���^�[�͍���҂̃��B�V���[���i�T�~�[���E�\�[�j�[�j���ƂɘA��ė��邪�A���̂Ƃ����傤�ǃ��^�[�̕���Ń����_���K�������t����\�肾�������y�Ƃ��r�����܂��Ă��܂��A���e�͂��̂��Ƃœ��������ς��������B���͂Ƃ�����A���e�̓��B�V���[���𖺂̌�������Ƃ��ĔF�߂�B���B�V���[���̓��^�[�̉Ƒ��ƌ𗬂��n�߂邪�A���̓��ޏ��̉Ƒ��������Ă�����ɋC�t���n�߂�B
�@�W���C���[�W�̕��e�͗L���Ȑ����Ƃ̃A�����g���[���E�p���N�i���[�n���E�A�K�[�V�F�[�j���������A�ނɃ_���T�[�ɂȂ邱�Ƃ������Ă��Ȃ������B�A�����g���[���́A�o���^�i�[�e�B�����t�w�̗x�肾�ƔF�����Ă���A�j�����̗x���x�邱�ƂȂǂ����Ă̂ق����ƍl���Ă����B�W���C���[�W�͕��e�ɔ��R���x�葱���Ă������A���ɗx�邱�Ƃ����߂錈�ӂ�����B���g�i�[�͈ˑR�Ƃ��ėx�葱���Ă������A���q�̃V�����J���̎������������ɁA��͂�x�邱�Ƃ����߂Ă��܂��B����́A�Q�l�͖��̃��^�[�ɕ��X�Ȃ�ʊ��҂������Ă����B
�@���^�[�̌����͑听�������߁A��]�Ƃ̔�������X���������A�C�O�����̑�\�ɑI���قǂł͂Ȃ������B�܂��A���g�i�[�͖��̐����Ɋ�Ԕ��ʁA���ւ̎��i�ɋ�Y����B�܂��A���B�V���[���͌���������^�[�ɗx��𑱂������邱�Ƃ������̂́A�����S�O���Ă��镔�����������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�O�x�̔т����x�肪�D���ȂR�l�A�W���C���[�W�A���g�i�[�A���^�[�̈�ƂɁA�������ʂ̐N�ł��郔�B�V���[�����э��܂��邱�Ƃɂ��A��Ƃ̊���������ɂ����f��B���݂̃V�[���Ɖߋ��̃V�[���i�Ԃ݂�тт��摜�ɂȂ��Ă���j�����������āA�R�l�̗x��ɂ������M�A���ɃW���C���[�W�ƃ��g�i�[�A���g�i�[�ƃ��^�[�̊Ԃ̕��x�ƂƂ��Ă̋����S�A���i�S�Ȃǂ�`�ʂ��Ă����B���قȃX�g�[���[�����邱�ƂȂ���A�V���[�o�i�[�炪�x��o���^�i�[�e�B�����̃_���X���f���炵���A�C���h���x�f��Ƃ��Ă��y���߂�B
�@����̎��ƂȂ�̂́A���x�ւ̏�M�ƈ�����l�ւ̈���̊Ԃ̔��݂ł���B�܂��A�W���C���[�W�͕��e�A�����g���[������x�邱�Ƃ�}�����ꂽ�ߋ�������A���ꂪ�g���E�}�ƂȂ��Ă���Ɠ����ɁA�_���T�[�Ƃ��āA�ȃ��g�i�[�̍˔\�Ɏ��i���o���Ă����B���g�i�[�́A�x��𑱂��邽�߂ɃA�����g���[���Ɩ�������킵�A�v���x���x��Ȃ��悤�Ɏd������B�܂��A���g�i�[�͖��̃��^�[�ɁA����Ǝ��i�̓��荬����������������Ă����B�����̊���̌��������܂��`�����Ήf��Ƃ��čō��Ȃ̂����A�V�[���ƃV�[���̂Ȃ����ɑ�����肪����A������ƕ�����Â炢�\���ɂȂ��Ă��܂��Ă����Ǝv�����B�܂��A�Ȃ����J�������h��Ă���̂��C�ɂȂ����B�f�掩�̖̂�肩�A�f��ق̐ݔ��̖�肩�͕�����Ȃ��������A�n�I��ʂ��h�ꑱ���Ă����̂Ō��ɂ��������B
�@�W���C���[�W���������A�[���t�E�U�J�����[�A���g�i�[���������V���[�o�i�[�A���^�[���������A�k�[�V���J�[�E�V�����J���̂R�l���o���^�i�[�e�B������x��V�[�����������������B���ł���є����đf���炵�������̂̓V���[�o�i�[�̃_���X�B�V���[�o�i�[�͗L���ȃo���^�i�[�e�B�������x�Ƃ̉ƌn�ɐ��܂�A�C���h����̃_���T�[�Ƃ��Đ��E�Ŗ������l���������A�q���̍�����f��E�ɂ��o�����A���X�̖��������Ȃ��Ă���B���g�ŐU��t�������Ƃ����o���^�i�[�e�B�����̗x��́A�f�l�ڂŌ��Ă����̏o���҂Ƃ͑S�����x�����Ⴄ�����B�ޏ��̃_�C�i�~�b�N�ł��đ@�ׂȓ���������ƁA�C���h���x�̉��̐[�����v���m�炳���B�f�撆�ŃV���[�o�i�[�̃o���^�i�[�e�B�����̃_���X�����\�ł���̂́A�傫�ȓ����ƂȂ��Ă���B
�@���^�[���������A�k�[�V���J�[�E�V�����J���́A�L���ȃX�B�^�[���t�ҁA�����B�E�V�����J���̖��ł���A����܂��L���ȃW���Y�E�{�[�J���X�g�A�m���E�W���[���Y�ٕ̈�o���ł���B�����B�E�V�����J���̈�Ԓ�q�̃X�B�^�[���t�҂Ƃ��Č��݂������A���o�����o���Ă��邪�A�X�B�^�[�����n�߂�O�̓o���^�i�[�e�B����������Ă��������ŁA�f��f�r���[��̂��̍�i�ł��x����I���Ă���B�������V���[�o�i�[�̗x��Ɣ�ׂĂ��܂��ƁA����肪����͎̂d���Ȃ��B�A�k�[�V���J�[�͍אg�ł��邽�߁A�����ڂő������Ă��镔��������B���x�Ƃ͏����ӂ����炵�����炢�����͂��o�Ă����B�����A�t���Đn�ŏK�����悤�ȓ����ł͂Ȃ������̂͊m�����B
�@�f��̓o���K���[��������ł���A�o��l���̂قƂ�ǂ͉p��݂̂�����ׂ�B���n���b���͎̂g�p�l�݂̂ŁA����ɂ͉p�ꎚ�����o��B�܂�A�T�^�I�ȃq���O���b�V���f��̌���\���ł���B�����A�ŋߋC�ɂȂ�̂́A�C���h�l���p�������ׂ�q���O���b�V���f��̑����́A�p��̕\��������I���_�ǂ݂��ۂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B�܂�A���܂茻���ɑ����Ă��Ȃ��Z���t�ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�Ɋ�����B�p��ƃq���f�B�[���K�x�ɍ����Ęb���̂���Ԍ����ɋ߂��̂����A�q���O���b�V���f��ɂ́A�����ɓo��l���ɉp��݂̂�b�����Ă�����̂������B���̑O�����uHyderabad Blues2�v�ł�������ۂ����B�q���O���b�V���f��̌��E�������������B
�@�i�V���i���E�A���[�h����܂����Ƃ͌����A�����f��̍\���ɋ^�₪�c�������A�C���h���x�t�@���ɂ͕K���̉f��ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B
�@�����́A��T��������J�̃q���O���b�V���f��uLet's Enjoy�v���o�u�q�A�k�p���Ō����B�ē̓X�B�b�_�[���g�E�A�[�i���h�E�N�}�[���ƃA���N���E�e�B���[���[�A���y��MIDIval
PunditZ�B�L���X�g�͎��V�l�o�D�̃I���p���[�h�ŁA�uGirlfriend�v�i2004�N�j�ɏo�����Ă����A�[�V�[�V���E�`���E�h���[�A�o�q�̃��[�q�g�E���F�[�g�E�v���J�[�V���ƃ��[�t���E���F�[�h�E�v���J�[�V���A���[�~�j�[�E�i�[���W���[�V�[�A�V���E�p���f�B�g�A���B�m�[�h�E�V�F�[���[���g�A�J�r�[���E�X�B���A�T�q�[���E�O�v�^�[�A�W���X�v���[�g�E�X�B���A�h�����E�X�B���A�h�����E�W���K�[�X�B���[�A�A�[���Y�[�E�S�[���B�g���[�J���A���[�V���j�[�E�`���[�v���[�A�s���[���[�E���[�C�A���[�W�[���E�O�v�^�[�ȂǂȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
������V���E�v���T�[�h�A�h�����E�X�B���A
���[�~�j�[�E�i�[���W���[�V�[�A�A�[�V�[�V���E�`���E�h���[�A
�A�[���Y�[�E�S�[���B�g���[�J���A���B�m�[�h�E�V�F�[���[���g�A
���[�V���j�[�E�`���[�v���[ |
�� |
| Let's Enjoy |
�@��f���[�̃t�@�[���n�E�X�Ń_���X�p�[�e�B�[���J����邱�ƂɂȂ����B�p�[�e�B�[�̎�Î҂̓A�����J�A��̃i�C�X�K�C�A�A���}�[���i�A�[�V�[�V���E�`���E�h���[�j�B�A���}�[���̐e�F�őo�q�̃��}���i���[�q�g�E���F�[�h�E�v���J�[�V���j�ƃ��^���i���[�t���E���F�[�h�E�v���J�[�V���j���c�i�߂邱�ƂɂȂ�A�A���}�[���̗F�l���������҂��ꂽ�B
�@�V�����[���[�i�A�[���Y�[�E�S�[���B�g���[�J���j�̓A���}�[���̌��ޏ��������B�������S�N�O�ɃA���}�[�����A�����J�֓n���Ă����x���A������荇���Ă��Ȃ������B�V�����[���[�͗F�l�̃\�[�i�[���i���[�V���j�[�E�`���[�v���[�j�ƃs���[�i�s���[���[�E���[�C�j�Ƌ��Ƀp�[�e�B�[�ɏo�Ȃ���B�V�����[���[�̃A���}�[���ɑ���C�����͕��G�������B
�@�A���}�[���̑�w����̗F�l�A���O�i�V���E�p���f�B�g�j�̓��[�}�[�i���[�~�j�[�E�i�[���W���[�V�[�j�ƂT�N�Ԃ��t�������Ă������A�܂��Q�l�͓��̊W�Ɏ����Ă��Ȃ������B���[�}�[�̒a�������A���}�[���̃_���X�p�[�e�B�[�Əd�Ȃ������߁A���O�̓��[�}�[���p�[�e�B�[�ɗU���B
�@�J�����i���B�m�[�h�E�V�F�[���[���g�j�̓~���[�W�V�����ɂȂ邽�߂Ƀf���[�ɂ���ė�����҂������B�����ɉ肪�o�������Ԃ��Ă������A�A���}�[���̃p�[�e�B�[�ɗU���Ă���ė���B
�@���[�W���_���i�h�����E�X�B���j�̓��f���ɂȂ�̂��Ė����W���ŋؓ���b���Ă���n������҂������B�A���}�[���̃t�@�[���n�E�X�Ńp�[�e�B�[������̂��A���f���ɂȂ�`�����X�Ɖ��ɔE�э��ށB
�@���̑��A�n�b�s�[�i�J�r�[���E�X�B���j�A�\�[�f�B�[�i�T�q�[���E�O�v�^�[�j�A�o�j�[�i�W���X�v���[�g�E�X�B���j�̂R�l�g��A�t�@�b�V�����E�f�U�C�i�[�ŃI�J�}�̂a�i�i�h�����E�W���K�[�X�B���[�j�Ȃǂ��p�[�e�B�[�ɏo�Ȃ���B
�@�A���}�[���ƃV�����[���[�͋v���U��ɍĉ�邪�A���܂����݂��̋C�����������\���Ȃ��ł����B���O�ƃ��[�}�[�̓p�[�e�B�[�������̂��ł��������ꏊ�����߂ĕ��Q���Ă����B���[�W���_���͕������z���ĉ��ɐN�����邪�A���傤�ǂ����ŗ������ւ����Ă����a�i�Əo��B�a�i�̓��[�W���_���������߂ă��f���ɂ���Ɩ��邪�A���[�W���_���͂a�i���������ڂŌ���̂Œf��B�P�l�ŗ�������ł��郉�[�W���_�������āA�s���[�͉��ƂȂ��䂩��A�����|����B�n�b�s�[�A�\�[�f�B�[�A�o�j�[�̓p�[�e�B�[���̒n�}���Ȃ����čx�O��������A�U�X�Ȗڂɑ���������Ɖ��ɒH�蒅���B�J�����̓V�����[���[�Əo��A��d���ɔޏ��̂��߂ɉ̂��̂��B�V�����[���[�̓J�����Ɏ䂩��邪�A�Ō�ɂ̓A���}�[���Ƃ���߂��B���O�ƃ��[�}�[�͒N���̃x���c�̒��ł���Ɨ��������Ă���������Ƃ��ł����B
�@�������āA�y�����_���X�p�[�e�B�[�̖邪�X���čs�����B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�uDil Chahta Hai�v�i2001�N�j�A�u�����X�[���E�E�F�f�B���O�v�i2001�N�j��A�W���[�W�E���[�J�X�ē̏�����u�A�����J���E�O���t�e�B�[�v�i1973�N�j���v�킹��t�Q���f��B�f���[�ݏZ�̎�҂��������ꂼ��̎v�f��ړI�������āA��f���[�x�O�̃t�@�[���n�E�X�ŊJ�Â��ꂽ�_���X�p�[�e�B�[��K��A���ꂼ��̐t���G���W���C����Ƃ����X�g�[���[�ŁA���炷���͑債�����ƂȂ��̂����A���I�������̑u�����͂Ȃ��Ȃ��̂��́B���ꂾ���o��l���������f����܂Ƃ߂�̂͂�����������̂����A���܂����ꂼ��̓������������Ă���A�N���N����������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�o�Ă���o��l���S�Ă�����ƌ����Ă������̂����A�ꉞ�p�[�e�B�[�̎�Î҃A���}�[�������ƂȂ��ĕ��ꂪ�i��ł����B�j���̗����Ƃ����ϓ_���猩��ƁA�A���}�[���ƃV�����[���[�A�V�����[���[�ƃJ�����A�s���[�ƃ��[�W���_���A���O�ƃ��[�}�[�̂S�g����̂ł���B�����w�̒��ň�Ԗڗ����Ă����\�[�i�[���́A�A���}�[���ɋC������悤�ɂ������Ă������A���Ǒ債������͂��Ă��Ȃ������B�R���f�B�[�Ƃ����ϓ_���猩��ƁA�n�b�s�[�A�\�[�f�B�[�A�o�j�[�̂R�l�g�̍s�����ʔ��������B���ɖ����Ă���r���A���ē��̂��߂ɉ������j�o�[���g�E�u�[�V�����i���[�W�[���E�O�v�^�[�j���Ԃɏ悹�Ă��܂��B�o�[���g�E�u�[�V�����͂R�l�t�h�ɗU���B�Ƃ��낪�����㩂ŁA�o�[���g�E�u�[�V�����͂X�X�X���s�[�������ς���ē����Ă��܂��B���̑��A�o�q�̂c�i�A���}���ƃ��^�����`���Ŏ����Ԃ̃p���N�ɂ�荻���̐^�ŗ����������Ă��܂��V�[����A���O�ƃ��[�}�[�̂��Ƃ�Ȃǂ��ʔ��������B���������o���Ă����̂̓��[�W���_���B�p�[�e�B�[�ɏo�Ȃ�����f���ɂȂ��Ǝv���ĉ��ɐN��������̂́A����ɂ��Ă��ꂽ�̂̓I�J�}�̂a�i�������B���[�W���_���͌��ǃ��f���ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�Ō�Ƀs���[�̓d�b�ԍ����Q�b�g����B�M�^�[�������ăp�[�e�B�[���ɗ����J�������悩�����B��d���A�J�����̓V�����[���[�ɒe����������B
�@�p�[�e�B�[�̓r���ɒ�d�ɂȂ�Ƃ����V�[���́A�Ȃ��Ȃ������ɑ����Ă��Ă悩�����B���������X���W���ɃR�[���J�[�^�[�ōs��ꂽ�e�h�e�`���[���h�t�C���h�Γ��{�̎����ł���d���������B�C���h�ɂ����āA��d�͐����̒��ő傫�Ȗ�肾���A��d���Ȃ��ƃC���h�Ƃ����C�����Ȃ�����s�v�c���B���������Ӗ��ŁA�p�[�e�B�[���̒�d�Ƃ����̂͂����Ƃ����˂��Ă����B
�@�悭�C���h�f��̃_���X�V�[�������āA�u����Ȃ̃C���h�ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ��v�ƌ����l�����邪�A���̓C���h�f��̃~���[�W�J���E�V�[���̂悤�ȃ_���X�p�[�e�B�[�́A�s���Ƃ���ɍs���Α��݂���B���̉f��ŕ`����Ă����f���[�̃t�@�[���n�E�X�ɂ�����_���X�p�[�e�B�[���A�����ăt�B�N�V�����ł͂Ȃ��B�G�߂ɂȂ�A�A���A��A�������̏W�܂�p�[�e�B�[���s���Ă���B������A�f���[�̃p�[�e�B�[�������_�Ԍ��邽�߂ɂ��A���́uLet's Enjoy�v�͂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@��������uDance Like A Man�v�ŁA�q���O���b�V���f��Ŏg����p��ɂ��Ĕᔻ���q�ׂ����A���̉f��̌���͌����ɒ����ɑ������A���̒��㗬�w�̌��ꂾ�����B���Ȃ킿�A�p��ƃq���f�B�[��̃`�����|���ł���B���ꂱ���A����̃n�C�\�Ȏ�҂������g���Ă���{���̉p��ł���A�{���̃q���f�B�[��ł���B����������A�q���f�B�[��Ɖp��̗Z���`�A�q���O���b�V����ł���B����̂��̂Q�̌���̉ؗ�Ȃ�Z���ɁA�l�́A�g���R��A�y���V�A��A�|���g�K����A�p��Ȃǂ̊O�����A�I�[�X�g���E�A�W�A�n����A�h�����B�_�n����Ȃǂ̓y����A�T���X�N���g��A�u���W��A�A���f�B�[��A�p���W���[�r�[��Ȃǂ̃C���h����������X�Ǝ�荞��ōs�����A�q���f�B�[��̃_�C�i�~�Y��������C������B�܂��A�l�I�ɂ͂�����������̉f�悪��Ԓ������₷�����������₷���B���ȏ��ɍڂ��Ă���悤�ȃR�e�R�e�̃q���f�B�[���o��l�����b���q���f�B�[��f�������͂���ŕ�����₷���̂����A�����̌���ɑ����Ă��Ȃ����Ƃ������̂ŁA�����C�ɂȂ邱�Ƃ�����i�Ⴆ�ٔ����̃V�[���Ńq���f�B�[���b���Ă����肷�邱�ƂȂǁj�B
�@���y��MIDIval PunditZ�Ƃ����j���[�f���[�o�g�̃��j�b�g���S�����Ă���i���̋ł͂�����x�L�������j�A�S�Ȃقڃ_���X�i���o�[�B�uSabse Peeche Hum Khade�v�ƁuSubah�v�̂Q�Ȃ����̓A�R�[�X�e�B�N�E�M�^�[�̉����S�n�悢�e����蕗�̋ȁB�ǂ�����Ȃ��Ȃ������̂ŁA�@���������}�X�^�[���Ă݂����Ȃł���B
�@�قƂ�ǐV�l�ŁA���O���o����̂���ς����A���̒�����܂��V���ȃX�^�[���o�Ă���̂��낤���B�uLet's Enjoy�v�́A�f��Ȃ̂Ɍ��I�������͐���t�x�肫�����悤�ȋC���ɂȂ�A���j�[�N�ȉf��ł���B
�@����̓��L�ȂǂŃq���f�B�[��f��̌���ɂ��ď����G�ꂽ�̂ŁA���ꂩ��C���h�f��ɂ��ĊT�ς��Ă݂悤�Ǝv���B
�@�C���h�͑����ꍑ�ƂƂ��ėL���ł���B���@��ł́A�����p��Ƃ��ăq���f�B�[��A�����p��Ƃ��ĉp�ꂪ�ݒ肳��Ă��鑼�A���݁A�u���@��W�����K��̏�����v�Ƃ��ĂP�V�̌��ꂪ�F�肳��Ă���B����獇�v�P�X����̓��A�X�B���f�B�[��ƃR�[���N�j�[����������P�V����̕������C���h�̎����ɋL�ڂ���Ă���B�܂��A�ŋ߁u�ÓT��v�̃J�e�S���[���V�����ł��A�^�~���ꂪ�u�ÓT��v�ɔF�肳�ꂽ���A���̓���������ړI�Ƃ������̂����܂����悭������Ȃ��B�����͂����܂Ō��@��E�@����̘b�ł���A���ۂɍׂ�������E�����̕��ނ����Ă����ƁA���S�̌��ꂪ����Ƃ���Ă���B�����̑������Ԃ́A�f��ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B
�@�C���h�ʼnf�悪���߂č��ꂽ�̂͂P�X�P�Q�N�������B���������̂Ƃ��͖����f��ł���A�َm���X�g�[���[�̐��������Ă������߁A�َm��ς��邾���Ŋe����ɊȒP�ɑΉ����邱�Ƃ��ł����B�Ƃ��낪�A�P�X�R�P�N�Ƀg�[�L�[�f��̐��삪�C���h�Ŏn�܂��Ĉȗ��A�C���h�f��͕K�R�I�Ɋe�n��̌���ō����悤�ɂȂ�A����ʉf��Ƃ����V���ȏ�Ԃ��������B�P�X�T�U�N�ɂ́A�C���h�͕��������������ɏB���ĕ҂���邱�ƂɂȂ�A����ʉf��͂��Ȃ킿�B�ʂ̉f�敶�����Ƃ����C���h�Ǝ��̏����o�����B���̒��ł����ɉf�搧��{���������̂��A�q���f�B�[��i�k�C���h��сj�A�e���O��i�A�[���h���E�v���f�[�V���B�j�A�^�~����i�^�~���E�i�[�h�D�B�j�������B�܂��A�T�e�B���W�g�E���[�C�i�T�^�W�b�g�E���C�j�ēȂǂ̊���ɂ��A�x���K���[��i���x���K���B�j�̉f������E�I�ɗL���ƂȂ����B�����A�C���h�S�y�̉e���͉͂��ƌ����Ă��q���f�B�[��f�悪��є����Ă���B�m���ɐ���{���Ō���A�q���f�B�[��f��̓e���O��f���^�~����f��ɕ����邱�Ƃ��������B�Ⴆ�P�X�X�T�N�̃f�[�^�ł́A�S����̐���{���V�X�T�{�̓��A�q���f�B�[��f��͂P�T�V�{�A�e���O��f��͂P�U�W�{�A�^�~����f��͂P�U�T�{�ł���A�q���f�B�[��f��͐���{���œ�C���h�̊e�f��E�ɕ����Ă���B�������A�e���O��f���^�~����f��́A�C�O�s��������Ί�{�I�ɂ����̏B�ł�����f����Ȃ��̂ɑ��A�q���f�B�[��f��̓C���h�S�y�Ō��J�����B�q���f�B�[��ɑ��锽���̋����^�~���E�i�[�h�D�B�ł��A�q�b�g���Ă���q���f�B�[��f��͂�����Ə�f�����B�������A�Q�O�O�R�N�̃f�[�^�ł́A�S����̐���{���W�V�V�{�̓��A�q���f�B�[��f��Q�Q�Q�{�A�e���O��f��P�T�T�{�A�^�~����f��P�T�P�{�ƂȂ�A�q���f�B�[��f��̉e���͂��ߔN�}���ɑ����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�q���f�B�[��w�K�ƃq���f�B�[��f��͔��ɑ����������B�q���f�B�[����w�Ԃ��߂Ƀq���f�B�[��f�������l�����邵�A�q���f�B�[��f����悭�������������߂Ƀq���f�B�[��������l������B�w�K���ʂ���l���Ă݂�A�q���f�B�[��͑��̊O����Ɣ�ׂĔ��Ɍb�܂ꂽ����ł���B�q���f�B�[��f��Ƃ����A����ȏ�Ȃ����ނ����݂��Ă���̂��B�������@�Ɗ�{�P�����ʂ蓪�ɓ���Ă����A���Ƃ̓q���f�B�[��f����������悤�Ɍ��Ă��邾���Ŏ��R�ƃq���f�B�[��̗���͂��[�܂��Ă����B�f�撆������Ȃ��P�ꂪ�o�Ă�����}���Ƀ��������Ă����悤�ɏ����w�͂���ƁA��b�͂��t���Ă���B�v���N�����Ă݂�Ζl���g���A�q���f�B�[��ɑ����M�ƃq���f�B�[��f��ɑ����M�͏�ɕ\����̂������B�q���f�B�[��̂��߂Ƀq���f�B�[��f������āA�q���f�B�[��f��̂��߂Ƀq���f�B�[�������Ă����悤�Ȃ��̂��B
�@�����ȂƂ���A�ŏ��̓��͉f��̒��ɏo�Ă���q���f�B�[������S�ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B����䂦�A��ǂ��Ȃ��Ȃ�f����������������B���ł��o���Ă���̂́A�܂��f���[�ɏZ�ݎn�߂ĊԂ��Ȃ����Ɍ����uYaadein�v�i2001�N�j���قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��ĉ������v�����������Ƃ��B�܂��A�q���f�B�[��Ɏ��M���t���n�߂��Q�O�O�Q�N�Ɍ����uAgni Varsha�v���悭������Ȃ������B�����A�i�m�t�Ŗ{�i�I�Ƀq���f�B�[���w���w�юn�߂Ă���́A�q���f�B�[��f��̗���͔͂���I�ɃA�b�v�����B���ł͓��{��̉f�������̂Ɠ������o�Ńq���f�B�[��f������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ǝ������Ă����B�����A���ŋ߂c�u�c�Ō����uMughal-e-Azam�v�i1960�N�j��uUmrao
Jaan�v�i1981�N�j�́A�������Ă����قǗ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�܂��A�uChameli�v�i2004�N�j����������̂ɋ�J�����f�悾�����B�������A�uLagaan�v�i2001�N�j���c�u�c�ʼn��߂Č������Ă݂�ƁA���͂��̉f��͗�������̂ɑ�����������f��ł��邱�ƂɋC���t�����B��L�̉f��͑S�ē����q���f�B�[��f��ł���B����Ȃ̂ɁA�Ȃ������ł���f��Ɨ������������f�悪����̂��낤���H
�@���́A���ȏ���u���ȂǂŃq���f�B�[����w�����ł́A�S�Ẵq���f�B�[��f������S�ɗ������邱�Ƃ͍���ł���B�������A�����q���f�B�[���m��Ȃ����͊i�i�ɗ���͂��A�b�v����͓̂��R�����A������x�܂ōs���ƁA�����ō����ǂɂԂ�������B�����Ə�ŋ������f��͊W������B���̎�ȗ��R�́A�q���f�B�[��̎ؗp��A�����A�g�������̑��l���ƁA����ƕ���̊i���ł���B
�@�q���f�B�[��f��̌���ɂ͑傫�������ĂT��ނ���\�\�@���z��`�I�q���f�B�[��A�A������`�I�q���f�B�[��A�B�����I�q���f�B�[��A�C�n��I�q���f�B�[��A�D�E���h�D�[��B�ȉ��A���ꂼ���������B
�@�@���z��`�I�q���f�B�[��͂�����W���q���f�B�[��ł���A�����̃^�C�v�̉f��ł́A�o��l���͋��ȏ��ɍڂ��Ă���ʂ�̕��@�A��b�A�����ŃZ���t������ׂ��Ă����B�Ⴆ�uKuch Kuch Hota Hai�v�i1998�N�j�Ȃǂɑ�\�����A�t�@�~���[�����T�^�I�C���h�f��́A���̃^�C�v�̌���ł��邱�Ƃ����ɑ����B�{����ƂŏK�����ʂ�̃q���f�B�[�ꂪ�o�Ă���̂ŕ�����₷���A�܂��q���f�B�[��w�K�ɍœK�̉f��ł���B
�@�A������`�I�q���f�B�[��́A�����Љ�̌�������̂܂ܔ��f���Ă���A���ʂɃq���f�B�[����w�K���������ł͗�������̂�����ł���B�����̏ꍇ�A�}�t�B�A�≺�w�K���̐l�X���b���A�u���[�N���ȃq���f�B�[�ꂾ�B�ŋ߂��̃^�C�v�̃q���f�B�[��f�悪�����Ă���A�Ⴆ�Ώ�ŋ������A�����o�C�[�ɏZ�މ������t�w����l���́uChameli�v�Ȃǂ͂��̗�ł���B�uMunna Bhai M.B.B.S.�v�i2003�N�j�����̈��ŁA�o��l���̓R�e�R�e�̃����o�C���[�E�q���f�B�[�i�����o�C�[�Řb����Ă���q���f�B�[��j��b���B
�@�B�����I�q���f�B�[��́A����������T���X�N���g��̌�b�𑽂��g�p�����q���f�B�[��ł���B���Ɂu�V���b�h�E�q���f�B�[�i���q���f�B�[��j�v�ƌĂ�Ă��邪�A���ɏ��Ȃ킯�ł��Ȃ��A�������ĕs���������������q���f�B�[��̂悤�ɕ������邽�߁A���̌ď̂͌l�I�ɂ��܂�D��Ŏg���Ă��Ȃ��B�q���h�D�[���̐_�l����l���̂s�u�h���}�Ȃǂł悭�g����q���f�B�[��ŁA��L�́A�_�b�����ɂ����uAgni Varsha�v�͂܂��ɂ��̃^�C�v�̌��ꂪ�g���Ă����B������A���ʂ̃q���f�B�[�������������ł͏o�Ă��Ȃ��P�ꂪ�����o�Ă��邽�߁A���i���當��ɐe����ł��Ȃ��Ƃ���Ղ�Ղ낤�B�C���h�l����������Ƃ��Ȃǂɘb���q���f�B�[����A���̃^�C�v�ł��邱�Ƃ������B
�@�C�n��I�q���f�B�[��́A����̎���ݒ�E�ꏊ�ݒ�Ȃǂ����ʓI�ɏ����o�����߂ɁA�Ӑ}�I�ɑn��o���ꂽ����ł���B���̍D�Ⴊ�uLagaan�v�Ŏg���Ă���q���f�B�[�ꂾ�B���l�������b���q���f�B�[��́A�W����ł��Ȃ���ǂ����̕����ł��Ȃ��B�}�g�D���[�n���̕����A�u���W����x�[�X�Ƃ��đn��o���ꂽ�A�u�ˋ�̓c�ɕفv�ł���B���{�̕��|��i�ł��A�o��l���Ɂu����́`���ׁv�݂����ɘb�����āA�n���F�̂Ȃ��c�ɏL�����o�����邱�Ƃ����邪�A���傤�ǂ���ƈꏏ�ł���B���̂悤�ȗ��R�ŁA�q���f�B�[��̕����̒m�����Ȃ��ƁA��������̂ɑ�����������B
�@�D�E���h�D�[��́A�A���r�A��E�y���V�A��̌�b�������g��ꂽ�q���f�B�[��Ɨ������Ă��������낤�B�����A�����ł̓q���f�B�[��ƃE���h�D�[��̋c�_�ɂ͐[���������炸�A�����u�E���h�D�[��v�Ƃ��邱�Ƃɂ���B���K�����̋{�삪����́uMughal-e-Azam�v��A���X�����̏��w����l���́uUmrao Jaan�v�ł́A�q���f�B�[��Ƃ������E���h�D�[�ꂪ�g���Ă���B����āA�q���f�B�[��̒m�������ł͑����ł��ł��Ȃ���b�������B���ɁA�K�U�����Ȃǂ��r�܂��ƁA�E���h�D�[��̐[���m���Ȃ��ɂ́u���@�I���@�I�v�Ɗ��Q�̐����グ�邱�Ƃ͕s�\�ł���B���Ȃ݂ɁA�@���z�I�q���f�B�[��̉f��ł��A�ނ���E���h�D�[��̌�b�������g���Ă���A�u�q���f�B�[��f��ɏo�Ă��錾��̓E���h�D�[�ꂾ�v�Ǝ咣����l�������B
�@��{�I�Ƀq���f�B�[��f��͂����T�̓��̂ǂꂩ�̌���^�C�v���g���邪�A�f��ɂ���Ă͓o��l���̓����ɍ��킹�Ęb������̃^�C�v��ς��邱�Ƃ�����B�Ⴆ�uDev�v�i2004�N�j�Ƃ����f��ł́A��l�������͇@���z��`�I�q���f�B�[��A�܂��͇D�E���h�D�[��ɋ߂��@���z��`�I�q���f�B�[����A���X�����̐����Ƃ͇D�E���h�D�[����A�q���h�D�[���k�̐����Ƃ͇B�����I�q���f�B�[����g���Ă����B�����̌�����`�I�g���������܂Ƃ߂āA�A������`�I�q���f�B�[��ɕ��ނ��Ă��܂����Ƃ��\��������Ȃ��B�܂��A�f��S�̂��@���z��`�I�q���f�B�[��ł��A�}���̂̉̎����D�E���h�D�[��I�ł��邱�Ƃ͓��풃�ю��ł���B���́A�f�批�y�̉̎��ɂ̓E���h�D�[��I��b�����p�����X���ɂ���A����𗝉�����ɂ͂�͂�E���h�D�[��̒m�����K�v�ƂȂ邱�Ƃ������B
�@�Ƃ���ŁA�q���f�B�[��f��ɂ͉p������������o�Ă��邪�A�������f��̗����̂��߂ɉp��̒m���͕K�������K�v�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���ɇ@���z��`�I�q���f�B�[��^�C�v�̉f��̒��̉p��̃Z���t�̌�ɂ́A�K���q���f�B�[�ꂪ���邩�炾�B�Ⴆ�A�uWhat are you doing?�v�ƌ�������ɂ͕K���ukya kar rahe ho tum?�v�Ɨ���̂��B�q���f�B�[��f��̑����́A�p�ꂪ������Ȃ��l�X���l���ɓ���č���Ă���B�C���h�l�͉p�ꂪ���܂��Ǝv���Ă���O���l�����������������A�C���h�l�P�O���l�̒��ŁA�p�ꂪ������l�́A�܂��܂��P���ɂ������Ȃ��ƌ����Ă���B������A�q���f�B�[��f����p�ꂾ�炯�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B
�@����܂ł̓q���f�B�[��f��Ɍ����Ę_���Ă������A�ŋߗ��s�̃q���O���b�V���f����l���ɓ����Ƙb�͂����������G�ɂȂ�B�q���O���b�V���f��Ƃ͂܂�A�C���h���p��f��̂��ƂŁA�o��l�����p���b���̂����A�b�͂����P���ł͂Ȃ��B�S���p�ꂵ������ׂ�Ȃ��q���O���b�V���f�������A�q���f�B�[��ƃ~�b�N�X���ĉp���b���q���O���b�V���f�������B���̃~�b�N�X�̎d�����A�����፬���̏ꍇ�����邵�A��u�������n�ꂪ���邱�Ƃ�����B�S���p�ꂵ������ׂ�Ȃ��q���O���b�V���f��ł����Ɏv���t���̂́A���̑O�����uDance Like A Man�v�B���̑��A�m�q�h�i�݊O�C���h�l�j�ɂ���ĎB�e���ꂽ�q���O���b�V���f������̌X���ł��邱�Ƃ������B���̎�̃q���O���b�V���f��́A�p�ꂳ��������Ζ��Ȃ������ł��邾�낤�B�q���f�B�[��Ɖp��̃`�����|���Ői��ł����f��́A�Ⴆ�uLet's
Party�v���L���ɐV�����B���̃^�C�v�̉f��́A�q���f�B�[�ꕔ���Ɏ������o�邱�Ƃ͏��Ȃ��A���S�Ƀq���f�B�[��Ɖp��̃o�C�����K�������f��ƂȂ��Ă���B���̃`�����|���f��������������p��̎g�p���������q���O���b�V���f��ɂ́A���n�ꕔ���Ɏ������t�����Ƃ������A�Ⴆ�uMr.&Mrs. Iyer�v�i2002�N�j��uKing of Bollywood�v�i2004�N�j�Ȃǂ���\�i���B�������p�ꂳ��������Η����\���낤�B�܂�A�q���O���b�V���f��ƌ����Ă��A�p�ꂳ��������Η����ł���f��ƁA�p��ƃq���f�B�[��̗�����������Ȃ��Ɨ����ł��Ȃ��f��̂Q��ނ�����̂��B���Ȃ݂ɁA�����̌���ɍł��������f��́A�p��ƃq���f�B�[��̗����̒m�����v�������o�C�����K���f��ł��邱�Ƃ��w�E���Ă����B
�@�ŋ߂̓q���f�B�[��f��ƃq���O���b�V���f��̐�����������f����o�Ă������A��{�ƂȂ�Z���t���p�ꂩ�q���f�B�[�ꂩ�ł܂����ʉ\�ł���B���{�̍ۂ��p��f�悩�q���f�B�[��f�悩���L�������̂Łi�C���h�ł͉f���f�O�Ɍ��{�ؖ������f���o����邪�A�����ɉf��̌�����L����Ă���j�A���̔��ʂ͑傫�Ȗ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@��������ƁA�q���O���b�V���f����܂ރq���f�B�[��f��̐��E���P�O�O���y���ނ��߂ɂ́A�q���f�B�[��̒m���̑��A�p��A�T���X�N���g��i���Ȃ��Ƃ�����I�q���f�B�[��j�A�q���f�B�[��̕�����e��o���G�[�V�����A�E���h�D�[��Ȃǂ̒m�����K�v�ƂȂ�Ƃ������Ƃł���B�������A����͌���I���ʂ���q�ׂ������ł���A���̑��ɂ��C���h�����ɑ��闝����A�M��m�������Ƃ��Ƃ͈Ⴄ�S�\�����K�v�ƂȂ邪�A���ꂪ�f��Ƃ����|�p�`�Ԃ̑傫�ȃE�G�C�g���߂Ă���ȏ�A����𒆐S�ɘ_����������Ȃ����낤�B�q���f�B�[��f��́A�Ɠ��̐��E�ɂ�������邱�Ƃ��ł���A���ꂪ������Ȃ��Ă����炷���������ł��Ċy���߂�f��ł���A���ꂪ������x������ǂ�ǂ�y���݂������Ă������A��������ȏ�[���Nj����悤�Ƃ���ƁA����̓q���f�B�[�ꂪ���܂ŕ���ł������j�ɐ[���[���͂܂��Ă������ƂɂȂ�A��Ȃ����̂悤�ȉf��ł���B
�@���Ȃ��Ƃ������P�����Ԃ́A�A�C�V���������[�E���[�C�����߂ĉp��̉f��ɒ��킷��uBride & Prejudice�v�̘b��Ŏ����肾�����B���̉f��́A�L���ȉp��������ƃW�F�[���E�I�[�X�e�B���̌ÓT�I���������uPride
& Prejudice�v�i�M��́u�����ƕΌ��v�܂��́u�����ƕΌ��v�j���x�[�X�ɂ����q���O���b�V���f��ŁA�ḗu�x�b�J���ɗ����āv�i2002�N�j�ň���L���ƂȂ����p���ݏZ�̃C���h�l�����ēO�����_���E�`���b�_�[�B���̊�Ԃ�����Ċ��҂���ȂƂ������������ł���B���́uBride & Prejudice�v���{������C���h�ň�Ăɕ���ꂽ�B���Ȃ݂ɁA�C���h�l�ϋq��z�����āA���̉f��͉p��o�[�W�����ƃq���f�B�[��o�[�W�����̗��������J����Ă���B�p��o�[�W�����̑薼�́uBride
& Prejudice�v�A�q���f�B�[��o�[�W�����̑薼�́uBalle Balle! Amritsar to L.A.�v�ł���B���e�͑S���������Ǝv����̂Œ��ӂ��K�v���B�����͉p��o�[�W�����́uBride
& Prejudice�v���o�u�q�A�k�p���Ŋӏ܂����B�p��o�[�W������I�̂́A����͂�͂�A�C�V���������[�E���[�C���p��̉f��ɏo������Ƃ����o�������d�v�Ȃ̂ł���A�q���f�B�[��o�[�W����������̂͑����ד��Ȃ悤�Ɏv�������炾�B
�@����́uPride & Prejudice�v�����A�f��̑薼�͂�������������uBride & Prejudice�v�ƂȂ��Ă���B������f����Ⴂ�����̌������e�[�}�ɂ��Ă���A���������Ӗ��Łupride�i�����j�v���ubride�i�ԉŁj�v�ɕύX�����̂��Ǝv�����A���́uB�v�͓����Ƀ{���E�b�h�́uB�v���Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B�ē͏�q�̒ʂ�O�����_���E�`���b�_�[�A���y�̓A�k�E�}���N�A�B�e�ḗuAsoka�v�i2001�N�j�̃T���g�[�V���E�V���@���B�L���X�g�́A�}�[�e�B���E�w���_�[�\���A�A�C�V���������[�E���[�C�A�A�k�p���E�P�[���A�i�[�f�B���E�o�o���A�i���B�[���E�A���h�����[�Y�A�i�����^�[�E�V���[�h�J���A�s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[�A���[�O�i�[�A�C���f�B���[�E���@���}�[�A�j�e�B���E�K�i�g���[�A�\�[�i�[���[�E�N���J���j�[�A�_�j�G���E�M���[�X�A�}�[�V���[�E���]���A�A���N�V�X�E�u���f���ȂǁB���{�ł����J�����\�������邵�A�y���݂ɂ��Ă���l�������Ǝv���̂ŁA�������ꂩ�猩��\�肪����l�́A�ȉ��̂��炷�����]�͓ǂ܂Ȃ��������������Ȃ��B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�}�[�e�B���E�w���_�[�\���i���j��
�A�C�V���������[�E���[�C�i�E�j |
�� |
| Bride & Prejudice |
�@�A�����g�T���ݏZ�̃o�N�V�[���i�A�k�p���E�P�[���j�ƃo�N�V�[�v�l�i�i�[�f�B���E�o�o���j�̉Ƃɂ͂S�l�̎o���������B�ォ��W�����[�i�i�����^�[�E�V���[�h�J���j�A�����^�[�i�A�C�V���������[�E���[�C�j�A�}�[���[�i���[�O�i�[�j�A���L�[�i�s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[�j�ł���B�W�����[�͑�l�������i�ŁA�����^�[�͌��������ŁA�}�[���[�͌ÓT�|�p�ɂ͂܂��Ă���A���L�[�͊����ȏ��̎q�������B�ŋ߂̃o�N�V�[�v�l�͂S�l�o���̌����̂��Ƃœ��������ς��������B
�@������A�o�N�V�[��Ƃ͗F�l�̌������ɏo�Ȃ��A�����ʼnp���ݏZ�̃C���h�l��x���o�����[�W�i�i���B�[���E�A���h�����[�Y�j�A���̖��̃L�����i�C���f�B���[�E���@���}�[�j�A�����Ă��̗F�l�ŕč��̑�x���E�B���E�_�[�V�[�i�}�[�e�B���E�w���_�[�\���j�Əo��B�o�����[�W�̓W�����[�Ɉ�ڍ��ꂵ�A�W�����[���o�����[�W���C�ɓ��邷�����A�_�[�V�[�ƃ����^�[�͉��ƂȂ����݂��C�ɂȂ�Ȃ���������������B�����^�[�̓_�[�V�[�̍����ȑԓx�A���ɃC���h��n���ɂ����ԓx���C�ɐH��Ȃ������B
�@�o�����[�W�̓W�����[�ƃ����^�[���S�A���s�ɏ��҂��A�����Ńo�����[�W�ƃW�����[�̒��͈�w�[�܂����A���s�����_�[�V�[�ƃ����^�[�̒��͂܂��܂������ɂȂ����B�����������^�[�̓S�A�ŃW���j�[�E�E�B�b�J���i�_�j�G���E�M���[�X�j�Əo����ė��ɗ�����B�E�B�b�J���̓_�[�V�[�̒m�荇�����������A�ނ�ь������Ă���A�����^�[�Ƀ_�[�V�[�̈����𐁂����ށB����Ƀ_�[�V�[�������ɂȂ��������^�[�̓E�B�b�J�����A�����g�T���ɏ��҂��ĕʂ��B
�@�W�����[�ƃ����^�[�̓A�����g�T���ɋA���ė��邪�A�����ɃE�B�b�J��������A�o�N�V�[�Ƃɋ��邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�����̃��L�[���E�B�b�J���Ɉ�ڍ��ꂵ�Ă��܂��A�Q�l�̓f�[�g������悤�ɂȂ�B�������o�N�V�[�Ƃɂ͕č����T���[���X�ݏZ�̃C���h�l��x���ʼn����̐e�ʂ̃R�[���[���ԉŒT���ɂ���ė���B�R�[���[�̓����^�[�ɖڂ�t����B���̂Ƃ��A�����g�T���ł̓i�����[�g���[�̃K���o�[�Ղ��J�Â���A�o�N�V�[��ƁA�_�[�V�[�A�o�����[�W�A�E�B�b�J���Ȃǂ��X�e�B�b�N�E�_���X��x��B�����ŃR�[���[�̓����^�[�̗F�l�`�����h���E�����o�[�i�\�[�i�[���[�E�N���J���j�[�j�Əo��B�R�[���[�̓����^�[�ɋ������邪�A�����^�[�͋��ɂ����l���̉��l�����o���Ă��Ȃ��R�[���[���D���ł͂Ȃ��A�f��B�R�[���[�͓{���ăo�N�V�[�Ƃ��o�Ă��܂��A���̂܂܃`�����h���E�����o�[�ɋ������Č������Ă��܂��B�_�[�V�[�A�o�����[�W�A�L�����A�E�B�b�J������C���h����ɂ����B���̌�A�o�����[�W����W�����[�ɉ��̘A�����Ȃ��A�E�B�b�J���̓��L�[�ɂd���[���𑗂葱���Ă����B
�@�S�l�o���̌��������܂��������A�o�N�V�[�v�l�͏ł��Ă������A���̂Ƃ����T���[���X�̃R�[���[����d�b������B�R�[���[�ƃ`�����h���E�����o�[�̌����������T���[���X�ōs����̂ŁA�S�l���̃��X�s���q��p�ӂ����Ƃ̂��Ƃ������B���k�̃`�����X�ƃo�N�V�[�v�l�͂�����ӂ��Ԏ��ʼn������A�v�l�A�����^�[�A�W�����[�A���L�[�̂S�l�����T���[���X�Ɍ��������ƂɂȂ����B���̓r���A�����h���ŃX�g�b�v�I�[�o�[���ăo�����[�W�Ɖ���Ƃ������A�����ɂ����̂Ƃ��ނ͉p���ɂ͂��Ȃ������B����A���L�[�͖����ɃE�B�b�J���Ɖ�A�f�[�g�����Ă����B
�@���T���[���X�Ńo�N�V�[��Ƃ̓_�[�V�[�̉ƂɌĂ�A�ނ̕�e�L���T�����i�}�[�V���[�E���]���j�▅�̃W���[�W�[�i�A���N�V�X�E�u���f���j�Əo��B�����^�[�̓_�[�V�[�ƃf�[�g�����āA�_�[�V�[�ɑ��ĕʂ̊��������n�߂�B�����A��e�̃L���T�����̓����^�[���C�ɓ����Ă��炸�A�R�[���[�ƃ`�����h���E�����o�[�̌������Ń����^�[�Ƀ_�[�V�[�̗��l���Љ�ĂQ�l�̒����Ӑ}�I�Ɉ����B�܂��A�_�[�V�[���W�����[�ƃo�����[�W�̌������ז����Ă������Ƃ�m��A�����^�[�͊��S�Ƀ_�[�V�[�Ɉ��z�������B�_�[�V�[�͂₯�����ɂȂ��ă����^�[�Ɉ��̍��������邪�A�ޏ��͎e��Ȃ������B
�@�����h���ɖ߂����o�N�V�[��Ƃ�ǂ��āA�_�[�V�[�������h���ɂ���ė���B�����Ń��L�[�ƃE�B�b�J�����f�[�g�����Ă��邱�Ƃ�m��B���̓E�B�b�J���̓_�[�V�[�̖���D�P�������ߋ������댯�Ȓj�������B���L�[�̐g����Ȃ����Ƃ�m���������^�[�́A�_�[�V�[�Ƌ��Ƀ��L�[��T���o���A�A��߂��B���̌������������ɁA�_�[�V�[�ƃ����^�[�̒��͋}���ɐڋ߂��A�₪�ĂQ�l�͌������邱�ƂɂȂ�B�܂��A�W�����[�̂��ƂɃo�����[�W���K��A�����Ɍ�����\�����ށB
�@�����^�[�ƃo�����[�W�A�W�����[�ƃ_�[�V�[�̌������̓A�����g�T���ŃC���h���ɐ���ɏj��ꂽ�B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�O��u�x�b�J���ɗ����āv�̓q���O���b�V���f��̓T�^��ŁA���p���f��Ɍ���Ȃ��߂���i�ł��������A����͉p���̏������x�[�X�ɂ��Ă���Ƃ͌����A�C���h�f������ۓI�ɁA���p��ɂ����f��Ƃ��������������B�C���h�f��Ƃ��Č��������x�y�������A�p���f��Ƃ��Č����ꍇ�̕]���ɂ͋^�╄���t���B�ꌾ�Ō����A���҂��͉��̍�i�������B
�@�X�g�[���[�̑�͌���Ǝ��ʂ��Ă��邪�A���䂪�C���h�̃A�����g�T���A�S�A�A�p���̃����h���A�č��̃��T���[���X�ƂȂ�A����̂T�l�o�����S�l�o���ƂȂ�A�o��l���̑������C���h�l�ɂȂ��Ă���_�ő傫�ȈႢ���������B�܂��A����ł͖����̃��f�B�A�͋삯�������Ă��܂����A����ł̓C���h�I�ǐS���������̂��A����Ƃ��C���h�f��I��c�~�n�b�s�[�G���h�̕K�R�����K�v�������̂��A���L�[�͋삯�����O�Ƀ����^�[��ɑj�~����邱�ƂƂȂ����B����ŃG���U�x�X�i�����^�[�̃��f���j�ƃ_�[�V�[���u�Ă��̂͊K���̍����������A����ł͕����̍��ƂȂ��Ă����̂����M���ׂ����B���ɂ�����Ƃ̑���_��T���Ă����ƁA�C���h�l�ƃC���h�f��̎���������邩������Ȃ��B�����A��{�I�ɂQ�O�O�N�O�̉p���ŏ����ꂽ����́A�����قnj��݂̃C���h�f��̋Ɏ��Ă���ƌ����Ă������낤�B����́u���Y�Ɍb�܂ꂽ�Ɛg�̒j���ł���A�Ȃ��ق������Ă���ɂ������Ȃ��Ƃ����̂��A���Ԉ�ʂɔF�߂�ꂽ�^���ł���v�Ƃ����L���Ȉ�߂Ŏn�܂邪�A����̓C���h�f��̕������ɂ��������Ă͂܂�B�������A���ꂱ�������̉f��̍ő�̌��_��������������Ȃ��B
�@�q���O���b�V���f������ɗ���ϋq�́A�ʏ�̃C���h�f��Ƃ͈�������̂����߂ė��Ă��邱�Ƃ������B�O��u�x�b�J���ɗ����āv�͐��ɂ��������ϋq�ɑi����������̂����������߁A�C���h�ł��s�s���̒��㗬�K���w�𒆐S�Ɏe���ꂽ�B����͂���Ɠ����ē̍ŐV��Ƃ������ƂŁA���Ȃ���҂����ĉf��قɑ����^�C���e���w���������Ƃ��낤�B���̊ϋq�ɃC���h�f��̏Ă������݂����ȉf��������Ă��͂悭�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��A�����^�[�ƌ����j�����č��l�ł���K�v�͓��ɂȂ��悤�Ɏv�����B�č��ݏZ�̑�x���m�q�h�i�݊O�C���h�l�j�ŁA���g�̃��[�c�ł���C���h�ɕΌ��������Ă��鍂���Ȓj�A�Ƃ����ݒ�ɂ��Ă��܂��Ă��f��͐��藧���A���̕����q���O���b�V���f��Ƃ��Đ[�݂��o��悤�Ɏv�����B����ɁA�C���h�̏��_�I���݂ł���A�C�V���������[�E���[�C���O���l�ƌ������Ă��܂��Ƃ����v���b�g�́A�ʂ����đ�O�Ɏe�����̂��s���ł���B�A�C�V���������[�łȂ��Ă��A�����̏������O���l�ƌ�������Ƃ����b�́A�����̏������O�G������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����{�\�������Ă���j���ɂ́A�����I�E�S���I�Ɏe�ꂪ�����Ǝv����B���̉f��͊C�O�ł������[�X�����悤�����A���܂�ɃC���h�f��I�߂��邽�߁A�l�͂���قǃq�b�g���Ȃ��Ɨ\�z����B
�@�f�撆�͑����̃~���[�W�J���E�V�[���A�_���X�V�[�����}������Ă����B�p���W���[�u������������n�܂�A�S�A�̃p�[�e�B�[�A�i�����[�g���[�̃_���f�B���[�i�X�e�B�b�N�E�_���X�j�ȂǁA�C���h�̖��͂�]���Ƃ���Ȃ��i�ߏ�ɁH�j�`���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�����A�u�x�b�J���ɗ����āv�ł��������������A�O�����_���E�`���b�_�[�ē̉f�悩��́A���̃q���O���b�V���f��ɂ悭������A�C���h�����ւ̑��h�⓲�ۂ����܂芴�����Ȃ��B�ޏ��ɂƂ��āA�C���h�����͉f����̒��S�e�[�}�ł͂Ȃ��A�f������藧�Ă鑕���i�ɂȂ��Ă���悤�Ɋ������B
�@�L���X�e�B���O�ɂ��^�₪�c�����B�A�C�V���������[�̑�����A�}�[�e�B���E�w���_�[�\���́A�u�U�E�����O�v�i2002�N�j�Ȃǂɏo�����Ă����j���[�W�[�����h�o�g�̎��j�D�B�����A�n���T���Ȃ����ł܂����Z�͔͂��W�r��Ƃ��������������B�A�C�V���������[���g���A���̍��ۉf��Ƃ������Ƃŋْ����Ă����̂��A������Ɖ��Z�����������B�o�N�V�[�ƂS�o���̔z���������Ƃ͎v���Ȃ��B�E�B�b�J�����������_�j�G���E�M���[�X�́A�u�X�p�C�_�[�}���Q�v�i2004�N�j�ɂ��o�Ă����o�D�����A���܂�Ɉ����炷���ăE�B�b�J�����ɂ͎�����Ȃ������B������ɔ�߂����j�q�A�Ƃ����j�D��T���ׂ��������B�o�N�V�[�����������A�k�p���E�P�[����������ƃA�s�[���Ɍ��������A���X�����o�N�V�[�v�l���������i�[�f�B���E�o�o���͏G��B�u�J�[�}�E�X�[�g���@���̋��ȏ��v�i1996�N�j�Ŏ�l���}�[���[�����������C���f�B���[�E���@���}�[�i�C���h�l�ƃX�C�X�l�̃n�[�t�j���A�o�����[�W�̖��L�������������Ă������A�ޏ��̉��Z�������I�ł悩�����B�܂��A�o�����[�W���������i���B�[���E�A���h�����[���A���f��Ń��[�W�E�X�B���������Ă����j�D���B
�@�uBride & Prejudice�v�́A�q���O���b�V���f������҂��Č��ɍs���Ɗ��ҊO��ɏI���f�悾���A���i�q���f�B�[�ꂪ������Ȃ��ăC���h�f����h�����Ă���l�ɂ͂��������ăI�X�X���ł���f�悩������Ȃ��B�����날�̃A�C�V���������[�E���[�C���p��Ŋy���߂�̂��B���Ԃ���������q���f�B�[��ł́uBalle Balle! Amritsar to L.A.�v�����āA����ׂĂ݂����Ǝv���i�P�O���P�S���̓��L���Q�Ɓj�B
�@�����͐V��q���f�B�[��f��uShukriya�v���o�u�q�A�k�p���Ō����B�uBride & Prejudice�v�Ɠ������J�ƂȂ�A�e�������Ȃ��Ă��܂��Ă��邪�AL.K.�A�[�h���@�[�j�[��������^�����Ƃ����L���������̂ŁA�ӏ܂��鉿�l�͂��邾�낤�Ǝv���A�f��قɑ����^�B
�@�uShukriya�v�Ƃ́u���肪�Ƃ��v�Ƃ����Ӗ��B�ē͐V�l�̃A�k�p���E�X�B���n�[�B�uTum Bin�v�i2001�N�j�̃A�k�o���E�X�B���n�[�ē̒�炵���B���y�̓q���[�V���E���[�V���~���[�A���B�V���[���E�V�F�[�J���A���[�Q���h�����f�[���F���h���̍���B�L���X�g�́A�A�[�t�^�[�u�E�V���_�[�T�[�j�[�A�V�������[�E�T�����A�A�k�p���E�P�[���A���e�B�E�A�O�j�z�[�g���[�A�C���h���j�[���E�Z�[���O�v�^�[�A�A�[���e�B�[�E���w�^�[�ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�A�[�t�^�[�u�E�V���_�[�T�[�j�[�i�E�j��
�V�������[�E�T�����i�����j |
�� |
| Shukriya |
�@�p���ɏZ�ޑ�x���̃C���h�l�A�W���_���i�A�k�p���E�P�[���j�́A���������U�O�̒a�������}���悤�Ƃ��Ă����B�Ȃ̃T���f�B���[�i���e�B�E�A�O�j�z�[�g���[�j�A���̃A���W�����[�i�A�[���e�B�[�E���w�^�[�j�ƃT�i���i�V�������[�E�T�����j�́A�W���_���̒a�����p�[�e�B�[�̏����ŖZ���������B�܂��A�W���_���͎��g�̒a�����ɁA���N�̖����������a�@�̊J�@�����s�����Ƃ��v�悵�Ă����B�W���_���͕�e�����Ŏ����Ă���Ƃ������̂́A���ɖ`���ꂽ�n�����l�X�̂��߂̖����̕a�@��ݗ����悤�Ɩ����Ă����̂������B
�@�Ƃ��낪�A�}�ɃW���_���͂������Ȑ����悤�ɂȂ�B�ŏ��͋C�̂������Ǝv���Ă������A���̐��͎��_�̐����Ɗm�M����悤�ɂȂ�B�a�����̂S���O�A���_�̓W���_���Ɂu���O�̖��͂��ƂQ���Ԃ��v�Ɛ鍐����B�W���_���͂�����e��邪�A���_�Ɏ��g�̖������A�u���O�ɐl�Ԃ̓���͕�����Ȃ����낤�v�ƌ����ƁA���_�͒a�����܂ł̂S���ԁA�P�\�����ꂽ�B
�@�Ƃ���ŁA�T�i���ɂ͍ŋߋC�ɂȂ�j���������B�M�^�[�e���̃��b�L�[�i�A�[�t�^�[�u�E�V���_�[�T�[�j�[�j�ł���B�T�i���̓��b�L�[�̂��Ƃ��^���̐l���Ǝv���Ă�������ŁA���b�L�[���T�i���̂��Ƃ��C�ɂȂ�n�߂Ă����B�T�i���͕��e�̒a�����p�[�e�B�[�Ƀ��b�L�[�����҂���B�Ƃ��낪���̒���A���b�L�[�͌�ʎ��̂ɂ���Ď���ł��܂��B
�@���_�ɂ���ĂS���Ԃ̗P�\���W���_���́A���̎��Ԃ�L���Ɏg�����ƍl���Ă����B����ƁA�ނ̂��ƂɁA���b�L�[�̐g�̂����_������ė���B���_�́A�W���_���̌��t�ɉe�����A�l�Ԃ̐��E��̌����ɂ���ė����̂������B���_�̓W���_���̉Ƃɋ���悤�ɂȂ�B���b�L�[������ė����Ǝv�����T�i���́A���������т������B���_�̓W���_���̉Ƒ��Ƌ��ɕ�炷���ɁA��e�̈��A�Ƒ����J�A�����ăT�i���Ƃ̗���̌�����B
�@���ɃW���_���̒a�����A�܂�ނ̎��ʓ�������ė���B�W���_���͊��a�@�̊J�@�����s���A��ɂ͒a�����p�[�e�B�[���s���B���_�̓T�i�����ꏏ�ɂ��̐��ɘA��čs�����Ƃ��邪�A�T�i���������Ă���̂̓��b�L�[�ł���A���_�ł͂Ȃ����Ƃ�������ނ͂�������߂�B�T�i���͕��e�Ǝ��_���b���Ă���̂����R�����Ă��܂��A���e���������ʂ��ƁA�����ă��b�L�[�͖{���͎��_�ł��邱�Ƃ�m�邪�A�������Ȃ������B�a�����p�[�e�B�[�̓r���A�W���_���͂�������ƐȂ��O���A���̂܂��_�Ƃ��̐��֗����B��������Ă����T�i���̑O�ɁA���b�L�[���߂��ė���B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@���܂�b��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A�߂����ƍK�������荬�������C���ɂȂ�N���C�}�b�N�X�����C���悢���삾�����B��̓u���b�h�E�s�b�g�剉�́u�W���[�E�u���b�N����낵���v�i1998�N�j�Ɏ��Ă��邪�A����ɁA�q���h�D�[���̍Ղ�ł���J�����[�E�`���E�g��D�荞�_�ŁA�C���h�l�̐S��ł�i�Ɏd�オ���Ă����B�܂��A���݃C���h�͑c�搒�q���s�����ԃV�����[�b�h�i�s�g���E�p�N�V���j�ł���A���̎����̓C���h�l�͍����Ȕ����������Ȃ����ƂŒm���Ă���B�������R�ŁA�z����Ђ����̎����ɉf��������[�X���邱�Ƃ������X���ɂ���̂����A���̉f��͂܂��ɃV�����[�b�h�ɂ҂�����̉f�悾�����B
�@�O���͂��肫����̃{�[�C�E�~�[�c�E�K�[���I�W�J�őދ����������A�W���_���̑O�Ɏ��_������钆�Ոȍ~�A����͋}�ɖʔ����Ȃ�B���b�L�[�����͎��_�ł��邱�Ƃ�m���Ă���̂̓W���_�������ŁA�T�i���͔ނɗ�����悤�ɂȂ�B�Ȃ̃T���f�B���[�����b�L�[���C�ɓ���A�䂪�q�̂悤�ɂ��킢����B���̂悤�Ȉ���͎��_�ɂƂ��ď��߂Ă̌o���������B
�@�ł��D��Ă�����ʂ̓J�����[�E�`���E�g�̃V�[���ł���B�J�����[�E�`���E�g�̓C���h�f��ɓx�X�o�Ă���Ղ�ŁA���{�Ō��J���ꂽ�u�~�����v�i1999�N�j��u�A�V�����v�i1994�N�j�Ȃǂł��o�Ă����B���A��ōՓ��͌��肳���̂Ŗ��N���t�͕ς��̂����A���N�͂P�O���R�P�����Ƃ���Ă���B���̓��A�����̏��������͒�����ӂ܂łP�����A�������H�����܂Ȃ����i�Ȓf�H�����A������������v�ɒf�H��j�鐅�����܂��Ă��炤�V�����s���B���o�I�ɂ́A�~�`��⿁i�ӂ邢�j�Ɍ������āA���ɕv�̊�����Ƃ������삪�L���Ɏc�邾�낤�B���̍Ղ�͕v�̒������F�邽�߂̂��̂ł���B�J�����[�E�`���E�g��ʂ��āA���_�͐l�Ԃ�������l�̒������F��s�ׂ�m��A�W���_���͍Ȃ̋F���������������������ł��܂������̉^���ɗ܂���B�܂��A�T�i���ɃJ�����[�E�`���E�g�̋V�������Ă��炤���ƂŁA���_�͔ޏ��ւ̈����m�ł�����̂ɂ���i���_�ɃJ�����[�E�`���E�g������Ƃ�����ʂ͗�Âɍl����Ί��m�����E�E�E�j�B
�@�V�l�j�D�C���h���j�[���E�Z�[���O�v�^�[�����郄�V���̑��݂͑������܂��g������Ă��Ȃ��������B�T�i���̓��V���Ƃ����c����݂�����A�ނ̓W���_���̉�Ђ̏d�������߂Ă����B���V���͖����ɃT�i���ɗ����Ă����̂����A���b�L�[�����ꂽ���Ƃɂ��A��Ђł̒n�ʂ����������ɂȂ������肩�A�T�i���܂Ń��b�L�[�Ɏ����čs���ꂻ���ɂȂ�A�ނށB���V���̓`���s�����ق��ă��b�L�[���E�����Ƃ܂ł���̂����A���_���E����͂����Ȃ��A�`���s�������͌��ނ����B���_�͂��ꂪ���V���̍������ł��邱�Ƃ�m�����̂����A���ɔނ�ӂ߂Ȃ������B�����܂ł͂悩�����̂����A���̌�}���Ƀ��V���͕���̒��ő��݊��������B���V���ɂ͂����ЂƊ撣�肳���Ă������������B
�@�x�e�����o�D�A�A�k�p���E�P�[���ƃ��e�B�E�A�O�j�z�[�g���[�̉��Z�͕���̂��ǂ��낪�Ȃ��قǑf���炵�������B���ʂ̐N�Ǝ��_�������������A�[�t�^�[�u�E�V���_�[�T�[�j�[���A�x�X�g�̉��Z�����Ă����Ǝv���B�����A�����炭�ϋq�̔]���ɍł��N���Ɉ�ۂɎc��̂́A�T�i�����������V�������[�E�T�����ł���B�ޏ��́uThoda
Tum Badro Thoda Hum�v�i2004�N�j�Ƃ����S�����s��ɏI������f��Ńf�r���[�������������A�l�͂��̉f��Ŕޏ������߂Č����B�Z���ڂ̊�Ȃ���A�C���h�l���D�������ȃ^�C�v�̌��N�I���l�ŁA�ڂ��N���N�����Ă��ĕ\��L���Ȃ̂������B�x������C�������Ă����B�l�ɂ͎Ⴋ���̃}�[�h�D���[�E�f�B�[�N�V�g��J�[�W���[�����v���N���������B���ꂩ��啨���D�ɂȂ��Ă����Ɨ\�z���Ă���B�Ȃ����~�j�X�J�[�g���悭�͂��Ă���A���ɍۂǂ��A���O�������������̂��C�ɂȂ����B�p���`�����D�Ƃ��Ĕ���o������Ȃ̂��B
�@����͑S�҃����h���ł���A�����h���ƃX�C�X�Ń��P���s��ꂽ�Ƃ����B���ɊC�O��ɂ���K�v�͂Ȃ������Ǝv�����A�C���h�f��̂��Ƃ������ƂŁA���̕ӂ�͂��܂�ӂ߂Ȃ��ł����B
�@�u���肪�Ƃ��v�Ƃ����Ӗ��̑薼�́A�����炭������������l�Ԃ�������l�X�ɍł������������t�Ƃ������Ƃ��낤�B�f�撆�A�W���_���͂��낢��ȈӖ������߂ĉ��x�����ӂ̌��t�𑽂��̐l�ɓ��������Ă����B�Ō�͎��_�ɂ���ނ́u���O�����ɂ��ꂽ�S���Ԃ͐l���ōō��̓��X�ɂȂ����B���肪�Ƃ��v�Ɗ��ӂ���B���_���A�l�ԂƂ��Đ��������������Ă��ꂽ�W���_���Ɋ��ӂ̌��t���q�ׂ�B�W���_�����Ō�ɍȃT���f�B���[�Ɍ������t�A�u�����ł��l�ƌ������Ă���邩���H�v���悩�����B
�@���݁A�uBride & Prejudice�v���b�肾���A���́uShukriya�v���Ȃ��Ȃ������f��ł���B�O���̂��肫����ȓW�J���䖝����A��͍K���ȗ܂𗬂����Ƃ��ł��邾�낤�B
�@�ŋ߃f���[�͋}���Ɋ����Ȃ����B�P�T�ԂقǑO�ɐ����ԑ����ĉJ���~��A�C���������������A���̂܂㏸�����ɗ��܂��Ă��銴�����B���ɒ��ӂ̗₦���݂͂P�Q�����݂ł͂Ȃ��낤���B�l�͓��ɂ����ɃV�����[�ɂ̓M�U���i�d�C������j���g�p���Ă���i�C���h�ł̓z�b�g�E�V�����[���ґ�i�ł���A���╗�C����j�B���̂܂܋Ɋ��̓~�ɓ˓����Ă��܂��̂��낤���B
�@�X���܂ł͎��Ԃɗ]�T���������̂����A�P�O���ɓ���A������Ƃ��Z�����Ȃ��Ă����B�^�[���E�y�[�p�[�ƌĂ��_�������|�[�g�ƁA�Z�~�i�[�E�y�[�p�[�ƌĂ�錤�����\�p���|�[�g���P���Ƃɂ��P�{�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃɂ���ĈႤ���A��̃^�[���E�y�[�p�[�͂P�O���ȓ��A�Z�~�i�[�E�y�[�p�[�͂P�P���ȓ��������ƂȂ��Ă���B���ݎ��Ƃ��S����Ă���̂ŁA���v�W�{�̃��|�[�g���܂Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�P�T�ԂɂP�{�̃��|�[�g���d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Z�ɂȂ�B�����ăZ�~�i�[�E�y�[�p�[���o���A���\���I���鍠�ɂ͂��������e�X�g���҂��Ă���B
�@�����͂���ƂP�{���|�[�g���d�グ�Đ��ꐰ�ꂵ���C���������̂ŁA�o�u�q�A�k�p���ɐ�������q���O���b�V���f��uBride & Prejudice�v�̃q���f�B�[��ŁuBalle Balle! Amritsar to L.A.�v�����ɍs�����B�����͂������ꂪ�Ⴄ�����ŁA���e�͑S���ꏏ�ł���B����āA���炷���ɂ��Ă��P�O���W���i���j�̓��L�����Ă��炢�����B�����ł́A�p��łƃq���f�B�[��ł̔�r�A�܂��V���ɋC�t�������ƂȂǂ��܂Ƃ߂�B��͂�l�^��ɂȂ�̂ŁA�f������Ă��Ȃ��l�͂��܂�ǂ܂Ȃ�����������������Ȃ��B
�@�܂��A�p��ł������Ƃ������q���f�B�[��ł̕����A���y���߂��悤�ȋC������B���ɉp������q���f�B�[��̒������\�͂̕��������Ă��邽�߁A���e���������ł������Ƃ���������A��͂�C���h�l���p�������ׂ�f������q���f�B�[�������ׂ�f��̕������R�ɂ���Ȃ�C���h�f��̐��E�ɓ����Ă�����B�܂��A�Q�x�ڂ̊ӏ܂��������߁A�ׂ��������ɂ܂Œ��ӂ������邱�Ƃ��ł����B
�@�薼�́uBalle Balle!�v�Ƃ́A�p���W���[�r�[��̊������ŁA�u���I�v�u������`�I�v�u�t���[�I�v�݂����ȈӖ��B�p���W���[�u�n���̃o���O���[�E�_���X�Ȃǂ����Ă���ƁA�悭�_���T�[�������u�o�b���[�A�o�b���[�I�v�ƗY���т��グ��B���̑��A�u�n���b�p�I�v�u�V���[�o�[�I�v�u���b�o�[�I�v�Ȃǂ������悤�ȈӖ��ŁA�����̌�b�������ł��m���Ă���ƁA�p���W���[�u�B�̓`�����x�o���O���[�E�_���X�̉̎����y���߂�悤�ɂȂ�B���łɑ��ɂ��o���O���[�Ȃǂŕp�o����ȒP�Ȍ�b�������Ă����ƁA�`���N�E�f�[�E�p�e�[�i�K���K���s�������I�j�A�N�b�f�B�[�i���̎q�j�A�W���O�j�[�i�C�}�h�L�̏��̎q�j�A���[���i�������l�A�e�����l�j�A�\�[�j�[�i�����x�b�s������j�A�q�[���[�i�_�C�������h���x�b�s������j�A�i�[�`���i�_���X�j�A�����_�[�i�^�[�o���j�A�L���p�[���i�Z���j�A�K�b�f�B�[�i�ԁj�ȂǁB�����̌�b�́A���̉f�������ۂɂ��𗧂��낤�B
�@����͐����ւ��������B�܂�A�p��ł̕����I���W�i���ŁA�q���f�B�[��ł͂��̏ォ�琁���ւ������Ă���B�O���l�o�D�̃Z���t�𐺗D�������ւ��Ă����͓̂��R�����A�C���h�l�o�D�̃Z���t�����ۂ̖{�l�̐��ł͂Ȃ��l��������������Ȃ��B���̕M���̓A�C�V���������[�E���[�C���B�A�C�V���������[�́u�q���f�B�[��ł̐����ւ�������Ȃ�Č_�ɏ����ĂȂ��v�Ɛ����ւ���f�����炵���B���ɁA�A�k�p���E�P�[���̐����{�l�ł͂Ȃ��悤�Ɏv�����B���D��N������Ă������͒m��Ȃ����A�J�[�g�D�[���E�l�b�g���[�N�i�A�j�����`�����l���j�ł悭���������������������悤�ȋC������B�r���}�������~���[�W�J�����A�q���f�B�[��i�܂��̓p���W���[�r�[��j�̋ȂɂȂ��Ă����B�����A���y�����͉p��������n��̕�����ɂ����B�p��̃C���h�f��I�~���[�W�J��������͈̂�a��������B���������uLagaan�v�i2001�N�j�́uO Rey Chhori�v�ł��C���h�f��I�p��~���[�W�J�����������B
�@�������Ă݂āA�A�C�V���������[�ɂȂ��e�C���������Ȃ������̂����悭���������B���ʁA�{���E�b�h�f��̓X�^�[�V�X�e�����̗p���Ă���A����̒j�D�⏗�D�͂�肩�����悭�A��������������悤�ɍH�v����Ă���B�Ⴆ�A�b�v�̃V�[�������|�I�ɑ���������A�ށ^�ޏ������w�̍����e����������ŕ��ׂȂ�������A�Ɩ����H�v���Ĕ����Ȃ�ׂ�������������A�Ƃ��낢��ȋZ�@������Ă���B���������̉f��ł̓O�����_���E�`���b�_�[�ē͈���������z�������Ă��Ȃ������B���̂��߁A���̉f��ł͎��ۂ�萔�������ɐ_�X����������A�C�V���������[���A���̘e����G�L�X�g���̒��ɕ���Ă��܂��āu���ʂ̐l�v�Ɖ����Ă��܂��Ă����B����ł��āA�A�C�V���������[�͊�ȂɃL�X�E�V�[�������悤���B���Ȃ��Ƃ��R��A�L�X�̃`�����X�����������i�P��̓E�B�b�J���ƁA�Q��̓_�[�V�[�Ɓj�A�ǂ���L�X���O�ŏI�����Ă����B�������E�Ɍ����ĉH��������������A���Ƀn���E�b�h�Ŋ�����������A�m�[�L�X�ł͂���Ă����Ȃ����낤�B�ʂ����ăC���h�̏��_�͐��E�̏��_�ƂȂ邽�߂Ƀv���C�h���̂Ă�̂��낤���A����Ƃ��C���h�̏��_�ŗ��܂�̂��낤���H�܂��A�A�C�V���������[�������ɂȂ�V�[�������������A�قƂ�ǔޏ��̑S�g�͉f����Ȃ������B
�@������Ƃ̌���������ē��f�扻������������A�����̎��_���S�̉f�悾�Ǝv�����B�����̋����Ǝコ�A�������ƏX���̃R���g���X�g���A�j���ɂ͂�����Ɛ^���ł��Ȃ����炢�I���ɕ`����A�����ɂƂ��Ăǂ������l������ԍK���Ȃ̂����l��������͂�����f��ł���B�������m�̊W�͔����k���ɕ`����Ă������A�j���̓o��l���̕`�ʂ̓X�e���I�^�C�v�ł��e�����B��������Ɠ����m���ł���B����䂦�A�o�N�V�[�����������A�k�p���E�P�[���A�_�[�V�[���������}�[�e�B���E�w���_�[�\���A�E�B�b�J�����������_�j�G���E�M���[�X�Ȃǂ̐��ݔ\�͂���������Ă��Ȃ������B
�@�͂����茾���ĉf��̃L�����N�^�[�͂�������܂�[�݂��Ȃ��̂����A�E�B�b�J�������͋c�_���鉿�l������Ǝv���B�E�B�b�J���̓_�[�V�[�̓���̑��q�ŁA�_�[�V�[�Ƃ̔n�̐��b�����ĕ�炵�Ă����B�_�[�V�[�Ƃ͋��Ɉ���������������A�ނ̓_�[�V�[�̖����P�U�̂Ƃ��ɔޏ���D�P�����A�������삯�������悤�Ƃ������߁A�_�[�V�[�͖���D���Ԃ��Ĕނ�Ǖ������B����ȗ��Q�l�͉���Ă��Ȃ������̂����A�S�A�ŋ��R�ĉ��B�_�[�V�[�̓z�e�������̂��߂ɃS�A�ɗ��Ă�������ŁA�E�B�b�J���̓C���h��n�R���s���ăS�A�ɗ��ꒅ���Ă����B�����^�[�̓C���h�ɑ��ĕΌ������_�[�V�[�������A�u���������Ă���Ύ����Ă���قǁA�{���̃C���h���牓������v�Ǝ咣����E�B�b�J���Ɏ䂩���B�E�B�b�J���̓����^�[�Ƀ_�[�V�[�̈����𐁂����݁A�܂��܂��ޏ��̓_�[�V�[�������悤�ɂȂ�B�_�[�V�[�͂��������^�[�Ɂu�E�B�b�J���ɂ͋C��t����v�ƌ��������ŁA�[���b�܂ł͂��Ȃ������B�A�����g�T���ɃE�B�b�J��������ƁA�ނ̓��L�[�ƒ��ǂ��Ȃ�B���L�[�̓����h���ł���������ނ�K�˂邪�A�ނ͑D�㐶���҂������B�Ō�Ƀ����^�[�̓E�B�b�J���ƃ_�[�V�[�̖��̊ԂɋN������������m��A�E�B�b�J�����烉�L�[�����߂�����ŁA�E�B�b�J���̓_�[�V�[�A�����^�[�A���L�[�̂R�l���炻�ꂼ�ꉣ���āA����Ȗ��H�ƂȂ�B�E�E�E���ʂɍl������A�P�l�̖ʂ����Ԃ������������炵�߂��Ĉꌏ�����ƌ��������Ƃ��낾���A�悭�l������A�������̃_�[�V�[�������������^�[�ƌ������A�n�R�ȃE�B�b�J�����A�ߋ��ɉ߂���Ƃ����Ƃ͌����A�܂������^�[�ƃ��L�[�̓�e��ǂ����Ƃ����Ƃ͌����A�s�K�Ȍ�����H��̂́A���ǁu�������ƌ������ׂ��v�Ƃ������̊ܒ~���Ȃ����ʂƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B���̓_�́A�C���h�f��̈�ʓI�X�g�[���[�Ƒ����قȂ�悤�Ɏv����B�C���h�f��ł́A�n������l������x���̑��q�܂��͖��Ƌ������z���Č�������Ƃ����X�g�[���[�����������D�܂��B
�@����̂T�l�o�����S�l�o���ɂ����̂͌����������ƌ�����B�����Ƃ��e�������Ȃ��Ă��܂��Ă����͎̂O���̃}�[���[�B�ÓT���y��ÓT���x���Ȃ����M�S�ɏK�����Ă��鏗�̎q�Ƃ�����̐ݒ�ȏ�ɁA����ꏊ�͓r���̃R�u���E�_���X�����i����͂���ʼnf�撆�����Ƃ����͂̂���V�[�������j�B�O���I�ɂ��S�l�o���̒��ň�Ԍ���肪���Ă���A���킢�����������B�����W�����[���������i�����^�[�E�V���[�h�J���͖Ƀs�b�^�����Ɗ��������A�A�C�V���������[�ƕ��ԂƂ��܂蒷�����ۂ��Ȃ��̂���_�������B�l���̃��L�[���������s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[�́A�A�C�V���������[�������S�o���̒��ň�Ԗڗ����Ă����B
�@���Z�Ƒ��݊��ōۗ����Ă����̂́A�o�N�V�[�v�l���������i�[�f�B���E�o�o���ƁA�o�����[�W�̖��L�������������C���f�B���[�E���@���}�[���B�������ł��������̉��k���܂Ƃ߂悤�Ɩ�N�ɂȂ��e���A�i�[�f�B���͑��X�������A���D������������o���Ȃ��獋���ɉ������B����A�C���h��n���ɂ��A�o�����[�W�ƃW�����[�̌�����ʔ����v��Ȃ��L�������A�C���f�B���[�͑薼�u�����ƕΌ��v������݂̂ő̌������悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ɁA�ϋɓI�ɉ������B�i�[�f�B���̉��Z�͉f��̎������߂Ă������A�C���f�B���[�͘e���̂����ɂ��܂�ɑ��݊������肷���āA�����o�����X���������Ă����悤�ɂ��v�����B
�@�G�L�X�g�����ǂ�����W�߂��̂��͒m��Ȃ����A���̕��ɂ���l�X���悭���Ă݂�Ƃ��������y�����B�����炭�v���̃G�L�X�g���ł͂Ȃ��A���n�Ōق����l��������������̂ł͂Ȃ��낤���B�~���[�W�J���uLo Shaadi Aayi�v�ł̓q�W�����[���o�ꂵ�ėx��o�����A�l�͂��̃q�W�����[�͖{���ł͂Ȃ����Ǝv�����B�{���̃q�W�����[���f��ɓo�ꂳ�����f��Ƃ����̂͋L���ɂȂ��B�܂��A�N���C�}�b�N�X�ł͌������������^�[�ƃ_�[�V�[���ۂ̏�ɏ���Ă���V�[��������B���̃V�[���ɉf���Ă����ێg�����A�ǂ����Ă��{���ł���B�A�C�V���������[�����ɏ悹�āA�݂��ق���т����Ȃ̂����A�����K���ł��炦�Ă���悤�Ȕ����ȕ\��������Ă��Ĕ��܂��������B���ɂ����̃V�[���ł́A�x��Q�O�̒��Ɂu�����N�����Ă�v�ƃ|�c���Ɨ����Ă���l�����Ėʔ��������B
�@�A�����g�T�������䂾������������A�X�B�N���ő�̐��n�ɂ��ăA�����g�T���̃����h�}�[�N�A�������@�����x���f���o����A�X�B�N���k�ɂƂ��Ă͂��߂ł����f��ƂȂ����Ǝv���B���ɖl������ł����ꏊ�́A�O�����h�L���j�I����T���[���X�̃����O�r�[�`�Ȃǂ��B�����h���̃V�[���ʼnf���Ă����V���n�͂��������L���Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���i�p���ɂ͍s�������Ƃ��Ȃ��̂ŕ����炸�j�B
�@�G���f�B���O�E���[���ł́A�W���b�L�[�E�`�F���f���낵�����y���݂m�f�V�[�����W������B�O�����_���E�`���b�_�[�ē��o�Ă���A�}�[�e�B���E�w���_�[�\���ɕ���������A���l�̂�������Ɨx������ƁA��肽�����肾�B�A�C�V���������[�̐��̊���`���b�ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@���{�l�ʼnp��ƃq���f�B�[�ꂪ����������l�͂���قǂ��Ȃ��̂ŁA���ʂ̐l�͖��킸�p��ŁuBride & Prejudice�v������ׂ����낤�B�������A�����q���f�B�[�ꂪ������Ȃ�A�q���f�B�[��ŁuBalle
Balle! Amritsar to L.A.�v�̕����A�C���h�f����L�̗v�f�u���X�v����葽�����邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv����̂ŁA�I�X�X�����B�ʂ����ē��{�Ō��J�����Ƃ�������̂��͕�����Ȃ����A���܂�ɃC���h�f��I�����������̂ŁA��ʎ͓����������Ȃ��B�p���ł����Ɍ��J����Ă��邪�A�����͗l�X�ŁA��^�̗��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������B���s�I�ɂ͂܂��܂��Ƃ̂��ƁB�u�x�b�J���ɗ����āv�i2002�N�j�̓x�b�J���l�C�����Z����Ă����̂ŁA����͂�������������Ċ��肷�ׂ����낤�B
�@�P�V���t���̃T���f�[�E�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɁA�f���[�̉q���s�s�A�O���K�[�I���ƃm�C�_�̔�r���f�ڂ���Ă����B
�@�O���K�[�I���̓f���[�쐼���A�n�����[�i�[�B�ɂ���X�ł���B�O���Ƃ́u��������Ă��Ȃ������v�A�K�[�I���́u���v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA�O���K�[�I���͖�������{��ɂ��Ă��܂��u�������v�ɂȂ�B�����炭�̂̓T�g�E�L�r������ʂɍL�����Ă����̂��낤�B�������A����O���K�[�I���̓f���[�s���̊Ԃōł��z�b�g�ȃV���b�s���O�E�X�|�b�g�ɋ}���������B�O���K�[�I���̒��S�n�̓��[���E���[�h�B�V�e�B�[�E�Z���^�[�A���g���|���^���A�U�E�v���U�A�T�n�[���[�E���[���ȂǁA�x�O�^���僂�[������������ł���B��s�ɐ��i����������H�ƒn�тƂ��Ă��}���ɔ��W���Ă���A�X�Y�L��z���_�ȂǁA���{��Ƃ̍H�������B�ŋ߃O���K�[�I���ł́A�I�x���C�n�̍����z�e���A�g���C�f���g���I�[�v�����A�܂��܂��ڂ̗����Ȃ��X�ƂȂ��Ă���B
�@����A�m�C�_�̓f���[�����A�����i�[�͂̌��������ɂ���E�b�^���E�v���f�[�V���B�̊X���BNOIDA�Ƃ́A�uNew Okhla Industrial Development Area�i�j���[�I�[�N���[�H�ƊJ���n��j�v�̗��ł���B���Ȃ݂ɃI�[�N���[�̓����i�[�͐��݂ɂ���X���B�m�C�_�͌�Ֆڏ�̓s�s�v�ŁA�Z�N�^�[�P�A�Z�N�^�[�Q�Ƃ����悤�Ȗ��@���ȏZ�����t�����Ă���B�Z�N�^�[�P�W�����ƓI���S�n�ƂȂ��Ă���A�V�l�}�R���v���b�N�XWAVE��A�������̃f�p�[�g������B�����i�[�͂ɉ˂����Ă���A�f���[�ƃm�C�_�����ԋ��A�g�[���E���[�h�́A���{�̎O�䌚�݁i���O��Z�F���݁j���{�H�����L�����H�ŁA�܂�œ��{�̍������H�̂悤�ɂ��ꂢ�ȓ��H�ł���B�H�����S���������������������Ƃ́A�H�����ɍH�������������O�Ⴊ�Ȃ������C���h�ɂ����Ċ��ɓ`���ƂȂ��Ă���B�{���Ɂu�C���h�l���r�b�N���v�̏o�����������������B
�@�O���K�[�I���ƃm�C�_�̑��ɁA�f���[���ӂɂ̓t�@���[�_�[�o�[�h�i�f���[�쓌�A�n�����[�i�[�B�j��K�[�Y�B���[�o�[�h�i�f���[�����A�E�b�^���E�v���f�[�V���B�j�Ȃǂ����邪�A���W�x�⒍�ړx���猩����A�O���K�[�I���ƃm�C�_�̔�ł͂Ȃ��B
�@�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɂ́A�O���K�[�I���ƃm�C�_�̓����A�����A�Z�������ꂼ�ꕪ�͂���Ă����B
�@�O���K�[�I���̍����Z��n�̒n���͂Q�V�O�O�`�R�O�O�O���s�[�^�����t�B�[�g�ŁA�Q���R�����̕����̂P����������̉ƒ��͂W�O�O�O�`�P�Q�O�O�O���s�[�B���݃O���K�[�I���ɂ͂U�̃��[��������A�Q�O�O�U�N�܂łɂP�V�̃��[���i�����̓V�l�R���t���j����������\��B�W�Ԑ��̃f���[�E�O���K�[�I���E�G�N�X�v���X�E�F�C�A��ÃR���v���b�N�X�̃��f�B�V�e�B�[�Ȃǂ������ԋ߂ł���B�O���K�[�I���̂T�̒����Ƃ��āA�@��f���[��x�Ƃ������n�̗ǂ��A�A�A�p�[�g�̐ݔ��̗ǂ��A�B�O���l�A���ƉƁA���ƂȂǂ��W�Z����R�X���|���^���I���͋C�A�C���ۋ�`�ւ̐ڑ��̗ǂ��A�D�Ő�[�̔��������y���������Ă�������ŁA�S�̒Z���Ƃ��āA�@�f���[�ɐڑ����铹���Q�����Ȃ����ƁA�A������ʋ@�ւ��s�ւŁA���Ɨp�Ԃ��K�v�ƂȂ邱�ƁA�B�n�������x�����Ⴍ�A���s�����[���Ȗ��ƂȂ肤�邱�ƁA�C�d�C����������Ă��炸�A��d���p�����邱�Ƃ��������Ă����B
�@����ɑ��A�m�C�_�̍����Z��n�̒n���͂Q�R�O�O�`�Q�T�O�O���s�[�A�Q���R�����̕����̂P����������̉ƒ��͂W�O�O�O�`�P�Q�O�O�O���s�[�B���݁A�Z�N�^�[�P�W�A�Q�V�A�U�R�ɍ��v�R�̃��[��������A�Q�O�O�U�N�܂łɂP�Q�̃��[�����I�[�v���\��B�A�W�A�ő�̃��[���A���j�e�N�E���[�����I�[�v���ԋ߂Ƃ����B���̑��A���ۋ�`��������m�q�h�V�e�B�[�A�^�[�W�E�G�N�X�v���X�E�F�C�A����ȃA�~���[�Y�����g�E�p�[�N�Ȃǂ����݂���Ă���A���ʌo�ϓ�����v�悳��Ă���B�m�C�_�̂S�̒����Ƃ��āA�@��f���[�܂��͒����f���[�ւ̐ڑ��̗ǂ��A�A�n�������x������r�I�������ƁA�B�d�͉�Ђ̖��c���ɂ��d�͋�������r�I���肵�Ă��邱�ƁA�C�����̕a�@������A�A�|���a�@�ɂ��߂����Ƃ��������Ă�������A�S�̒Z���Ƃ��āA�@�����̈����A�܂��͎����������Ƃ����C���[�W�̈����A�A�Z��ɑI���������Ȃ��A�����Z��n�����Ȃ����ƁA�B�}���ɔ��W���Ă���ɂ��ւ�炸�A�����ڂ̃C���[�W�����邱�ƁA�C���ӏZ���̋��{���Ⴂ���Ƃ��������Ă����B
�@�l�́A�m�C�_�ƃO���K�[�I���ł́A���|�I�ɃO���K�[�I���ɑ��ɂ��ʂ��Ă���B�n�}�Ō���ƁA�l�̉Ƃ���̋����̓m�C�_�ƃO���K�[�I���ł͂����ς��Ȃ��̂����A���_�I�ɃO���K�[�I���̕����߂��C���[�W������B�m�C�_�̓����i�[�͂��z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA����������ۂ���̂��Ǝv���B�ŋ߂͋v�����m�C�_�ɍs���Ă��Ȃ��̂Ő��m�ɂ͕�����Ȃ����A�O���K�[�I���̕����f�������ɂ��V���b�s���O����ɂ�������Ӗ��ŕ֗����B�������A���Ɨp�Ԃ�����̘b�����B���݂̓o�C�N�������Ă���̂ŁA�O���K�[�I�����m�C�_���ȒP�ɍs���邪�A�o�C�N���O�͂ǂ�����u�n�̉ʂāv�Ɏv�������̂��B�Q��قǃo�X�ɏ���ăO���K�[�I���֍s�������Ƃ����邪�A�s�������Ŕ��ɔ��Ă��܂��A��������x���Ȃ�ƋA��̑����ƂĂ��S�ׂ������B�o�C�N�������R�̂ЂƂ́A�ʊw�̗����ɉ����A�O���K�[�I�����s���͈͓��Ɏ��߂����������Ƃ��傫���B
�@���߂ăO���K�[�I���ƃm�C�_�������ăf���[�̒n�}�����Ă݂�ƁA���ɃR���m�[�g�E�v���C�X��C���h��̂��钆���f���[�́A�f���[�������ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t���B�O���K�[�I���A�m�C�_�A�C���f�B���[�E�K�[���f�B�[���ۋ�`�Ȃǂւ̃A�N�Z�X���l����ƁA�����̊O���l��b�`�ȃC���h�l�����Z�����f���[�������A�u�����f���[�v�Ȃ̂��B�f���[��w�Ȃǂ�����k�f���[�́E�E�E�������k���Ӌ��n�тƂł����̂����Ă��炨�����E�E�E�B�O���K�[�I���ƃm�C�_���z�b�g�E�X�|�b�g�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂����A�R���m�[�g�E�v���C�X���͂��߂Ƃ���̂���̃f���[�̃}�[�P�b�g�͎���ɋꋫ�ɗ����������ƕ����B�ŋ߃f���[���{�́A���X��X�g�����̉c�Ǝ��Ԑ������ɘa���i�X���Ԍߌ�V�����ߌ�P�P���j�A�i�C�g�E�V���b�s���O���\�ɂ������A������O���K�[�I���ƃm�C�_�ɑR���邽�߂̑[�u�ł���B
�@�O���K�[�I����m�C�_�̖u���́A�l���C���h�ɗ��w������ɋN�������B���߂ăC���h�ɗ������i�P�X�X�X�N�j�́A�R���m�[�g�E�v���C�X���f���[�̃V���b�s���O�̒��S�����Ǝv���Ă������A�����͂������������Ƃ��낤�B���̍��́A�T�E�X�E�G�N�X�e���V�������o���ĊԂ��Ȃ������悤�ɋL�����Ă���B�l�����w�����N�i�Q�O�O�P�N�j�ɂ̓A���T���E�v���U���V�����V���b�s���O�E�X�|�b�g�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă����B�������A����͍���O���K�[�I���ƃm�C�_�B���S�������Ɋ��ɓ��{�̍��x���������I����Ă����l�ɂƂ��āA���݂̃f���[�̔��W�A�C���h�̔��W�́A�V���ȋ����ł���A�V���Ȏh���ƂȂ��Ă���B
�@�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɂ́A�O���K�[�I���m�C�_�Ƃ������ƂŁA�Q�̉q���s�s�̋����S�����L�����f�ڂ��Ă������A�b�a���`���[�h�E�G���X�Г�A�W�A�x���̃A���V���}���E�}�K�W���В��́A�u�Q�̓s�s�͑S���ʂ̐������ł���A�����I�ɂ̓O���K�[�I���m�C�_�ł͂Ȃ��A�O���K�[�I�����m�C�_�ɂȂ��čs�����낤�v�Ɨ�ÂȃR�����g���Ă����B�܂��O���K�[�I�����m�C�_�����{�l�̖ڂ��猩���瑫��Ȃ������������A���W�r��Ƃ��������Ȃ����A�����炭�P�O�N�キ�炢�ɂ́A�ǂ�����A�W�A�ő�̃V���b�s���O�E�X�|�b�g�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�C���h�ɂ͑����̃`�x�b�g�n�̐l���Z��ł���B�W�������[���J�V���~�[���B�̃��_�b�N�n����X�B�b�L���B�ɏZ�ސl�X�̓C���h���Ђ����`�x�b�g�n���������A���̑��ɂ��`�x�b�g���瓦��Ă�������C���h�e�n�ɏZ��ł���B�������j�I�w�i���������ƁA�`�x�b�g�͂V���I������Ɨ��������y��ۗL���Ă���A���̒��������Ƃ��Γ��ȏ�̊W�������Ă������A�P�X�T�O�N�A�ё����钆�����Y�}�R���A�u�������x����̐l������v�𖼖ڂɃ`�x�b�g�N�U���J�n���A�`�x�b�g�̕����A�Љ�A�@���̓O��I�j����s�����B�P�X�T�X�N�Ƀ_���C�E���}�@�����C���h�ɖS������ƁA���̌��ǂ��ĂP�O���l�̃`�x�b�g�l�����ɃC���h�ɖS�������B�Ȍ�A�S�O�N�ȏ�ɓn���ă_���C�E���}�@���̓`�x�b�g���̕��a�I������i�������Ă���A�ŋ߂̓`�x�b�g�Ɨ���f�O���đΘb�D����咣���Ă��邪�A�������{�͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ��B�C���h�ɂ����ă`�x�b�g��������X�Ƃ��ċ�������̂́A�`�x�b�g�S������������q�}�[�`�����E�v���f�[�V���B�̃_�����V���[���[�A���̏B�s�V�����[�A�N�b���[�A�}�i�[���[�ȂǓ��B��сA���x���K���B�̃_�[�W�����A�J�����|���ȂǁA�܂��J���i�[�^�J�B�̃}�C�\�[���Ȃǂł���B�f���[�k���̃}�W���k�E�J�E�e�B�b���[��h�r�a�s�߂��ɂ��`�x�b�^���E�L�����v������A�`�x�b�g�l�������W�Z���Ă���B
�@�P�V���t���̃T���f�[�E�G�N�X�v���X���ɂ��ƁA�P�O���W������R���Ԃɓn���āA�_�����V���[���[�̃}�N���[�h�E�K���W�ɂ����āA�~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g���s��ꂽ�Ƃ����B�~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g�͂Q�O�O�Q�N���疈�N�J�Â���Ă���A���N�łR��ڂƂȂ�B��͂�~�X�R���͕ێ�w����ᔻ���Ă���A�S�������̃T���h���E�����|�`�F���u���m�����̈��e�����o��v�Ƃ��ς˂����A����ł���Î҂͋��s���A���������Ȑ��ʂ��グ�Ă���悤���B�Q�O�O�Q�N�̃~�X�R���D���҃h���}�E�c�F�����́A�~�X���E�ό��R���e�X�g�ɂ����ă~�X�����Ɠ����X�e�[�W�ɗ����A�`�x�b�g�l�̊��т𗁂т��Ƃ����B
�@�V���ł́A���N�̂T�l�̌��҂̓��̂P�l�A�J���T���E�f�B�b�L�[�ɏœ_�Ăď�����Ă����B
�@�J���T���E�f�B�b�L�[�̓`�x�b�g�����̃i�O�`�����܂�B���Z���ƌ�A�_���T�[�ɂȂ�̂��ă_���X�E�X�N�[���ɒʂ������A��ʎ��̂ɂ�蕉�����Ė�����߂�������Ȃ������B���̌�A�Ō�w�Ƃ��ē����Ă����B�Q�O�O�R�N�̃~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g�̂��Ƃ�F�l���畷�����f�B�b�L�[�́A�������o�ꂵ�����ƍl����悤�ɂȂ����B�f�B�b�L�[�͗��e�Ɂu�l�p�[���ɏ���ɍs���v�ƌ����ă`�x�b�g����ɂ���B�Ƃ��낪�A�p�X�|�[�g�����������Ă��Ȃ��ޏ��ɂƂ��āA�l�p�[�������͊ȒP�ł͂Ȃ������B�ޏ��͐藧�����R�����[�v�P�{�œo��A�[���X����蔲���āA�l�p�[���ɓ������Ƃ����B�����A�_���C�E���}�@���ɉ���ƂƁA�~�X�R���ɎQ�����邱�Ƃ������l���āA�������z�����������B�l�p�[���ɓ����Ă���͂Ƃ�Ƃq�Ŏ��͐i�B�ޏ��̓`�x�b�g�l����Z���^�[�ɓd�b���ăg���b�N����z���Ă��炢�A�J�g�}���Y�ֈړ������B���T�Ƃ͑S���Ⴄ�J�g�}���Y�̔ɉh�������f�B�b�L�[�́A�������{�ւ̔���������ɋ��߂��Ƃ����B�f�B�b�L�[�̓J�g�}���Y�̃z�e���Ō����S�O�O�O���s�[�œ����n�߂��B�~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g���ĂъJ�Â���邱�Ƃ�������ƁA�f�B�b�L�[�͑�������p���𑗕t�����B����p���ɔޏ��́A�C���h�ɍs���邾���̋����Ȃ����Ƃ������Ă������B�~�X�R���̎�Î҃��u�T���E�����M�����̓f�B�b�L�[����̎莆�����ƁA�ݕă`�x�b�g�l�W���[�i���X�g�A�c�F�����E�����h���ɘA�����ĉ������o���Ă�������B�����h�����瑗���Ă�������R�O�O�h���ɂ��A�f�B�b�L�[�̃~�X�R���Q���̖��͐��Ɍ����̂��̂ƂȂ����B�f�B�b�L�[�́A�l�p�[�����瓯�����~�X�R���ɎQ������\�[�i���E�f�B�b�L�[�Ƌ��ɃJ�g�}���Y����f���[�܂łR���ԃo�X�ɏ���Ă���ė����B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�J���T���E�f�B�b�L�[
���̐l�����w�́E�E�E�H |
�� |
�@�~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g�́A�܂��W���̐����R������J�n���ꂽ�B�`�x�b�g��̕��G�Ȋ���ɔz�����āA�����R���͈�ʂɔ���J�ōs��ꂽ�B�X���ɂ̓X�s�[�`����|��I���s���A�T�l�̌��҂͂��ꂼ��`�x�b�g�Ɋւ��鎩�_���q�ׁA�܂��`�x�b�g��̉̂��̂����B�ŏI���̂P�O���ɂ͌��ʔ��\���s��ꂽ�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�����ߑ��p�̌��҂T�l |
�� |
�@���āA�����Ń~�X�R���̌��҂����̃A�b�v�ʐ^�����Ă݂悤�B�J���T���E�f�B�b�L�[�̎ʐ^�͏�ɍڂ������A���̂S�l�̌��҂͈ȉ��̒ʂ�ł���B
| �� |
|
|
|
�� |
|
 |
|
 |
|
|
�h���h�D�v�E������ |
|
�\�[�i���E�f�B�b�L�[ |
|
|
 |
|
 |
|
| �� |
�^�V�E�����`�F�� |
|
�e�B�����C�E�h���} |
�� |
�@�h���h�D�v�E�������̓E�b�^���[���`�����B�f�w���[�h�[�����܂�ŁA�f���[��w���ƂŁA���݃f���[�̃A�E�g�\�[�V���O��ЂɋΖ����Ă���B�\�[�i���E�f�B�b�L�[�̓��T���܂�ŁA�w������ɃC���h�ɖS�����A���݃l�p�[���ŗ��e�̎d������`���Ă���B�^�V�E�����`�F���̓X�B�b�L���B�K���g�N���܂�ŁA�v�l�[��w�ŃR���s���[�^�[�w�m���擾�A���݃K���g�N�̏��Z�p�ǂɋΖ����Ă���B�e�B�����C�E�h���}�̓q�}�[�`�����E�v���f�[�V���B�r�[���o�g�A���X�[���[�̊w�Z�Ŋw��A���݂̓��[�L���b�v�E�A�[�e�B�X�g�ɂȂ邽�ߏC�s���B���āA���̂T�l�̒��ŒN���~�X�E�`�x�b�g�ɑI�ꂽ�̂��낤���E�E�E�H
�@�c�O�Ȃ���A�킴�킴�~�X�R���̂��߂Ƀ`�x�b�g����S�����ė����f�B�b�L�[�̓~�X�E�`�x�b�g�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�Q�O�O�S�N�̃~�X�E�`�x�b�g�ɋP�����̂́A�K���g�N�̃^�V�E�����`�F���B�������ራ�����A�~�X�R�����҂̂T�l�����Ă݂�A��ڗđR�Ń����`�F������Ԃ��킢���Ƃ������Ƃ�������B�X�s�[�`���|��I�ł������������т��悩�����悤���B�����`�F���̓v�l�[��w�ɒʂ��Ă����Ƃ����A�~�X�V�����ɑI�ꂽ�Ƃ�������A�`�x�b�g�l�̒��̃~�X�R���̔e�҂ƌ�����B�~�X�E�`�x�b�g�ɂ͏܋��P�O�����s�[�ƁA���N�̍��ۃ~�X�R���ɎQ�����錠�����^����ꂽ���A�����`�F���͏܋��̈ꕔ���_���C�E���}�@���Ɋ�i�����Ƃ����B����ɂ��Ă��R���͔��Ɋy�������Ǝv���̂����E�E�E�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�~�X�E�`�x�b�g�ɑI�ꂽ�^�V�E�����`�F�� |
�� |
�@�Ƃ���ŁA�~�X�R���o��̖����ʂ������f�B�b�L�[�́A�_���C�E���}�@���ɉy�����Ă��烉�T�A��Ƃ����B�������p�X�|�[�g�Ȃ��Ŗ��o���������߁A�{���Ŕޏ��͍߂ɖ����\�����傫���B����ł��ޏ��͋A��ƌ����B�u���̃��b�Z�[�W�𐢊E�ɍL�߂邽�߂ɂ̓~�X�R�������Ȃ������́B���͎����̖��̒��ɐ����Ă����B���̑㏞���o��͂ł��Ă����B�v�ʂ����ă~�X�E�`�x�b�g�E�R���e�X�g���`�x�b�g�{�y�ōs������͗���̂��낤���E�E�E�B
�@���Ȃ݂ɁA�~�X�E�`�x�b�g���E�F�u�T�C�g������B
�@�����P�T�ԁA�C���h�̃j���[�X�Ƀ��B�[���b�p���̖��O���o�Ȃ��������͂Ȃ��B�P�O���P�W����A��C���h�̓`���̑哐�����B�[���b�p�����A�^�~���E�i�[�h�D���{���iSTF�j�ɂ��ˎE���ꂽ�B���B�[���b�p���́A�^�~���E�i�[�h�D�B�A�J���i�[�^�J�B�A�P�[�����B�ɂ܂����閧�ђn�т�����ɂ��ďۉ�Ɣ��h�i�T���_���E�b�h�j�̖��f�ՂɊւ���Ă������A�x�@�A�X�ьx�����A�����ƁA�|�\�l�Ȃǂ̎E�l��U�����J��Ԃ��Đl�X�����|�̂ǂ��Ɋׂ�Ă����A�C���h�́uMost Wanted�v�������B���܂Ŕނ��E�����l�Ԃ̐��͂P�Q�O�l�ȏ�A�ۂ̐��͂Q�O�O�O���ȏ�A�ނ̎�Ɍ������Ă������܋��͍��v�T�T�O�O�����s�[���Ɠ`�����Ă���B�̑傫������A���߂ă��B�[���b�p���̎����C���h�ɗ^�����e���̑傫�����v��m�ꂽ�B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���B�[���b�p�� |
�� |
�@���B�[���b�p���̃t���l�[���̓N�[�Z�E���j�X���[�~�[�E���B�[���b�p���E�O���_���ƌ����B���B�[���b�p���̐��N�����͕s�������A����ɂ��ƂP�X�T�Q�N�P���P�W�����ƌ����Ă���B�ނ̓^�~���l�����A�J���i�[�^�J�B�̃S�[�s�[�i�[�^�����̌�i�K���̉Ƃɐ��܂ꂽ�B���B�[���b�p�������߂ďۂ��E�����̂́A�܂��P�O�̂Ƃ��������ƌ����Ă���B�ނ͖����Ƃ��Ĉ��������T�����@�C�E�O���_���i�Z���B�A���E�O���_���Ƃ��j�ɁA�ۂ̎�̘r���Ė��c�ɒ��ԓ��肷��B�P�X�U�X�N�ɃM�����O���m�̑������烔�B�[���b�p���͏��߂ĎE�l��Ƃ��A�P�X�V�Q�N�ɑߕ߂���邪�����Ɏߕ����ꂽ�B�O���_���͂W�O�N��ɏۉ�̗A�o���֎~�����ƁA���h�̖��A���J�n���A�ނ̎���A���̎d���̓��B�[���b�p���Ɏp���ꂽ�B�P�X�W�U�N�ɂ����B�[���b�p���͑ߕ߂��ꂽ���A�ێߋ����Ďߕ����ꂽ�B���̂Ƃ��܂Ń��B�[���b�p���͂܂����f�ՃO���[�v�̃h���ɉ߂��Ȃ��������A���B�[���b�p�����{�i�I�ɗU����E�l�Ɏ����ߎn�߁A�R���܂��͓����Ƃ��ċ������悤�ɂȂ�̂͂P�X�W�V�N����ł���B����ɁA���B�[���b�p���ƌx�@�̑������N��������̂́A�X�т̎�����ړI�Ƃ������{�����ݗ����ꂽ�P�X�X�O�N���炾�B�Ƃ��낪�A�P�X�X�P�N�Ƀ��B�[���b�p���͐X�ьx������������߂炦�Ďa�A�x�@�͈�U�̐��𐮂�������������Ȃ��Ȃ����B�X�R�N�ɃJ���i�[�^�J�B�x�@�̓��B�[���b�p���ɑR���邽�߂̓��{����ݗ����A���B�[���b�p���̍ȃ��g�D���N�V���~�[�ƒ�̃A���W���i����ߕ߂���B�����A�A���W���i�����S�����Ɏ��S�������Ƃɂ��A���B�[���b�p���̔ƍ߂͂���ɋ��������A�x�@����X�ьx���������X�ƗU������E���ꂽ�B�^�~���E�C�[��������̌Ձi�k�s�s�d�j��i�N�T���C�g�i�ɍ��ߌ��h�c�́j�Ƃ��A�g���Ă����Ƃ���Ă���B���B�[���b�p���̌`�e������������哐���ւƔ��̂́A�J���i�_�f��E�̑�o�D���[�W�N�}�[���̗U���������炾�낤�B���B�[���b�p���͂Q�O�O�O�N�V���R�O���ɁA����ɂ������[�W�N�}�[����U�����A�g����ƍȂ⒇�Ԃ̎ߕ������߂��B���[�W�N�}�[���͓��N�P�P���P�S���ɉ������邪�A����ɂ��ƂQ�����s�[�̐g������x����ꂽ�Ƃ����B���{�͂����ے肵�Ă���B�Q�O�O�Q�N�W���Q�T���ɂ́A�J���i�[�^�J�B�̂g�D�i�[�K�b�p����b�����B�[���b�p���ɗU������A���N�P�Q���W���Ɉ�̂Ŕ������ꂽ�B����ȍ~�A���B�[���b�p���͖����߂Ă����B�a�C�������Ƃ������Ă������ŁA���x�̓^�~���f��E�̑�X�^�[�A���W�j�[�J�[���g�̗U������ĂĂ����Ƃ������Ă���B
�@���B�[���b�p���̎ˎE�́A���{���ɂ��Ȗ��ȍ��ɂ���ĒB�����ꂽ�B��A�̍��̓I�y���[�V�����E�R�N�[���ƌĂ�Ă���B�U�O�O�O���������̐X�т̒����烔�B�[���b�p���������o���̂́A�����̎R�̒�����j��T���o���悤�ɍ���ł��邱�Ƃ���������{���́A���B�[���b�p����X�т��炨�т��o�����@��͍�����悤���j��ύX�����B��킪�����n�߂��̂͂Q�O�O�R�N�T�������炾�����B���{���́A���B�[���b�p������Ɉ��Ăđ������莆�̖T��ɐ��������B�莆�̒��ŁA���B�[���b�p���͗L�]�Ȏ�҂����𒇊ԂɈ��������悤�v�����Ă����B���{���́A���B�[���b�p���̂��ƂɃX�p�C�𑗂荞�ނ��߁A�Q�l�̑�w�����܂ނS�l�̈�ʎs���̎u��҂��P�������B�x�@�����g��Ȃ������̂́A������Ƃ����d���⓮��Ő��̂���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��B�ނ�̓��X�����ߌ��h���ĐX�тɓ���A���B�[���b�p�������铐���ɍ��������B�ނ�͂Q�O�O�R�N�U���ɂP�X���ԃ��B�[���b�p���Ƌ��ɐ������A����I�����g���ċA���ė����B���̏��ɂ��A���B�[���b�p���͔�����ƃ��E�}�`�������Ă��邱�Ƃ����������B�Q�O�O�S�N���߁A���{���̓��B�[���b�p���̌���x�����s���Ă����������𒇊ԂɈ�������邱�Ƃɐ��������B�Q�O�O�S�N�T���A���B�[���p���͖ڂ̎��Â����邽�߂̃A�����W�����̕������Ɉ˗������B���{���͕�͖Ԃ菄�点�����A���̂Ƃ��͒��O�ɂȂ��ă��B�[���b�p�����v���ύX�������߁A���͐��s����Ȃ������B�����A���{���͔E�ϋ������̃`�����X��҂����B���̃`�����X�͂P�O���P�R���ɍĂіK�ꂽ�B��͂胔�B�[���b�p���͖ڂ̎��Â̂��߂ɕ������ɃA�����W���˗������B���{���͂P�O���P�W���ߌ�P�O���P�T���̎��Ԃ��w�肵�A�~�}�����ɕϑ������Q�l�̓��{�������~�}�Ԃɏ悹�đ��荞�B���B�[���b�p���͂R�l�̒��ԂƋ��Ɏ��Ԓʂ茻�n�Ɍ���A���̋^�����Ȃ��~�}�Ԃɏ�荞�B���̊ԁA���{���̓��B�[���b�p�����������\���̂���S�Ă̓������A�ނ�����̂�҂��\�����B�P�O���S�T�����A�~�}�Ԃ������n�т̂ЂƂ܂œ��B����ƁA���{���͂܂��͍~�Q����悤�Ăт������B�����A�������������C���Ă������߂ɓ��{�������������B�e����̖��A�S�l�̓����͎ˎE���ꂽ����A�~�}�����ɕϑ����Ă������{���������́A�e���킪�n�܂�O�ɑ����ɖ݂̒��ɉB�ꂽ���ߖ����������B���B�[���b�p���̈�̂ɂ͂R�����̒e��������A�ꔭ�͔]��ł������Ă����B���B�[���b�p�������E�����\�����w�E����Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
���B�[���b�p���̈�� |
�� |
�@�P�X���̐V���ɂ́A��Ăɏ�̂悤�ȃ��B�[���b�p���̈�̂̎ʐ^���f�ڂ��ꂽ�B���{�̐V���ł͍l�����Ȃ��c���ʐ^�����A�C���h�ł͋��e�͈͂ł�����肩�A�`���̓����̍Ŋ��Ȃ̂ŁA���炵��I�ɂ��߂ł����ʐ^�Ȃ̂�������Ȃ��i�l�b�g�ł��ǂ�ǂ�f�ڂ���Ă���̂ŁA�l������ɏ]���j�B�����Ɠ������e�e�őł�������Ă���l�q��������B�������A�����̐l�X���c�O���点���̂́A�ނ̕E���葵�����Ă������Ƃł���B���B�[���b�p���́A�Ɠ��̕E�ŗL���������̂����A�a�@�ł̎��Î��ɐ��̂����̂�����邽�߂��A�E�͕��ʂ̌`�ɐ������Ă����B
�@���B�[���b�p���̎ˎE�ȍ~�A���낢��Șb�����Ԃ���킹�Ă���B���B�[���b�p���̎c���Ȉ��s����ח��Ă�L��������A���܂Ń��B�[���b�p�����߂܂�Ȃ������̂́A�����ƂƂ̋��͂ȃR�l�N�V���������������炾�Ǝw�E����_��������B�x�܂������̂悤�Ȍ`�ł̎ˎE�ւ̔ᔻ������A�^�~���E�i�[�h�D�B�̃W�����[�����^�[�B����{�����B�W���C�E�N�}�[�������́u�S�̎��������v���̂悤�ȃR�����g�����X�ƕ���Ă���B���B�[���b�p�����u�����v�ƌĂԐl������A�u���r���t�b�h�v�u�����{�[�v�ȂǂƉp�Y�����悤�Ƃ���L��������B���N�Q���Q�P���t���̃^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɁA�u���B�[���b�p���͎��̒a�������}�����Ȃ����낤�v�Ƃ����肢�t�̌��t���f�ڂ���Ă������Ƃ܂ň��������ɏo����A�u�l�͉R��t�������͉R��t���Ȃ��v�ƁA�肢�D���ȃC���h�l�̊�т����ȋL���܂ł������B�܂��A�����̋L�҂��w�E���Ă������A���B�[���b�p���̂悤�ȓ������Ö��ՂƂȂ����̂́A�X�тɏZ�ޗ}�����ꂽ�����������̕s���̒~�ςł��������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���B�[���b�p���͐X�т̖��Ɏ{�����s���Ă������߁A�ނ炩��،h�̔O��������Ă����Ƃ����B���Ȃ݂ɁA���B�[���b�p���Ɍ������Ă������܋��͓��{���ɂ���ĕ��z����A�I�y���[�V�����E�R�N�[���ɎQ�����Ă��������ɂ��ꂼ��R�O�����s�[�ƕs���Y���ܗ^�����Ƃ����B
�@�C���h�̓����ƌ����A�f��uBandit Queen�v�i1994�N�j�̃��f���ƂȂ����A�������v�[�����E�f�[���B�[���L�����낤�B�P�X�T�W�N�ɃE�b�^���E�v���f�[�V���B�̕n�������t�̉Ƃɐ��܂ꂽ�v�[�����E�f�[���B�[�́A�P�P�̂Ƃ��Ɍ���������̂̕v�̖\�͂ɑς����˂Ȃ��Ȃ��ē��S���A���̌�Y�����ɓ�������M�����O�ɗU������ă��C�v���ꂽ����̎����߂��������ʁA�����ƂȂ��ĕ��Q���J�n���A�P�X�W�O�N����E�b�^���E�v���f�[�V���B�Ŗ\��܂�����B�₪�Đ��{�Ǝi�@��������ĂP�X�W�R�N�Ɏ��A�P�P�N�̒������I������͍���c���ɓ]�g�A�Ŋ��ɂ́i�Q�O�O�P�N�j�ÎE�����Ƃ����g������̐l���𑗂��������ł���B���B�[���b�p�������͎i�@�����Őf����Ă����̂����A�ނ̓v�[�����E�f�[���B�[�ƈ���Ĉ�ؐX�т̊O�ɏo�悤�Ƃ��Ȃ������B
�@�v�[�����E�f�[���B�[�̎��A�����ă��B�[���b�p���̎��A������A�̃j���[�X����ׂ�ƁA�S�Ȃ��������₵���C�����ɂȂ��Ă���B�u�����v�Ƃ������݂́A���{�ɂ��邾����������A�����b���̘b�ɏo�Ă��鑶�݂ł���B�q���̍����v���o���ƁA�u�����v�Ƃ������݂ɋ��|�Ɠ����ɉ��ƂȂ����}���������Ă����悤�Ɏv���B�������A�����C���h�ł́A���ꂪ�����ɑ��݂���B�C���h�ł͂܂����������ԂƂ������c���Ă���̂��B����͓���������A�q�W�����[������A�哹�|�l������A�d�C���K�X���Ȃ����ɏZ�ݐ̂Ȃ���̐������c�ސl�X������ł���B�C���h�𗷂���ƁA����璆���̐��������������A�����̈�Ոȏ�ɗ��l���h������B�����A�哐���ƌĂ��l�X�����������Ă������Ƃɂ��A����炪�A��X�̖ڂ̑O�Ŏ���ɋߌ���̔g�ɉ���������Ă����悤�Ɋ������B����͈���Ŋ�������ƂȂ̂�������Ȃ����A����Ŕ��ɔ߂������Ƃ��B
�@�����A���B�[���b�p��������ɂ����W�����O���ŁA�V���Ȓ����I���}�������܂�Ă���B����́A���B�[���b�p�����W�����O���e�n�ɉB��������T���ł���B���B�[���b�p���͌x�@�ɋ}�P�����̂�����A�����U�����Ĕ閧�̉B���ꏊ�ɉB���Ă����Ƃ���Ă���B�����Ƌ��ɏۉ�┒�h���ǂ����ɉB����Ă���悤���B�ߗׂ̕����������͊��ɕ�T���ɏ��o���Ă���A�n���x�@����{���ɂƂ��Ă����B�[���b�p���̉B���ꂽ���Y�̑{�����}���ƂȂ��Ă���Ƃ����B�����̕�T���Ƃ́A�܂��h���I�ȃj���[�X�ł���B
�@�Q�T���t���̃f���[�E�^�C���Y�E�I�u�E�C���f�B�A���ɁA�C�}�h�L�̑�w�����g���i�E���i����H�j���t�����W����Ă����B�C���h�S�y�̑�w�ɍL�܂��Ă��錾�t������A�n������̌��t������B�ǂ��܂Ŗ{�����A�f���[�̑�w�ɒʂ��l�ł��悭������Ȃ����A�ꉞ�Љ�悤�Ǝv���B
���V����
�@�V�����̂��Ƃ��A�f���[�ł́uFuchcha�v�A�v�l�[�ł́uPacchad�v�܂��́uMachhar�v�A�����o�C�[�ł́uBachcha�v�A�A�n�}�_�[�o�[�h�ł́uBachchu�v�܂��́uLangot�v�ƌĂԁB�C���h�̑�w�ł͐V�����ɑ��āu���M���O�v�ƌĂ����̐V���������߂��s���邽�߁A�u�V�����v�Ƃ������t�͓��ʂȈӖ��������Ă���B�f���[�́uFuchcha�v�͂��������悭�m��ꂽ���t���B�ꌹ�͂悭������Ȃ����A�u���L���z�v�݂����ȈӖ����Ǝv����B�v�l�[�́uMachchar�v�́u��v�Ƃ����Ӗ��B�u���u�����邳���z�A�Ƃ����������낤���B�����o�C�[�́uBachcha�v�ƃA�n�}�_�[�o�[�h�́uBachchu�v�́u���q�l�v�Ƃ����Ӗ��B�A�n�}�_�[�o�[�h�́uLangot�v�́u�ӂ�ǂ��v�u�����v�Ƃ����Ӗ��B���{��́u���В��v�Ǝ����悤�ȈӖ����낤���B�uPacchad�v�͈Ӗ��s���������B
���C�P�C�P�̏��̎q
�@���킢�����̎q�A�Z�N�V�[�ȕ��𒅂����̎q�̂��Ƃ��A�f���[�ł́uKhandala�v�A�v�l�[�ł́uRoohafza�v�A�����o�C�[�ł́uChhamiya�v�A�A�n�}�_�[�o�[�h�ł́uFatakdi�v�܂��́uChipkali�v�A�o���K���[���ł́uJill�v�܂��́uPoonay�v�ƌĂԁB�f���[�́uKhandala�v�͌ꌹ�s���B�}�n�[���[�V���g���B�ɂ��铯���̔����n�Ƃ͕ʂ��Ǝv���B�v�l�[�́uRoohafza�v�̓y���V�A��Łu�u���ȁv�Ƃ����Ӗ��B�V�����o�g�i�V���[�x�b�g�̌ꌹ�j�Ƃ������ݕ��̏��W�ɂȂ��Ă��邽�߂ɍL�܂������t���Ǝv����B�����o�C�[�́uChhamiya�v�́A�����炭��̖鉹�u�`�����`�����ichham-chham�j�v���痈�Ă���Ǝv����B����ȊO�͈Ӗ��s���B���̑��A���킢�����̎q���u�}�[���imaal�j�v�ƌĂԉB�ꂪ���邪�A����͊��Ɂu�C�}�h�L�̌��t�v�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���悤���B
�������������j�̎q
�@�����������j�̎q�A���{��̑���Ō����u�C�P�����v�̂��Ƃ��A�f���[�ƃo���K���[���ł́uDude�v�A�v�l�[�ł́uYum�v�A�uStud�v�A�uRaapchandus�v�܂��́uHero�v�A�R�[���J�[�^�[�ł́uGuru�v�A�����o�C�[�ł́uHottt�v�ƌĂԁB�f���[�ƃo���K���[���́uDude�v�͉p�ꂩ�痈�Ă���B�u�C��艮�v�u�I�V��������v�݂����ȈӖ����B�����������ɒ��ӁB�u�h���[�h�v�ł͂Ȃ��u�f�B�E�h�v���C�}�h�L�̔����炵���B�m���ɂ��̌��t�͂悭�g���Ă���B�v�l�[�́uYum�v�uStud�v�uHero�v���p��̌�b���B���ꂼ��u�����v�u��n�v�u�p�Y�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�uRaapchandus�v�̓q���f�B�[��܂��͌��n�ꂩ�痈�Ă���Ǝv���邪�Ӗ��͕s���B�R�[���J�[�^�[�́uGuru�v�́u���t�v�Ƃ����Ӗ����B�O���͌��X�u�d���v�Ƃ����Ӗ������A�����Ԍy���Ӗ��Ŏg����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����o�C�[�́uHottt�v�́u�z�b�b�b�v�Ɣ�������̂��낤���A�p��́uhot�v���痈�Ă���͖̂��炩���낤�B
�������������j
�@���{��̑��ꂾ�Ɓu�ނ����z�v�Ƃ��u�����傢�j�v�Ƃ��ɂȂ�̂��낤���A���������ꏏ�ɂ��邾���ŕ����������Ȃ�悤�Ȓj�̂��Ƃ��A�f���[�ł́u404 Error�v�A�v�l�[�ł́uPakao�v�A�A�n�}�_�[�o�[�h�ł́uJhinga�v�A�o���K���[���ł́uBlade�v�A�����o�C�[�ł́uKita-Patti�v�ƌĂԁB�f���[�́u404 Error�v�͌���B�C���^�[�l�b�g�̃u���E�U�łt�q�k��t�@�C����������Ȃ��Ƃ��ɏo��G���[���B�m���ɂ��̃G���[���o��ƃC���C������B�h�s�卑�C���h�炵���B�ꂾ�ƌ�����B�v�l�[�́uPakao�v�́A�q���f�B�[��́upakaanaa�i����������j�v�Ƃ��������̔h����ŁA��͂�u�C���C������v�Ƃ����Ӗ��ł���B�A�n�}�_�[�o�[�h�́uJhinga�v�́A�����ɂ��Ɓu�G�r�v�Ƃ��u�ȉԂɕt�����v�Ƃ����Ӗ��̂悤���B�o���K���[���́uBlade�v�ƃ����o�C�[�́uKita-Patti�v�͂����炭�ǂ�����u�n�v�Ƃ����P�ꂩ�痈�Ă���Ǝv���邪�A�͂�����Ƃ͕�����Ȃ��B
���ދ��Ȑ搶
�@�ދ��Ȑ搶�̂��Ƃ��A�f���[�ł́uChaatu.com�v�A�v�l�[�ł́uDrag�v�A�A�n�}�_�[�o�[�h�ł́uBhonpu�v�܂��́uDabbo�v�A�o���K���[���ł́uChaat�v�A�����o�C�[�ł́uPakao�v�A�R�[���J�[�^�[�ł́uTan�v�܂͂��uHalu�v�ƌĂԁB�f���[�́uChaatu.com�v�́A�u�r�߂�v�Ƃ����Ӗ��̓����u�`���[�g�i�[�v���痈�Ă���B�u�`���[�g�D�[�v�́u�]�݂����r�߂���悤�ɑދ��Ȑl���v�B�u.com�v�̕����͐������Ȃ��Ă������낤�B�o���K���[���́uChaat�v�������ꌹ�ł��낤�B�v�l�[�́uDrag�v�́u�ދ��Ȑl�v�Ƃ����Ӗ��̉p��̑���ł���B�A�n�}�_�[�o�[�h�́uBhonpu�v�́A�����Ԃ̃N���N�V�����̂��ƂŁA�]���āu�������邳���l�v�݂����ȈӖ��ł���B�������A�n�}�_�[�o�[�h�́uDabbo�v�́A�u�}����v�Ƃ����Ӗ��̓����udabaanaa�v�̔h����ŁA�u�V�b�I�Â��ɁI�v�݂����ȈӖ��B�f���[�̉B��ƊW����Ǝv����B�����o�C�[�́uPakao�v�͏�L�́u�����������j�v�ŏo�Ă����B�R�[���J�[�^�[�́uTan�v�uHalu�v�͂悭������Ȃ��B
����w�f�r���[�̓c�ɏ�
�@�c�ɂ̍��Z�ł͖ڗ����Ȃ����̎q���������A�s��̑�w�ɓ��w���Ĉ�C�ɃI�V�����ɖڊo�߂��悤�ȏ��̎q�̂��Ƃ��A�f���[�ł́uGTH�v�A�v�l�[�ł́uFukra�v�܂��́uHMT�v�A�A�n�}�_�[�o�[�h�ł́uB2B�v�A�����o�C�[�ł́uKakubhai�v�܂��́uBehenji�v�ƌĂԁB�f���[�́uGTH�v�Ƃ́A�uGhati Turned Hep�v�̗��ŁA�܂�u�E�l�Ƃ���I�V��������ցv�Ƃ����Ӗ��B�v�l�[�́uFukra�v�́A�u�����Z���X��������ҁv�Ƃ����Ӗ��́u�t�[�J���v�̏����`���Ǝv����B�uHMT�v�́uHindi Medium Types�v�Ƃ����Ӗ��B�k�C���h�̊w�Z�ɂ͎��Ƃ��p��ōs���uEnglish Medium�v�ƁA�q���f�B�[��ōs���uHindi
Medium�v�����邪�A���̌�҂̊w�Z���o�������̂��Ƃ��w���悤���B�������A�O�҂̕����Љ�I�n�ʂ͍����B�A�n�}�_�[�o�[�h�́uB2B�v�́uBindu to Britney�v�̗��B�r���h�D�[�Ƃ͓T�^�I�ȃC���h�l�����̖��O�ŁA�u���g�j�[�͗L���ȕč��̃A�C�h���̎�u���g�j�[�E�X�s�A�[�Y�̂��Ƃ��B�����o�C�[�́uKakubhai�v�́A�u�Z�M�v�݂����ȈӖ������ǂ����������Ŏg���Ă��邩�s���B�uBehenji�v�́u�o�M�v�Ƃ����Ӗ����B
�@���̑��A���낢��Ȏ�Ҍ��t���ڂ��Ă����̂ŁA�ʔ������̂��s�b�N�A�b�v���Ă݂�B
���uDigital�v�́u���������v�A���������n�̓V�˂��ۂ��C���[�W���B
���uBombaat�v�́u�f���炵���v�A�p��́ubomb�v���炩�B
���uChatlya�v�́u�搶�ɂ��ׂ������g���w���v�A��L�́u�ދ��Ȑ搶�v���Q�ƁB
���uT2M2�v�́uTu Tera, Mein Mera�i�N�͌N�́A�l�͖l�́j�v�̗��ŁA�܂�u���芨�v�B
���uNag�i�ցj�v�͏��̎q�̊ԂŎg���鑭��ŁA�u�f�[�g�ȏ�̂��Ƃ����߂�j�v�B�Ȃ��C���h�l�̒j�����z�Ɏv���Ă���B
���uJKG�v�́uJoru ka Gulam�v�̗��A�u�Ȃ̓z��v�Ƃ����Ӗ��ŁA�]���āu�����̐K�ɕ~���ꂽ�j�v�B
���uAKN�v�́uAaj ki Nari�v�̗��A�u�C�}�h�L�̏��v�Ƃ����Ӗ��ŁA�u�ǂ������JKG�̒j��߂܂��ăL�[�v���Ă������m���Ă��鏈���p�ɒ����������v�B
���uChopsticks�v�́u�����ꏏ�̒��ǂ��J�b�v���v�B
���uPappudo�v�́u�Ԕ����v�B
���uPipudo�v�́u�g�ѓd�b�v�A�s�[�v�[�邩�炾�낤�B
���uStamp�v�́u�L�X�v�A�X�^���v�������A�݂����ȃC���[�W���낤���B
�@�����̌��t���S�Ė{���ɃC���h�l�̎�҂Ŏg���Ă��邩�͋^�킵�����A�������������͕����o���̂�����̂��������B�����̌�b���K������ɂ́A�C���h�l�̎�҂̗ւ̒��ɐϋɓI�ɓ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@���܂������A�C���h�l��w���̒��ōł��|�s�����[�ȃq���f�B�[��̑���́A�u�p�^�[�i�[�ipaTaanaa�j�v���Ǝv���B���̓����͌��X�u�������v�u����ɂ���v�u�悹��v�u���v�u���ӂ�v�݂����ȈӖ������A��w���̊Ԃł͂����ƕʂ̈Ӗ��Ŏg����B����͓��{��́u�t�������v�Ǝ����悤�ȈӖ��ł���A�j�����猾���A�u���̎q���i���p����v�u���̎q�ƃf�[�g����v�u���̎q�Ƃ�������v�u���̎q�����������A��v�݂����ȕ����Ŏg����B�����炭�u���ӂ�v�Ƃ����Ӗ����]���āA���������g�����������̂��낤�B������������̌��t���g���̂��͂悭������Ȃ��B�q���f�B�[��ł͑������Ǝ������������ɋ�ʂ���̂ŁA�����������珗�̎q�́u�f�[�g�����v���A�������u�p�^�[�i�[�v�̎������`�u�p�g�i�[�v�Ŏg�����肷�邩������Ȃ��B
�@����̓��L�̏�Ƃ��āA�q���f�B�[��w�K�ҕK�g�̏��ł���I�b�N�X�t�H�[�h��w�o�ł́uTHe Oxford Hindi-English Dictionary�v���Q�l�ɂ������A�P�O�N�ȏ�O�ɕҎ[���ꂽ�����ɂ��ւ�炸�A�����������낢��ȑ��ꂪ�ԗ�����Ă��ċ������B�����A����ł�����������ɕs�ς̂��̂͂Ȃ��B�q���f�B�[��ɂ����X�ƐV�����B��A���ꂪ���܂�Ă��Ă��邱�Ƃ�������B
�@�����Q�T�Ԃقǂ͏h��ɒǂ��Ă��ĉf������ɍs���Ȃ������B����ƒ��x�݂ɂȂ����̂ŁA�����V��q���f�B�[��f������ɍs�����B���������f��̓��[���E�S�[�p�[���E���@���}�[����̃z���[�f��uVaastu Shastra�v�B�o�u�q�v�����[�Ŋӏ܁B
�@�薼�ɂȂ��Ă��郔�@�[�X�g�D�E�V���[�X�g���Ƃ́A�ꌾ�Ő������Ă��܂��u�C���h�̕����v�ł���B�Z�����l�Ԃɗ^����e�����l�������C���h�̓`���I���z�w�ŁA�Ⴆ�Ζk���͍Ւd�A�쓌�͑䏊�A���͐H���A�A�����ɐQ���A�k�͕ɂȂǂƋK�肳��Ă���B�f�撆�ł����@�[�X�g�D�Ɋւ��錾�y���������邪�A���Ƀ��@�[�X�g�D�E�V���[�X�g�����d�v�ȕ����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�ē̓T�E���u�E�E�V���[�E�i�[�����O�B�L���X�g�̓`���N�����@���e�B�[�A�X�V���~�^�[�E�Z�[���A�G�w�T�[�X�E�`�����i�[�A�T�[���[�W�[�E�V���f�[�A���[�W�p�[���E���[�_���A�s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[�A�v�[���u�E�R�[�z���[�A���[�X�B�J�[�E�W���[�V�[�ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�`���N�����@���e�B�[�i���j��
�X�V���~�^�[�E�Z�[���i�E�j |
�� |
| Vaastu Shastra |
�@�v�l�[�x�O�ɂ��鉮�~�Ɉ�Ƃ������z���Ă����B��Ƃ̃��B���[�O�i�`���N�����@���e�B�[�j�A����̃W���~���i�X�V���~�^�[�E�Z�[���j�Ƃ��̂S�̑��q���[�n���i�G�w�T�[�X�E�`�����i�[�j�A�����ăW���~���̖��̃��[�f�B�J�[�i�s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[�j�̂S�l�������B
�@�ŏ��ɈٕςɋC�t�����̂̓��[�n���������B���[�n���́u�Ƃɖl�����ȊO�ɒN��������v�ƌ����A�}�j�[�V���ƃW���[�e�B�[�Ƃ������O�̂Q�l�́u�����Ȃ��v�q�������ƗV�Ԃ悤�ɂȂ����B�ŏ��͎q���̋�z���ƋC�ɂ����߂Ȃ��������e�����A����ۂ��������悤�ɂȂ�A���[�n���̗l�q������ɂ��������Ȃ�ɂ��A�ٕς��������悤�ɂȂ�B�ق������C�h�i���[�X�B�J�[�E�W���[�V�[�j����̕ώ��𐋂��A���[�f�B�J�[�Ƃ��̗��l�̃����[���[�i�v�[���u�E�R�[�z���[�j�����B���[�O��̗��璆�ɎS�E���ꂽ���Ƃɂ��A���|�͌����̂��̂ƂȂ�B
�@�₪�ĖS�삽���̓��B���[�O�A���[�n���A�W���~����ɂ��P���|����E�E�E�B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�u���̉f������ĉ����N�����Ă��A�v���f���[�T�[�͈�ؐӔC���܂���B�v���T�ԑO����Ӗ��[�ȃL���b�`�R�s�[�Ƌ��ɁuVaastu Shastra�v�̗\���҂�����Ă����B�����炭�u���|�̂��܂�S����ჂƂ��ɂȂ��Ă��m��Ȃ���v�Ƃ����Ӗ��������Ǝv���̂����A���ʓI�ɂ��̃L���b�`�R�s�[�́u�f��̏o���������Ă������Ăˁv�Ƃ����Ӗ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���[���E�S�[�p�[���E���@���}�[���g�́A�C���h���z���[�f��̑������uBhoot�v�i2003�N�j���z����z���[�f��ł͂Ȃ������B�������Ȃ���A�]���ł���_�����������B
�@�X�g�[���[��f���Ȃǂ́A�X�^�����[�E�L���[�u���b�N�ḗu�V���C�j���O�v�i1980�N�j�Ɨގ��_�������B�v�̐E�Ƃ���Ƃł��邱�ƁA�Ƒ��ɏ����Ȏq�������邱�ƁA�x�O�̉��~�Ɉ����z���Ƃ���ȂǁA�ݒ�͂��Ȃ莗�ʂ��Ă���B�u�V���C�j���O�v�ň�ԗL���ȃV�[���́A�q������L���O�֎ԂŃO���O�����V�[�������A�uVaastu Shastra�v�ɂ��A�S�������ł͂Ȃ����A����ɋ����e�������Ǝv����V�[�����������B���������X�g�͂����Ԉ�����B���D�ꂽ�I�����ɂȂ��Ă�������̂����A�c�O�Ȃ���u���܂ł̕��͋C���Ԃ��v���炢�̂Ђǂ��I�����������B�ǂ����Ȃ�u�V���C�j���O�v�Ɠ����G���f�B���O�ɂ��Ă��ꂽ�����C�����悭�f��ق��o�ꂽ�̂����E�E�E�B���炷���ɂ͊����ď����Ȃ������B
�@����ł��A�J�������[�N�͔��ɂ悭�l�����Ă����B�S�Ẳ���ۂ̌��ɂȂ����̂́A�~�n���ɂ������s�C���Ȍ`�̑�������̂����A������J���������ł����Ƃ�ƕ\�����Ă����B�Z���t�ł͂��̂��Ƃ͂قƂ�ǐG����Ă��Ȃ��B�܂��A�`���ɂ�������Ƃ�����������Ԃ��T�b�ƒʂ�߂���V�[���A�u�����R�̏�ɃJ������u���đO��ɗh�炵�Ȃ��牮�~�S�i���f���V�[���̃J�������[�N�Ȃǂ���ۂɎc���Ă���B
�@�u�V���C�j���O�v�̂悤�ɁA���̂܂܃J���������ŖS��̎�����\������Αf���炵����i�ɂȂ�����������Ȃ����A�c�O�Ȃ���f�撆�A�S�삽���͎��̂������ēo�ꂵ�Ă��܂��B���������ʉ����ߏ肷���A�s�v�ȕ����A�S���Ӗ��̂Ȃ������ł��u�Y�M���[���I�v�Ƃ���������̂ŋ����߂������B�Ȃ����~�ɖS�삪�Z�ݒ����悤�ɂȂ����̂����A��̖��W���邱�Ƃ��Î����ꂽ�ȊO�͖��炩�ɂ���Ȃ������B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
�S��̂P�l�A�}�j�[�V�� |
�� |
�@�������o�D�����̉��Z�͂قڃp�[�t�F�N�g�B���Ɏ�l���̃X�V���~�^�[�E�Z�[���A�q���̃G�w�T�[�X�E�`�����i�[�A���X�������C�h���̃��[�X�B�J�[�E�W���[�V�[���f���炵�������B�X�V���~�^�[�E�Z�[���̉��Z�́uSamay�v�i2003�N�j�̍D�����z����ǂ��B�q���̓C���h�f��̎�_�����A�G�w�T�[�X�E�`�����i�[�N�̉��Z�͎��R�őf���炵�������B�ŋߍ˔\�̂���q������������A���Ɋ������B���[�X�B�J�[�E�W���[�V�[�����������C�h�́A���B���[�O�ƃW���~���̑O�ł͔L�����Ԃ����ŁA���[�n���ɂ́u�������ƕ����˂��Ƃ������̏o�鏬���ɕ����߂邼�I�v�Ƌ�����ɁA�Ƃ̂��̂𓐂ޑ��X�����z�������B���ɁA�uBride
& Prejudice�v�i2004�N�j�łS�l�o���̖������������s�[���[�E���[�C�E�`���E�h���[���o�����Ă������Ƃ����M���ׂ����B���������킢���킯�ł͂Ȃ����A�s�v�c�ƈ�ۂɎc���菗�D���Ǝv�����B�����A�uBride
& Prejudice�v�Ɠ����悤�Ȗ��������̂͋��R�Ȃ̂��A����Ƃ����̕����̏��D��ڎw���̂��낤���B
�@�f�撆�A�~���[�W�J���E�V�[���͈�Ȃ��B���̂�����f���Ԃ͖�R���Ԃ���B�|���f��ł͂��邪�A�N���C�}�b�N�X�ł͏����炱�ڂ�邩������Ȃ��B
�@�i�m�t�̓��ՓT�ƌ����A�H�̑I���Ət�̃z�[���[�ł���B�P�P���S���̑I�����ߕt���Ă���A�L�����p�X�ł͘A���������I�����킪�J��L�����Ă����B�����̓W�F�l�����E�~�[�e�B���O�i������j�Ŏ��Ƃ͋x�݁B���̋x���́u�t�@�[�G�_�[�E�E�^�[�l�[�E�P�E���G�i���܂����p���邽�߁j�v�A������o�u�q�A�k�p���Ő�T������J�̃q���O���b�V���f��uFlavors�v�������B
�@�uFlaovrs�v�͕č��ݏZ�̃C���h�l��҂����̗����A�A�E��A���ی����Ȃǂ����C�g�^�b�`�ŕ`������i�ł���B�ē̓��[�W�E�j�f�B���[���[�ƃN���V���iDK�B�L���X�g�́A���[�t�A�v�[�W���[�A�A�k�p���E�~�b�^���i�v���f���[�T�[�����C�j�A�W�b�L�[�E�V���j�[�A�A���W�����E�V�����[���[�X�^���A�o�[���e�B�[�E�A�[�`�����[�J���A�v�j�[�g�E�W���X�W���[�A�K�E�����E���[�����A���[�q�g�E�V���[�A�X�B���[�V���[�E�J�g���[�K�b�_�[�A���[�V���}�[�A�K�E���O�E�����[�X�ȂǁB�f�l�̔o�D�����l�o�����Ă���B
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
Flavors |
�� |
| Flavors |
�@�č��̓��݂ɏZ�ރJ�[���e�B�N�i���[�t�j�Ɛ��݂ɏZ�ރ��`���i�[�i�v�[�W���[�j�́A�����d�b�ł��낢��Ȃ��Ƃ�b���������������B��������`���i�[�͖���������������������A���ꂪ�Q�l�̒����}�ɗh���Ԃ��Ă����B
�@���h�i�A�k�p���E�~�b�^���j�͕č��l�̃W�F�j�[�i�W�b�L�[�E�V���j�[�j�ƌ������邱�ƂɂȂ����B���h�̗��e�i�A���W�����E�V�����[���[�X�^���ƃo�[���e�B�[�E�A�[�`�����[�J���j�͌������ɏo�Ȃ��邽�߂ɃC���h����č��ɂ���ė����B���e�̓W�F�j�[�̗��e�����ɗ������Ă��邱�Ƃɋ������A�W�F�j�[���ƂĂ��C�ɓ���B
�@�A�V���[�N�i�v�j�[�g�E�W���X�W���[�j�ƃW���X�i�K�E�����E���[�����j�͕č��ɗ������̂̐E���Ȃ��u���u�����Ă����҂������B���[�����C�g�̃��B���F�[�N�i���[�q�g�E�V���[�j���ŋ߉��ق��ꖳ�E�҂ɂȂ��Ă��܂����B���������B���F�[�N�́A�w������̃N���X���C�g�A�M�[�^�[�̂��Ƃ��Y����Ȃ������B�����������l�Ŕ��e�t�̃L�����f�B�[�i���[�V���}�[�j�́A���E�҂R�l�g�̐������Ǘ����Ȃ���ނ���܂��B
�@�T���M�[�^�[�i�X�B���[�V���[�E�J�g���[�K�b�_�[�j�̓j�L���i�K�E���O�E���B���[�X�j�ƌ������ĕč��ɈڏZ�������A�����ދ��Ȑ����𑗂��Ă����B����A�j�L���͉��ق���Ă��܂��A�Ȃɂ͓����Ŗ����E�T�������Ă����B
�@���h�ƃW�F�j�[�̌��������ߕt���Ă����B���`���i�[�͏o���œ��݂ɗ��ăJ�[���e�B�N�Ɖ���A�Q�l�̒��͎���ɂ�����Ă����B�J�[���e�B�N�͖{���̓��`���i�[�ƌ����������Ǝv���Ă������A�F�l�Ƃ��ĉ߂��������Ԃ������������߁A�Ȃ��Ȃ��{�S��ł��������Ȃ������B
�@���B���F�[�N�̓M�[�^�[�����Ɍ������Ă������Ƃ�m��ɓx�ɗ������ށB���Ԃ����͔ނ����݂ɘA��o�����ނ̐S�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B�L�����f�B�[�͂���Ȕނ��C�����Ĉ�ӂ�������ɂ��Ă����邪�A��������������Ƀ��B���F�[�N�̓L�����f�B�[�̂��Ƃ��D���ɂȂ��Ă��܂��B
�@���h�ƃW�F�j�[�̌������̓��A���e�̑��A�J�[���e�B�N�A�A�V���[�N�A�W���X�A���B���F�[�N�A�T���M�[�^�[�A�L�����f�B�[�A�j�L���炪�o�Ȃ���B���B���F�[�N�����ł���Ă����M�[�^�[�́A���̓j�L���̍Ȃ̃T���M�[�^�[�������B���`���i�[�͌������̑O�ɋ����čs���Ă��܂����A�J�[���e�B�N�͓d�b�Ń��`���i�[�Ƀv���|�[�Y������B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�q���O���b�V���f��̖͔͍�ƌ����Ă�����i�������B�č��ɏZ�ނm�q�h�i�݊O�C���h�l�j�P���A�m�q�h�Q���A�o�҂��C���h�l�A�����ė��s�ŗ����C���h�l�A���ꂼ��̐l���`�ʁA�S��`�ʂ��I�݂ŁA�e���|�����������X�s�[�f�B�[�ɐi��ŐS�n�悢�B���ꂾ���ɁA���X�g���������Ȃ������̂��c�O�������B
�@����ƌ����Ď�l���ƌĂׂ�L�����N�^�[�͂��炸�A�o��l���͂قړ������o�Ԃ��������B�X�g�[���[�̎��ƂȂ�̂̓��h�ƃW�F�j�[�̌������ł���A���h�̗��e�̃g���`���J���ȍs���������Ƃ�����U�����A���̃L�����N�^�[�����ꂼ��ɑ��݊��������Ėʔ��������B�Ⴆ�A���B���F�[�N����Ђ�����ق����V�[���B��i�̔��l�͎�����ɐU�郔�B���F�[�N�����Č����B�u����̓C�G�X���A�m�[���H�v����ł����B���F�[�N�͎�����ɐU��B�����܂ł��Ȃ��A���̎d���̓C���h�l�́u�C�G�X�v�����A�O���l�ɂ͂Ȃ��Ȃ���������Ȃ��B���ǃ��B���F�[�N�͉��ق���Ă��܂��B�z�����Ƃ����Ă����̂̓T���M�[�^�[�ƃj�L�����B�j�L������Ђ��N�r�ɂ���Ă��܂��̂����A������Ȃ̃T���M�[�^�[�ɂ͌��킸�ɖ����l�b�g�J�t�F�ŏA�E���������Ă����B����A�T���M�[�^�[�͑ދ��Ȏ�w�����𑗂��Ă���A�����ߌ�S�������TV�h���}�������P���̊y���݂������B������F�l����j�L�������ق��ꂽ���Ƃ�m���Ă��܂����A����ł��ޏ��͕v�̑O�ʼn�������Ȃ������B���̓��A�j�L���͎���������ق��ꂽ���Ƃ�ł�������B�T���M�[�^�[�͔ނɑ��āu�������d������Ȃ��B���Ȃ��͓���������������B�������炢�x�e���Ă������ł���B�ꏏ�ɉ߂����鎞�Ԃ��ł��邵�v�Ɖ������Ԃ߂�B��������Ԗʔ����͉̂��ƌ����Ă����h�̕�e�ƃW�F�j�[�̂��Ƃ肾�B��e�̓W�F�j�[�Ɂu�O�Ƀ{�[�C�t�����h�͂����́H�v�u����͗F�B�H����Ƃ�����ȏ�H�v�u���Ȃ��Ƌ߂����W�������́H�v�ƍ��@��t�@�蕷������A�u�ߋ��͉ߋ��A�C�ɂ���K�v�͂Ȃ���v�ƌ����āA�u���Ȃ��̓A�����J�l�����ǁA�Ƃ��Ă��������ˁv�Ə��B�W�F�j�[�̕����A�����������e�������Ă��邾���ɁA�C���h�I�Ƒ��̉���������������B��e���W�F�j�[�ɐl���̌P���Ƃ��ė^�������t�͂悩�����B�u�l���̓g���u�����炯����B���h�ƌ���������������̃g���u�����N����ł��傤�B�ł��A�������ĕʂ̐l�ƍč�������ꂪ��������Ƃ͎v��Ȃ��ŁB���Ǔ����悤�Ƀg���u�����N���邾����B�����͐l���ň�x�����ƍl���āA���̒��Ŗ����������Ă����悤�ɓw�߂ĂˁB��������A�������v�w�݂����ɖ��i��������B�v���̌��t���ăW�F�j�[�́u���͌����ă��h���狎�����肵�Ȃ�������S���āv�Ɩ���B
�@���̂悤�ɑ����̓o��l���𗍂ݍ��킹���X�g�[���[�́A���X�g�̎����̂���������ԏd�v�����A���̉f��ł͌��ǂ��ꂪ���܂������Ă��Ȃ������B���h�ƃW�F�j�[�̌������Ƀ��`���i�[�ȊO�͏o�Ȃ���̂����A����ɂ���ĉ����A���������N����Ȃ��Ă������肵���B�B��A���B���F�[�N���D���������M�[�^�[���T���M�[�^�[���������Ƃ��T�v���C�Y�������B�����A�S�̓I�ɂ悭�ł����f�悾�����̂ŁA���X�g�ő䖳���Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B
�@�q���O���b�V���f��Ƃ������Ƃœo��l���͉p�������ׂ�̂����A�T�^�I�ȃC���h�a�肩��ANRI2���̂��ꂢ�ȃA�����J�p��܂ŁA�l�X�ȉp�ꂪ�������Ă����B�q���f�B�[��ƃ^�~����i�����j�����������o�Ă��邪�A�p�ꎚ�����t���Ă���B
�@���������W�F�j�[���Z���t�̒��ŁuHindi Temple�v�ƌ����Ă���̂����B���{�l�͂悭�q���f�B�[��̂��Ƃ��u�q���h�D�[��v�ƌĂ�ł��邪�A�A�����J�l�ɂ����܂�u�q���f�B�[�v�Ɓu�q���h�D�[�v�̋�ʂ����Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B�q���f�B�[�͌��ꖼ�A�q���h�D�[�͏@�����ł���A�����̍����̓R�~���i���Ȗ��ɂ��Ȃ����Ă��܂��̂ł��܂�D�܂����Ȃ��B
�@�s�s���̃V�l�R���𒆐S�Ƀ����O�����������ȗǍ�q���O���b�V���f�悾�B�������Ɍ��J����Ă���O�����_���E�`���b�_�[�ḗuBride & Prejudice�v�i2004�N�j�����D�ꂽ�N���X�I�[�o�[�f��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�l�͂��˂��˃C���h�̓h���N�G�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���̍l�����C���h�ɏZ��ł��铯����̓��{�l�ɖ������Ă������������ӂ��Ă��炦�邱�Ƃ������̂ŁA�����ŗ��_���Ăāu�C���h���h���N�G�v�Ƃ������Ƃ𗧏��Ă݂����Ǝv���B
�@�܂��A�h���N�G�Ƃ̓G�j�b�N�X�Ёi���X�N�E�F�A�G�j�b�N�X�Ёj�̑�q�b�g�s�u�Q�[���u�h���S���N�G�X�g�v�̗��ł���B�P�X�W�U�N�ɔ���������ۂ�Љ�ۂƂȂ�܂Ől�C���A�Ȍネ�[���v���C���O�Q�[���i�q�o�f�j�Ƃ������삪�m�����ꂽ�B�����l�Ɠ������炢�̐���̐l�����Ȃ�A�h���N�G��m��Ȃ��l�͂��Ȃ��Ǝv���B�ȒP�ɐ�������A�Q�[���̖ړI�͓G�̐e�ʂ�|���A�P���~�o���邱�ƂȂ̂����A�����̎�l���̓��x�����Ⴍ�A�������Ȃ��ɓ������̂ŁA�����X�^�[��|���Ēn���Ɍo���l�Ƌ����҂��A���x�����グ�đ����𐮂��X����X�ւƗ��𑱂��āA�ŏI�I�ɐe�ʂ�|���B�h���N�G�͌��ݑ�V��܂Ŕ�������Ă���A����������W�삪���������\�肾�B�h���N�G�ƌ������ꍇ�A�����̃V���[�Y���I�Ɏw���Ă��邱�Ƃ��������A�l�͂����ł́A���ɃQ�[���V�X�e�����V���v���������A�����̃h���N�G�̂��Ƃ�O���ɂ����Ďg���Ă���B�u�C���h���q�o�f�v�Ƃ��Ă������̂����A�h���N�G�̖��O���o�����������肪�����̂ŁA�u�C���h���h���N�G�v�_�Ƃ��Ă����B
�@�܂��C���h�̃J�[�X�g���x���h���N�G���ۂ��B�h���N�G�ɓo�ꂷ��l�X�́A��l���ȊO���������݂�ȉ��炩�̎d�����l�Z�������Ă���B���퉮�͕�����Ђ����甄�葱���A�h��͂Ђ�����h��葱���A�͂Ђ������葱���A�h���͏�ɏh���ł���B����͂��Q�[������낤�ƕς��Ȃ��B�C���h������Ɣ��ɂ悭���Ă���B���͂Ђ����������������A�b�艮�͂Ђ�����b����������A�I�[�g���[���[�͂Ђ�����I�[�g���N�V���[���^�]��������B�s�s���ł͐l�̓���ւ�肪�������Ȃ��Ă�����̂́A�c�ɂ֍s������T�N�O�ɉ�����l�������ꏊ�œ������Ƃ����Ă����Ȃ�Ă��Ƃ̓U���ł���B�����������̗��ꂪ�~�܂��Ă��邩�̂悤�ȏ�Ԃ��h���N�G��z�N������B
�@��������Ă���l�̍s�����C���h�ƃh���N�G�ł͂����������Ă���B�C���h�̓��ɂ͉ɂȂ����������̂�т肵�Ă��邱�Ƃ������B�O���l�̎p������ƁA�u������Ƃ������ɗ��Ȃ����v�Ɨz�C�ɐ��������Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B������b�����킷�Ƃ��݂������ɑł������āA�v��ʏd�v�ȏ������ꂽ�肷�邱�Ƃ����邵�A�ςȘb�ɘb�肪�ڂ��Ă������Ƃ�����B�����������̐l�X�Ƃ̉�b�̋@�����A�h���N�G�Ƃ悭���Ă���B�h���N�G�ł��A���̏��邽�߂ɊX�̐l�X�ƐϋɓI�ɉ�b�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�S�Ă̐l���d�v�ȏ��������Ƃ͌��炸�A���܂�Ӗ��̂Ȃ����Ƃ�b���Ă���l������B
�@�C���h�ł��h���N�G�ł������W�͔��ɏd�v�ł���B���{�̂悤�ɂ����ȏꏊ�œ������̂��Ă���悤�Ȃ��Ƃ͏��Ȃ��A������̂���ɓ���邽�߂ɉ����̎s��֍s�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������B�Ⴆ�ΗF�B�̉Ƃɍs�����Ƃ��A�֗������ȕi���A���������I�V�����ȃO�b�Y���u���Ă������肷��B���R�A�������~�����Ȃ�B�u����ǂ��Ŕ������́H�v�ƕ����ƁA�e�ȗF�l�Ȃ�u�����s��́����̓X�Ŕ����Ă�v�ȂǂƋ����Ă���邾�낤�B���̏��ɏ]���čs���Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ����Ƃ������B����̐l�ɓ����A����Ƃ��̓X�����������Ƃ��͑傫�Ȋ�т�����B�h���N�G�ł��A�X�ɂ���Ĕ����Ă��鏤�i���Ⴄ�̂ŁA����̂��̂���ɓ���邽�߂ɉ����̊X�֑���L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������B
�@�o���l��ς߂ΐςނقǁA���������y�������֗��ɂȂ邱�Ƃ́A���{�ł��C���h�ł��������Ƃ��B�������A�C���h�ł͂��ꂪ���Ɍ����ł���B�Ⴆ�A�R���m�[�g�E�v���C�X����T�E�X�E�G�N�X�e���V�����ɃI�[�g���N�V���[�ōs�����Ƃ���B�܂��T�E�X�E�G�N�X�e���V�������ǂ̂��炢�̋����̏ꏊ�ɂ��邩������Ȃ��Ƃ��́A�I�[�g���[���[�ɂP�O�O���s�[���炢���ӂ��������邱�Ƃ��������낤�B�������A���x���R���m�[�g�E�v���C�X�ƃT�E�X�E�G�N�X�e���V�������������Ă���A�K�����i������ɕ������Ă���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ����ɁA�f���[�̐������I�[�g�^���������ł��Ă���B��d�␅�s�����C���h�ł͓��풃�ю��̖��ł���B�ŏ��̓��͌˘f���̂������͂Ȃ����A�Z��ł�����Ɏ���Ɋ���Ă��āA�ŏI�I�ɂ́u���A��d���v���炢�̑Ή��ɂȂ�A���₩�ɉ����d����E�\�N��p�ӂł���悤�ɂȂ��Ă���B������o���̎������낤�B�܂��A�C���h�̕�������j���w�ׂΊw�ԂقǁA�����◷�s���y�����Ȃ邱�Ƃ��A�o���l�㏸�ɂ�鉶�b���ƌ�����B�q���f�B�[��Ȃǂ̌��n��̏K���ɂ��A�������l����̂ڂ��������h�����Ƃ��\���B���{�̂悤�ɁA�C���h�͎Љ�S�̂��֗���Nj����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�l�̓w�͂����ɏd�v�ł���B
�@�C���h���l�Ƃ̒l���������Q�[�����o�ł��̂���Ԃ悢�ƌ����Ă���B���܂�^���ɂȂ肷����̂��݂݂��������A���ƌ����đS���l���������Ȃ��̂��u���{�l�͋��������悢�v�Ƃ�����ۂ��C���h�l�ɖ��łɗ^���Ă��܂��Ă悭�Ȃ��B��b���y���ނ悤�ɒl�i��������悤�ɂȂ��A������������Ɋy�����Ȃ邾�낤�i�����A�C���h�l�̒l�������͐^�����̂��̂����E�E�E�j�B�c�O�Ȃ���A�h���N�G�ɂ͒l�������Ƃ����V�X�e���͂Ȃ����A�C���h���l�Ƃ̌��͊��o�I�ɂ̓����X�^�[�Ƃ̐퓬�ł���B
�@�������Ȃ���A�l����ԃh���N�G��������̂́A���炩�̎����葱�������Ă���Ƃ����B�C���h�̎����葱���͑S�ăy�[�p�[���[�N�B�����ɕ֗����̒Nj��Ȃǂ͑S���Ȃ��B��w�̓��w�葱���ɂ��Ă��A���w�菑�̓���A���ނ̋L���A��o�A�ӔC�҂̏����W�߁A�w��̔[���ȂǂȂǁA���낢��ȃv���Z�X���o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ӔC�҂���ɂ���Ƃ͌���Ȃ����߁A�P�l�̃T�C������ɓ���邽�߂ɂ����ȂƂ�����������A�P�̏��ނ�����Ȃ����߂ɗ����o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�������A���ʂ�҂��߂ɉʂĂ��Ȃ��҂��������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������炢�́A�h���N�G�����߂Ƃ���q�o�f�ɂ͂悭����C�x���g�ł���i���p��Łu�t���O���āv�Ƃ������j�B�������A���͎҂ɃR�l����������d�G��n�����肷��ƁA�ώG�Ȏ葱�����M�����Ȃ����炢�ȒP�ɏI����Ă��܂����肷�邱�Ƃ��������肵�āA���Z�A�ւ���A�����������낢�둶�݂���̂��ʔ����B�ォ��U��Ԃ��āA�u���̂Ƃ����̏ꏊ�ł��̐l�ɋ��R���Ȃ�������A�����葱���͐i�܂Ȃ��������낤�v�Ǝv�����Ƃ��������A���������\�蒲�a�I�o����C���h�ƃh���N�G�ɋ��ʂ��Ă���B
�@�����A�C���h���h���N�G�ƌ��Ȃ��悤�Ȍ����́A���ۂɃC���h�Ő��܂�C���h�Ő������Ă���C���h�l�����ɂ͎���ȍl�������B������h���N�G�Ɍ����悤�Ƃ��A���ꂪ�ނ�̌����ł���A���̒��Ő^���ɐ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������O�����痈����X���A�u�C���h�̓h���N�G���v�ƌ������Ƃ́A�ォ�猩�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�^���Ă��܂��B�������A�C���h�l�̎v�z���悭���Ă݂�ƁA�u���̐��E�͐_�l�̃��[���[�̏�v�Ƃ����l����������B�u���[���[�v�Ƃ́u�V�Y�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�_�l�͂��̐��E�Ɂu�V�ԁv���߂ɕ����~��Ă���ƍl�����Ă���B�Ⴆ�u���[�}�[���i�v�ŕ`����Ă��郉�[�����q�Ɨ��������[���@���̐킢�ɂ��Ă��A�ǂ�������ʂ͕������Ă��Ȃ���A�����āu�V�ԁv���߂ɐ푈���s�����̂��B�܂�A���[���͐��`�̖����A���[���@���͈��̖����������Ƃ��������ŁA�{���I�ɂ͐_�l�̍s���́u���V�Y�v�ł���A�l�Ԃ͂�������ɏ]�������Ȃ��B���́u���߂̓N�w�v���C���h�l�̎v�z�̍����ɂ���B�u����Ȃ݂��߂Ȑ��������Ă���̂ɁA�Ȃ�����Ȑl�Ԃ炵���Ί�������邱�Ƃ��ł���̂��낤�H�v�Ǝv�����Ƃ������̂����A�������L�̂悤�ȃC���h�l�Ɠ��̍l�������e�����Ă���Ǝv����B�Ⴆ�ǂ�Ȗ���^�����悤�ƁA���̖������������邱�Ƃ����[���ł���A�Q�[���̏��҂ւ̓��Ȃ̂��B���ǁA�u�C���h���h���N�G�v�_�́A�C���h�̒������j�̒��ł͓��ɐV�����l�����ł͂Ȃ��A�C���h�l���g���u���̐��̓Q�[�����v�ƍl���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���H
�@�����͂o�u�q�v�����[�ŐV��q���O���b�V���f��uMorning Raga�v�������B�ē̓}�w�[�V���E�p�b�^�j�[�A���y�̓}�j�E�V�����}�[�ƃA�j�g�E�n���B�L���X�g�́A�V���o�[�i�E�A�[�Y�~�[�A�v���J�[�V���E���[�I�A�p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[���A�����b�g�E�h�D�x�[�A�V�����[���E�V�����}�[�A���B���F�[�N�E�}�V�����[�A�i�Z���A���B�W���C�ȂǁB
| �� |
|
�� |
|
 |
|
| �� |
������v���J�[�V���E���[�I�A
�p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[���A
�V���o�[�i�E�A�[�Y�~�[ |
�� |
| Morning Raga |
�@�A�[���h���E�v���f�[�V���B�̂��鑺�B���y�̍˔\���������X�����i���^�[�i�V���o�[�i�E�A�[�Y�~�[�j�́A�F�l�Ń��@�C�I�����t�҂̃��@�C�V���i���B�[���ɗU���āA�R���T�[�g�ɏo�����邽�ߊX���������B�X�����i���^�[�̑��q�}�[�_���ƃ��@�C�V���i���B�[�̑��q�A�r�i�C���ꏏ�������B�Ƃ��낪�ޏ���̏�����o�X�́A���̍x�O�ɉ˂��鋴�Ŏ����ԂƏՓ˂��A�͂ɗ����Ă��܂��B���̎��̂ɂ��A���@�C�V���i���B�[�ƃ}�[�_���͎���ł��܂����B����ȍ~�A�X�����i���^�[�͎����̉߂��������Ŕ����邽�߁A�����������o���A�Ђ�����ƕ�炵�Ă����B
�@�Q�O�N��A�n�C�_���[�o�[�h�ɏZ��Ń~���[�W�V������ڎw���Ă����}�[�_���i�v���J�[�V���E���[�I�j�́A�d�������߂Ė{�i�I�ɉ��y�������n�߂�B�}�[�_���̓o���h���Ԃ��W�߂Ă����B�v���U��ɑ��ɋA�����}�[�_���́A���R�s���L�[�i�p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[���j�Əo��B�s���L�[�����X�������ɏZ��ł���A�v���U��ɑ���K�˂Ă����Ƃ��낾�����B�}�[�_���ƃs���L�[�͈ӋC�������A�ꏏ�Ƀo���h�����邱�Ƃɂ���B
�@�n�C�_���[�o�[�h�ɖ߂����Q�l�́A�s���L�[�̕�e�J�v�[���v�l�i�����b�g�E�h�D�x�[�j�̋��͂����Ȃ���ׁ[�V�X�g�ƃh���}�[�������āA���X�g�����ʼn��t���n�߂�B�����A���y�ɉ��̋������Ȃ��l�X�̑O�ʼn��X�Ɖ��t�������邱�Ƃɋ^����o�����}�[�_���͂����Ɏ��߂Ă��܂��B�s���l�����}�[�_���͍Ăё��ɖ߂�A����e�̗F�l�������X�����i���^�[��K�˂�B�}�[�_���͐���ޏ��Ƀo���h�ɓ����Ă��炢���������B�X�����i���^�[�͍ŏ��͒f����̂́A�v�̊��߂�����A�o���h�ɋ��͂��邱�ƂɂȂ�B
�@�₪�ăn�C�_���[�o�[�h�Ńt���[�W�������y�̃R���T�[�g���J����邱�ƂɂȂ����B�}�[�_�������͂���ɏo�����邽�߂ɁA�X�����i���^�[�ɊX�ɗ���悤�ɗ��ށB�������X�����i���^�[�͎��̌���̋��Ƀo�X������ƁA�̂̎S�����v���o���Ď�藐���A�o�X����~��Ă��܂��B���ǃR���T�[�g�̓L�����Z�����ƂɂȂ����B
�@�X�����i���^�[�͂��̑���A�s���L�[�ɐ��y�������邱�Ƃɂ����B�s���L�[�̓X�����i���^�[�̉ƂɏZ�ݍ���Ő��y���K���B�₪�ĕʂ̃R���T�[�g���n�C�_���[�o�[�h�ōÂ���邱�ƂɂȂ����B�}�[�_����͍Ăяo�����邱�ƂɌ��߁A�X�����i���^�[�ɂ��X�ɗ���悤�ɗ��ށB�s���L�[�̓X�����i���^�[����Ԃɏ悹�ċ���n��A�����N����Ȃ����Ƃ��ؖ�����B�܂��A�s���L�[�͎��͂Q�O�N�O�̎��̂Ńo�X�ɏՓ˂����Ԃ��^�]���Ă����̂́A�������������e���������Ƃ��}�[�_���ƃX�����i���^�[�ɑł�������B
�@�R���T�[�g�̓��B���ɂ̓X�����i���^�[�����ꂽ�B�s���L�[�͔ޏ��ɉ̂��悤�ɗ��ށB�X�����i���^�[�͈�u�S�O���邪�A�̂��o���A�ϋq���犅�т𗁂т�B |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
�@�����͂Ȃ��̂����A���܂�������オ��ɂ����銴�̂������q���O���b�V���f�悾�����B�ē͌��X����ƂŁA�Q�C�f��uMango Souffle�v�i2003�N�j���B�����l���B�uMango Souffle�v�͂��Ȃ艉��������̂��߁A���Ȃ艉�����ۂ��f��ɂȂ��Ă��܂��Ă������A�uMorning
Raga�v�ł͂��̓_�͉��P����Ă����B�������A�܂��f��̕��@�ɂ��܂芵��Ă��Ȃ��Ƃ��낪����悤�Ɏv����B
�@���̉f�悪�����Ȃ��Ǝv�����̂ɂ́A���y�̗ǂ��A���Z�̗ǂ��A�����ēc�ɂ̔_���̗ǂ��̂R�_�̂��������낤�B
�@�薼�ɃC���h���y�̐��p��u���[�K�v�������Ă��邾������A���y���e�[�}�̉f�悾�����B����ʼn��y���S���ʖڂ�������ڂɎ�����Ă��Ȃ������̂����A�J���i�[�e�B�b�N���y�i��C���h�̌ÓT���y�j�����ɂ������͋C�������o���Ă����B�ÓT���y�ƃL�[�{�[�h�A�h�����A�x�[�X�Ȃǂ����킹���t���[�W�������y�������Ȃ������Ǝv���B�C���h�̌ÓT���y���Ă���ƁA�C���h�͑f���炵���Ɖ��߂Ď�������B���������̉f��ł��`����Ă���悤�ɁA�C���h�̔_���ɂ͗D�ꂽ�A�������Ă���m�炴��鉹�y�Ƃ���������������������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B�uDance Like A Man�v�i2004�N�j�ł������悤�ɁA���̉��̕ϓN���Ȃ����k����i���f�[���_�[�X�B�[�j���ÓT���y�������Ă���V�[�����������B
�@�剉�͉��ƌ����Ă��V���o�[�i�E�A�[�Y�~�[���B�C���h�L���̉��Z�h���D�ŁA�uCity of Joy�v�i1992�N�j�Ȃljp��̉f��Ƃ��������ǂ��B�Ȃ����q���O���b�V���f��ɂ����o�����Ȃ��p���[�U�[�h�E�]�[���[�r���[�����D���B�p���[�U�[�h�͂��܂�q���f�B�[�ꂪ���ӂł͂Ȃ��̂��낤���H����Ńf�r���[�Q��ڂ̃v���J�[�V���E���[�I���������������Z�����Ă��Ă悩�������A����̕\�����������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɗ������B���̂R�l����������A�s���L�[�̕�e���������������b�g�E�h�D�x�[�����������o���Ă����B�ޏ��́ukal Ho Naa Ho�v�i2003�N�j�ɂ��t�@���L�[�Ȗ��ŏo�����Ă����B
�@�C���h�̓c�ɂ͂����������邢�B���ꂾ���Ŕ��ɊG�ɂȂ邩�炾�B�f��ɂ���A�ʐ^�ɂ���A�Ƃ������c�ɂ֍s���Ď蓖���莟��ɉf���ɂ��邾���ŁA���炩�̌|�p�������������̂��o���Ă��܂��B�C���h�̔_���͂����������͂Ɉ��Ă���B���̉f��ł��c�ɂ̖��͂������Ղ�ƕ`���Ă����B�X�����i���^�[���Z��ł���Ƃ́A�����O�̓��L�ŐG�ꂽ�A���@�[�X�g�D�E�V���[�X�g���ɏ����Đv����Ă���T�^�I�ȃC���h�̉Ɖ����Ǝv�����B���l�̒��ł͐����������R���f�B�[���ۂ����ŏo�Ă��Ă悩�����B�ނ͏�ɃA���i�v�[���i�[�Ƃ������̐����ƈꏏ�ɂ���A�u�����N���Ă����O�̓~���N���o���āA������͂���邾���v�ƌ����������Ă���Ƃ��낪�ʔ��������B
�@�u��C���h�̂��鑺�v������Ƃ���Ă������A���炩�ɃA�[���h���E�v���f�[�V���B�̔_��������ƂȂ��Ă���A�B�s�n�C�_���[�o�[�h�̉f�����A�`���[���E�~�[�i�[�����܂߂Ă�������o�Ă����B�Ō�̃R���T�[�g�̓S�[���R���_�[�Ԃ̑O�ōs���Ă����B����͊�{�I�ɉp�ꂾ���A���l�����̓e���O���b���B�����Ɖp�ꎚ�����o��B
�@�q���O���b�V���f��͎��̍�����i�������̂ŁA�q���f�B�[��f������D��I�Ɍ��邱�Ƃɂ��Ă���B���̉f��̓q���O���b�V���f��̒��ł͊����x�̒Ⴂ�f��ƌ�����B�����A����ł���L�̂R�_�ɂ�茩�鉿�l�͂���f��Ɏd�オ���Ă����Ǝv���B
|
|
|
|
|
�m�d�w�s���Q�O�O�S�N�P�P��
|
|
| *** Copyright (C) Arukakat All Rights Reserved *** |



