本日から、インド版「ロリータ」として話題になっていたヒンディー語映画「Nishabd」が公開された。監督はボリウッドを代表する曲者映画監督、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー。2005年に「Nisshabd」という題名のベンガリー語映画が公開されており、タイトルが似ているということで直前になって公開中止を求める裁判が行われていたが、「もし不平があったらもっと前に訴えることができたはず」として、その訴えは却下され、無事公開となった。
題名:Nishabd
読み:ニシャブド
意味:沈黙
邦題:ジヤー
監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー
制作:アドラブス
音楽:ヴィシャール・バールドワージ
出演:アミターブ・バッチャン、ジヤー・カーン(新人)、レーヴァティー、ナスィール、シュラダー・アーリヤ、アーフターブ・シヴダーサーニー(特別出演)
備考:チャーナキャー・シネマで鑑賞。

ジヤー・カーン(左)とアミターブ・バッチャン(右)
| あらすじ |
写真家のヴィジャイ(アミターブ・バッチャン)は、広大な紅茶園の中で妻アムリター(レーヴァティー)と共に静かに暮らしていた。2人にはリトゥ(シュラダー・アーリヤ)と言う18歳の娘がいた。彼女は街の高校に通っていたが、テストを終え、休暇を家族と過ごしに戻って来ていた。今回、彼女は友達のジヤー(ジヤー・カーン)も一緒に連れて来た。
ジヤーは特殊な環境に育った変わった雰囲気の少女であった。両親は離婚し、母親と共にオーストラリアで育った。母親は再婚しようとしていたが、彼女はそれが気に入らなかった。ジヤーはヴィジャイに惹かれ、次第に彼を誘惑するようになる。ヴィジャイの行動も段々おかしくなって来る。遂にジヤーはヴィジャイに「私はあなたのことを愛してる」と言い、ヴィジャイも「イエス」と答える。ジヤーはヴィジャイに口づけするが、それをリトゥが見てしまう。
リトゥはそのことを母親に言えず、ただジヤーを追い出そうとする。だが、アムリターは2人が喧嘩をしたものと思い、真剣に取り合わなかった。そのとき、アムリターの兄(ナスィール)がやって来る。リトゥは叔父にそのことを打ち明ける。驚いた叔父はヴィジャイを説得する。だが、ヴィジャイは自らアムリターにそのことを打ち明けてしまう。ショックを受けたアムリターは1人部屋に篭って泣き出す。
また、そのときジヤーの友達のリシ(アーフターブ・シヴダーサーニー)が彼女を訪ねてやって来る。リシはジヤーに惚れており、明日の誕生日に驚かそうと思って密かにやって来たのだった。だが、ジヤーはリシを嫌っており、彼を追い返そうとする。
だが、自分の行動が家族全てを傷付けたことを知ったヴィジャイは、ジヤーを家から追い出す。その後、崖に身を投げて死のうと考えたヴィジャイであったが、死ねずに家に戻って来る。彼は残りの人生をジヤーとの思い出の中で過ごすことに決めたのであった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Naach」と似た雰囲気の、美しくもエロチックな作品。スタンリー・キューブリック監督の「ロリータ」(1962年)の焼き直しではなく、老年の男性が未成年の少女に恋をするという点を除けば全くのオリジナルストーリーである。アミターブ・バッチャンの重厚な演技も素晴らしいが、この映画の中心は何と言ってもジヤーを演じた新人女優ジヤー・カーンであろう。彼女がいなければこの映画は成り立たなかったし、もし別の女優が演じていたら全く別の雰囲気の映画になっていただろう。早くもジヤー・カーンは今年最大の新人と噂されている。
登場人物の心理や、これから起こる出来事を予感させる絶妙なカメラワークが映画を盛り上げていたが、その中でもジヤーの肢体の描写の仕方は突出していた。特に強調されていたのは、彼女の脚である。先日発表されたフィルムフェア賞で新人賞を獲得したカンガナー・ラーナーウトも、「Woh
Lamhe」(2006年)の中で脚を必要以上に露出していて印象に残ったが、「Nishabd」のカメラはそれ以上にジヤー・カーンの脚を執拗に映し出していた。ボリウッドの脚フェチ化が進行しているように思える。

ヴィジャイが次第にジヤーへの恋に落ちていく様子も、非常にリアルに描写されていた。映画は基本的にヴィジャイの独白によって進んで行く。彼はジヤーに恋してしまった理由を、以下のように自己分析していた。「人間は老年になると、死への恐怖を感じるようになる。それを忘れるために、若者の方へ心が向くのだ。」「Dil Se」(1998年)の「Jiya Jale」が、2人の気持ちのシンクロの象徴として使われていた。もちろん、ジヤーという名前と曲の題名が掛けられている。また、ヴィジャイとジヤーの会話はどれも緊張感溢れていて素晴らしかった。
他に、ジヤーが庭のホースで水を浴びるシーン、アムリターがジヤーへの恋に狂ったヴィジャイを一喝するシーンなども映像的にパワーがあった。
しかし、エンディングはベストではなかっただろう。ジヤーを追い出し、一応家庭内に平穏を取り戻したものの、父親としての威厳と家族内の愛情は消滅してしまった。リトゥは突然米国留学を決め、妻はよそよそしい態度になった。ヴィジャイは自殺しようとするが、それよりもジヤーとの思い出を胸に残りの人生を生きることに決め、家に戻って来るのである。この終わり方は中途半端だったのではないかと思う。とは言え、ヴィジャイの自殺で幕を閉じるよりは数倍マシだ。
「Nishabd」でデビューしたジヤー・カーンは曰くつきの女優である。1987年にニューヨークで生まれ、ロンドンで育ったジヤーは、英文学、演劇、オペラ、舞踊などを修めた。ジヤー・カーンの母親はラビーヤーという名の女優だが、噂によると父親は映画プロデューサーのターヒル・フサインらしい。ターヒル・フサインは有名男優アーミル・カーンの父親であり、それが本当ならジヤー・カーンはアーミル・カーンの異母兄妹ということになる。だが、ターヒル・フサインは公式にはそれを否定している。「Nishabd」で似た境遇のジヤー役を演じたジヤー・カーンの気だるい表情には、演技ではない真の感情が隠されているのかもしれない。
また、映画中、「ボリウッドの帝王」アミターブ・バッチャンと、新人女優ジヤー・カーンのキスシーンがあり、話題になっている。
ダンスシーン一切なし、2時間の国際標準上映時間にまとめられた「Nishabd」は、心に突き刺さる重い展開と、19歳のジヤー・カーンの怪しい魅力が見所の小品である。多様に進化するボリウッドの一翼を堂々と担うことができる映画と言える。
「Lagaan」(2001年)のアカデミー賞外国語映画賞ノミネート以来、インドでは毎年アカデミー賞でインドの作品がどれだけ健闘できるかが注目されるようになった。2006年度は「Rang
De Basanti」がインドの公式エントリー作品となったが、ノミネートには至らなかった。代わりに、カナダからエントリーされたディーパー・メヘター監督の「Water」が外国語映画賞にノミネートされた。ディーパー・メヘター監督はインド生まれのインド人女性監督で、「Water」も生粋のインド映画だが、現在カナダのトロント在住のため、カナダからのエントリーとなった訳である。残念ながら「Water」も受賞を逃したが、今年もアカデミー賞の牙城にインドの作品が食い込んだことで、インドの映画界は一応面目が保たれた形となった。
メヘター監督は1998年に「Fire」、1999年に「Earth」という名の映画を公開しており、この「Water」は三部作の最終作に当たる作品である。「Fire」では現代インドのジェンダー、性、結婚の問題が描かれ、「Earth」では1947年の印パ分離独立がテーマとなった。そして最後の「Water」は、さらに時代が下り、1938年のインドが舞台となっている。テーマは未亡人問題である。
題名:Water
読み:ウォーター
意味:水
邦題:ウォーター
監督:ディーパー・メヘター
制作:デーヴィッド・ハミルトン
音楽:ARレヘマーン
作詞:スクヴィンダル・スィン
出演:ジョン・アブラハム、リサ・レー、スィーマー・ビシュワース、サララー(新人子役)、クルブーシャン・カルバンダー、ワヒーダー・レヘマーン(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。
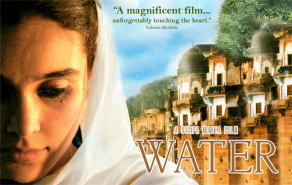
リサ・レー
| あらすじ |
8歳の少女チュイヤー(サララー)は、幼児婚をした相手が死去したことにより、幼くして未亡人になってしまう。両親は彼女をヴィドヴァーシュラム(未亡人の集住所)へ入れる。ヴィドヴァーシュラムのボス、マドゥマティーはえげつない人間だったが、「ディーディー」と呼ばれるシャクンタラー(スィーマー・ビシュワース)おばさんや、美しいカリヤーニー(リサ・レー)がチュイヤーの面倒をよく見た。チュイヤーも次第にヴィドヴァーシュラムの生活に慣れて来る。
ある日、ガート(河岸)で沐浴をしていたカリヤーニーとチュイヤーは、弁護士の試験を終えて帰って来た青年ナーラーヤン(ジョン・アブラハム)と出会う。ガーンディーの思想に影響を受けたナーラーヤンは、インドの独立を夢見ており、英国の支配に安住する友人を必死に説得していた。ナーラーヤンはカリヤーニーに一目惚れしてしまい、頻繁にヴィドヴァーシュラムを訪ねるようになる。やがて2人は結婚することを決める。
ところが、インドの宗教は未亡人の再婚を認めていなかった。ナーラーヤンの母親は絶句し、マドゥマティーはカリヤーニーの髪の毛を刈って部屋に閉じ込める。だが、シャクンタラーは僧侶から「未亡人の再婚を認める新しい法律が出来た」と聞き、カリヤーニーの再婚を手助けする。カリヤーニーはヴィドヴァーシュラムを出て、ナーラーヤンのもとへ駆け込む。
ところが、カリヤーニーはナーラーヤンの父親がドワールカーナートであることを知って結婚を諦める。なぜならカリヤーニーは、マドゥマティーによって売春をさせられており、その顧客がドワールカーナートだったからである。カリヤーニーは入水自殺をする。また、ナーラーヤンは父親の所業を知って家を出る。
カリヤーニーを失ったボスは、今度は代わりにチュイヤーに売春をさせる。それを知ったシャクンタラーは、チュイヤーを連れて逃げ出す。折りしも、町の鉄道駅でガーンディーが少しだけ公演を行うことになった。ガーンディーは大衆の前で、「神が真実なのではなく、真実が神なのだ」と説く。シャクンタラーは動き出す列車を追いかけ、チュイヤーをガーンディーに託そうとする。ちょうどその列車にはナーラーヤンが乗っており、彼はチュイヤーを受け取る。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
インドの未亡人問題は、通常の日本人にはあまり理解できない問題であるが、インドでは度々題材となる大きな問題である。ヒンドゥー教徒の日常生活の規範を規定したマヌ法典では、未亡人は不吉な存在とされ、未亡人になった瞬間からこの世のあらゆる快楽から切り離された生活を送らなければならないことが規定されている。そのため、未亡人は映画で描かれていた通り、ヴィドヴァーシュラムという未亡人集住場に入れられることも多い。今でもヴィドヴァーシュラムは存在するし、僕も実際にブリンダーヴァンで訪れたことがある。また、マヌ法典では未亡人の再婚が固く禁じられている。未亡人の救済の道はただ2つ、夫の死と共に焼身自殺(サティー)するか、夫の弟と結婚するかである(後者の解決法はインド映画でも時々出て来る)。未亡人問題の中でも最も深刻なのが、幼児婚とセットになった未亡人問題だ。インドでは、幼少の頃に結婚相手が決められる習慣があった(今でも田舎ではある)が、その相手が幼くして死んでしまうと、少女は顔を見たこともない旦那のために一生未亡人として暮らさなくてはならなかった。「Water」で焦点が当てられているのも正にこの問題である。
また、裏のテーマとしてガーンディーの思想に対する庶民の視点も取り上げられていた。田舎に住む人々は、古くからの因習に固執しており、ガーンディーが説く社会改革思想は全く受け容れられていなかった。また、富裕層は英国支配を礼賛し、インド独立などありえないと考えていた。その一方で、ナーラーヤンのような若者が、ガーンディーに影響を受けて独立運動へ飛び込んで行く様子が描かれていた。しかし、1938年という年代には疑問が残った。南アフリカからインドに帰って来たガーンディーが本格的に社会運動を始めるのは1918年で、1920年代には既にインド全土にその名が知れ渡っていたはずであるが、映画中ではガーンディーがあたかも新たに出現した救世主のように描かれていた。確かに田舎ではまだまだガーンディーの名はそれほど認知されていなかったかもしれないが、「Water」の舞台はそれほど田舎でもないだろう。よって、年代をもう15年ほど遡らせた方が現実味があったのではないかと思う。
ちなみに、映画の舞台となった町は、最後に出て来る鉄道駅によると、ラーワルプルという場所である。元々「Water」のロケはヴァーラーナスィーが予定されており、映画のポスターの背景にもヴァーラーナスィーのガートの写真が使われているが、ディーパー・メヘター監督を敵視するヒンドゥー教過激分子の妨害により、ロケを中断せざるをえなかった。このときのキャストは、シャバーナー・アーズミー、ナンディター・ダース、アクシャイ・クマールであった。その後、監督は全く新しいキャストと共にスリランカで映画撮影を決行し、完成させた。よって、風景には北インドではあまりないようなトロピカルさが出てしまっている。
「Water」は、ヴィドヴァーシュラムに放り込まれたあどけない少女の視点からインドの未亡人問題を捉えており、切なくも美しい作品に仕上がっていた。しかし、今になって70年前のインドを舞台に未亡人問題を取り上げることに疑問を感じた。映画の最後に一応、現代でもインドに未亡人問題が残っていることが伝えられるが、もしそうなら現代を舞台にした映画にすべきだったのではないか。1938年を舞台にしたら、単に過去の社会問題を取り上げた歴史映画として受け止められてしまう可能性もあるだろう。
だが、観客の心に染み入る美しいシーンがいくつもあった。ヴィドヴァーシュラムには、ラッドゥー(お菓子)を食べたくて仕方のない老婆ブアーが住んでいた。ブアーは事あるごとに昔食べたお菓子のことをみんなに聞かせていた。未亡人はお菓子を食べることも禁じられている。ブアーの望みは叶わぬ望みなのである。だが、チュイヤーは町の寺で乞食をして得た小銭でラッドゥーを買い、ブアーにこっそりプレゼントする。ブアーは顔をくしゃくしゃにして喜び、ラッドゥーを一気に呑み込む。その晩、ブアーは死んでしまう。
ナーラーヤンとカリヤーニーの逢引きのシーンも幻想的だった。無数のオイルランプの灯る大木の下、2人は愛の言葉を交わす。ナーラーヤンはサンスクリット詩人カーリダーサの有名な詩「メーガドゥータ」を引き合いに出し、雲に愛のメッセージを乗せて送る恋人たちの話をする。
主人公チュイヤーを演じたサララーは、時々表情が固いことがあったが、難しい役をよくこなしていた。なんと彼女はメヘター監督がスリランカで見つけた少女で、英語もヒンディー語も話せなかった。セリフも、音で覚えてしゃべっていたと言う。それを考えれば上出来と言えるだろう。スター男優の王道を行っているジョン・アブラハムがこのようなシリアスな映画に出演するのは違和感があったが、特に重要な見せ場もなく、映画の調和を崩すようなことはしていなかった。美しい未亡人カリヤーニーを演じたリサ・レーは、インド人とポーランド人のハーフ。外見がインド人離れしており、適役とは言えなかったが、繊細な演技ができる女優だと感じた。その他、スィーマー・ビスワースやクルブーシャン・カルバンダーと言った名脇役俳優が出演していた。
音楽はARレヘマーン。「Water」のサントラCDにオリジナル曲は5曲のみだが、どれも非常にレヘマーンらしい音楽である。雨のシーンで流れる「Aayo
Re Sakhi」は、インドの雨に含まれる喜びをよく表しているし、ナーラーヤンと結婚を前にしたカリヤーニーの心情を描写した「Sham Rang
Bhar Do」も美しい曲である。「Water」はインドでの一般公開は2007年3月であるが、実は2005年公開の映画であり、レヘマーンの音楽も一時代前の彼の音楽という感じである。
インドで公開されたバージョンはヒンディー語であったが、おそらく英語版も存在するはずである。ヒンディー語バージョンで使われていたヒンディー語にはヴァーラーナスィー辺りで話されているボージプリー方言と思われる訛りが加味されていた。
2006年度アカデミー賞外国語映画賞ノミネート作品の「Water」は、カナダの映画ということになってはいるものの、そのテーマと魂はインド映画そのものである。作品として優れているばかりでなく、インドの未亡人問題を理解するのに役立つ映画と言える。
インドの警察官。

インドの警官にヒゲは付き物である。警官にヒゲが生えているのではなく、ヒゲに警官がくっ付いているのではないかと思うこともあるくらいだ。それほど警察とヒゲは切っても切れない関係にある。警察だけではない。男が男らしくあるためにヒゲは必須である。今一番人気のボリウッド・スター、アビシェーク・バッチャンを見てみるがいい。ジョン・アブラハムを見てみるがいい。皆、多かれ少なかれヒゲを生やしている。あのシャールク・カーンですら、「Paheli」(2004年)でヒゲ付きで登場したし、アーミル・カーンも「Mangal
Pandey」(2004年)でヒゲ(自毛)をふてぶてしく撫で回してインド独立に貢献した。ヒゲをきれいに剃りあげた男が、大学で不良上級生に「エー、チクネー」と呼ばれていじめられるのはボリウッド映画ではお馴染みのシーンである。だが、やはりヒゲは何よりまず、警察官の象徴と言っていい。あの太っ腹とヒゲさえあれば、誰でも警察官に採用していいのではないかと思う。

アビシェーク・バッチャン(左)とアーミル・カーン(右)
その警官のヒゲを巡る論争が巻き起こっている。事の発端はムンバイー警察に届いた1枚の進言書。その中で、警察官のヒゲを必須とすることが提案された。理由は簡単である。警察官のアイデンティティーの原点は恐怖にあり、ヒゲを生やすことでそれを効率的に実現できるからである。この進言書は、ヒゲ賛成派とヒゲ反対派を生んだ。さらに、「どっちでもいい」「個人の自由に任せればいい」という中道派が間を取り持っている状態である。既にヒゲが絶滅の危機に瀕している日本の人々から見たら何とも馬鹿馬鹿しい論争であるが、まだ「マルダーンギー(男らしさ)」が幅を利かせているインドでは、これは警察のみならず男の尊厳自体に関わる非常に重要な問題である。パンジャーブには「मुछ
नहीं ते कुछ नहीं(ヒゲがなければ何もない=ヒゲを生やしていない男は男じゃない)」という諺もあるくらいだ。果たして警察官にヒゲは必要か否か、どうやらその論争はデリーにも飛び火しそうだ。3月15日付けのヒンドゥスターン紙折込版メトロ・リミックスによる。
ヒゲ反対派の言い分はこうである――警官はただでさえ図体がでかく、怖いイメージがある。その上にヒゲを生やした警官はさらに怖く見える。折りしも警察は「ピープルス・フレンドリー」を掲げているところだ。デリー警察のスローガンも「सदैव आपके साथ(いつもあなたのそばに)」である。ヒゲを生やした警官は、警察のフレンドリーなイメージを損なう可能性がある。また、警察はスマートに見えなければならない。そのためには、ヒゲを犠牲しなければならない。警官からヒゲをなくせば、女性も安心して警察署に苦情や相談をしに行くことができるようになるだろう――
一方、ヒゲ賛成派はこんなことを言っている――警察にとってヒゲは非常に重要だ。ヒゲにより恐怖感が増す。警察は犯罪者や悪党を懲らしめることが第一の仕事だ。そのためにはヒゲがまずは大事である。人民が警察を恐れなくなったら治安は保てない。それに男にヒゲは必須である。最近は女性も髪を短くしているから、ヒゲがなくては男か女か分からない――
中道派の意見はこんな感じだ――ヒゲは警官のドレスコードにはなりえない。ヒゲを生やすも生やさないも個人の自由だ。確かにヒゲを生やすことによって恐怖感は増す。そしてそれが似合う警官もいる。だが、ヒゲを生やさない方がスマートに見えて似合う警官もいる。だから、警官全員に無理にヒゲを生やさせることはできない――
中道派の意見がどう見てもまともなのだが、それでも論争になるところがインドの面白いところだ。どうやらこの論争の原点には、2004年に射殺された伝説の盗賊ヴィーラッパンの影響もあるらしい。ヴィーラッパンはその特徴的なヒゲで知られていた人物である。あのヒゲに影響され、やはり警察たるもの立派なヒゲがなくては、と考える警官がいたようだ。ただし、ヴィーラッパンが射殺されたときには、彼は自慢のヒゲをそり落としていた。変装のためと見られている。

ヴィーラッパン
ヒゲを剃ったら、ただのチャーイ屋のおっさんに見えそうだ
確かにラージャスターン州などの警官には立派なヒゲを生やしている人がいて、それを見ると「ヒゲっていいなぁ」と思ってしまう。少なくとも絵として最高である。
実はインドでは、ヒゲを生やした警察官が特別手当をもらえる地域がいくつか存在する。例えばマディヤ・プラデーシュ州のジャブアー県では、ヒゲを生やした警察官にのみ、毎月30ルピーの特別手当が出る。また、インド陸軍でも、ヒゲを生やすために兵士に給金が支給されたり、立派なヒゲを生やした兵士が表彰されたりするらしい。
だが、少なくともデリーの警察の中では次第にヒゲはトレンディーではなくなって来ているようだ。それに今のところ、デリー警察では警官のヒゲを義務化するような提案はなされていない。ヒゲの衰退により、フレンドリーな警官が増えるといいのだが・・・。
日本人には全く知られていないだろうが、現在カリブ海の西インド諸島では、クリケットのワールドカップが開催されている。最近やたらソワソワしているインド人が増えたのはそのためだ。そのワールドカップに狙いを定めて制作されたと思われるヒンディー語映画が本日から封切られた。「Hattrick」である。「ハットトリック」はサッカーでお馴染みの言葉だが、元々はクリケットの専門用語。投手が打者を3球連続でウィケット(アウト)にする離れ業のことを言う。「Hattrick」は最近ボリウッドで流行りのオムニバス形式。クリケットを題材にした3つの小話が1つの映画になった映画である。
題名:Hattrick
読み:ハットトリック
邦題:ハットトリック
監督:ミラン・ルトリヤー
制作:ロニー・スクリューワーラー
音楽:プリータム、ラージェーシュ・ローシャン
出演:ナーナー・パーテーカル、クナール・カプール、リーミー・セーン、パレーシュ・ラーワル、ダニー・デンゾンパ、ハルシャ・ボーグレー(特別出演)、ジョン・アブラハム(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段、リーミー・セーン(左)とクナール・カプール(右)
中段、ナーナー・パーテーカル(左)とダニー・デンゾンパ(右)
下段、パレーシュ・ラーワル
| あらすじ |
サルブジート・スィン、通称サビー(クナール・カプール)はクリケット狂の若者。カシュミラー(リーミー・セーン)と結婚した後も、クリケットのことばかり考えていた。困ったカシュミラーは友人に相談する。友人は、夫と一緒にクリケットを観戦すればいいと助言する。クリケットを見だしたカシュミラーは、マヘーンドラ・スィン・ドーニー選手に一目惚れしてしまう。一方、カシュミラーが熱狂的ドーニー・ファンになってしまったことに気を悪くしたサビーは、急にクリケットが嫌いになる。
サティヤジト・チャヴァン(ナーナー・パーテーカル)は、公共病院に勤めるくそ真面目な医者であった。彼は決して笑顔を見せることがなかった。病院に、元人気クリケット選手のデーヴィッド・アブラハム(ダニー・デンゾンパ)が腎臓疾患で入院して来る。病院中はパニックになるが、クリケット嫌いのサティヤジトは全く動じない。デーヴィッドはサティヤジトに、ワールドカップ観戦のためにTVを用意してくれと頼む。最初は頑として受け付けなかったサティヤジトだったが、クリケットを見れば病気が治るという彼の挑戦を受け、彼の個室にTVを入れる。
ヘームー・パテール(パレーシュ・ラーワル)はロンドン在住のインド人。12年間、英国の国籍を取得するために奮闘していた。彼は英国を愛していることを移民局に知らしめるためにありとあらゆる手段をとるが、娘は父親のそういう卑屈な態度を嫌っていた。ヘームーは空港で掃除人として働いていたが、仲間内では税関に勤めていると嘘を付いていた。彼は白人のインド人に対する差別に腹を立てながらも、白人のウェイターを罵り、黒人を見下す態度を取っていた。
とうとうサビーとカシュミラーは別居状態となってしまう。だが、サビーは家族に説教され、カシュミラーを少しも気遣っていなかった自分に気付く。サビーは、カシュミラーたちが結婚する友人の独身最後の日を祝うバチャラーズパーティーにストリッパーとして乱入し、カシュミラーに許しを乞う。
デーヴィッドはすぐに腎臓移植手術を行わなければ命が危なかった。だが、デーヴィッドはワールドカップ決勝戦を見てからでないと手術はしないと言い張る。そこでサティヤジトは、決勝戦をでっち上げてデーヴィッドを騙そうとする。作戦は成功し、デーヴィッドは手術を受ける。手術のおかげでデーヴィッドは快方に向かうが、実は彼は自分が見た決勝戦はでっち上げであることに気付いていた。
ヘームー・パテールは移民局で面接を受ける。だが、どうも結果は思わしくなさそうだった。彼は必死に官吏に泣き付くが、無駄であった。絶望したヘームーは仕事を1週間もさぼった。また、娘が黒人と付き合っていることを知って激怒し、家族崩壊の危機に直面する。友人たちも、ヘームーが実は空港で掃除人をしていることを知ってしまう。全てが思い通りに行かなくなったヘームーは自殺も考えるが、国籍取得審査の結果を聞きに行く。そうしたら何と合格していた。ヘームーは晴れて英国人になることができた。だが、なぜか心は軽くならなかった。必死にクリケットのインド代表を応援していた自分の姿が思い出された。家に帰ると、国籍取得に成功したことを事前に知っていた家族、友人、同僚たちがサプライズ・パーティーを用意していた。ヘームーは皆の温情に涙する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
3つのストーリーはほとんど相互に関与せずに進んで行く。クリケットでひとつにまとまっているように見えるのだが、よく見るとそういう訳でもない。特にヘームー・パテールのストーリーはそれほどクリケットと関わっていなかった。だが、それぞれに特色があり、佳作と呼べる作品になっていた。
サビーとカシュミラーのストーリーは最もありがちなものだろう。カシュミラーは甘い新婚生活を夢見ていたが、クリケット狂のサビーは妻のことなどお構いなしに毎日クリケットの試合を観戦する。友人は困ったカシュミラーに助言する。「そんなの簡単よ。あなたも一緒にクリケットを見ればいいのよ。試合じゃなくて選手を見るの。女の子はみんな、イケメン選手を見るためにクリケットを見てるのよ。」試しに夫とクリケットを観戦してみるカシュミラー。もちろんサビーは大喜び。だが、そんなカシュミラーの目に飛び込んで来たのは・・・インドチームの新大砲、マヘーンドラ・スィン・ドーニーであった!そのときからカシュミラーの頭の中ではドーニードーニードーニー・・・という声が四六時中響き渡るようになる。それに気付いたサビーは、逆にクリケット大嫌いになってしまうのであった。
多少非現実的だが、話として一番映画的にまとまっていたのは、サティヤジトとデーヴィッド・アブラハムのストーリーだった。デーヴィッドは、インド人なら誰でも知っているほど超有名な元クリケット選手であった。だが、クリケット嫌いのサティヤジトは彼の名前すら聞いたことがなかった。決して笑顔を見せないサティヤジトに対し、デーヴィッドは2つの要望を出す。ひとつはクリケットを観戦するためのTV、もうひとつは彼の笑顔であった。デーヴィッドは腎臓移植手術をしないと命が危なかったが、ワールドカップ決勝戦を見るまで手術はしないと言い張る。そこでサティヤジトは一計を案じ、決勝戦(インド対英国)の試合を偽造し、デーヴィッドに見せる。試合は見事インドの優勝!だが、元クリケット選手のデーヴィッドにとって、そんなあさはかな偽造を見破るのはお手の物であった。それでも彼はその騙しに乗り、試合を見終えた後に手術を許可する。手術が終わった後、彼はサティヤジトに、騙しであることを見破っていたと明かす。なぜ分かっていながら騙しに乗ったのか、との質問に対しデーヴィッドは、「クリケットも大事だが、お前の笑顔を見てみたかったんだ」と答える。
最も弱かったのはヘームー・パテールのストーリーだ。クリケットと直接関係なかった上に、終わり方の詰めが甘かった。ヘームー・パテールは、英国国籍取得を夢に12年間、空港の掃除人という彼にとっては屈辱的な仕事をして来た。家の壁にエリザベス女王のポスターを貼ったり、英国コスチュームを着たりして何とか英国愛を創出するが、その卑屈な態度が彼の人生を狂わして行く。だが、最終的に彼は英国国籍を取得する。すっかり諦めていたヘームーは呆然とする。家に帰る間、なぜか思い起こされるのは自分の心の奥底にこびりついているインド人としてのアイデンティティーであった。ここで英国国籍取得をキャンセルするという筋にしておけばよかったと思うが、結局最後はなぜか家でサプライズ・パーティーが準備されており、ヘームーが感動の言葉を述べて終了、といういい加減なエンディングになっていた。
ミラン・ルトリヤー監督は、「Taxi No. 9211」(2006年)の監督。エンドロール・ナンバー「Wicket Bacha」で映画のキャストと共にジョン・アブラハムが特別出演していたが、これは「Taxi
No. 9211」つながりだろう。同作品ではナーナー・パーテーカルとジョン・アブラハムが共演しており、エンドロール・ナンバー「Meter Down」で2人で粋な踊りを踊っていたが、「Hattrick」の「Wicket
Bacha」はその続編みたいな感じになっていた。
やはりインド映画界随一の曲者俳優ナーナー・パーテーカルが熱い。笑顔を決して見せない医者、というのは打ってつけの役だ。陽気なダニー・デンゾンパとのコントラストもよかった。コメディーをやらせたら右に出る者はいないパレーシュ・ラーワルは、今回は比較的シリアルな役に挑戦。しかし、シリアスな中にも滑稽さがにじみ出ているのは彼の持ち前の才能であろう。クナール・カプールは「Rang
De Basanti」(2006年)でブレイクした男優。あのときのままの髪型とヒゲで登場。彼はこのまましばらくこのスタイルを踏襲するのであろうか。モジャモジャッとした外見の割には甘い笑顔で、そのアンバランスさが人気を呼びそうだ。若手の中では注目していい男優である。ヒロインのリーミー・セーンは可もなく不可もなくといった感じであった。
ところで、僕が見ていたときに上映事故が発生した。明らかに序盤のシーンが、終盤に突然挿入されていたのだ。どうりで前半はストーリーが掴みにくかったはずである。おそらくリールの順番を間違えてしまったのだろうが、PVRのような高級映画館でこういうことがあるのは残念である。
クリケットのワールドカップ期間中は、さすがのボリウッドもクリケットに観客を取られて苦戦する傾向にある。敢えてこの期間に、クリケットを題材にした映画をぶつけるのは新たな試みだ。インドチームの応援映画的要素もふんだんに盛り込まれていた。興行収入が気になるところである。
デリーにはユネスコ世界遺産が2つある。デリー中部にあるフマーユーン廟とデリー南部にあるクトゥブ・ミーナールである。面白いことに、これら2つの世界遺産の近くには、有名なイスラーム聖者の廟がある。フマーユーン廟の近くにはハズラト・ニザームッディーン・アウリヤーの廟が、クトゥブ・ミーナールの近くにはクトゥブッディーン・バクティヤール・カーキーの廟があるのである。そして、それらの世界遺産がそこにある理由も、これらの聖者廟が深く関係している。ニザームッディーン廟は比較的有名だが、メヘラウリーにあるクトゥブッディーン廟は少し知名度が落ちるだろう。だが、どちらもデリーで最も重要な聖者廟である。また、クトゥブ・ミーナールの名前の由来を時々「勝利の塔」だとか、「奴隷王朝創始者クトゥブッディーン・アイバクが建てたからそう名付けられた」などと解説している文章を見るが、それらは誤りである。クトゥブ・ミーナールの「クトゥブ」の意味はそもそも「北極星」であるし、クトゥブッディーン・アイバクによって建造されたから名付けられたわけでもない。聖者クトゥブッディーンの名から取って付けられたのである。今日は、クトゥブッディーン廟を訪れてみた。
カージャー・クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー、通称クトゥブ・サーヒブは、北インドに初めてイスラーム政権が樹立した12世紀末~13世紀初めにデリーに住んでいた聖者である。元々ペルシアのウシュで生まれたクトゥブ・サーヒブは、アジメールの有名な聖者カージャー・モイーヌッディーン・チシュティーの一番弟子となった。カーキーと呼ばれるのは、瞑想中「カーク」と呼ばれる食べ物しか食べなかったからである。クトゥブ・サーヒブは1236年に没するが、その名声は死後ますます高まり、デリーを支配した歴代の皇帝もクトゥブ・サーヒブに特別な敬意を表していた。奴隷王朝を樹立したクトゥブッディーン・アイバクは彼の名を取ってクトゥブ・ミーナールを建てたし、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルはクトゥブッディーン廟のすぐ近くに自分の廟を建造した。あのマハートマー・ガーンディーも暗殺の数日前にクトゥブ・サーヒブを参拝した。当然、クトゥブ・サーヒブの信仰は今でも全く衰えていない。モイーヌッディーン・チシュティーが、アジメールに来る参拝者はまずクトゥブッディーンの祝福を受けるべし、と宣言したため、アジメールのチシュティー廟を訪れる巡礼者はまずデリーのクトゥブッディーン廟を詣でる慣わしになっている。また、ハジ(メッカ巡礼)から戻った人々もクトゥブッディーン廟を訪れる。つまり、クトゥブ・サーヒブは生前から死後にかけて、実に800年以上に渡ってデリーの人々から宗教関係なく信仰を集めている強力な聖人であり、彼の廟はデリーで最も古いイスラーム聖者廟なのである。さらに、信者たちはクトゥブ・サーヒブは死んでおらず、今でも生きていると信じている。クトゥブ・サーヒブは、透明になるマントをかぶっただけであり、神様と祝福された者のみが彼の姿を見ることができるという。そして、デリーが何度も徹底的に破壊されながらもその都度再生しているのは、クトゥブ・サーヒブの霊力のおかげだと考えられている。
クトゥブッディーン廟はメヘラウリーの住宅地のど真ん中にある。目立つ目印などはないので、普通にメインロードを通っていたのでは見過ごしてしまうだろう。最も容易なのは、メヘラウリーのバススタンドやアドハム・カーン廟(別名ブール・ブライヤーン)のある辺りから、人に道を尋ねつつ行く方法である。クトゥブッディーン廟にはいくつか入り口があるが、北から入るのが最も一般的だと思われる。花などのお供え物を売る店が軒を連ねており、靴を預ける場所もたくさんある(EICHER「Delhi
City Map」P142 G3)。

クトゥブッディーン廟の入り口
クトゥブッディーン廟は、本人の廟を中心として、信者の墓廟、モスク、ミーナール(塔)、ムガル朝皇帝が建てた宮殿などで成り立つコンプレックスとなっている。クトゥブ・サーヒブの廟の四方は壁で囲まれており、男性のみ中に入ることができる。女性はスクリーン越しに礼拝を行う。現在では立派な廟になっているが、元々は土で出来た質素なものだったらしい。現存しているドーム屋根の建物は、1944年建造で古くはない。

クトゥブ・サーヒブ

女性はスクリーン越しに礼拝
クトゥブッディーン廟の敷地内にはミーナールが立っているが、高くないのでランドマークにはなっていない。これも古いものではなく、最近立てられたもので、これからゆっくり増築されていきそうな雰囲気であった。

ミーナール
また、ミーナールの近くにはバーオリー(井戸)もあったが、現在ではゴミ捨て場のようになってしまっていた。聖者の力を持ってしてもインド人のポイ捨てを止めることはできなかったということか・・・。

バーオリー
クトゥブッディーン廟の西側には、ザファル・マハルと呼ばれる宮殿が残っている。宮殿自体は、ムガル朝末期の皇帝アクバル2世(在位1806-37年)が建造したものであるが、その赤砂岩と白大理石で出来た門はムガル朝のラスト・エンペラー、バハードゥル・シャー・ザファル(在位1837-57年)が建て直したものであるため、そう呼ばれている。雨季が終わるとザファルはこの宮殿に移り、8月~9月に祝われるプールワーローン・キ・サイル祭を鑑賞したと言われる。この宮殿の敷地内には、ムガル朝末期の皇帝やその家族の墓がいくつか並んでいる。バハードゥル・シャー1世(在位1707-12年)、シャー・アーラム2世(在位1759-1806年)、アクバル2世などである。ムガル朝末期の皇帝の墓がここに集中しているのは、彼らがクトゥブ・サーヒブの熱心な信者だったこともあるのだが、政治的理由からアジメールのチシュティー廟への参拝が困難になったこともあるらしい。

ザファル・マハルの門(左)と、門から眺めたクトゥブ・サーヒブ(右)
バハードゥル・シャー・ザファルも生前に自分の墓をここに作ったのだが、彼はインド大反乱の首謀者の1人としてラングーン(現ミャンマーのヤンゴン)に流刑となり、そこで没し、そこで埋葬されたため、使われずにそのまま残っている。ウルドゥー詩人でもあったザファルが詠んだ以下の詩はあまりに有名である。
ہے کتنا بدنصیب ظفر دفن کے لئے
دو گز زمین بھی نہ ملی کو یار مین
Hai Kitnā Badnasīb Zafar Dafan Ke Liye
Dō Gaz Zamīn Bhī Na Milī Kū-e-Yār Men
ザファルよ、お前は何と不幸なのか、墓のために
愛する土地に2ガズ(約180cm)の土地すら得られないとは
ザファルがこの詩で詠んだ「کو یار(直訳すると「愛する人の路地」)」とは、クトゥブッディーン廟のあるメヘラウリーの狭い路地のことを言ったのであろう。

ザファルが埋められる予定だった場所(左)と、
クトゥブッディーン廟前の路地(右)
ザファル・マハルの中には自由に入れるようになっており、近所の子供たちの遊び場となっていた。クリケット・ワールドカップが行われている昨今、ここでは伝統的なグッリー・ダンダー(棒で球を打って遊ぶ遊び)が遊ばれていた。また、門の前のちょっとしたスペースでは、近所の老人たちがトランプゲームに興じていた。
| ◆ |
3月23日(金) Namastey London |
◆ |
カリブ海の西インド諸島で開催中のクリケット・ワールドカップ。本日インドはスリランカと重要な一戦を行う。もし敗北したら、インドは屈辱的な予選敗退となる。既にパーキスターンの予選敗退が決定しており、今年は伝統の印パ戦は見られない。それだけでも残念なのだが、インドが決勝トーナメント進出に失敗すると、ワールドカップの楽しみは無になってしまう。そればかりか、パーキスターン代表のコーチが変死しており、かなりきな臭い状況となっている。どうなってしまうのだろうか?
そんなインド人にとって重要な日である本日、映画館に新作ヒンディー語映画「Namastey London」を見に出掛けた。正午の回であったにも関わらず、意外にも映画館は観客で溢れており、盛り上がりも上々であった。
題名:Namastey London
読み:ナマステー・ロンドン
意味:こんにちは、ロンドン
邦題:ナマステー・ロンドン
監督:ヴィプル・アムルトラール・シャー
制作:ヴィプル・アムルトラール・シャー
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー
作詞:ジャーヴェード・アクタル
振付:サロージ・カーン、アシュレー・ロボ、ラージーヴ・スルティー、ポニー・ヴァルマー
出演:リシ・カプール、アクシャイ・クマール、カトリーナ・カイフ、ウペーン・パテール、ジャーヴェード・シェーク、クライド・ステンデン、ワーディヤー、リテーシュ・デーシュムク(特別出演)、チャールズ英皇太子(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

カトリーナ・カイフ(左)とアクシャイ・クマール(右)
| あらすじ |
ジャスミート(カトリーナ・カイフ)はロンドンで生まれ育ったインド系英国人の女の子であった。彼女は自分をインド人とは考えておらず、ジャズと名乗っていた。パンジャーブ出身でロンドンで衣料品店を経営する父親のマンモーハン(リシ・カプール)は、インド人としてのアイデンティティーを拒否する娘の言動に不安を抱いていた。また、マンモーハンの親友でパーキスターン人のパルヴェーズ・カーン(ジャーヴェード・シェーク)も同じ世代間ギャップに悩んでいた。息子のイムラーン(ウペーン・パテール)が英国人と結婚しようとしていたからである。
ある日マンモーハンはジャズを連れてインドへ行く。名目はインド観光であったが、真の目的はジャズの婿探しであった。何人かの婿候補とお見合いをした後、マンモーハンは故郷のパンジャーブで親友の息子アルジュン・スィン(アクシャイ・クマール)を最適の婿だと判断する。アルジュン・スィンもジャズに一目惚れであった。だが、ジャズは違うことを考えていた。インドで結婚式を挙げたとしても、英国では無効だと考えたジャズは、面倒を避けるためアルジュンとインドで結婚式を挙げる。アルジュンはジャズと共にロンドンへ行くが、そこでジャズは、自分は英国では独身だと宣言する。また、ジャズには英国人の恋人チャーリー・ブラウン(クライド・ステンデン)がおり、彼と結婚すると言い出す。ショックを受けたマンモーハンは酒びたりになってしまうが、アルジュンは諦めなかった。彼はジャズの軽薄な行動に少しも抗議せず、ただ愛を示し続ける。
最初はアルジュンを英語もできないただの田舎者と馬鹿にしていたジャズであったが、アルジュンの誠意ある行動とインド人としての誇りに次第に心を動かされる。一方、チャーリーはインド人を馬鹿にする言動を何度かするようになり、ジャズの気持ちは変化する。
チャーリーとジャズの結婚式が教会で行われようとしていた。アルジュンはジャズを教会まで送って行き、2人に「結婚おめでとう」と流暢な英語で声を掛け、去って行く。いざ神父から結婚の誓いを促されると、ジャズは沈黙の後に「ノー」と答え、教会から逃げ出し、アルジュンを追いかける。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
ロンドンを舞台にしているものの、テーマは「結婚」という伝統的なインド映画。男の方が一度結婚した自分の妻の心を勝ち取るという筋は、「Hum Dil
De Chuke Sanam」(1999年;邦題「ミモラ」)そのもので、「結婚後の恋愛は結婚が勝つ」というインド映画の法則を地で行く映画だが、ポスト・アイシュワリヤーの有力候補、カトリーナ・カイフのステップアップのための映画として価値のある作品であった。
英国人とインド人(カシュミール人)のハーフで、美しさとかわいさを見事に兼ね備えたスーパーモデル、カトリーナ・カイフは、「Boom」(2003年)でボリウッド・デビューを果たした後、数本のインド映画に出演して来た。しかしながら、英国育ちのカトリーナはヒンディー語が苦手で、今まで別人の吹き替えで対応して来た。だが、この「Namastey
London」で彼女は初めて自身の声で出演している。当然、セリフにはヒンディー語も多用されているし、パンジャービー語も含まれている。英語はともかく、インドの言語はまだ流暢とは言えないレベルだが、カトリーナ・カイフの「完全デビュー」として歓迎すべき一作品と言えるだろう。アイシュワリヤー・ラーイのボリウッド引退が噂されている中、インド映画界はアイシュワリヤーに代わる「女神」を早急に求める必要に迫られている。プリヤンカー・チョープラーがその筆頭だが、カトリーナ・カイフもその有力候補だと言える。何しろ、アイシュワリヤーと付き合っていた過去のあるサルマーン・カーンが、新しい恋人に選んだのがカトリーナである。今のところほとんど外見のみで女優をしているカトリーナであるが、かつてのアイシュワリヤーも同じようなものだった。ただ、カトリーナにはひとつアイシュワリヤーにはない大きな魅力がある。笑顔よりもどちらかというとすまし顔の方が魅力的な、非人間的美しさを持ったアイシュワリヤーに対し、カトリーナは笑顔がとても魅力的なのである。「Namastey
London」でも、その笑顔で観客の心を惹き付けていた。カトリーナ・カイフは、今、成長が最も楽しみな女優である。
しかし、「Namastey London」の中で彼女が演じたジャズの役は、全く感情移入できるキャラではなかった。アルジュンと結婚をし、彼をロンドンまで連れて来ながら、「インドでの結婚は無効」と言い渡す様は、あまりに自分勝手で思いやりがなかった。土壇場で彼女はアルジュンを選ぶが、それも婚約者のチャーリーの気持ちを考えないやり方であった。アルジュンがジャズの心を勝ち取ったと受け取ればハッピー・エンディングであったが、結局ジャズの身勝手な行動で周囲が迷惑を被っただけの映画になってしまっていたことは否定できない。
アクシャイ・クマール演じるアルジュンのキャラも中途半端であった。パンジャーブの片田舎で生まれ育った生粋のパンジャービーという設定で、その彼とロンドン育ちのジャズとのギャップがこの映画の核だったはずだが、ロンドンに来た途端、アルジュンは全く田舎っぽくなくなってしまい、最後には急に流暢な英語を話し出して、実はインテリな男だったことが判明する。この展開は脚本の破綻と言っていいだろう。
リシ・カプールや、パーキスターン人俳優ジャーヴェード・シェークなど、脇役陣は堅実な演技をしていた。期待の若手男優の1人、ウペーン・パテールもいい感じだった。また、英国人俳優も多く登場していた。冒頭ではリテーシュ・デーシュムクが特別出演する。
映画中では、英国における人種摩擦がかなりクローズアップされていた。インド人に対する英国人の差別もあったし、同時に英国人に対するインド人の差別的視点も描かれていた。英国人チャーリーと結婚しようとするジャズに対し、父親のマンモーハンは激怒するし、パーキスターン系英国人イムラーン・カーンと英国人女性の結婚でも、双方の両親はお互いに対する差別的感情を露にしていた。特に女性の両親はイムラーンに対し、テロリストが親縁者にいないことを証明することと、キリスト教への改宗と改名を結婚の条件に出していた。
さらに、英国東インド会社の官僚を祖父に持つ英国人老人のインド差別もあった。チャーリーとジャズの婚約発表パーティーにおいて、その老人はインドのことを「蛇使いの国」と表現し、インド人と結婚しようとするチャーリーを暗に嘲笑していた。だが、それを聞いたアルジュンはインドの素晴らしさ、偉大さをとうとうとヒンディー語で演説し、老人の言葉を失わせる。インド人には爽快な1シーンだったことだろう。
音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。「Namastey London」のサントラは、やはりヒメーシュらしさが出た一作となっており、彼の歌う「Chakna
Chakna」、「Viraaniya」、「Yahi Hota Pyaar」などは「これぞヒメーシュ!」という音楽である。ただ、「Namastey
London」の中で最も優れた曲はラーハト・ファテー・アリー・ハーンの歌う「Main Jahaan Rahoon」であろう。
言語は基本的にヒンディー語だが、英語のセリフが非常に多用される。この映画ではなんと英語セリフのシーンでヒンディー語字幕が入る。英語のセリフが多用されるシーンで、英語の分からない観客のためにヒンディー語のナレーションが入ることは、「Lagaan」(2001年)など、今まで数例あったが、ヒンディー語字幕が入った映画は初めて見たかもしれない。ただ、字幕の転換が早過ぎて読んでいられない。また、インドではまだまだ文字の読めない人が多いし、ヒンディー語圏外の観客のためにもなっていない。ヒンディー語字幕は普及しないと思われる。その他、パンジャービー語のセリフがちらほら見受けられた。
また、どういうコネで実現したのか分からないが、映画中にはチャールズ皇太子が出演している。インド映画に英国王室の王族が生出演したのは初めてのことかもしれない。
「Namastey London」は、外見はオシャレな感じだが、中身は伝統的な方程式に則った典型的インド映画と言っていいだろう。カトリーナ・カイフの美貌とヒメーシュ・レーシャミヤーの音楽が最大のセールスポイントだ。
| ◆ |
3月25日(日) ブラフマプトラ寮ホステルナイト |
◆ |
ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)は俗に言うレジデンシャル・ユニバーシティーで、キャンパスはひとつの生活共同体となっている。学生も教授も職員もほとんどの人がキャンパス内に住んでおり、課外交流も活発である。キャンパスは大まかに、教育研究の場である中心部を除けば、ウッタラーカンド(北ブロック)、パシュチマーバード(西ブロック)、ダクシナプラム(南ブロック)、プールヴァーンチャル(東ブロック)に分かれており、それぞれ居住区域となっている。その名付け方も面白い。ウッタラーカンドはヒマーラヤ地方風の名称、パシュチマーバードはイスラーム的名称、ダクシナプラムは南インド風名称、プールヴァーンチャルはビハール地方風名称であり、インド文化の多様性を密かに主張している。現在、学生寮は15前後あり、それらはインド各地の河の名前が付けられている。
デリー在住の学生や、寮での生活を好まない学生はキャンパス外に住んで通学することもできる。このような学生は「デー・スカラー(Day Scholar)」と呼ばれる。僕も当初はキャンパス外に住んでいたため、デー・スカラーであった。だが、大半の学生はどこかの寮に住んでおり、寮住まいを前提にいろいろな物事が進んで行くため、デー・スカラーは時々肩身が狭い。例えば、初対面の学生は必ず「どこの寮に住んでる?」と質問し合う。そのときにデー・スカラーだとちょっと悲しい気分になるのである。しかも外国人なので、キャンパス外に住んでいると、何だか一般の学生たちと一線を引いてお高くとまっているような印象を持たれるような被害妄想もあった。キャンパス内で催される各種イベントも、寮に住んでいなければ参加しにくかったり情報すら入ってこなかったりして、デー・スカラーには不利である。そのような理由から、以前から寮生活に憧れていた。去年の8月から僕はブラフマプトラ寮に住み始めた。
ブラフマプトラ寮は、他の学生寮と比べて少し特殊である。まず、この寮に住む資格があるのは、M.Phil.(博士課程中期)またはPh.D.(博士課程後期)の男子学生のみである。つまり、B.A.(学士課程)やM.A.(修士課程/博士課程前期)の学生は入寮できない。また、外国人留学生には優先的に割り振られるものの、一般のインド人学生は、一定期間、他の通常の寮に住まなければ、ブラフマプトラ寮への入寮資格は得られない。ブラフマプトラ寮の最大の特徴は、全ての部屋が一人部屋であることだ。JNUの学生寮は基本的に相部屋となっているが、ブラフマプトラ寮は全て一人部屋である。他に全一人部屋の寮は、女子寮であるヤムナー寮だけである。さらに、ブラフマプトラ寮は他の寮に比べて離れた場所にあるため、静かな環境の中住めることも魅力である。
JNUの各寮では3月頃にホステルナイトという寮祭が催される。本日はブラフマプトラ寮のホステルナイト最終日であった。ホステルナイトは数日に渡って祝われ、23日にはステージショーなども行われていたが、最も盛り上がるのは最終日のイベントである。イベントと言っても、やることは食べることと踊ることしかないのだが、なかなかどうしてみんなここぞとばかりに派手に着飾り、親しい友人を招待し、一緒に弾けるのである。ブラフマプトラ寮の寮生は年齢層が高く落ち着いた雰囲気のある人が多いので、ホステルナイトもそんなに盛り上がらないだろうと予想していたが、他の寮に比べても遜色のない盛大なイベントになっていた。学生だけでなく、プールヴァーンチャルに住む教授たちの家族も遊びに来たりしており、寮祭というよりもプールヴァーンチャルの祭りという感じがした。
まずは「食」のイベント。寮の外に結婚式会場のような幕が張られ、午後8時頃から徐々に人が集まるようになった。やがて入り口には長蛇の列が出来るようになり、会場に入るのに30分以上並ばないといけないような混雑ぶりになった。業者の影響であろう、会場は正に結婚式会場である。新郎新婦のいない結婚式といった感じだ。インドのお約束に従い、料理はヴェジとノンヴェジに分かれている。ノンヴェジは、タンドゥーリー・チキンとマトン・カレーであった。他に、ダヒー・バラー、ダール、ライス、グラーブ・ジャームン、アイスクリームなどが共通メニューになっていた。普段、メス(寮の食堂)の料理を食べているインド人学生にとって、ホステルナイトの料理はご馳走なのである。

おいしそうに食事をする人々
午後11時過ぎくらいから次第に会場は寮内の食堂ホールへ移動する。食堂ホールにはスピーカーや照明器具が設置され、臨時のダンスホールへ変貌していた。最初は子供が2、3人踊っていただけだが、ふと目を離したすきにダンスホールは踊り狂う学生たちとその熱気で埋まっていた。流れる音楽はもちろんボリウッドのヒットソングやパンジャービー・ソング!たまに西洋の音楽も流れるが、盛り上がるのはやっぱり「デーシー(国産)」ミュージックである。
ところで、先日日本に帰った折に新しいデジカメを購入したため、隣の部屋に住んでいるオリッサ出身のゴーパール君に古いデジカメを破格の値段で売ってあげたのだが、それ以来彼はまるで新しい玩具を与えられた子供のようにデジカメを持ち歩き、事あるごとに写真を撮りまくる写真魔となってしまった。ホステルナイトでも彼は写真を撮りまくった!ダンスホールでみんなが踊り狂っている中でもシャッターを切りまくった!インド人の学生がどんなことをして楽しんでいるのか、日本に住んでいる人にはなかなか分からないと思うので、ゴーパール君が撮った数々のスナップ写真の一部を公開しようと思う。実は上の食事中の写真もゴーパール君が撮ったものだ。

踊れ踊れっ!

あ~ら、よ~いよいっと

ハレ~クリシュナ~

女も負けちゃいないわよ

震源地はここでした

ガーリブ通ります

あつあつの2人

バッレ~バッレ~

ふ~一休み

サルマ~ン

ゴーパール・ダンスを見よ!
(右がゴーパール君です)

英印再合併
インド人たちと踊っていていつも非常に不思議に思うのは、僕がこれだけ真面目に最新サントラCDを買い集めて一生懸命聴いているのにも関わらず、彼らの音楽の知識が僕を遥かに上回っていることである。オールディーズの知識においてかなわないのは年季が違うので仕方ないが、21世紀以降の音楽もやっぱりみんなよく知っていて、イントロが流れた途端にみんな察知して歌いながら踊り出すのである。普段、映画なんてあまり興味なさそうな人でも、踊り出すとあら不思議、最新ヒット曲を実によく抑えているのである。また、寮にはデリー以外の地方からの学生が多いのだが、パンジャービー・ソングの人気が意外にも根強いのも気になる点である。やはりあの独特のシャッフル感は全インド人を熱狂させるだけのスパイスを持っているということなのだろうか?そしてやっぱり彼らはパンジャービー・ソングもしっかり抑えているのだ。僕はディープなパンジャービー・ソングになると全く付いていけないのだが、彼らは知っているのか知らないけどとにかく踊っているのか、やっぱりノリノリで踊る。本当に不思議な民族だ。そして何より不思議なのは、ほとんどの人がアルコールなどの力を借りず、シラフで踊り狂っていることである。
ボリウッド・ファンとしては、ディスコタイムに流れる曲目はいちいち気になるものだ。やはり2006年のヒット曲からの選曲が多かった。「Rang
De Basanti」からは「Rang De Basanti」や「Paathshala」、「Aksar」からは「Jhalak」、「Gangster」からは「Ya
Ali」、「Krrish」からは「Dil Na Diya」、「Omkara」からは「Beedi」と「Namak」、「Kabhi Alvida
Naa Kehna」からは「Where's The Party Tonight」、「Woh Lamhe」からは「Kya Mujhe Pyaar
Hai」、「Dhoom:2」からは「Dhoom Again」、「Don」からは「Ye Mera Dil」などなど。同じく「Don」の「Khaike
Paan Banaras Wala」は、新旧両方を流すという粋な計らいがあった。インド人が大好きな曲のひとつだ。
とりあえず2007年の映画音楽の中では、「Honeymoon Travel Pvt. Ltd.」の「Sajanji Vaari Vaari」が自分の中では大ヒットだ。映画中でケー・ケー・メーナンが踊ったようなハチャメチャな踊りをすると受けまくりである。
過去のヒット曲も根強い人気であった。確認できた中では、「Hum Dil De Chuke Sanam」の「Dholi Taro Dhol Baaje」、「Dil
Chahta Hai」の「Koi Kahe Kehta Rahe」、「Kal Ho Naa Ho」の「It's The Time To Disco」、「Khaaki」の「Aisa
Jaado」、「Mujhse Shaadi Karogi」の「Mujhse Shaadi Karogi」、「Bunty Aur Bubli」の「Kajra
Re」、「Dus」の「Dus Bahaane」と「Deedar De」、「Maine Pyaar Kyun Kiya」の「Just Chill」、「No
Entry」の「Ishq Ki Gali Vich」、「Salaam Namaste」の「Salaam Namaste」などが流れた。
宴は深夜2時半まで続いた。そのときにはもう僕はシャワーを浴びて寝ていたのだが、どうやら最後に乱闘騒ぎがあって警察沙汰にもなったようだった。こうしてブラフマプトラ寮の夜は更けて行った・・・。
| ◆ |
3月28日(水) The Namesake |
◆ |
世界的に有名なインド系女性映画監督であるミーラー・ナーイル監督の最新作「The Namesake」。インド系米国人女性で、ピューリツァー賞受賞作家のジュンパー・ラーヒリーの同名小説を原作にした映画である。原作は日本でも「その名にちなんで」という邦題で翻訳出版されている。「The Namesake」は米国で3月9日に公開され、高い評価を受けている。インドでは1週間遅れて3月23日に公開された。インドでも都市部を中心にヒットとなっており、デリーの映画館ではチケット入手が困難となっている。今日は苦労して夜の回のチケットを入手し、鑑賞することができた。
題名:The Namesake
読み:ザ・ネームセイク
意味:名をもらった人
邦題:その名にちなんで
監督:ミーラー・ナーイル
制作:ミーラー・ナーイル、リディア・ディーン・ピルチャー
原作:ジュンパー・ラーヒリー
音楽:ニティン・サーウニー
出演:カール・ペン、タッブー、イルファーン・カーン、サヒラー・ナーイル、ジャシンダ・バレット、ズレイカー・ロビンソン
備考:PVRアヌパムで鑑賞。
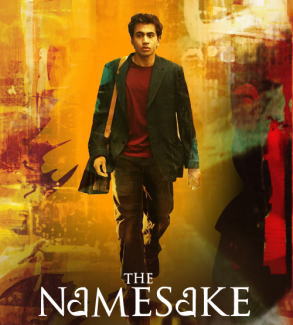
カール・ペン
| あらすじ |
カルカッタの伝統的なベンガル人家庭に生まれ育ったアシーマー(タッブー)は、米国在住のベンガル人アショーク・ガーングリー(イルファーン・カーン)と結婚し、ニューヨークに移住する。彼女にとって、住み慣れたカルカッタと違い、ニューヨークは全く孤独の地であった。やがて2人の間には長男と長女が生まれる。ゆっくりと名前を付けようと思っていたアショークであったが、米国では出生後すぐに名前を届け出ねばならず、ふと思い付いたロシアの文豪の名前ゴーゴル(ゴーゴリ)を長男の名前にする。一方、長女はソニアと名付けられた。
月日は流れ去った。ゴーゴルとソニアはニューヨークの文化の影響を受けて育った。特にゴーゴルは自分のヘンテコな名前を気に入っていなかった。ゴーゴルは、インド旅行をきっかけに建築に興味を持つようになり、建築家への道を進んでイエールに住み始める。また、彼は名前をニキルに改名する。
ニキルにはマクシーン(ジャシンダ・バレット)という米国人のガールフレンドができ、両親にも紹介する。そのときアショークはオハイオへ単身赴任しようとしていた。出立を前にアショークはニキルに、ゴーゴルと名付けた本当の理由を話す。
アショークが学生の頃、列車に乗って父親に会いにカルカッタからジャムシェードプルへ向かっていた。そのとき読んでいたのがゴーゴリの短編集であった。同じコンパートメントに乗ったおじさんに、彼は世界へ出ていろんな経験を積むように諭される。だがそのときその列車は事故に遭ってしまう。生存者がほとんどいない大事故であったが、アショークはゴーゴリの本を握り締めて振っていたために発見され、一命を取り留める。そのことがあってから、アショークは海外へ移住し、息子にゴーゴルと名付けたのであった。
アショークはアシーマーに見送られてオハイオに旅立った。だが、その先で彼は急死してしまう。父親の訃報を聞いたニキルは、ヒンドゥー教の伝統に従って頭を丸め、ニューヨークに戻って来る。マクシーンも葬儀に参列するが、ニキルは全く人が変わってしまっていた。ニキルとマクシーンは破局する。アシーマーとニキルは、アショークの遺灰を河に流すためにカルカッタへ行って来る。
喪も明けた頃、アシーマーはニキルに縁談を持ちかける。相手はかつてお見合いをしたことがあったマウシュミー(ズレイカー・ロビンソン)であった。当時は気色の悪い女の子であったが、いつの間にか色気のある女性になっていた。ニキルはマウシュミーと結婚することを決める。また、兄に続いて妹のソニアも婚約する。
2人の子供が身を固めたのを見届けたアシーマーは、家を売ってカルカッタへ帰ることを決意する。彼女は最後に親しい友人を招いてパーティーを開く。だがそのとき、マウシュミーが結婚後も元恋人のフランス人と付き合っていたことが発覚する。それを知ったアシーマーはカルカッタへ帰ることをためらうが、ニキルは母親を送り出す。また、ニキルはかつて父親からプレゼントされたゴーゴリの短編集を見つけ、そこに書かれていた父親のメッセージを見つける。
カルカッタに戻ったアシーマーは、結婚前に習っていた声楽の勉強を再開する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
現在主に活躍している海外在住インド系女性映画監督は3人いる。アムリトサル生まれ、デリー育ち、トロント在住のディーパー・メヘター監督、ケニア生まれ、ロンドン在住のグリンダル・チャッダー監督、ケーララ州生まれ、デリー育ち、ニューヨーク在住のミーラー・ナーイル監督である。興味深いことに、3人ともパンジャーブの家系である。だが、3人の作る映画はそれぞれ特徴がある。最近、ディーパー・メヘター監督の「Water」が公開されたが、彼女はインドの社会問題を好んで取り上げる傾向にある映画監督である。「Bend
It Like Beckham」(2002;邦題「ベッカムに恋して)」で有名なグリンダル・チャッダー監督は、やたらとインド人女性×白人男性のロマンスをテーマにした映画を撮り、どちらかというとインドの因習を打ち破るメッセージを送っている。それに対しミーラー・ナーイル監督の映画の多くは、インド文化の素晴らしさを再発見させてくれるような魅力に溢れている。僕はこの3人の中ではミーラー・ナーイル監督を最も高く評価している。
「The Namesake」も、NRIの家族の絆を描きながら、インドの美しさ、インド文化の素晴らしさを伝える内容となっており、非常に力強い作品であった。原作は読んだことがないので比較はできないが、2時間の映画に収めるため、おそらくかなりの部分が省略されていたのではないかと思う。例えば、原作ではゴーゴルの人生に3人の女性が現れるが、映画では2人しか出て来なかった。また、それぞれの女性との破局の過程も詳しく描かれておらず、恋愛と結婚が映画の主題になっていないことは明白であった。
その代わり強調されていたのは父親アショークとゴーゴルとの関係である。アショークは物静かで口数少ないベンガル人という設定で、ゴーゴルにあまり口出ししようとしなかった。ゴーゴルが改名したいと言い出したときも、父は「ここはアメリカだ。自由にすればいい」と反対しなかった。だが、父の死後、ゴーゴルは父が自分に投げ掛けてくれた言葉のひとつひとつを思い出すのであった。ゴーゴルという名前の由来もそのひとつである。そして彼は、長年悩まされてきたアイデンティティーの葛藤から解放され、インド人としての自分を受け容れるのである。
また、主人公はゴーゴルよりもむしろ、母アシーマーの方だったと言える。彼女は結婚を機に米国へ渡り、25年間、夫と子供たちのために尽くす。そして子供たちが独立した後、彼女はカルカッタへ戻ることを決意する。帰る前にアシーマーは、25年間インドのことを常に思い出していたこと、そしてインドに帰った後は米国で出会った友人たちのことを思い出すであろうこと、だが、米国という国自体は決して懐かしく思わないだろうことを述べる。彼女のその言葉に、故郷への憧憬以上に、インド人としてのプライドを感じた。映画は、アシーマーがカルカッタへ帰った場面を持って終了する。
インドの映像も非常に美しかった。こんなことを言うのは失礼かもしれないが、インド人の目でこれだけインドを美しく描写できるのは稀なことではないかと思う。やはり、海外に在住していると、視点も外国人のものに近くなるのであろう。喧騒と混沌のカルカッタですら、巧みな映像表現力により、魅力的に映し出されていた。それに加え、アーグラーのタージ・マハルも出て来る。スクリーンで見るタージ・マハルはまた違った迫力がある。意味もなくタージ・マハルが出て来るのではなく、一応ストーリーに絡められている。ゴーゴルはタージ・マハルを見て感動し、建築学を学ぶことを決めるのである。また、米国の風景もインドに負けず美しく描かれていた。その美しさには、思わず観客席から溜め息が漏れるほどであった。それらに加え、ベッドシーンもいくつか出て来たが、やはり監督が女性なだけあり、乾いた美しさのある映像であった。
主演の3人は皆素晴らしい演技であった。特にイルファーン・カーンの間を活かした演技は群を抜いていた。タッブーも負けてはいなかった。10代の少女から40代の女性までの演じ分けは甘かったような気もするが、特に後半の演技は絶品であった。この2人が、コールカーターのヴィクトリア記念堂で交わす会話は微笑ましかった。
ゴーゴルを演じたカール・ペンは、インド映画界では初登場の俳優だが、米国では名の知れたインド系の男優らしい。本名はカルペーン・スレーシュ・モーディーというコテコテのグジャラーティー名だが、NRIの若者にありがちな「名前の西洋化」をして、カール・ペンを名乗っているようだ。最近ではハリウッド映画「Superman
Returns」(2006年)や、人気TVドラマ「24」などに出演している。米国生まれだけあって、きれいなアメリカ英語を話していた。
妹ソニアを演じたサヒラー・ナーイルはミーラー・ナーイル監督の姪で、「Monsoon Wedding」(2001年)にも出演していた。また、マウシュミーを演じたズレイカー・ロビンソンは、英国人、スコットランド人、インド人、ビルマ人、イラン人、マレーシア人の血を受け継ぐ混血の英国人女優である。
言語は基本的に英語だが、ベンガリー語も多用される。ほとんどのベンガリー語セリフには簡潔かつ分かりやすい英語字幕が付く。ベングリッシュ映画と言ってもいいだろう。また、ほんの少しだけヒンディー語も聞こえて来た。
ミーラー・ナーイル監督の「The Namesake」は、インド人のインドへの回帰を美しい映像と共に描いた傑作である。インド映画ファンだけでなく、全ての映画愛好家に受け容れられるだけの普遍性を持った作品で、日本で公開されてもおかしくない。



