| ◆ |
9月5日(水) リッジの博物館、マーンガルバニー |
◆ |
紀元前2600年から紀元前1800年頃まで栄えたとされるインダス文明。その滅亡の原因には諸説あるが、インダス文明の生命線となっていたインダス河とガッガル・ハークラー河(神話上のサラスワティー河)の流域変動が滅亡の原因となったと言うのが有力な説のひとつだ。
グジャラート州のパーランプルから端を発し、ラージャスターン州を貫いてデリーに突き刺さるアラーヴァリー山脈。インド亜大陸で最も古い山脈であり、アラビア海システムとベンガル湾システムを分ける重要な分水嶺となっている。ラージャスターン州アルワル辺りを飛行機から眺めると、どこまでも続く平野の中を岩がちの山脈がまるでシーサーペント(海蛇)のように所々地表に体を出しながら、デリーへ向かっている様子が見えるだろう。
アラーヴァリー山脈は、最も高いマウント・アブー(ラージャスターン州)で標高1,722mあるものの、その末端のデリーではせいぜい2.5~90mほどだ。しかも連続した山脈にはなっておらず、途中にいくつか切れ目がある。デリーに顔を出したアラーヴァリー山脈は、地元ではコーヒー、パハーリーまたはリッジと呼ばれる。便宜的にデリー大学周辺のリッジをノーザン・リッジ、大統領官邸裏山のリッジをセントラル・リッジ、JNUやクトゥブ・ミーナール周辺のリッジをサウス・セントラル・リッジ、デリーの南の州境を形成するリッジをサザン・リッジと呼んでいる。
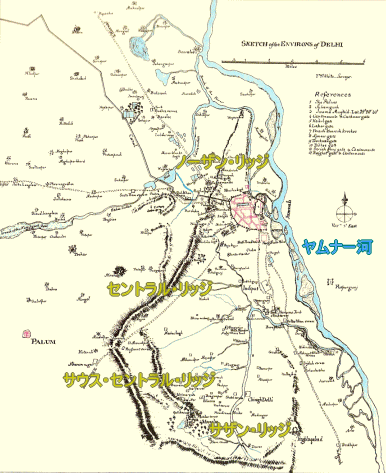
デリーは歴史的に、リッジとヤムナー河に囲まれた三角地帯に位置して来た。地勢図上で見ると、「歴史的デリー」はアラーヴァリー山脈の揺り籠にスッポリ収まり、ヤムナー河で蓋をされているかのような形になる。ただし、「現代デリー」の範囲はアラーヴァリー山脈の西側やヤムナー河の東側にまで広がっている。
今ではヤムナー河はアラーヴァリー山脈の東側、つまりデリーの東側を流れている。だが、どうも昔はアラーヴァリー山脈の西側を流れていたらしい。ヒマーラヤ山脈から流れ出たヤムナー河は、パンジャーブ地方東部を流れ、アラーヴァリー山脈の西側を進み、ラージャスターン地方を流れ、アラビア海に注いでいた。つまりそれは、ヴェーダなどの神話に出て来るサラスワティー河そのものであった。アラーヴァリー山脈の隆起などの原因によりサラスワティー河が流れを変え、アラビア海システムではなくベンガル湾システムに合流したのは紀元前1800年とされる。これはインダス文明滅亡のタイミングとピッタリ一致する。よく、プラヤーグ(イラーハーバード)のサンガムでは、3つの河が合流していると言われる。ガンガー(ガンジス)河、ヤムナー河、サラスワティー河である。だが、実際に目に見えるのはガンガー河とヤムナー河の合流だけだ。その矛盾の説明として、3つめのサラスワティー河は地下から合流していると言われる。だが、河の歴史を見ると、ヤムナー河こそサラスワティー河であったのだ。サンガムでの3つの河の合流は、そういう意味では正しい。
また、最新の研究によると、ガンガー河も元々はアラビア海システムの一員だったようだ。しかも、当時ヤムナー河(サラスワティー河)とガンガー河の合流点はデリーにあったと言われる。ヤムナー河よりも東から流れ出るガンガー河は、現在のデリーでヤムナー河と合流し、ラージャスターン地方を通ってアラビア海へ注ぎ込んでいた。ガンガー河が流域を変えてベンガル湾システムへ移行したのは、紀元前1万年頃のことのようだ。
ヤムナー河がアラビア海システムに合流した当時、ヤムナー河はデリー北部でアラーヴァリー山脈の西側へ逸れ、そこから東向きにカーブを描き、サザン・リッジを突っ切って、ファリーダーバードへ抜けていた。徐々に、だが地理学上ではかなり急に、ヤムナー河の流域は西から東へと移動した。現在ファリーダーバード県には、スーラジクンドやバドカル・レイクのような湖が点在しているが、これらは全て、古のヤムナー河の流域だったようだ。4月21日の日記で紹介した雄大なスーラジクンド・ダムも、元々はヤムナー河をせき止めていたに違いない。

スーラジクンド・ダム
元々ヤムナー河の豊かな水を受け止めていたサザン・リッジは、現在では険しい岩山と鬱蒼とした森林が織り成す秘境となっている。大都会デリーのすぐそばに、これほど荒々しい自然が残っているのを見つけるのは感動的ですらある。最近、サザン・リッジの自然を存分に楽しむことが出来るドライブコースを発見した。それは、トゥグラカーバード~スーラジクンド~バドカル・レイクを通り、グルガーオン・ファリーダーバード・マールグを疾走するコースである。トゥグラカーバードからバドカル・レイクまでの道はEICHER「Delhi
City Map」を見ればすぐに分かるが、ファリーダーバードとグルガーオンを結ぶグルガーオン・ファリーダーバード・マールグの大部分は地図範囲外になってしまっている。IIページのインセットの181の左隣にある「←Gurgaon」の道を通って行けば、Iページの176の右隣にある「→Faridabad」に出る。トゥグラカーバードからグルガーオンまでのこの道が最高に爽快なのである。大部分の道路は綺麗に舗装された広い道で、周囲の景色も最高。トラックの交通量が多いのが玉に瑕だが、デリーから気軽に足を延ばすことが出来るツーリング&ドライブ・コースとしてお勧めしたい。だが、既に不動産業者もこの辺りの風景の素晴らしさに気付いているようで、グルガーオン寄りの場所では、壮大な緑のカーペットの中に、高層マンション群が建っていた。

グルガーオン・ファリーダーバード・マールグの風景
グルガーオン寄りの場所には既に高層マンション群が
ところで、どうしてこの道を通ることになったかと言うと、それは半年ほど前から探していたある森林を見つけるためであった。その森林の名前はマーンガルバニー(Mangarbani)。たまたま購入したプラディープ・クリシャン著「Trees
of Delhi」という本にマーンガルバニーの記述があり、是非行ってみたいと思っていた。
現在リッジに生えている樹木のいくつかは、実は昔から生えていたものではない。1857年のインド大反乱以降からリッジの「緑の革命」が起こり、外来種が植樹されるようになった。それは特に1911年のデリー遷都宣言以降加速した。その結果、デリーのリッジの風景はだいぶ変わってしまった。その象徴が、地元の人々からダーオ(Dhau/Dhao)と呼ばれる木である。英語名がないところを見ると、インド特有の木のようである。学名はAnogeissus
pendula。大修館の「ヒンディー語=日本語辞典」には、ダーオ(धाव)は「ミソハギ科落葉中高木【Lagerstroemia parviflora】」と書かれているが、これだとサルスベリに近い木ということになる。かつてダーオはリッジを初めとしたデリー中に生えていたようなのだが、放牧による食い荒らしや生態系変化により、ほぼ絶滅してしまった。セントラル・リッジにはいくらか残っているようだが、ノーザン・リッジからは完全に姿を消し、サウス・セントラル・リッジを構成するJNUやメヘラウリーでもほとんど見られなくなった。確実に見られるのはプラガティ・マイダーンである。ホールNo.8の前にある2本の大きな木がダーオのようだ。
だが、デリーのすぐ近くに、ダーオの森林が手つかずのまま残っている場所がある。それがマーンガルバニーである。地元では、マーンガルバニーは聖人グダリヤー・バーバーに守られた森と信じられている。言い伝えでは、マーンガルバニーの木を折ったり、家畜に草を食べさせたりした者は、とてつもない不幸に見舞われるとされている。その迷信により、マーンガルバニーのダーオ林は現代まで守られ続けて来た。クリシャン氏はマーンガルバニーを、「デリー・リッジの真の姿を保存する小さなアウトドア博物館」と表現している。
「Trees of Delhi」には、マーンガルバニーは「デリーの南、ファリーダーバードとの州境から数kmの地点にある」とだけ書かれていた。とりあえずいつもお世話になっているEICHER「Delhi
City Map」で探してみたのだが、マーンガルバニーは見つからなかった。そこで、ファリーダーバードに住んでいる人に会うたびにマーンガルバニーについて質問していたのだが、その場所を知る者はいなかった。こうなると何が何でも発見して行きたくなるのが人情と言うものである。
・・・だが、人間は物忘れをすることが出来る生き物でもある。マーンガルバニーのことなどすっかり忘れていた先日、急にファリーダーバード在住のヒンディー文学者ヴェード・ヴャティト氏から電話があり、マーンガルバニーが見つかったとの吉報を受けた。早速ヴェード氏の家を訪れたのだが、彼が「発見」してくれたのはバクティ詩人スールダースの生誕地のことで、僕が探しているマーンガルバニーではなかった。しかし、地元でちょっとした権力を持つ「ソーシャル・ワーカー」の家に行き、「Trees
of Delhi」に載っていたグダリヤー・バーバー寺院の写真などを見せて、マーンガルバニーについて聞いてみたら、「ソーシャル・ワーカー」の子分の1人が「思い当たる場所がある」と言ってくれた。どうもそれはグルガーオン・ファリーダーバード・マールグの途中にあるらしい。と言う訳で、後日マーンガルバニーを探す旅に出た訳である。
その人の話では、グダリヤー・バーバー寺院は、グルガーオン・ファリーダーバード・マールグを通っていれば絶対に目にする、見過ごさずにはいられない、とのことであった。よって、昨日はとりあえずファリーダーバードからグルガーオンまでその道を通ってみた。だが、特に写真で見た寺院のようなものは見当たらず、グルガーオンに到着してしまった。その日は疲れたのでデリーに戻り、今日再びマーンガルバニー捜索に挑戦した。
しかし昨日一応の手がかりは掴んでいた。グルガーオン・ファリーダーバード・マールグの途中にマーンガル(Manger)という村を示す看板があり、その辺りにマーンガルバニーがある可能性が高かったのである。今日はマーンガルを目指して走った。マーンガル村を示す看板はチャッタルプルへ通じる道との三叉路近くにあるが、マーンガル村自体はその奥へさらに数km走って行ったところにある。マーンガル村は、なだらかな山々に囲まれた非常に美しい村だった。デリーから本の少し離れた場所に、100年、200年前とほとんど変わらないような農村風景が現れるのには驚きを禁じ得なかった。

マーンガル村
グダリヤー・バーバーの寺院は、村の手前の急な坂を下り、マーンガル村に入ってすぐに右に曲がり、未舗装の泥道を道なりに進んで行った先にある森林の中にあった。だが、どういう運の巡り合わせか、この日グダリヤー・バーバーの寺院では何かのイベントが行われており、森の中に大量の人々が詰めかけていた。

何かのイベント
そして近くの池では子供たちが楽しそうに水浴びをしていた・・・。

水浴びする子供たち
う~む、全然「聖なる森」のイメージと違うのだが・・・。
しかし、突然やって来た不審者を凝視するそこら辺の人に聞いてみたら、イベントが行われていた寺院(何の寺院かは分からず)は森の中ほどにある一方、「Trees
of Delhi」に掲載されていた小さなグダリヤー・バーバー寺院はもっと森の奥にあることが分かった。そこでバイクから下りて森の中を歩いて行ってみた。

バイクを下りて徒歩で移動
途中すれ違った人に、ダーオの木はどれか、と聞いてみると、ここら辺に生えている全ての木がダーオだと言う答えが返って来た。デリーではダーオの木を知っている者など1人もいなかったが、ここではすぐに通じたこと自体に感動。確かに周囲には、「Tree
of Delhi」に載っているクネクネしたダーオの木がたくさん生えている。間違いない、デリーではほぼ全滅したダーオが生い茂ると言うマーンガルバニーに足を踏み入れたのだ。

階段の両側に生えているクネクネ曲った木がダーオ
途中から現れた階段を上って行くと、その先に、「Trees of Delhi」にも掲載されていたグダリヤー・バーバー寺院が出現した。寺院と言うよりも、祠である。2階建ての小さな建物で、上部にはスマートなドームが乗っかっていた。1階には火が灯され、お供え物が散乱しており、2階にはグダリヤー・バーバー像が安置されていた。中には誰もいなかった。

グダリヤー・バーバーの祠

左は1階、右は2階
グダリヤー・バーバーの祠の2階からは、マーンガルバニーのダーオ林を見渡すことが出来た。

マーンガルバニー
マーンガルバニーでは不思議な体験もした。まず、祝福の雨が降って来たことである。マーンガルバニーを目指してJNUを出たときと、グダリヤー・バーバーの祠に辿り着いたときに、ポツポツと雨が降って来た。今日雨に降られたのはその2回だけだった。全然強い雨ではなく、すぐに止んでしまったが、何となくグダリヤー・バーバーに祝福されているような気分になった。また、マーンガルバニーを歩いていたら、ある老人に話しかけられた。それだけなら特に何の変哲もない話なのだが、その老人は僕に「久し振りに来たね、何年振りだろう」と親しげに挨拶して来たのである。僕は初めて来たのだが・・・。多分、似たような人が以前に来たのであろうが、もしかしたら何か前世からのつながりがあるのかもしれない、と少し不思議な気分になった。しかも、その老人だけでなく、なぜか僕のことを、以前から知っているかのように接してくれる人が何人もいた。水浴びする子供たちの写真を撮っていたら、裏から別の老人に声を掛けられ、「プラサードを食べて行きなさい」と、プーリーやハルワーを頂いた。また、手を洗う水を探していたら、いろんな人が親切に場所を教えてくれた。田舎のインド人は大体親切だが、そういう親切さとはちょっと違ったものだった。何と言うか、僕のことを完全に外部の者として捉えていないというか、ちょっと顔見知りの外国人みたいな感じで扱ってくれたのである。何だか不思議な場所だった。
幸か不幸か、今回はものすごく込み合っているときにマーンガルバニーに来てしまったので、また後日暇なときに、静かなマーンガルバニーを見に再訪してみようと思う。
ところでこのグルガーオン・ファリーダーバード・マールグの途中にある村々は、グッジャルの村である。グッジャルは基本的に牧畜民だが、英領インド時代には犯罪者カーストに指定された部族でもあり、昔から盗賊行為を働くことが多かったとされる。今でも時々この辺りでは強盗被害に遭う人がいるようである。マーンガル村もずばりグッジャルの村だ。マーンガル村やマーンガルバニーからは特に危険な雰囲気を感じなかったが、もし行くときは最大限注意を払うべきであろう。
1993年に犯した武器不法所持で6年の懲役刑を言い渡され、一時服役していたものの、最近保釈されて各地の寺院巡りをしているサンジャイ・ダット。その主演作の「Dhamaal」が本日より公開された。
題名:Dhamaal
読み:ダマール
意味:大騒動
邦題:ダマール
監督:インドラ・クマール
制作:アショーク・タークリヤー、インドラ・クマール
音楽:アドナーン・サーミー
作詞:サミール
出演:サンジャイ・ダット、アルシャド・ワールスィー、リテーシュ・デーシュムク、ジャーヴェード・ジャーフリー、アーシーシュ・チャウドリー、プレーム・チョープラー、アスラーニー、ムルリー・シャルマー、ヴィジャイ・ラーズ
備考:PVRナーラーイナーで鑑賞。
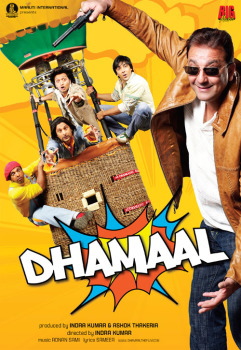
左から、ジャーヴェード・ジャーファリー、アルシャド・ワールスィー(下)、
リテーシュ・デーシュムク(上)、アーシーシュ・チャウドリー、サンジャイ・ダット
| あらすじ |
デーシュバンドゥ・ロイ(リテーシュ・デーシュムク)、アーディティヤ(アルシャド・ワールスィー)、マーナヴ(ジャーヴェード・ジャーファリー)、ボーマン(アーシーシュ・チャウドリー)の仲良し4人組は、家賃滞納のために下宿を追い出されてしまった。たまたま彼らは人里離れた場所で自動車事故現場に遭遇する。自動車に乗っていたボース(プレーム・チョープラー)は息を引き取るが、その前に4人に一生かけてため込んだ1億ルピーの在りかを教える。それは、ゴアのセント・カテドラル・ガーデンの大きなWの下とのことだった。4人は一攫千金の幸運に狂喜する。
ところがそのとき、カビール・ナーヤク警部補(サンジャイ・ダット)がやって来る。カビールは過去10年間ボースを追いかけて来たが、その死体を前に愕然とする。彼は不審な4人を警察署に連行しようとするが、4人は隙を見て逃げ出す。
4人は、ボーマンの父ナーリー・コレクター(アスラーニー)の愛車を無断で借りてゴアを目指す。ところが、ジャングルの中の近道を通ったために車は壊れ、爆発してしまう。一方、ボース逮捕に失敗して上司から左遷を言い渡されたカビールは、警察署に自動車の盗難届を出しに来たナーリーと会い、その息子が4人組の1人であることを知る。カビールとナーリーは一緒に4人を追尾する。ナーリーは大破した愛車を見つけて復讐の鬼と化す。
追跡の結果、カビールは4人を捕まえるが、彼は警察上層部を信頼できなくなっており、1億ルピーを自分のものにしようと考えていた。5人は1億ルピーを山分けにする契約を結ぼうとするが、それは仲たがいによって破談となり、先に見つけたものが独占できるということになった。5人は我先にとゴアへ向かう。
ロイは途中で盗賊に出くわして殺されそうになるが、1億ルピーを山分けする話を持ち出して、一緒にゴアへ向かう。アーディティヤとその弟のマーナヴは、ヒッチハイクしながらゴアへ向かう。ボーマンは途中で父親に見つかるが、やはり1億ルピーの話を出して一緒にゴアへ向かうことになる。また、カビールは途中で仮装した子供たちの乗ったバスに乗り込んでゴアへ向かう。
7人はセント・カテドラル・ガーデンに着き、「W」を探し回る。それは、「W」型に重なったヤシの木のことであった。その下を掘ると、本当に1億ルピーが出て来た。再びその配分を巡って喧嘩が起こるが、その漁夫の利を得る形でカビールが1億円の入ったバッグを持って逃げる。彼は気球に1億円を乗せて逃げようとするが、自分が乗り遅れてしまい、気球だけ飛んで行ってしまう。しかし、気球も燃料切れでそれ以上上には上がらず、そのまま風に流されて漂う。7人は一生懸命気球を追う。
夜中までかけて気球を追った結果、やっとのことで7人は1億ルピーを手にする。ところがその場所は、孤児のための義捐金募集の場であった。引っ込めなくなった7人は仕方なく1億ルピーを孤児たちに寄付する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
コテコテだが面白い単発ギャグをうまく組み合わせて、一応ストーリー性のあるひとつのコメディー映画にしていた。単発ギャグに力を入れ過ぎて中盤から終盤にかけてスローテンポでグダグダの展開になっていたきらいがあるが、最後は急転直下、全く予想外の感動的エンディングでまとめていた。佳作のコメディー映画と言える。
ボリウッド初心者の日本人にはなかなか理解しがたい事実なのだが、サンジャイ・ダットはインド人の間でナンバー1の人気を誇っていると言っても過言ではない。映画監督や俳優の中にも、彼を神のように信奉する人が少なくない。例えばサンジャイ・グプター監督は、サンジャイ・ダットをいかにかっこよく演出するかに命をかけている奇特な映画監督だ。「Kaante」(2002年)、「Musafir」(2004年)、「Zinda」(2006年)など、ここ最近の彼の映画は全てサンジャイ・ダットが主演である。「サンジャイ・ダットと仲間たち」「サンジャイ・ダットを囲む会」みたいな、「サンジャイ・ダット+若手俳優数人」の映画もよく作られる。例えば「Plan」(2004年)や「Shaadi
No.1」(2005年)がその例だ。そのような映画を見ると、サンジャイ・ダットの人気におんぶに抱っこしながら、若手の俳優たちを売り出そうとしている魂胆が見え隠れする。「Dhamaal」もその一例のように見える。サンジャイ・ダット以外の主演の中に、サンジャイ・ダットに匹敵するような俳優は1人もいない。敢えて言うなら、「Munnabhai
MBBS」(2003年)や「Lage Raho Munnabhai」(2006年)でサンジャイ・ダットと共演したアルシャド・ワールスィーだが、彼の存在感もサンジャイ・ダットあってのものであり、まだ1人立ちできるほどの実力はない。
だが、実際に「Dhamaal」を見てみると、意外なことにサンジャイ・ダットの見せ場は少なく、代わりに他の4人がそれぞれの持ち味を活かして頑張っていた。最近絶好調のリテーシュ・デーシュムクは、二枚目半の容姿を存分に活かした「キザなドジ男」を演じ、アルシャド・ワールスィーは「Munnabhai」シリーズで培った胡散臭い演技を全開させ、ジャーヴェード・ジャーファリーも水を得た魚のようにノンストップのおとぼけギャグで突っ走っていた。それに加え、まだ本格デビューから日が浅いアーシーシュ・チャウドリーもいい感じの演技をしており、4人組のケミストリーは見事に成功していた。
ひとつひとつのギャグはしょうもない。日本にもよくあるコント劇のようである。飛行機に乗っていたらパイロットが気絶し、代わりに操縦桿を握るボーマンらは空港管制塔と交信して着陸の方法を聞く。管制官(ヴィジャイ・ラーズ)はいろいろもったいぶったあげく、「操縦桿の近くに赤いボタンがあるだろう」と言う。それを聞いたボーマンはすぐに赤いボタンを押してしまう。すると管制官は「それを押してはいけないと言おうと思ったのに・・・」とのたまう。ボーマンは大パニック。・・・こんな感じのギャグが続く。
しかし、古典的ギャグがつまらないと言うわけではなく、むしろ分かりやすくて大笑いできる。ボリウッドのコメディー映画はセリフ回しで笑わせることに力を入れる傾向にあり、ヒンディー語が分からないと何が面白いのかよく分からないということが少なくないのだが、「Dhamaal」なら誰でも笑えるのではないかと思う。特にジャーヴェード・ジャーファリーは見ているだけで笑いがこみ上げて来る。
この映画には特殊なことに、ヒロインが1人もいない。確かにストーリー上、ヒロインは必要なかった。無理にヒロインを入れるよりも数倍賢い選択である。
音楽はアドナーン・サーミーだが、それほど優れた楽曲はなかった。
「Dhamaal」は、4人の若手男優のコメディーが面白い佳作のコメディー映画である。今年のヒット・コメディー、「Partner」や「Heyy
Babyy」に比べると派手さに欠けるが、見て損はない。
8月30日、ヒンディー語TV局ライブ・インディアが囮捜査のスクープ映像を放送した。その放送は、オールド・デリーはダリヤー・ガンジにある政府系のサルヴォーダヤ女学校の女性数学教師ウマー・クラーナーが、学校の女学生や個人授業をしていた女子生徒を使ってポルノビデオを作ったり、売春の斡旋業をしていると言うものだった。囮捜査では、TV局のレポーターがビジネスマンになりすましてウマー・クラーナーと接触し、電話での会話を録音し、売春婦を斡旋するところをカメラにとらえた。
その音声と映像が放映された直後、学校に子供を通学させている両親たちや近所の人々がサルヴォーダヤ女学校の前に集まり、やがて彼らは暴徒と化した。暴動によって警察のジープなど、近くに止めてあった自動車やバイクが数台燃やされ、鎮圧に当たった警察官数人も負傷した。また、トゥルクマーン門周辺の店はシャッターを下ろさざるを得なくなった。さらに、ウマー・クラーナーは警察に保護・逮捕される前に暴徒によってリンチに遭い、怪我を負った。ウマー・クラーナーの自宅からは数十枚のVCDが押収された他、彼女の電話記録には教育機関に所属する多数の人物との連絡の形跡があり、デリーの教育界の一部が売春斡旋ネットワークと化している可能性も取り沙汰された。また、事件発覚後すぐに政府はクラーナーを教師職から解雇した。学校の女性教師が教え子を使って売春斡旋を行ったりポルノビデオを作ったりしていたというニュースは、デリー市民の間に驚きと怒りを巻き起こした。証拠はTV局が放映した囮捜査の音声と映像のみなのにも関わらず、世論はウマー・クラーナーを勝手に犯人と決め付けていた。

リンチに遭うウマー・クラーナー
ところが事件発生から数日後から奇妙な点が発覚し始めた。まず、TV局が放送した隠しカメラ映像に映っていた女性が、実はウマー・クラーナー容疑者の教え子でも何でもないことが分かった。彼女は売春婦でもなかった。しかも一番の被害者であるはずの女性は、クラーナー容疑者を告訴することを拒否した。さらに、事件発生から1週間後の9月6日に事態は急展開を迎えた。警察が囮捜査映像の未編集テープを調査したところ、囮捜査自体が捏造であった可能性が高まったのである。未編集テープには、クラーナー容疑者が売春婦の斡旋を何度も拒否している姿が映し出されていた。彼女はそんなコンタクトすら持っていないと語っていた。しかもそのテープからは、囮捜査を行っていたTV局のレポーター自身が、クラーナー容疑者に売春婦を斡旋を強要していたことが発覚した。その後彼は知り合いの女性をあたかもクラーナー容疑者によって斡旋された売春婦であるかのように映し、それらの映像をうまく編集して、囮捜査映像として使ったのである。一方で、警察はクラーナー容疑者を犯人と断定する証拠をひとつも見つけることが出来なかった。女性は虚偽の証言をした疑いで逮捕され、TV局のレポーター、プラカーシュ・スィンも逮捕された。
9月7日付けのタイムス・オブ・インディア紙によると、どうやら黒幕は、ウマー・クラーナーに私怨のあった、ヴィーレーンドラ・アローラーという人物だったようである。彼はクラーナーと金銭問題で揉めており、彼女に復讐するためにプラカーシュ・スィンを巻き込んで全てを仕組んだようだ。ヴィーレーンドラ・アローラーは現在逮捕されている。
さらに興味深いことに、プラカーシュ・スィン容疑者は以前別のヒンディー語TV局に訓練生として勤めており、捏造映像を作ったのもそのときだったようだ。だが、そのTV局は囮捜査の信憑性の低さを理由に放送しなかった。その後、彼は新しく設立されたTV局ライブ・インディアに転職し、そのテープを無断で前のTV局から持ち出して売り込んだ。ライブ・インディアは、一気に世間の注目を集めるために、多少問題があってもその捏造映像を放送してしまったのだろう。
ただし、まだ事件の全貌は明らかになっておらず、現時点で結論を出すのはまだ早い。今まで分かったところによると、ウマー・クラーナーは、公務員でありながら副業で貿易会社を経営しており、その設立資金をヴィーレーンドラ・アローラーから借りたまま返さなかったらしい。それが事件の直接の原因となったようだ。ヴィーレーンドラ・アローラーから特ダネを得たプラカーシュ・スィンは、ビジネスマンに成りすましてクラーナーに商談を持ちかけ、その見返りとして売春婦を求めた。また、前述の通り、クラーナーは最初は売春婦斡旋を断っていたのだが、最後には折れ、アローラーに売春婦の斡旋を依頼したと言う。また、売春婦としてカメラに収められたのはリシュミー・カンナーという女性で、スィンの知人のメディア関係者であった。今のところ、これらの人物は全て逮捕されている。クラーナーもまだ完全には無罪と断定されていない。
今回の事件は3つの点で考えさせられる。ひとつはメディアによる捏造。日本でも新聞やTV局による捏造が問題になっているが、インドでも全く同じである。インドの新聞は昔からしょうもない記事がけっこうあるが、しょうもないだけなら笑って済むからかわいいものである。だが、囮捜査(スティング・オペレーション)の習慣が定着して以来、正確性やモラル性が吟味されていない報道が垂れ流されることが多くなって来た。有名人や権力者の知られざる悪事を暴くという目的ならまだしも、恨みのある人間を罠にはめるために囮捜査が行うというは、インドのメディア戦争と放送倫理がかなり危険な水域に達したと言わざるをえない。既にメディアによる囮捜査の規制が議論されている。
さらに、インド人も捏造された情報に踊らされやすいことが分かる。最近はどの家庭にもTVがあり、家庭にTVがあればずっとTVを見ている人も少なくない。ひとたび誤った情報が放送された場合の伝播の速さは日本以上かもしれない。8月30日、捏造囮捜査映像が放映された直後に、ウマー・クラーナーの勤務する学校前に群衆が集まるというのは異常な速さだ。学校の先生たちも、群衆が集まるまでニュースのことなど全く知らなかったと言う。
そして、9月4日付けのデリー・タイムス・オブ・インディア紙にも載っていたが、インドで集団による私刑の習慣が根強いのも恐ろしい。民衆が、容疑者を警察に引き渡したり裁判所が判決を出す前に、よってたかって制裁を加えるのである。そしてこういう場合、止める人は警察を除いて現れない。怒りの矛先はしばしば鎮圧に乗り出した警察にも向かう。こうなると、日頃の鬱憤を晴らしているだけである。いわゆる「祭り」というやつだ。最近の日本ではネット上での「祭り」がほとんどだが、インドではまだまだ肉体的暴力に訴えた「祭り」が根強い。時には警察までもが集団リンチに加わることもある。
ただ、少し心の温まる記事もあった。捏造ニュースが放映され、ウマー・クラーナーが集団リンチに遭った後、新聞記者は取材のためにクラーナーの自宅も訪れた。家は閉ざされており、クラーナーの家族は誰も家にいなかった。大家はインタビューに対し、「私もTVの映像を見たときはショックを受けたが、クラーナーさんの家族には善意の気持ちから安全な避難場所を提供した。彼らが帰って来るのを待っている」と答えた。情報に踊らされやすい大家だったら、即刻クラーナーの家族を追い出していたことだろう。実際、事件が発覚した後、クラーナーの同僚たちは異口同音にクラーナーの勤務態度などを批判し、仲間でないことを証明して必死に自分の身をかばおうとしていた。メディアの情報に左右されず、彼らに人道的な援助をした大家はきっと人間の出来た人に違いない。カリユグ(末法)の世の中だが、まだインドにはダルマ(正義)がかろうじて残っているように感じた。
最近ラーム・ゴーパール・ヴァルマーの映画の調子が悪い。「Ram Gopal Varma Ki Aag」に失敗に続き、先週の金曜日に公開された同監督プロデュース作「Darling」の評価も最悪。かつては「ボリウッドのクエンティン・タランティーノ」と呼ばれたヴァルマー監督であるが、インドの映画ファンたちの間では彼に対し、もはや憤慨や失望を通り越して、「一体どうしちゃったの?」という憐憫の情が沸き起こっている。と言うわけで「Darling」は敬遠し、もうひとつ先週から公開された「Apna
Asmaan」を見に行くことにした。
題名:Apna Asmaan
読み:アプナー・アースマーン
意味:自分の空
邦題:僕の空
監督:カウシク・ロイ(新人)
制作:ウマーング・パーフワー
音楽:レジー・レーヴィス
作詞:メヘブーブ
出演:ドゥルヴ・ピーユーシュ・パンジュアーニー(新人)、イルファーン・カーン、ショーバナー、ラジャト・カプール、アヌパム・ケール、バルカー・スィン、ナスィール・アブドゥッラー、ウトカルシャー・ナーイク
備考:PVRアヌパムで鑑賞。
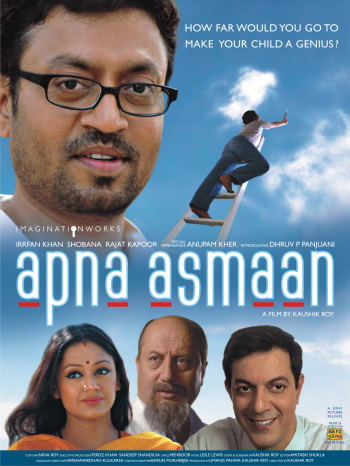
上段左はイルファーン・カーン
下段左からショーバナー、アヌパム・ケール、ラジャト・カプール
| あらすじ |
プラスチック会社に勤めるラヴィ・クマール(イルファーン・カーン)と、その妻で元舞踊家のパドミニー(ショーバナー)の間には、ブッディラージ・クマール(ドゥルヴ・ピーユーシュ・パンジュアーニー)という知能障害の15歳の子供がいた。ラヴィは、ブッディが幼い頃に高いところから落としてしまったことがあり、それが彼の知能障害の原因になったのではないかと悩んでいた。ただし、掛かり付けの医者セーン(ラジャト・カプール)はそれを否定していたし、パドミニーも表立ってそれを責めていなかった。パドミニーは数学オリンピックでチャンピオンになったことがあり、息子も数学の道に進ませるという夢を持っていたが、知能障害のブッディにそれは無理だった。ブッディは毎日絵を描いて過ごしていた。両親はブッディの描く絵をゴミ同然に扱っていたが、ドクター・セーンだけはブッディの才能を認めていた。
あるときラヴィは、脳障害を治し、凡人を天才に変貌させる奇跡の薬ブレイン・ブースターを開発したドクター・サティヤ(アヌパム・ケール)のことを知る。その薬は猿に対しては効果が証明されていたが、まだ人間の臨床実験は行われていなかった。ラヴィはサティヤに会い、ブレイン・ブースターを譲り受ける。だがちょうど同じ頃にドクター・サティヤには逮捕状が出され、彼は姿をくらましてしまう。
ラヴィはブッディにブレイン・ブースターを注射する。するとブッディは見違えるほど頭のいい少年に変貌した。しかし、それまでの全ての記憶を失っていた。それでもラヴィとパドミニーはブッディの障害が直ったことを喜んだ。今までギクシャクしていた家族は急に幸せに満ちたものになる。
ブッディは、健全な子供になっただけでなく、数学の天才になっていた。彼はやがて世間から注目を集めるようになる。しかし、依然として両親のことを他人扱いし、怒りっぽい性格になっていた。彼は自分の名前も気に入っていなかった。いつしか彼はアーリヤバッターを名乗り始める。
息子の変貌ぶりに最初は喜んでいたパドミニーであったが、不良少年となった息子を見て、元のブッディを求め始める。彼らはドクター・セーンに相談した。セーンは偶然ドクター・サティヤの居所を知っており、ラヴィは息子を元に戻すための薬を手に入れる。その薬により、ブッディは元に戻る。
ラヴィとパドミニーはブッディの絵の才能に気付き、個展を開く。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
「Black」(2005年)の成功を機に、障害者を主人公にしたり冗談にした映画がボリウッドで一時期流行ったことがあった。冗談にするのはもってのほかだが、障害者を主人公にしてチープな感動を売り物にする映画もいい気はしない。この映画も、最初の方ではそんな印象を受けたが、メインテーマは違った。「Apna
Asmaan」の主題は、子供に自分の夢を押しつける親の罪であった。知能障害児を主人公に据えたのは、そのテーマを強調するためのひとつの手段であった。脳を活性化させ、凡人を天才に変えるブレイン・ブースターという架空の薬も、多少SF的ではあったが、あくまでメッセージを強調するために導入された道具に過ぎなかった。
主人公のブッディは知能障害児であった。その原因は不明だが、幼少の頃、父親のラヴィが「高い高い」をしていて誤って落としてしまったのが原因ではないかと両親は考えていた。ブッディは「Hum
Honge Kamyaab(僕たちは成功するぞ)」という歌を繰り返し歌い、毎日絵ばかり描いていた。母親のパドミニーは息子を数学者にしたかったが、それは実現不可能な夢であった。ブッディの描く絵に注目していたのは、ホームドクターのセーンのみであった。ある日、ブレイン・ブースターのおかげでブッディは天才に生まれ変わるが、理性を失い、暴力的な子供になってしまう。それを見た両親は元のブッディを求め始める。最終的にブッディは元に戻り、両親はブッディの絵の才能を伸ばすことに努力を払うようになる。
インドの教育熱は日本以上だ。しかも学校の成績によってヒエラルキーが出来てしまっている。優秀な子供は理系へ進み、理系に進めない子供がその他の学科に進むのである。理系に進んだ子供の方が、高収入の職業に就ける可能性が断然高い。よって、インドの両親は、子供のため、自分のために、子供に必要以上の勉強を押しつけるのである。それで伸びて行く子供はいいが、それに応えられない子供は、最悪の場合、自殺という道を選んでしまう。「Apna
Asmaan」は、子供を一定の方向へ向かわせるのではなく、子供の興味や才能をよく見て、それを最大限に活かせる方向へ進ませることの重要性を説いている。「僕の空」という題名にもそれがよく表わされている。
さすがインド映画だな、と感心したのは、天才になったブッディと、「ラーマーヤナ」に出て来る羅刹王ラーヴァンが巧みに重ね合わされていたことだ。ラーヴァンは10の顔を持つ羅刹として描かれるが、10の顔とは全能の賢さの象徴である。すなわち、彼は一度に前後左右、斜め左右前、斜め左右後ろ、そして上と下の10方向を見渡すことが出来た。だが、その圧倒的な賢さ故に慢心し、身を滅ぼしてしまった。天才的数学者となったブッディは、ラーヴァンが退治される日であるダシャヘラー当日に、元の知能障害児のブッディに戻る。「世界の全ての話は『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』の中にある」と言われるが、少なくともインド映画は今でもこれら二大叙事詩の影響下にあり、それが他の映画界にはない力となっている。
ただ、「Apna Asman」は感動できる映画ではあったものの、メッセージを強調するあまり、現実感が希薄で観客をスクリーンに引き付ける魅力に欠けた映画になってしまっていた。もし批判するとしたらその点であろう。
「Apna Asmaan」は基本的にフィクションであり、その中に出て来たブレイン・ブースターという薬も架空のものだが、一応モデルになった子供がいるらしい。現在16歳のオスコ君は、中度の自閉症で、てんかんによる微細胞障害症候群に冒されている。そのために彼は通常の学校に通うことが出来なかった。だが、彼は天才的な芸術の才能を持っていた。彼は動物に対して多大な愛情を抱いており、彼の絵の主題の多くも動物である。最近ムンバイーでオルコ君の展覧会が行われたが、大成功に終わったと言う。オルコ君の絵は、映画の中や、公式ウェブサイトで見ることが出来る。
ブッディを演じたドゥルヴ・ピーユーシュ・パンジュアーニーは、本作がデビュー作ながら、知能障害児状態時と天才数学者時を全く違った雰囲気で演じ分けており、尋常ではない才能を感じた。ただし呂律が良くなく、セリフが聞き取りにくかった。訓練すれば、きっといい俳優になるだろう。新人の脇を固めるのはベテラン俳優陣。イルファーン・カーン、ショーバナー、ラジャト・カプール、アヌパム・ケールなど、インド映画界の演技派が揃っている。皆文句ない演技であった。
音楽も効果的に使われていた。特にスクヴィンダル・スィンの歌う「Katra-Katra」が印象的な使われ方をしていた。
「Apna Asmaan」は、多少無理のあるストーリーではあるが、監督が観客に伝えたいメッセージはひしひしと伝わって来る佳作である。
8月21日の日記で、インドの街頭の主役とも言えるオートリクシャーが生誕50周年を迎えたことを報告した。今日は、インドの鉄道駅の「主役」の50周年の話である。9月12日付けのタイムス・オブ・インディア紙の記事による。
一部のリッチな旅行者を除き、鉄道はインドを旅する者全ての重要な足である。そして、インドのカオスをまざまざと目にするのも鉄道駅である。うねり流れて行く群衆、毛布に包まれ地面に寝る家族、切符売場前の長蛇の列、場違いに脳天気なアナウンスの声、飾りと化した金属探知器、数時間遅れて到着する列車、プラットフォームを疾走するバイク、線路に下りて向こう側へ渡る人々、目を血走らせて何個もの荷物を頭に乗せて運ぶ赤服のポーター、こんなところにまでいる牛と犬・・・。インドに初めて降り立った旅行者の目には、何もかもが新しく、そして混沌として見える。
そしておそらく、そんな旅行者の注目を必ず引くことになるであろう物体が、派手な電飾で彩られ、駅の構内にポツンと置かれている電飾体重計である。もちろん、何も知らない人には、それが体重計であることに気付くのには時間がかかる。殺風景なインドの駅の中で、ピカピカと色電球を光らせる体重計は異様に目立つ。そして、数分でもそれを観察し続けていれば、インド人がその上に乗って体重を計る姿を目撃することに成功するであろう。

電飾体重計
ところでインドには、体重計ひとつで生計を立てる体重計屋なる職業が存在する。道端に座り込み、体重計をポンと前に置いて、客が来るのをひたすら待っている。日本人には、「体重なんて家で測れるのにこんな商売がどうして成立するのか?」と不思議でならないのだが、見ていると、なかなかどうして、体重計屋を利用して自分の体重を測って行く通行人が少なくないのである。ただ単に体重計を持っていない家庭が多いだけなのかもしれない。もしくは、体重計屋があるために一般のインド人は体重計をわざわざ買う必要を感じていないのかもしれない。だが、どうもインド人は体重測定を一種の娯楽として捉えているのではないかと感じることが多い。
そんなインド人の体重測定好きを商機にしようと思ったのかどうかは不明だが、ノーザン・スケールズ・カンパニー(Northern Scales Company)という会社が電飾体重計を開発した。電飾体重計第一号が設置されたのは1957年。場所はデリー駅(オールド・デリー駅)であった。つまり、今年で50周年と言うことになる。
現在、1回の体重測定にかかる料金は1ルピー。この値段は15年間変わっていないと言う。台の上に乗り、1ルピー硬貨をコイン投入口に入れると、体重がプリントされた小さな紙が出て来る。インドでは珍しい自動販売機タイプの機械だ。紙の裏には人気女優の顔も印刷されている。電飾体重計が登場した当時、そのヒットの要因となったのはどうも体重測定機能よりもむしろ、女優の顔がプリントされて出て来ることにあったようだ。人々は、ヘーマー・マーリニーやワヒーダー・レヘマーンなどの写真欲しさに電飾体重計に群がった。当然、プリントされる女優の顔は時代によって変遷しており、現在ではビパーシャー・バスやマッリカー・シェーラーワトが印刷されている。
また、その紙には占いやちょっとしたメッセージもプリントされて出て来る。そのパターンは30種類あり、定期的にアップグレードされているそうだ。しかも、同じメッセージが続けて出て来ないように工夫もされている。
興味深いことに、国営のインド鉄道が民間企業による電飾体重計を駅構内に設置することを許可した背景には、釣銭の確保という目的があったようだ。切符を販売しているとどうしても釣銭のための細かいお金の不足に悩むことになる。それを解消するため、1ルピー硬貨が集まる電飾体重計設置を許可したのである。ちなみに、売上の35%が駅側の取り分となっているようだ。
現在、デリーには電飾体重計は合計105台あると言う。だが、商売はうまく行っていないらしい。かつて1台の1日の収入は100ルピーだったが、今では50ルピーほどのようだ。
いつかあの電飾体重計がインドの駅から姿を消すときが来るのであろうか・・・。
| ◆ |
9月14日(金) Nanhe Jaisalmer |
◆ |
ラージャスターンの砂漠は魔法だ。あの風景には、どんな映画でも素晴らしい作品に見せてしまうだけの魔法がある。あの砂漠が、あの青空が、あの城が、あの衣装が、そしてあの夕陽がスクリーンに映し出された途端、否応なしに映画の中に引き込まれてしまう。本日より公開の「Nanhe
Jaisalmer」。題名通り、ラージャスターン州切っての風光明媚な観光地、ジャイサルメールを舞台にした映画である。ただジャイサルメールを感じたくて映画館に足を運んだ。
題名:Nanhe Jaisalmer
読み:ナンネー・ジャイサルメール
意味:主人公の名前
邦題:ナンネー・ジャイサルメール
監督:サミール・カールニク
制作:Kセラセラ、ダルマ・モーション・ピクチャーズ
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー
作詞:サミール
出演:ボビー・デーオール、ドイジ・ヤーダヴ(新人)、ヴァトサル・セート、プラティークシャー・ローンカル、シャラト・サクセーナー、ビーナー・カーク、ラージェーシュ・ヴィヴェーク、ルシター・スィン、ヴィヴェーク・シャウク、スクヴィンダル・チャハル、アーディル・ラーナー、ローケーシュ・パンディト、スディール・クマール、カラン・アローラー、ヴィクラーント・タークル、アムリーシュ・シャルマー、アルン・クマール
備考:PVRナーラーイナーで鑑賞。

左はドイジ・ヤーダヴ、右はボビー・デーオール
| あらすじ |
ナンネー・ジャイサルメール(ドイジ・ヤーダヴ)は、ヒンディー語、英語、ドイツ語、フランス語の4ヶ国語を話す、ジャイサルメールで一番の子供ガイドだった。ナンネーはラクダのラージャー・ジャイサルメールと共に観光客相手にサファリの商売をしていた。ナンネーのヒーローは映画スターのボビー・デーオール。彼は毎日ボビー・デーオールのことばかり考えていた。昔、ボビー・デーオールがジャイサルメールでロケをしたとき、ナンネーはボビーの友達になったのだった。ナンネーは読み書きが出来なかったため、姉に代筆してもらって、毎日ボビーに手紙を書いていた。
ある日、ボビーが再び映画のロケのためにジャイサルメールを訪れるというニュースが入って来た。ナンネーは狂喜乱舞し、ボビーが必ず自分を訪ねてやって来ると自信満々だった。果たしてナンネーとボビーは再会し、それから毎日のように会って話をするようになる。
その頃、ジャイサルメールではマダム主催の夜間学校が開かれていた。マダムは、学校に行っていない子供や読み書きの出来ない大人に最低限の教育を施そうと努力していた。だが、無理矢理学校に行かせられたナンネーはやる気がなかった。既に一人前にお金を稼いでいるナンネーにとって、勉強は無意味なものでしかなかった。しかし、読み書きが出来ないことで同年代の観光客の子供たちからからかわれたのをきっかけに、ナンネーは一生懸命勉強を始める。そして、姉の結婚式のための招待状に、ボビー・デーオール宛の宛名を自分で書けるようになる。
ボビーは姉の結婚式に必ず来ると約束したが、彼が来たのは結婚式が終わってからだった。しかもナンネーは、今まで話をして来たボビーが自分の幻だったことに気付く。
それから数年後、ナンネーは自身の思い出を綴った「Nanhe Jaisalmer」という本を出版し、ブッカー賞を受賞する。その授賞式にボビー・デーオールが現れ、ナンネーはやっと念願のボビーとの再会を果たすことが出来たのだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
主人公ナンネー・ジャイサルメールを演じた子役ドイジ・ヤーダヴのはつらつとした子供らしい演技だけが光る駄作であった。
ジャイサルメールに住むナンネーは、幼い頃に「友達」になったボビー・デーオールの大ファンという設定であった。しかし、この時点で通常のボリウッド・ファンなら一様に首を傾げるはずだ。「ボビー・デーオールの大ファン?そんな人いるの?」その設定自体からこの映画はつまずいている。サルマーン・カーンやサンジャイ・ダットならまだしも、ボビー・デーオールでは説得力が足りない。そのような設定なので、ボビー・デーオールが本人役で登場しているが、どちらかと言うと架空の映画スターを演じた方がよかっただろう。
映画は、成長したナンネーがブッカー賞を受賞し、過去を回想するところから始まる。だが、こんなしょうもない思い出や妄想を本にしたところで、国際的な賞がもらえるとは思えず、この点でも転んでしまっている。
子供が主人公なだけあって、やや子供向けの映画になっていた。子供向けの映画ならば、もっと楽観的な展開が欲しかったところだ。しかし、「Nanhe
Jaisalmer」は、ナンネーの前に現れたボビーを最後の最後で幻としてしまっており、夢も希望もないストーリーになってしまっていた。
結局この映画が伝えたかったメッセージは、映画の最後に出て来る「想像力には想像できないほどの力がある」ということなのだろう。ボビー・デーオールの姿を想像することで、ナンネーは困難を克服し、自分の将来を切り開いた。だが、ナンネーに身に起こったことはあまりに特殊な出来事で、それを全ての子供たちに当てはめるのには無理がある。この映画を見て、「想像って素晴らしい」と思えるだけの説得力がない。むしろ、現実に引き戻されるエンディングであったのではないか。これは映画の根本的な欠陥である。つまり、七転八倒の脚本なのである。
それでも、古都ジャイサルメールを元気いっぱい走り回るナンネーの姿は微笑ましく、十分観客を引き付けるだけの力がある。ナンネーを演じたドイジ・ヤーダヴは、TVCMによく出演している子供俳優だ。本作で映画デビューとなる。また、ジャイサルメールの風景も素晴らしい。やはりラージャスターン州の風景には魔法が宿っている。
音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。だが、ラージャスターンの民謡「Kesariya」以外、ラージャスターンっぽい雰囲気を醸し出している曲はなかった。あくまでヒメーシュっぽい音楽が押し通されていた印象である。
ラージャスターン州が舞台になっていただけあり、ラージャスターン地方特有の語彙がいくつか出て来た。例えば「Khammā Ghanī(खम्मा घणी)」。これはラージャスターン地方やグジャラート州のカッチ地方で使われている挨拶である。「khammā」は「許し」という意味の単語「kshmā(क्षमा)」が訛った形で、「ghanī」は「とても」という意味。直訳すると「カンマー・ガニー」は「誠に恐縮です」「大変失礼しました」みたいな意味だが、出会ったときや別れるときに使われる。また、ラージャスターン州では「姉」は一般に「ジージー」と言うが、それも使われていた。
「Nanhe Jaisalmer」は、黄金都市ジャイサルメールの風景と、主人公ナンネーの元気いっぱいの演技を楽しむ以外、特に取り柄のない駄作である。
| ◆ |
9月16日(日) 殺人バスはなぜ撲滅されないか |
◆ |
ここ最近、毎日のようにブルーラインが紙面に登場する。
ブルーラインとは、デリーの私営路線バスの総称である。なぜブルーラインと呼ぶのかは分からないが、元々私営路線バスは車体を青で塗られていたからなのではないかと思う。今ではあの時代のデリーのことを知る日本人は少なくなってしまったが、ほんの5、6年前までは、デリーには2種類のバスが走っていた――緑バスと青バスである。緑バスは州営で、デリー交通公社(DTC)が運営していた。青バスは前述の通り私営で、州交通機関(STA)の認可の下、運営されていた。2002年の公共交通機関一斉CNG化により、デリーのバスも州営・私営共にCNG化され、それをきっかけに車体の色も白と黄と緑を基調としたデザインに一新されたのだった。
ブルーライン・バスの運転の荒さは前々から話題になって来た。まるで弱肉強食のインドの道路のヒエラルキーの頂点に居座っているかのように我がもの顔で爆走。けたたましくクラクションを鳴らしまくり、他の車両を蹴散らしてひたすら直進することもあれば、まるで二輪車を運転しているかのように車両と車両の間を縫ってスラローム走行をすることもある。そして道のど真ん中で堂々と停車して乗客の乗降を行い、後続の車両の障害となって大渋滞を誘因。しかも同じ進行方向のバス同士でレースをし、バス停で乗客の取り合いを行う。わざと相手の行く先を遮るような停車の仕方をしたり、バスを並走させて運転手・車掌同士で舌戦を交わすこともしばしば。さらに、バス停で乗客が集まらないと、延々と停車して一定数を集めようとするため、酷暑期にバスに乗っていると暑くて暑くて仕方がない。耐えかねた乗客たちからの「チャラ~・デ~(早く発車しろ)」の声も完全無視。こんな状態なので、ブルーライン・バスを巡るトラブルは絶えない。もちろん、交通事故も多い。
昔からブルーライン・バスによる人身事故は少なくなかったと思うのだが、最近は以前にも増して増えたように思える。毎日のように、「またブルーラインの餌食に」「ブルーラインの呪い、まだ続く」など、ブルーライン・バスによる人身事故を報じる見出しが新聞に掲載される。2003年以降、ブルーライン・バスによる人身事故で亡くなった人の数は275人。今年だけで既に69人がブルーライン・バスの暴走によって命を失っている。デリー州政府はブルーライン・バス対策に乗り出しているのだが、なかなか効果的な方策を打ち出せていない。現在、DTCバスの台数は1,600台なのに対し、ブルーライン・バスは4,000台強。デリーのバス交通に占める私営バスの割合は圧倒的だ。よって、ブルーライン・バスの規制をあまりに強化し過ぎると、バス利用の通学者・通勤者が移動の足を失うというジレンマがある。
週刊誌テヘルカーの2007年9月22日号に、ブルーライン・バスの黒幕にメスを入れる記事が掲載されていた。
どうもブルーライン・バスの多くは、強力な権力を持った政治家や官僚が直接的・間接的に所有しているようだ。それがブルーライン・バスの規制の障害となっている。例えば国民会議派の政治家で、連邦都市開発省の副大臣を務めるアジャイ・マーカンは、従兄のスリーンダル・マーカンの名義で、3台のブルーライン・バスを所有している。インド人民党(BJP)の州議会議員カラン・スィン・タンワルは、従兄のクリシャン・タンワルの名前を使って、8台のバスを所有している。デリー警察本部長のオーム・プラカーシュ・バールドワージは、妻の名義で2台のバスを所有している。この中でも特にタンワルはデリーのブルーライン・バスの「ドン」とも言える強力な力を持っているようだ。「タンワル(Tanwar)」の名前が車体に書かれているバスには、いくら交通違反をしようとも、警察は手が出せないと言う。あまりに特権的な力を持っているため、実際にはタンワル所有のバスでなくても、「タンワル」の旗印を掲げて運行しているバスまであるようだ。確かにデリーの道路では「タンワル」バスをよく見掛ける。ちなみに、オーム・プラカーシュ・バールドワージの話によると、1台のバスから得られる毎月の利益は15,000ルピーほどのようだ。
ブルーライン・バスの問題の根源は、運転手の質の低さである。まともな運転技術と交通規則知識のない運転手がバスを運転しているため、交通事故や数々の問題が発生する。一応、州政府はバス運転手の資格として、高校卒業レベルの教育と、5年間の運転経験と、政府系運転学校からの証明書の取得を求めているが、この基準はほとんど骨抜きになってしまっている。デリーの道路を走っているバスの少なくとも15%は政治家や警察によって所有されているからだ。
しかも、ブルーライン・バスの運営者は交通警察に毎月一定額の賄賂を支払っており、それがさらにブルーライン・バスの横暴を助長している。現在、ひとつの信号につき毎月100ルピーの賄賂を払うことで、いかなる交通違反も見逃してもらえるような暗黙の協定があるようだ。例えば、ルート78のバスのルート上には17個の信号がある。よって、運営者は交通警察に毎月1,700ルピーを支払えば、あとはお咎めなしである。
それだけではない。州営のDTCの役人、運転手、車掌もブルーライン・バス運営者と密通している。例えばあるDTCの車掌は、DTCバスの発車をわざと5分遅らせることで、同タイムテーブルのブルーライン・バスがより多くの乗客を得られるように画策している。このちょっとした工作により、彼はブルーライン・バスの車掌から毎週100ルピーほどの「御礼金」を得ていると言う。
インドの様々な事象は、一見混沌として見えるが、深く掘り下げていくと実はかなりシステマティックに組織化されているということが多い。デリーの殺人バスの実態もその例外ではないようだ。裏社会のシステマティックさが、一般市民が快適に暮らせるような便利でシステマティックな社会作りの障害となっている。
■10月10日(水)キラーラインと違法また貸しも参照のこと。
16世紀・・・何も食べず、何も飲まず、灼熱の砂漠を裸足で歩く1人の男がいた・・・その男の名はジャラールッディーン・ムハンマド・アクバル。偉大なるムガル帝国の皇帝であった。北インドに一大帝国を築き上げ、莫大な富を手にし、豊かな教養と寛大な心を持っていた。世界は全て彼の思いのままであった。ただひとつのことを除けば・・・!アクバルは、アーグラー郊外のスィークリー村に住む聖人サリーム・チシュティーの祝福を受け、その唯一の願いを叶えるため、皇帝の身でありながらそのような荒行をしていた。その願いとは――どうか私に、私のことを父と呼ぶ声を聞かせて下さい!サリーム・チシュティーはアクバルに3人の息子が生まれることを予言し、果たしてその通りとなった。長男は聖者の名を取ってサリームと名付けられ、後の皇帝ジャハーンギールとなった。また、アクバルは聖者にありったけの敬意を表するため、スィークリーに首都を遷した。ファテープル・スィークリーである。ファテープル・スィークリーにはサリーム・チシュティー廟があるが、その伝承から子宝を願う人々が参拝に訪れている。
インドには他にも、子宝成就を第一の看板に掲げた寺院、聖者廟、祠が数え切れないほどある。人間の最も原始的な祈りは「子供」であったに違いない。今でも息づくインドの宗教的情熱を見ていると、「子供が欲しい」「健康な子供が生まれて欲しい」という願いが宗教の原点にあったのだろうと感じられる。
21世紀・・・時代は変わり、皇帝はいなくなったが、子宝を願う親の気持ちにほとんど変化はない。現在インドで急速に伸びつつあるビジネスがある。それは受胎ツーリズム(Reproductive
Tourism)。こう書くとかっこいいが、早い話がレンタル子宮ビジネス、代理母出産ビジネスである。安価な子宮を求め、先進国から子供のいない夫婦がインドに押し寄せている。新手のアウトソーシングとの冗談まで飛び出るほどだ。
代理母出産でインドが注目を集めるのにはいくつか理由がある。まずは何と言ってもその安さ。代理母が認められている先進国では、代理母には200~250万ルピーほどの謝礼を支払うのが相場だが、インドならその十分の一の20~25万ルピーで済む。また、先進国では代理母を探すのに多大な苦労を要するが、インドでは代理母志願者はいくらでも見つかるようだ。さらに、インドの医療技術は発展途上国の中でも高度な水準にあり、しかも医者は英語を話すため、コミュニケーションの問題も少ない。妊婦のケアや出産に要する医療費も先進国に比べたら安い。それらに加え、インドでは代理母出産を規制する法律が無に等しい。このような理由から、インドでは一躍受胎ツーリズムが盛んになって来ている。現在のインドの受胎ツーリズム市場規模は4億5千万ルピーと言われている。
代理母は、デリー、ムンバイーなどの大都市や、グジャラート州のような代理母ビジネス先進州で容易に見つかると言う。グジャラート州のアーナンドという町には、代理母ビジネスを推進しているアーカンクシャー不妊クリニックがあり、農村部の女性の間では子宮レンタルが普及している。代理母になるのは、農村の女性の他、メイド、工場労働者など、下位中産階級の女性がほとんどだ。だが、貧しくなくても、まとまった収入を求めて代理母を希望する女性もいると言う。代理母になるにはいくつか資格がある。既婚であること、健康な子供を産んでいること、母体が健康であることなどである。
子宮を商売の道具にすることに対し、臓器売買などと同一視して批判する声もある。先進国の裕福な夫婦による、途上国の貧しい女性の搾取ではないのか?これこそ女性を「子供を産む機械」に貶める行為なのではないか?だが、アーカンクシャー不妊クリニックの女医ナイナー・パテールは代理母ビジネスを「関わった全ての人が得する社会奉仕」と表現している。不妊に悩む夫婦は自分の遺伝子を受け継いだ子供が生まれることで幸せになるし、代理母になった女性の家族は多額の収入が得られて、自身の子供の育児や教育のためにお金を使うことが出来る。しかし、受胎ビジネスが盛んになるにつれて、法整備を求める声も大きくなって来ている。近頃インドでは受胎ツーリズムは既に新聞などでポツポツと話題になっているが、ここ数年の内に大きな問題になるような気がする。
それでも、代理母を巡る当面のトラブルは、代理母の夫にあるようだ。金欲しさに妻を無理矢理代理母にさせたり、妻が代理母をして得た謝礼を取り上げて好き勝手に使い果たしてしまう夫がいるようだ。それを避けるために、代理母ビジネスを推進するクリニックでは、代理母の謝金が夫の手に渡らないように、代理母の名義の銀行口座を開設させたりして工夫しているようだ。
アクバルに子供を授けた聖者サリーム・チシュティーのおかげで、スィークリー村は今や国際的に名高い世界遺産ファテープル・スィークリーになってしまった。代理母出産技術は、果たしてインドの農村にファテープルを呼び込むのであろうか?
| ◆ |
9月21日(金) Loins of Punjab Presents |
◆ |
本日からインド映画が3本公開された。まずは、ニューヨークで開催されたファーストラン映画祭2007で最優秀長編映画賞を受賞したヒングリッシュ映画「Loins
of Punjab Presents」を見に行った。
題名:Loins of Punjab Presents
読み:ローインス・オブ・パンジャーブ・プレゼンツ
意味:パンジャーブのライオン提供
邦題:デーシー・アイドル
監督:マニーシュ・アーチャーリヤ
制作:マニーシュ・アーチャーリヤ
出演:シャバーナー・アーズミー、アジャイ・ナーイドゥ、アーイシャー・ダールカル、スィーマー・レヘマーニー、ダルシャン・ジャリーワーラー、ラブリーン・ミシュラー、イーシター・シャルマー、ジャミール・カーン、クナール・ロイ・カプール、マイケル・レイモンディ、コリー・バセット、マニーシュ・アーチャーリヤ、シャーン(特別出演)、アヌーシュカー・マンチャンダー(特別出演)
備考:PVRナーラーイナーで鑑賞。

シャバーナー・アーズミー
| あらすじ |
米国ニュージャージー州の田舎町で、ボリウッドの映画音楽をテーマにしたのど自慢コンテスト「デーシー・アイドル」が開催された。主催者は、東海岸一の豚肉業者ローインス・オブ・パンジャーブ。コンテストには多くの参加者が集まった。「ロングアイランドのマザー・テレサ」と呼ばれる女性慈善事業家リター・カプール(シャバーナー・アーズミー)、バーングラー・ヒップホップ歌手のバルラージ・ディーパク・グプター(アジャイ・ナーイドゥ)、通称ターバノートリアスBDG、ボリウッド女優志望のサーニヤー・レヘマーン(スィーマー・レヘマーニー)、グジャラートの一族郎党を引き連れて参加のプリーティ・パテール(イーシター・シャルマー)、白人ながらインド文化マニアのジョシュア・コーヘン(マイケル・レイモンディ)とその恋人オパマ(アーイシャー・ダールカル)、ITエンジニアのヴィクラム・テージワーニー(マニーシュ・アーチャーリヤ)などである。
オーディションが行われ、リター・カプール、サーニヤー・レヘマーン、プリーティ・パテール、ジョシュア・コーヘンなどが選考に残った。当日のイベントは大盛況で、シャーンやアヌーシュカー・マンチャンダーなどのプロのシンガーもゲストで呼ばれていた。
10人の候補者が歌を歌った結果、2人が最終的に残った。リター・カプールとプリーティ・パテールである。どうしても賞金を手に入れたかったリターはプリーティに、モデルの仕事をオファーし、わざと負けることを持ち掛ける。リターは決勝前に姿を消す。リターが行方不明になったことにより、ジョシュアが繰り上がる。だが、観客からは白人がインド人ののど自慢コンテストの決勝に残ることに不満の声が上がる。それを見たジョシュアはインドの国歌「Jana
Gana Mana」を歌う。そのおかげでジョシュアは優勝する。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
最近インドでは「インディアン・アイドル」というスター発掘番組が人気だが、その舞台を米国のインド人移民社会に移し、そのイベントの裏舞台の人間模様やドタバタ劇を描いた映画であった。参加者はボリウッドの映画音楽を歌うのだが、映画自体にマサーラー・ムービー独特のテイストはほとんどなく、薄味な展開だった。個性的な参加者たち・・・と言いたいところだが、いまいちその個性を磨き切れておらず、映画の世界に入り込むことが出来なかった。この映画が映画祭で映画賞を取ったというのは信じがたい。
映画の中で唯一興味深かったのは、白人がインド映画音楽のど自慢大会に出演し、出演者や観客から「なぜデーシー(インド人)の大会に白人が出るのか」とブーイングを受けるという展開である。しかも彼の恋人はインド人で、それでまたからかわれていた。もしかしたらインド人の間にはそういう感情があるのかもしれない。特に賞金がかかっているので、普段よりも心が狭くなることはありうる。しかし、普通に考えたら、インドの文化に興味を持ち、ボリウッド映画音楽のど自慢大会にまで出演しようとする外国人がいたら、誇り高いインド人は温かく歓迎するはずだ。それを考えると非現実的であった。ブーイングの嵐を、インド国歌「Jana
Gana Mana」を歌って収めるという展開は、王道というか、陳腐というか、完全に予想出来た展開だった。
イベント当日、サーニヤー・レヘマーンがヒンディー語がほとんど出来ないことが発覚し、出場資格を取り消されてしまう一幕もあった。これは有力候補を蹴落とそうとするリター・カプールの陰謀に他ならなかったが、出場規定には十分なヒンディー語能力が要求されており、出場資格停止はやむを得ないことであった。ところが、オーディション中にサーニヤーと仲良くなり、当日会場に応援に来ていたヴィクラムは、「ヒンディー語が出来ないインド人は山ほどいる」と主張して観客を味方につけ、主催者に彼女の出場を認めさせる。このプロットの裏にどのような制作者の意図があるのか分からなかったが、もしかしたら「ヒンディー語はインド人の国民性の象徴にはなりえない」というメッセージが込められていたのかもしれない。
シャバーナー・アーズミーなどを除けば、映画に出演しているのは米国のインド系移民社会で割と有名な俳優たちのようだ。監督のマニーシュ・アーチャーリヤも重要な役で出演している。
言語はほとんど英語。ボリウッド映画音楽を歌うので、歌は当然のことながらヒンディー語である。それ以外にもセリフの中にヒンディー語、パンジャービー語、グジャラーティー語などが混ざるが、ごくわずかである。ヒングリッシュ映画の中でも英語のシェアが高い映画に分類されるだろう。
ちなみに、「Loins」とは「Lions(ライオン)」の誤表記。誤表記とは言えど、パンジャーブ人の間で十分に普及した「訛った英語」であり、パンジャーブらしさが出ている。
上映時間は1時間半ほど。2時間半~3時間のインド映画に慣れていると、非常にあっけなく終わってしまうように感じる。日本では、この映画の展開に非常に似た「のど自慢」(1998年)という映画も制作されており、日本人にも目新しさはあまりないだろう。「Loins
of Punjab Presents」という題名からは何やら謎めいたものを感じるが、特に題名が何か重要な秘密を持っていたということもない。総じて、鑑賞する価値のある映画とは思えない。
ボリウッドでは、男優を3、4人集めて主人公に据えたコメディー映画がよく作られる。「Hera Pheri」(2000年)、「No Entry」(2005年)、「Shaadi
No.1」(2005年)、「Deewane Huye Paagal」(2005年)、「Tom Dicky and Harry」(2006年)、「Golmaal」(2006年)、「Heyy
Babyy」(2007年)、「Dhamaal」(2007年)などがその例である。主役級の男優が集まればそれなりに楽しいのだが、二流三流の男優しか集まっていない映画もある。そういう場合は監督の力量が問われる。本日より公開の「Dhol」も、二流三流の男優が4人集まった微妙なコメディー映画。だが、監督は「コメディーの帝王」と呼ばれるプリヤダルシャン。監督の名前だけで見に行くことを決めた。
題名:Dhol
読み:ドール
意味:太鼓
邦題:ドール
監督:プリヤダルシャン
制作:パーセプト・ピクチャー・カンパニー
音楽:プリータム
作詞:イルシャード・カーミル、アーシーシュ・パンディト、マユール・プリー、アミターブ・ヴァルマー
振付:ロンギネス・フェルナデス、ポニー・ヴァルマー
出演:シャルマン・ジョーシー、トゥシャール・カプール、クナール・ケームー、タヌシュリー・ダッター、ラージパール・ヤーダヴ、オーム・プリー、パーヤル・ローハトギー、アルバーズ・カーン、ムルリー・シャルマー、アスラーニー
備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左はタヌシュリー・ダッター、
右は上からシャルマン・ジョーシー、クナール・ケームー、
トゥシャール・カプール、ラージパール・ヤーダヴ
| あらすじ |
無職でくの坊4人組のパッキヤー(シャルマン・ジョーシー)、サム(トゥシャール・カプール)、ゴーティー(クナール・ケームー)、マールー(ラージパール・ヤーダヴ)は、人生一発逆転のためには大金持ちの女の子と結婚するしかないと悟る。ある日、彼らが住む家の隣にかわいい女の子(タヌシュリー・ダッター)がやって来た。女の子の名前はリトゥだった。
リトゥの祖父ダーダージー(オーム・プリー)は大企業の社長であった。リトゥの両親は早くに亡くなり、兄のラーフルも謎の死を遂げた。リトゥは兄の死の謎を解明するために来ていた。
4人組はリトゥに近付くために、まずはリトゥの祖父母に近付こうとする。しかし、ゴーティー、サム、マールーは次々と失敗を犯し、しかも顔を覚えられてしまう。そんな中、パッキヤーだけは運良くリトゥと仲良くなることに成功する。しかも、ラーフルが妹の結婚相手として決めていたジャイがパッキヤーということになり、パッキヤーはリトゥと結婚することになる。残りの3人は歯ぎしりしてくやしがる。
ところが、ラーフルが頻繁に連絡していたソフィーという女性の存在が明らかになり、リトゥはソフィーと出会う。ソフィーは、実はジャイの許嫁であった。だが、ジャイは既に死んでいた。リトゥはソフィーから真実を聞くことで、パッキヤーたちが嘘を付いていたことが発覚する。4人組はあっけなく振られてしまう。
ところが、ラーフルとジャイが殺された理由は、「ドール」なるものを持っていたからだった。あるマフィア(ムルリー・シャルマー)は必死にそのドールを追っていた。4人組はマフィアに捕まり、ドールはどこかと拷問される。4人組は何とか隙を見て逃げ出すものの、今度はリトゥたちが捕まってしまう。やはり彼女たちもドールが何かも分からなかった。4人組の活躍でリトゥたちは解放される。
その後、リトゥとソフィーはジャイの家へ行き、ジャイの遺品を調べる。その中からドール(太鼓)が出て来る。だが、そこへマフィアがやって来る。絶体絶命の危機に陥るが、ガスを出しっぱなしにしていたため、ライターの火をつけたマフィアは爆死してしまう。
一件落着し、リトゥたちはナーシクへ帰って行った。ドールは4人組に託された。マールーがドールを地面に叩きつけると、中から大量の札束が出て来た。マフィアが探していたのもこれだった。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
そこそこ笑えるコメディー映画。だが、プリヤダルシャン映画の中ではつまらない部類に入る映画であろう。コメディーに「ドール」の謎というサスペンスの要素を取り入れたのはいいが、それが意味を成すのは終盤のみであり、その謎も結局ありきたりのものだった。また、解決されずに残った要素もあり、全体的にまとまりに欠けた映画であった。
コメディー部分の面白さの大半は、ラージパール・ヤーダヴの猿のようなハチャメチャな演技のおかげである。彼が1人で映画を背負っていたと言っても過言ではない。残りの3人、シャルマン・ジョーシー、トゥシャール・カプール、クナール・ケームーは、特に持ち味を活かせたわけでもなく、誰が演じてもいいような存在感でしかなかった。この内の1人を削ってもストーリーには全く影響がなかっただろう。紅一点のタヌシュリー・ダッターも魅力に欠けた。
マフィアが追う「ドール(太鼓)」が重要なキーワードとなるのは映画終盤であり、しかもそれが実際に登場して映画の本筋に絡むのは最後の最後になってからだった。ドールにあっと驚く謎が隠されていればまだ良かったが、その謎とは、太鼓の中に大量の現金が入っているだけで、観客の予想の範囲内であった。もっとうまくドールをストーリーに絡めることが出来たのではないかと思う。
深く考えてみると、エンディングでも解決されない問題がいくつかあった。例えばマールーの叔父さん。4人組は冒頭で大量の借金をしてしまう。その元金はマールーの叔父さんが出したのだが、叔父さんは抵当に金の装飾金を預かる。借金が返せなくなって4人組が失踪すると、叔父さんはその装飾金を売ろうとするのだが、それらは偽物で、叔父さんは警察でありながら警察に逮捕されてしまう。その後叔父さんがどうなったかはエンディングでも語られていなかった。おバカなコメディー映画なので、深く考える必要はないのだが、映画中に登場して4人組のおかげで痛い目に遭った人々がどうなかったかを最後に少し出すと話によりまとまりが出来たのではないかと思う。
ラージパール・ヤーダヴは既に人気のコメディー俳優だが、その他の3人は現在苦闘中の男優たちである。シャルマン・ジョーシーは「Rang De Basanti」(2006年)でブレイクし、「Life
In A... Metro」(2007年)でも好演を見せた。3人の中では一番の出世頭であろう。本作でも最も主人公的な立場にいた。だが、いまいち持ち味を活かせていなかった。トゥシャール・カプールは、TV業界で絶大な力を持つエークター・カプールの弟で、長年ボリウッドで苦戦しているが、中々ブレイク出来ない男優だ。顔に正直にダメ男路線で行けば一定の地位を獲得できると思うのだが、下手にヒーロー男優路線に走ってしまうので、「痛い奴」扱いされてしまう。それでもトゥシャールのコミックロールは割とはまっているのだが、やはりラージパール・ヤーダヴの前では印象が霞んでしまう。クナール・ケームーは、「Kalyug」(2005年)や「Traffic
Signal」(2007年)で注目を集めている男優だ。これまで異色のヒーローを演じて当たって来たので、しばらくその路線で行けばよかったのだが、「Dhol」では普通の男優になってしまっていた。つまり、3人とも「Dhol」では沈没してしまっていた。
音楽はプリータム。映画の面白さに比例して、音楽もいけてないものが多かった。
「Dhol」は息抜きするには悪くないコメディー映画だが、プリヤダルシャン監督の映画にしては名前負けであった。
インドは歴史が書かれて来なかった国だとよく言われる。文字がなくて歴史が残っていないのなら世界中でありふれたことだが、インドには、南アジアから東南アジアまで広がる「インド系文字文化圏」を形成するほどの影響力を持った優秀な文字が昔から存在した。それなのに歴史書らしきものが残されていないのは特殊なことのように思われる。インドで歴史書が書かれ始めるのは、イスラーム教徒到来以降である。
その一方で、インドには神話と伝承の伝統があった。歴史の補完を成すものが「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」などの神話・古典文学だと考えられている。これら二大叙事詩で描かれている出来事は完全なフィクションではなく、何らかの歴史的な出来事に基づいて書かれていると言う考え方をする人は少なくない。しかし、それらはあくまで神話であり、文学作品であり、歴史そのものではない。ある学者は、「もし『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』を歴史書として読んだら、それらには多くの神話が含まれていると感じるだろう。もし神話として読んだら、それらには多くの歴史が含まれていると感じるだろう」と絶妙な発言をしている。それらの叙事詩や神話・伝承を読んで歴史性を感じることはあっても、歴史書と考えるのは完全な間違いだ。現代的な意味での歴史は、インドには長い間存在しなかったと断言しても間違いではないだろう。
では、なぜインド人は歴史を書こうとしなかったのであろうか?そもそも歴史という概念がなかったのであろうか?もし「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」に何らかの歴史性があるなら、なぜ現代で言う文学という形で歴史を残そうとしたのであろうか?
その問いにはいくつかの答え方が出来ると思う。だが、神話を文学と置き換え、インドとインド人の文脈で「歴史と文学」という問題を考えるとき、まず思い浮かぶのは、ヒンディー文学の巨匠プレームチャンド(1880-1936年)が短編小説集「マーンサローヴァル」第1巻の冒頭で書いている一文である。インドの思想や哲学の重要なキーワードをなるべく残すように翻訳してみた。
ある批評家が、歴史は全て現実でありながらアサティヤ(真理ではないこと)であり、説話文学は全て創作でありながらサティヤ(真理)である、と書いていた。この言葉の意味は、歴史からは殺人、反乱、欺瞞のようなアスンダル(美しくないこと)のみを見せ付けられるからアサティヤだと言うことに他ならない。欲望から起こる最も残虐な、傲慢から起こる最も下等な、そして嫉妬から起こる最も低俗な出来事が歴史には書かれ、それを読んだ人々は、人間はなんと非人間的なのか、と考え出すだろう。少々の私欲のために兄弟は兄弟を殺し、息子は父親を殺し、王は無数の人民を虐殺する。それを読むと、心には嫌悪の情が沸き起こる。決してアーナンド(平安の感情)は沸き起こらない。そしてアーナンドを提供しない事物はスンダル(美しいこと)ではない。そしてスンダルでないものは、サティヤでもない。アーナンドのあるところにサティヤがある。文学は想像の産物である。だが、その核心的要素はアーナンドを提供することである。よって、文学はサティヤである。人間がこの世界で得た、または得ているサティヤとスンダルを文学と呼んでいる。物語も文学の一部である。
文学なら、悪人には必ず報いがある。読む人々はそれで安心し、正しく生きるための勇気を得、道徳観を養うことが出来る。だが、歴史には必ずしもそういうことが起こらない。登場するのは、誰かを殺した人物か、誰かに殺された人物ばかりだ。平穏で平凡な一生を送った人物はほとんどの場合「歴史的に重要でない」とされて無視される。人間の最も美しい部分から生じた出来事は多くの場合歴史の本筋には組み込まれず、人間の最も汚ない部分から生じた出来事の連続が歴史として記録される。歴史を学んでも、人格を形成する上でプラスになるようなことは少ない。プレームチャンドの言いたい所はこういうことだろう。彼は、サティヤ⇔アサティヤ、スンダル⇔アスンダル、アーナンドという特別な用語を使って、歴史と文学の違いをかなり分かりやすく説明している。これはインド人の考え方を理解する上で大きなヒントになるように感じる。かつてインド人男子の必須教養は、サーヒティヤ(文学)、サンギート(音楽)、シャーストラ(経典)の「3S」だったと言われるが、その中に歴史は含まれない。インドでは、サティヤでないもの、サティヤのないものに価値が置かれて来なかったのである。現代的な意味の歴史はサティヤではない。それがインド人の歴史観の欠如に影響を与えたとしてもおかしくないだろう。逆に、歴史的出来事の記録にスンダルとサティヤとアーナンドを求めるならば、想像力を用いて、神話や叙事詩のような形にするしかなかったのである。
だが、プレームチャンドは文学者だったため、歴史に対する文学の優位性を強調して上のようなことを声高らかに宣言したのだと思う。インド人が歴史に興味を持って来なかったのは、もう少し単純な理由があるからだろう。ある場所でこのようなことを言っているインド人がいた。
いずれにせよ、歴史的正確性への執着は、インド的なものと言うよりも西洋的なものだ。歴史家たちは、インド人が伝統的に「正確な」歴史書よりも神話や伝承を創作する習慣があったと述べ、インドには歴史のセンスがないと嘆く。それは間違いない。しかし、我々はその「批判」に対する弁護をするよりもむしろ、自分たちの非歴史的な文明観を誇るべきだ。なぜなら我々の祖先たちは直感的に、神話が歴史よりも文明の確実な理解を提供することを知っていたからだ。実際、インド人として、我々は神話の創造を信じ、歴史を消し去ってしまう。歴史は結局のところ勝者の価値観でしかなく、物事がどのようであったかでしかない。一方、神話は我々に、人々がどのようになりたいのか、本当に望んでいたことを教えてくれる。
インドには歴史観がなかったのではなく、歴史を書くことが禁止されていたのだとされる。もし歴史が自然に生じて来るものならばいいが、歴史は残念ながら誰かによって書かれて行くものだ。誰かが書くものには必ず主観が入る。結局歴史は特定の誰かの物の見方に過ぎず、それは多くの場合、勝者の価値観でしかない。しかも、書かれた歴史は後から恣意的な書き換えが可能である。また、特にインドのように侵略と征服にさらされて来た地域では、歴史は悲嘆と憤慨しか生まず、紛争の火種しか得られない。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の対立が起きるようになったのも、西洋人によってインドの歴史が書かれるようになって以来のように思われる。一方、口承の形を取って受け継がれる神話は、民族の総体的な記憶である。民族の数世代に渡る縦の軸と、同時代の民族の横の軸をひとつにまとめるものだ。インドには古代からいろいろな民族が流れ込んで来たが、歴史が出来る前は神話によってひとつにまとまって来たように思える。神話の作者は民族そのものである。「ラーマーヤナ」や「マハーバーラタ」には一応作者がいることになっているが、それはむしろ編集者または翻訳者という立場であり、神様から授かったものを編集したり翻訳したりしたという形になっている。当然神話も時代を経るごとに変わって行くものだが、それは特定の個人や国家の私利私欲に基づいたものではなく、民族と文明の道徳観や願望が形になって行ったものだ。歴史はインドをひとつにしないが、神話はインドをひとつにする。それだけではない。東南アジアやインド系移民が多く住む国々にまでインドの神話が伝わり、土着化して今でも語り継がれているのを見ると、神話にはさらに巨大な力があるように思える。歴史にはそのような統合力はないし、むしろ国内的にも対外的にも統合と調和の障害になることが多い。だからインドでは歴史は書かれず、神話のみが紡がれて来たのである。別の言葉で言えば、インドでは歴史は心で感じ取るもので、宗教に近いものだった。決して知識や学問ではなかった。
しかし、現代のインド人にはそのような祖先の偉大な知恵を理解する人がほとんどいなくなってしまったように思われる。現在インドでは、神話と歴史がまるで飲酒と運転のように危険な化合をして大きな爆弾となっている。そもそもインドではここ20年ほど、神話を歴史として捉え、政治的に利用しようとする動きが強まっていた。1992年のバーブリー・マスジド破壊事件はそれがひとつの臨界点に達した出来事だったが、最近は落ち着きを見せている。代わって現在最もホットなのはラーマ・セートゥ問題である。Indo.toのOgata氏の伝説の橋という記事で詳しく書かれていたが、インドとスリランカの間には、アダムス・ブリッジまたはラーマ・セートゥと呼ばれる通路状の細い浅瀬がある。インド人の間でこの特殊な地形は、「ラーマーヤナ」でラーム王子の軍勢がランカー島に渡るために作った橋の残骸だと信じられている。この辺りの水深は1.5~3.5mほどで、船舶は航行できず、インド洋とベンガル湾を行き来するにはセイロン島を回って行かなければならない。ない。よって、このラーマ・セートゥに水路を掘って、船舶がインドとスリランカの間を航行できるようにする計画がある。だが、その名の通りラーマ・セートゥはラーム王子の遺産と考えられているため、その破壊はインド人の宗教的感情を傷つける行為として問題となっている。さらに、この問題に関し、中央政府が9月12日に最高裁判所に対し、「『ラーマーヤナ』は歴史書とは言い難く、そこで描写された登場人物や出来事が歴史的に存在したという証拠はない」という宣誓供述書を提出したことにより、火に油が注がれることになった。数世紀の間、インド人の心の中で拠り所として存在して来たラームを、「歴史」という外来の概念に則って、「証拠がないから存在は証明できない」とされたら、それは精神的侵略というものであろう。上で引用した文章も、それに関する記事の中にあったもので、9月15日付けのタイムス・オブ・インディア紙に掲載されていた。インドの伝統的な文脈で言うならば、例え「ラーマーヤナ」に歴史的・考古学的根拠がなくてもラーマ・セートゥはインドの文明に関わる事物であり、破壊されるべきではない。宗教的な問題を差し置いても、水路の建造による経済効果は疑問視されており、むしろ環境に与える悪影響の方が懸念されている。そんな状況の中、ましてや、「ラームは存在しない」などと特定の宗教を否定するような発言をするのは、憲法でも否定されている行為である。統一進歩連合(UPA)政権は印米核協定でかなり政権運営が困難な状態に陥っていたが、それを遥かに越えるパンドラの箱を開けてしまったようだ。もちろん右派の野党がこのチャンスを逃すはずがない。最近元気がなかったインド人民党(BJP)も、ラーマ・セートゥ問題によって命を吹き返したように一気に活発になり、ここぞとばかりに「ラーム!ラーム!」と与党批判に乗り出している。9月12日にはデリー各地で世界ヒンドゥー協会(VHP)とBJPの活動家たちがラーム・セートゥ問題に抗議して一斉道路封鎖を行い、大渋滞が発生した。今でも問題は沈静化していない。
一度インド人の間に「歴史」という概念が生まれ、そして権力を持って来たことで、神話は大きな転機を迎えていると言っていいだろう。かつて歴史は神話に従属するものだった。「ラームは存在するか否か」などという問いは問題外だった。インドを旅行すれば、神話上・伝承上の空想でしかないものが、「歴史」として実体を持って存在している様を目にすることが出来る。例えばハリヤーナー州クルクシェートラのジョーティサルには、「クリシュナがアルジュンに説いたバガヴァト・ギーターを一緒に聞いた菩提樹」なる怪しげな樹が実しやかに存在するし、ラージャスターン州チッタウルガルには、ムハンマド・ジャーイスィーの叙事詩「パドマーワト」で書かれたアラーウッディーン・キルジーとパドミニーの間の空想上の物語が、なぜか歴史的建築物を伴って存在する(詳細)。インドには他にも、本当か嘘かよく分からないが、神話や伝承に便乗したような巡礼地や観光名所が至る所にある。そもそも「マハーバーラタ」にも「ラーマーヤナ」にも、王族の主人公が野に下って十数年放浪生活をする下りがあり、インド中に「ラーム王子ご一行様が滞在した場所」「パーンダヴァの5王子が一時期住んでいた洞窟」と言うような便乗商法の乱立を許す素地が元から用意されている。彼らがストーリー中王城に留まってほとんど外に出なかったら、神話の伝播はその地域のみに限定されていたことだろう。二大叙事詩の大ヒットの秘密は、どちらも歴史に準拠していたからではなく、歴史を生み出しやすかったことにあるように思える。つまり、インドでは神話が歴史を生んでいた。神話と歴史が混同されることはあっても、神話の方が絶対的に優位に立っていた。だが、今では神話と歴史の地位が逆転しただけでなく、神話は歴史と比べて否定されるおとぎ話、または歴史そのものとして利用される代物に成り下がってしまった。そうなった場合、インドの神話の最大の特徴は最大の弱点となって表出する。それは、時間の概念は滅茶苦茶なのに、現実では有り得ないような種々の空想が入り混じっているのに、主要な場所だけはかなり正確に記録されているという点である。アヨーディヤー問題もラーマ・セートゥ問題も、それぞれの場所がどこにあるか分からなかったら起こり得なかった問題だ。
インドはちょうど、ダシャヘラー祭とディーワーリー祭と言う、ラーム関連の大祭が続く期間に入る。BJPの牙城、グジャラート州の州議会選挙も近付いているし、早期の下院総選挙の可能性も取り沙汰されている。BJPやヒンドゥー至上主義者たちは与党追撃の手を緩めないだろう。
| ◆ |
9月24日(月) 白熱の印パ決勝戦Twenty20 |
◆ |
今年3月~4月に西インド諸島で開催されたクリケットのワールドカップ。クリケット大国のはずのインドとパーキスターンはまさかの予選敗退を喫し、両国の熱狂的なクリケットファンたちは大きな屈辱と失望を味わうことになった。しかし、名誉挽回の機会は案外早く巡って来た。今年から新たな試みとして開始されたクリケット新ルール「Twenty20」のワールドカップが南アフリカ共和国で開催され、インドとパーキスターンは順調に勝ち進んで決勝戦で激突することになった。印パのクリケットファンにとって、国際大会の決勝戦で因縁の対決を見れること以上の幸福はない。一気にインドは一足早いお祭りムードに入った。市場からは花火が飛ぶように売れ、5つ星ホテルの高級レストランから道端の安食堂まで、決勝戦上映の準備が急ピッチで始まった。映画館まで上映スケジュールを変更して試合の上映を決定。これは只事ではない。決戦の日は本日9月24日。インド時間では午後5時半から試合開始。観戦のために会社を休む熱心なインド人も多かったと言う。今日会社を休んだインド人は、どんなうまい言い訳を思い付いても信じてもらえないだろう!
何だかんだ言って、やはりクリケットはインドの宗教だ。そして印パ戦の興奮は何にも代えがたいものがある。クリケットのワールドカップでも、決勝戦よりも印パ戦の方が盛り上がると言われているほどだ。今回はワールドカップの決勝戦かつ印パ戦。これで盛り上がらないはずがない。おそらく向こうのパーキスターンでも状況は全く同じだろう。しかし、インドやパーキスターンに住んでいない人にこの興奮は分からないかもしれない。
という訳で、これは2003年のワールドカップ印パ戦以来の一大事だと、今までTwenty20を観戦して来なかった僕もどこで決勝戦を観戦するか決めなければならなくなった。運良く、我らがブラフマプトラ寮の有志がどこかから巨大スクリーンを借りて来て観戦会を開く計画を立てているという情報をキャッチした。寮生からレンタル料を捻出するため、ちゃっかり数十ルピーの寄付も集めていた。寮のみんなと印パ戦を観戦すること以上に興奮することはない。
Twenty20は、各チーム最大20オーバー(120球)という制限付きの、最も短期決戦のクリケットルールである。今までクリケットの国際試合では、テストマッチとワンデー・インターナショナル(ODI)の2つの試合形態があった。テストマッチは5日間続くオーバー無制限2イニング制の試合で、ODIは1イニング制50オーバー(300球)制限の1日マッチである。だが、ODIでもスポーツの中では試合時間が異常に長い部類に入り、それがクリケット普及の障害のひとつになっていたことは否めなかった。そこで、さらに短時間で試合の決着が付くTwenty20ルールが考案された。1イニングは約80分で終わり、1試合は2時間半~3時間ほど。ちょうどインド映画の上映時間と同じくらいで、スポーツの観戦時間としても標準的になった。スピーディーかつパワフルな展開が売りで、クリケットはより現代人の趣向に合ったスポーツに進化したと言っていいだろう。各個人、各チームの能力差が最も出やすいルールとも言われている。
インドチームのキャプテンは若き大砲マヘーンドラ・スィン・ドーニー。今年のワールドカップでは全然ダメだったが、いつの間にかだいぶ貫禄が出て来た。決勝戦では負傷のためにヴィーレーンドラ・セヘワーグの出場が見送られたが、今回のトーナメントで調子がいいユヴラージ・スィンやルドラ・プラタープ・スィンは健在である。また、試合会場には、映画スターのシャールク・カーンやUBグループのヴィジャイ・マーリヤー会長が観戦に訪れていた。観客席では、やはり旬の「Chak
De! India」の横断幕が目立った。しばらくインドのスポーツ躍進の合言葉になりそうだ。
試合はパーキスターンが先攻(つまりインドのバッティング)となった。オープナーのガウタム・ガンビールが絶好調で、どんどん点を重ねて行ったが、大爆発が期待されていたユヴラージ・スィンやマヘーンドラ・スィン・ドーニーは早々にアウトになってしまった。今までのインドの試合から考えると比較的スローペースで進み、結局Twenty20の勝敗のひとつの目安と言えそうな160ランに3ラン足らない157ランで20オーバーを使い果たし、バッティングを終えた。Twenty20はとにかくオーバーが限られているので、積極的にバウンダリー(4sや6s)を狙って行かなければならないのだが、インドチームはかなり慎重に戦ったと言えるだろう。
30分の休憩を挟み、後半戦が開始された。早い段階でインドはパーキスターンからいくつものアウトを奪ったが、パーキスターンのイムラーン・ナズィールが積極的なバッティングをし、バウンダリーの山を築いた。この時点でパーキスターンが優勢となるのだが、イムラーンがランアウトになったことでパーキスターンのペースは急に落ち、次々にバッツマンがアウトになって行った。徐々にパーキスターンを追い詰めるインド。だが、インドの誤算は「バッジー」の愛称で親しまれるスィク教徒ボウラーのハルバジャン・スィンだった。彼が投げるボールが今日はなぜかよく打たれ、試合後半で6sを連発された。既に残りオーバーが少ないこともあり、一気に攻勢に出るパーキスターン。しかし、インドも着実にアウトを取って行った。試合はどちらに転ぶか分からなくなった。
最終オーバーは本当にドキドキものだった。パーキスターンに残されたウィケットは1つだけ。だが、6球の中で13ラン以上を取ればパーキスターンの勝ちという微妙な状況。パーキスターンのバッツマンはミスバーフル・ハク。さて、インドは誰をボウラーに選ぶか・・・。絶好調のイルファーン・パターンとルドラ・プラタープ・スィンは既に4オーバー投げ切っている(Twenty20では各ボウラー4オーバー制限)。ハルバジャン・スィンはどうも調子が悪い。そこでインドのキャプテンは、若手のジョーギンダル・シャルマーを最後のボウラーに選んだ。だが、第1球目はワイドボールとなり、インドはみすみす1ランを敵に与えてしまった。これでパーキスターンの勝利条件は6球の中で12ランとなった。2球目はゼロ。だが、3球目でミスバーフル・ハクは6sを飛ばし、一気にパーキスターン有利に。4球の中で6ランが勝利ラインだ。インド絶体絶命のピンチ!4球目。ミスバーフル・ハクは再びバウンダリーを狙う!だが、球は空高く打ち上がってしまった。その着地点にはシュリーサントが。10億人が息を呑んだ・・・落とすな・・・落とすな・・・キャッチ!アウト!これで試合終了となり、インドはパーキスターンに5ラン差で勝利した。
これで、Twenty20ワールドカップ初代優勝国はインドとなった。インドのワールドカップ優勝は実に24年振りとなる。興味深いことに、Twenty20の新ルール導入に最も強硬に反対していたインドが、ワールドカップを手にしたのである。さらに、この勝利で「ワールドカップでインドはパーキスターンに敗北しない」というジンクスがまた守られたことになる。予選でも両国は対決したが、引き分けだった(新ルールのボールアウトでインドがポイント獲得)。
最後まで分からない展開だったため、勝利が決まったときの寮のみんなの喜びようは尋常ではなかった。当然、インド各地で同じような大騒動が起こったことだろう。
パーキスターンも惜しかった。よく粘ったと思う。一時はパーキスターンに不利な展開となっていたが、終盤の追い上げはすさまじく、インドにとっては冷や汗ものであった。最後の最後で勝利を急いだのが結局敗因となった。それにしても、ただでさえ最近政情不安定なパーキスターンのこと。もしかしたらこの敗北は政局にも少し影響するかもしれない。

インド優勝おめでとう!
Twenty20ワールドカップ決勝戦でクリケット大国で永遠のライバルのインドとパーキスターンがちょうどぶつかることになったのは、興行的にも筋書き通りの大成功だったと言えるだろう。本大会は、実はTwenty20ルールが今後継続されるか否かを決定する試金石という意味合いもあったのだが、この盛り上がりを見れば、これからポピュラーになって行くのは確実のように思われる。既にTwenty20ルールのクリケットは2010年の広州アジア大会でも正式種目に採用されている。日本でも本気でプロモーションすれば、短期決戦の新クリケットはけっこう流行るかもしれない。2007年、クリケットは新たな時代に突入したと言える。
南アジアにスーフィズム(イスラーム神秘主義)をもたらした聖人モイーヌッディーン・チシュティー(1141-1230年)の廟は、ラージャスターン州アジメールにあり、インドのみならず近隣諸国から多くの参拝客を集めている。彼がアジメールを拠点に選んだのは、当時北インドで有力だったチャウハーン朝の首都が当地に置かれていたからである。モイーヌッディーンは1230年に没するが、チシュティー教団の主導権は弟子から弟子へと受け継がれて行き、彼らが移り住んだ場所に広まって行った。そして、その弟子たちの定住地にはやはり死後に廟が建てられ、現在まで信仰の対象となり続けている。チシュティー教団に属する聖人の廟は、インド・パーキスターンにまたがって各地に散らばっている。
デリーにもチシュティー教団に属する聖人の廟が3つある。ひとつはメヘラウリーにあるクトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー(1173-1235年)、通称クトゥブ・サーヒブの廟。クトゥブッディーンはモイーヌッディーンの一番弟子であり、デリーにイスラーム教政権が確立した奴隷王朝時代に生きた聖人である(3月18日の日記参照)。ふたつめは、フマーユーン廟近くにあるニザームッディーン・アウリヤー(1238-1325年)の廟。EICHER「Delhi City Map」ではP98のF6になる。ニザームッディーンは、モイーヌッディーンの弟子ファリードゥッディーン・マスード・ガンジシャカル(1179-1266年)のさらに弟子にあたり、詩人・音楽家として知られるアミール・クスロー(1253-1325年)の師匠としても知られる。デリーの人々からは、スルターンジー(皇帝様)またはメヘブーベ・イラーヒー(神の恋人)の愛称で親しまれている。ニザームッディーンはキルジー朝~トゥグラク朝時代に活躍した。みっつめは、GKIIの西にあるナスィールッディーン・メヘムード(1276-1356年)、通称チラーグ・デリー(デリーの灯火)の廟である。EICHER「Delhi
City Map」ではP130のG5になる。トゥグラク朝時代に生きた聖人だ。だが、上記2つの廟に比べたらチラーグ・デリー廟は格も知名度もグンと落ちる。特にニザームッディーン廟の威光は絶大である。毎日大勢の参拝客が訪れ、ニザームッディーンの墓に花を捧げている。ラマダーン(断食月)の夕方には参拝者にイフタール(断食明けの食事)が振る舞われ、木曜日にはカッワーリー(賛美歌)の生演奏を聞くことが出来る。また、ニザームッディーン廟の周辺は、彼の名を取ってニザームッディーンと呼ばれており、ちょっとしたイスラーム・タウンとなっている。ニザームッディーンはマトゥラー・ロードを境にニザームッディーン・ウエストとニザームッディーン・イーストに分かれている。ニザームッディーン・ウエストは、ニザームッディーン廟を擁する門前町で、バーザールと庶民的な住宅街となっている。一方、ニザームッディーン・イーストは閑静な住宅街。中東諸国の外交官や駐在員などはこの辺りに住居を構えることが多いようだ。

ニザームッディーン廟
そのニザームッディーン廟から南に約10km行った場所に、トゥグラカーバードと呼ばれる大規模な城塞都市遺跡がある(EICHER「Delhi City
Map」P146)。トゥグラカーバードは、トゥグラク朝の創始者ギヤースッディン・トゥグラク(?-1325年)によって、リッジの山中に2~3年という短い期間で建設された。デリーの歴史を彩る「7つの都市」の中では最も辺鄙な場所にあると言っていい。当時「デリー」はクトゥブ・ミーナールのあるメヘラウリー付近を指していたことを考えても、辺境に変わりない。トゥグラカーバードがこのようなアクセスしがたい場所に建設されたのは軍事的理由が大きい。13世紀からデリーは度々モンゴル人の侵略を受けており、その脅威に備えなければならなかった。トゥグラカーバードは、当時デリーに建造された城塞都市の中では圧倒的に堅固な城壁を備えている。また、新王朝を樹立した皇帝が自身の威信を巨大な城塞によって示そうとしたとも考えられる。

トゥグラカーバード城塞
一見何の関連もなさそうなニザームッディーン廟とトゥグラカーバード城塞。だが実は、歴史と伝承はこのふたつの遺構を切っても切れない関係にしている。
キルジー朝最後の皇帝クトゥブッディーン・ムバーラク・シャーが暗殺された後、キルジー朝に将軍として仕えていたガーズィー・マリクが混乱を収めて政権を握り、1320年にギヤースッディーンを名乗ってトゥグラク朝を樹立した。その頃、デリーではニザームッディーン・アウリヤーが絶大な人気を集めており、歴代の皇帝たちはその力を恐れていた。クトゥブッディーン・ムバーラク・シャーも、ニザームッディーンに無礼を働いたため、彼の呪いとも言える予言によって不慮の死を遂げたとされている。ニザームッディーンは、貧者には宗教の別なく最大限の援助をしたが、高圧的な権力者には一貫して厳しい態度を取った。
トゥグラク朝を樹立したギヤースッディーンは、すぐに「ニューデリー」の建設を開始した。工事を急がせるため、皇帝はデリー中の職人たちを新首都建設に充てさせた。一方、ちょうど同じ頃、ニザームッディーンは自宅のそばにバーオリー(井戸または貯水池)を建設していた。周辺の住民が清潔な水を飲めるように、との配慮から開始された慈善事業であった。だが、職人たちが皆、皇帝の厳命によりトゥグラカーバードの建設に駆り出されてしまったため、工事はストップしてしまった。そこでニザームッディーンは、油を買って明かりを灯すことで、夜間に職人たちにバーオリーを造らせた。皇帝にも聖者にも逆らえなかった職人たちは、昼はギヤースッディーンのためにトゥグラカーバードを建設し、夜はニザームッディーンのためにバーオリーを建設した。ところが、昼夜休みなく働かされた職人たちはすぐに弱って来て、城塞の工事は停滞するようになった。その理由を知ったギヤースッディーンはデリー全土に命令を出した。「ニザームッディーン・アウリヤーに油を売ったり与えたりすることを禁ずる」。だが、ニザームッディーンは少しもうろたえなかった。彼は人々に、バーオリーの水を油代わりに使うように言った。その言葉通り、奇跡が起こった。なんと、バーオリーに溜まった水が日没後に油に変化したのである。そのおかげでバーオリーの工事は続行した。だが、ギヤースッディーンも負けていなかった。彼も、異教徒との戦いによって聖なる力を身に付けていた。ギヤースッディーンはバーオリーの水に呪いをかけた。途端に水から異臭が発するようになり、飲み水として利用できなくなってしまった。こうなったらニザームッディーンも黙っていない。彼はトゥグラカーバードに対し、有名な呪いをかけた。
या बसे गुज्जर
या रहे उज्जर
yā base gujjar
yā rahe ujjar
グッジャルの住居となるべし
さもなくば廃墟となるべし
果たしてトゥグラカーバードの運命はニザームッディーンの呪い通りとなった。トゥグラカーバードはギヤースッディーンの存命中に完成したものの、結局市民が定住することはなく、モンゴル人の攻撃にさらされることもなかった。後を継いだ息子のムハンマド・ビン・トゥグラクはすぐに首都をデカン高原のダウラターバードに移し、再びデリーに遷都したときも、トゥグラカーバードには戻らず、新たにジャハーンパナーと呼ばれる城塞を建造した。現在もトゥグラカーバードは広大な荒地となっており、グッジャルと呼ばれる牧畜民たちが家畜を放牧する場となっている。トゥグラカーバードの城壁の内部には2つの村があるが、どちらもグッジャルの村である。かつては盗賊の住処になっていたとまで言われるトゥグラカーバード城塞だが、現在では入場料を取って観光客に開放されている(インド人5ルピー、外国人100ルピー)。トゥグラカーバード城塞の中で最も高いビジャイ・マンダルに上ると、360度のパノラマでデリー郊外の雄大な光景を楽しむことが出来る。他にも広大な敷地を散歩して回ると、いろいろな発見があるだろう。遺跡の入口は南側にあるが、これは元々裏口であり、正式な門ではない。トゥグラカーバードを訪れる観光客は少なく、閑散として無常感溢れる遺跡である。

トゥグラカーバード内部
遠くにデリー都心部が見える
また、ニザームッディーン・アウリヤーが造ったバーオリーもニザームッディーン廟の北に残っている。昔は泳げるぐらいに水がきれいだったようだが、現在では汚物の浮く汚ない貯水池に過ぎない。ギヤースッディーンの呪いも実現したように思われる。

ニザームッディーンのバーオリー
ところで、ギヤースッディーンとニザームッディーンの確執はこれだけではない。晩年、ギヤースッディーンはベンガル地方に遠征した。遠征には寵愛していた次男も従っており、長男のムハンマド・ビン・トゥグラク(1300-1351年)はデリーで留守番を任されていた。首尾よくベンガルを征服し、ギヤースッディーンがデリーに凱旋することになった。そのとき、デリーではこんな噂が流れた――皇帝はデリーに到着次第、ニザームッディーンを反逆罪で処刑するつもりらしい・・・!ニザームッディーンの弟子や信者たちは震え上がった。遂にギヤースッディーンはデリー郊外にまで辿り着いた。弟子たちがニザームッディーンにそれを伝えた。「皇帝がすぐそばまで来たようです!明日にはデリーに到着するでしょう!」だが、ニザームッディーンは落ち着いた声で、ペルシア語でこんな言葉を発した。
دلی دور اشت
dillī dūr ast
デリーは遠い
師の言葉の真意を理解しなかった弟子たちは、一刻も早くデリーから逃げるように進言した。だが、ニザームッディーンは同じ言葉を繰り返すだけだった。
ھنوز دلی دور اشت
hanūz dillī dūr ast
まだデリーは遠い
その頃、ムハンマド・ビン・トゥグラクは父をデリーの外で迎えていた。彼は仮設のチャトリー(東屋)を建て、その下に皇帝を座らせて、歓迎と祝福の式典を行った。皇帝は次男と共にそこに座っていた。ところが、ムハンマド・ビン・トゥグラクが席を外した瞬間、そのチャトリーは崩れ、ギヤースッディーンと次男は屋根の下敷きになってしまった。ムハンマド・ビン・トゥグラクは急いで工具を持って来させ、崩壊した屋根を取り除かせたが、時既に遅く、皇帝と次男は遺体で発見された。ギヤースッディーンの遺体はトゥグラカーバードに運ばれ、埋葬された。そしてムハンマド・ビン・トゥグラクがトゥグラク朝第二代皇帝に即位した。だが、皇帝の不可解な死に対し、デリーではこんな噂がまことしやかに流れた――チャトリーの崩壊は事故ではなく、息子によって仕組まれたものではないか?さらに、崩れた屋根を取り除いたとき、皇帝はまだ息があったとの情報もどこからか聞こえて来た。ニザームッディーンが皇帝の死をほのめかす発言をしたことから、ムハンマド・ビン・トゥグラクとニザームッディーンが共謀してギヤースッディーンを暗殺したとの見方をする人も出て来た。確かに皇帝の死によって最大の利益を被ったのはこの2人である。だが、どちらにしろ、真相は歴史の闇の中である。ただ、ニザームッディーンが発した「デリーは遠い」という言葉だけが、「目的地はまだ遠いこと」を表す諺となって歴史から抜け出し、今でもよく使われている。
ちなみに、ギヤースッディーンは生前に自分のための墓廟を造らせていた。彼は現パーキスターンのムルターンにも墓を造ったが、埋葬されたのはトゥグラカーバードの南にある廟である。三角形プランの強固な城壁に囲まれた、小さいが美しい廟だ。彼はこの廟を「ダールル・アマン(平和の住居)」と名付けた。ここでは、インド・イスラーム建築の初期の完成形を見ることが出来る。この廟には、ギヤースッディーンの妻や寵臣、長男ムハンマド・ビン・トゥグラクの墓の他、ギヤースッディーンの愛犬の墓まである。現在トゥグラカーバードの南は広大な平地になっており、子供たちのクリケット場になっているが、かつてここは巨大な貯水湖で、ギヤースッディーン・トゥグラク廟は湖の中に浮かんでいた。

ギヤースッディーン・トゥグラク廟
このようにライバル関係にあったギヤースッディーンとニザームッディーンだが、皮肉なことに、死期はほとんど同じであった。ギヤースッディーンの死後、ニザームッディーンもすぐに死去し、彼が60年間住んでいた場所に墓が作られた。死後もニザームッディーンへの信仰は衰えず、時の皇帝や富豪たちの寄進によって、彼の廟はどんどん豪華さを増して行った。また、ニザームッディーン廟内や周辺には、歴史上非常に重要な人物の墓がいくつか存在する。フマーユーン廟はその筆頭であるが、ニザームッディーンの弟子だったアミール・クスローの墓や、ペルシア語・ウルドゥー語の詩人ミルザー・ガーリブ(1796-1869年)の墓などがあり、感涙モノである。ちなみに、ガーリブの墓の隣にはガーリブ・アカデミーがあり、ガーリブ関連のちょっとした博物館や、ウルドゥー語・イスラーム教関連書籍を集めた図書館がある。

アミール・クスローの墓(左)とミルザー・ガーリブの墓(右)
ニザームッディーン廟もトゥグラカーバード城塞も、以上のような歴史や伝承を知らなくても十分楽しめる遺跡・観光地である。世界遺産フマーユーン廟の観光後に時間があったらニザームッディーンまで足を延ばしてみてもいいし、デリーで1日暇が出来たら、是非郊外のトゥグラカーバードまで遠足気分で行ってもらいたい(トゥグラカーバード近辺では飲食物は手に入らないので注意)。だが、やはり伝承を理解した上でこれらの遺跡を見ると、汚ないバーオリーも廃墟となった城塞も、見違えるほど魅力的に見えて来る。
| ◆ |
9月27日(木) Chak De!効果とクリケットの復権 |
◆ |
インド映画を批評する際、その映画がインドの社会にどれだけ影響を与えたのか、という点も考慮すべきだと思う。インド映画はインドの世相を反映すると同時に、インドの社会を動かすだけの力を秘めている。ボリウッドには脳みそを空っぽにして見なければならない娯楽映画も多いが、年に1、2本は必ず社会に何らかの影響を与える重要な作品が生まれる。そういう観点で見ると、昨年は「Rang
De Basanti」と「Lage Raho Munnabhai」が社会に大きな影響を与えた重要作品だと言える。
さて、今年はどうだろうか?
何度も書いて来たように、2007年はボリウッドの不作年になりそうである。昨年は1ヶ月に1本はヒット作が生まれていたが、今年はインパクトのある作品が少ない。だが、8月になってようやくインド全土を動かす傑作が生まれたようだ。その作品の名前は「Chak De! India」。女子ホッケーを主題にした、シャールク・カーン主演のスポ根映画である(同作品の批評は8月10日の日記で既にしたので、そちらを参照していただきたい)。この映画の合言葉「Chak De!」がインドのスポーツ界のカンフル剤となっており、映画公開以降、インドの各スポーツは国際大会ですこぶる調子がよい。
ここで「Chak De!」という言葉について説明しておこう。「Chak De!」とは元々パンジャービー語で、バーングラーの歌詞の中によく登場するフレーズである。原義は「持ち上げろ!」という意味だが、「頑張れ!」「元気出せ!」「ガンガン行こうぜ!」みたいな意味で使われる。「Chak De Phatte!」というフレーズでも使われる。こちらは「床板を持ち上げろ!」という意味になるが、やはり同じように応援したり高揚した気分を表したりするときに発せられる。その語源には諸説あり、スィク教のゲリラ隊がムガル朝の軍隊の追撃を阻止するために、件の合言葉によって一斉に河に架かった橋の床板を取り外したことから来ているとも書かれているが(参照)、僕はどこかで読んだキャロムボード起源説が一番信憑性があるのではないかと思う。パンジャーブ文化の中心地ラーハウルの下町では、キャロムボードのことを「パッテー」と呼んでおり、「Chak
De Phatte!」とは「ゲームを終わりにしろ!」「敵をやっつけろ!」という掛け声だったらしい。それが次第に上記のような応援の言葉になったという訳である。語源がどうであれ、「Chak
De!」は昔からインドでポピュラーなフレーズだった。だが、「Chak De! India」がこの言葉とスポーツを結び付けたため、一気にインド応援の合言葉として定着したのである。
元々、2007年のボリウッドの流行はスポーツ関連映画だった。「Hattrick」、「Say Salaam India」、「Bheja Fry」、「Chain
Kulii Ki Main Kulii」などはクリケットを直接的・間接的に主題としており、「Ta Ra Rum Pum」はモーターレース、「Apne」はボクシングがテーマの映画だった。ところが、女子ホッケーというインドではマイナー中のマイナーなスポーツをテーマにした「Chak
De! India」が登場し、大ヒットを飛ばした途端、インドはまるで最強のマントラ(真言)を手に入れたかのように、スポーツの世界で次々と前代未聞の業績を上げるようになった。まず火を噴いたのは男子サッカーであった。インドのエースストライカー、バイチャン・ブーティヤー率いるインド代表は、8月下旬にデリーで開催されたネルー杯の決勝戦でシリア代表を破り、25年のネルーカップの歴史の中で初めて優勝を果たした。翌日の新聞には喜びに沸くサッカー選手の写真と共に「Chak
De!」の文字が躍った。その興奮冷めやらぬ9月上旬、今度は男子ホッケーがチェンナイで開催されたアジアカップで韓国を破り優勝。2003年にもインドは優勝しており、二連覇を果たしたことになる。サッカーよりもさらに映画「Chak
De! India」のテーマに近かったことから、やはり合言葉は「Chak De!」となった。ちなみに、肝心の女子ホッケーは準決勝で敗退してしまった。
そして9月24日の日記でも書いたが、9月下旬に南アフリカ共和国で行われた男子クリケットのTwenty20ワールドカップ。インドは決勝戦で見事宿敵パーキスターンを破り、Twenty20ワールドカップ初代チャンピオンに輝いた。印パ戦の視聴率は47.2%だったようだが、この数字は実際の感覚より低い気がする。まるで全インド人が中継に見入っていたかのようであった。このときも、「Chak
De!」は10億人の合言葉となり、「Chak De! India」の主題歌はあたかも新たな国歌のようにTVから、ラジオから、そして人々の口から流れ出た。試合会場に、「Chak
De! India」の主演シャールク・カーンが観戦に訪れたことも、「Chak De! India」の雰囲気を高めていた(ただし、シャールクは新作「Om
Shanti Om」のTシャツを着ていた!)。

印パ戦試合会場に応援に駆け付けたシャールク・カーンと
その息子アーリヤン
しかし、男子クリケットのワールドカップ優勝は、インド人を「Chak De! India」のメッセージとは違う方向に持って行ってしまった。今年3月~4月に西インド諸島で開催されたクリケットのワールドカップ(こちらは50-50ルールのODI形式)で、インド代表はまさかの予選落ちとなってしまった。このせいでクリケット選手は戦犯扱いされ、インドでは一時的にクリケット熱が冷めてしまった。3月~4月には、ワールドカップへの便乗を狙ってクリケットを主題にした映画がいくつか公開されたが、ほとんどはフロップに終わった。逆に、興味深いことに、当時公開中でそこそこの客入りだった「Namastey
London」が、インドの予選敗退と同時にヒットに浮上した。クリケットという娯楽を失い、人々の足が映画館に向いた、ということもあるだろうが、「Namastey
London」には主演アクシャイ・クマールが英国人に対してインドの素晴らしさをとうとうと演説する場面があり、それがワールドカップ予選落ちで自信を失ったインド人たちにかなり受けたようである。クリケットのインド代表のワールドカップ予選落ちは、映画界だけでなく、スポーツ界にも波及した。クリケットが大スランプに陥ったために、他のスポーツがクローズアップされることが多くなったのである。クリケット一辺倒だったインドのスポーツ界にとって、これはいい傾向だった。「Chak
De! India」も、女子ホッケーというインドではマイナー中のマイナーなスポーツを敢えて取り上げることにより、「クリケットだけがスポーツではない」というメッセージを観客に訴えることに成功していた。
だが、インドのクリケットはすぐに復活した。

凱旋したクリケット選手たちを迎えるムンバイーの市民たち
Twenty20ワールドカップ優勝チームは26日にムンバイーのマリン・ドライブで凱旋パレードを行ったが、そこには2万人のファンたちが集まり、大騒動となった。おかげで選手たちが乗ったバスは立ち往生となり、30kmの道のりを進むのに6時間以上もかかったと言う。インド代表主将のマヘーンドラ・スィン・ドーニーは、「ムンバイーは誰にも止められない街だと言うが、我々はムンバイーを1日の間止めてしまった」と自信満々に語った。一時政権を追われたクリケットがインドの宗教として完全に復権したことは、上の写真を見れば誰の目にも明らかであろう。
ワールドカップ優勝の熱気にあやかりたい政府、クリケット関係機関、企業も、ここぞとばかりに選手たちに特別報酬金を用意した。インド男子クリケット協会(BCCI)は、各選手に800万ルピーのボーナスを発表。サハーラー・パリワールは各選手に住居をプレゼントし、エア・インディアは5年間飛行機乗り放題のパスを発行した。本大会で「1オーバーに6つの6s」という大記録を打ち立てたユヴラージ・スィンは、BCCIからさらに1千万ルピーとポルシェのボーナスが与えられた。また、各州政府も次々と自州出身の選手たちに報酬金を出すことを決定している。一夜にしてクリケット選手たちには金銀財宝の雨が降り注いだ。
ところが、面白くないのはその他のスポーツをしている選手たちである。クリケット選手が活躍すると政治家は競って多額の報酬金を発表するが、その他のスポーツ選手が業績を上げてもほとんど無視するか、なけなしの金を「施して」それで終わりにしてしまう。ここのところ他のスポーツも好調であったため、その長年蓄積されて来た不満がとうとう実際の行動になって表れるときが来た。舞台はカルナータカ州、主人公は先日アジアカップで優勝したホッケーの選手たちである。事は、カルナータカ州政府が、同州出身でTwenty20ワールドカップで活躍したクリケット選手2人にそれぞれ50万ルピーの報酬金を与えることを発表したことにより起こった。インド中がワールドカップ優勝に沸く中、同州出身のホッケー選手やそのコーチが、クリケット選手のみ優遇する政府の姿勢に抗議し、州首相官邸前でハンガーストライキをすることを発表したのである。もしかしたら同様の動きが他のスポーツ界でも広がって行くかもしれない。
「クリケットだけがスポーツではない」というメッセージを掲げて公開された「Chak De! India」。そのマントラによってインドのスポーツ界は俄然活気付いた。だが、結局そのマントラの最大の恩恵を被ったのは、他でもないクリケットであった。クリケットは短い暗黒時代を終焉させ、見事インド人の自尊心の象徴に返り咲いた。マヘーンドラ・スィン・ドーニーという新カリスマと、Twenty20という今までにないエキサイティングな新ルールを引っ下げて・・・。
| ◆ |
9月28日(金) Johnny Gaddaar |
◆ |
全くノーマークだったのだが、突然「Johnny Gaddaar」というなかなか面白そうなスリラー映画が公開された。監督のシュリーラーム・ラーガヴァンは「Ek
Hasina Thi」(2004年)でデビューした映画監督で、これが2作目となる。英国人ミステリー作家ジェームズ・ハドリー・チェイスや、アミターブ・バッチャン主演の「Parwana」(1971年)へのオマージュが散りばめられた、70年代テイスト溢れるユニークな映画だった。
題名:Johnny Gaddaar
読み:ジョニー・ガッダール
意味:裏切り者のジョニー
邦題:裏切り者のジョニー
監督:シュリーラーム・ラーガヴァン
制作:アドラブス・フィルムス
音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ
作詞:ジャイディープ・サーニー、ハルドカウル、ニーレーシュ・ミシュラー
出演:ダルメーンドラ、ヴィナイ・パータク、ザーキル・フサイン、ダヤー、リーミー・セーン、ニール・ムケーシュ(新人)
備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ダヤー、リーミー・セーン、ニール・ムケーシュ、ダルメーンドラ、
ザーキル・フサイン、ヴィナイ・パータク
| あらすじ |
ムンバイー在住の隠居ギャング、シェーシャードリー(ダルメーンドラ)は、バンガロールに住む警察の友人カリヤーンと、2,500万ルピーの取引をしようとしていた。シェーシャードリーは資金を調達するため、4人の部下を集めた。カジノを経営するプラカーシュ(ヴィナイ・パータク)、ディスコを経営するシャールドゥル(ザーキル・フサイン)、巨漢シヴァ(ダヤー)、そして若手のヴィクラム(ニール・ムケーシュ)。5人は500万ルピーずつ出し合い、2,500万ルピーを作った。4日後にはこれが2倍になって返って来る算段であった。一方、シャールドゥルの妻ミニ(リーミー・セーン)とヴィクラムは恋仲にあり、2人はこの取引が終わったらカナダへ逃亡しようと計画していた。だが、ヴィクラムは「Parwana」を見ている内に、2,500万ルピーを独り占めにする陰謀を思い付いた。アリバイを作るため、ヴィクラムはシェーシャードリーに、計画実行の前日にゴアへ行くと告げた。だが、彼の自動車はゴアへは向かわず、プネーへ行った。そこで一泊した後、自動車を置いて飛行機でゴアへ向かい、ゴアのホテルにチェックインして、シェーシャードリーの知り合いと会談した。その後再び飛行機でムンバイーへ戻った。
シェーシャードリーはシヴァに、ムンバイーからバンガロールへ列車で金を持って行き、そこで金を受け取って、すぐにムンバイーへ戻って来るように指示を出した。シヴァは金を持って列車に乗り込んだ。ところが、その列車にはヴィクラムも乗っていた。彼はクロロフォルムでシヴァを眠らせ、その隙に金を奪い取ろうとしたが、シヴァは意識を失う前に抵抗し、ヴィクラムは顔を見られてしまう。しかもシヴァは意識を失うときに頭を強打してしまい、死んでしまう。ヴィクラムは仕方なくシヴァの死体を列車から捨てる。ヴィクラムはプネー駅で降り、自動車に乗ってゴアへ向かった。ゴアでシェーシャードリーからシヴァの死を電話で伝えられ、ヴィクラムはムンバイーへ戻る。
シェーシャードリーの家に着いたヴィクラム。だが、シェーシャードリーはヴィクラムがシヴァを殺したことに勘付いてしまう。恐れたヴィクラムは隙を見てシェーシャードリーを撃ち殺す。そこへプラカーシュとシャールドゥルもやって来る。ヴィクラムは一旦家の外に出て、何食わぬ顔をして玄関にやって来る。ドアを破って中に入った3人は、シェーシャードリーが死んでいるのを発見する。
バンガロールからカリヤーンがやって来て、2日以内に犯人を捕まえると約束する。当初カリヤーンはシヴァが生きていることを疑い、シヴァの恋人ヴァイジャヤンティーを拷問するが、すぐに鋭い嗅覚でヴィクラムがやったと気付く。ヴィクラムはカリヤーンに捕まりピンチに陥るが、カリヤーンは待ち伏せしていたヴァイジャヤンティーに殺されてしまう。
その頃、プラカーシュはギャンブルに負け、多大な借金を負ってしまった。そこでシャールドゥルとヴィクラムは金を貸すことにしたが、その中に偽札が含まれていることが発覚する。実はプラカーシュは、シェーシャードリーに渡した500万ルピーの中に偽札を含ませていた。その金が自分の手元に戻って来たことを知り、シャールドゥルがシヴァを殺して2,500万ルピーを盗んだと考える。プラカーシュはそのことをヴィクラムに言うが、ヴィクラムは自分が犯人だとばれるのが怖くて、プラカーシュをも殺してしまう。
残ったのはシャールドゥルとヴィクラムだけになってしまった。シャールドゥルは偶然、シヴァが死んだ日にヴィクラムがプネーにいたことを知り、彼を殺そうとする。まずはヴィクラムから家の鍵を奪い、彼の家で2,500ルピーを探す。ヴィクラムは金を貯水タンクの中に隠していたが、それは発見されてしまう。シャールドゥルはその金を自宅へ運び、ヴィクラムを殺そうとする。だが、そこへ自分たちの不倫がばれたと勘違いしたミニが駆け込み、その隙にヴィクラムはシャールドゥルを射殺する。
ヴィクラムはシャールドゥルの服を着て彼の家へ行き、奪われた金を取り戻そうとする。だが、彼は後ろから何者かに撃たれて死んでしまう。撃ったのはプラカーシュの妻だった。彼女は、シャールドゥルが夫を殺したと思っており、シャールドゥルに復讐するために待ち伏せしていたのだった・・・。 |
 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
スリラー映画は、先の展開が読めないハラハラドキドキ感が決め手である。誰が犯人なのか?どのように完全犯罪を崩して行くのか?そして全ての謎が明かされるときは、観客が納得できるような解説をしなければならない。だが、残念ながらインドのスリラー映画の大半は、どこかで見たような、どこかで読んだような、結末が事前に分かってしまうストーリーばかりだ。しかも強引なこじつけが多いので、スッキリしないことが多い。インドのスリラー映画はまだまだ未熟だと言わざるをえない。よって、よっぽどのことがなければインドのスリラー映画を見る気にはなれないのだが、「Johnny
Gaddaar」は突然変異的に優れたスリラー映画に仕上がっていた。
「Johnny Gaddaar」は、アミターブ・バッチャンが悪役を演じた1971年公開の映画「Parwana」の犯罪シナリオがベースになっている。つまり、アリバイを作るために列車に乗ってある駅からある駅まで移動することにし、始点と終点に目撃者を設ける。一方で、途中の駅で降りて飛行機で別の場所に移動し、犯罪を犯し、元々乗っていた列車に乗る、という筋書きである。列車での移動が数日かかることがあるインドならではの犯罪だ。「Johnny Gaddaar」の主人公ヴィクラムは、「Parwana」の手法を真似て犯罪を犯す。犯罪の手法は最初に観客に提示され、犯罪者の心理状態と末路に焦点を当てて描いた映画であった。ヴィクラムが警察官のカリヤーンに、「お前、アミターブ・バッチャンが好きなら、『Parwana』は見たことがあるか?」と核心を突く質問をされてうろたえるところなど、よく出来ていた。
1971年の映画がベースになっているためか、当時最盛期だったダルメーンドラが出演しているためか、全体的に70年代テイストの演出が施されていた。所々に渋いギャグも散りばめられており、監督のセンスの良さを感じた。また、カメラのアングルも凝っており、緊張感が出ていた。
主演のニール・ムケーシュは、名プレイバックシンガーのムケーシュの孫で、やはりプレイバックシンガーのニティン・ムケーシュの息子になる。リティク・ローシャンに似た顔立ちで、新人としては演技は合格点だった。ヴィナイ・パータク、ザーキル・フサイン、リーミー・セーンなどもいい演技をしていた。意外にダルメーンドラがミスキャスティングだったように思う。呂律が回っていなかったのが一番気になったが、ギャングのご隠居にしては優しすぎる印象を受けた。
音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイだが、一般のインド映画のようにミュージカル・シーンが入ることはなく、シャンカル・エヘサーン・ロイらしい音楽は聞かれなかった。
基本的にヒンディー語で、英語が多少混じる程度だが、一瞬だけタミル語が出て来る。バンガロールのシーンでは、カンナダ語映画のスーパースター、ウペーンドラ出演の映画の看板も出て来た。監督が南インド出身なので、少しだけ南インドの隠し味を混ぜたのであろう。
「Johnny Gaddaar」は、インド映画の中ではよく出来たスリラー映画だった。ユーモアと緊張感が程よく調合されており、70年代の雰囲気がいい味を出していた。見て損はない。



